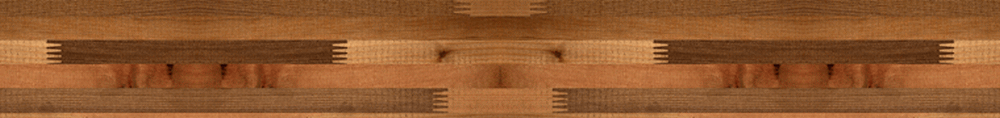2012年04月の記事
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-

ゲームプランニングの第一歩 その2
こんにちはenoです。 1Q、約20分間のゲームを5分単位で考えたとします。 例えば、まず5分間はマンツーマン・ディフェンスでスタートして、相手に6回の攻撃があって、5本のシュートを決められたとしましょう。 そうすると、この5分間のマンツーマン・ディフェンスは機能していないことになる。 そこでゾーン・ディフェンスに変えてみる。 そのゾーン・ディフェンスもオールコートのゾーンがいいのか、ハーフコートのゾーンがいいのか、またはトラップ・ゾーンがいいのかを考えるわけです。 今度は相手の攻撃が7回あった中で、シュートは2本しか決められなかった。 こうなるとそのゾーン・ディフェンスが成功していると判断するわけで、そうすれば、「このディフェンスをもう少し続けてみようか」ということになるのです。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2012年04月27日
コメント(0)
-

ゲームプランニングの第一歩 その1
こんにちはenoです。 私が40数年間バスケットボールを指導してきて思うことがあります。 まず、最初にやらなくてはいけないことは、相手チームの"スカウティング"ではないということです。 つまり、相手に対してどうこうする前に、まず自分のチームが、チームとしてやりたいこと、練習中に指導してきたことを、いかに100%発揮できるかということが大事だということなのです。 『 自分達の出来ること 』 『 力を発揮できる姿勢を持つこと 』 まず、これを第一に心に留めておいてください。 さらにゲームを戦っていく上で必要になってくることは、相手の対応について出来る限り、先手、先手を打って事態に対処していく事だと思っています。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2012年04月26日
コメント(0)
-

不利を覆す1対1の攻防 その18
こんにちはenoです。 多くの情報のおかげで、次のプレーを読むことに長けた選手が増える一方、直線的にリングへとアプローチできる選手は減少している気がします。 ペリメーター(ペイントエリアの外側から3Pラインの内側)の選手はドライブでインサイドをついてみる。 ファウルを貰えるかもしれませんし、上手く抜き切れば、その後は、相手はスタンスを広くとってディフェンスをせざるを得なくなるようになります。 インサイドの選手もボールを貰って即、アウトサイドに反してしまうのでなく、ピボットを踏んで頑張ってみる。 そうすることでシュートまで持って行ける可能性が出て来るだけでなく、ヘルプマンを引き上げることにより、他の選手をノーマークの状態にしてあげることが出来るのです。 選手がマークマンに勝てるように仕向けるのは、何も監督だけの仕事ではありません。 選手自身がそうした気持ちをたずさえ、練習で培った成果を発揮する努力や、あらゆる事象に対応し得る臨機応変さが重要な意味を持ちます。 それだけに、監督が一方的に話し続けるミーティングではなく、ある部分では選手に考えさせ、そして行き詰った際に選手と監督が双方向から言い合える環境作りが大切だと強く感じます。 この章END ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2012年04月23日
コメント(0)
-

不利を覆す1対1の攻防 その17
こんにちはenoです。 同じペースで動き続けていれば高いほうが有利であるという事実をもとに、"ストップ・オフェンス"は編み出されたが、ダッシュ&ストップに加え、鋭い動きを可能にする身体作りはケガの防止にもつながるのです コート上の5人にそれぞれ20センチの身長差があっても、「芝生を慣らすように【持てる要素】を延ばしていくと、ひょっとしたら君たちの方が大きいかもしれない・・・」と、そんなふうに言って、自信を持たせるようにもしていました。 勿論、そこには個々のファンダメンタル、強靭な脚力、そして集中力や精神的な強さといったベースが必要不可欠です。 つまり、身長差を覆す術は、私の経験上ですが、実際にあるのです。 身長差を例にしながら、チーム作り全般まで話を広げさせていただきましたが、最後にもう一度、『1対1の原理・原則』に立ち戻り、リングに近づくという原点を忘れずに指導にあたって欲しいと思います。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2012年04月19日
コメント(0)
-

不利を覆す1対1の攻防 その16
こんにちはenoです。 高さのあるチームと戦う際には、バック・ランも欠かせない技術です。 バック・ランで自陣に戻る習慣がついていれば、視野が失われない分、先手を打つことが出来ます。 小さいチームであれば、全員がフロント(前向き)・ランと同じくらいのスピードでバック・ランでも戻れないと、高さがあり、しかも速攻を展開するようなチームには太刀打ちできないのです。 視野を十分に維持して、インターセプトあるいはスティールを成功させたら、こちらは、それに輪をかけるように攻めます。 ボールを奪ったら5秒以内に相手リングまで持っていくような練習を繰り返し行ったものです。 その『5秒オフェンス』を成功させるには、ボールマンともう一人が走るだけでは相手に対応されてしまう。 そこから、『スリー・ライン』の速攻がシステム化されたという訳です。 個々、あるいはチームとしての必要性が生じた場合、原理原則を考慮したうえでのそうした発想を試してみるべきだと思いますが皆さんはどうお考えになるのでしょうか。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2012年04月16日
コメント(0)
-

不利を覆す1対1の攻防 その15
こんにちはenoです。 振り返って見ると、チームを指導していた当初は、『20センチ差ならどうにかなる』という意識を持って指導にあたっていたような気がします。 前項でご説明したストップ・オフェンスに自信を深めたのに加え、他にも色々な工夫に試行錯誤を繰り返す日々を送っていました。 身長は足の底から頭のてっぺんまでを計測した数値ですが、実際の試合で大きな意味を持つのは、足の底から腕を伸ばした高さ、いわゆるリバウンド身長です。 その高さを伸ばそうと、脚作りだけでなくジャンプ力をつける工夫もしました。 また、肩関節を柔軟にして、腕が上がる高さを伸ばすような工夫も奉効しました。 高さのあるチームと戦う際には、バック・ランも欠かせない技術です。 自分達が攻めた後、高さのあるチームがどういう攻め方をしてくるか、一瞬も見逃すわけにはいかないからです。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2012年04月14日
コメント(0)
-

不利を覆す1対1の攻防 その14
こんにちはenoです。 指導者のタイプも十人十色ですが、私は自分で出来ないことは人には教えられない。 と、自認しており、"コクシング・パス"、"コクシング・シュート"などの辛い練習も選手と共に実行しました。 筋肉痛は並大抵ではありません。 余談ですが、私が指導を始めた当初、トイレはほとんど和式だったために、筋肉痛で座れないということもありました。 しかし、こうした練習を積み重ねることで筋肉と骨格が強くなり、ストップ&ダッシュが可能になるばかりか、関節の可動域も広がります。 だからスクワットのような格好での中腰、いわゆるバスケットボール・スタンスを長時間持続させても、何一つ不平、不満を言う選手はいませんでした。 最近の選手は、辛いとすぐに棒立ちになってしまうのではありませんか?そこで指導者の方が妥協してはいけません。 ある一定期間は我慢させる。 苦しい時期を乗り越えれば、ケガを寄せ付けないようになり、ひいては身長差をカバーできるだけの脚力が備わるわけです。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2012年04月11日
コメント(0)
-

不利を覆す1対1の攻防 その13
こんにちはenoです。 数メートル先にボールを放り投げ、それをノーバウンドで拾わせる。あるいは、わざとキャッチしづらいパスを出してシュートを打たせる。 こうしたメニューを私はそれぞれ、"コクシング・パス"、"コクシング・シュート"と命名して選手に取り組ませていました。 『コクシング=酷使ing 』は文字通り、身体を酷使して脚作りを進めるというもの。 しかし、それは同時にストップ・オフェンスに不可欠な要素を各々の肉体に宿らせるという手順を踏んでいたということでもあるわけです。 ちなみに、私は今でも選手に取り組ませるメニューを自分の身体にも課す習慣を継続させています。 自分が行うことによって、そのメニューの良い部分と、悪い部分がハッキリするからです。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2012年04月04日
コメント(0)
-

不利を覆す1対1の攻防 その12
こんにちはenoです。 皆さんも、瞬時のストップやチェンジ・オブ・ディレクションの重要性をいくら認識していても、選手になかなか伝わらないとご苦労されているのではありませんか? 脚作りが思い通りに進まず、結果的に負傷につながるという苦い経験をされた方も少ないと思います。 確かに、練習で酷使し過ぎて負傷する場合もあるかもしれません。 特に低年齢期の選手に筋力トレーニングを課すのは禁物ですし、多少のトレーニングが必要だとしても慎重に行う必要があります。 しかしながら、ある一定の年齢に達し筋肉と骨格がしっかりしてきたら、身体を酷使するようなトレーニングも時に必要ではないかと感じます。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2012年04月02日
コメント(0)
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-
-
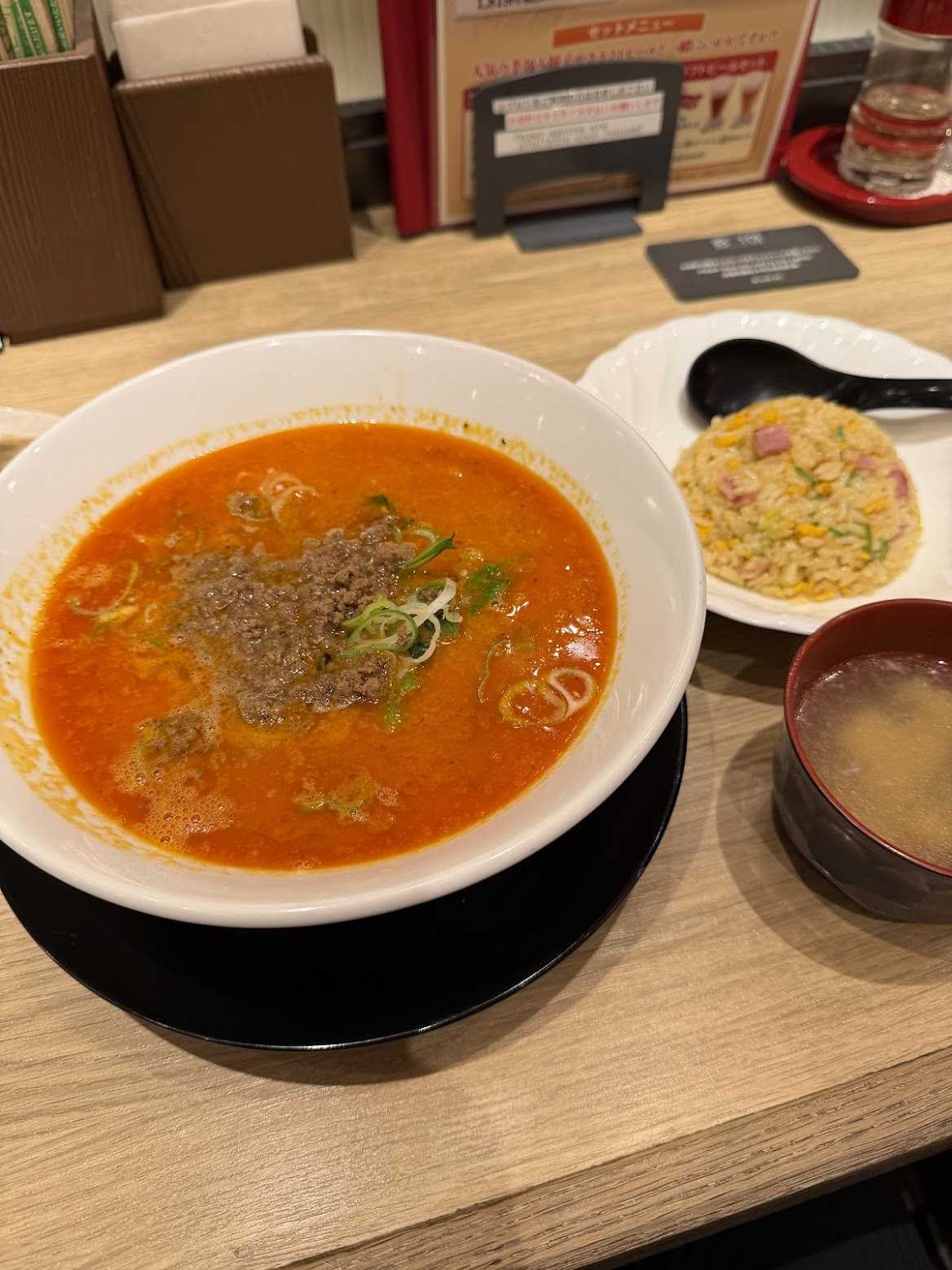
- 【金鷲】東北楽天ゴールデンイーグル…
- 育成1位は俊足巧打
- (2025-11-23 06:59:38)
-
-
-

- 福岡ソフトバンクホークスを応援しよ…
- ホークスを日本一に導いた小久保監督…
- (2025-11-13 22:51:08)
-
-
-

- サッカーあれこれ
- FC今治×北海道コンサドーレ札幌J2
- (2025-11-23 18:28:03)
-