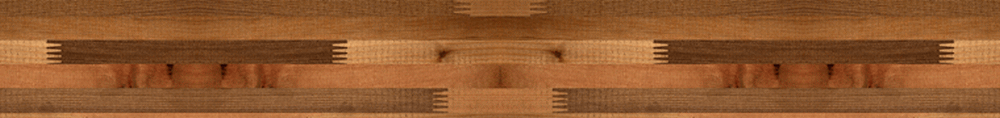2012年09月の記事
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-

今、何故、コーチングなのか その5
こんにちはenoです。 【7】 : 出会いがしらの一言 「おはよう」の一言が関係をつくるチャンスになります。 【8】 : 同じ言葉を繰り返す コーチングの基本的な哲学は、「安心感で人を動かす」というものです。 相手の言葉を繰り返すことで、相手が今そういう状態にあることを認めているという意味があり、その結果、安心感を与えるのです。 【9】 : 絶妙なあいづち 「あいづち」はほとんど無意識のうちに打っています。 「あいづち」を打つ時の声のトーン、声の大きさ、タイミング、顔の表情、そして言葉がそれ自体の選択の一つで、人は話す気になったり、逆に話す気を無くしてしまったりします。 【10】 : 気持ちを話す 人を育成しようと思ったら相手から信頼される必要があります。 その時、とても大事なキーワードになるのが相手に自分の気持ちを伝えるということです。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2012年09月29日
コメント(0)
-

今、何故、コーチングなのか その4
こんにちはenoです。 【4】:信頼して・沈黙して・旅に出す 「答えは必ず相手の中にある」という信頼を持つ。 構いすぎないでしばらく黙って見守って、そして答えを教えるのではなくて自分で見つけさせましょう。 【5】:向こう側から見る 人はほとんどの場合「自分の側」から状況を見ています。 状況を正確に分析するには相手の立場に立って考えて、向こう側に回って状況を観察します。 【6】:かたまりにする 「かたまりにする」ことをチャンク・ダウンに対してチャンク・アップと言います。 幾つかの小さなものを大きな塊にまとめあげて、具体的なものの集まりから抽象的な概念を抽出します。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2012年09月26日
コメント(0)
-

今、何故、コーチングなのか その3
こんにちはenoです。 【2】 : かたまりをほぐす 人は自分の過去の体験を一つのチャンク(かたまり)にして脳の中にストックする傾向があります。 相手のかたまった言葉や体験を受けて、それをほぐす。またかたまりを見つけてほぐす。 このように相手の話や現状の実態を質問やドリルによってほぐしていき具体化していくことを「チャンクダウン」と言う。 相手から多くを引き出すためには、まず「小さくて」必ず応えられる質問やドリルからしていくことが鉄則である。 【3】 : 「なぜ」と「なに」 「なぜ」ではなく、「なに」が相手を警戒させずに答えやすくします。 「なに」を使うことにより今までよりもずっと短い時間で多くの情報を引き出すことが出来ます。 「なぜ」と言いたくなったら、グッとこらえて「なに」を使ってみましょう。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2012年09月24日
コメント(0)
-

今、何故、コーチングなのか その2
こんにちはenoです。 支配されることも、守られることもない代わりに、「やりたい」という自分の意志でことを起こすことが求められるようになりました。 その結果、「やりたいこと探し難民」が多数出現したのです。 そんな人々の「やりたい」を支えるサポートシステムが「コーチング」と言えるのではないでしょうか。 コーチングをする立場として意識しなければいけないこととして、 1: 引き出すコーチングの定義で「引き出す」とは、相手さえもまだ自分の内側に眠る「出来る」に気づいていない情報を引き上げ、新たな行動の指針となる知識に変えていくことです。 真剣に引き出してくれる人が一人いるだけで、その人生はずっと豊かなものになる。 引き出すための第一歩は、相手が下しているシャッターを少しでも上げることです。 そのシャッターを上げるには、常日頃から「通りがかりの一言」を大切にする必要があります。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2012年09月20日
コメント(0)
-

今、何故、コーチングなのか その1
こんにちはenoです。 【今、何故、コーチングなのか 】 今までの日本社会(企業社会)は上位下達(*1)の縦型社会でした。 (*1) 『上意下達 』 (じょういかたつ)人間関係上における上位者の命令、指示、言葉などを、下位者に伝えて意思の疎通を図ること。 トップに支配される組織は安全であり、トップが作る「流れ」に乗る限り、それが例え自分のやりたいこととは違っていても、やるべきことをやっていれば、組織から守ってもらえたのです。 日本人には独創性が無いと言われますが、それは一握りの人がつくる「流れ」の中で守られて暮らしてきた我々の結果です。 ところが、情報技術の驚異的な革新と発展は、人々の生活を一変させました。 世界中の出来事が、PCや携帯端末を使って検索すれば、一瞬にして誰にでも分かるようになり、トップしか知りえなかった情報を誰もが簡単に手に入れられるようになっています。 流れの中で「ねばならない」と自分を駆り立ててできたことが、「やりたい」という意思に変えなければ行動を起こせなくなったのです。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2012年09月14日
コメント(0)
-

1-2-2 , 3-2 のゾーンについて考察する その17
こんにちはenoです。 ディナイ・ディフェンスの場合、ワン・フォーのような形でオフェンスにポジションをとられて、バックドアなどを仕掛けられたら、ヘルプのしようが ありません。 繰り返しますが、基本、基礎、そして適切な理由付けを選手に与えることが大切です。 我々が教えなければならないのは、型ではなく、バスケットボールの本質の部分なのです。 フォーメーションを考える前に、パス&ランとスクリーンの基本を教えてください。 ディナイを教える前に、まず、ビジョン、ポジション、そしてボールライン、ボールサイドの原則を教えてください。 まずは、バスケットボールの本質を、本気で指導者が考えてみてはいかがでしょうか。 それには、まずご自身がコートに立って、やってみることです。必ずそこから見えてくるものがあります。 それを指導者自身が実体験でつかめば、ここは、こう伝えたほうが選手には伝わるという術を見つけ出せるはず。 この章END ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2012年09月12日
コメント(0)
-

1-2-2 , 3-2 のゾーンについて考察する その16
こんにちはenoです。 オフェンスがウィングでボールをもらうときなども同じです。「型、決まり事」ではなく、「基本、本質」なのです。 Iカット、Vカット、Lカット、様々なカットがありますが、「Lカットでもらえ!」と教えてもダメなのです。 ボールサイドカットをしようとして入らない。だから、戻ってボールをもらう。これでLカットが完成するわけです。 ボールサイドをカット出来るのならばまずそのラインをカットすればいいのです。そこで、抑えられて初めてLカットという選択肢が浮上するのです。 ディフェンスでも、それと同じことが言えるでしょう。 現在、ワンパス・ディナイという守り方が主流となっています。しかし、これをディフェンスの基本だと思ってはいけません。 ディフェンスの基本には、ボールライン、ボールサイドというものがあります。全ての攻撃は、ボールサイド、ボールラインから始まるのです。 ですから、ボールラインより上のオフェンスというのは怖くない存在です。ディフェンスは、ボールラインまで下がる。これが基本です。 オフェンスは、ディフェンスにディナイでつかれて、シュートを打てず、ペネトレートしようとしても次のカバーがすでに準備している。 これが、ディフェンスの基本なのです。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2012年09月08日
コメント(0)
-

1-2-2 , 3-2 のゾーンについて考察する その15
こんにちはenoです。 最後に、ゾーン・ディフェンスの話からは少しそれますが、もう一度、「基本」というテーマについてお話させてください。 例えばオフェンスの場合、PGが左サイドにポスを出したとします。 その時、インサイドの選手のためにパス&ランをしてスペースを空けたり、右サイドの選手にアウェイ・スクリーンにいくのはなぜでしょう? それが「型だから、決まりだから」という指導方法では、選手は混乱してしまいますし、心からは納得できないでしょう。 これは、ボールをもらった選手が、1対1をするのに十分なスペースを確保するために行うプレーなのだという、「本質であり基本」だということを、指導者の方は教えてあげてください。 そうすれば、ディフェンスが、スペースの邪魔になる部分に残らないように、パスを出した選手はどんな動きをすればいいかを考えられるようになるはずです。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2012年09月05日
コメント(0)
-

1-2-2 , 3-2 のゾーンについて考察する その14
こんにちはenoです。 ローテーションが完璧にできるようになった場合、さらに効果的なゾーン・ディフェンスにするための練習方法として、全ての選手に全ポジションを守らせるといいでしょう。 たとえ試合では守らないポジションでも、他のポジションを理解できます。 オフェンスも同じことが言えますが、自分のポジションだけしか経験しないと、そのポジションのことしか分かりません。 他のポジションを経験することで、そのポジションの難しいところ、易しいところが分かります。 ゾーンの場合、上の選手は、下の選手に対して『短い距離しか走らない』という認識があるかもしれません。 しかし、下のポジションを経験してみれば、ボディー・コンタクトの厳しさが違うことを体験として知ることが出来ます。 一方、上の選手が安全そうに見えても、実は安全ではないという状況もあります そんな実情を体験として理解できるようになり、人のポジションの重みをすることが出来るわけです。 ローテーションが出来るようになった後、ハイポスト1人、ローポスト2人、アウトサイドに5人のオフェンスを配置して、ぜひ全員に全てのポジションを経験させてあげてください。 ■ 榎本のまぐまぐメルマガ(当ブログと内容が違います)『 Never give up! ~バスケットボールと共に歩んだ道~ 』 はこちらから http://archive.mag2.com/0001186611/index.html ■ このブログに関する、ご意見、ご質問、ご要望はこちらまで enosann★gmail.com( 迷惑メール防止のため、★を@に置き換えてください。■ ブログランキング参加中。押していただけると励みになります。
2012年09月01日
コメント(0)
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-
-

- テニス
- 今年最後の三連休中日 ~当方には関…
- (2025-11-24 00:10:05)
-
-
-

- 楽天イーグルスにアツいエールを送ろ…
- 2004年に発生した中越地震から10月23…
- (2024-10-24 00:22:47)
-
-
-

- 福岡ソフトバンクホークスを応援しよ…
- ホークスを日本一に導いた小久保監督…
- (2025-11-13 22:51:08)
-