2008年10月の記事
全25件 (25件中 1-25件目)
1
-
なぜ学会は政治に進出したのか
天理教の政界進出昭和21年、政界進出。昭和25年には衆院に10人、参院に4人もの教団関係者を擁した。多分に勢力誇示するのが目的であった。昭和20年代は天理教一人勝ち。しかし昭和27年、創価学会の発展にともない、失速。もともと政治理念が無かったゆえである。日本の宗教団体の政界進出4パターン1. いち早く政治に乗り出し、やがて失速し、撤退した天理教、生長の家等。2. 自前の政治団体は持たないが、選挙で既成政党に影響を及ぼす立正佼成会、霊友会等。3. 自宗派の代表を政界に送る一方で、既成政党にも一定の影響を保ちたい仏教、キリスト教等の各派。4. 独自の理念と基盤をもち、独自の運動を展開した創価学会。【「池田大作の軌跡」】潮07・12号 抜粋(つづく)
October 31, 2008
コメント(0)
-
なぜ学会は政治に進出したのか
日蓮主義者の系譜田中智学=日蓮宗から出家、後に還俗して「国柱会」を結成。日蓮宗と国家主義をマッチさせた。「日蓮主義」「八紘一宇」「国立戒壇」のネーミングを残している。政治団体「立憲養正会」を結成し、衆院選に出馬するも落選。信者に宮澤賢治、高山樗牛(文学者)、北原白秋、石原莞爾(軍人、満州事変を首謀)。日蓮宗の井上日召=テロによる国家改造を目指し、テロ組織「血盟団」を結成。蔵相・井上準之助、三井財閥総帥・団琢磨を暗殺。北一輝=二・二六事件の首謀者。妹尾義郎=新興仏教青年同盟結成。社会主義運動を進めた。日蓮主義は右翼も左翼も生み出した。いずれも壊滅的な道をたどっている。「日蓮を用いるとも、悪しく敬えば国が滅ぶであろう」(日蓮の言葉)【「池田大作の軌跡」】潮07・12号 抜粋(つづく)
October 30, 2008
コメント(0)
-
なぜ学会は政治に進出したのか
五・一五事件の衝撃(昭和7年)青年将校による犬養毅暗殺で、政党政治は終焉した。そのまま軍閥政治が到来する。思想統制の暴風の中で、創価教育学会の弾圧が始まる。戸田理事長の戦後の政界「それにしても今の政治は本当に悪い。本当に悪い政治家ばかりだ!」「いずれは、われわれも選挙で戦わねばならぬ時がくる。政治は好きだとか、嫌いだとか、いっておれない段階が必ずくる」「僕は、政治は好かない。だが仏法者の使命であれば、そんなことは言っておれない」「御聖訓を拝し、現代の国家組織を考えていくと、どうしても政界に進出せざるをえないのだ」「いずれ時が来よう。その前に、やらねばならぬことがある」【「池田大作の軌跡」】潮07・12号 抜粋(つづく)
October 29, 2008
コメント(0)
-
なぜ学会は政治に進出したのか
牧口会長と普通選挙立憲政友会総裁・犬養毅はS5・11・18に「創価教育学体系」発刊によせて題辞を掲載している。それほど牧口初代会長の学説に共鳴していた。「創価教育学体系」発刊は弟子である戸田城聖の奔走によるところが大きい。犬養毅の側近・古島一雄は戸田城聖と親しい。古島一雄は創価教育学会の顧問を務めた。犬養・鳩山は創価教育学会の後援組織・創価教育学支援会のメンバーであった。犬養毅と牧口会長。古島一雄と戸田理事長。立憲政友会と創価教育学会。「犬養は、一個の人間に焦点を当てた牧口会長の教育理念に共鳴した。そしてまた古島も、牧口を支える戸田理事長の姿に、青年期から犬養を護り続けた自身を重ねあわせたのでしょう」(犬養毅研究の第一人者・時任秀人、倉敷芸術科学大学教授)【「池田大作の軌跡」】潮07・12号 抜粋(つづく)
October 28, 2008
コメント(0)
-
なぜ学会は政治に進出したのか
「大阪事件」最終陳述・ 宗教を信ずるものが選挙活動をやるのが、なぜ悪いのか・ 我々の選挙支援は、憲法に保障された国民の権利である・ 私は民主主義が続くかぎり、選挙をやる。絶対に勝ってみせる。無罪判決(62・1・25)公明政治連盟結成(62・1・26)「公明党の前身となる政治団体の正式発表である。無罪判決の翌日。まだ検察による控訴の可能性も色濃く残る時点である。公明党結成への本格的な一歩は、大阪事件という一在冤罪事件の中から踏み出された。」公明党。衆議院議員31人、参議院議員21人、地方議会3051人。(2007年10月現在)大企業や資本家、労働組合がバックにあるわけではない。宗教団体を母体に誕生した。日本の政治史上、類例を見ない。それだけにまた、これほど中傷・批判にさらされた政党もない。いまだ人は問う。なぜ学会は政治に進出したのか。なぜ学会は政党を創立したのか。真相に迫る。【「池田大作の軌跡」】潮07・12号 抜粋(つづく)
October 27, 2008
コメント(2)
-
仏法は感傷ではない
「だれが幸福にしてくれるのか。だれもしてくれない。政治も、科学も、幸福を与えてくれない」「不幸な人、虐げられている人が、可哀想だからといって、いつまでも一緒に泣いていてどうなるというのか?それでは、ただの安同情だ。仏法は感傷ではない。大事なのは現実だ。どう宿命に打ち勝つか。どう局面を開くかだ」「私は仏法の指導者だ。相手に同情して、ともに泣くより、どうすれば相手が立ち上がれるかを具体的に考える。それが指導者として『責任を果たす』ことである」「幸せになり切るんだよ。『なる』じゃないよ。『なりきる』んだよ!」【池田大作の軌跡】潮08・11号***************************信心で 師子王心を 取り出だす
October 25, 2008
コメント(0)
-
今一重強盛な志で
日蓮大聖人は、乙御前の母に対して、「これまでのあなたの信心の深さについては、申し上げるまでもありません」(御書1220P、通解)と最大に称えられた上で、「其よりも今一重強盛に御志あるべし」(同P)と、今まで以上に強盛な信心に励んでいくよう、促されています。同じお手紙の続く部分でも「いよいよ強盛の御志あるべし」「志をかさぬれば・他人よりも色まさり利生もあるべきなり」(同1221P)と、一層、信心を奮い起こすよう、呼びかけられています。 ◇日蓮大聖人の仏法は、「本因妙の仏法」です。過去の結果にとらわれたり、また、安住したりすることなく、常に未来に目を向けて戦いを開始する。“今”この瞬間の自身の一念と行動で、将来を主体的に変えていく。――「いよいよ」「これから」と挑戦する姿勢が大切です。日蓮大聖人は、門下に対して何度も「いよいよ」と呼びかけられています。難の渦中にあった四条金吾に対して、「いよいよ強盛の信力をいたし給へ」(同1143P)、「いよいよ道心堅固にして今度・仏になり給へ」(同1184P)、「これに・つけても・いよいよ強盛に大信力いだし給へ」(同1192P)と何度も激励を。また、夫亡き後、子どもたちに信心を教えながら、純粋な信仰を続けてきた南条時光の母には、「いよいよ信心をいたさせ給へ」「なをなを信心をはげむを・まことの道心者とは申すなり」(同1505P)と力強い励ましを送っています。 ◇大聖人御自身、53歳で身延へ入られた後も、8年間で約300編にのぼる御書を執筆され、門下一人一人を激励。御入滅の直前にも「立正安国論」を講義されるなど、生涯、不惜身命の闘争を続けられました。「月月・日日につより給へ」(同1190P)――日々前進の信心を貫いてこそ、真の人生の勝利を得ることができるのです。【「乙御前御消息」学習のために】08・10・1創価新報
October 24, 2008
コメント(2)
-
妙法の実践に励む人を守護
日蓮大聖人は、妙楽大師の「止観輔行伝弘決」(天台大師の「摩訶止観」の釈)の文を引かれ、心が堅固であれば、「神の守り」すなわち諸天善神の守護が強く現れる、と仰せです。 ◇法華経安楽行品第14には「諸天は昼夜に、常に法の為の故に、而も之れを衛護し」(法華経440P)と、諸天善神が妙法を信じ、弘教を実践する人を守護することが述べられています。「元品の法性は梵天・帝釈と顕われ」(御書997P)――私たちの生命に本来具わる仏としての生命(元品の法性)の働きが梵天や帝釈という諸天善神として現れます。したがって、どこまでも私たちの信心が根幹となります。大聖人は、「南無妙法蓮華経と申す人をば梵天・帝釈・日月・四天等・昼夜に守護すべしと見えたり」(同558P)、「身命をおしまぬ法華経の行者あれば其の頭(こうべ)には住むべし」(同1442P)と仰せです。宇宙の根本法則である南無妙法蓮華経の妙法を唱えることで、宇宙それ自体に具わっている善なる働きが現れます。そして、その働きは信心の強弱によって決まるのであり、不惜身命の信心に励むことこそ、何よりも大切なのです。【「乙御前御消息」学習のために】08・10・1創価新報
October 23, 2008
コメント(0)
-
大将軍の信心
「信心」が燃えていれば、全宇宙がその人を守る。「必ず心の固きに仮(よ)りて神の守り則ち強し」(妙楽の言葉)大聖人が繰り返し、引いておられる一句です。「信心の強さによって、諸天が守る強さが決まる」と。信心している人間が「大将軍」になれば、その家来である諸天善神が、元気いっぱいに働く。将軍が――信心が弱ければ、家来は働きません。「つるぎなんども・すすまざる人のためには用る事なし」(御書1124P)です。諸天善神は、広宣流布に「いちばん戦っている人」を、「いちばん大切に」守るのです。 ◇(諸天に頼ったり、すがったりするのでは)弱々しい惰弱な人間をつくってしまう。それでは何のための信仰か。「強き信心」とは、一人立つ精神です。大聖人が「詮ずるところは天もすて給え諸難にもあえ身命を期とせん」(同232P)と言われた。諸天の加護などいらない、命をも捨てようという、その信心にこそ、厳然と諸天の加護があるのです。広宣流布のためなら、何もいらない。その信心に立てば、一切が必ず開けます。仏法は勝負です。勝たねば無意味です。(『池田大作全集』第31巻<法華経の智慧>438P)【「乙御前御消息」学習のために】08・10・1創価新報
October 22, 2008
コメント(0)
-
強き祈りで勝て
御聖訓には仰せである。「ひとたび南無妙法蓮華経と唱えれば、一切の仏・一切の法・一切の菩薩・一切の声聞・一切の梵天・帝釈・閻魔法王・日天・月天・衆星・天神・地神、乃至、地獄・餓鬼・畜生・修羅・人・天界の一切衆生の心中の仏性を、ただ一声に呼びあらわしたてまつるのであって、その功徳は無量無辺である」(御書557P、通解)妙法の音声(おんじょう)は、我らを護る諸天を動かし、全宇宙の仏性を呼び覚ます。日本中、世界中に響くような強い一念で、朗々たる勤行をすることだ。弱々しい勤行ではいけない。また、皆で行う場合、合わない勤行ではいけない。勤行・唱題は仏の音声である。その声は全宇宙に届く。荘厳なる儀式なのである。力強い唱題で、健康・長寿、そして勝利、また勝利の日々を送ってまいりたい。【8・24記念各部合同協議会】聖教新聞08・8・25
October 21, 2008
コメント(0)
-
「人生勝利」の突破口は必ず開ける!
嵐が近づいてくる。リンゴ園を営む青年は、気が気でなかった。暴風雨が吹き募る。丹精こめて育てたリンゴが、相次ぎ吹き落とされていく……。胸が張り裂けそうになった▼やがて、青年は気が付く。同じ木になっているリンゴでも、わけなく落ちるリンゴと、なかなか落ちないリンゴがある。彼は、はっとした。――台風は毎年、来る。それを覚悟せずにリンゴ園を経営するのは、天に甘えているに等しい。嵐が吹いても、落ちないリンゴを作ろう!▼青年は新たな意欲で、営農に取り組む。吹き落とされたリンゴは“被害”と思わず、逆に天の特別の“たまもの”と感ずるようになった。落ちたリンゴはジャム工場に売り、その収益は社会のために使っている――▼東北の一青年のそんなエピソードを紹介しながら、作家の下村湖人は書いている。「非運に処する最上の道は、なんといっても、非運の中に天意を見いだしてそれに感謝することでなければなりません」▼まさに「大悪を(起)これば大善きたる」(御書1300ページ)。それを可能とするものこそ、強き祈りと勇気と希望と執念だ。いかなる苦境にあろうとも「人生勝利」の突破口は必ず開ける。朗らかに、にぎやかに、大感動の朝を目指して!(英)【「名字の言」】聖教新聞07・7・23「聖教新聞」宝さがし「台風は毎年、来る。それを覚悟せずにリンゴ園を経営するのは、天に甘えているに等しい」全くそのとおりだ。「順調に行くのが当たり前、思い通りにことが運ぶのは当たり前」と思うのは甘えの何ものでもない。仏法は、「随縁真如の智」と説く。変化への対応だ。それには柔軟な思考と、強盛なる信心が不可欠。血を吐くような努力が必要なのだ。獅子奮迅 今日も負けじと 前三後一
October 18, 2008
コメント(0)
-
喜んでもらうために会う
リーダーが友のところへ会いに行く。それは「喜んでもらう」ためである。何かを押付けて、嫌な思いをさせるのは、愚かなリーダーだ。我らには、大いなる夢がある。その実現へ、皆が「喜んで、やろう!」と奮い立つ。それでこそ、名リーダーである。久しぶりに会う友も、いるだろう。大事なのは、「喜んでもらうこと」。そのために心を尽くすのだ。私も、いつも、そうしてきた。喜んで題目!喜んで行動!そして喜んで、ともに勝利の万歳をしていきたい。苦難をも喜びに変える。これが仏法である。日蓮大聖人は仰せである。「大難来りなば強盛の信心弥弥(いよいよ)悦びをなすべし」(御書1448頁)何があろうと「すべてが喜び」--これが仏法の根幹である。そうではなく、「すべてが地獄」なら、これほどの不幸はない。それは邪教である。【山梨最高協議会でのスピーチ】聖教新聞07・9・21K地区のO支部副婦人部長さんは、3年前、がんに侵されていることがわかりました。丁度その頃、法戦があり、戦い切って手術に臨もうと決意をされました。迫りくる恐怖と戦いながら、先生の指導を求め、お題目根本にご夫妻で拡大へと走られました。何の悔いもなく戦い切ったあと、手術は大成功。見事、病魔に打ち勝ち宿命転換の実証を示されたのです。この度の法戦も、御本尊様から命を賜ったのだとの報恩感謝の心で、力の限り戦おうと決意をされました。さらなる対話・拡大のため郷里の学校の卒業名簿を頼りに、見ず知らずの方のお宅へ、勇気と智慧をわき出だせながら、毎週土日に6S、T市、T県へと、ご夫妻は自動車で西奔東走されています。その功徳か、ご主人のO副支部長はこの不況の中でも、仕事の受注がどんどん入り、勤め先の社長さんも、「なんで、あんただけに、注文が来るねん?」と驚いておられるそうです。今日も、ますます元気に全国へ飛び回っておられます。同じくK地区のK(婦)副本部長さんは、今回の法戦は一家和楽を願い、家族で戦おうと決意されました。ご主人が何とか活動家になってもらいたいと願い、12日に区民運動会を終えご主人の実家があるS県N市へ。先方から大変歓迎されたそうです。このように、壮年部の活動家作りに婦人部のお力を賜り、本当に感謝しております。本当に有難うございました。
October 17, 2008
コメント(0)
-
成功するよう願い祈る
行動する人は、世の中にたくさんいますが、行動しながら、成果や成功を願い祈る人は少ないものです。結局、最終的には行動しているのに成果を出せている人と、そうでない人の大きな違いの一つは、行動しながら「願い祈る」ことができるかどうかです。なぜだか分かりますか?ただ一生懸命行動しているのと、行動しながら祈っている人とは、一つの大きな違いがあるかなのです。それは何でしょう?一言で言うと「執念」です。願い祈っている人には、目標や達成へのものすごい執念が出てきます。ですから、何度上手くいかなくても、挫折しても、困難に追い込まれても、絶対に諦めません。執念でもって、這い上がってきて行動し続けます。それこそ、最後の最後まで。先に紹介したエイブラハム・リンカーン大統領(何度も落選しても諦めずに大統領になることを目指して、行動し続けた)やカーネル・サンダーKFC創業者(何度も事業に失敗し、大借金を負い、生活保護を受けるようになっても、周りの人の反対を押し切り行動し続けた)がそうです。彼らもとにかく行動しながら、願い祈りました。逆に言うと、やることはやっていたので、後は結果が出るよう、成功するよう願い祈るだけだったのではないでしょうか。まさに「人事を尽くして天命を待つ」思いで。私も今まで生きてきて、必死でしたが、単に行動だけをしていた場合はことごとく失敗しました。強い願い、深い祈りがあったときは、「何が何でも成功するぞ!」「死んでも成功させるぞ!」という凄い執念が湧いてきて、ある種の強烈な「成果を出すぞ!」オーラ、「成功させるぞ!」オーラが放たれ、それを察知した周りの人が、どんどん助けて、応援してくれました。今振り返ってみると、自分ひとりの力ではダメだったのです。いろいろな人の助けや応援があったからこそ、成果も出て成功できたのです。それだけ、願い祈るという行為というのは、威力があるのです。正確に言うと、願い祈っていると、その思いがすごい迫力となって言動に出るのでしょう。それで、周りの人が感動し、ついつい助けてくれるのでしょう。【一流の行動力】浜口直太 著/グラフ社「聖教新聞」宝さがし頑張るといっても、無計画ならば効果は期待できない。戦略的に計画を立て、その計画に則って行動することである。その根本には執念が必要。祈り抜き、智慧を出し、執念の行動を起こす。そこに、成功のカギがある。
October 16, 2008
コメント(0)
-
社会も企業も変化の連続
「世の中に安定している会社なんて、一つもありません。社会が激動しているんだから。日々激戦に勝ち抜くために、どの会社も必死です。発展している会社は常に商品開発や機構改革などを行い、真剣に企業努力をしています。たとえば、食品会社にしても、医薬品の分野に進出したり、生き残りをかけて、懸命に工夫、研究し、活路を開いているんです。どの業界も、食うか、食われるかの戦いです。昨日まで、順調であっても、今日、どうなるかわからないのが現実なんです。大会社に入っても、別会社への出向もあれば、人員整理もある。また、倒産することだってあるでしょう。だから、『この会社に入れば安心だ。将来の生活は保障された』などと考えるのは間違いです」 学生たちは、真剣な顔になっていた。挑戦を忘れ、依存の心をもった人が何人いようが、発展の力とはならない。伸一は言葉をついだ。「就職する限りは、どんな仕事でもやろうと、腹を決めることです。たとえば、出版社というと、多くの人は編集をイメージするが、会社には経理もあれば、営業もある。また、受付もあれば、清掃や営繕を担当する部門もある。有名出版社に入ったとしても、どこに配属されるかはわかりません。また、自分の好きな部署に配属されても、部署は、状況に応じて変わっていくものです」皆、頷きながら話を聞いていた。「社会も企業も、常に変化、変化の連続です。その時に、自分の希望と違う職場だから仕事についていけないとか、やる気が起こらないというのは、わがままであり、惰弱です。敗北です。就職すれば、全く不得意な仕事をしなければならないこともある。いやな上司や先輩がいて、人間関係に悩み抜くこともあるかもしれない。しかし、仕事は挑戦なんです。そう決めて、職場の勝利者をめざして仕事に取り組む時、会社は、自分を鍛え、磨いてくれる、人間修行の場所となります」【新・人間革命 創価大学の章】より
October 15, 2008
コメント(0)
-
負けじ魂
先日、一人の壮年本部長を取材。昨年、会社が倒産。ハローワークに通うも、過去の高い職責が仇に。「こんな私が人を励ませるのか」との弱気に負けじと、学会活動に奔走。半年後、再就職を勝ち取った。その体験を会合で語った。事情を知る友、初めて聞いた友、皆が感動の涙。人知れぬ苦闘を重ねつつも、一切から逃げずに広布の指揮を執り続けた、わが本部の“父の背中”を友は誇らしく思ったことだろう。人生には三つの坂があるという。上り坂、下り坂、「ま・さ・か」。予期せぬ一大事に落胆し、人生の下り坂を転落するか、「ここが勝負どころ!」と奮起し、上り坂への起点とするか。「地域広布の柱」との自覚に燃え、その奮闘の後姿が、無言のうちに、周囲に勇気を与えている壮年部をたたえたい。【「名字の言」】聖教新聞07・6・17付掲載
October 14, 2008
コメント(0)
-
不屈の師子王の生命こそ仏である
「生まれつき耐えられぬようなことはだれにも起こらない」とは、古代ローマの哲人皇帝マルクス・アウレリウスが語った人生哲学である。若き青年の君よ!何があろうが、断じて屈するな!断じて負けるな!前進をあきらめるな!法華経に説かれている「能忍」とは、「よく堪え忍ぶ」という意義を持った言葉である。仏の別名のことだ。つまり、来る日も来る日も、苦難と苦悩に満ちた、この危険千万である娑婆世界にあって、「何ものにも断じて負けない!」という不屈の師子王の生命こそ、仏であるというのだ。熱い涙を流し、苦悩の日々を乗り越え、悲しく歌ったあの日を勝利に変えながら、真実の栄光を、真実の幸福を勝ち取った、汝自身の魂の英雄の姿よ!【随筆 人間世紀の光「大中部に轟く正義の勝鬨 青年が立てば堅塁城は不滅」】聖教新聞04・4・28
October 11, 2008
コメント(0)
-
逆境の時こそ智慧をわかせ!
私もまた、逆境の時こそ、智慧をわかせして、「こういう指針を示そう」「こうやって味方を広げよう」と、人知れず手を打ってきた。ただ一人、悩み抜き、祈り抜きながら。皆が苦しんでいる時に、自分は涼しい顔をして、高みの見物を決め込む。そんな卑劣な傍観者になってはならない。無責任な人間は、敵よりも始末が悪い。【第21回 新世紀本部幹部会】聖教新聞08・9・9「聖教新聞」宝さがし御本尊を信じる。信じて強く祈る。人生勝利の決め手は生命力だ。生命力には、智慧と過ちのない具体的な行動が含まれる。度胸もだ。いや、生命力とはその三つそのものであるといえる。だから真剣に祈るのである。獅子奮迅 今日も一日 前三後一
October 10, 2008
コメント(0)
-
勝利の法則―決め手は生命力と福運
「題目を唱え、真剣に祈って仕事に臨んだ日に、予定外の降ってわいたような商談が、とんとん拍子にまとまる。そんな経験は、数え上げれば切がない。私の“勝利の法則”は、強き祈りです。御書に仰せの『法華経を信ずる人は・さいわいを万里の外よりあつむべし』(1492P)を深く確信しています」 ◇その胸中には、人生の師・池田名誉会長の指針が、深く刻まれている。「必要なのは、現状を正しく分析し、打開の道を見つける『知恵』である。その『知恵』を、どんな局面でも行き詰ることなく発揮していける『生命の力』と『福運』が大事なのである。その源泉が『信心』である」【体験談】聖教新聞08・9・4
October 9, 2008
コメント(0)
-
熱意なくして成功なし
仕事の楽しさは厳しさ乗り越えた充実感今、若い人たちの間には“仕事は面白くやるべきだ”という風潮もあるようだ。確かに楽しく仕事をするのはいいことだろう。しかし、遊びの中にある「責任のない楽しさ」と、仕事から生まれる「責任のある楽しさ」はまったく別のものである。遊びの楽しさを仕事に求めてはいけない。いうまでもなく仕事は地道で厳しいものである。その中で成果を上げようと思うなら、何よりも溢れるような“熱意” がなければならない。絶対に成し遂げてやろうという強烈な熱意があってこそ、その人の才能や知識が十分に生きて、工夫と知恵が生まれる。壁にぶつかっても、「もう少しやってみよう」「あの人に教えを請うてみよう」ということになり、成功を重ねることで喜びが得られ、仕事が楽しくなっていく。すなわち、仕事での楽しさとは、あくまでも厳しさを乗り越えた上での充実感である。その過程はつらく、夜も眠れないことがある。それを乗り越えられるかどうかが勝負の分かれ目で、そのためには、まず、“熱意ありき”なのである。もちろん熱意さえあれば成功するかというと、必ずしもそうとはいえない。しかし、「熱意がなければ成功しない」ということは確実にいえる。さらにいえば、熱意を持って人一倍の努力を続けているものには、たとえその道で成功が得られなくても、捲土重来、次の新しい仕事で成功するといった例がよくある。あるいは、努力している姿を見て、上司から、「その仕事では残念だったが、この仕事は君の能力を発揮するにふさわしい仕事だと思うからこの仕事をやってみないか」と声が掛かり、おのずとチャンスが広がっていく。何も仕事に限らない。熱意なくして成功を望むのは、ガソリンなしで車を走らせようとするのと同じ。私はそう思っている。江口克彦:PHP総合研究所代表取締役社長【部下としての心構え】公明新聞08・8・27
October 8, 2008
コメント(0)
-
「一人」が歴史を変える
「一念」で決まる!一念の決意が人生を変える。「一人」で決まる!一人の行動が歴史を変える。行動だ!動くことだ。電光石火のスピードで勝負だ。恐れていれば何も生まれない。学会も協議しながら動き、動きながら協議する。この阿吽の呼吸で勝ってきたのだ。彼女(世界子ども慈愛センター ベティ・ウィリヤムズ会長)は、対立する「双方の陣営」の家へ足を運び、勇敢に扉をノックしていった。だれが味方に変わるか、わからない。自らの先入観こそが、最大の敵である。一人の心に灯された勇気の炎は、燎原の火の如く燃え伝わった。恐怖は伝染する。だが勇気も伝染する。これが、会長の信念だ。ゆえに、まず「一人」!一人の味方をつくることだ。ピラミッドも、頂上からは建てられない。一つ、また一つ堅固な土台を積み重ねていって、初めて頂点に達する。勝利の金字塔も同じである。まず、零から一を生む。これが勝負の急所だ。「一は万が母」なのである。【世界との語らい】聖教新聞08・9・14「聖教新聞」宝さがし世界恐慌の恐れ…祈りそのものが勝負。決しておろそかにしてはならない。頑張っていれば何とかなる、というのは迷信。なんともならない。自分は自分でしか救えない。信心は、強烈な自己責任の世界だ。だからこそ祈りを根本に、諸天善神を呼び起こすのだ。「信心のこころ全ければ平等大慧の智水乾く事なし」(秋元御書1072P)
October 7, 2008
コメント(0)
-
なおいっそう、強盛な信心を
「前々からの信心の志は、言い尽くせぬほど立派なものでした。しかし、これからは、なおいっそう、強盛な信心を奮い起こしていきなさい。その時は、ますます十羅刹女の守護も強くなると確信していきなさい」(御書1220P、通解)人生には、これまでの壁を破り、生まれ変わったように、立ち上がるべき時がある。今がその時なのだ。その原動力となるのが、強く、正しき信仰である。三世永遠の法則である。大仏法への大確信なのである。過去の壁を破って、決然と立ち上がれ!自分が今いるその場所から!【随筆人間世紀の光 尊き婦人部の皆様に贈る 母を幸福に!それが平和の大道】06・6・10
October 6, 2008
コメント(0)
-
メンターを持つ
人間が最も頑張れる方法の一つは、メンターを持つことです。なぜなら、メンターは最も明確で具体的な目標になりますので、頑張りやすいのです。歴史的にも、メンターを持っている人と、そうでない人の成果の差は歴然としています。やはり単なる数字の目標と、実在する人間の目標では、努力する祭に力の入れ具合が違ってくるのでしょう。 ◇メンターができると、メンターがやってきた以上の行動がとれるよう、挑戦し始めます。成功された方、偉業をなされた方には、本人は気付いていないかもしれませんが、必ず周りにメンター的な存在の人がいます。そのメンターを目指して、どんどん行動し始めるのです。それも、最低限メンターがやってきたことを。メンターの何がすごいかと言いますと、並外れた 行動力を持っていることです。それで、成果を出し、また成功するには、皆が驚くような行動力が必要であることを悟ります。逆に、メンターのように徹底的に行動していけば、成果も読めるのです。【一流の行動力】浜口直太著/グラフ社
October 4, 2008
コメント(0)
-
全魂込めて激励
◆ 証言(西口良三さん)この裁判の時(昭和32年)も、私は車で先生を送り迎えをしていました。いまだに印象深く思い出されるのは、悠然たる先生のお姿です。先生は一歩も引かず戦われ検事の矛盾が、裁判で一つ一つ明白になっていったことがこのときであったのを知ったのは、ずっと後のことでした。私は、先生を車にお乗せし、京都に向かいました。名神高速道路もない時代で、国道1号線といっても、まだ完全に舗装されていませんでした。車の中、先生は御書を出して読まれたり、メモを出して書き物をされたりしていました。思索を巡らされ、メモ帳に何か書かれたりもしていました。ガタガタとゆれ続ける車中でも、先生はずっと仕事をされていたのです。先生は1分1秒も、会員のために無駄にできないと仕事を続けられていたのです。一瞬、バックミラーを見ると、ちょうどメモをかばんの中にしまわれたので、“今がチャンスだ。なにか一言でも先生に指導を頂こう”と思いました。しかし、先生は目を閉じられたのです。休まれるのかなと思いました。違いました。口が動いているのです。題目をあげられていたのです。背筋をピンと伸ばし、毅然たる姿勢でした。普通でしたら、2、3時間たったら足を上げたり、体を横にしたりするところを、先生は全く姿勢を崩されないのです。ひとつの隙もありません。「私は、ただ会員が幸せになること意外、考えなかった」と先生はよく言われています。今、振り返ってみると、先生は若き日より、一貫して、「会員を守るために、根っこになり、屋根になっていく」ことだけを考えながら、行動されていたのです。池田先生は、裁判がどんなに大変でも、会員の中に入られ、激励をしてくださいました。裁判の疲れで、食事をとることもできないこともありました。しかし、先生は、そんな中でも会合に出席してくださいました。私たちは、「先生、今日は早くお休みください。会合は私たちが力をあわせて勤めます。どうかお休みください」と何度も申し上げました。しかし先生は、「大阪の同志が私を待ってくれている。私とともに、広布のために戦ってくれている。大阪の同志が喜んで集まっているのに、私が出ないわけにはいかないよ」と言いながら、会場に向かわれたのです。そして、学会歌の指揮を力いっぱい執られ、皆を全魂込めて激励してくださったのです。まさに、体を張って、命をかけて、関西の同志を激励してくださったのです。【不滅の“精鋭十万”結集!】大白蓮華08・10月号
October 3, 2008
コメント(0)
-
困難と戦う力を自身の中から開発
仏法は、自身の限りない成長をもたらす“生命根本の法則”を解き明かしています。だれ人も無限の可能性が生命に具わっていると説きます。私たちの活動は、この可能性を開発して、現実に直面する人生、生活の課題を乗り越えさせていく原動力を培うものです。「自身の幸福」という意味では、各人に、人生のさまざまな苦悩を乗り越えていく崩れざる幸福境涯を確立させていくのが、仏法の目的となります。◇ ◆ ◇では、どのようにして、このことは可能となるのでしょう。もちろん、仏法の信仰は、単なる気休めではありません。また、気の持ちようで課題を“克服”するものでもありません。自身に備わる力を開発し、引き出し、現実に苦悩を乗り越えさせていくものです。日蓮大聖人は、信仰の様々な実践は、すべて自身の「一念」(=瞬間の生命)に納まる功徳善根であると捕らえています(御書383p)。つまりどこまでも生命を磨き、その可能性を開発していくための仏法であり、そのための活動であるのです。信仰の実践は、具体的には自身の目標を掲げて挑戦していくものです。その途中、数々の困難との格闘もあります。しかし、だからこそ、智慧や勇気という生命に具わる偉大な力を、内面から、さらに大きく引き出していくことができます。あらゆる人に「人間革命」をもたらし、人生の意義をより豊かにする信仰が仏法なのです。【「あなたの学会理解のために」】聖教新聞07・06・16付掲載
October 2, 2008
コメント(0)
-
「臆病にては叶うべからず」
(若き日の日記)「師の下に、巣立つ栄光。世界一の青春。われに悔いなし。われに幸あり。大阪の折伏、断然、群を抜いていく。楽し。上げ潮の関西。油断なく、美事な指揮を執りぬこう」破竹の勢いで、わが関西は勝っていった。このとき学んだ有名な御書をもう一つ、拝しておきたい。「なにの兵法よりも法華経の兵法をもちひ給うべし、『諸余怨敵皆悉摧滅』の金言むなしかるべからず、兵法剣形の大事も此の妙法より出でたり、ふかく信心をとり給へ、あへて臆病にては叶うべからず候」(御書1192P)臆病者では、戦にならない。「勇敢な信心」こそ、兵法の究極なのである。【青年部代表研修会】聖教新聞08・8・8「聖教新聞」宝さがし行き詰ったら原点に戻れ。あれこれ悩み考えても仕方がない。考えれば考えるほど、絶望に行き着く。そのときは、一心不乱の題目だ。「法華経の兵法」とは題目を真剣に唱えることである。湧きいずる 知恵と力は 祈りから
October 1, 2008
コメント(0)
全25件 (25件中 1-25件目)
1
-
-

- 政治について
- 中国人の観光客が途絶えることになり…
- (2025-11-15 16:40:41)
-
-
-
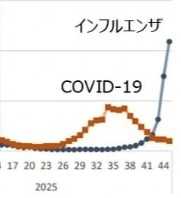
- 気になったニュース
- 抗インフルエンザ薬”ゾフルーザ”に、…
- (2025-11-15 14:06:05)
-
-
-

- あなたのアバター自慢して!♪
- 韓国での食事(11月 12日)
- (2025-11-15 02:35:31)
-






