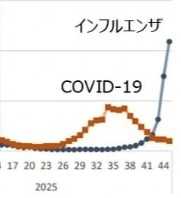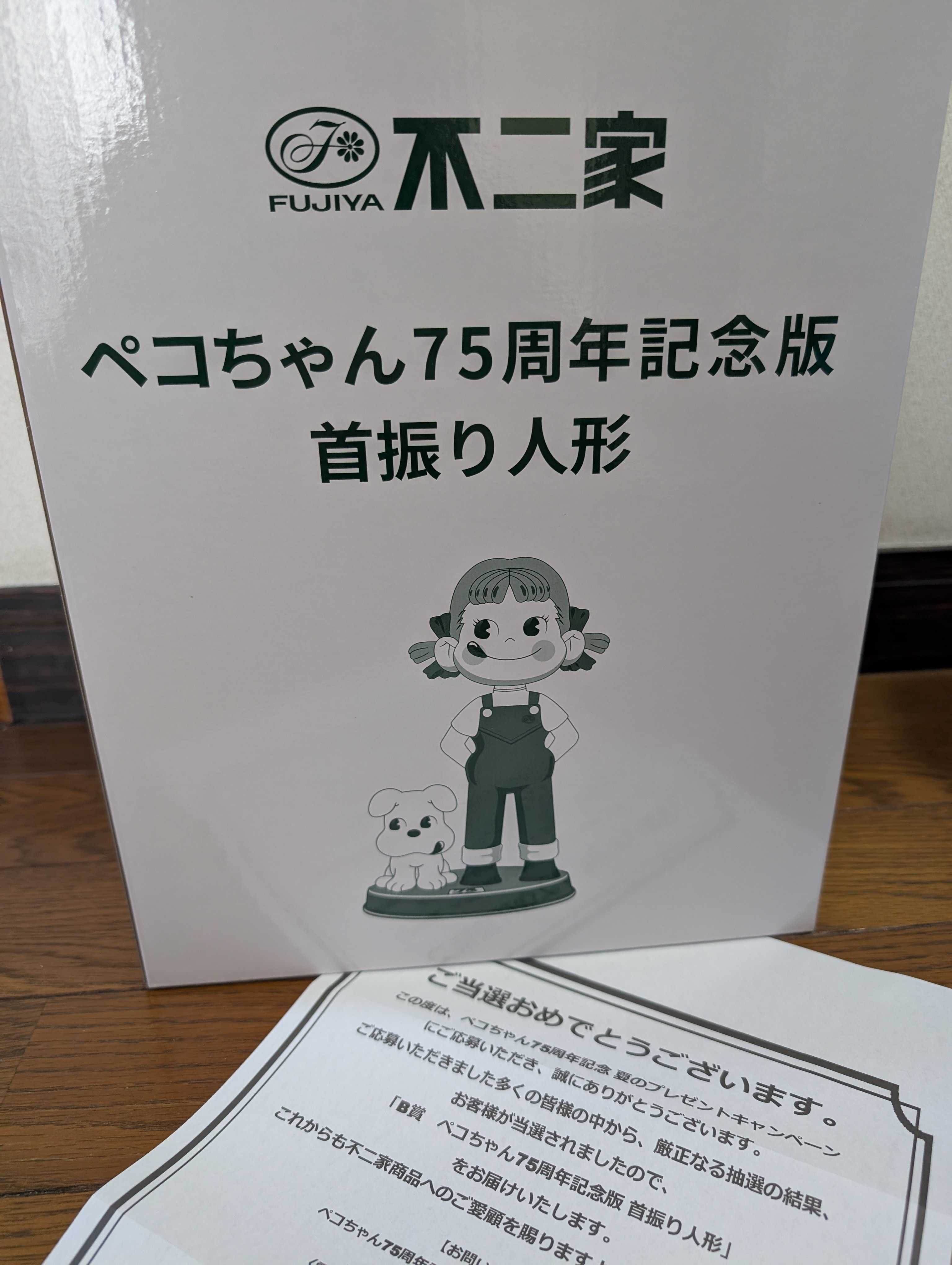2025年01月の記事
全41件 (41件中 1-41件目)
1
-
食肉を培養する
食肉を培養する科学文明論研究者 橳島 次郎環境問題の解決に寄与も昨年6月、ニワトリの細胞から人工的に作られた鶏肉の販売が、米国で初めて認可された。これより前の2020年にはシンガポールで、同じく鶏の「培養肉」の市販が認可されている。本連載ではこれまで、幹細胞からさまざまな臓器や体組織をつくる技術が、再生医療だけでなく、西寧の始まりや生体内の働きを再現し調べるモデル胚やモデル臓器の研究にも使われていることを紹介した。この先端的な細胞培養技術がさらに活躍の場を広げ、食肉を作ることにも応用されているのである。ニワトリの外ウシや、酒などの魚肉の培養の開発も進んでいる。昨年10月にはペットフード用の培養肉がEUで認可されている。私たちが食べる家畜や魚肉は、筋肉の組織である。だから動物から筋肉になる細胞を採取し、酸素と栄養を与えて培養に成形すれば、立派な食肉を作れる。生きた動物を犠牲にせずに食料を得られるのが倫理的な利点となる。また、家畜の飼育、解体処理、輸送の家庭で消費されるエネルギーと排出される二酸化炭素などの温室効果ガスを減らすことができるのも大きな利点とされている。特に牛の商家機関唐らは大量のメタンガスが出る。世界で派出される温室効果ガスの4%が牛のゲップによるという。さらに、牧畜に必要な広大な土地の利用と水資源の消費を少なく抑えられる利点も指摘されている。漁業での乱獲による海洋生物資源の枯渇も防げる。培養肉は、人類の食糧問題と環境問題の解決に寄与できる、有望な先端技術なのだ。普通の動物の細胞を使うので安全性に問題はないとされるが、EUではまだまだ人間が食べる肉としては認可されていない。また培養肉も製造には電力と水を使うので、長期間にみて環境負荷がどれだけ少ないか、わからないともいう。製造過程に高度の技術を要しコストが非常に高いもの短所だ。現状では普通の肉の数倍の価格になるという(鶏肉450㌘で2300円という試算がある)。さらに、安全性だけでなく、畜産労働者の雇用を奪うとの懸念もあって、イタリアの国会は昨年11月に培養肉の生産、販売、輸出入を禁止する法案を採択した。日本でも開発研究を進める大手やベンチャー企業があり、日本細胞農業協会という振興団体もできている。植物性タンパク質で作る代替肉も普及するなか、培養肉を私たちの食卓に受け入れるか、受け入れるにはどのような条件が必要か、議論していく必要があるだろう。 【先端技術は何をもたらすか—13—】聖教新聞2024.1.23
January 31, 2025
コメント(0)
-
誰も置き去りにしない
誰も置き去りにしないこの姿勢こそが今こそ必要能登半島地震の発生から3週間インタビュー 東北大学災害科学国際研究所 栗山 進一所長——東北大学災害科学国際研究所として、「令和6年能登半島地震」が発生した直後から、被災者の命を守るための情報や東日本大震災の教訓を次々と発信されていますね。 「令和念能登半島地震」の被害状況は、13年前の東日本大震災の光景と重なり、胸を痛めています。まずは東北大学災害科学国際研究所を代表し、自信で亡くなられた方々に謹んでお悔やみ申し上げるとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。私たち災害所では、地震発生直後から情報収集や情報支援を行ってきました。具体的には、工学、理学、医学、人文社会科学、情報科学、防災教育実践学など多岐にわたる分野の専門家が学外の関連機関と連携し、地震と津波のメカニズムの解明、被害状況の推計を行い、被災地への正確な情報提供に努めてきました。 低温症を防ぐ——今月9日には、災害研として、被災地調査を行う研究者の状況報告をはじめ、各分野の専門家が過去の教訓や最新の研究を踏まえ、どのような支援が必要となるかを発表する「速報会」を開催されました。正確な情報をいち早く伝えるということが、大きなポイントだと思います。 速報会には、オンラインも含めて2100人を超える方々が参加しました。〝今、被災地では何が起きているか〟〝今後、どのような事態が予想されるか〟に、大きな関心が集まっていると実感します。その上で、どのような支援を行うとしても、まずは正確な情報をもとにしなければなりません。〝東日本大震災経験した東北だからこそできる支援を〟との思いで、被災地の状況を的確に把握しつつ,過去の教訓を踏まえて、必要となる対策等をお伝えしました。中でも、発災当初から訴えてきたのは、被災地が冬の寒冷地であり、「低体温症」を防ぐことです。低体温症とは、代謝によって発生する熱と、体から逃げていく熱のバランスが取れず、体温が低くなってしまう状態のことです。最悪の場合、心肺停止となってしまう危険があります。歯がカチカチと震える譲渡委は、低体温症の初期状態ですので、注意が必要です。特に高齢者の場合は、暖房のある避難所などにいても、在宅避難をしていても、十分に食事が取れていないと、低体温症になる可能性があります。また避難所の様子などを報道で見ても、まだ床の上に直接、布団を敷いていたり、畳の上で雑魚寝をしていたりする状況があります。たとえ布団を敷いていても、冷たい床や畳によって体温は奪われてしまいます。支援が十分届いていない地域もあるでしょうが、成能なら「段ボールベッド」を活用してもらいたいと思います。断熱性能が高い段ボールベッドは、防寒に効果がありますし、高さがある分、高齢者は立ち上がりやすくなります。また、床に落ちた飛沫やホコリなどを吸い込むリスクも減るので、感染症などを防ぐことにもつながります。 デマ情報に注意——白湯を飲んだり、上着の下に新聞紙を詰めたりするだけでも低体温症の対策になると呼びかける専門家もいます。これまで聖教新聞としても、電子版などで「避難生活中の健康を守るポイント」など、被災後の生活で注意する点を紹介してきましたが、支援物資がなかなか届かない地域でも、そうした情報をもとに、一人ひとりが身近なところから対策を取ることが必要だと思います。 まずは、そうした正しい情報をもとに、自分自身の意餅を守るための行動を続けていただきたいと切に願います。その一方、正しい情報を得る上では、フェイクニュースが横行していることも認識しておかなければなりません。災害研では、能登半島地震が発生した今月1日から7日間のX(旧ツイッター)で発信された情報を分析しました。「地震」を含む発信数は250万件を超え、「津波」や「低体温」「能登+透析」「地震+薬」などに注目が集まっていることが分かりました。しかし同時に、今回の地震は〝人為的に起こされたものだ〟と不安をあおる情報も見られ、「人工地震」を含む発信数は7万6000件を超えています。こうした根拠のないデマを流したり、ほかの人と共有したりすることは、同か慎んでいただきたい。またSNSは、そうしたデマ情報が含まれていることも理解していただき、必ず「発信元」を確認し、正しい情報化を確かめていただくことが大切です。 苦しむ人に寄り添うため求められる地域社会の力 関連死への懸念——被災地については今後、どのようなことを懸念していますか。 いわゆる「災害関連死」の増加です。災害による負傷の悪化や、避難生活などによる心身の負担によって命を落としてしまうことですが、2016年に起きた熊本地震では、この災害関連死が自身による直接死の4倍を超えました。地震から助かっても、まだまだ命を落としてしまう危険性があるということです。この災害関連死が起こらないようにすることが、今後の第一の課題です。現時点で心配なのは、狭い車中などでの避難生活で血行不良を起こし、血栓が肺に詰まって肺塞栓などを発症する「エコノミークラス症候群」です。トイレに行く回数を減らすために水分補給を控えるという方もいらっしゃいますが、それでは血流が悪くなり、エコノミークラス症候群のリスクを上げてしまいます。健康を守るためにも、必要な水分は取り、こまめな運動も心がけてください。また、感染症のまん延による肺炎や下痢などの症状や、高血圧や糖尿病などの慢性疾患も心配されます。中には、日頃から服用していた薬を避難生活で中断せざるを得なくなった方もおられるでしょう。これが長期化すると、重大な健康被害を起こすことも懸念されます。「お薬手帳」を持っている方は携帯していただき、被災地を訪れている医療救急班に遠慮なく相談してください。 決して無理せず——被災者の中には、2次避難(※1)で慣れ親しんだ土地を離れることにストレスを感じたり、故郷で仕事を続けることに対し、悩みを抱えたりしている方もいます。生活の再建を急ぐあまり、自分の健康状態を顧みずに無理をする人もいるのではないでしょうか。そうした方々の心身の傾向も懸念されます。 災害関連死の過去の事例では、震災後の疲労などによって心不全や菜園などを発症したり、地震のショックや与信への恐怖が原因で急性心筋梗塞を起こしたりすることが挙げられています。被災地で暮らす方々には、決して無理をしないでいただきたいと思います。災害研では、東日本大震災の教訓のもとに、「災害後のこころの健康のための8カ条」を作成しましたが、その中で強調していることも〝自分を追い込まないようにして休みを取ること〟〝つらいことは一人で我慢しないこと〟などです。自分自身の健康を守るためにも、決して無理をせず、悩んでいることは家族や周囲の人に話し、気持ちを分かち合うことを心がけてください。また、災害が及ぼす影響は、決して一過性のものではありません。東日本大震災の被災地では、家屋の損害の程度が大きいほど、肥満や不眠、喫煙、うつ、産後高血圧症のリスクが上昇することが報告されています。家の再建や仕事のことなど、自分の将来に見通しを持てるかがメンタルヘルスに大きく影響することから、行政には生活再建も含めた一日も早い対策を期待したいと思います。そのほか、被災地の子どもたちに対する継続的な教育支援をはじめ、あらゆる分野で課題が浮き上がってくると思いますので、支援を途切れさせないことが必要となるでしょう。 苦しむ人に寄り添うため求められる地域社会の力 災害弱者に配慮——栗山所長は、速報会で〝誰も置き去りにしない〟という視点が大切だと強調されていましたね。 東日本大震災では、災害関連死の4人に1人が障がい者だったことが分かっています。これは避難生活の中で、障がい者が意見を述べる場がなく、適切な対応を受けられなかったことが原因です。その教訓を踏まえ、「仙台防災枠組2015-2030」(※2)が世界会議をきっかけに、「インクルーシブ防災」の必要性が叫ばれるようになりました。これは老若男女を問わず、生涯がある人のない人も、誰も取り残さないことを目指した防災の理念です。災害関連死を起こさないためにも、この防災のあり方が今こそ大切であると確信します。インクルーシブ防災については、徐々に理解が進んでいますが、まだまだ課題も残っています。熊本地震を経験した育児中の女性へのアンケートを見ても、小学校に避難している時に、「おにぎりを配りますので、並んでください」とアナウンスがあったが、1歳と3歳の子どもをひとりで見ている状況では並ぶことができず、食事が手に入らなかったという声がありました。また今回の能登半島地震の被災地からも、医療的ケアを必要とする方から「周囲も大変な状況の中で、支援や協力を申し出ることに申し訳なさを感じている」との声が届いています。こうした〝災害弱者〟から順番に取り残され、命を落としてしまうのが災害の現場です。まずは、自らの行動や努力だけでは、自分の命を守ることができない人がいることを、周囲の人たちが知ることが重要です。 声に耳を傾ける——そうした配慮が大切とは分かっていても、被災地の最前線では、自分や家族のことで精いっぱいで、他者のことに気を配るのが難しいという状況もあるかと思います。 そうした状況にあることも、よくわかります。だからこそ、まずは支援活動に携わる人や、2次避難先で受け入れる側の人などに〝誰も取り残さない〟との意識を持っていただき、一人一人の声に丁寧に耳を傾けていきたいと思います。私自身、これまでインクルーシブ防災を推進する上で、さまざまなケアが必要な方に、普段の生活や震災の時、何に困ったかなどを聴いてきましたが、話を聞く中で、初めて気付く課題も少なくありません。医療的ケアを必要とする必要とする仙台市在住の20代のある女性と、そのお母さんに話を聞いたときのことです。この女性は、車いす生活を余儀なくされているのですが、人工呼吸器などの必要不可欠な荷物が8個もあり、車いすを含めると90㌔もの重さになることを教えていただきました。そうした状況も踏まえ、これからの災害に備える「特別避難計画」を一緒につくってきましたが、その中で、一番困っている人を守ろうと思って考えた手段や知恵を用いれば、より軽い障がいの人はもちろん、あらゆる人を救っていけることを実感しました。今では、それが〝誰も置き去りにしない〟一番の近道だと信じていますし、そのために必要なことは、それぞれが自分のいる場所で、そうした身近な一人一人の声に耳を傾け続けてくことだと思っています。もとろん、そうしたコミュニケーションは、災害が起こる前も大切ですが、災害が起きてからの方がもっと重要で、今こそ必要になっています。 ——今後、県外でも避難者を受け入れる「広域避難」が進んでいくことが報じられています。身近な人の声に耳を傾ける姿勢は、決して被災地だけの話ではなく、他地域すむ人々にも求められるのではないでしょうか。 「広域避難」などで被災者を受け入れる地域の方々には、一人一人の多様な状況に、少しでも寄り添っていただきたい。その上で、身近な人の声に耳を傾ける姿勢というのは、たとえ被災者を受け入れている地域でなくても、また障がい者が身近にいなくても、必要なものだと思っています。例えば今回、親戚や家族が被災した人が身近にいるかもしれません。また、今回の被災地でなくても、過去の災害での経験がフラッシュバックして、心身の不調を訴える人もいます。そういった意味では、創価学会をはじめとする、様々な地域社会の力が必要です。〝誰も置き去りにしない〟〝苦しんでいる人のために尽くす〟という思想は、創価学会の考え方でもあると認識していますし、現実として人の生きる力を支えていますよね。今こそ、皆さんには、身近な人の声に耳を傾け、悩む人がいれば、気持ちを受け止めていただきたいと思います。立場や役目は異なりますが、私たち災害研としても、被災地の方々のために総力を挙げ、〝誰も置き去りにしない〟支援を続けていく決意です。 くりやま・しんいち 1962年生まれ。医学博士。専門は分祀疫学、災害公衆衛生学。東北大学理学部物理学化、大阪市立大学医学部医学科を卒業。多さは私立大学医学部付属病院第3内科医師、民間企業医師、東北大学大学院医学系研究科環境遺伝医学総合研究センター分祀疫学分野教授などを経て、2012年に東北大学災害課国際研究所災害公衆衛生分野教授に就任。2023年から同研究所所長。 (※1)被災地の避難先から、インフラの整ったホテルや旅館などの安全な場所に移ること。(※2)2015年に仙台市で行われた国連同祭世界会議で採択された、2030年までに災害の被害者数提言などを実現するための指針。 【危機の時代を生きる希望の哲学】聖教新聞2024.1.20
January 30, 2025
コメント(0)
-
スポーツウォッシングとは
スポーツウォッシングとはスポーツライター 西村 章代表例はベルリン五輪皆さんは「スポーツウォッシング」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。東京五輪を控えた2020年ごろから、日本でもちらほらと見かけるようになりました。これは、「スポーツの熱狂によって、人々の関心や意識が社会の問題からそらされている」様子を表す言葉です。簡単に言い換えると、スポーツを使って国家や政権、企業などのマイナスイメージを覆い隠そうとする行為です。皆さんは、日々、スポーツを観戦したりしていることでしょう。でも、手に汗握る勝負の楽しみや体を動かす喜びが、何か都合の悪いことをウヤムヤにするために利用されているとしたら……。そんなスポーツウォッシングについて知ってもらいたく、近著『スポーツウォッシング』(集英社新書)を出版しました。スポーツウォッシングの典型例としてよく取り上げられるのは、1936年のベルリン五輪です。ナチス政権下で、彼らが自分たちのイメージを好転させるために利用した大会として知られています。ヒトラーとナチス政権に対しては、この大会以前から厳しい批判が向けられていました。しかし、大会が始まると、「ヒトラーは胃今日の世界において、最高ではないとしても屈指の政治的指導者だ」「素晴らしい新設、細やかな思いやり、丁寧なもてなしを受けたという印象」などの記事が世界的な大新聞に掲載されるほど効果を発揮したのです。 熱狂・感動の裏に隠される不都合 プレゼンス向上と表裏一体ただ、これほど緻密で露骨でわかりやすいケースは、現実には少ないのが実情です。たとえば、W杯サッカーのカタール大会。スタジアム建設などの過酷な労働環境で、多くの出稼ぎ労働者が亡くなりました。また、地域的に女性や性的マイノリティーに対する差別も根強く、それらの批判から目をそらせるためのスポーツウォッシングではないかと指摘されました。この大会の一面として、スポーツウォッシングの作用があったのは間違いないでしょう。ただ、サッカーは彼らにとっても重要な文化で、スポーツ全般に力を入れる彼らが国際大会を招致しようと思うのも当然のこと。自国の世界的なプレゼンス(存在感、影響力)を向上させたい、という国家戦略と表裏一体なのです。だからこそ、スポーツの熱狂や華やかさのみに気を取られていると、それが覆い隠している問題を見過ごしてしまいます。カタールには、MotoGPの取材でかれこれ20年間訪れています。しかし、建設現場で働く人々がたくさん命を落としている過酷な労働環境の問題を理解したのは、初期取材から10年以上が経過した2010年代中ごろでした。日本のメディアは、中東の出稼ぎの労働者問題や性的マイノリティーの抑圧に対してもともと関心が薄く、W杯開催前から欧州メディアがスポーツウォッシングに批判的検証を行い、参加選手たちも人権抑圧に反対の声を上げていたのに対し、日本ではメディアも選手たちも目と耳と口を閉ざしているように見えました。 知らないうちに忍び寄るスポーツウォッシングの問題は、一筋縄でいかない分かりにくい問題です。でも、何かおかしいなと感じることが第一歩。「スポーツに政治を持ちこんではならない」と、よくいわれています。この言葉の理解について、日本とそれ以外の国々でかなり意識のズレがあるようです。近年、差別や平和問題などに対して、選手たちのアピールが増えています。たとえば、東京語会陰では女子サッカー選手たちが試合前に片膝をついてアピールしました。この行為は差別反対の象徴として、NFLのコリン・キャパニックが始めたものです。人種差別反対の意思表示として国歌斉唱の際に規律せず、片膝をついたのです。また、2020年の全米オープンテニスでは、大坂なおみ選手が黒いマスクで登場。マスクには、警察の人種差別的な暴力の被害に遭った犠牲者たちの名前が記され、BLM運動の支持を訴えたことは、世界的に話題になりました。日本のスポーツ報道は、「競技に感動した、楽しかった」という側面だけをいつも強調します。しかし、そんな結果に一喜一憂している私たちは、実は大事なことから目をそらされてしまっているのかもしれません。東京五輪の際、政治家の中からこんな発言が聞こえてきました。「こんな時だからこそ、五輪を開催すれば、不平不満を忘れてくれる」と。現代のスポーツはまるで古代ローマの〝パンとサーカス〟のように、娯楽で気をそらせて、市民をおとなしくさせる道具に使われているのかもしれません。スポーツウォッシングは、まるでヌエのように、その姿を見抜きにくい存在だからこそ、知らないうちに忍び寄ってきて、気付いたらそこにいるのです。 =談 【文化・社会】聖教新聞2024.1.18
January 30, 2025
コメント(0)
-
郷愁と共によみがえる幼少時代
郷愁と共によみがえる幼少時代作家 村上 政彦チュット・カイ「追憶のカンボジア」本を手にして想像の旅に出よう。用意するのは一枚の世界地図。そして今日は、チュット・カイの『追憶のカンボジア』です。本をきちんと読むためには、作者の経歴を知る必要があります。彼はフランス植民地化のカンボジアに生まれ、高等教育を受けて法科経済大学長などを務める一方、小説の執筆や翻訳を精力的に行っていた。ところが、1970年代半ばにポル・ポト政権が誕生して以降、知識人であることが分かれば生命の危険があるため、偽名で過酷な強制労働に従事。その後、独四阿政権が崩壊しても、同国に表現の自由がないことからフランスに亡命して、タクシーの運転手をしながら小説を書き続けた。重要なのは、カイが本来の居場所とコミュニティーを失ったデャスボラ(離散した民)であることです。彼の出身地であるコンポンチャム州は、メコン川流域の自然に恵まれた風土を持つ。ここで過ごした子ども時代が『追憶のカンボジア』の核になっています。本書の冒頭に置かれた「寺の子ども」は、子どもが寺に住み込んで、僧侶の世話をしながら、読み書きそろばんを習う古くからのカンボジアの習慣に材を取っています。ここでカイは「私」の一人称を使って物語を進める。私と親友のチャイは、寺のタオ先生のところに寄宿している。そこでの生活が描かれるのですが、これがたっぷりノスタルジー(懐かしむ気持ち)を含んでいるたとえば雨季——。「メコン河は大きな海となり、水はありとあらゆる沼や池に流れ込む。(中略)人々はみな道の両側で、竹製の笊やら籠を漁の器具にして、麴漬け用の小魚を掬った。あっという間に大きな笊に半分ほどの小魚が獲れた。ああ、カンボジア! 豊富な魚! 水ある所に魚あり!」この作品が書かれたのは、カイがフランス国籍を得た後です。ディアスボラとなった作者にとって、子ども時代が脳未知なノスタルジーと共によみがえるのは自然なことではないか。人が懐かしいと感じる時には、過去の出来事を美しく化粧し、甘く味付ける。特に異国にあれば、なおのこと。ここでカイが「ああ、カンボジア!」と呼びかけているのは、愛国心からではなく、愛郷心でしょう。人がノスタルジーを求めるのは、現在に満足しておらず、未来の期待をもつこともできない場合ではないでしょうか。タクシーのハンドルを握ってフランスの街を走るカイの脳裏に、子どもの頃の故地が浮かんでも不思議ではない。2作目の「フランス学校の子ども」も、コンボチャムのフランス学校に通う子供たちを描いています。3作目の「かわいい水牛の子」では、ポル・ポト派が登場します。カイは、郷里を蹂躙した人間たちを、どうしても書かずにはいられなかったのでしょう。[参考文献]『追憶のカンボジア』岡田和子訳 東京外国語大学出版会 【ぶら~り文学の旅㊶海外編】聖教新聞2024.1.17
January 29, 2025
コメント(0)
-
〝共に喜ぶ〟って、とても幸せ
〝共に喜ぶ〟って、とても幸せ総神奈川教育部女性部長 陸田 由喜子りくた・ゆきこ 創価大学卒業後、神奈川県川崎市内の公立小学校に勤務し、現在は校長を務め、る。1968年(昭和43年)入会。川崎市在住。支部副女性部長。 〝どの子も安心して楽しく過ごせる学校に〟——昨年4月、小学校の校長に就任するに当たって決めたスローガンです。そのために「自分にできる精一杯のことを」と強く決意して、校長として日々をスタートしました。子どもだけでなく、教員も安心して過ごせる場所にしようと、普段から、学校に関わる一人一人のことを尊重して、どこまでも励ましに徹し抜いています。とはいっても、特別なことは何もありません。まずは朝、昇降口に立って、投稿する児童たちとあいさつを交わし、〝いつも見守っているよ〟と示すところから。すべて、学級担任や、教員として勤めてきた経験の中で教わったことです。これまでの〝宝〟の日々が、今この時に生きていると深く実感しています。 価値を見いだして〝私を本物の教師にしてくれた〟と思える経験をしたのは、教員になって間もない頃。〝学級崩壊〟状態のクラス担任として、どうしていいか分からず、ひたぶるに祈る中で、ふと気付きました。〝自分の辛い状況を、何とかしたいと祈っているけれど、一番つらいのは、子どもたちじゃないか〟当時、問題行動の中心となっていた子は、家庭が複雑な事情を抱えていたのです。「自分のためだけでなくて、子どもたちの幸福のために真剣に祈り続け、なんでもやっていこうと決めたときから、問題行動はなくなっていきました。このクラスは、今でも同窓会を開くほどの深い絆に。中には、私と同じ教育の道を歩んでいる子もいます。私自身が変わり、〝一人をどこまでも大切に〟との心で行動をするようになったことが大きかったのだと思います。特別な配慮と支援を必要とする児童が、多いクラスを担当した時も、子どもの持つ可能性を信じ、励ましの声をかけ続けました。子どもの幸福を願い、関わっていく中で、わたしや保護者も、あっと驚くような成長を見せてくれたのです。時には、「言葉が届かなかった……」と思うほど手ごたえがないまま、子どもたちが卒業を迎えたクラスも。けれど後に、その子どもたちが高校を受験したタイミングで、「先生の言葉を糧に中学校では、生徒会を頑張りました」「先生に迷惑をかけちゃったから、高校にちゃんと受かったことを報告に来ました」と驚きの言葉が。〝こちらの励ましの言葉や子どもたちを信じる心は、絶対に伝わっている〟〝子どもはみんな伸びようとしている〟と確信した瞬間でした。また、子ども同士の関りも、教育においては重要です。クラスメートの関りのおかげで、教室が安心できる場所になった例も、実際に多くありました。そういう温かな人間性を育むのも、教師の声かけ一つから始まると思います。子どもは本来、本当に素晴らしい考え方や、優しい性格を持っているけれど、時分では絶対に気付いていないことが多いのです。大人の声掛けが大事なのです。校長として現在、すべての学級を訪れて授業の様子を見守ることに注力しています。子どものノートを除きながら、「これってすごく良いアイデアだから手を挙げて、発表してみたら」などと伝えると、子どもは「え、そうなの?」と言いながら、うれしそうにしています。子ども同士のやりとりの、ふとした瞬間にも、「今、〇〇ちゃんのことを考えて行動できて、えらかったね。優しかったね」と、その価値を見いだしてあげることで、自信が育まれていきます。この「ふとした瞬間」に、適切に言葉をかけてあげることは、とても難しいことです。何が一番良い言葉なのかをゆっくり考えてしまって、時を逃しては、子どもに伝わらないからです。とっさの瞬間に、子どもの気持ちを正しく捉え、一番、子どものためになる言葉をかけてあげられるよう、教師自身が常に自分の生命を磨き鍛える人間革命が欠かせないと実感しています。池田先生の「子どもにとっての最大の教育環境は教師自身」との指針の通りです。 心と心の〝橋渡し〟さらに、子どもを大きく育んでいくには、他者との心も結びつきも大事です。地域の野菜農家の方がSDGsを教えてくれる特別事業を行い、その方の作った野菜が給食に出たり、「まち探検」で商店街を訪れたり。身近な人との結びつきが強くなった分だけ、「その人のために、地域のために、何か自分の力を使いたい」と子どもは感じるようになります。実際にゴミ拾いや、小さなバザーの開催などを通して感謝の声をかけられると、とってもうれしくなって、もっと地域が好きになっていきます。〝自分も地域のために、人のために力になれる〟と自信がつきます。これって、「世界平和」の第一歩なんじゃないかと思うんです。「『喜』とは、自他共に喜ぶことなり」(新1061・全761)の御文の通りです。「自分だけでなく他者と共に喜ぶことって、とても幸せなことなんだ」と、子どもたちに感じてもらいたい——そう強く願いながら日々の挑戦を重ねています。子どもたち、教職員、保護者と地域の方々、関わる全ての人同士、〝橋渡し〟をして、人と人とのつながりを強めていくことが、校長としての私の使命です。池田先生が〝最後の事業〟と言われた教育に、長年携わらせていただいたことに感謝でいっぱいです。先生が願われた「子どもの幸福のための教育」の実践に、これからも取り組み続けていきます。 陸田さん教えて小学校生活を充実させるため、親にできることはありますか?まずは、睡眠・食事・排せつといった生活のリズムを整えることです。たっぷりと寝て、朝ご飯をしっかり食べて、排せつも終えて、学校へ。これが、お子さんのやる気や集中力、心の安定につながります。また、宿題や翌日の準備をする時間を決めるなどの習慣を身につけさせることも、学校生活の事実のためには大事です。とはいえ、今は共働きのご家庭も多く、完璧にリズムをつくるのはどうしても難しいこともあるでしょう。そういう場合も、窮屈に考えなくて大丈夫です。一番大事なのは、日常生活や学校での出来事を、親が子どもと一緒に驚き、喜び、楽しむことです。「ありがとう」「いいね」「うれしいね」「えらかったね」「おもしろいね」という〝あ・い・う・え・お〟を意識しましょう。それでも不安や心配があるときは、気軽に担任の先生に相談してみてください。 【紙上セミナー励ましの校長先生】聖教新聞2024.1.16
January 28, 2025
コメント(0)
-
死生観を問う
死生観を問う島薗 進著日本の文芸から掘り起こす東北大学教授 佐藤 弘夫評人は死を運命付けられた存在である。時間の経過に伴って、故人の物理的な痕跡は完全に消滅する。しかし、人は死者を忘れることはない。なぜ私たちは、亡き人の面影に触れるべく虚空に指先を伸ばし続けるのであろうか。なぜ避けようのない自身の死に、これはどこまで思い悩むのであろうか。本書の著者である島薗進氏は、長年にわたって東京大学で教鞭をとってきた。我が国における死生学研究の第一人者である。本書では、古代の記紀神話・『万葉集』から、鴨長明・西行・芭蕉・夏目漱石を経て、現代の若竹千佐子にいたる、数多くの文芸作品が取り上げられる。それらの作品を素材として、作者がどのように死と向き合い、いかにして死後の安心を確立していったかを考察していく。自在に過去と現在を行き来し、時には杜甫の詩や『ルバイヤード』などの海外の作品に触れながら、伝統的な日本列島の死生観を掘り起こそうとする著者の旅は、単に時間を遡るだけの旅路ではない。著者はこれらの心の琴線に触れる作品を通じて思索を深め、内面の一番深い部分に垂直に沈み込んでいこうと試みる。その意味において、本書はみずからの「魂のふるさと」を求めて彷徨を続けた。著者自身の心の旅の軌跡である。これまで禁欲的な実証研究に徹してきた著者が、あえて封じてきた生の肉声が時おり行間から響いて、読者の内面と共鳴する。いま日本では伝統的な家の解体や単身世帯の増加など、家族の在り方が大きく変貌している。葬送儀礼と墓の形態も歴史的な大転換を迎えている。かつて人々に共有されて死後の安心を生み出していた時代の死生観が、今日失われてしまった。著者は、誰もが「自身の死生観」を探求しているところに近代という時代の特色があるとする。今私たちは、手探りで自らに安心をもたらす死生観を求めなければならない時代になった。本書はその旅を始めようとする人にとって、格好のガイドブックとなるに違いない。◇しまぞの・すすむ 1948年、東京都生まれ。主教学者。東京大学名誉教授、上智大学グリーフケア研究所前所長。NPO東京自由大学学長。主な研究領域は、近代日本宗教史、宗教理論、死生学。 【読書】公明新聞2024.1.15
January 27, 2025
コメント(0)
-
政党助成金とカルテル政党
政党助成金とカルテル政党浅井 直哉著政党の利害が一致した90年代の政治改革慶應義塾大学名誉教授 小林良影 評1990年代の政治改革の際に、政党や政治家個人に対する企業・団体の政治献金を制限する代わりに公費による政党助成金が導入された。しかし、政治改革関連法案では政治家や候補者が支部長を務める政党支部への企業・団体献金を認めることになり、実質的には以前と大差ない状況である。また、企業・団体によるパーティ券購入が抜け道になるなど、90年代の政治改革の不十分さが露呈している。従来、政党については、議員や名望家から資金を調達する「幹部政党」と党員から徴収する党費と支持団体による献金が主体となる「大衆政党」に分けられ、さらに総花的な政策を掲げて幅広い支持層の獲得を目指す「包括政党」があるとみられていた。これに対し、リチャード・カッツとピーター・メアは、本来、政策が異なり対立状況にある政党同士の利害が一致することでカルテルを形成する「カルテル政党」があると指摘した。本書は、このカッツらの指摘が日本に妥当するのかどうかを政党助成金の獲得に焦点を当てて検証し、政党助成金を巡り日本の政党の利害が一致して「カルテル政党」という構図が見られることを明らかにした。具体的には、政党助成金の要件を現職国会議員5人以上か、前回の衆院選あるいは前回ないし前々回の参院選の得票率2%以上とすることで、既存政党の分裂や離島など現職議員による新規政党は政党助成の対象になっても国会外の近畿政党は対象とならない点で、既成政党の利害が一致しているさらに、政党助成による交付額を各党の将収入の3分の2までとする上限規制について、政党助成以外の収入が少ない社会党とさきがけによる規制撤廃の意向を受けた自民党が政権維持を優先して自社さ政権で撤廃したことも、政党間利害の一致による「カルテル」であると著者は指摘する。また、著者は政党助成制度導入後の各党に財務を詳細に分析し、公明党は事業収入が年間収入の大部分を占めて安定的な資金構造を有する政党であることから、自民党や民主党のように政党助成への依存度が高い政党とは区別している。なお、最近の選挙における投票率の低下が著しい。政治に対する有権者の信頼を回復するためには、政党同士が自分たちの利害のためにカルテルを結ぶのではなく、政治改革の本来の趣旨に立ち返り、お金がかからない「きれいな政治」を実現するためのカルテルを結んでもらいたい。具体的には、透明性確保のためにすべてのパーティ券購入を銀行振り込みにしたり、購入者の公開基準寄付と同じ5万円超までに引き下げたり、法令違反があれば会計責任者だけでなく連座制で政治家も罰する法改正が必要であり、そのためのカルテル実現のために、ぜひとも先頭に立って改革を進めてもらいたい。◇あさい・なおや 1990年、東京都生まれ。日本大学大学院法学研究科博士後期課程修了。博士(政治学)。日本大学法学部特別助教を経て、日本大学法学部専任講師。 【読書】公明新聞2024.1.15
January 27, 2025
コメント(0)
-
▼「八紘一宇」と日蓮主義
▼「八紘一宇」と日蓮主義中島 まず、昭和の全体主義に対する影響力という点で見た場合、伝統仏教の中で戦前に最も多く力を持ったのは、日蓮主義だと一般に言われています。天応崇敬を掲げる超国家主義的な変革運動の指導者の多くが、日蓮主義の影響を受けているからです。日本を中心に世界統一を目指すという、あの「八紘一宇」という言葉も日蓮主義の国柱会から出てきたものです。 島薗 「八紘一宇」は「世界を一つの家にする」という意味です。もともと「八紘」は八つの方位、すなわち世界を意味する言葉として古代中国に用いられたものですが、黒柱会の創始者・田中智学が『日本書記』から転用して、一気に広がりました。「八紘一宇」の理想のもと満州事変を起こした石原莞爾も国柱会の田中智学との関りが非常に強かった。では、この日蓮主義と超国家主義の関係を中島さんがどう見ているのか、そこから議論を始めましょう。 ▼ふたつの『超国家主義』論——丸山眞男と橋川文三中島 日蓮主義と超国家主義の関係を私が考え始めた時に、導きの意図になったのは橋川文三の議論でした。ここでは丸山眞男と橋川文三による分析を対比しながら、説明させていただきます。丸山は『超国家主義』を「極端なナショナリズム」と解釈しています。彼は明治期の健全なナショナリズムが大正デモクラシー後に帝国主義的なウルトラ・ナショナリズムへと変容したことを強く非難しました。第一章で『一君万民ナショナリズム』を説明した際にも触れましたが、健全なナショナリズムは「国家は独裁者や一部の特権的な政治家のものではなく、国民のものである」という国民主権の理念とリンクしています。国籍をもつ国民はすべて平等な主権者であるという主張は、管理要求としての「下からのナショナリズム」とつながっているわけです。しかし、丸山は言います。明治期のナショナリズムは、大正・昭和と時代が進むにつれゆがんだものに変容し、「超・国家主義」という極端な国家主義になってしまった。つまり、自由民権運動のような「下からのナショナリズム」ではなく、国家が民衆を支配する「上からのナショナリズム」が肥大化し、アジア諸国への侵略的な植民地主義へと発展したのだと。 島薗 その丸山眞男の『超国家主義』論に異を唱えたのが、橋川文三ですね。彼は丸山眞男のゼミで教えを受けていたわけですが。 中島 そうです、「長」という文字には、「極端な」という意味だけでなく、「~を超えて」と使われるように「超越する」という意味もありますよね。橋川文三の見方によれば、戦前の「超国家主義」は、「超国家・主義」つまり「国家を超える主義」「国家を超越する主張」なのです。丸山眞男が言うような「極端なナショナリズム」というだけでは理解できないと分析するのです。その橋川が「昭和維新試論」をはじめとする超閣下主義論で取り上げたのが、一九二一年に当時の財閥を代表する安田善次郎を暗殺してその場で命を断った朝日平吾、そして一九三一年に関東軍参謀として満州事変を実行した石原莞爾、一九三二年の血盟団事件を起こした井上日召、一九三六年の二・二六事件の首謀者である国家社会主義の北一輝でした。そこで橋川が指摘したことは、彼らはみな、非常に深い煩悶、悩みを持った新しい世代の青年たちだったということです。この青年たちは、宗教や文学、あるいは哲学に主体的な関心を持ち、自己の解放と結びつくと、国家を超えたなにかと一体性を求めるような思想となる。つまり、煩悶青年たちが人生論的な斑紋を乗り越えるために、国家を超えた形で宇宙と一体化するというイデオロギーとして出てきたのが超国家主義であって、昭和の全体主義もその一環として見直さなければ解けないのではないかと言ったのです。 島薗 そうした煩悶青年たちの始まりについて、私は第二章で話をしてきたわけですね。 中島 丸山眞男よりも、橋川文三の議論の方が戦前の超国家主義の本質をとらえていると私は考えています。ただ、丸山と橋川ふたりの議論を重ね合わることで、ナショナリズムと宗教の相乗効果を読み解けるのではないかと思うのです。まず、橋川が指摘するように、超国家主義の土台には、自我をめぐるナイーブな斑紋が存在しました。彼らは価値のある生き方を求めるがあまり、個を超越した存在と一体化し彼らを宗教へと導いていくわけです。 島薗 スピリチュアルな生き方を追い求めるわけですね。 中島 そうです。そのときに、国体というものが、理想的な価値をもつものだと感じられる。したがって、国家と同化するということは、自己を解放し、崇高な理想に自分自身を溶け込ませていくことになるわけです。さらに、そのような理想的な国家は、普遍的価値を浴びることになります。そこに、「国家」から「超国家」へと拡張していくロジックが生まれる。つまり、究極の国家主義は、理想的な国家によって人類を救済する「超国家主義」となるわけです。 ▼超国家的な力で国家を救済しようとする日蓮宗島薗 今のお話を伺うと、日蓮主義のほうが、橋川の言う超国家主義と親和性が高いように感じますね。外への拡張主義という意味での「超」は、幕末以降の日本が尊王攘夷から開国に転じ、西洋の白鳥主義にならって尊王植民地主義となったと考えるとしっくりすると思います。国家神道がそのまま中華思想的な拡張主義に向かうということです。しかし、それだけでは思想的に弱いので、普遍主義的な宗教思想を取り込んでいく。ちょうどキリスト教が植民地主義を後押ししたのと同じように、です。もちろん、親鸞主義も日蓮主義も、丸山的な意味での超国家主義、つまり極端な国家主義のほうへ傾斜していった側面はあります。潜在的には親鸞主義も日蓮主義も、国家主義と対立する要求はあったはずなのですが、親鸞主義の場合は、個人の内面性を尊ぶということが国体論との緊張関係をなくし、むしろ国体論に乗っていくものになっていくものになってしまった。いわば、内面中心主義的な思想が、国体論と結びついていった側面が強いと思います。一方、日蓮主義について言えば、日蓮主義にはもともと国家救済のヴィジョンがあるんですね。たとえば、日蓮自身が元寇の危機に察して、法華仏教による国家救済を唱えました。しかし、超越的な力によって国家を秀才するヴィジョンが日蓮主義にあるということは、国家をも超越する力の存在を見ているということです。つまり、橋川文三の言う「国家を超える」意味での「超国家主義」ともつながりやすい親和性がある。田中智学の「八紘一宇」は中華思想的な発想による「世界を一つの家にする」という意味だと申し上げましたが、これが日蓮仏教的な「国家を超える」と重なる。だから、橋川的な意味での超国家主義と日蓮主義はとても近いですよね。 ▼人生論的斑紋が超国家主義へと接続する回路中島 私の考えでは、評論家・高山樗牛が田中智学の日蓮主義と出会ったことによって、人生論的煩悶が超国家主義へと接続する回路が誕生したと思うのです。 島薗 高山樗牛は、煩悶青年の先駆けのような人物ですよね。 中島 はい、一八七一年生まれですから、藤村操たちよりも少し世代が上ですが、若き日の高山樗牛は、立身出世願望に突き動かされながら、一方で世俗的欲望への嫌悪に苛まれ、苦悩しながら、文学にのめり込んでいった。自我の苦悩を抱え、暗中模索する彼にとって、文学による自然との一体化こそ求めるものだったわけです。 島薗 藤村操や三井甲之と同じ思考ですね。 中島 高山樗牛は東京帝国大学に入学すると、当時、大ブームだった、ハーバード・スペンサーの社会進化論に傾倒していいます。社会進化論では、人間社会も理想的な姿にむかって進化するといふうに考えます。自然は未来に向かって進化している。自然の一部である人間も、その法則に従って進化し続ける。人間は自然と一体化することによって、世界を思想化することができるのだと。高山樗牛は、このような煩悶青年の先駆けたちは、社会進化論を通して「苦悩からの解放」と「世界の有機的統一」を重ね合わせる思考様式を作り上げていったのでしょう。彼らにとって、自己の解放は世界の解放と直結していたわけです。低大卒業後、評隣家となった高山樗牛が最後に傾斜していったのが田中智学の日蓮主義です。彼は智学の思想に同化していきます。そこで見出したのが「超国家的大理想」です。事故と背海外低下し、一つの宗教的理想のもとに世界が統合されるヴィジョンこそが、高山樗牛の至った最後の境地でした。 ▼法華経と国体の一体化を説いた田中智学島薗 高山樗牛が出会った田中智学は、近代日本の仏教史を見るうえで、最重要と言っていい人物です。二人が出会ったのは一九〇〇年頃でしたよね。 中島 実際に面会したのは一九〇一年ですね。田中智学が「宗門之維新」を広く問うた年です。 島薗 だいたい教育勅語が発布されて、一〇年がたったころですね。歴史区分の第一期の終わりにあたりますが、そのころになると、すでに国家神道は正統的なイデオロギーとして地位を確立していました。他の社会制度が整ったこの時期に、国家神道のシステムもできあがったのです。したがって、仏教は「私的な信仰」という限定的な領域だけで活動を許され、最終的には国家神道に協力するという姿勢をとらなければならなかったのです。この時期以降、宗教的信仰を国家社会の発展や変革のヴィジョンと結び付けるには、信仰を国体論と結びつけることが不可欠になります。田中智学は、まさにそうした課題に積極的に臨んだ人物でした。若き日の田中智学の主張は日蓮宗と日本仏教の革新というところにありました。彼は生ぬるい宗門の体質に失望して、還俗して在家として日蓮宗を広める運動に取り組んだ。たとえば、先ほどの『宗門之維新』では日蓮宗を変革して、世界を救済するという意気込みが語られるわけです。ところが、一九〇二年の講演会や体系的教学講義で国体論を取り入れるようになります。(『世界統一の天業』『本化妙宗式目講義録』)。そこからだんだん国家神道のほうへ向かっていき、一九一四年に法華経と国体との一体を説く「国柱会」という団体をつくる。 中島 田中智学は国体論への傾斜を強めていくわけですね。そのことの彼のイデオロギーの特徴は、法華経とか、日蓮遺文の中に国体論的なものを読み込んでいくということにありました。たとえば、末法の世に出現する上行菩薩を天皇だと言ってみたり、法華経の中の「転輪聖王」や「賢王」といった存在を天皇と同一していくわけです。こうしたイデオロギーに基づいて、田中智学が組み立てたヴィジョンにも、社会進化論的な発想が色濃く感じられます。たとえば、彼は非常に発展段階論的な思考様式をとっています。まずは在家信者によって新しいグループがつくられ、そしてそれが本体の日蓮教団を大きく揺り動かしていく。されにしれによって国民が日蓮思想へと感化され、その延長線上に天皇が日蓮主義へと改宗し、国立戒壇、つまり国家によって仏門に入るための戒律を授ける壇が建立され、日蓮主義国家が誕生する。まさに発展段階論的なヴィジョンです。 【愛国と信仰の構造「全体主義はよみがえるのか」】中島岳志・島薗進著/集英社新書
January 26, 2025
コメント(0)
-
「同和」に名を借りた血税の食い荒らし
「同和」に名を借りた血税の食い荒らし〈不可解な支援はまだある。融資返済期限の九一年、愛食は食肉卸売市場に併設して「中部食肉部分肉流通センター」を立ち上げた。総事業費は約四十五億三千万円だった。愛知県と農水省の外部団体・畜産振興事業団は事業費の六一パーセントに当たる約二十七億八千万円をこれに補助した。フジチク・愛食が二十四億円の融資を返済していないにもかかわらず、愛知県はさらに巨額の補助金を出したわけだ〉俗にいえば、「泥棒の追い銭」だが、フジチク・愛食はもちろん、県や畜産振興事業団に、顕著なのは公金意識の欠如である。推察すれば、こういう論理になろう。原資は国民の血税であり、輸入牛肉に課した関税である。担当者の懐が痛むわけでなく、うるさ型を寄こせというなら口封じや関係改善のため、くれてやる。経済的に差別を解消していく一助になるという大義名分もつくことだし、無利子融資や補助には所得の再分配といった機能がある。誰であれ、カネをつかめば使う。つまりは経済的な波及効果がある以上、誰に公金をバラ撒いてもよい。バラ撒くことの罪は少ない。他方、公金をもぎ取る側は、先祖代々差別されてきた、これまでに差別をされた分を自分の代で取り戻して何が悪い、取り戻したために、誰か被害者が出るか、どこにも被害者はいない、と考える……。おそらくはこうした論理が「逆差別」や新たな社会的不公平を生み出してきた。しかしハンナン・フジチクグループの場合、カネは還流して反社会性の強い暴力団をも養うことになった。最大の被害者は金の出し手である国民であり、県民であるわけだが、国民の多くは納税者意識が薄く、税の多額さや使途に無関心である。〈二〇〇一年六月、名古屋市は市内食肉市場の統合を図った。史には市が出資する第三セクター「名古屋食肉市場」(藤村勲社長)が別にあった。個々の社長はフジチク社長・藤村芳治の親族である。名古屋市は五十九億二千万円を支払い、フジチク系の愛食から卸売業務など営業権を買い取り、社員も一部引き受けた上、名古屋食肉市場に統合した。が、愛食は倉庫業を主に存続している。同社は依然、愛知県から引いたカネを返済していない。高度化融資が二十四億円、県と畜産振興事業団からの補助が二十七億八千万円、食肉地方卸売市場の買い取りに五十九億二千万円、計百十一億円が愛食に流れた〉こうした金はどう社会に役立てられたのか、単にフジチクを富ませたに過ぎないのではないか、と誰しも思う。ハンナングループにおける松原食肉市場の統合と同じ構図がどこにも見られる。同和に名を借りた公金のバラ撒きであり、公金の食い荒らしである。 【食肉の帝王・同和と暴力で巨富を掴んだ男】溝口 敦著/講談社+α文庫
January 25, 2025
コメント(0)
-
声を上げよう
声を上げよう作家 伊東 潤2023年は国内外を問わず波乱の一年だったが、24年も能登半島大震災という辛い幕開けとなった。経済面でも、今年は中国経済の大減速は不可避で、日本もそのあおりを食らう公算が大だ。さらに長引くウクライナ戦争の終わりがいつ見えるのか、ガザ地区の戦争は沈静化されるのか、こうした世界的混乱が台湾海峡に波及しないかなど、心配は尽きない。こうした中、これからの日本をどうすべきか、中長期的視点から考えるべき時が来ていると思う。無力な一個人にとっては、生活防衛の方が大切かもしれない。しかし世界平和あっての生活だということを忘れてはならない。一人ひとりが世界情勢に関心を持ち、非道な権威主義国や深刻な環境問題に声を上げていくことで、政治をまっとうなものにしていくのだ。つまり一人ひとりがサイレント・マジョリティーから脱し、声を上げることで、世の中を変えていくべきなのだ。国内政治の腐敗も行き着くところまで来てしまった感がある。国民が声を上げないから派閥政治はいつまでも続き、能力重視ではなく、人間関係や派閥の論理によって大臣が決まるという不条理が、今でも罷り通っているのだ。もはや国内外に待ったなしの状態となっている。こんな時だからこそ、一人ひとりが強い意志をもち、悪いことには悪いと言える日本にしていかねばならない。残念なことだが、国内外を問わず、今年は良い年にはならないだろう。それでも一人ひとりが世界の一員という自覚をもって声を上げることで、希望ある未来が開けてくるに違いない。今こそ利他を重視していく時なのだ。今年が、そんなきっかけとなる年になることを切に願っている。 【すなどけい】公明新聞2024.1.12
January 25, 2025
コメント(0)
-
博物館経営を考える
博物館経営を考える追手門学院大学教授 瀧端 真理子非営利と相いれないNPM居場所機能を強化し利用者増を昨年は国立科学博物館のクラウドファンディングで、博物館がまさかこのような経営難に陥っているとは、との声も聞かれたが、日本の博物館は世紀が変わる頃から財政的に厳しい状況に置かれていた。高度経済成長期以降の博物館の設置運営状況を概観してみよう。1970年代には日本列島改造論、第三次全国総合開発計画のもと、全国各地に博物館が建設された。86、87年度には円高不況を克服するために大型補正予算が組まれ、内需を中心に日本経済は回復し、バブル景気が発生した。88年に自治省は「ふるさと創生」の一環として、「地域総合整備事業債」の仕組みを作り、各地でこれを活用した大型の博物館が誕生した。91年のバブル経済崩壊後、95年の阪神淡路大震災による財政出動などを経て、日本の財政は主要国中最悪の水準となった。96年には行政改革会議が設置され、翌97年、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI法)が成立、99年には独立行政法人通則法が制定された。2001年には東京、京都、奈良の国立博物館3巻を統合した独立行政法人国立博物館が設立され、また、国立科学博物館は独立行政法人国立科学博物館となった。2003年には地方自治法改正により指定管理者制度が導入された。PDI、独立行政法人、指定管理者制度に通底するのはNew Public Management(NPM)と呼ばれる手法で、これはアングロサクソン諸国で行われた行政改革の背景理論である。日本では「官から民へ」の掛け声のもと、市場メカニズムの活用が求められた。博物館を含む大型公共施設建設の際にはPFIの導入が検討されるようになった。PFIは民間資金の主導によって効率的に公共施設を作り、運営しようとするものである。公立博物館では指定管理者制度の導入が進んでいるが、この制度は、地方公共団体が議会の議決を経て指定した団体(民間事業者を含む)に「公の施設」の管理運営を行わせるものである。21年度文部科学省「社会教育調査」によれば、公立博物館(類似施設を含む)の30%で指定管理者制度が導入されている。指定管理者制度には期間の定めがあるため、長期にわたる賃料の収集や展示企画、利用者との長期的な関係構築が保証されず、学芸員の継続雇用も困難である。一方、独立行政法人化した国立間では運営交付金が減らされ、自前で稼ぐことを求められ、光熱費の上昇に対応できない事態に追い込まれたのである。永続性と公開性を特徴とし、国際的に悲哀力感と定義される博物館の運営はNPMとは相いれない部分が多く、政策的な見直しが必要である。また数多く設置されてきた公立博物館は、人口減少と高齢化の進行中、地域での居場所機能を強化することで利用者を増やし、税金で支えられると同時に、付帯事業収入と寄付を館が直接収受できるよう、国は制度改革を行うべきである。(きたばた・まりこ) 【文化】公明新聞2024.1.12
January 24, 2025
コメント(0)
-
よみがえる廃校舎
よみがえる廃校舎面影残し、第二の人生往時のよさを見直し児童や生徒の減少に伴い全国で廃校が相次ぐ中、リノベーションを施し第二の人生を送る「元学校」がある。かつて子どもの声が響いた学びやは、地域時移民や観光客らが集う交流の場として新たな役目を担っている。神戸市兵庫区の北部、平清盛が居を構えたとされる古くからの住宅街に2022年7月にオープンした複合施設「ネイチャースタジオ」。旧市立湊山小学校を地元企業が回想し運営する。山や川に近く、校門を抜けた先には芝生に畑、果樹を設けた庭園が広がる。後者には、児童らが使った棚が残るハーブ店や就職室を衣替えしたビール醸造所が並ぶ。体育館はカレーやタコスなどを味わえるフードホールに。保育園や就労支援施設も家移設する。理科室と図書室を改装した「みなとやま水族館」には、癒しを求め、毎週火曜人もいる。管内の生きものは約250種。大型魚はいないが、児童用の椅子に腰を下ろし、けなげに泳ぐ魚を見ていると時がたつのを忘れそうになる。親子で訪れた利用者は「懐かしさと、こぢんまりとした雰囲気でゆったり過ごせた」とほほ笑む。児童減で湊山賞が141年の歴史に幕を下ろしたのは15年。地域の拠点の再生を求める声もあり、市は19年に跡地利用の事業者を公募した。運営会社の社長は往時のにぎわいを知る卒業生。「ピカピカの商業施設をつくるのではなく、縁豊かな字住宅地の良さが見直される未来像を考えた」開業から20万人以上が来場。25年には介護デイサービス施設などが入る新館も建つ。「地域の象徴だった学校と住民の愛着を生かした生活課に取り組みたい」と意気込む。 ノスタルジー覚える千葉県南西の鋸南町に15年開業した「道の駅 保田小学校」はいたるところに残る設備や道具がノスタルジーをくすぐる。同町は人口7000人弱の約半数を光栄者が占めるが、22年度に同施設の来場者は90万人に上った。飲食店やギャラリーが軒を連ねる校舎1階。「里山食堂」は名物のアジフライを給食の食器に盛り付けた再現メニューを提供する。学習机で味わえばタイムスリップした気分に。2回は消失に泊まれる「学びの宿」。客室にある黒板では、誰にも怒られずに自由にチョークで書く餓鬼が楽しめる。体育館を改装したいちばの野菜や魚が集まる。開業を機に生産者組合が組織された。「ここへの出荷が高齢者の生きがいになっている」と住民は語る。自身も花を卸しており「また母校に通うことになるとは」と笑みがこぼれる。23年10月、隣接する幼稚園跡地を活用し施設を拡充。「校長」を務める中村康さんは「誰しもが持つ学校への思いを大切にしつつ、住民と観光客の接点の場でありたい」と話す。 宿泊施設や交流の場に 地元で愛される施設文部科学省によると、2002~20年度に廃校となった全国の公立学校は1年当たり約450校、計8580校に上る。うち3分の2ほどが、残った校舎などの施設を活用している。最も多いのは統合紅野校舎や私学への転用など学校として再利用で、スポーツ施設や公民館、高齢者施設にも使われる。注目されるのは、民間事業者などによる新たな業態での活用だ。建設コストが抑えられるほか、「慣れ親しんだ公社が残ると住民にも受け入れられやすい」(文科省の担当者)という。各地の事例を見ると、地元の原材料を使った食品工場や直売所は6次産業化や雇用創出に貢献。教室にはシェアオフィスや芸術家のアトリエなど創業・創作の場に。工程や体育館などの広い空間を生かし、ドローン開発施設や博物館、魚の養殖場へ転身した所もある。文科省は10年から「みんなの胚校プロジェクト」を開始。活用事例の紹介や事業さとのマッチングに乗り出した。担当者は「民間の柔軟な発想で住民に愛される施設が増えてほしい」と話す。 【文化Culture】聖教新聞2024.1.11
January 24, 2025
コメント(0)
-
本阿弥光悦の大宇宙
本阿弥光悦の大宇宙東京国立博物館学芸企画部長 松嶋 雅人光悦(1558~1637)は、刀剣三事(磨礒・浄拭・鑑定〈とぎ・ぬぐい・めきき〉)を家職とする名門一族・本阿弥家に生まれ、能書として知られ、諸芸に秀でた。「光悦流」という一大潮流をつくり出した光悦の書は、巧みな筆遣いでしたためられた数多くの和歌巻や和歌色紙が知られる。大胆で奇抜な意匠の国宝「舟橋蒔絵箱」をはじめとして、いわゆる「光悦絵巻」が高く評価されている。また光悦は樂常慶、道入とも親交を深め、自ら手捏ねした楽茶碗の優品の多くが現在に伝わる。さらには光悦と角倉素庵とが出版したとされる「嵯峨本」は、料紙と装丁に意匠を凝らしたもので、なかでも「光悦謡本」は豪華な装本である。しかし光悦研究が詳細に進められていくなかで、「嵯峨本」の校閲の版下揮毫ということに対する疑念も生まれ、更に光悦絵巻の伝来品に疑問を呈する意見も出されるほどの状況となっている。現時点においては、光悦の実像は曖昧模糊となり、混迷の状況にあるといえるのである。そこで光悦の実像に少しでも肉薄するために、特別展「本阿弥光悦の大宇宙」では、光悦が厚く進行した当時の法華信仰の様相に目を向け、光悦が当時、法華信徒としてどのような活動をしたのかを踏まえ、造形上の校閲研究の成果と切り結ぼうと考えている。 法華の町衆文化から 創造の実像に迫る 光悦はと町衆の一族である本阿弥家を出自とする。町衆とは都市部において、商人や商工業者が共同体を営み、能や茶の湯といった文化の担い手となった人々のことをいう。そして彼らの多くが法華信徒であった。法華信徒は夫婦、一家、一族すべてが同信であることを日蓮教団から求められたが、本阿弥家はとくに近親との同族結婚が多い。これらの通婚形態は、専門的技術の秘匿性を高める意味をもつ。また本阿弥家は他の法華町衆とも縁戚関係を結んでいる。光悦の姉の法秀は尾形道柏に嫁いだが、その曾孫に尾形光琳、乾山の兄弟が出ている。また「京の三長者」といわれた後藤家の5代徳乗の妻が、本阿弥家10代の光室の娘である妙室である。また茶屋四郎次郎家は、朱印船貿易で富を築いたが、3代清次の娘の妙春は、光室次男である光的に嫁した。このように本阿弥家が縁戚を結んだ法華信徒は、富裕な上層町衆であった。元和元年(1615)、光悦は京都洛北の鷹峯の地を徳川家康より拝領したという。その地の様相を呈した、いわゆる「光悦町古図」が伝わっているが、光悦屋敷の周りにこの光嵯らとともに本阿弥一族、茶屋四郎次郎、緒方宗柏、蓮池常有らといった法華町衆の名が確認される。そこで留意すべきことは、光悦町に住した人々は悉く法華信徒でなければならず、また当時、荒れ果てた地であった鷹峯を新地開発することを幕府側が承知していただろうということである。鷹峯は各家の家職に即した物流の要衝ともなり、光悦の造形に必要となるさまざまな材料となる物資も、同信の人々によって占有されたであろう。そして光悦が作陶や書の揮毫に勤しむことそのものが功徳となって、この鷹峯の地が寂光土となるのである。(まつしま・まさと) 【文化】公明新聞2024.1.10
January 23, 2025
コメント(0)
-
万物の黎明 人類史を根本からくつがえす
万物の黎明 人類史を根本からくつがえすデヴィッド・クレーバー、デヴィッド・ウェングロウ著酒井 隆史訳「現代の方が進んでいる」という思い込み国立科学博物館長 篠田 謙一 評私たちホモサピエンスは二十万年ほど前にアフリカで誕生した。十万年くらい前になると、頭の形や脳の容積が私たちと同じ化石が見つかっており、今の私たちと姿形は変わらない人類となったようだ。そして六万年前にはアフリカを出て世界に拡散したこともゲノムの研究から分かっている。しかし十万年以上の歴史をもつ人類史の中で、実際に私たちが文字資料から知ることができるのは五千年ほど前からにすぎない。分かっているのは最後の五パーセントなのだ。私たちが何ものなのかという問題を考えるスタートは、人類成立の時期までさかのぼる必要がある。しかしこのような事情から、人類の本性については、こうだったはずだという仮定を置かなければならない。実際には、「人類の本性は善良な未開人だった」という立場と「野蛮な未開人だった」という立場のいずれかから出発している。一方で、今世紀になると考古学や人類学の分野で新たな研究が進んだことで、文字のない数万年前にさかのぼって社会の様相が分かるようになってきた。本書は、その知見をもとに社会の発展の様子を考察したのだ。仮定として人類の本性に萩毛布が就き、従来の社会の発展のプロセスは、すべて再考する必要があることが明らかになった。考えてみれば、出アフリカを成し遂げた集団は、今の私たちと同等の知力と体力を備えていたはずで、歴史の最初から「未開の人々」であったはずはない。私たちは「今の方が進んでいる」という思い込みから、現実を見ていなかったのだ。現代社会に閉塞感を感じている人は多いだろう。戦争の世紀だった二十世紀を経て、人類は平和な社会を構築することを目指したはずだった。しかし国連は機能不全に陥って、今や第三次世界大戦すら招きかねない状況になっている。人類全体の生存を脅かす地球の温暖化を止める合意形成すらできず、環境の悪化に対して手をこまねく状況が続いている。資本主義の行き詰まりを指摘する言説もそれなりの説得力をもって受け入れられるようになった。この閉塞した現代社会に替わる社会の有り様というのはあるのだろうか。本書の著者であるグレーバーとウェングロウは、古代社会やアメリカ大陸先住民の社会を詳細に調べ、人間社会の可能性は私たちが考える以上に多様で、歴史の中で様々な実験が繰り返されてきたことを指摘する。本書では、国家とは何かとい考察作を始めとして、農耕の発展が人口増加を促し、そこから社会のヒエラルキーが生まれるという定説を据え直し、真の人類社会の姿を描き出している。そこから明らかになった結果は衝撃的ともいえるものだ。過去の集団が行った社会的な実験の中には、これらの私たちの社会を考えるうえでのヒントもある。本書を読むと、過去を知る研究が、いかに重要かが分かるだろう。◇デヴィッド・クレーバーロンドン・スクール・オブ・エコノミクス人類学教授。2020年2月逝去。デヴィッド・ウェングロウロンドン大学考古学研究所比較考古学教授。 【読書】公明新聞2024.1.8
January 23, 2025
コメント(0)
-
『赤毛のアン』全8巻の翻訳を終えて
『赤毛のアン』全8巻の翻訳を終えて作家・翻訳家 松本 侑子拙訳の最新刊『アンの娘リラ』が発行された。これは『赤毛のアン』シリーズの第8巻にして最終巻である。このシリーズは、アンの誕生から50代までの人生、そしてカナダの19世紀後半から20世紀の激動の時代を、作家L・M・モンゴメリが30年以上かけて書いた壮大な大河小説だ。新刊『アンの娘リラ』では、1914年に第1次大戦がはじまる。案の息子3人は志願兵としてカナダから欧州の戦場にわたり、英仏路の連合側として、敵国ドイツ軍と戦う。この小説は、カナダ東部プリンス・エドワード島の小さな村を舞台に、アンの末娘リラの視点で、第1次大戦の戦況、少しずつ戦時体制に巻き込まれていく銃後の生活、出征兵士とリラの恋と成長を描く。モンゴメリは、きれいごとではない戦争の現実を綴っている。案は兵隊の靴下を編んで戦地に送る。リラは演芸会で愛国的な詩を暗唱して、青年に出征を呼びかける。ある男は戦争を賛美する。またある男は反戦を訴えるために敵国ドイツのスパイと疑われ、家の窓に投石される。案の家政婦スーザンは、政府の軍事費になる戦時国債を買うよう演説する。案の長男は意気揚々と出征する。次男は、自分が敵兵を殺すことも、自分が殺されることも恐れ、そんな臆病な自分に絶望する。しかしドイツ軍の攻撃で女性や子供が死んでいく戦禍に義憤をおぼえ、激戦地にむかう。三男は18歳の若さで戦闘機のパイロットになる。戦場に行った村の男たちの戦死、失明や脚切断が伝えられるも、首都オワタの議会では徴兵制が可決。アンの一家はそれを支持する。そしてカナダ兵60万人が出征した対戦は5年目に入る……。今もウクライナと中東で戦闘が行われている。『アンの娘リラ』は、同じ第1次大戦を描いたレマルク『西部戦線異状なし』、ヘミングウェイ『武器よさらば』に匹敵する戦争文学だ。 戦争やアンの生涯を通じて、幸福な生き方と人間愛を描く アン・シリーズは児童書と思われがちだが、海外では20世紀カナダ文学として高く評価されている。拙訳は日本初の全文訳として、奥深い魅力に満ちた芸術的な原書に忠実に訳した。巻末には訳註を付け、小説中の257~585項目を開設した。例えばモンゴメリが各巻の冒頭に置いた英米詩、作中に引用されるシェイクスピア劇などの膨大な英文学。またカナダは移民による多民族国家であり、スコットランド系のアン、北アイルランド系の親友ダイアナなど、登場人物の民族も紹介した。一番の魅力はアンの生き方だ。アンは父母をなくして親無き子になるが、11歳でグリーン・ケイブルズ農場のマシューとリラに引きとられて降伏に育つ。シリーズ全8巻は、アンの友情、勉学、恋愛、球根と婚約、仕事、結婚、妊娠出産、育児、戦争、老い、家族との死別と、人生の喜びも悲嘆も描く。アンは不幸や苦しみを経験しても、日々の暮らしに小さな幸いを見つけて感謝して生きようとする。そこには、幸福に生きるためのモンゴメリの人生哲学、限りある命を生きている人間への愛が込められている。(まつもと・ゆうこ) 【文化】公明新聞2024.1.7
January 22, 2025
コメント(0)
-
天保山と昭和山
天保山と昭和山武庫川女子大学名誉教授 丸山 健夫大阪市港区の天保山エリアは、水族館「海遊館」や大観覧車がある観光スポットだ。実はその一角に「日本一低い山」天保山がある。天保の時代、すぐ横を流れる安治川の川底をさらえる大工事があった。当時の安治川が、多くの船が行きかう大坂の海の玄関だった。そこでたまった土砂を取り除き、水深を確保したわけだ。このとき、さらえた土を盛り上げてできたのが天保山である。標高約十八㍍の頂上には灯台もでき、船の航行の目印となった。桜が植林され茶屋も建ち、江戸時代の観光地ともなる。ところが幕末の砲台建設に山が削られ、今では周辺が天保山公園になった。天保山の登山をしようと公園まで行くと、これが天保山と思ってしまう大きな丘がある。天保山の頂上は、公園北側の港を望む川岸だから注意しよう。「日本一低い山 大阪・天保山山頂4.53m」の看板が迎えてくれる。ところが大阪には、昭和時代につくられた昭和山も存在する。場所は大正区の千島公園内だ。地盤沈下で大阪市が再開発を計画した。地域の防災拠点ともなる山をつくり、周辺には区役所やスポーツ施設、高層住宅をつくろうとした。ちょうど一九七〇年の大阪万博の開催が近づく時期だった。インフラ整備で大阪市営地下鉄の新線建設工事が始まった。そこで地下鉄のトンネルを掘って出た土を、再開発に回すことができた。こうして地下鉄の土地を盛り上げ、昭和山がつくられた。標高三十三㍍のその山頂に登れば、港がきれいに見渡せる。目の前に世界最大級のトラス橋・港大橋の赤い橋脚が見える。その橋の先にある人工島・夢洲で来年、大阪万博が開催される。 【すなどけい】公明新聞2024.1.5
January 22, 2025
コメント(0)
-
龍になる、想像力の秘密
龍になる、想像力の秘密帝京大学教授 濱田 陽人知超える自然の力が潜在『法華経』に八歳の龍王の娘が、並み居る高弟たちを差し置いて、仏陀の説法を聴き、その意を深く理解して成仏するという説話がある。安土桃山から江戸初期に活躍した天才絵師、長谷川等伯の手になる善女龍王の絵画が、愛らしい凛とした少女と龍の姿を描いていて印象的だ。このエピソードのせいだろうか。やがて、悩みを抱いた人間が龍に姿を変え、その後、『法華経』の功徳によって救われる、という話が多数生み出されることとなった。『今邪気物語集』には、人が、龍、あるいは龍蛇に姿を変える話が数多く収録されている。なぜ、直ちに、ありがたい晴天の力によって救われるのではなく、一度、龍に姿を変えるのだろう。それは、わたしたち人間が、ときにあまりに強い感情を胸に宿すことがあり、それを受け止めるための、龍のような器が、必要だったからではないだろうか。今日では、人が龍になる、というような想像力は、古い伝説。そして、ファンタジーの世界のなかに閉じ込められている。けれども、龍は、たんなる空想の産物ではない。その起源は、現代の考古学的成果によれば、およそ八千年前にさかのぼる。今日の中国東北部、遼河が流れる山岳地帯、採集狩猟民の文化のなかで、龍の佇まいは誕生した。夏や殷の王朝が成立する以前、黄河や長江の二つの大河のはるか北方で、比較的小規模の、多様な部族たちのなかで、龍は、人々が大切に考えていた壱岐小野の存在を取り入れながら、豊かな造形を身にまとっていった。後に、黄河文明、長江文明にも取り入れられ、やがて高句麗古墳壁画で最高の霊性をたたえる青龍が描かれる朝鮮半島に、そして、日本列島には弥生時代に伝わったが、龍の意匠の驚くべき生命力の秘術は、その起源が、採集狩猟民の小集団の文化にあることに由来する。たしかに龍は、中国皇帝や朝鮮の王、日本の天皇のシンボルにもなった。しかし、恋に悩む乙女や、我が子を思う母、道を失った男性もまた、自らを龍の姿に託すことができたのだ。つまり、龍の最古層には、帝国や王朝の権威ではない、わたしたちを守護してくれる、自然の、人知を超える力が存在している。角は鹿、頭は駱駝、目は兎、頂は蛇、腹は想像の生きものの蜃、鱗は鯉、爪は鷲、掌は虎、耳は牛の、九つの動物に似るという九似説では、龍の本質をとらえることはできない。龍は、いくつもの動物の部分を切断して接合したような、西洋にいうキメラではない。むしろ、角をもつあらゆる動物、鱗をもつあらゆる魚類や爬虫類など、様々な生きものとそれらが棲む生態がまるごと含まれており、その一部が表に表れているだけと考えればよい。そして、まさにその世界こそ、はるか旧石器時代から、わたしたちが生きてきた環境そのものであった。その一員であるからこそ、人は、龍になること、龍のメタファーを身に帯びることができたのだ。温暖化、生物多様性破壊など、日常化した環境危機に直面するなかで、今後いかに生きていくべきか。その岐路において、龍ほど、わたしたちの想像力を、深く激しく、刺激し続ける存在はない。(はまだ・よう) 【文化】公明新聞2024.1.5
January 21, 2025
コメント(0)
-
日本型リーダー像の源流は西南戦争にあり
日本型リーダー像の源流は西南戦争にありこれからお話しするのは、近代日本画外へ外へと「攻勢防御」を発動する、少し前のことです。この国の中で日本人同士、最新鋭の武器を駆使した本格的な近代戦争が戦われました。明治十年(一八七七)の西南戦争です。この戦争こそが、本書の主題となる日本型リーダーシップの原型をつくったといえると思われます。それゆえに、しばらくおつきあいください。学校教育で教えられる西南戦争というのは、「鹿児島の不平士族の氾濫を明治新政府が鎮圧した」と、まあ、教科書ではせいぜい一、二行くらいしか書かれていません。そのイメージも、おそらく刀を振り回す肉弾戦というようなものではないかと思われますが、実際はぜんぜん違います。西郷軍は日本最強の軍隊でした。戊辰戦争に勝って明治維新を実質的に成し遂げたのは、薩長の軍事力ですが、中でも薩摩陸軍は圧倒的だった。明治十年の西郷軍は、薩摩を出撃当初の兵力一万三千人、章十一万一千挺、大砲六十文と、当時としては堂々たる大軍です。「不平士族の叛乱」などというレベルではない。はっきりいって戦争です。西郷が薩摩の鶴丸上の厩跡につくった私学校は、県下各所に百以上の分校があり、三万人の生徒がいたといいますから、その半数近くを引き連れていたことになります。新政府の政党軍はというと、数こそ三万七千(増派前の数)と上まっわていますが、明治六年(一八七三)からはじまった徴兵制により集められた農民や商工民の次男、三男といったところが中心です。やっとつくりあげた兵隊です。明治十年時点で、新編成の新政府軍がどれほどの練度であったかといえば、西郷軍と比較してまだ貧弱だったと言わざるを得ません。御親兵の中でも精鋭といわれた薩摩軍の半数近くが西郷さんと一緒に薩摩に引き上げましたが、その西郷軍は歴戦のつわもの、維新の戦士からとなっています。新政府軍の参謀長として参戦した長州の山形有朋が、戦況報告書で百人余の薩摩軍抜刀隊が突如、長剣を振りかざして斬り込んでくる、そのためわが軍の新兵は、驚愕して敗走する者が多いと記しています。いわば軍人対素人という構図だったのです。最強の西郷軍に対抗するためには、政府軍は最新鋭の装備を整えて抵抗するほかありません。もし負ければ、せっかくの維新政府機構は崩壊してしまうのですから。西郷軍は攻撃目標を、九州における政府の権時拠点、熊本城(熊本鎮台)に定めました。西郷らが鹿児島を発った四日後、大久保利通、木戸孝允、伊藤博文、山形有朋など政府参議は、西郷らを賊軍として討伐することを決定、「鹿児島県逆徒征討軍」を派遣することが天皇の裁可を得ます。「総督」には有栖川宮熾仁親王が任命され、「参軍(参謀長)職」には山形有朋陸軍中将と川村純義海軍中将が就きました。山形は侍出身、といっても足軽よりももっと下の階級ですが、軍艦として騎兵隊を率いてイギリスやフランスなどの列強相手の下関戦争をやり、戊辰戦争では岡城攻防戦を戦った生粋の軍人でした。戊辰戦争のときも総大将となった有栖川宮の役どころは、「指揮官」というよりまさに「ミカドの名代」。お維新からたかだか十年、漢軍が自らの正当性を示すパフォーマンスはまだまだ重要だった。勢い総大将はおごそかなる権威があればいい、実際の指揮官たる参謀長および幕僚さえしっかりしていれば、戦さはうまくいくと考えたのです。ここに日本型リーダーシップの発祥がありました。 【日本型リーダーは、なぜ失敗するのか】半藤一利著/文藝春秋日本型リーダー像の源流は西南戦争にあり
January 21, 2025
コメント(0)
-
虫垂炎
虫垂炎人口の1割、若者にも起こる急病今日のポイント投薬数カ月後の〝待機〟手術も〝突然の腹痛〟が起こることで有名な虫垂炎。近年、治療法も変化しているといいます。この疾患について、西京都病院外科の平島相治医師に聞きました。 虫垂内圧の上昇で細菌が増殖し発症——よく〝盲腸〟と呼ばれる疾患ですね。虫垂炎は、俗に「盲腸」といわれますが、盲腸は大腸の一部の臓器名です。「虫垂」は、この盲腸に連続する小さな管状の臓器で、ここに炎症が起こるのが虫垂炎です。 ——盲腸の炎症ではないのですね。なぜ虫垂に発症するのですか。虫垂の中が、食物の内容物やリンパの腫れ、まれにですが腫瘍によって閉塞すると、虫垂内の圧が上がり、血液の循環障害が起こります。さらに細菌が増殖するなどして、虫垂炎を発症します。現在のところ、はっきりとした予防法はありません。 ——どのくらいの人に発症しているのでしょうか。日本人のおよそ1割が経験する病気といわれています。病気といえば高齢者に多いものですが、虫垂炎は若者や子どもにもよく起こる病気です。 ——症状は?みぞおちの痛みや食欲不振、吐き気などから始まります。痛みが、徐々に右下腹部へ移動するという特徴があります。発熱を伴うという特徴も珍しくありません。 ——診断はどのように?右下腹部を中心に、おなかを押したときに痛みが強くなる「圧痛」や、逆にお腹から手を離したときの方が痛みが強く出る「反跳痛」などがあるかを確認します。ただ、こういった症状は虫垂炎以外でも見られますので、虫垂炎を疑えば、血液検査で炎症の有無を確認します。超音波検査、腹部CT検査などの画像診断も併せて行い、診断を確定します。虫垂炎は、炎症が軽い方から順に、「カタル性」「蜂窩織炎性」「壊疽性」と分類されます。重いケースでは虫垂そのものが壊死し、穴が開いてしまい、強い腹膜炎を起こします。 ——虫垂炎というと「すぐに手術が必要」「おなかに傷跡が残る」という印象があります。依然は虫垂炎と診断されたら、できるだけ即時の手術を行っていました。一方で、俗に「散らす」と呼ばれる抗生物質を用いた保存的治療(薬物療法)もありました。それでも早期の手術が行われていたのは、抗生物質の効果が十分でなければ虫垂炎の重症化すると考えられていたからです。 抗生物質の進歩約8割の症例に有効しかし、近年では画像診断や抗生物質の進歩によって、およそ8割の患者に保存的が有効であるとの報告が出ています。〝初回治療として、保存的治療は手術に劣らない〟といった欧米の論文にもあります。また、保存的治療が有用なケースに、発症から一定時間経過し、強い炎症を伴っている虫垂炎があります。炎症の強い患者では、手術時間や手術中の出血量、術後の合併症や在院日数が増えます。保存的治療で効果があれば、炎症の強い時期の手術を回避でき、即時手術が持つデメリットを解消できます。 休暇を活用して手術も受ける人も——保存的治療にデメリットはないのですか。約2割の患者には保存的治療は効きません。その場合は、途中で手術療法に切り替えることがあります。また、虫垂自体は残るため、報告にもよりますが、保存的治療の後、約2割に再発があります。さらに、壮年期以降の虫垂炎には、盲腸がんや虫垂がんが原因の場合があり、治療的手術だけでは、がんを放置してしまいます。こう言ってデメリットを最小限に抑えるため、最近は保存的治療後に、大気的に虫垂切除手術を行うことが増えています。 ——待機的手術?まず保存的治療を行い、虫垂炎が治癒してから2~3か月〝待機〟した後に、無症状であっても虫垂を切除します。述前に検査も行い、がんの有無なども調べられます。待機的な修水切除術では、おへそを”~3センチ切るだけの腹腔鏡手術が主流です。入院も3~5日間と短く、休暇を活用して手術を受ける方もいます。 ——虫垂は摘出しても問題はないのでしょうか。ヒトの虫垂は、退化した痕跡の臓器といわれています。一方、腸内細菌の正常化などに関わっているという研究もあるのですが、虫垂切除後の後遺症は少ないため、手術をためらうことはありません。 ほかの疾患の可能性も負担少ない治療法を——夜間や休日に発症を疑う症状が出たら、すぐに救急にかかった方がよいのでしょうか。虫垂炎の初期は、私たちが一時的に体調を崩したときに出るような症状の中で、すぐに虫垂炎を想像しづらいと思っています。ただし、虫垂炎は自然治癒の可能性が低い病ですので、下腹部痛や初夏を伴っている際は、少なくとも翌日までの受信をおすすめします。症状が強い場合は、救急を受診してください。 ——どの診療科に行けばよいのでしょう。同じような腹痛や発熱を伴う痛みには、他に「胆のう炎」「頚室炎」、女性であれば婦人科疾患の可能性があります。虫垂炎との診断を受けるには、内科を受診するのが最もスムーズだと思います。日本では、成人における虫垂炎治療の明確なガイドラインはありませんので、病院によって治療方針に幅があります。だれもがかかり得るありふれた病ですので、医師と相談し、できるだけ体に負担をかけない治療法を選択できるとよいと思います。 【医療Medical Treatment】聖教新聞2024.1.4
January 20, 2025
コメント(0)
-
戦争は防御から始まる
戦争は防御から始まる急所を読み誤った帝国陸海軍部クラウゼヴィッツは、「戦争は防御から始まる」と言っていました。わたくしたちは戦争が攻撃から始まると思い込んでいます。クラウゼヴィッツの主張とは、まるであべこべ。篠田訳をちょっと引用しますと、「攻撃は逃走よりむしろ敵国の略取を絶対的目的するからである。それだから戦争の概念は、防御とともに発生するのである、防御は戦争を直接の目的とするからである。この場合に防御、即ち敵の攻撃を余資することと闘争とは同一物である」いわれてみればそのとおりなのです。いくら攻撃側が暴れまわっても、相手の抵抗がないことには戦争状態をつくりだすことはできない。たしかに戦争になるかならないか、最後の決め手を握っているのは、攻撃側よりも、攻撃を受ける側なのかもしれません。奇妙な議論にもみえますが、太平洋戦争を思い返すとその正しさを実感せざるを得ないのです。ABCD包囲陣だの石油の全面禁輸なのだと、アメリカン戦争政策による〝攻撃〟なんかどこ吹く風とばかり、柔軟な外交交渉をえんえんと続けていたら、そしてまた、あり得ないと思う人が多いかもしれませんが、春・ノートをあっさり受諾していたら、その交渉をぐたぐたと続けているうちに、電撃作品であれほどまでに好調だったナチス・ドイツが一転、ロシア戦線で敗色あらわになります。世界情勢が一変し、とるべき日本の制作は大きく変更されて戦争にならなかったかもしれないのです。 島国を守るという視点クラウゼヴィッツを読んでいてハッとさせられたのは、近代日本の戦略思想にはもともと「防御の思想」というものがなかったということです。たとえば、太平洋戦争中の航空機や軍艦の防御をみればそれが明白です。令式戦闘機は御存じのように、乗員席の後ろに鉄の防御版を置かなかった。攻撃の運動性能を上げるために期待を軽くすることを、搭乗員の命を守ることより優先させた。戦艦「大和」当時の世界一の戦艦で、大きさと攻撃力が世界一でしたが、対空防御についてはほとんど想定していません。「攻撃は最大の防御成」とは帝国海軍ともに信奉する考え方でした。満州事変から太平洋戦争にいたる政戦略の外へ外へのエスカレーションは、まさしくこの攻勢防御思想によるものでした。日本は細長い島国で、真ん中に山脈が背骨のように通っていて平野が非常に狭い。周囲が海なのでどこからでも入ってこられる。日本本土を守り抜くことなんて不可能で、地政学からいえば大きな欠点を持っています。防御上、北からの脅威に備えるために朝鮮半島をとる。その朝鮮半島を守るためには満州をとる。満州を守るためには内蒙古を、次には北支那をとる……とにかく外へ外へ、となっていきました。南方も同様です。本土防御のためにマリアナ諸島をとる。さらにマーシャル諸島をとって不沈空母の基地にして、防御態勢をしく。その防御態勢は攻撃体制でもあった。そしてラバウルからニューギニアへ、さらにオーストラリアまで……構成の限界点をまったく無視しました。思い返すにつけ、なんとばかなことを考えたものか。とにもかくにも日本軍の戦略戦術思想のなかに、クラウゼヴィッツの「戦争は防御からはじまる」という大命題はなかったのです。はじめから「攻撃は最大の防御成」でした。大本営のエリート参謀たちは、彼の『戦争論』に目を通していたのでしょうが、公正と豪魚を明確に区別するというある意味では根本的な考え方には、まったく関心を寄せなかったというほかない。明治から昭和までの近代日本の栄光を悲惨も、つまるところは「攻勢防御」の思想の産物だったのです。 【日本型リーダーは、なぜ失敗するのか】半藤一利著/文藝春秋
January 20, 2025
コメント(0)
-
二つの日本史の転換期
二つの日本史の転換期日本の歴史には、二つの大きな転換期がありました。一つは戦国時代。もう一つは明治維新です。それぞれ特徴をみていくと、現在を幕末・維新期になぞらえることの無理がよくわかると思います。生後九時台というのは、応仁の乱の乱からはじまるといわれていますが、この戦国の争乱期には、百年以上続いていた足利将軍による室町幕府に一応の権威はあったのです。ところが、その権力統治がぐずれたことで、その上に乗っていたものがすべて崩れ去って、治安・秩序が完全に失われました。いったん秩序体系が崩れてしまったことで、従うか従わせるかという、ほんとうの力比べではアないと決着がつかないことになった。これが戦国時代という転換期の特徴です。これまでは血筋、血統による身分で秩序がピシッと決められていたのだけど、そういう身分の固定化というのが強くなくなった。あるいは崩れ去ったというのもまた、この時代にみられる特徴です。そういう状況を背景にして、独自の世界観をもってリーダーシップを発揮したのが、戦国時代の武将たちでした。織田信長にしろ、武田信玄にしろ、彼らはこのごちゃごちゃの世界の中で天下統一を目指して立ち上がり、自分の才覚を発揮して家臣たちを引っ張り、版図を広げていったのです。それにくらべて幕末の徳川幕府は、権力機構がしっかり根づいていました。決してグズグズ崩れてはいません。徳川幕府は最後の最後のところまで、権威も権力もあった。各藩だってそれぞれに秩序が保てていた。戦国時代は力と野心があれば、とにかくがむしゃらにやりさえすればよかった。けれど、完成してしまっている幕藩体制下では、改革を唱え大変大きな軋轢を生む。ついには自分の殿様を倒さないと改革はできなくなってしまった。改革派は、守旧派と揉み合っているうちに、幕藩体制のうしろ側に、天皇というたいへんな権威が存在していることを発見します。権力はないけれども、いやむしろ権力を振り回さなかったからよけいに、純粋に大いなる権威を保持できていた天皇という存在に気づいた。当時は「御門」とな、「すめらみこと」とか呼んでいたわけですが、その天皇を担いで一か八かの命がけの仕事をすれば、権力をほしいままにしている幕藩体制をひっくり返すことができると、彼らは考えた。それに、外国の武力というかつて想像したこともない力が外から加わってきていいた。西郷隆盛、大久保利通、高杉晋作ら、明治維新でリーダーシップを発揮した人も、戦国武将たちもひとしく命がけでではあったでしょう。けれど、戦国武将が何もないところを突っ走った感じであるのにくらべて、明治維新は分厚いコンクリートの壁にぶつかるようにして、旧体制をぶち壊そうとしたのです。つまり、外圧を前にしても国家秩序は決して崩壊していなかった。それで改革しようというわけです。では現在はどうか。状況は、ずばり戦国時代と思います。日本はいま、まさにグズグズの体制になっている。そして、広室は政治的権威を持たないことが憲法ではっきり決まっていますから。今の政治体制を支える権威はどこにもありません。また現代は、下克上の時代。天下をとろうと思えば、誰もがとれるという状況になっているのです。しかもネットでつながってそれが社会を変えるきっかけとなっている、そんな軽い時代でもある。維新のときと、状況はずいぶん違います。第一に、天誅を受けなくてすむ。ですから、いまリーダーシップがやたらに論ぜられている。要求されているのです。この先の見えない、浮遊している国家を何とかキチッとしたものにしてほしい。そうした人材よ出でよ、いまこそ、というわけです。でも、そんな簡単に織田信長や徳川家康が出てくるはずはありません。今の日本にこれというリーダーがいないのは、日本人そのものが劣化しているからだと思います。国民のレベルにふさわしいリーダーしか持てない、というのが歴史の原則であるからです。 【日本型リーダーはなぜ失敗するのか】半藤一利著/文藝春秋
January 19, 2025
コメント(0)
-
「リーダーシップ」の成立したとき
「リーダーシップ」の成立したときリーダーシップという言葉は、もともとは軍隊用語です。戦前、我々国民は、軍事には一切関知すべからず、ということになっていました。軍事予算については国会で審議しますが、軍の方針とか軍隊内部のリーダーシップなどということについて、外部者が議論することなどあり得ません。軍事学などと言う校是があった大学はなかった。帝国大学ですらなかった。ところが戦後になって、やたらに「リーダーシップ、リーダーシップ」と言うようになった。この場合のリーダーシップは、ビジネスの世界のことをもっぱら言っているわけですが、軍事学の擁護や考え方をビジネスの世界のことをもっぱら言っているわけですが、軍事学の擁護や考え方をビジネスの分野に当てはめることが、アメリカではしばしば行われていましたから、それが日本に持ち込まれて、日本人もありがたく拝聴したというわけです。「ビジネス戦略」などという言い方もありますが、これなど「戦略」「戦術」という純粋に軍事用語として作られた言葉がそのまま使われています。戦後になるまで一般には無縁だったリーダーシップ論ですが、日本の軍隊が何も研究してこなかったというと、そんなことはない。陸軍では明治以来、参謀本部が軍事学の研究を行っていました。言わずもがなかと思いますが、参謀本部というのは、作戦を考えその命令を出す、陸軍のいわゆる軍令機関の総本山。海軍は軍令部です。明治の参謀本部の中に「戦史課」という部署が置かれました。まずは関ケ原の合戦とか、長篠の合戦といって、戦国時代の戦士を調査・分析・研究対象としました。それぞれの合戦の戦略・戦術はどんなものであったとか、築城技術、兵器・装備の詳細、また軍政についても当時の資料から研究しています。時代を経るごとに研究対象は、更に日清戦争、日露戦争、日支事変にまでおよび、その中から「指導者はいかにあるべきか」ということを引き出そうとしていました。その集大成の一部が、優しく書き直されて「旧三宝本有編集」の『日本の戦史』シリーズとして今も刊行されています。 戦国武将のお手本では、その大元の戦国武将は、何をもってハントしていたか。中国地方の有力武将である毛利元就、九州の島津義弘など、朝鮮半島に近い領地を持つ武将らはさかんに文献を輸入していたようですが、これは特別。東国の武将たちはそうもいかず、みなひとしく、数少ない主要文献を学んでいました。武田信玄、上杉謙信、そして織田信長らが読んだ主要文献とは、中国の兵法書。『孫子』、『呉子』、『六韜・三略』といって、いわゆる武経七書です。中でももっとも読まれたのが、「彼を知り己を知らば、百戦殆うべからず」という有名なフレーズで知られる「孫子の兵法」。そして「六韜・三略」でした。わたくしは武田信玄と上杉謙信の川中島の合戦を書いたときにくわしく調べたのですが、信玄がこれらをじつによく学んでいたことに驚きました。少年時代に臨済宗の禅僧岐秀の指導で兵法書を勉強しています。とくに『孫子』十三篇は暗記するくらいでした(『徹底分析 川中島合戦』PHP文庫)。その兵法書が、いったいどんな内容であったのかみてみます。まず「孫子の兵法」。将の将たる人間は、「智」、「信」、「仁」、「勇」、「厳」をしっかりと持てと言っています。「智」とは敵に優る智慧であり、敵に手を読まれずに、しかも敵の手の内を読み取る力。「信」とは、心正しく偽りがなく、部下の信頼を集めること。「仁」とは思いやり、労り。これは人間としていちばん大事な、人を慈しむ心。「勇」とは、ここに臨んでよく忍耐し、危険を恐れずなすべきことを行う力。「厳」とは、けじめをはっきりする厳しさのことです。江戸時代のもっとも有名な兵法家山鹿素行は、「智信仁勇厳」のうち一つでも欠けるときは、武将の実にあらざるなり、つまり武将の資格がないと言いきりました。「智信仁勇厳」を備えている者こそが、リーダーとしての有資格者である、と。きわめて抽象的な話ではありますが、戦国武将はみなこれを読んで心得とし、時分の修練の目標としたわけです。 【日本的リーダーはなぜ失敗するのか】半藤一利著/文芸春秋
January 19, 2025
コメント(0)
-
撰時抄
撰時抄創価学会教学部編末法は南無妙法蓮華経を弘める時文永11年(1274年)10月に文永の役が起こり、日蓮大聖人が警告し続けてきた他国侵逼難が現実のものとなってしまいました。 元の死者が斬首される一度、撤退した元(大元。モンゴル帝国の皇帝フビライ・ハンが中国を征服して建てた王朝)は、次にモンゴル人で元の官僚である杜世忠らを正式の使節として派遣しました。よく・文永12年(1275年。4月25日に建治に改元)4月15日、長門国室津(現在の山口県下関市内)に到着します。その目的は、日本に服属を勧告するためでした。しかし、鎌倉幕府は彼らを使節として扱わず、ただちに捕縛して鎌倉に侵攻し、9月7日、杜世忠以下5人を竜の口で斬首しました。杜世忠らの処刑について、大聖人は同じ月のうちに、鎌倉から駿河国(現在の静岡県中央部)に戻った門下の西山殿から報告を受けます。その御返事には、「科なき蒙古の使いの頸を刎ねられ候いけるこそ不憫に候え」(新1946・全1472)と、幕府の暴挙に対する歎き・憤りと使者への憐憫の情がつづられています。3年後弘安元年(1278年)にも、「ああ、もし平左衛門尉殿や相模守殿(=北条時宗)が私を用いられていたなら、先の蒙古からの使いの首を、決して切らせることはなかったでしょう。今は後悔されていることでしょう」(新1493・全1059、通解)と、幕府の誤りを責められています。 「撰時抄」を御執筆元からの報復が予想され、対外情勢が緊迫する建治元年(1275年)、大聖人は「撰時抄」を御執筆されます〈注1〉。同抄では、まず、「仏法を学せん法は、必ずまず時をなら(習)うべし(仏法を就学しようとするなら、必ず時を習うべきである)」(新160・全256)と主題を示し、仏法を弘める際は、必ず「時」を根本の基準として、それに応じた教えを説くべきであると仰せです。この「時」とは、特定の教えを説くべき仏教のうえでの時であり、単なる時代や人心の移り変わりのことではありません。さらに、「我滅度して後、後の五百歳の中、閻浮提(=私たちが住む世界全体)に広宣流布して、断絶せしむることなかれ」(新164・全258)という法華経薬王品の文(法華経601㌻)は、法華経の肝心の法が第五の五百歳(末法の初め)に閻浮提に広宣流布されることの文証であること示されます。「後の五百歳(第五ノ五百歳)」が悪世であること、また、悪鬼入其身〈注2〉の高僧(僭聖増上慢)が国王から民衆まで(俗衆増上慢)をたぶらかし、仏の真実の教えを弘める「智人」(法華経の行者)を迫害させることを確認されます。そして、法華経の行者に対する迫害は、正法を滅ぼす大謗法であるから、釈迦・多宝・十方の諸仏が、諸天善神らに働きかけて謗法を警告するよう促すので、天変地異が盛んになると訴えられています。さらに、諸仏のこの警告を無視すれば、「前代未聞の大闘諍、一閻浮提に起こるべし」(新165・全259)と述べられ、その時、人々はわが身を惜しんで一同に南無妙法蓮華経と唱えるようになると仰せです。 密教が亡国を招く次に、正法・像法・末法という三時において、インド・中国・日本の三国で、仏法がどのように広まったかを史実に即して具体的に示された後、経文に説かれる通り、悪世に難をしのんで正法を弘める大聖人御自身が、「閻浮提第一の法華経の行者」(新175・全266)であると宣言されます。続いて、〝正法・像法にまだ弘められなかっら深い教えで、末法の初めに一閻浮提に広宣流布史べき教えとは、どのような名で、どのような内容であるか〟という問いが掲げられ、これに答え「るにあたって、末法広宣流布の障害となっている三つのわざわい(禍)」(新184・全271)として「念仏舅前週と真言宗」(同)を挙げられます。その上で、これらの三宗よりも「百千億万倍信じがたき最大の悪事」(新193・全279)があると言われるのです。それが、第3代天台座主の慈覚(円仁)の行状です。彼は師である伝教大師(最澄)の真意を見失い、密教経典の方が法華経よりも優れているという誤った協議を唱えました。大聖人は、その誤りを厳しく糾弾されていきます。そして、亡国の法である真言によって蒙古調伏を祈るなら、「還って本人に著きなん(還著於本人、注3)とあるように、亡国の結果を招く警告をされています。 「衆流あつまりて大海となる」 法華経を受持する人は第一大聖人は、文応五年(1260年)の「立正安国論」御執筆の時点では、人を謗法に向かわせ亡国を招く「一凶」を、一乗の教えである法華経をないがしろにする専修念仏と断じられました。以来15年を経た「撰時抄」御執筆の時点では、密教による祈禱に期待を寄せる社会の風潮を最大の問題とされたと拝されます。とりわけ、今まで破折を控えられてきた密教化した天台宗〈注4〉を、いよいよ緊迫する国難の中で糾弾されています。自界叛逆難と他国侵逼難を予見し三度にわたって公言したことは「三度のこうみょう(高名)」(新204・全287)であると述べ、二つの難が現実のものとなったことは、人々が正法を求める契機となるので、かえって広宣流布の前兆・随想と言えるとし、次のように宣言されています。「衆流あつ(集)まりて大会となる。微塵つ(積)もりて須弥山となれり。日蓮が法華経を信じ始めしは、日本国には一滴一微塵のごとし。法華経を二人・三人・十人・百千万億人唱え伝うるならば、妙覚の須弥山ともなり、大涅槃の大海ともなるべし。仏にな(成)る道は、これよりほかに、またもと(求)むることなかれ」(新205・全288)と。さらに、伝教大師(最澄)の言葉や法華経の文を引いて、諸経の中で「第一」の経典である法華経を受持する人は「第一」の人であると明言されます。弟子たちにも「心みに法華経のごとく身命もお(惜)しまず修行して、この度仏法を心みよ(試しに法華経に説かれる通りに身命も惜しまず修行して、この機会に仏法が正しいかどうかを試してみなさい)」(新210・全291)と、如説修行に徹するように呼びかけられます。最後に、謗法充満の悪世においては法華経に説かれる不軽菩薩らのように不惜身命で正法正義を貫く実践をするべきであると訴え、諸天善神の加護を確信して死身弘法の実践をするように促して結ばれます。「撰時抄」では、大聖人御自身が「一閻浮提の法華経の行者」として前代未聞の大法を弘めること、瑞相の根源を知る閻浮提第一の智人であること、自界叛逆難と他国侵逼難の兵乱をかねてから知る閻浮提第一の聖人であることが示され、末法下種の教主であると明らかにされています。そして、「前代未聞の大闘諍」の時に、その災難の根源である謗法を打ち破って解決するために、これまで弘められたことのなかった大白法(正しい教え)である南無妙法蓮華経を打ち立て、不惜身命の実践で全世界に広宣流布していくことを呼びかけられました。 前代未聞の大白法を世界に 密教批判を強めるこの年(建治元年)の12月、真言の僧・強仁からの書状が、身延におられる大聖人のもとに届きます。仏法の正邪を決しようと法論を迫る内容だったようです。大聖人はその日のうちに返書を記されます。(「強仁状御返事」)。その中で大聖人は、暗闇の中で錦の衣を着て見分けがつかず、谷底にあっては立派な松の見いだされないのと同様に、地方で私的に論争しても、正式な判定がなされず、決着がつきにくいので、朝廷と幕府に訴えて、公の場で対決するよう提案されています(新875・全184、参照)。翌月の建治2年(1276年)1月、大聖人は故郷・安房国(現在の千葉県南部)の清澄寺の知人の僧侶に宛てて書状を送り、「真言の注釈書を借用してきてほしい。このようなことは真言師が大勢騒いでいるので言うのである」(新1206・全893、趣意)等と、真言宗の開祖・弘法(空海)の著作を求められます。さらに「摩訶止観」はじめ、天台宗の著作も必要であると記されています。そして、「今年はことに仏法の邪正たださ(糾)るべき年か」(同)と仰せになっていることから強仁ら真言の僧らとの公場対決の実現に備えられていたと拝されます。身延入山以降、大聖人は、従来の真言宗(東寺〈教王護国寺〉を中心とする東密と称される)だけでなく、真言化(密教化)した天台宗(台密)への批判を強めていかれました。朝廷も幕府も、元の襲来に対して、諸寺に銘じて密教による調伏の祈禱を盛んに行わせていた時期です。文永11年(1274年)の「曽谷入道殿御書」、文永12年(=建治元年〈1275年〉)の「曽谷入道殿許御書」、「教行証御書」、「三三蔵祈雨事」、「大学三郎殿御書」、「高橋入道殿御返事」、「神国王御書」、そして「撰時抄」と、法華経を誹謗している真言の教えを次々と破折されたのです。(続く) 池田先生の講義から(『三度の高名』について)予言は、三世永遠の法を教えるための一つの智慧の形です。永遠の法は見えない。それを智慧によって形に現し、人々の信を促していくのです。(中略)永遠の法を知る智慧を「形」に現し、「行動」に現し、「実証」として現してこそ、法は広まっていくのです。広宣流布は、一人から一人へと、法を唱え、伝える実践を積み重ねていく以外にないのです。(『池田大作全集』第33巻) 〈注1〉 本抄は執筆された後、推敲され、建治2年(1276年)の「報恩抄」御執筆以前には完成していたと思われる。完成後も推敲して性本を作成された可能性が考えられる。〈注2〉 法華経勧持品第13の二十行の偈の文(法華経419㌻)。釈尊滅後の悪瀬に法華経を弘める者に迫害を加える三類の強敵の様相を説いた中の一句。三類の強敵には悪鬼が身に入り、正法を護持する者を迫害すると説かれる。〈注3〉 法華経の行者に呪いや毒薬で危害を加えようとする者は、かえって自らの身に、その害を受けることになるとの意。法華経観世音菩薩普門品第25に説かれる(法華経635㌻)。〈注4〉 天台宗は密教による祈禱を重用し、郷里の面でも密教経典を法華経よりも優れていると位置づけるようになっていた。 【関連御書】「蒙古使御書」、「兵衛志殿御書(親父入信の事)」、「撰時抄」、「強仁状御返事」、「清澄寺大衆中」 【参考】「池田大作全集」第33巻「御書の世界〔下〕」第十四章)、同第27巻(「撰時抄」講義)、「第白蓮華」2010年4、6~8月号「撰時抄」講義①~④) 【日蓮大聖人 誓願と大慈悲の御生涯】大白蓮華2024年1月号
January 18, 2025
コメント(0)
-
訪日外国人にも人気
訪日外国人にも人気昭和レトロ茨城大学教授 高野 光平人との密な触れ合いが醍醐味定番観光地から穴場スポット探訪へ最近、レトロな観光地や施設が、訪日外国人たちに人気だという。横町の飲み屋やスナック。昔ながらの純喫茶。大正や昭和初期に建造された古いビル。ドライブインによく置いてあったうどんやホットサンドの自動販売機。昭和三十年代の街並みを再現した西武園ゆうえんち、などなど……。日本通の旅行者たちは、浅草や京都のような定番スポットに飽きて、渋い観光地やあまり知られていない穴場を好んで訪れるが、そのひとつがレトロスポットなのだ。彼らは探訪の様子をSNSで発信し、それを見て興味を持った人が、日本に来て同じ場所に訪れるのである。レトロを好むのは万国共通の感性だ。日本でもここ5~6年、若者を中心にフィルムカメラやカセットテープなどのアナログメディアを愛でる流行があるが、これは海外でも同じである。1980年代から2000年くらいの文化やファッションが世界的に再評価されて、アメリカではY2K、韓国ではニュートロと呼ばれる。一昔前のセンスはダサくて敬遠されるが、ふた昔前のセンスは一周回ってオシャレに見えるものだ。二十世紀終盤の時代がちょうどそこにはまって、若い人には魅力的に映るのだろう。アナログ機器の独特の手触り。横町の飲み屋で人と人とが密になって触れ合う感じ。まさに、触れるのがレトロの醍醐味であり、コロナ禍で失われていた人間社会の基本がそこにある。一方で、アナログ機器は操作が面倒くさい。横町の飲み屋も酔って絡まれたりして、なかなか面倒くさい。これは短所であるが、長所でもある。何でもスマホで済む、なんでもオンラインで人と合わずに済む、簡単で楽で時代を私たちは受け入れつつも、何か物足りなさを感じている。レトロの面倒さは、そんな心の隙間を埋めてくれるのだ。それは世界共通の感覚ではないだろうか。外国人の日本のレトロに癒されるように、日本人もまた、東南アジアの雑然とした市場や、ヨーロッパの古い街並みに心地よいレトロを感じるだろう。地理的に遠い異国情緒と、時間的に遠いレトロがかけあわさり、まるで夢の中にいるようなファンタジーを味わうことができる。それは現実の場所だけではなく、映像でも可能だ。ここ十年ほど、YouTubeでは1980~90年代の日本の音楽(とくにシティ・ポップと呼ばれるジャンル)や、アナログビデオで撮影された当時の東京の風景などが外国人にうけている。動画には、「行ったことないけど懐かしい」「すんだことないけど帰りたい」というコメントがたくさんつくのが恒例だ。世界中の文化を吸収して唯一無二の個性を作り上げた東京という都市は、世界中の人々のノスタルジーを受け入れ、レトロな癒しを提供できる懐の深さを持っているのかもしれない。なんとも不思議な観光資源である。(こうの・こうへい) 【文化】公明新聞2023.12.29
January 18, 2025
コメント(0)
-
各地に息づく和食文化
各地に息づく和食文化ふじのくに地球環境史ミュージアム館長 佐藤 洋一郎コメの生産地が北海道に各地の伝統食(=和食)が消えつつある——。大きな理由の一つは、食材が手に入らなくなってきたことにある。温暖化の影響で、昔から使われてきた食材が取れなくなっている。例えば利尻昆布、魚介類全体が北上する傾向にあり、もともと北海道でとれた昆布は、もっと北の樺太やサハリンなどに移動してしまうかもしれない。また、コメにしても5~10年後には、九州で作れなくなり、主産地が北海道に移ってしまう子も知れない。「ただ、場所が変わるだけじゃないの」と思う人もいるだろう。植物はどの緯度帯で栽培するかが重要。花の咲く時期は、昼間の長さが関係している。したがって、緯度によって、開花時期などの反応が全く変わってしまうのだ。だから、北海道でコシヒカリを育てようとする場合、温度条件はクリアできても、昼の時間が短いため、花は咲くのはすっかり秋ということが起こる。そのため、別の場所で育てる子は、品種改良が必要になるのだ。二つ目は人手不足。料理人どころか、店の後継者もない状況。大きい店はともかく、小さい店になると、料理人の人手不足は深刻だ。和食文化は、一流だけで保っているものではない。広いすそ野があってこそ、高い頂上も存在できるからだ。さらに人手不足は、一つ目の食材不足にも関係している。例えば京料理では定番の「くず粉」。大昔は京都市内で栽培され、半世紀ほど前には若狭や奈良に移った。現在はほとんどの粉が中国から輸入されている。クズの根っこを白い粉にするには、ものすごく手間がかかるため、今では職人がほとんどいなくなってしまった。現在は輸入できているが、いつどうなるか分からないのが現状なのだ。 消えつつある伝統食食材とれず、人手不足が原因 形は違っても同じ「雑煮」2013年、ユネスコ無形文化遺産に「和食 日本人の伝統的な食文化」が登録された。しかし、何が和食か分かりにくい。実は、「一汁三菜」という言葉が誤解を招いている。その多くの人が一汁三菜が和食の形だと思ってはいないだろうか。だとすると、外国人が日本食として挙げる代表格の、すき焼き、寿司、天ぷらは和食ではなくなってしまう。日本には、各地で昔から食べられてきた料理がある。さらに、よそからの影響を受けて変化した料理もあるかもしれない。ただ、そのいろいろなものをひっくるめて和食と言えるのではないだろうか。和食という一つの形があるのではなく、各地で手に入る食材をおいしく食べるための手段が和食なのだ。だから、それぞれの土地にそれぞれのスタイルがある。日本には式があり、季節や場所によってとれる食材は変化するため、ひたと南、東と西、日本海側と太平洋側といったように、食文化が異なるのが当然。全国にルーツがあるのが和食なのだ。以前、函館に行ったときに、こんなことがあった。宿泊先で料理をしようと思い、市場で鰹節を買おうとしたところ、ここにはないと言われた。一瞬、出汁を取らないのだろうかと思ったが、実は汁物には魚が入るため、出汁として穂昆布だけでよく、鰹節は必要ないのだ。またお正月になると、どこの家庭でもお雑煮を食べるだろう。しかし、地域によって雑煮の内容は異なる。わあたしは父が東日本、母が西日本生まれだったため、関西の白みそ仕立ての雑煮と、東日本の澄まし雑煮の両方を食べてきた。東西だけでなく、もっと細かく、各地にいろいろな雑煮があり、その形は違っていても、誰もがお正月になると雑煮を食べる。これが和食の姿なのだ。各地に息づく伝統食を守ることが、和食文化を守ることが、和食文化を守ることになるのだ。各地に息づく和食(伝統食)を紹介したいと、近著『和食の文化史』(平凡社新書)を出した。また、農水省では「うちの郷土料理」として、県ごとに30品目ずつ紹介している。ハレの日の料理ばかりでなく、家庭料理も多い。県ごとに紹介されているので、出かける際には参考にしてほしい。 =談 さとう・よういちろう 1952年、和歌山県生まれ。ふじのくに地球環境史ミュージアム館長。農学博士。総合地球環境学研研究所副所長、京都府立大学特任教授・京都和食文化研究センター副センター長などを経て現職。先日、京都市文化功労者に認定。著書に『和食の文化史』『食べるとはどういうことなのか』など多数。 【文化Culture】聖教新聞2023.12.28
January 17, 2025
コメント(0)
-
反戦の思いを込めた古代の喜劇
反戦の思いを込めた古代の喜劇作家 村上 政彦アリストパーネス「女の平和」本を手にして想像の旅に出よう。用意するのは一枚の世界地図。そして今日は、アリストパーネスの『女の平和』です。このコラムではたくさんの現代作家を紹介してきましたが、今度は大古典作家です。アリストパーネスは、紀元亜鉛400年前後に活躍したギリシャの詩人・劇作家。本作は戯曲として発表されました。舞台は、果てしない内戦の続くギリシャのアテーナイ。主人公の女性リューシストラテーが城山(アクロポリス)に通じる門のところへ現れます。そこにカロニーケ、ラムピトー、ミュリネーなど、各地から彼女の招集によって女性たちが集まってくる。リューシストラテーは、戦争に狂奔する男たちをしずめ、和平を結ばせる計画を打ち明けました。それは女性たちが、思い切り美しく装い、しかし夫や恋人など男たちには身を任せない、というやり方です。戦争をしている男には、指一本触れさせない、というやり方です。そうすれば、男たちは武器を捨てるに違いない。女性たちは城山(アクロポリス)に立てこもり、改革を実行します。彼女たちが拠点としたこの場所は、革命の象徴で、ここを占拠することは、すなわち革命のはじまりを意味します。女性たちの中から、何人か恋しい男のもとへ逃げ出そうとする者もいるが、そのつど、リューシストラテーに諫められて戻る。やがて、とうとう女性たちのストライキに屈した男たちは、和平を結ぶことになります。恋しい妻に会いに来て、翻弄される哀れな男の姿が、この劇の見せ場の一つでしょう。アリストパーネスは、喜劇詩人でもありました。しかし、この戯曲の喜劇としての層を深く掘ると、違った面が見えてくる。劇中、『戦争は男の仕事だ』というホメーロスの叙事詩『イリアス』から引いた言葉が出てきます。それに対し、リューシストラテーは、「戦争は女の仕事だ!」と言うのです。この矛盾を読みに解くには、彼女の「あたしたちは戦争の二倍以上の被害者」という台詞に着眼しなければならない。女性は、夫を軍隊に取られる。さらに、自分の産んだ子供を兵士として線状に送り出す。つまり、戦場に不可欠な、若い兵士を産み育てるのは女性——だから「戦争は女の仕事だ!」となる。『女の平和』では、男たちに戦争をやめさせるため、ストライキをすることになっています。観客(読者)は、欲望に踊らされる男たちの姿を笑う。しかし女性たちの行いを穿ってみると、むざむざ戦場で奪われる命なら、最初から生まない、と読める。つまり、ストライキは、単に男たちを懲らしめるためだけではなく、生殖のための行為を放棄することに行き着く。女性によって「政治」が変わる。これが、古代の喜劇に込められた主題なのでしょう。[参考文献]『女の平和』 高津春繁訳 岩波文庫 【ぶら~り文学の旅㊵海外編】聖教新聞2023.12.27
January 16, 2025
コメント(0)
-
正常な呼吸が長寿の基盤
正常な呼吸が長寿の基盤医学博士 須藤 英一さんすどう・えいいち 医学博士。山王病院呼吸器センター内科副部長。国際医療福祉大学教授。山形大学医学部卒業。東京大学大学院修了。東京大学医学部付属病院老年病科助手(現助教)、カナダマギール大学研究所・アルパータ大学呼吸器グループ派遣留学、大蔵省印刷局東京病院内科医長を歴任。呼吸器専門医など。肺炎、気管支炎、気管支ぜんそく、かぜ症候群などの診断と治療などに従事。 ポイント① 咳や痰が長引き、異常音は病院へ② 1に理3回の深呼吸でリラックス③ たばこは20,30年先をむしばむ 外の影響を直接受ける機関】呼吸は、空気中の酸素を体内に取り入れ、不要になった二酸化炭素を外に排出する大切な働きをしています。息を吸って鼻や口から入り込んだ空気は、期間を通栄、肺にある機関誌の中を進んで、末端の肺胞に到達します。子の肺胞で、酸素と二酸化炭素の高官が行われているのです。息を吐くと二酸化炭素が排出される仕組みになっています。外気と砂がっている呼吸器は、周囲の環境や空気中の影響を直接受けるため、健康を左右する機関であると言えます。呼吸で肺が動く時、肋骨と呼吸筋が連動しています。呼吸筋は、20種類以上あり、息を吐く時に動く「呼吸筋」と息を吸うときに動く「吸気筋」に分けられます。中でも最も重要なのが、肺の下部にある横隔膜(吸気筋)。安静時の呼吸の約80%は、横隔膜が担っています。こうした呼吸筋を鍛えることで、呼吸器の健康は保たれ、後で紹介するようなさまざまな健康効果が得られます。今回は、日常的に実践してほしい基本的な「呼吸法・呼吸筋トレーニング」を二つ紹介します。 肺機能アップで期待できる効果】呼吸の好不調を見極めるポイントは、問題なく普段通りの息ができていることです。反対に、咳や淡が長引いたり、「ゼーゼー」「ヒューヒュー」といった呼吸音があったり、明確な異常がある場合は、早めに呼吸器中を受診しましょう。軽度の息苦しさなど、呼吸筋を鍛えることで改善する症状もあります。また、肺の機能が高まると、血行が良くなり酸素が体の隅々まで生き渡ります。その結果、肺の健康のみならず、全身の機能にもよい効果をもたらすのです。期待できる六つの効果を紹介済ます。① 免疫細胞が活性化され、は血球の中のリンパ球が増える。結果的に、ウイルスや菌への撃退力が高まります。② エネルギーが消費され脂肪が燃焼する。③ 体内の隅々まで血が巡り、冷え性が改善。④ 腹部の血行が促進され、便秘改善。⑤ 腹筋や横隔膜が刺激され、腹圧が高まり、これも排便がスムーズに。⑥ 肺活量は増え、筋肉も鍛えられる、声が出しやすくなる スマホやパソコンで呼吸が浅く】心理的ストレスが高まったり、緊張状態が続いたりする時は、自律神経の交感神経系が優位になります。現代の〝ストレス社会〟に生きる私たちは、心身をリラックスさせる手段を持っておきたいものです。そこでオススメなのが深呼吸(腹式呼吸)です。というのも、息を吸うときは、自律神経の交感神経が優位に、履く時は副交感神経が優位になるからです。深呼吸でゆっくり息ウを破棄、リフレッシュする時間をつくりましょう。一方で、無意識な呼吸は、浅い呼吸(胸式呼吸)になりがちで、息を吸う方が多くなります。特に、スマホやパソコンを使う時間が長いと、首や背中を曲げた姿勢が続き、肺が膨らまず、呼吸がより浅くなります。最近の研究では、深呼吸をすることでセロトニン(幸せホルモン)が出るとも言われています。不安やストレスから解消され、落ち着きたい——そんな時な深呼吸をしてみましょう。できれば1日3回以上、1回1分提訴は続けると良いでしょう。ゆっくり眠りにつける効果が期待されます。 喫煙で肺胞は破壊される】空気の通り道となる、気管支の内側には、たくさんの毛がついています。これは線毛といい、入ってくるウイルスや菌、異物を捕まえます。繊毛が正常に働くために大切なのが、適度な湿度です。湿度が低くなり、体が乾燥すると、線毛の運動が弱まります。乾燥を防ぐため、水分をこまめにとることも、呼吸を健康に保つために実践できる工夫の一つです。また、加湿器などを利用し、適度な湿度に保つことも効果的でしょう。ただし、〝湿度は高ければ高いほど良い〟というわけではありません。カビや真菌は高い湿度を好みます。これも呼吸器を害する原因になるので、気を付けたいところです。最後に強調したいのが、呼吸をつかさどる肺にとって、一番よくないのが、やはりたばこだということです。肺胞は、喫煙により、どんどん破壊されていきます。〝不調を感じたら、すぐにやめれば回復するだろう〟という考えは大間違い。残念ながら、たばこによって一度壊れた肺胞は、元には戻りません。たばこの体への影響は、喫煙から20、30年後に出てくるときもあり、肺気腫(今は慢性閉塞性肺疾患〈COPD〉と分類される)などの命に係わる病にかかるリスクが高まります。呼吸器は、穂家の臓器と比べ、日常的に健康を意識することが少ないかもしれません。しかし、〝人生100年時代〟のQOL(生活の質)を上げるため、ケアすることが不可欠であることを知ってほしいと思います。 呼吸法・呼吸筋トレーニング口すぼめ呼吸① 首や肩の力を抜いて、鼻から「1、2」とゆっくり息を吸う。② 口をすぼめて、「3、4、5、6」とゆっくり長く息を吐き出す。※息を数時間の2~5倍の時間をかけて息を吐くのを目標にする。1日に何回行ってもいい。 ポイント:口から30cm離れたところにかざした手のひらに、かすかに息を感じる程度の強さでいい。 横隔膜呼吸① 仰向けに寝て膝を軽く曲げ、おなかに重り(砂糖袋など)をのせ、口をすぼめてゆっくりと息を吐く。この時、おもりが下がっていくのを意識する。② おなかの重りを上げるように意識しながら、鼻から息を吸う。 ※1分間で、①~②を4回繰り返す(1セット)。 1日3回行う。 ポイント:重りは500ℊ程度から始め、徐々に重くして、3kくらいまで上げるのを目標にする。 【健康PLUS+】聖教新聞2023.12.26
January 15, 2025
コメント(0)
-
ケアし合う関係を生むのは「する時間」より「いる時間」
ケアし合う関係を生むのは「する時間」より「いる時間」インタビュー㊦ 兵庫県立大学准教授 竹端 寛さん無駄に思えても——インタビューの前半では、子育てを通じた「ケア」の経験や、「ケアし合う関係」が生み出す豊かさについて、語っていただきました。そうした関係をつくるためには、どのような実践が求められるのでしょうか。 ケアには、圧倒的に「時間」がかかります。例えば、育児でいえば、子どものご飯を準備する。一緒に遊ぶ、ほかにも「お父ちゃん、これ見て!」と言われるたびに、今やっていることを中断して話を聞くなど、多くの時間が必要になります。前回に引き続き、また私の失敗談からお話しすることにします。育児を始めた当初、1日数時間ほど娘の面倒を見たら、〝やったつもり〟になっていました。子どもが寝ている時や、妻が娘を見ている時など、「この時間を含めて、私も家におらなあかんの?」と思ってしまったのです。それを話すと、妻からは「いてくれるだけで、安心できる」「ちょっと声をかけたら来てくれるのが大事なのよ」と言われました。ここでも、私がいかに仕事ばかりに集中してきて、賃金労働を中心にした考え方をしているのか、ということに気付かされました。仕事などの労働における人間の使い方は、具体的な「〇〇する」という、作業を中心にした「する時間」です。一方で、ケアでは「いる時間」、つまり存在を共にしている時間に価値があるのです。一見すると無駄に思える時間も、そこに一緒にいることが、インタビューの前半でお話しした「あなたと共に考え合う(ウイズネス)」という姿勢につながります。 相互依存の世界——インタビュー㊤では、ワーカホリック(仕事中毒)的な働き方をしていた経験を話していただきました。そうした生活と、「ケアし合う関係」に基づく生活では、何が異なるのでしょう。 ケアし合う関係は、お互いを必要とする関係性であり、こうした相互依存的な関係性こそが、ケアの醍醐味だと思います。「相互依存の世界」の意義は、その対極にある「自己利益の世界」を考えるとわかりやすいです。自己利益を追求するだけという弱肉強食の論理では「次に追い落とされるのは自分かもしれない」という不安と恐怖が生まれます。そこには、競争に負けるのは自分の責任だという、脅迫的な自己責任の論理があります。それとは違い、妻や子どもと一緒にいる相互依存的な関係性は、自分中心主義では成り立ちません。子どもの隊長や、やりたいことを優先しつつ、親自身の考えと折り合いをつける日々は、親の自己利益のみでは完結できません。子ども中心に回る生活は、親にとっては利他的というか、没我的な関係でもあります。私の場合、自己利益の世界観を超えることで、「責任」に関する感覚の転換がありました。自己利益の政界でいわれる「自己責任」には、懲罰的な響きがあります。自分でしたことなんだから、自分で責任を取らなければならない、という義務の論理です。一方で、子どもの養育は、親にとって義務でもありますが、同時に悦びでもあります。懲罰的な自己責任とは違った、より肯定的な責任を引き受ける感覚があるのです。政治学者のヤシャ・モンクは、育児や困窮上程の親類の世話になっていて、それも一つの社会貢献であると述べ、肯定的責任像を提起しています。わたしも、家事や育児の責任を引き受ける中で、自分には父親として生きる意味や価値があるのだと、自身の存在を丸ごと肯定的に感じられるようになりました。娘へのケアは、私を力づけてくれることでもあったのです。ケアし合う関係は、ケアを試みる側の人間的な成熟にも、大きな役割を果たします。かつて、仕事の成果や他人との比較でしか自分を評価できなかった私自身が、娘へのケアを通して、生きる姿勢が大きく変わっていったのです。こうした変化は、親子だけに限りません。私自身の学生とのかかわり方も変わりました。以前は、リポートの提出期限を守れない人を「ダメな学生」と思い込んでいました。けれど、今は「言語化できない苦しいことがあるのかも」と、考えるようになりました。自己責任の論理で見れば、「期限を守れないと、社会では通用しないよ」と、責めたくなります。しかし、本当は社会が許さないのではなく、「私があなたを許せない」と言いたかったかもしれません。弱肉強食の論理の中で、これまで「ちゃんとやってきた」自分の成功体験に引き当てると、一人一人の事情に思いをはせた関りが、できにくくなります。だからこそ、変わらないといけないのは「指導する側」だと思います。ケアし合う関係性を作るために、子どもでなく親が、性と背はなく教師が、部下でなく上司が、変わることが求められているのです。 違いを知る対話——ケア関係を友人や同僚などにも広げようとすると、多様な考え方を持つ人同士で、相いれない場面もありそうです。具体的には、そう接していけばよいのでしょうか。 他者が持つ、自分には理解しきれない性質を「他者の他者性」と呼びます。友人や同僚はおろか、妻や子どもといった家族であっても、完全には理解できません。どんなに頑張っても、私は妻や娘にはなれないし、私の理解しえない他者性が残り続けます。例えば、妻と結婚して20年たち、毎日会話していますが、今でも「そんなこと知らなかった」という気付きがあります。他社には、想像もつかない他者性があるため、他者と意見を完璧に一致させることは、無理だとも言えます。それでは、物事を決まるときには、どうすればよいのでしょうか。オープンダイアローグという精神療法の提唱者であるトム・アーンキルは、「違いを知る対話」と「決定のための対話」を分けるやり方を教えてくれます。彼が務めていた研究所では、方針を決定する時などに、まずテーマについてお互いに思いをざっくばらんに語り合う「違いを知る対話」に時間をかけます。それを経て、お互いを理解したうえで、「では、どうするか?」という「決定のための対話」を行うと、方針がうまく決まりやすいそうです。「違いを知る対話」で大切なのは、相手の言っていることを、そのまま「理解しよう」とすることです。これはm「許し」や「共感」とは違います。相手の主張が自分の考えと合わない場合でも、無理して許さなくてもいいし、共感しなくてもいいのです。たとえ「訳が分からない」と思ったとしても、相手がなぜそう考え、そう話しているのかを「理解しよう」とすることが、相手とつながる根拠になります。つまり、ありのままのその人の存在を丸ごと承認するのが「違いを知る対話」なのです。それを経て「決定のための対話」を行えば、決定の質がより良いものになります。これは、とても面倒なことでもあります。けれど他者には、自分が想像しえない他者性があることを見つめていくと、それと同時に、自分自身にも「己の唯一無二性」ともいえる、他所と違う固有の性質があることに気付きます。こうした対話のプロセスが「ともに思いやる」「ケアし合う」関係性の基盤になるのです。 実践の楽観主義——完全には分かり得ない他者だからこそ、対話を続けることが必要なんですね。 完璧には分かり得ない他者を相手にするわけですから「引き裂かれそうな葛藤」に直面することもあります。私の家庭でいえば、6歳の娘は、本人の思いをグイグイぶつけてきます。親としては、理解するより「ちゃんとしてよ!」と叱って、共生的に従わせたくなる時もあります。けれど、そうした葛藤が最大化する場面こそ、「他者の他者性」に出あう最大のチャンスなのです。娘をケアする中で痛感するのは、「他人と過去は変えられない。変えられるのは自分だけ」ということです。父である私が何と言おうと、しっかりした医師をもって娘は、すがすがしいくらい反発してくれます。まるで娘が「私には、お父ちゃんとは違う、他者性があるで!」と言っているかのようです。同時に、そうやって自己表現ができるのは、父親に表現したら理解してくれるからだという安心感を持っているからだとも感じます。そんな時、父である私は、イライラする自分をいったん脇に置いて、何とか娘の自己表現を読み解こうと奮闘する毎日です。こうやって相互承認を繰り返す中で、娘との信頼関係ができていき、お互いの尊厳を大切にできるようになっていきます。これが「ともに思いやる」というケア関係なのだと思います。 ——創価学会でも、日常の活動の中で、さまざまな「対話」の場面があります。苦悩や葛藤を共に経験する中で、「ともに思いやる」関係ができていくということは、実感として納得できます。 悩みや葛藤を抱えながら、それに「共感」「共苦」するというのは、本来、宗教のコミュニティー(共同体)が果たしてきたことでもありますね。現代社会においては、そうやって多様な一人一人をそのまま受け入れてくれるコミュニティーを複数持つことが大切だと思います。私自身も、子育てコミュニティーにも所属しつつ、同時にシュミの合気道につながっているコミュニティーもあります。そうしたケア中心の生き方が広がれば、自己責任の論理で誰かを排除するのではなく、誰もが生きやすい社会に、少しずつ近づいていくと思っています。そのために、今日からできるケアの実践は、具体的な誰かと会って、「違いを知る対話」を通して関係性をつくっていくことです。他者には、自分は分かり得ない部分が必ずあります。けれど、わからないからこそ、対話ができるという希望があるとだと思います。イタリアの医師バザーリアは「〇〇だから、できっこない」と、やる前にあきらめの姿勢を「理性の悲観主義」と言いました。それより大事なのは、「実践の楽観主義」だと唱えたのです。言い換えれば、「できない100の理由」を探すより、「できる一つの方法論」を共に考え合うということです。例えば、目の前で赤ちゃんが泣いている時に、「今はケアできない理由が……」などと言っている暇はありません。「ケアは実践ありき」なのです。具体的な他者と関わり、対話的な関係を結ぶこと。そうした楽観主義的な実践が、ケア中心の社会につながっていくと信じています。 【危機の時代を生きる「希望の哲学」】聖教新聞2023.12.23
January 14, 2025
コメント(0)
-
地層の面白さ
地層の面白さ〝石の世界〟案内人 古白井 亮一どうやってできたのかみなさんは、地層と聞くとどういうものを思い浮かべるでしょうか。典型的な地層は、文字通り砂と泥の層が縞模様」になっているもの。中学校の理科では、地層のでき方として、砂や泥などの砕屑物が水流や風によって運ばれ、浅い海で砂、深い海で泥が堆積してできると説明されます。しかし、海底で徐々に連続的にたまっていたとすると、同じ場所に同じような砕屑物が堆積するはず。浅い海と深い海の状態が繰り返されることで、砂や泥の縞模様になると説明されますが、短時間で繰り返すのは非現実的です。では、縞模様の地層はどのようにできたのでしょうか。実は、混濁流という現象が関わっています。混濁流は、兄弟で起きる雪崩のようなもの。堆積物のたまる海底は、斜面になっていて、沖に向かって深く下がっていきます。それが何かの拍子に崩れると、混濁流となって斜面を滑り落ちていくのです。やがて、海底の斜面がなだらかになると、混濁流の堆積物は重いものから順に沈むことになります。初めに砂などの重たい粒が堆積し、その上に巻き上げられた泥が覆うように積もっていきます。このようにして、砂と泥の層ができます。混濁流は、大きな地震などによって起きると考えられています。きれいな縞模様の地層を見て、数百年から数千年くらいの感覚で繰り返し発生している大地震など、ダイナミックな地球の活動を創造してもらいたいのです。 過去の出来事を記録地層の中には、千葉・南房総市の千倉層群畑層のように、縞模様が崩れてパッチ上になったものもあります。どうしてばらばらの状態になったのでしょうか。通常、地層に左右から大きな力が加わると、曲がることはあっても、このように割れてしまうことはありません。これは液状化が原因です。液状化は、水分を含んだ地層が、巨大地震などで激しく揺られると起こります。阪神・淡路大震災や東日本大震災でも報告されていますが、地面から砂を大量に含んだ水が地表に噴出する現象です。一度できた地層が液状化でバラバラに破壊され、再び泥に埋もれて、このような地層になったのです。 縞模様は異変の痕跡泥質層から得られる多くの情報 隕石衝突説のはじまり恐竜の絶滅は巨大な隕石の衝突のせい——この「隕石衝突説」が生まれたのも、ある地層の研究からでした。隕石に多く含まれているイリジウムという元素が、中生代と新生代の境界、約6600万年前の地層から大量に見つかったのです。同じ時代の地層は、日本でも見ることができます。北海道・浦幌町にある根室層群活平層です。青緑色がかった暗いグレーの地層の中に、厚さ数㌢の黒い層があります。これが中生代と新生代の境。道東は日本の中でも珍しく、中生代後期から新生代前期にかけての連続的な地層が見つかっています。この黒い層には、隕石由来のイリジウムが含まれていただけでなく、シダ植物の花粉の化石も見つかっています。シダ植物は、日差しが弱く、寒い所でも生き延びることができます。隕石の衝突による環境の変化にも耐えることができたのでしょう。地層とそこに含まれる鉱物や化石を調査することで、過去の事件も分るのです。日本列島がどのようにできたのか、そんなスケールの話に行きつくのが地層の面白さです。各地のジオパークや博物館などで、その場所の地質的な話題が紹介されています。面白い地層を見つけて、太古の地球に思いをはせてみてはいかがでしょうか。=談 こじろい・りょういち 1960年、東京都生まれ。国土地理学院で測量や地図作製などに従事。現在は、地層・化石・岩石など〝石の世界〟について、わかりやすく伝える執筆活動に取り組む。近著に『すごい地層の読み解きかた』がある。 【文化Culture】聖教新聞2023.12.21
January 13, 2025
コメント(0)
-
卓 球
卓 球筑波大学名誉教授 株式会社THF代表 田中 喜代次多世代で手軽に楽しめる種目卓球は世界各国で行われ、オリンピック競技として広く知られています。今年、現役を引退した女子の石川佳純さんをはじめ、伊藤美誠選手や平野美宇選手、早田ひな選手、男子では張本智和選手らの若手の活躍により、空前の人気上昇となっています。野球の一流投手では、人体の損傷で外科手術を受けるケースが多いですが、卓球はラケットもボールも軽いため、スポーツ傷害が少ないのが特徴です。プレー中に相手と接触するリスクも少なく、健康的スポーツの代表格といえるでしょう。80台後半になれば、ひ孫と卓球をプレーする人もいます。自分の体力や年齢、技術に合わせて行うことができる上、ルールも理解しやすいことから、多世代で一緒に手軽に楽しめるスポーツです。居住地内の公立体育館や公民館、交流センターなどに卓球台が設置されている場合も多く、夜間時など天候や時間に関係なく、大いに楽しめます。卓球を継続して続けていくことによる長所は、卓球台が小さく、相手との距離が近いことから、俊敏性や道的バランス、動体視力が高まります。外出時における他社との接触や自転車での衝突事故、転倒事故なども防げるでしょう。危険が差し迫った際に、俊敏に回避する能力も高められます。一方卓球は屋内で行われるため、紫外線を浴びることが少ないことから、骨強度(骨密度+骨質)は高まりにくいかもしれません。日光の紫外線を浴びると体内にビタミンDが作られて、カルシウムの吸収を高めるからです。卓球以外の時間帯に、朝や昼に20~30分でも適度に紫外線を浴び理機会をもつことも勧めます。また、まれに肉離れや筋肉の断裂、足のねんざ、膝の損傷などが起こる可能性があります。そこで、ストレッチなど日ごろから身体の入念な手入れとともに、プレー中には頑張り過ぎない心掛けが必要になります。 【チェレンジ! 生涯スポーツ―<6>―】公明新聞2023.12.19
January 12, 2025
コメント(0)
-
旅する江戸の女性たち
旅する江戸の女性たち東洋大学法学部教授 谷釜 尋徳各地の美味や芝居見物を求め困難をもろともしない行動力江戸後期、伊勢参りをはじめ諸国の寺社を巡る旅が庶民の間で大流行する。その担い手は男性だけではなく、女性が遠くの土地まで観光旅行に出かけることも珍しくなかった。泰平の世が訪れた江戸後期には、貨幣経済の浸透や交通インフラの整備も含め、女性が旅をしやすい環境ができあがっていたからである。江戸時代の旅は徒歩移動が基本だったため、女性も懸命に長距離を歩き続けた。女性たちの旅日記を分析すると、1日平均の歩行距離は30㎞におよぶ。男性の平均が1日約35㎞程度だったので、女性は男性に匹敵する歩行能力を持っていたことになる。江戸時代の街道は、参勤交代のために整備されたエリアもあったが、道幅の狭い急勾配の峠道や、荒波の打ち寄せる海岸沿いの難所も存在した。また、軍事的な理由で橋のない大河が多く、東海道の大井川では工学を払って河越忍足に担がれ、水中に落下する恐怖に耐えて渡らなければならなかったという。江戸を守るように設置された関所では、女性は関所手形を準備したうえ、厳しい取り調べを受けなければ通行が許されなかった。ところが、江戸後期には無手形で旅する女性が急増し、周辺の宿屋に案内賃を渡して関所破りをする女性も現れる。女性にとって、街道の通行はスリル満点の冒険の連続だったのである。数々の浮き身に遭いながらも、女性たちが相次いで旅の世界に身を投じたのは、そこに苦難を吹き飛ばすような魅力を感じていたからだろう。女性の旅日記を読み解いていくと、大都市では芝居見物に通い詰めることが定番の行動パターンだったらしい。江戸滞在中の丸一日を芝居見物に充てる女性も多くみられた。現代人と同じく、江戸の旅人が心待ちにしたのが旅先のグルメである。女性たちも、各地の名物やスイーツ、時には懐石料理の豪華なフルコースまで、道中のグルメを食べつくした。文政8年(1825)、江戸神田(東京都千代田区)の商家の妻、中村いとは、伊勢参りの装柱で名物を食べ歩き、旅日記にグルメ評論を書き残している。なかには、「蕎麦は美味いが汁の醤油味がまずい」などとケチをつけた例もあり、女性目線の実食レポートとして面白い。湯水のように各地の大金を落とした女性もいる。文久2年(1862)、由利郡本荘(秋田県由利本荘市)の裕福な町人女性、今野於以登は、およそ5カ月間の大旅行の最中に約30両を使った。於以登は、各地の名物で胃袋を満たし、名産品を買い漁り、温泉につかって心身を癒し、都市観光を満喫し、お座敷遊びや芝居見物に熱中するなど、これでもかと遊び倒す。金に糸目をつけない、豪快なセレブ旅行である。江戸の女性たちの徒歩旅行は、どうしても困難な側面だけにフォーカスしがちである。しかし、人間が歩くスピードで進行する旅の世界は、道中に広がるさまざまな異文化を漏れなく吸収するには打って付けだった。私たちが想像するよりもずっと、江戸時代の女性たちは活力にあふれた魅力的な旅を楽しんでいたのではないか。 たにがま・ひろのり 1980年、東京生まれ。2008年、日本体育大学大学院後期課程修了。博士(体育科学)。専門はスポーツ史。著書に『江戸の女子旅—旅はみじかし歩けよ乙女—』(晃洋書房)、『スポーツの日本史—遊戯・芸能・武術—』(吉川弘文館)など。 【文化】公明新聞2023.12.20
January 12, 2025
コメント(0)
-
豊かな里水と生きる
豊かな里水と生きる瀬戸内海流域の水環境小野寺 真一 川や地下水、ため池、また、それらがつくる地形、生態系を利用し、豊かな暮らしを育んできた瀬戸内地域。『瀬戸内海海流域の水環境—里水—』では、人と水環境の共存・共生のシステムを新たに「里水」と定義し、海流全体での自然と人間生活の持続可能性について論じている。編著者の小野寺真一・広島大学大学院教授に聞いた。 有効に利用する仕組み瀬戸内地域は年間の平均降水量が1200㍉を下回るなど、全国的にも降水量の少ない地域です。さらに気温は全国と比べて高く、蒸発散量も多いため、水資源として利用できる水は他の地域と比べても少なくなっています。一方、この地域は古くから多くの人が住み、活動も盛んだったことから、この限られた水資源を有効に利用する仕組みも数多く存在してきました。例えば、大小無数に構築された、ため池、さらに、そこから南洋された地下水を再利用する仕組みとして、人工的に字面を彫り込んだ「出水」など、山から流れてしまわないよう、陸域で有効利用する仕組みが人工的なものを含め、多様な形態で築かれています。少ない水資源を持続的に利用してきたこうした仕組みは、「里水」という概念で捉えることができるのではないかと考えています。里山、里海は既に一般的になりましたが、人が自然環境を積極的に利用鹿と要することで保全につながるという点は、ため池や地下水の利用など、水を巡る環境にも当てはまります。さまざまな形態(河川、湧水、地下水、湖沼など)で存在する水は人々に利用され、その一方で、それぞれの場で保全効果があったと評価できるのです。 地下水、出水、ため池瀬戸内地域で、里水における重要な役割を果たしているひとつが地下水で、その利用は多様な形で行われています。山から海へ向かって流れる水には、地表を流れる水と地価を流れる水があり、大陸地域では両者の割合は約20対1と、地表を流れる水が圧倒的に多いのですが、日本のように急こう配で、降水量の少ない瀬戸内地域では相対的に地価を流れる水の割合が上がります。例えば、香川県の土器川流域では約1対1になるなど、地価を流れる水の重要度は高くなっています。また、地価を流れる水は滞留する時間も長く、場所によっては陸域に100年以上とどまることもあり、渇水の年には大切な水資源になります。灌漑用水源として利用されてきた「出水」は、この地下水を修水する地域独特の仕組みです。この出水は水田からの浸透水を再利用するシステムとしても有効で、深刻な渇水年だった1994年には、丸亀平野(香川県)における干ばつ被害の軽減に大きく寄与したとされます。また、ため池は全国で約21万カ所ありますが、その約6割が瀬戸内地域に分布し、農業用水を確保する目的で造成されています。その役割は香水時に臼井を一時的に貯留する香水調節、土砂流失防止などの防災機能や希少な生態系の保全にまでわたっています。さらに人工的に築造された池でありながら、実際には周辺の地下水を涵養し、地域の水循環に寄与する重要な機能も持っているのです。 温暖化の影響防ぐ対策にも 持続可能な連携の実現地球規模で進行中の温暖化は、世界各地の気候や生態系に影響を与えていますが、日本列島では降水量の変動として顕著に表れているといえます。渇水年の増加や1日の降水量が100㍉を超えるような集中豪雨の頻発はそれを物語っています。こうした降水量の変動は、使用可能な水資源の量の減少につながっています。しかし、ダムに偏った現在の水システムは、こうした降水量の変動に十分対応できず、増加する水資源のロスを防ぐことはできません。こうした状況に対しては、一時的に雨水を貯留するため池や、地下水を繰り返し利用するといった、里水の有する機能を維持し、向上させていくことが非常に有効であると私は考えています。そのためには、山から海に向かって流れる水の流域環境と、そこに住む人々をつなぐ連携が今後重要になってくるでしょう。私はそれを「流域環境とそこに住む人々双方の利益のための持続可能な連携」(SATO-NET)として実現できるのではないかと考えています。単なる流域間のネットワークではなく、上流域、下流域でそれぞれ利益を共有できる仕組みを実現し、地域の里水の機能を高めていくということです。私たちの研究グループ(共編著者の齋藤光代・広島大学大学院準教授ら)では、上流域の農業地域における肥料成分を多く含む地下水を農地で再利用し、肥料の削減に加えて、下流域の汚染防止を図るという仕組みも提案してきました。近年、里山と里海の連携が検討される場面も見られるようになっており、瀬戸内地域では河川の上流から下流を含むエリアでの全体的な協議を行うといった取り組みもされています。瀬戸内地域は水資源に乏しく古くから渇水被害にさらされてきた地域だけに、水を得るためにより苦労を重ねてきました。その結果としての効果があったことは明らかであり、将来に向けては、水循環、水利用という点で流域の連携が重要であり、価値を共有しつつ、里水の機能を高めていくことが重要であると考えています。 おのでら・しんいち 1964年、東京都生まれ。博士(理学)。広島大学准教授などを経て現職。流域吸・流域吸・物質循環研究に取り組む。著書に『リンの事典』(編著)などがある。 【社会・文化】聖教新聞2023.12.19
January 10, 2025
コメント(0)
-
モデル臓器で生命現象を再現
モデル臓器で生命現象を再現科学文明論研究家 橳島 次郎疾患の解明や創薬への応用も最先端の細胞培養技術を駆使して、立体的なミニ臓器を作ったり、合成樹脂のチップを作って栄養や酸素を循環させ、生体内で起こる現象を再現する研究が盛んになっている。こうした研究手法をマイクロフィジオジカル・システム(MPS)という。身に臓器研究では、例えばミニ肺を作って、コロナウイルスがどのように感染し排煙を起こすかを調べたり、ミニ腸を作ってウイルスのさまざまな変異株を感染させ、増殖や細胞障害の度合いを比較する研究が行われている。チップ上の臓器研究では、今年、京都大学など肝臓と省庁の培養細胞チップをつないで、肝炎が起こる仕組みを明らかにするモデルを作った。米国ではチップ上の台帳に免疫細胞を組み込んだモデルを作り、がんなどの研究に生かす成果が発表された。他に腎臓、膵臓、骨髄、皮膚などのチップ上のモデルと、それらをつなぐシステムを作る研究が行われている。卵巣、卵管と子宮などのチップをつなぎ性周期と卵子の熟成を再現するモデルも作られている。MPSは薬物が各臓器の間で同代謝されるかを調べ、毒性や効果を検証する創薬研究での対応が最も期待される。マウスなどで試すよりも人の体内で起こることを的確に再現できるので、動物実験の代替法として認められれば、実験動物の犠牲を減らすことができる。また患者の細胞を使ってMPSを作れば、その人にどの薬が効くか効かないかを実際に投与する前にテストできるので、最適の個別化医療を実現する基盤技術にもなる。MPSでは脳神経系のモデル作製も行われ、脳科学の基礎研究や実験動物では再現が困難な精神疾患の研究に役立てられている。例えば自閉症の患者の細胞から培養したミニ脳を用いて、この病気に特有の脳の働きの異常を明らかにした研究が発表されている。だが、ミニ脳となると、倫理的な懸念も出てくる。多くのニューロンがつながって働く高次のモデルの構築を目指すと、感覚や意識のある存在を作ってしまわないかが問題となる。また、より生体内に近い環境で脳の活動を再現する方法として、ミニ脳を生きたマウスの脳に移植する研究が行われているが、わずかとはいえ人間の脳を持つネズミを生み出すことになるので、倫理的な是非が問われる。前々回取り上げたモデル胚作りも、MPSの一発展型と見ることができる。どんなのをどこまで作ってよいかが議論の的になる。 【先端技術は何をもたらすか—12—】聖教新聞2023.12.19
January 9, 2025
コメント(0)
-
池波正太郎を読む
池波正太郎を読む生誕100年を迎え、台東区名誉区民に文芸評論家 菊池 仁時代小説のジャンル融合し独自の物語盗賊世界や暗黒街、食事場面も盛り込む池波正太郎は、今年で生誕一〇〇年を迎えた。人気は年を重ねるごとに増大しつつある。その人気を裏付けるように15日には、出生地の台東区から名誉区民の称号が贈られた。改めて人気の秘密を探ってみた。根強い人気を得ているのは、『鬼平犯科帳』、『剣客商売』、『仕掛け人・藤枝梅安』、『真田太平記』の四大シリーズである。理由は、時代小説の愛好家の好物である武士道もの、捕物帳、市井人情もの、剣豪もの、戦国もの、忍者ものといったジャンルを融合、網羅し、それぞれ独自の世界観で物語を構築しているからである。中でも『鬼平犯科帳』は、規律を重んじる武士道精神と市井人情ものを読みやすい捕物帳形式で連作化したことが多くの読者をつかんだ。極めつけは誰も書かなかった江戸の闇である盗賊の世界や暗黒街を主要舞台としていること。前段に『闇の狩人』と、闇は知っている」がある。この二作の主題を発展させて、複雑な人間関係と、組織のしがらみに縛られ、必死に生き延びようとする闇住民の生きざまを、細部に目を配りながら描いている。特に、江戸の治安を守る火付盗賊改め型の長官・長谷川平蔵を豊かな人間性を備えた本物の男として造形したこと。慕う部下たちとのチームワークや、盗賊も虜にしてしまうエピソードなど、楽しみな名編が数多くある。『剣客商売』は、剣豪小説の面白さに時代性を巧みに取り入れ、人情ものの温かさで包み込んだまったく新しい剣豪ものと言える。女好きで世間を裏も知り尽くしている小兵衛の飄々とした生きざまが得がたい魅力となっている。これに息子との交情、女武者三冬など個性豊かな面々が加わり、大河小説の趣を呈し、爽やかな読後感を堪能できる。『仕掛け人・藤枝梅安』は、時代小説の新たなジャンルを開いた異色作である。驚嘆したのは理不尽な金と権力の横行で、踏み潰された庶民の怨嗟を掬い取る仕組みを描いたことだ。文中に出てくる仕掛け人に関する用語は、 すべて作者の造語である。虚構を精巧な細工した手で物語に取り込む手法は、シリーズの特色でもある。梅安は作者が江戸の歴史を渉猟し、想像力を駆使してきた彼岸に見えた幻の江戸といえよう。効果を上げているのは、匂い立つような食事の場面を満喫できること。『真田太平記』の面白さは、戦国時代の激動の中で翻弄される小藩真田家の攻防に、忍者の熾烈な暗闘を織り込んだ手法にある。それがテンポの良い雄渾な流れとなって、大河を作り上げた。藩祖真田信之と忍者の交情を描いた直木賞受賞作『錯乱』で文壇に躍り出た作者は、これを起点に『夜の戦士』、『忍者丹波大介』、『蝶の戦記』、『忍びの旗』等の作品で、戦国史を一貫して忍者の目を通して描くという離れ業をしてのけた。この成果を基に作者の成熟が加わり、結実したのが『真田太平記』である。最後に、長編のお勧めは、『編笠重兵衛』、『おとこの秘図』、『さむらい劇場』の三冊。作者は短編の名手で、一冊だけ挙げれば『あほうがらす』がいい。(きくち・めぐみ) 【ブック・サロン】公明新聞2023.12.18
January 8, 2025
コメント(0)
-
違和感に耳を傾ける
違和感に耳を傾けるそれが行動を変える種となるハーバード大学医学部准教授 内田 舞さんうちだ・まい ハーバード大学医学部准教授。小児精神科医。マサチューセッツ総合病院小児うつ病センター長。3児の母。2007年に北海道大学医学部卒業。11年にイェール大学精神科研修終了、13年にハーバード大学・マサチューセッツ総合病院小児精神科研修終了。著書に『ソーシャルジャスティス 小児精神科医、社会を診る』(文春新書)、『REAPPRAISAL』(実業之日本社)がある。 2021年1月、妊婦としてはあまり前例のない段階で、新型コロナワクチンを接種した、小児精神科医の内田舞さん。接種直後の写真がSNSで反響を呼び、日本でもその名を知られるようになりました。現在、ハーバード大学医学部准教授、マサチューセッツ総合病院小児うつ病センター長を務めています。3児の母としても多忙な中、心や脳の科学について、さまざまなメディアで発信を続ける内田さんに、その放熱の源と、日本のジェンダー問題に抱く思いを聞きました。 ■人種差別を経験した幼少期21年1月当時、日本では「ワクチンをうつと流産する」「不妊になる」というデマがまん延していました。科学を通して人間と社会を支える医師でありたいと思っていた私は、日本のそうした状況を見過ごすことはできませんでした。ワクチンに関して、現段階で分かっていない情報を併せて伝えることで、自分の気持ちにしっくりくる判断をしてもらいたい。そのために自分ができることは全力でやろうと、日本メディアからの取材対応や行政機関への講義、SNSのライブ配信を行いました。そうした活動の動機になっているのが、ソーシャルジャスティス(社会正義)への強い思いです。ソーシャルジャスティスとは、私の独自の解釈も交えると、「弱い立場に置かれた人の尊厳が守られるために、何をしたらいいかを考えること」です。私は小学生の頃、アメリカ、スイス、日本の3カ国で、転校を5回経験しました。そのたびに、すでに出来上がっているコミュニティーに入っていかなければなりません。友人には優しくしてもらったり、声をかけてもらったり、とても助けられました。一方で、人種差別の現実も経験しました。同い年ぐらいの子どもたちに講演で囲まれて、つばをかけられたこともあります。人種によるヒエラルキー(海藻)が存在し、「アジア人=下に見ていい」という社会の雰囲気がありました。こうした経験から「人種や属性で差別されたり、不平等な扱いを受けたりするのはおかしい。社会からなくしていきたい」と、強く思うようになりました。この医師は、幼少期から今に至るまで変わりません。私の心の芯にあります。私が住むアメリカには、ヘイトクライム(憎悪犯罪)も存在します。日本にも、障がい者や性的マイノリティーの方、在日外国人の方などに対する差別があります。女性に対する差別もなかなか改善していません。 ■女性医師が増えたら医療崩壊する?日本では、18年に東京医科大学の入試で女性受験者が不利になる点数操作を受けていたことが発覚しました。ショックだったのは、その事件以上に「平等に合理を判断したら、女性医師ばかりになってしまう」「女性医師が増えたら、日本の医療はどうなるんだ」という声の多さでした。アメリカの医師は、約4割が女性です(19年時点)。女性医師の割合が7割を超える国もあります。もちろん、これらの国で女性医師が増えたことによる医療調査による医療崩壊は起きていません。17年に行われた21%、OECD諸国で最低レベルとなっています。「女性医師は主産があるから」との意見も聞きます。私自身はサンゴ12週間で復職しました。日本の医療現場では、12週間という期間もあっても、一人の医師がかけては診療が持たない現状があるようです。そうした環境では、医師は自分の体調不良や家族の病気にも対応できず、休暇も取れません。性別や既婚未婚に関わらず、誰もが心身の健康を育み、私生活を充実させる権利があります。「女性」という性別に目を向けるのではなく、労働環境を見直すべきです。そのためにも、こうした労働環境やジェンダー不平等の背景にある「固定観念」や「無意識の偏見」を考える必要があります。 ■〝いつもと違う〟経験をする社会の中で、〝女性はこうあるべき〟というメッセージを何度も受け取ったり、〝周りで目にする女性はこういう人が多い〟という経験が積み重なったりすることで、「固定観念」という「習慣」がつくられます。習慣化した試行を変えるには、新しい環境に身を置く、属性も背景も全く違う人と話すなど、〝いつもと違う〟経験をすることです。違和感や言葉にできないもやもやも大切にしてください。「自分の考えとは違う」「相手は間違っている」など、ネガティブな感情を抱いた時はそのまま受け流さず、いったん立ち止まって、自分の考えと向き合う作業を行うのです。これを心理的アプローチで「再評価」と言います。性評価は、相手を理解するためのアプローチとしても有効です。その人がどんな経験を持ち、どんな思いでその言葉を発しているのか、相手の立場に立って創造する。つまり「他者の靴を履く」と比喩される「エンパシー(共感)をもって、相手の考えを評価するのです。まったく別の捉え方や視点に気付けるようになります。 ■意識をアップデートし続ける上司の姿勢日本では、意思決定層の大半を占める上の世代に対して、「あの人たちの考えを変えることはできない」と感じている若い世代が多いと聞きました。私は、世代というよりも、個人によるところが大きいと思います。なぜなら、私の上司たちは、世代とともに自身の意識や感覚をアップデートし、次世代のエンパワーメントに尽力してくれているからです。70年代の男性上司は、出産後に論文の感性が遅れてしまっている私に対して、次のような言葉をかけてくれました。「『ゆっくりでもいいから、馬から降りないこと』が一番大事だよ」「どんなに遅いペースでもいいから、続けていれば、必ずその努力の蓄積は実る」——この言葉は今でも私の支えになっています。90代の男性教授は、21年度に入学したハーバード大学医学部の6割が女性だったことを「大きな進歩だ」と受け止めつつも、「ハーバードもここまで進歩したからもう進歩しなくてもいいわけではない」と語っていました。彼らの姿から、私自身もまだまだ変われると励まされます。固定観念や無意識の偏見を抱くのは誰であっても同じです。だからこそ、それらに気付く努力が大切です。あきらめの心や無力感に覆われた時は、自分が苦しんだことを、後輩や子どもに引き継がせたくないと決めるだけでもいいと思います。その意思が、変化の種となって自分自身の行動を変え、社会を前進させる一歩になります。 【▪ライフスタイル】聖教新聞2023.12.17
January 7, 2025
コメント(0)
-
「境界知能」とは
国内推計1700万人「境界知能」とは立命館大学(児童精神科医) 宮口 幸治氏に聞くみやぐち・こうじ 神戸大学医学部卒。医学博士。臨床心理士。児童精神科医として精神科病院や医療少年院に勤務し、1016年より現職。一般社団法人「日本COD-TR学会」代表理事。主な著書に『教会認知の子どもたち』(BS新書)、『ケーキの入れない非行少年たちのカルテ』(新潮新書)など。 知能指数(IQ)の平均域と知能障がいのはざまに当たるIQ)70~84の「教会知能」の人は、全国に1700万人(人口比約14%)いると推計される。その多くは社会に適応して生活しているが、中には教育や福祉の支援につながることができずに、〝生きづらさ〟を抱えたまま暮らす人もいる。教会知能の人をめぐる現状や支援の在り方などについて、立命館大学の宮口幸治教授(児童精神科医)に聞いた。 平均と障がいのはざま周囲の理解得にくい生きづらさ抱える どんな状態か——境界認知の人には、どんな生きづらさがあるか。宮口幸治教授 一見、日常生活を送る姿は健常者と何ら変わらないので、仕事でミスをくり返したり、困りごとが起きてパニック状態になったりして困難を抱えることが多いが、周囲の理解や助けを得られにくい。いわば〝普通〟に見えるのに〝普通〟ができないため、やる気の問題だと誤解されてしまい、適切な支援につながれない恐れがある。こうした人々は、仕事が長続きしなかったり、犯罪に巻き込まれたりといった問題に直面した後に検査を受け、境界認知だと判明することが多い。社会に出る前の学校生活では困難が目立ちにくいので、仮に学校の授業についていけなくなっていたとしても、恥ずかしさから誰にも相談できず、単に「勉強の苦手な子」として扱われてしまうケースも少なくない。——何が生きづらさにつながっているのか。宮口 境界認知の人の特徴として、「5セット+1」が挙げられる。①認知機能の弱さ②感情陶製の弱さ③融通の利かなさ④不適切な自己評価⑤退陣スキルの乏しさ——そして、身体的不器用さがある。最後をあえて+1としているのは、小さい頃からスポーツを通して身体機能に優れている人もいるからだ。これらは①見たり聞いたり創造する力が弱い②感情をコントロールするのが苦手③予想外の出来事に弱い④自分のことを客観的に見るのが難しい⑤人とのコミュニカ―しょんが不得意⑥力加減ができない——と言い換えられる。 学校で認知機能訓練を〝克服〟へ早期発見・対応が大事 必要な取り組み——どのような支援が求められているか。宮口 抱えている困難の〝克服〟へ、早期発見・早期対応が大事だ。先に紹介した「5点セット+1」の特徴も踏まえて当人の状況をよく理解し、生きづらさを和らげるための力を身につける取り組みが必要で、ほぼ全ての人が通う義務教育現場で実施するのが望ましい。小学校の段階から、学習の土台となる認知機能のトレーニングを実施すれば、認知機能を鍛えるとともに一人一人の特性も把握できるので、早くから個別支援が可能になる。社会を出てからでは、教会知能の自覚がない人を見つけ出して支援につなげるのは困難だ。——具体的には。宮口 既にいくつかの小学校で採用されているが、私が考案した認知機能強化トレーニング「コグトレ」は、学習面、社会面、身体面で子どもを支援する包括的なプログラムで、朝の会の10分程度で行える。タブレットなどの情報通信技術(ICT)端末にも対応しているので現場の負担を大きく増やさずに済む。なお、トレーニングを行う崔は、境界知能の子だけではなく全員を対象にする方がいい。補習のような位置づけでは子どものプライドを損ねてしまうし、誰にでも苦手分野は存在する。皆で一緒に取り組むからこそ、継続した活動になる。 本人の気持ちを大切にして支えて ——保護者は境界認知の子どもをどう支えていけばいいのか。 宮口 「多様性を大事にして、ありのままを受け入れたい」「少しでも苦手な部分を減らしてあげたい」といった周囲の価値観を押し付けず、本人の話を聞き、その気持ちを大切にしてほしい。本人が少しでも頑張りたいと思っているのであれば、自立を目指して伴走者として寄り添い、成長を促してあげるのが大人の使命ではないか。ただ、なかなか本音を正直に言えない子供もいるので、やる気のサインを見逃さないことも重要だ。 大人になって判明しても——特性知れば不安和らぐ——大人になって自分が境界認知だと分かった人のアドバイスは宮口 まず、自分の特性を知ることが大切だ。自らの弱みを正しく理解すれば不安を和らげられる。そして、誰かに言いくるめられて利用されそうなときなど、困ったときに備えて相談先をつくることが大事だ。なお、人の知能について、はっきりとした学説があるわけではない。現時点の主流の説に基づいて作られた知能検査で分かるのがIQという位置付けなので、絶対的なものではないし、状況で数値が変化する可能性もある。障害者手帳や療育手帳も取得する基準としては必要だが、IQの数値はあくまでも参考程度だ。大切なのは、自分の特性に合わせたトレーニングで生きづらさを少しでも緩和することだ。 公的な定義なく乏しい支援孤立・困窮など〝負の連鎖〟に陥る懸念も境界認知は、IQの平均域(85~115)にも、知的障がい(約70未満=自治体ごとに数値が異なる)にも該当せず、知的能力の上限は中学3年生程度とされる。正式な病名や診断名ではないため、公的支援の対象外。ただ、1965~74年の間は、IQ70~84が『「境界線精神遅滞」と定義され、知的障がいの一つとされていた。教会知能の人を巡っては、勉強、仕事、人間関係などで生きづらさを感じているものの、適切な支援を受けられずに社会的な孤立や経済的な困窮に陥り、罪を犯したり、うつ病などの精神疾患を引き起こしたりする〝負の連鎖〟が懸念されている。犯罪という意識はないまま特殊詐欺の〝受け子〟として利用されたり、言葉巧みに操られて性被害に遭ったりするなどのケースが報告されている。2019年11月には、境界知能の女子大生が空港のトイレで女児を出産し、直後に殺害するという痛ましい事件が起きた。公判では、女性が幼少期から繰り返し叱責を受けたため自信を喪失したりすることが明かされ、弁護側は何でも相談できる人がいれば事件は起きなかったと主張。女性は21年9月、懲役5年の実刑判決を言い渡された。 【土曜特集】公明新聞2023.12.16
January 6, 2025
コメント(0)
-
多様な性を尊重できる社会に
多様な性を尊重できる社会に河口 和也(広島修道大学教授)2回の意識調査からLGBT、SOGI、Xジェンダー、アセクシャル——みなさんは、これらの言葉の意味が分かりますか。2015年、東京の渋谷区と世田谷区で同姓パートナーシップ制度が導入され、性的マイノリティーに対する理解が進み始めました。しかし、いまだ同性愛者への無理解、差別は根強いものがあります。私の研究グループでは、15年、19年に、性的マイノリティーに関する意識調査を行いました。その結果、一つの傾向として、高齢男性になるほど同性愛に対し不寛容だということが分かりました。年代別比較では、全体的に年齢が上がるほど抵抗感を持つ人が増えます。また、男女の比較では、女性より男性の方が不寛容でした。また、職業別にまとめたデータがあります。専門技術系、管理職、事務営業、販売サービス、技能労働、農林漁業に分け、職場の同僚が同性愛者だった場合の反応を聞いたもの。管理職と農林漁業で6割以上が「嫌だ」「どちらかといえば嫌だ」と回答。管理職の理解が低いのは、職場日働きにくさにつながる結果と言えるでしょう。もう一つのポイントは、身近な人が同性愛者やトランジェスターだった場合にどう反応するか。近所の人、職場の同僚、きょうだい、子ども、の別に聞きました。「嫌だ」「どちらかといえば嫌だ」という人が、近所や同僚の場合は40%程度。しかし、きょうだいや子どもの場合は70%前後になります。つまり、一般的な話としては理解していても、身内となるとネガティブに反応してしまうのです。 高齢男性ほど非寛容身内には無理解な人が多い まず知ることが重要まずは、冒頭の新しい言葉をはじめ、性的マイノリティーについて知ることが非常に重要です。基礎的な知識を持たないで、良い悪いの判断はできません。今は、知らないからいやだと判断する人が多いのではないかと思います。実際、どのような不都合があるのでしょうか。例えば、トランジェスターの子どもの場合、制服の問題があります。男女どちらの制服を着るのか。最近では、女子がスカートでなくズボンという、男女共用の制服も登場しているほど。また、体育のプールの授業はどうするのか、音楽の合唱ではどのパートを歌うのかなども。音楽の授業に関しては、アメリカではガイドラインがあります。テノール(男性高音)とあると(女性低温)を降り合わせて、その中間に立ってもらい、どちらのパートを歌ってもいいようにするのです。こうしたちょっとした工夫は、知っているかどうかの違いが大きいでしょう。ただ、特定の問題や課題のみに矮小化されてしまうのは残念です。あの人たちは、「かわいそうな人だ」として同情の眼差しでしか見られないようになってしまうからです。社会全体が変化し、プライドパレードのように、自分たちの存在や価値を再認識できる場も増えています。問題や課題も多く残っていますが、自己肯定しながら暮らしていけるように変わってきているのです。 文化的な視点も必要実は、クィアビジョンという新しいアプローチがあります。性的マイノリティーが映像表現の中でどう捉えられてきたかを研究する視覚です。例えば、米ハリウッドでは、1930年代にはセクシャリティーは自由に表現されていました。男性同士が抱き合って踊るシーンなどが普通にあったのです。ところが38年にヘイズ・コードによる自主規制が始まり性的マイノリティーを含め、多様な性の在り方を認める。それが、多くの人が、より生きやすい社会につながるのだと思います。=談 ※言葉の意味LGBT=レズビアン、芸、バイセクシャル、トランジェスターの頭文字を取った、性的マイノリティーを表現する言葉SOGI=「どんな性別を好きになるのか」「自分自身をどういう性だと認識しているのか」という言葉Xジェンダー=男性・女性のいずれかにも属さない政治人を持つ人アセクシャル=他者に対して性的欲望を抱くことができない、また希薄な人 かわぐち・やずや 1963年、愛知県生まれ。広島修道大学教授。専門は社会学、ジェンダー論。現代日本の生をめぐる諸現象や諸問題の研究を行うとともに、法整備にくけ、各地で講演を行っている。 【文化Culture】聖教新聞2023.12.13
January 5, 2025
コメント(0)
-
異名者と呼ばれる別人格を創造
異名者と呼ばれる別人格を創造作家 村上 政彦フェルナンド・ペソア詩選「ポルトガルの海」本を手にして旅に出よう。用意するのは一枚の世界地図。そして今日は、フェルナンド・ペソア詩選「ポルトガルの海」です。ポルトガルは、15世紀の大公開時に世界に覇を唱え、国家として頂点を極めました海洋国家だったポルトガルの海を謳ったペソアの詩の一節——。「塩からい海よ お前の塩のなんと多くが/ポルトガルの涙である子とか/我らがお前を渡ったため なんと多くの母親が涙を流し/なんと多くの子が空しく祈ったことか」彼らは困難を乗り越えて海を制覇しましたが、その後は、だんだん没落していく。ペソアが生まれた20世紀の頃には、ヨーロッパの中では後進性が指摘されていたようです。ペソアは幼くして父を失い、7歳の時に母が再婚。その相手が外交官だったため、赴任先の南アフリカ共和国へ。ポルトガルへ戻ったのは、ほぼ10年後でした。この間、ペソアは英国式の教育を受け、英語の方に馴染んでいた。この出来事が、のちに詩人をして、独自の試みを際立てさせたと分析する向きもあります。それは「異名者」の想像です。ペソアは今でこそ私兵に肖像画印刷されたポルトガルの国民詩人ですが、生前はほとんど無名でした。出版した詩集は『歴史は告げる』の1冊だけ。しかし死後になって、膨大な草稿が発見されました。これらの作品は。ペソアだけでなく、彼が創造した「異名者」たちの手にもよるものです。複数の筆名を駆使した書き手は少なくないのですが、ペソアの「異名者」は人格、要望、職業など細部にわたって作り込まれています。例えば、ペソア自身が師と仰ぐアルベルト・カエイロは「自然詩人。一八八九年四月十六日13時45分。リスボン生まれ、一九一五年に結核で死去。金髪碧眼、中背で蒲柳の質だがそうは見えない」と続いて生活面にまで至ります。そして、カエイロの詩——。「わたしの視線は向日葵のようにたしかだ/わたしは道を歩く きまって/右を見たり左を見たり/ときには振り返ったりして……/一瞬 一瞬 わたしに見えるものは/これまで見たことのないもの」ペソアの想像した「異名者」は70人超。彼はそれだけの人格を創造し、それぞれに作風の異なる詩や文章を書かせました。なぜ、そのような試みをしたのか。「詩人とは虚構う人だ/その虚構いのあまりに完璧であるため/現実に感じる苦痛まで/苦悩であるかの如く虚構う」(ペソア)ペソアは自身を劇詩人と定義していた。「異名者」は彼の想像したいのちを生きた。詩人の可能性を極めた複数者としての生は、混沌のにぎやかさに満ちていたことでしょう。[参考文献]『ポルトガルの海(増補版)——フェルナンド・ペソア詩選』 池上今夫編訳 さいりゅうしゃ1『現代詩手帳』1996年6月号 思潮社 【ぶら~り文学の旅㊴海外編】聖教新聞2023.12.13
January 4, 2025
コメント(0)
-
推敲とは?
推敲とは?東京大学教授 安藤 宏小林秀雄が興味深い文章感を述べている。(『文学と自分』)。一般の人は文章を書く際に、まず、「書きたいこと」が先にあり、それをうまく表現できたものがよい文章だったと思っている。だが、文学者は違う。「書きたいこと」が「書かれたもの」と別にあるわけではなく、「書かれたもの」こそがその人の総てだというのである。拙く書く、都いうことは拙くしか考えられなかったということなのであって、自分は本当はもっとちゃんとした考えを持っているのだ、というのは言い訳に過ぎない。その覚悟があるからこそ、全神経を集中して文章を何度も練り直していくことにもなるだろう。おそらくここには「書く」という行為の極意が隠されている。まずモヤモヤした考えがあって、それを言葉にしてみる。読み返してみると、これではダメだと思ってあらたに書き直す。それを読み返してみて、さらに書き直す。その試行錯誤のプロセスにこそ、自分が「考えていたこと」に出会うドラマがあるのだろう。「推敲」という言葉は、ともすれば最終的に字面を整えたり微修正を加える、というレトリカルな意味にとられがちだ。だが、それは単なる手直しなのではなくて、実は自身と対話をくり返しながら発見をしていくドラマそのものなのである。もちろん短文のエッセイなど、一筆書きの文章の持ち味といのもあるだろう。私の場合、小さい時から「一筆書き」が苦手で、いつも原形をとどめないぐらい書き直してしまうので、あるいはその言い訳もあって推敲を重視しているのかもしれない。だが、「相か、自分は本当にそういうことが言いたかったのか!」という発見は、ほかの何物にも代えがたい喜びだ。こうしたプロセスを通して初めて、書かれたものこそが総て、という割切りが可能になるのだと思う。 【言葉の遠近法】公明新聞2023.12.13
January 3, 2025
コメント(0)
-
現代に生きる「養生訓」
現代に生きる「養生訓」内科医 奥田昌子さんおくだ・まさこ 内科医。京都大学大学院医学部研究科修了。京都大学博士(医学)。愛知県出身。健康並びに人間ドック実施機関で、30万人近くの診察に当たる。現在は航空会社産業医を兼務。著書に『病気にならない体をつくる 超訳 養生訓 エッセンシャル版』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)ほか多数。 目的は幸せに生きること——『養生訓』の魅力とは?具体的な健康法に加え、「何のために健康になるのか」という〝養生哲学〟が示されているところが、最大の魅力だと思います。著者の貝原益軒は、寿命の長さや病気の有無だけではなく、幸せに生きることが養生の目的であると説いています。当時の庶民でも読めるように、ひらがなを多く使って書かれていること、元気で長生きした著者の生き方に説得力があったこと、印刷技術が発展したことなどの理由から当時のベストセラーになりました。 ——貝原益軒とはどのような人物ですか。1630年、福岡藩士の家に生まれ、医師・儒学者として藩に仕えました。最晩年まで健康で、83歳で亡くなる前年に「養生訓」を出版しました。小さい頃に体が弱かったことが、洋上の道を深めるきっかけになったと言われています。あらゆる分野に精通した優秀な学者でしたが、「実行しなければ知っているとはいえない」という信念を持っていました。中国医書に基づき、さまざまな健康法を自分で試し、本当に良いものを選び出していきました。長い時間をかけて集めた知見が、彼のなかで整理されたのが80歳を過ぎた頃だったようです。『養生訓』は彼の人生の集大成です。 ——時代背景を教えてください。当時は、江戸中期の元禄時代——産業が発展し、文化は成熟、都市部の生活は華やかでした。安い値段で脂が手に入るようになり、あんどんを使用して、夜遅くまで起きる習慣がついた時代でもあります。街には飲食店や屋台が多くあり、食生活も豊かだったようです。そのため、食べ過ぎが原因で病気になるケースも増えました。また、武家社会だったため、規則や締め付けが厳しく、ストレスも多かったようです。現代に生きる私たちが抱える問題値、共通点が多いですよね。 生活習慣の改善が重要——養生訓を読むと、予防医学の重要性を改めて感じます。その通りです。養生訓では、「ほとんどの人は長生きできる体をもって生まれてくる。しかし、せっかく丈夫に生まれても、養生の方法を知らなかったばかりに、生きられるはずだった年齢間瀬生きられないことがある」と、生活習慣の重要性が、説かれています。100歳で元気な方々も、元々の体のつくりが違うのではなく、日々の努力と工夫によって長生きできているのだと教えてくれています。 ——生活習慣の改善は、何から始めたらいいのでしょうか。何か特別なことをする必要はありません。養生訓には、「節度ある食事と睡眠が養生の鍵となる」とあります。加えて、「老若男女を問わず、ダラダラせずに体を使うことだ。これが養生の秘訣である」と指摘しています。日常生活のなかで、自分のできることは人に頼まず自分でするなど、意識して体を動かすことが健康につながるのです。 「腹八分目」は一週間単位でOK——『養生訓』といえば「腹八分目」が有名ですね。はい。「少し残して八分か九分でやめるのがよい。腹いっぱい食べると、後で苦労することになる」と、満腹になることを戒めています。もし食べ過ぎてしまった場合は「一日単位、一週間単位で腹八分目にすれば」」挽回できる位というのも、うれしいポイントですな。 ——他にも、食事の注意点はありますか。「夕食は日がくれたら早く食べる方がよい。消化吸収を十分に済ませてから寝るためである」とあります。たしかに、就寝前に食べると睡眠の質が下がり、逆流性食道炎のリスクも高まります。深夜の飲食は満腹感が感じにくく、食べ過ぎにもつながります。また、「飲酒後に酔いが残っていたら、餅、団子、麺類などの炭水化物、星がし、果物などの甘いもの、そして脂っこいものを飲んだり食べたりしてはならない」とも書かれています。飲酒の直後に等が肝臓に運ばれると、アルコールの分解が遅れて悪酔いしやすくなります。また、油は胃に長くとどまるため、二日酔いの吐き気が強くなる場合があります。〝締めのラーメン〟には要注意です(笑)。 日本人にはやっぱり和食——日本人と外国人の体質の違いについても言及されています。「日本人は穀物中心の食生活を送ってきたため、肉をたくさん食べると病気になりやすい」と、外国人に比べて日本人の胃腸が弱い点を指摘しています。現代の研究では、胃腸の構造や機能に関する、遺伝子の差だと考えられています。昨今、日本の食文化は西洋化し、肉をよく食べるようになりました。〝もう日本人の体質も変わったのでは……〟と思う人もいるかもしれません。しかし、基本的には遺伝子は300年程度では、ほとんど変わりません。本来、日本人の体に合うのは伝統的な和食なのです。 ——特に胃腸が弱い人へのアドバイスはありますか。「魚は生のままの方が消化しやすく胃にもたれない」。これは科学的に証明されています。塩漬けや焼き魚など身が固くなる魚料理は、胃腸に負担がかかります。火を通す場合は、身がふっくらする程度にしましょう。さらに、根野菜などの硬くて筋の多い野菜は「薄く削り、煮て調理する」ことを勧めています。繊維を短くすることで、胃の働きを助けます。また、「野菜を干してから煮れば胃腸が弱っても食べられる。(中略)干すことで甘くなり、栄養成分が増す」とあります。これは水分が抜けて濃縮されることにもよりますが、シイタケはホストビタミンDが増加することが分かっています。 住環境や口腔ケアにも言及——食生活以外にも、さまざまな健康の知恵が詰まっていますね。「気が滅入るような暗い部屋は健康をむしばむ。逆に、明るすぎる部屋は落ち着かずに手中できない」「湿気はじわじわと深く体を傷つける」などと、住環境についても触れられています。また「食後すぐに歯を磨けないときは、茶で口を何度かすすぐとよい」とは、近年、注目されている口腔ケアに通じます。 ——生活の一つ一つ、丁寧に見直すことが大切ですね。健康法というのは、何か特別なことではなく、普段の生活の中にあるということを教えてくれていると思います。たとえ病気を抱えていたとしても、一病息災という言葉があるように、病気をしたからこそ健康になれるという考えもあります。大事なことは、体の声に耳を傾けることです。だれもが、自分の中に〝健康になるための種〟が埋まっていることを知っていただければ、うれしく思います。 【健康PLUS+】聖教新聞2023.12.12
January 2, 2025
コメント(0)
-
相談を受けた際の対応
相談を受けた際の対応産業医・精神科医 井上 智介まずは相手の行動に感謝を伝えるこの連載も最終回となりました。たくさんの人に読んでいただき感謝しています。今までの記事では、自分のメンタルが不調になった時、どうコントロールすればよいかについてお伝えしてきました。最終回は、もしもあなたの大切な人から「メンタルの調子が悪い」「もう消えたい」と言われたとき、どう対応すればよいかをお話しします。まず、絶対にやってはいけないことは、相手のしんどい気持ちから屁を背けることです。どう対応すればいいか分からないため、「時間が立てばよくなるんじゃない?」と言ってしまうかもしれません。しかし、相手は勇気をもってあなたに知らせています。まずは「教えてくれてありがとう」と相手の行動に感謝を伝えてください。そこからも気の利いた言葉やアドバイスは必要ありません。それよりも、消えた厭い思うほどの辛さを抱えている現状や背景に思いをはせ、相手がいてくれるので助かっていることや、いなくなることへの寂しさを伝え、相手につながりを感じてもらって孤独感を減らすように心がけてください。もちろん、メールのやり取りや電話で噺を聞くのもいいですが、無理に何かを話さなくても、沈黙のままそばにいているだけでも強くなる絆があるので、一緒に過ごす時間も大切にしてください。ただ、あなたも一人で受け止めすぎず、病院への受信など他につながることにも、ゆっくりと背中を押してあげください。(おわり) 【若者のメンタルヘルス⑩】公明新聞2023.12.12
January 1, 2025
コメント(0)
全41件 (41件中 1-41件目)
1