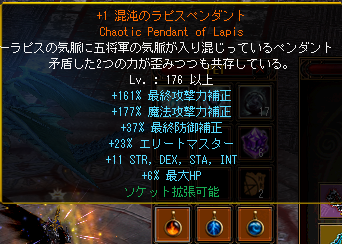2013年05月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
稽古 ~弧拳の効用~
長期の休みには、自分のための稽古として、技術面での研究をしている。 正月に引き続き、GWには「受け」の技術に工夫を加えることにした。 「弧拳」と呼ばれる、手首を内側に折り曲げた時の外側の関節部分を 受けの中で本格的に活用するようになったのは、40代の半ば頃からだ。 現存する多くの会派同様、私も「弧拳」に関する認識は浅いものだった。 多くの技術書などに紹介されている「弧拳受け」は、防御技術として 見ると、リスクばかり大きい、形骸化されたもので、「型(形)」から 適当に解釈したものと思われる。 深く研究してみると、素手による真剣な攻防の中で、自分の指を痛めずに 開手による「掛け」や「掛け崩し」などを行う場合の流れの一部に、この 「弧拳」が非常に有効なことがわかってきた。 研究した結果を組手で試す(勿論、手加減されては困るので、相手は私が 弧拳を研究中であることは知らない)なかで、面白いように活用できる ことが体感でき、いまでは「このためにあるのでは?」と思う位に、自分 のものになってきた。 土曜日はグローブ着用なのでこの技術は約束組手でしか使えないが、どの 参加者も、私が受けに弧拳を使っていることを判別できないようだ。 素手での組手も行う月曜日にしても、メンバーがもっと研究心を持てば 私に受けられた時の感触から、弧拳を使っていることはわかるはずだが、 こちらもまだ気づいていないようである。 もちろん、稽古体系として組み込めるレベルまで、練習方法などが確立 できたら、紹介するつもりではいるが、まだまだ汎用的なものにはなって いない。 稽古の奥は深く、やるべきことはまだまだある。面白い。
2013/05/31
コメント(0)
-
安倍政権の外交
精力的な外交を展開している安倍政権。 休みなく各国を周る首相に、消滅しつつある一部野党が「渡航費が無駄」 なんて見当違いな批判しか出来ない程、前政権のひきこもり振りとは 対照的である。 「あからさまに中国を包囲するような外交は中国を刺激するだけ」という 拝中政治家の批判もまた、見当違いである。 現政権は、中国にも韓国にも、最初にアプローチはしている。 拒否しているのは、中・韓である。 「中国なしには日本経済は立ち行かない」と統計も見ずに騒いでいた似非 評論家たちも「取引先の多角化によるリスクヘッジ」という基本を再認識 したのではないだろうか? 願わくば、多角化の先に「選択」という外交を期待したい。 国としての方向性・国民性が日本の価値観に合致する国と「仕方なしに」 付き合う国にたいする外交姿勢にメリハリをつけて欲しいものだ。 特にアフリカに関しては、私がビジネスを通して知る限り、とんでもない 国もまだまだ多い。 気が付けば、意図しない争いに巻き込まれないためにも、慎重な選別は 必要になると思う。
2013/05/30
コメント(5)
-
地震予知は不可能と政府公式見解
快哉を持って迎えたい報道だった。 東日本大震災の頃にも書いたが「地震予知が可能である」として、 貴重な税金を無駄に使うのは、他にも見られる情けない現実としても、 「予知が可能」と国民に変な期待を持たせることの弊害が大きい。 この件に関しては、もう20年も前から学者の世界では常識となって いたことである。 私も、横浜で行われた某カンファレンスで、良く知るところの教授など から伺い、地震予知は現時点では不可能、と確信するようになった。 結局、東大を頂点とする旧帝大の持つ「既得権益」のひとつでしかなく、 事実、これだけ成果があがらないのに、高性能コンピューターの開発など 周辺分野を含めると、膨大な予算が注ぎ込まれ続けていたのは異常である。 新聞では、決して大きな記事ではなかったことは残念だが、政府が公式に 「予知は無理」と宣言したことの意義は大きい。 地震をはじめ、多くの天災は予測不可能である。故に、とにかく備えを 固めるとともに、いつ被災者になるかわからない「覚悟」を持って生き なければならない、ということを改めて思い知らされた報道である。
2013/05/29
コメント(2)
-
「出口のない海」 横山秀夫
「永遠の0」を薦めた友人に、代わりに薦められた一冊。 直ぐに文庫版を入手して読み始めたが、この映画化作品を既に観て いたことを想い出した。 映画版は、主役がワイドショーへの話題提供の方が印象に残る、 演技が暑苦しい市川海老蔵主演だったが、正直、あまり面白くなかった 印象があり、半信半疑で読み進めた。 読了して、読んでよかったと思った。映画版とはまったく異質の作品だ。 「人間魚雷回天」の話ではあるが、小説は、若者たちの青春群像である。 涙々の「永遠の0」に比べると、終わり方がこれまた爽やかである。 横山秀夫氏の作品は、初めて読んだのだが、文体は非常にスムースで 読みやすい。
2013/05/28
コメント(0)
-
稽古 ~点を狙う・別解~
前回に記した、突きで点を狙う稽古。 その次の稽古でも、同じようにやらせてみた。 点を狙う訓練というと、ミットの中央の丸印や、小さいミット、 或いは小さなボールなどを、パートナーが動きながら構え、それを 打つような訓練がすぐ頭に浮かぶだろう。 確かにそれは充分に効果的な訓練であるが、「掴んではいけない」, 「グローブを嵌めているので掴めない」という競技ルールからの発想 を一旦捨てると、別のアプローチが見えてくる。 古伝の技術に多い、相手を動けない状態にして、ほぼ静止している 急所(点)を打つ、というものである。 残されている半世紀ほど前の技術書、記事などには良く、 「据えものにして打つ」などと表現されている技術がそれである。 私が最初に入門した道場でも、相手の足の甲を踏みつけながら攻撃する、 或いは、相手の攻撃を掴まえて攻撃するなどという技術は、日常的に 教えられていた。 もちろん、今でも多くの会派で行われていると期待したいが、私の知る 限り、組手を行う場合は、競技ルールに沿ったものであることが多く、 普段の稽古でも、競技での反則技はあまり稽古されていないようである。 動く相手を捉えるために、ボクシングジムに「出稽古」に行った著名 選手の話を記事で読んだことがあるが、それではあくまで反射神経に 頼った技術の範疇を出ない。 生涯を通じた護身も目的とした武道であれば、もっと現実的な方法論も 提示し、上達できる稽古でなければならないだろう。
2013/05/27
コメント(0)
-

江ノ島クリーンキャンペーン
藤沢市のイベント・クリーンキャンペーンに出掛けた。 一応、軽く誘った愚息も「学校でも環境委員なので」ということで、 一緒に行くことになった。 翌週の鎌倉遠足に備えて、デジカメ練習中の愚息の、撮影練習という ことで、江の島のイベントを終えてから、数km西の海浜公園での イベントに廻って、日曜日の午前中を過ごすことにした。 予想外の晴天で、朝9時とは云え夏の暑さ。 1時間、真面目にゴミを拾い、クリーンキャンペーン終了。 かなり重厚な財布を拾ったのには驚いた。現金はなかったが、中には Suicaが残されていた。 恐らく、隣の公園でどこぞの輩がカツアゲでもして、中身を抜いて 砂浜に投げたのだろうと、勝手に推測した。 砂浜には、とにかくタバコの吸い殻が多く、同じ喫煙者として恥かしい 限りであった。 こんな私でも、吸い殻は必ず携帯灰皿などに入れて、持ち帰っている。 この日の湘南海岸は、サーフィンのイベントなどもあり、サイクリング ロードもかなり混んでいた。 写真は、集合前、8時半ごろ愚息がLumixで撮影。 enoshima_2013-0526 posted by (C)kirk1701
2013/05/26
コメント(0)
-
愚息の調理実習
週末の授業で「朝ご飯を作ろう」という調理実習があるということで、 愚息がパンを一斤持って出掛けた。 班ごとにメニューを決めて作るということだが、聞いてみると、 和洋折衷で、私ならご遠慮したいメニューだったが、帰宅後に確認した ところでは、皆で楽しく食べたらしい。 自身が小学生の頃、やはり調理実習での出来事などは昨日のように 覚えており、改めてもろもろ思い起こした。 私の頃は、小学校では「家庭科」があったものの、中学校になると、 男子は「技術」女子は「家庭」と勝手に決められており、大いに不満を 持ったことなどが思い出された。 小学校の家庭科用に配られた裁縫箱が、なんとも男心をくすぐる代物 だったこともあり、授業で行った「雑巾作り」などは持ち前の器用さで、 ほぼ完璧に仕上げたものだ。 当然、中学ではさらに難しい裁縫にチャレンジできるものと期待して いたのだが、強制的に「技術」を受講させられ、それはそれで、これ また得意で、製図、木工、最終学年はラジオ作りと楽しかったのだが。 愚息は中学で、家庭科を学べるのだろうか?
2013/05/25
コメント(0)
-
バイオハザード リベレーションズ
「6」は頓挫してしまったが、今回は入り込めている。 ボチボチやっているので、まだ1週目の2/3程度だが、 ドキドキハラハラ、時には胃が痛くなるようなイライラ、と バイオらしい展開に好感が持てる。 「4」~「6」で定番となったアクション路線の面白さを残しつつ、 「24」を見ているような展開も良い。 いつもは飛ばしてしまうムービーも、今回は楽しみながら観ている。 操作キャラクタが変更になっても、「4」のアシュリーの時のように、 画面のこちらから撃ちたくなるようなイライラはない。 CGはさらに精細になっているが、舞台をうまく使いまわしているので、 HDDでのサイズは3GBを切っている(PS3版)点も評価したい。 武器の保有・強化に関しても、過去作からの改善が見られる。 この路線で年に1作位のペースで進んで欲しいシリーズである。
2013/05/24
コメント(16)
-

M92F DESERT STORM ( MGC )
HWモデルガン。 マルシンやタナカから発売されている現行品と比べても、全く 遜色ない外観、作動を持つ傑作のバリエーション。 M9のABSは、発火用に控えも数丁所有しているが、これは未発火 のままコレクションすることになりそうである。 外箱も、M9の流用ではなく、それっぽいデザインのオリジナル パッケージ。 当時のMGCの勢いが窺える秀作である。 MGC_M92F_DESERT_STORM-01 posted by (C)kirk1701 MGC_M92F_DESERT_STORM-02 posted by (C)kirk1701
2013/05/23
コメント(4)
-
サムライの拳 山平 重樹著
現在、国際空手道・三浦道場を主宰する三浦美幸氏の反省を、空手 経験者でもある著者が描いたノンフィクション。 三浦氏は、剛柔流~極真会館~国際大山空手道~独立という経歴を 持つ空手家だが、極真会館時代に全日本優勝、百人組手完遂という 実績を残している。 マスコミと共に大きくなった極真会館は、館長大山氏はじめ、多くの 幹部・元選手が自伝などを出版している。 が、多くは底の浅い武勇伝を中心とした独りよがりの作品が多く、 所詮、若手の稽古生が読むのに適した程度のものばかりである。 現館長・松井氏など、30歳頃で既に自伝を出版している。 まだまだ修行期にあるべき年代だろうに、と呆れたものである。 勿論、黒崎氏、山崎氏などの自伝のような例外もあるが。 この作品は、その点、関係者以外の者が読んでも十二分に楽しめる 快作である。 著者の筆力もさることながら、三浦氏自身が、あの団体特有のスキャ ンダラスなエピソードからは縁遠い、実力、人格を兼ね備えた武道家 であることが、作品を通した爽やかさを醸しだしている。
2013/05/22
コメント(0)
-
影法師 百田尚樹著
今度の舞台は江戸時代の小藩。 「武士」という階級がすでに官僚化・世襲化している夢の持てない 現実の中、己の美意識を捨てずに筆頭家老まで登り、藩のためにある 事業を成し遂げた勘一と、その親友、彦四郎の物語。 作中の「現在と過去」、四半世紀を行き来しながら、勘一と共に、 読み手も得心する構成となっているのは、「永遠の0」同様。 優れた友人が人間を成長させることを、嫌みなく描いている点は 「ボックス!」同様である。 文庫版の最後には、なんと「袋とじ」が付いている。 雑誌で紹介された初稿にはあった最終章が、単行本化の際には削除 されていたものを復刻収録されているとのこと。 読もうかどうか迷ったが、私は結局、袋とじを開くことにした。 最近の映画DVDの特典映像「もう一つのエンディング」みたいな感じで 妙にわくわくして読んだ。 作品の本線とはまた別の、何とも切ないエピソードがそこにあった。
2013/05/21
コメント(0)
-
稽古 ~点を狙う~
私が勝手に好敵手(ライバル)と定義している、180cm前後の若手二人。 約束組手をさせている最中に、その内ひとりの、とんでもない欠点 に気がついた。 突きが、およそ5cm程度、狙点からずれているのである。 「点を狙う」という武道的な稽古をしてきた月曜日の稽古だが、 なまじグローブも導入しているために、こういうことが起きる。 「何年稽古しているのか?」という気持ちで、多少苛立ちながら、 矯正方法を提示した。 その日持っていたハンカチの端に、直径1cm程度の小さな結び目を 作り、それを人差し指の拳頭だけで突くようにアドバイスした。 予想通り、拳がズレるメンバーは、10発の内、3~5発しか当らない。 彼のライバルは、7発程度当てる。 当然、私は100%当てる、というより、こんなことが出来ないようでは 空手とは云えない。 高校時代、修行歴1年で、私は突きのみならず、相手の加えたタバコ どころか、フィルタだけに剥いたものを蹴り飛ばしていたのだ。 初期のメンバーは、この辺りがキッチリ出来ており改めて指導すること もなかったこともあり、油断していたことを反省した。 稽古で1cm程度の的を打ち抜けないようでは、組手や実戦では、10cmの 的も捉えられるものではない。
2013/05/20
コメント(2)
-

U.S.N 9mm M9 Dolphin HW ( Marushin )
昨年の発火復帰でM93R(KSC)を撃った流れでABS製のこのモデルに 辿りついた。 ABS版は発火は絶好調で、家族の評判も良かったのだが、スライド (ファイアリングブロック)にヒビが入り、撃つ度に深くなり、 遂には、作動不良を起こすに至った。 試しにマルシンに修理に出したら、しっかり直ってきた。 他のベレッタ系同様、スライドストップは気まぐれである。 このモデルはコレクション用に求めたHW,ベレッタマークのグリップ 付きのモデルである。 正直、発火しなければコレクションすることのなかったモデルだと思 うが、このHWの他、シルバーモデルなども揃えてしまった。 「HWは撃たない」というのは冬場の誓いで、もしかしたら来月あたり、 コイツも発火してしまうかも。 Masushin_Dolphin_HW-01 posted by (C)kirk1701 Masushin_Dolphin_HW-02 posted by (C)kirk1701
2013/05/19
コメント(0)
-
ボックス! 百田尚樹著
「永遠の0」が面白かったので、Amazoneでさらに数冊、ポチッてしまった。本作は、しげりんさんからお薦めいただき、ポチッとしたものだ。昨年末頃だったか、CSで映画版を既に観ていた。映画の方もかなり面白かったと記憶しており、本作を読むに際しても、映画の配役のイメージはついて回ってしまったのは仕方ないところだ。しげりんさんのコメントどおり、本当に爽やかな若者達の物語だった。ボクシングを通して青春を描いた小説は幾つかあったが、リアルに描こうとするあまり、ボクシング界の暗い側面を必要以上に描きすぎる嫌いがあった。 この作品は、ボクシングを徹底した量的訓練と、科学的アプローチ、その上に闘志が必要な、難易度の高いスポーツ。と位置付け、ドロドロした「どつきあい」の臭みを見事に消して仕上げた作品だと評価したい。天才肌のボクサーと努力型のボクサーを並べる古典的な描き方ながら、かなりの取材量に裏付けられ、味わいのある台詞のおかげで、グイグイ引きこまれた。著者の百田氏に関しては、Amazoneの書評などを読むと、「創作力に欠ける」とか「過去作の焼き直し」という系統の批判も多いようだが、仮に過去の作品にヒントを得た「焼き直し」であっても、面白ければそれでいいのではないだろうか?映画で云うところの「リメイク」が小説であってもいいはずである。創作といっても、読者がついていけないような作家の内面などを延々と描かれるより、事実の断片を並べて、料理してくれて面白ければ、それはそれで大歓迎である。
2013/05/18
コメント(4)
-
風の中のマリア 百田尚樹 著
寿命30日のオオスズメバチの「ワーカー」として生まれたマリア。 幼い「妹」たちのために狩りを続け、闘い続けるマリアの生涯を 描いた作品である。 子どもの頃はあんなに関心のあった昆虫は、いつしか「気持の悪い」 存在になってしまっていた身としては、昆虫世界に慣れるまで暫く 時間が掛ってしまったが、1/3程度読み進んだあたりからは、すっかり 違和感なく読むことが出来た。 メスとして生を享けながら、卵を産めない「ワーカー」の悲哀よりも 目の前の使命に没入し、命を削るような闘いを繰り広げるマリアの姿 には当然、「永遠の0」に登場する英霊の姿が重なってくる。 引いて観てみれば、大宇宙の時間的スケールの中では、人間の一生も、 カゲロウ同様、一瞬のものである。 擬人化されたマリアの視点で描かれる彼女の生涯は、人間の、少なく とも私のそれよりは、遥かに潔く、シンプルである。 思考することを覚えた人間は、果たして本当に幸福だったのだと言え るのだろうか? あれこれ屁理屈をこねて、上手に(と本人が思っている)生き延びて いくことより、不器用だが黙々と自分の信念に従って生きる生き方を、 「カッコいいなあ」と思ったことはなかっただろうか? この作品ではカマキリさえ、本当にカッコいいのだ。 人生の折り返し点を、とうに過ぎた身で読んだこの作品、ちょうど さわやかな晴天に恵まれた日に読んだこともあり、なんとも爽やかな 気分で読了した。
2013/05/17
コメント(0)
-
宇宙創成 サイモン・シン
このところ、読書量が戻ってきている。 学生時代は、日に4時間は電車に乗っていたので、ほぼ毎日1冊の ペースで読みまくっていた。 現在は朝、勤務先の駐車場に停めた車内での一人だけの時間が、最も 集中して読める時間である。 このところは、面白い作品に巡り会えたこともあり、自宅に居る時で も読書に時間を振り向ける比率が多くなっている。 さて「宇宙創成」 つい先日、136億歳から137億歳に年齢の延びたこの宇宙が、どのように して生まれ、どうなっていくのか?を、研究し続けた古今の研究者の エピソードとその研究成果を、歴史エピソード的にわかり易く列挙した ものである。 小難しい理論で埋められた本ではなく、客観的史実をベースに過去の 研究者たちのエピソードが描かれており、彼らの意外なハチャメチャ ぶりが存分に楽しめる。 地動説証明に貢献し、現在、月のクレーターに名前をとどめる、ティコ ・ブラーエなど剣をふるっての決闘で鼻を落とし、義鼻をつけていた上、 その最後たるや、晩餐会で尿意を我慢し過ぎての死である。 一部の資産家を除き、どの研究者も「身体を張って」観測出来る環境を 得て、研究成果を挙げている点、天文ファンとして、感情移入出来る。 「測り知れぬ価値を持つ宇宙の像を捉える事が出来たのは、頑健極まる 天文学者だけであり、またその行為は心身の鍛練ぶりを示すもの」と 作者は断じる。 宇宙望遠鏡に名を残すハッブルなどは、その典型例であろう。 その輝かしい業績に比べて、人柄の悪さと、並はずれた体力、そして 限り無い自己顕示欲は、むしろ爽快ですらある。 当然彼も決闘経験者である(笑) 天文学は、洗練されたエリートの学問ではないことが改めてわかる。
2013/05/16
コメント(0)
-
岳飛伝 第3巻 北方謙三
刊行間隔は長いが、若いころと違い数ヵ月があっという間なので、 苦にならない。 ただ、絶筆とならないように北方氏の健康を願ってはいる。 作家本人も予想外の長さになった水滸伝シリーズだが、三作目と なればさすがにダレてくるかと思ったが、意外に面白い。 腐敗した「宋」に真っ向から闘いを挑んだ男たちの群像を描いた 一作目を痛快なアクション小説とするならば、その後を描いた 二作目は直接の後日談。 気になっていた登場人物の行く末を確認させてくれるような作り になっている。 そして三作目では、昨今の国際情勢も想起させられるような、社会 派ドラマの様相を見せている。 作家本人の「視点」の変化が、比較的わかり易い作品である。 その中で、前作で登場した「岳飛」が、本巻あたりから、非常に 魅力的な人物に変貌してきている。 そして、梁山泊の強者たちのその後も、戦死ばかりでなく、穏やかに 引退している者もいたりと、ホッとさせてくれる描写も。 スーパースターが居なくても、充分に面白い小説となっている。
2013/05/15
コメント(0)
-
稽古 ~ちょっと荒れ気味~
土曜日の稽古が、2週連続でやや荒れ気味である。 毎回、組手の時間になると、一人は稽古場の隅で横になっている。 1週目は、蹴りを掛けられてそのまま追い打ちの上段回し蹴りを ブロックしつつ、後方に倒れ込んだ参加者が、後頭部を強打。 その後、近所の脳神経外科で検査。異常は無くホッとしたが、検査 結果が出るまでの時間は、本当に重い時間だった。 2週目は、ボディブローを貰って呼吸困難になった参加者が横たわる 横で、組手稽古が続いた。 苦しみ方が尋常ではなかったが、これは多分に個人差があるので、 息を通して横にさせて回復を待った。 10分程で、組手に参加してきたので、大丈夫だろう。が、油断は出来 ない。 女性・子どもが中心の土曜日の稽古だが、過去には何度か病院の世話 になるケースがあった。 各自の技量が上がってくると、仕方のないことなのである。 もちろん、組手自体、ある程度の技量、身体が出来ていないものには やらせていないのであるが。 怪我をさせないのが密かな自慢でもあるうちの稽古だが、各自の技量 が上がり、格闘技である以上、各自の持つ闘争本能の発露も、これまた よしとしなければならず・・・。 とにかく、安全面により配慮するしかない。
2013/05/14
コメント(0)
-
夏八木勲さん逝く
「ゴーイング マイ ホーム」で演じる役柄のために痩せたと本人は トーク番組などで話していたのだが、さすがにその後の痩せ方は、 尋常ではなかった。 また一人、好きな役者さんが居なくなってしまった。 私の中での、氏の代表作は、映画では「白昼の死角」「戦国自衛隊」、 TVドラマでは、剣客商売の嶋岡礼蔵役となろうか。 幸いなことに、CSでは定期的に旧い映画・ドラマが放送されており、 毎日のように観ていると、故人もまるでまだ現役で活躍しているかの ように錯覚させてくれることが多々ある。 「スタートレック」劇場版の中の1作における、音声解説で、主演の W・シャトナーとL・ニモイが作品の製作当時を振り返る特典があり、 その中で、俳優が亡くなっても作品は残り、その中で俳優が活躍し続 けることについて、二人が語り合うくだりがある。 L・ニモイは、作品は俳優のある一時期を切り取った「写像」である ため、自分の死後も上映され、楽しまれることには抵抗がない。と、 述べていたのに対し、W・シャトナーは、「自分の死後、自分の作品 が上映され、その中で自分が生きているように動くのは嫌だ」と対照 的なコメントだった。 夏八木氏は、どちらなのだろうか? ご冥福をお祈りしたい。
2013/05/13
コメント(0)
-
稽古 ~筋肉を緩める~
悩ましいところなのだが、高齢になってくると俗に言うところの アウター・マッスルは落して、インナー・マッスルを鍛えた方が、 武道としての動きは維持できるように思える。 それでも若手を力でねじ伏せるような組手の必要もあり、ここ数年、 ウェイトトレーニングも再開しているのだが、連休前、組手の中で あまりに「力」に頼ってしまった局面があり、じっくり考えた。 ということで、このひと月、ウェイトトレーニングは全く行わず、 立禅などを中心とした稽古に勤しんでいる。 相手の攻撃を捌いたり、カウンターを打つときの動きから、かなり 力が抜け、スパッと入る感じの手応えが戻ってきたような気がする。 40年近いキャリアを重ねても、こうして試行錯誤しているのは、 情けない限りではあるのだが、教えを受けた先人の記憶、遺された 書籍などを「鵜呑み」にしてしまうわけにはいかず、自分の身体で キッチリ検証しなければ気が済まないのだ。 もちろん、腹筋など、健康的な生活を維持するための筋トレは毎日 (腹筋などは毎日行っても問題ない)行っている。
2013/05/12
コメント(0)
-
「永遠の0(ゼロ)」文庫版 百田尚樹 著
「読み損なわなくて良かった!」と思わせてくれる作品は最近では 少なくなってきた。 もちろん、こちらが歳を取り、感性が鈍くなって来ていること、著名な 作品は読んでしまった、などの理由もあろうが、新人作家とされる方々 の作品に期待外れのものが多かったのも事実である。 芥川賞、直木賞などの作品は目を通すようにしているが、正直、嘆息し てしまうような作品ばかりである。 さて本作。 いわゆる「戦争もの」「特攻隊もの」という範疇に括っては勿体ない程 読後感が重く、それでいて爽やかな作品である。 何年かに一度、自身の来し方などを振り返る時に、物差しになるような 見事な「漢(おとこ)」を描いた作品である。 著者は「探偵ナイトスクープ」の構成作家などの経歴を持つ50代後半。 若さゆえ、文章力・表現力の点で物足りないところが確かにある。 しかし、それを相殺してあまりあるストーリーの魅力。 終盤は、人前で読むのがヤバイと感じ、自宅でじっくり読んだ。 涙腺が緩むのを感じたが「簡単に泣いてはいけない」とも思い、滲む 文字を追い、なんとか読了した。 しばし放心の後、頁を繰ると「解説」があった。 「解説」を記した人の名前を見た時に、ささやかな抵抗は打ち砕かれ、 家族に見られたくなくて、風呂に入って泣いた。 いままで読み損なっていたことを後悔すると同時に、「解説」とともに 読む事が出来た幸運も感じた。
2013/05/11
コメント(4)
-
「実録・連合赤軍 あさま山荘への道程」(2008)
CSで観た。3時間を超える長編である。 あさま山荘事件の頃は小学生だった。連日、帰宅するとTVに齧りついて いたことをうっすら覚えている。 今回、映画作品ながら、連合赤軍の道程の一部を丁寧に描いたこの作品を 観て、仙石や菅など、雑魚とは言え、この連中の残党が、ほんの数年間で も、国の中枢に居たという事実に、ゾッとした。 もちろん、ステレオタイプでものを観てはいけないのだが、事実、仙石な どは「自衛隊は暴力装置」など、当時の思考のままでなければ出てこない ようなフレーズを、国会の場で使ったりしていた以上、往時を引き摺って いると判じても無理はない筈だ。 ビックリしたのは、6歳年下の家内の反応である。 「これ、本当の話?」と尋ねられたのだ。 風化の早さもあるが、彼らに影響を受けたものの多くが、熱が冷めたよう にサッと転身した、その転身の見事さも窺がえよう。 私自身は、通った大学の門の前に、ヘルメットとゲバ棒を持った学生と、 機動隊のバスが睨みあっているのを観て「こんな連中、まだいたのか?」 と心底驚いたものである。 さらに驚いたのは、同級のものの中から数人が、いつの間にか講義に出席 しなくなり「活動」に身を投じたことである。 「あれは熱病みたいなものだった」なんて流してはならない数年間を、 それなりの迫真力で描いた作品だと思う。 そう言えば、5/11に行われた民主党の反省会では、きっちりした「総括」 は行われなかったようである。
2013/05/10
コメント(0)
-
さとり世代
ラベルをはらなければ気が済まない、頭の悪いマスコミらしい表現である。 「さとり世代」といわれる人達の特徴を聞いていると、物欲まみれの私 なんぞは、尊敬すらしてしまうのだが、世の「大人」たちには面白くない らしい。 「車を欲しがらない若者なんて」などと平然とコメントする「大人」達を みていると、20年の長きに亘り、この国が不景気に暗くなっていた理由 のひとつが解るような気がする。 何でも類型化しなければ気の済まない、思考するスタミナの欠如、徹底 した「事実の積み上げ」より、手近な流行りの理論に飛びつきやすい、 等を特徴とした世代が経営する立場に廻ってから、経済力の根幹をなす 民間企業の業績自体が悪化してきたのである。 仕方もなかろう。彼らの多くは、大学時代にまともに勉強していないので ある。向学心のあった者には「勉強できる環境ではなかった」という不運 とも言えるだろうが。 今の「ゆとり世代」どころではない。 「勉強だけではない」という側面は確かにあるが、勉強していなければ どうしようもない分野もある。さらに、大学とは 「未知の命題に対してどのようにアプローチするか?」ということを学ぶ 場でもある。 そこで手抜きをしてしまっては、現実の企業経営に立ち向かえるだけの 素養がない、ということにも繋がってしまうだろう。 最終的には、個人の真面目さ、ということになれば、世代を云々したり、 低次元の思い込みで、揶揄するよりもやるべきことがあるだろう。
2013/05/09
コメント(0)
-

写真撮影用アイピース
随分昔、まだ銀塩写真時代にPENTAXから発売された拡大撮影用アイピース。 もちろん既に生産中止になっている。 メーカーによれば 「月面や惑星面を撮影するために、特別に設計された拡大撮影レンズです。 従来の眼視観測用アイピースでは補正しきれなかったディスト-ション (歪曲収差)から像面湾曲など、拡大撮影に影響を及ぼす諸収差を極限 まで低減。 中心から周辺までシャープで歪みの少ない描写特性が得られます。」 ということだが、確かに、月面や太陽面の撮影では威力を発揮した。 焦点距離は、3.8mm,14mm,24mmで、ツアイスサイズなのでカメラアダプタ にセットして使う場合にも、軽量で済む。 焦点距離の短い鏡筒などにも好適である。 某専門誌のフォトコンで入選させていただいた時期には、ほとんどこれを 使用して撮影していた。 この時期は、既にCCDを使用していたので、銀塩のみならず、デジタル化 にも存分に威力を発揮した優秀なアイピースと言える。 アイレンズが小さいので、デジカメを使用した最近の惑星撮影にはあまり 出番はないのだが、最近流行り出した「拡大○○法」(私は古典的な手法 をデジタルに応用しただけだと思っているのだが)などには活用できると 思う。 PENTAX_XP_38 posted by (C)kirk1701 PENTAX_XP_14 posted by (C)kirk1701 PENTAX_XP_24 posted by (C)kirk1701
2013/05/08
コメント(0)
-
ボディブロー復権?ボクシング世界戦
内山の防衛戦は、不覚にも見逃してしまった。 「デビュー当時は引退していると思っていた」と自身が語る33歳を 超え、今は「いつまでやれるか楽しみ」という内山は、今回も、自身を 甘やかすことなく、さらにハードなトレーニングを積んで臨んだという。 結果は、ボディで相手をのたうちまわらせてのKO勝利とのこと。 拳を捻る内山独特のパンチが「下突き」のように喰い込んだのだろう。 是非観たかったものだ。 井岡と宮崎のW防衛戦はしっかり観た。 ミニマム級とは思えない、牛相撲のようなパワーあふれる打ち合いを 制し、KOした宮崎。 脚の筋肉を見た限り、まだまだ階級を上げられるのではないか? そして井岡。 天才というより、破綻のない秀才型のボクサーである。 今回も無理をせず、試合をコントロールすることに務め、相手の疲れを 見極めて、ボディでKO。 3人とも相手はかなりのテクニシャンで、顔面だけの打ち合いであった ら結果はわからなかったかも知れない。 そのせめぎ合いの中で、ボディでKOできることを見せた内山、井岡は 技術的にもまだまだ伸びるのだろう。 愛すべき性格でコッテ牛のような試合展開をする宮崎にも期待したい。
2013/05/07
コメント(0)
-

目盛環を使った天体の導入
息子用に購入した天体望遠鏡の架台は、所謂経緯台方式だが、 自動導入装置が付いており、セッティングして、目立つ天体(恒星)を 視野に導入して「アライメント」ボタンを押せば、後はそれを基準に 勝手に目的の天体を導入してくれる。 私の使用している赤道儀も、写真のEM-200Temmma2,ビクセンアトラクス など、自動導入はいまや当たり前の機能である。 以前は「望遠鏡が基準点からどの位動いたか?」を把握するデジタル式の エンコーダーなどを使っていたマニアも居た。 ドライブで言えば、エンコーダー時代はカーナビ、現在の自動導入架台は カーナビに自動運転システムが付いたようなものと言える。 確かに便利になったものである。以前トライした「メシエマラソン」では 自動導入をガンガン使って、一晩でメシエ天体を全て観たりもした。 然し、然し、である。 野外観測でバッテリーが切れたらそれまで。 肉眼で見える天体を、フリークランプで導入した後は、手動で追尾も 出来ないのである。 そこでこの連休。息子に敢えて、目盛環を利用した導入を授けた。 目立つ天体を視野に導入し、その赤経・赤緯に合わせて目盛環を合わせて 固定する。 後は、導入したい天体の赤経・赤緯に合うまで、望遠鏡を動かせば良い。 昔はこうやって導入して、肉眼では見えない淡い天体を導入して楽しんだ ものである。 自動導入を使うにしても、星図も読めなくては趣味としての楽しみも半減 である。 数日トライして、なんとか目盛環による導入の「概要」がわかってきた 息子。 「星図のhとかmとかって、そういう意味だったのか!」と得心がいった 様子である。 sekidougi_memorikan posted by (C)kirk1701
2013/05/06
コメント(0)
-

S&W M39 ABS ( MGC )
銃本体は2009年にUPしたものだと思う(発火目的でABSモデルはオクで 何挺が入手しているので自信がない)が、木製グリップの色合いを観て いただきたく、またLumixの練習も兼ねて撮影した次第。 HWよりもABSの方が、ソフトライティングの反射光と赤味の強いグリップ が好みのコントラストに撮れる。 32AUTOやウッズマンなどMGCの金型を引き継ぎ、手を加えて再販して くれているCAWあたりから、これもリメイクされないかと期待している。 M59の安直なバリエーションと言われる向きもあるが、かなり手間を かけて設計されたものであることを、旧いMGCのタブロイド紙で読んだ 記憶がある。 我々の世代には、名銃・44AUTOを想起させるモデルとして迎えられた モデルだった筈である。 ショートリコイルの再現など、マルシンのモデルと比較すると減点される ポイントも多いかもしれないが、作動重視のシンプルなこのモデル、今 握っても、充分魅力を感じる。 MGC_M39ABS_01 posted by (C)kirk1701 MGC_M39ABS_02 posted by (C)kirk1701
2013/05/05
コメント(2)
-

ツアイス・サイズのアイピース PENTAX Or9 & Or12
最近の天体望遠鏡用のアイピースと云えば、スリーブ径が31.7mmの通称 「アメリカン・サイズ」が2inchスリーブのものが主流である。 このアイピースは、スリーブ径24.5mm、通称、ツアイス・サイズと呼ば れる、いまではレトロの部類に入るアイピースである。 Orというのは「オルソスコピック」の略で、特定の構造を示すものでは なく「整った像」という意味である。 昔は良質の天体望遠鏡も製作・販売していたペンタックスは、アイピース のラインナップも凄まじかった。 これはその中の2本である。 我が家でも実用的には、デジカメ専用の簡易カメラアダプタの中にセット し易いサイズなので重宝されている以外は、新型のアイピースに押され、 アイピース用のBOXの片隅に仕舞込まれていることが多かった。 ところが一転、このところのマイブーム、昭和レトロ鏡筒での観望に於いて、 俄然稼働率がアップ。 何しろ、鏡筒に付属してくる接眼部は、全てツアイス・サイズなのである。 もちろん、変換リングで、現行アイピースが使えるようにもしているが、 そこはそれ、当時ものの鏡筒には、当時もののアイピースと、使いまくって いる。 最近の整像性とアイレリーフを追求したアイピースは、カメラのように レンズ枚数が多くなっており、いくら優れたコーティングを施しても、 「ヌケ」の良さの点では、このアイピースには敵わない。 アイレンズ(覗く側のレンズ)が小さいことで、ビギナーには使い辛いが、 我々世代は、もともと小さいアイレンズに慣れているので、さほど苦になら ないものだ。 事実、特にレトロの屈折鏡筒に関して言えば、HM(ミッテンゼーハイゲン) やこのOrなどで覗くと、相性の良さがハッキリと確認できる。 手放さなくて良かった! Pentax_or12 posted by (C)kirk1701 Pentax_or9 posted by (C)kirk1701
2013/05/04
コメント(0)
-
稽古 ~見切り~
劇画などでも紹介されていたので、稽古している者は誰でも耳にした ことがあるはずの「見切り」 相手の攻撃の間合い、或いは軌道を自分の身体すれすれのところで かわすことで、反撃する時の距離を最短に保てるということなのだが。 そのほか、相手に「当った」と思わせた直後に空振りさせることで、 体勢を崩したり、心理的に疲れされるのも効果とされている。 気をつけなければいけないのは、自身の動きが悪くて、余裕で避けた つもりが、ギリギリになってしまった、という芳しくない結果を、 「見切ったぜ」と勘違いしてしまう者もいる(笑) 若い頃は、深く理解も出来ぬまま、とにかくギリギリでかわすのが 見切りと思い、測り損なって相手の攻撃を貰ってしまう間抜けな様に なることも何度かあったが、30歳を過ぎて、スタイルの異なる会派に 身を置いてからは、見切りというものは、組手の中において、もっと 全体的に捉えて行うべきものであることがわかってきた。 飛んできた攻撃を見切るのではなく、最初から相手の攻撃の終点を 読み、相手と同時に動きながら、自然にギリギリ当らないところに 予め動いているべきである。 すなわち、組手全体がコントロール出来ていなければ、相手の攻撃を 全て見切ることは不可能である。 もちろん、後進に対しては、技術的な側面で「見切り」を習得する訓練 を工夫し、彼ら同士の組手などで効果が上がっているのは確認できては いるのだが、組手全体をコントロールするためには、まだまだ経験と 訓練が必要である。 何より、失敗を恐れない気持の強さ、そしてある程度、天性のクソ度胸 も必要なのは事実である。
2013/05/03
コメント(4)
-

#3776 CHERTRES BLUE ( PLATINUM )
昨年の万年筆展だったか、プラチナの「スリップシール機構」の紹介 パネルを観た。 半年以上放置しても、キャップさえつけておけばインクの乾燥を防げる、 ということだが、我々のような愛好者のほとんどが、インクを入れた 万年筆は決して乾燥しないように小まめに筆記している筈だ。 それよりも、国産万年筆の場合、文句なしの実用性に比べてデザインの 点でイマイチであり、既に数本#3776シリーズを持っていることもあり、 購入する機会がなかった。 年末だったか、この万年筆の予約受付が開始されることをネットで知り、 上品なブルーのデザインに、即、予約してしまった。 字幅はF。既に手帳用に極細を1本常用しているので、こちらは日記用 に使っている。 先に述べたように、ほぼ毎日使用しているので、スリップシール機構を 試す機会がないのは残念だが、書き味は相変わらず良く、書いた時の バランスは、まさに日本人向きである。 プラチナのコンバーターは、全く当てにならないので仕方なくカート リッジを使用している。 新機構も良いが、コンバーターと首軸のはめ合いに不安の無い品質管理 を期待したいものだ(笑) PLATINUM_CHERTRES_BLUE-01 posted by (C)kirk1701 PLATINUM_CHERTRES_BLUE-02 posted by (C)kirk1701
2013/05/02
コメント(5)
-
首相・閣僚のGW外遊
昨年までは、本当に腹の立つような文字通りの「外遊」にイライラ したものだが、今回は、ロングランの安倍首相はじめ、他の主要閣僚も それぞれ、それなりに有効な国を選んで訪れているように思える。 特に意図的に中国を抜いた(閣僚会談拒否は中国側からしている)経路 を観ているだけでも楽しい。 首相の日露首脳会談に関しては、メドベージェフ対民主党という全く 動きの無かった時代から、少しづつ、動き始める期待が持てる。 北方領土に関しては、ポツダム宣言受諾後に日ソ中立条約を破棄(この 破棄の正当性については、小生の知る限り議論が対立しており、どちら かを選択はできないが)して、どさくさまぎれに侵攻して簒奪したもの と認識しているが、70年近い実効支配がある以上、安倍総理が言及した 「帰属を明確にする」というのが、現状精々であろう。 ずっと以前書いた記憶があるが、北方領土に関しては自治区のような 形にして、日露の将来に向けての有意義なエリアになるといいと思って いるのだが。 今回の外遊で「アフリカが欠けている」と例によって左巻き評論家が くさしているのを聞いたが、あの連中はどうしても中国というフィルタ を通してしか物事を考えられないらしい。 知見のあるビジネスマンに聞けば「中国が席巻している」とされる アフリカ諸国の中で、旧宗主国が英(語圏)の国々との関係に関しては、 ODAなども含め、かなり評価できる状態であることがわかるだろう。 その情報はもちろん政府ももっているのだろう。喫緊の課題がない時点 でのアフリカ外遊は見送られた、と考えるのが自然であろう。 また、外遊のコストを計算してくれているTV局もあったが、「内向き」 とされてきた日本外交を批判してきた側が、ちょっと外交を活発にすれ ばコスト云々なんて、とにかく足を引っ張りたいのだろうが、もっと 国民の知的水準にあった番組づくりをして欲しい。 というより、低脳マスコミはもう、事実だけ伝えて、後はバラエティ でもやって、自然消滅して欲しい。
2013/05/01
コメント(2)
全31件 (31件中 1-31件目)
1