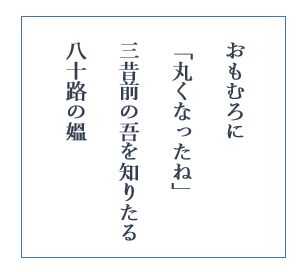全75件 (75件中 1-50件目)
-
立春大吉
「東風凍を解く」(とうふうこおりをとく)今日の旧暦・七十二候です。東から風が吹きはじめ、厚い氷を溶かし始める時期。東の風とは、春風のことをいい、七十二候では、この候が第一候となります。「東風ふかば、にほひおこせよ、梅の花...」道真公も詠ってらっしゃいますね。ですが、今年は溶かすほどの氷が、張らなかったようです。さて、節分で鬼を祓って、福を招き入れたところで、(恵方巻きにもかぶりついたところで...笑)今日は立春。今年の気が本格的に動き始めるといいます。以前、立春からの一週間は、今年の雛形になると聞きました。立春からの過ごし方は重要ですよ...と。怒らず、イライラせず、心穏やかに、人とは和を保って...と言いますが、実際にはなかなか...。そうはいかないことのほうが多いですね(経験談)でもこの一週間、心穏やかに過ごしたなら、今年一年は、なし崩し的に? 芋づる式に?(...笑)心穏やかに暮らせようというもの。なんだか解釈が間違っていそうですが、(間違ってますね、たぶん...汗)立春一週間を、少し意識して過ごしてみると何か見えるものがあるかもしれないと思う私です。ところで、今日は新居で使う家電を買いにいきます。自分なりに見積もったところ、思ったよりも...。(あぶら汗)もしかして散財の一年?? と思った私でしたが、いえいえ、古きを捨て、新しく出発の一年なのだと思い改める私でした。それにしても、ドラム式洗濯機は諦めなきゃダメかな...(溜息)
February 4, 2007
-
真綿のふとん
二月になりましたね。明日は節分。春までカウントダウン。ブログも春らしく黄色。たまごいろ。さて、昨日はおふとんを注文してきました。お客様用と自宅用の敷ふとん。それぞれ二組。一組は打ち直して...。結婚二年目のお正月、主人の実家から帰った私達はその足で、私の実家へ新年の挨拶に。家に着き、...なんだか寒気が、と思っているうちに、高熱を出して、大風邪をひいてしまいました。(甘え以外の何ものでもないですね...ははは。)母が客用ふとんを敷いてくれました。身体を横たえた時の、真綿のやわらかさが、とても、とても、ここちよく、母の優しさのように思えたのでしょうか。治るころ、真綿の敷ふとんを作る、と固く心に決めていました。それからずっと、おふとん生活の私ですが、結婚前はベッドに寝ていました。ベッドに寝ることは、童話の中のお姫様のようで、乙女心は真綿につつまれていましたが、今は、身体を真綿でつつまないと、乙女心がしょんぼり、元気がなくなってしまいます(笑)ふとんの柄をあれこれと選び、打ち直されてふんわり、ふかふかになって戻ってくる...。ひだまりのような幸福。「市内に40件はあったお店がね、ここ15年くらいで14件に減っちゃったよ。」とは、布団店のご主人の談。やっぱりベッド派が多いことや、一人暮らしの学生、社会人は、安く使い捨てられたほうが便利、という背景があるようです。ところで私、掛けふとんは羽毛です。...ええと、なんというか、首や肩に巻けるあの感じ。それはそれで、真綿にない良さがありますね(笑)
February 2, 2007
-
木挽きさま
昨日は、洋裁教室で仲良くなった方とお会いしました。年が明けてから初めてお会いするので、久しぶりに話も弾み、会話は、いま建設中の家に話に。私より、ひとまわり上のその方なら、解ってくださるだろうと、今の木造住宅事情について、つい熱く語ってしまいました。事情について書くと、長く熱くなってしまうので(笑)他のサイトに譲りますが、最終的には、安いとはいえ外材使用ばかりで、日本の木はなぜ使えないのかしら(使えても高額になる)という話に、東北の農家ご出身の、その方は笑って言いました。「だいたい、コビキサマがいないもの。」「コビキサマ?」「木を切る人!」「....ああ、木挽きさま!」木挽きさまという言葉を初めて聞く私は、のこぎりを挽くマネをしながら答えました。その方が言うには、ご実家は山もあるそうで、自分と同じ年の木が、家を建てるくらいはあるとのこと。木を切り、木の皮を剥ぎ、乾燥させ、山からおろし、町まで運び...と高額なお金がかかるということもあるのですが、その前に誰が木を切ってくれるの?木挽きさまもいないのに...?という話になるのだそうです。当然のように、山は荒れているとのこと。木挽きさまは、様とつくからには、尊いお仕事だったのかしらと聞くと「尊いというか....やっぱり危険な仕事で、誰にでもできることではないし、自然への畏怖から、大きな木は精霊みたいなものがあると考えていたでしょうしね。それを扱う人だから...ね。」私の実家はごく普通の、小さな家ではありますが、大工さんがカンナで木を削って造っていました。それが普通でした。それから30年は経っていません。日本林業の荒廃、なんて難しいことをいうつもりはありませんが木挽きさまの話を聞き、ふたたび日本の山や木について考えてしまう私でした。
January 18, 2007
-
固定された場所で
2006年・下半期備忘録も書きなさい、と主人からのリクエスト。というよりは、せっかく始めたのだから多少はなんとかしなさいと、遠回しに言っています。(はーい、すみません...)上半期備忘録でも書きましたが、家を移ることが決まりました。実際の引越は今年なのですが、昨年はその準備で様々に決めなくてはいけないことがあり、事務手続きがありと日々暮れていった下半期でした。大変ながらも楽しいことのはずの、新たな家への準備。友達からも「...いろいろ考えるのもワクワクするわね。」と言われます。それは本当にそうで、うれしい気持ちであることにかわりはないのですがなんだか心が安定しない自分がいるのですね。考えてもしょうがないことや、まず起こり得ないと思われることが、小さな泡のように浮かんできては消え、さざ波立つ。ああ、この感じ...前にもあったと思い立ちました。就職した時。結婚した時。善きこと二つの転機に、私はもやもやと不安定。大きく居場所が変わるとき、私はいつもいつも同じような心持ちになります。単調と思える日々、しかもそれが地味だったりすると、くつがえすような、ワクワクした変化を望む自分が出てきたりしますが、それは、現実的な居場所が決まっているからこその安定した気持ちの表れなのですね。居場所が固定されると、気持ちも固定されたように思う人もいます。固定した場所があることで、初めて気持ちを広げられる人もいます。どちらに視点を置くクセがあるかで、心持ちとは変わるのですね。さて、いままでの例でいくと、新しい生活に、安定着陸するのに3年くらいはかかる予定...(長い!)解っちゃいるのに...止められない!?
January 10, 2007
-
寒中お見舞い申し上げます
十五日までは、小正月...とはいえ、あけまして....は、あまりにも遅い今日。寒中お見舞い申し上げます。昨年訪れてくださった皆様、ありがとうございました。ブログを続けていこうか迷う日々ではありますが、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
January 10, 2007
-
女心と秋の空
上半期備忘録も終わり(二件で終わりです...笑)、家の間取りに頭悩ませていますが、昨日はあまりに考えすぎて、今日起きたら、お肌がざらざら。口の上には、ぷつんとできものが...。どう見ても、昨日の考えすぎが、たたっている様子。そんなに考えてもしょうがないことを、延々と考えてしまうところが、私にはあります。しかも、考えて建設的な結論が出るなら良いのですが、極端な結論がでてしまいます。昨日も、食べることもおろそかに、洋裁の宿題もそっちのけで、間取りを考えていたものの、最後は、決まりかけていた案をまったく白紙にしようというようなことを口走る始末。主人も、怒るを通り越して、呆れ顔。心身共に、良くないほうに傾きつつあるなと思ったので、今日は家事をしたり、買い物に行ったり、洋裁の宿題をしたり...。身体を動かすようにしていました。(宿題、しないといけませんよね...へへへ)そんな中、宅配便がきました。たのんでいた本でした。「私の洋風料理ノート」 著:佐藤雅子パラパラとめくっているうちに、新しい家でこんな料理を作るのって素敵よね~、と想像しているうちに、楽しくて、晴々とした気持ちになってきました。「その間取り案で、いいんじゃない?」そう言いにきてくれたように思えてきました。不思議なもので、その後は、お夕飯も楽しく作れた気がします。どちらもちょっとしたことなのですけどね~。女心は、自分でも、わからなくて困ります(笑)
September 21, 2006
-
家探し、自分探し
先週まで暑かったのに、ここ数日の雨と急に涼しく(寒く、といってもいいくらい)なったので、体調くずされている方もいるのではないでしょうか。そんな私も、先日の満月あたりから胃腸の動きがあまりよくないのです。月の動きが体調に作用するのは、意識していると案外に当てはまるようです。月のせいというよりも、夏の冷たいものの飲食が胃腸のお疲れとなってでてきている...のは、わかっているのですけどね...。皆様も、お身体大切に。お腹大切に(笑)さて、今年上半期備忘録2。家を移ることになりました。洋裁教室1学期が7月に終わり、9月まで(2学期が始まるまで)少しのんびりできるわ、と思っていたところ、取って代わるようなこの話に、休む間もなく家一色の日々に。不動産屋さんはもちろん、ハウスメーカー、家族親戚を含めた身近な人に話を聞き、本も読み、ネットもフル活用。家を購入する(または建てる)人がする、おおよその研究を一通りこなしたと思います。自分探し、という言葉がありますが、家探しは、まさに自分探しでした。私達が選んだ物は、今住んでいる駅近くの建築条件付きの土地でした。家を選ぶには、いろいろな要素があると思いますが、あれこれ悩んだ末、利便性を選んでいるということは、なんといいますか...結局、私(主人も)、便利な生活が好きなのね、と自分自身に見せつけられてしまいました(苦笑)いままで引っ越したいと思っても、引っ越すことができずにいた私達に、いろいろなことが重なり、家を購入するという機会が、めぐってきました。輪が回り、家がやってくるようです。
September 14, 2006
-
洋裁
久しぶりに日記を書こうと思います。今年上半期の備忘録として。4月から洋裁を習い始めました。以前から習いたいなと思いながら、うまくタイミングがあわなくて見送ること3年くらい。小学校卒業くらいまでは、母お手製の服を着ることが多かった私。お針やミシンは身近なもので、ちょっとした手芸、パターンのある洋服なら、見よう見まねで作ったこともあり、針を持つ抵抗感はあまりなく、それどころか、まあまあよ...なんて鼻の伸びるような気持ちでいました。運針から教えてくださる、その教室で自分の針運びが自己流のおかしな癖がついたものであることを知り、しつけひとつ架けるにも、四苦八苦。伸びた鼻はポッキリと落ちてしまいました。そんな状態ですから、週一回の教室はもう、ふうふう。しかも毎週、ここまではお家で...と宿題もでます。これまた、ふうふう。途中、いやになりながらも、(癇癪、おこしてました...ははは。)なんとかできたあがったスカートとブラウス。それを着て、先生と皆で写真を撮ったときは、本当にうれしい気持ちでした。皆勤できたこと。先生のお手伝いがあった(かなりありました...汗)とはいえちゃんと着られるようなものができたこと。写真を撮りながら、なんとなく誇らしい...そんな気持ちでした。1学期を終えただけですが、採寸をして体に合わせた服を、きちんと作るということはいくつもの工程を経るということを知りました。私の作ったものは基本も基本、裏地なしの一重ものでしたが、それでも丁寧だと感じたくらいです。そして、着た時の感じ...これがまたとてもいいのです。一言でいうなら ”無理がない” のですね。昔は、それなりの値段で(けして安くはなかったらしいですが)洋服を作ってくれる所がたくさんあったと聞きました。私の家は裕福な家ではなく、ごく普通のサラリーマン家庭でしたが、母が良いスーツやコートが欲しいという時など、たまにオーダーをしていたのを、小さな私は覚えています。9月から2学期が始まりました。相変わらず、ふうふうなのですが、裕福な気持ちを味わたくて2学期もまた、通っています。
September 11, 2006
-
コーラと国産レモン
久しぶりにコーラを飲みました。暖かな日和、というほどではありませんでしたのに、外出をした帰り道、喉が渇いたのでしょうか、家が近くなるにつれて、なぜか無性にコーラが飲みたくなってきました。お店で500mlを二本、国産レモンを一袋。少しの氷とレモンの薄切をコップに入れてコーラを注ぐと、シュワーと炭酸がおいしそうな音をたてます。ほとんど一気に飲んで、ふぅーと溜息。にっこり。満足。清涼飲料水って、あまり身体に良くないのよね...などと思いながら満足する私。ファストフードと呼ばれる、食べ物があります。身体に良くない、食生活の乱れの槍玉に挙げられたりしています。その土地で生まれた食べ物や、郷土料理を大切にする...。最近では無農薬など、広い意味での身体に良いものを採ることの意味合いも含まれている...。そんなスローフード運動と対極にある食べ物です。私自身も、身体にこわしてから、食事を大切にしようと、飲料水を含んだ、ファストフード的なものを、全く食べないようにしたことがあります。身体に良いものだけを採ることで、身体が改善すると信じているようなところがありました。もちろん実際に、身体によかったのですが、不思議なもので時々、ファストフード的なものを食べたくなる自分がいました。それでもそれは、身体に悪いからと、欲求には答えないでいることが続きました。ある日、こんな文章を読みました。「うちも以前はね、食べ物にこったことがあったの(玄米食とか無農薬野菜のこと)、 でもね、この世界(俗世)に生きている限りは、なんでも食べなきゃやっていけないってことに気づいて、やめたの。」時折のファストフードを、身体に許してあげる。コーラに無農薬の国産レモン。すこし笑ってしまうような、矛盾を抱えて、私の食べ物に対するスタンスは、そんなところに落ち着いています。
April 1, 2006
-
雷の声
「雷乃ち声を発す」(かみなりすなわちこえをはっす)今日の旧暦・七十二候です。遠くで雷の声がし始め、驚かされる時節とあります。東洋の考えでは、雷は、季節は春、方角は東、色は青か若草色、などと言われます。どの意匠をみても、すべて誕生を連想させ、生まれたての赤ちゃんのようなみずみずしさを思わせます。不思議なもので、今日の七十二候以前に咲く春の花は、花がとても目立ちます。夏の、葉も花もどちらも勢いよく盛る感じとは違って、葉が出ていない、または、あまり葉を感じさせないものが多いように思います。この雷、実際の雷でもあるのでしょう。春の、花が散って葉が出始めることを思うと、吹き出すように広がる、若葉の音とも思えます。若葉風の吹くまえに、春爛漫。花疲れの出ませんように...。
March 31, 2006
-
溜息ふたつ
「桜始めて開く」(さくらはじめてひらく)今日の旧暦・七十二候です。本格的な春となり、桜の花が咲き始める頃です。...という解説もいらないくらい、街は、桜、さくら。春霞。先週のある日の夜、主人に、「週末はお花見かな~?」と、水を向けたところ、「夜桜、観にいこうよ。」「夜桜?どこに?」「六義園。」リクギエン? 夜桜...寒い...風邪引くかも...と、ピクニックのようなお花見を、想像していた私は、後向きな単語を、浮かべていました。夜桜は久しく観ていません。名前から想像するに日本庭園...行くことにしました。ソメイヨシノより早咲きの、このしだれ桜は、来る人を出迎えるように、大門をくぐると、すぐのところにありました。あでやかに咲く桜に、人だかりがして、そこここにカメラを向ける人、人。この美しい大名庭園は、桜ばかりでなく、松もまた見事。水面に触れんばかりの松の枝が、華美になることなく、美しく照らし出され、「幽玄とは、きっと...こういうことをいうのね...」と、ホゥという溜息ばかりが漏れます。神社やお寺、庭園など、いわゆる名所といわれる場所の木々は、なぜあんなにも大きく、また、普通みることのない、意志をもっているかのような、表情をみせるのでしょう。入場券に”回遊式築山泉水庭園”(カイユウシキ/ツキヤマ/センスイ/テイエン)とあります。それがどういうものなのか、判らない私ですが、そこにある場の気が、良いものであるのは感じとれたような気がしました。木々は、取り巻く気を栄養として、自らの精霊を育てているのかも...と思う、夜桜見物でした。さて、六義園に行くのに一つ手前の巣鴨駅で降り、歩いて行ったのですが、たぶん元は武家屋敷が並んでいたのだろうと思わせる、高い塀に囲まれた立派なお宅ばかり。皆、申し合わせたように、セキュリティー会社の赤いシールが貼られて...。「邸宅って言うのは、こういうのを言うんだろうな...。」と主人。ここでもまた、溜息をつく二人でした。(笑)
March 26, 2006
-
サボテンの花
毎年、節分をすぎた頃になると、気になるものがあります。エアコンの室外機の上に置かれたサボテンです。旅行で伊豆に行き、買い求めたものです。最初は水色の楕円の鉢に、まあるいのが二つ、ならんで植わっていました。毎年、判るか判らないくらいづつ、大きくなって、窮屈そうだったので、ひとつひとつの鉢に植え替えました。そうしたら、次の年に、ひとつには濃いピンクの花。もうひとつには檸檬色の花。サボテンの花なんて、植物園か、愛好家のところでしか見ることのできないものだと思っていました。ガラスの温室などない、外に置き放しのサボテンが、何で花をつけたのか、何をしたからなのか、最初はわかりませんでした。小学生のころにみた映像が、小さな記憶としてありました。くる日もくる日も、日照りが続き、荒野のような、砂漠のようなところに、干からびた様子のサボテン。ある日、雲が厚くなり、雨が落ちてきます。恵みの雨.....雨季がやってきたのです。ナレーションが言います。降り続いた雨が上がり、再びカッと、熱い太陽が照りつけると、みるみる花が咲き始める。手品をみているような自然の驚異。胸躍らせた、その記憶のとおり、私は水をあげたようなのです。サボテンは他の草花や木々のように水が欲しいという感じを、あまりみせません。それでも、冬には冬の、夏には夏の表情をみせます。冬は縮こまって、しかも針のような綿毛みたいなものをマフラーのようにぐるぐると巻いて寒さをやり過ごしているようですし、夏に水をあげると、「ああ、おいしかった!」というようなぷっくりした表情になります。(これが結構おかしい...笑)節分から2月の後半にかけて、小さな花芽のようなものが見えてきます。ですが、今年はそれが見えません。もう少ししたら、出てくるかな、出てくるかなと心待ちに見ていたのですが.....。こころなしか、しょんぼりした雰囲気のサボテンに、なんとなく、すまない気持ちの私。やっぱり、今年の冬は寒かったのですね....。
March 23, 2006
-
春分
「雀始めて巣う」(すずめはじめてすくう)今日の旧暦・七十二候です。今日は春分。春の気が盛んになり、雀が巣を構える時節とあります。七十二候には、さまざまな季節の動植物ができますが、巣を作るのは雀だけなのです。この後、ツバメも登場しますが、巣を作るとは記されていません。ちょうど今の時期、入学、転勤と、年度切り替えの引越しが多いからでしょうか。新たに居を構える人が多いことを、上手にあらわしたものなのかもしれませんね。さて、お彼岸の今日。お墓へは、遠距離の都合上、土日に参ったこともあり、ぼた餅を食べながら、野球を観て「世界一!日本!!」とはしゃぐ、のんびりとした休日となりました。街には、白木蓮が満開で、その白い小鳥が飛び立つころ、桜が咲き始める....。初めてを始める人。改めて始める人。新たに始める人。人々は移動を始め、世界がカラフルに動き始める春。春がきたのですね。
March 21, 2006
-
菜虫蝶と化る
「菜虫蝶と化る」(なむしちょうとなる)今日の旧暦・七十二候です。成長した菜虫(青虫)が、紋白蝶となる時期です。幼虫の間、一所懸命に葉をはみ、蛹になれば、危ういことなど気にも留めないような、堅牢の姿。そして、美しい姿へと生まれ変わり、空へと飛び立つ。蝶には不思議な魅力があるように思います。”秘すれば花” の 「風姿花伝」。世阿弥の著した、能楽の伝書。古典をすらすら読める力があるといいのですが、残念ながらそうではない私は、リンボウ先生こと、林 望さんのお書きになった「すらすら読める風姿花伝」(講談社刊)で、この古典のよさを知りました。”ひとつ、秘する花を知ること。 秘すれば花なり。秘せずは花なるべからず、となり。 この分け目を知ること、肝要の花なり。” (秘めておくことが大切だということを知ること。 秘めておくからこそ、それが花になる。 あからさまに公開してしまったら、もはや花ではない。)これは、能楽のことだけではなく、私達の、生活の中に生きる言葉ではないかと思います。大地の上を、一所懸命に這い回るように生き、時にはじっと、身を固くしなくてはいけない時もあるでしょう。でもそれは、秘めてこそ花になる。昔、蝶になることは、表立つことだと思っていました。すこしばかりの年を重ね、そうばかりではないのだと知ってからも、他の蝶をみると、自分も、とあせって追いかけて行きたくなる.....。そんな気持ちになることもしばしば。秘すれば花...は、堅牢な蛹の姿なのかもしれません。
March 15, 2006
-
FAXが春を連れて...
「桜始めて開く」(さくらはじめてひらく)今日の旧暦・七十二候です。本格的な春となり、桜の花が咲き始める頃...。河津桜など、早咲き桜のたよりも聞かれます。「今年は、梅と桜が一緒ね。」と、道行く人の会話。梅に菜の花、桜にチューリップ。昨日は、お訪ねしたブログに、白木蓮の話もありました。各地から、花便り、春便り。そろそろ、母からファックスが届きそうです。「お暇な時でいいですから、ドライブに行きましょう。コースを考えてみました....。」以下、一案として...と、ズラズラと行きたいところが書いてあります。テレビや新聞の花便りに、母の遊び心も芽を出すようです。突然来る春便りに、心づもりをするのも私の春の準備です。
March 10, 2006
-
「四季の味」
あ、「四季の味」が出てる...春号。すこし浮き足だちました。以前から、気になっていた雑誌でした。パラパラと見ては、棚に戻して迷っている...。そんなことを一年くらい続けたでしょうか。春号から買う、っていうのもいいなと購入しました。この料理雑誌が好きなのは、素材の名前を漢字で表記しているところです。栄螺、菠薐草、桜鱒、筍、独活、ジャガ薯...。(さざえ、ほうれんそう、さくらます、たけのこ、うど、じゃがいも)食べ物の名を、漢字で書くことも、読むことも、あまりない私。ふりがなも符ってあるので、こんなふうに書くのねと勉強になります。「そこでためしに、とろりと軟らかく仕上げたキャラメルのアイスクリームを こんどは緑釉の線描を施した小鉢に盛ってみた。 すると、まるで日溜まりに丸くなって眠る子猫のように見えるから傑作。」とは、口絵の文章。ガラスの器もいいけれど、焼き物の器を使うことを氷菓らしからぬ、春風駘蕩の佇まいもご愛嬌と、締めくくっています。秀逸。そして、キャラメル色のアイスが食べたくなりました。
March 9, 2006
-
お砂糖あれこれ
お砂糖の話を今日もまた...。ひどく身体をこわしたことがあり、その時にいろいろな健康に関係する本を読みあさり実践したことがあります。絹の五本指靴下に半身浴。一日一万歩にストレッチ。ストレスにならないようなのんびりした生活....。当然、食べ物にも気を使うようになりました。マクロビオテックとまではいかないものの、自然食品店といわれるところに一時、入りびったこともあります。その時、白砂糖は身体によくないと、はちみつや黒砂糖、三温糖、てんさい糖などに切り替えて白砂糖をすっかり追い出してしまった時がありました。でも少ししてから、白砂糖もお砂糖コレクションの中に戻してあげました。料理をしていると、白砂糖のほうがなじみやすいなと思う献立があるからでした。酢の物や、胡麻和えなどの和え物。厚焼き玉子はお日様色に。ケーキは色つやよく、ジャムの透明感もきれいです。健康関係の本が唱う、白砂糖の害については私もそう思うところがあるのですが、甘味のひとつとして、うまく使ったらいいのではと最近は思っています。...なんてケーキを頬ばりながらじゃ、説得力なしですね。(今日は私の誕生日...小さな声で)
March 6, 2006
-
ばら印のお砂糖
忘れられないお砂糖があります。「ばら印の角砂糖」大日本明治製糖というところが作っているのですが、2年くらい前に、海外ものの食品を扱うコーヒーショップで見かけて、そのパッケージに一目惚れ。ばら色の台紙に小さな白ばらの絵がちらばり、真ん中に「ばら印の角砂糖」と、ゴシックで白抜きしてあります。すこし昔な感じのする箱の中には、きちんとお行儀よくならんだお砂糖達。薄いセロハンにつつまれて、大事に造られた感じがします。私がこの角砂糖にこだわるのには、角がきれいだから。最近の角砂糖は、角の部分が、こころなしか削れてる。あめ玉のようにひとつの袋にいれられていては、そうなってしまうわよね....と、思う私。特別な味がするというわけでも、値段が高いというわけでも、ありませんでした。その箱入り娘のような行儀のよさに、いつもいつも使うのではなく、ちょっと特別というお茶の時間に少しづつ使っていたのですが、なくなってしまいました。今日、意外にも100円ショップで「ばら印の白砂糖」に会いました。角砂糖はありませんでしたが、すこし忘れかけていた薔薇色のパッケージを思い出して、その500gのお砂糖を買いました。またいつか、巡り会えるといいなと思いながら...。
March 5, 2006
-
父の再挑戦2
昨年、父が一度あきらめたパソコンを、再挑戦している旨の日記を書きましたが(「父の再挑戦」参照)あれから細々と続き、今日もまた講師をしてきました。先日、一つの作品が(と、あえて書きます)でき上がりました。その名も「セールスマン心得(基礎編)」(う~ん、なんかすごい...)「基礎編?基礎というからには、応用編もあるの?」との問いに「応用編は実践だ!」と言い切る父。「.....。」(う~ん、何となく何も言えない...)マニュアル作りに協力しました。パソコン初心者にありがちなことがたくさんありました。2ページ分の打ち込みを消してしまったり、その予防に、自動的にバックアップが取れるようにファイル設定して帰ると、次に来たときは、バックアップのバックアップファイルができていたりと、「ああ、もう!」なことに、我慢強さの鍛錬をしているようでしたが、表紙をつけ、黒い製本テープで綴じられたマニュアルが完成したときは、私もうれしい気持ちでいっぱいでした。昨年の12月、父は会社を退任しました。営業一筋、いわゆる叩き上げで、登ってきた父が、たぶん誰に残すともなく、作りたいと思ったマニュアルです。私も一部、もらいました。よく読めば、今流行りの自己啓発系の本に書いてあることと同じ様なことが書いてあります。でもそれは、父が培ってきたものの中から出てきたもの。A4にびっしりと、17ページに及ぶマニュアルには、営業マンとしての注意を、こと細かいところまで、いろいろと書いてあります。その最期に、父は「健康であれ」と書いていました。.....すこし涙がでました。やはり同じ様で、同じではないのです。たぶん私は時折、この「セールスマン心得」を開くことでしょう。
March 4, 2006
-
上巳の節句
雛祭りは、上巳の節句。五節句の一つです。旧暦では最初の巳の日に、このお祭りがなされます。中国では、この日に川で身を清め、穢れを祓う習慣がありました。それが日本では、平安時代に取り入れられます。人形を作り、それに穢れを写して川に流す....。それが、江戸時代に庶民の間にも広まり、今に続いています。あかりをつけましょ、ぼんぼりに。お花をあげましょ、桃の花。海老やでんぶ、錦糸卵にきぬさや、菜の花。春霞のようなちらし寿司に、手毬麩の浮かぶ、蛤のお吸い物。貝合わせの遊びは、蛤。他の貝とは合わさることのない、夫唱婦随の象徴。この娘が、よき伴侶に恵まれますように。遠い昔から連綿と、人の願いはいつも同じで、親ともなれば、ひとしおに。春の弥生の、このよき日。なによりうれしい雛祭り。
March 3, 2006
-
センスを勉強する
美容院でスタイリスト(髪を切ってくれる人)さんとセンスの話になりました。そのスタイリストさんは、新人採用の担当もなさっている方です。「シャンプーの上手な子は、必ず伸びますね。」と、スタイリストさん。美容院のお客を十数年している私も、それは常々感じていたので、「それは、とてもよく分かります。」と相槌を打ちました。「そして、センスもいい。」「シャンプーとセンス、関係あるんですか?」と私。「シャンプーも技術ですから、教えれば誰でもできるんですが、 人の気持ちを読めない子は、だいたい下手だし、なぜかセンスも悪いですよ。」と....。新人さんは、髪を切るといった、髪型デザインをすぐにさせてもらうことはできず、シャンプーや髪を巻くなどの、アシスタント業務から始まります。そんな地味な仕事を一所懸命に、お客様のことを考えていかにできるかに、センスの善し悪しがあらわれるようです。センスを磨くというと、もともと持っている才能を、更に磨きをかけるような感じがありますが、勉強しようという気のないところに、センスはないという事なのでしょう。「センスとかいう以前に、一所懸命な子は、見ていて気持ちがいいですしね。」センスとは、磨くのではなく勉強するものかもしれないと勉強になった(笑)一日でした。
January 31, 2006
-
一月一日
ローカルニュースで、横浜中華街の模様が映し出されていました。今日は春節。旧暦の一月一日です。アジア地域では、この春節を大切にする国が多く、日本も昔はそうでした。日本の旧暦とは、太陰太陽暦のこと。新月を、その月の一日(ついたち)として、日をめくっていく暦。明治六年に改暦されるまで、この月の満ち欠けを基準にした暦が使われていました。つい百年くらい前まで、日本は今日がお正月だったのですね。日本の文学や社会的事件は(改暦以前のもの)、旧暦に当てはめるととてもしっくりくると聞きます。新暦のお正月(ついこの間ですね...)に、書道をたしなむ方からいただいた書き初めを取り出してみていました。「新しき年の初めの初春の今日降る雪のいやしけ吉事」(あたらしき、としのはじめの、はつはるの、きょうふるゆきの、いやしけよごと) 大伴家持”新しい年のはじめである初春の今日は、降り積もる雪のようにいよいよ重なれよい事が。”今年一年、よい一年でありますように....。
January 29, 2006
-
血は水よりも
調子に乗って、また画像をアップしてみました(笑)家の光では、きれいに撮れませんねぇ。(前回のは喫茶店。同じ携帯とは思えない...汗)これは昨年生まれた姪の誕生日のために作りました。それにしても、姪というのはなんでこんなにかわいいのでしょう!?誤解を招く言い方になるかもしれませんが、私が、子供(赤ちゃん、幼児くらいまでの)にいだく感情というのは、姪が生まれるまで、ペットをかわいがるのと同じくらいのものだったと思います。かわいいとは思っても、母性豊かに接するということにまではならない自分がいました。ですが、ですが....。なんでしょうか...この気持ちは?? 今まで味わったことのない気持ちでした。かわいくて、かわいくて、しかたがないのです。もう、他の子とは違う”特別”なのです。こんな気持ち、親にも、妹にも、(えーと...)それから主人にも、感じたことがない愛おしさです。自分がこんなに叔母バカになるなんて、思いもよりませんでした。抗いがたい、遺伝子の成せる技。「血は水よりも濃い」とは、こういうことなのですね。こんな小さな命に、教わるなんて、どんな人にも、どんな時にも子供はやっぱり宝物なのですね。(叔母馬鹿日記で、すみません...。)
January 27, 2006
-
Good Luck
初めて画像をアップしてみました。デジカメは持っていないので、携帯で撮影したものです。友達が結婚することになりましたので、その婚約プレゼントにクローバーとてんとう虫の刺繍額を贈りました。友達と言っても、彼女は一回り年下の女の子。友達?後輩?義理の姪?と様々な気持ちにさせてくれる大切な友達です。四つ葉のクローバーは幸運を。てんとう虫の使いは、幸せを運ぶ。図案のタイトルも”Good Luck”天使や鳩、花束などの図案を刺そうかと思いましたが、二重に幸せの、この図案に決めました。彼女もとても喜んでくれて、私の気持ちも幸せに....。三重まるの一日でした。ところでこの図案、エレンさんという方が運営する海外の刺繍サイトで無料で提供されているものです。「EMS Cross Stitch Design」会員登録する必要がありますが、クリスマスやイースターなどの図案もあり、見ているだけでも楽しい気分になります。
January 19, 2006
-
心の畑
昨日は、一足飛びに春がきたのかと思うくらいの暖かさでした。街ゆく人々も、ショートコートやジャケットコートの人がほとんど。昨日の天気予報で、今日はまた寒くなると言っていました。バスを降りて歩きます。表通りを歩いてもよいのですが、住宅街をぬって行きます。どの地域にも高級住宅街というのは、存在するようで、私の街にも、そんな一角があります。(我が家はそこに含まれません...ははは(泣))私がそこを歩くのが好きなのは、お庭が素敵なお宅が多いから。今なら寒椿や蝋梅。木瓜の花なんかも咲いています。そして....木蓮のつぼみもありました。だいぶ大きくなっているように思いました。そんな花たちを見ながらの、頬にあたる風は昨年ほどの冷たさを感じないようです。寒暖計や計測器などの機械は、寒さの数値を示すのでしょうが、肌は、春の風と光を感じ取っているように思うのです。”一年のうちでも最も寒さの厳しい季節。 凍てつく大地の下で、春の準備が着実に進んでいるように 私たちの心の畑も、眠らせているわけにはいきません。 重い雪におおわれているようでも、 種子や球根はじっと芽吹きのときを待っています。”今日買った「婦人の友」二月号の扉に書いてありました。身体が春を感じとったなら、心の畑もそろそろ起こさなくては...。春になったら、何しよう??
January 16, 2006
-
お正月に思う
四段お重・二組分のおせち。お鍋いっぱいの黒豆。お雑煮の下ごしらえ。鰆に蛤、百合根にうなぎ。お菓子やみかん、大福茶。すき焼き肉まで買い込んで。什器、漆器を洗い、お鏡さんをしつらう。花を生け、お祝い箸に家族の名前。結婚してからずっと、お正月は主人の家で過ごしてきました。義母とふたり、大晦日の夜遅くまで、お正月の準備に追われていました。前日まで仕事をし、帰省という遠距離移動で主人の家にいく私にはその”準備”は最初、暮れの疲れた身にせまる”やっかいな仕事”でしかありませんでした。同じ時期に、結婚した友人達は、初日の出を見に行ったり、年変わりとともに初詣。旅行、デパートの初売り。出かけなくても、本を読む、テレビを見る。家庭を持てば、お正月の準備は多少はあれど、好きなことを好きなようにしている...。友達はみな、結婚する前の年末年始とさほど変わらないように思えました。「みんな楽しく自由にお正月を迎えるのに...なんで私だけ...」主人に文句を言ったこともありました。誰も味方がいないように思え、蒲団に旧姓の名前をつけて、私の味方はこの蒲団だけ、なんて言っていたこともありました。七年前に義母が、昨年義父が亡くなりました。今年も、主人の実家でお正月を迎えましたが、二人きりのお正月に、沢山の食べ物は、もう要りません。自由になりました。初日の出も、旅行も、買い物も、これからは、好きなことを好きなように、できるようになったのです。あれだけ焦がれた”楽しいお正月”を手にして、なぜか寂しいのは、贅沢でしょうか...。いつの間にか私は、この”やっかいな仕事”に楽しみと気概を見つけだしていました。好きになっていたのですね....。家族の為に、お正月をしつらう。心待ちにする家族。義父と義母の気持ちに、今頃、追いつきながら、墓前に手を合わせる、元日となりました。「でもさぁ、やっぱり今までで一番くつろいだ感じに、みえるけど?」「....。」主人からみると、そう見えるようです...(苦笑)
January 6, 2006
-
今年もよろしくお願いします
昨年「もくれん草紙」に訪れてくださった皆様、おつき合いくださって、ありがとうございました。喪中のため、お祝いの言葉は書けませんが、今年もまた、どうぞよろしくお願いいたします。 平成十八年一月 もくれん天使
January 1, 2006
-
三つのメニュー
鳥の唐揚げ(または、骨付き鳥もものロースト)フライドポテト色とりどりの野菜と玉子のサラダこの三つのメニューに、いくつかのオートブルやフルーツポンチ、和風な煮物に、お寿司を頼むことや、ピザを焼くこと...ある年は、どこからか習い覚えてきたおしゃれな西洋料理...。などなどが、その年の気分で加わり、我が家の(実家の)クリスマスのごちそうができあがります。子供のころから変わることのない、三つのメニューは、作るのも簡単、クリスマスでなくても作れるものばかり。鳥唐揚げはスパイシーなものではなく、砂糖醤油の和風味付け。フライドポテトは冷凍は使わず、必ず生のじゃがいもを使い二度揚げ。サラダはできるだけ色を華やかに、かるく塩をして青臭さをとり、玉子は必ず入れる。コツともいえない、普通の料理。普通の家の、普通のクリスマス。子供の私達は、それぞれに結婚をし、家族が増えても三つのメニューは変わらず登場し、毎年きちんと売り切れてくれます。そして最後に、女王様のお出ましのように、赤い苺のクリスマスケーキ。ロウソクを吹き消したら....。「ケーキ、どの部分が食べたい?」Merry Christmas!!
December 24, 2005
-
地雷復
「乃東生ず」(なつかれくさしょうず)今日の旧暦・七十二候です。夏至の「乃東枯れる」(なつかれくさかれる)と対をなす候です。(6/21の日記参照)今日は冬至。草木がいずれも枯れる、この冬のただなかに、夏枯草のみが緑の芽を出し始める...とあります。中国古典の一つに易経があります。易というと、筮竹じゃらじゃら...といった占いを思い浮かべてしまうものですが、一つの書物として読むと面白く、示唆に富んだ言葉が勉強になります。詳しく勉強した訳ではありませんが、64の卦からなる易経を読んでいて思うのは、人を含む森羅万象、そこには、何事にも絶対性は存在しないという希望が書かれているような気がするのです。冬至をあらわす卦。「地雷復」(ちらいふく)。大地の下で、かすかに春が鳴っています。遠雷のように。陰に極まった瞬間から陽に。寒い冬がずっと続くという絶対性は、そこにはありません。夏に枯れた草がほのかな緑を見せる。日差しが一日と長くなり始める。かぼちゃの甘煮に、柚子湯で、ちいさなちいさな音を立て始めた春をそっとお祝いしましょうか。
December 22, 2005
-
虹が架かるまで
「虹蔵れて見えず」(にじかくれてみえず)今日の旧暦・七十二候です。空に陽気なくなり、虹も見かけなくなる頃。旧暦四月中頃の「虹始めて見る」(にじはじめてあらわる)と対を成すものなのですが、今日から四月までは虹は架からないのかというと、実際はそうでもないようなのですね。一月ごろ(新暦)のキンと澄んだ空に架かることもままあるようなのです。俳句をなさる方ならご存じのようで、”冬の虹”という季語もあるようです。七十二候では、冬至まで「冬になっていくのね...ぽつん。」といったマフラーやセーターで体を包みたくなる、寒そうな感じの語句がつらなるようです。あつあつのお鍋にシチュー、おでんや鍋焼きうどん。バターのかけらを落としてココア。ホットミルクもおいしい。少し変わったところで、ホットカルピス。時々は甘酒なんかも(すこし苦手)いいかしら。....エトセトラ虹が架かるまで楽しみましょうか。
November 22, 2005
-
金盞花
「金盞香」(きんせんかさく、又は、きんせんこうばし)今日の旧暦・七十二候です。金盞は水仙の異名。”こうばし”というのは、花が開くとよい香りがしますね。水仙の花咲く様子をあらわしています。金盞銀台という、銀の台の上に金の杯が置かれているさまがこれもまた、水仙の花が咲く感じをあらわしているという中国の言葉もあります。中国の工芸茶(お湯の中で花開いたようになるお茶)にも金盞銀台と名のつくお茶があるとか...。(きっときれいなのでしょうね~。)春から夏に咲く「キンセンカ」は「金盞菊」といいやはり花の咲く姿が金杯のよう、というので付けられたようです。冬の気配がさらに強くなり、水仙の花も咲き出す時節ということなのですがわたしの感覚には、どうもピンときません。寒い冬を耐え越えて、雪どけの頃に咲く花。そこに健気さを見る花、といったおもむきだったのですが...。南のほうでは、もう咲いているのでしょうか。なんとなく、しっくりこない今日の七十二候です(笑)(勉強不足なのかしら...。)
November 17, 2005
-
「祝婚歌」
今日は、紀宮さまの結婚式でしたね。テレビでは、久しぶりの慶事に、祝賀のご様子を追って報道していました。また、街のそこここに、ひかえめながらもお祝いの垂れ幕などが掲げられ、胸ふさぐ事件の多い中、よいニュースと思いました。吉野 弘さんという方がお書きになった「祝婚歌」という詩があります。 二人が睦まじくいるためには 愚かでいるほうがいい 立派すぎないほうがいい ・ ・ 完璧なんて不自然なことだと うそぶいているほうがいい ・ ・ 立派でありたいとか 正しくありたいとかいう 無理な緊張には 色目を使わず ゆったり ゆたかに 光を浴びているほうがいい ・ ・ (童話屋刊・「二人がむつまじくいるためには」) ※詩篇は短いものなので、すべてを引用しませんでした。この詩に(この詩集に)出逢ったのは、一年くらい前のことです。いっぺんに好きになってしまい、結婚する方がいたら、贈る言葉にしようと思っていました。今日のメモワールとして、記しておこうと思います。「黒田慶樹さん、清子さん、ご結婚おめでとうございます。」
November 15, 2005
-
絵と陶器
招待券をいただいたので、東京都美術館で開催中の「プーシキン美術館展」に行ってきました。マティスの「金魚」があざやかな招待券です。きっと、パンフレットや電車の中吊り広告などで目にした方も多いのではと思います。絵の鑑賞が趣味というわけではありませんが、写真や本などの印刷では、感じ取れない絵のもつ雰囲気、色を見るのは楽しいことと、天井の高さからくるのでしょうか、美術館のもつ静謐な静けさが好きで、いそいそと出かけました。大混雑、でした。(溜息)それでも、これは見ておきたいなと思うものはむりむり前に出て、見てきました。(強引)モネやゴッホ、ピカソにゴーギャン、ルノワールとどれもこれも有名どころばかりでした。わたしが、これら”海外の油絵”を見て思うことはどのようなモチーフであっても、色使いが”明るい”ということです。絵を描く人は、たぶん知らず知らずに、民族性が反映された好む色、を選んでいるように思われてならないのです。先日、益子の陶器市に行ってきました。沢山のお店が並ぶ中、海外の作家さんのお店もちらほらとありました。益子焼きですから、民芸調で、すこし無骨な感じが持ち味です。ですが、海外の作家さんは、益子焼きでありながら、どことなく”テーブルウエア”という言葉が似合う。それが、不思議な持ち味となっていて面白いなと思ったのです。その時に使われていた水色が、日本の陶器には見られない水色だと感じました。その水色がありました。今日の絵画の中に。カラリとした水色。わたしは、絵も陶器も、なにかを語るなんて、知識もなにもない、素人。でも、なんとなくわかる気がするのです。絵を描くとき。陶器を造るとき。あの”明るい水色”を、日本のわたしは選ばないのだろう、と。きっと選べないのですね。交通網、電信機器の発達で、せまくなったと感じる世界。一幅の絵、陶器ひとつに、真似のできない民族性を感じ、尊重するとき。やっぱり、まだまだ世界は広いのだと、うれしくなります。
November 13, 2005
-
赤福
「地始めて凍る」(ちはじめてこおる)今日の旧暦・七十二候です。陽気も消え失せ、大地も凍りはじめる。五日前のさざんかといい、立冬を過ぎてから、景色は、兆しのように思える冬の支度を始めたようです。ここで言う”凍る”には、「水以外のものが」という但し書きがつくようです。水が凍り始めたら、本格的な冬...ということなのでしょう。さて、今日はうれしいお土産がありました。主人が関西方面にいくことがありましたので、頼んでいたのです。躑躅色の包装紙に包まれた、赤福。お伊勢参りのお土産として有名です。沢山の新種のお土産がある中、なぜ赤福?特にめずらしくもないのでは...といわれそうですが、わたしのお目当ては、その中に入っている”伊勢だより””伊勢だより”は、京都の版画家、故・徳力富吉郎が、実際に伊勢めぐりをしながら20年費やして完成させた400種ほどの木版画。裏には店主の文章が添えられています。文章の終わりには、その日の日付が記載されて、もし仮に、毎日買っても、一年間は違う栞がついてくる...。そしてそれは、製造年月日ともなり、赤福の新鮮さをも、あらわしています。付属のヘラで、こそげ取るようにお皿に分け、頬ばりながら、栞を観る。読む。八個入りのあんころ餅がくれた福々しい今日の一日です。
November 12, 2005
-
たき火
「山茶始めて開く」(つばきはじめてひらく)今日の旧暦・七十二候です。山茶は”つばき”と読みますが、さざんかのこと。山茶は、つばきの漢名です。♪さざんか、さざんか、咲いた道 たき火だ、たき火だ、落ち葉焚き... (童謡:「たき火」第二節)わたしが子供の頃は、お寺や畑、大きな農家の庭など、たき火をしている晩秋、初冬の風景がありました。農家のお友達の家に行くと、そのお家のお爺さんが、たき火でお芋を焼いてくれて、みんなで食べた思い出もあります。いまは本当に見られなくなりました。少なくとも町中では...。いま、たき火をしようもなのなら、「ダイオキシンの発生が...云々」と、お役所の人が飛んでくる。たなびく煙のゆくえ、火事の危険性から、近隣から苦情がくる。と、街のあり方、生活のあり方に、それは許されない状況になっています。今日、いつも通る道、マンションの植え込みにさざんかが一輪、咲いていました。楽しくて、おいしくて...身も心もあたたまった、たき火の思い出。白いさざんかが、思い出させてくれました。
November 7, 2005
-
お知らせ
いつも訪問してくださっている皆さん、ごめんなさい。風邪をひいたようなのですが、なかなか抜けきらず更新がままなりません。パソコンの画面がちょっとつらい感じです。もうすこしお休みしたいと思います。
November 1, 2005
-
おめでとう。
ロッテが優勝しましたね。31年ぶりとのこと。野球のことを、そんなに詳しくないわたしでも、いままでずっとがんばってきて、花開いたという感じが見てとれます。主人が大喜びです。ロッテ優勝のニュースや掲示板を見て、パソコンを占領。ようやく、わたしに解放となりました。今日のメモワールとして、記しておこうと思います。千葉ロッテマリーンズ、優勝おめでとう!!
October 26, 2005
-
掃除が先
日本では、台所やトイレなどの水場にも神様がいると考えますね。信仰という特別なことではなく、お正月には、小さな鏡餅やしめ縄を飾って、お世話になった一年の感謝をあらわす。そういった家庭が多いようにおもいます。煮立ったお湯をそのまま、流しに流すと病気になる。トイレ掃除を毎日すると安産になる...などなど。台所器具の傷みを防ぐ、出産に備えて足腰を鍛える、と、ちゃんと実生活に則した理由がありますが、神様が戒めているということで、言うほうもいいやすく、守るほうも守りやすいというよい方便になっています。ご親戚が神主さん、という友達がいます。その友達も、特別に信仰があるというわけではないのですが、伯父さんが言っていましたと、話してくれたことがあります。「皆、台所やトイレには神様がいるから、 きれいに掃除をしておかなくてはと、いうけれど、 そうではないのね。 掃除をして、きれいになったところに、神様はいらっしゃるの。 神様が先ではなくて、掃除が先。 汚くしていると、いなくなってしまうらしいのよ。」トイレのカバー類が、だいぶくたびれていたのできれいに掃除をして、用意していた新しいものと取り替えました。清々しくなった空間を見ながら、その話を思い出していました。帰ってきた主人が、「申し訳ない気がする」と言っていました(笑)神様がいらしてくれたようです...。
October 24, 2005
-
秋の色
「霜始めて降る」(しもはじめてふる)今日の旧暦・七十二候です。今日は二十四節気でも霜降です。字をみるがごとく、両方ともに同じ意味で、陰気深くなり、露は雪と化して草木の葉は黄変する...。秋深くなり、早朝には時に霜がおり、冬の到来が感じられてきます。自転車を買いました。二年前、自転車に乗り交通事故に遭ってから、(軽い膝の打撲ですんだのですが)乗るのが怖いという気持ちはなかったと、思うのですが、なんとなく遠ざけているといった感じで二年が過ぎていました。自転車に乗っていかなくてはならない距離に行ってみたいお店ができたことや、始めてみたいなと思っていることに、自転車が必要になってきたことが重なって、買うことに決めたのです。高級自転車を買うわけでもないのに、「フレームの形が...」などとあれこれ迷います。いちばん迷ったのが、色です。赤や紺が候補に上がり、今まで乗った色のことも考えましたが、家を出るときから、なんとなく決めていた白にしました。久しぶりに乗る、真新しい白い自転車と、天高く、青い空。映画のように、自転車に乗ってどこまでも渡っていけるよう。あとは、わたしの体力と自転車で行ける範囲に、紅葉の赤があったら、もう言うことないのですが...。なかなか、すべてはそろわないものですね(溜息)ともあれ、明日からの外出が楽しくなりそうです。
October 23, 2005
-
用の美
昨日買ってあった、「リンカラン」の11月号。今日の楽しみと、わくわくしながらページをめくりました。先日の「クウネル」もそうですが、”眺めつつ感じ取るように” 読んでいくのが楽しい雑誌だと思います。特集は、民芸についてでした。木にきつく巻き付き、その木を枯らしてしまう、ヤマブドウの蔓を取り除きそれを編み組細工で、籠に生まれ変わらせる。捨ててしまうような、とうもろこしの皮を、編んで作る、象牙色のスリッパ。戦争で未亡人となった女性達に、生きる糧と希望を与えようと生まれた毛織物.....などなど。長い年月をへて、工夫、改良を重ね、芸術の域にまで達するものばかりとなっている、民芸の多くは、生活に必要といったところから、始まっています。そこに暮らす人々の手から生まれる、とりどりの「用の美」は素朴でありながら、静謐な雰囲気さえ感じさせてくれます。リサイクルなんて言葉のない時代から、静かな声で教えてくれるリサイクルの精神です。
October 22, 2005
-
壁紙かえました
以前から、良い壁紙がないかしらと探しては試し、探しては試し、をしていました。「和な暮らし」というsioさんが運営するサイトに気に入ったものがあったので、張り替えてみました。タイトル部分との雰囲気を壊さず、うまくとけ込んでいるように思い気に入っています。この三日間、主人の出張があり、実家に帰っていました。父は、渡りに船とばかりでパソコン講習開始です。一日中画面に向かっているのに、夜は遅くまでテレビを見ている始末。(苦笑)なんでそんなに疲れないの、と思うくらいです。そんな訳で、今日は早めに休もうと思います。(弱音)
October 21, 2005
-
髪はいのち
「頭が硬いですね。」美容院での、頭皮マッサージの時のことです。カタイ? 考え方が柔軟ではないということ??などと考えていると、「ほら、頭蓋骨と頭皮がくっついて、あまり動きませんよ。」さらに、肩のマッサージの時も凝っているといわれました。肩こりは最近あまりないと思っていたので、話したら、「そうですね...肩すじというよりリンパの流れが悪いという感じですかね~」頭が凝っている、リンパの流れが悪いなんて、初めて言われたのでビックリしてしまいました。リンパの流れが悪いと、髪の艶やこしにも影響するとのこと。平安の昔、絵巻物にみるように、長い長い髪を大切にしてきた女性の姿があります。女性の髪には霊性があるなどとも言われました。(すこし怖いですが)髪を切るときは、出家し尼僧となる。それ以外は、年を重ね、老婆となろうともあまり切ることなく、髪を大切に長くしていたようです。ある日突然、髪を切りました、なんていえば、失恋?それとも、何かあった?と、今でも冗談で返す言葉があるくらいです。髪は女のいのち、と言う言葉。普段はあまり意識しませんが、(頭が硬い、なんて言われると(笑))大切にしていきたい言葉です。
October 19, 2005
-
虫愛ずる姫君
「蟋蟀戸にあり」(こおろぎとにあり)今日の旧暦・七十二候です。その昔、蟋蟀はキリギリスのことでした。万葉集などの歌集にもよく詠まれ、また、蒔絵や螺鈿の意匠として使われることもありました。秋の虫をあらわす総称として、蟋蟀は愛されていたようです。さて、蟋蟀というと思い出すお話をひとつ...。小さい頃のわたしは、蝉を採ったり、蝶々の鱗粉も平気、それどころか、箱いっぱいに蝉の殻を集めていて見つけた母が、青ざめ怒るといった(あたりまえですよねぇ...)まさに”虫愛ずる姫君”でした。ある秋の日、近くのお寺でこおろぎを見つけたわたしは、かわいいとでも思ったのでしょう。家に持ち帰り、小さなプラスチックの虫かごに、土と大きめの石をいれ、胡瓜の餌をいれると、満足して蓋を閉めました。夜になり、寝る頃になりました。何を思ったのか、虫かごを枕元に持ってきてご丁寧にもバスタオルをかけたのです。寒かったらいけないと、夜になると猫のハウスに毛布をかける祖母をまねたのです。小さかったわたしは、両親と同じ部屋に寝ていました。リリリリ、リリリリ....リリリリ、リリ...。真夜中、人の気配が消えたころ、枕元でこおろぎが鳴き始めました。遠くで聞けば心地よい虫の音も、枕元なら騒音です。翌日、怒りで青くなった母に「捨ててきなさい!!」と言われたのは、言うまでもありません。大人になると、子供がするように愛ずることは、苦手になります。和歌や俳句、絵や写真など、様々な方法を覚えそれを通じて、愛ずる気持ちをあらわしていきます。いま思い起こしても、蝉の殻やこおろぎが、なんでそんなによかったのか、解りませんが身近な命が造る不思議さ、美しさに魅せられたその気持ちは、子供のころから変わりなく、今こうして、移る季節を綴ることで、昇華しているのかもしれません。
October 18, 2005
-
おろしゆず
今年は秋になってから、雨の日が多いですねぇ。朝から、しとしと、うすら寒い月曜の朝に、少し気分も滅入りがちです。先週仕入れておいた、出始めの青いゆずを使っておろしゆずを作ることにしました。青ゆず(10個)の皮のみを、陶器のおろし器で、おろします。ごりごり...ごりごり...結構、力がいります。一個、二個と、おろすうちに、やがてボウルの中に、若緑、萌黄のふんわりとした、ゆずの香り山ができました。おろし終わったら、今度は青とうがらしを10本。内の種をとり、細かく細かくみじんに。今度は深緑の、辛い山。おろした同士を合わせて、和えて、小さなビンに詰め込みます。秋だというのに、小瓶の中は若葉織りなす春のよう。気分もすっかり、晴れてきました。このおろしゆず、焼き魚や煮物にふりかけていただきます。秋には少ない緑色、そして香りと辛みの組み合わせが、秋の味覚を一層ひきたててくれます。※ ところで、このおろしゆず、 作り方には、青とうがらしも陶器のおろし器でおろすとなっているのですが、 わたしは、どうしてもうまくおろせません。 それで、包丁を使ってしまうのですが、ほんとうは金気を使わない方が いいのだと思うのです。(金気は早く悪くなるように思います) どなたかうまくおろす方法をご存じでしたら、教えてくださいませ。
October 17, 2005
-
父の再挑戦
土曜、日曜と、父のパソコン講習の先生をしていました。一時期パソコンにトライしてみたものの、投げ出した父は、再挑戦と一念発起。パソコンも新しくあつらえ(というよりも古すぎて使いものには...笑)「短期間で覚えるのだ」と鼻息も荒く、一生懸命です。先生も、朝早くから呼び出されました。ふぅ。教えていると、父とわたしは似ているのね...と改めて実感します。新しいことを覚えていく時の方法や、何を寄り所にしようとしているのか、どのような場面を不安に思うのかなど、自分を見ているようです。「短期間で覚えるのだ」に見られるように、ある意味、力わざで世を渡ってきた父。教えていても、どちらが先生か分からなくなるときがありますが、新しいことを始めようとする人は、赤ちゃんが一所懸命、立とう、歩こうとしているような、かわいらしさと健気さがあって、応援しないわけには、いられません。さあ、わたしも何を始めましょうか...。
October 16, 2005
-
ブックカバーの周辺
ブックカバーについてのコメントに、お返事を書きながら、すてきなブックカバーを、かけてくれる書店は少ないな~と思いかえしていたところ、今日の朝日新聞・朝刊に、”進化中です、ブックカバー”という見出しが、目に飛び込んできました。早速、読んでみました。ブラジャケ(ブランドジャケットの略)という、企業とタイアップしたブックカバーが好評で書店の集客力向上や、来店動悸のひとつになっていることなど、(首都圏と関西の一部の書店においてあるそうです。)本を売る戦略のひとつとして、ブックカバーが注目されているのですね。確かにわたしも、ブックカバーが素敵だったりすると得したような気分になりますし、その書店の本に対する、強い心意気のようなものを、感じる気がして、またそこに行こうと思ってしまいます。読み進むうちに、出版社のHPなどでも、サービスとしてブックカバーのダウンロードプレゼントがあるとの記事にうきうきしながら、紹介されていた福音館書店のHPに行きました。福音館書店は子供の本で有名な出版社。かわいらしい、ブックカバーが手に入りました。印刷して、文庫にかけてみます。「.....明日、喫茶店にいこうかな~。」家で読めばいい本を、外で読みたくなりました。ブックカバー見ている人なんて、きっと誰もいないんですけど...ね。本を読み終われば、捨てられてしまうブックカバー。(捨てない人もいるのかな?)環境問題から、その是非を問う話もありますが、それは、またの機会に...。
October 14, 2005
-
婦人の友
「婦人の友」11月号を買いました。「婦人の友? 主婦の友ではなくて...?」と店員さんに聞かれてしまう時もあるこの雑誌ですが、創刊からじつに100年を越える息の長い雑誌です。わたし自身も、読み始めたのはここ2,3年。最近、スローライフ系の雑誌が流行っていますが、これは究極のスローライフ雑誌なのではと、思います。100年ということは、明治に創刊されたものなのですが今読んでも古いとは思えず、逆に新しく感じるように思います。(硬派な感じ、ではありますが...(笑))紹介されるお料理や家事のヒントも実用的で参考になること、しきりです。先日の”葡萄のアーモンドケーキ”も、実はこの雑誌に紹介されていたものでした。ここに登場する主婦の皆さんは、鏡といわれるくらいの方達ばかり。到底及ばない生活を、おくるわたしですが、毎月1回、気持ちを新たに毎日の生活を大切にしようとはげましてくれる雑誌です。
October 13, 2005
-
最後の節句
「菊の花開く」(きくのはなひらく)今日の旧暦・七十二候です。お正月から始まった五節句の、最後を飾るのは重陽の節句です。旧暦では一昨日になります。陽数(奇数)の最大が二つ重なるということで、菊酒を酌み交わし、栗ご飯をいただくことで、不老長寿を願う行事です。また「着せ綿」という、夜、菊の花に綿をかぶせ、その綿に染み込んだ夜露で顔をなでると、美貌をたもてるといった風習もあったそうです。良き伴侶に恵まれますように...(桃の節句)世に秀でる人となりますように...(端午の節句)など、五節句のひとつひとつに、昔の人は願ったものですが、ひとつひとつの行事は違っても、すべては”心身の健康を願う”という、我が子や家族への祈りの気持ちだったのではと思います。吉数と呼ばれる陽数が重なる月日に、お祝いするその心は世界の様々な風習がもたらされるようになった現代でも変わることはありません。健康でなくては、何事もかなうことはありませんものね。今流に言えば、”健康なくして、成長なし”...?(汗)
October 12, 2005
-
蜘蛛の糸
「筋トレ」という、わたしがよく行くHPがあります。「筋トレ」というと、身体を鍛えているのね、と言われそうですが(実際に、そういった人が検索でよく来られるようです...(笑))HPの冒頭に”星占い系テキストコンテンツサイト”と、うたわれているとおり、占星術のHPなのです。運営者の石井ゆかりさんの軽妙な言いまわしと、時に哲学を思わせる占いに引き込まれて、いつも楽しませていただいています。石井ゆかりさんのブログに「すなお」という気になる記事があったので、今日のブログに書こうと思います。どこかで読んだ話しなのですが、素直と言う字、素と直で、できています。素は、主と糸。”主(神)の糸が直に(じかに、ちょくに)、自分に降りてくる”と、考えるのだそうです。人を押しのけてまでもという自我の誇示や、人をおとしめて浮かび上がろうとする、その気持ちを越えて、人や自然の中で、生かされている自分を感じたとき、その糸は降りてくるのだそうです。そして、神の気持ちが直に伝わり、その人は自身の”働き”をするようになるというのです。ここでいう神とは、”自然や宇宙への畏敬の念”と、とらえていいと思います。偉業を成し遂げる人や、名を残す芸術家はきっと、この糸が降りてきている人達なのではと、思います。それは普通の人であっても、心地よく生きている人というのは、やはり、糸が降りてきているのではないでしょうか...。言い古された言葉かもしれませんが、”無心”とか”無我”というものなのかもしれません。そういえば、芥川龍之介の「蜘蛛の糸」。あれも、そんなお話でしたっけ...。
October 11, 2005
-
「丸善」京都河原町店
今日で京都の「丸善」が閉店しました。梶井基次郎さんの「檸檬」で有名な本屋さんです。(関連記事)わたしも、何度か足を運んだことがありました。丸善は、丸の内に新しく本店ができたことで今年の四月、日本橋本店も、書籍部門と洋品部門に分かれ、本の扱いは、店舗も小さく、場所は移動しています。それに続いての京都店の閉店でした。日本橋本店も、京都店も「舶来」という言葉が似合う本屋さんでした。「檸檬」が執筆されたころの丸善は知りませんが、人々の心に強く、舶来の匂いをいだかせる、憧れの本屋さんであったろうことは、想像に難くありません。舶来という言葉、今はあまり使われなくなりました。諸行無常、とはいいますが、”舶来品” が ”海外製品” に変わってしまうような、時代の変化は寂しく思います。丸善・京都店、移転してまた開業予定とのこと。舶来品の面影を、残して欲しいとねがいます。
October 10, 2005
全75件 (75件中 1-50件目)
-
-

- 私なりのインテリア/節約/収納術
- クリスマスの飾りつけ キャンドルス…
- (2025-11-26 07:39:45)
-
-
-
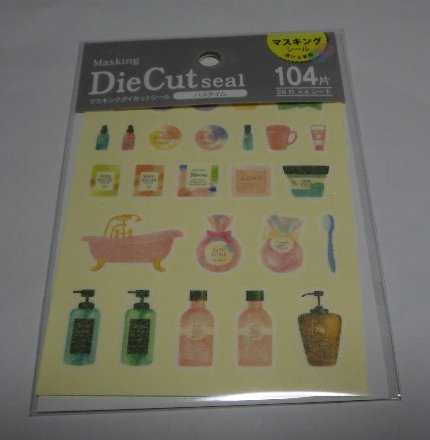
- 100円ショップ
- マスキングダイカットシール バスタ…
- (2025-11-27 01:27:34)
-