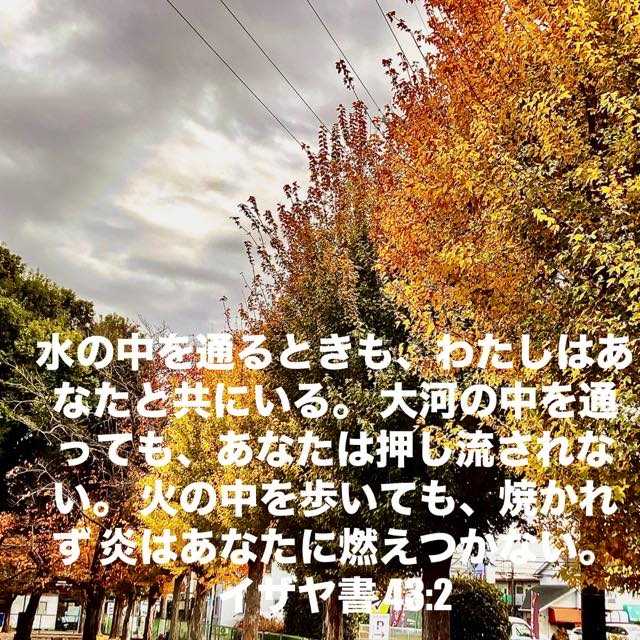2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2007年03月の記事
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-
涙の卒業式 2007.3.22
涙の卒業式......といっても、泣けたのは私。卒業してしまった息子は、嫌な奴と離れられて、サバサバしている様子。 とにかく今日で、小学校ともお別れなのだ。 朝の9時半に、ちょうど間に合って体育館に行くと、5分ほどして「第27回卒業式を始めます」の声と共に、卒業生がエルガーの「威風堂々」の曲をBGM に入場。 あの曲を聴くと、「ああ、卒業式なんだなぁ」とジ~ンとくるんである。 5年生たちの代表の子たちが挨拶を述べたり、「校歌」や「卒業生を送る歌」を歌う。 6年生たちが、今度は小学校の思い出を順番に語る。 ここはまだ子供なので、ひとりの代表がスピーチをするのは難しい。 女の子「まだ暑い夏の終わり」 男の子「みんなで組み体操に取り組んだ」 女の子「練習は苦しかったけれど」 うちの子「みんなの心がひとつになった」 ......という具合である。 その後、卒業生全員が、歌を数曲歌った。 その前に、校長先生がお話をされた。 「この世で一番硬いもの、それはダイアモンドです。このダイアモンドを磨くのは何だと思いますか?それはやっぱりダイアモンドなのです。ダイアモンド同士が磨き合って、あのような美しい輝きが生まれるのです。人間も同じです。人は、人によってのみ、磨かれ、成長することができるのです。これからも、友だちとの出会い、先生との触れあいや人間関係を大事に、切磋琢磨されながら、大きく歩んでいって下さい」 私は、「うちの子は、6年になって、いじめにあったから、人間関係ということに、あまり信頼をおけなくなっているかもしれないな」と思ったが、やっぱり、この校長先生のお言葉にはじ~んときた。 お話を聴きながら、「第27回卒業式」と書かれたプログラムの表紙に目を落とした。 表紙には、息子が6年間せっせと通った、急な坂道の上、山の上にある小学校の建物が描かれている。 その絵を見ていると、とたんに涙がじわ~っと滲んできた。 私は、「アトピーを治すために、家から近くて安全な、山の上の小学校」を探そうと、6年前一生懸命だった。 その時の辛い、大変な気持ちを思い出したのだった。 「この坂道を登って......ここがこれから通う小学校になるのかな」 住んだこともない、山の上。 とても不安だった。 運動会、授業参観、その度に通ったこの山の坂道...... それらが今は懐かしく、もうこの坂道を通ることはないのだと思い、泣けてしまったのである。 息子は、卒業式の後、校門の前で写真を撮らせてくれたが、どうも元気がない。 それまで毎日、朝から午後の3時過ぎまで、超スパルタ式で、卒業式の練習をしてきたからかもしれない。 「卒業証書を受け取った後、みんなの前を向いて、決意表明を言ったでしょ。ちょっと声に元気がなかったね」 「しんどかったから......」 息子の「決意表明」(=将来の夢)は、「将来は、人の役に立つ仕事をしたいと思います」だった。 「あの決意表明はさ、先生が『何か言え』って言うから、むりやり『言わされた』んだよ」 子供は、何かというと、大人から「...させられた」と言う。要するに自分の意志ではない、ということだ。 それでも、少しは息子が自分で考えた言葉なのだから、「人の役に立つ仕事をしたい」というのは、本音なのだろうと思う。 「人の役に立つ仕事...って、どんなことをしたいの?」 「ん~まだ分からん。お医者かな」 「ああ、なるほど。確かにお医者に向いてはいるよ」 「でも...お医者じゃなくてもいいや...も~まだ分からん。僕に何になってほしい?そっちで決めて」 「親が決めて、『これこれになれ』なんて押し付けたくないよ。でも、じゃあ学校の先生は?」 「あ~先生か...でも、生徒が暴れたり、いろいろと学校は問題があるんだし...大変そう」 要するに、息子の「夢」というのは、まだ漠然としているんである。 それでも、「人の役に立つ」「友だちの気持ちを大事にする」などの心はしっかりと根付いている。 具体的には、美術関係の仕事に興味がありそうなのだが...... ところで、中学の入学式は4月11日。それまでは、「まだ小学生ってことだよね~♪」と、春休みを満喫するつもりだった。 でも、卒業式に、今まで風邪やインフルエンザで休んでいた子たちが、無理して出てきたので、病気をうつされてしまった。 それで、卒業式の後は元気がなかった。 翌日からは、ぐた~っと寝込んでしまった。 ちょっと残念な春休みになってしまったんであった。
March 22, 2007
コメント(0)
-
比較する心理 2007.3.20
子供が小学校最後の通知表を持って帰って来た。今日は終業式だった。そしてあさってが卒業式。 息子が小学校に入ってからの通知表は、私が小学生の頃と違う。成績を、無味乾燥にA, B, C などとつけない。 国語なら、「文字をていねいに書く」「文章を読み取る力がある」「文章を書く力がある」...など、内容がきめ細かい。 そして、それらに応じて、「たいへんよくがんばりました」(昔でいうならA)、「よくがんばりました」(B)、「もう少しがんばりましょう」(C)という所に先生の○が各々付けられる。 通知表をこの学校では『あゆみ』と呼ぶ。 裏には、「『あゆみ』は、その学期で、お子様がどんな成績をとったか、を重視するのではなく、どんなことに力を入れたか、そういった点にぜひ注目して頂くためのものです。お子様が頑張ったことがらを、どうか励まして、次の段階に自信を持って進んでいけるよう話して下さい」...と書いてある。 学歴社会が過熱して、子供の心が歪み、不良が増え、大人になってもその傷が残り、また、成績ばかりを重視した結果、「生きる力」がなくなり、人との競争心だけが剥き出しになる、そういう社会になってきたのが、1980年代じゃなかったか...と思う。 それで、「小学校のうちから、その子供ひとりひとりの努力を大切に、個性を大切に」という意味合いで、通知表の内容も改められたのだろう。 それでも、名称は「通知表」「通信簿」から「あゆみ」になったところで、子供にとっては、それは、やっぱり「通信簿」「成績表」に変わりはない。 どうしても、「たいへんよくがんばりました」がいくつあったか......友だちの誰々と比べて、多かっただの、少なかっただの、そういう話題になる。 教室では、「あゆみ」を渡された後、日頃嫌な子が近寄ってきて、「な~『たいへんよくできました』って、お前いくつあったん?」と訊いて来たそうだ。 息子は、「お前のも見せろよ」と言ったが、敵は息子の分だけ見て、後は逃走。 背後から、息子はそのでかい敵の体にのしかかり、敵が「わぁぁ~っ!ぐるじぃ~」ともがいている間、そいつが持っていた「あゆみ」を取り上げ、敵の背中の上で、とっくりと拝見させてもらったそうだ。 「あいつ、『平方cm』を『センチ2』、『立法cm』を『センチ3』 なんて言うくせに、『たいへんよくがんばりました』が、3個もあった」......との結果報告が私にあった。 また、これまた別のいじめっ子の「あゆみ」を、その日は向こうから見せてくれるという奇特なことがあったらしい。 その子は、掛け算がまだよくできない。 「なぁ、5×9って何?」「7×8って何なん?教えて」... 小学6年にもなって、「5×9って何?」だなんて、ほとんどギャグの世界ではないか。 息子は、その子に「5×9?36」とでたらめを言うと、「嘘やろ」と来る。 「そんなら、それくらい自分で考えろ」と息子が言うと、相手は「ホンマ、お前ってジコチュウやな」と憤るらしい。 その子の「あゆみ」は、「あんなに勉強できないのに、『たいへんよくがんばりました』が1つあった。あんな奴に1つあること自体、信じられない。あとは、『もう少しがんばりましょう』がズダダダダダダダダ~ッとあった」...... そう息子は笑って報告した。 肝心の息子の「あゆみ」は、「たいへんよくがんばりました」は5つ。その中で、算数が2つ。「図形や量を理解する」「計算の力がある」というところである。 その他は、理科が1つ。「自然や生き物をよく観察できる」。また、保健で、1つ。「人間の体の仕組みをよく理解できる」。 もうひとつは、図工で、「創造的な絵画・作品を作ることができる」―となっていた。 私は、子供が、「創造的な作品を作る力がある」と評価されたことが嬉しかった。 これが、他の理科や保健の評価と共に、この子の個性なのだと思った。 だが、息子の一番の友だち(息子に言わせると、「ただのゲーム友だちで、親友じゃない」子)は、私学を受験し、某私立大の付属中学に合格した。 その子は、ずーっと、3年生の頃から塾に通い、今では、高校の数学だって余裕で解ける...そうである。 体つきは、息子よりもがっしりしていて、少し背も高い。 でも、月齢は幼く、今月17日で、やっと12歳になったばかり。声も、話し方も、息子より幼い。 息子は、その子の成績のことをよく話す。 「皆が20分かかって、解く算数や国語の問題でも、あの人は5分ですらすら...なんだよ。もう、頭の中、ど~なってんのって言いたい。人間コンピューターなんだよね」 それで、「あの人は、『たいへんよくできました』が、ズダダダダダダダダダダァ~ッと並んでる人なの。『よくできました』なんて1つもなし」......などと、自分とその子とを比較する。 人間は、どうしても、他の人と自分を比較する心が抜けない。 けれども、私は、Aに値する成績がいくつあったか、その数は、あまり問題にならないと思う。 むしろ、「創造性」「自然観察」「人体の仕組みの理解」などに○がついている...そっちの方が大事だ。 それらが評価されて、初めて、その子なりの、世界にひとつしかない個性というものが活きてくる。 私は、そう息子に話したかったが、話しかけたところで、その「エリート」と呼ばれる友達が遊びに来てしまった。 また、折りを見て、「自分の個性を大事にね」と話したいと思う。
March 20, 2007
コメント(0)
-
小学校もあと四日 2007.3.15
今日は3月15日。卒業シーズン到来である。 昔、私の大学は、卒業式は決まって3月15日だった。(私は、短大卒業~大学卒業~大学院卒業と、卒業式を3回も経験したので、女の子の学歴に世間が冷ややかだった昔、自分でも、「卒業式のオバケ」などと思い、自分にウンザリしていた。) ところで、うちの息子も、初めての卒業式は、もう来週の木曜日である。 来週までには、土・日以外に、水曜日の春分の日...... 3日間の休みがあるので、もう小学校に登校するのは後わずか4日だけ。 もう宿題もない。明日から午前中だけ。 小学校での学習、特に5,6年の算数・国語(漢字)などは、万全とはいっていない様子だが、ほぼ7・5割はクリアーしているようだ。 「春休みは、6年の漢字と計算の復習をする」と言っている。 けれども、いじめや嫌がらせにあいながら、根気よく通った6年のクラスも、もう終わり...... その解放感は、親の私もよく分かる。 昨日から、私は「これ面白いよ」と言って、大和和紀のラブコメ 『N.Y. 小町』 を勧めたところ、息子は「笑える」と言って、夢中で読んでいる。 「男として育てられた16歳の娘、志乃が明治維新直後の東京とニューヨークを舞台に展開するコメディ」なのだが、「真面目で美人なのに、突然変なことを言ったりしたりするし、男言葉だ」というせいか、少女漫画でも、息子は面白がって読んでいる。 そうしてリラックスしている息子に、「小学校の復習をしなさいよ」などと、野暮なことはいいたくない。 勉強は、彼がやる気になっている時に勧めるようにしている。 普段でも、外出時に、同じクラスの子が同じマンションに住んでいるケースが多いため、人目を気にする息子である。 卒業式も、「卒業式の後、校門の所で、卒業証書を持ったところを写真に撮りたい」と言ったら、「ダメ」と断られた。 「写真を撮っているところを、他の奴らに見られたくない」と言うんである。 「でも小学校の卒業式は、一生に一度なのに...」 「じゃあ、卒業式が終わった別の日に、誰もいない時に、校門の前で撮るならいい」となった。 卒業すれば、6年で一緒だった嫌な子たちともお別れだから、いいではないか、と思うのだが、中学に入れば、また嫌な子たちが一緒に入ってくる。 けれども、別の小学校からも新1年生が入ってくる。 その中に、親友ができればなあ...... 不安と期待が入り混じる時期なんである。
March 15, 2007
コメント(0)
-
このブログは日記か小説か英語学習か? 2007.3.7
2005年の7月に、このHP (その時はBlog とは言わなかった)を開設した。当初の目的は、「英語学習のためのノウハウ伝授&学習ツールのご紹介&(読解力向上のための)英文掲載」だった。 そのテーマは、未だに変わっていないのだが...... 英語に関わるHP を作成することで、英語学習に迷いを感ずる人々のお手伝いをすると同時に、自分の勉強にもなる。 ずっと続ければ、人生日々の目標ができて、老齢になっても、「ボケ防止」になるんではないか、などと考えたりした結果、作り始めたこのHP...... でも、2005年の秋頃、病気をして、大学の仕事などにトラブルが生じた。そうなると、な~んとなく、仕事に使うテキストを見るのが、辛くなる。 それでも、「仕事は仕事」と割り切っていた。それで、英語が嫌いになったわけではない。 ところが、2005年の12月、何か音楽を聴いていた私は、急に、昔から書いていた物語を、一挙に「小説」として、HP に掲載しようと思い立った。 それで、英語学習のページは「工事中」(今もだな~)のまま、小説を書くことに突入してしまったんである。 もともと、音楽好きの私は、音楽で何か、文章を書きたくなる、という傾向がある。 大学も、院も、論文を書く時は、フィル・コリンズとかティアーズ・フォー・フィアーズ(Tears for Fears)なんかのロックを聴きながら書いていた。 その後、日本語で研究論文を2,3本書いたのだが、その時も、やっぱりBritish Rock を聴きながら、である。 なぜか、ノリのいい曲を聴かないと、文章が前に進まない。それに、ノリのいい曲を聴いてると、研究対象の「英国詩」のイメージが、より vivid になってくるんである。 (論文、書くのに、「プロ野球巨人戦」の放送を聴きながら書いた、という後輩がいたなぁ......) その後、小説を書くうち、「あっそうだ。これを英訳してみよう」などと思い立った。 小説には、台詞の部分や、情景・人物・心理描写などが織り込まれる。それらを英訳することは、勉強になるし、けっこう面白いんじゃないか~? ......そう思ったわけなんである。でも、どうしても、原文の日本語の小説の方が先に進んでしまう。 しかし、体調の良い時は、「そろそろ英訳もしてみよう」と思う。やってみると、やっぱり面白い。(図々しいのだが、英訳する以上は、外国の方が読んでも分かるように、ちゃんとした英語で......というのを心がけているんである。) そういうわけで、このブログは、記事の分量としては、「小説」「日記」「英語学習記事」の順番になってしまった。 2006年、薬害ショックで死にかけた後は、またまた大学との仕事でトラブル。しばらく英語のテキストは見るのも嫌になった時期が続いた。 それでも、今でも英語は、もう20年以上何だかんだと付き合っているので、やっぱり理屈抜きに好きである。 ところで、小説をもっと大きい字で、livedoor Blog に掲載しているのだが、これは(前にも書きましたが)、お話の最初の部分を読もうとすると、作者の私でも、至難の技?である。 それでも、よーく調べたら、こうなっていた。 まず、掲載した小説の部分は、「新着記事」として、画面の左サイドバーに並ぶ。 それが、話の古い部分は下に、新しい部分は上に......となっているので、上から下へ、「★第12部」第○○章~「★第11部」第○○章...となってしまう。 また、小説の前の部分はどうなっていたっけ?と確認したい場合......画面の一番下まで進むと、「前の記事」という部分があるので、そこをクリックすると、前のお話が表示される。 しかし、小説の冒頭に辿り着くのが、またまた「?」の連続。結局、画面の一番下「前の記事」をクリックするしかない。(笑) こんな調子で、作者自身が「これ読みにくいじゃないのよさ。投稿する順番、変えなきゃ(汗)」なんて思っているわけなのだが、一時、「小説Blog Ranking」で300位にまで落ちこんでいたのが、本日は、177位にup していた。 どこかで読んで下さっている方々に、感謝申し上げます。(今、一番、必死になっている読者は、私の分かる範囲では、私の母です。小説の舞台となる地名、人物関係をメモりながら、読んでおります。) あと、Seesaa(シーサー)Blog にも、小説を分離・掲載(というか、投稿)している。 こちらは、小説をもっと大きく、1、2、3......と分けつつ掲載。行間を1行ずつ空けて、読みやすいようにと思ったのだが、Seesaa のは、字と字がくっつく傾向にある。 だから、かえって読みにくかったりする。(苦笑) こちらのBlog では、お話の順番は、「新着記事」は右サイドバーにあり、一応、上から下に読めるように投稿が反映されるようだ。 また、その右サイドから、例えば「第38章」をクリックすると、小説の文章の上部に、小さく「第39章」ーTOPー「第37章」と表示されるので、前後の話の流れを確認するには便利である。 このSeesaa という会社のBlog サービスは、投稿する記事の分量に制限がないので、たくさん書きたいものがある人にはうってつけなのではないかと思う。 (これは、子供の「ドラクエ裏技攻略掲示板」の作成者が、Seesaa を利用していることで知ったのですが......) しかし、何のかんの言っても、まずはこの「楽天Blog」の方を大事にしていかねば......と思っている。 (長々と小説のことを書きましたが......できましたらこちらもお付き合い下さいませ。)
March 7, 2007
コメント(0)
-
ダニエル・ラドクリフにショック 2007.3.6
今日、海外のネットニュースに、「英国俳優のD. ラドクリフさん 全裸で舞台に」という見出しがあった。 ダニエル・ラドクリフ......あの「ハリー・ポッター」の看板俳優。今17歳。記事の写真は、上演中の彼の上半身が写っていた。 髪も、あの「ハリー」とは違って、金髪で短く切った、ロンドンの今風の若者スタイル。 「......ち、違う人みたい......それに舞台でヌード?」 映画とは違って、舞台だから、いつでもライブ。 舞台のストーリーや演出の上で、ヌードになる必然性もあったのだろう。 「勇気があるなぁ~」 果たして、ラドクリフの the nude が舞台芸術になり得たか否かは、これは観た人により判断が任される。 (ちなみに、「芸術」 art を意識しない場合の「ヌード」は、英語では、be completely naked というんだそうである。) ルネサンスの昔、(今はバチカン市国内の)システィーナ礼拝堂の天井画をローマから依頼されたミケランジェロは、聖書のエピソードを基に、自由自在に人物像を描いた。 いつも天井を向いて絵を描いていたので、その大事業が終わった後も、しばらく、首を下に下ろすことができなくなったそうである。 ミケランジェロは、彫刻家でもあったので、人間のありのままの「裸体美」を、油絵で立体的に描こうと苦心した。 それで、現在のような、素晴らしい礼拝堂天井画が完成した。 けれども、その礼拝堂が落成し、天井画が一般公開された時、当時のルネサンス時代の人々は眉をひそめたそうである。 「神聖な礼拝堂に、よりによって、人間の裸体を描くなんて!」 非難ゴウゴウの中、ミケランジェロは仕方なく、腰の周りに衣服を描いたとかいう話も読んだ覚えがある。 それでも、フィレンツェなどで、ミケランジェロなど、中世の巨匠たちの彫刻が、街中に溢れているわけなのだが、それらは衣服をまとった人物像ではない場合が多い。 たいていの人は、「優れた芸術だな」と感じる。 だが、子供は違う。イタリアでも、そういう彫刻を見て、小学生は、「なんでこの人、裸なの~?」と笑うそうだ。 人間のありのままの姿、その曲線美やバランス、立体感や影を研究し、理想を高めて、ひとつの絵画や彫刻として完成した場合、それが「芸術」となる。 でも、人間のありのままの姿を、ただ「情欲の対象」として眺めた場合、それらはただの淫乱な「画像」と堕す。 人間の姿というのは、危ういところで線が引かれていると思えてくる。難しい問題かもしれない。 最近は、小学生から、インターネットを自由に検索することができる時代。 私の息子も、(今は冷めたけれど)DS の「動物の森」の情報掲示板や、今熱中している「ドラクエ」の裏技情報掲示板などを検索する。 それでも、息子が「ドラクエ」を検索したら、なぜか、どど~んと「アダルトサイト」(これを今小学生たちは「エロサイト」と呼ぶ)が表示されてしまうらしい。 もう、言葉では表現するのがはばかられるほどの、淫乱かつ変態的「動画」がネット上、はびこっていて、それを、小学生が見てしまう...... 今は、そういう時代なのだ。 そう割り切ってもいられないほど、本当に「健全な青少年育成」の障害となるぐらい、「困ったサイト」が氾濫している。 「健全な」というのは、「年齢に見合った情緒を育む」という意味があるのだと思う。 でも、「困った世の中だなぁ」と思っていたこの私が、冒頭の、「ラドクリフの the nude」という記事を見ている時、息子が学校から帰ってきてしまった。 息子は、この記事を見て、意味がイマイチ分からなかった。仕方なく、私は説明した。 「あのね、あのラドクリフがね、『ハリー・ポッター』 とは別の、演劇の舞台でね、何も着ないで演技したんだって」 「えっ......何も?全部着ないで?」 「そうなの~(汗)お風呂に入る時と同じ格好でね」 息子には、これは相当なショックだったらしい。 普段から、「エロサイトがまた出た。気持ち悪い」と言っては、すぐに画面を消していた彼。 よく学校から来る「不審者(最近は露出狂が圧倒的に多い)のお知らせ」に、笑いながらも、気味悪がっている12歳の彼。 「ラドクリフは、変な目的で、服を脱いだんじゃないよ」 こう言っても、息子はショックを隠せない。 「でもさ......そんなことをする人だったなんて......」 息子は、「ハリー・ポッター」の第五作が映画化されるのを楽しみにしていたのだが、「も~う、観たくない」と言いだした。 あんなに「ハリー・ポッター」のファンだったのに...... そう思うと、私はとても残念な気持ちになってしまった。今は、息子は、「性」というものに、微妙な感覚と関心が芽生えつつある。 それだけに、こういう類いのものには注意が必要なのだった。 本当に、ネットの記事は、不用意に、子供の前で見たりするもんじゃないな、と猛反省したんであった。
March 6, 2007
コメント(0)
全5件 (5件中 1-5件目)
1