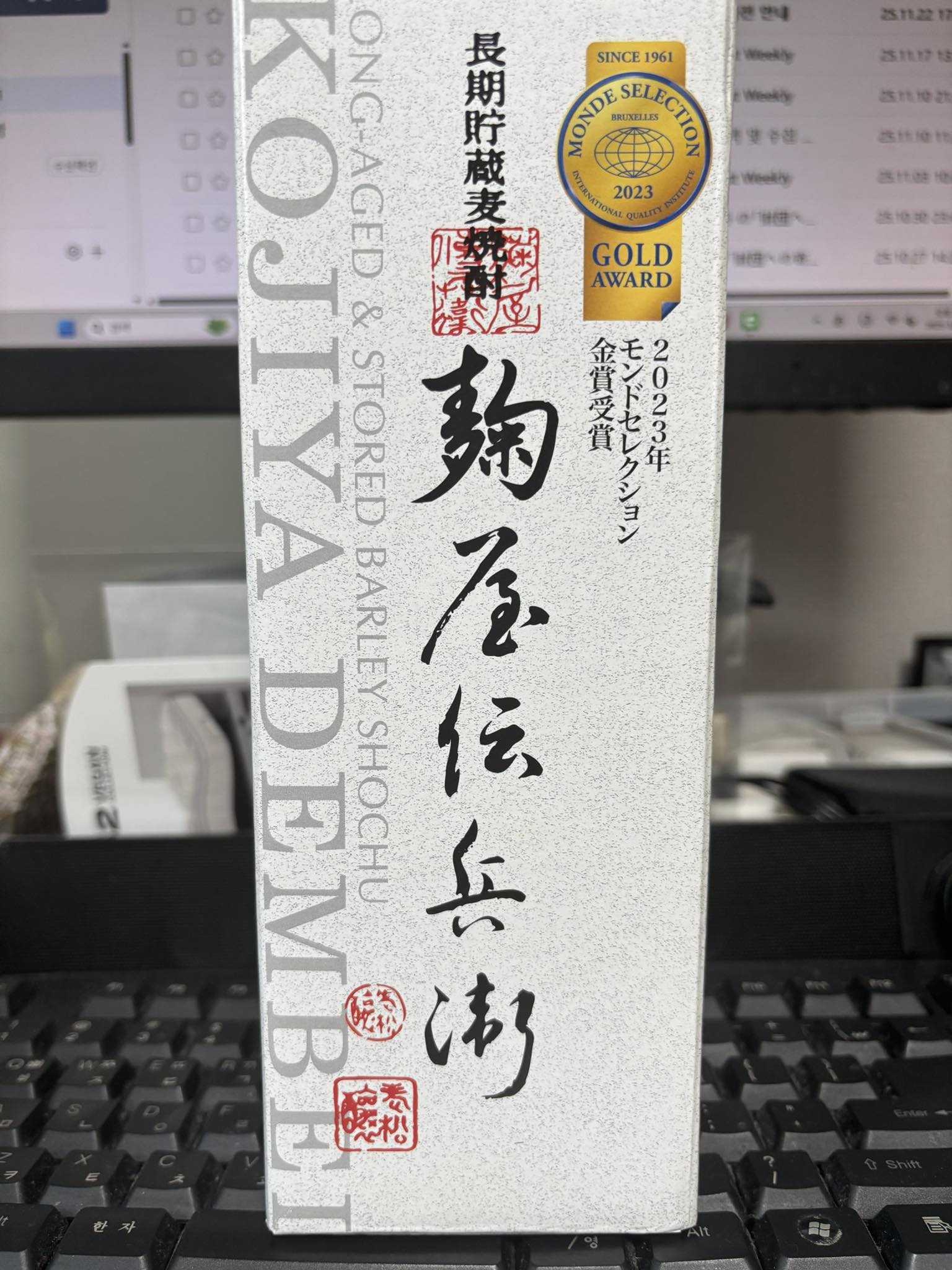2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2008年04月の記事
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-
滑川「食の匠」のホタルイカ料理
食育研究会の今年度の新事業は、「食の匠」に学ぶ伝承料理。県内にたくさんいる「食の匠」の伝統食の知識を、料理教室という形で披露していただくほかに、インタビューなどで伝統食の記録も残していきます。 その第一弾が「食の匠に学ぶほたるいかと甘エビの料理」! 5月17日に開催です。 そのための試作・試食会を滑川で行いました。 教えてくださる匠は、倉本禮子さん。漁協婦人部でホタルイカ料理の普及につとめています。 ホタルイカのゆで方一つからして、技がある!ぷっくりとゆであがったホタルイカは、まとめておかないで一匹一匹並べておくと、色が変わらないのだそうです! ホタルイカのお刺身をつくるには、まず足を取る、目玉を取る、内臓をとる、卵を絞り出す、軟骨を抜くという工程できれいにしていきます。 こうすろと、内臓でおいしい塩辛ができるし、ホタルイカの卵料理もできるんです。「捨てるところがほとんどない」エコ料理になります。 素材を大切にする匠の姿勢に、感激のあまり泣く貴代美ちゃん・・・ こうして作ったお刺身から、ホタルイカの寿司をつくります。 塩辛もほんとうにおいしい!!! 滑川では「ホタルイカ観光船」が始まっていますが、倉本さんはそのチケット売りの仕事を午前1時~2時くらいにやってから、4時頃ホタルイカを仕入れに行き、寝ないでこの試作にきてくれました。 ほんとうにホタルイカを大事にしている姿は、感動ものです! ぜひぜひお時間のあるかた、17日の料理教室に参加してくださいね! 「食の匠にまなぶホタルイカと甘エビの料理」 ほたるいかと甘エビを使った伝承料理、そして新しい料理などをとり混ぜて春の献立に仕上げました。 匠のお人柄に触れ、郷土、そして食に対する思いを聞き、その土地の風を感じながら、楽しく料理をして、いただきましょう。 きっとお腹だけではなく、心も温かさで一杯になることでしょう。 どなたでも気軽にご参加ください。 指導:倉本禮子さん(富山県認定、とやま食の匠、滑川市在住) 日時:平成20年5月17日(土) 10:30~13:30(実習とお話) 場所:富山県民会館6F調理室 献立 ほたるいか春のもてなし寿し ほたるいかからし酢みそ ほたるいか塩辛 おからのマッシュサラダ エビのすまし汁 定員 : 30名(先着順) 参加費 : 3000円 持参していただくもの:エプロン、三角巾、手ぬぐい、筆記用具等 お申し込み、問い合わせ 電話=牧野 090-2122-3803 ファクシミリ=澤井 076-435-5625 メール=toyamaitadakimasu@yahoo.co.jp 主催:「食育研究会 いただきます!」 ↓ http://toyamasyokuiku.web5.jp/
2008年04月30日
コメント(4)
-

「写真家といくとなみチューリップフェア2008」
4月24日、「写真家といくとなみチューリップフェア2008」のイベントを開催しました。このところ、毎日いい天気だったのに、この日に限って雨!でも雨天催行です。となみチューリップフェアは450種、100万本ものチューリップがみられるとあって、毎年、多くのお客さまの訪れるイベントで、とくにゴールデンウィークは、花も見頃にになってたくさんのお客様で道も渋滞します。そこで、一足早くすいている平日に撮影会を・・・と企画いたしました。富山市在住の写真家、大志摩洋一さんが講師として同行、花の写真の撮り方などのアドバイスをいただきます。「雨だからとがっかりしないで、雨だからこそとれる写真を撮りましょう」という大志摩先生。雨だから撮れる写真とは、「水滴のついたしっとりした花のアップ」そうです、好天では撮れないような趣ある写真が撮れるのは、雨だからこそ!いくつかアドバイスをもらってから、午前中はおのおの、カメラを手に撮影です。寒かったけど皆様思い思いの写真を撮ってきたようです。昼食会場の「山の手倶楽部」に移動し、プロジェクターを使いながら、大志摩先生からいくつかのアドバイスをいただきました。光を前から当てる場合、横からあてるばあい、逆光の場合では写り方がどのように違うかなどの実例をご紹介いただきました。参加してくださったお客様は、写真は好きだけれどあまりカメラは得意でないという方が多く、参考になったことも多そうです。またカメラ好きのお客様も「自分のいつもとるものとは違うものが撮れた」と喜んでくださいました。参加者の写真の講評もする予定でしたが、PCの不調で断念。次回はPCの予備も用意しておきますね大志摩先生といく、撮影と写真講座のツアーは、これからも開催していく予定です!
2008年04月24日
コメント(6)
-

梨の花、満開です!
うちの目の前にある「呉羽山」の、向こう側が梨畑。今が梨の花の全盛期でとてもきれいです! このほど、この呉羽梨のオーナー(1本)になりました!で、いまの季節は、実をならせるための「授粉」をやらなくてはなりません。この土日の作業でしたが、土曜日は天気がよかったにもかかわらず、花が濡れているということで日曜日に、やりました! 天気もよく、気持のいい~!青空。 梨は「幸水」なのですが、ほかの種類の花粉をつけてやらなくてはならないそうです。 ピンクに着色した花粉をもらって、「梵天」でつける! ふわふわたしたものです。「耳かきのほわほわでいいですよ~」ということですが、呉羽梨の生産者、カンナさんに借りてきた本当の梵天でつけます。 ほっといたら何千個も実がつきそうなくらいに、梨の花が咲いていますが、大きくするには、花も実もセレクトしてへらしていかなくちゃなりません~もったいない!でももったいないと思っていたら実がならない~! 泣く泣く、摘花してました。今日の作業は1時間くらいでした。 5月末くらいから、ついた実を選んで落としていく作業をやるそうです。それがまたもったいないらしいです(笑) 今日はいいお天気だったので、本職の農家の人も作業してました。 農家の人が使うのは「電動交配機ラブタッチ」というマシンです。 電動の羽から花粉が出てくる・・・ネーミングがおかしいです。
2008年04月21日
コメント(6)
-
かきやま工場見学
富山では、おかき・あられのことを「かきやま」っていうのだそうです。 南砺市(福光)にあるかきやまのメーカー、「日の出屋製菓」の「ささら屋まつり」に行ってきました! 「ささら屋」というのは通販のブランド名だそうで・・・ 「ささら屋まつり」は金土日の3日間の開催。試食販売やテントでの農産品販売などなどのイベントで、初日の18日だけ工場見学があるんです。初日の初回を予約し行く! 朝9時半には現地到着。いろんなおかきが売っているし、モチの試食もやってる。さっそく、買う!(笑) こちらの工場では、富山県産の「新大正もち米」を100%使ってモチをつき、その餅を冷却、裁断、乾燥させてじっくり焼いて、味をつけて製品にしています!ふつうは、モチ米ではなく餅の粉末で作るところが多いそうです。餅をついてからできあがるまでに1週間から10日ほどかかるという手の掛け方!のりや昆布、しょうゆなどの材料もすべて国産です。 おいしいのも納得! 工場内は撮影不可でしたが、どの工程もみることができました。ついた餅を乾燥させたものを、いろんな形に切っていろんな形の製品になります。10種類から25種類位を作っているそうです。最後に焼きたての「かきやま」をいただく!みんなわらわらと群がっていただきました。「残さず持って行ってくださいね^^」というお嬢さんの言葉に甘えて全部もらってきました!(キヨミちゃんはマイバッグに詰め込む!) しかし工場見学の場所だけでなく、ささら屋の店内でも、おかきは食べ放題においてあり、お茶もコーヒーも無料です。 100円のぜんざいをいただき、無料のかきやまをたらふくたべ、さらに、みそ造りでお世話になった有機農業やってるミノグチ組の山菜てんぷらも食べる!またしても腹いっぱいになる・・・♪ ところで「おかき・あられ」と「せんべい」の違いってわかりますか?「せんべい」はウルチ米からできますが、「おかき・あられ」はもち米からできます。おかき・あられの違いは、サイズの違いのようですが・・
2008年04月18日
コメント(3)
-
ほたるいかの身投げ
富山湾の春の風物詩といえば、ホタルイカ。3月から6月ごろに、メスのホタルイカが産卵のために、沿岸に集まってくるのです。春先には、定置網でこのホタルイカを採っています。滑川や新湊で、この定置網漁を見る「ほたるいか観光船」も出ています(午前3時ごろ出港し、朝方戻ってくる)。ホタルイカの寿命は1年で、定置網で捕獲しているのは、夜中に産卵し終わったメスの個体だけなのです。昼間は水深200メートルほどの深い所にいるそうです。 そのほたるいかが、ここ富山では、「身投げ」をするのです! それは新月の夜、晴れて波が穏やかな日には、たくさんのホタルイカが浜に打ち上げられるという現象です。今年も3月くらいから何度か身投げの様子が新聞にでていましたが・・・・ウワサに聞く身投げをぜひ一度見てみたいと思ってました。 で。土曜日に行こうと思ったけど、疲れて寝てしまって断念。 きのう4月6日は新月!しかもお天気も良い! というわけで、夜12時近くに、車で15分ほどの「八重津浜」という海水浴場に行ってみました! 浜の近くに住んでいる友人をピックアップ♪網とバケツと懐中電灯をを持ってさあ、海へ! 浜に行ってみると・・・いるいる!たくさんの人たちが、ホタルイカをすくいに来ています。にぎやかです! 空には北斗七星など星空が広がっています。 ほたるいかはどんどん、浜に上がってきていて、海中をさらうとすぐにホタルイカがすくえます。 なかには腰まで濡れない釣り用ズボンをはいて海中を歩いて網をひっぱるだけでとってる人も・・・ ちょうど潮が満ちてきているのでしだいに浜に来るほたるいかの量も増えてきます。 そして、打ち上げられたホタルイカが青いベルトのように、浜べに光っているんです!ほんとうにきれい! 打ち上げられたのを拾えば簡単だけど、砂を噛んでるから、海中からとったほうがいいんだって。 バケツ一杯のホタルイカを採取いたしました。 なんか、かわいそうなのですけど、1年の寿命だというし、打ちあがって鳥に食べられちゃうんですよね・・・ ホタルイカのはかない命、大事にいただかねば。 でも、これじゃぁ地元の人は、お金払ってホタルイカを買いませんわね~。 2時半ごろ帰宅し、すぐにゆでる!たくさんゆでる!あと、沖漬けにもしました。いちおう、目とかとったのもつくりましたけど、あまりに大量なので作りきれず・・・。生の沖漬けは一度冷凍しないと、寄生虫がいるらしく。内臓は生では食べないよ うにと言われています。 そんなこんなで、お風呂にも入って寝たのが4時半くらいになってしまいまいました。。。
2008年04月06日
コメント(5)
-
日記をまとめてアップしました
※一か月以上日記を更新していませんでした。じつはmixiでばっかり書いていたので、こちらにまとめて貼り付けておきました!※今日から4月ですね!私の富山での生活も丸2年が過ぎ、3年目に入ります。本日、旅行業協会に入会金を払って、「株式会社エコロの森」がいよいよ旅行会社としてスタートします。すでに県庁からは「富山県知事登録旅行業第3-266号」の登録が完了したとのお知らせをいただきました。いやぁ~、2年前に富山に来たときは、よもや旅行会社を経営することになるとは思ってもいませんでした。起業したいという気持ちはあったけど、当初は ・ずっとやりたかった自然学校のような体験活動の仕事 ・前職での経験から、就職支援の仕事 ・ライターとか編集の仕事というような漠然とした考えだったのです。「とやま起業未来塾」に入ったことで、こうしたアイディアを形にすることを学び、だんだん「エコツアー会社」という方向性が見えてきました。エコツアーとは環境にやさしく地域活性化につながるツアーモデルなのですが、着地型旅行の世界になります。着地型旅行は旅行業法の規制緩和で、小さな会社でもやりやすくなることなどを知り、また多くのエコツアー会社が、旅行業法のすきまをぬいながら(いわばグレーゾーンで)ビジネスをしていることを知ったため、ちゃんと旅行業法の枠組みのなかでエコツアーができたらいいなと思うようになりました。旅行業法のなかでやるには、旅行会社として旅行業登録する必要があります。そのために必要なのが「旅行業務取扱管理者」の資格。なのでまず、その資格を取ることを昨年のステップにしました。また昨年は富山市の公募提案型モデルツアーを実施しましたが、自分が旅行会社でないと、他の会社に旅行業務(※交通と宿泊の手配)を委託しなくてはならないのがほんとうに面倒だな~(しかも手数料もかかる)と実感。というわけで回り道しましたけど、昨年は資格も無事とり、今年2月に会社創業、そしていよいよやっと旅行会社になるわけですヨ。ここまできたけど、実際には「これから」のほうが重要です。会社にした以上、ちゃんとビジネスをしていかなくちゃいけない~!いろいろわからないことだらけのなかで、やりたいことだけが先走りしていますが、これからは経営者としてやるべきことをやらなきゃなりません。ひゃ~。余談ですが「ツアーを行う」ということは、旅行業法に基づいて行うということ。そのために旅行会社では資格をもった管理者を置き、「営業保証金」(あるいは弁済業務保証金分担金)というお金を用意して、旅行者のために態勢を整えています。しかし、世の中では旅行会社ではないのにツアーを実施しているところが多いらしいですね。ネット上で無資格で高額のツアーを企画したり実施したりしているところもあるそうです。私はそうした法律に抵触しないために回り道をして旅行会社をわざわざつくりました。これからもコンプライアンスを重視し、どんな法律にも違反しないように、できることをやっていきたいと思います。たとえば外国人への観光案内を「業務」として行うには「通訳案内士」の資格というのは必須なのです(そうでなければボランティアガイド=無償に近い=でしかできません)。将来、海外旅行やインバウンドのツアーも扱いたいので、とらなくてはならない資格(あるいは有資格者の雇用)だなと思います。また、3種の旅行業という小さい会社での「募集型企画旅行」のできる範囲は限られています。今のままでは富山県内全域をカバーできないのです。私の事務所のある富山市とそれに隣接する市町村のみで「募集型」のツアーができるのですが、高岡市、黒部市などは富山に隣接していないのです。だから将来的には、こうしたところにもオフィスをだしていかなくちゃ。なんとかそこまで会社を大きくできるのか。それとも売上あがらず廃業するのか。すべてはこれからの私次第ですね!ぜひぜひ応援してください!
2008年04月01日
コメント(3)
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-
-

- 日本各地の神社仏閣の御朱印
- 後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 …
- (2025-11-24 00:00:13)
-
-
-

- ぶらり、歴史の旅、歴史探訪(歴男、…
- 仙台の旧町名「保春院前丁」(今の住…
- (2025-11-22 00:00:15)
-