2025年01月の記事
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-

子どもたちをもて遊ぶカメ(タートル・トーク)Tokyo Disney Sea
東京ディズニーシーの奥の方、「アメリカンウォーターフロント」というエリアに大きな蒸気船「S.S.コロンビア号」が“停泊”していて、その船尾にある海底展望室で「タートル・トーク」という名のアトラクションに“参加”した。アメリカンウォーターフロントには、古き良きアメリカの街並みが再現されていて、この辺りに来ると僕はいつも感動する。その一角に、小さな子どもたちが列をなす場所があることを、僕は今まで知らなかった。今回は夜だったので列は短かったけど、それでもたくさんの子どもたちが元気に入場を待っていた。船尾の大きな窓の外にやってくるウミガメのクラッシュが、入場したゲストたちに次々話しかけていく「タートル・トーク」。まさにタイトルそのままのアトラクションだった。見たところ、子どもたちの多くはリピーターのようで、ウミガメさんとお話がしたくてみんな一生懸命に手を上げていたし、ウミガメさんを「クラッシュ!」と、友達のように呼んでいた。めでたくウミガメさんに指名されたゲストは基本的にイジられまくるのだけど、みんなそれを楽しんでいた。子どもたちやお母さんお父さんからの質問に即興で答えていくカメさんは、深夜放送のDJのように子どもたちの心をガッチリ掴んでいて、すごいなぁ、と思ったし、楽しんでいる子どもたちの姿もみんな可愛くて、同じ空間に紛れ込んで見ているだけでも心が柔らかくなった。アトラクションが終わってぞろぞろと外に出ると、そこはまた古き良きアメリカ。場違いとも言えそうなアトラクションを楽しんだ僕は、「お前たち最高だぜ!」「ウォー!」とかクラッシュの口ぐせを小さな声で呟きながら、大きなクリスマスツリーをしばし眺めた。
January 28, 2025
コメント(0)
-
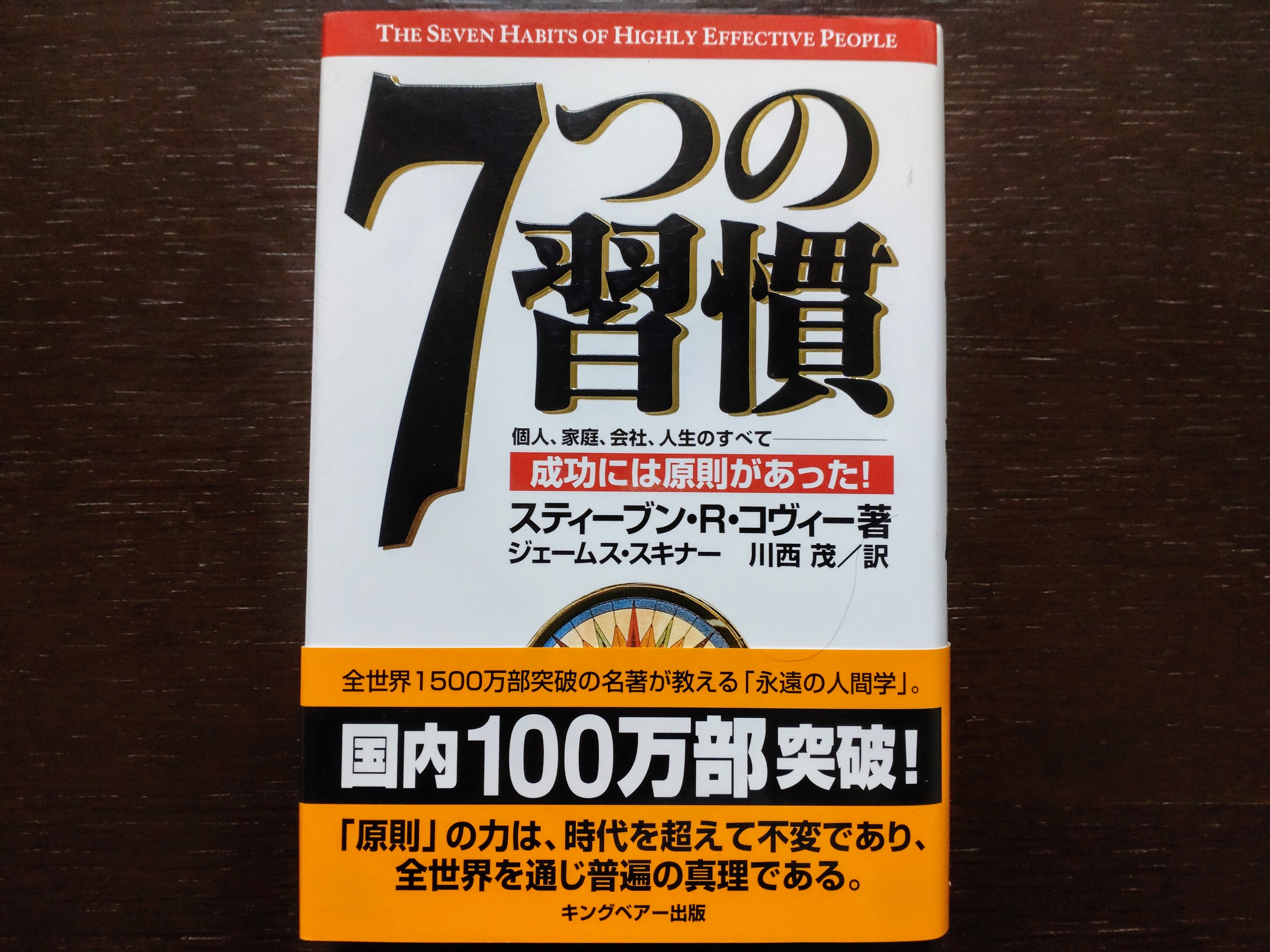
第五の習慣「理解してから理解される」(「7つの習慣」スティーブン・R・コヴィー)
七つの習慣のうち「第五の習慣」までたどり着いた。「僕にはできていないことが多いなぁ…」と思いながら読んでいるせいか、スイスイとは進まない。一方で「ごもっとも」とうなずくことも少なくないので、何とか最後まで読み通してみようと思っている。「第一の習慣」から「第四の習慣」まで順に振り返ると…①今の困難な状況を他人のせいにせず、自分ができることを見つけ、自分の力が及ぶ範囲を少しずつ広げていこう。②状況が改善された状態(ゴール)を具体的にイメージしてから最短距離を進んでいこう。③状況を改善するために必要なことは放置せず、主体的に着々と処理しよう。④関わる者すべてがメリットを感じられる形で状況の改善を目指そう。という趣旨だったと思う。そして「第五の習慣」の主題は「理解してから理解される」。この章を自分なりにまとめると、例えば子どもと向き合った時に…・子どもが直面している問題を、勝手に理解したつもりになるな。まず子どもの話を聞け。・「わかるわかる、俺もそうだった」とか偉そうに言うな。今、子どもにとって親の昔話なんてどうでも良いし、そんなものと自分の悩みを一緒にされたくもない。・解決策を教えようとするな。答えは子ども自身の中にある。じっくりと会話を積み重ねて子どもが持っている解決策を引き出してあげよ。・子どもの思いを理解するためだけに子どもと話をしろ。子どもを導くためでも説得するためではない。本当の理解者にしか子どもは心を開かない、これも、その通りだと思うし、相手が自分の子どもなら、僕もやってみようと素直に思える。だけど著者は、子どもではなく、自分と相性が良くない相手、信頼関係がまったくない相手に対しても、同じように傾聴し、理解し、その上で自分の気持ちを伝えよ、と言う。正直、これは厳しい、と思った。問題を改善したければそうする以外にない、とコヴィーさんは言うが、今の僕のレベルでは、「悪いのは向こうなのに、なんで俺があいつに擦り寄らなきゃだめなのさ。そんなこと絶対やんない。」とか言って拒否するに違いない。できるようになる日は来るのかなぁ、来たらいいなぁ…そう思いながら第六の習慣に進む。
January 24, 2025
コメント(0)
-

映画「サンセット・サンライズ」【感想】
コロナ禍と東日本大震災の両方がストーリーに深く組み込まれている作品。とりわけ、東日本大震災の話題に触れることが今もって苦手な自分としては、この映画を観るか、それとも観ずにおくか迷った。結果、脚本が宮藤官九郎さんなので観ようと決めた。出演は、菅田将暉さん、井上真央さん、中村雅俊さん、竹原ピストルさんほか…皆さん個性的で、重たいテーマながら最後まで楽しく観ることができた。涙の中に笑いが込められている、悲しさの中にも明るさがある、官九郎さんらしい映画だな、とも感じた。ただ、楽しく観られたとは言え、映画の一場面に、百香(井上真央)が夜の岸壁にひとり軽自動車を停めて、津波で死んでしまった2人の子どもたちの歌声をカーステレオで再生している場面があって、それはほんの短いシーンだったけど、たまらなく悲しすぎて辛すぎて、どうしようもない気持ちになった。代われるものなら代わってあげたい…。そう思わずにいられないほど、あの震災は愛らしく愛おしいたくさんの命たちを奪っていってしまった。その時の感情が瞬時に蘇った。それと共に、何の役にも立てていない自分、無力な自分に嫌悪しながら、この災害で生き残るべきは自分だったのだろうか…などと、考えても意味のないことを仮眠のソファでグダグダ考えていた震災後の日々も一緒に思い出された。東京と三陸の町が舞台のこの作品には、被災地と被災者に対する東京からの視点も軽くぶち込まれている。正論だけどなかなか言えないひと言。両方に軸足がある官九郎さんだからこそ書ける脚本だな、と思った。映画の中で流れる「思い出のアルバム」がひたすら心に染みて、泣けた。
January 20, 2025
コメント(0)
-

懐かしさにどっぷり…「海底2万マイル」(東京ディズニーシー)
土曜午後のディズニーシー。目標としていたアトラクションをひと通り楽しんだ後、待ち時間が短そうなところを子どもがアプリで探してくれて、とりあえず…という感じで海底2万マイルの列に並んだ。40分待ちくらいだったと思う。「ミステリアスアイランド」と呼ばれるエリアの眺めは開園当初から変わっていない気がして懐かしかった。「ここは宇宙かなぁ、地球かなぁ」と昔の僕。「んー、宇宙かなぁ、地球かなぁ…」と昔のわが子。こんな会話をしながら、当時小学生だった子どもと列に並んでいたことを思い出した。まったくの無意識だったけど、今回も同じような話題をすっかり大人になった子どもに振っていた。「ここは宇宙のイメージなのかな。地球なら噴火口みたいな所かな…」と今の僕。「センター・オブ・ジ・アースがあるから地球じゃない?」と今のわが子。子どもからの返事は今回かなりドライだったけど、確信があるわけでもないらしく、かと言ってスマホで調べるでもなく、正解はどっちでもいいみたいな感じで、ダラダラ話をしながらアトラクションの順番を待っていた。のんびりと楽しい時間だった。海底2万マイルは、とりあえず…の選択だったけど、6人乗りの潜水艇の旅は記憶にある印象よりもずっと密度が濃かった。きっと以前はアトラクションにスリルだけを求めていたから物足りないように感じていたのかもしれない。1回乗っただけでは見切れない程の仕掛けが船内にも深海の中にもあることを今回初めて知った。
January 17, 2025
コメント(0)
-

仙台の旧町名「茂市ケ坂」(今の青葉区花京院一丁目ほか)
茂市ケ坂(もいちがさか)かつての茂市ケ坂は、昭和45年2月1日に住居表示が行われ、今は青葉区花京院一丁目と本町一丁目のそれぞれ一部になっている。写真の右側の細い道が、町の北側から見た茂市ケ坂。仙台駅に向かう左側の幹線道路(駅前通)から微妙な角度をつけて広瀬通に向かって下っている。幹線道路の「駅前通」は、かつて仙台城の城下町が開かれた当初の町割りと平行に走っていて、一方、茂市ケ坂は政宗公が晩年暮らした若林城造営に伴う町割りと概ね平行している。(赤線がかつての茂市ケ坂)この町割りから茂市ケ坂周辺は、仙台藩の城下町拡大に伴って、新しく城下町に組み込まれていったエリアなのだろうと思われる。広瀬通に建つ辻標41番「茂市ケ坂/元寺小路」は茂市ケ坂を次の通り説明している。・仙台七坂の一つで元寺小路から花京院通に上る坂。・盲人茂市が住んでいたという。・藩政時代、坂の両側と坂下から元寺小路東部は職人町だった。・白百合学園敷地は、政宗夫人愛姫の母が建立し、弁財天を本尊とした真言宗密乗院の跡地。・明治三十二年から戦災時までは第一高等女学生が坂を往来した。説明にある「白百合学園敷地」には、今は東北電力本社ビルになっていた。そしてこの場所には「第一高等女学校」跡地を示す石碑もあった。ちなみに第一高等女学校の変遷は次の通り。(宮城県宮城第一高等学校HPより)明治30年 仙台市高等女学校明治33年 宮城県高等女学校大正7年 宮城県立第一高等女学校大正8年 宮城県第一高等女学校昭和23年 宮城県第一女子高等学校平成20年 宮城県宮城第一高等学校(男女共学)戦後、「一女」と呼ばれていた女子高の前身がここにあったことを初めて知った。ちなみに僕の祖母が通っていた「北海道庁立札幌高等女学校」の創立は明治35年。きっと明治30年代に、女子への高等教育の場が全国横並びで作られたのだろう。ただ、設立は横並びでもその後は少し違っていて、札幌の高等女学校は戦後すぐに男女共学(札幌北高)になり、一方、仙台の高等女学校は平成20年までずっと女子高(宮城一女)のままだった。北海道の人たちは、男女別学の制度に明治時代から疑問を持っていたのかもしれない。そして宮城の人たちは「男女七歳にして席を同じうせず」を戦後に至っても当然と考えていたのかもしれない。そんな想像をしてみた。
January 12, 2025
コメント(0)
-
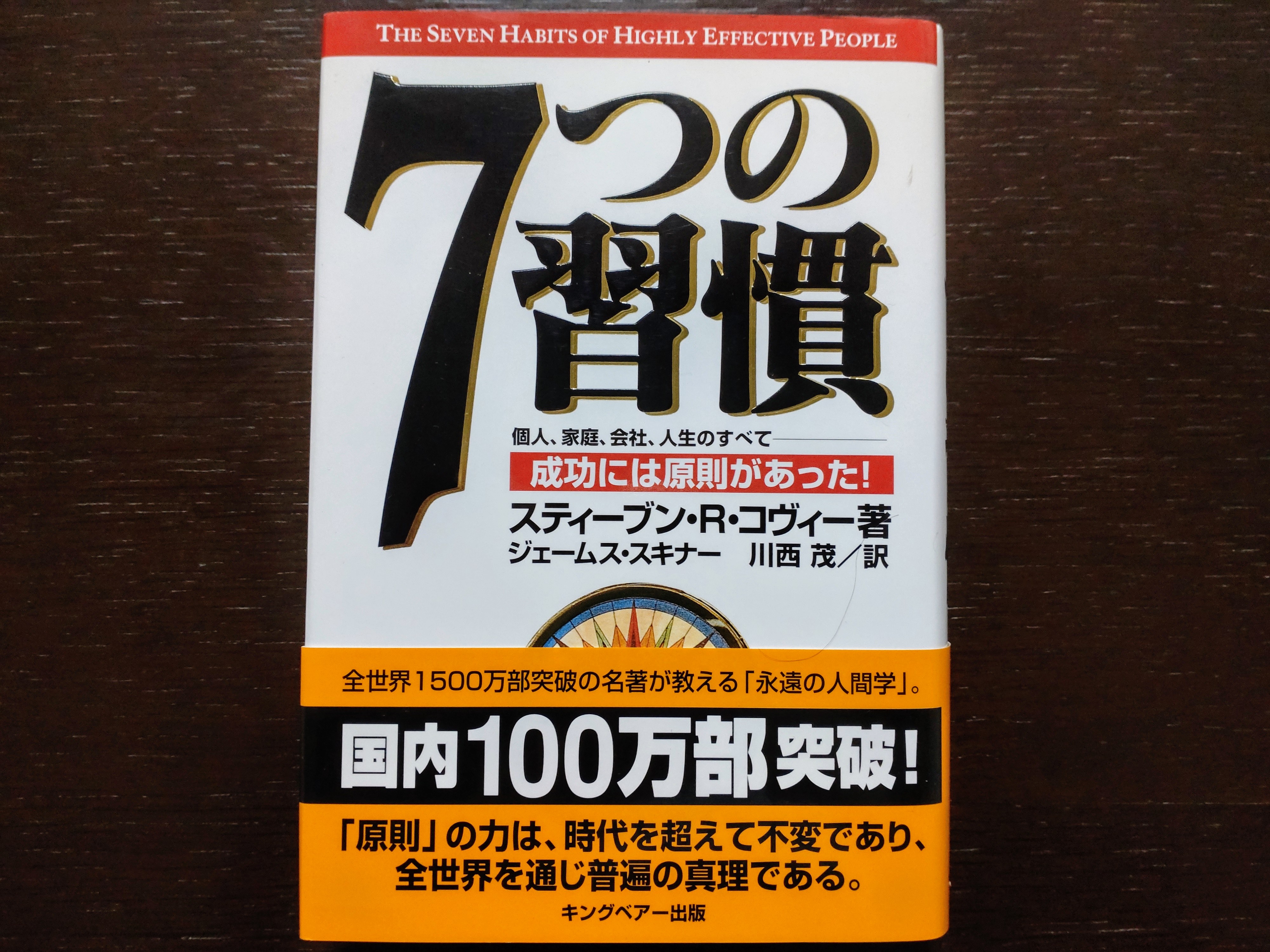
第四の習慣「Win-Winを考える」(「7つの習慣」スティーブン・R・コヴィー)
著者、スティーブン・R・コヴィー氏が「永続的な幸福と成功を支える基本的な原則」と説く「7つの習慣」のうちの4つ目。【第四の習慣「Win-Winを考える」】(以下、勝手な要約と勝手な感想)ここまで「第一の習慣」から順に、①今の状況を他人のせいにすることなく、状況改善のために自分ができることを見つけ、そこに集中しよう。②最終的にあるべき状況を明確化しよう。どのようにやりたいか、ではなく、どうなりたいかを考えよう。③その目標を達成するために「重要だけど急ぎではないこと」を放置することなく取り組み、緊急事態に追われるだけの日々、つまり、ただ忙しいだけの後手後手の日々から抜け出しておこう。そして、第四の習慣に進む前段として、信頼を得る努力をコツコツと重ねておこう、といったことが書かれていた。「第四の習慣」は、これらができていることを前提に、皆が勝者になることも可能な仕組み、つまり、Win-Winの結果も期待できる仕組みを考えよう、と説いている。なぜなら、どんな仕事も自分だけの努力で、あるいは自分の部署だけの頑張りで成功を得られるものではなく、他の部署の協力も得ながら、そして取引先とも同じ方向を向きながら取り組んで初めて上手くいくものだから。例えば社員表彰の表彰基準を考えてみる。売上上位の社員を表彰するシステムは、必然的にそれ以外の社員を敗者に位置付けてしまいかねず、これはWin-Winの発想ではない、とこの本は語る。それよりも、それぞれの部署が設定した目標を達成できたかどうかを評価基準とすることで、努力次第ですべての部署が表彰され得る仕組みとすることができるのではないか。そうすれば、他の部署や他の社員を蹴落とすような発想は消え、目標達成のために部署間での支援体制も生まれるのではないか、と著者は言う。読んでみて、これはまぁ、おっしゃる通りかな…と思った。特に経営者目線で考えるなら本当にその通りだと思った。ただ、揚げ足とりのような言い方になるけれど、例えば人事を考えてみても、昇進ポストは限られているという事実は厳然としてあって、そこにどうしても仲間内での競争みたいなものは生まれてしまうよね、とは思った。担当者時代を振り返れば、同僚に負けたくないという気持ちが一つのモチベーションになっていた記憶があり、職場内競争にもメリットはあったと思っている。一方で、部下が挙げた成果を自分の成果として語る上司は実在したし、仲間の実績を懸命にこき下ろそうと陰口を叩きまくる同僚の姿もしばしば見てきた。Win-Winを考えることで、こういう人たちがいなくなるのだろうか、と考え始めると頭の中が混沌としてくる。繰り返すが、決して「そんなのきれい事だよ」と難癖をつけたい訳ではない。だけど、この本の通りにできていない自分が悔しいのか、それともやっぱり心のどこかで「そんなに上手くいかないよ」と思っているのか…素直さに欠ける読み方を僕はしてしまっている。これではこの本を書いた人に申し訳ない、できるだけ斜に構えて読まないようにしよう、と思いつつ「第五の習慣」に進むことにする。
January 7, 2025
コメント(0)
-

頑張って撃ちまくったけど…(トイ・ストーリー・マニア)Tokyo Disney Sea
東京ディズニーシーの「アメリカンウォーターフロント」エリアにあるトイ・ストーリー・マニア。ここには前に来たことがあるような錯覚を覚えたけど、15年前にここはなかったはず。何だろう、この既視感…日が沈んでから来てみると、昼間に前を通った時とは景色が違った。街全体が光り輝いていて美しかった。入口はどこだろう?ウッディの口から入るのかな?と思いながら近づいてみると、予約方法によって入口が分かれていて、僕たちは脇の方から中に入った。ひとしきり列に並んだ後、トラムに乗り込んで、銃を持って、後はひたすらターゲットめがけて撃ちまくった。プレイヤー1が僕の点数。2が子どもの点数。どちらも超初心者の点数にとどまった。子どもは不本意だったらしく、かなり悔しがっていた。まぁこんなもんかな、と僕は思った。今度来たときは少なくてもこの倍は取ろう!と心に誓った。楽しかった。
January 2, 2025
コメント(0)
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-
-

- 日本全国の宿のご紹介
- 【静岡*焼津・藤枝・御前崎・寸又峡…
- (2025-11-28 14:11:49)
-
-
-

- ディズニーリゾート大好っき!
- (自分用記録) ~「ディズニー・ク…
- (2025-11-23 19:05:02)
-
-
-

- 中国&台湾
- 高市首相、台湾有事での 「集団的自…
- (2025-11-27 19:34:43)
-







