2025年02月の記事
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-
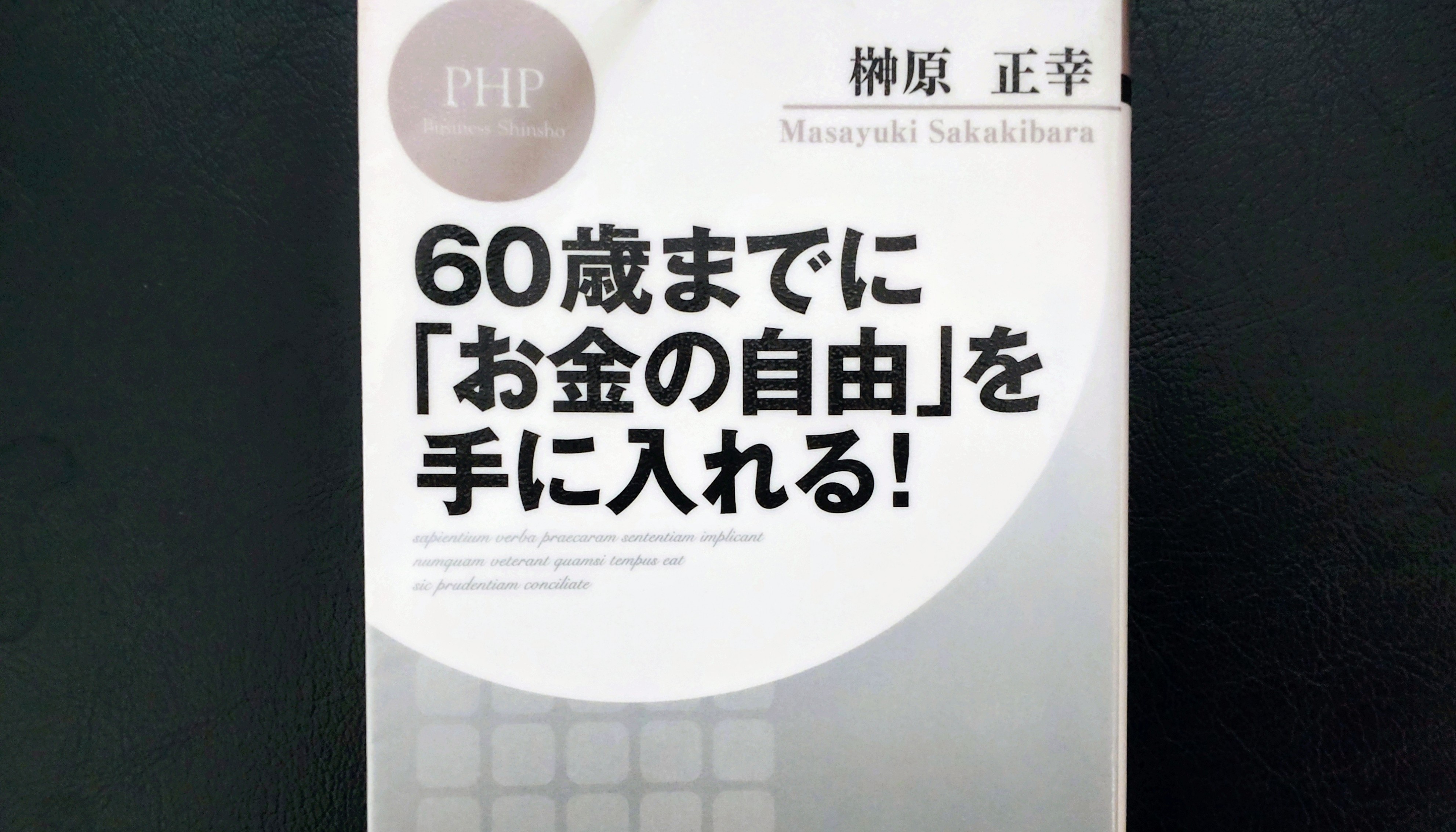
『60歳までに「お金の自由」を手に入れる!』(榊󠄀原正幸 著/PHPビジネス新書)
本のタイトルに惹かれた。この本を書いた榊󠄀原さんは、大学の先生を早めにリタイアした方。株式投資の本も執筆している。老後についてまじめに考えて来なかった僕も、少しは考えた方が良いかな…と思い、この本を手に取った。【感想をざっくりと…】年金だけでは足りない生活費を預金の取り崩しで補っていてはやがて資産が枯渇してしまう。手持ちの資金は減らさずに運用益で暮らしていきましょう、とこの本は説いている。とは言っても、資産運用の話ばかりではなく、仕事を「イヤな仕事」と「イヤじゃない仕事」と「好きな仕事」の3つに分類して、好きな仕事に就くのは難しくてもイヤじゃない仕事を探して、それが見つかったらできるだけ続けましょう、と繰り返し書いている。ここがこの本の言わんとすることの大きな部分かな…と感じた。以下に、目次の中から印象的な項目を抜き出してみる。【目次から抜粋】第1章 60歳までに「ハッピーリタイア」をしよう!・今や、60歳で辞めることこそが「ヤンリタ」(注:ヤングリタイアメント)・「一生働くのが当たり前」という時代に備える・目指すべきは、一生安心できる「エターニティ」を手にすること第2章 日本版FIRE―「FIRE60ターゲット」とは?(注:Financial Independent Retirement Early)・日本ではむしろ「FIRA60」を目指すべき第3章 早く達成すべきは「イヤじゃない仕事」に就くこと・「イヤじゃない仕事」に就けば、人生の幸せの半分が手に入る第4章 「お金の問題」にどう対処するか・資産運用のススメと副業のススメ第5章 資産運用の具体策―「安心・安全」な株式運用術・配当の受け取りを主軸にした、盤石の資産運用法・どの株を、いつ買えばいいのか―投資対象の絞り込み・いつ、いくらで売ればいいのか―売り値の決定第6章 「ヒマだ病」た闘う覚悟―FIRA60達成後の未来・「人生でやり残したことリスト」を作る終章 本書でお伝えしたかったこと・この世の天国は「オレの庇護の下でぬくぬくと暮らすこと」【資産運用の具体策の実践】イヤじゃない仕事をできるだけ続けることが実現できたとしても、それでも将来的な目減りが見込まれる年金を補う運用収入の確保は欠かせない。ということで、第5章「資産運用の具体策」の「投資対象の絞り込み」について、東証に上場している某ヘルスケア企業に当てはめて試してみた。《その株を買うかの選択》A:国際優良企業に当てはまるか?海外売上高比率が30%以上か?など基準は4項目。→やってみたところ、結果は2勝2敗B:財務優良企業に当てはまるか?東証プライム上場企業か?など、こちらも基準は4項目。→この結果は3勝1敗AかBのどちらかをすべてクリアしていれば投資対象になりうるが、今回選んだ会社は(立派な会社だと思うのに、それでも)この本的には株を買う対象として十分とは言えないようだ。《いつ買うかの選択》①過去5年間の実績から一定のルールで引き出される安値圏→この会社の場合1,400円くらい②最近の株価→1,800円くらい仮にこの会社の株を買うとして、それは今ではなくて、あと400円くらい下がったら買い時ということになるようだ。こうしてみると、すごく堅実な作戦だと感じる。そして、こういう考え方は今までしたことがなかったな、とも思った。一度試してみても良いかもしれない。
February 26, 2025
コメント(0)
-

大森貝塚遺跡庭園(品川区大井)
子供の頃、歴史の授業にはあまり興味がもてなくて、特に縄文時代とか太古を扱う4〜5月頃の授業は自分とは無縁にしか思えなくて、受けていて辛かった。だけど教科書に載っていた「大森貝塚」という言葉は不思議なことに今も頭に残っている。大森貝塚を学ぶための野外教育施設のような「大森貝塚遺跡庭園」は、JR大森駅から歩いて数分、大田区と品川区の境にあった。ポートランド(米国)出身のモース博士が1877年6月に大森貝塚を発見したとのことで、園内には博士の胸像があった。胸像の奥には銘板があり、モース博士との縁で品川区とポートランド市が姉妹都市になっていることを説明していた。大森貝塚という名前から、姉妹都市を結ぶなら大森がある大田区ではないのかな?と思ったけど、きっとこの地(品川区大井)により強いご縁があったのだろう。遺跡を守るためだろうか、庭園の入口にはゲートがあって、夕方には閉まるようだ。園内には発掘された貝塚の展示があり、説明板もいくつかあって、教育施設っぽさも漂っているけれど、全体的には普通の公園。この日は近くの保育園から子どもたちが遊びに来ていた。人間が生活していた証(貝塚)が大森・大井の地で発見されたことが歴史上いかに重要な事件だったのか、僕には今も良くわかっていない。ピンと来なかったからこそ「大森貝塚」という言葉が子供の時分からずっと記憶に残っているのかもしれない。今回、この庭園に来て、僕も少しは賢くなれただろうか…。昭和4年(1929年)に建立された記念碑。庭園の南端、線路を見下ろす場所に置かれていた。
February 21, 2025
コメント(0)
-

仙台の旧町名「宮町」(今の青葉区宮町ニ〜四丁目)
宮町(みやまち)仙台東照宮の石段に立って南の方向を眺めてみると、宮町の通りが鳥居の向こうにまっすぐ延びていた。かつての町名「宮町」は、仙台東照宮の門前町として拓かれた。昭和45年2月1日の住居表示によって、今は宮町ニ〜四丁目になっている。〔仙台市「歴史的町名復活検討委員会報告書(平成21年1月)」より〕東照宮から2〜3分歩いた交差点に建つ辻標86番「宝蔵院/宮町」は、宮町を次のとおり説明している。・東照宮の門前町で、北六番丁から東六番丁北端までの南北の町。・承応3年(1654)玉手崎の天神社跡地に東照宮が造営された際に町割りがなされた。・全戸に五百文の田畑が与えられ、年貢や町の諸役が免除されたほか、仙台祭の日には絹布着用の特権が与えられていた。・御宮町・権現町ともいわれた。(JR仙山線の踏切近くに建つ「《宮町》通り」の標柱)仙台市HP「道路の通称として活用する歴史的町名の由来」では、《宮町》をこう説明している。・権現町・御宮町ともいい東照宮の門前町であることによった地名。・上御宮町・下御宮町の2区から成る。・「仙台鹿の子」によれば、門前町百五軒、1軒につき五百文ずつの御用捨田畑がが付けられ、無年貢であったという。・また酒類・塩・たばこ以外の店売については諸役を免除されたが、その代わり東照宮への奉仕が義務付けられていた。わからない言葉がいくつかあるので調べてみた。「玉手崎」は今の東照宮がある場所。天正19年に徳川家康公が葛西大崎一揆の視察を終えた帰り道に、この地で伊達政宗公と休憩したとの故事により、東照宮造営の地に選ばれたとのこと。(参考:宮城県神社庁HP)(かつて「玉手崎」と呼ばれていた東照宮の境内)「天神社」は、今は宮城野区榴ケ岡にある榴岡天満宮。平安時代の天延2年(974)に今の京都府に創建された後、天文20年(1551)から東照宮の場所にあったとのこと。(参考:榴岡天満宮HP)「仙台祭」は、東照宮造営の翌年、1655年に始まった東照宮例祭。江戸時代を通じて行われ、2代藩主伊達忠宗以降13代まで全ての歴代藩主が仙台祭に合わせて東照宮に参拝したとのこと。(参考:仙台東照宮HP)宮町の南端と思われる場所に、個人の建立と思われる石碑が建っていた。「北 是より御宮町」「この地 昭和四拾五年まで宮町壱番地」と書かれていた。東照宮の門前町の誇りのようなものを感じさせてくれた。
February 16, 2025
コメント(0)
-
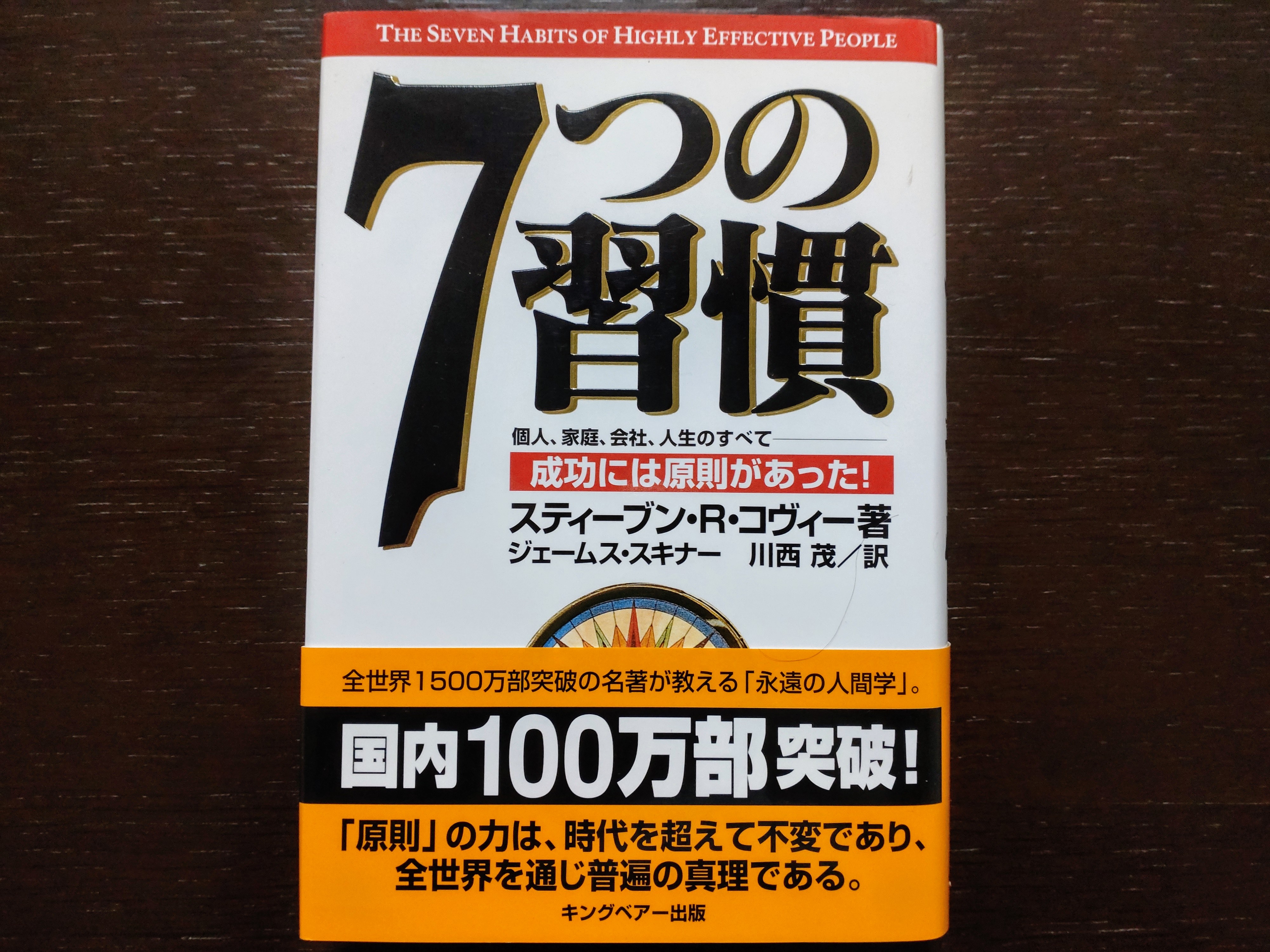
第七の習慣「刃を研ぐ」(「7つの習慣」スティーブン・R・コヴィー)
読み続けてきた「7つの習慣」も、いよいよ最後の7つ目の習慣。「第七の習慣」の後に「再びインサイド・アウト」の章が締めの言葉として綴られ、フィナーレとなった。【第七の習慣「刃を研ぐ」】「自分を磨き、自分の内面から湧き出る良心(原則)に従って、世の中に尽くしなさい」一言で、と言われたら僕は「第七の習慣」をこうまとめる。そして「第七の習慣」を読んだ後で、例えば「第一の習慣」を解釈し直すと次のようになると思う。・今の状況が大バカ野郎のせいで引き起こされたとしても、あなたがやるべきことは状況を改善するために自分ができることを見つけ、それに取り組むこと。大バカ野郎をやっつけることはあなたの課題ではない。人間は世の中の役に立つために生きているのだからそこに集中しなさい。なるほど…と思った。「あいつの尻拭いをさせられている」とか、「あいつのせいでこんな思いをしてるのに、あいつは申し訳ないとも思っていない。」等々…何か問題が起きると、僕の頭の中は、それをやらかした「あいつ」に支配されるのだけど、この本は、「あいつ」のことをまったく相手にしていない。この本が焦点を当てているのは、「問題が存在していること」と、それに対して「自分ができること」。改めて、なるほど…と思った。その昔、教会で牧師さんから似たような話を聞いた気がする。ひょっとすると、キリスト教の教えがこの本の背景にあるのかもしれない。今回、久しぶりにこの本を手に取るにあたって、耳障りの良いところだけ摘み食いするような読み方はやめようと思った。その結果、読み終えるまでに随分と時間がかかったし、自分に足りないところを次々と見せつけられた。時々読むのをやめたくもなった。こんな立派な人になれる日が来るのかな、というのが今の感想。かと言って、「きれいごとを並べている」などどこの本を批判する気にはまったくならない。この本に書いてあることは正しいと思っているし、この本の記憶がいつの日か、何かの場面で僕の内面から湧き出てくるのではないか、と淡い期待も抱いている。まずは、この本を自分なりに真剣に読み通した僕を褒めておこうと思う。
February 11, 2025
コメント(0)
-

タワー・オブ・テラーでゾワッ(東京ディズニーシー)
タワー・オブ・テラーは本国アメリカでは別のアトラクションに変わってしまったと聞いた。ちょっと残念。でも、その新しいアトラクションもそのうちぜひ経験してみたいとも思う。アメリカンウォーターフロントの一角にあるタワー・オブ・テラーに、今回は朝と夜の2回、普通に順番待ちをして乗った。朝は、列の前後で制服ディズニーを楽しむ子どもたちがキャッキャしていて、さらにはエレベーターボーイを務めるキャストさんも軽い雰囲気で案内してくれていて、全体的に明るい雰囲気だった。純粋にエレベーターのスリルを楽しんだ。一転して夜は、列に並んでいる時から、なんとなく雰囲気が不気味で、キャストさんの語り口も静かで、どことなくホーンテッドマンション的な空気感の中で絶叫型アトラクションを楽しんだ。朝のタワー・オブ・テラーも夜のタワー・オブ・テラーも、どちらも相変わらずとても良かった。何度乗ってもゾワッとするスリルがあって、相変わらずとても良かった。
February 6, 2025
コメント(0)
-
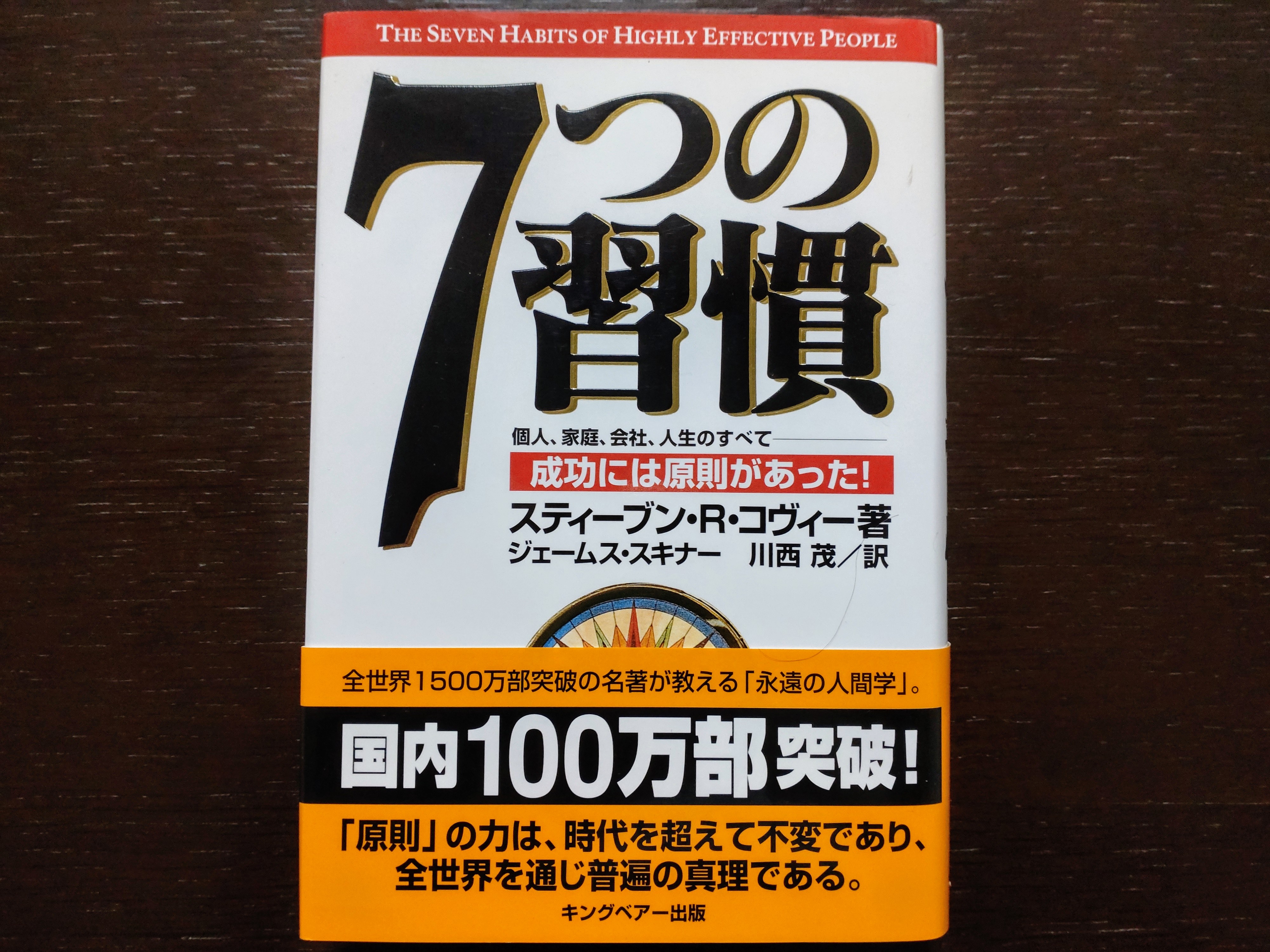
第六の習慣「相乗効果を発揮する」(「7つの習慣」スティーブン・R・コヴィー)
「7つの習慣」の6番目。第一の習慣から順に、自分なりに要約すると、①自分が置かれている状況を他人のせいにしない。自分ができることを見つけてそこに集中する。②状況の改善に取り組む前に、進むべき方向をしっかりと見定める。さもなければ努力がムダになり兼ねない。③状況改善のために必要なことは急かされる前に計画的に取り組む。さもなければ緊急事態に振り回されてムダに忙しいだけの日々になる。④相手をやっつけるのではなく、双方にとって良い結論を求める。⑤自分の立場を主張する前に、相手の考えが理解できているかを相手と一緒に確認する。そして「第六の習慣」は【相乗効果を発揮する】「相乗効果を発揮する」とは、一言で言うなら、対立する相手と主張をぶつけ合う中から、どちらの当初案も上回る「第三の案」を導き出せ、ということだと理解した。「まず担当者案を示さなければ話は前に進まない」「叩かれても叩かれても、叩き台を出し続けろ」と言われ続け、自分に言い聞かせ続けもしてきた自分としては、この考え方にかなり共感できた。言い出しっぺは批判に晒されやすく、嫌な思いもするけれど、受けた批判の中には具体的な提案もある。それを丁寧に拾っていくうちに、当初の案がどんどんブラッシュアップされていく。そう思ってきたし、この手法は間違いではなかったと思っている。ただ、その「実践」が成り立たない状況、つまり、そもそも「第六の習慣」を適用しようがない状況はしばしばあると感じていて、その時どうすれば「相乗効果を発揮する」状況に持っていけるのか、この本を読みながら、著者に聞いてみたい気持ちで一杯になった。例えば、相手方が問題意識を持っていない場合。ある部署のマネジャーが代わった途端、成績が目に見えて落ち始めた。この状況をどう立て直すか。話し合いを持ちかけてもそのマネジャーは、これまで通りやっているので問題ない、と言うばかり。さらに、成績が落ちているのは社会情勢の変化であり担当部門の問題ではない、経営が考えるべきことだ、と主張。ならばと、経営側から具体的な提案をしてみると、現場を知らないくせに…と言わんばかりに嘲笑しつつ「だったらこんな時はどうしますか?教えてください」などとその提案を潰しにかかる。さて、このマネジャーに失格の烙印を押す前に、どうすれば「相乗効果を発揮する」段階に持っていくことができるのか…。おそらく、「信頼残高」がゼロまたはマイナスになっていることがそもそもの問題だし、相手のせいにするばかりで自分ができることを見出そうとしていない。相手を理解する努力も足りない、相手とのWin- Winもまったく考えていない、等々、著者には散々言われそうな気がする。第一から第六の習慣まで、何ひとつできていない状況だと…。だけど正直に言うと、「何も変えたくない、何もやりたくない」人物とどうすればアイデアをぶつけ合えるのか、信頼残高を積み上げていけるのか、この本の内容を実践できるのか、今の僕にはイメージができない。どうしたら良いのだろう…いよいよこの本から落ちこぼれてしまったかな…と思いつつ、いよいよ第七の習慣に進む。
February 1, 2025
コメント(0)
全6件 (6件中 1-6件目)
1










