2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2005年08月の記事
全16件 (16件中 1-16件目)
1
-

★ 安井三吉 『帝国日本と華僑 日本・台湾・朝鮮』 青木書店(新刊)
投票先を考えるためにも、大切な外交問題。本日は、華僑世界の成立と、日本の外国人政策について、とりあつかった研究書をご紹介いたしましょう。工業化、植民地労働力、黒人奴隷労働の廃止、蒸気船などのプル要因と、人口増加などのプッシュ要因でおこった、膨大な華僑の流れ。江戸時代、長崎では福建省出身者の同郷グループが作られていた。日本の開国後は、神戸などに福建・広東・三江の同郷グループが進出して、「開国はアジアへの開国」といわれるほど、アジア向輸出入を支配したという。驚くべきことに、日本の華僑対策は、江戸幕府の鎖国以来の施策に変化がなかったらしい。1894年、日清戦争によって清国の領事裁判権は廃止され、条約改正後は外国人に内地雑居が認められるものの、● 窓口地域・居住地域を限定する● 商人は受け入れるが、労働者は受け入れないという方針を一貫して華僑にだけは採用し、旧居留地・雑居地に居住を制限していたという。また、製造業への参入と土地保有は禁止されていたらしい。20世紀初頭、華僑の指導層は、日本国籍をもち、協調・定着化傾向を示していた。それが、1910年代以降、日本の侵略による日中関係の悪化にともない、華僑の民族意識は高揚してゆく。第二次大戦、神戸華僑は弾圧された。また華僑は、「反日」を強める南洋華僑の日本支持へ転換させる働きかけや、汪兆銘政権支持などの戦争協力を迫られたらしい。● 労働者が8割をしめた、台湾華僑一方、台湾華僑は、台湾割譲後、住民が日本国籍に変更されたことから生まれた。総督府は、「南国公司」という請負会社をつくって、外国人とは異なる特殊な管理下に華僑をおき、開発に従事させた。また、華僑と台湾人の結合をおそれ、子弟の公立学校への編入も、華僑学校の建設も、認めなかった。1920年代、台湾人の社会運動の高まりに、華僑も「差別撤廃運動」がおきて、弾圧が加えられたという。戦後、台湾における華僑の消滅とともに、日本に「台湾出身華僑」が誕生する。1947年から、台湾出身華僑は、戦勝国民扱いになったエピソードも面白い。● 商人中心であるものの、労働者に農民が多い、朝鮮華僑当初、清国の領事裁判権におかれたが、日清戦争後、租界の撤廃がおこなわれても流入を続けたという。華僑は単身わたるものが多く、男女比は「10:1」。当初、朝鮮人の対中国移住もあって、日本国内と違い、無制限受入がおこなわれていた。そのため、万宝山事件にみられるように、中国の朝鮮人問題は、朝鮮の中国人問題に波及しやすかったという。低賃金・劣悪環境によって、ストライキが頻発したのも、朝鮮華僑の顕著な特徴。1920年代、日本人下層民の雇用問題から、朝鮮人の日本移住制限策がとられるとともに、朝鮮人の雇用問題のため、中国人の朝鮮移住制限策がとられるようになったらしい。また歴代中国政府の華僑政策も、詳細でたいへん参考になります。「海禁」によって棄民状態であった華僑も、1860年以降、海外渡航がみとめられ、1893年には帰国が許可されることになったという。それは、保護すべき対象、経済的力量を利用すべき対象として認識されたことを示し、在外領事館の開設など、さかんな華僑保護へむけた政策がとられたらしい。また、海外の中国系の人々に、中国人意識をもたせるため、国籍法で血統主義を採用するとともに、「父が不明、無国籍で、母が中国人」でも中国人とされた。そのため、二重国籍を容認する施策となって、今も居住国の民族主義と衝突しているらしい。 とはいえ、一番驚愕させられるのは、● 東アジア(日・朝)の華僑数は、華僑全体(4000万)の1%にみたない● 戦前は、日本人の中国・朝鮮・台湾向け移民数は、 中国人の朝鮮・台湾・日本向け移民数を圧倒していたという事実ではないだろうか。そのとおり。実は、日本や韓国は、華僑のもっともいない地域のひとつ、なのである。「強制連行」「徴用」の時代をのぞけば、日本人の朝鮮への移民数は、朝鮮人の日本への移民数よりも、多かったというのも知られていない事実ではないか。単純労働力の受入を拒否しておきながら、いったん労働力不足になると、強制連行でつれてくるのが、日本クオリティ。日本に強制連行した4万人の中国人への賃金は未払いのまま。それならまだ許せる(?)としても、なんと企業には「中国人労働者使役による損失」補償がなされたという。ボッタクリ企業、すげえ。心温まるエピソードであろう。個人補償について、ぐだぐだ後でいわれる理由がわかるというもの。なにより、「華僑」へ適用された、単純労働者流入コントロールが、現在の入管法に連綿と受け継がれているという指摘が、おもしろい。交流と共生の時代、少子高齢化に直面している現在、どうむきあうかは、歴史問題とともに問われているという。ただ、「内務省的入管」的移民観から、いきなり「交流と共生」を!といっても、共感を得るのは、難しいのではないだろうか。むしろ、日本人の活動ネットワークの広がりを説く中で、守るべき広範な利益の一つとして、そうした「共生と交流」を位置づけていく方が、受け入れられやすいのではないだろうか。21世紀、「中国の世紀」にどうむきあうのか。それを考えさせてくれる一冊になっています。お勧めです。評価 ★★★☆価格: ¥3,570 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Aug 31, 2005
コメント(6)
-

★ 珊瑚事件より深刻な<朝日新聞>虚偽メモ問題
マスコミで大きく騒がれた、朝日新聞の虚偽メモ事件困ったものです 朝日新聞社は29日、田中康夫・長野県知事らの新党結成問題について、田中知事の取材メモをねつ造し、虚偽の記事を掲載したとして、同日付で長野総局の西山卓記者(28)を懲戒解雇し、木村伊量・東京本社編集局長らを減給・更迭するなどの処分をしたと発表した。 記事は21日付朝刊2面に掲載された新党結成をめぐる「『第2新党』が浮上」と22日付朝刊3面に掲載された「追跡 政界流動」の2本。 同社によると、長野総局で県政を担当する西山記者は、亀井静香・元自民党政調会長と田中知事の会談場所について、田中知事から取材したような内容の情報を社内に報告。この情報を基に同社は21日に「両氏が長野県内で会談した」との事実と異なる記事を掲載。22日にも田中知事が「亀井さんも、郵便局を守れっていうだけでは選挙に負けますよ。サラリーマン増税反対とか、もっと言うことがあるでしょう」などと話したとする西山記者の虚偽情報を基にした記事を載せた。 23日の定例会見で、田中知事が「確認取材を受けていない」と指摘したことから、社内調査を実施した。西山記者は調査に対し「田中知事からこれぐらい聞けるんだというのを総局長に見せたかったのかもしれない。あとから考えれば功名心だったかもしれない」と話しているという。 その他の処分は▽金本裕司・長野総局長=減給・更迭▽脇阪嘉明・東京本社地域報道部長、持田周三・政治部長=けん責▽曽我豪・政治部次長=戒告▽吉田慎一・常務取締役編集担当=役員報酬減額10%3カ月。処分は29日開いた臨時取締役会で決め、田中知事と亀井氏側に謝罪した。同社は30日朝刊で「おわび」記事を掲載し、読者に説明するという。 ▽吉田慎一・朝日新聞社常務取締役(編集担当)の話 あたかも取材をしたかのような報告メモをつくり、それが記事になるという、朝日新聞の信頼を揺るがす極めて深刻な事態が起きてしまいました。田中康夫・長野県知事や亀井静香・元自民党政調会長ら関係者と読者のみなさんにも深くおわび致します。特別チームを社内に立ち上げ、傷ついた信頼の回復のため具体策を早急に公表します。 ■朝日新聞の発表内容要旨 社内調査によると、西山卓記者は長野総局長らを通して政治部から亀井、田中両氏が「(8月)中旬に2人が会っていた」という情報について情報があったら知らせてほしいと頼まれていた。 記者は20日、長野県塩尻市で開かれた車座集会で取材をしたが、国政に関する話は出なかった。その後、田中知事に対する直接取材をしなかったが、2人が長野県内で会談していたと知事から取材できたかのような虚偽の情報をメールにし、総局長や県政キャップ、政治部記者に送った。 発覚の端緒は23日、知事が県庁で開いた定例会見。知事は「亀井氏と会ったのは東京都内であり、長野県ではお目にかかっていない」「この件について朝日新聞記者の確認取材は受けていない」などと指摘した。 21日付朝刊の「長野県で会談」という部分と22日付朝刊の記事中、亀井氏と会談した知事が「亀井さんも、いろいろ大変かもしれないけど、郵便局を守れっていうだけでは選挙に負けますよ」などと話した、とされている部分が、いずれも虚偽情報に基づいていたことが判明。さらに、第2新党結成の前日に知事が「民主党だけでなくいろいろな政党に友人がいる」と周囲に漏らした場面や「郵便局守れだけでは」の見出しも、こうした虚偽情報に基づくものであることが分かった。 社内調査に対し、記者は「知事からこれぐらい聞けるんだというのを総局長に見せたかったのかもしれない。あとから考えれば功名心だったかもしれない」などと話している。(毎日新聞)これはとても深刻な問題です。これを、伊藤律架空会見や、珊瑚礁など一緒にすることはできない。比較にならないほど重大な問題です。3大全国紙の筆頭、朝日新聞の強みとは、なんといってもその強力な組織取材力です。これに匹敵するのは、天下のNHKか、読売新聞か、共同通信程度。他紙では、まるでお話にもなりません。今回、朝日新聞は、5箇所訂正するという。該当記事からみれば、中核を構成しているとはいえ、ほんの一部にすぎません。つまり、何十人もの記者をさまざまな箇所にはりつけ、取材メモをかかせて提出させて、あの記事は構成されていたことをしめしています。「時々刻々」など政局取材時の質の高さは、この分厚さにあるわけです。岩見隆夫、岸井成格などの大物記者の取材力に依存する毎日新聞。政治家にとりこまれ、ウェットな浪花節に堕してしまう読売新聞。その点、政局になっても比較的ウェットにならず、同時進行する政治劇において、その組織力とアンカーによって俯瞰的に追ってゆく、朝日新聞の政治記事のスタイルは、なかなか重宝するものがあったわけです。こうした組織取材というスタイルは、朝日新聞の政治面における、署名記事の少なさ、にもつながっているといえるでしょう(この点、毎日新聞以外は同じ)。組織力と署名記事の少なさは、表裏一体でもあるのでしょう。今回の衝撃は、その朝日新聞最大の「強み」、組織力とアンカーによって構成するスタイルが、モロ裏目にでてしまったことにあります。組織取材でも、やはり最後は記者に依存せざるをえません。その強みを支えていた組織力も、記者が蝕まれていてはどうにもならない。車体を動かす、タイヤがパンクしているようなものです。今回の朝日の失態は、そのことを示している訳です。悲しいかな、はっきりいって朝日の編集局は頭をかかえているでしょう。決定的な対策を打ちようがないからです。社内チェックといっても、取材源にあたれない整理部や校閲部では、真偽をチェックしようがありません。どこまでも、出稿元である「●●」部記者を信用するしかない。ヘタに一線記者を上層部が締めあげても、逆に士気をおとしてしまうだけでしょう。組織力を最大の強みとしていたがゆえに、今回の失態はあまりにも深刻です。縮小再生産・守りの姿勢に走っているがゆえに、今回の事態はおきたなどとはおもいたくありませんが、そう思わざるを得ないものがあります。荒療治ではありますが、やはり<原則署名記事化>以外ないのではないでしょうか。今のところ、組織取材の必要がない、スポーツ面や国際面にしか署名記事はありませんが、これを組織取材、アンカー署名にまでおしすすめてゆく。出世しないと署名記事がかけないという今のあり方は、ジャーナリズムとしての志をいだいて、入社してきた人々を満足させるものとはいえないはずです。入社したばかりの人々にも、足を使って取材させることを徹底的にさせるためにも、署名記事化は有効のように思えるのですがどうでしょうか。朝日新聞にもとめられているのは、強みを損なうことなく、ジャーナリズムとして再生することでしょう。一刻も早い立ち直りを期待したいとおもいます。人気ランキング順位
Aug 30, 2005
コメント(6)
-

★ 社会保険庁有志 『年金をとりもどす法』 講談社現代新書 2004年12月
総選挙でどの党に1票を投じるか。そのことをかんがえるために、とても大切な問題のひとつ、年金・福祉。本日ご紹介する本は、積立金の放漫運用とムダ使いで揺れている、年金についての新書です。2004年7月の参議院選挙以降、とんと聞かなくなった年金問題。とはいえ、何か一つでも、問題が解決をみた訳ではありません。戦後、与野党とも票田維持のため、特例だらけのバラマキ年金をつくりだした罪。自治労とノン・キャリアの団結によって、電算化すら自体すすまない、社会保険庁。25年以上の納付期間と免除期間によって、はじめて「1/2 or 1/3」の国庫負担を受けられる、非合理さ。扶助(福祉的要素=国費投入部分)と自助(保険的要素=保険拠出量部分)の曖昧さから、続出する年金への不満。これを読めば、ニュースの裏側に潜む、年金問題への理解が深まるとともに、あまりにもひどい実態に泣けてくることうけあいでしょう。とはいえ、これだけには、とどまりません。実践的な年金獲得戦略に徹している、この本書。相談に行く前に知っておくべきポイントが、抑えられています。● さまざまな職業パターン別に、年金相談にいく際の、ポイント解説● 公的年金制度の仕組● 日本の年金Q&A● 年金をとりもどす5大戦略とくに、最後の「特例」を利用した取りもどし方法は、たいへん面白い。15年の加入で、恩給や救済年金をもらいながら、「濡れ手で粟」の老齢厚生年金までもらう方法。25年収めなくても貰える年金。同棲する場合は、住民登録をしておくといい。国民年金と厚生年金のダブりに注意。不服審査制度を活用せよ。幹部になるほど年金制度はわからない。相談は朝か夕方に。会社辞める場合は、障害厚生年金や遺族年金を出させるためにも、健康診断を。老齢厚生年金の受給者の再就職は自営業に限る。40年すぎたら国民年金納付を中止せよ…アルバイトでも、常勤者のおおむね3/4以上の出勤なら、会社は厚生年金加入を義務付けられているらしい。請負契約社員にも、会社は厚生年金加入させて、保険料を負担しなければならないという。舅や姑に仕えても、嫁には未支給年金は支払われない。「繰り上げ」「繰り下げ」支給の損益分岐点はどこか? なにより、高度に発達した資本主義社会なら、法人所得が個人所得を上回るのは当然のことなのに、なぜ国民の頭数で算出する人頭割計算で負担がまかなわれ、正社員ではなくパートを雇い入れる企業の負担が、免除されてしまうのかという問いかけも面白い。豆知識にとどまらない、こんな横溢する問題意識だけでも、十分に参考になるのではないでしょうか。とはいえ。この本は、現制度を前提とした年金獲得テクニック術の教授に、もともと真価があるはずです。ところが、それは根本からひっくり返されてしまう。最後は、私的な「年金改革」案によって、締めくくられているからです。推奨される制度、年金の「2階建て一元化」。高齢者の貧困を防ぐため、「全額国庫負担」(税金投入)を軸とする≪最低保証年金制度≫の創設と、「保険料負担」による≪比例年金制度≫。この本のセールスポイントを無くしてしまう年金改革。それこそ、筆者も願っているという、この大いなるパラドクス。その良心は、なかなか心地よい。そして、あまりにも複雑怪奇すぎる年金の改革は、この国の多くの庶民の願いではないでしょうか。この提言に、我々はどう答えるべきなのか。その回答こそ、今回の総選挙で問われている争点のひとつといっても、まちがいありますまい。団塊世代のいっせいの退職を、2007年から迎えて、「待ったなし」になっている年金問題。このチャンスを失えば、とんでもないことになってしまう。ぜひ、ご一読の上、総選挙に参加してみてはいかがでしょうか。評価 ★★★価格: ¥735 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Aug 29, 2005
コメント(0)
-

★ 津田雅美『彼氏彼女の事情 21巻(最終巻)』花とゆめコミックス(新刊)
(ネタバレ注意!)どうにも、違和感が拭えないラストです。このシリーズは、20巻のレビューにも書いてみたので参考にしてください。そもそも20巻は、男3名がよってたかって水商売の女性1名を排除することで、安定した関係をむすびなおすという、すさまじく「情けないお話」でした。ここで、実際のストーリーは、ほぼ終っているといえるでしょう。最終巻は、その「落穂拾い」をしつつエンディング…ということなのでしょうが…浅葉秀明くんの中学時代の話は、とても面白い。浅葉くんは、女性を心底から必要としてくれている。そのため、女性からもてる。彼と付きあう女性は、きっと幸せになれるでしょう。しかし、浅羽くんは、付き合っても幸せになれない。だから、浅葉くんに告白することなく、友達のままでいることをえらんで、卒業していった一人の女性。それを丹念にえがいた、冒頭に収録された小品。正直、なかなか泣かせてくれた。うまいとさえおもった。違和感は、これがラストとどう絡むのか、わからない所にあります。ラストはかなり衝撃的でした。舞台は、16年後。35歳の浅葉くんは、宮沢雪野と有馬総一郎の娘、有馬咲良16歳に告白されてしまう。浅葉くんの「光源氏計画」炸裂!といった所です。浅葉くんは、有馬咲良を心底から必要としてくれている。そのためその咲良から愛を告白される。それはいいんだ。問題は、浅葉くんは、なぜ「幸せになれるのか」。そのまま卒業していった彼女と咲良の違いはいったい何か。それがまったく分かんないのだ。その「幸せ」について、浅葉曰く大好きな雪野と総一郎の娘だから当たり前かって、何ですかそれ。ぜんぜん、説明になっていないじゃない。だいたい、それ以前の女性は、「幸せ」をもたらさない女性だったのか?それなら、どうして、彼は心底から女性を必要としていたのか?とりあえず、その疑問を脇に置いておくとしてもです。欠如を埋めてくれる有馬家の娘に、喜びを噛みしめていた浅羽くん。なら、告白した有馬の娘は、どのように欠如を埋めたのだろう。これすらよく分からない。私の欠如は、浅葉くんに埋めてもらえる。だけど、私は浅葉くんの欠如を埋めてあげられない。私の欠如を埋めることで、浅葉クン自身の欠如を埋めるよう、浅葉くんに強いてしまう。それは、愛の欺瞞にすぎない。そのため、告白しなかった女性をえがいたのが、冒頭に収録された作品のはずです。浅葉君の欠如は、有馬咲良が埋める。だけど、有馬咲良自身の欠如は、浅葉はどう埋めるのか?「幸せになれるでしょう」と書かれているのは確かです。でも、どうやって。ここがさっぱり分からないので悩んでしまう。ここで浅羽くんの欠如を埋めることによって、有馬咲良の欠如を埋めることなど、あってはならない。それは愛の欺瞞ではないか。冒頭、浅羽くんに愛の欺瞞を強いるゆえに、身を引いた感動の女性の物語が、ラスト、有馬の娘が愛の欺瞞を選びとることで、浅葉が幸せになる物語に変質してしまっている。これは致命的におかしいのではないか。いったい、浅葉くんに告白しなかったあの女性の決断は、なんだったんだ…(初キスは浅葉くんだったけど)というか、愛の欺瞞を16歳の娘に強いていることを気付かない、そんなニブい浅葉くんを登場させるなんて、繊細な浅葉の大ファンとしては、断じて許せないのですけど…ストーリーテラーらしく、20巻を上回る衝撃のラストを用意してくれた。それはたしかに嬉しい。だけど、細部の微妙な味わいが、ずいぶん大味になってしまったのが残念。とはいえ、9年間、ご苦労様でした。評価 ★★★☆価格: ¥410 (税込) 人気ランキング順位
Aug 28, 2005
コメント(3)
-

★ 岩田規久男 『日本経済を学ぶ』 ちくま新書 2005年1月
本日は、現代日本の構造改革・経済政策から高度経済成長まで、はば広い実証的なマクロ経済分析をおこなっている、代表的なリフレ派研究者の本をご紹介いたしましょう。小泉構造改革の信任選挙をひかえる今日、とるべき経済政策を記していて、必見の書籍のひとつになっています。ポイントをまとめておきました。● 産業政策は、高度成長期にも機能していない高度成長は、貿易自由化による自由な競争の結果であった。産業政策・行政指導などの規制分野は、銀行などみても、まったく伸びていない。高度経済成長の終焉は、原油価格高騰ではなく、キャッチ・アップ効果の低下(クラフツ)と、「国土の均等発展」を名目とした地方分散・都心分散政策~「逆構造改革」(八田達夫・増田悦佐)~などによる、生産性の低迷が原因とされています。規制緩和や自由化は、アメリカの電力、イギリスの鉄道の事例にみられるように、「退出」という選択肢のない上下分離方式などの不適切な施策ですすめると、顧客の利益にならないらしい。● 「執行と監督」の分離が必要な日本的経営日本的雇用慣行、≪企業別労働組合、企業内訓練、終身雇用・年功序列賃金≫は、高い熟練と労使関係の安定化によって、労働生産性を高めるものであった。また日本企業は、能力別賃金制も柔軟にとりいれつつあり、90年代の不況と日本型経営は、無関係という。これまで、「所有と経営」の分離下でも株主と会社関係者の「蜜月」が続いたのは、経営目標がスケール・メリットとマーケット・シェアにおかれ、株主利益と経営者・従業員利益が相反しなかったためらしい。株式持合下、投資信託会社どころかメイン・バンクも、コーポレート・ガバナンスの機能をはたしてこなかったという。● ナショナル・ミニマムと「受益者負担の原則」をわけてゆく必要性 (責任取らない主体に任せない) 特殊法人改革は、道路公団、住宅金融公庫のみの不充分な改革であった。政府金融機関など、他の改革には手をつけられていない。「郵貯による民間金融の補完」は、マヤカシにすぎない。ナショナル・ミニマムを見直すとともに、どれだけそれ以外の領域に、≪受益者負担の原則≫を導入できるか。「国庫補助負担金」「税源配分」「地方交付税」の地方財政≪三位一体≫改革も、この点が郵貯と同様に、とても重要であるという。3割しか政策経費のない財政再建のためには、名目成長率をあげる重要性が強調されています。また年金については、賦課方式による世代間格差の問題のみならず、税金と保険の区別が曖昧なのも、問題のひとつとして批判されています。老後生活保護と企業税負担の2つの側面から、基礎年金部分への税金投入が唱えられているものの、消費税をあてるのは、税の公平性の観点からみて、やはり問題があるらしい。● バブル期における銀行の盛んな不動産投資は、 金融自由化よりも、企業の金融構造の変化(資金余剰主体化)にある● 日本経済の課題は、デフレからの脱却である土地神話によって、リスク分散=「卵をひとつのバスケットに入れない」を忘れ、不良債権をかかえてしまった銀行。90年代大不況の原因は、潜在成長率の低下でも、労働生産性の低下でも、「構造改革の遅れ」でも、「非生産的な公共投資」でもない。むろん、不良債権による「銀行貸し渋り」説も、追い貸しによる「優良企業締出・低生産性企業温存」説も、正しくないという。大不況は、「債務デフレ」=「バランス・シート」不況にほかならない。構造改革は、マクロ経済の不安定化をもたらす。必要なのは、マクロ経済を安定化させる政策である。それは、90年代のデフレ期待を根絶させる金融政策、量的緩和からインフレ・ターゲット(1~3%)への、政策レジームの転換とコミットメントに他ならない、という。この簡略な紹介からも、経済政策のさまざまな論点が、コンパクトにまとめられていることが分かるでしょう。悪いのは、独占。エンロン事件にみられる利益相反的行動への誘因は、市場ルールの整備で。環境問題は「市場の創出」で。このような「退出と声」戦略(byハーシュマン)が採れる≪市場競争の必要性≫は、なんども繰りかえされていて、考えさせられるものがあります。ほかにも、「70の法則」≪70を成長率や利子率で割ると、何年で倍になるかの計算法≫。土地と店舗を借りて経営したイトーヨーカドーと、土地値上がり益で経営拡大を行なった、ダイエーの差。バブル期、開発案件を提案し受注する「造注」に走って、地主の銀行借入の際、債務保証をおこなった建設業者の悲劇など、豆知識もたいへんありがたい。とくに、2001年、関係が断たれたはずの郵貯と財政投融資の≪腐れ縁≫は、総選挙の投票先にもかかわる、必見の部分ではないでしょうか。そもそも、融資先を探すインセンティブがなく、今ですら「財投機関債」はわずか。依然として「財投債」が発行されている現実は、政府保証が外れないままの改革とともに、小泉的郵政民営化の虚妄を的確に突いていてすばらしい。また、不況=低生産性企業温存説(だからダイエーなど不良債権企業は清算されるべき、につながる説)は、供給能力と需要の差=≪GDPギャップ≫が解消されない限り、高生産性企業従事者と失業者を生んで、社会全体では生産性を低下させるだけの≪合成の誤謬≫にすぎないらしい。バッサリ謬論を切り捨ててくれるさまは、痛快至極であります。いささか残念な部分は、プライマリー・バランスの前提となる、国債発行残高と純債務の違いが書かれていない所でしょう。とはいえ、もっとも感動的なのは、 すべての労働者を本当に保護するのは、労働組合でも、雇用保険でも 労基法でもなく「求人競争」であり、所得格差を縮小させるのは、 所得再分配ではなく経済成長であることをキッパリとのべている部分ではないでしょうか。経済の語源、「経世済民」の学にふさわしい、近年忘れられがちな、守らなければならない最後の一線の提示。総選挙への一票を投じる前に経済をかんがえておきたい貴方に、お勧めの一冊といえるのではないでしょうか。評価 ★★★☆価格: ¥819 (税込) 人気ランキング順位
Aug 26, 2005
コメント(3)
-

★ 新井孝重 『黒田悪党たちの中世史』 NHKブックス (新刊)
素晴らしい。一読後、感動が止まりません。本日は、井沢元彦や自由主義史観など、トンデモ歴史観に洗脳された人々にむけて贈られた、格好の解毒剤をご紹介いたしましょう。日本の中世闘騒と自力救済が横行する中で、「平和」をうちたて「公」を創出する手続きとしてむすばれた、水平的原理の盟約=≪一揆≫。これを国家的な「公」秩序に回収しようとする、戦国大名勢力。この中世社会における≪一揆的構造≫の出現と崩壊について、伊賀国名張郡東大寺領黒田荘の定点から描きあげた本書は、壮大な叙事詩の趣さえ感じさせます。これが面白くないはずがありません。このブログをお読みの方々のため、豊穣な内容を簡潔にまとめておきましょう。● 「私物化」の危機にさらされていた中世的荘園東大寺領内の杣工は、公領にむけて、所領・住民の一体支配を妨げる、さかんな≪出作≫(他所領耕作)をおこなった。また、公領荘民は、雑役から逃れるため、または国衙に結集する武士に対抗するため、出作民と≪所従・因縁≫などによって結合し、寺門の下に身を寄せていった。それが、公領百姓の「寄人化」、公領の「寺領化」をもたらしたという。1174年、黒田荘の一円寺領化(私領の取得と公領の支配権引渡し)は完成をみた。● 僧の私生活の肥大化がおこした、寺院の荒廃奈良時代以降、寺僧は三面僧坊から出て暮らすようになり、本尊は荒廃の一途を辿った。その荒廃した寺院の修造のため、僧の自覚的な結集が促され、東大寺の中世寺院への脱皮と荘園形成がはじまったという。もともと、僧は学問と修行にいそしむのみで、俗務にタッチできなかった。寺僧≪大衆≫は、荘園の寄人・荘民と結合して、政治的膨張をとげた。平安期にみられる、比叡山などの大衆運動≪嗷訴≫は、わが国最初の≪一揆≫であるという。その在地出作民・荘民のエネルギーをすいあげた大衆運動、≪嗷訴≫の発展は、平氏による南都の焼き討ち(1180年)をひきおこすほどであった。● 一揆の「集団性」「水平性」の原理は、 寺僧大衆の集会「満寺一揆」の形式が移植されたもの一揆の正当性は、その主張の内容如何にはなく、全員一致、≪一味同心≫にあるらしい。≪一味同心≫に神の意思、正当性のあらわれをみる貴族たちは、≪嗷訴≫をおそれたという。中世寺院は、「衆議」「一味同心」によって、寺院経営や荘園管理などにも自治がおこなわれていた。寺の「衆議」と村の「衆議」がかさなる所に、共同体としての荘園、が出現したという。● 遺言は、救霊と生存中の財産の享受を結合させるためにむすばれる、 遺言者と神の代理人との保険契約であるという平安から鎌倉にかけて頻発した、天変地異と飢餓・疫病。それは、「往生」を保証する浄土教の普及や燈油聖の出現をもたらして、死体「打ち捨て」から「埋葬」へと、死のあり方そのものを変容させてゆく。そうした変容にともない出現した「寄進」は、自分への供養のためにおこなう冥界での保険であり、病者と大仏の間をとりもつ「燈油聖」を介して、東大寺へと田土がながれこんだ。また浄土教の普及は、俗名から法名(阿弥陀仏号)へ、黒田荘の住民名の転換さえもたらしたという。それは、仏への結縁をもとめるパトスのあらわれとともに、呪詛をふせぐために実名を伏せていたらしい。● 悪党の出現と荘園制度の解体寄進された「作手」は、荘園制度外におかれた、領主権とも身分関係とも関係ない、市場売買可能な「収益権」であった。作手(=地主支配)の拡大は、荘園内荘官の既得権を縮小させて≪悪党≫の出現をまねくとともに、≪名主≫(-下人関係)から「地小作関係」に再編させ、荘園の解体と≪郷(村落)≫をうみおとしてゆく。荘園外の庶民経済の発展は、流通・交通にたずさわる前期的資本家たちの活動によって、住民が荘園外に個別的にネットワークを形成することをおしすすめてゆく。荘園制度による地域秩序は融解して、「悪党化現象」を惹起したという。● ≪一揆≫による寺院・村落全体意思形成の高度化と、 自力救済の否定の先に出現した、武勇の徒「悪党」鎌倉末~南北朝時代、惣領の一族統括権の衰退は危機感をうみ、分割相続から単独相続への転換、庶子・非一族縁者の「主従化」をおしすすめ、「国人領主」の出現をうむ。ところが畿内では、本所(=寺)権力と百姓にはさまれて封建権力に成長できず、個別・孤立した武装民段階に止まったという。惣寺の直接的支配は、地主としての性格を強めていた寺僧と在地との結びつきをつよめ、≪嗷訴≫を模倣した在地の「一揆」を生み、惣寺の経営をゆるがしていく。「全体」に収まらぬ武勇の徒は、幕府の法治主義と対立し、寺院・村落の「全体」からはみだした武装民と結合して「悪党」となって対峙した。彼らは、銭の力を背景にして、新興勢力を形成したという。● 戦乱の伊賀と中世の黄昏南北朝の内戦は、全国を股にかけた土地から遊離した軍事勢力となって、遠隔地間の所領経営を不可能にさせ、所領を一つに集中させる「国人領主化」の道を切り開いた。15世紀名張郡黒田荘は、八幡宮所領に移るものの、寺僧私領の「≪地子米≫納入停止」=「都市-住民」の個別ネットワークの清算を介して、村落としての「地域自立化」の道をたどってゆく。1560年~81年までの間、伊賀の地侍たちは、「惣国一揆」=コミューン体制をつくりあげたものの、織田信長の伊賀侵攻によって、惣型(水平型)の民衆結合、中世的世界そのものが終焉する。 元来共同体の権利だった山川藪沢の狩魚猟民の活動。それが、「供御人」身分の成立とともに、貢納と引きかえの権利として、守護者に天皇が立ち現れ、周囲に営業権を主張してゆく。鮎の「押し鮨」のお話、「悪」の意味の変遷など、随所に庶民生活がうかがえるのも、すばらしい。むろん、この書における、ある種理想化されたかのような、中世的自治の把握を批判することは、たやすい。ここで示された、中世的水平(惣的)結合と、近世的な垂直結合。その対称性は、どれほど、自明なものと言えるであろうか。コミューン同士は、またはコミューン主要成員同士は、水平的であるかもしれない。しかし、そこには、垂直的な関係が、わかちがたく附属しているであろう。そもそも、兵農分離によって、地侍を追放した近世村落こそ、≪惣≫的な水平的結合の完成形態とさえ、いえるのではないか。その疑念とあたかも符合するがごとく、中世における侍と農民の身分的差異の変遷・流動性については、あまり描かれていない。いささか物たりない。とはいえ、古代から近世までの、土地所有権の重層的な形成・展開過程中世寺院・村落社会における自治の展開過程この2つの展開過程が有機的にむすびつき、黒田荘を介して中世社会が照射されているのは、実に嬉しいではないか。おもえば、戦後日本中世史学、否、戦後歴史学の出発点は、東大寺領黒田荘において武士と荘民の成長過程をえがいた、石母田正『中世的世界の形成』(伊藤書店、1946年)であった。中世の山村に、ある種のコミューンを見出して、原基的な日本、日本の伝統と重ねあわせてきた、日本の中世史研究。その莫大な研究蓄積にもとづいて描かれた、中世の寺僧と民衆の世界の面白さ。おそらく、この分野における、屈指の概説書ではないでしょうか。図書館や本屋で確認・お求めになったうえで、ぜひお読みいただきたい一冊になっています。評価 ★★★★価格: ¥1,176 (税込) 人気ランキング順位
Aug 24, 2005
コメント(0)
-

★ 徐京植 『ディアスポラ紀行』 岩波新書(新刊)
一読後、落胆が止まらない。いったい『世界』は、どんなつもりで、この人に連載させたのだろう。ディアスポラ=離散民。原義は、ユダヤの離散民。「祖国」(祖先出身国)、「故国」(自分の生誕国)、「母国」(現在国民として属している国)の3者が、分裂した存在。1947年、母国がない中で、日本国籍を失った存在≪在日朝鮮人≫。韓国軍事政権下の政治犯で獄中闘争をおこなった兄2名をもつ、母語が日本語、母国語が朝鮮語の在日二世。その彼が、世界各地をまわりながら、その地の出来事や文学・アートに、暴力と離散と、死の痕跡をさぐる紀行文。もともと、期待して読まないはずがない。日本ではなかなか見えない、≪在日朝鮮人≫。「パーリア」(被差別者)の位置にあった、先人の生き方にたちたい。にもかかわらず、分裂するアイデンティティは、強烈な上昇志向に駆り立て、「死」が「肩の荷をおろす」こと、と言われるような生き方を強いられてしまう。かつて在日と韓国の同胞が、民主化運動を通し≪合流≫することを夢見た筆者その願いは、果たされることはない。1970年代、民主化のシンボルであった詩人金芝河が、≪朝鮮民族=聖杯民族≫を唱える国粋主義へ転落したことをなげき、芸術にまで国境をもちこみ、国家の枠組強化に奉仕してしまう美術批評を悲しむ。「地上の楽園」などではないことを知りながら、「宙釣り」を停止させるため、北朝鮮へ帰還していった在日芸術家の悲劇。筆者は、朝鮮人を引き受けることにためらう。「光州事件」のモニュメント群にも、韓国ナショナリズムにも、こぼれおちてしまう「何か」を感じて、ためらう。そして、犠牲者の墓苑を、在日を、ディアスポラであることを、選びとろうとする筆者の旅は、過去への告別の旅であるかのようだ。アウシュビッツの極限の環境で、自らが「証人」「人間」「イタリア人」であることを確認した、イタリア系ユダヤ人、プリーモ・レーヴィ。自らを支える「母文化」が、ナチスにのっとられた、ドイツ系同化ユダヤ人、ジャン・アメリー。両親を殺した者たちの言語で詩を書き続けた、東欧のユダヤ人、パウル・ツェラーンフランツ・ファノン、サイード、アーレント、シリン・ネシャット、ザリナ・ビムジ…ディアスポラを生みおとした「近代」そのものを尋ね、さまよう。とはいえ、随所に違和感がぬぐえない。徐京植は、ディアスポラでは断じてない。どうして彼は、「在日朝鮮人」というシニフィアンに、自己の実存をとっくの昔にゆずりわたしておきながら、自分がディアスポラであると思えるのだろうか?その不快感は、NHK番組制作の際、ディアスポラの意味を理解させるため、フェリックス・ヌスバウムの絵『ユダヤ人証明書をもつ自画像』のポーズを真似て、外国人登録証をかざすエピソードでピークに達した。「在日朝鮮人」をユダヤ人になぞらえようとする、その欲望のおぞましさよ。ツェラーン、アメリー、レーヴィ…。かれらディアスポラがいつ、「○○系××人」として自己を形成したのか。ふざけるな、とさえ思う。葬式をめぐる、「死者の国民化」の一節。かれが、非「在日」としか日本人を表象しないのは象徴的だ。それは、日本人が在日を非「日本」と表象することとパラレルであろう。「否定」を通してしか、出現することのない主体≪国民≫。かれは、「在日」のシニフィアンに自己をゆだねたまさにその瞬間、それが「日本」というカテゴリーをつくりだし強化する行為でもあることに気付かない。マルクス主義も自由主義も答えない、生の「有限性と偶然性」からくる不安。それを「連続性と有意味性」に変換することで、個人の生の意味を回収する装置、≪不死の共同体≫ナショナリズムを鋭く批判しながら、自己が「在日朝鮮人」という形で≪共犯者≫になっていることに思いいたらない。在日2世文承根と1世李禹煥のアートの差異に気付きながら、「在日朝鮮人」のカテゴリーでくくられるおかしさに思いいたらない。在日「女性」がまったく取り上げられていないことは、その例証であるかのようにおもえてならない。ディアスポラは、近代国民国家の先に、血統でも文化でもない、国境にも区切られない、理不尽の起こらぬ「真実のくに」をさがしもとめるという。ディアスポラこそ、近代以後の、生の先取りであると語る。その確信は美しい。とはいえ、ゾーエーたるディアスポラのビオスへの渇望こそ、国民国家が行使する「生権力」の存立条件の一つではなかったか。その意味で、ディアスポラの戦いは、どこまでも絶望的である。美しい、どこにもない、「真実のくに」という、酷薄なユートピア。それへの希望を語って、筆がおかれる。この書は、ただの「在日朝鮮人紀行」として書かれるべきだったように思えるのは、私だけであろうか。評価 ★★価格: ¥777 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Aug 19, 2005
コメント(8)
-

★ 2つの「百合」の差延 今野緒雪 『マリア様がみてる 薔薇のミルフィーユ』(7月新刊) と竹本泉 『さくらの境』(6月新刊)
先日、百合姫の創刊を寿いだ際、ブログで語りきれなかった部分があった。本日は、コミックの新刊紹介もかねて、それについてとりあげておきたい。それは、男の欲望、「萌え」としての百合について、である。そもそも女性は、子供から大人へと成長する過程で、男性よりもはるかに切実に、自らの性にむきあわざるをえない。それは時に、男性などとくらべ、あまりにも理不尽な形であらわれてしまう。そうした特性こそ、少女漫画という特異なジャンルを成立させるとともに、異性間交遊にともないがちな、異性間の理不尽な「非対称性」が慎重に排除された、ある種「純粋な関係性」としての恋愛物、「ボーイズ・ラブ」をうみおとす原動力になったといえるでしょう。むろん、異性間の理不尽な非対称性を排除するためには、なにも男性のみが登場人物である必然性は、どこにもありません。ここに、ボーイズ・ラブの裏側に、「百合」というジャンルの出現がもたらされることとなった。これらは、遊鬱様のブログでも論じられています。ぜひ、ご参考にしてほしい。なにより「ボーイズ・ラブ」も、「百合」も、女性が、女性であることによって、傷つくことはない。「純粋な関係性」「女性の傷つくことのない」百合というジャンル。ところが、近年の百合ブームと受容は、男性を中心にすすめられてきた。ここで、男性的な百合受容の典型として取りあげたいのが、冒頭の画像でごらんになっている、竹本泉『さくらの境』(メディア・ファクトリー)でしょう。まさしく、男性にとっての百合とは何であるか、その典型的な作品になっているのです。登場人物は、女子高生の3人と猫10匹(あと、翻訳家)。彼女たち(といってもカップルはそのうち2名だけど…)は、悩まない。「自分が百合であること」に対して。ノホホンと、ひたすらイチャイチャ。(竹本泉の芸風なんだけど…)本当にそれだけなのです。なにより竹本泉がこの作品を描いた理由は、「百合ブームだから」らしい。さすがに、『あおいちゃんパニック』以来の熱烈なファンの私でさえ、この安直な姿勢には、激怒してしまった。「トウィンクルスター・のんのんじー」「トランジスタにビーナス」でもそうだが、女の子が抱き合っていれば、それが百合とでもいう気なのでしょうか??所詮、男にとって百合とは、可愛い女の子(=萌え)がいちゃつくだけ、なのだろう。そして、融合的一体化の悦びを、味あわせてくれるものなんだろう。だからこそ、コインの裏側、「ボーイズ・ラブ」に目が向くことは、決してない。それと、まったく対照的なのが、現在の百合ブームの先駆けとなった、これ↓今野緒雪『マリア様がみてる 薔薇のミルフィーユ』(集英社コバルト文庫)でしょう。このシリーズの総評は、かつて「悦び」がいざなうファシズムで論じてあるので、今回は新刊のみをあつかいます。今回の新刊も、また、とても素晴らしい。とくに第三章。遊園地でデートする、赤薔薇姉妹のお話が絶品のできばえ。赤薔薇様の婚約者でありながら、それを解消させた柏木さん。それはホモを婚約者に告白することで解消させたわけなんだけど、実は彼は…悲しいのは、祐巳さんも、柏木さんも、決して報われることがない。両者とも、それをきっちり自覚している所まで悲しい。どこまでも、優しくて泣けてくる。百合をめぐるの2つの方向性「純粋な関係性」「女性の傷つくことのない」楽しみと、「萌える女の子」「融合的一体化」の楽しみ。そこに差しこむ、ボーイズ・ラブという問題系。「百合」の商品化の過程で、消費者(おもに男性)の欲望にあわせてまぎれこむことになった後者は、決して夾雑物とはおもわない。圧倒的な同人活動によって、もはや商品化自体、同人活動の氷山の一角に過ぎない、「ボーイズ・ラブ」。それとは、ことなる状況下におかれたに「百合」にとって、こうした共犯関係をとりむすぶこと自体、商品化するための撒き餌なのかもしれない。そもそも、何らかの形で商品化されることを通してしか、ジャンルの存続はありえないのだから。こうした、未分化のジャンルには、かけもち作家も多い。ボーイズ・ラブと百合姫に描いている影木栄貴(竹下登首相の孫で有名)は、その代表といえるでしょう。だからこそ、願わくは、ボーイズ・ラブの影・落とし子に止まらない、「百合」というジャンルの方向性にしかかけない「何か」に、一刻もはやくチャレンジしてほしい。あれほどまで女性の望んだ、女性が傷つくことがないジャンルでさえ、「可愛い女の子」という存在を通して、収奪してしまう男性社会。それからの一刻も早い独立こそ、望まれているのだから。たぶん。人気ランキング順位追伸 ● 竹本泉『さくらの境 1巻』MF(メディア・ファクトリー)コミックス評価 ★★価格: ¥580 (税込) ● 今野緒雪『マリア様がみてる 薔薇のミルフィーユ』集英社コバルト文庫評価 ★★★★価格: ¥420 (税込)
Aug 17, 2005
コメント(2)
-

★ 洪夏祥(宮本尚寛 訳) 『サムスン経営を築いた男 李健煕(イゴンヒ)伝』 日本経済新聞社 2003年11月
本日は、三男でありながら韓国GNPの2割を稼ぐ財閥を引きつぎ、トヨタ自動車にも匹敵する純利益1兆円(≠100億ドル)のサムスン電子を創業した、李健熙をえがいた本をお薦めします。これがなかなか渋い。DRAM、SRAM、cdma式携帯電話、TFT液晶ディスプレイ、モニター、電子レンジなどで、世界シェア1位のサムスン電子(2002年)。その原動力は、アメリカに5年間放浪し東京に2度7年留学した、李健熙現会長の桁違いのパワーと思索にあったことがよくわかるでしょう。・ エンジニアとして機械を分解するのみならず、犬育成から歴史にいたる まで、なにごとにも専門家レベルになるまで止めない探究心・ 父・李秉吉吉の残した「傾聴」「木鶏」の精神にならう・ 「一石五鳥」「1人の技術者が10~20万人を養う」にみられる、 シナジー効果の推進と、人材育成の極端な強調・ 「妻と子供以外のあらゆるものを変えろ」をとなえ、 重病だった企業文化の一大変革に邁進・ 「管理のサムスン」とよばれた秘書室制度の解体と、「集積化」推進・ 企業分割と、集権型から分権型経営への転換・ GE、SONY、モトローラなど、世界一流企業の方法を徹底的に調査分析…「量から質へ」長時間におよぶ大会議で、今現在にうけつがれるこの経営方針に転換させた際、「変わりたくない人は変わらないでいい。衣食住は保証する。足を引っ張るな」などとは、なかなか言えるものではありますまい。また、社員の自己啓発のため、「7時出社、4時退社」制度の創始などをふくめて、随所に李健熙の経営に関する独創的な考え方が光っています。また、「サムスン用語集」「サムスン・マニュアル」の存在も面白い。トヨタなど真の一流企業は、世間とはまったく異なる体系をもつため、用語も独自になってしまう証なのかもしれません。他にも、国家に様々な企業を献納させられた軍事政権下の三星財閥の悲哀や、一方的に良い製品の生産を被支配者に強要して対価を払わなかったため、磁器技術を途絶えさせた悪しき韓国(李朝)の伝統など、韓国に関する豆知識も、実に豊富でおもしろい。最後に収められた、李健熙の人となり・日常生活・経営哲学だけでも、かなりの成功の秘訣が拝めてよい。経営書としては、かなりよくできた本といえるのではないでしょうか。 むろん、サムスン電子の「選択と集中」経営の成功の影には、1997年の経済危機とIMF進駐によって、三星財閥が電子、金融、化学・重工業の3分野に再編・整理・売却させられたことがあるでしょう。サムスンは、移動通信関連、半導体設計、動画圧縮、システム・インターフェース技術など、基本技術で遅れがめだちます。テコ入れがおこなわれたはずの技術部門は、成果をあげたとはいいがたい。基幹技術の外注は、ブランド・イメージをそこない、ロイヤリティをかさませてしまう。むろん、筆者のみならず李健熙も、そのことに警鐘を鳴らし、さらなる人材育成によって、この難関を突破しようとしている。ただ、基幹技術の依存は、むしろ新製品の開発力を衰えさせかねないことがほとんど述べられていないのはマイナスでしょう。その意味で、「ソニー・ショック」以降、日本では非サムスン・モデルへの回帰が、家電分野などでは始まっています。分業を極端におしすすめることが利点につながる、現在の経営環境にもっとも適応した、サムスン電子の「選択と集中」経営。それを可能にした、変化の速い21世紀型のエレクトロニクス産業。その選択が吉とでるか、凶とでるか。本書は、そんなことを考えながら読むには最適の書といえます。評価 ★★★価格: ¥1,680 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです 追伸 大阪金剛組って、本当に西暦578年に創業した会社なんだろうか…
Aug 14, 2005
コメント(1)
-

★ 小菅信子 『戦後和解』 中公新書(新刊)
戦争のあと、訪れる和解という発想。人はいう。過去を痛切に認識して、未来を建設しよう、と。人はなぜ、半世紀前の苦痛の記憶をいつまでも忘れないことで、平和の強化がもたらされると思えるのか。いったい、この一見矛盾した言説・思想は、どのように出現したのか。● 戦後和解は、「講和=忘却」が破綻した所にあらわれた、 歴史的現象であること。● その和解のためには、加害と被害をめぐる善悪の「線引き」と、正義・ 不正義の「バランス」がもとめられていること。● 現在、中国とドイツは、被害と加害、立場こそ違えども、 今や戦後平和構築パターンとなった「和解」の精神に、もっとも忠実な 国家であること。切れ味はおや?っとおもわせる鋭さである。一読をお薦めしたい本のひとつです。古代社会では、戦後=復讐であったらしい。キリスト教世界では、正戦論と騎士道で無差別殺戮を制限するとともに、講和の際には、戦争の悲惨さを神の御前で認め合い、「妥協」のため被害を忘却することがおこなわれていた。ところが19世紀、社会の世俗化、民主化、ナショナリズムの発達、国際法の形成の流れの中で、講和とともに敵をゆるし、悪行を忘却できなくなったという。それは、第二次大戦後、ニュルンベルク・東京裁判の、勝者が敗者の悪行を裁き、敗者を再教育するスタイルとなって完成する。ただ、ここで忘れてはならないのは、無罪・有罪の「線引き」をおこなうことによって、有罪人を殉難者にすることなく、憎悪に身をゆだねがちな戦勝国民と無罪の敗戦国民との間で和解を促すため、裁判が存在することだという。その意味で1978年、靖国神社へのA級戦犯合祀は、日本側による致命的な≪「戦後和解」の否定≫に他ならない。こうした「過去を直視しない日本」は、原爆(無差別爆撃)や植民地支配が裁かれなかった東京裁判のもつ二流性と、日米和解のみが「冷戦」によって進んだため、もたらされたものらしい。原爆は、反ユダヤ主義を監視するイスラエルと同じ、核保有国を監視する立場にたたせたためという指摘も、うなずかされるものがあるでしょう。「線引き」と「バランス」ゆえに高く評価されたドイツ。それと正反対だった日本。そのため、米国以外との「戦後和解」は、まったく進まなかったという。オランダ・カナダ・イギリス・豪州軍兵士への捕虜虐待は、欧米でステロタイプの反日世論をつくりだして、1980年代まで執拗な日本批判が繰りかえされた。とくにイギリスでは、捕虜たちの激しい日本批判は、アジア戦線で戦った兵士たちのおかれていた社会的位置とも、かかわりがあるらしい。これが変貌するのは、1990年代になってからのこと。両国間の民間交流こそ、その流れをかえ、1998年の橋本謝罪を受け入れさせる前提をつくったという指摘も面白い。戦後平和構築のパターンとして普及した「戦後和解」の思想の精緻な追跡。1995年、村山談話は、東京裁判で裁かれなかった植民地支配の加害性をみとめる、画期的なものであったこと。戦争を煽るとともに監視もする、ジャーナリズムのもつ「両義性」を指摘。ほかにも、高名なドイツの莫大な賠償措置は、ナショナル・アンデンティティと密接にからんでいたこともさることながら、ドイツ統一まで国家間賠償をおこなえなかったためなど、随所に小技も効いていて、とてもおもしろい。いささか難点をいえば、中国政府と一般大衆の関係、中国の姿勢変化(本当にあったのか?)などについて、平板な分析にとどまっている点でしょうか。その平板さは、分かったような気になって、書いているだけではないかという疑念をいだかせかねない。とくに、「バランス」と「線引き」、「和解」など、主体によって内容を異にする曖昧なシニフィアンで、戦後平和構築のパターンを切り取るのは、結局、何も言っていないことと同じではないか、所詮和解とは≪誤認≫でしかないのではないか、という疑念がぬぐえない。とはいえ、1990年代から2005年にかけて、イギリスと日本でおこなわれた「和解」の実践は ――― 過去の戦争によって引き裂かれた者たちが、未来の平和と共生を誓う ――― 感動的ですらある。ナショナリズムにもとづいた記憶ゆえに、今も「線引き」と「バランス」による戦後和解(東京裁判と死刑なしのBC級戦犯裁判)の忠実な信奉者として、靖国神社参拝に過敏に反発せざるをえない、中国。中国との和解には、どのような展望があるのか。困難を認識しながらも、その暗闇にさしこむ、一条の光。それが何であるかは、ぜひ、手にとって読むことで、確認してもらいたい。評価 ★★★☆価格: ¥777 (税込) 人気ランキング順位
Aug 12, 2005
コメント(6)
-

★ 興梠一郎 『中国激流 13億のゆくえ』 岩波新書(新刊)(2)
(承前)● ラテンアメリカ化(発展途上国の市場経済化失敗)とソ連化(社会主義国の市場経済化失敗)のリスクにさらされる中国中国版バブル経済問題は、過剰銀行預金による預貸利鞘の縮小から、不動産投資拡大によってひきおこされたものの、政治システムそのものに起因している。地方政府は、出世競争からGDPを引きあげたいため、自ら賄賂や企業経営をおこなっているため、中央に従わない。消費力の弱い中国は、銀行融資と国債による、投資主導型成長にならざるをえない。投資過剰による過剰生産は、企業利潤を直撃して、証券市場低迷から銀行依存が深まっており、銀行の不良債権比率は4割におよんだ。金融と財政は、今後も中国が成長を続けられるのか、最大の不安要因となっている。その半面、軽工業・化学・医薬品・電子・機械において、マイクロソフト、テトラパック、ミシュラン、ノキア、モトローラ、コダック(シェア5割)などにみられるように、外資の市場独占は独占禁止法導入が検討されるほど加速している。工業生産高の3割、輸出入の5割は外資系。中国産業の自主技術開発能力は、欠如していて、中国には全要素生産性の向上がみられない。● 民主化の模索民主化デモこそ起きていないものの、自治意識が高まっている。行政の肥大化と腐敗の温床であった「請負」統治の末端部、居民委員会は機能マヒして、統治能力を失いつつあるためだ。共産党の推薦候補以外の自薦候補が人民代表大会に出現。人民代表の造反による不指名。郷鎮政府のトップを民選する動きや、5万件もの陳情などがまきおこっているものの、共産党が多数派を形成する方法の歪みは消えていない。8000万ものインターネット人口とメディアの活発な活動は、世論を動かし、権力をおそれない体制内知識人なども登場しているという。中国社会は多元化しつつあり、硬直化した政治がもたらした「改革」の歪みをめぐって、左派(計画経済)と自由主義派(欧米型統治システム)の論争がまきおこっている。ただ、真の解決には、一党独裁放棄と民主化というダブーにふれないわけにはいかない。活発な「草の根」の抗議行動は、体制内民主派など民主化につながるかは、いまだ予断できないという。これらの要約からみても、この本がどれくらい、中国社会の現実に対して、きびしく正確に分析ているか、みなさんも理解することができるのではないでしょうか。中国の比較優位は、あくまで、最終組立工程における低賃金と錬度の高い労働力にあるだけに、ラテンアメリカ化するのではないかという恐怖は、相当のもののようです。今では、かつての発展をささえた開発独裁は、制度疲労もはげしく、経済発展の足をひっぱりはじめているという。ただ、いささか残念な点をのべるとすれば、楽観論と悲観論を棚上げにして中国の現実を見極めようとするあまり、中国イメージの分裂がおきる肝心な所が、ややボカされてしまっている感がある部分でしょうか。「悲観的な材料が多いにもかかわらず、なぜ経済発展が続くのか」「ひどい政治体制なのに、なぜ政治体制が永続しているのか」悲観論は、なぜ「今」、中国経済が発展しているのか、なぜ「今」抑圧的な政治体制が永続しているのかを説明できない。だからこそ、その回答は、つねに外在的なものとして語られてしまう。曰く、外資。曰く、強権的な公安権力による弾圧と、愛国教育。そして、いつかは中国の発展がとまり、中国が崩壊するんだ、と呪文のような言説がたれながされ続ける。あらかじめ、いつ、なぜ、どのようにその事象が起きるのかを言わないまま、そんな予測をすることに、いったいなんの意味があるのだろうか。(いつかは発展はとまり、崩壊するに決まってる)ここから見落とされてしまうのは、その一見非合理なことを可能にする原因は、つねに「内在」されており、一見「非合理」なものは、別種の「合理性」をもつものではないか、という視角ではないだろうか。民主化を阻害しているのは、共産党ではなく、中国社会そのものの特質から、生み出されたものではないか? 中国経済の驚異的な発展(楽観材料)を支えているのは、その農村の貧困そのもの(悲観材料)に由来しているのではないか?本書では、2つのイメージを生むものが、分裂した形での言及にとどまってしまい、深くふみこめていないのが、いささか気になる所でした。とはいえ、現代中国分析には、必見の書であることは確かです。ぜひ、本棚の片隅においてみてはいかがでしょうか。評価 ★★★★☆価格: ¥819 (税込) 人気ランキング順位
Aug 9, 2005
コメント(1)
-

★ 興梠一郎 『中国激流 13億のゆくえ』 岩波新書(新刊) (1)
昇竜中国は、どこへ向かおうとしているのか。生の中国の現実を知りたい。中共のフィルターを通さない、そして中国への偏見も排除した、本当の中国の姿が知りたい…みごと、その願いは、かなえられた。そんな欲望をもつ人のための、待望の著作が岩波新書から出ました!2005年度刊行新書では、吉見俊哉『万博幻想』(ちくま新書)と並び、ハイレベルの知的興奮があなたに訪れることに疑いありません。ぜひ、周囲の書店でお買いもとめください。<内容簡介> 中国を理解するキーワード● 絶大な党書記の権力による、汚職の蔓延 政府機関のトップは、ナンバー2以下にすぎない。紀律検査委員会も、司法機関(公安・検察・裁判所)を指導する党政法委員会も、人民代表大会も党書記の下におかれている。私有財産の国有化(社会主義化)が逆転して、国有財産の私物化が進み、2001年末で4000名の汚職容疑者が50億元の金をもって国外逃亡中という。● 与えられた任務を完遂するだけの「下請け」=郷鎮政府の構造問題中央は、農業税に非税費用徴収を一本化させる改革をおこない、中央財源も郷鎮政府に移転させるなどしているものの、巨大な財政支出を余儀なくされ、公務員のリストラもすすまない。「国家請客、地方買単」(国家が客を招いて、地方が金を払う)のシンボルは、義務教育。地方政府は、貸倒をおそれて銀行が貸さない以上、農民に転嫁するしかない。農民は、農産品価格が増産で低迷している以上、負担軽減をもとめて、集団抗議・衝突が相次ぎ、秘密結社の復活までみられるという。● 住民暴動頻発の中核にある強制収容にまつわる「土地所有権問題」不動産開発にともなうバブルは、都市部にかぎらない。錬金術のタネは、土地使用権を持たぬ住民から「計画経済の論理」=安値=で収容して、それを土地使用権つきの「市場経済の論理」=高値=で売却する、政府・不動産・土地評価機関・取り壊し業者一体の利益構造である。そこには、「取り壊し・立ち退き」条例の不備、物権法の不在がある。インフラ・企業の誘致合戦は、無償に近い土地譲渡をうみ、ますます住民に安値収用という形で転嫁されてしまう。この香港をモデルとする開発は、不動産バブルを生み、17兆元の人民元貸出残高のうち半分以上が不動産担保で、党・縁戚者一体の利権あさりの場となっている。土地使用権譲渡収入は、貴重な地方政府の財源収入となっていて、歯止めがかからない。企業と地元裁判所は一体となっていて、司法機能も働いていない。● 三農(農民・農村・農業)問題と「二極化」する社会農業向支出(支援・救済・基本建設・科学技術)は、国家財政の7%にすぎず、地方財政が全体の8割負担を強いられている。サポートが不十分な上、農業金融機関の都市不動産投資がおきて、農村金融の空洞化と高利貸が出現している。6割の人口をしめる農村部への衛生投資は、2割に過ぎない。ジニ係数は現在0.45以上に達していて、都市・農村間だけではなく、都市内部、地域間、業種間(社会資源の管理者)でも深刻でありながら、税金は逆進課税となっていて再分配の機能をはたしていない。● 頻発する労働争議の裏事情労働争議が多発する中国。それは、大都市の建設現場でいちじるしい。ところが、低賃金かつ苛酷な労働を強いられる出稼労働者への賃金不払は、「地方政府⇒不動産会社⇒建設会社⇒施工業者⇒民工」という資金の流れが、マクロ金融政策の引締と、地方政府の代金未払によって、とくに生じているという。● 国営・外資に挟撃される、私営企業の命運● 政治が経済を支配する、市場経済(=官僚経済)財政収入源の4割をしめる国営企業に対して、私営企業は5%、都市部では工業生産額は1/3、雇用者数は1/2にすぎない。銀行貸出も、国営企業中心で、南方では民間高利貸が公然の秘密になっているという。また金持ちは、国有財産横領など、不正手段で蓄財したイメージが強く、私有財産権を認めがたい。そのため私営企業は、政府との交渉(賄賂)に精力を傾けざるをえない。国営企業のガバナンスは、党委員会・紀律検査委員会・労働組合と、新設「株主総会・取締役会・監事会」の軋轢がひどく機能していない。国営企業は、絶大な権限をもつトップの私物、政治家の政争の道具というのも珍しくない。また、「政府と企業の分離」市場経済化は、財政収入源の国有企業売却にしたがい、政府・警察・学校・軍隊が収入をもとめ会社経営をはじめ、私営企業を圧迫することがおきている。(その2に続きます)評価 ★★★★☆価格: ¥819 (税込) 人気ランキング順位
Aug 8, 2005
コメント(3)
-

★ 瑞穂れい子とジェンキンス夫人の会編 『猫ふんじゃったはフランスではカツレツと呼ばれている』 YAMAHAミュージックメディア、2004年
ムダな知識を集めて悦びを感じるのは、人だけだというが、そんな人にふさわしい本をここで紹介したい。・山田耕作が「作」を「筰」に改名したのは ⇒頭がハゲていたからである・オーボエはケースから出して10分間以上放っておくと ⇒割れる・スウェーデンのバンドにカーデガンズがあるが、ジャカルタには、 ⇒セーターズというバンドがある・「ハッピー・バースデー」の歌は ⇒盗作者のつけた替え歌だった・BGMは ⇒高所不安を紛らわせる エレベーター音楽が始まりだった・「三拍子揃う」とは ⇒大鼓・小鼓・笛のことである・レッド・ツェッペリンは、 ⇒頭の鈍いアメリカ人にリードと呼ばせないために、 LEDと表記した。正しくはLEAD(鉛)。・映画音楽の始まりは ⇒映写機の音をゴマかすためだった・ギリシアの国歌は ⇒158番まである・「聖(いと)しこの夜」の正しい歌いかたは ⇒ギターを伴奏にすることである・史上最初にリサイタルを開いたのは ⇒フリードリッヒ・リストである・そのピアニスト・リストは晩年 ⇒聖職者となった・ハーモニカを発明したのは ⇒ベンジャミン・フランクリンである・ベートーヴェンは35年間で ⇒79回も引っ越した… こんな調子で、あらゆる音楽にまつわる、トリビア(無駄知識)が延々とつづき、屈託のない披露がたまりません。かなり素晴らしい本であることがわかるでしょう。あわせると94個。それに関する、オマケの無駄知識まで披露されています。なにより、流れを壊すタモリもいなければ、意味不明のトリビア製造もない。おまけに、「トリビアの泉」に使われていないものが多い(はず)。そのため、明日使っても、だれもネタ元が分からない。そんな、無駄知識が満載されているのが嬉しい。恋人に知識を披露したい。そんな貴方にお薦めの一品となっています。ご紹介したこの13個のトリビア。もし、面白いと感じたら、ぜひご一読あれ。評価 ★★★価格: ¥1,365 (税込) 人気ランキング順位追伸 ついでに唐沢商会『脳天気教養図鑑』でも紹介しようとおもったら、 画像がぜんぜんないでやんの…どこも完全に品切れらしい。
Aug 6, 2005
コメント(0)
-
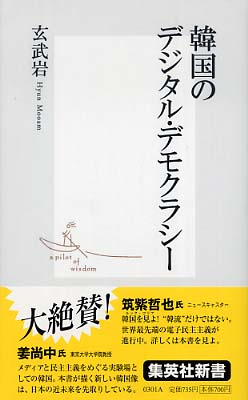
★ 玄武岩 『韓国のデジタル・デモクラシー』 (2)集英社新書 (新刊)
(承前)● 「歴史の清算」が行なわれるのは、民主主義の確立に必要なためである植民地時代の親日派の摘発がおこなわれているが、それは「反日」的外交政策をおこなっているのではない。保守既得権益層は、もともと民族派のフリをした親日派なのに、これまで60年間、政権を独占してきたため、かれらの対日協力行為が裁けなかった。ベトナム戦争での韓国軍の残虐行為の摘発などをみても、歴史の清算は、国内における過去の恥部へのケジメとしておこなわれている。この7月、施行された新聞法や、他にも、私立学校組織改編、国家保安法廃止、戦後の歴史真相究明が課題であるという。「偏狭」「誤解」「傲慢」…この書には、多くの問題があるといえます。とくに、「左翼=ナショナリズム」を自覚していないことは致命的といえるでしょう。また、日本の政治構造を理解できていないくせに、ウリ党の「上向式公薦方式」「党員資格強化」を礼賛し、自民党と比較して「新しい」などといってしまう手法には、虫唾が走ってしまう。インターネット市民勢力のパロディ水準の勝手な批評など、正直、どうでもよい。とはいえ。盧泰愚、金泳三、金大中…韓国の新大統領はいつも就任期間中は讃えられてきた。またお定まりの礼賛本、退任後は盧武鉉も刑務所行きだろう…などとおもってはいけない。なにより大切なことは、韓国左翼ナショナリズムの≪固有の論理と息吹≫が、保守メディアのプリズムを通すことで曲げられることなく、一冊の本として我々に伝えられたことにあるでしょう。ながらく、田中角栄逮捕に踏み切った東京地検特捜部は、韓国では神話的存在であったこと。また、2002年大統領選の鄭夢準の盧武鉉支持撤回、2004年大統領弾劾政局のときの「ネチズン・放送局VS新聞」の動きと戦いは、読んでいて息つまるほどの、迫真のレポートとなっていて、たいへん素晴らしい。筆者の指摘する、韓国のネチズンの目指す「感動の政治」『「嗤う」日本のナショナリズム』(NHK出版)とも通底する、「感動の共同体」の創出。≪日韓のインターネット言論における「感動の共同体」という補助線≫われわれは、この補助線を引くことで、素晴らしい収穫をえることができるのではないか。これによって、韓国のネット市民勢力に「反改革・反統一・反民族」と批判される朝鮮・東亜日報は、プチ・ナショナリズムによって「反日」と批判される朝日新聞・NHKと比較することができ、日韓のネット言論をまさしくパラレルなものとして、位置づけることが可能になるのですから。とくに、戦前「対日協力」をしながら戦後「民族紙」を自称してきた「反統一」朝鮮日報への批判は、戦前「軍部協力」しながら戦後は「左翼」「反日紙」と断じられる朝日新聞への批判と、完璧なまでにシンクロしていることに興味をむけたい。これは、「愛ゆえのシニシズム」という機制こそ欠いているものの、「感動の全体主義」という水準では、おなじものではないのか。筆者は、日本ネット右翼と韓国ネット左翼の相似形が、まるで理解できていない。そして、かつての韓国左翼の民主化運動をささえた、日本の市民派左翼勢力に対してエールさえ送ってさえいる。帯で礼賛する、姜尚中・筑紫哲也にしても理解しているとはおもえない。それは、日本ネット右翼の嫌韓厨が、自己と韓国左翼との相似形をまるで理解できていないため、「拉致家族問題」などにおいて、さかんに韓国保守勢力にエールを送り続けている姿と、まったく同じものではないか。そうなのだ。たぶん、日本ネット右翼の希望の星、安倍晋三は「日本の盧武鉉」なのだ。いや、盧武鉉こそ、「韓国の安倍晋三」なのかもしれない。どちらにとって、より不本意なレッテルなのかは、分からないが。たぶん、この本は、筆者の意図と反して、そして日本のネット右翼の通念とも反して、こうした変奏と誤読を可能にするからこそ、我々にとって豊穣な本なのではないだろうか。そして今まさに、韓国の左翼ナショナリズムにおきつつある、ある種の挫折と変奏が、あたかも日本ナショナリズムの挫折と変奏を予言、もしくは乖離が観察できるからこそ、この書は非常に強烈な問題提起をしている書ではないだろうか。筆が進みすぎたようだ。ともかく、ご一読あれ。評価 ★★★☆価格: ¥735 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Aug 4, 2005
コメント(4)
-

★ 玄武岩『韓国のデジタル・デモクラシー』 (1) 集英社新書 (新刊)
韓国で今、何がおきているのか。日本の保守系メディアに取り囲まれた環境では、全体像がみえてこない、韓国でおきている「民主化」運動のすべてがわかります。盧武鉉政権下の韓国で秘かにすすむ、政治の地殻変動を描く、迫真のレポートといえるでしょう。ぜひ買うべし!!この書のポイントは多岐におよび、かなり有益といえます。● 「維新体制」下における「朝・中・東」三大新聞の「権言癒着」● 軍事政権の統治技術として生まれた「地域主義」実は意外と新しい地域主義。それまで深刻なものではなかった全羅道(湖南)差別は、71年朴正熙の大統領選三選と「維新体制」を機に、産業化にともなって韓国に定着していったらしい。光州事件は、湖南民を被差別の運命共同体にさせ、金大中に自らの命運を託させる心理を生みおとしてしまう。それが、非湖南民の湖南民への反発を高めて、それが螺旋的に地域主義を昂進させる、悪循環を発生させていったらしい。この史実は、みなさまにとっても、目からウロコではないでしょうか。「維新体制」以後、一部のジャーナリストをのぞけば、朝鮮日報・中央日報・東亜日報などは、免税措置、非税務調査、社主利益保証などによる、報道統制受入と引きかえのさまざまな特権で、軍事政権下、大いに発展することになったという。● 民主化の聖地「光州」と反米運動の誕生79年10月、朴正熙暗殺によって迎えた民主化運動「ソウルの春」は、80年5月17日戒厳令布告と、18日光州への特殊部隊の投入、27日道庁の占拠によって幕を閉じた。そして、全斗煥の第五共和国がはじまる。平時でも、韓国軍はアメリカが作戦統制権をもつ。それなのに、なぜ全斗煥たちは軍隊を動かせたのか。光州事件は、アメリカ=解放軍の虚像を奪いさり、今燃えさかる反米運動の起点となったという。● 「言論権力」化した「朝鮮・中央・東亜」と市民勢力の対決1980年代後半以降、民主化運動の過程で、MBC・KBSなどの放送では民主化は進んだ。ところが、社主の強い新聞ではまるですすまなかった。あまつさえ、保守系「朝・中・東」三紙は、市民が闘争で勝ちとった民主化の最大の受益者となって、「言論権力」とよばれるようになったらしい。その保守メディアへの反発から、ハンギョレ新聞、市民記者によるインターネット新聞「オーマイニュース」、専門記事サイト「プレシアン」、コラムサイト「ソプライズ」、そして「アンチ朝鮮日報」運動、が生まれてきたという。そうした流れは、「政経癒着」「動員政治」を覆したい人々を生みだして、民主化運動にたずさわった商業高校出身者の弁護士ながら、出身地釜山で地域主義の壁に阻まれていた、盧武鉉を一躍押しあげる原動力になったらしい。その一方、反共主義と地縁・血縁・学閥の既得権で組織化されていた韓国保守勢力は、危機感をいだいて、インターネット言論への参入や、アイデンティティの創造を模索しているという。● 盧武鉉政権の政治改革とは何かインターネット言論が生んだといえる盧武鉉政権は、自らの不正資金疑惑に対する特別検察の受入、イラク派兵、核廃棄物処理施設問題などで、支持者の離反をまねくことになった。そうした苦境の原因の一つは、それまで強大な大統領権力の中枢にあった、情報機関・検察などの権力装置を、政治からあえて独立させようとした、盧武鉉の政治改革にあるという。盧武鉉政権は、制度変革ではなく、民主的コミュニケーションの確立をめざす政権らしい。● 盧武鉉と大統領弾劾政局盧武鉉は、じぶんも関わらざるをえなかった、地域主義的な、旧来のボス型金権政治からの脱却を目指しているらしい。そのため、不正資金疑惑において、あえて側近を検察に差し出すことで、それ以上の不正資金疑惑をかかえていた野党ハンナラ党に大打撃をあたえさせた。そしてそれとともに、地域主義をこえるために、統合新党「ウリ党」をたちあげたという。これが、ハンナラ・民主両党の野合というべき提携をうみ、弾劾政局をもたらしたが、かえって地域主義に立脚する両党の互いの支持基盤を侵食することになった。このときハンナラ党代表は、朝鮮日報で光州事件に加担して、のちに軍事政権の要職についた人物だったため、「クーデターVS民主」の図式と受けとられた。進むも退くもできず、両党は強行採決に追いこまれ自爆。弾劾政局を主導した民主党は崩壊寸前に追いこまれ、ハンナラ党は、慶尚道地域政党に転落してしまったという。(その2に続きます)応援もヨロシク評価 ★★★☆価格: ¥735 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Aug 3, 2005
コメント(1)
-

★ 佐藤卓己 『八月十五日の神話』 ちくま新書(新刊)
名著『言論統制』(中公新書)でその名を高らしめた、佐藤卓己。「朝日新聞の予定稿」「怪しい玉音写真」「8月15日という物語=歴史」…扇情的な文句が並ぶ。終戦とは何かをどこまでも追求した作品になっています。8月10日、ポツダム宣言受諾の御前会議の内容が世界に伝えられる。8月14日、最高戦争指導会議と閣議の連合会議で、天皇、終戦に署名。8月15日、玉音放送で国民に発表。8月16日、自衛戦闘を除く即時停戦を発令。8月17日、18日、海軍と陸軍で全面的停戦予告。19日、発令。22日、実施。9月2日、降伏文書調印、終戦詔書発表。9月2日こそ、世界「終戦」の主流。日本はなぜ8月15日が終戦なのか。それは、戦後、『国民的記憶』として創られたものだ、という。講和条約発効とともに、9月2日「降伏記念日」は消えた。そして、1955年頃までに、8月6日の被爆体験から、8月15日の玉音体験にいたる、「8月ジャーナリズム」は完成をみたという。それは、「敗戦=占領」から「終戦=平和」であり、「反省」から「平和」への国民的記憶の再編を意味していた。だがそれは、「8・15革命」(丸山真男)を信じるものと、降伏を忘却したい保守の「8・15聖断神話」との合作としてうまれたものだという。玉音放送は、国民全員の「儀式への参加」を通して集合的記憶になった。そして、ラジオで戦前からおこなわれた「盂蘭盆会法要」(お盆)の再編と、「夏の甲子園」中継とともに、国民的メディア・イベントとして定着してゆく。中国は、中曽根靖国参拝以降、アジアへの加害を問う日本のメディアにあわせて、8月15日に「終戦」を移しつつあるらしい。歴史認識とは、現在の国際政治を映すもの、政治そのものである、とする議論もたしかに面白い。高校歴史教科書では、9月2日終戦の記述が圧倒的であること。1963年から81年にかけて、日本の経済大国化とともに、「侵略」から「進出」に書き改められていったこと。世界史と日本史では、同じ会社の教科書でも記述が違うらしい。丸山真男の転向はいつか?。敗者は、映像をもたない。玉音放送をめぐる不安定な写真こそ、玉音放送の記憶に我々を回帰させるのだ… 先学に多くを依拠しているとはいえ、視点はとても斬新です。ただ、今回の仕事には、正直落胆を禁じえない。何よりぶったまげたのは、中国の戦勝記念日≪9月3日≫が、スターリン【中ソ同盟の歴史的遺産】にされていることでしょう。それはもともと、45年9月3日、重慶で慶祝式典が開かれ、復員推進と憲政実施をうたった『中国国民党為抗戦勝利告全国同胞書』が発表され、【抗日戦争結束日】を9月3日にしたことに起源がある。それが1946年、「抗日戦勝記念日」となってゆくのですが、なぜか<9月3日に定めた1951年「中共」布告内にみられる、ソ連への賛辞・感謝>⇒<50年中ソ同盟>⇒<蒋介石も45年「中ソ同盟」を締結して9月3日に定めた>と遡及されてゆき、「ソ連標準」(=9月3日)にあわせたと断定されてしまう。いったい、なにを根拠にしてるんでしょう? なにより中国人には、独自に祝うべき日がないと想定されているかのような、佐藤氏の発想がおそろしい。台湾で、9月3日が「軍人節」になったのは、もう「ソ連」にあわせる必要がないため。中共が、終戦日をソ連標準から日本標準にかえたのは(【注】 別に変えてはいない)、歴史認識を政治化させるため、と説かれてしまう。日本では、「創られた記憶」をさまざまなメディアで検証しながら、中国では「教科書」記述、台湾では教科書さえ出てこない。意図的な情報操作か? これが、『言論統制』を執筆した人物のおなじ仕事とは、とうてい思えない。また、高校教科書「9月2日終戦」が世間に広まっていない理由は、8月15日が民族解放=<光復節>の韓国に配慮する、アジアの戦争被害を重視する歴史教育のせいにされてしまう。配慮の内容が意味不明なまま… どうみても、「終戦」と「降伏調印=敗戦」は、日本ではシニフィエがちがい、「降伏=終戦」の観念がないためにしかみえないのだが… おまけに、韓国の<光復節>は、60年間、8月15日らしい。ならば「8月15日終戦」は、日本標準ではなく、韓国標準ではないのか? 本書の枠組を用いれば、「記憶の55年体制」「記憶の再編」とは、日本が韓国にあわせてゆく過程ではないのか? なぜ検討もされていないのだろう? これだけで、いかにいい加減な枠組で議論しているか、理解できるというもの。 それだけに、8月15日「戦没者慰霊の日」、9月2日「平和祈念の日」として、お盆と政治、戦没者追悼と戦争責任を分離させよ!!という筆者の提言も、いささか唐突に映ってしまう。むろん、8月15日で見失われるものをとらえるためで、賛意は惜しまない。とはいえ、操作主義的メディア観として「つくる会」教科書側とその「反対者」も批判した当人が、「終戦記念日の内向化」への批判自体が国民統合を強化すると嘲笑した当人が、さらには「8月ジャーナリズム」と皮肉った当人が、「操作主義的」な、「8月15日批判」を、「8月ジャーナリズム」にのせて展開するのは、矛盾も極まっているのではないだろうか。そもそも、≪8月15日≫≪終戦≫の≪国民的≫≪記憶≫というものは、それぞれ多様で、開かれていて、個人的で、それでいて、移ろいやすく消えやすいもの、であるはずだ。だからこそ毎年、≪8月15日≫≪終戦≫は、その内容を更新・確認しなければならなくなるのではないか。そこに、メディア・イベント「8月ジャーナリズム」が、すこしずつ変容をとげながら、毎年のように展開されていった理由があるに違いあるまい。その容器に入れられる中身は、だれも一義的に確定することなどできはしない。ならば、これに≪9月2日≫≪平和祈念の日≫を付け加える、佐藤氏の唐突な提案に、いったいどれほどの意味があるというのだろう。評者ならずとも、疑問を感じてしまうのではないか。たんに、圧倒的な≪鈴木庫三日記≫ のメッキが剥がれて、メディア史の地金が出てしまっただけなのかもしれないけれど…そのため、評価は低くしてある。ご寛恕願いたい。評価 ★★☆価格: ¥861 (税込) 人気ランキング順位追伸 そういえば、「朝日」「毎日」の8月15日予定稿への批判も、考えてみればかなり不思議な話です。「降版時間」に制約される新聞は、今も、とくにスポーツ記事などを中心に、予定稿を整理部に出稿して、ストックしつづけています。非常事態になれば、そうしたストックは、しばしば整理部の判断で、別の記事にさしかえられてしまう。また写真は、記事を書いた人が撮るわけではないし、写真・記事の見出しは整理部がつけるもので、出稿先は関知しない。この3つ、写真・見出し・記事内容の不統一は、分権的メディアである新聞において、なかなか避けることはできない。なぜ佐藤氏は、それを知りながら(知らないはずがない)、この3つが統合されていないことを問題視するのだろうか。それは、ありもしない集団的記憶という、「統合」された何かを問題視する、氏の姿勢とつながっていて、たいへん興味深い。
Aug 1, 2005
コメント(0)
全16件 (16件中 1-16件目)
1










