2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2005年06月の記事
全15件 (15件中 1-15件目)
1
-

★ 糟谷憲一 『朝鮮の近代』 山川出版社
侵略を正当化するためのイデオロギーを提供することになった、「朝鮮社会停滞論」と戦前の歴史学。その克服のため、戦後、「内在的発展」過程の究明がすすめられ、朝鮮近代史像は根本的に改められたという。その到達点と現状をふまえて、1863年の大院君政権成立から、1910年「韓国併合」までの通史を描く本書。やや古いけど、なかなか楽しめる本になっています。李朝後期の、商品経済の発展にともなう、高密度の定期市網の出現。17世紀以降、「小中華思想」の誕生がみられ、庶民文化の成長を示すハングル小説も盛行したという。18世紀先鋭化する、四色党派(老論・少論・南人・西人)の党争。そんな門閥政治も、19世紀、外戚の「世道政治」によってさらに細かい党派に。大院君政権は、書院整理&王権強化(&鎖国政策)策をおしすすめ、「斥和碑」建立に見られる「衛正斥邪」派の形成がみられました。一方1873年、閔氏政権の成立とともに、「開化派」が出現します。宗主権強化をはかる清に対して、「開化派」は、急進派(日)と穏健派(清)に分裂。1884年甲申事変で、急進開化派のクーデターは失敗。日本の勢力は後退しました。しかし1894年、「反日反閔氏政権」を掲げた東学党の乱を契機に、大院君を担ぎ出して、日本は閔氏政権を打倒。日本は、東学党再蜂起も鎮圧して、1895年以降、内政改革「甲午改革」をおしすすめます。三国干渉の結果、日本を抑えるため、閔妃などを中心に親露派が形成されることになります。1895年、閔妃殺害後も、改革が推し進められ、1896年、反発する「衛正斥邪派」は、「反日反開化」の義兵闘争をはじめました。ソウルから軍隊が離れた隙に、親露派は高宗をロシア公使館に連れ出すクーデターを遂行。ところが、義兵闘争は、親露派政権も敵視します。何とか鎮圧するものの、改革への逆行が。そこで、開化派官僚を中心に、独立と近代化をめざす「独立協会」が結成され、反露闘争と君主権を制限する運動をはじめます。皇帝派・守旧派は、君主権強化で独立維持と経済自立化をねらう。1904年日露戦争は、内政干渉をゆるす日韓議定書と、翌年の日韓保護条約の調印をまねき、06年には統監府は設置されます。ハーグ密使事件を機に、第三次日韓協約。義兵闘争は、1905年からはじまり09年に最盛期を迎えるものの、日本側警察による焦土作戦、懐柔・分断作戦によって鎮圧されてしまう。独立協会をついだ、大韓協会の反日愛国啓蒙運動も弾圧。1909年7月、日韓併合閣議決定。11月、伊藤博文暗殺。12月、一進会の「合邦声明書」。1910年4・5月、露英の承認。1910年8月、日韓併合。こうまとめると、韓国が反日一色になる理由が、なんとなく見えてきます。てゆうか李朝は、読んでいるこちらが腹のたつほど、バラバラなのですな。なにせ、併合条約に調印した李完用は、元々親露派らしい。大院君を担ぐ勢力は、つぎつぎかわる。独立派は、反露、反日定まらず、訳分からない。義兵闘争と開化派は、独立運動しているのに、まったく協力しようとしない。むろん、大院君と閔氏のからみもあるのでしょう。これに、複雑な四色党派がからむ感じ。かの高名な朝鮮の朱子学まで、党派で系列化されていた(嶺南学派の李退渓は、南人派らしい)のには、驚くばかり。そりゃ、植民地化の歴史から汲みだされる教訓は、どんなに主義主張や、地域や、党派を異にしても、とりあえず外に対しては民族は「一致団結」して、日本など外敵にあたることですよ。そういや、韓国のサッカー記者は、韓国に連敗続きの中国サッカー代表に「恐韓症」よばわりしてました。無礼な表現だなあ、とおもったものの、案外、こういう形になって一致団結が表現されているのかもしれません。とりあえず、日本、清国、ロシアが入り乱れて、朝鮮半島を狙うさまは、複雑怪奇のひとこと。朝鮮の「自主」と「属国」をめぐる、さまざまな格闘が繰り広げられています。日本は、かなりスリリングな橋を渡ってきたことがわかって面白い。隣国の近代史を知らない人には、お薦めの入門書ではないでしょうか。評価 ★★★価格: ¥765 (税込)追伸 何冊かもっているけど、山川の世界史リブレットは、どれもかなり面白いです。ご参考にどうぞ ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Jun 29, 2005
コメント(2)
-

★ 鈴木孝昌 『現代中国の禁書 民主・性・反日』 講談社+α新書(新刊)
すばらしい新刊がお目見えしました。その丁寧な取材によって、共産党言論弾圧模様と、現代中国の言論マップをほりさげる、質の高いルポルタージュになっています。これを読んだ方は、ただちに買うべし!総勢7名におよぶ、豪華な中国共産党の「発禁」「身柄拘束」ラインナップ。「愛国者同盟網」 盧雲飛 「中国民間保釣連合会」とともに、ネットで活発な署名活動をおこない、無視 できない「反日世論」を形成して、「日本常任理事国入り」「新幹線導入」 を阻止 「対日関係新思考」 馬立誠 今では日本が中国を恐れている、として、時殷弘・孫淑林・魯世巍・馮昭奎 らとともに民族主義を排し、「普通の国」日本でも受け入れることを提言 『中国農民調査』 陳桂棣・呉春桃 当局に尾行されながら、安徽省の農村改革モデル地区 50箇所をまわり、地 方官僚・農村幹部の腐敗、口封じのため農民を殴り殺す警察など、100名を 実名で告発蒋彦永・人民解放軍301病院医師 2003年4月、衛生相のSARS鎮圧宣言の虚偽を告発し、当局の「SARS隠し」 を明らかにしただけではなく、楊尚昆発言などを引用しながら天安門事件の 再評価を要求『遺情書 -私の性愛日記』 木子美(李麗) おなじく発禁処分になった衛慧の小説『上海ベイビー』とならぶ、24歳の女性 による自己の性生活をつづった「性愛日記」の出版。李鋭・元毛沢東秘書 かつて「彭徳懐反党集団」として下放された、三峡ダムに反対し、体制内政治 改革をもとめ、胡耀邦の名誉回復をもとめる、元共産党中央委員の党長老 「討伐中宣部」 焦国標 農村貧困、不払賃金、公衆トイレ…すべての問題が解決されないのは、 報道を禁じた党・中央宣伝部の責任だ、と討伐を主張する北京大助教授胡錦濤党総書記の三権(党・政府・解放軍)掌握後、いったんはメディア規制を緩めたかのようにみえたものの、現在では胡錦濤周辺が、統制強化に乗りだしているという。毛沢東が反対派を燻りだすため使った、「百花斉放、百家争鳴」と同じ手口なのか、という批判は重い。現在は、馬立誠論文が掲載された「戦略と管理」も、他の批判したメディアと同様に廃刊になり、ネットへの統制も強化されているという。1000万件もの陳情が届く、絶望的な農村社会の窮状。上の動向を気にせざるを得ない、中国社会。『中国農民調査』の刊行のいきさつなどは、感動的ですらあります。ただ、どうしても評者は、「禁書」を筆者が誤解しているのでは?という疑念が拭えない。そもそも、いにしえの王朝時代から、なぜ禁書のはずの本が、現代にまで伝わってしまうのか。それは、もともと「禁書」は出版されているもので、民間が平然と所蔵・流布させているものだからですよ。だいたい、常識を働かしてみればいい。政府高官は、「禁書」の疑いのある本を読む暇なんか、あると思いますか?たいてい、点数稼ぎの「下僚」が大真面目にとりあげて上司に報告。上司が別の下僚に叱責。大慌てで下僚が禁令、というパターン。そんな「禁書」は、はては水滸伝から、占い・カレンダー・参考書など、多岐にわたって「脈絡がない」「笑ってしまう」のは当然のこと。だれも、統一した基準で規制しているわけではないのだから。近年の禁書は、王朝時代のありように戻っているだけにすぎない。そんな、中国共産党の禁書対象が、「討伐中宣部」から性生活におよび、緩んだり厳しくなったり、保守だの開放的だのに「見えてしまう」のは、13億もの人間の活動を考えれば、あたりまえのことでしょう。いくら、禁書を羅列しても、共産党が危険視する一貫した「ダブー」の体系が、その禁書群から浮かびあがるはずがない。そこに、一貫したダブーを「勝手に」読み取ろうとするから、人は「笑ってしまう」という行為におよぶしかないのです。それは、「笑う」人間の思考法に問題があるにすぎない。決して、「禁書」をおこなう、中共に原因があるのではない。そもそも勘違いの根源は、「禁書」という現象の背後に、統合された主体=「共産党の言論統制」を読みとろうとする、筆者の手法そのものにある。「現象」の裏に「一貫した」「本質」を仮定しようとする思考は、トンデモの繁茂する土壌になりやすい。麗しき日本の伝統の裏に、「万世一系の天皇制」をみる国学。資本の運動の裏に、階級支配の本質をみるマルクス主義。「反日」の背後に、連動する左翼ネットワークを読みとろうとするアホ右翼。…分からないものに言葉をあたえようとすれば、「曖昧な」シニフィアンに「逃避」してしまう他はない。この書の中でも、つねに禁書にして弾圧する相手は、「当局」となっています。顔のみえない異様な敵。きわめて都合のいい、実に曖昧な言葉。その通り。「当局」以外の言葉など、カフカの城同様、与えようがない。それは、現象の裏に本質が、そして首尾一貫した主体などが、どこにもなかったことの裏返しにすぎません。日本、帝国主義、朝日新聞、伝統、階級支配…今回、ここに加わったのが、中国共産党ということなのでしょうか。その辺がすこし残念です。「一貫した」主体など、現象の裏に「本質」など、そんなものどこにもありはしないのに…い、いかん、暗くなってしまった。今回は誉める予定だったのだ、、、そんな欠点などあっても、気にもならないほどの力作にはなっているのです。ぜひ、ご購読あれ。評価 ★★★★価格: ¥820 (税込)人気ランキング順位
Jun 27, 2005
コメント(2)
-

★ 今村弘子 『北朝鮮「虚構の経済」』 集英社新書(新刊)
参りました!思いもよらない、北朝鮮の驚愕の事実。その建国当初から、一貫した「計画なき計画経済」「援助漬け大国」中・ソの援助なしでは、計画経済すら達成できない「三元化経済」の北朝鮮(計画経済、第二経済委員会【軍事産業】、闇経済の3つ)今の北朝鮮はなぜ生まれたのか。朝鮮戦争以後、どの社会主義国よりもはやいスピードで、農業集団化と企業国有化を達成させた北朝鮮。とはいえ、本書によると、その歩みは以下の通りだったという。1 繰り上げ・超過達成運動による、人員と機械を消耗させた無謀な増産運動。2 「四大軍事路線」などの過重すぎる国防負担。無意味な重化学工業路線。3 「千里馬運動」は、北朝鮮版「大躍進」。中・ソの援助で失敗が顕在化せず、 「主体農法」「速度戦」なるものが、以後もくりかえされた。4 プラント導入も、輸出の何倍もの年間債務支払をかかえデフォルト状態。5 80年代には、「全国土棚田化」で土壌流出、農業崩壊。6 90年代は、ソ連崩壊、韓国と社会主義国との国交樹立、自然災害の頻発で、 経済は崩壊状態。国家予算は半減したという。エネルギーも食料もない。 肥料も農薬も作れない。農業機械も動かせない。7 こうした苦境は、1970年代から連綿として続いていて、 90年代からのものではない。回復の兆しもない。最近の経済政策も、無謀の極みらしい。請負制など「農業改革」を先行させないで、価格改革だけ着手。余剰人員削減がすすむ、中国の国営企業改革。それに比べて、勤務先で仕事のない過剰労働力が、3割から5割にもおよびながら、人びとから隔離する形で外資導入が図られ、進出企業には自由がないらしい。投資する人もすくなく、経済波及効果も当然期待できないという。赤十字間でむすばれた帰還協定によって、北朝鮮にかえった在日は、「成分」では下から10番目の「動揺分子」だったとの指摘もおもしろい。1974年以降、自称「無税国家」の悲惨さ。この本では、北朝鮮は「改革開放」よりも、農民の生産インセンティブを高める「調整政策」をとるべきであると、経済改革の提言もおこなわれています。資料がない、北朝鮮をどう分析するべきか。ここで、虚偽にまみれがちな証言や、妄想と願望がふくらむ観測記事などに頼らず、「友邦」中国における「北朝鮮研究」を手がかりにしようという、著者の発想がなかなか面白い。それは成功している。さすがに評者も、1950年代には、朝鮮戦争で荒廃した国土の立て直しだから、北朝鮮経済には発展がみられたと思っていた。しかし、これすらも中ソの援助のためという。援助額縮小の1960年代、70年代では、計画経済すらまともに達成できていないらしい。「○ヵ年計画」すら、まともに建てられていなかったとは……(93年以降、計画を立てることすら放棄されている) 人びとは、70年代から「窮乏慣れ」してしまっている。そして、経済制裁も、中国が賛成しないかぎり、ほとんど効果はないという。むろん、韓国や台湾のように、「中間階級」などの民主化を支持しそうな受け皿もみられない。その分析は、手堅く、面白い。たしかに目からウロコが落ちました。北朝鮮経済に興味のある方なら、必見の書になっています。評価 ★★★価格: ¥714 (税込)人気ランキング順位
Jun 24, 2005
コメント(0)
-
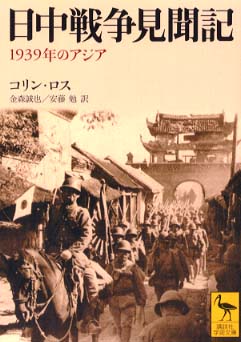
★ コリン・ロス(金森誠也・安藤勉 訳) 『日中戦争見聞記 1939年のアジア』 講談社学術文庫
「中国」は、世界の中心、ひとつの「文明」の中心なのだ。バスや鉄道で、中国北部を旅していたとき、たしかにそう感じる一瞬があった。夕日に映える、山吹色の麦秋の大平原。のどかに広がる麦畑に浮かぶ雑木林と赤茶けた岩肌。そして残酷なまでに美しい空。その息をのむような美しさに囚われた。どこまでも、人がいて畑がある。人は、2500年間、この大地を耕してきた。これからも、おそらく、耕し続けるのだろう。そして、この大地に騒がしくも根をはって、彼らが耕し続けるかぎり、ここは、世界の中心、文明の中心であり続けるのだ…彼の地を踏むなら、大なり小なり、誰もが抱くそんな確信と予感を、評者もいだいた。かように人は、中国の大地へと、アジアの大地へと、いざなわれてきた。この書は、アジアの大地にいざなわれた人びとの、肉声がしるされている点で興味深い。著者は、ナチス・ドイツに併合されたオーストリア人。写真記者。ドイツ人として来日。自動車で日本をめぐって、朝鮮半島に渡って満州、モンゴルを縦断。そこからは上海、香港経由で、重慶政府の支配地域に足をはこんでいます。日本軍の重慶爆撃にも、直面した筆者。まさしく、副題の「1939年のアジア」にふさわしい、紀行文にしあがっています。おまけに筆者は、皇道派荒木文相(!)、満州国総務長官・星野直樹、南次郎などとの会見に成功しています。われわれにとって、面白くないハズがない。へんに枠にはめて理解しようとはしない、ゴツゴツした雰囲気そのままの描写が、読み手にはとても喜ばしい。当時の日本社会に確実に忍びよる、戦争の疲弊。滅びつつあるようにみえる、朝鮮民族とモンゴル族の運命への同情。かれは、朝鮮と満洲(そして中国)の光景をかえつつある、帝国日本の挑戦に、賛嘆を惜しもうとはしません。中国社会の観察には、端々に辛辣さがみられます。一見、絶望的にみえる中国社会。その逆に礼賛されているかのような日本。とくに、彼にとってあまりにも奇天烈かつ理解不能であった、日本の神道儀礼の模様を活写した箇所などには、おもわず笑みがこぼれます。「奥津城」靖国神社の儀礼の様子。捉えどころのない中国人の描写。この書からは、当時のアジアの呻き声が、時をへてよみがえってくるような、そんな錯覚さえおぼえます。ヨーロッパ人だけに、アジアのことは理解できていない。どこまでも、そのレンズは歪んでいます。だからこそ、かれの目からみえる日本・アジア像は、もう一つのたしかに実在した「日本・アジア」として、われわれの惰性ともいえる思考に修正をせまる、迫力ある見聞記になっているのでしょう。それは、アーカイブによってつくられたものとは異なった、「記憶の歴史」として紡ぎ出される、従軍慰安婦の証言と同じ「もう一つの歴史」を提供してくれているのかもしれません。おまけにコリン・ロスは、冷酷にも、最後に勝つのは蒋介石ではなくても、中国であることを理解しています。個人としての中国人の優秀さを疑わない、ロス。そして、ヨーロッパのアジア支配、白人支配の終焉を目の当たりにして、何かを「予感」しているロス。しかし、コリン・ロスは、それが何であるか言葉にすることができません。人は、事態が「現実化」してはじめて、あとづけによって、その「予感」が来たる「現実」の「前触れ」であったことを知ることができます。現実化しない内は、その予感は何を意味しているのか、語ることができない。そうした「予感」は、後にはすべて、「中国共産党」の勝利をつげるものとして、読み替えられてきました。中国の汚濁も、弱さも、きたるべき中国革命の、清浄な救済の「前触れ」として、あとから読み替えられてきたのです。この書にはそれはない。かれは、1945年に死んでいるからです。その「予感」にしたがい、熱心な観察をおこないながら、その予感がなにを意味したかはわからない。全編を通底する、何かを予感していながら、語ることのできない、そんなもどかしさ。だからこそ、なにものにも収奪されることがなかった、「もどかしい」ばかりの「予感」によって生まれたこの見聞記は、価値が高いものとなっているといえるのではないでしょうか。そこにある原石のままの可能性たちの群れ。むせかえるような、アジアの雑踏。1990年刊行された書の文庫化。この機会に、ぜひ手にとってみてはいかがでしょうか。評価 ★★★価格: ¥1,103 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Jun 21, 2005
コメント(1)
-
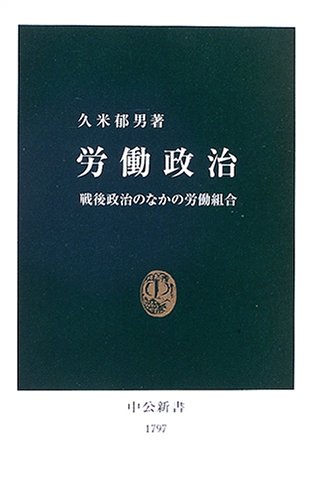
★ 久米郁男 『労働政治 -戦後政治の中の労働組合』 中公新書(新刊)
う~ん、なにがつまらないのかなあ。ずいぶんと意欲的な本なのに。読売新聞傘下からくる、保守臭漂う「帯」に騙されてはいけない。ほんと、こうした帯でずいぶんと損しているようにおもう。労働組合の功罪は、政治的立場によって、左右されやすい。労働組合は、1970年代から出現した「新しい政治主義」=「大企業労使連合」から、中曽根行革を支持していた。それが、なぜ今では抵抗勢力視されているのか。それには、そもそも労働組合は、どのような形で利益を組織してきたのか、労働組合の分析の重要性がここでは宣言されています。そのために使う道具立ても、説明が行き届いています。利益(圧力)団体は、政治学でどう位置づけられるのか。多元主義では、圧力団体の存在は、否定されない。「影響力」であろうと、「効率的政治市場」仮説をとろうと、多数の専制を防ぐことができる、柔軟なシステムだという。ただフリー・ライダーの存在ゆえに、「少数の優位」をもたらしがちな、【集合行為問題】が生じる。「特殊政治団体」という批判は、そこに集中しやすい。「効率的な経済」と「大きな政府」は、スウェーデンなどでは両立していた。それは、労働組合が「包括的」な組織で、国民経済の生産性を高めるインセンティブがあったことが大きい。オルソンによれば、包括的集権的労働組合と社民党政権、分権的弱い労働組合と保守政権の組み合わせがよく、平等主義的な賃金体系も、民間労働組合の覇権が貫徹しているなら問題はないという。日本は、包括的な経団連の活動だけではなく、ミクロレベルで労組は「包括的」で、産業間移動とはことなった、企業内での調整がおこなわれた。労働政策も、利害調整型の経済合理的なものであった。そうした、自民党一党政権下、拡大しつつも非政治化されていた、政策過程における労働組合の関与。それは、1990年代、政治化される。それは、グローバリズムによる経営攻勢ではなく、労働戦線統一と政界再編によるものだという。90年代、弱者保護と再分配に積極的な、官公労を中心とした労働組合の影響力がつよく、橋本行革では反対にまわったという。そうした動きを生むことになった、「連合」成立前史も充実していてすばらしい。産業報国会を基礎に出発した、戦後労働組合。共産党・産別会議と総同盟の対立。総同盟のコーポラティズム路線の挫折。産別会議に対抗する組合民主化運動の末生まれた、総評の「左傾化」。総評からの全労会議の分離。同盟、新産別、総評、中立労連の四ナショナルセンターの成立の過程は、なかなか面白い。「春闘」の開始は、民間製造業セクター主導で、組織化されていない労働者の賃金標準化機能をになったという。1950年代、労使の「生産性連合」の確立とともに、長期低落傾向の1970年代の社会党が左翼路線を強める中ですすむ、1967年から始まる労働組合統一化の流れ。1975年、「スト権スト」の敗北は、総評左派の政治主義の衰退と、民間労組の経済主義の覇権が確立をもたらした。1989年、74単産800万人のナショナルセンター「連合」の誕生。そこでは、「統一」を急ぐあまり、労働組合主義、経済合理主義の路線の貫徹を、官民統一の際に確認できなかった。それが、「改革へ抵抗する労組」像にしているという。いまひとつ面白くないのは、おそらく2つ理由があるとおもう。ひとつは、分析手法そのものの問題。そして、もうひとつは、鍵となっている「経済合理的」「効率的」の説明が、一言もないことであろう。まず、立論のかなめにあたるはずの、アンケートの分析がおかしい。本書第四章に登場した、新自由主義的諸改革に対する、労働組合を2つにわけるためにもちいられた、「政府への役割期待」の項。たしかにそこでは、官公労と民間労組は思想に違いがみられ、後者は「小さな政府」を指向していたことが、アンケート調査によって検出されている。しかし、行政改革を支持した民間労組は、どうして中曽根行革と同じように、90年代、政府の提出する「住専処理法」「地方分権法」「産業再生法」に賛成しなければならないのだろう。これらの法案のどこに「行革」が存在しているのか?まるでわからない。 しかも、90年代における官公労と民間労組の、政府法案への態度(賛否)の差異は、アンケートからは検出されていない。都合が悪い結果がでたから、出したくなかったのだろうか。おまけに、クラスター分析では、労働組合の政府法案への賛成度があがっており、普通の利益団体化しているという。そもそも、この本の出発点となったアンケート調査の分析そのものに、評者は疑念をいだいてしまう。さらにいえば、国民経済「全体」において、「経済合理的」「効率的」とは何なのか。そのことについての説明がまるでない。なるほど。たしかに経済を語るには、念頭においておかねばならぬ理念だ。しかし、なにが「経済合理的」「効率的」であるかを、どうやってそれぞれの「主体」が判断できるのか。そもそも、労組も、企業も、政府も、個人も、「経済合理的である施策とは何か?」をめぐって、常に争っているのではなかったか?(むろん、自己の利益をそうした美辞麗句で粉飾するわけだが)。「経済合理主義」組合運動ならば、なぜ小泉構造改革を支持しなければならないのか? これらの説明がどこにも書かれていない。そこには、暗黙の前提に「政府は合理的」という考えがあるとしかおもえない。それは、中曽根~小泉改革のバックボーンとなった、新自由主義的改革のスローガン=「市場は合理的」の対極にある思想ではないだろうか?官公労以上に、筆者ご自身が「改革抵抗勢力」ではないのか?靴(理論、結論)に合わせて足(現実、歴史)を切る。そんな感じが、どうしてもぬぐえなかった。1980年代と90年代の、労働組合の「改革」に対する反応の違い。それは、労組をとりまく「好不況」といった環境にこそあるようにおもえる。そういえば、2000年総選挙で「構造改革」を唱えたのは、組合を基盤とする民主党だった。しかし、ここでは何ひとつ言及がない。どうやら、「改革」という言葉さえ同じなら、中曽根とおなじ対応を橋本・小泉に与えないとダメで、民主は考慮に値しないようだ。というか、一歩間違えれば、アカデミズムを装った、ただのデッチアゲ、イカサマ、プロパガンダに堕してしまうのではないか?労働組合運動史と、圧力団体をめぐる理論整理が、とても刺激的で面白い。評価は、その2つの分だけにしました。いささか残念な感じがします。評価 ★★☆価格: ¥840 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Jun 20, 2005
コメント(2)
-

野中英次 『魁!!クロマティ高校 打撃・走塁編 13』 講談社少年マガジンコミックス(新刊)
「この漫画がとても面白いんですよ♪」その昔、とても綺麗な韓国人女子留学生に、そういって手渡されたのが、この人が描いた、『課長バカ一代』(講談社)だった。あれからもう何年も立つ。いま、彼女は何をしているんだろう。野中英次のお礼です、と僕が彼女にわたした漫画は…聴かないで欲しい。たしかに「面白かった」とは言ってはくれたけど……恥ずかしい想い出のひとつだ。閑話休題。野中英次を知らない人には、「池上遼一の絵柄でギャグマンガを描く人だよ」と説明することにしている。全力で関節を外しまくるギャグが、この人の真骨頂でしょう。脱力させられすぎて、やる気があるんだか、ないんだか、分からない。チャームポイントなんでしょうか、これ。とり・みきに言わせれば、コメディ漫画なのかもしれないけど。あ~、中身ですね。ギャグを説明するのも変ですけど…。お相撲編。相撲のマワシの起源についての話が延々つづきます。てか、この本の表題についた「○○編」は、もう中身と関係ないですから。夢見がちな子供に大人の世界を説教する、お笑い芸人プータンの芸能界論が過激で光っていていいです。われらがネット番長、藤本貴一も大活躍します。ラブのな日記がついていて大変お得です。でも、プータンを困らせた子供じゃないけど、野中先生、最近疲れてませんか?ギャグがいまいちなんですけど。というか、今まですっかり忘れていましたが、登場人物の名前などは、結局問題ならなかったのですね。ちなみに、マニエル高校、デストラーデ高校、山口ノボル、他には…まあいいや。もし、興味をもたれましたら、『課長バカ一代』のベストセレクションがあるので、そちらを買って芸風をたしかめてから、本編をお買いもとめください。たぶん、こちらを買う方が確実です↓ 追伸そういや、過激なマンガといえば、あさりよしとお先生の『重箱の隅』『ラジオマン』(過激すぎて未刊)を思い出したけど、どうなったんだろう。評価 ★★★価格: ¥410 (税込)人気ランキング順位
Jun 19, 2005
コメント(3)
-

★ 山田由美子 『第三帝国のR.シュトラウス 音楽家の<喜劇的>闘争』 世界思想社 2004年
「戦前日本はナチスと違う!ファシズムではなかった!」と喋るアホがいる。逆の意味で、まったく同感だ。ナチス・ドイツはカッコイイヒロヒト・ニッポンはカッコワルイドイツの文化を愛するものにとって、日本と一緒にされてはたまらない。本物のエリートは、植民地朝鮮ですら欧米にあこがれた。モンペに国民服。猫背のチビが現人神になったため、欽定憲法明記の帝国議会が潰せない。その現人神はのうのうと生きて、人間宣言。やったことは大してかわらないのに、何やらせてもマヌケでジメジメ。その証拠に、サブカルをみよ。敵役はナチスだらけだ。ヒロヒトをお呼びなのは、それ以上にダサい、中国くらいしかない。ドイツの名誉のために、「マヌケファシズム」くらいが好ましい……失礼。世界に鼓吹された、「ドイツ音楽の絶対性」バッハ、モーツアルト、ベートーヴェン、ワーグナー、ブラームス… その正統な嫡子にして「最後の大音楽家」、リヒャルト・シュトラウスくらい、その偉大さが評価されていない音楽家も珍しい。ひとつにはシュトラウスは、ワーグナーの楽劇様式の完成者とされ、それ以後の活動は「衰退」とみられたこと。なにより、解任されたとはいえ、ナチス政権下、帝国音楽局総裁に就任したためでしょう。本書は、その評価に敢然と異をとなえ、音楽史の再考をせまります。「喜劇」によって「昏迷の時代」を治癒せんとする、老芸術家の40年にもおよぶ、後半生の孤独な戦いをえがきだすことによって。西欧啓蒙主義への反発から、汎ゲルマン主義をもとにして、「非理性」をかかげたドイツ・ロマン主義。退廃・不安・倦怠におおわれた世紀末。その脱却からか、第一次大戦やナチス台頭時には突如として、狂信的愛国主義や「自由からの逃走」に熱狂してしまう。自由と「全体性への渇望」の狭間にゆれるドイツ。そうした「時代の迷妄」を代表する台本作者、ホーフマンスタールとの「オペラ史上空前の黄金コンビ」による創作活動。ただ、悲壮・勇壮感あふれた愛と戦いの神話=「悲劇」にこだわる、彼との共同作業は、不協和音の連続だったのです。バイエルン生まれの個人主義者。そして陽気なシュトラウスは、「かけがえのない個人」をえがこうと、「喜劇」台本をもとめました。そこに、ホーフマンスタールを介して時代を治癒しようとする、シュトラウスの努力を嗅ぎつける筆者。「ワーグナーの後継者」は台本作者にめぐまれない。「空疎な台本」で、その音楽の才能を浪費しつづけるシュトラウス。時代を治癒せねば。人々に悲劇ではなく喜劇を! 今こそオペラ・ブッファ(喜劇オペラ)、純粋喜劇の復興を!そこにあらわれた、ユダヤ人作家シュテファン・ツヴァイク。70歳の老巨匠の手に、待望の台本がとどいた!その名は「無口の女」。そこに訪れた、1933年のナチスの政権掌握。息子フランツは、ユダヤ人女性と結婚していました。絶望的な状況下、第三帝国の支配原理そのものを愚弄した、シュトラウスの命をかけた活動が、ここからはじまるのです。喜劇オペラ「無口の女」の台本にそった、<喜劇的>闘争が。メンデルスゾーンの銅像が壊され、マーラーとマイヤベーヤの上演が禁止され、ユダヤ人音楽家がつぎつぎと追放されていった、ナチス・ドイツ。そのナチスが、狡猾な魔術師によって翻弄され、ユダヤ人台本作家のオペラ「無口の女」は、とうとう上演されてしまうのだ。あわや、ヒトラーとゲッペルスが、初演に臨席させられる予定だったとは! その顛末は、ぜひ読んでみて確認してほしい。それだけではありません。1935年7月、当局に公然たる反ナチ活動が知られ、総裁の地位を解任されるものの、その後もシュトラウスは粛清されることなく、ナチスの獅子身中の虫として生きつづけます。『オリンピック讃歌』『紀元2600年祝典音楽』の指揮・作曲のみならず、ナチをあてこするように、オペラ『カプリッチョ』『ダナエの愛』『平和の日』を送りだした、シュトラウス。戦時下に行なわれた数々の闘争。かれが音楽にこめた精神と哲学は、ヨーロッパの教養ある人びとの目をゴマかすことはできない。「ナチ協力者」の汚名も、人々の歓呼の声で晴らされることになる。1949年逝去、享年85歳。この要約だけでも、そのすばらしさの一端は理解できるでしょう。ナチス協力の過去ゆえに、後期ロマン派を代表した、若い頃の交響詩とオペラしか評価されてこなかった、シュトラウス。そこに筆者は、セルバンテス、ベン・ジョンソンに連なる、一貫した「反ロマン主義」「反ワーグナー」音楽としての、連続性と発展性を見出そうとします。そのアイデアと精緻な実証は成功しているといってよいでしょう。むろん、豊潤な先行研究にたよっている部分が多いのは、難点かもしれません。とはいえ、知られざる一面には、さらに別の角度が加わっているのです。邦訳文献の少なさもあって、讃えられるべきことでしょう。「自分がアーリア人であることを証明できる作曲家を二人あげよ」解任後の1935年暮、帝国音楽局から届いた、作曲家の資質を問う調査書。その質問の一つに、リヒャルト・シュトラウスは、こう記入したという。 「モーツアルト」「ワーグナー」伝統と、未来とをつなぐ、自負と諧謔。なんと心地のよいことか。シュトラウス・ファンやクラシック・ファンだけが読むのは、あまりにももったいない。音楽が「もうひとつの政治」であった国ならではの、激烈な闘争の数々。ナチスに興味のある方なら、ぜひ読むべき、すばらしい好著になっているといえるでしょう。評価 ★★★★価格: ¥2,310 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Jun 17, 2005
コメント(4)
-

★ 金賛汀 『拉致 -国家犯罪の構図』 ちくま新書(新刊)
正直なところ、「拉致問題」に興味がわかない。所詮、アカの他人です。それが日本人というだけで、大騒ぎできる感覚がよくわからない。ツチ族難民や、北朝鮮飢餓民や、JR脱線事故犠牲者の方が、大量に死んでいるだけに、とても嘆かわしい。横田夫妻のセリフ「めぐみは生きてます!」「北朝鮮に制裁を!」。それを聴くたびに、生きているなら問題ないだろう、「拉致」でなぜ制裁せねばならん?核武装や中立朝鮮の出現の方がよほど問題だろう、と思ってしまう。まいったね。おかげで、テレビ・新聞・週刊誌・ネットの「石石混交」の情報をスルーしてきた。2004年9月、「救う会」調査部門から独立した「特定失踪者問題調査会」は、1953年から2003年(!?)までの二百数十名の失踪者名簿を発表している。こうした動きには、「便乗商売もいい加減にしたらどうだ?」とさえおもっていた。とことん、傍観者であった。こんな評者からみても、「拉致」問題を理解するために、かなり面白い本に仕上がっています。その理由は、北朝鮮・南進統一のための「革命」「戦争」の継続の中に、日本人拉致を位置づけようとする、一貫した体系性=全体への指向があるからでしょう。建国以来の北朝鮮政治と朝鮮総連の動きの分析は、目からウロコの思いがします。敗戦後、密航によって結ばれていた日本と朝鮮半島。当初、さまざまな派閥があった北朝鮮。金日成は、内務省を掌握し反党分子を粛清してゆくことで、絶対的地位につきます。朝鮮戦争で後方基地となった日本。朝鮮総連の多くは、ふたたび外国の植民地になるのではないか、という疑念から、米軍の動向をさぐり、戦争反対をとなえ、吹田事件などの騒擾行為をおこしたという。とはいえ日韓国交回復以前は、日本人は韓国へ往来がなく、対韓工作に日本人を利用する余地はなかったという。1965年以降の韓国経済の回復によって、あせる北朝鮮。それは、武力解放路線へとなって、ベトナム戦争のような韓国内ゲリラ作戦の展開になってあらわれた。日本人旅券を不正使用した北朝鮮工作員の活動も、監視の緩い海外で韓国人協力者をつくるため、この頃からはじまったという。この当時までは、工作員は日本生まれ、日本育ちで、日本人を拉致する必要はまったくなかったらしい。「必要なら日本人拉致」は、1969年の金日成指示までまつ必要がある、といいます。それは、米ソのデタントによって、武力解放路線を禁じられ、韓国内の反政府勢力による軍事政権転覆の必要性が生じたためらしい。そこに登場したのが、1973年から75年に、金日成の後継者の地位をかためた金正日。世襲には、「朝鮮解放の英雄」に劣らぬ「統一」の金看板が必要だったという。「対韓工作」機関を金仲隣から奪取した金正日。1970年代にもなると、党連絡部の対韓工作員は、さすがに老齢化してきていた。在日朝鮮人は、出身成分では「動揺分子」にあたり、対韓工作活動には、教官にするにも、工作員にするにも、機密保持からみて使うことができない。おまけに在日は、1970年代には「帰還」を拒絶するようになった。そこで、あたらしい工作員の専門的資質の向上と、1980年代の海外拠点での活動のために、この時期に集中して、あとくされのない韓国人や日本人の拉致活動がおこなわれたという。そして、韓徳銖・金柄植らの幹部の牛耳る朝鮮総連は、党連絡部の韓国軍部などを対象にした対韓工作に、在日の疑問や不満をよそに積極的に関与してゆく。死刑判決をうけた多くの在日たち。大物工作員と、それに協力を強いられる人々の描写。そして、北朝鮮の工作活動のさまざまな試行錯誤も、詳細に記されていておもしろい。なにより、見通しの良さがたいへん心地よい。有用な人材を革命の大義のため連行する「拉致を犯罪視しない」国家体質は、1930年代のパルチザン活動から、連綿と続くものらしい。韓国側の拉致被害者は、「北朝鮮礼賛声明」を出させられたため、その家族は被害者でありながら、KCIAの厳しい取調べにあい、スパイの家族扱いされて、世論に訴えることができなかった。「太陽政策」を推進する金大中・盧武鉉政権でも、バックアップされていないらしい。左右双方から、見捨てられているという。帰還事業の悲劇も、朝鮮総連結成時に韓徳銖の方針に反対した、日本共産党系活動家の帰国者が狙い打ちされ、政治犯収容所に入れられたという。自称保守論壇誌で暗躍する、元・共産党関係者の素性をかんがえると、なかなか味わい深い話ではないか。また、TBSと「調査会」の迷走と謝罪は、記憶にあたらしい。垂れ流されていながら、誰も責任をとろうとしない「リーク情報」。こうした真贋を嗅ぎわけ、踊らされないようにするためにも、必須の本なのかもしれません。ただね。公開された新資料があるはずもなく、巷間に流布した証言などによって構成されている本書。これが、小泉2002年訪朝以前に出されていたら、たしかに素晴らしい本かもしれません。しかし、今になっては、これではいささか問題あるのではないか。だって、その大部分は、小泉訪朝以前から分かることばかりなのですから。また、体裁上、北朝鮮と朝鮮総連の責任を一応追及してはいるが、金正日の釈明以前の彼らを責める資格が、はたしてどれくらいあるのか。むしろ、在日と総連とをきびしく峻別することで、在日への批判をかわそうとしている、そんな姑息さを感じさせなくもないのは、タマに傷になっています。むろんそんなことは、われわれが要求するような筋合いではないのですが。あと、「国家の拉致」として戦前日本の朝鮮人・中国人狩りと一緒にされてもなあ。そもそも、「隠そうとしていない」日本と一緒にされても、かなり困るんだけど。実は、そこに「時代の転換」と50年間の人権感覚の変容があるはずなんだけど、「革命」と「戦争」という視角を打ち出しておきながら、打ち出した本人が気付かないのはどういうことだろう。とはいえ、問題系を整理するためには、お勧めの一冊にはなっています。評価 ★★★価格: ¥735 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Jun 15, 2005
コメント(5)
-

古川隆久 『政治家の生き方』 文春新書
なかなかの好著です。われわれには、あまり馴じみのない、明治憲法体制下の議会政治家たち。6つのテーマで12名の政治家をえらびだす。明治から昭和前半にいたる、政治家群像。「憲政の神様」 犬養毅と尾崎行雄。「首相の座をめぐる明暗」 床波竹次郎と浜口雄幸。「雄弁家」 永井柳太郎と西岡竹次郎。「策士」 森恪(つとむ)と秋田清。「地方政界から国政へ」 木下成太郎と田辺七六。「ライバル」 前田米蔵と鳩山一郎。キャリア官僚出身政治家の草分けだった床波の挫折。ジャーナリストから転進した犬養・尾崎の軌跡。犬養に気に入られ、政界再編に奔走する秋田。日中戦争中、副総理格に登りつめた永井と、都市型政治家の先駆け西岡。地元政界に睨みを効かした田辺。戦時議会下、政治の危機にあって、軍部と妥協と交渉を重ねた前田。われこそは、選挙民の負託をうけたるものなり!官僚や軍部、藩閥などと張りあう、議会政治家の気概がここちよい。でもね。現代の政治家も、棺桶に入れば評価されるものさ。「昔は全存在をかけた」「日本人も学べ」という、編集者とおぼしき人が書いた、表紙裏の「あおり」の胡散臭さが鼻につく。全存在をかけない政治家など、そもそも名を残しはしない。「あ~う~」宰相大平正芳は、「保守本流の見識」を代表する政治家にされたではないか。安倍晋三など人気者は、これとは逆になりやすい。また筆者の二大政党制にこだわるな!「大同団結」「保守合同」をとなえる政治臭も、この本の価値を随分さげています。だいたい何故、日本に定着しないはずの二大政党制が、それでも必ず回帰してきて、しかも一定の成功(あんな社会党でも、それなりの成功をみているとはいえる)をみるのか。その考察が決定的に欠けているのではないか。「同じような主張」ならば2つもいらない? 一見同じにするため、どれくらい「2つとも」苦労しているか。筆者は「中道化原理」を学ばれた方が良いのではないか? 過度の歴史主義は、悪質な政治プロパガンダに利用されやすい。文春新書らしいとはいえ、その見本のような著作を読まされると、いささかゲンナリさせられてしまう。この書では、こうした「一方的な思い入れ」からくる、前田米蔵など「戦時議会」部分の面白さが際だっています。それだけに、なんかとても残念におもえます。 評価 ★★☆価格: ¥735 (税込) 人気ランキング順位
Jun 13, 2005
コメント(1)
-

★ 新宮一成・立木康介 『フロイト=ラカン』 講談社選書メチエ(新刊)
さっそく私は叱られてしまった。ラカンを語るなら、ラカン『エクリ』を読め!ジジェクやコプチェクの本で代用するマネはするな!! すみません、スラヴォイ・ジジェクで間にあわせています。読む暇もありませんし、分からないし。あと、精神分析の臨床に身をおけ!と言われても…カントの「物自体」、ヘーゲルの「絶対知」に対して、フロイトは「出会い損ない」を語った。本書では、フロイトの発見はジャック・ラカンに掬われることで、「再発見」されたと整理します。人間は、言語活動(夢もその一つ)で現実から引きはがされる中、どのように「現実」に到達できるのか。人間は、快感原理にしたがい死をめざすものではないか。ラカンは、フロイトという泉から何を汲みだしたか。無意識から「他者の語らい」を。自我から「主体」を。ナルシズムから鏡像段階を。失われた対象から、「対象a」の理論を。エディプスコンプレックスからシニフィアンを。「快感原理の彼岸」から「享楽」を。(本書のラカン理論の概略: 興味のない人は飛ばしてください )無意識は、他者の欲望の場で、言語によって構造化されている。鏡像は、本質的に他者のもので「想像界」に属す。他者への攻撃性は鏡像の奪いあいにもとづく。その「想像界」は、イメージでの自己認識とそれによる他者関係のことで、絶望的に不安定だ。それを第三者として外側から支えるのが、「大文字の他者」。ナルシシズムは、自我理想(象徴界)として機能して、主体が想像界を生きられるものする。では主体とは? ラカンは象徴界への「主体」の参入を「疎外」とよぶ。人は、他者から与えられるシニフィアンに同一化することで、主体を生成する。主体は、シニフィアンと「存在」との間で分裂を余儀なくされる。主体の真理を保証するはずの「大文字の他者」は、それ自身自らの正しさを根拠付けるシニフィアンをもたない(「メタ言語はない」)。この困難を前にして、主体はその「欠如」について、「対象a」という欠如で、埋め合わせをおこなう。主体は、それ以前の生存を「対象a」に移してしまう。大文字の他者の欲望を示すシニフィアンは、ファルスである。「去勢コンプレックス」によって、男性のエディプスコンプレックスは没落し、女性のエディプスコンプレックスの形成がはじまる。「精神病」は、「父の名」のシニフィアンを棄却する「排除」によって、象徴界ではなく、幻覚・妄想という形で「現実界」に出現してしまうことをいう。享楽は、「快=善」という象徴界の論理をこえた欲動的な、カント・サド以来の「悪の幸福」をとらえるための枠組である。享楽は「不可能」なものだが、法は禁止することで享楽をささえ、法を破ることで手に入れることができるという錯覚をもたらす。享楽をシニフィアンに接合させるファルス関数によって、性別の決定とともに合法化された「ファルス享楽」は、対象aによって運ばれる。ファルス享楽は男性的なものだ。女性的な語れない「追補享楽」というのもある。もっぱら対象aによって運ばれるがゆえに、「幻想」を生きるほかはない。「女はない」「性関係はない」。ファルスは、超越的な他者の意思を仮定する思考法にとらわれさせるもとになる。そして「転移」は、「大文字の他者」の欲望である「対象a」を発見するための装置である。うんぬんかんぬん…(概略終わり)ハアハアハア… つ、疲れる…。まとめるだけで、こっちは死ぬような思いでした。ラカンといえば、シニフィアンの優位。シニフィエをシニフィアンの「遡及作用」「効果」に還元することによって、フロイト・「事後性」「心的外傷」の理論を拡張したというのが面白い。語りえないものは、シニフィアンとの同一化によって、事後的に修復される。言語で不可能にされて手放した真理を、人は「尊いもの」と読みかえ、真理を守る仕組を社会につくりあげるという。メディア(媒体)にまきこまれてしまっている、主体。個人情報こそ、あなたの社会的アイデンティティであって、あなたは間違いの多いコピーでしかない。南京事件否定派などの歴史修正主義は、それを支える内容がナチスの利用した手法と同じであり、かれら自体がその発言内容を裏切って、大量虐殺への道がどのように切りひらかれたのかを説明している、「喜劇」の再演にすぎないこと。そして、ホロコーストの核心は表象【不可能性】にあること。象徴界は、自己完結することはありえない…。これらの洞察は、いろいろな面で社会に応用できるでしょう。ジャック・ラカンは、汲めどもつきない、思考の泉となっているのです。あと、政治・宗教・哲学・教育の「主の語らい」に対して「精神分析家の語らい」を構想するラカン。実は、かのスラヴォイ・ジジェクの理論的バックボーンは、ジャック・アラン・ミレールの明晰な整理にあるらしい。知らなかったなあ。なんといっても、赤間啓之『ユートピアのラカン』(青土社刊)でけちょんけちょんに貶されていたので、どんなやつかと思っていました。「フロイトのハイデガー化」といわれたジャック・ラカン。その一端がわかる格好の入門書となっています。あとは『エクリ』を読むだけだ…絶対無理。追伸 「親鸞とラカン」の共通性は余計すぎるとおもうゾ。評価 ★★★★価格: ¥1,680(税込) 人気ランキング順位
Jun 11, 2005
コメント(1)
-

★ 吉本佳生 『金融広告を読め どれが当たりで、どれがハズレか』 光文社新書(新刊)
すばらしい。「資産運用の新約聖書」の登場です。お茶の間にとどく、中国株、インド株などをはじめとした、様々な新商品。本書は、外資系金融と金融工学の神話をぶっ壊し、そのほとんどがボッタクリ商品であることをマニフェストします。外資に立ちおくれる邦銀の姿も、べつの一面が見えてくることでしょう。その大概のものが、バブル期につかわれて、あとで問題になった商品の焼き直しにすぎなかったりします。あなたの一生を左右する資産運用。ダマされて預けてしまう前に、ぜひ読んでおきましょう。たかが1200円の出費ですむのですから。とりあえず、本書の要点をまとめておきます。1 高金利預金は、適用利率の期間に注意せよ。2 外貨預金は、バカ高い為替手数料を2度とるためにあります。3 利用額に上限をつけるキャンペーンは、まだマシ。4 広告は、バカな客と賢い客を選別するためにおこなわれる。5 セット商品は、手数料を稼ぐためだけに開発された、使えない商品。6 セット商品は、単独金融商品より、顧客はほぼ確実に「損」をする。7 長期預金は、インフレに弱いので、中途解約条項を絶対に確認せよ。8 リスクは予想される結果バラつき。リターンは予想される利益の期待値。9 ハイ・リスク、マイナス・リターンがほとんど。売買コストを勘案せよ。10 株式投資信託、地方債、年金保険は、ETFにくらべ売買コストが高い!11 価格変動リスクだけとれ!(信用リスク、流動性リスクは負うな!)12 ソニー銀行の外貨預金は、他のそれや証券会社のMMFよりいい。13 外貨預金は、かならず、その通貨国の国債金利と比較せよ。14 個人向け国債はまあまあ。社債と国債の利回り格差は、倒産確率と考えよ。15 元本保証「年金保険」「特約つき○○」やEB債(他社株転換条項付債権)、 そして「特別勘定」(ほぼ株式投資信託)の文字をみたら、 手数料稼ぎのボッタクリとおもえ。16 REIT(上場不動産投資信託)、エマージング債券などの投資信託は、 「販売手数料」と「信託報酬」の比率をみよ!ほとんど不利。 「毎月分配型」はさらに不利。 経路依存オプションは、さらにボッタクリ。17 リスク限定型投資信託を買うくらいなら、株式オプション取引をやれ。18 欧米プライベートバンクは、高級ホストクラブ。19 金融商品の広告は、家電広告とは異なって、宣伝コストの分だけ割高。20 商品ファンドや、中国・インド株なども、手数料が不明でコストも高い。…結局、「自分で勉強して株式」もしくは、国債ということらしい。どんな商品を買っても、必ず「手数料」分だけ損をします、ってあたりまえのことなんですけどね、これ。しかし…「元本保証+高利回り」という顧客の欲ボケにつけこんでは、オプション取引の売側に回らせ、金融機関は確実に「オプション買い+手数料」を稼ぐ構造をつくっているとは…。名トレーダーでならした藤巻健史ですら、「オプション売」だけは生きた心地がしない、と語っているくらいです。こんなのが、はやりの金融工学なら、「大人げね~~」としかいいようがありません。なにを極端なことを。あるいは、「これだけでは、良く分からないなあ」と思われた方は、ぜひ本書を手にとって確認してほしい。だいたい、金融工学を駆使したボッタクリは、生半可なことでは理解できるはずがありません。冒頭には、手引書がわりに、カラーで広告モデルつき。本文にも同じ広告があるので、二度手間のため分厚くてちょっぴ高い。できれば、「索引」もつけてほしかった。ただ、この書の価値を損なうものではありません。お勧めです。評価 ★★★★価格: ¥1,260 (税込) 人気ランキング順位
Jun 9, 2005
コメント(7)
-

★ 中国の見果てぬ「民主」の夢 諸星清佳 『中国革命の夢が潰えたとき 毛沢東に裏切られた人々』 中公新書 2000年
天安門事件から16年。そういえば、読んでなかったな、と本棚から引っぱり出して読んでみた。中公新書は、保守(読売)にこびた、ウケねらいの本が多い。やはり、題名から感じたとおり、くだらない本だった。いや、内容はとてもいいんだ。みんなに読んで欲しいくらいです。「惨勝」といわれた第二次大戦。日本の降伏でやっと手に入れた平和。重慶談判、政治協商会議において、国民党・共産党の妥協はならなかった。たび重なる武力衝突から、1945年~49年の内戦。そして、圧倒的劣勢だった共産党による、奇跡の「人民中国」誕生へ。そんな中で忘れさられたもの。1945年、国民党と共産党の2大党派の対決の中で、孫文の遺言にしたがい、政治プログラムには、「訓政」(国民党による政治代行)から「憲政」(国民への大政奉還)への移行がのぼることになった。そこに出現した第三勢力、民主党派の躍動。羅隆基、章伯鈞、章乃器、梁漱冥、施復亮、謝雪江、聞一多、馬寅初…さまざまな意見をもつ、左は共産党シンパから、右は英米型ブルジョア民主主義者までふくんだ、キラ星のような第三勢力の光芒。かれらは、「連合政府」をとなえ、最後まで和平の望みを捨てない。極度の対立の中で、国共両党の調停をおこなう。訓政にこだわって、拙劣な対応をおこなう国民党。劣勢もあって巧妙なプロパガンダでたちまわる共産党。かれら民主党派は、内戦勃発後、国民党の弾圧に見切りをつけ、「連合政府」をとなえる共産党と提携していく。かれらの「民主」の夢を建国後つぎつぎと反故にしていった、中国共産党。1957年の反右派闘争、1966年文革によって、かれらを襲った非業の死の数々。まさに涙なしには読めない物語なのです。だからこそ、読んでいてむかついてしまう。いったい、民主党派のなにが面白くて、こんな本を書いたんだ。「武力をもって覇を争う中ではむなしい『正しさ』」「具体性がない」「バラバラ」「中国共産党に呑み込まれてしまった」「民主党派としては、中国共産党に同調・期待するしかなかった」紋切り型表現の数々。むなしい『正しさ』?バカも休み休みいってほしい。民主党派は、国共とちがい、軍隊をもたない。「力」をもたぬものは、「言葉」によって説得するしかない。「力」がないからこそ、言葉の「正しさ」に賭けるしかないのです。「正しさ」こそが、民主党派の存在の「証」ではないか。己の言葉を信じる人たちが、バラバラなのはあまりにも当たり前でしょう。それなのに、「力のなさ」と、空しさによって否定してしまうとは。それは、民主主義の夢、そのものの全否定ではないか。空しくない民主主義など、全体主義の別名にすぎまい。さらに腹が立つのは、第三勢力における、中国共産党シンパの顔が見えてこないことです。なぜ彼らは、コミュニズムを選びとったのか。民主党派の中共シンパどころか、共産党員の顔も、まるで見えてこない。だから、中国共産党に「呑み込まれる」という、なんとも受動的な表現に止まってしまう。どこまでいっても、コミュニズムの「魅力」がわからない。毛沢東に騙された? 一億総懺悔ならぬ、十億総詐欺被害者かよ。おめでてえな、まったく。最後、香港民主派の今後に注目せよ、という。今年も開かれることになった香港民主派の天安門事件追悼集会わたしは、天安門事件の「再評価」をもとめる民主派に違和感を禁じえない。どうして、「謝罪・賠償」ではなくて、「再評価」をもとめているのか。どうして、評価を定める資格が、政府にあるなどと、考えることができるのか。共産党と国民党が双生児であったように、共産党と香港民主派は双生児にすぎないのではないか。言葉を信じるしかなかった、解放以前の民主党派・第三勢力。それは今もなお、不朽の輝きをおびていることがわかるでしょう。だからこそ、彼らの存在を根本的に裏切るような、そんな人間によってこの書がかかれたことが残念でならない。評価 ★★☆価格: ¥756 (税込) 人気ランキング
Jun 7, 2005
コメント(42)
-
★ 朝日新聞に降伏した読売社説を祝福する(笑)
あ。むろん、これ皮肉ですよ。5月25日の日記で、小泉靖国参拝問題への「内政干渉だ!!」とする、単細胞な反発に警鐘を鳴らしていたのだが、とうとう読売は「国立追悼施設」構想をとなえだした。「国立追悼施設」は、左派を中心に主張されつづけた構想であった。読売流にいえば、「読売新聞が朝日の軍門に降った」ことになるのでしょう。やれやれ。WEBからすぐ消す読売新聞なので、ここはあえて全文を引用させてもらう。 ■ 靖国参拝問題 国立追悼施設の建立を急げ(読売新聞)小泉首相は、いったいこれまで、どのような歴史認識、歴史観に基づいて靖国神社に参拝していたのだろうか。 2日の衆院予算委員会で、小泉首相は民主党の岡田代表の質問に答弁し、極東国際軍事裁判(東京裁判)で有罪とされた、いわゆるA級戦犯について「戦争犯罪人であるという認識をしている」と述べた。 “犯罪人”として認識しているのであれば、「A級戦犯」が合祀(ごうし)されている靖国神社に、参拝すべきではない。 連合国軍総司令部(GHQ)が定めた「裁判所条例」に基づく東京裁判が、国際法上妥当なものであるかどうかについては、当時から内外に疑問の声があった。インド代表のパル判事による「全員無罪」の判決書はその典型である。 フランス代表のベルナール判事や、オランダ代表のレーリンク判事も、裁判所条例の合法性や、国際法上の適用に疑問を表明した。 また、サンフランシスコ講和条約発効後、いわゆるA級戦犯の刑死は国内法上は「公務死」の扱いにされた。 「A級戦犯」として禁固7年とされた重光葵氏は、戦後、鳩山内閣の副総理・外相となった。終身刑「A級戦犯」だった賀屋興宣氏は、池田内閣の法相を務めている。言うなれば“犯罪人”が法の番人になったわけである。 しかし、「A級戦犯」が閣僚として、“名誉回復”されたことについて、諸外国からとりたてて異議はなかった。 そうした歴史的経緯から、いわゆるA級戦犯は、「戦争責任者」ではあっても“犯罪人”ではない、とする議論も根強くある。 いわゆるA級戦犯が、靖国神社に合祀されたのは1978年のことである。翌79年に、そのことが明らかになるが、当時の大平首相、次の鈴木首相は、従来通り、靖国神社に参拝している。 大平首相は「A級戦犯あるいは大東亜戦争というものについての審判は、歴史が致すであろうと私は考えております」として、いわゆるA級戦犯が“犯罪人”であるかどうかについての認識表明は留保した。 小泉首相は、岡田代表の質問に答える中で「首相の職務として参拝しているものではない。私の信条から発する参拝」と述べ、私人として参拝しているとの立場を表明した。 私的参拝であるなら、参拝の方法も考えるべきではないか。昇殿し、「内閣総理大臣」と記帳するのは、私的参拝としては問題がある。 公的、私的の区別については、三木首相が1975年に参拝した際に「私人」と言って以来、関心の対象となったが、その後の首相は、概(おおむ)ね公私の区別について、あいまいにしていた。 鈴木首相の時代には、公私の区別についての質問には答えないという方針を打ち出している。 しかし、小泉首相のようにはっきりと「首相の職務として参拝しているものではない」と言うなら、話は別である。 首相の靖国参拝を巡っては、以前から「問題解決」の方法としてのA級戦犯分祀論がある。だが、現在の靖国神社は、一宗教法人だ。政治が「分祀」せよと圧力をかけることは、それ自体、憲法の政教分離原則に反することになろう。 「分祀」するかどうか、あるいは「分祀」できるかできないかなど、祭祀の内容を解釈するのは、一宗教法人としての靖国神社の自由である。 ただ、国内にはさまざまな宗教・宗派があり、現実に、宗教上の理由からの靖国参拝反対論も多い。 靖国神社が、神道の教義上「分祀」は不可能と言うのであれば、「問題解決」には、やはり、無宗教の国立追悼施設を建立するしかない。 小泉内閣の誕生した2001年、福田官房長官の私的懇談会が、戦没者の追悼のあり方について検討を進め、翌年には国立、無宗教の追悼・平和祈念施設の建設を提言する報告書をまとめている。 どのような施設にするのか、どう追悼するのかといった点で、報告書は具体性に乏しい面もあるが、早急にその内容を詰め、新しい追悼施設の建立に着手すべきだろう。 米国のアーリントン墓地には、外国の元首などがしばしば献花を行う中心施設として無名戦士の墓碑がある。 国立追悼施設も、屋外施設でよい。東京都心の新宿御苑の一角に、記念碑のような追悼施設を建てればいいとの議論があるが、十分に検討に値する。 毎年、8月15日に政府が主催している全国戦没者追悼式は、従来通り東京・九段の日本武道館で行えばいい。 ただ、小泉首相が靖国参拝をやめたからといって、ただちに日中関係が改善されるわけではない。 もともと、A級戦犯合祀が明らかになった後も、大平、鈴木首相の靖国神社参拝に対し、中国からの表立った異議はなかった。 異議を唱えるようになったのは、1985年に中曽根首相が「公式参拝」の形をとってからである。中曽根首相はその翌年に、中国の抗議に屈して、靖国神社への参拝を中止した。いわば中国に外交カードを与える結果になった“失政”が今日の混乱を招いた。 その後、天安門事件で共産党統治の求心力に危機感を抱いた中国は、「愛国・反日教育」の強化に転じ、年々歳々、膨大な数の反日世代を育て続けている。 4月に行われた反日デモのスローガンは、当初、日本の国連安保理常任理事国入りの問題であり、台湾問題だった。 今後の日中関係を考えるうえで、そうした中国の国内情勢も、注視していく必要がある。5月25日付日記で読売や産経を批判したのは、「靖国参拝=内政」という論理がもちだされたからであった。ここで知らない人のために、左派の論理をわかりやすく説明しておきたい。靖国神社の問題はなにか。それは、「個人の自由」と「外交」の2点に凝縮される。まず、個人の信教の自由が侵害されている。本人の意思とは関係なく、勝手に戦死者を「神」として祭る宗教。キリスト教徒や、戦前迫害をうけた新仏教などは、靖国神社に批判のまなざしを向けるのはそのためだ。だから左派は、靖国神社を違憲とする。そして、アジアへの凄惨な加害のシンボル「A級戦犯」を、戦死者を神として「顕彰」する施設。これで参拝などしていては、先の大戦を世界に反省したことにはなるまい。ゆえに、顕彰ではない追悼のための、無宗教施設が必要なのであった。だからこそ、左派は本質的に小泉首相の靖国参拝を批判しきれないなぜなら、小泉首相の信教の自由は当然、いかなるときにおいても、認められなければならない権利だからだ。だから「私人参拝」なのである。ここに、靖国神社参拝問題が、えんえんと問題にされてきた遠因がある。左派は、決定的な一打を打ちだすことができない。たとえば、朝日新聞の論調を思いおこしてほしい。つねにアジア外交への障害を問題にして批判的な論陣をはってきた。それは当然だ。「個人」から出発する左派の理屈からすれば、小泉首相を「個人の信仰の自由」の方向から批判することなどできないのである。そこを見落とす、知性のない人は、相手に「反日」というレッテルをはることになる。だからこそ小泉首相は、「深い追悼」をあらわす、と信仰を強調してきた。それゆえに朝日新聞の社説は、どんなに反対しようと、小泉首相のその思いが靖国を参拝することで果たされるのかという次元でしか、批判することができない。それは、左派からすれば、当然の節度といえよう。「行くな」と踏み込むわけにはいかないのだ。ところが読売や産経は、「外交」しか読みとることができなかったようだ。対抗策に「内政干渉」などと言いはじめた。これによって、小泉首相の靖国神社参拝は、「内政」へと次元が移った。小泉は、左派の「信仰の自由」をもちいることで、自己正当化できていた。それが、読売・産経の手によって「内政」になった。内政は外交と連続する以上、安倍晋三などの自民党閣僚や保守系新聞社は、靖国神社参拝が「政治」であることを追認したにひとしい。読売は、今回の社説でも「政治」の論理から靖国参拝をとらえる。「失政」と書いた部分を見てほしい。「政治」の論理ならば、靖国神社参拝の当否は、あくまで外交における功罪・損得で判断せざるをえない。だからこそ「失政」になる。そして、「戦争犯罪人」と判断するならば行くな!という論理も、功罪・損得から判断されているに違いあるまい。小泉首相の参拝は、犯罪人の顕彰にしかならず、失敗という判断があるのだろう。また読売は、いつも「法」「条約」解釈を延々たれながす傾向があることをおもえば、法と密接にかかわる「罪」に反応してしまった、とみることもできよう。それらは簡潔に整理すればこうなる。A 「14名=戦争犯罪人」なら靖国神社参拝不可B 「14名≠戦争犯罪人」なら靖国神社参拝可しかし、これは朝日新聞などの社説と比較しても、酷いとしかいいようがない。なぜならここには、残る2つの次元がないものとされているからだ。C 「14名=戦争犯罪人」でも靖国神社参拝D 「14名≠戦争犯罪人」でも靖国神社参拝不可Cの次元は、小泉首相の立場である。A級戦犯以外の英霊の追悼をおこなおうとすることが、なぜ切り捨てられなければならないのか。そもそも理解に苦しむ。また、Dの次元だってあるはずであろう。そもそも天皇が裁かれない「東京裁判」になんの意味があろう。天皇は、マッカーサーに命乞いをして、木戸日記提出に見られるような、「司法取引」をしたにすぎない。昭和天皇からGHQに差し出された、国体護持のための生け贄という意味で、「昭和殉難者」(by 靖国神社)とは事態の半面を正確に射ぬいている、という立場もあっていいはずだ。むろん、こういう人は、靖国には反対であろう。こうしたさまざまな次元をもつであろう、靖国神社。1億人もいれば、人それぞれはちがう。それなのに、一刀両断にAとBの2つに整序してしまい、参拝に反対どころか、しないようにせまる。これは、個人の自由という観点から出発して、靖国神社のイデオロギーを問題視してきた左派の論理とは、「国立追悼施設」の結論はおなじでも、次元をまったく異にしたものである。つねに、国家的見地から出発して、個人の権利を論じる姿勢をもつ、国家主義的な読売新聞。だからこそ、小泉首相靖国参拝に反対してきた朝日社説の微妙な言いまわしをとびこえて、「行くべきではない」とまでいえるのではないか。そこに抜けおちているのは、「個人の権利」という観点である。だからこそ、読売の社説は無惨である。参拝擁護の社説を出しながら、朝日新聞とおなじ結論にしかならない。しかも、小泉首相の靖国参拝が外交上の失点であることくらい、本人が戦争犯罪人と考えようが考えまいが、なんの関係もなく、とっくに確定したことではないか。そんなことは、出し手ではなく、受けとり手の問題のはずだ。そして左派はみな、「外交」に不利益をおよぼすからとして問題にしていたのである。さんざん、擁護した挙げ句、このザマ。読売に踊らされた人には、同情を禁じえない。人気ランキング
Jun 6, 2005
コメント(3)
-

★ 藤沢秀行 『野垂れ死に』 新潮選書(新刊)
泣いた。不覚にも泣いてしまった。失格だ。「勝負師」藤沢秀行。今年、80歳。おおらかな性格で親分肌。若手棋士相手に「秀行塾」を開き、熱心に教えた。たびたび「秀行軍団」を率いて中・韓を訪れては、若手に稽古をつけたため、「日中・日韓逆転の戦犯」あつかいされたこともあった。ともに、囲碁という芸をきわめるため、集うもの同士。追い抜かれたら抜き返せばいいんだ。ケチくさいことをいうな。本人は気にもしない。今も中・韓の若手棋士から慕われている。「1年を4勝でくらす、いい男」「ポカさえ無ければ、俺が最強」「初物食い」「異常感覚」…さまざまな形容。50台で、囲碁界国内最高とされるタイトル、棋聖戦6連覇。66歳で7大タイトルの王座を奪取。しかし、そんなところがすごいのではない。とにかく、人間が大きい。言葉にならないほど大きい。周りからは、「秀行先生」と誰彼となくよばれる、その包容力の大きさ。空前絶後の、破天荒な生き方。あこがれます。「呑む、打つ、買う」アル中。繊細な人なので、アルコールの力を借りないとやってられない。「お●んこ」「低脳」とさけび、暴れまわって警察にご厄介。しぜんアル中にかかる。禁断症状の中で「酒断ち」をして棋聖戦を防衛。行いのためか、3度もガンにかかる。今度こそ死ねるとおもってもしねない。ガンの方が先に死んでしまう。なにかが間違っている。博打好き。日本棋院から前借なんてなんのその。競輪で厄介な筋から金を借り、沢建設をつくり手形を振出まくる。「今回、手形を忘れたけど、手形の更新をお願いします、後で破いておきます」という言葉を信じたところ、破かれたはずの手形の請求が。一再ならずあったというこの話。やはり気にもしない。買う。妊娠させた女性は、数知れず。正妻のもとにつぎつぎ来る認知要請。本人は平等に愛しているらしい。家を買った直後から、正妻のもとに3年間帰らなかったため、家路を忘れた男。いまでは、着る服から病気まで、妻なくては生きていけない。妻には文句ばっかり。周囲にはのろけ、妻の耳に伝わるようにしているらしい。ごちそうさま。秀行自伝という形態。ほとんど知っている話ばかり。それなのに、何か悟りでも開いたのかとおもわせるような内容と流麗な文章で、読み出したらとまらない。それは囲碁へ捧げられた愛の深さにある。酒を飲んでも、競輪にかよっても、不倫をしても、起きている間は、片時も囲碁のことを忘れない。何やらせてもできる人なのに、あえて囲碁のみに没頭し、可能性を削りおとしていった先にある境地。酒に飲まれたのではない、「囲碁に飲まれた」人生だけが語れる、そんな領域があること。それを確信させてくれる、すばらしい本といえるでしょう。最後の一節。結婚後、はじめて妻のために用意したという、かれのプレゼントに泣いてしまった。不倫をしたことのある男性は、ぜひ読んで参考して欲しい。やはり、人間の器のちがいなのかなあ。凡人が渡すと、逆に怒られると思うんだけど、、、神仙の境地に達したものだけができる、余得かもしれない。評価 ★★★価格: ¥714 (税込)現在の人気ランキング
Jun 4, 2005
コメント(7)
-

松浦章 『中国の海商と海賊』 山川出版社
強力な華僑ネットワークが存在する、東アジア~東南アジア。マラッカ海峡では日本人が海賊におそわれ、一時話題にもなりました。これは、「中国人の海」の歴史的淵源をたどった、格好の入門書になっています。唐代、イスラム商人が広東に来航。宋代以後、さかんな海上交易にともない、海賊活動も本格化するようになったといいます。とくに元代は、どの王朝よりもさかんな海上進出がおこなわれ、イスラム商人なども来航し、海賊などの招聘につとめたという。エジプト・アレクサンドリアを上回る、海上交易の中心だった、福建省泉州。とくに倭寇との関係は、われわれの興味をひくものがあります。明朝は、「海禁」=「朝貢貿易」をおこなっていました。鄭和の南海遠征などは有名です。しかし1523年以降、日本との朝貢貿易の停止にともない、「嘉靖の大倭寇」が誕生したという。襲撃は、東北の風がふく、4~5月、10~11月。倭寇は、中国海賊とむすびついて、環東シナ海に巨大な海上勢力が誕生しました。大倭寇で名高い、王直の知られざるエピソードは大変面白い。むしろ清代は、沿海貿易と外国貿易の区別をつけておらず、空前の海上交易の発展をみたという。米穀・大豆・砂糖など、単品大量海上輸送がおこなわれた清代。海船経営も、商業目的から運賃収入を目的にかえて、運輸業の自立化がはじまりました。商人の交易対象国も、固定化。それまでの不定期交易から定期交易へと深化してゆきます。多くの中国人は、こうした定期交易のルートにのって、南洋へとわたって、交易活動に従事していったという。南海で遭難した日本人は、中国人の定期船ネットワークを利用して、日本に帰国していたというのも、知られざる一面でしょう。「世界史リブレット」という形態もあって、薄さのわりにやや値段が高いのが難点か。すぐ読めてしまうのでもったいないかも。ただ、昔の海上交易のやり方なども、具体的に記されていて、大変わかりやすいのが喜ばしい。やはり今とは、まるで違う。昨今、拡大しつつある中華経済圏。日本では、倭寇後は「朱印船貿易」「鎖国」で終わってしまうため、あまり知られていません。だからこそ、現代の華僑ネットワークにつながってくる部分は、本書の白眉となっています。少し古いけど、お勧めしたい本のひとつです。評価 ★★★価格: ¥765 (税込)人気ランキング
Jun 2, 2005
コメント(0)
全15件 (15件中 1-15件目)
1










