2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2005年12月の記事
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-

★ 鈴木貞美 『日本の文化ナショナリズム』 平凡社新書(新刊)
ご隠居、てーへんだ!てーへんだ! 。天皇制は発明されたものだったんだ!くまさん、なに朝っぱらから騒いでんだよ。そんな所に立ってないで、こちらにお入り。 これが騒がずにおれますか、ご隠居。この本によれば、紀元節も武士道もニセモノで、「穢れ思想」は日本だけのものではないらしいんですぜ。そして、東洋美術は「精神(気)の表現」、といった日本美術論も、ヘーゲル『美学講義』を密輸入しての発見にすぎないというんです。「漢文」を含んでいる日本文学史ってのも、考えてみりゃ、イカサマだ。ラテン語叙述をいれたイギリス文学史、みたいなもんじゃないですか。世界でそんなバイリンガルな自国「文学史」をもつ国は、日本と朝鮮くらいしかないんですぜ。ちきしょー!騙された!いきり立つのはおよしよ、くまさん。そんなのあたりまえのことじゃないか。そもそも「武士道」ってのは、新渡戸稲造によれば、「民族の信仰」としての神道を起源として、陽明学の知行合一をあわせたもの…なんだよ?。「民族」ってなんだい。そんなの「伝統の捏造」に決まってるじゃないか。天皇と庶民を一つの家族として強調するために、「血統」「家族」なる観念でさえ、本当は近代に入って強調されてくるんだ。漢文もそうだろう。明治の公文書が漢文体だったんで、むしろ漢文教育が強化されてるんだ。漢詩創作の全盛期は、実は明治だというしな。徳川期には「漢文~和漢混淆文~和文」の幅広い読書層が形成されていて、「俗語体」による明治「文学革命」なんてものはなかった、ってことをしらねーのかい。それだけじゃないんです、ご隠居。「自然を愛する日本人」「童謡」ってのも、明治のつくりものらしいんだ。松尾芭蕉たち「ワビ・サビ」や幽玄の美なんてのが、日本文化の神髄、「日本的」なんていわれだしたのも、大正時代らしいんだ。狂言や、闘茶・大名茶なんて、わざわざ無視されて。なんか騙された感じですよ。おらあ、もう、何を信じていいのか分からなくなっちまったい。なんだい、なんだい。いきなりしおれちゃって、どうしたい、くまさん。お茶でもおあがりよ。キリスト教的<普遍主義>からの独立が必要だったヨーロッパ諸国とちがって、日本は「国家神道が中核」にされて国家形成してきたんだ。だから日本では、ヨーロッパとは違って、<神道的>(宗教的)への距離がとれないで支柱にされることが、政治や文学などをみても多いんだな。そんな成立事情からくる特有の捻れは、文化ナショナリズムに典型的に現れやすい。20世紀、マスメディアの発達による大衆社会の出現、総力戦体制、民族独立運動の高まりによって増幅されるんだ。だいたい、大正期なんて、エロ・グロ・ナンセンスの世紀じゃないか。その反発から、吉川英治「平和のための剣」(宮本武蔵)の創作など、復古調「日本的」なるものを生む。いい例が、その本に紹介されている、筧克彦『古神道大義』だろ。なんでい、ご隠居。読んでいたんですか。てっきりご存じねえとばかり。おう。読まいでか、くまさん。宇宙大生命と自己を一体化する思想、大正期「生命中心主義」が、大東亜共栄圏<皇軍の論理>の底流に流れこんでいるとは驚かされたね。「現人神」天皇は、宇宙大生命の現れであり、人々は「天皇の赤子」で、皇国は人類救済の大使命をもつんだとか。「古神道」は、侵略・退宿もなく一切を包容するなんて、本家キリスト教超越的絶対神も顔負けの、ウルトラ普遍主義。しかもその普遍主義は、宗教を絶対者に帰依するものととらえ、それを保障する精神共同体を構想する、ドイツ・プロテスタント神学の密輸っていう体たらく!! ご隠居、あっしはもう情けなくて。なんだか涙が出てくらあ。おいおい、涙じゃなくて鼻水じゃないか、くまさん。この手ぬぐいでふいとくれよ。皇民化教育で「言葉」を奪う一方、大東亜共栄圏のため、外地他民族文学の翻訳があふれたというのも、面白いじゃねえか。「帝国主義からのアジアの解放」と「アジアの支配」の矛盾が、はしなくも丸みえだよな。戦後編もまたいい。三島由紀夫「英霊の声」「文化防衛論」は、平和文化の象徴(津田・和辻)、天皇主義アナーキズム(林房雄)など、戦中に生まれ、戦後展開した<文化ナショナリズムの綜合>というのもいいね。丸山真男が「歴史意識の古層」として突き止めた「なる」論理は、実は「大日本帝国の<実在>」ではないのか?との問題提起も泣かせるよな。そうなんですよ。あっしらが「日本」と思ってたものがみな「大日本帝国」のニセモノだったなんて。あの万系一世の天子様も、韓国にゆかりを感じます、なんてぬかす始末。いったい「日本」なんてもの、どこにあるんですかねえ、ご隠居。悪いけど、それはないね、くまさん。『脱中心化』された空虚。その周りに無限に増殖してゆく「日本」的なるものの言説。過去に遡及的に発見され、伝統が再生産されてゆくだけにすぎないんだ。「伝統」は、以前ならヘーゲルやプロテスタント神学がツールとして使われたみたいだけど、今ではお手軽にパソコンでネット情報ってことじゃないかな。明治の見取図として、西欧文明化・ロマン主義・国粋主義・文化改良の座標軸をつくって、そのあらゆる方向性に対する妥協として「天皇制」を位置づけたのも面白かったね。 ちくしょう、騙した奴、許さねえ。探し出して、ぶんなぐってやる!おいおい、よさないか。くまさんは極端なんだ。だいたい、おれたちが「西欧」とおもってるものでさえ、「イスラム」からの密輸によって成立してるんだ。今のイスラムも、西欧の参照によって成立している…とすれば、<固有>のものなどは、どこにもない。いやあるとすれば、その「個」同士をむすびつける、見えない「鎖」ではないかな。鎖が切断された、まさにそのとき、ニセモノの主体たる「日本」がたちあがる。文化相対主義は、ナショナリズムの差別的で残虐な側面を支える論拠として利用されたことを批判するのだけど、文化多元主義もまた切断線をかえるだけにすぎない。それなのに、この本では文化多元主義をむやみと礼賛しているのは、いただけないね。おや、風向きが変わって来ましたね。でー、ご隠居。結局、なにが言いたいんですかい、この本は。ニセモノ以外、さっぱりわからねーくまさんよ。教科書なんじゃないかな。エランヴィタルのようなご専門をのぞくと、ちょっといかがわしい記述もちらほらと散見するよね。とくに中国絡み。今川了俊『難太平記』や貴族の「私史」程度の異議申し立てなら、中国では「雑史」「野史」「稗史」などでいくらでもされてるだろ。その辺の線引きは、微妙だよね。あまり知らないなら触れない、という方法もあったんじゃないか。また、資本主義とイスラムの対立をみるのも、どうかね。その辺、ちょっと割り引いちゃうよね。するってえと?新書としては合格点、っという感じかな。(続く、のか???)評価 ★★★価格: ¥903 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Dec 29, 2005
コメント(2)
-
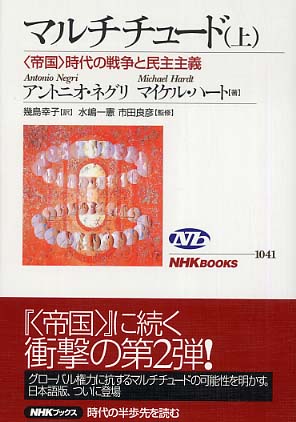
★ アントニオ・ネグリ&マイケル・ハート 『マルチチュード (上・下)』 4 NHKブックス(新刊)
(承前 、、)ネグリ&ハート『マルチチュード』シリーズも第四弾。実は、お忘れかもしれませんが、これまで要約だけしかやっていません。評価は、これまで書いてこなかったのです。本当は、3回でおわらせて、「めぐりあいマルチチュード」「哀戦士」と洒落こみたかったのですが、要約とレビューをあわせると、半角1万字を越えてしまうからでして…それで評価なんですが…正直、ぬるい。ネグリ&ハートは、哲学書であって、行動指針ではない、といい、マルチチュード三部作の次回作まで予告されているものの、日本ではあまり言及されていない第三世界の「現状分析」以外、取りたてて見るべきものがあるとは思えない。まず、「帝国」と旧来の「国民国家」の行使する、<権力>形態の違いがよく分からない。同意と服従を拒否する、特定社会集団を抹殺することができる生権力の担い手は、国民国家であって<帝国>ではない。<帝国>は、アメリカや他の国民国家を介してしか、「生権力」の行使をおこなっていない。であるならば、帝国とアメリカとはいかなる関係にあるのか。マルチチュードを抹殺できない<帝国>とは何なのか。この辺、議論と既述が錯綜しているだけにすぎず、純粋な「帝国」というモデルにおける、<権力>が不分明なままである。柄谷行人に、「グローバル資本主義(帝国)がどれほど深化しても、国家やネーションは消滅しない」と言われるのも、誤読っぽいようにみえて、ゆえないことではない。また、政治綱領としてはたして魅力的なのか?についても、深刻な疑念を禁じえない。マルチチュードは、人種やジェンダーによって、権力の階層秩序が決定されない、問題にならない世界をめざすのはいい。その階層秩序の存在<そのもの>は、問題視されていないのは、いかがなものだろう。人種、ジェンダーにかわって、別の尺度で階層秩序が形成されるだけでは、ユートピアを喚起する能力に乏しすぎるのではないだろうか。もっとも、必然的に移行するというのであるならば、ディストピアでも構わないのだが。さらにいえば、<帝国>と<マルチチュード>という概念の設定にも、疑念を拭いきれない。<共>によって、<帝国>と<マルチチュード>の次元が出現するのは、構わない。ならば、自己組織化するマルチチュードこそ、<帝国>のネットワーク秩序をささえているのではないか? このヘーゲル的「反対物の一致」という素朴な疑問に、筆者はどのように答えるのであろう。この潜勢力は、いかなる切断によって、<帝国の崩壊>に移行するのか。その<切断線>の提示がなければ、来るべき<帝国の崩壊>のためにたちあがる<マルチチュード>が存在するとはおもえないのだが。そもそも、一番深刻な問題点は、国家と帝国では規模の違いからくる民主主義を理解していないと批判しておきながら、世界的レベルの<共>―――オープンソースでもいい―――がまったく伝わってこないことにあるのではないか。「公」「私」の間に出現する、世界的<共>とは何だろう。たとえばその一部、「インターネット」を考えてみよう。それらのインフラを支えるのは、通信会社と電力会社―――巨大資本であることは、言うまでもあるまい。未来の<共>的生産能力、マルチチュードの逆転した歪んだ姿と「金融資本」はとらえられているが、お茶を濁す程度で終わってしまい、「巨大資本」そのものの分析は、まったく疎かにされてしまっている。<帝国>と<マルチチュード>の分割を可能にした、<共>―――それ自体、巨大資本が提供するのだが―――そのものへの対決を抜きにして、<帝国>の崩壊はありえまい。ところが、<帝国>VS<マルチチュード>のハルマゲドンを描きながら、その「抵抗」するべき巨大資本については、遺伝子工学企業などの<共>を利用する側のみしか言及されておらず、<共>を創出する側については目配りが行きとどいていない。ほとんど、ブラックボックス、「消えた媒介」となりはててしまっている。ということで、ちょっぴり辛辣に採点させていただいた。とはいえ、小技については、たしかに面白い。読み応えがあるのは確かなのだ。左翼の思考になじみたい方、第三世界がいかなる状況に直面しているか知りたい方、などにはお勧めかもしれません。評価: ★★★価格: 上巻 ¥1,323 (税込) 下巻 ¥1,323 (税込)関連日記アントニオ・ネグリ&マイケル・ハート 『マルチチュード (上・下)』 NHKブックス(1)アントニオ・ネグリ&マイケル・ハート 『マルチチュード (上・下)』 NHKブックス(2)アントニオ・ネグリ&マイケル・ハート 『マルチチュード (上・下)』 NHKブックス(3) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Dec 26, 2005
コメント(0)
-

★ 竹内洋 『丸山眞男の時代―大学・知識人・ジャーナリズム』 中公新書(新刊)
丸山真男とは、なにものなのか。なにゆえ、あのような広大な影響力をもちえたのか。 あらゆることについて何事か知っており、何事かについては あらゆることを知っている (ジョン・スチュワート・ミル)という意味では、サルトルとならぶ、最後の<普遍的知識人>戦後言論空間における、丸山神話。その成立過程について、丁寧に追跡・俯瞰・解剖してくれる、優れた本が上梓されています。今や、ほとんどの人々は、丸山真男とは何者だったのか、老人の回顧譚でしか知ることはできません。戦後、隔絶した<進歩的知識人>であった丸山真男と、その言説を支えた時代の息吹。皆さんもぜひ、追体験・確認されてみてはいかがでしょうか。丸山真男の学問の原点、そして戦後の大衆戦略の出発点は、1930年代~敗戦までの<暗い谷間>に由来するという。民間右翼思想家・蓑田胸喜と原理日本社による、リベラル大学教授に対するファナティックな思想攻撃。河合栄治郎、美濃部達吉…<帝大粛正>の真の狙いは、欧米崇拝と唯物的個人主義といった国体破壊思想を守り続ける、「大学自治」の解体にあった。正統的学歴コースから時間的に逸脱していた蓑田胸喜は、「大学知識人とその予備軍」に対して激しい敵意をいだくものの、彼の「いなか丸出し」のハビトゥス(身体文化)は、欧化した知識人である大学人たちの拒絶をまねいた。彼らの糾弾は、「排除された<排除する存在>」の様相をおび、政争に利用されただけの、悲劇的な結末(縊死)をむかえてしまう。丸山は師・南原繁によって、平泉澄らの国粋主義的日本精神論を超克するような、「科学的」な日本政治思想の研究をもとめられた。これが<丸山学>の始まりであるという。蓑田の陰におびえていた丸山にとって、敗戦は解放に等しい。それは丸山に「反・反共主義」的立場を強いることになった。1930年代の日本社会の病理は、インテリと大衆の文化的切断にあったとみるとともに、丸山の仕掛けた「疑似インテリ」概念による大衆の戦争責任免罪は、「大衆のインテリ化」「大衆をインテリに同伴させる」ため採られた意図的な戦略という観点は示唆にとむ。1955年頃から、共産党批判をはじめ、共産党と距離をおきはじめた丸山。それは、共産党に入党しなくても、充分に良心的で進歩的でありうる、左翼の新しい正統の創出であるとともに、折からの1960年安保闘争における全学連主流派と共産党の決裂によって、その創出された空間に大量のノンセクト・ラジカルがながれこんだ。それは、丸山の市民主義=「在家仏教主義」―――組織の指令ではなく自発的に活動する市民たち―――が現実化することを意味するとともに、その彼らを直接掌握することで、丸山は巨大な影響力を振るうことになったらしい。その丸山の権威の源泉は、「権力の倫理化」によって主体意識が欠如した支配層を論じた『世界』の処女論文をのぞけば、ジャーナリズム媒体にほとんど書かないことにあったというから驚きではないか。また、文学部とは違い、法学部に属していたことで、政治・ジャーナリズム活動が地位と威信にマイナスにならなかったことも大きいという。文学部的講壇アカデミズムを漂わせながらも、法学部的実践活動をあわせもつことを可能にした、日本政治思想史のポジション。丸山は、大学とジャーナリズム、双方が互いに威信と学問資本を倍加させあう、象徴交換効果を手にすることができた。大学とジャーナリズム、法学部と文学部、西欧と日本、インテリと大衆…丸山はあらゆる点で2重3重の仲介者であった。その意味で、彼は終生、「半可通」という批判がついてまわることになったという。1960年代になると、「大衆の知識人化」ではなく「大衆知の学問化」をもとめる吉本隆明などを筆頭に、左右両極から、激しい丸山批判が、噴出することになる。丸山をよすがとする大衆インテリの反逆は、全共闘運動で頂点に達した。反体制だけではモダン=ファッションになりえない時代に、ゲバ棒、ヘルメット、覆面、バリケード、大衆団交などの独自のファッションと演劇空間を創出した全共闘。急激にすすむ高等教育の大衆化を前にしては、もはや大学卒というだけでは、プロレタリアート化したインテリにすぎない。その怨嗟の中で、1969年2月24日、丸山は全共闘学生から激しい糾問をくらう。かつて、右翼学生から津田左右吉でさえ受けなかった激しい糾問をうけて、1971年、丸山は定年を待たずして57歳で東大を退職する。保守化がすすむ社会の前に、失敗におわった丸山の大衆啓蒙の戦略。ただこの事態の推移に苦々しさを感じながらも、日本社会の古層「執拗な持続低音」として流れる、「なる」<生成論理>を発見したことによって、丸山は認知的協和に到達したのだというくだりは、実に皮肉が利いていてすばらしい。なにより面白いのは、「丸山体験による丸山世代」である筆者にふさわしい、個人的な丸山ショックが縷々述べられている点でしょう。赤穂浪士討ち入り事件の処分をめぐる幕閣の論争の中に、絶対主義と封建主義の矛盾をみる丸山…たしかにその切れ味は、今なお面白い。この本くらい、丸山ショックを理解させてくれる本は、少ないでしょう。広島で被爆体験。長谷川如是閑に私淑。意外とエリート主義的な姿も、かいま見えてきます。異なる資本(政治・経済・アカデミズム)間の交換比率の決定を通して、ますます肥大するジャーナリズム。今、マスメディアに登場するトリックスター的な大学教授たちは、丸山真男を先駆者としているのか、否か。答えのない問いかけによって、本書が締めくくられるのも、実に心地よい。とはいえ、さまざまな通行する丸山論の洗礼を浴びたものにとって、また前著『教養主義の没落』(中公新書、2003年)を読んだものにとっては、衝撃はずいぶんとおちてしまうのが難点かもしれません。50年代から60年代への日本社会の展開も、前著で詳細に説明されているので、デジャブーに苛まれてしまう。もともと、蓑田胸喜や津田左右吉の一件を知っている人がみれば、うまく視角を切り出してはめ込みましたね、位の感想しかいだけまい。「本来のインテリ」もファシズムに協力していた!「疑似インテリ」悪玉論は間違いだ!というのも、もう何十年も前から様々な論者に批判されているので、今さらまたか、という感が漂ってしまう。もうすこし見せ方に工夫がほしい。しかし、この本はやっぱり面白い。そう自信をもってお勧めできる。それは、『ル・モンド』紙にのった弔文が訳出されているからである。やや長くなるが、読者の便のために全文を引用しておきましょう。丸山真男は、8月15日木曜日、82歳で逝去した。丸山は、専門の政治学の領域に、人間の行為の意味という人文的考察の次元をつけくわえた学者だった。丸山の思想は、1950年代-60年代に、赫赫たる威光と日本の近代や民主主義を理解するための洗練された概念枠組みを呈示したことで、同時期のサルトルに匹敵する。日本学士院会員だった丸山は、ハーヴァード大学やプリンストン大学でも教鞭をとった。敗戦直後、丸山は知的世界を一変させた。思想は、ドイツ観念論やカール・マンハイムの知識社会学によって培われたが、明晰さに加え、概念の再構築という創造性に富んだものだった。マルクス主義者たちが「近代主義」と名づけた潮流―――歴史分析と経験的研究が、倫理的な配慮と強く結びついた進歩主義の一形態―――の代表的な理論家だった。超国家主義と無責任の体系に関する考察や近代意識の形成を歴史の中に見いだす営為によって、日本の進むべき道を示した。日本思想の古層についての探究は、丸山の思想に無比の深さをもたらした。かくて丸山は、戦後民主主義の中心的人物の一人となった。丸山の反省的な企てのスケールの大きさについて、哲学者久野収はつぎのように言う。「思想に関して言えば、丸山以前にはソナタしかなかった。丸山は、私たちに交響曲を与えてくれたのだ」。丸山学派という新しい潮流は、政治に参加する(アンガージュ)知識人の一世代全体が形成される坩堝となった。というのも、丸山は、ハンナ・アーレントのように「出来事を考える」ことに努めたからである。彼は、「選択のとき」というアピールによって、日米安保条約反対闘争(1960)に非常に大きな影響を与えた。これについて、「丸山真男は私たちに共通語を与えてくれた」というのがノーベル文学賞受賞者の大江健三郎である。父親によってリベラルな考え方を培われ、東京帝国大学法学部を卒業した丸山真男は、日本の批判的朱子学思想家で「日本のマキャベリ」である荻生徂徠を研究して、全体主義の「暗い谷間」に生きた。そこから1952年刊の大著『日本政治思想史研究』が生み出されることになる。その第一章はフランス大学出版局(PUF)から刊行されたばかりである。丸山は、この本で、日本の近代は、欧化という外生的な要因によるものか、それとも内生的な要因によるものか、あるいはその両方かという、近代日本における重要なイデオロギー的ジレンマを扱っている。この問題については、福沢諭吉を手がかりにしてさらに探究が続けられた。 敗戦直後に、丸山は一連の論考を発表した。その一部は『現代[日本の]政治の思想と行動』という題で英訳されており、そのなかでも有名な論文「超国家主義の論理と心理」は、日本が通りぬけてきたばかりの時期を対象にした鋭い考察である。日本思想の分析に対する主要な貢献の一つに、1961年刊の小著『日本の思想』がある。最後の著作は、1992年に出版された論文集『忠誠と反逆』である。そして16巻からなる『丸山真男集』は、現在刊行中である。 60年代末、異議申し立てをする学生たちはアカデミズム界の巨人である丸山を重んじようとはしなかった。学生の暴力に衝撃を受け、丸山は定年になる前に大学を辞職し、その後は歴史研究に専心して沈黙を守った。 にもかかわらず丸山の知的な寛大さには変わりはなかった。知的寛大さは大人の美徳であるが、なかなかにもちあわせにくい美徳である。公的なインタビューに応じることはなかったものの、来訪者を快く迎え、現在を考えるために歴史の糸をつなぎ合わせるという作業に長時間を割くことを厭わなかった。五里霧中になって方向を見失うと、人々は、いつも丸山真男に助けを求めることができたのだ。丸山がその寛大さを惜しむことなく与えた日本の知識人の一世代全体といくばくかの外国人たちは、今、寄る辺なき孤児のような寂寥感を拭い切れない。(本書12~15頁)どうです?なかなか感動的な弔文ではありませんか。ここまで惜しまれた人物とは何者なのか、確認してみたくなりませんか?新書でたったの900円。ぜひ、ご一読あれ。評価 ★★★☆価格: ¥903 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Dec 22, 2005
コメント(3)
-

★ 一ノ瀬俊也 『銃後の社会史』 吉川弘文館 (新刊)
いやあ、これは素晴らしい。戦後の遺族運動がなぜあのような―――戦争責任に向かい合うことなく、靖国神社国家護持や恩給増額を声高に叫ぶ―――かたちをとってしまったのか(本書4頁)このような刺激的な問いをたてて、遺族たちの心情とその生活―――「銃後の社会」―――にせまる本書は、なかなかの出来映えを示しているといえるでしょう。やや高いものの、お勧めの一冊になっているのです。簡単に要約しておきましょう。● 終戦間際まで続いていた、盛大な「赤紙の祭り」最寄りの交通機関や駅での盛大な「見送り」や「壮行会」は、見送る側・見送られる側にとって相当な経済負担だった。そのため軍部は、自粛させようとしたものの、「士気」を維持するためにも認めざるを得なかったらしい。家族との面会は許されていたものの、軍は「情報漏れ」「スパイ」活動を気にして厳しい制限を加え(出征先の情報は家族を通じて、周囲に漏れまくっていたらしい)、別れを告げられないまま、南方へ出征して戦死したものが多かったという。● あくまで前線兵士の士気維持のためにおこなわれていた遺族政策死ぬまではいい。ところが、いったん死んでしまうと、地域社会の出征家族を見る目は、急に冷たくなってしまう。夫や息子の死を受け入れる過程で、「見返り」をもとめる意識は強かった。太平洋戦争時、国民が黙っていないという理由で中国撤兵を拒否したのは、故のないことではないという。実際、「軍事扶助」は厚かったものの、働き手を失った家族が暮らしていけるレベルではなかった。また、戦前に生活扶助を受けることは、「選挙権」をとりあげられたりする「恥辱」に等しい意識もあって、<当然の権利>と<恥辱>の狭間にあって、貧窮に苦しんだものも多かったという。また遺族婦人の「性」を管理するため、方面委員(今の民生委員)が派遣されていたものの、戦死した夫の恩給を家長に横どりされたりしたケースもあったらしい。● 「名誉の遺族」という名の監視体制● 前線兵士向けに量産された、恵まれぬ遺児達が厚遇をうけたという美談遺族にプライドをもたせるとともに、国への「権利意識」「特権意識」に転嫁させてはならない。「あるべき遺族」として国民を飼い慣らすため、政府は皇族・侍従を遺族視察のため各地に訪問させ、「聖恩」のありがたさを知らしめるとともに、遺族の不満を吸い上げていったという。そのハイライトは、天皇制を内面化させてゆく教育装置としての、遺児たちの靖国参拝。遺児たちの書き残した作文で浮きあがってくる「靖国での父との再会」は、不気味なまでの迫力に満ち満ちています。「靖国での父との再会」に喜ぶ遺児たちに注がれていた、「父なし子」という偏見―――戦死した父の名誉をつぐべきにもかかわらず、父親がいないので人の道を踏み外すおそれがある、だから監視しなければならない―――は、戦後、就職差別という形であらわれたという。● 銃後社会全体が遺族の栄誉を称揚していた、 <奪われた過去>を取り戻す“正しい”運動としての遺族運動戦後、周囲の遺族に対する嫉妬・好奇の眼差しは、厳しかったという。生活保護は屈辱をあたえ、軍人恩給をもらうことにさえ、風あたりは強かった。そのため遺族は、肉親の死を「平和日本建設の<礎>」として正当化することになって、なぜ遺族が英霊なのか―――不正義の侵略戦争ではないのか?―――という観点は後退してしまったという。次代の兵士を動員させる必要がなくなると、「肉親が死んだ場所」「最後の様子」「遺骨」を伝える<戦死の体系>は崩壊した。死ぬ場所も教えられず、「空の遺骨」を渡される、そんなぞんざいな扱いを受けた遺族たちの怒り。肉親の死が信じられず、はてしなき「遺骨収集の旅」をおこなう姿は、涙なしには読めません。豆知識もなかなか。戦時中、政府は遺族会結成を阻止しようとしていたという。また、召集令状は葉書でくることはないのに、「一銭五厘の葉書で…」と言われているのは、「戦死第一報」の通知が葉書でくることと混同されたのではないか?という指摘も面白い。国家社会の恩恵が不当にも奪われ、戦争犯罪人のように扱われたことへの怒りにつき動かされた、戦後の遺族運動。「戦争責任」論者は、遺族運動を批判することで、彼らに「戦争責任」をおしつけて「事たれり」としてきたのではないか?という批判は、鋭いものがあります。激励した社会の責任は、どうなるのか? いくら愛国心を内面化しても、結局、戦時中でさえ国は決して応えてくれているとはいえないことを語り、警鐘を鳴らす筆者の姿勢には、とても好感がもてるものがあります。とはいえ、本当の問題は、その先にあるのではないか。国家に裏切られるか否かが、問題なのか?。ナショナリズムのかかえる問題は、国家は期待に応えてくれるはずだ、応えなければならない、と「あえて騙されてみる」次元にこそ、核心があることを見落としているのではないか。国家は、戦前戦後を通して「慈愛に満ちた眼差し」で包摂することに成功してきたという。しかし、ナショナリズムとは、古今東西、制度面における生の包摂を期待して唱えられたことがあっただろうか?。その意味では、本書の内容がナショナリストたちにどこまで伝わるのか、いささか心許ないように思えるものの、一読の価値のある素晴らしい書物であることは疑いありません。冬の寒い日のお供に、ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。評価 ★★★☆価格: ¥1,785 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Dec 19, 2005
コメント(17)
-

★ アントニオ・ネグリ&マイケル・ハート 『マルチチュード (上・下)』 3 NHKブックス(新刊)
(承前)「第三部 民主主義」そしてネグリたちは、マルチチュードによる民主主義が如何なるものなのか、その構想へと足を踏みいれていく。主権と構成的権力の関係が切断され、主権のみ切り離されて存在する<帝国>。その状況に対しては、構成的権力は主権の再建ではなく、絶対民主主義の実現に向けられなければならない。このプロジェクトの根幹をなす「抵抗」は、どのようにしたら構成的権力の形態に変容させることができるのか。考察は深奥にすすんでいく。● 社会の管理運営システムにとって、合理化の力学上不可避な「代表制」 に侵食されてきた、民主主義● 「世論」は、民主主義的な代表物にはならない 「世論」は権力関係によって規定される「抗争の場」にすぎない左右両派に、グローバリズム反対・賛成の両派が存在している。左では、社会民主主義と、グローバリズムが民主主義を促進すると考える、自由主義的コスモポリタニズムの思潮。右では、伝統的価値観に危機をもたらすとする保守派と、ネオコン。この4つの思潮は、規模の違いからくる民主主義の危機を理解しておらず、自由を優先して民主を蔑ろにするため、いずれも民主主義とグローバリズムの問題に立ちむかうことができていない。18世紀の革命家は、「全員による全員の統治」を考えており、「代表制」による縮減は「民主主義」と対立するものであることを理解していた。20世紀の社会主義は、「政治と経済」を別扱いにすることが抑圧構造の鍵であることを洞察し、直接民主制と自主管理を目指したものの、「代表制」を要請する論理によって、議会代表制以下のレベルにまで「民主」が蝕まれてしまった。右翼ポピュリズムは、「代表」への徹底的な「主権」委譲を「伝統」によって正統化することで、この行き詰まりを解決しようとする、社会主義の歪んだ嫡子であると云う。また「世論」概念も、合理的な個人の表現でも、社会的な大衆操作でもなく、「代表」制にかわる技術的・統計的な代替物にもなれないとされている。● 「生」をめぐる抗議行動にこそ、民主主義のプロジェクトが宿っている● アメリカ単独行動主義、ユーロの創設など、地域権力の自己主張によって <帝国>的秩序が動揺していることは、グローバル「貴族」や マルチチュードにとって好機の到来でもあるもはや<帝国>では、立憲主義の3原則―――代表なくして課税なし、権力の分割、言論の自由―――は、いずれも蝕まれてしまった。外部なき<帝国>の階層的包含に対して、今現在、さまざまな抗議行動や「陳情書」が突きつけられている。それに対応して、権利と正義をもとめる動きが、「公民権」ではなく「人権」に基盤をシフトしつつ主張されつつある。しかし、人権は「法的枠組」ではなく「レトリック」でしかない。そのため、ユーゴ空爆のような最悪の事態が、「人権」の名のもとに引きおこされてしまう。グローバルな「法」「国際法廷(ICCなど)」は、<帝国>法体系にすぎない。「説明責任」は人民に向けられていない。その民主的正統性の絶対的欠如にも関わらず、国内における「民主主義と法による統治」の実践を媒介にすることで、我々に押しつけられてしまう。その変革は、「公」への回帰ではなく、<共>を取りもどし創造するための、あらたな制度的メカニズムにならなければならない。グローバルな代表制、連邦主義、法廷、税制、議会…いずれも現在の不公正や不平等を緩和することができるが、それでは十分ではない。我々は、18世紀に立ちもどって、政治的創造力に富むおもいきった行動が必要だ。18世紀とはちがい、複数性を<一>に還元させてはならない。とはいえ、新しい動きには歓迎できる一面もあるらしい。1999年、シアトルWTO閣僚会議でおこなわれた数々の抗議行動は、グローバル・システムに対するすべての異議申し立ての結集場所を提供してしたことに意義があると云う。<帝国>の危機は、土地・種子・知識・情報などの必要不可欠な生産資源に対して<共>的アクセスを創出し、世界における潜勢的な生産力を現実化するための、「貴族」と「マルチチュード」、相容れぬ両者の戦略的提携を可能にするチャンスでもあると云う。新自由主義的な政策は、市場と金融の領域で顕著なものの、この事態にも2面性を嗅ぎつける。デリバティブ取引などの「金融資本」の巨大化は、未来の<共>的生産能力を表象する、マルチチュードの逆転した歪んだ姿でもあるのだ。● <共>の力を通して主権を破壊するのに不可欠なものは、 政治的な愛の再建である マルチチュードの民主主義には、あらゆる政治理論の一致した原則、統治できるのは「一者」のみ―――君主制、貴族制、民主制―――民主制でさえ、「人民」「国民」(「党」?)という主体に統合されていなければならないのだ―――が障害として立ちはだかる。主権かアナーキーか、しか選択肢が与えられていない。ところが、<帝国>にあっては、戦争、政治、経済、文化のあらゆる権力と生産の境界が曖昧化し、ひとつ社会的生を丸ごと生産する様式、生権力に収斂している。「主権と資本」の一体化の進展。しかし主権は、統治者と被統治者の二者関係を必要とする。<帝国>は、被統治者を搾取できても排除できないのだ。 <共>にもとづく社会関係を創出するマルチチュードの力は、経済・政治・社会における自己管理・自己組織化によって、主権とアナーキー、統治者と被統治者の分割点に、主権から逃れた新しい世界の創造をおこなうのだ。決定を下す一者が存在しない、協調的に活動する神経の群がりである脳のように、マルチチュードの意思決定は、その中から全体に意味を与えるような決断が立ちあらわれてくる。マルチチュードは、不服従と差異をもとめる権利のみしかもとめないし、権力に対してはいかなる義務も負っていない。「戦争と暴力」を基盤におく<帝国>では、民主主義のプロジェクトは、恒常的な暴力にさらされるので、「武器をとっての逃亡」「抵抗」にならざるをえない。<帝国>の暴力には、悲劇的な非対称性を崩すことが求められるが、むしろテロの応酬にみられるように「奇妙な対称性」を産み落とし、帝国秩序を強化してしまいかねない。民主主義のための有効な武器は、愛である。新しい可能性を象徴する殉教。政治的な愛の再建。構成的権力を失った主権<帝国>が打ち倒される、切断(革命)の時間到来の予感を語って、本書は締めくくられている。 (続きは鋭意執筆中 どうか応援お願いします)かなり長い内容の要約になった上、更新も思うようにすすまず、みなさまにご迷惑ばかりかけて申し訳ない。1万字の字数制限もあって、レビュー部分は、次回に回したいと思います。4回も分載することになってしまい、ごめんなさい。評価: ???? (今はまだ秘密です)価格: 上巻 ¥1,323 (税込) 下巻 ¥1,323 (税込)関連日記新世紀の共産党宣言 (1)アントニオ・ネグリ&マイケル・ハート 『マルチチュード (上・下)』 NHKブックス(新刊)新世紀の共産党宣言 (2)アントニオ・ネグリ&マイケル・ハート 『マルチチュード (上・下)』 NHKブックス(新刊) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Dec 16, 2005
コメント(0)
-

★ 豪華絢爛、ホスト部へようこそ 葉鳥ビスコ 『桜蘭高校ホスト部 7 (7) 花とゆめCOMICS』(新刊)
うわ。見つかってしまった。どうも、このブログでは、コミックやサブカルをレビューすると、あまり 人気がでないのですよね。個人的には、ちょっと残念なんで、みんなに気づかれないように書こうとしたのですが…見つかってしまいましたか。残念。見捨てないでくださいまし。前回、由貴先生の本をとりあげたとき、尊敬する遊鬱さんからこんな返事を頂いてしまいました。不肖わたしめもorz 遊鬱さん 私が白泉社の少女漫画に耽溺するきっかけとなったのが由貴香織里先生です(画集に留まらず、限定天禁セットとかドラマCD総べて収集しました)。現在の価値観、(耽)美至上主義をビジュアルに明示してもらった(認識させられた)という点でおっしゃるところ総べて共感します。超美麗な絵で禁忌、狂気の境界を蹂躙していく恐るべき力がありました。天使禁猟区は読み返すと使い切れていない設定というか穴もちらほら目に付きますがそんなことはどうでもいいだけの圧倒的な密度がありました(初期の短編も)。遊鬱さんが「orz」となるのは、無理もありません。こうなることもあろうかと、こんなことも書いていましたっけ。↓読んでいる女性に出くわすと、困難はさらに倍加する。話があわない。だいたい、読んだ絶対量の問題が横たわるので、こちらの話なんて歯牙にもかけてもらえない。そもそも「体系的に読む」なんて行為は、女性のいわば身体言語といえるジャンル、少女漫画のジャンルにおいては、男性「だから」やる行為にすぎない。とても太刀打ちできない。まあ、それですら序の口にすぎない。本当の恐怖とは、「話があってしまった後」に訪れるのだが、それは後回しにして…話があってしまった後、「う~ん」と思ってしまうんですよね。「なんか間違えてしまったかも?」と。遊鬱さん指摘の「耽美至上主義」「超美麗な絵で禁忌」「狂気」…由貴先生のファンなら、何ひとつ差し挟むべきことはありません。作中に登場するキャラ、ロシエル様に「萌え萌え」にならない由貴香織里ファンなんて、この世にはいないでしょう。しかし、ロシエル様は男性で、僕は男性なんですよね…少女漫画は、女性が男性を賞味するためのジャンルです。どんなに女性が綺麗に描けていても、それは作品の出来不出来とは関係ありません。あくまでどこまで男性をきっちりと描くことができるか?が勝負なんですよ。少女漫画を「正しく」楽しむには、女性の視点から男性を味わうことができなければならない。ところが、正しく楽しめることができればできるほど、「男性として」みればまったく「正しくない」状態になってしまうのです。厄介ですよね。これがクリアできれば、実は「やおい」と「少女漫画」の間には、線引きなど引けないことに気づいてしまう。そうなると、少女漫画を楽しむ要領で、「やおい同人誌」も楽しめてしまうのですが、この障壁は意外と高いらしい。こうした修行を積むと、男性でありながら、ちまたの可愛い男の子たちをみかけると腐女子妄想変換(どっちがウケでどっちがタチか?)できるようになれます。これができるようになったときには、さすがの私もひどく落ちこんでしまいました。ちなみに私ですが、ホモ漫画の大傑作、羅川真理茂大先生『ニューヨーク ニューヨーク』全4巻(白泉社)が体質的に辛くって読めなかったことから分かるように(今は随喜の涙を流して読了しております)、ホモの気はまったくありません。ところが、私以外に実践している一般男性には、お目にかかったことがありません。参ったね、こりゃ。閑話休題。冒頭のコミックに戻りましょう。少女漫画の王道のような作品です。主人公ハルヒ(なぜか女性なのに男装して、ホスト部に入っている)をのぞけば、女性は<つけたし>みたいなもの。豪華絢爛の男性ホストが女性を歓待する、そんな夢のような少女漫画(←ここ笑う所です)金持ちボンボンたちの集う学園ドラマとくれば、神尾葉子『花より男子』(集英社マーガレットコミックス)【台湾では『流星花園』という名でドラマ化され、F4ブームが巻きおこったそうです】を思いだされる方も多いでしょう。あれよりも、もっと荒唐無稽にして、もっと恋愛色を薄めた、ラブコメディーといったら、分かってもらえるかもしれません。なにせ登場人物は美男子揃い、おまけにホスト部。むろん、どうみてもホスト部に集う男性陣、ホスト部に遊びにくる女性陣、ともども「ホスト」なるものを根本的に勘違いしている訳ですが、むろんこの差延を賞味するのが醍醐味な訳でして、いちいち突っ込みを入れるのは野暮というものでしょう…勢いにまかせて、物語を消費するだけです、、、いかん、動物化しかねん。ここまで、女性をいい加減に描く少女漫画は、すがすがしい。津田雅美先生以来、LALAの久しぶりの大型新人ですし。ぜひ、ご一読あれかし。ところで、本巻メインの聖ロベリア女学園ですが…紅薔薇様白百合会『マリみて』のパロディですか???ヅカ部の文字をみて、大受けしたんですけど。評価: ★★★☆価格: ¥410 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Dec 14, 2005
コメント(1)
-

★ 山之内克子 『ハプスブルクの文化革命』 講談社選書メチエ 2005年9月
皆様は、ご存じでしょうか?われらが私的なものと考えている休暇や娯楽でさえ、近代において、国民国家の手によって、根本的な再編・管理を受けていることを。本日は、18世紀、ハプスブルク統治下オーストリア帝国における、余暇・娯楽の管理体制の創出をあつかった研究をご紹介いたしましょう。『ベルばら』でおなじみ、王妃マリー・アントワネットの母親マリア・テレジアと、その子ヨーゼフ2世。彼ら2名の手によって推進された社会編成原理の構造的転換は、われわれの知的好奇心を刺激する素晴らしい題材といえるでしょう。ぜひ、お読みいただきたい本なのです。オーストリア帝国。「美食の都」、演劇と祝祭の都市ウィーン。北部ドイツとはまったく違い、贅沢と浪費の生活に酔いしれていた、ウィーン。「啓蒙君主」ヨーゼフ2世に期待して訪れたドイツ人が、一様にその失敗を予感した町。プロテスタント的な合理主義・進歩主義・節制と勤勉とは対極にあって、カトリック・イエズス会系の出版検閲も厳しい、文化の廃墟とみなされていた帝都。実は、享楽のスペクタクルや食文化は、北ドイツの出版業界と読書層の緊密なネットワークが果たしたような「啓蒙の運び手」=メディアの役割を担っていたという。「民衆に広く娯楽を付与する者」としての君主像。 スペクタルがどうしても必要なのです。これがなければ、 もはや、誰もこのような巨大な宮廷に留まろうとはしないでしょう。 (マリア・テレジア)それは、都市の時間と秩序を管理しようとする、専制的な国家改革の一環であったという。厳かな宗教行事から聖祝日、誕生日、祝祭日だけでも、157日もあったウィーン。贅沢・浪費として視角化される年中行事は、身分秩序を刷りこませるためのメディアとして機能していた。そのため、既成の身分秩序を転倒させる祝祭の数々は、絶対王政期において強力に排除されていく。民衆の祝祭「謝肉祭」における、仮面着用の慣習は厳禁された。すでに19世紀初頭になると、このような仮面の着用にみられる「カーニバル」的な「逆さまの世界」は、民衆の中でさえ理解不能になってしまう。マリア・テレジア期における、雪橇(そ)りパレードの創出や、「演劇」における「即興演技の禁止」などの管理政策。これらは、祝祭空間における民衆の位置づけが、「参加するもの」から「見物するもの」へ、決定的に変容した象徴であるという議論には、唸らされるものがあるのではないでしょうか。庶民がヤジを飛ばし、風刺や諧謔をおこない、しばしば参加することもあった、反合理主義的カオス文化の象徴、演劇。これが「参加型」から「受動型」へ根本的に変容していくのです。もともと余暇・娯楽と労働は、前近代においては分離していなかった。労働と娯楽、信仰と娯楽は、未分化の状態であったらしい。朝は、みんな一斉に起床。その後、教会のミサに出向いて、日没まで13時間から17時間も仕事。ミサや礼拝を名目にして、仕事を中断するのが、慣習となっていたという。信仰と結びついた娯楽。「楽しみ」や「気散じ」は、独立した地位が与えられておらず、信仰や職業にかかわる、何らかの「名目」が必要であったらしい。「牛追い」など突発的な事態が発生すると、嬉々として参加して、公空間を突如、祝祭空間にかえてしまう民衆たち。臣民の不断の労働こそ国力増強の大前提であるならば、労働と余暇の分離は欠かすことができない。祝日を削減するとともに、日曜・祝日を神聖化して「余暇」として割り当てた、マリア・テレジア。本書によると、啓蒙専制君主ヨーゼフ2世(1765-90)は、さらにラジカルな改革をすすめたという。バロック的、イエズス会的な信仰生活の変革を目的とした啓蒙主義。それは、世俗的な快楽を啓蒙主義的価値観を通して正当化していくことで、娯楽から教会を追放して影響力を払拭するという方法をとったという。「聖なる時間」が消え、「楽しみ」が恒常的におこなわれるとともに、労働と娯楽のリズミカルな繰りかえしで営まれる日常生活。それは、「緑地散策」「アウガルテンの開放」などの緑地開放政策で頂点に達するという。18世紀、啓蒙主義の「社会的平準化の理想」のデモンストレーションをかねた、「万人に開放された場所」。こうした緑地開放政策は、ウィーンを特色づけた、美食趣味とスペクタクルでさえ変容させてゆく。アウガルテンは、近代的科学技術を用いたスペクタクル産業と庭園の結合、スペクタクル庭園―――万国博覧会から大衆遊園地・アミューズメントパークへの流れ―――実際、ウィーン万博会場を経て、今では遊園地になっている―――の先駆けとなって、一大娯楽集積施設になってゆく。上流階級まで「牛追い」に熱狂し、カーニバルでは歌い踊る、参加型の娯楽文化は、興行師による「娯楽の消費者」「節度ある受け手」として、身体のレベルまで改変させられてしまう。それは、宮廷=「公的生活圏」の頂点にたちスペクタクルの提供者でもあった皇帝が、「私的生活圏」に後退してゆく過程でもあったというから、その大風呂敷からくる面白さはとどまる所を知りません。礼儀・服装の制限を廃止して、一時的な儀典=公的空間からの離脱=「微行(お忍び)」を告げず、臣下の家に夜歩きをおこない、親密なおしゃべりを楽しんだ、ヨーゼフ2世。位階の顕示によって支えられた宮廷文化は、動揺してゆく。宮廷行事の祝祭は、貴族主導で私的に催されるものになってしまう。日常的な娯楽パターンの定着、宮廷スペクタクルの消滅、宮廷儀式の「私化」は、都市社会において未曾有の変容を産み落とす。それは流行・モードの誕生であり、多様な時間サイクル、個人の孤立化・都市コミュニティの喪失であった…いかがでしょうか。興味をもっていただけたでしょうか。なによりも、近代における文化の系譜学になっているのが嬉しい。スペクタクル、流行、演劇、緑地…われわれが見慣れたものは、近代以降、つくりあげられたものにすぎない…そう言うのは、確かにたやすい。しかし、それが史実として追跡され提示されると、やはり圧倒的な臨場感があるといえるでしょう。今もときおり見かける、突発的な娯楽や仕事と未分化の娯楽。それは前近代の残滓と言っていいのかな? なかなか考えさせてくれる歴史書なのです。ハプスブルク王朝や、絶対王政、「ベルばら【笑】」…これらに興味がある人だけが読むのでは、本当にもったいないくらいの選書というしかありません。メディア論、公共圏論などさまざまな所に目配せされており、娯楽・文化を軸とした近代の一大歴史スペクタクル(笑)が展開されているのです。こんなにすばらしい概説書と言うものは、なかなかお目にかかれるものではありません。ぜひ、ご一読いただきたい。評価 ★★★★価格: ¥1,680 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Dec 12, 2005
コメント(5)
-
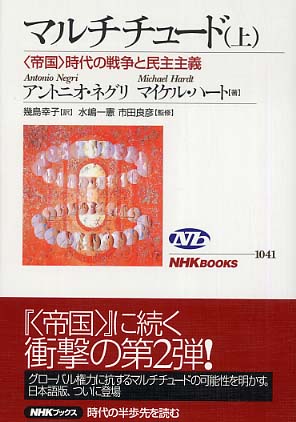
★ アントニオ・ネグリ&マイケル・ハート 『マルチチュード (上・下)』 2 NHKブックス(新刊)
(承前)「第二部 マルチチュード」この章ではマルチチュード概念について論じられています。グローバル化した世界における<政治>に関する理論は、国家をモデルとした近代の政治体に関する2つの理論、「絶対主義的」主権論と「共和・立憲主義的」な主権論を引きついでいるため、いずれもグローバルな政治を把握できていない。そして、そのいずれも民主主義を展開できていない。ネグリとハートは、このような問題意識から、マルチチュードなる概念を練りあげていきます。● マルチチュード概念は、「主権の伝統」全体に対する挑戦であるという● <共>で生産されたものが<私>的に占有されること、これが搾取であるマルチチュードは、同一性と差異性の対ではなく、<共>性と「特異性」との対で理解しなければならない概念であるという。まさに、資本が「特異性」(=個人)を有機的な統一主体に仕立てあげようとするとき、集合的な生政治的生産をおこなう形象として現れる。グローバル化のプロセスの内部にありながら抗うマルチチュード。それは、「労働者階級」とは違い、拡張的な概念である。今日の労働と社会は、情報化を強いられていて、知性・コミュニケーション・情動労働が重視される「傾向」にある。組立ラインの直線的な関係から、分散型ネットワーク特有の不確定な関係性への変容。もはや、農業労働者・農村貧困者である「農民」でさえ、工場労働者・サービス産業労働者と切り離された存在ではない。また、雇用と失業の境が曖昧なポスト・フォーディズムの時代では、「貧者」や「失業者」「女性」「パートタイマー」「移民」を主要な政治的役割から排除してきた、マルクス主義的区別は、廃棄されなければならない。社会的生産は、ますます<共>になりつつあり、工場と賃労働の内「外」に依存しつつあるからだ。私たちは全員、「社会的生産」に従事する「貧者」なのである。労働組合は、他の社会運動と合体されなければならない。● グローバルな権力秩序に向けられる国民国家の行動=「脱国家化」● 拡大する<共>は、所有に対しての伝統的な考えである、 労働の延長としての資本主義的権利や権原を弱体化させてゆく国民国家の権力と機能は、グローバルな枠組の中で変容しているのであって、力を失った訳ではない。このグローバル秩序では、非固定的な、国境で括ることができない、「労働と権力のグローバルな分割」がおこなわれている。それは、一握りの人の富と大多数の「労働と貧困」を恒久化する階層秩序、<グローバルなアパルトヘイト>に他ならない。その秩序とは、相互作用の自己調整(国際会計基準、商人法)、国民国家間での調停、超国家的なグローバルな権威(IMF、世界銀行)の、3つのレベルの規制装置が一緒に働く、グローバルな擬似政府を構成している。9・11以降、顕著になってきた「大きな政府」への欲望は、ケインズ主義的再分配とは無縁の、「セキュリティ」の肥大化にすぎない。そのセキュリティは、「非物質的生産」にも向けられていて、ナップスター問題や遺伝子組換技術の発展にみられるように、知的所有権やバイオ所有権の途方もない拡大を引きおこしている。それは、社会的生産の基盤である<共>の私有化による囲いこみであって、民営化による腐敗のみならず、マルチチュードの生政治的生産性、すなわち非物質生産そのものを阻害して弱体化させてしまう。<共>による<共>の掘りくずし。この事態は、私的所有を守るものが暴力以外にない、という状況を引きおこしかねない。問われているものは、<共>へ介入できる民主的なアクセスをどうするか、であるのだ。● 「私」と「公」のどちらにも抗して属さない、<共>の実践を!もはや、社会的統一体や「人民」の再建・再生は、意味をなさない。労働と<共>の螺旋状の拡大は、もはや個人と国家を、「器官と身体」のアナロジーで了解させてくれない。マルチチュードとは、社会的な「肉」、モンスターなのである。習慣やパフォーマンスや言語は、「過去」の重みと社会的相互作用による制約を受けながらも、日々、他者とのコミュニケーションを通じて再生産される、人びと共有の「社会的自然」である点で、<共>の生産を理解するのに参照となるだろう。いずれも、その能力は<共>から生まれ、<共>を産出して、<共>の中でおこなわれてきた。ところが「新自由主義」は、社会的領域では「公」の極端な拡大、経済的領域では「私」の極端な拡大で、この領域を窒息させようとしている。<共>の政治戦略の構築には、公共財・サービスの「民営化」イデオロギーの虚妄を暴くだけではすまない。「公」(=国家)の領域は、官僚にかわってマルチチュードが管理運営に参画するのみならず、多様な特異性のもとづく<共>の枠組を前進させなければならない。この章では、既存の左翼陣営から『<帝国>』に投げかけられた批判、「アナーキズム」「レーニン(前衛)主義者」「産業労働者の敵」「ポストモダンのレーニン主義者」「労働者のことしか気にかけていない!」「不完全な弁証法」「サバルタンを忘れている」「北の代弁者」「非現実的」(ほとんどの批判は、通暁しない人間には理解できないと思うけど…)に対する、ネグリ&ハートの回答も収録されていて、ほとんど必読に近いと言えるでしょう。また、毛沢東主義プロジェクトが世界的に適用可能であるのは、農民の「社会的生」まるごとを変革する「生政治」的闘いだったから、というのも面白い。<農民階級の最終的政治目標は階級としての自分自身の「消滅」にある>パラドクスには、唸らせるものがあります。とはいえ、ミヒャエル・バフチンを援用しながら、特異な主体のポリフォニー的集まりの中での「対話」といった、各主体の共的構成を通して、人々はカーニヴァル的な喜びを獲得する…などの補論はなくてもいいような気もするが…。 (続きは鋭意執筆中 どうか応援お願いします)評価: ???? (今はまだ秘密です)価格: 上巻 ¥1,323 (税込) 下巻 ¥1,323 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Dec 8, 2005
コメント(1)
-

★ 山口二郎 『ブレア時代のイギリス』 岩波新書(新刊)
この題名から判断してしまうと、森嶋通夫『サッチャー時代のイギリス』(岩波新書 1988年)のヒソミにならおうとする、「お手軽な本」としか思えない。おまけに、筆者が大問題のひとつ。これまで、小選挙区制度による2政党制を強力に推奨して、イギリス労働党に好意的だった、政治学者山口二郎。サッチャーを毛嫌いしていたことで、対象との否応のない格闘を迫られ、全編に緊張が漲っていた、森嶋の誉れ高い新書の<後釜>を彼が書くのか?? どこまで、対象を客観視して書けたのか、読んでいないものがみると、いささか心もとない。とはいえ、なかなか面白かった。イギリス政治のバックボーンを解説した、なかなかの入門書といえるのではないでしょうか。● 「当然の与党」労働党の誕生2(大)政党制とはいえ、選挙で勝って首相の地位に就いた労働党党首は、ブレアが3人目にすぎない。保守党こそ「当然の与党」で、労働党の政策は国民に信を置かれていなかった。「1つの国民」の名の下、保守・労働両党とも、「福祉国家」に対する「バッツケリズム」と呼ばれるコンセンサスが存在していた。サッチャリズムは、「民営化」「小さな政府」によってコンセンサスを打ち壊してしまう。教育や医療の荒廃の中で、労働党は、総選挙4連敗。その最中、前任者スミス党首とブレアは、党改革に立ちあがって、ブロックボート制の廃止、国営化条項の削除する。この際、激しい論争を公開でおこなうことによって、マスコミの目をひきつけ「改革」のイメージを有権者にアピールすることに成功をおさめたという。● 「環境整備型国家」「人間の力を強化する国家」へ転換したイギリスブレア路線「福祉国家の現代化」では、もはや「結果の平等達成」が放棄されていると云う。狙いは、グローバルな競争の中で適合した、自立した人間を作り出すこと。「競争力強化」と「公平性」の追求が目指されているらしい。貧困家庭では、そもそも教育をうける機会が無い。「社会的排除」は、知識・技術を身につけることができないため、そうしたものが不必要なブルーカラーの雇用数の減少によって就職難に陥ってしまい、貧困の再生産が生じることによって生まれる。雇用政策では、自立支援策と現金給付を巧みに組み合わせることで「社会的包摂」をおこなった。教育でも、学力引きあげ、競争強化がねらわれる。そのため、格差の拡大をおさえる程度しか効果がないという。 ● 「政治の人格化」「反既成政党政治」とともに 「市民運動」と「地方自治」が活性化させたブレア労働党既成政党への不満、左派的政策の普及によって、明確な対立軸がつくれない… 「政治の人格化」「反既成政党」のパラダイムは、イギリスが一番最初にあらわれた国であるらしい。それは、擬似的な直接性によって、人々の不満をすくいあげる「大統領型首相」類型を生みおとして、議会制民主主義の形骸化がすすむ一方、市民運動と地方自治は、むしろ活性化しているという。ブレア労働党の新しさは、「国家か、市場か」の枠組では捉えず、「自発性と無償労働と協力原理」にささえられる「社会」の領域において、市民セクターの拡大と強化を積極的に推進している面にあるという。● ブレア外交の特徴「国際協調主義」と、安全への全体主義極東のゴミ売新聞などもそのお先棒を担いだことで有名な、イラク大量破壊兵器のウソ。そうした、無理ともいえる対米協調をおこない軍事的一体化がみられる一方で、前政権とは比較にならないEU重視をおこないバランスをとっているという。また、途上国債務削減についての積極的なイニシアティブにみられるように、「人権」「民主主義」を重視した労働党伝統の国際協調主義は健在であるらしい。ただ、安全に関しては保守政権よりも「邪心がない」ことを強調できる分、取締強化はテロ・移民・迷惑行為など多岐にわたっていて、保守党以上に強硬で、妥協がない面があるという。● イギリス政治に「社会民主主義」を埋めこんだ97年体制 「ビッグ・テント」の成立コミュニケーション総局を設け、「スピンドクター」によるメディア・コントロールを展開したブレア。その成功の一因は、税金と治安面で保守党と同質化させた一方、効率的な公共サービスの提供という面で差異化することに成功したことにあるという。ただ、保守党と戦うとき、労働党を支援する伝統的な支援者は、困惑を隠しきれていない。様々な公共サービスの改善がみられるにもかかわらず、「政権維持が自己目的化」などの批判を招くのは、中間層をつなぎとめるため、ブレア労働党があえて賞賛回避をおこなっているためだという。このへん、自画自賛の小泉自民党との差異ともなるだろう。「目からウロコ」賞を進呈したい。● 「第三の道」がかかえる、社会管理する「生活リスク」の複雑化と、 敗者救済のむずかしさ「生活リスク」を誰が管理すべきか? それをめぐる争いが、「社会民主主義(リベラル)VS新自由主義(保守)」の対立であるという。社会全体でリスクを管理する方が効率的であるのは当然ではあるものの、20世紀中葉のようにリスクの質が分かりやすい時代は、とっくに過ぎさってしまった。それが、「小さな政府」による極端な「生活リスク」への無為無策を、「生存のリスク」を言い立てることで覆い隠して集票活動をおこなう、「恐怖の政治」戦略が横行する原因であるという。市場適合型の人間をつくりだしても、生まれるであろう敗者はどうすればいいのか?とともに、政治的処方箋を提示することが求められている、として本書は終わる。今、迷走をしているように見える、前原代表率いる民主党。その状況に引きつけて読むと、参考になる部分がとても多いのではないか。なによりも、守るべき理念は何で、そのため現実とどう妥協しているのか。それが分らないのが、民主党のかかえる最大の問題のひとつであろう。保守と社民の同居は、日本政治の縮減であるから、ある程度、止むをえまい。また純化路線など、論外に等しい。とはいえ、理念がどっちで、妥協がどっちなのか分からないのでは、明確なメッセージを発することはできまい。遠からず、次の総選挙までに、民主党は「背骨」となる理念の提示が迫られている。その意味で、伝統的自民党政治を「第一の道」、小泉自民政治を「第二の道」、そして来る時期必ず必要とされるはずの社会民主主義的「第三の道」になるべきではないか?と提言している本書は、かなり参考になるのではないだろうか。ビッグテントは、明確なメッセージと人々を奮い立たせるような価値観の提示をさせにくくするという。とはいえ、ビッグテントなくして多数をとることはできない。多くの人びとが、入ってくれるビッグテントの創設。それを民主党に願って止まない。評価 ★★★価格: ¥735 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Dec 6, 2005
コメント(1)
-

★ アントニオ・ネグリ&マイケル・ハート 『マルチチュード (上・下)』 NHKブックス(新刊)
左翼の間では、話題騒然になった、アントニオ・ネグリ&マイケル・ハート『<帝国>』(以文社、2003年)の刊行。今、その姿を世界にあらわしつつある、グローバル秩序。その担い手は、旧来の版図をもった帝国とも、植民地とともに形成された「帝国主義」の帝国とも違い、超国家的制度や資本主義的大企業などとともに、支配的な国民国家すら節点とする、ネットワーク状の権力<帝国>であるという。人びとの生の奥深くまで浸透してゆく<帝国>的な生権力にあらがう、特異的かつ集団的な主体、マルチチュード。マルチチュードに基づいた、グローバル民主主義と「対抗-<帝国>」的プロジェクトは、はたしてどこまで実現可能なのか。<帝国>への対抗可能性と、主体マルチチュードについて探求した『<帝国>』の続編が、NHKブックスから刊行されることとなりました。長らく待望されていただけに、まことに喜ばしい限りです。上・下あわせて2冊。「第一部 戦争」「第二部 マルチチュード」「第三部 民主主義」の3部構成になっています。それにあわせて、飛び飛びになると思いますが、これから3回にわけて、ネグリ&ハート『マルチチュード』を要約して、みなさんにこの場を借りて紹介していきたいと考えています。「第一部 戦争」● マルチチュードは<多>なる概念で、<共>を基盤におく単一の同一性には縮減できない、文化・人種・ジェンダー・民族性、異なる労働形態・生活様式・世界観・欲望といった、無数の内的差異からなるマルチチュード。それは、多様な社会的生産の担い手をすべて含むという。マルチチュードは、「大衆」の均一性とも、「人民」の同一性とも無縁なため、相互の協働とコミュニケーションのネットワークを可能にする<共(the common)>を見出さなければならない。労働は<共>をうみ、<共>は労働を可能にして、螺旋状に拡大してゆく。非物質的・無形財を創出する労働は、とくに<共>的側面が強く、21世紀の現代社会では、支配的な地位をしめつつあると見なしている。● <帝国>は、恒常的な戦争状態を生み出して<生権力>を掌握する● 現在のあらゆる地域紛争は、<帝国>の内戦にすぎない「三十年戦争」以降、戦争が主権国家同士のみ行なえるものとして<例外状態>に追いやられたのは、少なくとも「国内」では平和を常態=規範として確立させるためであった。その近代的原理は、もはや通用しない。戦争と政治の区別はない。軍事活動と警察活動は、「麻薬」「対テロリズム」戦争のように一体化し、内外の障壁は低くなり、近代で追放されたはずの中世的「正戦」思想が復活しはじめた。戦争状態下では、民主主義の停止が永続化する。死を直接支配する<生権力>体制では、戦争はグローバル秩序を作りあげる構成的権力の一環となっていて、戦争は「セキュリティ」の名の元に正統化されている。本来暴力と対立するはずの人権や、国際法、怪物的な「敵」の創出など、様々なものが正当化のため動員されてゆく。暴力をたえず運用することは、規律・管理を機能させる上で欠くことができない。とはいえ、正統なる政府・人権・戦争規則は曖昧になって、何がテロリズムであるかすら、容易に判別することができない。が、その暴力は、<帝国>のヒエラルキー秩序を「維持するもの」と「脅かすもの」、この2つにわけることができるという。● 貴族と傭兵隊長に似た、<帝国>と軍の関係● マルチチュードの生政治的生産の「先触れ」である軍事革命(RMA)と、 「軍生複合体」の誕生こうした転換は、1970年代にさかのぼる。戦争の焦点は、相手の破壊から、敵の生産へと移り、米ソとも高度の警察行動が一般化するようになった。ハイテク軍事技術とアメリカ一極集中、大規模戦闘可能性の消滅は、戦争を変革してゆく。それまでの「国家総動員」とは対極にある、小規模部隊の投入による「脱身体化」。征服する先の文化・法律・政治・保安に関して、住民に指図して生権力をになう、機械の人工「器官」と化した傭兵たち。とはいえ「脱身体化」された兵士は、アメリカにしかない。圧倒的な非対称性の下、あらゆる標的にされるアメリカ軍は、「全方位的支配」=生権力支配を目指してゆく。「従属した生」を拒絶するものは、生そのものを武器にかえる、自爆攻撃を敢行するしかない。今や、帝国が直面する敵は、ゲリラ型抵抗をさらに押しすすめた、中心をもたないネットワーク状の「群がり」である。これに対応するためには、<帝国>の傭兵、アメリカ軍は、ネットワーク型にならねばならない。もはや、単独行動主義か多国間協調主義か、親米か反米かの二者択一の選択肢は意味がない。国益に固執する一方、普遍主義的・人道主義的レトリックをおこなうアメリカ外交。この2つの「例外主義」は、帝国主義と<帝国>とのハザマで、アメリカが揺れていると解釈されるべきだという。● 出現しはじめた、生政治的<共>を民主的に組織するための戦い● <帝国>とマルチチュードの戦いは、<帝国>が、その正統化のために 「戦争」に訴えるのに対して、マルチチュードは、その政治的基盤と しての「絶対民主主義」に訴えるこの「戦争」の恒常化による<帝国>権力に対して、マルチチュードは「戦争に対する戦争」をおこなわなければならない。その戦いは、近代において夢みられ実現されなかった、自由と平等からなる多様な関係に拠る<全員による全員の支配>、真の意味での民主主義への欲望に基づかなければならない。近代におけるそうした抵抗は、洋の東西を問わず、分散した反逆勢力によるゲリラ戦から、近代的な人民軍を組織せん、とするものであった。その意味で内戦は、近代化の原動力とよぶにふさわしいものであったが、人民闘争の非民主的性格―――「集権化と階層秩序」が不可避―――は、国家建設の段階で第三世界諸国を苦しめることになる。それはキューバ革命や文化大革命においても払拭できていない。そもそも「人民」では、住民の同意にも、「主権」による指令にも使われてしまう。 「人民主権」によらない、マルチチュードの生政治的生産にもとづく、新しい正統性の確立、絶対的民主主義は可能か? 筆者たちは、70年代以降、小規模・柔軟・可動性の高いポスト・フォーディズム生産への移行と軌を一にした、反アパルトヘイトからフェミニズムにいたる、都市を舞台にした新しい抵抗の出現―――最大限の自律性を保証する、中心をもたないネットワーク型構造―――に希望を託す。アルカイダや麻薬カルテルは、こうした構造とは次元を異にしているものであるらしい。(つづく 、) (続きは鋭意執筆中 どうか応援お願いします)評価: ???? (今はまだ秘密です)価格: 上巻 ¥1,323 (税込) 下巻 ¥1,323 (税込) ←このブログを応援してくれる方は、クリックして頂ければ幸いです
Dec 3, 2005
コメント(0)
全10件 (10件中 1-10件目)
1










