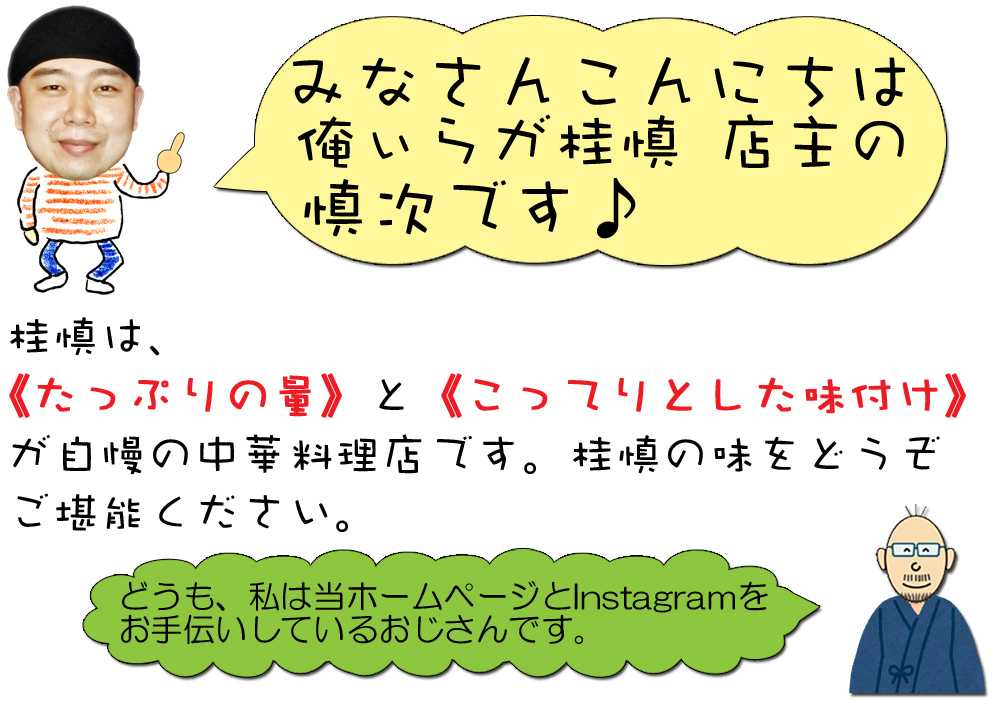2011年09月の記事
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-

サンク・オ・ピエの定番メニュー、4、追記です
フォアグラの話をしておいて、ワインのことに触れなかったのは片手落ちでした。フォアグラって肉系だしコッテリしているから濃い赤ワインが合うんだろうと思っている方が多いでしょうね。ソムリエでもそういう風に思っている人も結構いるくらいですからね。 フォアグラのソテーやテリーヌなどを前菜的に食べるときは、基本赤ワインの出番ではありません! これは、焼きリンゴ添えのフォアグラソテー。これに合うワインは、フランス最大の大河ロワール川流域のシュナンブラン種の甘口白ワインが最高に合います。もちろん、サンク・オ・ピエには、そのワインあります。 このイチジク添えなら、フランスはアルザス地方のゲヴェルツトラミネールの甘口無しには味わえません。もちろん、サンク・オ・ピエではいつでも用意してあります。 この他にも、冷製のテリーヌの場合なら、ボルドーのソーテルヌ周辺の貴腐系ワインが最高です。(もちろん用意してありますよ!)他にも、ハンガリーのトカイの貴腐ワインなどもありますし、ちょっとマニアックな濃いめのシェリー酒なども用意してあります。 少しワインに詳しい程度な方ではおそらく知らない組み合わせのフォアグラとワインのマリアージュが楽しめますよ!どれも特殊なワインですから、まず置いてある店は少ないでしょうね。サンク・オ・ピエは、フォアグラがたくさん出るので、それに合わせたワインもたくさん出ます。だから、特殊なワインでもいつも置いておけるし、グラス売りで気軽に味わっていただけるようしているんです。 まあ、こんな組み合わせは一々覚えなくても大丈夫。サンク・オ・ピエに来て、料理を注文したら、「料理に合うワインをグラスでお願い。」と言っていただければ間違いなく出てきますからね! 飲んでワインそのものが美味しいという事と、ワインと料理がうまくマッチするという事とは少し次元が違います。ワインだけの味では、物足りなかったり、甘かったり、酸っぱかったりしても、料理と合わせると思いもよらぬ心地よさが出てきたりします。 特にフォアグラのような特殊な食材には、合わせるワインが難しいです。 サンク・オ・ピエに来て、フォアグラを食べるときは「これに合うワインを」と言ってみてくださいね。
Sep 30, 2011
-

サンク・オ・ピエの定番メニュー、4
気温が下がり湿度も下がってだいぶ秋らしくなってきました。これから寒くなるまでの時期は一番好きです。昨日届いたさかもとこーひーの秋冬定番ブレンド「ベラ・ノッテ」をさっそく飲んでみると、秋を感じる穏やかな味わいで、、、コーヒーに季節を感じるなんて、さかもとこーひーを知らなかったらなかったでしょうね。私の料理にしても、さかもとさんのこーひーにしても、フレンチやコーヒーという外来の文化ですが、作り手としては日本の風土に合わせて季節感を出しているところが、共通点を感じます。ある種のわびさびがあると思うんです。 ご予約限定!富士幻豚のコースは、10月いっぱいくらい受け付け予定です。富士幻豚は本当に美味しいので、まだ召し上がっていない方はぜひ試してください!ご予約お待ちしております。キノコやジビエもぼちぼち出てきましたので週明けの4日から「サンク・オ・ピエ秋のコース」を始めます。詳しくは、3日月曜日にホームページにアップ予定です。 11月に入れば、スモークサーモン作りも始まり、ジビエの入荷も本格的に、、、第三木曜日には、ボジョレーヌーボー解禁と、秋冬は美味しいものが目白押しで、楽しい季節ですね。 サンク・オ・ピエの定番中の定番と言えば、フォアグラのソテー!お昼のコースのMenu BやディナーコースのMenu Cまたはオプション選択で選べます。この画像のフォアグラの相棒はイチジク。そのほかにも春は春キャベツ、初夏の新玉ねぎ、夏の茄子や冬瓜、この時期はこのイチジクやたまに洋梨、もうすぐリンゴ、ちょっとぜいたくをしてポルチーニ茸、人気が高い大根添え、そのほかにもジャガイモのピュレやアメリカンチェリーもありますね、、、たまにピュイ産のAOCレンズ豆とか、レーズンやプルーンなどドライフルーツのコンポートなんかもやります。 とても人気で、サンク・オ・ピエは小さな店なのに月に10キロ前後使います。最高記録は月に約50キロ近く!フォアグラのソテーは、お昼で45gくらい夜で60gくらいですから、50キロと言えば1000人前近くです。お客様の中には、一人で200グラムも300グラムも召し上がる方がいらっしゃいますので、こんな量になるんですね。 私のフォアグラ料理のレパートリーはかなり多く、おそらく世界でもトップクラスじゃないかと自負してます。だから、需要にこたえて「フォアグラ・マッドネスのコース」というフォアグラ尽くしのフルコースもやってます。これは、前菜からデザートまで全部フォアグラ料理という恐ろしい!?コースで、超高カロリーですからフォアグラ大々々好きな方にしかお勧めしませんが、フォアグラ尽くしなんていうコース料理は、誰にでもできることではないので、世の中のフォアグラ大好き人間を救済するという社会的責任を感じてやっています。(笑) この25年くらいフォアグラを毎日のように焼いてきました。最初のころは、ハンガリー産のガチョウのフォアグラが主流で、今よりももっと品質が悪くて値段も高ったです。バブルのころのフレンチブームグルメブームに乗って輸入量が増えて価格も品質もだんだん良くなってきました。とくに90年代後半からは、フランス西南地方産の鴨のフォアグラが主流になってきました。最近は、冷凍技術の劇的な進歩もあり、冷凍の鴨のフォアグラもフレッシュ物と区別がつかないようなってきました。フレッシュ物は空輸ですからどうしてもコスト高になってしまうので、優秀な冷凍物があるのは助かります。 で、フォアグラとは何か?ご存知の方も多いでしょうが、ガチョウや鴨のレバー(肝臓)を肥大させて脂肪肝にしたものです。よいフォアグラを作るためには、まず鳥を健康で頑強に育てなければなりません。そのためには、しっかり運動させて健康的なえさを与えて大事に育てます。そのあと出荷前に暗くした静かな小屋に移してトウモロコシをたくさん食わせて肥育します。最近鴨のフォアグラが主流なのは、フランスでバルバリー種の鴨の雌と北京ダックで有名なチェリーバレー種の鴨の雄をかけ合わせたミュラールという品種が開発されてからです。ガチョウの場合は体も大きく結構気性も荒いので、飼いずらいらしいです。まあ、ハンガリーでは今でもガチョウのフォアグラが主流ですが、、、。フォアグラの歴史は、結構古く古代ローマ時代にはもう食されていたようです。その後中世の暗黒時代に一度廃れたようですが、ルネサンス期あたりからは高級食材として定着したようです。ルネサンス後期のころまでは、フランスはヨーロッパの中では田舎な国でしたから、意外にもフォアグラの本場は古来からイタリアだったんです。ただもう今は、断然フランスが生産量でもトップです。フランスが年産18000トンくらいで、ハンガリーとブルガリアがそれぞれ200から250トン前後ということで、イタリアでは輸出するほどは作られていないようです。 フォアグラは約六割が脂肪分ですから、焼くと溶けて脂が出ます。とくに鴨のフォアグラは熱に対してデリケートで溶けやすいです。ガチョウのフォアグラは、かなり熱に強いので、素人が調理するならガチョウのほうがやりやすいでしょう。サンク・オ・ピエでは、ほとんど西南フランス産の鴨のフォアグラを使っています。鴨のほうが香りがたつし、味わいが軽いことが気に入っています。大変デリケートな食材ですから、長年ブランドや品質にはこだわってきました。メーカーや季節の違いなどで、品質にばらつきがあるんです。しっかりしていて溶けにくいものがあれば、すごく溶けやすくて焼くと極端に痩せてしまうものもあり、また溶けにくすぎて口当たりが悪いものなど、フォアグラにはうるさいです。ただもう長いことやってますから、品物をちょっと見て触れば品質はすぐわかりますけどね、、、。 そういうわけで、焼くと溶けるので、多くの料理人が中までしっかり火を入れ切らないので、生臭みやいやな脂っこさが出てフォアグラが不味くなってしまいます。かといって少しでも焼きすぎれば、脂が抜けてそっけないものになってしまいます。最悪焦げた高野豆腐みたいな、、、。 最高の仕上がりは、表面はカリッと香ばしくしっかり焦げ目もついてメイラード反応による旨味が最高潮で、中は上手に焼いたオムレツのように切るとトロリと溶けている状態です。で、サンク・オ・ピエのフォアグラのソテーはいつもそんな感じです。私は作る料理どれにもそれなりの思い入れと勘所があるので、どれが得意というものはないつもりなのですが、「サンク・オ・ピエへ行ってフォアグラ食わずにどうするんだ!」という常連さんは間違いなく多いですし、仕入れミスでフォアグラを切らしたらきっと怒られるんだろうなと思って、いつもしっかり在庫するようにしています。
Sep 30, 2011
-

サンク・オ・ピエの定番メニュー、3
サンク・オ・ピエを始めてかれこれ10年、色々な料理を作ってきました。数えたことはないですが、1000種類とまではいかなくても、100や200という事もないだろうという事で、、、まあ、数百種類の料理はやってきたでしょうか? そんな中で、少しずつ作り方やスタイルを変えながらも定番となって不動のメニューになっているものがいくつかあります。そんな料理を紹介していこうかと思います。 これは、地鶏レバーのテリーヌ。最近はときめき鶏のレバーと富士幻豚の背脂で作っています。肉系のテリーヌは、脂肪分が約半分が基本。魚のテリーヌが半分生クリームなのと似てますね。基本的な配合は、レバーが500グラムに背脂が500g塩13グラムナツメグとコショウを少々と三温糖かカソナードを3グラムくらい。私の場合、レバーの血抜きはしません。ただし新鮮なレバーに限りますが、、、。レバーと背脂を交互に肉挽き機にかけてミンチにするんですが、その時に材料が冷たいことが肝心。出来れば3度以下位が良いです。ミンチを使わずに、フードプロセッサー回すこともありますが、1キロもの材料が一気に入るのは業務用サイズじゃないと無理ですね。 ミンチができたら、調味料を入れてよくかきまわします。冷えているとここで粘りが出てテリーヌ生地がよくつながって滑らかな仕上がりになります。この時に温度が高いと粘りが出なくて、食べるとざらついた上に脂が分離して不味いテリーヌになってしまいます。ハンバーグなどもそうですが、捏ねていて手が痛くなるくらい肉が冷たくないと生地がまとまらないんです。 つなぎに卵や粉類、コクだしに生クリーム、香りづけにポルト酒やブランデーなどを加える人もいますが、私の場合は余計なものは入れません。千葉市産の新鮮レバーと美味しい富士幻豚の脂だけです。塩胡椒ナツメグは最低限の調味料で、砂糖は若干の発色作用を期待して入れてます。もちろん甘さは感じない程度です。 バターを塗り、ベーコンを貼りつけたテリーヌ型に出来た生地を入れて湯煎にかけ170度くらいのオーブンで蒸し焼きにします。途中何回か湯煎に氷を入れて温度が上がりすぎないようにします。焼き時間は約1時間。焼き上がったら、軽く重石をかけて形を整えながら室温まで冷まし。手でつかめるくらいに冷めたら冷蔵庫に入れます。翌日すぐ食べられますが、ラードを流して、空気から遮断し冷蔵庫で数日熟成させるとさらに美味くなります。 焼いたバゲットのスライスにたっぷりのせて頬張るのが一番美味い食い方ですが、それではコースの前菜には不向きなので、サンク・オ・ピエではサラダを添えてお出ししています。 料理人をやっていますと、自分で作ったものを手放しに美味しく食べるという事は少ないんです。やはりプロの舌は厳しいですし、まして自分に対してはなおさらです。美味しいかどうかというより、ちゃんと思った通りに出来ているかどうか?が、一番のポイントだからです。上手く出来ていると、思った通りの味という訳ですから、それはそれで今更感動はないわけです。かと言って、思いもよらないほど美味しいなんて言うのも、また自分でコントロール出来てなくて腹立たしいわけです。 でも、自分でも美味しいなぁと思うのが、このレバーのテリーヌなんですね。シンプルの極みでごまかしなしという感じが気に入ってます。 とにかく、レバーと背脂と塩だけみたいなものですから、材料の挽き方、捏ね方、火の通し加減などがすべて完璧でないと絶対に美味しくできません。私の料理の基本的なスタイルなんですね。塩で味を決めて、正確に火を通すだけ。素材がよければこれ以上やることはないでしょうという考え。 実際、このレバーのテリーヌを何人かの後輩に目の前で作って見せて教えたことがありますが、あとで自分で作って同じようにできたという話は聞いたことがありません。シンプルなレシピの怖さはそういうところにあるんです。あまりに種も仕掛けもないので、技術の差がもろに出てしまうんですね。教えた後輩の中には「きっとあのオヤジ他に何か技を使ってるに違いない」なんて思ってるやつもいるかもしれませんけど、それはないです(笑) プレーンオムレツを考えてみれば分かるかもしれませんね。卵2個に生クリームを少しと塩胡椒、バターとサラダオイル適宜。あとはフライパンとお箸かフォークですね。きれいな木の葉形に焼きあげて、「表面はほんのり香ばしく焦げ色がついて切ると中から半熟な卵が流れ出す。」というオムレツを焼けるようになるにはかなりの訓練が必要です。しかもそれを仕事で、どんなに忙しくても正確に出来るようになるには相当な訓練がいります。たかが卵焼きされど、、、という事でしょうか? それにしても、3.11の地震といいこのところの台風。まったく天災人災天災と続きますね、、、。さらに、、、、最近衝撃的だったのが、光速を超えたニュートリノが観測されたという話。これが本当なら、世界中の物理学者がひっくり返ります!アインシュタインの相対性理論が否定されてしまう訳ですからね!宇宙の始まりや終末、タイムマシーンの可否や宇宙戦艦ヤマトのワープなど時空間の移動に対する根本的な考え方が変わってしまう可能性があるからです。まあ、これは料理には関係ありませんが、、、いや、少しあるかな??
Sep 26, 2011
-

サンク・オ・ピエの定番メニュー、2
サンク・オ・ピエを始めてかれこれ10年、色々な料理を作ってきました。数えたことはないですが、1000種類とまではいかなくても、100や200という事もないだろうという事で、、、まあ、数百種類の料理はやってきたでしょうか? そんな中で、少しずつ作り方やスタイルを変えながらも定番となって不動のメニューになっているものがいくつかあります。そんな料理を紹介していこうかと思います。 これは、魚のテリーヌ。テリーヌというのは、、、 こういう器の名前なんです。この中に何かを入れて焼いたり蒸したり、あるいはゼラチンで固めたり、重石をして固めたりしたものをたいていは冷製の前菜として切り分けて出すものです。 ハムにしてもテリーヌにしても仕込みの手間はかかりますが、オーダーが入ったらサラダと一緒に盛り付ければすぐに出せるので、私のような一人仕事の料理人としては重宝する存在です。しかも、近頃はこういうものを手作りする人が少ないですから、ありふれたメニューながら美味しいものを出せば、確実に実力を示せるわけです。 「今更テリーヌいなんて古いだろう。たいして美味くないし、、、。」なんて言っている料理人が多いのでしょうが、私が相手にするのは同業者でもフレンチの専門家でも特別な食通でもありません。普通のお客様がほとんどです。そういう意味では、こういうオーソドックスなメニューをきちんと美味しく出すことがとても大切だと思っています。常連さんの中には、いつ来ても必ず魚のテリーヌと言う人もいるくらいですから、手は抜けません。 さて、魚のテリーヌは魚のムースが基本となります。このテリーヌ型は、1キロ用なので魚は450gくらいです。基本白身魚です。鯛、スズキ、ヒラメ辺りがベスト。金目鯛や黒ムツなんかもいけますし、サーモンやマスも良いです。甘みを出すために帆立貝を入れるのも良いです。それから海老類も良いですね。その魚をフードプロセッサーですり身にして、塩8グラム、ナツメグと白コショウ少々と卵白2個分を加え、さらに回します。鮮度いいとすごく腰が出ます。というか鮮度良くないのじゃ使えないですけどね、、、。そこに生クリームを少しずつ全部で500ccくらい加えます。私の場合は脂肪分35%の軽いクリームですが、47%とかの重いクリームを使えばより重厚な味わいになります。いずれにしても魚とクリームがほぼ同量というのが基本です。 これはだいたい70年代辺りからの作り方です。もう少し昔だと、パナードと言って、小麦粉とバターを加熱して捏ねたシュー生地のようなものをつなぎに入れたりしてました。今ほど流通がよくない頃でしたから、鮮度が落ちた魚だと少し粉系を入れないと生地がつながらなかったのかもしれませんね。私はパナードを使ったことはありませんが、、、。 まあ、そのようにしてできた生地にガルニチュール(具材)として帆立やサーモンあるいはキノコなどを混ぜ込んだりして、バターを塗ったテリーヌ型に入れて、湯煎にかけ、170度から180度くらいのオーブンで蒸し焼きにします。約1時間かかりますが、途中で湯煎の温度が上がりすぎないように氷を入れたりします。 火が通ったら荒熱を取って冷蔵庫で一晩くらい落ち着かせれば出来上がり。あとは型から出し、カットして盛り付ければいいわけです。 20年くらい前に初めて作りましたかね。たしか、、、。その頃は、和食用の入船というブランドのすり身を使ってやらされました。粘りがないので、ボールを氷水に当てて1時間くらい練らないとコシがでなくて苦労した思い出があります。でも、今思うとパサパサして多分分離した感じだったんでしょうね。今は、ちゃんとした鮮魚を使ってますから、かなり美味しいと思います。うちのマダムが好きなので、いつも一切れ目の端っこは彼女が味見担当です。 魚のテリーヌは、フレンチの歴史の中では新顔のほうなんです。テリーヌと言えば、本来は肉系だったり、フォアグラだったりが主流でした。70年代後半ごろからか、いわゆるヌーベルキュイジーヌ(新フランス料理)のころからのヘルシー志向の流れなんです。だから私の魚のテリーヌはだいたい40年くらい前の作り方が基本です。でも、半分生クリームでどこがヘルシーなんだか?という感じですけどね(笑) 久しぶりのうちの猫たちです。手前が雌3歳の「ノアール」黒トラ猫。上が「レノン」通称レノ坊、2歳の和猫黒と純血ソマリのミックスです。 黒トラのノアールさんです。煮干しが大好き。夜私が帰ってくると、「煮干しちょうだい」と、冷蔵庫の前でドアに手をかけて待ってます。 レノ坊は、遊び好き。この体制で猫じゃらしか何かで遊んで欲しくて待ってます。 ちょっと山猫風な柄が魅力です。 先週末のいつものK氏のワイン会には、富士幻豚を主に出しました。うちのお客様でもっとも味にうるさい方たちなんですが、やはり富士幻豚は大好評でした!ワイン会メンバーのさかもとこーひーのさかもとさんがブログで、絶賛してくれました。ありがとうございます。富士幻豚、本当に美味いです。ぜひ食べてみてください。
Sep 19, 2011
-

サンク・オ・ピエの定番メニュー、1
サンク・オ・ピエを始めてかれこれ10年、色々な料理を作ってきました。数えたことはないですが、1000種類とまではいかなくても、100や200という事もないだろうという事で、、、まあ、数百種類の料理はやってきたでしょうか? そんな中で、少しずつ作り方やスタイルを変えながらも定番となって不動のメニューになっているものがいくつかあります。そんな料理を紹介していこうかと思います。 これは、前菜の一番人気。養老渓谷産もち豚のスモークハムと生ベーコン。2006年ころから作り始めて、ずいぶん変化してきたが最近ほぼスタイルが決まってきた。 これが最初のころ。今はもう使っていない皿に盛られているのが懐かしい。ハムは、まず塩漬けから始める。専門的に作る場合は、ソーミュール液という一定濃度の塩水に硝石やスパイスやハーブなどまた発色剤や保存料なども入れてそこに肉を漬けこんで塩漬けにする。塩水がベースなので塩分濃度などが管理しやすいので、大量生産向きですね。 私の場合は、直塩法と言って、肉に直接塩を振っていくやり方。これは、最初から変わっていない。大きなラップを広げて肉を置き、地中海のカマルグ産の塩をミルで挽きながら塩を振ります。肉の厚みや脂ののり具合を見ながら塩を振ってから、ラップできっちり包んで数日ほど冷蔵庫で漬けこみます。スパイスやハーブ類もちろん発色剤や保存料も一切使いません。肉と塩だけです。 このハムを作りだしたきっかけは、市販の物に美味しいものがないからなんです。日本の法律では、ソルビン酸などの添加物を一定量入れないとハムとしては売れないんですね。それが原因で、日本のハムは何を食べてもどこか同じような味がするんです。ところがフランス産やイタリア産のハムは肉と塩だけでシンプルに作らているものが多いんです。しかしフランスやイタリア産のハムの美味しいやつは結構いい値段するので、これがまた使いづらい。それなら自分で作るか!という事で、やりはじめました。 そこで、一般的な方法である、、、ソーミュールで塩漬けし、ボイルして火を入れ、スモークして仕上げるという方法は完全に無視しました。 直塩で塩漬けし、オーブンで火を通し、冷燻でスモークして仕上げるという方法をとっています。その火の通し方がこの5年の間いろいろ変わってきました。はじめは、オーブンを低温(130度)にセットして、肉をシリコンペーパーに包みそれをさらにアルミホイルに包んでオーブンで3時間かけて火を通します。低温でゆっくり火を通しますからかなり柔らかいのですが、シートに包んで火を通すのでちょっと蒸れた感じになります。肉の表面が湿っているとスモークがうまくかからないので、最近はオーブンを250度にセットし、肉を3分ほど入れては、温かいところで6分以上休ませるという私得意の長時間ロースト法で火を通している。だからハムというより、ローストポークなのだが、実際に仕上がったものを食べると上質なハムという感じになっている。桜のスモークチップの風味がまた心地よい感じです。 生ベーコンのほうは、やはり直塩で漬けこみ、数日後冷燻にかける。その後真空パックにかけて氷温庫(-5~6℃)で熟成させる。 養老渓谷のもち豚は、千葉県の南部の養老渓谷で作られている美味しい豚です。もち豚という銘柄は、日本各地で作られていて、値段もピンキリなんですが、養老渓谷産のもち豚はその中でも一番高級なものです。餌と飼育法が良いのでしょう。変な癖がなく脂もきれいで美味しい肉です。 この5年くらいのノウハウで、最近は富士幻豚のハムやパンチェッタ、ラベルルージュのマグレ鴨の生ハムや去年の秋はイノシシのハムもやりました。上質な肉を塩だけで仕上げた美味しくてナチュラルなハム。サンク・オ・ピエでしか味わえませんよ!
Sep 15, 2011
-

本当に希少な富士幻豚、中ヨークシャー種の豚
これが中ヨークシャー種。乳首が大きいので母豚ですね。鼻が少し上向きなのがこの豚の特徴です。 日本では、年間約1600万から1700万頭の豚が出荷されているらしいのですが、中ヨークシャー種の豚はそれに対して、数100頭という少なさだそうです。 まさに幻ですね!サンク・オ・ピエでも、発注したからと言って必ず入ってくるわけではありません。今やっている超希少種富士幻豚を楽しむコース、おかげ様で大好評なんですが、今週は、肉が足りなくなってしまいました。ご予約はお早めにお願いします。 戦前は美味しい豚という事で、日本でも世界的にも主要品種だったのですが、成長が遅く子供もたくさん産まない品種なので、生産効率が追求された戦後はすっかりすたれてしまったわけです。一時は日本でたったの7頭まで減ってしまったこともあったそうです。 幻の豚の味わいをぜひお試しください。 台風12号が大変な被害でした。温暖化のせいなのか、近頃の台風は大型で強いものが多いですね。残暑もまだ続きそうですが、だいぶ秋らしくなってきました。食材業者さんからは、早くもキノコやジビエの案内が入ってきていますし、酒屋さんにはもうボジョレーヌーボーの予約も済ませました。秋本番も近いですね。キノコのコースなんかも考えているところです。 早くもあの震災から、半年。9.11テロからもう10年ですか、、、。9.11のテロはちょうどサンク・オ・ピエを開店した年の秋でした。トレードセンターに突っ込む旅客機の映像をあまりのことに現実とは思えずに呆けて見ていたのが思い出されます。 まあ、色々ありますがサンク・オ・ピエでは季節の美味しいものを用意してお待ちしております。
Sep 10, 2011
-

超希少!富士幻豚のコース
大好評の富士幻豚(ふじげんとん)のコースの詳細です。富士幻豚は、富士山麓で桑原さんという世界的にも有名な畜産家が手掛ける中ヨークシャー種という希少種の豚です。その希少さは、国産豚のなんとわずか0.2~0.3%の流通量だそうで、まあなかなか手に入れることすら難しいわけです。 戦前までは美味しい豚ということで、世界的にもたくさん飼われていたのですが、戦後の食糧難のこともあり、世界的に生産性のよい豚の品種改良が進んで、美味しさは二の次にされるという事態が進んだ結果、成長が遅く子供もたくさん産まない中ヨークシャー種は、ほとんど廃れて本国イギリスにはもう一頭もいないそうです。 21世紀も近くなったころから、世界各地の生産性は悪いが美味しいという豚が見直され始めて、フランスのビゴール豚やバスク豚、スペインのイベリコ豚のべジョータ、ハンガリーのマンガリッツァ豚などが次々と復活したり注目を集めてきました。日本の豚はそれに少し遅れて、21世紀に入ってからこのところ格段に良くなってきました。特に九州の黒豚が有名ですが、この富士幻豚は希少性と食味の良さから黒豚を超えるものと言っていいと思います。 一皿目は、Salade de lard fume de FUJIGENTON et Jambon fume de FUJIGENTON とろける!富士幻豚の自家製パンチェッタと赤身が美味しい富士幻豚もも肉の自家製スモークハムのサラダ仕立て。パンチェッタは奥のほうですね。自家製のドライトマトも添えてこれがまた美味いです!モモハムは赤身の美味さ、パンチェッタは、脂の美味さと口解けの良さを味わっていただきたいです。一般的に豚の脂の融点は、38度前後ですが、富士幻豚の脂は32.8度で融けるという事です。だからパンチェッタの口解けが見事です!ちょっとないですよ!!本当に美味いですから、、、。定番のワインの組み合わせは、シェリーのマンサリーニャ・パサダかほんのり甘いカリホルニアのジンファンデルロゼが良いですね! 2皿目は、Petit cassoulet de FUJIGENTON et foie gras chaud 富士幻豚と白インゲンの小さなカスレ仕立て、フォアグラ添え。 これはカスレを仕込んでいる様子。カスレというのは、西南フランス地方の郷土料理なんですが、フランス全土で親しまれているフランス人が大好きな料理です。本場西南地方では、地域ごとまたは家庭ごとにいろいろ作り方があるんです。この料理の主役は白いんげん豆!これはまず間違いありません。 まず、ガチョウか鴨の脂で玉ねぎニンニクエシャロットなどを炒めます。私の場合、ガチョウや鴨の脂の代わりにフォアグラのくずを炒めて脂を出して使います。そこに富士幻豚のハムやパンチェッタの落とし肉とロース肉の端肉などを加えて炒め、水で戻して柔らかくした白いんげん豆を加えて、少しのトマトソースとトマトペーストに薄めのブイヨンを入れて煮込んでいきます。豆が半ば崩れてグタグタになるくらいがよい感じ。 実はカスレという料理、本物はは脂ギトギトなんです。仔羊を入れたり、鴨やガチョウのコンフィを入れたり、もちろん豚肉(ソーセージなども含めて)肉類の脂っこいやつが大量に入ります。それを土鍋に入れて、パン粉を振ってグラタンのように焦げ目をつけて出してくるのですが、、オレンジ色の脂が2センチくらい浮いているような脂っこい食べ物なんです。西南フランス産の濃ーーい赤ワインがよく合いますが、はっきりいって日本人にはちょいと重すぎるので、私の場合は脂肪分はかなり控えめです。それでも十分濃厚ですけどね、、、。 このように盛り付けて、パン粉を振って上火で焼き色を付けてから、、、 フォアグラのソテーをのせます。白いんげんとフォアグラの脂が絶妙にマッチして、フォアグラ料理なのに赤ワインがよく合います。 さて、続くメインは、Cote de cochon de FUJIGENTON roti 富士幻豚の背肉の低温長時間ロースト どうです!このしっとりとした焼き上がり。250度のオーブンに2~3分入れては暖かいところで5~6分休ませるということを繰り返して、肉の温度を少しずつ上げていきますから、肉にストレスがかからずに柔らかく仕上がるわけです。低温長時間ローストというと低い温度のオーブンに入れると思うでしょうが、そうではなく肉自体の温度を低温に保ちながら焼いていくということなんです。最低でも1時間半くらいはかかります。ですから予約のみということになるんですね。 カマルグ産のフルール・ド・セルをぱらりと振りかけ、黒胡椒を挽き、ポルト酒と赤ワインに赤ワインヴィネガーと蜂蜜も少し入れて仕上げたソースです。 さて、デザートがまたゴージャス!Ganache de Manjari grand cru de Valrhona,Petit mont blanc aux marrons Glace myrtille a ma jardin ヴァローナ社、グランクリュ、マンジャリの生チョコ 小さなシェフ風モンブラン 自家菜園のブルーベリーのアイスクリーム それに合わせるはもちろんさかもとこーひー!このデザート専用のブレンドです。 ヴァローナのグランクリュ、マンジャリのショコラはとても印象的な味わいです。上質なコニャックや木イチゴのリキュールでも入っているかのような芳醇な風味でちょっとびっくりします。もちろんそういうアルコール類が入っているのではなく、ショコラその物の風味がそこまで芳醇なんです。マダガスカル産の最高級カカオ豆を使った逸品です。もちろん値段も最高級です。 モンブランは、まず栗入りのフィナンシェを焼き、その上にフランス産の栗100%のマロンペーストを使った軽いマロンクリームを絞って、イタリア産の栗をラム酒風味のシロップで煮たものをトッピングしてあります。ケーキ屋さんのモンブランと違ってクリームが軽くて上品な感じです。 アイスクリームは、卵を使わないで作りました。ちょっとハーゲンダッツ的なイメージの味わいに仕上げてあります。最近取れた自家菜園のブルーベリーのコンポートをたっぷり混ぜ込んで、きれいな紫色で目に良いというアントシアニンがたっぷりです。 またこのデザートに専用ブレンドを合わせると、、、これがまた美味いです!特にヴァローナのグランクリュ・マンジャリの生チョコは、ちょっと言葉が出ません。素晴らしいマリアージュです。もちろん、モンブランとは当たり前のように合うし、ブルーベリーアイスクリームと合うのはおそらく、マンジャリのベリー系果実味に合わせたこーひーだからでしょうね、、、。今回もさかもとさん良い仕事してくれました。ありがとうございます。 というわけで、超希少種富士幻豚を楽しむコースは、ご予約限定メニューです。
Sep 5, 2011
全7件 (7件中 1-7件目)
1