2018年03月の記事
全18件 (18件中 1-18件目)
1
-

京都さくらよさこい2018
親バカ日誌。今日の京都は快晴、もの凄い人でした。平安神宮にて
2018.03.31
-

労基署に「労働時間改善指導・援助チーム」
4月1日から全国の労働基準監督署に、働く方々の労働条件の確保・改善を目的とした「労働時間改善指導・援助チーム」が編成される。「労働時間相談・支援班」は労働時間相談・支援コーナーを設置し、主に中小企業主に対して、法令に関する知識や労務管理体制についての相談への対応や支援。「調査・指導班」では、任命を受けた監督官が、長時間労働を是正するための監督指導を行うとのこと。www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000199557.html社労士の仕事を取るなっつーの。
2018.03.31
-

再雇用の賃金減に違法判決(福岡高裁)
北九州市の食品会社が定年を迎える社員に、再雇用(継続雇用)の条件として賃金を25%相当に減らす提案をしたのは不法行為にあたるとして、会社に慰謝料100万円の支払いを命じた福岡高裁の判決が確定した。佐藤明裁判長は再雇用について「定年前後の労働条件の継続性・連続性が一定程度確保されることが原則」との判断を示した。判決は昨年9月7日付。原告、会社双方が上告したが、最高裁が3月1日にいずれも不受理の決定をして確定した。原告代理人の安元隆治弁護士らによると、再雇用後の賃金引き下げを不法行為とした判決が確定したのは初とみられる。再雇用をめぐる企業の実務に影響しそうだ。判決によると、原告は食品の加工・販売を手がける九州惣菜(そうざい)(北九州市門司区)に2015年まで40年余り正社員として勤めた。60歳の定年時は経理を担当し、月給は約33万円だった。同社は、再雇用後は時給制のパート勤務とし、月給換算で定年前の25%相当まで給与を減額する条件を示したが、原告は拒んだ。高裁判決は、65歳までの雇用の確保を企業に義務づけた高年齢者雇用安定法の趣旨に沿えば、定年前と再雇用後の労働条件に「不合理な相違が生じることは許されない」と指摘。同社が示した再雇用の労働条件は「生活への影響が軽視できないほどで高年法の趣旨に反し、違法」と認めた。(後略)2018.3.30 朝日新聞再雇用改め、定年延長制度に切り替える企業が増えている。背景はもちろん人材確保難。定年延長といっても多くは条件変更が伴ってると考えられる。本ケースもさずがに75%ダウンは容認できないが、25%ダウンだったらどうだろう。日本の労使慣行上、違法とまでは言えないと思う。同一労働同一賃金。漸く議論が深まる空気が醸成されつつある。
2018.03.30
-

最近読んだ本(ひよっこ社労士のヒナコ)
ひよっこ社労士のヒナコ [ 水生 大海 ]価格:1620円(税込、送料無料) (2018/3/17時点)日常よくありがちな話を小説風にアレンジされている。法改正に対応。非専門書。中途半端な立ち位置の印象。
2018.03.17
-

日本労務学会
日本労務学会の関西部会例会(関大梅田キャンパス)の第3報告へ。「2017年の日本の人事部ー人事ポリシーと人事部の特性ー。発表者は神戸大学の平野光俊氏、コメンテーターは同志社大学の石田光男氏。共に当分野の第一人者であるが、殊に石田先生は権威、重鎮と言える。フロア傍聴者もほとんど大学教授。そんな中に飛び込んでみるも、理解できたのは話の40%くらい。まぁ良い刺激にはなるわな。ひとつ言えることは、偉い先生方はドロドロした労働現場をあまり知らないこと。お客様からの罵声を浴びた経験もなかろう。悪質クレームによる土下座体験もなかろう。私の強みはそれくらいか。
2018.03.17
-

未払い残業代20億円
JR西日本は16日、未払いの時間外賃金があったとして、従業員1万4200人に総額19億9000万円(1人当たり月平均5600円)を支払うと発表した。2017年3月に大阪労働局から是正勧告と指導を受け、本社や支社、現場の内勤社員1万7700人について調査し、未払い分が判明した。今月の給与支給日に支払う。調査対象は15年3月1日~17年3月末。社員が申告した勤務実績と、パソコンの起動時刻や電子メール送信歴などを照合した。未払いの時間数は計80万1200時間(1人当たり月平均約2.3時間)だった。サービス残業は主に始業時間より早く出社する形で行われていた。期間中にサービス残業時間が計500時間を超えた社員は、駅などの助役を中心に15人おり、最大は計1192時間だった。(時事通信 2018.3.16)依然として自己申告制を採用している企業も多い。始業・終業時刻の確認は、「現認」または「タイムカード・ICカードなど客観的な記録」が基本のキ。「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
2018.03.16
-

ココロカフェ
仕事帰りに関大梅田キャンパスKANDAI Me RISEラボへ。ココロカフェ season2―喜怒哀楽のココロ-、「クレーマーとの付き合い方 その心理と対策の極意」講師は池内裕美教授。参加者は30名程度で若い女性が多かったように思う。本当にスタバのカフェを飲みながら、お菓子を食べながらのスタイルで、とても心地よい時間でした。法務部門の仕事ではクレーム対応も重要な業務のひとつ。キーワードモンスターカスタマー、サイレント・マジョリティ、SNS拡散、ホスピタリティ、不寛容社会、過剰批判社会、リカバリー・パラドックス、苦情の2007年問題、三現主義、NGワード、確証バイアス、エスカレーション、傾聴、グッバイ・マネジメント、カタルシス効果、アンガーアタック、感情労働、共感ストレス、グループ・ディブリーフィング、セルフ・コンパッション等
2018.03.14
-

無期転換回避か
4月から有期契約労働者の「無期転換ルール」が本格適用されるのを前に、解雇や契約更新の拒否といった「雇い止め」に関する相談が急増している。日本労働弁護団が今月3日に行った無料電話相談では103件、2月の連合の電話相談でも雇い止めを中心に3日間で752件の問い合わせがあった。無期転換を回避するために解雇し、業務委託に切り替えるなど悪質な例もあるという。無期転換ルールは、契約期間が通算5年を超えた有期契約の労働者が、定年まで働ける無期契約に転換できる制度。2013年4月施行の改正労働契約法で定められ、5年後に当たる今年4月から権利を得る労働者も多いとみられる。無期転換が進めば労働者は生活が安定するが、企業側には、解雇がしにくくなり人件費の増加につながるとの懸念がある。同弁護団に労働者から寄せられた相談では、5年以上働けないように有期契約の規則を改訂し、無期転換を回避する企業が多かった。また、労働条件の切り下げを提案し、拒否したら解雇するケースや、突然試験を導入して契約更新しない例も少なくないという。同弁護団の棗一郎幹事長は「昨年の暮れから相談が増えてきた。法律違反の可能性がある事例が相当ある」と話す。(2018.3.12 時事通信)大学職員なども同じような目に遭っていると聞く。法律の専門家もおられる環境ですら、法の趣旨を逸脱したおざなり対応の様相を呈している。民間、殊に中小は言わずもがな。
2018.03.12
-

総長カレー
今日の京都は快晴。 京大経済研究所シンポジウム: 豊かさを育むエビデンスベース社会の実現に向けて 第7回「明るい社会の未来像」へ。食する機会を逸していた総長カレーをいただきました。ん。思ったより普通。ボンカレーの方が美味しいかも(笑)たまたま前期日程の合格発表日と重なっていたようで、キャンパスは大変な騒ぎになっていました。応援団がでかい声を張り上げている。体育会系の学生さんに胴上げをされている。早くもサークルの勧誘合戦が繰り広げられている。不動産仲介会社が下宿のあっせんパンフレットを配布している。そこココで記念撮影が行われている。そんな中、うつむき加減で出町柳駅に向かう親子の姿。つらいな。振り返れば、私の半生も失敗と挫折の繰り返しだったかも。大学受験、失恋・・そして司法試験も道半ばで撤退。それでも元気に生きている。これでいいのだ。
2018.03.10
-

君たちはどう生きるか
吉野源三郎氏の「君たちはどう生きるか」の漫画が爆発的に売れているニュースをよく見聞きする。古い話になるけど、高校合格発表~入学までの間にはじめて出された課題が、この本を読んで感想文を書くことだった。いわば遊ばせないために課される入学前の宿題ですね。あれから33年も経ったか。随分と久しぶりやな~、コペル君。当時の岩波文庫でなく、漫画で再会してみようか。青春の懐かしい匂いがするかもね。
2018.03.09
-

正社員との賃金格差 最高裁判断へ
非正規雇用の契約社員らが、正社員との待遇格差は労働契約法に違反するとして会社側に賃金の差額の支払いを求めた2件の訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は7日、原告側と会社側双方の意見を聞く弁論を4月下旬にそれぞれ開くことを決めた。最高裁はどのような労働条件の格差が「不合理な差別」に当たるか初判断を示すとみられる。2013年の法改正で新設された労契法20条は、正社員と契約社員の労働条件に不合理な差をつけることを禁じている。賃金格差が労契法違反に当たるかが争われた訴訟は各地で起こされており、最高裁の判断によっては非正規雇用の待遇改善を求める声が高まりそうだ。また、政府が今国会への提出を目指す働き方改革関連法案には「同一労働同一賃金」の実施が含まれており、議論に影響を与える可能性もある。2件のうち1件は、横浜市の運送会社「長沢運輸」で定年後に再雇用された運転手3人が、賃金を3割前後減らされたとして同社に差額分の支払いを求めた訴訟。小法廷は4月20日に弁論を開く。1審・東京地裁は16年5月、「特段の事情がない限り、職務内容が同一なのに賃金格差を設けるのは不合理だ」として会社側に約415万円の支払いを命じた。これに対し東京高裁は同11月、「定年後の賃金引き下げは広く行われ、社会的に容認されている」として原告側の逆転敗訴とした。2審の結論を変更する場合に必要な弁論が開かれるため、2審判決が見直される可能性がある。もう1件は、浜松市の物流会社「ハマキョウレックス」の契約社員の運転手が、正社員との各種手当の差額分を支払うよう会社に求めた訴訟。小法廷は4月23日に弁論を開く。この訴訟で大阪高裁は16年7月、手当ごとに格差が不合理か検討し、通勤手当など4種類について「正社員だけに支給することは違法だ」として会社側に計77万円の支払いを命じた。(2018.3.8 毎日新聞)近年では最も注目される労働裁判であろう。格差が違法と判断されたなら、画期的な判決であると同時に社会が大混乱に陥ることになる。私的予測ではなんやかやと理由をつけて、合理的格差は合法であり、一部〇〇手当は正規・非正規の別なく一律に支払え。こんな玉虫色の内容になるのではないだろうかと思う。
2018.03.09
-

懲戒解雇は無効(大阪地裁判決)
国立循環器病研究センター(大阪府吹田市)の職員だった50歳代の男性が、妻の病気を理由に異動を拒んで懲戒解雇されたのは不当として、職員としての地位確認などを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は7日、「異動命令は無効で、懲戒権の乱用」として男性を職員と認め、同センターに給与の支払いなどを命じた。判決によると、男性は2016年2月、同センターから大阪府内の他病院に異動を命じられた。男性は妻がうつ状態とし、「夫の職務や勤務先が変わると不安感が強まって生活が成り立たなくなり、異動内示後は死にたいと望むほど悪化している」とする医師の診断書を提出。異動の撤回を求めたが、同センターに認められず懲戒解雇になった。内藤裕之裁判長は判決で、異動先を運営するのは同センターとは別の独立行政法人で、本人の同意のもと、労働契約を締結し直す「転籍出向」にあたると指摘。一方的な異動命令は無効とし、「男性の妻の症状は重く、不当な動機による異動拒否ではない」と述べた。同センターは「主張が認められず遺憾。判決内容を検討して控訴するか決めたい」としている。(2018.3.8 読売新聞)転籍の場合は、本人の同意なしでは難しい。これが単なる異動なら通常甘受すべき範疇ではないかと思う。ちなみに弊社の場合、本ケースは距離的に「転勤」ではなく「転属」と呼んでいる。日常茶飯事のできごとであって、何らの問題もなし。
2018.03.08
-

友愛労働歴史館
出張ついでに久し振りに友愛労働歴史館へ寄ってみた。いつも通り閉店ガラガラ状態。高野房太郎、片山潜、鈴木文治、松岡駒吉、賀川豊彦。そんなもん知らんがな。ってな方が殆どでしょう。運動史の研究家も高齢者ばかり。先人たちの苦労の上に現在の労働環境があるわけですが、なぜ1日の労働時間が8時間になったのか。多くの労働者は知らない。
2018.03.07
-

最近読んだ本(労働基準監督署があなたの会社を狙っている)
紙面の多くが講義形式による行政法関連(行政行為と行政指導の違いなど)の解説で占められている。社労士&行政書士の方には復習テキストとしては良書だと思います。行政法を全く知らない方でも大丈夫。監督官からは???といった声があがりそう。労働基準監督署があなたの会社を狙っている [ 河野順一 ]価格:1080円(税込、送料無料) (2018/3/4時点)
2018.03.04
-

裁量労働制の議論
裁量労働制を全社的に違法に適用し、昨年末に厚生労働省東京労働局から特別指導を受けた不動産大手、野村不動産の50代の男性社員が過労自殺し、労災を認定されていたことがわかった。男性は裁量労働制を違法適用された社員の一人だった。東京労働局は遺族からの労災申請をきっかけに同社の労働実態の調査を始め、異例の特別指導をしていた。労災認定は昨年12月26日付。同労働局は、同じ日に特別指導を公表していた。安倍晋三首相や加藤勝信厚労相は今国会の答弁で、同社への特別指導を裁量労働制の違法適用を取り締まった具体例として取り上げたが、特別指導は過労自殺の労災申請が端緒だった。安倍政権は、裁量労働制の対象拡大を働き方改革関連法案から削除し、来年以降に提出を先送りすることを決めたが、今の制度でも過労死を招く乱用を防げていない実態が露呈した。改めて対象拡大への反発が強まりそうだ。(後略)(2018.3.4 朝日新聞)裁量労働制については、すでに専門業務型&企画業務型が法定されているが、手続きが煩雑で殆ど導入されていない。これをガラガラポンしたのが新生裁量制&高プロ制であり、導入しやすいものにすり替えるのが目的。そして経済界の票獲得が狙い。一部に騙されている方もおられるが、労働者によってのメリットは薄いといえる。
2018.03.04
-

裁量制あきらめ、高プロは?
今国会に提出予定の働き方改革関連法案から、裁量労働制の適用拡大を削除すると、安倍晋三首相が参院予算委員会で正式表明した。安倍首相が1月の衆院予算委で「裁量労働制で働く方の労働時間の長さは、平均的な方に比べれば一般労働者より短い」と答弁したことに端を発した問題である。答弁の基になった厚生労働省の調査は、裁量制労働者と一般労働者で手法の異なる不適切なものだった。安倍首相は答弁を撤回し陳謝する事態に追い込まれ、その後も厚労省調査に数百件もの「異常値」が発見された。こんなずさんな調査を法律の必要性の根拠とすることはできない。関連法案から削除するのは当然である。裁量労働制は、実際の労働時間に関係なく、あらかじめ労使で決められた時間を働いたとみなし、その分だけの賃金を支払う制度だ。厚労省は裁量労働制で働く人の労働時間の実態を再調査し、労働政策審議会で改めて協議してもらう考えだ。これまた当然である。(後略)(2018.3.3 沖縄タイムス)さすがに沖縄タイムスの論調は激しい。昨日、連合大阪「2018春季生活闘争 総決起集会」をのぞいてみたところ、スピーチも裁量労働&高度プロフェッショナル制度への批判が主だった。高プロは、旧ホワイトカラーエグゼンプションの呼び名変更。つまりゾンビ法案。こちらは経済界からの圧力により、ゴリ押しで成立させるのではないでしょうか。追伸:先日、当ブログにて取り上げた私鉄総連「南海電鉄労働組合」の若手がステージで決意表明されていました。やっぱり。
2018.03.03
-

過労自殺裁判(大阪地裁判決)
大阪市内で店舗展開するうどんチェーン「小雀弥(こがらや)」の店長だった男性(当時34歳)が2009年に自殺したのは、 長時間労働によるうつ病が原因だとして、遺族が運営会社側に約8000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、 大阪地裁は1日、自殺と業務との因果関係を認め、約6960万円の支払いを命じた。(2018.3.1 毎日新聞) 遺族は、調理師として働いていた男性の自殺は過労が原因として、労災請求をしたものの、大阪西労基署は不支給を決定。その後、行政訴訟でも大阪地裁は請求棄却。しかしながら、遺族が黒門小雀弥と同社の経営者を訴えた民事訴訟では、一転、大阪地裁は安全配慮義務違反を認めた。行政訴訟と民事訴訟で判断が分かれたケース。
2018.03.01
-

働き方改革関連法案
安倍晋三首相が、今国会に提出する働き方改革関連法案から裁量労働制の対象拡大に関わる部分を削除する方針を表明したことについて、実現を求めていた日本商工会議所、経団連、経済同友会の財界3団体トップからは1日、失望や遺憾の声が相次いだ。(中略)経団連の榊原定征会長は1日、「柔軟で多様な働き方の選択肢を広げる改正として期待していただけに残念に思う。今後、新たな調査をしっかり行い、国民の信頼と理解が得られるよう全力を尽くしていただきたい」との談話を発表した。経済同友会の小林喜光代表幹事は「世界と比して低い生産性の向上が求められる中、今回の事態は極めて遺憾だ」などとするコメントを出した。(2018.3.1 毎日)春闘真っ最中の折、労働組合サイドしては、してやったりといったところか。
2018.03.01
全18件 (18件中 1-18件目)
1
-
-

- 政治について
- 立花党首が齊藤さんを繰り上げた選択…
- (2025-11-23 15:27:00)
-
-
-

- 今日のこと★☆
- - 23. NOVEMBER * Alena Igorevna Le…
- (2025-11-23 15:09:38)
-
-
-
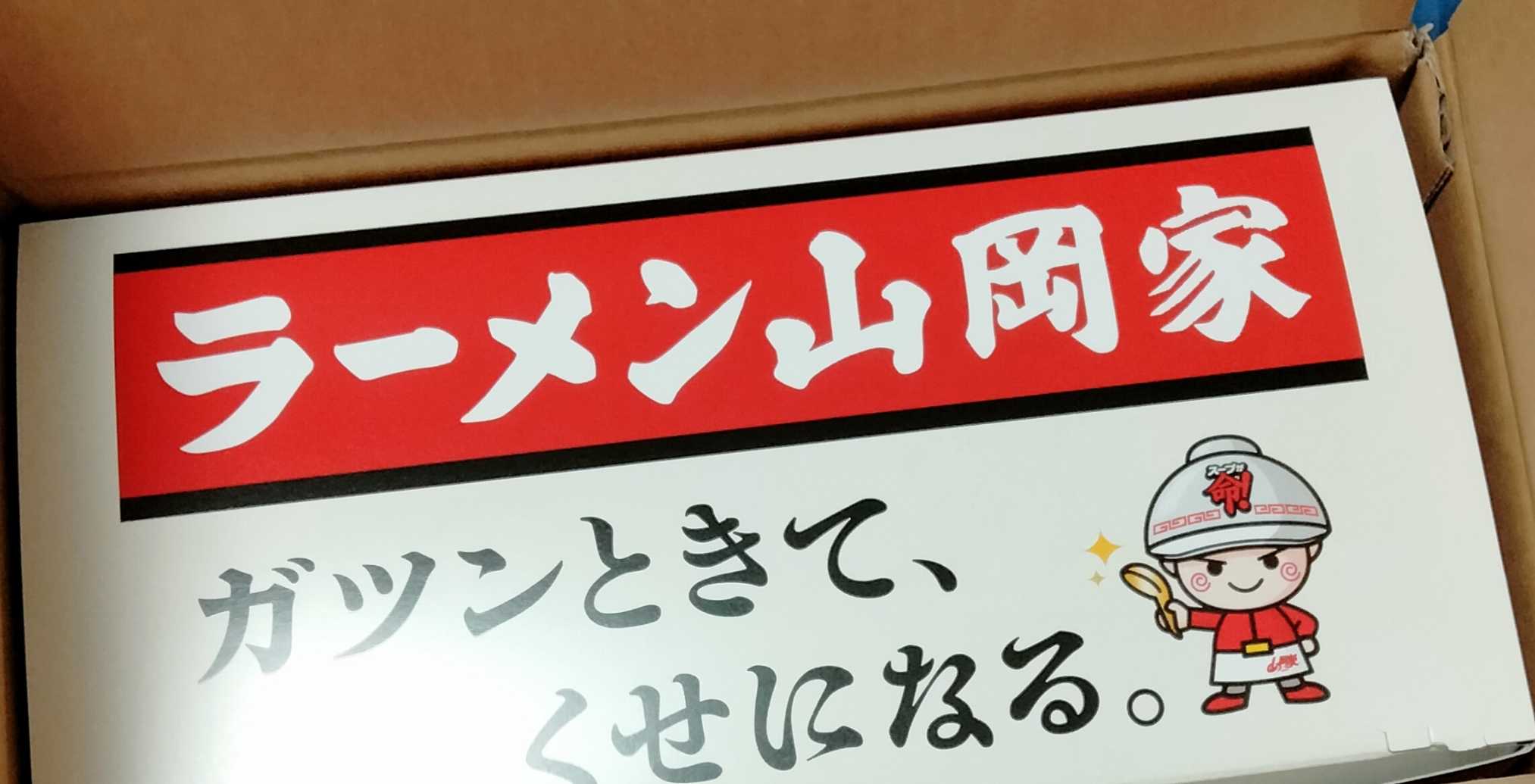
- 株主優待コレクション
- 丸千代山岡家:鍛えなくちゃ~:大関…
- (2025-11-23 15:32:12)
-







