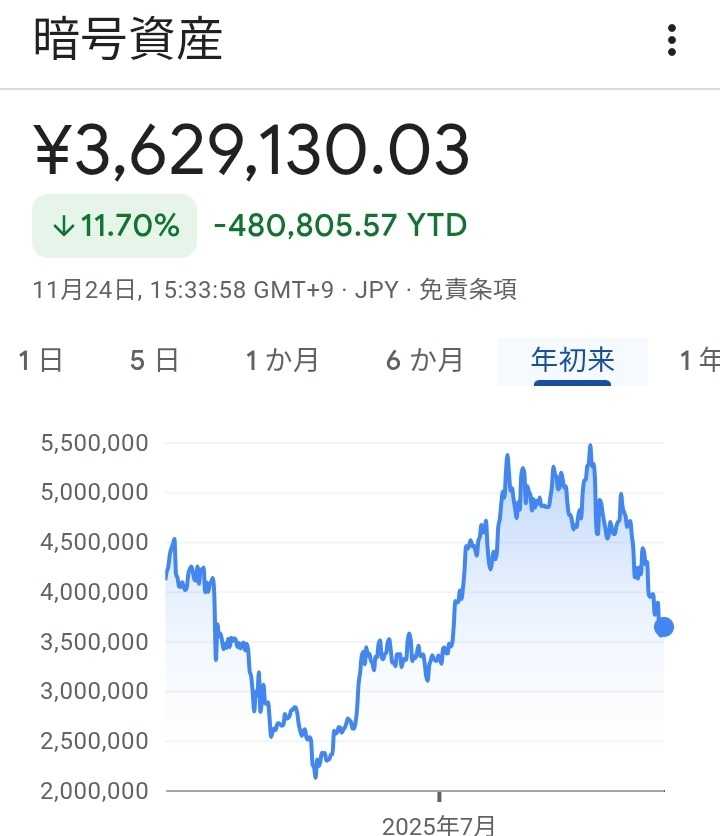2019年06月の記事
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-

浜大津へ
心理学系の講習会で滋賀県へ。終日を屋内で過ごしたので、雨の影響はほぼ無し。JR大津駅で降りたのは20数年ぶりかも知れない。近年、再開発されたのか、きれいな駅前。そして時代に取り残された商店街、そんな風景でした。京都~山科~大津。電車で2駅、僅か10分で、えらい変わりよう。
2019.06.30
-

日弁連会長声明
日弁連が「職場のハラスメントに対する実効性ある法整備を求める会長声明」を公表。“この度のILO条約の採択を契機として、我が国においてもセクシュアルハラスメントについての明文の禁止規定を設けることはもとより、その他のハラスメントについても、その防止と救済に有効な法整備をすることが求められる。”と。賛成
2019.06.28
-

アシックスでパタハラ(東京地裁)
スポーツ用品大手のアシックス(神戸市)の男性社員(38)が育児休業明けに復帰したところ、希望しない部署に配置転換されるなどの「パタニティー(父性)ハラスメント」(パタハラ)を受けたとして、慰謝料440万円などを求める訴訟を28日、東京地裁に起こした。男性の支援団体によると、男性は2011年に入社し、スポーツ用品の販売促進などを担当。その後、人事部に異動し、15年2月から1年余り、18年3月からも約1年間育児休業を取った。最初に職場復帰した後は関連会社に出向し、倉庫で荷下ろしなどに従事した。約3カ月後に本社に戻ったが、現在も希望する営業職には戻れていないという。男性は「男性社員に育休を取らせないようにするための見せしめだと思う。提訴が、子育てしやすい環境を整える一助になれば」と話した。アシックスの話 訴状が届いていないので、コメントは差し控える。カネカに引き続き、アシックスも。事実関係が不明なままで一方的に報道される。会社の言い分もあるだろうが、ここまで大きなニュースになれば、社会的な影響も大きい。就活生にはどう映っただろう、株主総会はどうだ、社員のモティベーションは。そして売上への影響は。従業員満足、エンゲージメントにシフトした経営が求められる。
2019.06.28
-

セクハラで賠償命令(京都地裁)
私立の通信制高校「つくば開成高校京都校」(現京都つくば開成高校、京都市下京区)の校長から勤務中にセクハラ行為を受け精神障害を患ったとして、東海地方の元講師の女性(32)が、当時の校長(66)などに対して慰謝料など約7千万円の支払いを求めた訴訟の判決が28日、京都地裁であった。久留島群一裁判長は、「立場の違いに乗じて性的自由を侵害した」とセクハラ行為を認め、元校長側に約594万円の支払いを命じた。判決によると、2012年4月~同年7月、女性が講師として勤務していた同京都校の校長から、校内で抱きしめられたり、胸を触られたりしたほか、他の通信高校の視察帰りにラブホテルに連れて行かれ同意のない性交渉を強いられた。女性は、うつ病や心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症し、休職。14年には、セクハラ行為に伴う休業が労災認定された。(2019.6.28 京都新聞)校長かいな?形式上は勝訴だろうが、訴額約7,000万円に対して、約600万円では訴訟経済上、割が合わない。費用倒れだと思う。最近、先輩が長年営んでこられた「京都新聞」販売店を廃業された。活字離れ、新聞不況を肌で感じた。
2019.06.28
-

精神疾患労災が過去最多
厚生労働省は28日、仕事が原因でうつ病などの精神疾患にかかり、2018年度に労災申請したのは1820件だったと発表した。1983年度の統計開始以降最多で、6年連続の増加。精神疾患の労災認定は465件だった。うち自殺(未遂含む)が76件あり、いずれも前年度より減少。過重労働が原因の脳・心臓疾患による労災認定は238件で、15件減少した。うち、死亡(過労死)は82人だった。全体の申請数は前年度から計125件増加。特に精神疾患で女性からの申請が99件増えた。担当者は「精神疾患も労災だという認識が高まり、申請増加につながったのではないか」と話した。(2019.6.28 共同通信)精神疾患も個性だとする考え方もある。一説ではLGBTも左利きと同程度の割合だとか。いよいよダイバーシティ・共生社会の到来。これからはこころの時代。
2019.06.28
-

パワハラ相談が最多更新
厚生労働省は26日、2018年度に職場の問題をめぐり全国の地方労働局などに寄せられた相談件数を公表した。パワハラなど「いじめ・嫌がらせ」に関する相談は前年度比14.9%増の8万2797件と、過去最高を更新。厚労省は「社会的な関心が高まっており、労働者が気付いて相談するケースが増えている」とみている。法律の問い合わせや法令違反のケースを除いた全体の相談件数は5.3%増の26万6535件。いじめ・嫌がらせの相談は内容別でトップを占め、「自己都合退職」が5.9%増の4万1258件と続いた。人手不足による転職の増加に加え、パワハラなどで仕事を辞める人も多いという。一方、「解雇」に関する相談は2.0%減の3万2614件だった。リーマン・ショック後の10年度から9年連続で減少が続いている。パワハラをめぐっては、今年度に入り、企業に防止措置を義務付ける改正労働施策総合推進法が成立。国際労働機関(ILO)は職場での暴力とハラスメントを禁止する初の国際条約を採択するなど、防止に向けた機運が高まっている。(2019.6.26 時事通信)人手不足の中、退職代行サービスが花盛り。辞めさせてくれない。怖い?先日、当社の若手からも・・。情けないな~(某HPより)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「辞めたいけど、言い出せない、辞めさせてもらえない」そんな状況にいるのなら、お気軽にご相談ください。〇〇〇〇があなたの退職に必要な連絡を、代行いたします。ご相談を頂いた当日から対応可能です。お客様のお時間に合わせて、休日や深夜でも可能な限り、対応しております。会社への連絡は〇〇〇〇が代行いたしますので、もう上司と話す必要はございません。退職届の提出や貸与品の返却も郵送でOKです。次の職場が肌に合わなくても、ご安心下さい!〇〇〇〇を一度ご利用いただいたお客様は、次回以降、1万円ディスカウントでご利用いただけます。
2019.06.26
-

厚労省が「ハラスメント悩み相談室」を開設
厚生労働省は、民間委託で「ハラスメント悩み相談室」を開設。職場での各種ハラスメントで困っている人からの相談を電話、ホームページ上の相談フォーム、メールで受け付ける。相談は無料で匿名でも可能。メールからは24時間受付。電話相談は、平日12:00〜21:00、土曜・日曜10:00〜17:00。[フリーダイヤル]0120-714-864 https://harasu-soudan.mhlw.go.jp/
2019.06.17
-

ローソンFC加盟が団交申し入れ
埼玉県春日部市内でローソンのフランチャイズチェーン(FC)加盟店を経営する50代の男性が14日、24時間営業の見直しなどを求めて、個人加盟労働組合を通じ本部に団体交渉を申し入れた。ローソンのFC加盟店主が本部に団交を申し入れるのは、2011年以来。本部側は団交には応じず、個別に対応する意向だ。男性側は、時短営業の容認、チャージ(経営指導料)の見直し、アルバイト人件費の支援、契約内容の口外を禁じる契約条項の削除―の4点について、協議に応じるよう要請。本部側は、今年3月に中央労働委員会がFC加盟店主を労働組合法上の労働者と認めない判断をしたことを理由に、これを拒否した。東京都内で記者会見した男性は、低収入を補うため自身は月400時間、妻は夜間に月250時間勤務しているなどと説明。「これだけ働いても成り立たないのがコンビニの現状だ」と訴えた。ローソンは「これまでの状況を確認し、今後オーナーと真摯(しんし)に協議して対応していく」としている。(2019.6.14 毎日新聞)本部として、まともな対応だと思う。フランチャイズチェーンビジネスは、本部と加盟店の信頼関係の構築、これにに尽きる。
2019.06.14
-

ハラスメントを全面禁止(ILO)
フランスのマクロン大統領は11日、スイス・ジュネーブで開催中の国際労働機関(ILO)年次総会で演説し、職場でのセクハラやパワハラなどハラスメントを禁止した条約案について「素晴らしい内容だ」と述べ、全面的な支持を表明した。一方、日本代表は10日の委員会で、制定の議論に積極的に加わると表明しつつも、条約案を支持するかどうかは「まだ明確にしなければならない点がある」と指摘、慎重な姿勢を崩さなかった。ILOは今回の総会で、ハラスメント対策として初の国際基準となる条約案の採択を目指している。(2019.6.12 共同通信)国内法の整備がどうのこうの。いつもの決まり文句ね。どんどん世界に置き去りにされるぞ。
2019.06.12
-

朝日新聞が不当労働行為(東京都労働委員会)
朝日新聞社の一部の従業員が加入する新たな労働組合に、掲示板使用などの便宜供与を認めるかが問われた審査で、東京都労働委員会は10日、団体交渉に誠実に対応するよう同社に命じた。具体的な理由を説明せずに便宜供与を拒否したことが不当労働行為にあたると判断した。都労委によると、朝日新聞社の従業員数人は、新たに労働組合「東京管理職ユニオン」の支部を昨年1月につくり、会社に対して、既存の労組と同様に会議室や掲示板を利用させることなどを求めた。会社側は、組合との間に信頼関係がいまだ存在しないなどとして応じず、組合が都労委に救済を申し立てていた。都労委は朝日新聞社の対応について、組合の理解を得ようとする努力などを欠いており、不誠実な団体交渉にあたると判断。また、合理的な理由を示さずに要求を拒んだことは支配介入にあたるとも指摘したが、便宜供与については今後、労使の団体交渉で解決するべきだとした。朝日新聞社広報部は「命令書の内容を精査し、今後の対応を検討します」とのコメントを出した。(2019.6.10 朝日新聞)さすが朝日新聞。自社に関する内容も堂々と報道している。よし。
2019.06.10
-

職場のハイヒール強制について
民間企業などで、足に負担のかかるハイヒールやパンプスを履くことを女性に事実上強制している職場があることについて、根本匠厚生労働相は5日の衆院厚労委員会で「業務上必要かつ相当な範囲」と述べ、容認する姿勢を示した。ネット上では、職場でのハイヒールなどの着用強制に反対する声が広がり、3日には厚労省に約1万8800人の署名が提出されている。立憲民主党の尾辻かな子氏が着用義務づけの必要性をただしたのに対し、根本氏は「女性にハイヒールやパンプスの着用を指示する、義務づける。これは社会通念に照らして業務上必要かつ相当な範囲かと、このへんなんだろうと思う」と述べた。一方で、「けがした労働者に必要もなく着用を強制する場合などはパワーハラスメントに該当しうる」とも述べた。高階恵美子厚労副大臣は「強制されるものではない」と答弁した。職場でのハイヒールの着用をめぐっては、俳優の石川優実さん(32)が3日、「強制反対」に賛同する署名を厚労省に提出。飲食店やホテルなどで接客を担当する人が着用を強制されている場合が多いといい、強制を禁止する通達を企業に出すよう求めている。(2019.6.5 朝日新聞)業種業界によるのではないか?例えば、シティホテルのフロント業務でスニーカーは如何なものか。ビジネスホテルならOKか。こんな議論だろうと思う。制服着用はあってもこと細かに就業規則には記載しない。内規で定められているのなら、基本的に従うべきではないだろうか。で、外反母趾等の事由があればオプトアウト。
2019.06.05
全11件 (11件中 1-11件目)
1