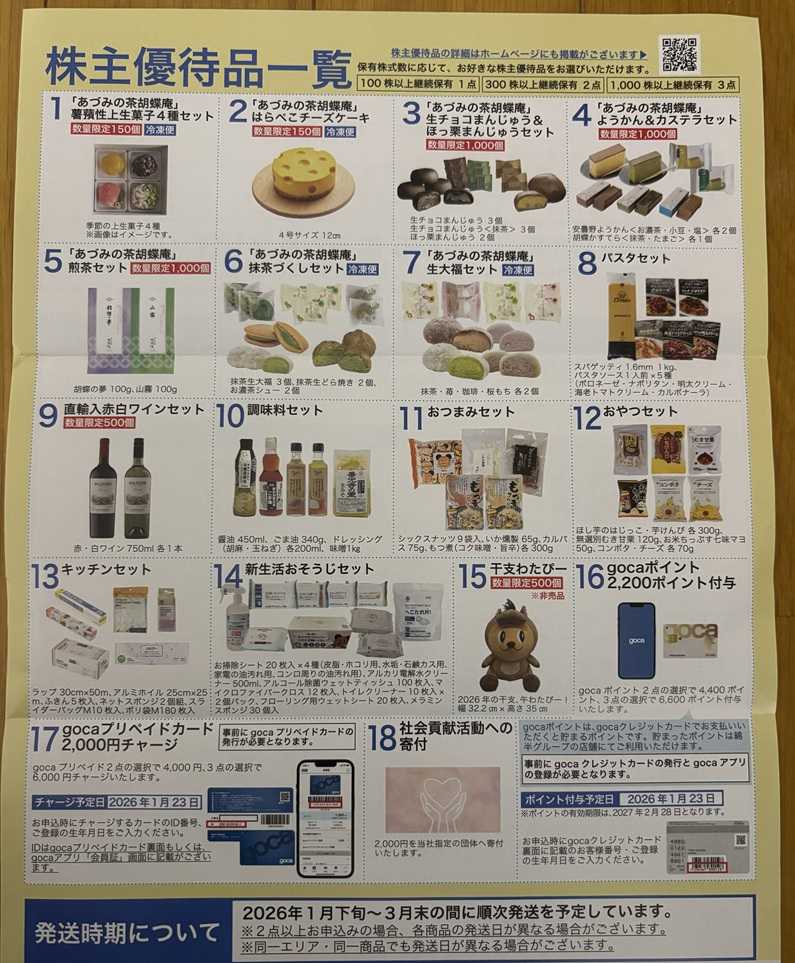2006年12月の記事
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-

農的幸福論
藤本敏夫さんは歌手の加藤登紀子氏のご主人で、2002年に亡くなりました。 その藤本さんの生前の原稿を本にしたものを読みました。 ”農的幸福論 藤本敏夫からの遺言”(2002年12月 家の光協会刊 加藤 登紀子編)です。 共感できることが多い内容です。 次のように言っています。 ”地球社会の性格に変化を与えはじめている。現に炭酸ガスの増大によって地表の温度が上がっているという報告が出されている。なぜなら、炭酸ガスは幅射熱の吸収量が大きく、大気中に炭酸ガスが増えれば増えるほど気温がだんだん上がってくることは事実なのだ。炭酸ガスがいまの二倍に増えれば気温は3度以上上昇するといわれている。二度も大気中の気温がちがうということはたいへんなことである。人間は空気を破壊しているだけではないじ人間は生物の母、海をも急激に破壊している。毎日、河川をとおして工場廃液は海に流れ込み、廃油や重油は海面になんのちゅうちょもせず廃棄される。海が地球上の70%を占め、大気の64倍の容量を持っているから、その天然の浄化作用はまだびくともしないとはいえ、局部的な汚染の集中はその海域の水中生物を死滅させ、汚物はヘドロとなって底に蓄積され、プランクトンも住まない死の海と化するのである。 その海はなんの生命の交流をも許さない地球社会のガン病巣である。人間は地球の交流パイプを切断している。空気、水の汚染はその主要なパイプなのであり、緑の迫害の中にその生命のパートナーを失っている。生命のコミュニケーションを失った地球社会は、それゆえに各種の社会の絶滅を招きつつあるといえよう。生命を絶たれた肉体は各所で腐敗しはじめた。人間社会も遅かれ、その運命に見舞われるのであろう。” そして、人間は万物に謝らねばならないと言います。 ”人間は他の生物とちがって、自分の体を変えることなく、自分の体とは別に道貝や機械を作って進んできた。だから、人間は自分のやっていることがどのようなものなのかということが、ほんとうはよくわからない。そしてある日、突然気づいたとき、自分のやってきたことに自分自身が耐えられなくなっているということになる。人間には空気や、水のいたみはわからないし、他の動物や植物たちの不満はわからないのだから、救われるまでは、人間がどこまで地球社会の一員として自分たちの立場を理解するかにかかっている。いまや、もう手遅れかもわからないと思う人もいるかもしれない。 恐竜やマンモスが、みずからの繁栄の中にみずからの滅亡を準備したように、人間もまったくそのとおりなのかもしれない。恐竜やマンモスは、自分が何をやっているのかを死にたえるときでもわからなかった。人間もいま、自分が何をやっているのかがわからないのである。頭脳活動という他の生物にはない機能をもちながら、そして、その機能を生みだしてくるとき、自分と自然の関係を率直に見つめ、狩猟のあと、馬の軽やかな走りざまや、魚の自由自在の泳ぎつぶりや、草花の清らかな可愛いさや、海の大きさ、空の清潔さに思いを馳せて、生命というものにうたれた、その気分を忘れ去っているのである。地球の破壊を人間は中止せねばならない。空気の汚染、水の汚れ、緑の迫害、土の死、万物が友であり、万物が命をともにするものである。人間は空気や水や緑や土や、そして数多くの動物たちに謝ろう。私たちは地球社会の代表選手なのだから、地球社会全体の祝福を受けて、協力を受けて、この生命を燃焼させねばならない。”
2006.12.30
コメント(0)
-

箱根は雨のち晴れ
26日~27日箱根に行ってきました。箱根町港から海賊船に乗りました。 26日は大雨、27日は晴天でした。
2006.12.28
コメント(0)
-

食ビジネス7つの秘訣
いざなぎ景気超えといわれますが、地方企業と中小企業、特に小規模企業は苦境に陥ったままです。 商店街では、今後5年間に95%の個人商店がやめていくか破産するとまで言われている、そうです。 しかし、こうした不況、企業倒産時代の中にあっても、元気に売上、業績を伸ばしている企業があります。 廃業の危機にさらされながらも業績を回復し、新たな時代の価値観を生み出している企業もあります。 ”食ビジネス7つの秘訣”(2005年7月 誠文堂新光社刊 矢崎 栄司著)を読みました。 不況の中でがんばっているスモール食ビジネスを紹介しています。 食は人が生きていくために最も大切なもので、不況に強いといわれていましたが、ここにも不況の影響が押し寄せています。 日本の食ビジネスは、いま、大きな転換期にさしかかっており、農業人口の減少、耕作放素地の急増、中山間農地・山林の荒廃、中小小売店の激減、大企業の農業進出等があり、食ビジネスも企業論理、市場原理の方向へ進んでいます。 そこで、食ビジネスの原点に立ち帰り、食に対する新たな価値を創造してがんばっているスモール食ビジネスのノウハウに注目が集まっています。 秘訣とは、・個に対応する品質重視の時代・消費者に学べ、自らも消費者と知れ・私たちの商品のヘビーユーザーは誰か?・反常識から発想せよ・情報・文化 逆流の時代・まずはコミュニティありき・キーワードは自分の言葉です。地方発産地で元気にがんばる食ビジネス、新規就農希望者の受け皿になる外食が有機野菜生産・卸に進出、都会発大手を駆逐する食ビジネスパワーの源、ネット通販が恐竜化したカタログ型通販を駆逐する事例が紹介されています。
2006.12.23
コメント(0)
-

青梗菜
ちんげんさいです、青軸、パクチョイなどと呼ばれていたそうです。 広まったのは1970年頃からとか。
2006.12.21
コメント(0)
-

非道の大陸
アメリカも分け入るとこのようなものなのでしょうか。 アメリカを非道というのは、アメリカが巨大で不可解な存在であるからでしょうか。 ”アメリカー非道の大陸”(2006年11月 青土社刊 多和田 葉子著)を拾い読みしました。 あまりよい読み方ではないかもしれません・・・。 これは、旅する作家が切りひらく新世界アメリカの物語のようです。 著者の多和田葉子さんは、日本語とドイツ語両方で作品を書いているドイツ・ハンブルク在住の作家です。 1960年、東京都中野区生まれ、立川高校時代から第2外国語としてドイツ語を習い始め、早大ロシア文学科卒業後、1982にドイツのハンブルク市にあるドイツ語本輸出取次ぎ会社に研修社員として就職し、現在に至るまで中断なくハンブルク市に在住しています。 1987年に、ドイツの出版社から初めて二か国語の詩集を出し、その後ドイツ語で短編小説を書いています。 ハンブルク大学の修士課程を修了し、ハンブルク市文学奨励賞を受賞しました。 日本でも、群像新人賞、芥川賞受賞を受賞しました。 2000年に、チューリッヒ大学博士号を取得し、文学博士になりました。 そして、泉鏡花賞受賞受賞、Bunkamuraドュマゴ文学賞受賞、谷崎潤一郎賞受賞、ゲーテ・メダルなど、創作と学問の世界でいまもっとも輝いている人の1人でしょう。 非道の大陸では、主人公のあなたが、自動車で砂まみれになりながらアメリカ各地を旅して、出会った人々、目にした出来事などが綴られています。 スラムポエットリー、鳥瞰図、免許証、フロントガラス、きつねの森、マナティ、練習帳、水の道、馬車、メインストリート、とげと砂の道、無灯運転・・・。 それぞれが1つ1つの短編であり、同時に全体を構成しています。 拾い読みですが、不思議な感じの残る小説です。
2006.12.16
コメント(0)
-

さむくなりましたが元気です
さむくなりましたが元気です。 いろいろ収穫がありました。
2006.12.14
コメント(0)
-

食の安全・安心
地球の人口は現在60億人ですが、そう遠くない将来に90億人になる予測が出ています。 現在でも地球上には飢えに苦しんでいる人がたくさんいるのに、あらたに30億人も養う食料をどう確保するのでしょうか。 以前から懸念していたことです。 ”現代の食とアグリビジネス”(2004年5月 有斐閣刊 大塚 茂・松原 豊彦編著)を読みました。 現代の食と農をめぐる情勢を身近な食の現状から食料システムの全体像を解明しようとしています。 これまでにわたしたちの食生活は大きく変貌し、それと連動してフードビジネスが進展してきました。 これからも人口爆発に伴って、食の事情も大きく変化していくと思われます。 食料の増産という観点から、農業・食料の工業化とグローバル化の進展は必然の動きです。 また、遺伝子組換え作物などの出現もこの食の問題への対処法の1つではないでしょうか。 農業・食料の工業化とグローバル化が進む中で,遺伝子組換え作物など食の安心・安全の問題が出ています。 遺伝子組み換えなど、自然の摂理を変化させるとなんらかの反動があるのではないかという気もします。 BSE感染牛、鳥インフルエンザ、輸入冷凍野菜の残留農薬、食品の不当表示、遺伝子組み換え食品などなど。 食の安心・安全は本当に大丈夫でしょうか。
2006.12.09
コメント(0)
-

エンドウを植えました
エンドウを植えました。 芽が出てきました。
2006.12.07
コメント(0)
-

相即相入
この世になぜ戦争が絶えないのかというと、人間は闘争がないと生きてゆけぬように出来ているからであるといいます。 本当でしょうか? ”禅百題”(1991年 春秋社刊 鈴木 大拙著)を読んでいる途中です。 平易な文章で書かれた随感随録の書ですが、1つ1つのテーマが考えさせられるものですので、ゆっくり読んでいます。 鈴木大拙氏は明治3年石川県金沢市本多町に生まれ、石川県専門学校時代に西田幾多郎氏と出会い、生涯の友となったといわれています。 中途退学し一時英語教師となりましたが、上京して東京専門学校、東京帝国大学に学び、本格的に坐禅に取り組み始めたとのことです。 明治30年に渡米し、足掛け12年間を過ごしました。 帰国後、日本と欧米を行き来しつつ、仏教の研究と普及に精力を注いだそうです。 「相即相入」には次のようにあります。 ”実際、闘争そのものが生であり、生そのものが闘争である。それ故、生のあるところには必ず闘争があるのである。” 世界の戦争と平和を考えると、平和の時代はなかったか、あってもごくわずかでした。 「這箇(しゃこ)」には次のようにあります。 ”人間は居るところが違うと、なかなかに相互の理解がつかぬものである。” 同じ平面上の人でも、空間をいくつかに分割して、その一部分一部分に立つと、どうも喧嘩が出来てしようがないそうです。 しかも人間は二人になると、同時に同じ空間を填充していられないので、闘争は人間界のつきものだ、といいます。 皆様はどう思われますか? 空間的存在として、空間的論理の領域を出られないかぎり、人間はお互いを食べ合って食べ尽くすよりほかない運命をもっている、といいます。 ではどうすればよいのでしょうか? ”時間でも空間でも、何かの工合で、その間に何かの差異を生ずることがあると、相互の了解が不可能にもなろう。” ”が、また何かの工合でお互いに競い合うことがなくなるかもしれぬ。” ”我も人も、彼も此も、山河大地も、花紅柳緑をもみな容れて、しかも自分はその中に収められぬ自主自由の絶対の一句子がないといけない。” 這箇とは「民」のことのようです。 相いれないものをいれて、なお余りあるところの思想によって、矛盾や衝突はあるにはあるが解消のできぬものではない、とのこと。 矛盾そのものが解消だからである、なるほど。
2006.12.02
コメント(0)
全9件 (9件中 1-9件目)
1