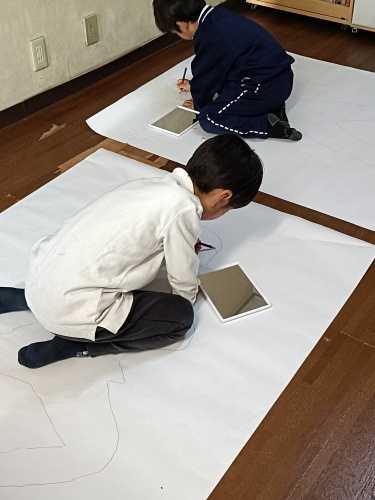2007年05月の記事
全19件 (19件中 1-19件目)
1
-
ステキな友だちも、その子もほめる!
今日の日記はもう書いたのですが、たまっていたメールをどんどん読んでいたら、『親力診断テスト』での「子どもへの言い方の例」でとてもうまいものがあったので、紹介します。以下、メールマガジン「親力で決まる子供の将来 」No844(2007/5/17発行)より引用。================================== ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※わが子の友達がすごく行儀がよかったのを見て、あなたはわが子に何と言いますか? 親力診断テスト※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※わが子の友達が遊びに来ました。その子は玄関で脱いだ靴をきちんと整頓し、「おじゃまします」としっかり挨拶し、おやつを出したら「おいしそう!ありがとう」と言いました。さて、その子が帰った後、あなたはなんと言いそうですか? A:あなたは、あんなにしっかりやらなくてもいいからねB:あなたも、よその家に行ったときしっかりやってねC:さすがに、あなたはいい友達を持っているね 親力診断http://education.mag2.com/oya/=====================================正解の言葉だけこんなに目立たせてしまったので、診断を受けるドキドキ感が無いですが、多分このサイトを見に来られるぐらいの教育に関心の高い方なら、わざわざ目立たせなくてもすぐ正解が分かったと思います。ただ、この言い方、とっさのときに、なかなかここまでうまく、本人も友だちもほめるような言い方はできませんって。(^^;)テストのページへのリンクは、 もうだいぶ前のメールでのリンクなので、 そろそろ次の問題に更新されてしまっているかもしれません。
2007.05.29
コメント(0)
-

『地球大予測(2)オーケストラ指揮法』★★★★★
『地球大予測(2)オーケストラ指揮法』(高木善之、総合法令出版、1996、1650円)オススメ度 ★★★★★コレはすごい本です。あまりにすごすぎて、ずっとこのブログで紹介しようと思っていたのに、紹介しきれずにいました。詳しくは読んでください。「指揮者」(のような指導者的立場)にあこがれるかた、「誰のためにもなる解決」を求めておられる方、高木善之さんの考え方にひかれる方は、ぜひ。10年前の本のため、今では少し手に入りにくいかも。 ・・・これだけでは内容がさっぱりわからないので、いちおう具体的な引用をまじえて紹介します。 この本には私は付箋を4箇所貼ったのですが、そのラストの付箋を貼ったページを、引用します。(p315)なお、ほかに付箋を貼ったところは、とってもいいことが書いてあるのですが、内容が深く、引用すると長くなりすぎるので、紹介できません。=================================自分ができるのは、気付くチャンスを作ること。気付くチャンスを作るにはどうすればいいか。事実を伝えること。具体的提言をすること。そして、気付く邪魔をしないこと。(略) よく聞くこと。共に考えること。気付くまで待つこと。本当の幸せには対立は無い。================================ ここだけ読んでも、かなり抽象的にまとめて書いてあるので、感動は無いかもしれません。感動は、本の中の具体的なエピソードにあります。実際に読んだ方のコメントをネットで検索されると、そのあたりのことは少しはわかるかもしれません。なお、「ネットワーク地球村」(高木さんが代表をしている)の公式サイトに行くと、さすがにうまくこの本の特色をまとめてあります。================================== 指揮者だった著者(高木さん)の指揮者としての体験も たっぷり書かれていて、「ああ、プロとはそういうものか!」と まさに驚き(ショックと感動)です。 しかしそれ以上に、人間関係の非常に重要なポイントを教えてくれます。 オーケストラというプロ集団、個性の強い人々(音楽家、演奏者)がどのように心を合わせ、 本気で力を発揮するのか、人間関係について多くの気付きが書かれています。 命令や理屈では人を本当にはまとめることはできない。 そこに究極の人間関係があります。 人と人とのつながり、その根底にあるのは何か。 それは・・・それはこの本を読んでください。 夫婦、子育てなどの家庭の人間関係、職場の同僚や上下の人間関係、 そうした問題に悩む方、あるいは人の上に立つ人には「必読の書」だと思います。 この本は経営セミナーでもよく紹介され、経営者によく読まれていますが、 誰にでも役立ちます。これまでの価値観が覆されるような意識転換が起こります。 まさに「目からウロコ」という本です。ぜひお読みください。引用元: http://www.chikyumura.org/book/okesutora.php====================================================アマゾンでは、8件の読んだ人のレビューが寄せられ、その全てが最高点(5つ星)です。しかも、中身を少し見ることができます。(楽天からアマゾンへのリンクはできないらしいので、 検索を使う等して行ってみて下さい。 「オーケストラ指揮法」で検索すると、この本の情報がけっこうヒットします。) web拍手を送る
2007.05.29
コメント(0)
-

『「頭がいい」とは、文脈力である。』★★★★★
★読書メモ『「頭がいい」とは、文脈力である。』(斎藤孝、角川書店、2004、1200円) ★★★★★ 5つ星!!こういった言い切りがきもちいい。おすすめの一冊です。以下、本を読んで線を引いたところから部分抜粋=======================================・鍛えれば身につく「場を読む力」(鍛えれば身につくということは、だれでも身につくということ。 生まれつきだとか、今からじゃしょうがない、とあきらめてしまうことは ないという意味で、非常に励まされる考え方です。)・意味をつかまえたときのすっきり冴え渡った感覚が 幸福感につながります。・物事の関係を縦横から捉えることができるということ・関連性までもきっちり把握できているということ・ 「頭がいい」というのは状態のことであって、 誰でも、何歳からでも変えられるのです。・ 自他関係ばかりでなく、「他他関係」にまで気を配れる人は、 かなり文脈力に富んでいます。・受け取り手の頭の中で起こることを計算 ・ 関係の中で新しいものを生み出していけるような力。 そういう力を「頭がいい」と見なしたい。・アイデアを生むというのは、 今までつながっていないものをつなげること 網ができていくイメージ ・相手はつねに意味のあることを言っている という確信。 それが重要なのです。・元に戻る、違うところにつなげる、 それができることが文脈力の基本・ピンボケをはっきり「指摘」する。・その質問の脈絡を問う。・具体と抽象を往復できる力 =「たとえば」と「つまり」の効果的な使い方・ カオスとコスモス ~混沌と秩序を往復するような運動がおもしろい ↑ ↓・あんまりまっすぐつながっていたらおもしろくない・ある現実からどれだけの意味を引き出す技術を持っているかによって、 幸福度は変わる。・(サッカーで)いろいろ考えすぎのプレイが増えている。 → もっと シンプルにプレイしよう・物理や数学の世界では、シンプルにすることができる人ほど 頭がいいと見なされています。 ・頭を鍛えることは、一種のスポーツ・十の力でやらなければつづかないようなことを、 からだを使って延々とやることで突き抜けていく・自分のからだを関わらせていくこと、 踏み込んでいくことで、 現実を質感あるものとして捉えることができるようになる。・(テンションを上げる導入のグループワーク) 最初にいきなり拍手とハイタッチ(1)スタートを合図に、 グループになった4人全員が立ち上がって拍手をする。(2)発言者が声を出しながら、 他の3人とパンパンパンとハイタッチをする。 ・本来、学校とは、 「頭がいい」状態を何度も経験させ、 それを技化させ、 そこに一生を通じて幸福感を感じられるようにしてあげる、 そういう場所だと私は考えています。 =======================================学校の教師としても、これからもっと成長していきたい一個人としても、非常に納得でき、参考にしていきたいことが山盛りつまった1冊でした。 なお、最後にp184より、もっとも印象に残った一段落を引用します。(読みやすいよう改行しています)====================================== 視点を自在に移動できると、自分への囚われというものが少なくなっていきます。 しくじったって、たいしたことないや、とか、これがダメでもこんなふうにすればいい、と思えるようになる。 これは自己肯定にもなりますが、他人を認めることでもあり、社会という枠組みの中で生きやすくなることでもあります。======================================= ここまで読んでくださって、ありがとうございました。 この読書メモが、あなたにも参考になるものであれば幸いです。 web拍手を送る
2007.05.28
コメント(0)
-
土日の出来事
修学旅行引率から2時間遅れで帰ってきた翌日、土日と今度は合唱団の合宿。泊まった後総会を朝だけで失礼して吹奏楽イベント「自由演奏会in KOBE」へ。地元の小学生と一緒に吹奏楽の演奏をするのはとっても楽しい♪(うちの学校にも金管バンドクラブがあればいいのにな~)なお、僕のパートは打楽器です♪打楽器は太鼓もシンバルも、鳴らすだけでもとっても快感です(^0^)大学時代の演奏を思い出しながら、鳴らしまくってきました。 この会場での「自由演奏会」は3回目の参加でしたが、今回は前よりも演奏曲目がガラリと変わっていました。一番気に入ったのは、合唱で有名な「怪獣のバラード」合唱で参加しましたが、圧倒的な吹奏楽の音量に音がかきけされる(>。<)ポップでナイスな往年の名曲です。 その後は帰宅して明日の校内委員会の準備・・・のはずが、夕食を食べに行って、おいてあったマンガを読んでかなり時間をつぶしていたりして・・・(ふむふむ、横の体重移動(シフトウエイト)をすばやくおこなうには、 足の親指の強化が有効なのだな・・・~『はじめの一歩』より)校内委員会の準備は帰ってからちゃんとやりました。短時間ですが。 そんなこんなでイロイロあったイベント尽くしの日々が終わり、また明日からいつもどおりの日々です。(とはいえ、水曜には5年生の「田植え」引率でまた出るのですが・・・。)
2007.05.27
コメント(0)
-
修学旅行へ~行き先は、岐阜・愛知
明日から修学旅行。引率で、岐阜県、愛知県と行ってきます。岐阜も愛知もちゃんと行ったことはないので、修学旅行引率で初めて行くことになります。子ども用の「しおり」を見ると、「行く前にしっかり下調べをして行くように」と書いてあるので、調べてみました。・瑞浪(みずなみ)化石博物館 「瑞浪市からは、今から2000万~1500万年前の新生代の化石が たくさん見つかります。」 博物館はちょっとしかのぞかずに、すぐに昼食になりそうです。 ・土岐川の河原で化石採集 「ここから見つかる化石は、 今から1700万年前(新生代第三紀中新世)の貝・植物などの化石です。」 はたして化石のおみやげがとれるでしょうか。 化石採集はやったことがないので、全くさっぱりわかりません。・美濃和紙の里 たまーに総合的な学習の授業で和紙作りをやっている学校があります。 きれいに作るのには細心の注意がいるような気がします。・うだつの上がる町並み 『「うだつ」とは、 屋根の両端を一段高くして火災の類焼を防ぐために造られた 防火壁のこと』 うだつを上げてきます。ええ、上げてきますとも。・ 鵜飼い 「鵜(ウ)を使ってアユを獲る伝統的な漁法のひとつ。 岐阜県、愛知県、京都府などで行われているが、 特に長良川での鵜飼いが最も有名である。」 『鵜が口にした魚は噛まずに丸呑みにするため、 人の言葉の真偽などをよく考えずそのまま相手の言葉を信じ込んでしまう という意の「鵜呑みにする」という言葉の起源ともなった。』・和船造船所 1日目は非常にたくさんの見学をします。消化不良にならないかな。。。2日目には・明治村に行きます。 SLが村内を走っているそうで、それに乗るのが楽しみです。(乗るのか?) ちなみに私は「古きよき時代」は好きですが、一番好きなのは大正時代です。「大正村」って、あるの・・・?(^^;)
2007.05.23
コメント(4)
-

DS学習ソフトで楽しく知力アップだ!(^^)
DSの学習ソフトでよさそうなものを調べてみました。ニンテンドーDSとは何か?タッチペンで実際に画面に書き込むことができるというインターフェイス(入力操作)のおかげで、学習面でもかなり期待できるゲーム機です。(このブログでも過去に何度かとりあげました。)最近では、なんと実際に学校で試して効果があったとかで、授業中にさせている学校もあるのだとか。◆ ゲーム機で語彙力4割アップ 京都・八幡 ↑上のリンク先の毎日新聞サイトによると、「(京都府八幡市)市教委は、国の支援を受けてゲーム機600台を購入。 今年度、全中学2年生の英単語学習に導入することにした。」らしいです。おうっ! おそるべし ニンテンドーDS!!そんなわけで、ひさびさに、おすすめの学習ソフト紹介。いってみよう!!DS陰山メソッド電脳反復 ます×ます百ます計算 定価 2,800円これは以前から知っていましたが、「百マス計算しかできないのか」と思っていました。調べなおすと、●十ます→三十ます→五十ます→百ますと段階的にレベルアップ。らしいです。「10マス計算」があるなら、かなり初歩の段階から使えます。また、マス計算以外に●「フラッシュ計算」や「エレベーター計算」、 パズル感覚の「虫食い算」、暗算力をUPする筆算もあるということで、いろいろな形態で「かず」に関する学習を進められそうです。●1年生レベルの「数の認識」から4年生レベルの「わり算の筆算」まで。 「今日の課題」では19段階のレベルを無理なくステップアップ。 とのこと。これは買ってみても、いいかも!?(^0^) アンパンマンとあそぼ あいうえお教室4410円[税込]豊富な画面写真が入った紹介記事~「ファミ通ドットコム」もっと幼児向けの学習ソフトでよさそうだと思ったのはコレ。フルボイス仕様なので、文字が読めないお子様にも適しているそうです。・全部で15種類の知育ゲームを収録。 5つのテーマランドに3つの知育があり、 DSの機能を活かした読み書き練習や子供の大好きなぬりえや 演奏などの遊びも盛りだくさん。とのことで、一度試してみたい逸品です。(^^)・ 玩具メーカーであるアガツマのロングセラー商品である 「あいうえお教室」をゲーム内で再現!とのことで、期待がもてます。 さて、上の2本のソフトは私は(まだ)買っていないソフトですが、私が持っている中で、「子ども向け」としておすすめのものを最後に紹介。最近Wii版がよく宣伝されています、コレです! やわらかあたま塾 メーカー希望小売価格2,800円 (税込) メーカー公式サイト 内容はかなりの初級からかなりの上級まで選ぶことができ、かなりの範囲の「やわらかあたま」をカバーする問題バリエーションがあります。また、ドラッグしてポン!とかの直感操作でできるものが多く、子どもから大人まで楽しめます。難点を言えば、ゲームを始める前のメッセージが大人向けで漢字を使った長いメッセージなので、小学校低学年ぐらいの人は、メッセージはどんどんとばしてゲームをしなければならないことです。(^^;)
2007.05.22
コメント(0)
-

ネットで学校で歌う合唱曲をサーチ!
最近、小中学生が歌う合唱の曲をまた調べていて、よさそうなものをネット注文でCD購入!というのが続いています。今日も1つ届きました。今聴いています。今日届いたCDのおめあては中山真理さん作詞・作曲の『Smile Again(スマイル アゲイン)』この方の『おそすぎないうちに』という詞と曲が大好きなのですが、この『Smile Again』もすてきです。ただ、メッセージを語るように歌う歌い方のほうが合っている気がするので、合唱できれいに響かせるより、ひとりでも「語るように」心を込めて歌ったほうがいいかもしれません。この前に届いたCDのおめあては『Song is my soul』(高橋 浩美 作詞・作曲)。その前は『サッカーによせて』(谷川俊太郎 詩・木下牧子 曲)今メーカー確認しているのは『さよならは言わないで』(三浦真理 作詞・作曲)を含むCDです。インターネットだと、合唱そのものは聴けなくても、メロディや伴奏を聴いたり、歌詞を読むことはできるので、とっても便利ですねえ。ところで、インターネット上でもっとも学校で歌う合唱曲をリスト化しており、データだけでなく、実際に音楽データとつなげてあって聴いて確かめることができるのはたぶんここです。↓◆X‘s amusement campushttp://kai.2.pro.tok2.com/entrance.html リスト表示がとても見やすく整理されていて、知らない曲もいろいろ聴いていきたくなります。 音色は、メロディーの音がはっきり聴こえるように設定されています。専用MIDI音源(無料のものもあり)を用意されて、よい音質でお楽しみください。なお、ここ以外に◆『Mr.J‘s Room』◆いまげのMIDIおもちゃ箱も調べるなら、ほぼすべての学校で歌う合唱曲は聴くことができるはずです。上の2サイトは、MIDI(音楽データ)の演奏表現に力を入れており、非常に感動的な演奏を聴くことができます。 あなたも、ぜひ♪ ところで、Web拍手というのをはじめました。押されると、私が喜ぶので、ぜひ押してください。(^^)↓ web拍手を送る
2007.05.21
コメント(2)
-
鼻と口の奥の空間を鳴らす~共鳴発声法
土曜日はひさびさの合唱練習に行ってきました。声楽の先生に、曲をする前の発声練習を指導してもらいました。そこでの気づきをメモしておきます。いい声の出し方ですが、口の奥、鼻の奥に、見えないですが空間があります。そこを開く、声の道を通す、というのが大事になります。そこで、普段はあまり意識しない舌の位置、これを意識してみましょう。舌がのどをふさいでしまわないよう、「あー、いー、うー、えー、おーーーー」このとき、舌を下の前歯にくっつけて、 舌が動かないようにしましょう。(母音の発声では、舌を動かす必要はありません。)口の中の空間を広くしようと思ったら、できるだけ「うー」の口で発声するといいです。 声の出し方なんて、普段全然気にしてませんが、それだと、いいときと悪いときのちがいがなんとなくでしかわからず、科学的に「いい声の出し方」を再現することができません。こういう、発声のコツをしっかりと指導してもらって、言葉や自らの動きで「記憶」することができれば、再現も容易になります。 発声に関しては、歌を歌うときだけでなく、人に(特に大勢の人に)向かって話す場合にも大事なこと。また、「声に出して読む」ときにも大事なこと。つまり、けっこうみんなにとって、大事なことなんです 。口の形や舌の動きの練習なんて、マニアックなようでいて実はみんながやってもいい基本的な練習なのかもしれませんよ。(^^;)ちなみに、小学校の教室では、「音読練習」と称してけっこう継続的にやっていたりします。
2007.05.20
コメント(0)
-
「特別支援教育士」の取得を目指します。
昨日はひさびさに地域の熱心な先生方が集まる教師サークルに参加しました。先生方の実践レポートや口頭報告に大変刺激を受けた1日でした。2次会では、近くに座った方々が「特別支援教育士」取得の勉強をされていることを聞いてびっくり。私もちょうどこれを取得しようと思って、申請書類を取り寄せたところです。市教委の人に、「特別支援教育にかかわる資格取得について、補助が出たりしないですか?」と聞くと、「全くでない」ということだったのでちょっと残念ですが、がんばって勉強してみようと思います。◆特別支援教育士 http://wwwsoc.nii.ac.jp/sens/ なお、特別支援の教員免許も現職者はとりやすくなっているはずなので、それもあわせて「どうやったらいいのかな」とアンテナを張っている最中です。
2007.05.19
コメント(4)
-
コメント・トラックバックの書き込み制限を解除しました
少し前に、コメントやトラックバックの書き込み制限を解除しました。以前、制限を加えたときに、「書き込みができなくなったよ~」という声が何件かあり、それについてはできるようにしたつもりでしたが、今回、完全にオープンにしました。迷惑メールみたいな不適切な書き込みにはそのつど対処しようと思います。そんなわけで、「楽天」会員でない人も、誰でもコメントがつけられると思いますので、広くいろんな方のコメントを、よろしくお願いします。
2007.05.19
コメント(0)
-

特別支援教育の本(今から注文する本)
アマゾンが、特別支援教育の分野で新刊が出るのを今か今かと待っていたある先生の新刊を知らせてくれました。どうも4月のうちに出ていたようです。これは買わないと!ただ、今回は学校の研修図書費で買ってみようかと思います。わりと予算を取っていただいているので。おなじように、学校で注文したい本を、芋づる式に情報を引き出してみました。どれも、著者の先生や、Webで分かる概要から、自費で買っても損はないと思える本です。基本的にこのブログでは買って読んだ後のおすすめ本を紹介するのですが、今回は読む前から紹介します。以下の本たちです。1. 『特別支援教育学級担任のための教育技術』(青山新吾/上条晴夫、学事出版、2007/4、2100円) ↑青山先生、上条先生ともに何度かお話を聞かせていただいたことがありますが、 お二人ともとても信頼できる方です。 「教育」の今後に生かせるとても具体的な内容が書かれてあると確信します。【目次】(「BOOK」データベースより)第1章 特別支援教育の授業技術・10の原則(授業展開の見通しを明確にし、安定した授業をしよう/1時間を1つの単位とした授業構成とオムニバス方式による授業構成を使い分けよう/1時間の授業の中に、必ず全員参加できる場面をつくろう ほか)/第2章 特別支援教育の授業づくり―授業成立のための教育技術(授業構成の技術/環境・場づくりの技術/子ども理解の技術 ほか)/第3章 特別支援教育の学級経営―集団づくり・子どもの関係づくり(集団づくり/子ども同士の関係づくり) 2. 『みんな違ってみんないい学級崩壊の教訓を生かした特別支援教育へ』 ←このタイトルにひかれます。えじそんブックレット(品川裕香/高山恵子、新科学出版社、2003、500円)←お買い得!【目次】(「BOOK」データベースより)はじめに すべては学級崩壊からはじまった/第1章 対談 特別支援教育の現状と課題―ホントに求められているものってなに?/第2章 一番必要なのはハートからの共感―LDを持った少年を、先生が理解した日/第3章 私たちにできること!―AD/HD、LD、AS等の理解と対応/第4章 誰にだって、できることはある!(大学との連携で子どもたちへの支援を進める―兵庫県神戸市の場合/略)/第5章 学童保育・塾の役割 3. 『気になる子がぐんぐん伸びる授業LD・ADHD・アスペルガー症候群』 ←やはり授業の中で何ができるかは大事です。(品川裕香/高山恵子、小学館、2006、1300円)【内容情報】(「BOOK」データベースより)「LDもADHDもアスペルガー症候群も、私は勉強したからもうだいたい知っています」。そう思われた方、ちょっと待ってください。実は、LD、ADHD、アスペルガー症候群などとひとくちに言っても、一人ひとり状態像がまったく違います。それに、大切なのは、障害名を知ることではなく、その子の特性からくる問題と今苦手なことを理解し、支援・指導することなのです。気になる子をさりげなくサポートしている先生は、以前から全国に確かに存在したのです。その技を学校全体のシステムとして広げること、これこそが特別支援教育ではないでしょうか。教室でよく起こる57事例に添って解説。【目次】(「BOOK」データベースより)第1章 子ども編(まったくできないわけではないけれど、読み書きが苦手な子には?/読み書きだけでなく、聴くことが苦手な子には?/指示通りに動けない子には? ほか)/第2章 教師編(専科の先生と連携するには?/校内で孤立1 学校全体が特別支援教育に積極的でないときには?/校内で孤立2 管理職に理解がないときには? ほか)/第3章 保護者編(子どもがADHDだと思うが、保護者にどのように伝えればいい?/「アスペルガー症候群だと思う」と話したら、保護者が強く反発/障害名を伝えるのではなく、いろいろな状態像があることを知ってもらう ほか) 4.『教室でできる特別支援教育のアイデア172(小学校編) シリーズ教室で行う特別支援教育』 ←前から買いたかったのですが、保留になってました。(月森久江、図書文化社、2005、2520円) 【内容情報】(「BOOK」データベースより) 本書は、教育現場の要望に応えるとともに、教師や指導者、巡回相談員、スクールカウンセラー、保護者にも幅広く活用できるよう、わかりやすく具体的な支援策を示してあります。さらに、タイトルからの検索で、知りたい情報がすぐ手に取れるような構成になっています。 【目次】(「BOOK」データベースより) 第1章 学習に関する支援(聞くことが苦手な子/話すことが苦手な子/読むことが苦手な子 ほか)/第2章 ライフスキルの支援(集団での話し合いができ ない子/係や当番活動ができない子/衝動性の高い子 ほか)/第3章 問題行動への対応(教室を飛び出す/他者や自分を傷つける/友達の物をすぐ取る ほ か) 情報ばかり多くなってしまいましたね。おわります。(^-^;)
2007.05.17
コメント(0)
-

斎藤孝『偏愛マップ』
ひさびさに、読んだ本の紹介です。軽いやつ、一丁。 『偏愛マップキラいな人がいなくなるコミュニケーション・メソッド』(斎藤孝、NTT出版、2004、約900円)【目次】(「BOOK」データベースより)第1部 偏愛劇場(偏愛マップって何だろう?/奇跡の出会いを体験しよう/ドキュメント・偏愛マップ合コン)/第2部 あこがれの偏愛ワールド(実はとっても知性的!(岡本太郎)/偏愛マップの先生(向田邦子)/いかがわしいまでの偏愛者(寺山修司)/やっぱりラブ&ピース(ジョン・レノン)/元気あふれる偏愛文士(坂口安吾))/第3部 偏愛マップであそぼ(ノミニケーションに代わるコミュニケーション/こんな場面で使いたい) 以前より、斎藤孝氏の提唱する「マッピング・コミュニケーション」というのにはかなり興味がありました。視覚的に情報をマッピングし、それを共有してコミュニケーションをする、というだけで、確かに話はしやすくなるし、共通の話題を見つけて盛り上がることも増えるでしょう。いろいろなところに応用が効くはずです。こういう、応用が効くものを、「基本」と呼ぶのです。マッピング・コミュニケーションはまだまだ社会上大衆認知された「基本」とは言いがたいですが、その可能性を見れば、私は「基本」として多くの方に学んでいただくだけの価値があると思います。そんなわけで、興味をもたれた方は、ぜひ読んでみましょう。なお、次のようなこととも、つながりが深いと思います。 ・ウェビング ・グルーピング ・ペア・トーク ・構造化 ・具体化 ・強調 ・共通項探し ・芋づる式 ・プラスの相乗効果 ・共有なんか、教師用語っぽいのや、今思いつきで浮かんだ言葉もまざってますが。 ちなみに、本に書いてあったのですが、合コンでは、「行きつけのマッサージ師がいるというのは話題になるらしい」ということです。私はよくマッサージのお世話になるので、今度合コンしたら、その話題をふってみます。(笑)最後に、巻末に書いてあった著者からの推薦の言葉を引用。「この方法はビジネスの世界で強力な力を発揮する」「仕事の生産性を決めるのは、コミュニケーションの密度と速度」私もこれに同感します。私が主になって進めている職場の校内委員会では、実はこういった点を重視してホワイトボードに板書をするようにしていました。(今年度は私は板書係ではなく司会をしていますが。) なお、類書に『ストレス知らずの対話術 マッピング・コミュニケーション入門』があります。これは私はまだ読んでいません。
2007.05.16
コメント(2)
-
たあいもない日記
今から、たあいもない日記を書きます。GWに熊野古道に行く前あたりから、足の裏の皮がむけやすくなっていて、最近はそれがかなりのピーク、歩いていると痛くてしょうがない。そのため、今日は仕事を早め(18時すぎ)に切り上げて、皮膚科に行こうと決めていました。 阪神「御影」駅の近くにある皮膚科を調べていたので、そこへ。 曜日ごとに午後休診だったのを、ちゃんと記憶していなかったので、電車の中では、「火曜はやってる日かな」と不安でした。 ビルの前の看板を見ると、火曜、「19時まで」で「〇」がついていました。よし、あいてる。ビルの4階が皮膚科です。4階の電気がついていなさそうでしたが、気にせずエレベーターで4階へ。 皮膚科の入り口に到着。張り紙が1枚。・・・「診療は18時までに変わりました」 ビルの前の案内表示も変えといてね!!気を取り直して、「近くにもまだあったはず」と探していると、ありました。阪神「御影」駅北にも、皮膚科が1件。ここは夜20時までだ~ ・・・ 火曜日 午後 ×働きながら皮膚科に行くのも、一苦労ですな。 とはいえ、せっかく早めに仕事を終えて珍しく19時前に駅前をうろついているので、なんとしても今日診療してしまわねば!(足ももう限界だし。。。)これ以上自力で皮膚科をみつけるのは無理だと判断し、薬屋さんで聞いてみたところ、よく分かる人に電話をして尋ねてくれました。「え?あそこって、皮膚科でしたか? 何時まで? ぎりぎりですね。 あと10分くらいでいけると思うので、 待っててもらえます?」やさしい薬剤師さんが電話してくれたので、結局JR「住吉」駅南の皮膚科に行くことができました。 ちなみに、皮膚科のほうが優先でしたが、最近咳をするようになったので、「内科も行かないと」と思っていたのでした。なんと、ラッキーなことに、そこは内科もやっているお医者さんでした。そんなわけで、皮膚科の診療を終えた後、内科も見てもらい、 結局はまあ、よかったかな、という形で1日を終えることができました。ツイてる、ツイてる・・・かな。(>_^;)
2007.05.15
コメント(2)
-
「この場面でこうする!」~とても役立つ特別支援の研修形態
特別支援の研修に4~5月とよさそうなのにちょくちょく出かけています。その中でよかったものは、やはり具体的で即実践にむすびつきやすいもの。例えば、 神戸西山記念会館であったセミナーです。 ■神戸西山記念会館で寸劇を交えた講演会に700人以上の参加者。http://www.schoolweb.ne.jp/weblog/index.php?id=2770001&type=1&column_id=36423&category_id=1382&date=20070422他の都合と重なって時間的にあまり見られなかったのですが、どの先生方も楽しそうに演じられていました。また、昨日は淡路島でTOSSデー特別支援セミナーがあったのですが、そこにも行ってきました。http://tos-kitutuki.net/tossday/tossdayawaji.htmどちらも「模擬授業」「ロールプレイによる実演」が組み込まれ、「こんな状況のとき、こうだから、こう対応したらまずい、 こう対応したらよい」ということが、具体的に、目で見てわかり、 また自分の教室での記憶とも結びついて理解しやすく、実践的でした。このような研修がだんだん増えてきたことをうれしく思います。ただ、私は今は特別支援学級担をしているので、30人規模の学級指導をする機会がなく、こういった研修で、「よし、自分もやってみよう」と思っても試してみることができなくて残念です。「気になる子」への関わりは、ちょくちょくやってはいるのですが。学級担任の先生にもこういった研修をすすめておりますが、なかなか実際に足を運ばれる方がいないので、「一度見てもらったら分かるのになー」と思っています。Web上に模擬授業の様子とかアップしていただいて、「こんなのですよ、いいでしょう?」と具体的にお知らせできるといいのですが・・・。ちなみに私は演劇をしていたので、こういうのはかなり好きです。(^^)演技をすることで子どもの気持ちが見えてくることも多く、見る人にとっても、やる人にとっても、学びが多いやり方だと思います。ちなみに、「教育分野での模擬授業の一般Web公開」については、このブログでも以前お知らせしましたが、読売オンラインの教育ルネサンスフォーラムがだいぶ前からやっています。「特別支援の・・・」というわけではないですが、やはり動画で見られるので、見た者の「分かり感」が違います。
2007.05.13
コメント(0)
-
かけっこで速く走るには?~かけっこの指導
今日は、体育の個別特訓で、かけっこの指導をしました。指導時間は20分くらい?そんなに長くはしなかったと思います。でも、受け持ちの子のがんばりもあって、大変記録を伸ばしました。過去最高の記録が出たのでうれしくなって、私も50m走を走りたくなりました。交流学級の6年2組の先生と一緒に走りました。ほぼ同着でした。どちらかが威厳を落とすことがなくてよかったです。(^^;)受け持ちの子に「見とけよ」と言いましたが、後で聞くと「見てなかった~」(^^;)まったく、もう。。 まあ、そんなわけで今日おこなって効果的だったかけっこの指導について書きます。基本的にはどの子にも通用する方法ではあると思います。 1) まず、「目線」を教えます。 「遠くを まっすぐ 見る」 走っているときの目線がまず大事です。 これが遠くをまっすぐ捉えているようなら、 まっすぐ走れます。 この課題はすんなりクリア。 「すごい。よくできてる」とほめます。 2) 腕の振り を教える 最近気づいたことですが、 腕の振りは「ひじ」がポイントです。 ひじをひいて、グーの形に握って、 腰の入ったパンチが打てるといいのですが、 はっきりいってまず「パンチを打つ」ことなんて普段全然しないので、 へなちょこです。 当然腕の振りは全然シャープではありません。 見よう見真似でやらせても身体感覚がそもそも備わっていないので、 本人はまねしているつもりでも、全然甘いです。 こういうときは、手を持って、意識の勘所を声かけしながら、 一体化して腕ふりを続けます。 具体的には私は後ろに回って、子どもの手をとって、 「チャンチャンチャチャン」と運動会のかけっこの曲を口ずさみながら、 リズムよく振って振って振り続けます。 腕振りはかなり課題だったので、 左右交互の前に、まず「右」だけ というのをやりました。 「右」だけの腕ふりで、 シャープなスイングのイメージを作ってから、 →「左」 そして → 「両腕」とすすみました。 スモールステップでリズミカルに、成功のイメージを体得させる反復練習、 しかも楽しく効果音やBGMつき(ただし口ずさみ)でやりました。 これがわりと効いたようです。 ちなみに、似たような指導は受け持ちの子それぞれにおこなっていますが、 どの子も かけっこは 少しずつ 上達してきました。 ある子には「はっきり目的地がわかるゴールバー」が有効だったりと、 それぞれの子の特性に応じて、有効な手立ては少しずつ変わってくるのですが。 3)ここで 1回目の 50m走 を計測しました。 ・・・20秒以上かかっていました。 私は「それはいかん。18秒は余裕で切れるはず。 走り方をしっかり教えるからその通りにやればできる」 と声かけし、次の特訓に移りました。4) 今までの特訓が基本ですが、タイムを縮めるには、 ・スタートダッシュ ・ゴールを駆け抜ける の2点も重要になってきます。 これの練習も少ししました。 「スタートダッシュ」だけに特化した練習は以前やっていたのですが、 時間がかなり空いたので、忘れてしまってました。 やはり指導は継続してしなければなりませんね。 特訓のかいあって、 2回目の計測は 13秒台、3回目の計測は 12秒台でした。よくがんばりましたね。先生はとてもうれしいです。(*^_^*)
2007.05.11
コメント(0)
-
「線路」のハンコで子どもと楽しく勉強しよう
特別支援学級(障害児学級)担任として ちょっと思いついたグッズなのですが、 「線路」のハンコって、あると使えると思いませんか? 線路をつなげて長い線路を作ったり、 線路の周りに絵を描いたり・・・ ハンコだったらとってもお手軽にできます。 立体「線路」のおもちゃの、平面版。 しかもほぼ無限につなげられる! そういう教材をすでにご存知の方がいらっしゃったら お知らせください。 売ってなくても、教材屋に特注でつくってもらおうかな、 と思っています。
2007.05.08
コメント(4)
-

熊野古道旅行より帰ってきました
6日日曜、無事熊野古道をメインとした旅行から帰ってきました。車での往復は和歌山から奈良へ向かう山のど真ん中を通り、すばらしい山々の景色にとても爽快な気分になりました。また、これまで録りためていたCDやテープからお気に入りの曲をたくさん聴いたので、長いドライブも楽しめました。(「僕の見たビートルズはテレビの中」「海を見に行こうよ」 「パッとさいでりあの歌」等、かなり久しぶりに聴きましたが、 いやあ、いい歌です。(^^;))写真を撮ってきたので詳しい振り返りはまた今度書こうと思います。おおざっぱにどこに行ってきたかを書きます。(1日目)・谷瀬のつり橋(日本最長)・熊野本宮大社・大斎原(おおゆのはら)・忘帰洞(洞窟温泉):行くのに思いっきり迷う!(2日目)・朝、マグロのせり市に行くも、やってない。。。(翌日行きなおし)・熊野古道★ 10kmの山道(起伏の大変激しいコース)を 「熊野古道」の起点「滝尻」に向かって逆に歩く。 標準5時間くらいかかるところを、3時間半で歩く。 しかも、途中迷って民家のある道へ。 「一本道だから迷わない」と言われてたのにそれでも迷うって いったい・・・(>。<;) 午後は雨が降るという予報でしたが、 ご利益に恵まれ、この日は全然降りませんでした!(^0^) ・川湯温泉・わたらせ温泉・熊野本宮大社 泊(テレビがないと、夜することがないのだ、と気づきました。。。 昔の人が早く寝ていた理由はこれか!?) (3日目)・那智勝浦 生マグロのせり・那智の大滝・来た道を戻って帰る以下、時間があったので大阪で寄り道・仁徳天皇稜・千寿の湯(屋久杉風呂)
2007.05.06
コメント(0)
-
明日から熊野古道へ
今日は読書したり、本を買ったり、本を売ったり、とゆったりしてすごしました。 (古本屋、本を売りに行ったらまた4・5冊買ってきてしまった。。。 読んでも読んでも新しく買うほうが多いので そのうちうちの家は本に埋もれるんじゃないだろうか。)明日より、和歌山県熊野詣一人旅に行ってきます。熊野古道は、2004年に「紀伊山地の霊場と参詣道」としてユネスコの世界遺産(文化遺産)として登録されました。世界遺産としては珍しい、「道」の世界遺産です。(Web百科事典Wikipediaより) 古来、日本の有名人は何度も熊野に参詣しました。後白河上皇はなんと33回も熊野に行ったんだって!たくさん行けば行くほど、ご利益があるとされていたからです。昔は、今のようにぴゅっと行ってぴゅっと帰ってこれないので、山道を何泊何十泊として、危険を肌で感じながらの長旅だったのでしょう。今は車ですぐ近くまで行けるので便利ですが、山道の古い杉の木立を歩くと、そういった昔の人の苦労がしのばれるような気がします。詳しくは、例えばこんなページが詳しいです。http://www.hongu.jp/kumanokodou/kodou/index.htm事前学習として、本当は「神仏習合(本地垂迹(ほんちすいじゃく)説)」について勉強してから行くといいのですが、あまり勉強していません。 「世界遺産」とはいっても、その「意味」を知らなければ、たんなる山道、というようなことが書いてある旅行記があり、今からでもちょっと調べてみようかな、と思っています。でも、なんだかちょっとむずかしいのねん。。。(>。<) ちなみに、泊まるところですが、明日の宿泊先はなんと今日決めました。 GW中なので、なかなか空いていなくて苦労しましたが、明日は新宮近くのギリギリ三重県にあるビジネスホテルに泊まります。(ビジネスホテルサンライト http://www.ztv.ne.jp/gzubtbex/index.html)あさっては、熊野詣の目的地、熊野本宮大社のお寺(宿坊)に泊まります。高速道路が渋滞していたり、車での道中でかなり時間をとりそうなので、熊野古道を3~4時間のコースは歩きたいですが、どうなるかわかりません。車で走る道路のすぐ近くの山道を、1時間程度歩くだけになるかもしれません。なお、行きがけに十津川を通ります。日本一長いつり橋があるので、車道から近いこともあり、渡ってきます。また、熊の本宮大社の近くに、日本一広い露天風呂(わたらせ温泉)があり、そこも行きます。楽しみです♪温泉はほかにもよさそうなところが山ほどあり、スケジュールは細かく立ててませんが、どこに行くか悩みそうです。欲丸出しですが、いちおう今回は一人で行くすぴりちゅあるな旅です。古くから続く自然の息吹を感じ、古人の旅をなぞり、世俗を離れお寺に泊まるという、精神的に高尚な旅なのです・・・たぶん。
2007.05.03
コメント(0)
-

「『わかる』ということの意味」~『わかる』ということが、わかっていますか。
昨日の日記で、「わかる とは、 かわる こと」という、高木善之さんの言葉を引用しました。それに関連づけて、「分かる」ということをテーマにした教育書、佐伯胖(さえきゆたか)『「わかる」ということの意味』、1983、岩波書店を紐解いてみました。(▼今手に入るバージョンは・・・岩波書店、『子どもと教育「わかる」ということの意味新版』 1995,1800円)【目次】1 大人はわかっているのか?/2 子どもはわかろうとしている/3 「わかる」ことから「なっとくする」ことへ/4 何のためにわかるのか―文化的実践への参加 )(リンク先は新版ですが、私が読んだのは旧版です。 ページ数は、違っているかもしれません。) 同書p110より===========================「ほんとうは、君にはきっとすばらしい能力があるのだ」と本気で信じてくれる先生や親がいてくれれば、ボクもそんなに不安がって、「能力なし」とされまいとツッパることに忙しいということにはならないと思います。===========================親が子どもにしてやることで一番大事なのは、信じることだ、というのは、斎藤一人さんの近著でもふれられていました。(これは昨日読み終わった本です。斎藤一人『普通はつらいよ』 )このテーマは大変奥深いものなので、こうやっていろんな本を関連づけて徹底して追求していくと、いいかもしれません。「教育」の根本を考えることであると思います。逆に、これを全く深く考えずに「ただ教えているだけ」という教育になってしまった場合、それは大変危ういことのように思います。以下、佐伯先生の本より引用を続けます。 p118より==========================親や先生たちが、子どもから学び、子どもを原因としつつ、自らも変わり、子どもへのはたらきかけをしていく、という感覚があふれている環境をつくることこそ、今日何よりも必要なのではないかと思います。==========================ここで、「変わる」という言葉が出てきました。しかも、本人が変わることの前提として、「周りが変わる」ことにふれられています。大変示唆的です。 「わかる」「できる」「変わる」ということは、具体的にどのケースでどういうことか。これは突き詰めていく必要があるのではないか?具体的なケースは本の中を読んでいただくとして、まとめ的なことを、本の終わりのほうよりどんどん引用していきます。p170より ========================== 「本当にわかる」「本当にできる」ためには、まさにこの「できること」と「わかる」ことの相互作用が活発にならなくてはならないのです。しかし、そのためには、「中心的な問い」を適切に入れかえる必要があるのです。あるときは思い切って「できるようになること」に専念し、別のときには「わかるようになること」に専念し、しかも、その行ったり来たりをしながら、それらを通して自然に「わかる」ことや、自然に「できる」ことを自覚しなおすことがなければならないのです。============================ここの部分だけ読むと抽象的ですが、具体的な経験・エピソードを思い起こしながら、自分の頭の中にリンクを張っていってほしいのです。もしかすると、昔わかっていて、今は忘れてしまったことが、再び戻ってきたかもしれません。(^^) ちなみに、具体的な「わかる」方法論の中には、p182に、===============================・視点を意識する :「納得する」ための重要な手がかり===============================ということが書かれています。また、再三にわたって、「わかり直し」という言葉が使われます。p193===============================・私たちは人生の途上で何度も何度も「わかり直す」べきなのです。===============================そうすると、そもそも「学校」とは何か。 そういった、広く大きなところにまで行き着きます。 そもそも「学校」とは何か、「教育」とは何か。日々具体的な細かなことで悩みながら実践を積み重ねていると、つい目の前のことに追われるのみで、こういった大きなこと、原理・原則的なことを見失ってしまうことがあります。己の戒めに、今こういった本をもう一度読み返してみてよかったです。 p212以降より(部分引用を配し、覚えておきたい点をまとめた)===============================・学校というところ: 生涯を通して学び続けるための準備をするところ・学校で学ばなければならないこと (1) 自分が何を学ぶべきか選択できること (2) 自分で自分の学びが正しいか否かを判断できること (3) 他人や社会と交渉をもち、 社会や文化から新しい知識を吸収できること・学問というもの: 「ほんとうだとされていること」を学ぶことではなく、 まさに、自分自身で、本気で、 「何が本当なのか」と問うこと、問いつづけること ・他人から「感化を受ける」ことができるためには: (1)何が本当に価値あることかを求めつづけること。 (2)「表面的なこと」の背後には、常に、 「表面に現れていないこと」があるはずだと考え、 それがどんなものかを知ろうとすること (3)ものごとには常にさまざまな側面があり、 「かくかくしかじかである」という断定は できうる限り保留し、 いつでも、根本から考え直すことを辞さない覚悟をしていること。 =一言で言ってしまえば、「無知の知」 (自分が無知であるということの素直な受容)===============================非常にテーマが大きくなったところで、今日はこのへんで。 ところでこの本、なんと古本屋で105円で買ったんですよね。全くお買い得でした。定価で買ってもいい買い物なので、ぜひこれを読まれた教育関係者の方は、今手に入る新版を買って読まれることをおすすめします。佐伯先生の本は、他の本も、具体性に富んでいて読み物としてもおもしろく、基本をおさえたり、大事なことを確認する上で最適です。おすすめの教育学者さんです。
2007.05.01
コメント(0)
全19件 (19件中 1-19件目)
1