2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2010年03月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-

もの思いに沈む人
ようやく3月が終わり、年度も終わるといった気分です。はやく4月という文字を見て、気分も爽やかなようにとも思います。会社の食堂でランチを食べて終わって、レジに向かったところで、BGMが変わり、シューマンの花の曲が流れました。普段は映画音楽とかが多いなか、こんなマイナーな曲知っている人なんて誰もいないだろうなあと、イントロあて早押しクイズだったら、会社のなかで何千人いようがたぶん一番にボタン押せるのではとか、笑ってしまうようなことまで考えてしまいました。他のシューマンの曲に比べておだやかな気がしますが、いろいろ落ち着いた時期に作品を書いたのでしょうか。BGM: シューマン 花の曲 Op.19 ピアノ:リヒテルの演奏http://www.youtube.com/watch?v=6bn3PdTyj0Q ホロヴィッツの演奏 http://www.youtube.com/watch?v=hS9gJ9ESfw8&feature=related 質実剛健な演奏、繊細で蝶が舞うような演奏、どちらも好きです。 春の夕暮れ時、菜の花が川へりのテラスに咲いていました。 花の曲とか、カンツォネッタとか頭に浮かべて歩いていました。●ここからは昨日のつづきです。家でCD聴いていたものが、yoububeにもあって、驚きました。でもCDの解説には曲の背景や詩が書いてあったので、これも必要かと思いました。BGM:リスト 巡礼の年 第2年 「イタリア」より ピアノ:アルフレッド・ブレンデル第2曲:もの思いに沈む人 http://www.youtube.com/watch?v=D5auhsOTjyQ&NR=1 私は眠りに感謝する。石で作られしことを、さらに感謝する。地上に不正と恥辱がある限り。見ぬこと、感じぬことこそ幸い。私を目覚めさせることなかれ、声ひそかに語りたまえ。ミケランジェロの彫刻と詩を結び付けている作品。彫刻はフィレンツェのロレンツォ・ディ・メディチの墓に刻まれた彫像。第3曲サルヴァトール・ローザのカンツォネッタhttp://www.youtube.com/watch?v=pO-Abo1AR2o&NR=1第4曲ペトラルカのソネット第47番http://www.youtube.com/watch?v=EX5qVB5iENY&NR=1第5曲ペトラルカのソネット第104番(ブレンデル)http://www.youtube.com/watch?v=jqtAkeKYAyw&NR=1(ホロヴィッツ)http://www.youtube.com/watch?v=JdNNPcctrJY第6曲ペトラルカのソネット第123番http://www.youtube.com/watch?v=qrsXOCCjbQUどんなおもいでリストはイタリアを旅していたのか、聴いてみたくなりました。調べたくなりました。
March 31, 2010
コメント(0)
-
ココロの万華鏡というタイトルのエッセイ
最近、いろいろな記事を見て、特に癒される思いがするのは、香山リカさんのもの。有名経済評論家と喧々諤々というときもありますが、きわめて自然体で、無理のない語り口。こうして文章を書くことを日課としていて、見習いたいひとりでもあります。http://mainichi.jp/life/health/kokoro/news/20100302ddlk13070269000c.html毎日新聞のエッセイで「ココロの万華鏡」というものを連載されています。身につまされるようなできごとは、いつ何どき立ち会うこともあろうでしょうし、いろいろ参考にもしたいですね。BGM: リスト 巡礼の年 第2年 「イタリア」 第3曲 サルヴァトール・ローザのカンツォネッタ 第4曲 ペトラルカのソネット第47番 第5曲 ペトラルカのソネット第104番 第6曲 ペトラルカのソネット第123番 ピアノ:アルフレッド・ブレンデル 凍れる炎、見える盲目、泣き笑い。・・・・二面性を演じた歌は美しくもありはかないです。 第3曲のカンツォネッタは、自分自身、唯一リストを人前で弾いた曲。 なんだか懐かしいです。
March 30, 2010
コメント(0)
-

グビジンソウ・虞美人草
グビジンソウ・・・。最近なにかとお世話になっているようにも思えます。「ひなげし」といわずに、「グビジンソウ」と言ってしまう、言えるところも偉大な花のひとつということかもしれません。花言葉は「慰め、いたわり、陽気で優しい、思いやり」 すてきな言葉ばかりです。 グビジンソウ・虞美人草 ということばをはじめて耳にしたのは夏目漱石の小説タイトルから。この小説、タイトルだけできちんと知りません。夏目漱石が新聞社での小説デビューの作品、気負いすぎて賛否両論だというどこかのブログ感想文もありました。 それにしてもいろいろな登場人物が出てきます。ある尊敬する方に、「坂の上の雲」のあとの日本の歴史や時代背景を知りたければ、片っぱしから、漱石の作品を読みなさいと助言されたこともあり、最近ものすごく気にしております。えいやーで、ぱっと開けたページをとりあえず読むことにしました。心理描写の細やかなこと、春に関すること、テンポのある文章、ただそれだけでも惹かれてしまいました。「只(ただ)機一発という間際で、煩悶(はんもん)する。どうすることもできぬ心が急く。進むのが怖い。退くのが嫌だ。早く事件が発展すればと念じながら、発展するのが不安心である。従って、気軽な宗近が羨ましい。万事を商量とするものは一本調子のものを羨ましがる。春は行く。行く春は暮れる。絹の如き浅黄(あさぎ)の幕はふわりふわりと幾枚も空を離れて地の上に被(かぶ)さってくる。払いのける風も見えぬ往来は、夕暮れの為すがままに静まり返って、蒼然たる大地の色は刻々に蔓(はびこ)ってくる。西の果てに用もなく薄やいでいた雲は漸(ようや)く紫に変わった。」最初から読むと200ページをはるかに超えないとここへはたどり着けません。相当いろいろあった感じがします。●夏目漱石は虞美人草というタイトルをつけるとき、タイトルがなかなか決まらず、悩んでいたところ、花屋さんで偶然虞美人草を見つけ、名付けを決めたそうです。BGM:シューマン 3つのロマンス Op.28 第2曲 ピアノ:マリア・ジョアン・ピリス とてもおだやかな気分になれる曲。虞美人草の花言葉のようです。 http://www.youtube.com/watch?v=9a68ACS_nJM
March 29, 2010
コメント(0)
-

大庭さんが主人公の映画
とても寒い夕方、有楽町のスバル座というところで、映画見ていました。大庭さんが主人公・・・とタイトルに書きましたが、太宰治の人間失格。 主人公は大庭葉蔵(おおばようぞう)、太宰自身のこととも言われています。 戦後の日本の小説で600万部以上発行部数があり、夏目漱石の「こころ」と同じくらいで、この2つが飛びぬけているのだそうです。この映画、見よう見ようとおもっていて、ようやく時間とれたので行きました。ピアノの発表会のあとのご褒美の時間のよう。最近夜の上映がなくなり、夕方の会がこの日の最後、年齢層まちまち、それなりに人はいました。小説そのものは、簡単に見れるようになっていることもあって、映画のおさらいと原文のおさらいのような感じのこともしました。絵描きさんが主人公ということもあって、芸術論なんてのも、熱くでてきたりして、なかででてきたり共感できるものもあったり。こういう影のある人は結構もてる人なんだと見入ってしまったり。だんだんと堕ちていくところは物悲しくなりましたが、主人公は主人公でそれなりに精一杯生きているのだとおもうことにします。後見人の役をしているヒラメさんという役の人はちょっと怖く感じました。キャスティングが冴えわたっているようで、大庭葉蔵の生田さんは天才的。それをとりまく7人の女性役。はまり役の方ばかりでした。 音楽は、やはりシューベルト「アヴェマリア」でしたが挿入されていました。エンディングでのピアノのメロディはとても切ないものありました。音楽担当は、中島ノブユキ氏、 今後も気になりそうな感じです。● 映画館をでて、しばらく歩くと東京国際フォーラム。寒いなかでもチューリップの花壇は映画が暗かったせいかひときわ明るく感じました。5月のはじめになれば、また音楽家でいっぱいになるのでしょうね。はやく暖かい春がきてほしい感じがしました。
March 28, 2010
コメント(0)
-
「将棋界の一番長い日」のドキュメント
寒いしどこへも行く気もなく巣籠りの土曜日、いつものようにBS2で朝ドラをまとめてみて、俳句王国で季節感をかんじだあと、チャンネルをかえるのが一瞬遅かったために目にした番組だったのかもしれません。「将棋界の一番長い日」のドキュメント「毎年3月頃の、A級順位戦の最終局(5局が同日に開催される)が行われる日を、俗に「将棋界のいちばん長い日」と呼ぶ。約1年間かけて行われたA級順位戦リーグの最終日であり、名人挑戦者と2名の陥落者が確定する可能性が高い(既に挑戦者や陥落者が決まっていることもある)ため、プロ棋士をはじめとする将棋界からの注目が高くなる。例年、NHK衛星第2テレビジョンで中継が行われる。同局で将棋の中継が行われるのは、他には竜王戦と名人戦の七番勝負、地上波で放送しているNHK杯将棋トーナメントのみである」WEB上では、このように紹介されています。3月2日に1日かけて将棋のA級の棋士が10人、優勝者が名人戦へ挑戦、B級に降格する人2人、候補者が複数名、その日が終わってみないとどうなるかわからない、そんな男の世界を、テレビが完全中継。今回はそのなかのダイジェストのドキュメンタリー。1日といっても、9時ー5時のサラリーマンの世界ではなく、持ち時間6時間ずつでの対極、5組10人の将棋の世界でありますが、投了するのは深夜0時、深夜1時とまさに激闘、事務局も含めお開きになるのは深夜4時ごろ、意地とプライドをかけた戦いは見ているだけでハラハラするものありました。将棋人口は700万人ほどいるそうです、その中でのプロ棋士が数百人、名人の次の位がA級10人ですが、さまざまな生きざまがあるように思えました。http://partyinmylibrary.cocolog-nifty.com/party_in_preparation/2009/03/67a9-7184.htmlこんな途中経過を気にするブログもあるのかとも思いました。●自分と少ししか年が変わらない、谷川九段は、この日勝てば、久々に名人戦に挑戦できるところにいたのですが、残念ながら敗退。勝っても負けても堂々とインタビューに気持ちを答えられること、そんなに簡単にできるものではないと、姿勢・所作が美しい人と定評ありますが、見習いたいところがたくさんあるように思っています。●谷川九段は、私が中学生のころ、旺文社の「○○時代」という雑誌で連載されていたので知るところとなりました。1983年に21歳で史上最年少の名人になり、83,84,88,89,97年度5期名人、1991年に四冠王になったあと、しばらく黄金時代を築くかに見えたが、もっと下の世代の羽生善治とのデットヒートが続く。徐々に数年後ほとんどタイトルを奪われることに。2000年以降、大きなタイトルからは遠ざかっているもののA級順位戦という上位10人には28期連続でいて第一線でいることには違いありません。谷川九段が、色紙に「光速」「前進」「飛翔」「危所遊」とよく書くそうです。「危所遊」をみて??と思いましたが、松尾芭蕉の「名人、危所に遊ぶ」ということばからなのだそうです。「名人達人といわれる人は定跡から外れ、未知の分野にも冒険心を持って飛び込み、そこで楽しむ」という意味です。(ご参考)http://hobby.nikkei.co.jp/shogi/column/index.cfm?i=20020722s3028s3 たいへん共感しました。凡人であっても、そういうゆとりや遊び心は必要だと思っていますから。●きょうは、ピアノのおけいこ、いろいろできそうです。モーツァルトのK.545人に聴いてもらうこととなれば、35年ぶりになるのでしょうか。途中で短調に転調するところ、いろいろあって元にもどってくるところとかは、K.540の交響曲40番、K.620のオペラ「魔笛」・・・などにヒントがあり見ておいた方がいいとお告げがありました。せっかくの機会なので、そういうものに触れながらピアノの小さな曲にも戯れてみようと思っています。BGM: モーツァルト オペラ「魔笛」 K.620より 夜の女王のアリア「復讐の心は地獄のように燃え」http://www.youtube.com/watch?v=DvuKxL4LOqc&feature=related
March 27, 2010
コメント(0)
-
朗読3コマx2
何の気なしに、新聞のテレビ欄をみて、見てみたくなったもの。太宰治短編小説集 朗読をアニメーションとか映像化したものです。とても終戦直後にできた作品と思えないです。男女の描写は今も当時もそんなにかわらないように思えます。去年の秋の再放送のようです。昨日が、走れメロス・女生徒・雪の夜の話今日が、犯人・きりぎりす・トカトントン3つとも集中して聴けるほどでもありませんが、「走れメロス」は高校の教科書を思い出しながらハラハラしながら・・・・。「女生徒」は、いまのブログとか携帯メールとのりがおなじではないかと。「犯人」は、地下鉄銀座線や井の頭線、中央線もでてきて、当時の鉄道描写と犯人心理が絶妙。「きりぎりす」は、ぐさっとつきささるような感じがしました。ことばも出ません。男性の小説家がここまで女性心理のことをと。おそろしくおもいました。昨年秋のNHKの広告ファイル。http://www3.nhk.or.jp/pr/keiei/shiryou/soukyoku/2009/09/012.pdf今、映画館でもやっているし、なんだか追いかけたくなりそう。BGM:シューベルト 即興曲Op.90-3 なんだか聴いてみたくなりました。 この二人、共通点多そう。 いろんな意味であこがれます。
March 25, 2010
コメント(1)
-
「アルゼンチンよ泣かないで」久々に聴いてみることに。
BGM;アルゼンチンよ泣かないで リチャード・クレイダーマン(pf)http://www.youtube.com/watch?v=eMQKO_hXn5E 高校生のころ、リチャード・クレイダーマンのピアノが結構世の中賑わしていました。親からもらったお小遣いでこれが入っているLPレコードを買ったので、昭和54年の春から夏へにかけてのこと。このころはピアノはもう弾いていなかったので、よけいに覚えています。「渚のアデリーヌ」という曲がお目当てでしたが、この明るい曲はものすごく覚えています。なんでもいいからピアノピース買って、弾いてみようと自己流で練習はじめました。シューマン「トロイメライ」もそのひとつです。30年ほどたって、自己流で弾いている曲を指導者に聴いてもらいました。拍子感から和声からなにからなにまで細かいお話ありました。音楽というものの深さをあらためて感じるにいたりました。そんな簡単な曲ではないということ、思い知らされました。●はなしは「アルゼンチンよ泣かないで」にもどります。アルゼンチンという国がテーマになっていて、背景もなにも知らなかったのですが、エピータという映画が舞台になっていると最近しりました。100年ほど前は、世界のなかで豊かな国の代表国だったアルゼンチンは、第2次大戦後に工業化に失敗し、没落の一途をたどります。その原因を作った人がこの映画の主役(エピータ/エバ・ペロン)なのかということ最近知りました。最近では日本もこの国の行く末のようにたとえられ、アルゼンチン化という言葉をときどき伺います。話を知れば知るほど、聴けば聴くほど、どこかでやってきたことを、自分のところでもと。自分にできることはなにもありませんが、事実を発信することくらいはできるのではないかと思うようになりました。なにかのご参考になれば幸いです。●「日本がアルゼンチンになる日の予感がする。」2009/11/4 大前研一氏の日経BP時事コラムのタイトルhttp://www.nikkeibp.co.jp/article/column/20091104/193320/?P=1●「良い国日本アワー」という番組で、10年後の日本はどうなるかと予想・・・、40%の確率でアルゼンチン化、20%の確率で大繁栄、40%の確率で中華帝国化する(フィンランド化ともいわれている)予想。。。 「日本のアルゼンチン化」という検索キーワードで財務省 PRI財務総合研究所のレポート新潟大学佐野教授のアルゼンチンレポート 南米の自由化の失敗に学ぶよう指摘。http://www.mof.go.jp/jouhou/soken/kenkyu/zk051/zk051h.pdf藤原雄一郎の時事通信http://d.hatena.ne.jp/fujiwaray/20090826日本国際経済学会第67回全国大会 北米ラテンアメリカ経済分科会 レポートhttp://www.biz.u-hyogo.ac.jp/society/jsie200810pdf/20081012_08_C_A.pdf
March 24, 2010
コメント(0)
-

春の花壇
川辺にて、こんな花壇があって、春の日差しに囲まれているなか、ちょっと見とれてしまいました。普段毎日歩く道であっても、桜がこれから咲いてくるし、楽しくなる季節。3月はこれまでにも悲喜こもごもで、あまり得意な季節でないのですが、癒される感じがします。
March 22, 2010
コメント(0)
-
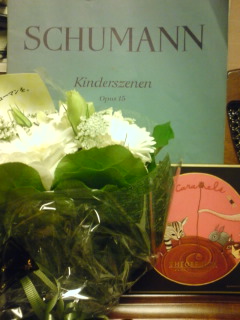
11回目のピアノの発表会
3月下旬にあるピアノの発表会は、2000年から出始めて11年目になりました。シューマン 子供の情景 op.15から珍しいお話、鬼ごっこ、おねだり、満足、重大な出来事、トロイメライ の小品6曲今回は、自分なりに楽しんで弾こうとおもったこと、子供のように弾こうとおもったこと、2月中旬から人前で弾かせていく場をさがしつつ準備をしました。2週間前のリハーサルから、細かいところはずいぶん変わってきた感じがして、またそのように思ってくださるかたもいて、うれしかったです。11年前からずっとご一緒している仲間も大切にしたいです。世の中の風景も年齢もずいぶんかわりましたが、変わらないものも結構あること実感します。ご来場いただいて、大変励みになりました。子供の情景に興味もってくださってうれしい限りです。細々とですがこれからも続けていきます。よろしくお願いいたします。
March 21, 2010
コメント(2)
-
はいどん/芸術劇場をみて・・・
http://www.nhk.or.jp/art/current/music.html#music0319「2009年が没後200年の記念の年であったフランツ・ヨーゼフ・ハイドン(1732~1809)、その作品や伝記に大きな関心が集まった。青年期は貧しい下積み生活を送り、1761年から大貴族エステルハージ家お抱えの楽団の副楽長、楽長を務めたハイドンは、長きにわたり大都会の流行から隔絶された立場にあったがゆえに、独創的な作品を生みだし、次第にヨーロッパ中で人気を博するようになる。1790年以降は一貴族のお抱え作曲家からヨーロッパの巨匠へと一気に飛躍を遂げた。とりわけ2度にわたるロンドン滞在時に初演した12曲のいわゆる「ロンドン・シンフォニー」はハイドンの人生の総決算ともいうべき傑作群である。公演コーナーで取り上げる「ロンドン・シンフォニー」の魅力を紹介する。 」*****NHKのホームページでは、次のように紹介されています。ほかにWEBで載っているハイドンのこととかを参考にしてみて、ちょっとこんな風に考えてみました。今風にいえば、三十歳手前まで、なかなか定職につけずにフリーで生活していたなかで、貴族おかかえの楽団に入り、ようやく定期収入を得るサラリーマン音楽家としてスタートした。自由な作曲とかも認められないなか、その範囲で活躍できる場を求めていった。五十代後半でオーナーが亡くなり、あらたなオーナーはまったくこの音楽の世界に理解を示さず、早期退職プランのようなものに乗っかる。その後新天地を求めてロンドンへ行き、1作品いくらでというスポンサーも見つかり、独立開業した状態で音楽活動を続け成功をとげた。●いろいろなWEBで見ていて、書いてあったことで印象に残ったこと、24歳年下のモーツァルトと出会ってからのこと、モーツァルトが得意とするオペラ、協奏曲をハイドンはまったく書かなくなったということ。自分自身が身をたてていく上で何をすればいいのか、お抱え楽団とはいえ、そのなかでいろいろ世間を知っていたからこそ、そういう判断ができたのでしょう。番組では、交響曲101,103,104と、3つ続けて流すというなかなかありえない番組構成でしたが、聴きながらいい人生を歩んだ人のひとりなのだなあとあらたえて感じました。
March 20, 2010
コメント(2)
-

ふかがわ
江東区のタウン誌「深川」というのをさっきから見ています。大河ドラマ「龍馬伝」で話題になっている岩崎弥太郎のことがずいぶん書かれていて興味深かったです。いまは土佐の話ばかりですが、明治時代になり、東京へ出てきてからのこと・・・坂本龍馬が近江屋で暗殺されて6年後、三菱商会を立ち上げたこと。清澄庭園という大名屋敷を改造した庭園は、東京都の名勝第一号なのだそうですが、明治11年に岩崎弥太郎がこの土地を買い取ったことからはじまり、趣味の庭園造りのものが今に至っていること。東京海洋大学は、その前は、東京商船大学といわれていました。その前身は、三菱商船学校であったということ。明治8年(1875年)に創設されたそうです。歩いてでも行けるところにいろいろ歴史を感じるものがたくさんあることを知りました。●1875年は、ブラームスが生きていた時代、ドビュッシーが生きていた時代、そういうことをついつい考えてしまいますが、洋の東西を行ったり来たりして考えるのも楽しいです。
March 18, 2010
コメント(0)
-
誕生曜日占い★☆
こういうものがあるということを、mixiで知ることとなり、自分自身を客観的に知りたいとよくおもっているのでやってみることにしました。生まれた誕生曜日は水曜日です。いろいろ属性があるのですが、「せせらぎ属性」ということになりました。 *****せせらぎ属性の方に秀でた能力深い探究心と鋭い先見性から紡ぎだす精度の高い計算力に秀でています。また、求められた役割に徹してやりきる正確性を備えているため、人材として重宝される人が多いようです。しかし、その正確さゆえにデリケートな一面もあり、人の好き嫌いが激しいなどの特徴もあげられます。周囲とのバランスをとるために時には自分自身のハメをはずしてみることが必要かもしれません。 せせらぎ属性の方の恋愛観リスクや無駄な恋愛を避け、自分はもちろん相手にも清廉潔白さ、関係の透明性を求める傾向があるようですが、逆にそういったものが見えないミステリアスな人に妙に惹かれてします一面もあるため、いい恋愛をするためには慎重さと軽率さのバランスをとることが重要かもしれません。 せせらぎ属性と相性のいい属性情熱的な実行力でいつも背中を押してくれる「燈(ともしび)」属性の方計画に対して大きな実りをもたらしてくれる「大地(だいち)」属性の方****単純なロードワークはまるで向かないということは、自覚しているので、なるほどと思いました。好き嫌いは激しいのはこれもよくわかっています。自分自身はあまりハメがはずせないかもしれません。居酒屋さんに行っても酔ってわからなくなるということはここ最近ありません。夜中の1時くらいに言われたことを翌日まで確実に記憶していることもあるので、ハメははずせないのでしょうね。自分ではなにもできない人なので、いろいろまわりの方に支えられていることを感じます。ミステリアスな人には妙に惹かれてしまいます。またそういうことに恵まれてきたようにも思います。相性のいい属性。背中を押してくださる方がいると自分は楽ですね。No.2のポジションにはまると案外楽しいのだろうと思っています。***せせらぎ ということばの響きは気に入りました。
March 17, 2010
コメント(2)
-
FM放送でクラシック音楽って・・・。
そういえば、最近FM放送もラジオそのものも聴く回数はめっきり減りました。会社に入ったころは、寮生活で、テレビは共同の部屋にしかなかったので、朝の目覚めの音楽も、休みの日の情報も、もっぱらFM放送でした。J-WAVEという放送局がちょうどできたころで、81.3というものに合わせていることも多かったです。そのもっと前、実家にいるときも、テレビのチャンネル争いするような家でしたが、FM放送はよく聴きました。ポピュラー、クラシック問わずです。1985年のショパンコンクール、ブーニンが優勝したとき、テレビでもドキュメンタリーが衝撃的なものでしたが、じっくり演奏を聴かせるという役割はFM放送が果たしていたように記憶しています。ショパンのピアノ協奏曲1番を1位のブーニン、4位の小山実雅恵さんとたてつづけに放送してカセットテープにA面B面に録音して、車のなかでよく聴いていたこともあります。会社のなかでも、人から聴いたはなしですが、ずっと午後休む人がいて、何をしているのかと思えば、ワーグナーのリングという長大なオペラを毎日FMで放送していて、それをエアチェックするためにそうしていたと、優雅な方のエピソードを聞いたことがあります。最近よくFM放送を聴いていたのは、数年前8週間入院生活していたとき。夕方からのFM放送でのベストオブクラシックとかとても楽しみにしていたこともありました。 ●http://cgi4.nhk.or.jp/hensei/program/ch.cgi?area=001&date=2010-03-21&tz=night&ch=07前ふりがやたらと長くなりましたが、3月7日に大阪のザ・シンフォニーホールで聴いた演奏(ブログ参照)が、今度の日曜日(3月21日)夜7:20から放送されます。作品19にこだわっていたのも、この日のベートーヴェンピアノ協奏曲2番があったから。もしよかったら、一緒に楽しんでいただけるとうれしいです。モーツァルトのK331のさわりだけというのもあります。
March 16, 2010
コメント(0)
-
フライングのさくら
他のさくらはつぼみ固しなのに隅田川の橋のふもとで一本だけこんなかんじ。気が早いのもひとつあってでもほっとしました。あと2週間もすればみんなこうなるのだし。 BGM: メンデルスゾーン 無言歌 Op.30-2http://www.youtube.com/watch?v=AF6IAcuokdc&feature=PlayList&p=7C2983481357726B&playnext=1&playnext_from=PL&index=8「安らぎもなく」とか「心配」とかのタイトル。あと1週間でピアノの発表会、去年弾いた曲をふと聴いています。無言歌はべんきょうになりました。内声がメロディのところ、ひとつめ、ふたつめ、みっつめと同じメロディを変化をつけてもりあげるところ。シューマンもよく似た曲想ありますし、あと少し煮詰めれるようしなければ。歌があるかのように弾けるといいですね。
March 15, 2010
コメント(2)
-

お芝居・シューマン・新宿御苑
「シューマンに関すること」という直球のタイトルのお芝居を見に行きました。新宿1丁目にあるサンモールスタジオhttp://www.sun-mallstudio.com/theatres.htm150人くらい入る小劇場。「舞台とクラシックの融合」をコンセプトに作品を作られている主宰の方の4つめの作品。今回はまだ構想段階から、この企画を教えてくださったり、率直な意見をと言われたり。19世紀半ばと21世紀の今の時代を行ったりきたりしながら、笑いあり涙ありパロディありでとても楽しかったです。クラシックのまったくなじみのない人にとってはシューマンの作品と言われてもぴんとこないのも無理ありません。そのなかでBGMで流したシューマンの作品は、この作曲家を本当に好きでないと出てこないだろうと思うものもいくつかありました。そういう共感できるものも多く垣間見ることができてとてもうれしかったです。(ご参考)劇団イボンヌhttp://engekilife.com/play/15066東京イボンヌ制作日誌http://tivonnu.exblog.jp/i2主宰者のブログhttp://ameblo.jp/crjys504/ ●ものすごくいい気分になり、春の陽気のなか、帰りに、最寄駅である新宿御苑のほうへ歩きました。新宿門と大木戸門のあいだあたりです。あと2週間もすれば、桜並木は満開にきっとなるのでしょう。大木戸門から甲州街道の起点である四谷4丁目、外苑東通りと交差する四谷3丁目まで、てくてくお散歩しました。おかげさまで今日も楽しい1日でした。(ご参考:新宿御苑)http://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen/http://www.fng.or.jp/shinjuku/shinjuku-index.html
March 14, 2010
コメント(0)
-

てんくう・リスト・2年ぶり
いろいろなところからご案内をいただいて、それをたよりにコンサートホールへ伺うのですが、それにしても東京23区内は、どの区もよく整備されたコンサートホールがあるものだと驚いてしまいます。この10年、15年でぜんぜんかわったことのひとつでしょう。足立区の北千住というところに、東京芸術センターというところがあり、21Fに天空劇場というコンサートホールがあります。天空劇場は英語では何って書かれているの??と思ったら、sky theater と以外に素直で日本語のニュアンスの深さを逆に感じてしまいました。21Fに登ると、隅田川沿いの街並みがきれいに見え、それほど離れていない東京スカイツリーもよく見えます。よく名付けられたものだと改めて感じました。昨日の16時からのコンサートは、そんなところで聴かせていただきました。(すみだトリフォニーからはしごしても、電車1本で行けることに感動もしました)http://www.art-center.jp/tokyo/recital/東京芸術センター定期演奏会 2009年度スケジュール小瀧 俊治 ピアノリサイタル 日時 : 2010年3月13日(土) 開場:15:30 開演:16:00 プログラム : (曲目変更後) ハイドン/ピアノ・ソナタ 変ホ長調 Hob.XVI-52 ショパン/ポロネーズ 第7番 変イ長調 Op.61「幻想」 ラヴェル/ラ・ヴァルス** リスト/巡礼の年第1年「スイス」より 第6曲「オーベルマンの谷」 ラフマニノフ/ピアノ・ソナタ第2番 変ロ短調 Op.36(1931年版)(アンコール) シューマン アラベスク op.18現在東京音大大学院在学中の方です。若さあふれる演奏、そのなかに繊細なところもあり、プログラム構成もよく考えられたものだと感じました。後半のオーベルマンの谷、たいへん感動しました。高いパフォーマンスの演奏、また聴きたいです。前半のピアノはプレイエル、後半のピアノはベヒシュタイン。こういうことができるのがここのホールの特色なのかも。繊細でかわいらしい音でのハイドン、ショパン。ストレートでまっすぐな音のなかでのリスト、ラフマニノフ。好みも人それぞれのなか、ピアノの音の聴き比べもまた妙味な感じでありました。● http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200801270000/実は、2年ほど前、ピアノゆめリサイタル at 朝霞市民会館という企画があって、自分もピアノを弾かせていただいたとき、すぐ後ろのプログラムで弾いた方で、いつか演奏会することがあったらと連絡先をお教えしていたもの。社交辞令ではなく、こうして連絡いただき、素敵なコンサートに出会えてよかったと、いろいろなご縁からつながる広場を大切にしたいと感じております。BGM:リスト 巡礼の年 1年 「スイス」よりオーベルマンの谷 LISZT - La Vallée d'Obermann Richter(pf)http://www.youtube.com/watch?v=5lt75uIgvvEhttp://www.youtube.com/watch?v=ZZxetM32JAE&feature=related
March 14, 2010
コメント(0)
-
こだわり・シューマン・ばんそう
すみだトリフォニー小ホールのカフェカウンターの壁の絵画、薄明かりのなか、ものすごいこだわりを感じます。そんななか、1時間ほど、アンサンブルを中心とした演奏を聴いてきました。シューマン 3つのロマンス 作品94伴奏でいつか弾いてみたい曲ということであればまっさきに思い浮かべるもののひとつ。今日はクラリネットとピアノで聴きました。2曲目、今日の春先の穏やかな日にびったりで癒されました。いろんな意味であやかりたいです。****p.s.自宅にもどってきて、またCDとか聴いています。BGM: シューマン 3つのロマンス Op.94より 第2曲 Einfach inning (単純に、内的に。) Heinz Holliger (Oboe) Alfred Brendel (Pinao) http://www.youtube.com/watch?v=lQaUequ7P4w家のCDはピリスなので、ブレンデルの伴奏は今日はじめて聴きました。速くなく、静かに流れる感じなので、これはまたいいですね。
March 13, 2010
コメント(6)
-
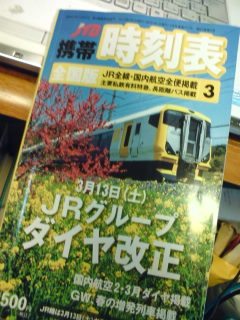
寝台列車ラストランのニュースをみて
3月は季節の変わり目、そして時代の変わり目、いままで普通にあったものが変わっていくところを見たりして、感慨にふけってしまうこともあります。3月2週目の週末に行われる恒例のダイヤ改正。ここで新型車両も大幅に増えたりするのですが、寝台特急「北陸」と夜行列車の急行「能登」が昨日でおしまい。朝のニュースでもずいぶん流れていました。駅まで行って「ありがとう」っていう人を長年走った車両にむかって言うこともいいなあと感じました。週末新橋や東京駅の近くにいることもあり、2年前に自分も同じことをしていました。★★寝台急行「銀河」最後の日http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200803140001/2年前に東京から大阪へ行く「銀河」の東京駅の光景は忘れません。かつて最終の新幹線に乗り遅れて、というか残業の準備で間に合わなくて、次の日の朝までに移動するとき何回か乗ったことあったので、これは見送りに行きました。★★急行「能登」は、寝台ではありませんが、いわゆる「上野発の夜行列車」のひとつ。のんびり金沢へ旅行したとき、一筆書きの旅をしたとき乗ったことあります。一筆書きの旅のとき、東京→直江津→長野→松本→新宿→東京この最初のルートで、「能登に乗りました。」2006年の夏休みのこと、夜明けのころの日本海を直江津港のあたりで見て、そのひとつ隣の駅が最寄の上杉謙信公ゆかりの春日山城へ。そこから川中島の古戦場へ行ったあと、サイトウキネンフェスティバルへというかわったプランでした。上野発の夜行列車http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200609030000/鱈ずしhttp://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200609050000/注文の多い料理店http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200609060000/手毬http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200609070000/サイトウキネン/内田光子リサイタルhttp://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200609080000/モーツァルトイヤーだった年に、ものすごい思い入れで聴きに行ったコンサートだったようにも記憶しています。またおもいつくままにいろんなところへ行ってみたくなりました。
March 13, 2010
コメント(0)
-
しずかに、モーツァルトの緩徐楽章。
静かに、モーツァルトの緩徐楽章を聴いてみたくなりました。 BGM: モーツァルト ピアノソナタ K.545 C-Dur 第2楽章 ピアノ:内田光子 http://www.youtube.com/watch?v=eQpsL_kh6pEソナチネアルバムにも、入っている曲、内田光子さんがアンコールでこの曲よく弾かれていて、自分自身もコンサートでも心があらわれるような演奏を聞いたことあります。楽譜上ではすぐ弾けそうな感じもしますが、これはこれでカンタービレで弾くこと、ちがう意味でも難しさも感じます。小学校5年生のときは、1楽章と3楽章だけやって、この楽章は弾かなかったかもしれません。なんだか忘れ物をしたような気にもなって、童心にかえってみたくなりました。●小学校5年生のころ、総理大臣は田中角栄、途中から三木武夫。三角大福(三木・角栄・大平・福田)といわれたあたり。春の遠足は奈良、秋の遠足は京都・・・・と書けば東京の人には怒られてしまいそうです。林間学校は高野山。広いお寺に泊まりました。電車に乗ってピアノ教室通っていました。子供料金15円。でもオイルショックで物価があがって、20円になり30円になり、子供ながらにインフレの時代を体験しました。石油の値段が4倍になって、どうしようもなかったらしいです。後で聴いた話ですが。トイレットペーパーがなくなる、砂糖がなくなる・・・とみんなで買いに行きました。ソナチネアルバム、結構好きで、練習するのが好きでした。ハノンのスケールとかツェルニーとかもやっていましたが、はやくクレメンティやらクーラウやらのソナチネの作品の時間にならないかなあとおもっていました。NHKのピアノのおけいこの番組よく見ていました。番組のおわりは、ベートーヴェンのソナチネアルバムにはいっているOp.49-2の2楽章だったこと覚えています。またいくつか弾いてみて、人前で弾けるものができればいいなあと思っています。
March 11, 2010
コメント(2)
-

春遠からじ
あまりに寒い日がつづいて、ちょっとびっくりしてしまいます。朝は電車が雪のことで停まってしまうくらいでした。そんななかで、春らしい看板をみたりするとほっとしてしまいます。東京ミッドタウンの看板。7年ぶりに人に会い、談笑しました。名古屋にいたときに会って以来、元気そうで何よりでした。この時も寒かった3月を思い出します。東京みたいにすぐに電車が来ずに、大手自動車会社の最寄駅なのにそこの電車は30分に一本。行ったばかりの電車の駅で28分も待ち、なんでこんなにちがうのだろうと、唖然としたことありました。とても厳しい会社でしたが、ここの担当していたらきっとどこでも通用するだろうと思ったりもしました。
March 10, 2010
コメント(6)
-

「ねこ」の写真展と3月9日
http://www.mitsukoshi.co.jp/store/1010/iwago/岩合光昭さんというねこの写真ばかり撮っている方の写真展、日本橋のデパートでやっていて、癒されました。「この星に、ねこがいる幸せ。」ほんとうにそう思います。 ●あまりに寒いので早く帰宅したのですが、テレビをつけたところ「クローズアップ現代」というNHKの番組で、高校生の就職問題とかがテーマで放送されていました。そのなかで、流れていた歌に感動しました。「3月9日」という歌があって、最近の卒業式にもっともよく歌われるのだそうです。「仰げば尊し」とか、せいぜい「贈る言葉」とかまではわかるのですが・・・、NHKのプロデューサーがわざわざ3月9日に特集して、歌詞を紹介するだけのものだと思います。BGM: レミオロメン 3月9日 http://www.youtube.com/watch?v=-j1JpwKETbU流れる季節の真ん中でふと日の長さを感じますせわしく過ぎる日々の中に私とあなたで夢を描く3月の風に想いをのせて桜のつぼみは春へとつづきます溢れ出す光の粒が少しずつ朝を暖めます大きなあくびをした後に少し照れてるあなたの横で新たな世界の入口に立ち気づいたことは1人じゃないってこと瞳を閉じればあなたがまぶたのうらにいることでどれほど強くなれたでしょうあなたにとって私もそうでありたい砂ぼこり運ぶつむじ風洗濯物に絡まりますが昼前の空の白い月はなんだか綺麗で見とれました上手くはいかぬ事もあるけれど天を仰げばそれさえ小さくて青い空は凛と澄んで羊雲は静かに揺れる花咲くを待つ喜びを分かち合えるのであればそれは幸せこの先も隣でそっと微笑んで瞳を閉じればあなたがまぶたのうらにいることでどれほど強くなれたでしょうあなたにとって私もそうでありたい
March 9, 2010
コメント(200)
-
1995.3.8-2010.3.8
昨日は久しぶりに実家に行きましたが、実家から離れてちょうど15年の日だったこともあり、いろいろ思い出しました。神戸の震災から少したったころで、これはこれで大変でしたし。自分自身は海外赴任のために、てんやわんやでした。さっき航空会社の時刻表を見たところ、北京へ行くのに、JALもANAも成田から2便、羽田から1便、大阪から1便1日にこれだけ飛んでいるのだとおどろきました15年前、JALもANAも成田からは1便でした。大阪からは、JALが日・水・木・土に1便で、ANAは来ていませんでした。それだけ人の行き来も増え、お互いの国が発展しているのだと実感します。●90年代前半に行ったコンサートhttp://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/2003シンフォニーホール相当多いです。恵まれました。いまここまで来日する人が関西にはたしてくるのだろうか。東京・大阪・もう一か所というのが、東京・ソウル・台北 とか こんなアジアツアーになっているのではと、ちょっと思ったりもしています。●定点観測、わりと記憶をたどってもまじめにしているのかも。一人暮らしの出発点が15年前の3月8日です。いまは2人暮らしになりましたが、まだ1年もたっていません。15年前に1ドル100円から99円になって大きなトップニュースだったので記憶に残っていますが、今は1ドル90円でも平気な顔になっていますし、いろいろ鍛えられているのかもしれません。
March 8, 2010
コメント(0)
-
のぞみ200
朝の新幹線、新大阪駅はあわただしく週明けの様相。6時0分、3分、8分と3本立て続けに発車、指定席は名古屋からは満席と館内放送あり、自由席は京都でいっばいになりました。 朝寝坊ばかりの自分ですが、京都を過ぎたあたりで朝日が登っていくところを気分よく見ました。雨模様ばかりだった週末でしたのでなおさらのこと。 東京駅には8:30までに着き、普通に会社行けます。 単身赴任が長いかたには当たり前の光景でも、ちょっと物珍しく思えました。 みんな無口で居眠りの人、英会話の勉強している人、バソコンいじっている人、これから海外に出かけるため大きな荷物もっている人、いろいろです。 携帯の目覚まし時計が所々で鳴ったりしていてサイレントモードにあわててしました。 さっき豊橋を通過しました。 また曇り空に戻ってしました。 のぞみ200(号)は、とてもいい響きですね。
March 8, 2010
コメント(0)
-
久々の大阪シンフォニーホール
シンフォニーホールは15年前大阪市民だったころはよく行きました。 サントリーホールよりも前からあります。 90年代前半、ベルリンフィル、ポリーニ、リヒテルなど聴きにコンサートに出かけた場所。ホールに入るだけでもうれしいです。 ● 実家に戻る用事でもあればと案内いただいていました。 大阪シンフォニカー交響楽団 第60回名曲コンサート レーガー モーツァルトの主題による変奏曲とフーガ ベートーヴェン ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調 Op.19 ブリテン 青少年のための管弦楽入門 指揮 寺岡清高 ピアノ 三輪郁 ナレーション 加藤燿子 ウィーンで学ばれた指揮者とピアニストで留学中の時期も重なっているとか。 指揮者の練習のときにオーケストラのかわりにピアノで、そういうエピソードも楽しかったです。 ベートーヴェンが25歳のときに作曲されたピアコンはリズミカルで若々しいです。春先のこういう季節にぴったりのよう。明るい音色がいっぱいのピアノに感動しました。 ウグイス色のようなドレスも花を添えた感じです。 オーケストラとピアノが格調高く見事に調和していました。 第3楽章がずっとあたまで鳴っています。 聴けて本当によかったです。 この模様は21日の夕方、NHK‐FMで放送予定あります。
March 7, 2010
コメント(0)
-
こどもの旅
乗り物がやっぱり好きで気が済むまで乗ってみたいということあります。 行くあてもなくということではなく行く目的地があってのことですが。 こどものような気分です。 3日ほど前になんとかリーズナブルにならないかといろいろネットでも見ました。 18切符は3月初旬から使えること、ムーンライトながらは季節列車になり、この週末は走っていないこと、いろいろ知らなかったこともありました。 結局17時に大阪駅から歩いて行ける、ザ・シンフォニーホールに行けばいいので、 のんびり雨の日の東海道の今の風景を楽しんでいます。 東京7:24発の普通電車は特急「踊り子」と同じ車両で快適でした。(写真参照) 熱海9:37発に乗り換え、静岡県の島田が終点でした。 曇り空のなか時々見える海は癒されました。 島田11:29発に乗りました電車は3両編成でそのわりに混雑していてようやく座れる状態でした。 浜松12:19発の普通電車はシートが横ならびでなく進行方向に向いて座れるので快適です。 もうすぐ豊橋に着きます。 豊橋13:03発は快速電車で大垣まで行きます。 その後米原でもう行き姫路行きの新快速に乗ればちょうどいい時間にホールに行けそうです。 こんな気分でベートーベンのピアノ協奏曲第2番op.19を聴いたら楽しいだろうなあと思っています。
March 7, 2010
コメント(2)
-
Op.19という名前にこだわって
19歳に戻りたいとか、子供になりたいとか、そんな感じでもないのですが、Op.19というキーワードをもとに、いろいろ検索していたらおもしろかったです。ベートーヴェンのOp.19ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調プレトニョフ(pf)アバド指揮ベルリンフィル(第1楽章)http://www.youtube.com/watch?v=aSXOKHbzw48ペライア(pf) (第1楽章)http://www.youtube.com/watch?v=aP_2QOGd2_4アルゲリッチ(pf) (第3楽章)http://www.youtube.com/watch?v=08NDvgGAxR8 (第1楽章)http://www.youtube.com/watch?v=y-nw1eNRwAM&NR=1ショパンのOp.19ボレロルービンシュタインhttp://www.youtube.com/watch?v=km4trfKIcJYアシュケナージhttp://www.youtube.com/watch?v=3F1ny5bgeNk&feature=relatedメンデルスゾーンのOp.19無言歌集NO.3 狩の歌リヒテルhttp://www.youtube.com/watch?v=GDB4IwYW37Eバレンボイムhttp://www.youtube.com/watch?v=lHVdJAed8_4&feature=PlayList&p=DF65C522375E620C&index=2No.5 ピアノアジタート(眠れぬままに)リヒテルhttp://www.youtube.com/watch?v=tJA8KVeHv34バレンボイムhttp://www.youtube.com/watch?v=sAA9Llwx-rU&feature=PlayList&p=DF65C522375E620C&index=4 シューマンのOp.19花の曲リヒテルhttp://www.youtube.com/watch?v=6bn3PdTyj0Q作品番号も若いので若かりしころの作品がいろいろ並びおもしろかったです。意識していなかったのに、去年の今頃弾いていた曲もでてきてびっくりです。まじめに練習しないといけません。今日人前で弾いたのはOp.15でしたが、Op.19の曲も弾けるといいですね。
March 6, 2010
コメント(4)
-

訓読み「みつぎ」
昨日の夜、東京駅前の本屋さんへ講演会を聴きに行きました。「税」は「ゼイ」と音読みで普通読みますが、「みつぎ」という訓読みがあること、はじめて知りました。http://www13.atpages.jp/shimapucchi/newpage16.htmlそういうテーマの講演会ではありませんが、耳に残りました。おととい同じ場所で講演会をされた方は、おかねをばんばん刷って、たくさん使ってデフレから脱却しましょうという論調、ハイパーインフレなどおこるはずがないという説明。(本だけ読んで聴いていませんが、書いてある内容からはたぶんこのようなこと)きのうの講演会では、国の赤字国際の累計額が、GDPの額に近づくとたいへんなことになる、2020年にIMFがもっとも危険な国として警鐘しているとのこと。戦後まもなくの新円切り替えは、GHQがやったのではなく日本政府がしたこと、多くの人が勘違いしている、という内容のなかでさまざまなお話。かたや、公認会計士・経済アナリスト、かたや元大蔵官僚・元国会議員。どちらも本は売れている。本屋さんは儲かればいいのでしょうけど、2人で対談でもすればいいのにと、ちょっとまじめに考えてしまいました。なにが正しいかということ、なにが真実なのかということも含めて、自分自身の軸をもたなければと強く感じました。官僚と政治の現場にいた、どちらからの立場でも、物をみてきた数少ない人として活躍していただきたいものと思っております。オリンピックのメダルの数だけではないですが、となりの国を追いかけるようになる時代になるとは、想像もできませんでしたし。1984年の株価と2010年の株価がほぼ同じということも教わりました。1Q84の村上春樹さんの小説ではありませんが、不思議な世界を感じました。●夜の部のつづきは、10年以上お世話になっている異業種交流会へ。主催者が九州の熊本に転勤するということで、ごあいさつだけでもと思って、今年で設立20年ということになりお祝いもかねて。伺ってよかったです。30代前半の1990年代後半、もっと上昇志向もありましたが、2010年になり、年は相応にとり、身を固める人は固め、転職してキャリアをあげている人もいれば、 弁護士さんとかは独立開業始める人もいたり、同じ会社に長くいながら経験をつんでいる人もいれば、少しおはなしするだけでもたくさん元気をもらった感じもします。年賀状だけの人と、10年ぶりくらいにあったりすると、うれしくなったりして、いろいろお祝いのメッセージをいただいたりで、こういう集まりの存在そのものに感謝しています。会場の高田馬場近くの居酒屋さんのトイレにあったもの。健康十訓少肉多菜 少塩多酢 少糖多果 少食多噛 少衣多浴 少言多行 少欲多施 少憂多眠 少車多歩 少憤多笑 やはり元気で健康でいることが一番だとおもい、あらためて読み直してみました。最近つくづくそうおもいます。(ご参考)http://www008.upp.so-net.ne.jp/jasmine/kenkoun.htmlhttp://blog.chase-dream.com/2009/01/16/514ほかのこともいろいろ書いてあって参考にしようとおもうブログもありました。
March 6, 2010
コメント(0)
-
ハワイアン=月見
ハワイアンバーガーというのが第三段のようで、いただきました。 夜遅くですがテキサスバーガーの時のように在庫切れになることなく普通に出てきました。 月見バーガーの発展型か辛口にしたのかという印象。 スパイシーで新たな境地にたったようなテキサスバーガー、捻りすぎた感じで妙な味だったニューヨークバーガー、それよりは庶民的な気がしました。 ネーミングの根拠はよくわかりませんが、ミーハーな人間にとってはしっかりお客になった感じ。 食べた日はまた雨降りでした。 頭のなかで鳴っているBGM シューマン=リスト 「献呈」 シューマン 子供の情景より「満足」 満足… キラキラした感じで弾けるといいです。 ガチャガチャにならず、美味しいという感じにでもなれば。 良くできた曲だとつくづく思います。
March 4, 2010
コメント(0)
-
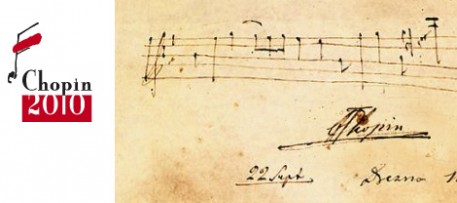
海の外のChopin2010
5月に開催されるラフォルジュルネのショパン・イベントのことは、先日少し書きましたが、海の向こうではどうなっているのだろうと、気になりました。2/2-3/1はショパン生誕200年のバースデーコンサートをしているみたいです。2/22 ピアノ:ブレハッチ 指揮A.ヴィット ワルシャワ国立フィルハーモニー 2/23 ピアノ:ポゴレリッチ 2/24 ピアノ:ペライア⁄アンデルシェフスキ 2/25 ピアノ:G.オールソン 2/26 ピアノ:ケナー⁄オレイニチャク 2/27 ピアノ:キーシン⁄G.オールソン 2/28 ピアノ:バレンボイム 3/01 ピアノ:ユンディ・リー⁄ダンタイソン⁄アルゲリッチ なんとも豪華ですね。ラフォルジュルネ・ワルシャワというのも夏にあるそうです。旅行会社のホームページに書いてありました。第16回ショパンコンクールは、10/2-23まで開催されます。オープニング・コンサートは10/1にあり、内田光子さんが演奏されるとか。http://chopin2010.pl/en.htmlポーランドのChopin2010、ご本家のこういうものも見つけました。指をくわえているだけですが、指をくわえているだけでも楽しいです。しばらく楽しめそうです。●ペライアとダンタイソンはメンデルスゾーンの無言歌のコンサートがやたらこれまでに印象残っていますが、幻想的なショパンの演奏も聴いてみたいです。内田光子さんはソナタの3番コンサートで1度だけ聴いたことあります。曲の組み立て方がなんて鋭い方なのだろうと惹きこまれたこと覚えています。アルゲリッチはどうしても演奏聴きたくて2年前別府まで行きましたが、目の覚めるようなスケルツォ3番聴いてみたいです。ショパンのピアコン1番はいろいろ聴いても、結局アバド指揮でアルゲリッチ(ピアノ)のものになったりします。BGM; ベートーヴェン ピアノ三重奏 第7番 変ロ長調 Op.97 「大公」 アシュケナージ(ピアノ)パールマン(ヴァイオリン)リン・ハレル(チェロ) 家の中でなっているものを静かに聴いています。 他力本願になるのもそれはそれでいいと思っています。
March 3, 2010
コメント(0)
-

桃の節句の前に
銀座5丁目の鳩居堂さんへ行くと雛人形のレターセットや飾り物でいっぱい。めったにお店に入らないのですが、季節感あふれるものをみるとうれしくなります。郵送するものもここ2-3日のあいだにあるので、いろいろ選んでみました。http://www.kyukyodo.co.jp/products/index_season.htmlそれにしてもこの歳時記、本当に1年中いろいろあるのだなあと感じます。このお店は年末にぽち袋を探しにきたりよくするのですが、春夏秋冬がはっきりしている日本のよさを感じます。偶然お店にたどりついたのですが、偶然ではなかった感じもします。BGM; ショパン 舟歌 Op.60 ピアノ:フリードリッヒ・グルダhttp://www.youtube.com/watch?v=4R8I7od5AGoグルダのCDは、一番晩年に出したプライベート録音に近いシューベルトの即興曲と楽興の時をよく聴きます。自分のためにピアノを弾くということもいいですね。
March 2, 2010
コメント(0)
-
ショパンの誕生日にラフォルジュルネのプログラムを眺める。
ショパンが生誕200年で3月1日が誕生日。昨日もすてきなレストランで、ショパンのエチュード・舟歌・スケルツォ・幻想即興曲とか聴かせていただきましたが、いくつか聴いてみたくなりました。さっきから、ラフォルジュルネ2010のプログラムを眺めています。I'univers de Chopinというフランス語のタイトルで、ショパンの宇宙 ということで5月連休に開催されます。 http://www.lfj.jp/lfj_2010/http://www.lfj.jp/lfj_2010/timetable/ショパンのプログラムだけでなく、ロマン派の作曲家もバッハもフランスものも紹介されます。プログラムを見ていて、ショパンと他の作曲家の組み合わせプログラム、いい感じな気がするもの、いくつか見つけましたので紹介します。 No.121モーツァルト:2台のピアノのためのソナタ ニ長調 K.448ショパン:2台のピアノのためのロンド ハ長調 op.73シューマン:4手のための子供の舞踏会 op.130よりNo.173モーツァルト:ピアノ三重奏曲 ホ長調 K.542ショパン:ピアノ三重奏曲 ト短調 op.8No.163ショパン:ノクターン 嬰ハ短調 op.27-1シューマン:8つのノヴェレッテop.21より 第2番 ニ長調、第8番 嬰へ短調ショパン:ノクターン ヘ長調 op.15-1アルカン:悪魔的スケルツォ ト短調 op.39-3ショパン:幻想曲 ヘ短調 op.49No.153"フォーレ・ショパン 前奏曲集" 曲目 フォーレ:前奏曲第1番 変ニ長調 op.103-1ショパン:前奏曲第15番 変ニ長調 op.28-15フォーレ:前奏曲第2番 嬰ハ短調 op.103-2ショパン:前奏曲第10番 嬰ハ短調 op.28-10フォーレ:前奏曲第7番 イ長調 op.103-7ショパン:前奏曲第8番 嬰へ短調 op.28-8ショパン:前奏曲第13番 嬰ヘ長調 op.28-13ショパン:前奏曲第14番 変ホ短調 op.28-14フォーレ:前奏曲第6番 変ホ短調 op.103-6ショパン:前奏曲第19番 変ホ長調 op.28-19ショパン:前奏曲第20番 ハ短調 op.28-20フォーレ:前奏曲第8番 ハ短調 op.103-8ショパン:前奏曲第1番 ハ長調 op.28-1ショパン:前奏曲第2番 イ短調 op.28-2フォーレ:前奏曲第4番 ヘ長調 op.103-4フォーレ:前奏曲第5番 ニ短調 op.103-5ショパン:前奏曲第21番 変ロ長調 op.28-21フォーレ:前奏曲第3番 ト短調 op.103-3ショパン:前奏曲第22番 ト短調 op.28-22オハナ:前奏曲第23番フォーレ:前奏曲第9番 ホ短調 op.103-9No.181メンデルスゾーン:歌の翼に op.34-2メンデルスゾーン:挨拶 op.19-2メンデルスゾーン:朝の挨拶 op.47-2メンデルスゾーン:旅の歌 op.34-6メンデルスゾーン:夜ごとの夢に op.86-4リスト:ラインの美しき流れのほとりリスト:唐檜の木はひとり立つリスト:私はまさに絶望しようとしたリスト:毎朝私は起き、そして問うショパン:17のポーランドの歌 op.74より 第1番「おとめの願い」 第5番「彼女の好きな」 第6番「私の見えぬところに」 第3番「悲しみの川」 第15番「花婿」 第16番「リトアニアの歌」 第14番「指環」 第10番「闘士」 No.362ショパン:スケルツォ第1番 ロ短調 op.20シューマン:ダヴィッド同盟舞曲集 op.6 No.353J.S.バッハ:前奏曲第3番 嬰ハ長調 BWV872(平均律クラヴィーア曲集第2巻より)ショパン:前奏曲第15番 変ニ長調 op.28-15「雨だれ」J.S.バッハ:前奏曲第22番 変ロ短調 BWV867(平均律クラヴィーア曲集第1巻より)ショパン:前奏曲第16番 変ロ短調 op.28-16J.S.バッハ:前奏曲第17番 変イ長調 BWV862(平均律クラヴィーア曲集第1巻より)ショパン:前奏曲第17番 変イ長調 op.28-17J.S.バッハ:前奏曲第12番 ヘ短調 BWV857(平均律クラヴィーア曲集第1巻より)ショパン:前奏曲第18番 ヘ短調 op.28-18J.S.バッハ:前奏曲第7番 変ホ長調 BWV876(平均律クラヴィーア曲集第2巻より)ショパン:前奏曲第19番 変ホ長調 op.28-19J.S.バッハ:前奏曲第2番 ハ短調 BWV847(平均律クラヴィーア曲集第1巻より)ショパン:前奏曲第20番 ハ短調 op.28-20J.S.バッハ:前奏曲第21番 変ロ長調 BWV866(平均律クラヴィーア曲集第1巻より)ショパン:前奏曲第21番 変ロ長調 op.28-21J.S.バッハ:前奏曲第16番 ト短調 BWV885(平均律クラヴィーア曲集第2巻より)ショパン:前奏曲第22番 ト短調 op.28-22J.S.バッハ:前奏曲第11番 ヘ長調 BWV856(平均律クラヴィーア曲集第1巻より)ショパン:前奏曲第23番 ヘ長調 op.28-23J.S.バッハ:前奏曲第6番 ニ短調 BWV851(平均律クラヴィーア曲集第1巻より)ショパン:前奏曲第24番 ニ短調 op.28-24No.373ショパン:ピアノ三重奏曲 ト短調 op.8リスト:トリスティア (巡礼の年 第1年「スイス」の「オーベルマンの谷」による編曲)チケットとりにくいでしょうし、そんなにたくさんコンサートに行かないかもしれませんが、見ているだけで楽しくなりました。 http://concertdiary.blog118.fc2.com/blog-category-39.html先にナントというラフォルジュルネの本拠地で、聴いてこられた、音楽評論家東条せんせいのブログにいくつかコンサートの感想がありました。(このせんせいと、ときどきコンサートホールでニアミスしてしまいます。顔はわすれられていないみたい・・・)BGM: ショパン 幻想曲 Op.49 ピアノ:クリスチャン・ツィメルマン やっぱりこれにしよう。 ミクシイで管理人も僭越ながらさせていただいていることだし。 なんだか静かに聴きたいです。
March 1, 2010
コメント(2)
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
-

- いま嵐を語ろう♪
- 嵐ライブ2026生配信を見逃さないため…
- (2025-11-23 20:15:02)
-
-
-

- 好きなアーティストは誰??
- 今日の朝はヒゲダンを聴きました☆&サ…
- (2025-10-26 11:00:38)
-
-
-

- 今日聴いた音楽
- ☆乃木坂46♪井上和×弓木奈於『のぎ鍋…
- (2025-11-24 05:16:13)
-







