2024年01月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
同僚の昇任
今日は所属先の大学で教授会があり、同僚のN先生が准教授がから教授に昇任されました~。 実は私が今回の昇任人事の主査でありまして、審査委員会を起ち上げたり、業績カウントをしたり、所見を書いたりといったことをしてきたので、今日の教授会での審理はちょっとドキドキ。まさかこちらの提案をひっくり返されるようなことはないだろうけど、書類の不備とかで流れる、なんて可能性はゼロではないからね。 というわけで、無事、教授会での承認をとりつけ、N先生の教授昇任が決まって、ホッとしました。 待機していたN先生に電話で、無事昇任のことを伝えると、本人も大喜びで。よかった、よかった。 大学の雑務も色々だけど、後輩同僚の昇任をサポートするのは、まあ、意義深いし、喜ばれることなので、責任重大だけど、話が来れば、避けたいとは思わないよね。先輩の責任として、引き受けて当然だ。 とにかく、今日はN先生にとっていい日になったし、私も嬉しく思っているところなのでございます。
January 31, 2024
コメント(0)
-
恩師の命日
今日は1月30日か・・・。じゃあ、私の小学校時代の恩師・山本茂久先生の祥月命日だ。 当時私は18歳。大学受験の頃だったのかな? 自宅にいて勉強をしていたら、父が変な時間に家に戻って来て、何やら母と話をしていて。それで父から、山本先生が亡くなられたのを聞いたのでした。享年53。心臓発作で、その日の朝、朝会中に倒れて救急車で病院に運ばれたものの、残念ながら。父も母も、私が小学校以来、先生の影響を非常に強く受けていたのを知っていたので、どう伝えようか逡巡していたのでしょう。 それ以前に病気で苦しんでいたとか、そういう前もっての話があれば別、あまりにも突然だったので、先生の死をどう受け止めていいのか、分かりませんでしたね。 それから一人でお通夜に行って。帰る前に、その日先生が倒れたという、小学部のグラウンド前のその場所に行って。真っ暗で。それから、電車に乗って泣きながら自宅に戻ったのでした。人前で、しかも電車の中で泣いたなんて、一生に一度のことだろうな。 あれから42年。もうとっくに先生の年齢を越えてしまいました。 あれ以来、私は毎年、2月の第一日曜日をお墓参りの日と決め、一度も欠かすことなく墓参を続けてきた。だから今回で42回目の墓参ということになるのかな。 私には、人生の師が4人居て、そのうちのお2人には既に著書を捧げております。そして一か月後に出る本は、3人目の師匠に捧げている。だけど、まだ山本先生には捧げてないのよ。 でも、先生に捧げる本は、もう既に9割方完成しております。来年には多分、完成することでありましょう。そうしたら、私は4人の師匠全員に対して恩返しをしたことになる。これが私の、研究者生活を始めた時からの計画だったものでね。 山本先生には、それまで待っていただくことにして、今年もまた、今週末に迫った日曜日の墓参に向け、週末は実家に戻る予定でございます。
January 30, 2024
コメント(0)
-
市民講座を頼まれる
県内某市の市役所さんから、市民講座の講師を頼まれちゃった。 この市では前にも講師を引き受けたことがあって、その時はジャズの話をしたんだよね。聞きに来る人の大半は60代から70代くらいの、定年過ぎた世代の人たちで、その人たちにとってはジャズは青春の音楽だから、結構評判は良かった。 調べてみたら、それは2015年の話。もう9年も昔のことだよ! 時間の経つのは早い! で、今回はアメリカ文学関連のことで話をしてくれ、という要請だったんだけど、それならばやっぱり今、私の主たる関心事であるアメリカの自己啓発本の話をしようかなと。 とまあ、そんな風にお返事しようかなと思ったのだけど、そんなようなことを家内に話したら、それは違うのではないかと。 60代、70代の人たちにとって、自己啓発本というのは既に縁遠いと。むしろその人たちの世代は、まだ文学なるものが重い意味を持っていたのだから、王道を行って、アメリカ文学そのものの話をした方がいいのではないかと。 なるほど。そうかもね。 ということで、考えを改めまして、オーソドックスなアメリカ文学の話をすることにしました。 考えてみれば、今やもう、所属大学ではアメリカ文学の講義をする機会すらないからね。市民講座で、私も年寄り、聴衆も年寄りという状態の中、アメリカ文学の話をじっくりするのもいいかもしれません。 そうしましょうかね。
January 29, 2024
コメント(0)
-
またもや悪だくみ
新著の出版もカウントダウン状態になり、後期の授業もそろそろ終わるタイミングで、本来であれば、年度末に出す予定の紀要論文を書かなくてはならないのですけれども、やっぱ新作の論文を書くというのは非常に疲れる。 で、面倒臭いなあと思っていたところで、またちょっと悪だくみを思いつきまして。 今から15年くらい前に、自分が指導しているゼミ生のために、卒論の書き方を指南する本を、所属大学の出版会から出版したことがあるのですが、それ、結構評判が良くて、何回か増刷した本なんですわ。 ところが、その本の在庫がそろそろ尽きてきたという連絡があった。 となると選択肢は二つあって、このまま大学出版会から再度増刷するか、はたまたいっそ一般の出版社から新版を出すか。 前者の場合ですと、販路が極端に限られてしまう。せっかく評判のいい本なのに、知る人ぞ知る状態。だったら、この際、一般の出版社から新版として出した方が、メリットがあるかなと。 「悪だくみ」というのは、このことね。 っつーことで、にわかにやる気が出てきたワタクシ。一般出版社からの出版を目指して、一部書き直しをしようかなと。 で、そういう思いで旧著を取り出してみると、さすがにこの15年ほどの時代の変化が如実に感じられる部分がある。 特に、インターネット利用に関する記述が、ちょっと古くなっているかなと。だって今はAIの時代だからね。AI時代に入った今、卒論を書く上でも、インターネットの利用の仕方が違ってくるわけよ。そこを大幅に書き換えないと、現代の卒論執筆指南とは言えないよね。 ま、そんなことを思いながら、一部改稿をし始めたのですが、何しろこちらは土台があるものを書き直しているだけだから、新作の論文を書くよりよっぽど楽。 で、人間というのは、楽な方に流れるのよ! ということで、本来であれば新作論文を書くべきところ、何故か急に古い原稿の改稿に取り組み出しちゃったというね。ダメだね、ワタクシも・・・。 とはいえ、夢は広がる。この新版、どこから出版しよう? 形態は? やっぱり新書として出すのがいいかしら? なーんてね。 まあ、新作論文の執筆がますます遅れそうですけど、仕事はしているんだから、許してね!
January 28, 2024
コメント(0)
-
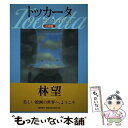
古本趣味の危機
昨日、古本カフェのようなところに行ったことを書きましたが、その時、林望先生の『トッカータ』という本を古本として売っていることに気づきまして。「洋画編」と「日本画編」の二種があって、それぞれ700円だったかな?これこれ! ↓【中古】 トッカータ光と影の物語 洋画篇 / 林 望 / 文藝春秋 [単行本]【メール便送料無料】【あす楽対応】【中古】 トッカータ光と影の物語 日本画篇(日本画篇) 光と影の物語/林望(著者) これは、何らかの洋画、ないしは日本画を見て、その絵からインスピレーションを得て、林先生が短編小説をものする、という出版社サイドからの企画ものだったのですが、刊行年は2001年でしたかね。ふうむ、今から20年以上前ですと、こういう企画ものが成立するほど、まだまだ日本の出版界はイケイケだったのでしょうか。 しかし、この企画を林先生に持って行ったというのは、出版社(文藝春秋)のお手柄というか、いかにも林先生がノリノリで引き受けられそうな企画だなと。 で、そういうことなら、是非買っちゃおうかなと思ったのですが、その時は考え直して保留にしました。アマゾンで見たら、もっと安い出品があったもので、ちょっと日和見したのよ。 しかし、後で考えてみて、わしも古本者として堕落したもんだなと。古本者にとって一番大事なことは「一期一会」でありまして、買うべき本に出合ったら、躊躇なく買うのが筋。それを知っていながら、二の足を踏んで買わなかったのだから、もう、古本者とは言えない。 でも、最近、自分はもう古本者ではないなと思うことが増えました。いい古本屋に行っても、馬鹿買いしなくなったもんね。「これを読む暇が自分にはあるのか?」「家にこれを置くスペースはあるのか?」ということが脳裏をよぎって、つい、買うのを躊躇ってしまうことが増えた。 歳をとるって、嫌ね・・・。 でもね、まだ私には夢があるの。引退してから、もう一度、シェイクスピアあたりから英米文学に本格的に向きなおろうかなというね。イギリスに行って、ちゃんとした革装のシェイクスピア全集とかを古本でどーんと買って。 ちょうどシャーロック・ホームズが探偵業を引退して養蜂に精を出す、みたいな感じでね。 そんな夢のような老後が来ればいいなあ・・・。
January 27, 2024
コメント(0)
-
豊川稲荷
大学からお休みをいただいて、一日、豊川稲荷に行ってきました。1月もほとんど終わりかけですが、まあ、ギリギリ新しい年の新しい月ということで、豊川稲荷に今年の成功祈願をしに。 その前に、豊川インター近くにある「鴨屋」というところでお蕎麦をいただいたのですが、とろろ飯とか、鴨肉を焼いたものなんかのセットになっていて、なかなか楽しいものでした。ここ、自宅近くにもある「キャナリイ・ロウ」というイタリアンの店の姉妹店なのね。 豊川稲荷は、数年前に一度行ったことがあるのですが、今回改めて行ってみると、前回のことを完全に忘れていたという。もう、まったく初めて訪れる場所って感じ。記憶力がやばいわ。大丈夫か、わし? しかし、とにかくお参りをして、例のキツネさんがたくさんいらっしゃる場所も再訪してきました。キツネさんにお賽銭をはずんでおきましたけれども、ちゃんといい運を持ってきてくれるでしょうか。 で、帰りに参道で稲荷ずしをお土産に。 で、さらに帰りに古本とコーヒーの店「BookCup」というところに行って、おいしいコーヒーをいただきつつ、古本を物色。今日は買うものがなかったのですが、ゆったりとした時間を過すことができました。 で、帰宅後、買って帰った稲荷ずしを夕食に食べたのですが、色々な味の稲荷ずしがセットになった奴だったので、味も単調にならず、面白い夕食になりました。稲荷ずしって、何となくオヤツ感覚というか、正式な食事というイメージがないのですが、今回本場のものを食べてみて、たまにだったらこれもありかなと。 っつーことで、今日は一日、キツネ・デーとなったのでした。
January 26, 2024
コメント(0)
-
上を見てもキリがないけど、下を見ても・・・
ちょっと必要があって、ヘミングウェイのとある有名な短篇を論じた論文を探しているのですが、なかなかいいのがないのよ。 探しているのは、「The Doctor and the Doctor's Wife」という有名な短篇を論じた論文なんですが、これほど有名な作品なのに、案外、単体では論じられていない。 で、そこを敢えてさらに探すと、何本かは出て来るわけ。 で、その出てきた論文を読んでみるのだけど、これがまあ、スゴイのよ。 何がスゴイって、もう、論文の体をなしてないものばっか。 だって、「論文」と言い条、あらすじが書いてあるだけなんだもん。あらすじを書いて、ちょっとその解説をして、それで終わりっていう・・・。 しかも、そのあらすじがきちんとしたものならいいんだけど、全然ダメダメで、あらすじにすらなってないっていうね。で、あらすじがつかめていないから、その解説も見当はずれっていう。 これで文学論文を書いたつもりになっているのだとしたら、犯罪だよね・・・。 私ら、学生時代から、スゴイ先生を大勢仰ぎ見てきて、いつか自分もああいう文学者になりたいと憧れてきたもんだけど、それは上を見ていたからそうなのであって、下を見たら、下の方にもすごいのがいたと。 それにしても、仮にも○○大学の教授と名乗っている人が、こんなのを書いて論文ですなんて言ってちゃいかんよね! もう、ビックリだわ。これじゃ、文学研究なんて必要ないと言われても、仕方ないな。
January 25, 2024
コメント(0)
-
大河ドラマの低迷打開策『大河ドラマ48』
定年後、すっかりテレビっ子になり、しかもNHKの番組ばかり見ている先輩同僚のK名誉教授。非常勤で大学に来られる度に、私とコーヒーを飲みながらテレビ番組談義に花が咲くのですが、そんなK教授曰く、どうも大河ドラマが面白くないと。 昨年の家康もイマイチだったようですが、それでもあれは戦国武将、人生のイベントには事欠かない。対して今年の大河は紫式部の恋模様ですから、これで1年持つのかと。 要するに、もう描くべき歴史的事件なりが底をついたということですよね・・・。 で、K教授と話していたんだけど、もう、アレをパクるしかないんじゃないかと。 何をパクるかって、ほら、あの『24』よ。実際の事件の一時間ごとに、ドラマも進行していくという奴。 たとえば『関ケ原48』とかいうのはどう? 天下分け目の関ケ原の戦いを48時間に分けて、一時間ごと、48回で描くという。『ポツダム宣言受諾48』とか。 よく知られた歴史的出来事も、それが起こっている最中の48時間を刻一刻と描いて行ったら、緊迫感があっていいんじゃない? ね。我ながらいいアイディア。NHK職員のどなたか、もし当ブログをお読みでしたら、上層部に耳打ちしてあげて~。
January 24, 2024
コメント(0)
-
那須川天心、からの表紙色校正と惹句完成
那須川天心選手のボクシング転向3戦目、ルイス・ロブレス戦を観たのですが、今回はなかなか良かった。 前の2戦は、まだまだ線が細いというのか、まだボクサーになり切ってないような印象を受けたのですが、今回は上体の筋肉の付き方もよかったし、いいジャブ、いいパンチを当てていて、急速にボクサーっぽくなっていた。今回もリング上で相手をKOしたわけではないけれど、4ラウンド開始前に相手が棄権する形でのTKOでしたし、あのまま続けていたら、いずれはKOできたでしょう。 それにしても、那須川選手の、相手パンチの見切りが凄いね。この距離なら届かないと見切ったら、まったく頭を動かさないもんね。余計な動きがない。これであと、もうちょいパンチ力が付いたら、確かに結構いい線行くのではないでしょうか。いい試合を見せてもらいました。 さて、それはともかく。 2月に出る拙著の表紙の色見本が届きまして。 色見本というのは、実際の表紙カバーのテスト版みたいな感じで、ほぼ、このまま表紙になるというものなんですが、派手さこそないものの、結構インパクトのある表紙で、平台で目立つのではないかと。 それから、拙著の惹句(=宣伝文句)も完成しましてね。 今回は、すごいよ。日本で一番有名なコピーライターであるあの方が、拙著のためにコピーを考えてくれたんですから! 私も偉くなったもんですわ。この素敵な惹句が帯について発売されるわけですから、強力な販促になることでしょう。楽しみ、楽しみ。 那須川選手もいい試合をしましたが、これから書店の平台という名のリングに上がる拙著にも、大いに頑張ってもらって、チャンピオンになってもらいたいものでございます。
January 23, 2024
コメント(0)
-
父のマフラー
このところ、マフラーをするというのが、ちょっと自分的にブームになっておりまして。 というのは、先日、実家に戻った際、父のマフラーを何本ももらってきたから。それ以前にも何本かもらったことがあったので、今、わが家には父のマフラーが7,8本もある。これをとっかえひっかえ、通勤時に首に巻いているわけ。 父は服道楽というのか、おしゃれな一面があり、スーツなんてほとんどすべてオーダーだった。「つるし」でスーツを買うなんて、父のよくするところではなかったんですな。まあ、そういう時代だったということもあるのかも知れませんが、「つるし」でしかスーツを買ったことのない私なんかと比べてもよほどおしゃれだったというべきでありましょう。 っていうか、今時、「つるし」なんて言葉、若い人に通じるのかな? まあ、それはともかく、そんな風ですから、父のマフラーなんてすべてカシミヤですよ。だから肌触りが違う。柔らかくて、暖かい! でまた、色やデザインもしゃれているのよ。私なんぞ、服といったら黒・グレー・紺ばっかりですけど、そういう暗い色の服に、父譲りのちょっと派手なマフラーを合わせると、いわゆる差し色というヤツで、各段におしゃれになる。 というわけで、父の遺品のおかげでにわかにおしゃれなジェントルマンに変身してしまったワタクシ。 それもそうなんだけど、父の遺品というのはいいね! 亡くなった父を身近に感じられる。父のおかげで暖かくしていられると思うと、余計にね。
January 22, 2024
コメント(0)
-
ここへきてコロナの流行
この前の水曜日、うちの科のスタッフ会議がありまして、新年初めの顔合わせがあったのですが、その翌日、スタッフの一人が高熱を発して倒れ、医師からコロナ罹患の診断を受けたとの連絡が。 で、おやおや、と思っていたら、今日、その時に会議に同席していた別なスタッフから、急に全身に痛みが起こり、医者に行ったらコロナと診断されたと。そんな自己申告が入って参りまして。 ええーーー! やばいじゃん、うちの科。明日以降も、次々とスタッフが倒れていったら、科としてはちょっと大変なことになりそうな。 っていうか、ひょっとしてワシも? 今のところ、自覚症状は一切なし。まあ、ワタクシの場合、インフルエンザに罹った人とずっと同じクルマで移動していて、それでもうつらなかったほどの猛者ですので、コロナにも罹患しにくいのではないかと勝手に自負しているんですけど、どうなんでしょうか。 ま、ワタクシに関して言えば、拙著の再校の仕事も今日で終わってしまったし、差し当たりすぐにやらなければならない仕事もないので、とりあえず今、倒れても大丈夫かな。 でも、もちろん病気には罹らないのに越したことはない。用心、用心。
January 21, 2024
コメント(0)
-
拙著最後の校正作業
2月に出る拙著の最後の校正作業をやっております。 これは再校なので、既に一度校正をして、修正済みのゲラなんですけど、それでもまだ思わぬところに修正すべき点が出て来るのよね~。 たとえば、「まえがき」の辺りで「出版社から原稿執筆を以来される」なんて書いてある。もちろん「依頼される」の誤りなんだけど、これ、最初の原稿の時点で何度も読み直して「これでよし!」と判断して提出し、それをプロの校正さんがチェックし、そのチェック済みのゲラを私も散々チェックした挙句、それでもちゃっかり残っていたミスだからね。 こういうミスがあると、ほんと、ゾッとするわ。プロの校正さんも含め何回厳しいチェックをしても、こうやってすり抜けるものがあるんだからね。 ちなみに、今回の再校チェックで著者校了となり、私の役目はおしまい。ここから先は出版社任せになるんだけど、この先の展開は案外早くて、もう2月13日には見本が出る。で、その10日後くらいには市販されると。 ひゃー、嬉しいねえ。自分の本が出るというのは、何度体験しても嬉しい。今度のはどうだろうか、売れるだろうか、書評は出るだろうか、評価されるだろうか・・・なんて、そんなことを思いながら反響を待つ楽しさよ。アーニャ、ワクワク! ということで今日と明日、再校チェックに最善を尽くしたいと思います。頑張るぞー!
January 20, 2024
コメント(0)
-

多井学著『大学教授こそこそ日記』を読む
多井学さんが書かれた『大学教授こそこそ日記』なる本を読了しましたので、ちょいと心覚えを。 これ、『交通誘導員ヨレヨレ日記』をはじめとする三五館シンシャから出ている一連のシリーズの一環として出ているもので、色々な職業の人の実体験から、外部からはなかなか見えないその職業の裏側というか、苦労話を暴露的に書くという本。私も前に『出版翻訳家なんてなるんじゃなかった日記』というのを読んだことがあって、それはそれで結構面白かった。で、今回の『大学教授こそこそ日記』ですが、これは先輩同僚のアニキことK教授からおススメされ、はい、と手渡されたもの。アニキに手渡されちゃったら読むしかないんでね。これこれ! ↓大学教授こそこそ日記 (日記シリーズ) [ 多井 学 ] さて、著者の多井学さんですが、これはもちろん身分バレを隠すためのペンネームであって、本名は別。上智大を出て、アメリカとカナダの大学・大学院を出た国際関係論の先生で、長野県のS短大に就職したのを始め、そこから国立の徳島大に移籍、さらにそこから関西学院大学に移籍して今日に至る、という経歴。ここまでわかれば、ちょっと調べれば本名はすぐに分かります。本もそれなりに出されている人ですね。専門書もあるけど、「大学教授になる方法」的な本もある。どの道、この手の本が書きたい人なんですな。 で、3つの大学、それも弱小私立短大、地方国立大、メジャー私立4大と、それぞれ異なるタイプの大学に勤めたことがあるというのがいわば強みで、それぞれの大学に勤めていた時期に経験したことを、面白おかしく書いている。それを読むと、それぞれの大学に特徴というか、くせがあって、そういう癖のある職場に適応しながら生きる大学教員の生態がよく分かります。 特に、私自身が国立大学に勤めているので、多井さんが徳島大学に勤めていた時の話はすごくよく分かる。となると、弱小私立大学に勤めている人、メジャー私立大学に勤めている人、それぞれ、この本を読むと「ある、ある!」となることでしょう。同業の人間からすれば「ある、ある!」だし、大学というところに関係がない人が読めば、「へえ、大学教授って、そういう職業なんだ」というのが分かるかも知れない。 ま、そんな感じで、「ある、ある!」と思いながら、軽くさらっと読んじゃった。 もっとも、最後のところで、多井さんが奥さんを亡くした経緯と、その後の辛い生活のことがちらっと書かれていて、愛妻家が妻を亡くすとこうなるんだ、というところがあり、そこはちょっと可哀想。私も愛妻家の一人として、奥さんには自分より長生きしてもらわないといかんなと、あらためて思った次第。 ということで、読んで特にためになるという類の本ではないけれど、大学教授の方、あるいは大学の先生になりたいなと思っている方には面白い本かもしれません。その程度のものとして、おすすめ、と言っておきましょうかね。大学教授こそこそ日記 当年62歳、学生諸君、そろそろ私語はやめてください/多井学【1000円以上送料無料】
January 19, 2024
コメント(0)
-
トランプ再選?
アメリカ大統領選、トランプ再選の目が出てきましたなあ。 少なくとも共和党に関しては、このまま圧勝しちゃいそうな感じ。相変わらず保守派の人たちに対する人気はあるからねえ。 問題は民主党だけど、バイデンだったら絶対に勝てない。バイデンに代わる若くて魅力的な人たらしが出てこない限り、このままトランプ再選で決まりじゃない? でもどうなのかな。今、民主党の候補者に、人たらしっているのかしら。どうなのかね。 だけど、トランプが勝つと、あの人はモンロー主義の人だから、ウクライナからは手を引きそうだな。ヨーロッパの騒乱には関わらないだろうから。 一方、イスラエル支持派だから、イスラエルの肩は持つ、そうすると、パレスチナ問題は一層こじれるでしょうな。 さらに、モンロー主義的観点からすると、東アジアにもあまり関心がなさそうだから、どこかの国が日本の領土を侵してきても、あまり積極的には関わらないでしょう。 そう考えると、日本としてはトランプ再選は、ちょっと怖いことになりそう。 民主党には、早くバイデンを引退させて、若い人たらしを候補者として立ててもらいたいものでございます。そうしないと、本当にトランプが勝っちゃうよ。
January 18, 2024
コメント(0)
-
朝日の力
私の古本道の師匠である岡崎武志さんがブログに書いていらしたんだけど、朝日新聞の「折々のことば」の欄に、岡崎さんのご著書の中のある文章が引用されたと。 そうしたら、知り合いの編集者とか恩師とかから祝電の嵐であったと。 まあ、そういうことを書かれていたのだけれど、なるほど、そうなんだ~。 朝日新聞って、私にはまったく縁がない新聞で、取ったことがないので本当のところはどうなのか全然分からないのだけれど、ひどい偏向報道の傾向を指摘する人も多い。だけど、それでも伝統があるというのか、大学関係の同業者の大半は、朝日を取っている。 だから、朝日新聞に拙著の広告が載ると、同僚たちから「釈迦楽さん、本出したの?」と言われることが多いんですわ。 やっぱり、朝日というのは、今でもそれなりに力があるということなんでしょうね。 だから「折々のことば」とか、それこそ「天声人語」とかに、自分の書いたもののことが取り上げられたりしたら、それこそ祝電の嵐になるのでありましょう。 岡崎さん、いいな~。そんな風ならば、私も朝日新聞に取り上げられたい。自己啓発的な言葉だったら随分拙著の中に書いているんだから、その中のひとつくらい、「折々のことば」が取り上げてくれたっていいじゃな~い。 ま、もうすぐ新著も出ることだし、ちょっと期待しちゃおうかな。
January 17, 2024
コメント(0)
-
色々な卒論
明日はうちの大学の卒論発表会(兼審査会)ということで、私のゼミ以外の、他の先生の指導学生の卒論を何冊か読んでいるのですが、そういうのを読んでいると、色々と考えさせられることがあります。 つまりね、ぜーんぜん違うのよ。他の先生の指導学生の卒論って。その違いたるや、笑ってしまうほど。 ゼミ生は指導教授のやり方に沿って卒論を書くわけで、そうなると指導教授が普段、どういう論文をどういう風に書いているか、ということの影響が非常に大きくなる。 で、うちみたいに、経済学の先生あり、法学の先生あり、情報学の先生あり、教育学の先生あり、文化研究の先生あり、といったごたまぜの科の場合、それぞれ論文の書き方が違うので、結果として学生の卒論もそれぞれになってくるんですわ。 で、私らみたいな文化研究組の先生がたの指導生たちの卒論は、面白いのね。テーマも含め。だけど、こと学問的厳密さという意味では、相当にアマアマなところがある。そこはテキトーなのね。 一方、社会科学系の先生がたの指導生たちの卒論は、堅苦しくてデータは豊富なんだけど、テーマ自体がつまらないし、研究の結果、導き出された結論も、間違ってはいないのだろうけれどもつまらない。 で、そういうつまらない卒論を読んでいると、ああ、こういう卒論を指導する先生の研究も、これと同じようにつまらないんだろうなと思うわけ。読んだことないけどね。 こういう研究じゃ、世間的に売れる本は書けないわな。 で、どうしてこんなつまらないテーマで論文書く気になるんだろうと、私なんかはビックリするんだけど、逆の立場からしたら、向こうは向こうで、こっちサイドの論文を、「こんなの、研究の名に値しない!」とか思っているんだろうな。 とにかく、同じ「研究」と言っても、研究者によって全然違うことを指しているんだということを、こういう機会がある度に、確認させられてしまうのでした。
January 16, 2024
コメント(0)
-
火事場泥棒
世に卑劣な犯行ってのが幾つかあるけど、「火事場泥棒」ってのもその一つだよね・・・。 今回の能登地震のように、地域全体が罹災し、困窮を究めているというところにわざわざ行ってだよ、それで泥棒を働こうというのだから卑劣極まりない。どういう育てられ方をして、どういう神経をしていると、そういうことをやろうという気になるんだろう。まったく、訳が分からないよ。 それも、犯行を犯した人間が、年寄りだったりして、しかも食うや食わずの貧しさで、食い物欲しさに切羽詰まって、というのならまだ分かるけど、若くてピンピンしている奴が、遠路はるばる被災地まで遠征していって、ここなら盗みたい放題だといわんばかりに犯行に及ぶとなると、もう、その時点で処刑して可じゃない? 実際、今回の能登地震でも、石川県の被災地まで行って、なんとミカン盗もうとした大学生がいたとか。その場で住民に見つかって、あっさり逮捕されたらしいですけれども。 で、そいつが近隣の県出身ってのならまだしも、なんと愛知県のヤツだってんですからね・・・。 ン? 愛知県? 愛知県のどこに住んでいる奴よ? そんな奴、絶対に許せな・・・ え? それって・・・。私の勤務先がある市町村・・・。 まさか・・・? いやいや。そんな、ねえ。そんなはずは・・・。うちは国立大学だよ! 厳しい共通試験を潜り抜けて、めでたく国立大学に入学できて、3年まで進学して、そんな愚行をするわけが・・・ え? 番地の手前まで大学と一緒・・・。つまり、うちの大学周辺のアパートに住んでいた奴・・・。 へえー・・・。うちの大学のすぐそばのアパートに住んでいて、他大学に通っている奴っているんだ。なるほどね~。 ・・・現場からは以上です。
January 15, 2024
コメント(0)
-
今時の高校生はスゴイのか、スゴクないのか
大学共通試験の二日目、お役御免となったワタクシは家でノンビリ。 ところで、共通テストの問題って、翌日の新聞に掲載されるのが常ですが、それを見ると、まあ膨大な量なのよね。これを一日で受験生は解かされるのかと思うと、若い連中も大変だなあとつくづく思います。しかも、今日も理系の科目を受験しているわけでしょ。共通試験を受けるために、高校生がどれほどの勉強を強いられるのかと思うと、可愛そうになってしまう。 で、高校生は大変だ、こんな大変なことをやらなくちゃならない高校生はスゴイ、と思うのだけれども、その結果、大学に入学してきた大学生と日々接して思うのは、どうしてこの連中はこれほど知性がないのか、ということ。 まず彼らについて感じるのは、彼らが何に対しても興味がない、ということ。「何に興味があるの?」と尋ねて、明確な答えが返ってきたためしがないもんね。特に外国のことにはまったく興味がなくて、なぜパレスチナでああいう紛争が起こるのかとか、まったく興味がない。興味がないから、何かを知ろうとして調べることがない。 外国人で、日本のアニメが好きだとか、コスプレが好きだとか、百均ショップが好きだとか、日本の武道が好きだとか、そういう人たちは沢山いるけれども、日本人の若者で、アメリカの○○が好きだとか、ブラジルの○○が好きだとか、そういう外国文化への強い興味を持っている者はほとんどいない。 外の事に興味がないだけでなく、古いことにもまったく興味がない。興味がないから、未知のものについての知識を得ようとしたことがない。そもそも「何かを知りたい」ということがまったくないんだよね。 彼らの「無知」というのは、単に「知識がない白紙の状態」というのではない。知識を得ようとする意欲そのものがないのだから。無知であるという意識もなければ、それを改善しなければということに気づきもしない状態。そういうのを、一言で言えば、「お馬鹿」ということなのだけれども。 そこが不思議なんだよね! これだけ勉強して、どうしてこんなにお馬鹿なんだろう? っていうか、これほどお馬鹿なのに、どうしてこんなに勉強ができるのだろう? こんなに勉強して、それが一切、身に付かないというのは、どういうことなのだろう? 彼らの脳って、コップとか皿みたいな感じなのかもね。そこに色々なものが入れられるし、載せられる。で、色々なものを入れたり載せたりした後で、「どれが一番面白かった?」と聞いても、「分かりません、覚えていません、ただ入れたり載せたりしただけですから」っていう感じなのかな? そうだとすると、何か、勉強の方向性に間違ったところがあるのだろうと思うしかないよね。 じゃあ、どうやったら彼らに「知りたい、分かりたい」という欲望を植え付けることができるのか。 文科省が本来考えるべきは、そこなんだけどね。
January 14, 2024
コメント(0)
-
例のヤツ、終わる
例の、一年で一番嫌いな仕事、終わり~! いや、明日もあるだろうと思われるかもしれませんが、ワタクシにとっては終わりなの。そう、今年に限り、1日目だけでお役目御免なのよ~。こんなこと、30年もやっていて初めて~。 っつーことで、同僚の皆さんがまだ明日も厳しい一日の仕事があるのに、ワタクシはお休みなの~。普通の日曜日~。 しかし、もう今日は疲れ切ったので、とにかく寝ます。お休みなさーい。ぐーぐー。
January 13, 2024
コメント(0)
-
明日に備えた新戦略
明日は日本全国の国立大学の先生方が、一年で最も嫌いな日。まあ、詳しいことは言いませんが、大変なのよ。 で、あまりの業務の辛さに、私は毎年、前日の夜になかなか寝付けませんで。嫌だなあ、嫌だなあと思っていると、熟睡できないのよね。 で、毎年、ひどい寝不足のまま業務につき、ただでさえ辛い業務がもっと辛くなるということを繰り返してきたわけ。 が! 人間、やはり過去から学ばないとね! っつーことで、今年の私は違います。新機軸というか、新戦略を打ち出してみた。 寝られないことを解消するためには、どうしても寝たくなるようにすればいい。つまり、明日の当日ではなく、その前日に寝不足になればいいのではないか?と。 つまり、今日、金曜日に早朝に起床し、しかもしっかり働いて寝不足になれば、金曜日の夜には疲れ切って、一気に眠れるだろうと。そうすれば、土曜日に寝不足になることはないのではないか? というわけで、ワタクシ、今朝はものすごく早く起床しまして、そのまま怒濤のように仕事を始めた次第。お昼の時点で、もう、相当眠い。 で、このまま午後もずっと仕事を頑張って疲れ切れば、きっと夜は熟睡だ! そして明日は、気分よく嫌な業務に取り組むことができるでしょう! とまあ、これが現時点での虎算用なんですけど、果たしてこれが吉と出るか凶と出るか・・・。 まあ、明日朝のお楽しみというところでございます。あー、眠い!
January 12, 2024
コメント(0)
-
新著の表紙デザイン
2月下旬に出る新著の表紙デザインが完成したということで、出版社の方から連絡がありまして。 自分の本の表紙というのは、当然、思い入れのあるものですが、これも出版社によってやり方が色々でね。 たとえば出版社の方で案を3つくらい作って、その中から著者に選ばせる、というパターンがある。私の一番最初の本がこのパターンでありました。 それから、どのデザイナーに頼むかを著者に選ばせる、というパターンもある。この場合、各デザイナーのデザインした作品を見て、この人に頼むのがいいのではないか、というのを著者側が選ぶことができる。最近私が出した二冊の本は、このパターンでした。 で、今回ですが、今回は私に選ぶ余地はなく、全部、出版社の方で決めるというパターン。だから、私としては、どういうデザインになるか、あまり口を出す余地がないと。 というわけで、ちょっと不安ではあったのですが、まあ、ちょっとユーモラスなデザインが出てきて、題字もちょっとヘタウマ風。面白いっちゃ面白い。さてさて、市場に出た時に、どういう風に受け取られるのか。楽しみではあります。 表紙デザインと同時に、著者としては最後となる再校のゲラも届いたので、これから先、最後の校正作業に入ります。1週間くらいはかかりきりかな。これが済めば、もう後は出版へ向けて最終調整に入る感じ。2月下旬なんてアッという間ですからね。 まあ、売れてもらいたいものでございますよ。
January 11, 2024
コメント(0)
-

報告とお礼がない
うちの大学は今日のお昼12時が卒論の提出期限。我がゼミ生のうち、一人だけ未提出の者がいたのですが、今日の10時頃、無事提出したとの連絡あり。これで全員提出が決定、今年度の卒論業務が終わりました。よかった、よかった。 それはいいとして・・・。 いや、実は昨日の夜の段階で、まだ6人のゼミ生のうち、二人が出していないと思っていたのよ。で、その二人には、夜の11時頃、「明日は絶対に提出しろ、何が何でも出せ。たとえ未完成でも出せ。あとひと息だから頑張れ!」と激励のメールを送っておいたわけ。 そうしたら、しばらくして、二人のうちの一人から、「今日(=昨日)、昼間に出しました」という返事が来た。 え゛ーーーーーーー! ウソだろ? 昨日は一日、じりじりして提出の報告を待っていて、それがないからまだ未提出なのだろうと思って心配していたのに! 私は、ゼミ生には「いいか、卒論を提出したら、出したその場でオレに報告のメールを寄越すんだぞ」と厳命していたんですわ。だって、私だって心配しているんだから。出したなら出したで、一刻も早くその報告が聞きたいじゃん? ところが、そのゼミ生は、私が夜中に激励のメールを出すまで知らんふりで、私には何の報告もなかったんだからね。それはちょっと、ねえ・・・。 まあ、私は「怒らずの誓い」を立てているので、怒りはしませんよ。しませんけど、ちょっとがっかりですわ。 これは岡野弘彦さんが書かれた『折口信夫の晩年』という傑作伝記に書いてあるんだけど、折口さんの住み込みの弟子であった岡野さんが、ある時、ある大学に就職が決まったんですな。 で、岡野さんという人はお堅いところがあるので、そういう報告はきちんと形を整えてしなければならないと思っていたわけ。で、折口先生と一緒に電車に乗って帰宅して、家についてから、正座をして、居住まいを正してから折口先生に向かって、就職が決まった報告とお礼を述べたと。 そうしたら、折口信夫が激怒した。なんで一緒に電車に乗っている時に報告しないのかと。君の就職が決まったのなら、私も嬉しい。なのにそれを今の今まで黙っているとは何事かと。そんな薄情な人間とはもう一緒に居れない。君には何か邪なところがあって、自分の知らないところで邪な手を使って就職を決めたのではないか。・・・とまあ、そういう感じで、もう、ほとんど破門の一歩手前くらいまでいってしまう。 まあ、折口信夫のこういう思いというのは、当時としてもちょっと行き過ぎなところがあるとは思いますが、私には分かるんだよね、そういう折口の気持ちが。 折口はね、就職が決まって嬉しいとか、そういう「喜び/嬉しさ」のことを「心躍り」と呼ぶのよね。心が嬉しくて踊り出す。その人間の根源的な喜びの気持ちというのは、感じること自体重要だし、それをシェアすることが重要だと考えていた。折口の短歌に対する評価もそれだから。美しいものを観た時の心躍りがそこにあるか、というね。 だから、自分の一番親しい弟子が、その心躍りを自分に示さなかったということがどうしても許せなかったわけよ。 で、ゼミ生というのは、私の弟子なのであって、その弟子が卒論を提出したわけでしょ。その心躍りを、どうして私に知らせてくれないのか、というのは、やはりある。これはね、礼儀とかそういうのじゃなくて、もっと深いものなのよ。 まあ、しかし、ゼミ生がそういう行動を取らなかったというのは、私の責任でもある。ゼミ生の行動は、私自身の行動の鏡像だからね。最近、私が自分のゼミ生たちをさほど可愛がらないから、そういうことになるのでしょう。 世界は変えられない。変えられるのは自分だけ。来年は、自分を変えて、ゼミ生たちが真っ先に卒論提出の報告をしてくれるような、いい先生にならないといかんですな。折口信夫の晩年 [ 岡野 弘彦 ]
January 10, 2024
コメント(4)
-
メルヴィルの息子の墓
『白鯨』で名高いハーマン・メルヴィルにはマルコムという名の息子がいて、この人はピストル自殺をしちゃうんですな。 で、当然メルヴィルはお墓を作りまして、そこに自作の墓碑銘を刻んだ。息子の死を悼む4行詩のようなものらしいのですが。 で、現代ってのはすごいもので、ネット上でこのお墓の写真を見ることができる。 ところが、いかんせん、光の加減が悪く、4行詩に何と書いてあるかは読めない。私はそれが読みたいのに。 で、このメルヴィルが息子の死を悼んでお墓に刻ませたものなのだから、そんなのどこでも読めるだろうと思っていたのですが、いざ、これを探そうとすると、なかなか出てこない。今日はそれを探して、ずっと大学の図書館に籠っていたのですが、メルヴィル関連の研究書を二十冊ばかりひっくり返していたのだけれど、どこにも出てない。 メルヴィルの伝記を書いた人、メルヴィルの研究をしていて伝記的事実を書いている人は沢山いるのだけれども、息子の死をメルヴィルがどういう風に悼んだかというのを調べた人というのは、案外いないのね。 いやあ、不思議だなあ。だって普通に考えてみ。ある人にとって、自分の息子が自分より先に死んだ場合、それも自殺だった場合、相当なショックを受けるのではないのか? そのことが、その人の人生に、なにがしかの影響を与えただろうと、想像しないのだろうか? というわけで、簡単に探せるだろうと思っていたことが、実際にはそうではないということが分かって、いささか愕然としつつ、この4行詩を見つけるのには案外、時間が掛かるのかなという予感がしてきて、ちょっとガックリしているワタクシなのであります。もし誰か知っている人がいたら、教えて! 日本メルヴィル学会会長の牧野有通先生とかに聞けばいいのかしら?
January 9, 2024
コメント(5)
-

映画『コヤニスカッツィ』を観る
相変わらずゼミ生からの卒論草稿を待っているのですが、全然来ない。待ちくたびれたので、この無駄な時間を有効に使おうと、映画を観ちゃった。観たのはかの有名な『コヤニスカッツィ』。 え? 『コヤニスカッツィ』知らない? まあ、知らないでしょうねえ。私もつい最近まで知らなかったもん。 これねえ、7年くらい時間をかけて作られ、ようやく1983年に公開されたドキュメンタリー映画で、ゴッドフリー・レッジオという人が監督を務めているんだけど、フランシス・F・コッポラがプロデュースの片棒を担いでいるので、むしろコッポラ作品であるかのように認識されている、レッジオ監督には気の毒な映画なの。 で、ドキュメンタリー映画とはいえ、ナレーションは一切入ってない。映像と音楽だけ。 内容は、人間の文明。人間のというか、アメリカの、かな。とにかくアメリカの現代文明が地球の自然の上に何を築き上げたか、ということ。それを批判するわけでもなく、誇るわけでもなく描くっていう。でも、まあ、一応は批判になっているのかな? というのも、本作のタイトルである『コヤニスカッツィ』とは、ホピ・インディアンの言葉で「平衡を失った世界」という意味だから。この世界は、バランスが崩れちゃったよね、と。 でも、映像自体は美しくもあるから、見ていると、ああ、キレイだなと思うことも多々ある。バランスは崩れているかもしれないけど、人間って、よくもまあ、これだけの人工物を作り上げたなという感慨はある。 だって、ちょっと前まで、人間なんてただのマシラに過ぎなかったんだよ?! そのマシラが、たかだか百年とか千年くらいのうちに随分すごいことをやってのけたじゃん、という思いはしてきますわ。 で、こういう、文明批判のドキュメンタリー映画が1970年代半ばに計画された、ってことが、私の研究的には意味があるわけ。つまり、これもまた、カウンター・カルチャーとかニューエイジの一つの成果なんでしょうからね。で、ここからさらに、アル・ゴアの『不都合な真実』とか、そういうのにつながっていくわけじゃん? というわけで、1980年代前半のアメリカを騒がせた話題の文明批判映画『コヤニスカッツィ』、しかと見届けた今日のワタクシだったのであります。これこれ! ↓【中古】コヤニスカッツィ [DVD] 監督:ゴッドフリー・レジオ 製作:フランシス・フォード・コッポラ/ゴッドフリー・レジオ
January 8, 2024
コメント(0)
-

伊藤礼著『狸ビール』を読む
・・・そうか、メイコも逝ったか・・・。また一つ、昭和が消えるのぉ・・・。 さて、卒論の提出日(10日)が刻一刻と近づいておるのに、ゼミ生の一人がまだ最終章の草稿を提出してこないっていうね。いやあ、ヤキモキさせるねえ。 で、今来るか、今来るかと待っているのも疲れたので、伊藤礼さんが書いた『狸ビール』というエッセイ集を読んでいたら、結局、最後まで読み切っちまったよ。これ、講談社エッセイ賞を獲った作品なんですが。 伊藤礼さんというのは、作家で文学評論家の伊藤整さんの次男さん。日芸の教授で、英文学の人。その意味では先輩でもあるんですが、英文学での実績より、エッセイストとしての業績の方が有名かも。 で、『狸ビール』は、多趣味だった伊藤礼さんの、(鳥撃ち専門の)ハンターとしての一面を綴ったエッセイでありまして、昔は英文学者が趣味で散弾銃を担いで野山を駆け回る、なんてことがあったんですねえ。 でまた、伊藤礼さんの鳥撃ちのホームグラウンドが、東京と神奈川の境、黒川とか栗木、柿生の辺りだったそうですが、これ、私の実家のあるところじゃん。それもまたビックリ。 で、猟の実体験や、猟における先輩たちとの交流、自分が猟をする心持ち、銃のこと、猟犬との絆のことなど、一巻通してそういう話題のエッセイが並んでいる。 まあ、今時の人間からすると、まるで経験のない話ばかりですから、読んでいて「ふうむ、そういうものなのか・・・」と思うことばかり。でまたその書きぶりが、計算高くないようで、ひょっとしたら計算ずくなのかと思わせるヘタウマの文章で、非常に特徴がある。 伊藤礼の文章の代表例を挙げるとすると、こんな感じ: 薬莢のなかの火薬はなぜ大爆発を起こすのか。 本来、火薬は火をつけてもただボーと燃えるだけのものだ。このかぎりでは、火薬というものはちっとも面白くない。ところが、この場合、火薬は薬莢という親指ぐらいのボール紙の筒の中にはいっている。筒の出口側には紙塞と称するボール紙一枚をへだてて、コロスという詰め物がぎゅうぎゅうにつめこんである。火薬が燃えてものすごい量の気体にかわると、気体は広い世界に出てゆこうとあせって、あれこれと行きどころを探す。しかし、薬莢は尻のほうも側面もしっかりと鋼鉄の銃身に包まれているから、けっきょく多少無理があるとは思いながらもコロスを押し出すことにする。 コロスは、薬莢のなかにぎちぎちに詰め込まれているから、そんなに押されても困るんだとおもいながらも、とにかく気体がものすごい圧力をかけてくるので薬莢のボール紙の円筒のなかをギシギシ音をさせながら、ずっていく。考えてみると気の毒なみたいだ。 ところがコロスのむこうがわには、またもや紙塞をへだてて散弾が詰まっている。膨張した気体がギュー、スポン、とコロスを薬莢の外に押し出すと、それと同時に散弾も押し出されて、銃身のトンネルを通り抜けて銃口のそとに弾のような速さで飛び出してゆく。 これが、鉄砲の引き金を引くと弾が飛び出すしかけだ。 世の中には、こうすればこうなるというたぐいのものがいろいろある。スピードを出しすぎると白バイに追い掛けられるとか、「お茶」と言ってみるとお茶が出てきたりするのもそうだ。 だが、そうは言っても、スピードを出しすぎてもどこにも白バイがいなかったり、「お茶」と言ってみると、しばらくして「お茶ぐらい自分で出したら」と不機嫌そうな声が聞こえてきたりする。 その点で、引き金を引くとはほとんど間違いなく即座に弾が出てくるというのは心あたたまることだ。(『狸ビール』111‐112頁) ね。ちょっと癖があるでしょう? この癖が面白いと思えばこの本は面白いし、この癖が嫌味だと思えば、この本は嫌味な本になる。 私としては・・・うーん、微妙かな。面白いような、嫌味のような、どっちに判断しようかなーって悩むところ。でもまあ、面白く無くはないので、良しとしましょうか。 というわけで、絶賛ではないけれども、読んで面白くなくはないというところで、教授のおすすめ!と言っておきましょうかね。これこれ! ↓狸ビール【電子書籍】[ 伊藤礼 ] しかし、ふと気が付いたんだけど、年明けに読んだ本って、土井善晴の『一汁一菜でよいと至るまで』にしても、伊藤礼の『狸ビール』にしても、偉大な父親を持ってしまった息子の本ですな。偶然そうなったんだけど、どちらの本も、父親コンプレックスの産物と言えなくもない。そういう運命を背負うってのは、傍目で思う以上にしんどいのかもね。
January 7, 2024
コメント(0)
-

土井善晴著『一汁一菜でよいと至るまで』を読了
本年一発目の読書として選んだ土井善晴さんの『一汁一菜でよいと至るまで』を読み終わりましたので、心覚えをつけておきましょう。 この本、タイトルが日本語としてちょっと変だなと思うのだけど、内容としてはとても面白いものでした。新年最初に読む本としてはすごく良かった。 土井善晴さんは、もちろん土井勝さんの息子さん。私も子供の頃、土井勝さんの料理番組(『きょうの料理』)、見てましたからね。土井勝さんの「(この料理は)お子たちにも喜ばれます」という決めゼリフ、よく覚えています。「子どものことを『お子』って言うんだ・・・」というのがすごく印象的でね。「(何かをかき混ぜるようなシンプルな作業を)これはお子たちに手伝ってもらうとようございます」とかね。 で、この本によると、戦後、花嫁修業に料理を習う、なんてことが流行し、元海軍主計だった土井勝さんが開いた料理教室が大人気となり、一時は数万人の受講生を抱える一大産業にまでなったのだとか。で、そんな人気料理研究家の息子として育った善晴さんは、ボンボンとして甘やかされて育ちます。だけど、その後、フランスの一流レストランで修行することになり、また帰国後は和食の名店・味吉兆で修行することになる。この若い日の厳しい修行時代があったから、善晴さんも単なるボンボンから一人前の料理研究家になれたと。 で、その後、善晴さんはお父さんの料理学校の教授陣に加えられるのだけど、時代はもはや花嫁修業の時代ではなく、また土井勝さんも病に倒れたりなんかして、料理学校の経営はどんどん左前になっていく。で、善晴さんは懸命に立て直しに奔走するのだけど、その一方、これは時代の流れなのだからと諦めるところもあり、その一方自分自身の料理研究所を設立し、新たなスタートを切ると。 そしてそうした一連の料理と向き合った人生の中で、最終的に善晴さんが到達した境地が、「一汁一菜」という考え方だったと。 善晴さんの考えでは、プロの料理と家庭料理は別物なんですな。プロの料理はプロの料理として確固たるものがあるのだけど、それはあくまでハレの料理であって、毎日食べるものではない。毎日食べるものではないからこその工夫(例えば、素材を長時間水にさらし、徹底的に灰汁と栄養素、風味を消し去って、そこにカツオだしや昆布だしの旨味を入れていく、とか)というのがあって、それはそれで美味しい。 だけど、家庭料理というのは、人間が生きる原動力となるもので、それはプロの料理とは異なる。毎日食べても食べ飽きないものでなければならず、その基本は一汁一菜、すなわち美味しいコメのご飯と、具沢山の味噌汁、この組み合わせだけでいいと。しかも、その味噌汁にしても、出汁なんて取る必要はなく、ただ良質の味噌をお湯で溶くだけ。そこに、旬の野菜やら、油揚げやら、肉やら魚やら、好きなものを適当にぶち込めばいい。それだけで必要十分な栄養をとれると。 なるほどね。 ま、この本はこんな感じで、善晴さんご自身の来し方と、料理に対する思いを綴った本なのであります。 で、大まかな紹介をするとそういうことになるのだけど、この本は細部も面白くてね。 たとえば、フランスでの修行時代の話で、フランスで外食することの意味、みたいなことが書いてある部分。 フランス人はめったに外食しないんですって。年に一回とか二回とか、そんなもんらしい。だから外食するというのは、フランス人にとって特別なイベントであると。そこで、レストランで何を食べるかというのは一大問題になってくるので、でかいメニューを見ながら、何を注文するか、30分くらいかけて悩むのが普通であると。しかも、料理を頼んだあとは、それに合わせるワインを選ぶのに、これまたソムリエと相談しながら相応の時間をかける。 で、そんな風に熟考の上決めた料理ですから、一皿全部食っていくのが当たり前で、「料理をシェアする」などということは絶対にない。友人の頼んだ料理が旨そうだからといって「一口ちょうだい!」などということは絶対にないんですって。一皿の料理は、それ自体がひとつの宇宙なのだから、それを一人で全部堪能するのが当たり前。 そしてフランスのレストランでは、テーブルの上に塩や胡椒があるのが普通で、どんな凄腕のシェフが作った料理であっても、最終的に味を決めるのは客であると。日本だと、一流シェフの料理に「塩が足りない」とか言って塩を振って食べたら失礼に当たるような気がしますが、フランスではシェフがどういおうが、自分が塩が足りないと思えば塩を振ればいい。これがフランス人の個人主義、なんですな。 とは言え、どこかの国の人たちみたいに、フランスに来てフランス料理の店に入って、「コースの順番なんかどうでもいいから、注文した品全部一度に持ってこい!」とか命じて、それを回転式円卓よろしく、テーブルを囲んだ者が好き勝手にワイワイしゃべりながらシェアして食べるとなると、それはちょっとどうなのかなと。善晴さんもフランス・レストランでの修行時代、そういうことをするどこかの国の人たちにはちょっと閉口したらしい。これは、自国の文化を他所でも押し通すやり方で、それはちょっと違うのではないかと。 あとね、味吉兆での修行時代の話も面白くて、吉兆の創立者・湯木貞一と、その右腕で善晴さんの直接の上司であった中谷文雄の懐石料理思想ってのがすごかったらしい。 和食の粋たる懐石料理、あれは大昔から伝統的にあるものだと思っている人が多い(私も含め)と思いますが、懐石料理ってのは、味吉兆が創り出したものなんですってね。で、じゃあ、懐石料理ってのは何かというと、茶の湯を料理の世界に取り込んだ料理であると。だから、「茶があるかどうか」が、懐石料理の本質だというわけ。 で、ではそこで言う「茶」とはなにかというと、要するに自然のことは自然に任せる、という思想。逆に言うと、すべて人為でやろうとしない、ということになる。 だから、材料をすべて同じ形、同じ長さに切りそろえた料理、なんてのは、懐石ではない。土筆のおひたしなんかでも、同じ長さに切りそろえた土筆なんか出しちゃダメ。だって、自然に生えている土筆には、長いのもあれば短いのもあるでしょ。だから、そこは自然に任せればいい。 料理の盛り付けにしても、たとえば小蛸の煮付けだとしたら、一皿に蛸の数は5つ、なんて数を決めるのは野暮。ワシっと掴んでワシっと盛るだけ。ある皿には蛸が5つ、ある皿には6つ、ある皿には4つであっても構わない。キレイに盛り付けた料理のひと皿を客の元に運ぼうとしたのを湯木が押しとどめて、その盛り付けを上からギュッと抑えつけて崩し、「よし、できた」と言った、なんて伝説もあるとのこと。 なるほど、「茶があるかないか」ねえ・・・。面白いなあ。で、土井善晴さんもそういう懐石料理の美学を習得するために、随分勉強されたそうで。料理の盛り付けに使う器の美を体得するために、美術館・博物館・骨董の店なんかを暇さえあれば巡ったとのこと。結局、いいものを見ることでしか、目は育たないんですって。 とまあ、そんなあれこれが書いてある。とても面白い本でした。新年一発目の本としては、上出来だったのではないでしょうかね。これこれ! ↓一汁一菜でよいと至るまで (新潮新書) [ 土井 善晴 ]
January 6, 2024
コメント(0)
-
健康第一! 緑茶生活の始まり
今年のね、なんて言うの、目標、みたいなものとして、ワタクシ、「健康第一主義」を掲げておるんですわ。 で、その第一歩として、緑茶を大いに飲もう!というのを、実行完徹しようと思っておりまして。緑茶は健康にすごくいいって言うじゃない? 私が緑茶に興味を持ったのは、先輩同僚の「アニキ」ことK教授の影響なんですが、K先生は静岡県出身ということもあって緑茶がすごく好き、その上、その飲み方がとても上手でね。 私のように緑茶を飲み馴れない者は、食事の脇に緑茶を置かれても、その飲み方が分からないんですな。だから食事中は一切手をつけず、食事を全部食べ終わってから、冷めた緑茶をぐーっと一気飲みしちゃう。 ところがK先生は違う。食事をしながら、その時々でちょっと一口お茶を飲み、口中を爽やかにしてからまた次の一口を食べるというのを繰り返す。そして食事を食べ終わるのと同時に、緑茶も飲み終わると。この絶妙の取り合わせが、見ていても見事でね。これがお茶所静岡県民のお茶の飲み方かと。 つまりね、寿司の時のガリの扱いと一緒なの。ガリってのは、寿司を食べる合間の、句読点のようにしてつまむのが筋であって、寿司を全部食べてから最後にガリだけガーッと食べる人はいないわけでね。 というわけで、ワタクシも過去、何度か、食事の時に緑茶を用意して、K先生のように緑茶を楽しもうと思ったことがある。だけど、いつも中途半端に終わって、結局習慣化するところまでは行かなかった。 そこで、今年こそは、食事中に緑茶を上手に飲むことを習慣づけようと、まあ、そういう風に決意したわけですよ。 で、ワタクシも考えた。今まで失敗してきたのは、やはり食事毎に緑茶の用意をするのが面倒だから、習慣化できなかったのだろうと。 そこで、「お茶パック」なるものを買ってきて、そこに適量のお茶っぱをあらかじめ入れて置き、そのパックを直接湯飲み茶碗にぶち込んでお湯だけ注げばいいようにしておいたらいいのではないかと。そうすれば、いちいち急須の用意をしなくてもいいし、事後に急須を洗う必要もないわけだから。 そして、お茶自体も美味しくなければ習慣化できないし、といってバカ高いお茶だったら経済的に収監できないだろうと考え、お安くて、しかも美味しいお茶の選定にも気を使いまして。結果、新東名高速の静岡SAに売っているという、「マルサン中野園 深むし茶」をゲット!これこれ! ↓マルサン 深むし茶 というわけで、これを早速、お茶パックに詰め、コップに入れてお湯を注げばいい状態にした。で、今日の夕食から毎日緑茶生活を始めようというわけですが、さてさて、上手く行くでしょうか? ま、何事でも新たに始めるというのは楽しいもの。上手く続いて、緑茶を飲むことが習慣化できたら、お慰み。そしてその結果、次の人間ドックの時の結果につながればいいなと思っているワタクシなのであります。
January 5, 2024
コメント(0)
-
名古屋に戻る
ひゃー、実家で年末年始を過ごした後、本日、名古屋に戻って参りました~。 で、早速旅装を解いたり、いただいた年賀状などを読んだり。教え子の子供がもう大学受験、などという話を読むと、他人の子ってのは成長が早いなと思いますね。 一方、いただいた年賀状の中に、「これを最後に、今後は年賀状のやり取りを卒業させていただきます」的なものもちらほらと。 まあ、「齢八十を超えたので・・・」などというのなら分かるのですが、大分年少の知人からそういうのをいただくと、さすがにちょっとビックリ。ああ、そう、もう私とは縁を切るということねと。 とはいえ、もうすぐハガキも85円だからな。もういい加減、年賀状などという前世紀の遺物にしがみつくのも、アレなのかもね。 と、色々考えさせられることあり。 そんな自宅での新年のスタートなのでした。
January 4, 2024
コメント(0)
-
初詣でで大吉、そしてキャデラック
今日は三が日最終日ということで、実家近くにある神社に初もうでに行って参りました。 初もうでもね、一昔前は大晦日の除夜の鐘を聞きながら、真夜中に家族総出で行って、神社も大賑わいで、振舞い酒やら甘酒屋らをいただいたりしたものですが、最近ではそういうこともなくなり。参拝客もまばらな中、三々五々出かけるようになりました。 でもね、やっぱり三が日ですから、まだまだ年明けの雰囲気は残っていて、おみくじをひいたり、お守りを買ったりと、新春の楽しみはあります。 で、今年のおみくじですが、私は「大吉」! さすがに気分がよろしい。向かうところ敵なしの心持で、今年も頑張ることにいたしましょう。 ところで、今日はもう一つ、楽しい知らせが。 アメリカ文学会の仲間のお一人で、私同様クルマ好きのK先生という方がいらっしゃるのですが、そのK先生とメールのやり取りをしている中で、先生がキャデラックATSというクルマの、しかもクーペにお乗りだという話を伺いまして。 ほ、ほう! キャデラックですか!! いや、実は新世代キャデラックというのは、デザインが抜群で、私も前々から興味を惹かれているクルマ。しかもATSとなりますと、サイズは日本のクラウンくらい、ギリギリ日本でも持て余さない大きさということもあり、食指の動くクルマなのよ。 ただ、キャデラックは基本、左ハンドルなので、日本で乗るにはどうかな・・・とためらうところもあり。 ところがK先生のお話ですと、多少、視界/見切り面で難ありと謂えども、左ハンドルでなんら支障がないとのこと。一般道での燃費はあまり褒められたものではないけれども、高速であれば結構伸びると。 ふうむ! そうだったのか! そんな楽しいクルマ談義があって、次の愛車候補にキャデラックが急浮上。ついネット上で在庫を探してしまったりして。 なにせ私はアメリカ文学者なんだから、クルマだって一度くらい、アメ車に乗らないといかんのではないかと思うところもありますしね! アメ車なら、キャデラックATSか、さもなければマスタングなんだよなー。K先生は、ファイヤーバードにも興味がおありのようだったけれども。 というわけで、クルマ好きのK先生から楽しいメールをいただいて、しかも大吉だし、今日はなかなか気分の良い日となったのでした。それにしても悩む~!
January 3, 2024
コメント(0)
-
男三匹、新年会
正月二日は、毎年、小学校以来の親友の二人、T君・E君と共に新年会をやることになっておりまして、今年も吉例に従い、午後から相模大野で飲んできました。 ま、飲んできたといっても、昼間からやっている飲み屋は少ないので、適当なレストランでビールとかワインのグラスを頼み、つまみとしてフライドポテトだの生ハムだのアヒージョだのを頼むだけの簡単なものなんですが。 寡黙なE君、やや寡黙なワタクシと異なり、T君はおしゃべりなので、三人で飲むとなると、会話の5分の4はT君に持っていかれるのですが、比較的遅くに結婚し、遅くに子供ができたT君のところは、一人息子が今年中学受験ということで、この冬はなかなかの騒動となっているらしく。受験に夢中な奥様と、受験そっちのけでのんびり屋さんの息子君との間の「勉強しろ!」「いやだ!」の攻防が激しく、T君としては身の置き所がないと。まあ、そういう状況に立ち至ったことのないワタクシとしては、ただただ「大変そうだなあ・・・」と思うばかり。まあ、その状況もあとひと月のことですから、T君には耐え忍んでもらいたいもの。 E君の方は、大企業の相当お偉いさんになっているのですが、会社が風力発電をやっていて、先だっての某政治家の風力発電関連疑惑にちらっとかかわっていたものだから、それはそれで結構大変だったのだとか。その一方、昨年は仕事でニューヨークとシカゴを回り、アチラの投資家に投資を促す仕事をしたり、同期会で有馬温泉で芸者をあげての大騒ぎをした話など、割と楽しめな話をきくことができました。彼の会社の同期会というのは、毎月5千円を積み立てているそうですが、それがたまりにたまって一人頭18万円にもなったので、それで有馬温泉で芸者遊びになったのだそうで、会社勤めをしていると、そういうこともあるんだなと。そういう世界と程遠いところに住んでいるワタクシとしてはビックリ。 とまあ、それぞれなんですけど、こうして小学校以来の友達同士、毎年、集まることができるのだから、感謝しないとね。別れ際、お互い健康に気遣ってまた来年もこうして会えるよう、祈念しながら甲斐さんしたことでございます。
January 2, 2024
コメント(0)
-

謹賀新年
新年あけましておめでとうございます。本年も本ブログをよろしくお願いいたします。 穏やかな年明けと思っていたら、能登方面では大きな地震があり、なんともはや、大変な元日になってしまいました。そちらにお住まいの皆さまの無事と、被害の少ないことを祈っております。 さて、ワタクシはと言いますと、まあ、例年通りの元日を過ごしております。午前中、ゆっくり目に起きて、お節を食べ、午後から新百合丘に行って初買いを楽しみ、夕食はピザをとって・・・といった調子。 元日の読書として、昨日買った土井善晴さんの『一汁一菜でよいと至るまで』が面白くて一気に半分くらい読んだのですが、初買いの時に立ち寄ったブックオフで、森博嗣さんの『作家の収支』という本を88円(それもポイントを使ったので、実質ゼロ円)でゲットしたもので、こちらも読み始めたら、これも面白くて、両方を代わる代わる読んでおります。これこれ! ↓作家の収支 (幻冬舎新書) [ 森博嗣 ] 森さんという方は、小説1作を30時間くらいで書き上げてしまわれるようで、それが数十万部売れて、何千万円だからの印税を稼ぎ出すのだとか。単純計算すると自給100万円となるそうですが、作家って、書ける人にとっては儲かる商売なんだなと。もう、研究者なんかやっているのが馬鹿馬鹿しくなってくるようなお話で、元日に読むにはピッタリの本でございます。「俺も一丁・・・」という野心が出てきますからね。 というわけで、野心の充填だけは例年通り、きっちり果たした元日となった次第。ま、野心だけで終わることが多いのですが、野心のない人生なんて、ねえ。それはつまりませんから。野心の充填、上等!ですわ。
January 1, 2024
コメント(0)
全31件 (31件中 1-31件目)
1










