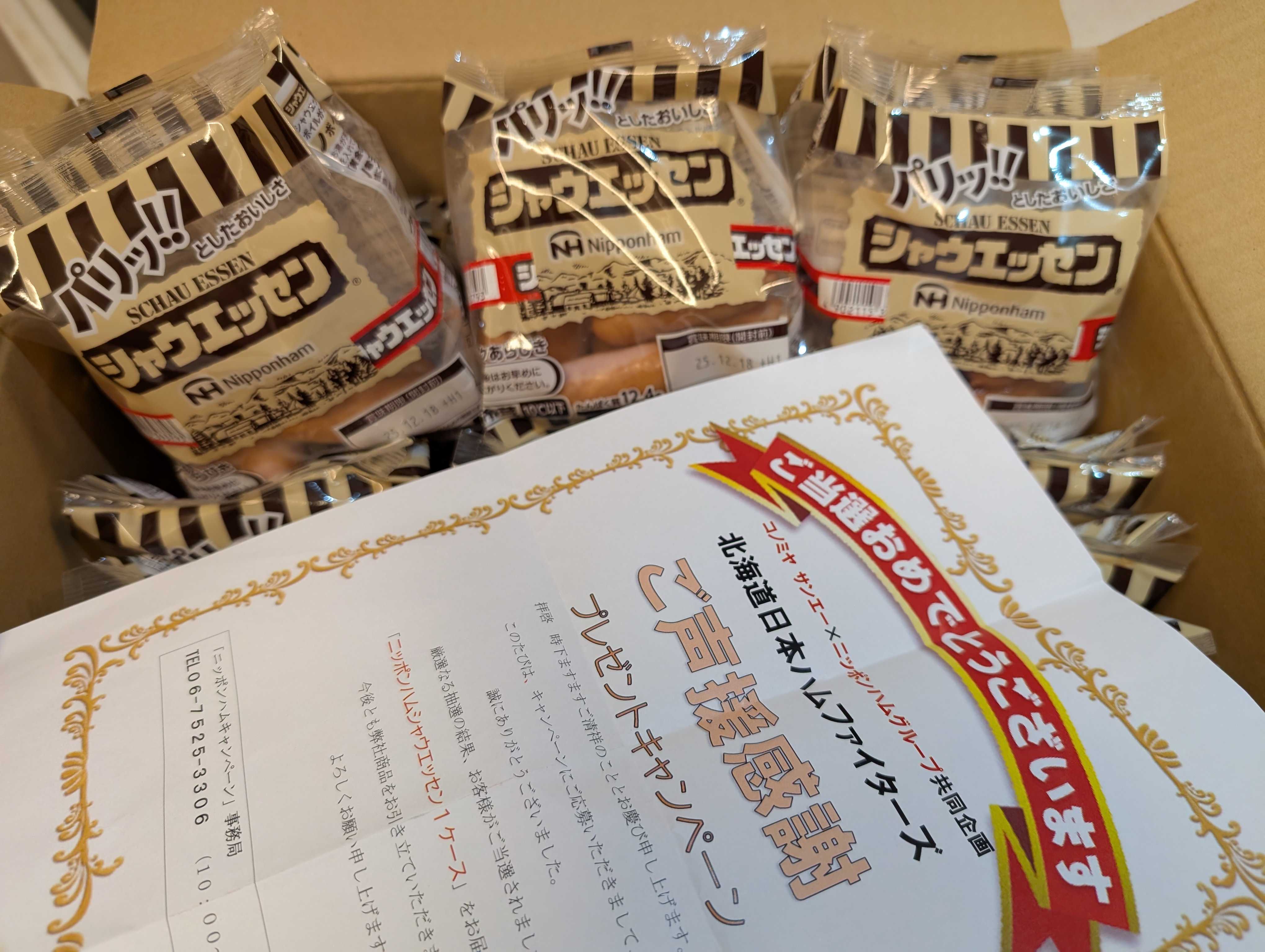2007年01月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
『ラッキーナンバー7』を見た
映画館のタダ券の期限が今日までだったので、今日は名古屋駅前の「ピカデリー」という映画館まで『ラッキーナンバー7』という映画を見に行きました。シネコン以外の映画館に行くのは久し振りです。 で、その『ラッキーナンバー7』。ブルース・ウィリス、ルーシー・リュー、モーガン・フリーマン、ベン・キングズレーといった大物が顔を揃えている割に、ぜんっぜん話題になっていないところに多少の不安がありましたが、見てみたら面白かったですよ。 失業したり、恋人に浮気をされたりして、ついていないある若者スレヴン(ジョッシュ・ハーネット)が、友人のニックを尋ねてNYにやってくるんです。ところがアパートを尋ねると蛻の殻。それどころか、どうやらこのニックという男はこの町のギャングのボスに多額の借金があったようで、人違いされた彼はそのボスのところに連行され、大人しく借金を返すか、それとも借金を帳消しにする代わりに、対立しているギャングの親玉の息子を殺すか、どちらかを選べと言われてしまう。 えらいことに巻き込まれてしまったスレヴンですが、ことはこれだけでは済まなかったんですな。実は友人のニックが、その対立するギャングの親玉からも借金をしていたらしく、スレヴンはこちらのギャング団にも捕まってしまい、借金返済の代わりに対立ギャング団のボスを殺すよう強要されてしまうという・・・。 ところが、不運なスレヴンが期せずして巻き込まれてしまったこの二つの殺人依頼には裏があるようで、どちらの背後にも謎の男(ブルース・ウィリス)の影が・・・。さてさて、スレヴンの運命やいかに? ・・・というような内容なんですが、面白そうでしょ? 実際、印象的な出だしから最後まで、割と飽きさせずに見せてくれます。 ということで、この映画に対する私の印象批評点ですが・・・ 78点です! 合格! ま、最後の方3分の2くらいで、すべての事情が分かってしまうというところがアレなんですけど、出てくる俳優がそれぞれいいので、結構見せてくれるんですよね。特に主人公役の若手俳優ジョッシュ・ハーネットが良くて、脇役の大物にぜんぜん負けてなかった。それから彼の恋人となるルーシー・リューですが、この配役も良かったんじゃないかな。それにしてもルーシー・リューという女優、あれこそはまさに西洋で大モテの「東洋の神秘フェース」ですね。 またスレヴンの(というよりは、ニックの)アパートの「ミッド・センチュリー」っぽい設えなんかもとても良くて、私のような建築好き・インテリア好きにはたまらないところです。この映画、話題にはなっていませんが、お金を払って見ても決して損をしたという気にはならないと思いますので、興味のある方はぜひご覧下さい。教授のおすすめ!です。 ただねー、この映画の邦題だけは理解できません。原題は『ラッキーナンバー・スレヴン』なんですが、なぜ「スレヴン」の部分を「7」に変えたのか? 音が近いから?? これは大いに謎でございます。それにしても、最近の邦題の付け方って、センスないね! さて・・・ここから先は映画自体とは関係がない話ですが、久し振りにシネコン以外の映画館、つまり昔ながらの映画館に行ってみて、ちょっと驚きました・・・。軽いカルチャー・ショック。映画館って、こんなだったっけ? という感じ。 そもそもね、この映画館、チケット売り場からしてビルの外にあるんですよ。チケットを買うのに、この寒空の中、ビルの外に並ばされるなんて思いもしませんでした・・・。 で、映画館の中も渋いんだ、これが。最新のシネコンのように客席の傾斜がきつくないので、前の席に座った人の頭がスクリーンの下の方とかぶさるわけ。こんな状況、久し振りに味わいましたわ。 それにスクリーンも小さいし、音響もプア。本編前の広告フィルムなんて「これいつの時代の?」というほど古く、フィルムにも雨が降っちゃってまともには見られません。 こんなんだったら、そりゃ誰だって最新設備の整ったシネコンに行きたくなるでしょう! 古い映画館が潰れていくのも当たり前だわ・・・と、私は思ったのでした。 ところがこれが大間違い。名古屋駅前のピカデリーは大人気らしく、チケットを買う人の列が絶えない状態。私が見た『ラッキナンバー7』もほぼ満席状態ですわ。これは一体どういうことなのでしょうか。名古屋駅のすぐ近くという立地条件のせいですかね? それだけで、あんな渋い映画館で人の頭越しに映画を見る気になるのかなあ・・・? ま、そんな大疑問も含め、久し振りに「懐かしの映画体験」に浸ることができたのでした。
January 31, 2007
コメント(6)
-
命日
今日は私の小学校時代の恩師Y先生の命日です。 先生が亡くなった日から、もう25年経つんですなあ。 25年前の今日は、寒い日でした。東京では朝方の気温がマイナス6度。 先生はその日、朝から体調が悪かったそうですが、その日、長野にある小学校への出張が入っていたために、無理をされたのでしょう。 そして朝会の時に倒れられ、救急車で北里病院に搬送されたのですが、およそ2時間後に息を引き取られたそうです。心臓発作でした。享年53歳。 当時高校生だった私が、先生の訃報を聞いたのは午後2時頃だったでしょうか。 私が詰襟の学生服のまま先生のご自宅に駆けつけた時には、既に弔問に訪れた同僚の先生方や父兄の方々が詰めかけておられました。 その中で一人、私の姿を認めたK先生が人の群れから飛び出してきて下さって、呆然としていた私の顔を覗き込むようにして一言声を掛けて下さいました。私がどれほどY先生を尊敬していたか、ご存じだったからです。 それから先、私の記憶はしばらく飛んでいます。私と同じようにY先生のお世話になった数多くの方々の悲痛な慟哭に気押されたのかも知れません。 その夜、先生のご遺体にお別れをし、自宅に帰る前、私は回り道をして自分の母校の校庭まで行き、先生がその朝倒れられた場所に立ちました。ぼんやりとして頭が回らず、悲しいという気も起こりませんでした。ただ寒いと思っただけ。 悲しさがようやくこみ上げてきたのは、家に向かう電車に乗ってからでした。人目につかぬよう顔を隠してはいても、涙が後から後から流れて仕方がありませんでした。 あの日から25年が経ったのですなあ。 あと10年も経てば、先生が亡くなった歳になろうというのに、まったく私は何をしているのでしょうか。毎年この日になるといつもそう思うのですが。 本当に先生に申し訳の立たない、恥ずかしいことでございます。
January 30, 2007
コメント(2)
-
シラバスがなんぼのもんじゃい!
ここ数年ですかねえ、大学側が「シラバス、シラバス」って騒ぎだしたのは・・・。 「シラバス」ってのは、要するに今年度どのような講義をするか、その予定を書き記したもので、ま、学生が履修する科目を選択する時の参考にするものですな。 だったら、「講義要項」って言えばいいじゃん。なんで「シラバス」なんて英語にしなくちゃいけないの? ま、それも気に入らないんですけど、とにかくこのところこの「シラバス」とやらをやたらに書かせたがるんだ。昔は半ページほど書けば許してくれたんですけど、このごろはばっちり1ページ書かないとダメなんですと。しかもちゃんと項目建てしないといけないので、「授業目標」「授業計画」「教科書・参考書」「評価基準」「備考」のそれぞれの項目に事細かに書かなきゃいけないんだそうで・・・。 しかも、「授業計画」に至っては、半期15回の講義で何をやるか、一回一回の予定を箇条書きで書けなんて言ってくるんですから馬鹿馬鹿しいったらありゃしない。 そりゃあね、大学の中に膨大な選択科目のがあって、学生はどれでも選びたい放題ってのなら、事細かなシラバスを作る意味もあるでしょうよ。しかし現実はどうかといえば、卒業単位を満たすために取らなければならない授業ってのはほとんど決まっていて、我々もそれを提供しているわけ。だから、どの教員がどんな講義をしようが、それを学生が気に入ろうが気に入るまいが、それを取らなければ卒業できないんですよ。学生に選択の余地なんて実際にはほとんどないんだ。 だから、もともとシラバスを作る意味自体が非常に曖昧なんです。それなのにまあ、形式ばっかり整えようとして・・・。 結局、こういうのは実は学生のためじゃないんです。大学審査機構対策、ひいては文科省対策ですわ。「シラバスをちゃんと作ってます」って言えるようにしておかないと、予算減らされるんですから。 しかし・・・仮にも大学っちゅーところはですね、高等教育機関ですよ。学習指導要領のある中等教育機関じゃないんだ。個々の教員が、その研究の最先端を一部学生に披瀝するところ、それが大学でしょう。となれば、前もってシラバスが書けない授業こそ、最高の授業ってもんじゃありませんか。 学生だって、そんなあらかじめ決められたレールに乗って走る電車みたいな授業、聞きたいのかえ? ワシなんか、シラバスなんかいつもいい加減に書くけど、きっちり書いている他の教員よりよっぽどいい講義するもんね。学生のアンケート見て見ろって。「今まで受けた大学の授業の中で、釈迦楽先生の講義だけが面白かった」と書いてくる学生のいかに多いことか! 言ってやったわ! さて、と。シラバス書こう(爆)。だって、明後日締め切りなんだもーん。 ま、そこが宮仕えの辛いところですわ。でもね、意地でも「えー加減な」シラバス書いたる。誰が一回一回の講義の予定まで書くかって!
January 29, 2007
コメント(2)
-
字数を減らす
私のような文系の研究者にとって、文章を書く、ということはほとんど日常的な作業であり、自ずと個々の研究者はそれぞれの「文章道」を極めていくことになります。 で、そのような生活を十何年も続けてきた挙げ句、立派な文章を書くには二つの重要な「奥義」がある、ということに私は気が付きました。 何だと思います? 「締め切り」と「字数制限」ですね。この二つがないと、文章ってなかなか書けません。 いや、実は今、あまり気乗りしない仕事をしておりまして、かつて自分が書いた文章を半分の長さにする、という作業をしているんです。内容は同じまま、文章だけ半分の長さにしろってんですから、厳しい注文です。 もともと、この仕事は気持ちが乗っていなかったので、もとの原稿を作るのでも精一杯だったんですが、それを今度は半分にしろって言われて、いささか滅入っているわけですよ。 しかし、文章道のもう一つの決め手である「締め切り」の方も近づいているので、今日は朝から泣く泣くこの作業に取りかかりましたよ。 ところがですね、ほとんどヤケになって自分の書いたものをばっさばっさ刈り込んでいると、段々サディスティックな快感が生じてくるんですわ。で、調子に乗ってさらにあっちを切り、こっちを切りしているうちに、あらま、なんとか半分の長さになったじゃあーりませんか。 しかも、結果としては短いバージョンの方がさっぱりして出来がいいという・・・。 やっぱね。「締め切り」と「字数制限」。これですわ。この二つが揃うと、いい仕事出来るね。 とまあ、あらためて文章道の奥義を体感したわけですが、しかし・・・それにしても今度の仕事は自発的なものではないだけに、冴えないっちゃ、冴えないなあ・・・。 あーあ、こんな仕事さっさと終わらせて、自分のための文章書かなきゃ。 ただ、自分のための文章だと、「締め切り」と「字数制限」がないもんだから、これまた書くのが難しいんだ・・・。 ま、難しいからこその文章道なんですけどね。 でも、いずれ頑張って、このブログを贔屓にして下さっている皆さんにもいいとこ見せるので、ひとつ応援のほど、よろしくお願いします。
January 28, 2007
コメント(6)
-
死後のお手紙
ちょいと小耳に挟んだところによると、某元国立天文台助教授の先生が病気で亡くなられたらしいのですが、その前に大手新聞に広告を出し、旧知の方々に、自分とどんな付き合いをしていたかを手紙に書いて、奥さんと娘さん宛てに送ってくれ、と頼んだのですって。 つまり、「私は亡くなった○○さんとは飲み友達で、よく仕事の帰りに楽しい酒を酌み交わしたもんです・・・」とか、「私は○○さんに励まされて、生きる勇気をもらいました・・・」なんて手紙を自分の奥さんと娘さんに送ってほしいというメッセージを、新聞に掲載した、ということでしょ。 で、もしそんな手紙が奥さんと娘さんのもとに一通でも届いたとしたら、それが最愛の二人に遺す「遺産」だ、というわけですよ・・・。 ええ話やな~。 もっとも私が同じことをやったら、ひどい内容の手紙が届くんだろうな~。「釈迦楽さんには、迷惑をかけられっぱなしでした・・・」とか、「釈迦楽先生に習ったことは、世間に出てから、結局一つも役に立ちませんでした・・・」なんてのが、じゃんじゃん届いたりして。 ふーんだ。いいもんね。ワタクシなんか、もっと別な計画があるんだもんね。 ワタクシ、いよいよ先が短いと知ったら、友人知人宛てにしこたま年賀状書いて、ストックしておくんだもんね。それで、家内に頼んで、毎年年末に投函してもらうんだもんね。 でね、死んだ年の翌年の年賀状には、「天国、うわさ以上だよ。お前も早くこっち来いよ!」とか書くわけ。で、それ以後は「こちらに引っ越して2年目だけど、近くに来たら寄ってって」とか、「天国に来て3年にもなると大分知り合いが増えてきた。そうそう、この前偶然『小森のおばちゃま』に会ったけど、あのまんまだったよ」とか書くわけよ。 めちゃくちゃ、面白そうでしょ! あ、それから、生前仲の悪かった奴には、「天国行きの人たちのリスト見たけど、お前、入ってないよ」とか書いてやるんだ~! あっはっは! は~。 ま、釈迦楽版「死後のお手紙」ってのは、そういう奴です。 人間、死ぬってのは、一大事ですからね~。皆さんもぜひ、その時になって慌てないよう、今のうちから死後の計画、立ててみて下さい。楽しいよ~。
January 27, 2007
コメント(8)
-
世界各地から手紙が届く
今日は事情があって、お昼は家内と外食で済ませました。 とはいえ、別にご馳走を食べようというわけではないので、どこか気軽に入れそうな店はないかと名古屋の郊外・星ケ丘あたりを車で徘徊していたところ、「街角屋」なるお店を発見。定食屋のチェーン店みたいな感じでしたけど、なんとなく今日の気分には合っていたので、ここに入ってみることにしました。 で、入ってみると、まあ吉野屋に毛が2、3本生えたような感じの店で、いかにも営業中といった風情のサラリーマンが一人でカウンター席についていたり、あるいは作業服を着たおっちゃんたちが2、3人でテーブル席についていたりします。年配の夫婦連れなんかもチラホラいたりして、それなりに流行っている様子。 さて、ここで我々が注文したのは「生姜焼き定食」680円と「はりはり鍋定食」730円。待つことしばしでやってきたそれは、ボリュームもたっぷり。肉だけでなく野菜も豊富だし、栄養のバランスが取れていそうです。 でまたお味の方も結構おいしかったんですわ・・・。特に豚肉と油揚げと水菜で作った「はりはり鍋」は、ずばりストライク・ゾーン!でした。こんな定食屋で舌鼓を打ったなんて告白するのは、グルメ教授としてはちょっと悔しいところですが、お腹が空いていたこともあってもりもり食べちゃった。何せ御飯はお代わり自由ですもんね~。 というわけで、家内共々お腹いっぱい、幸せな気分になり、帰りに三越デパートに入っている紅茶専門店「ルピシエ」で紅茶を三種ほど購入して帰りました、とさ。 さて、そんな感じでいい気分で帰宅してみると、今日はどうしたわけか世界各地から私宛てに手紙が届いているじゃあ、あーりませんか。 まず一通目はフランスから。これは私の教え子で、今南フランスの小さな町にパティシエ修行に出ているN嬢からの便りです。既に彼の地に到着して一月半ほどたったとのことですが、朝3時起きしての仕事ということで、生活面全般も含めてしんどい日々らしい・・・。でもなかなか頑張っているようで、地元の新聞に彼女がお菓子作りに勤しんでいる様子が報道されたとのこと。その新聞も送ってきてくれましたが、私のフランス語も大分錆び付いてしまって、何が書いてあるのかは大まかなことしか分かりません。でも、外国の新聞に報道されるなんて、大したもんですよ。立派、立派。我が弟子ながら、天晴れってなもんです。急いで励ましの手紙を書いてあげないといけませんな! それからもう一通はアムステルダムからですが、こちらはオランダ人の友人からの手紙。彼はテレビ・プロデューサーなんですが、日本の歌謡曲なんかのことも色々研究していて、今は「服部良一」にご執心の様子。で、服部さんが作曲した数々の名曲をCDで楽しんでいるらしいのですが、何しろ歌詞が日本語なので、内容までは分からないとのこと。そこでせめて曲のタイトルが何を意味するかだけでも知りたいということで、私に翻訳を頼んできたという次第なんです。 というわけで、彼の求めに応えてこれから歌のタイトルの英訳をしなければならないんですが、それにしても笠置シヅ子の「買物ブギー」とか、高峰秀子の「銀座カンカン娘」とか、果ては市丸姐さんの「三味線ブギウギ」といった懐メロの情緒って、ファッションの最先端を行くオランダ人プロデューサーに分かるんですかね・・・? 市丸姐さんの「三味線ブギウギ」って、「三味線ブギーでしゃしゃりつ、しゃんしゃん」って、アレでしょ? でも彼の仕事はテレビ関係だからなー。彼の企画の立て方によっては、案外、こういうのがオランダの若者の間でブレークしたりして・・・。 ちなみに「尼寺に和尚さんが」(服部シスターズ)って、どんな内容の歌なのか、ご存じの方、いらっしゃいますか? お色気コメディーソングなのかしら・・・。タイトルだけ英訳するにしても、歌の内容が分からないと、どんなニュアンスで訳せばいいのか、分かりませんのでね。もしどなたかご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示下さい。 とまあ、色々ありますけど、今日は面白いところで昼御飯を食べたり、世界のあちこちから手紙をもらったり、なかなかカラフルな一日となったのでした。今日も、いい日だ!
January 26, 2007
コメント(2)
-
アパ・ホテルよ、お前もか!
ニュースによると「アパ・ホテル」が耐震強度偽装ですって? ひゃー、びっくり! だって、泊まったことあるんですもん、アパ・ホテル。ま、問題になっている京都のものではないですけどね。 ちょうど2年くらい前のことですが、金沢に学会関連の出張があった時、駅前にあるアパ・ホテルに泊まったんです。で、その時の印象としては割と良かったんですよね。 確かに部屋は狭いのですが、どうせ寝るだけですからね。清潔であれば文句はないわけで、実際、そこは清潔でしたし。 で、確か割と豪華なバイキング形式の朝食もついていて、それで5000円しないくらいでしたかね。何だかやけに安いな、と感心した覚えがあります。 でまたもう一つ感心したのは、チェックアウトの方式です。手続きがすごく簡略化されていて、部屋のキーを専用のボックスに投げ入れるだけでそのまま出られるんじゃなかったかな? ま、そんなこんなでアパ・ホテルに対しては割といい印象を持っていたのですが、気が付くと案外あちこちにあるんですよね、このホテル。名古屋にもあります。聞くところによると、凄腕の女社長が潰れそうになっているホテルを次々に買収し、それを合理的に改装する形で系列ホテルをじゃんじゃん増やしているのだということですが、ま、安くて利用しやすいホテルが増えるのなら、別に悪いことではありません。 ということで、またどこか学会出張があったらアパ・ホテルに泊まってもいいな、と思っていたんですけど、そんな私にとっても今回の報道はちょっとがっかりです。やっぱり急に伸びる企業にはどこか歪みがあるんですかね・・・。 それにしても、日本のホテルって、ちょっと高過ぎます。大体、「一人いくら」という料金設定がおかしい。あれは「一部屋いくら」というふうにしなくちゃ。アメリカのホテルはたいていそうなっています。 っていうか、私なんぞ、アメリカではそもそもホテルなんか泊まりません。モーテルで済ませてしまいます。でまた、このモーテルというのが実に快適なんだ! 料金は安いところでは30ドルくらいからありますからね。これで二人楽々泊まれます。朝食がついているところも多いですし、なんの不足もない。で、ついでに言いますと、アメリカの高速道路はそのほとんどが無料ですし、ガソリン代も安いので、アメリカでモーテルに泊まりながら自動車旅行していると、ほんとお金がかからないんです。貧乏人でも長期の旅行が十分楽しめるようになっている。 あの快適さを思い出すと、何かとお金ばかりかかる日本の状況が嫌になるんですよね。よく「一家で一泊二日で東京ディズニーランドに遊びに行って、かかった費用が20万円」なんて話を聞きますが、そんな馬鹿馬鹿しいお金の使い方、私には出来ませんなあ・・・。 ま、そんな思いがあるだけに、非常に安い値段で頑張っているアパ・ホテルみたいなところに関しては、私は割と好意をもって応援していたんですけどね。 ということで、アパ・ホテルさんには今回の不祥事に真摯に対応し、企業体質を大いに改善して、再び庶民が心安く泊まれるホテルを日本中に作ってもらいたいもんです。
January 25, 2007
コメント(2)
-
勤労福祉会館という名のパラダイス
うちの大学からほど近いところに県営の「勤労福祉会館」みたいなのがあるんですが、これがこの3月をもって閉館という噂を聞き、ワタクシは大ショックでございます。 というのも、ここの1階にレストランがあり、同僚の「兄貴」ことK教授とよく食べに来ていたからです。ここ、大学に近い割には穴場で、他の大学関係者をあまり見かけないので、仕事関係の密談が出来たりして、すごく便利だったんですけどね・・・。 ま、そんなこともあったので、近日閉鎖の噂の真偽を確かめるべく、今日の昼食は兄貴と連れ立ってここのレストランでとることにしました。 ちなみにここでよく食べるのは「カツカレー」なんですが、今日は日替わりのランチプレートが「鳥のから揚げ&カレー」というものだったので、日和見してこちらを注文してしまいましたー。ま、ありがちなメニューですが、おいしかったです~。 で、料理を待っている間、年増のウェイトレスさんと雑談したのですが、閉鎖の噂はやっぱり本当でした・・・。この3月でレストランも含めたすべての設備が休業するのだそうです。 で、さらに話を聞いてみると、要するに今まで「県営」でやってきたこの種の施設が、来年度から「市営」になるんですって。で、市ではこの建物を1年かけて改修し、「生涯学習センター」みたいなものにして、再来年からの新規オープンを計画しているのだそうです。ふーん、そうですか・・・。 じゃ、ひょっとすると、市営施設として新規オープンする際に、レストランが何らかの形で再開することは十分ありえますな。そうなりゃ、こちらとしてはノー・プロブレムなんですけどね。 しかし、この施設を利用しているワタクシが言うのもなんですが、こんな辺鄙な土地に、こんな立派な勤労福祉会館なんか作っちゃった県も県ですよね。こんなところで泊まり掛けで会議とか研修会とかやる企業って、一体どのくらいあるんだろう・・・。ま、あまりないからこそ、県としては手放すことになったのでしょうが・・・。それにしても、こういう無駄な施設だって、県民の血税で作っているわけでしょ? でまた、レストランからの帰りがけに各種パンフレットを持ち帰って判明したんですけど、愛知県ってあちこちにこの種の「勤労福祉会館」を持っているんですな。尾西・一宮・半田・刈谷・鶴舞・瀬戸あたりに、それぞれ立派なのが建っているんですよ。 で、勤労福祉会館ってのは何をするところかと言えば、ま、安い料金で会議場とか研修所を提供してくれるところなんですが、ほとんどのところが宿泊施設を併設しているし、結局誰でも泊まれるので、要するに県営のホテルみたいなもんだと思えばいいのではないでしょうか。 で、宿泊施設だと見なした上で料金表を見るとビックリするんですけど、これがまた安いんだ。部屋を選ばなければ、一泊素泊まり1500円とか2000円ですもんね。 しかし、その一方でどの福祉会館もみんな中途半端な立地条件のところにあるので、観光の拠点に使えるというほどではないんだな~。ここに泊まってどうするの・・・、と途方に暮れるようなところにばっかり建っているんですもん。これじゃあいくら割安な料金だって、利用者は限られるでしょう。で、結局赤字になって、県の運営から切り離さざるを得ない、みたいなことになっちゃうんでしょうね。 ま、地方自治体のやることってのは、こういうレベルなんですな。夕張市が破産するのも当然ですわ。 でも・・・待てよ。・・・この瀬戸にある「愛知県労働者研修センター・サンパレア瀬戸」ってのは、ひょっとして面白いかも・・・。瀬戸の焼き物を見て、定光寺なんて古刹を見て、それでここに一泊してのんびりする、なんてのは案外いいんじゃない? 料金は・・・洋室2名部屋で一泊6800円(2名分料金)か。これでサウナ付き大浴場もあって、その上なんと「囲碁・将棋・麻雀・卓球・ビリヤードはいずれも無料」と来たもんだ! いいね、これ。いいよ! やっぱ卓球は鄙びた旅館の無料娯楽施設でやりたいよね! いや~、春休みとか利用して泊まっちゃおうかな・・・。っていうか、他の都府県にも、こういう隠れた激安宿泊所が結構あったりするんじゃないか知らん? そういうの、ネットで調べたら、案外掘り出し宿が見つかったりするのかも・・・。ひゃ~、楽しみ!! というわけで、御贔屓レストランの一時閉鎖を確認したにも係わらず、案外ウキウキして大学へ戻ってきたワタクシ(とK教授)だったのでした。今日も、いい日だ!
January 24, 2007
コメント(7)
-
キャロル・キングの歌声にうっとり
今日、大学から家に向かって車を走らせていた時、ラジオからキャロル・キングの歌が聞こえてきました。Love Makes the World というアルバムに収録されている "It Could Have Been Anyone" という歌です。It Could Have Been Anyone Do you know that you know me like nobody elseAll of my secrets and liesDo you know that you made me believe in myselfMade me believe I could flyAll the things that you sayThat I wait for each dayYou're almost too good to be true(Chorus) It could have been anyone, oh, anyoneA stranger out of the blueIt could have been anyone, oh anyoneThat I gave my heart up toBut it was you ちょうど冬の日が暮れようとしている時にこの曲ですからね・・・。なかなかいいもんでしたよ。 ということで、今日は少々センチメンタルに無口なワタクシなのでした。
January 23, 2007
コメント(4)
-

岸田秀著『不惑の雑考』を読む
昨日、二日間にわたるセンター試験が終わり、今日はその代休で大学はお休みでした。 しかし、今日は何だか足が筋肉痛で・・・。センター入試の試験監督って、結構体力要るんですよ。 試験監督中、机間巡視(またの名を機関銃巡視)をするのですが、この時足音を立てないよう気をつかって歩かなくてはならないんです。毎年受験生から「試験監督の足音がうるさい」という苦情が来ますのでね。 で、朝から夕方まで足音を立てないよう抜き足差し足で歩き回ると、これが足に来るんだ・・・。足音を立てないように歩くなんて、普段あまり心がけないですけど、こうしてたまに意識して歩いてみると、変に力が入ってしまってすごく疲れるんですわ。ほんと、ちょっとしたエクササイズですよ・・・。 あ! いいこと思いついた! デューク更家に続く新たなウォーキング・エクササイズ! 「釈迦楽流『猫足ダイエット』」ってのはどう? 足音を立てないことに気をつかいながら歩くだけで2週間で3キロ痩せる! みたいな・・・。 「あるある大事典」に話もちかけて見ようかな・・・(爆)閑話休題。 ところで毎年、センター試験の期間中、私は上着のポケットに文庫本を忍ばせておきます。さすがに試験監督を務めている間は読めませんけど、たとえば答案回収から次の試験までの5分、10分の休憩時間なんかにちょこちょこっと読もうと思ってね。 で、こういう時の読書というのは、初めて読む本はダメなんです。もう既に読んでいて、内容も分かっているけど再読したい本。それもあんまり難しくない奴。そういうのがいい。何せ細切れの時間を利用して読むので、そういう本じゃないと頭に入らないんですよ。 で、昨日私が読んでいたのは岸田秀の『不惑の雑考』(文春文庫)という本。岸田さんが40代の時に書いたエッセイを寄せ集めた本です。 岸田秀さんというのは、『ものぐさ精神分析』という本で一躍有名になり、一時はマスコミでよく取り上げられた人ですけど、今、どのくらい読まれているんでしょうかね。最近では、以前ほど名前を見かけないようですが・・・。 ま、それはともかく、岸田さんを有名にしたのは「唯幻論」という主張で、それによると人間というのは「本能の壊れた動物」だというのですね。で、本能が壊れているので、それとは別なものに頼って生きて行かなければならないんですが、その際人間が頼りにするのが「幻想」だ、というのです。たとえば日本民族には「血のつながった単一民族」という幻想がある。で、こういうふうに自分の民族を認識している国というのは他には例がなく、この特殊な自国に対する幻想を演繹していくと、なぜ日本人があれほど愚かな戦争に突入しちゃったか、なんてことがすごく明確に説明できたりする。 また日本の戦後思想のねじれを、男(アメリカ)にレイプされた女性(日本)の心境になぞらえて説明したりするんですけど、こういう説明の仕方も岸田さんの手にかかると実に説得力があるんだなー。ま、こういう説が学問的にどのくらい価値があるのか、私にはよく分かりませんが、無責任に読んでいる限り、「なるほど!」と思わされるところが多々あることは事実。大きな歴史的問題も卑近な事柄になぞらえて説明してくれるので、読み易いし分かり易い。 ちなみに岸田さんという方はその出生にまつわる家庭の事情がものすごく複雑で、それゆえ思春期の時に精神的にすごく悩んだ方なんですな。で、その時たまたまフロイトの精神分析に出会ってそれにのめり込み、その理論を応用して自己分析していったら自分の悩みの根源に辿り着くことが出来た。それで自分を苦しめていた悩みから解放されることが出来たんですね。ですから彼にとってフロイトの理論というのは、決して机上の空論ではなく、実質が伴っているわけですよ。岸田さんの心理学・精神分析というのは、そういうところから出発しているんです。彼の書くものに説得力があるのは、そのせいかも知れません。実体験に基づいていますからね。 ま、そんなこともあって、私も一時岸田さんの書かれるものを随分読んだのですが、今回久し振りに再読してみて、やっぱり面白いな、という認識を新たにしました。もし岸田さんの本を読んだことがないという方がいらっしゃいましたら、面白いですよ、とおすすめしておきましょう。 ところで、前に『不惑の雑考』を読んだ時には気づかなかったのですが、この本の文庫版の「あとがき」を俳優で作家の大鶴義丹が書いているんですね。私よりよっぽど若い人なのに、なんて生意気な・・・。 ・・・と思って今回、その解説も読んだのですが、読んだら「なるほど」と思いました。 大鶴さんって、東京にある「超お坊ちゃん学校」の高校に通っていたのですが、半年でそこを退学してしまったんですって。ま、彼曰く「ワルだったので」ということですが、とにかく飛び出してしまった。そしたら、16歳で学校に行っていないことがどんなに大変なことか、思い知ったというのですな。 たとえば、暇なので渋谷などの盛り場に行くと途端に補導されてしまう。「学校はどうした?」というわけです。あるいは、レンタルビデオ屋に行ってビデオでも借りようとすると、それも出来ないというのです。学生証がないので会員になれないんですね。 つまり、この日本において、16歳で学校に行っていないという状況がいかにしんどいか、というのを、彼は思い知るわけですよ。 でそんな身動きの出来ない状態の中で、大鶴さんは不良仲間とたむろしていたんですが、そんなある日、突然「こんなことではいかん!」という天啓を受け、「学校に入らねば!」と決意するんです。つまりその時点で「高校生でない人間」というネガティヴなアイデンティティから、「高校受験を目指す受験生」というポジティヴなアイデンティティへの大転換を成し遂げ、そのことによって思春期のアイデンティティ・クライシスを乗り越えることが出来たんですな。そして彼のような放校学生も受け入れてくれた和光高校に入学し、また和光大学で教鞭を執っていた岸田秀さんの本にも巡りあい、さらに自分の内面を強化することが出来たというわけ。彼が岸田秀の本の「あとがき」を書いているのには、そういう背景があったんです。 なるほどね~、って感じでしょ? そういうことならば、若い大鶴さんが岸田さんの本の「あとがき」を書く理由も理解できます。十分資格がありますよね。納得。 ただ・・・ま、敢えて言わせていただければ、私はそんな大鶴さんの「あとがき」を読んでいて、一つだけカチンと来たことがあるんです・・・。 実は大鶴さんの言う「都内の超お坊ちゃん学校」ってのは、私が小・中学校を過ごしたところでありまして、そこの卒業生として私は、この学校のことを「超お坊ちゃん学校」なんて呼んでもらいたくないんだなー。 確かにあそこは授業料のトンでもなく高い学校であり、その意味では「超お坊ちゃん学校」かも知れません。しかし、「お坊ちゃん」という言葉から連想されるような甘い学校では決してありません。独特の校風があって、それなりにタフじゃないと生き延びることは出来ないんです。夢のような素晴らしい学校なんですが、その一方で合わない人には合わない。で、その校風を知り抜いているからこそ、ワタクシは確信をもって言うのですが、大鶴さんはここの校風に合ってない感じがします。確かに半年持たないな・・・。 というわけで、いささか腹立ち紛れに言わせてもらいますと、彼は自分では退学の理由を「(自分が)ワルだったから」と言っていますが、真相は多分逆なんじゃないかしらん? ワルにこっぴどくいじめられたのではないの? 事実、そういう噂、聞いたことがありますもんね。人が知らないと思って、逆のこと言っちゃいけませんぜ、旦那。 だけど・・ひょっとして大鶴さんは、自分がその学校を退学したということを反芻する中で、意識的にか、あるいは無意識のうちにか、「いじめられて学校やめた」のではなく、「自分がワルだったから退学させられた」というふうにストーリー(=幻想)を書き換えたのか・・・。その方が受け入れ易いですからね。でまた仮にそうだとすると、まさにそのこと自体、「人間は幻想によって生きる」という岸田唯幻論のよき見本になっているんじゃん! じゃ、なおさら大鶴さんの「あとがき」は、岸田さんの本にふさわしいわけか・・・。 またまた納得。 ということで勝手に納得してしまいましたけど、そういうことも含め色々面白い本ですから、まだお読みでない方は是非!追伸: 『不惑の雑考』(文春文庫)をアフィリエイトしようと思ったのですが、絶版でした・・・。仕方がないので、ここでは岸田唯幻論の原点、『ものぐさ精神分析』をおすすめしておきます。こちらももちろん面白いですから、おすすめですよ~!これこれ! ↓ものぐさ精神分析改版
January 22, 2007
コメント(4)
-
大相撲初場所総括
大相撲初場所が終わりました。ということで恒例の総括と行きますか・・・。 しかし、「朝青龍が4場所連続、20度目の優勝を飾りました」って言った後、他に何を言えばいいの? って感じですなあ・・・。平幕の豊ノ島が12勝で一人気を吐いた以外、ほとんど言及するに足る活躍の力士が一人もいないのでは、もうどうしようもないですわ。 大体、大関が5人もいて、そのうちの誰一人として朝青龍に勝てない場所がずっと続いているわけでしょ? もうこいつら大関じゃないです。その名に値しない。白鵬にしても、琴欧洲にしても、ポロポロ負けやがって・・・。せめて千秋楽くらい、意地を見せてくれるかと思った朝青龍・琴欧洲戦ですが、大関がまるで稽古場のように裏返されて恥ずかしいったらない。あんな負け方したら、「次は殺してやる」くらいの気迫で朝青龍に立ち向かっていけばいいのに、どうせ来場所も土俵を這わせられることになるんでしょう。まったく、情けないったらありゃしない。 ま、その情けない大関の中では、千代大海だけ少し褒めてあげましょうか。このところ優勝争いに絡むほどの星を挙げられなくなってきたベテラン大関ではありますが、それにしてもここ数場所の相撲は悪くないんじゃないでしょうか。全盛期にしばしば見られた「引いて勝つ相撲」が影をひそめ、押しに徹する相撲を見せてくれるようになったのは、「遅かったり」とはいえ、評価に値します。 一方、白鵬と琴欧洲の今場所の相撲は良くなかった。どちらも立ち会い、まともにぶつからずに、ちょっと左右に変わって上手を取りにいくんですよ。二人ともまだ若いのに、そんな相撲とっててどうするんですか。まっすぐ当たって、差し手争いに勝って、その上で得意の四つに持っていくようじゃなくては・・・。 そういえば、今場所はそんな相撲ばっかりだったなあ。黒海もそう。立ち会い右に変わって上手を取りに行き、そのまま投げを打って勝つ、という相撲を覚えちゃって・・・。でまた、相手力士も馬鹿なもんで、黒海の作戦なんて見え透いているのに、どうしてその術中にはまって負けるんだろう? 少しは相手力士のことを研究しろよ、って感じです。 とにかく、そんなこんなでつまらない場所でした。 ほんと、これだけ大相撲好きの私の贔屓目から見ても、今場所はつまらなかったなあ。 もっとも朝青龍ファンにとっては、毎場所毎場所面白くて仕方がないのでしょう。私は思い切り朝青龍が嫌いなので、それでつまらないだけなのかも知れません。 たしかに朝青龍は強い。それは私も認めます。しかし、なんか「嫌らしい」んですよね、あの力士。一言で言えば「下品」というか・・・。特に勝った後の表情、懸賞金を受け取る時の芝居がかった仕種。あれ見てるだけでげっそりするので、朝青龍が勝った時はすぐテレビを消すようにしています。 と言いますかね・・・ま、はっきり言って私は朝青龍が嫌い、と言うよりも、むしろ「外国人力士」というのが受け入れられないんでしょう、相撲ファンとして・・・。 あ、ついに言ってもうた!(爆) ま、こういうことを言うと、各方面から批判されるんですよ。しかしね、これは別に国粋主義者的な発言ではないんです。 たとえばね、どんなに日本語のうまい、歌の上手な人であったとしても、ケニアから来た人が日本の演歌歌手としてデビューしたら、それ、受け入れられます? 「津軽海峡冬景色」ったって、あなたは太陽の国から来たんでしょ、と思ったら、もう聴いていられないんじゃないでしょうか。 あるいはどんなにセリフ回しのいい人だったとしても、金髪碧眼の人が「大石蔵之助」を演じたとしたら、『忠臣蔵』見る気になりますか? ならないでしょ? そういうことですよ。世の中には、本質的に「インターナショナル」じゃないものってのがあるんです。で、相撲がまさにそれで、あれはインターナショナルなスポーツじゃない。あれはね、日本の国の各地方から集まってきた力自慢が力を争う一種の神事みたいなもんなんです。だから力士たちが勝ったり負けたりするのを、日本の神様たちに見てもらって、その神様たちを喜ばす(そして五穀豊穣を願う)のが本来の目的なわけ。 まただからこそ、個々の力士が勝って喜んだり、負けて悔しがったりするのは見苦しいわけですよ。土俵に上った力士は一種の神主みたいなものなんだから、相撲の結果勝とうが負けようが、常に伏目がちに無表情を貫き、一礼して土俵を去る、というのが正しいあり方なんです。たとえばかつての名大関・北天佑を思い出して下さい。彼の土俵態度、あれこそが大相撲の醍醐味というものです。 で、そういう相撲本来のあり方を踏まえた場合、外国人の横綱が「喧嘩でもするつもりか?」と思うような仕切りをし、勝ったら勝ったで、「ざまあ見ろ」「してやったり」といわんばかりの態度を示し、がめつい商人を思わせるような下品な笑みで懸賞金を受け取り、最終的には優勝してしまうことに耐えられるか? ってことですわ。それを見ている日本の神様たちが果たして天上で手を打って興じてくれているかどうか・・・。私にはとてもそんなことは想像できません。 もちろん、私のそういう相撲観は個々の力士に対する好悪とは直接関係はありませんよ。たとえば私は安馬のような若者らしい力士が好きだし、琴欧洲の相撲に可能性を見ているし、旭天鵬の穏やかな人柄が好きです(おっと、旭天鵬は帰化したからモンゴル人じゃなくて日本人か・・・)。しかし、それとは別な次元の話として、上に述べたように、「外国人力士」というものは本来的に受け入れ難い、と言っているんです。 ・・・ま、そういうことです。 というわけで、今後もしばらくは朝青龍の天下が続くのだと思うと、「来場所が楽しみだ!」といういつものセリフが、心の底から出て来ないのが悲しいですけど、来場所は春場所です。春場所というのは「荒れる」のが持ち味ですから、誰でもいい、朝青龍以外の力士の優勝が見られるよう、横綱以外の力士たちの奮起を待ちたいと思います。
January 21, 2007
コメント(2)
-
センター入試でクタクタ!
今日はセンター入試初日。私も試験監督に駆り出されましたけど、これが大変なんだ! なんせ朝の集合から最後の試験が終わるまで10時間勤務ですよ。もうクタクタ・・・。 しかも初日の最後には昨年から導入された「リスニング試験」という奴があって、これがまた大変な試験なんですわ。英語のリスニングなんですけど、全国の受験生全員にICプレーヤーというのを配布して、30分間のリスニングをやらせるわけ。 しかし全国の受験生ともなると、50万人とか60万人という数ですからね。それだけの受験生の一人一人にICプレーヤーを配布するとなれば、中には不具合の生じるICプレーヤーが出てきてもおかしくはない。で、試験中にそういう機械的なミスがあった時はどうするか、なんてことが事細かに決まっているんですけど、これがやたらに面倒なんだ・・・。というのも、リスニングをしている他の受験生の迷惑にならないよう、当該の受験生とは「筆談」で事情を聴取しなければならないんです。筆談ですよ、筆談・・・。 それに、不測の事態はICプレーヤーの故障だけとは限りません。たとえば「問題冊子」に乱丁・落丁があるかも知れませんしね。 でも、入試本部が想定している幾多の不測の事態の中で「最悪のシナリオ」は何かと申しますと、答案の汚損があった場合、つまり、試験中に受験生が「オエ~!」とやった場合です。 その場合、どうするかと申しますと・・・我々試験監督がそのモノを「始末する」ことになっているんです~! そんなのヤダヨ~! しかも、この「オエ~!」のシナリオには、非常に奇妙な「キャッチ=22」が仕込まれているんだな~。 どういうことかと申しますと、たとえば試験中に気分が悪くなってトイレに駆け込んだとするじゃないですか。その場合、トイレに行っている間にもどんどん音声は流れているので、その間の問題には答えられないということになってしまいます。この場合、自己責任ということで救済措置はとられません。 しかし、気分が悪くなった受験生が、その場で「オエ~!」とやったとしますよね。その場合は、「答案汚損」というケースになるので、再テストが受けられるんです。 つまりどこで吐くかによって、扱いが変わるわけ。当然、試験室内で吐いた方が有利です。 ・・・だったら、試験室内で吐く奴が出るかも知れないじゃないですか! やめてくれ~! てなわけで、私も試験監督をしている間、「どうか『オエ~!』をやらないでくれ!」と祈り続けましたよ。しかし、今日は朝も早よから幾つも試験を受けて疲弊しきっている受験生の半分くらいが、今にも吐きそうな顔をしているんだ、これが・・・。もう、ヒヤヒヤ。 でも、私の祈りは天に通じたらしく、私の担当する試験室ではトラブル一切なし。他の試験室もほぼノートラブルだったようで、トラブル続きだった昨年のセンター入試と比べると、大分進歩が見られました。良かった、良かった。 しかし、そんな心配もあったものですから、疲れた、疲れた。もうクタクタ。でも、また明日も二日目があるんですよね・・・。ほんと、入試シーズンというのは、受験する方も監督する方も疲労困憊でございます。 ということで、明日も早いので今日はもう寝ます。お休みなさーい!!
January 20, 2007
コメント(4)
-
伊風人で生パスタを堪能!
今朝方、宇宙航空工学のF名誉教授と雑談していたのですが、その際、お土産(?)にNASA(アメリカ航空宇宙局)のステッカーをもらってしまいました。F教授は1970年代の半ば、NASAで2年ほどお仕事をされていたことがあるのでね。 で、話がNASA のことになったので、どうしてF先生はNASAで働くチャンスを得られたのですか? と問うと、当時、つまり先生がまだ30代の頃、先生のグループの研究がアメリカの学会に認められ、先生のお名前がアメリカでも知られるようになり、それでNASAの方から「こっちで働かないか」という声がかかったのだとか。NASA だけでなくスタンフォード大学からも招聘が来たと言うのですから、大したもんです。 F先生曰く、時代も良かったんですって。当時はまだアポロ11号が月面着陸して間もない頃でしたし、米ソの冷戦も続いていたので、科学の最先端はF教授のご専門の「航空宇宙工学」にあって、それだけ注目も浴び、助成金も欲しいだけ得られたのだとか。 ところが残念なことに、現在では、科学の最前線はもう他の学問分野に移ってしまったそうです。 じゃ、今、科学の最前線はどこにあると思います? 「生物学」だそうですよ。バイオロジー。今やノーベル生理学賞のみならず、ノーベル化学賞すら生物学者がとる時代なんだとか。ふーむ。 時代は「大宇宙」の研究から、人体という「小宇宙」の研究へと移行したんですな・・・。 ほんと、F先生とお話していると、色々な意味で啓蒙されます。 さて、話は変わりますが、今日はセンター入試の前日ということで大学はお休み。ということで、お昼は家内を連れて外食することにしました。向かったのは名古屋のベッドタウン、緑区は「滝の水」というところにある「伊風人」というパスタのお店。マンションの1階にあるこじんまりとしたお店で、テーブル席が4つ、あとはカウンター席だけ、20人も入ったら満杯になりそうです。 で、このお店の売りは、何といっても一日30食限定の生パスタ。幸い、我々が行った時はまだ残っていたので、私も家内も生パスタのメニューを注文しました。私は「スモークサーモンとほうれん草のカルボナーラ」、家内は「鶏ミンチとゴボウの和風クリームパスタ」です。 で、料理が出るまでの間、サラダ・バーとドリンク・バーを楽しむことにしました。今日はサラダが3~4種、それにポトフ風のホットサラダが出ていましたので、欲張って全部試してみましたけれど、どれも新鮮でおいしかったです。ドリンク・バーのジュースも100%ものが置いてありましたしね。 そして、いよいよ登場した生パスタですが、そのお味はと言いますと・・・ うま~い! 合格! 乾めんとは違う独特の食感を持った太めの生パスタが、クリーム系のソースによく絡んで実においしかったです。点数を付けるならば「カルボナーラ」が89点、「鶏ミンチとゴボウ」が93点というところですね。ちなみに今回我々は注文しなかったですけど、この店の「タラコ・スパ」はすごくおいしいそうですよ~。次は私もそれを頼んでみようかな。 サラダ・バー食べ放題、ドリンク・バー飲み放題で、生パスタランチが1480円、乾めんのメニューだとさらに100円ほど割安ですから、名古屋にお住まいでパスタ好きの方はぜひ一度「伊風人」をお試し下さい。教授のおすすめ!です。 さて、そんな感じで大満足しつつ帰路についた我らですが、せっかく外に出たのだから、もしこの近くに面白そうな雑貨屋さんでもあれば、ちょっと立ち寄っていくか、なんて話ながら車を運転していたところ、雑貨屋さんではないけれど、面白そうなお店を発見してしまいました。「タチヤ」という業務用っぽい生鮮食料品店です。ちょうど信号で止まったところに入り口があって、何だか大勢の人がわっさわっさ買い物をしていたので、ちょっと寄ってみようかということになったわけ。 で、入ってみますと、まさに業務用のスーパーという感じ。顧客にはレストラン関係の人が多いらしく、皆、野菜を箱ごと幾つも買っています。 実際、なんでも安いんだ、これが! 白菜の巨大な一玉、大きな人参7本がそれぞれ100円、山のようなじゃがいもが150円、ルッコラやイタリアンパセリのような小洒落た野菜も1パック30円。魚となると、ボイルした大きなタラバ蟹が1ぱい680円、塩引き鮭丸々1本580円、50センチほどのスズキが一尾150円とか、そんな感じですからね。その他、井村屋の冷凍あんまんが6個100円なんて言われると、もう買わずにはおられんじゃないですか!! ということで、家内共々、時に理性を失いかけては互いに「まァまァ、そう興奮しないで・・・」(←最近の我が家の流行語)と声を掛け合いながら、それでも買い物籠一杯分ほどは食料調達してしまいました。今や御禁制品となってしまった不二家の「カントリー・マアム」だとか「ホームパイ」の巨大パックなんかも買っちゃいましたぜ。 で、意気揚々と駐車場に戻ってみて気づいたのですが、こんな大安売りのスーパーに群がる人たちの車がまた高級車ばっかりなんだ・・・。ベンツ、ジャガー、ベンツ、クラウン、ベンツ、クラウン・・・みたいな感じ。そういえば、緑区滝の水周辺って高級住宅街だもんなあ。 分かった! この辺の人たちは皆、「タチヤ」で食料品を安く調達して、それでお金貯めて家と高級車を買ったんだ! かくして「伊風人」で生パスタを満喫し、「タチヤ」で格安食料品を山のように仕入れた我ら夫婦は、妙に納得しつつ家路についたのでした、とさ!
January 19, 2007
コメント(4)
-
怖し楽しの笑気ガス
ミルキーの食べ過ぎ、かどうかは分かりませんが、奥歯に虫歯ができてしまいました~。 ということで、今日は歯医者さんに行ってきました。 しかしですね、ワタクシの場合、これが大変なことでして・・・。 と言いますのも、ワタクシ、嘔吐反射がひどいんです。なので歯医者さんの治療というのはまさに地獄でございまして、毎回「オエ、オエ~」の発作で七転八倒するわけ。 ま、歯を削るとか、そういうのはまだいいんですが、粘土の塊みたいなのを「うにょ!」と押しつけて歯の型を取るのが辛いんですなあ。最近のものは固まるのが速くて、1分くらい我慢すればいいのですが、それが辛いんですわ、ワタクシには・・・。 ということで、近所の歯医者さんじゃ辛過ぎるということになり、愛知学院大学歯学部附属病院に行って来ました。 愛知県以外にお住まいの方は何のこっちゃとお思いになるでしょうが、愛知学院大学歯学部といったらこの地方の歯学部の名門。県内の歯科医は、そのほとんどがここを出ているのではないかというくらいのもんです。まさに愛知県の歯医者さんの総本山ですな。で、さすがに総本山だけあって、ここには「嘔吐反射外来」というのがあるんです。私のように、すぐ「オエ、オエ~!」となってしまう患者専用の治療体制が整っているわけ。私が藁にもすがる思いでここを訪れたのも、そういう理由だったんです。 ま、今日は最初ですから、とりあえず一般の外来で診ていただいたのですが、やはり私の「オエ、オエ度数」の高さを見た先生から、「これはやはり、嘔吐反射外来の方に行ってもらった方がいいですね」という診断をいただき、次からはそちらの方に行くことになりました。 もっとも、私と同じような患者さんが結構沢山いらっしゃるのか、次回は2ヶ月後ということになっちゃいましたけどね・・・。 で、今日は説明だけ受けてきたのですが、嘔吐反射外来にもレベルがありまして。まず一番軽いのは「笑気ガス」を使う奴。このガスを吸うと、ミョ~にリラックスしてしまって、恐怖心が無くなってしまい、たいていの場合は嘔吐反射も鈍くなるのだそうです。ちょうど寝入りばなのような、夢現の境地になるらしいんですな。顔つきもデレ~っとなって、笑っているように見えるので、この名前が付いているらしい。 で、これがダメなら次は静脈注射でもっと本格的に麻酔をかけた上での治療となり、それでもダメなら、最終手段として完全な全身麻酔で一気に治療、ということになるのだとか。 ま、全身麻酔というところまでは行きたくないので、「笑気ガス」作戦でなんとかうまいこと治療ができないかな、と、私としても期待しているんですけどね。 でも、その「笑気ガス」というの、ちょっと興味ありますねえ。夢現のうちに、気づいたら治療が終わっていた、なーんてことにならないか知らん。 ということで、2ヶ月先の治療日を、怖いような、楽しみなような、ミョ~な気持ちで待っているワタクシなのでした。ワタクシと同じように嘔吐反射で歯科治療に苦労している方、あるいは、歯医者さんで笑気ガスを吸ったことのある方、お便りお待ちしてま~す。
January 18, 2007
コメント(4)
-
イギリスにサムライ現る
相変わらず我が国は「殺人列島」の様相を呈しておりますなあ。兄は妹をバーラバラ、妻は夫をバーラバラ、漫画家志望の学生は刺し殺され、茨城では腹に包丁が突き刺さったままの死体が農道にゴロリですか・・・。 猫虐待男のニュースも嫌な話だなあ、と思っていたら、今日は大阪で変質者が3歳の坊やを歩道橋から投げ落としたそうで・・・。もう右も左も真っ暗闇ですな。 ほんと、こんなニュースばっかり聞かされていたら、この国は一体どういう国なんじゃと思いますよね・・・。 ところで、そんな暗い話題ばかりが新聞の紙面を飾る中、私が仕入れた「いい話」を一つ。 イギリスで最近、実際に起こった話らしいのですが、イギリス北部のある町のある民家に強盗が押し入ったんですって。民家には2人の女性が住んでいたらしいのですが、たまたま近くを通り掛かった私服警官2名が、女性たちの悲鳴を聞きつけ現場に急行! ところが、対する強盗は5人組だったんですな。これでは多勢に無勢で警官も手が出せません。それどころか自分たち有利と見てとった強盗団は警官2人組に反撃! ナイフを手に警官に襲いかかる! と、その時です! どこからともなく現れたサムライ一人! 手にした抜き身の日本刀で警官に襲いかかった強盗を一蹴! そして、あわてふためいて逃げ出そうとした強盗どもの前に立ちはだかり、警官たちと協力して見事5人の強盗を逮捕! そして、大方収拾がついたと見て取ったそのサムライは、現れた時と同じように、風のようにどこかへ去って行ったのだそうです。 実話ですよ、実話。今、イギリス警察は、この謎のサムライを追っているんですって。 それにしても、面白い話じゃないですか。私、こういう話、好きだなあ! 陰惨な事件の報道が多い中、異国の地に現れた正義のサムライの報道に、思わず快哉を叫んでしまったワタクシだったのでした。 さて、ここで一つ、ブログを読んで下さっている皆さんにご紹介したいことが・・・。 私の友人に夫婦でプロの陶芸家、というのがいるのですが、その奥さんの方、井上佳由理さんの作陶展が現在、大丸東京店10階にある「ギャラリーてん」というところで開かれています。会期は今日から1月23日(火)までの一週間。彼女の作品は私も幾つか所有していますが、非常に繊細、かつウィットに富んだ素晴らしい作品を作る方ですので、機会がありましたらぜひ一度ご覧になって下さい。きっと楽しい時間が過ごせると思いますよ~!
January 17, 2007
コメント(4)
-
不二家を歌おう!
不二家・・・。雪印に続いて信頼のブランドが・・・。 好きだったのになあ、不二家。ミルキーとか、やたらうまくないですか? 私の個人的な思い入れの中で、「森永キャラメル」は普通のお菓子だけど、不二家の「ミルキー」はなんかこう「ちょっと特別」みたいな位置づけだったんですけどね・・・。 それからぐるぐる渦巻きの「ノース・キャロライナ」! 名前からしてセンスがいいねえ! あと「ソフト・エクレア」。キャラメルの中から「うにゅ~」と出てくるクリームのおいしさたるや・・・。 もちろんペンシル・チョコレート、パラソル・チョコレート、あれも好きだったなあ。チョコレートなのに、チョコレート以外の形をしているというところに、子供心がどんなにくすぐられたことか・・・。 あと「カントリー・マアム」! 劇ウマ! だいたい、私はテーマソングがついているお菓子って、好きなんですよ。特に不二家は、そのほとんどのお菓子にテーマソングがありますからね。「ミルキーはママの味~」って、誰でも歌えるでしょ? じゃ、これ歌えます? 「とーれこちょ、とーれこちょ、るしんぺ、るそらぱ、とーれこちょ、不二家~、ペンシル・パラソル・チョコレート」・・・ これはちょっとコアな不二家ファンじゃないと歌えないか・・・。 じゃ、これはどう? 「ほっぺたに~、プーレゼント~、不二家ソフトー、ソーフトー、エクレア~」。 ユーミンですよ、ユーミン。昔、ユーミンはよく不二家のお菓子のテーマソング歌ってたんだよな~。「パーパは、兄さん。マーマは、姉さん。だーから僕たちー、と・も・だ・ち~。キャーンディーは、不二家!」ってね。 おお! なんか、楽しくなってきたゾ! 不二家以外だと、東鳩がいい歌作りますよね。「思い出の朝~、東鳩オールレーズン~」とかね。あと「キャラメルコ~ン、ほ、ほ、ほ、ほ、ほう!」も名曲だ。 大手ではやっぱり明治製菓ですな。「チョッコレート、チョッコレート、チョコレートはめ・い・じ」なんて、いいねえ。短調ですよ、短調。短調でお菓子の歌作るなんて、至難の技ですわ。桑田圭佑もビックリだ。あと、「ほーら、チェルシー、も一つー、チェルシー(あなたにも、チェルシー、あげたい)」も素晴らしい。「それにつけてもおやつはカール!」とか「ポポロン、ロン、ロン、ポポロン、ロン」も明治か・・・。 それに比べると、グリコは名曲に乏しいなあ。森永・ロッテもあんまり思いつかない・・・。ま、森永には「ピポピポ!」が、ロッテには「チョッコレートは、ロッテ!」が、それぞれありますけどね。 あ、じゃ、これはどう? 「キャン、キャン、キャンロップ、佐久間のキャンロップ。しゃぶっちゃった、なめちゃった、おいしかったわキャンロップ。キャン、キャン、キャンロップ、佐久間のキャンロップ」。懐かし~! あと「ライオネス・コーヒー・キャンディー、ライオネス・コーヒー・キャンディー、本場のコーヒーのー味。ライオネス・コーヒー・キャンディー。広がる味はコーヒー。ライオネス・コーヒー・キャンディー、ららら、ライオネス・コーヒー・キャンディー。コーヒー!」とかね。「本場のコーヒーの味」というところが、泣かせるなあ・・・。 ・・・何の話でしたっけ・・・? そうそう、不二家の話をしていたんだ。いいお菓子、いい歌、そしてペコちゃん・ポコちゃんのようなキャラクターを生み出してきた伝統ある製菓会社なんですから、しっかり建て直して、私のようなファンの信頼を取り戻して下さいよ。 それにしても、回収された不二家のお菓子、どうなるんだろう・・・。こっそりもらえないかな(爆)。
January 16, 2007
コメント(8)
-
ゼミ生と打ち上げ!
今日は卒論提出後、最初のゼミの日だったので、ゼミ後、打ち上げ会をしました。 で、我々一行が向かったのは「赤から」というキムチ鍋のお店。チェーン店らしいのですが、人気があるらしく、なかなか繁盛していましたねぇ。 ちなみに、この店のキムチ鍋には辛さが10段階あって、我々は「初心者オススメ」のレベル3を選びました。で、ここでウォームアップをした後、レベル4に格上げしましたが、これでも相当辛かった! レベル10なんて、とてもとても・・・。 でも、〆のラーメン、そして雑炊、うまかったなあ・・・。 さて、てなわけでキムチ鍋に舌鼓を打ちながらゼミ生たちと色々四方山話をしていたのですが、卒論提出後の彼女らはものすごく忙しい日々を過ごしているようで・・・。ま、卒業旅行に備えてバリバリにバイトを入れていることもそうなんですが、それに加えて就職先の会社の研修も多いらしく、中にはほとんど社員なみに働かされているのもいたりします。 そういう話を聞く度に、私は腹が立つんですよね~! だって私のゼミ生たち、3月31日までは歴としたうちの大学の学生ですよ。4月1日からは就職先の会社に魂を売ったかも知れないけれど、それまではうちの大学の預かりモンですわ。それをまあ、なんで勝手に「自分とこの社員」みたいな感じで使うんだよ! ふざけるなって! 学生生活も残りわずかというこの時期に、学生としてやるべきことはいくらでもあるはずなのに・・・。 で、私は腹立ち紛れに「そんな研修なんて、断ったれ!」とハッパをかけるのですが、「ようやく希望の会社に採用してもらった」という意識の強い学生たちとしては、そんなことが出来るはずもなし・・・。ほんと、不条理な世の中でございます。 しかし、そんな中で一つだけ私が「ほ、ほう!」と思ったのは、愛知県警です。私のゼミ生でひとり、婦警さんになる子がいるんですが、この子に県警から課せられた宿題というのは、なんと!「バイクの免許をとる」ということだったのでした。 ほ、ほう! って感じでしょ? でまたこのゼミ生というのがほんとに小柄な子で、中型バイクに跨がっているところなんてとても想像できないんです。でも、やっぱり婦警さんともなると、犯人を追っかけるのにバイクくらい乗れないとまずいのでしょうなぁ・・・。 それにしても、ちょっと面白い「宿題」ではありますね。 というわけで、職業によって事前の準備というものにも色々あるんだなあと、妙に感心してしまったワタクシだったのでした。今日も、いい日だ!
January 15, 2007
コメント(9)
-
ミクシィってどう?
最近、ネット上の図書検索エンジンとして「想・IMAGINE Book Search」というものの存在を知り、使い始めたところ、これがなかなか良いんですわ。一つのキーワードなりフレーズなりを打ち込めば、そこから連想される言葉も含めてサーチしてくれるので、思いがけない収穫があったりするんです。人文系の研究者にはまさにうってつけのサーチ・エンジンで、既にお使いの方もおられると思いますが、もしまだご存じないようでしたら、ぜひ一度使ってみて下さい。「教授のおすすめ!」です。これこれ! ↓想・IMAGINE Book Search しかし、インターネットってのは、ほんと加速度的に進化していきますね。大したもんだ・・・。 ところで、今日は一つ、このブログをお読みの皆様にインターネットに関することで質問があるんです。実は「ミクシィ」のことについてなんですけど、どうなんですか、アレ? いや、私自身はこのブログをやめてミクシィに移行するとか、そういうつもりはまるでないのですが、一つ考えていることがありまして・・・。 つまりですね、私の勤務先大学の卒業生を束ねる「同窓会」の窓口として、ミクシィが使えないかなぁ、と思っているんです。 現在、うちの科の同窓生も相当な数に上っておりまして、毎年一回、会報を発行するのも大変。その会報を卒業生のもとに送るための送料にしたって相当なもので、これが毎年徴集している同窓会費の相当部分を食ってしまうんです。 で、だったら、同窓会用にミクシィを立ち上げ、卒業生全員に登録してもらったらどうなのかな、と。そうしたら、時々私が大学の様子をそこに書き込んだり、卒業生が近況を報告しあったりすることも出来ますし、あるいはまたどこかで同窓会のパーティーをやるというのであれば、その掲示板としても使えるのではないでしょうか。今は印刷物として送付している「同窓会報」も、ペーパーレスにしてしまうことも出来そうですしね。 それに、一般のブログと違って一般公開ではないですから、卒業生以外の人が見るというような危険性もないですし。 あと、運営者に非公開でメールを送れるのであれば、卒業生の住所変更などの届け出も簡単に出来そうではないですか。色々いいことづくめのように思えるのですが・・・。 とはいえ、私自身はミクシィに入っていないので、実際にミクシィがどういうものなのか、今一つ分かっていないところもあります。果たして上に述べたようなことが可能なのかすら、実はよく分かっていないんです。 ということで、今、その辺の可能性を探っているところなんですけど、どうなんでしょうね、このアイディア? 何か致命的な問題点がありますか? ミクシィをやっていて、その辺のことに詳しい方、ご教示くださーい。
January 14, 2007
コメント(5)
-
池田満寿夫対談集『鳥たちのように私は語った』を読む
先日、実家に戻っていた時に古書店で買った池田満寿夫の対談集『鳥たちのように私は語った』(角川書店・絶版)を読みました。 この本、1976年から1977年にかけて池田満寿夫が行った芸術家や小説家たちとの対談をまとめたものなんですが、池田満寿夫が『エーゲ海に捧ぐ』で芥川賞をとるのが1977年の夏ですから、その直前の頃の話ですね。彼は芥川賞をとる前に角川書店の主催する「野生時代新人賞」をとっていて、ひょっとすると芥川賞も・・・と思われていたのですから、本業と副業の双方で波に乗っていた頃、と言えるでしょう。ですから、対談においても大御所相手に堂々と渡り合っていて、自分に対する自信が窺えます。 で、本書の中で満寿夫と対談しているのは誰かと言いますと、詩人で慶應大学教授の西脇順三郎、画家の加山又造、作曲家の武満徹、小説家の安岡章太郎、村上龍、吉行淳之介の計6名。まさに錚々たるメンバーですな。 で、相手が相手なので、どの対談も面白いですが、対談というのは、結局、その場の空気ですからね。活字におこしてしまうと、どうしても「とりとめのない話」のようになってしまいますから、それをここでさらに私が解説・紹介したところで、さらに面白くなくなってしまいます。ですから、興味のある方には一読をおすすめします、と言っておくに止めておきましょう。 ただ、一つだけ、加山又造との対談の中でちょっと面白いことが書いてあったので、それを紹介します。この時二人は「洋画と日本画の違い」ということについて話をしていたのですが、最近では日本画家でも油絵具を使う人もいたりして、画材の違いが両者を分けるとは言えなくなってきたのではないか、というような話の流れがあった後、ひょっとして「キャンバスを立てて描くか、寝かせて描くか」というところに大きな違いがあるのではないか、という話になっていったんです。 洋画はキャンバスをイーゼルに乗せて描きますから、絵を立てて描きますよね。一方日本画は紙を机の上に寝かせて描くことが多い。この違いが、洋画と日本画に影響を与えているのではないか、というのですな。 つまり絵を立てて描く洋画では、水平線(地平線)というものが重要になってくる。天と地を分ける線ですな。で、そうやって上と下がはっきり決まってしまうと、今度は必然的に奥行きというものが要求されるので、遠近法で奥行きも決まってしまう。となると、もうその段階で空間が厳密に限定されてしまいます。 ところが紙を机の上に水平に置き、四方から色を置いていく日本画では、空間が持つ「上・下・奥行き」というものが曖昧になり、画家もちょうど神様が天から人界を見下ろすような感じで、ものを描くことになるのではないか。つまり視界が四方に広がるような調子で描いているのではないか、というのです。 ほ、ほう、って感じでしょ? ま、上のアイディアは主として満寿夫のものなんですけど、加山さんもそれを肯定し、「洋画っていうのは植物的なもの、いわゆる根がはえていて、そこからの距離、厳密な距離計って描く。日本画の場合は動いて、わからなければそばによって、頭描く時はその高さから、脚描く時は視点を下げて、地面描く時は真下を向く」と述べています。そしてそれに加えて、「(ぼくは洋画家と違って)光と影では物を絶対に見ない。動と静、その差によって物の形が決まる。走る雲、動かない山、そこに一つの形が生まれる。光が朝であろうが、昼、夜であろうが構わない」と述べています。 なるほど、洋画は「光と影」、日本画は「動と静」ですか・・・。 で、だから加山さんなんかから見ると、光と影で物を描く「印象派」なんてのは、非常に古臭く見えるし、逆にセザンヌやピカソは分かるのだそうです。なるほどねぇ~! 私、今まで洋画と日本画の違いなんてことに、さほど深く思いを巡らせたことがありませんでしたが、こう言われてみると、なんかヒントをもらったような感じがしますね。二人の意見に賛同するかどうかは別として、次に洋画・日本画を見る時、注意してみるべき視点を与えられたような気がします。 ま、この対談集には、このような「ちょっとしたヒント」がちょこちょこあります。一読して損はない本だと思いますよ~。もし古書店や図書館などで入手できるようであれば、読んでみて下さい。 ちなみに、この本の巻末には、池田満寿夫が芥川賞をとった時の記者会見でのスピーチ・質疑応答も掲載されているのですが、こういうのを読むと、今からちょうど30年前の芥川賞というのが、いかに権威があったかというのがよく分かりますね。特に池田満寿夫のように、異業種の人が受賞したということが余計反響を呼んだのでしょうけれど、当時中学生に過ぎなかった私ですら、その時の大騒ぎのことをよく覚えていますもんね。 それに比べると、今、誰が芥川賞とったかなんていちいち覚えていないですもん。2年くらい前に二十歳くらいの小娘が二人、受賞したのは覚えていますが、その後、あるいはその前、誰がこの賞をとったか、覚えています? もう芥川賞とったから、その作家の将来はばっちり保証された、というような時代じゃないんでしょうな。かつて価値や権威のあったものも、今ではすっかり相対化されてしまったし・・・。 というわけで、芥川賞一発でその人の人生が変わってしまうような時代。そんな時代のことを懐かしく思い出しながら、私はこの池田満寿夫の対談集を、大いに楽しんだのでした。
January 13, 2007
コメント(2)
-
リニモに乗って、フレッシュネス・バーガーを食べに行く
今日は「生まれて初めて」ということを色々やりました。 まずは最初の「初めて」は、愛知万博で活躍したリニアモーターカー「リニモ」に乗ったこと。これ、一度乗ってみたかったんです。近くに住んでいるのに、まだ一度も乗ったことなかったんですもーん。 ということで、まずは車で「入ヶ池」というところまで行き、そこに車を停めて、リニモに初乗車! いやー、なかなかよかったですよ、リニモ。とにかく乗り心地が滑らか。レールの上を走っているわけではないので、レールの継ぎ目を踏む時の「ゴトンゴトン」という電車特有のリズミカルな振動がまるでないんです。まさに宙を行くような、未来的な乗り心地でした。 未来的といえば、運転手がいないというのも、未来的でしたネ。リニモって、無人走行をするんですよ。うまいことコンピュータ制御しているのでしょうけど、不思議な感じでしたなあ。 というわけで、ちょっとの間でしたけど、結構面白かったですーー。 ところで、なんで家内と私がわざわざリニモに乗ったかと言いますと、「藤ヶ丘」というところに行きたかったからなんです。実は、この駅の近くに「フレッシュネス・バーガー」が出店しているということを最近知ったものですから、こいつはぜひトライしてみなければ、ということになったんですな。既に食べたことのある私の姪に言わせると、マックなんかより遥かにおいしい、ということでしたので、前から食べてみたかったんです。 で、その「フレッシュネス・バーガー」なるものを生まれて初めて食べてみた感想はと言いますと・・・ ビミョ~! 我々が食べたのは、セット・メニューで、「フレッシュネス・バーガー」にポテト&スープ(またはコーヒー)がついて600円というものだったのですが、ま、「普通においしい」というレベルでしたね。方向性としてはトマトが挟んであったりして、モス・バーガーに近いものがありますが、それだったらモス・バーガーの方がおいしさにインパクトがあるかな、という感じがします。 ま、ひょっとすると一個430円の「クラシック・バーガー」を食べるべきだったのかも知れません。こちらの方はパテもより大きく上等な感じで、トマトの他にスライスしたタマネギなんかも入っているみたい・・・。いつかもう一度、このクラシック・バーガーを食べてみてから、「フレッシュネス・バーガー」に対する最終的な評価を下すことにしましょうかね。 でも、とにかく一応フレッシュネス・バーガーを食ったどー、ということにすっかり満足した我ら夫婦は、ついでに近くのスタバでコーヒー飲んでまったりしてから、再びリニモに乗って帰ってきたのでした。ちょっとした午後の散歩でしたけど、初体験が二つも重なって楽しかったです。 しかし、今日の「初めて」は、これだけではなかったんですなー。 髪の毛がボサボサに伸びてしまったので、床屋さんに行きたかったのですが、いつものお気に入りの床屋のおじさんが、どういうわけかこの頃店にいなくて、それで今日は別な床屋さんに行ってみた、というわけ。 で、今日行ってみたのは「3Qカット」という床屋さんなのですが、ここの売りは「10分、1000円」というもの。安くて早いんですよ。東京でよく見かける「QBハウス」みたいなもんですな。 前にもこのブログに書いたかも知れませんが、私が床屋に求めるものは「1に早さ、2に早さ、3、4がなくて、5に早さ」なんです。ですから、10分でやってくれるのなら、こいつは御の字だと思ったわけ。 実際、店に入ってみると、これがなかなか合理的なシステムでして。客はいきなり自販機に1000円を投入して「カット券」みたいなのを購入し、順番が回ってきたらこのカードを理容師さんに渡すんですな。これで会計は終了。あとは髪形の希望を伝え、チョキンチョキンとやってもらって、おしまい。シャンプーも顔剃りもなく、髪の切り屑は掃除機みたいので吸い取ってくれるだけ。たしかに10分で終わります。アメリカの床屋さんみたいで、シンプルこの上なし。 で、仕上がりですが・・・、ま、ちょっと雑なところがあるものの、私は別にこれでもいいかな。1000円で済んでしまうのも魅力だし。私、男の理容なんてこの程度のもんだろうと思っているところがあるんです。男は中身で勝負ですよ! ちなみに、この店に関して一つ私が驚いたのは、外国人の客の多さです。私の前に5、6人客がいたのですが、そのうちの2人は外国人でした。見たところ、東欧系の感じ。パッと見「琴欧洲と巴瑠都か!」みたいな感じでしたもん。彼らもまた、日本の普通の床屋さんの過剰サービスに辟易したのではないかしらん。 というわけで、今日はリニモに乗ってフレッシュネス・バーガーを食べ、1000円で髪の毛を切って大満足のワタクシだったのでした。この歳になって、一日のうちに3つも「初めて」の体験が出来たなんて、上出来、上出来!
January 12, 2007
コメント(5)
-
日本語テストでがっくり・・・
今、ワープロソフト「一太郎」や日本語変換システム「ATOK」などでお馴染みのジャストシステムが「全国一斉! 日本語テスト」というのをやっているの、ご存じですか? これ、今回で「第二回」らしいのですが、たまたまそれを知ったので、ついワタクシも受験してしまいました。もちろん、無料です。 テストは全部で30問。漢字の読み方や敬語の使い方など、日本語にまつわる様々な設問が揃っています。 とはいえ、何せワタクシ、「きょうじゅ」で・す・し~、日本語には多少なりとも自信はありますので、満点とって当たり前、間違えたとしてもせいぜい一問くらいだろうと多寡をくくっていたわけですよ。ところが・・・ がびーん。ワシ、4問も間違えてまった・・・。87点ですって・・・。「あなたの日本語は、なかなかのものです」なんて診断されたって、100点とるつもりだったワタクシにはちいとも慰めになりましぇーーん。 ま、負け惜しみを言いますと、もうちょい慎重に答えていれば、あと3問は正答することができたと思います・・・。 ただねー、1問だけは完全に間違っておりました。ワタクシが今まで思っていた漢字の読み方は、実は間違っていたっつーことです。ひゃー、ハズカシー!! これでは、ゼミの学生が私に向かって「ご指導・ご伝達のほど、よろしくお願いします」なんて言ってくるのを笑うことが出来ませんな・・・。(ご鞭撻だろ、ご鞭撻!) ということで、興味のある方、是非一度このテストを受験してみて下さい。自分がいかに間違った日本語を使っているか、よーく分かりますよ~。さてさて、あなたは釈迦楽教授の日本語力を越えられるや否や?!これがURLです! ↓第二回全国一斉!日本語テスト
January 11, 2007
コメント(14)
-
父の耳鳴り
正月、実家に帰って少し心配だったのは、父が耳鳴りに悩んでいたことでした。 ま、少し前からそんなことを電話で言ってはいましたが、実際に会って聞いてみると、耳鳴りってのは苦しいものなんだそうですね。あまり苦しいので、何だか物事すべてにやる気が失せてきた、なんて、父にしては珍しく弱音を吐いておりました。 もちろん、父はそのことで病院に通っているのですが、医者に回復の見込みを尋ねると、「耳鳴りは治らないよっ」なんて簡単にほざいたのだそうで・・・。父は「患者に向かって『治らないよっ』とは何事だ!」と怒っていましたけど、そりゃ、怒りますよね。医者の世界にも、仁術を施す職業に向いていない奴がいるようで・・・。 しかし、ちょっと気になったのでインターネットで調べてみると、確かに耳鳴りというのは、なかなか完治しがたい病気のようで、原因すらよく分かってないらしい。いや、原因どころか、そもそもどうして実際には鳴っていない音が聞こえてしまうのか、その原理自体がよく分かっていないんですってね。原理が分からないのでは、原因追究も、治療法も分かるわけがありません。 ということで耳鳴りというのは、つまるところ「いかに治すか」ではなく、「いかに慣れるか」にかかってくるんだそうです。 で、1990年代くらいから出てきたのがTRT療法という奴で、これは耳にセットした小さな機械から耳あたりのいい小さな音を出し、これを毎日数時間聴くことによって、耳鳴りの音が気にならなくなるように身体自体を慣らしてしまうというものらしい。 たとえば雑音に満ちた場所でも、自分の名前を呼ばれるとちゃんと気が付くように、我々の脳は「重要な音」と「重要でない音」を区別しているんですな。で、その小さな機械から流れる音を毎日聴くことで、耳鳴り的な雑音をすべからく「重要でない音」の範疇に分類するように脳を特訓してしまうわけ。ですから半年くらい経つと、たとえ耳鳴りがしていても、脳がそれを「重要でない音」と認識するようになっているので、その音が気にならなくなるのだそうです。この療法で、耳鳴りに悩んでいる人の8割は、「症状の改善」を感じるといいます。 日本でこの療法を積極的に採り入れているのは、慶應大学病院と名古屋市立大学病院らしいですけど、診察待ちが何ヶ月という状態だそうです。それだけこの世の中には耳鳴りに悩んでいる人が多いのでしょう。ある統計によると、高齢者の3人に1人は耳鳴りに悩んでいるそうですから。 ま、我が父上にも、いざとなれば慶應大学病院に行くことを勧めてみようか知らん。 それにしても、それだけ大勢の人が耳鳴りに悩んでいるというのに、その根本的な治療法がないということ自体、情けないことではございませんか。どうでも良いことに国のお金を浪費する前に、我が国政府には、確実に成果が期待出来る医療関係のことに相応の公的資金を注ぎ込んで欲しいものです。癌の研究しかり、アルツハイマー研究しかり、パーキンソン病研究しかり、そして「耳鳴り」研究しかり。 病気というのは、「明日は我が身」の世界ですからね。他人事じゃありませんぞ~!
January 10, 2007
コメント(3)
-
ぼーくらはみんな・・・
昨日、夜8時頃に東京の実家を出て、夜の東名をひとっ走り。途中、事故渋滞で30分ほどロスしながらも名古屋の我が家に夜中の1時頃到着。さすがにちょっと疲れましたなあ・・・。 で、その時点でメールを開けてみると、ゼミ生から卒論の書き方に関する質問が来ていたので、それに答えたりしていたらすぐに3時に。そこから寝たので、今日はどうも身体の芯に疲れがたまってしまって、朝からシャッキリしません。 それでも、大半のゼミ生は今日、卒論を提出したと思われますので、ようやくこれで今年度の卒論指導関係の仕事が終了です。ヤレヤレ・・・。 それにしても悲しいのは、「おかげ様で、今日、卒論を提出してきました!」という喜び&感謝のメールがゼミ生から届かないことですね。卒論の切れ目が縁の切れ目、なのかなあ・・・。一通でもそういうメールが来れば、私も少しは元気が出てくるのですが。 あんまり悲しくて疲れちゃったので、こういう時に私がよく歌う歌を歌ってしまいました。 たーりらった、たーりらった、たーりらった、シャンシャンシャン! たーりらった、たーりらった、たりらりらん、はいっ! ぼーくらはみんな、死ーんでいるー 皆さんよくご存じの、「ぼくらはみんな生きている」の替え歌ですが、これ大人になってから元気よく歌うと、すごく笑えて元気が出てきますよ。今元気のない方、騙されたと思って、ぜひ一度歌ってみて下さい。さん、はいっ! ほら。元気が出た。 というわけで、ある意味、今日は私にとっての「元日」。ようやく仕事から解放されましたのでね。ですから、明けましておめでとうございます。 さて、と・・・。そろそろ年賀状書こう。(爆) 実はまだ年賀状書き切っていなかったんですー。もう今さら年賀でもないんでしょうが、でも仕方ないもんね。ワシだって、好きで今頃年賀状書いているんじゃないもんね。忙しかったんだもんね。 で、実際、今日は朝からずっと年賀状書きしてました。まだ終わってませんが。書き終わったら、夜中に郵便ポストに投函に行く予定。早くケリをつけちゃいたいのでね。 まったく、我ながら何やってんだかって感じですけど、あとちょっと頑張ります。さ、元気出して行こう! さん、はいっ! ぼーくらはみんなー死ーんでいるーーーっと!
January 9, 2007
コメント(6)
-
西山美術館でユトリロ三昧
今日でついに実家での冬休みが終わりますー。 ということで、今日は両親を連れて地元に最近できた「西山美術館」というところに行ってきました。 西山美術館というのは、ようするに「ダスキン」という会社の社長が自分の趣味で作ってしまった美術館らしいのですが、ロダンとユトリロの専門美術館です。 ま、田舎に急にぽつんとできた、何となくいかがわしい(失礼!)美術館だものですから、最初はあまり期待もせず、「話のタネに」ぐらいのつもりで行ったのですけど、これが案外良かったんですわ・・・。 まずロダンですが、『考える人』(これもロダンの生前に鋳造した8体のうちの最後のものだそうです)や、デビュー作だった『鼻の曲がった男』なんかもあって、それなりに面白かったです。『鼻の曲がった男』というのは、コンクールへ出展するつもりで前日まで作っていたのだけど、たまたまものすごく寒い夜だったものだから、一夜明けたら作品が割れて、鼻も曲がってしまったのですって。で、さすがの若きロダンも絶望したようですが、半ばヤケになってその半分に割れ、鼻の曲がった男の顔を出展したら、なんとそれが彼の初めての入選作になってしまったのだとか・・・。運命ってのは、分からんものですな。 しかしロダンのコーナーでは、素描・版画もよかった。ま、当たり前なんですけど、すごく上手で、味わいがありました。 で、今度はユトリロの方を見たわけですが、こちらはロダン以上に圧巻。ユトリロの作品の中でも質のいいものが50点くらい展示されているんですよ。これにはちょっとびっくり。 ま、私は別にユトリロ・ファンというわけではなく、詳しいことは知らなかったんですけど、ユトリロってのは相当に数奇な運命をたどった人のようで。 まず彼の母親というのが、当時の若く有能な画家たち(ピカソとか、そういう連中ですわ)のモデルをやっていて、それで18才の時に、誰の子なんだか分からない子を生んじゃった。それがユトリロなんですな。 で、母親はその後もモデル業で浮名を流していますから、ユトリロは祖母の下で育つのですけど、14才で既にアル中となり、この宿痾に生涯悩まされ続けて躁と鬱を繰り返す生涯だったのですって。彼が絵筆を握ったのも、半ばアル中治療の一端だったようで、絵を描いている時だけ、少しはまともな状態になるのだとか。彼の母親は、通常の意味で言えばあまりいい母親ではなかったかも知れませんが、そんな息子を支えるために、絵の具だけはいくらでも買ってあげたそうです。で、ユトリロの方も、母を慕い、母親の言うことだけは素直に聞いたのだとか。 ユトリロの画業は6つの時代に分かれ、最初期である「モンマニーの時代」から「緑の時代」、「白の時代」、「色彩の時代」・・・などを経ていくらしいのですが、特に彼の真価が発揮されたのは「白の時代」で、この美術館にはこの時代の作品が19点もある。ユトリロはこの独自の「白」を出すために、貝殻を粉にしたもの、煙草の灰、白砂、それから鳩の糞までも絵の具に混ぜ、心血を注いで研究したのだそうで、確かにどれも素晴らしい出来。これは見とれてしまいます。 特に白の時代の絵を見ていると思うのですが、ユトリロの絵ってのは、まるで夢の中に出てくる風景みたいで、物音がしませんね。写実的なのに、どこか夢の中で見たしずーかな風景のようで、見ているとこちらの心もしずーかになってくる気がする。皇后の美智子さんがユトリロがお好きってのも、わかるような気がします。 また建物の壁など、白一色で平滑的に塗った部分など、ちょっとビュッフェを思わせるようなところもありますね。モダンで、ちょっとハッとするようなインパクトがあります。 ちなみにユトリロは晩年、51才の時に13才も年上の女性と結婚したようですが、この奥さんという人がパリ一の悪妻だったそうで、ユトリロの絵を勝手に売ってしまったり、酒を餌にユトリロに絵を量産させたりしたのだとか。そのせいか、晩年の絵は安い(といっても2千万、3千万のレベルだそうですが)のだそうです。 でも、私の目には、晩年の絵も、それはそれで軽みがあってよかったですけどね。 ところで、そんな感じで一通り見終わった頃でしたか、変な小男がやってきて、絵を見ている入館者を呼び集めるんです。何事かと思ったら、このおっさんが西山美術館の館長さん、つまりダスキン社長の西山氏だったのでありました。今日は休日だってんで、自らユトリロの解説をしようというわけです。 ま、一見、およそ芸術とは縁のなさそうなおっさんなので、こんな人の解説聞いてどうなるもんでもないだろうと思ったのですが、これが意外や意外、面白かったんですわ・・・。 確かに、これだけ熱を入れてユトリロを集めているのですから、やはり好きなんでしょうな。なかなかユトリロの生涯についてもよく知っているし、説明を聞いていても、情熱的なところがある。 で、所々、下世話な話も混じるのですけど、その下世話なところがなかなか面白いわけ。 たとえば、これだけユトリロの名品を揃えていると、デパートなどのユトリロ展に出展してくれと頼まれることもあるそうですが、「たかだか三万円の謝金くらいで、これらの絵を出す気にはなりません」なんて言われると、「ほう、絵のオーナーが展覧会に出展する時の謝金の相場はそのくらいなのか・・・」なんてことがわかります。 それから、やれ「絵を守るためにナショナルが作っている最高の絵画用電灯を使っている。この電灯1個7万円ですよ」とか、やれ「ここにある絵なんか、たかだか2千万くらいですけど、上の階にある奴は、どれもその10倍、20倍の値段ですよ」とか、やれユトリロ好きの美智子妃殿下に招待状を出したけど、おみ足がお悪いので、と断られてしまった、とか、そんな話がボロボロ出てくる。こういう下世話な話は、「評論家」大先生のレクチャーでは聞けませんからね。 決して皮肉ではなく、西山館長の話は面白かったです。 ということで、西山館長のレクチャーも楽しむことが出来たし、ロダン、ユトリロの名品も楽しめたし、冬休みの最後を飾る、なかなかのイベントとなりました。小田急線鶴川駅からタクシーで10分の西山美術館、教授のおすすめ!です。できれば日曜日など、西山館長のレクチャーを聴くことのできる日にいらっしゃるといいのではないでしょうか。 さてさて、今日はこの後軽く夕食をとってから、夜の東名をひた走り、名古屋に戻ります。明日からはまた名古屋からの「お気楽日記」となりますが、引き続きご贔屓に。それでは、また!
January 8, 2007
コメント(8)
-

明日は「成人の日」?
聞くところによると、明日8日は「成人の日」なんだそうですね・・・。 いやあ、成人の日は1月15日に固定しておけばいいと思うんですけどねえ。なんで第2月曜日にしなきゃいけないの? 毎年、日にちが移動する祝日なんて、ぜんぜん有り難くないですよ。こんな時に3連休にしたからって、国民が悦び勇んでバカンスに出かけるわけでもあるまいし。正月疲れでぐだぐだするだけでしょ。 逆に、週の真ん中辺に祝日があって、ちょっと行っては休み、ちょっと行っては休み、というふうになった方が、サラリーマンなんか身体が休まって助かると思うんだけどなあ。 そんなに3連休がいいのなら、元日も動せばいいじゃん? 「来年の元日は1月の第一月曜日」にするとか。ついでに天皇誕生日も「12月の第三月曜日」にしちゃう? 馬鹿馬鹿しい! 私・釈迦楽が日本の王様になったら、まずこのヘンテコな取り決めを反故にして、休日体系を元に戻しますね。成人の日は1月15日で結構、体育の日も10月10日で結構。 ワタクシ、王様になったら、やりたいこと一杯あるな・・・。由緒ある地名を変更して「希望が丘」みたいな名前にすること禁止、「さいたま市」みたいな馬鹿っぽいひらがなの地名禁止、などなど・・・。閑話休題。 さて、今日は両親と国宝・高幡不動にお参りに行って来ました。 高幡不動というのは関東三大不動の一つ。このあたりで生まれた新撰組の土方歳三と縁の深いお不動さんとしても知られていますが、我が釈迦楽家でも何となくこのお寺を贔屓にしておりまして、事ある毎にお参りしています。お不動さんってのは、「災厄から人々を守る」のではなく、「災厄をもたらす悪をやっつける」という、いわば攻めの姿勢の仏様ですから、なんかこう勇壮でいいな、と。以下、山門と本堂の写真をお楽しみ下さい。 で、いつものように本堂でお参りを済ませ、その後境内を一回り。帰りにお守りを買い、山門の前で売っている高幡不動饅頭を買いました。ちなみにこのお饅頭、これが結構うまいんだ。饅頭は茶と白の2種類がありますが、私が思うに、つぶ餡入りの茶の方がうまいのではないかと。 で、例年ですと、高幡不動の帰りがけ、参道にある古本屋を覗いていくというのが楽しみだったのですが、残念ながらこの古本屋が昨年店を閉めちゃったんですよね・・・。噂によると、高尾山の方に引っ越したってことですが、そんな遠くに行くなよ・・・。 この店、小さいけれど、なかなか上品な古本屋で、結構掘り出し物があったりして、楽しみだったんだけどなあ。 いつも思うことですけど、釈迦楽家が贔屓にする店はたいてい潰れるね。なんでですかね? ほんと不思議。今まで我が家がつぶした店なんて数知れずですよ。お気に入りの本屋は潰れる、お気に入りのラーメン屋は潰れる、お気に入りのピザ屋も潰れる、お気に入りのしゃぶしゃぶの店もステーキハウスも潰れる・・・。 ま、お気の毒です。 とにかく、そんなわけで、今日は恒例の高幡不動参りができて、何だか心持ちがさっぱりしたワタクシなのでした。今日も、いい日だ!
January 7, 2007
コメント(4)
-
「空師」の仕事に共感!
昨夜NHKのドキュメンタリーで「空師」のことが紹介されていました。 「空師」なんて言葉、私は初めて聞きましたけど、要するに巨木を伐採する人のことで、明治時代からある言葉なんだそうです。樹齢百年を越すような巨木となると、ただ根元に鋸を入れればいいってもんでもなく、まずは高所にある枝から切って行かなくてはならないわけですが、目の眩むような高いところまで登って枝打ちするその姿から「空師」と呼ばれているのでしょう。 で、このドキュメンタリーの主役は、熊倉さんという名の、見たところ三十台半ばとおぼしき若き空師だったんですが、これがまたいい男なんだ。 彼は中学くらいの時まで突っ張っていたらしいのですが、15才の時、たまたま親に黙ってバイトに行った先が空師の親方のところだったんですな。で、この師匠について木の伐採の仕方を習い、また仕事が終わったあとは飯を食いに連れて行ってもらったりしているうちに、「働いている」という充実感と、空師の仕事のやりがいというものにすっかり取り憑かれてしまった、と。 それ以来、この仕事一筋ってんですから、三十路とはいえ、もうこの道20年のベテランです。事実、彼の下には2人の若者が弟子として修行しに来ている。 ま、そんな熊倉さんなんですが、さすがにベテランの職人だけあって、良いこと言うんだこれが・・・。 彼によれば、今の日本には天然木なんてほとんど存在しないそうなんです。つまり、今ある木は、すべて人間の手によって植えられたものばかりなんですな。たとえば明治時代の人が、100年後にこの木が誰かの役に立てばいい、と、そんな風に考えて植えた木が、今、巨木になっているというわけ。 そういう木を伐らせてもらっているのだから、熊倉さんが木を伐る時はいつも、昔の人のことを思って心の中で礼を言うんですって。と同時に、それだけの木を伐る以上、一寸たりとも無駄にはできないという気持ちから、彼は地面スレスレのところから木を伐採する。これは腕がなければできるもんじゃありません。そうやって熊倉さんに伐られた木は、良質の材木となって、第二の人生を迎えることになるわけですよ。 また木には「伐り時」というのがある、ということも、熊倉さんは言ってましたね。人間は人間のエゴで、本来生を終えるべき木を無理やり生かしてしまっていることがある。たとえば巨木の脇に道路を通すので、木はそのままにして根の一部だけ切ってしまうことがあるんだそうです。そうするとその根の切り口からバイ菌が入るのか、やがてその木の幹には空洞ができてしまう。と、今度は倒壊の危険性があるというので、その空洞にセメントを流し込んでしまったりする。まさに人間のエゴです。 そんなことをするくらいなら、いっそ最初に伐採して、その木を木材として活かしてやればいいのに、と熊倉さんは言うわけですよ。そりゃそうですよね! で、熊倉さんとしては、なるべく木を活かす方向で木を伐ることをいつも心がけているそうなんですが、木を伐るったって、ただ単に電ノコを入れればいいというものでもありません。その木が住宅やビルの間に立っている場合など、伐採が非常に難しい場合がある。下手に切り倒したら、周辺の建物や電線なんかを傷つけかねませんからね。また木というのは、その木を見ながら育った人々にとっては、様々な思い出のよすがになっているので、そういう意味でも簡単なことではない。 そういう物理的な難しさと、人情の上での難しさ、そういうものを案配しながら、熊倉さんは上手に木を伐っていくんですなあ。思い出の木の枝打ちを依頼されれば、その木が弱らないよう木を配り、完全な伐採の場合は、その木の一部を記念に配ったり・・・。 しかも、熊倉さんのえらいところは、職人としての腕だけではないんですなあ。彼は自分を育ててくれた先輩たちを立てることを忘れない一方、後輩の育成についても本当によく考えていて、二人の弟子の教育ということにすごく力を入れているんです。伐採の仕事がない時など、わざわざ材木市場の入札なんかに弟子を連れて行って、材木の見立てから入札の仕方まで、一人前の空師として必要な知識を惜しみなく教えている。それも、高飛車にというのではなく、兄貴として、ね。 そして番組の終わりの方で、その弟子二人を伴いながら、非常に困難な状況の中で巨木を思い通りに伐り倒し、その切り株に腰を下ろして微笑んだ時の、熊倉さんの晴れやかな笑顔は、良かったですよ~。 で、そんな熊倉さんの夢、何だか分かります? 自分でいい木を捜し出し、自分の手で伐り、その材木を使って総木造のいい家を造る。そしてそこで障害をもって生まれてきたお嬢さんが、安心して暮らせるようにする。これが熊倉さんの夢なんですって。く~、最後まで泣かせるじゃないですか・・・。 ほんの1時間ばかりの番組でしたけど、実にさわやかな、いい番組でしたなあ。この番組、見逃した方も多いと思いますが、きっとそのうち再放送すると思いますので、その時にはぜひご覧下さい。 好漢の空師・熊倉さんを扱ったNHKのドキュメンタリー、「教授の熱烈おすすめ!」です。
January 6, 2007
コメント(4)
-
人の役に立つって・・・
年末、私が注文しておいた「補修用こたつヒーター」、届きましたよ。で、こいつを箱から出し、家の壊れたこたつに取り付けてみると、おお、枠にピッタリ~! で、4箇所をネジで留めたら、もうそれだけで完璧にセッティング出来てしまいました。私のような不器用な人間でも、ものの5分とかからないうちに、こたつの修理完了~! で、スイッチ・オン! おお! こたつ復活! 2万円の出費予定が5千円で済んじゃった! 両親からも感謝されちゃったし、メデタシ、メデタシ。人の役に立つって、なんか気分いいなぁ~! それにしても我が実家には、私の手助けが必要なことが沢山あって、嬉しい悲鳴です。たとえば父はコンピュータの操作に手こずっては、「おい、ちょっと・・・」と私を呼びに来ますしね。もちろん私だってコンピュータの使い方にさほど詳しいわけではないですけど、それでも父よりは分かっていますから、ちょちょいのちょい、と教えてあげると、まるで私が魔法使いででもあるかのように感心してくれます。 一方、母は母で、私が見張っていないと、妙なものを買ってきたりするんだ、これが・・・。 今日も、昼食を用意していた母が頻りに「何だか変なのよね~」と言っているので、何事かと思って台所に行ってみると、スパゲティの茹で上がりが妙だ、と言うんです。何だか変に平べったくなっちゃったと言うのですが・・・なーんだ、よく見るとこれ、スパゲティじゃなくて「リングイネ」じゃないですか! そのことを母に告げると、「あ~ら、そうなの?」ですって・・・。 それからこれは今朝方の話ですが、洗面所に「メンズ・ビオレ」のシェーヴィング・クリームが置いてあったので、さては甥ッコが忘れて行ったのかと思い、「これ、仙台組の忘れ物じゃないの?」と母に問うと、「あ、それ私の」なんて言うのでびっくり。なんと我が母は、男性用シェーヴィング・クリームを、洗顔フォームだと思って、知らずに使っていたのだそうな・・・。おい、おい・・・。 でも、まあ、考えてみれば無理もないですよ。単に「顔を洗う」ための石鹸類のことだけを考えても、今や何百種類もの製品が売り場に置かれているんですからね。パスタだって、そう。昔みたいに、「ママー・スパゲッティ」だけが置いてあるわけじゃない。何社のものメーカーが、それぞれスパゲティだ、リングイネだ、ラザーニャだ・・・・という調子で色々な種類の麺を販売しているんですもの、目の悪い年寄りに、それらの中から自分が欲しいものを選べという方が酷というものでしょう。 年寄りには、生きにくい社会になったわけですな~。 昔は若い者が年寄りに、「こういう時はどうするのか」と尋ねたもんで、それが年寄りの権威になっていたわけですが、今は逆ですもんね。年寄りがまごまごして、我々子供の世代に尋ねている。ATMの使い方然り、電車の切符の買い方然り・・・。 こんな世の中じゃあ、若い者が年寄りを邪険にするはずですよ。 しかし、そんなこと余裕ぶっこいて言っているワタクシ自身、いずれ、下の世代にあれこれ尋ねなければならない日が来るのかも知れません。嫌だね~。長生きはしたくないな。 ま、とりあえず時代錯誤的に儒教精神に溢れた我が釈迦楽家では、私が楯となって、この世の中の荒波から両親を守ってあげましょう。情けは人のためならず、ってね~。
January 5, 2007
コメント(2)
-
恐怖の風呂場
年末・年明けと、東京の実家で過ごしているわけですが、こうしてたまに実家で過ごす度に思うことが一つありまして。それは何かと言いますと・・・ 風呂場が、コワイ。 いや、別にオバケが出るとか、そういうのではなく、もっと現実的かつ物理的なことなんですが、実家で風呂に入っていると、時折ポツっとくるわけですよ。そう、天井からチメターイ滴が、ね。 夏はまだいいのですが、冬場はこれが辛い。背中に「ポツッ」と来る度に、思わず「うぉっ!」とのけぞってしまいます。それで、その「ポツッ」がいつ来るか分からないものだから、いつもビクビクしていなければならないという・・・。 こういうところが、世の「建築家」なる人種に対して、ワタクシが激しく不満を持つところなんですよね~。だって、「ポツッ」なんてのは、風呂場の天井にほんのわずか傾斜をつければ防げることでしょ? 風呂場の洗い場にはもちろん傾斜をつけて、流したお湯が排水口の方に流れるようにしているのに、どうして天井にも傾斜をつけないの・・・。簡単なことじゃないですか。 誰だって、風呂場の「ポツッ」を経験したことぐらいあるはずなのに、どうして設計のプロたる建築家がそういうことに気づかないんだろう。 しかし、家の設計に関して、そういうことは多いですよ。洗い籠と炊飯器を置いたら、もう作業場がなくなるキッチンとか。「どうしてここに?」と思うようなところにコンセントを設置するとか。どの家庭にも1台や2台はあるはずの「掃除機」の置き場がどこにもないとか。 それでいて建築系の雑誌なんかを見ると、どう見ても住み難そうなコンクリート打ちっぱなしの家とか、総ガラス張りで外から丸見えの家とか、そんなのばかりを得意気に掲載しているんだからな~。もっと普通に過ごし易い家を設計できる、ちゃんとした建築家って、いないもんですかね・・・。閑話休題。 さて、今日は姉のところの一家が仙台に帰って行きました。家族の人数が急に減った分、さみし~! その代わり、他にやることがないだけ、仕事はバリバリ進んでいますけどね。 卒論の添削も、あと一踏ん張りというところ。夕食後も、頑張って添削するぞ~!
January 4, 2007
コメント(6)
-
伝説の古本ハンター、西村老人に出会う
今日で正月も三日目。今日は所用で町田に行きましたけど、相変わらずすごい人出でしたなあ・・・。 町田ってのは、小田急線沿線のちょっとした町なんですけど、なかなか面白いところではあります。小田急デパートや東急デパート、それに丸井などいくつかデパートもありますし、「ジョルナ」(昔は「さいか屋」って言ったんですけど・・・)に代表されるテナントビルも沢山ある。それでいて、昔ながらの商店も数多く残っていて、まさに現代と昭和が混在しているような感じ。そういう意味では「吉祥寺」的なところもあるんですが、吉祥寺よりももう少し土臭いと言いますか、そんなところがありますね。 でまたこれが夜になると雰囲気が一変。風営法で新宿を追い出された皆さんが、この町を新たな根城にしているせいか、すごくヤバイ場所になってしまうところが、何とも不思議なところでして・・・。 ま、健全なのか不健全なのかよく分からない町なんですけど、私にとっては地元ですから、なんとなく親しみはあります。 で、そんな町田通のワタクシが、町田で立ち寄る喫茶店が「カフェ・グレ」。ここはとあるビルの2階にある、知る人ぞ知る名曲喫茶でございまして、大人~な雰囲気なんです。ロイヤル・コペンハーゲンのカップで出してくれるコーヒーもうまいし、チーズケーキも上々。何より、いかに町が喧騒に満ちていてもここだけはひっそりと落ち着ける、そんな穴場的なところがいい。 それでいて、いつ行っても何組かのお客さんは入っていますから、ちゃんと商売にはなっているんでしょうな。今日も、私と家内の後から60代くらいの初老の女性が一人で入って来られて、いかにも常連という感じでカウンターの奥の「いつもの」席に腰を落ち着けたあたり、なかなかいい雰囲気でしたよ。 さて、そんなカフェ・グレで一息ついて、所用を済ませた後、私が向かったのは駅の北側にある大古書店・高原書店でございます。インターネット上の古書店としても有名な高原ですが、本店はここ町田にあるんですな。一つのビルがまるまる店舗という大きなお店です。 ま、古書価をよく知っている店なので、すごい掘り出しモノがある、ということはあまりないのですが、それでも規模が大きいので、行けば何か必ず収穫がある、というところはある。 で、今日もありましたねぇ、収穫が。 まず見つけてしまったのがヘンリー・ミラーの『不眠症あるいは飛び跳ねる悪魔』(読売新聞社)の豪華美装本。吉行淳之介訳。これ、なかなか手に入らない本なんです~。私、ミラーの水彩画にまつわる本はすべて収集しているので、すかさずゲット! 正月早々、こんな本に出くわすとは、よほど運がいい。 しかし今日の古本運はこれだけに尽きませんでした。ミラー本と同時に私が収集の対象にしている池田満寿夫のエッセイ集(対談集・評論集・その他)を一挙5冊もゲット! 『同心円の風景』(毎日新聞社)、『鳥たちのように私は語った』(角川書店)、『美の王国の入り口で』(芸術生活社)、『池田満寿夫の人物デッサン』(河出書房新社)、『池田満寿夫グラフィティ』(潮出版社)の5冊ですが、一度にこれだけのものを収集出来たなんてことはこれまでに例がなく、さすが高原書店!とうなりましたよ。特に『池田満寿夫グラフィティ』は、前から捜していた本なので、見つけた時は胸が高鳴りました。 ところで、私が興奮して本を選んでいた時、レジのあたりで一人の老人が店員たちと話をしているのに気づきました。よほどの常連らしく、若い店員たちも皆顔見知りのようで、その老人が立ち去った後、「西村さんが頻繁にいらっしゃるから、新しい本をどんどん出しておかないとまずいよね」「年末にもいらしたのよ」などと話し合っていたり、そうかと思うと上の階から降りてきた店員が「さっき、4階で西村さんを見かけたよ!」などと楽しげに報告しに来たり、それに対して「いや、今までここにいらしたのよ」「今日も4千円ほど買って下さって」などと言い合ったりしている。うーん、やるな、西村老人。伝説の古本ハンターか・・・。 ま、私も景気よく西村老人の3倍くらいは買って、とりあえず新たな小伝説を作りましたけどね。 でも、どうやら西村老人は店員たちに小遣いすら与えているようでしたから、ちょっと太刀打ちできんなあ・・・。 しかし、どういう経歴の人物か知りませんが、古本屋に入り浸って好きなだけ本を買い、店員たちとも仲良しの老人なんて、なかなかカッコいいじゃないですか。私もそんな老人になりたいもんだ。 というわけで、今日は収穫もあり、興味深い人物もチラ見することが出来て、新年早々楽しい古本ハンティングとなったのでした。今年の古本運は上々だぞ! 今日も、いい日だ!
January 3, 2007
コメント(4)
-
男3人の新年会
毎年正月2日は小学校時代からの友人3人で新年会と決まっておりまして、今年も行って参りましたよ。 で、この集まりに、たとえば私の家内などの女っ気が加わりますと、とりあえず昼食会はホテルのレストランでシャンパンを開けて・・・ということになるのですが、今日はベーシックに男3人だけだったものですから、「このメンツで、ナイフ・フォークってもんでもねーだろ」ということになり、居酒屋での新年会ということになった次第。ま、それも気楽でいいですよね。 で、新年と久々の再会を乾杯で祝った後、四方山話となったわけなんですけど、友人たちの話を聞いていると、会社勤めも厳しいもんだと思わされますなぁ・・・。 たとえば大手建設会社で頑張るEは、昨年は厄年だったらしく、ぼーんと1億数千万の焦げつきを作って上司に大目玉を喰らったのだとか。工事を受注して仕事を完成させたはいいが、いざ支払いという時に相手先が倒産しちゃった、ということらしいのですが、建設業界ではこういう話はよくあることなのだそうで・・・。しかし、「珍しくない」というのと、「自分がその担当だった」というのでは話が全然別なわけでして、Eも後始末に相当苦労したらしいです。 「今度の人事は、覚悟しないといかんな・・・」とポツリと漏らしていたのが印象的でしたねぇ・・・。北風ひゅるる~~。 またもうひとりの友人Tは、年末まで茨城県の片田舎で仕事をしていたのですが、いろいろな意味で寒いところだったらしいです。 Tはまだ独身なもので、「で、茨城でいい人と出会わなかったのかよ?」と問いただすと、職場には二十歳そこそこの女性(パート)社員も沢山いるのだけど、その人たちはみーんな結婚していて、既に3人の子持ちだったりするそうな。もう他にすることがないのか、その辺りの人は高校を卒業するかしないかのうちに結婚しちゃうのですって。それじゃ、そんなところに四十男がノコノコ出て行っても、時すでに遅しですなあ。 ま、私も昨年はあまりパッとしませんでしたし、パッとしない野郎3匹、互いに互いの傷を舐めあって参りましたーーー。ま、今年こそ、いい年にしようと誓い合いながら、ネ。 でも、そういう話が気兼ねなくできる友人がいるというのも、幸せなことでございます。 それに、今日は悪い話ばかりではなかったんです。たとえばEの奴は、最近子供に手が掛からなくなってきたので、土曜日などはよく奥さんと一日かけて散歩するようになり、何度か美術展にも行ったよ、なんて柄にもないことを言っていましたし、Tも今年は一発、事業でも興して、来年の今頃は肩で風切ってやる、なんて鼻息が荒かったですし。そういう威勢のいい話があると、座も盛り上がります。 ということで、今日はTの今後の活躍を祈念して、恒例の新年会を解散して参りました。 私も来年の新年会には、一つ皆に自慢出来る成果を持って臨めるように頑張りましょう! 今日も、いい日だ!
January 2, 2007
コメント(0)
-
元日からショッピング
昨夜、NHKの『ゆく年 くる年』を見てから近所の神社まで初詣に行ってきました。ま、地元の小さな神社なんですけど、今年は例年になく初詣客が多かったですなあ。で、家族の健康や仕事の成功などを神前に祈った後、振る舞い甘酒をいただき、御神籤をひいて帰ってきました。御神籤は「大吉」でしたよ~。 で、夜が明けて正月元旦。お節にお雑煮を食べ、ちょっとお酒も飲んでいい気分。私の丹精を込めた黒豆も上出来で、よかった、よかった。 そして、午後からは近くの町まで買い物に行きました。ま、正月の町の賑わいでも見ようかな、ということで、ね。 で、「JCrew」だの「GAP」だの、あるいは「UNIQLO」だのの初売りを楽しんできました。それに「食器の洗いカゴ」だの「サーモスのポット」だのといった日用品の買い物も若干ありましたしね。町は福袋目当ての客も多かったし、なかなか賑やかでしたよ。それにドンドコドコドコ和太鼓の演奏なんかもあって、祝日の雰囲気もありました。 しかし、私なんかが子供の頃は、正月の三が日なんてのはどこのお店も閉まっていて、静かなものでしたけどね~。 それで唯一やっているのがパチンコ屋さんだったりして、暇を持て余した父が姉と私を連れて散歩に出た時など、「ちょっとやってみようか」なんて言って親子でパチンコをしたりしたもんです。なにせそういうところには日頃縁のない我ら親子なので、一台のパチンコ台を三人で囲み、一球パチンと弾いては、それが釘を伝ってクルクル下まで落ちてくるのをずっと見守り、「ああ、残念!」なんて言いながら、次の玉をパチンと弾く、といったような悠長な遊び方をしたものでございますよ。 それで1月4日くらいになってようやく商店が店を開け始めると、何だか急に買い物がしたくなって、普段は寄らないような馴染みのない店まで冷やかして歩いたもんです。ま、こんなのが私の子供の頃の「年明け」の感じでしたなあ。 ま、そんな時代と比べると、隔世の感がありますけど、それでも平和な国で元日からショッピングを楽しめるのですから、それなりにめでたい世の中なんでしょう。 さて、今日はこれから「ロールキャベツ」で洋風の夕食なんだそうです。お節にお雑煮の後では、なんとなくパンが食べたくなりますしね。その後は、また少し仕事でもしますか。
January 1, 2007
コメント(9)
全31件 (31件中 1-31件目)
1