PR
Calendar
Nov , 2025
Oct , 2025
Sep , 2025
Aug , 2025
Keyword Search
Comments
Freepage List

基本事情 写経一覧表(総合)[更新日付]

関連情報(アジア)

関連情報(中南米)

関連情報(ヨーロッパ)

関連情報(中東地区)

関連情報(アフリカ)

関連情報(北米ほか)

「年月日」から記事にアクセスする方法

世界規模データ

外国政府の統計 の出所

自由が丘氏等の寄稿一覧表(総合と自由が丘氏)

仮想旅行・歴史

鈴村興太郎博士の講話など

宇治見氏寄稿「ブラジル日本移民100年史」等

寺尾公男遺稿集

金剛山仙人

青雲荘亭主

ピケティ理論、所得格差分析など

山崎博司氏「こころの友」HPの一部保存

諸問題その他

司馬遼太郎「日本人とは何か」

マドレーヌ氏特別寄稿

Tsunami氏&Tigers&Mitsuya & Moomin Papa

土佐の高知(ふるさと)

父の癌闘病記

大学時代の思い出

会社勤務時代の思い出(OB時代も)

地元

海外出張

福島第一原発事故、地震、災害などへの対応

スポーツ・健康・病気関連(総合)

神尾米さんの「現代テニス」

宇宙・地球の未知

PCなど家電一般&HPやML & Fishing Mails

政治、法務関係など

年金など

ドキュメンタリーやドラマ・小説など

気候変動、資源・エネルギーなど

各種統計など

調理など

公害

家事一般(DIYを含む)

宗教
Category
寄稿(宇治見、マドレーヌ、トキめき橋氏ほか)
(68)自由が丘氏寄稿文
(189)Tsunami氏寄稿、SCRAP記事、写経・感想など
(326)政治・経済(国内統計etc.)
(725)世界、国際比較(国際統計etc.)
(228)生活全般
(129)基本事情(各国)
(114)アジア州
(257)ヨーロッパ州
(293)北米地区
(206)中南米地区
(112)オセアニア州
(104)中東地区
(51)アフリカ州
(126)宇宙の不思議・開発etc.
(71)気候変動など
(7)津波・自然災害
(30)自然の脅威、驚異etc.
(47)資源・エネルギー(陸・海洋etc.)
(49)発電・原発事故・放射能事故
(74)金融(事件含む)
(128)PC・家電
(229)スポーツ・余暇・車
(264)栄養・健康
(143)病気・伝染病など
(191)事故・災害
(102)福祉・厚生・年金問題
(59)公害
(15)流通(商品)・廃棄関連
(17)新技術
(30)友人・知人・地縁等
(40)土佐の高知
(63)夢
(49)お墓・葬儀・戸籍
(24)ガーデニング&DIY
(14)TV番組
(15)海外旅行
(6)国防/テロなど
(41)財政・税・電子証明など
(28)自治体、地元、遺産など
(37)店舗
(6)公衆道徳/法律など
(26)裁判/調停
(7)宗教
(21)ブログ
(31)テンプレート(表形式etc.)
(3)DVD収録など
(6)ホームページ、ウエブ会議など
(48)祝い事など
(14)会社時代
(22)学生時代
(7)物語り
(43)経済学研究
(26)思考紀行
(73)作業中マーク(終了次第削除)
(0)洞察力
(1)★
遺産の 処分について:
土地・建物には、費用ばかり先行して嵩んでしまうから、
相続を受けても、喜んでばかりはいられない。
特に、祭主としては、お墓の改葬、お墓の建碑、お祭りなどで
全費用を賄わないといけない。
祭主が全ての費用を背負うのが我が国の掟のようである。
★
建物は、帳簿上では資産としての価値は少しあっても、
実態は、鐵の部分が赤さびて、今にも壊れそうで、
近所迷惑になっている。
まずは、ボロ家を取り壊し平地にせねばならない。
そのために、自分で家財整理・プライバシー的なものを
処分し、その後は解体屋に頼んで、 もう潰すしかないのである。
★
税務を少し勉強した。
相続税については、「基礎控除額5千万円+法定相続人2名X
1千万円+葬儀費用」が相続財産より遙かに大きく、 ゼロである
基礎控除に対してさえ相続財産は遙かに低いのだからである。
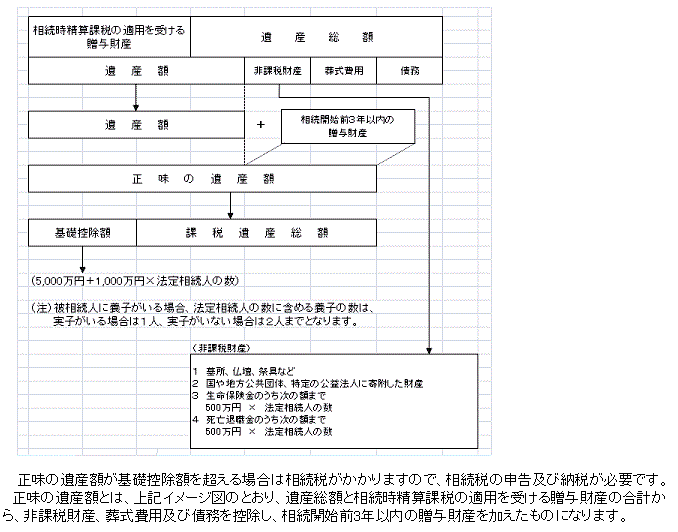
<国税庁資料より>
///
相続の場合は、短期、長期の区分は被相続人の取得した始期が
「税務基準の始期」になり、 その譲渡費用は被相続人の「取得費と
譲渡までの譲渡費用など」であるという。
相続取得始期 、譲渡費用を気にしていた小生は
税務を知らない馬鹿者であった。
///
被相続人が取得した時期は当然20年以上も前である。
ところが、取得費用は分からない。
権利書には、課税標準、登録免許税などが記載されているが、
それは、課税だけを目的に国が決めている標準に過ぎず、
相続人はその標準を使う便宜を持っていない。
建物については、自分で減価償却費を計算しなければならない。
他方で、人が住めない状態であっても、また、減価償却済みの建物であっても、
課税標準は決して大きく下がらないのである。
馬鹿な話のようだが、実際には取り壊すしかない建物でも、
かなりの課税標準になって徴税されているのである。
<国税庁は、建物の課税標準を減価償却計算にリンクすべきであると
小生は考えるが、全くリンクしていないのが現実である。不合理である。>
★
それでも、減価償却費は計算した方がいいだろう。
自宅の家財整理をしていると、昔の建築 契約書・領収書が
見つかるはずである。
それから、通常の減価償却費の1.5倍だけ長い引き当て期間を
設けて、建物滅失時点での建物価値を計算できる。
建物の改造費用も計上できるが、これにも減価償却の計算がいる。
もちろん、老朽化して取り壊さざるを得ないので、取り毀し費用も計上できる。
しかし、建物課税標準と、現実の減価償却費控除後の建物価値とは
大幅な相違があるであろう。
なぜなら、ほとんどゼロ価値であるに拘わらず、課税標準はなかなか下がらない
=税金は高止まり、なのである。矛盾が此処にもある。
★
また、土地の原価として、被相続人が契約した土地の売買契約書、
領収証をみることで、計上できる。
もう40年以上も前の土地の取得であった。
もし取得費用が分からないと、売却価額の5%と認定されるから
いくら価値がないと言っても、取得価額は大事である。
★
プライバシー関係の書類を当たっていたので、
捨てないで済んだのである。
ほっとしながらも、自分での税の計算は
脳幹梗塞の呆け頭には難しそうである。
リハビリにはいいのかも・・・
★
もちろん、不動産の譲渡所得は別申告であり、
長期保有だから税率は15%+5%=20%である。
「売却金額ー取得費ー売却費用(手数料を含む)」
が譲渡所得となる。
おっと、まだ売れない内から狸の皮算用をしている。
南海地震のハザード区域という、 それほど期待できない土地なのに・・
★
今回の相続財産の手続きで、自分が死んだ場合は
どうなるかを考えて、土地建物の売買契約書、建物改造契約書などの
証拠書類をキチンと整理しておいてやるべきだと思った。
被相続人の売買・建築契約時期が相続人に引き継がれるという、
税務上の起点の原則が判っただけでも良かったと思う。
★
呆けの戯言であった。
★
余計なことであるが、10%へ消費増税が囁かれている。
土地には関係ないが、建物には関係するから、
建物を建設したい人は来年10月までには完工・引き渡しを望むことが
もしかすると早い処分となるかも知れない。
こんなことを此処で囁いても仕方がないことであるが・・・
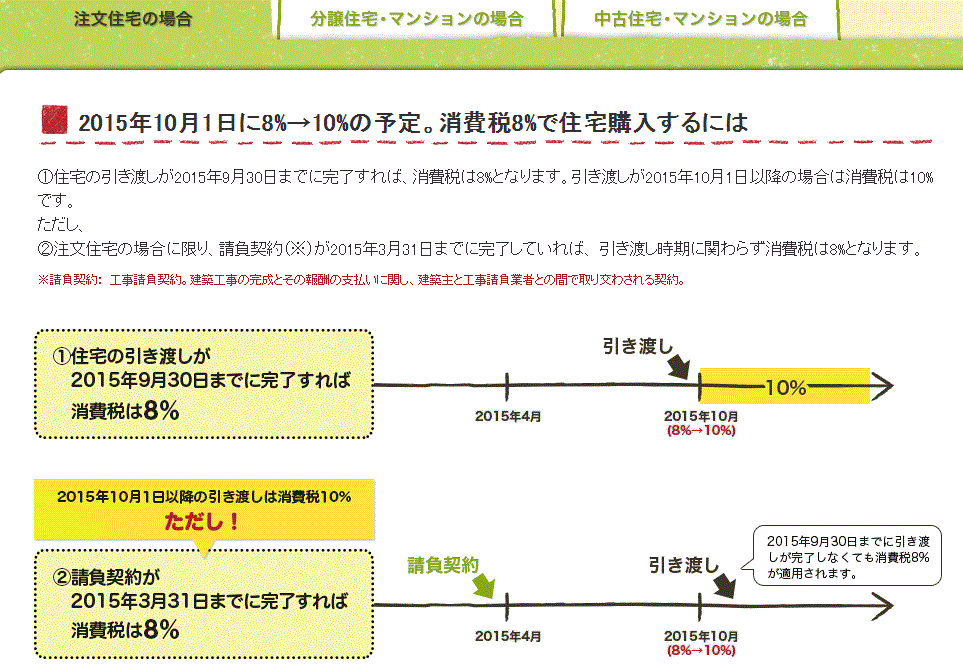
<WEBの建設メーカーのHPより>
★
-
コロナ禍での暫くぶりの「梨街道」→「墓参… Aug 6, 2020
-
市営霊園に彼岸明けのお墓参り Mar 24, 2018
-
「喪中ハガキ」について: 出し方や受… Dec 29, 2016









