2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2005年04月の記事
全51件 (51件中 1-50件目)
-
化粧を注意され・・・
「ホームで化粧を注意され、逆切れして電車に接触させる」なんていう、記事が出ていましたが。まあ、本人は化粧ではなく、汗をぬぐっていたといっているとか。必ずしも、線路に向かって突き落とすつもりもなかったんだろうけど。 でも、気になるのが、なんで注意をしたのかということ。別に、化粧をすることを推奨するわけじゃないけど、別にしたっていいじゃない。粉を撒き散らしながらやって、他の人に降りかかっているのなら別だが。 自分が気に食わないからといって、いちいち文句をつけていたら、きりがない。まあ、ワタシも普通の電車の中でタバコを吸っているオッサンや、ホームのベンチでタバコを吸っている女子高生などに注意したことはあるので、エラそうなことは言えませんが。 でも、女子高生に健康に悪いからとは言わない。それが、他の乗客も座っているベンチだから。だれもいないホームの端で吸っていても、多分文句は言わないでしょう。 まあ、人によって許せる基準と許せない基準があるんでしょうが。また、不快に思う基準と、それを注意などの行動にでるかどうかもかなり基準が違うでしょう。ついでに、それをやっているのが、自分よりも強いか弱いか。 みっともないけど、一応ケンカになって惨敗しそうな相手には注意をしない。生きる知恵とでも申しましょうか。 ウチの娘でもが、塾の帰りなど電車の中でワイワイやっていて他の客からにらまれていることもあるんだろうな。まあ、注意されても、キレないようには教育しておかないと。 でも、塾帰りの子どもなんて、いかにも注意したくなるような。「ワタシは教育的な指導をしています」って感じで。
2005.04.30
コメント(6)
-
夏期講習
夏期講習の日程を見て、驚いた。ほとんど休みがつぶれるじゃないか。これじゃあ、どこにも遊びに行けないじゃないか。6年になったら、ある程度しょうがないかもしれない。 ワタシは夏期講習をパスすることを提案したい。多分、奥様に却下されるだろうが。 ええ~い。もう辞めてしまえ。
2005.04.29
コメント(2)
-
4匹目のどじょう
別にたとえでも、なんでもなく、本当のドジョウのこと。うりぼうずが、学校の池から「救出してきた」、まっちぼうより少し大きいぐらいのドジョウ。家の水槽に放したものの、すぐにいなくなる。と、いっても、要するに、どこに隠れたかわからなくなるだけ。ここ何日も見ていないが、多分死んでもいないみたいだ。 この、ちびドジョウに限らずら、うりぼうずにとっては、金魚よりもドジョウの方が面白い様子。石の下にもぐりこんだり、少し砂利を多くしたら、生首のように頭だけ砂利から頭を出して、じっとしていたり。大きいのが三匹寄り添って寝て?いたり。 幼稚園の時に、つかみ取りで採ってきたやつだから、もう飼い始めて5年になるのだが。
2005.04.28
コメント(2)
-
脱線・叙勲
気になるコメントを見つけた。どこの新聞だったか、JR西日本の会長が、関経連の副会長を辞任しないと言う内容のもの。事故の対策に専念しても、副会長職には特に支障がないからというもの。 JRの会長を辞めるのは、事故の処理が終わってからという論理は成り立つと思う。しかし、事故対策に専念しても支障がないような役職だったら、しかも関西経済界の顔とも言える立場だったら、それは辞任して当然ではないだろうか。なぜ辞任の道を選ばないのか。 そこで思い当たるのが、叙勲。公共的な役職(この場合、関経連の副会長)を何年やれば勲○等(今は、等級ではないのか)と、ほぼ決まっている。関経連の会長ならば、1等(昔だったら)か。副なら2等か。もしかしたら、勲章ほしさに居座りを決め込んでいるのではないか。 もちろん、これだけの事故を起こして、叙勲の対象になるかどうか定かではない(東京大空襲の指揮官に勲1等をやるぐらいの国だからたかが、100人程度の事故では、別に関係ないかもしれないが)。 勲章とは、なんと愚かな制度であろうか。大げさにいえば、「これで天皇制国家の序列に組み入れられる」と、それに誇りを持つものたちが、いかに大勢いるかということの証しなのだろうが。 「公的」とされる団体の役職を何年やれば、ということで、その職にしがみつく輩が多い。叙勲の弊害の大きさは、計り知れないものがある。 あす、春の叙勲の名簿が発表される。
2005.04.28
コメント(0)
-
関西の鉄道
福知山線の事故で、関西の鉄道各社の競争の激しさがクローズアップされている。ワタシが住んでいたころは、長距離の移動以外は、まず国鉄(当時)を使うことはなかった。高かったし、遅かったし。ちなみに、当時嵐山に住んでいて、阪急ならば梅田まで300円ぐらい。国鉄なら、最寄り駅が嵯峨で、大阪まで、800円ぐらいかかっていた。まあ、山陰線を使うという、特殊事情もあったが。しかし、ほかの路線で考えても、よほど駅が近くないかぎりは、私鉄の方が便利だった。 ただ、今回の事件の報道を聞いていると、今ではだいぶ事情が変わってきているようだ。そもそも、福知山線なんて、ただのローカル線という認識しかない。宝塚なんて、まさに阪急の牙城だったはず。そんなところから、今回の列車のように、京阪奈丘陵の同志社の近くまで行く列車があったなんて(当時、同志社はまだあちらに移転していなかった)。 そういえば、大学の同級生の中には、鉄道オタク(当時、オタクなんて言葉はなかったが)が結構いたけど、彼らは、こういった事故があると、その能力がフルに働いてしまい、いろいろと解説してしまうんだろうな。
2005.04.27
コメント(1)
-
身長差
二卵性とはいっても、体格にはあまり差がなかったうりぼうず。でも、最近では「くう」の方が2センチほど高くなってきたような。そういえば、運動能力でも、かけっこの短距離でも「くう」の方が少し速くなってきた。学力の差はほどの開きはないが。 「双子といっても差があるのは当たり前」と、わかってはいても、ちょっとさびしさも感じる。まあ、それだけ個性が出てくるというのは、むしろ喜ばしいことなのかもしれないが。 そういえば、以前入っていた双子サークルで、まだ小学生の低学年なのに、身長で10センチぐらい差がある双子もいたっけ。そのくらい差が出来ちゃうと、周囲の理解を得るのにも苦労したんだろうなと、思ってしまう。
2005.04.26
コメント(1)
-
別荘がほしい
ウチのお子様たちが、なにを勘違いしているのか、別荘がほしいなどとわめいている。いったいなんだと思っているのだ。ビンボー人のほしがるものでないと、奥様も言い聞かせなければならないのに。 そういえば、スペインに別荘を持っている(ホントに今でも持っているのか不明)オジがいる。仕事で、そちらの方へ行ったときの衝動買いだとか。でも、スペインに別荘があるなんて、どんなお金持ちかと考えてしまうが、所詮はサラリーマン。なんせ、買値が300万ほどだったというから。もっとも、当時のスペインの物価水準だと、それなりのものだったのかも知れないが。 まあ、バカンスに訪れるヨーロッパ人への賃貸で、管理費用ぐらいは出ていたのかな。別に投資目的というわけではなかったようだが。 ちなみに、おじ夫婦は、そこに遊びに行ったことはないようで。なんせ、行くのに金がかかるし、所詮は日本人。そこでのんびり一ヶ月ぐらいボ~っと過ごす習慣はないのだから。 それでも、話のタネにはなるし、それなりに夢があると言えば、夢がある。ワタシは買う気ないけど。
2005.04.26
コメント(8)
-
列車事故
福知山線の事故で、新聞に過去の鉄道事故の一覧が出ている。1963年までは、何回も、100人以上が死亡する事故が起きている。八高線、桜木町、三河島、横須賀線と。今回のはそれ以来の規模という。 それだけ、昔に比べると、安全を確保する技術が進んだということか。その陰には、まさにプロジェクトX的な努力が重ねられていたのだろう。 今回の事故の原因は、まだ解明されていないが、それらの努力をもってしても防ぎ得ない、人為的なミス、管理体制の問題、あるいは置石といった犯罪行為があるのだろう。 それにしても、それまでこんな事態に巻き込まれると思ってもいなかった人々の上に突然ふりかかる不条理な出来事。不条理としか言うすべがないのだろうか。 終戦後の混乱期に起きた、八高線の2つの事故や、桜木町の事故。新聞の縮刷版でみると、なんと、一面のトップ記事ではない。当時は、それほど人がたやすく死んでいった時代だからなのだろうか。たしかに、300万人が死んだ(日本側だけで)戦争のあとなら、100人単位の事故なんて、そんなものとしか受け取れられなかったのかも知れない。
2005.04.26
コメント(0)
-
フリーター
ワタシの職場にも、アルバイトがいる。深夜勤なので、けっこう給料もいい。学生としては、破格といってもいいかもしれない。そこに落とし穴がある。 給料が良く、仕事も決して難しいものではなく、さらに社員に怒鳴られるなんてことも滅多になく、ようするに居心地がいい。 本来、学生のアルバイトといった仕事なのだが、そのまま居ついてしまうのが、何人もいる。ちょっと部署も異なるが、勤続20年を越すアルバイトもいる。ワタシが十年以上前に、今の職場にいたときの顔ぶれが、転勤で何箇所か回って帰ってきても、いたのである。 かつては、彼らのことを「坊や」などという呼び方をしていたが、もう、立派なおじさんである。 いくら、学生などには、条件がいいといっても、所詮はアルバイト。所帯を持つには苦しかろう。 しかし、派遣法だかなんだか知らないが、彼らのぬるま湯的な人生もいつまでも続くわけにはいかないようだ。なんでも、あと1年か2年で、契約が打ち切られるらしい。このアルバイトのほかに、何をしているか知らないが、少なくとも外の世界で通用するキャリアが身に付けられるような仕事ではない。いったい、これからどうなるのだろうか。 もちろん、彼らの自己責任といえば、その通りだが、安楽な立場を与えてきた方も、考え直さなければならないところがありそうな気がする。
2005.04.25
コメント(6)
-
みみずかわいい
コンポストの中をかき回していたら、さすがに春になったためか、ミミズが増えていた。それを覗きにきた「くう」が「ミミズかわいい」と、ミミズを手の上において愛でていた。そうか、かわいいか。ミミズを手の上にのせ、かわいいと言えるきみもかわいい。
2005.04.24
コメント(2)
-
文部省の戸惑い?
毎日新聞によれば、文部科学省にとまどいがあるとか。 きのう発表された学力テストの結果が上向いているからだとか。大臣のゆとり、総合学習否定発言があり、それの見直しに舵を切ったばかりなのに、その理由を覆される結果になったからだと。 なんなんだ。ただ、大臣の思いつき(たとえ、学力低下があるにしても、あの発言自体は、思いつきのようなものだと、少なくともワタシはそう思う)で方針を大転換したのに、その大義名分がなくなってしまうからといって、戸惑いはないだろう。 もちろん、一つのテストの結果で、右往左往するほうが問題といえば、問題。塾でも、テストの結果に一喜一憂しないようにといっているではないか。
2005.04.23
コメント(6)
-
こいのぼり
通勤の電車のまどから、いくら眺めても、こいのぼりが見つからない。子どものころならば、この季節には、そこら中にこいのぼりが大空を泳ぐ姿が見られたはずなのに。 最近、こいのぼりといえば、自治体や町おこしグループなどが、川などを横断させる形で、数百匹を泳がせるようなものばかり(大半は、子どもが大きくなって不用になったものを活用しているようだが)。普通の家庭で、普通に泳ぐこいのぼりが見られない。 ひところ、マンションのベランダなどで泳いでいた長さ1、2メートルぐらいのこいのぼりでさえ、滅多に見られなくなってしまった。子どもが減っているからか。それとも、習慣として廃れてしまったのか。 そういえば、ドイツに住む姉が、日本の知り合いからもらったこいのぼりを、庭であげると、けっこう近所で受けたという話を聞いた。 まあ、それも数百平米の庭のある家だからできることなのかも。こいのぼりをあげたくても、こいのぼりが泳げるだけのスペースのある庭なんて、滅多になくなっているから。しょうがないのかな。田舎にいけば、まだ泳いでいるのだろうか。
2005.04.22
コメント(1)
-
行く場所が・・・
ゴールデンウイークどこかに行こうと思っていたが、まったく考えがまとまらないうちに、時間ばかり過ぎ、どこでもいいかと検索しても、もはや列車などほとんど満席状態。どこにも行かずにすませるか。行っても、高くて混んでいるだけだし。
2005.04.22
コメント(6)
-
やまぶき
現在、隣家との境界線付近の藪と化しているあたりに八重のヤマブキが花盛り。栽培というよりは、勝手に生えてきて、勝手に育っているという感じか。 この付近の手入れをなんとかしたいと思っているのだが、斜面になっているので、どうしようかと、逡巡しているうちに、結局なにもしないで終わってしまう。今は、ヤマブキのほかにシャガも勝手に花を咲かせているので、それなりにきれいだが、まもなくうっとうしい藪になってしまう。 そんな、こんなで庭をみていたら、いつの間にか、すずらんの芽も伸びてきている。半月もすれば、花が咲き始めるのだろうか。今年はいつもより遅いような気もするが。
2005.04.21
コメント(2)
-
またまたオプション
「くう」がまた塾からオプションの案内をもらってきた。算数の苦手な子ども用のもの。確かに苦手なんだけど、そんなにオプション漬けにしていいものやら。金曜日にも、オプションが入って、「みい」と同じ時間に出かけなければならないが、水曜日まで。まあ、「みい」が行っているんだから、絶対ムリな時間帯ではない。仲のいい友達も、みんなその案内をもらったというから(類は友を呼ぶなのか)、友達がいなくてさびしいということもないとは思うが。 「必ずしも、受けなくていい」とは、言われているだが。
2005.04.21
コメント(4)
-
78歳
新法王が決まったが、なんと78歳。事前に候補に挙がっていた顔ぶれをみても、多くが70台だった気もするが、なんとまあ、ご苦労なことで。ヨハネパウロ2世が就任したのが比較的若かったから、いろいろと世界中を飛び回ることもできたが、これじゃあ大変そう。世襲がいいとは言わないが、世襲ならもう少しは若返りするのだろう。もっとも、最近どこも長寿になり、「次」になる人たちがイギリスのチャールズも50台後半、日本だって、もう45歳だもんね。新鮮さを期待されても困るか。
2005.04.20
コメント(2)
-
塾のお友達
塾のお友達って優しい子が多いのだろうか。このあいだのカリテで、とうとう応用で0点を取った娘に、「公開模試はそんなに悪くないんだから、ちゃんと見直しをすれば、ちゃんと取れるよ」などと、アドバイスをしてくれたらしい。前には、隣の男の子が居眠りしているのを突っついて起こしてくれたり。みんな「戦友」なんですね。それにしても、アドバイスを受ける前に、しっかりやらんかい。 もっとも、アドバイスを受けても、結局やらないことには変わりないんですが。
2005.04.19
コメント(4)
-
解散
ワタシが不在の折、隣家の奥様がウチご挨拶に来たらしい。 奥様と言っても、もう90歳を越えている。今度、娘さんのところに厄介になるということ。ご主人は、今年の初めに卒中で倒れて、一度はもどってきたが、結局入院。入院といっても、多分もう病院から帰ってくることはないのだろう。一つの家庭が解散するということなんだろう。 本当に、行き会えば挨拶するぐらいの関係だったが。 最近、「歳をとるということは、こういうことなのか」と、実感させられてしまうことが多い。 高齢化が進むこの地域。ワタシの住んでいる町会は、高齢化率30パーセント台だが、ある町会に至っては、45パーセントだとか。 30年、40年先を見通せなかった住宅政策の誤りというべきか。単に、少子化だけが原因ではない。 臨海部に続々とマンションが建っているが、結局これらの地域も同じような年齢の人たちがあつまり、同時進行のように高齢化していくのだろうか。
2005.04.19
コメント(0)
-
毎日かあさん
なんとも露骨なタイトルだが、毎日新聞で毎週月曜日に掲載されている西原理恵子のマンガ「毎日かあさん」が面白い。いわゆる子育てマンガ的なものは多いが、これだけむちゃくちゃで、ある意味で愛情あふれるものは少ないだろう。きょうのも、最後で雨上がりのぬかるんだ滑り台の下に寝転んだ子どもたちに「そこからみる空のいろはきっとちがうんだろうな」と、いう言葉でしめている。 こういう経験が、将来に生きるとか、そんなセコイことでなく、そこに寝転んでいた時の子どもは、それ自体幸せなんだろうなと。
2005.04.18
コメント(4)
-
自転車の名前
新聞の投書に、自転車の名前について、自転車置き場で自転車を整理している人からのものが載っていた。自転車に名前や住所、電話番号などを書いているとあぶないとのこと。なにか、それをメモしている人間もいたとか。確かに、このご時勢、危険と言えば危険なんだろう、持ち物にはなんでも名前を書きなさいなんて、いえない時代になたのだろうか。自転車はなくしても、防犯登録によって、警察経由で返してもらうべきなんだろう。 そういえば、子どもの自転車の名前、書いてなかった。
2005.04.18
コメント(14)
-
ささいなことで
どうも、年のせいか怒りっぽくなっていけません。つまらないことで子どもと衝突してしまい。子どもだけでなく、奥様とも(これは昔からですが)。しかも、子どもはすぐにケロリと忘れるのに、こっちはいつまでも根に持ってしまい(子どもも根に持っているかもしれませんが)すぐに不貞寝をしたり、ぷいと外に出たり・・・。年のせいというよりも、まだこちらの精神年齢が子どもということなんでしょうか。 一応、反省はするのですが、すぐに繰り返してしまう。ダメですね。その理由も、書くのが恥ずかしい内容なもんで。
2005.04.17
コメント(4)
-
5年の社会・資料集
教科書のことばかり書いていたが、その他の副読本というものもあったのを忘れていた。教科書がなくて、資料集だけでも学習できるほど、こちらの方が内容が多い。検定もないので機動的な編集もできるようで、巻頭から中越地震や台風、猛暑など昨年のトピックス的なことが掲載されている。 食料生産についても、米だけでなく、果物、野菜、酪農、から日本が輸入するエビの養殖のためのマングローブ林の破壊問題にまで触れられている。 学習指導要領に縛られる教科書と違って、副読本である資料集は、なんでもアリということか。これが充実していれば、教科書の「発展」なんてなくてもいいということか。社会が好きな子どもなら、たとえ授業でやらなくても、これを面白がって読むかもしれない。 と、なると、教科書の意味はどうなるのだろう。授業で別に使わなくてもいいのだろうか。 ついでに、ちょっと気づいたこと。この資料集に「わたしたちのくらしと工業製品」というコーナーに40~50年ほど前の暮らしのイラストが載っている。古い日本家屋で、台所は土間でかまどもついている。電気製品は、照明とラジオぐらいという感じ。 これを見て、40~50年前という設定が気になった。このころの日本は、今以上に生活の格差など、地域によって、あるいは階層によってあった時代ではないのだろうか。これが、たとえば、大都市部の給与生活者の家庭とか、なんとか断り書きを入れないと、誤解をまねくのではないかという疑問。この時代に生活者として生きていた母親にみせると、けっこう鋭く描かれた風景についての疑問点をしてきしていた。
2005.04.16
コメント(2)
-
神奈川の入試
神奈川県の県立高校入試、ずいぶん問題がありそう。前期が学力試験ではなくて、内申や面接によるものらしいが、その内申の学校間格差があまりにも大きい。絶対評価なので、昨年ほどではないにしても、今年も5の数で10倍ほどの開きがあったとのこと。 この現状に対して、県教委が何年かすれば落ち着くといった趣旨のコメントをしていたというが、何年かたったらと言っても、その間の生徒はどうなるんだ。たとえ相対評価にしても、内申というのは問題が大きい。
2005.04.15
コメント(6)
-
リハビリ病棟
いわゆる治療が終わったのか、父はリハビリ病棟へお引越し。 それにしても、この父親、何を考えているのか、いや、何も考えていないんだろう。リハビリのなんたるか、まったく理解していない様子。梗塞の影響でと、普通なら考えたくもなるが、それならば生まれたときから梗塞しているとしか思えないような、頓珍漢な発言ばかり。 母親も相手をするのに、苦労している。
2005.04.14
コメント(0)
-
5年の教科書・算数
この教科、本当によくわかりません。難しくなってんだか、簡単になってんだか。カラフルになったことだけは間違いないけど。練習問題の少なさは、別のドリルかなんかでまかなえば、それでいいとは思うが(これもまたカラフルでイラストもいっぱい)。自分の時代を覚えてもいないので比較もできない。 塾のテキストには、けっこうコラム的な読み物(ただし、ウチの子どもは読まない。親がけっこう読んでいる)も多いのだが。これは、算数の面白さを伝えるのには、格好の材料。でも、子どもが読まなければしょうがないか。
2005.04.14
コメント(1)
-
防衛大
会社に、防衛大の出身者がいた。ようするに、任官拒否組の一人というわけだ。そんな彼でも、人生の中で一番感激した瞬間は、卒業式の時に、帽子を一斉に投げ上げた瞬間だったという。 さて、その任官拒否の理由だが、別にそれが最大のものかどうか知らないが、大学校時代の成績が、そのまま定年までつきまとうことがその理由の一つだったようだ(要するに、成績が芳しくなかったということなのか?)。つまり、旧海軍のハンモックナンバーと同じ。学業成績が良かった人間が戦争がうまいわけでもなかろうに(戦争というと語弊があるが)。 未だにそんな慣行が続いているとは。もちろん、普通の大学や会社と違い、学生時代からそのための教育を受け、そのおんなじメンバーが、引き続き集まる社会だから、一般論ではいえないかもしれないが。 旧軍の伝統から脱却するのは難しいのか(しなきゃいけないと、誰も思っていなければそれまでだが)。
2005.04.13
コメント(6)
-
新担任
5年から、うりぼうずは二人とも、新しい担任の先生。どちらも男。一人は、熱血タイプで、あんまり塾などは賛成しない方と、聞かされていたようで、「みい」などは警戒していたが、いざなってみると、本人は楽しそう。けっこうどんな先生でも楽しんでしまうところがあるのは、いい性格なんだろう。「くう」は若い男の先生。講師で、まだ顔も見たことはないが、この先生のこともけっこう話はよくしてくれるので、まずは一安心。若い男の先生は、キャンプのカウンセラーなどで大学生ぐらいのお兄ちゃんと接することも多いので、ある意味で慣れているのかもしれない。まずは、順調なスタートかな? まあ、子どもにしろ、保護者にしろ、とにかくヘンナ先入観を持っていると、アラを探したくなってしまうので。
2005.04.13
コメント(2)
-
5年の教科書・図工
図工というのも、よくわからない分野だけど、「日本のアート」という項目の中に、海洋堂のフィギュアをみつけた。多分、チョコエッグの中に入ってるやつ。 アニメのヒロイン?のようなフィギュアが、アメリカの美術館で高値でお買い上げいただく時代なんだから、もちろん、美術の範囲は広いはず。海洋堂のフィギュアも、根付と一緒に並べてあった。確かに、共通する日本文化だろう。携帯ストラップなんて、まさに根付だもんね。 そういえば、教科書の冒頭から俵屋宗達の風神雷神が出ていたが、そこには、やはり風神を描いた中国の古い壁画も載せられており、文化が模倣とそこに新たな新機軸を加えることによって発展してきたことを暗に説明する形となっている。 確かに、便器にサインをしたことによって芸術観が一変したとすれば、小学生に教える美術の概念も変化するのだろう。だいぶ時間は経過したけど。 でも、ピカソも天才的なデッサン力がまずあって、それから独自の道を発見したことを考えれば、独創の前に地道な写生なども図工の教育の中に必要な気もするが、少なくとも授業の中ではあまり行われていないようだ。 とにかく、この分野はよくわかりません。
2005.04.12
コメント(2)
-
父親ばかりの入学式?
あくまでも伝聞ですが。 近所の中学校の入学式、「つきそいがお父さんだけ」という家庭が多いとか。別に、離婚の増加とか、そんな理由ではない。学校の役員を逃げるためだという。まあ、話だから、そういう人が何人かいたと言う程度かもしれないが。 もちろん、かわいい小学1年生に比べれば、親の方も「ぜひ出席したい」と言うほどではないのだろうけど。さすがに、小学校の入学式で、母親の出席が減っているという話は聞かない。 小学校の役員も大変かもしれないが、中学の役員となれば、けっこう深刻な問題もでてくるからなのか。でも、深刻だからこそ、向き合っていかなければならないのでは。以上、他人事でしたが。
2005.04.12
コメント(8)
-
反日
韓国で、そして中国で。どうも嫌われているようだ。そういえば、きのう会社でも、けっこう過激な意見が飛び交っていた。別に、デモをやろうなんていうのは一人もいないが。心の中では、けっこう反中国感情が高まっているようだ。 でも、そういうのって、口に出しているうちにどんどんエスカレートしていくんだろう。もちろん、あの黙ってみているだけの中国当局を見ていると、怒りたくもなるんだろうが。内政でいろいろと問題があるところに、憤懣が日本の方へ向かえば、それにこしたことはないのだろうが。 ただ、これにストレートに反応してしまうと、中国側は一層反感を募らせるだけ。「とりあえずは言わせておく」ぐらいしか、ないのではないだろうか。 これで、観光客減れば、困るのは先方だし、日本企業が進出に二の足を踏めば、あちらのリスクも相当に大きいはず。 すべてを金で勘定するのもどうかと思うが、もう少しみんなゼニ勘定で考えれば、冷静になれるのにと。 コイズミ氏の靖国問題にしても、あれはゼニ勘定からすれば、決して得になることではない。しかし、一度あれを持ち出すと、向こうも何らかの反応をせざるを得なくなる。それに対して、日本側も反発を受けたからといって、いちいち引っ込んでしまうわけに行かなくなるだろう。 それにしても、なんで日本は嫌われるのか。アヘン戦争のイギリスだってヒドイじゃないかといえば、それまでだが。そこらへんを冷静に分析してみる必要がありそうだ。相手が悪いとだけ言っていれば(それが事実としても)解決する問題ではないのだから。 まあ、根性ナシといわれれば、まさにその通り。
2005.04.11
コメント(2)
-
けっこうやるじゃん
あんまり、細かい数字を書くのも気が引けるが、今回の公開模試、まだ見直しをろくにやっていなかった。でも、結果だけは二人とも今までで一番いいのではないだろうか。「みい」など、算数は相変わらずだが、久々に国語が偏差値70台。漢字を二つ間違えたとか、わめいていたが、点数を見ると、それ以外には間違えていないぐらいのもんだ。「くう」も算数が彼女としては奇跡的な?数字をとっている。一喜一憂するなとはいっても、ときには「喜」がないと。 まあ、二人ともたまたま今回はツボにはまっただけなんだろうけど。
2005.04.11
コメント(2)
-
なんで講師ばっかり
自分が子どものころ、学校に講師ってあんまりいなかったような気がする。でも、最近の学校にはやたらと講師がいる。 二十年以上前に採用した教師が多すぎて、新規に採用しないからか。でも、これから団塊の世代の教師が一気に退職期を迎えて、急に教師不足の時代が来るともいう。 数年の間、講師をやらせて、その才能を見極めるのもいいのかもしれないが、採用される側としては、たまったもんではないだろう。あんまりそんなことをやっていると、優秀な人材ほど、他へ流出してしまうのではないだろうか。 大体、採用試験について聞こえてくるのは、コネの話が多い。意欲や才能のある人材を、いつまでも講師として処遇しているのは、将来に禍根を残すような気がするが。 うりぼうずの昨年までの担任は、今年も講師のまま。今年の担任の一人も講師のようだ。同じ仕事をしているのに、待遇の違いが大きすぎる。いくら、財政改革とは言え、なんでもかんでもパート労働化していては、若い講師たちのやる気も磨り減ってしまう。
2005.04.10
コメント(0)
-
一学年消滅?
うりぼうずの通う小学校、1学年だけ、1クラスのところがあったが、今年は転校生が多く、2クラスになったという。ところが、話を聞くと、隣接する小学校からその学年に大量の転入生があったからという。 その隣接する小学校は、かつては2000人を越すマンモス校だったところ。それが、地域の高齢化で若年人口がいなくなり、いまや100人をわずかに超える状態と聞いていた。 どうも、隣接小学校のその学年は、今回の大移動?で一人もいなくなったとの話を二人がしていた。たしかに、あまり少人数だと、父母も心配し子どもを転校させたくなるのかも知れない。隣接地域なら、比較的容易に転入させてくれるように、制度が確立したのか。でも、残された方としては、一学年ない常態では、学校運営が非常に難しいのではないだろうか。 同じ中学校区に3小学校があるといっても、もとは一つの学校が人数が過大になりすぎたために分割されたところ。学区も狭く、徒歩通学にもなんの支障もないところ。村のシンボル的な伝統あるところと違って、住民にも抵抗感はすくないだろうから、統合などは比較的容易と思われるが・・・。
2005.04.10
コメント(0)
-
5年の教科書・社会
さて、社会。基本的には地理だが、自分の子ども時代は、地誌的に、北海道、東北、関東などと地方ごとにわけて学んでいった記憶が。そして、関東なら利根川を中心に関東平野が形成され、京浜工業地帯があり・・・と、いった具合。しかし、今の教科書では食料生産、工業生産などと項目をたて、食料生産ならまず、庄内平野の米づくり、枕崎の漁業などを詳しく紹介。そこから派生させ、漁業ならば海流などにも発展させるといった手法をとっている。 また、工業でも大田区の町工場を取り上げ、町工場の部品が宇宙産業にとって欠かせないものを作っていることなどを紹介。いわゆる地理というよりも、広い意味での社会を学ぶ形態といってみてもいいのだろう。 ただ、全国の都道府県名など覚える余地はないだろう。主な山地山脈などに触れることもなさそうだ。一つの産業のあり方などを学び、方法論を獲得したうえで、あとは、個々人で発展させることを目指しているのだろう。 でも、国語で漢字を覚えることが必要なように、基本的な地名などの知識をどこでどう担保するか。そんなものいらないと、言い切ってもいいのだろうか。 ただし、昔のやり方でも、一般の人はどの程度まで地名などを記憶しているのだろうか。授業が終わると、すぐに忘れていたのではなかろうか。それならば、そんなものをムリに覚える必要もないのかも知れない。 その点、塾のテキストなどは、昔の社会科学習の形態をそのまま維持している形だ。しかし、こんな地名まで覚える必要があるのかというレベルまで記憶させているのも、ムダな気もする。学校教育では、やはりこの教科書のようなやり方の方がベターかも知れない。 なまじ社会の分野に関心を持っているだけに、いいんだか悪いんだか、わからなくなる。
2005.04.09
コメント(4)
-
春も盛り
急に春というより、初夏に近い気候になってしまった。おかげでサクラを始めとして、花が一気に咲いて、そして散ってしまいそう。庭でもアイリス、花ダイコン、シャガ、イチゴ、ユキヤナギなどがいっせいに咲いている。一番花が多い季節かな。 ミツバチ(だと思う)が盛んに飛び回っているが、いったいどこに巣を作っているのだろう。アシナガバチの巣は、毎年庭でも一、二箇所発見するが、ミツバチの巣は見たことない(そういえば、井の頭の動物園の木のうろにニホンミツバチが巣を作っているのはみたことがあるが・・・。
2005.04.09
コメント(0)
-
5年生の教科書・国語
国語の教科書は、よくわからない。よく、今の教科書からは、「古典ともいえる名作がなくなっている」というが、確かにそれはあまり見当たらない。「薄っぺらい(物理的に)」といえば、確かに薄っぺらい。 ただ、こんな文章が載るのかと思ったのが、「まんがの方法」という文章。まんがの表現方法(文法と言えばいいのか)について論じるもので、背景によって登場人物の感情をあらわすやり方(ガーンとショックを受けるような場面では、背景が真っ黒になったり、恋する乙女の背景がバラの花で埋め尽くされるやつ)の解説、コマを人間が突き破ることによって、驚きの強さを表現したり。 取り上げられているのは、ジャングル大帝、ポケモン、おもいでぽろぽろ、ちびまるこ、ドラえもんといったそれなりにさまざまな分野に目配りされている。 これなど、表現方法にはそれぞれ文法と呼べるような手法があることを考えさせるにはいい題材かもしれない。映画のモンタージュなどもその一つ(手塚マンガなど、かなり映画の手法を取り入れているが)。 名作を読む必要というのは、確かに理解できる。「まんが」を採用したのも、子どもの受けを狙ったという批判も的外れではないと思う。しかし、これだけメジャーな表現方法を解析する文章が、子どもの教科書にあったって、いいと思う。 とにかく、今の子どもがやらなくてはならないことが多すぎるのだ。さまざまな分野から、「これも必要」、「あれも必要」と言われるのだから。 この教科書を見ても、ディベート?のやり方も載っている。新聞などに載っているような「コラムを書こう」と言うものもある。自分のアピールの仕方なんてものもある。これなど、学校の勉強は社会にでて何も役に立たないと攻撃されたことへの一つの回答とも言えるだろう。実践的なものが多くなれば、器の大きさが決まっていれば、それ以外のものが少なくなるのはやむをえない。(だから、授業時間全体が減らされることに問題があると言えば、その通りだ。だからと言って、子どもになんでもかんでもやれと言うのは無茶と言うもの)。 教師にも、批判されなければいけないことは山ほどあるが、年々変わる題材に対応していくのも大変だ。
2005.04.09
コメント(2)
-
九段下から竹橋へ
出勤前に、少し時間が余ってしまったので、九段下で下車。ぶらぶらと大手町方面へ向かって歩いた。 九段下の駅から地上にでるとすぐに昭和館が。この館は、なんと形容すればいいのだろう。「苦難の昭和を記憶するために」建設されたとでもいうのだろうか。常設展示には、学童疎開の様子を伺わせる展示や、昭和の各時期の庶民の生活用具などが展示されているようだが。 きょうは、とりあえず「マンガと子どもたち~胸ときめかしたヒーロー、ヒロイン」という、企画展をやっていたので、覗いてみた。のらくろ、フクちゃんといった顔ぶれがならんでいた。それにしても、昔はよくこんなマンガがマンガとして存在したと言うと、言いすぎだろうか。この70年ほどの間に、恐るべき発展をとげたものだ。 昭和館を後にして、北の丸公園を抜け、科学技術館のヨコを過ぎると、国立公文書館。ここも年4回ほど企画展をやっているが、けっこう面白い。ちょうど特別展として「将軍のアーカイブス」が開催中。徳川将軍家がその蔵書などを保管した「紅葉山文庫」(その後、明治政府が受け継ぎ、現在国立公文書館が所蔵)の古書や古文書などが展示されていた。 さすが、名君というのか、家康、吉宗の書物に寄せる関心は高かったようだ。特に吉宗などは、中国の地理書などの収集にも力を入れ、現在の中国では失われたようなものも、けっこうここに保存されているという。単なる興味だけではなく、法律の制定、医学の充実などを図るためなど、その勉強ぶりが伺われる展示だった。また、択捉探検の近藤重蔵が、この文庫を管理する書物奉行なる役職についていたとは初めて知った。彼ら、江戸時代の司書の書き残したものも面白い。 ちなみに、この展示は4月24日まで。無料。 今回は行かなかったが、この隣の国立近代美術館の休憩室からみる、千代田城のサクラは、なかなかのものです。お暇な方は、ぜひ一度出かけてください。
2005.04.08
コメント(0)
-
5年生の教科書・保健
時間割に体育はあるが、保健はどうやって確保するんだろう。実際に授業をどうするかは別にして、この教科書もけっこう面白いものだ。 巻末にあるのは、「断り方の練習」 何を断るかって。親戚のおじさんに「ビールぐらい飲んでみろ」と誘われたとき、友達に「たばこを吸ってみたら」と、言われたとき。ロールプレイングとでもいうのか、おじさんや、悪友役のせりふが書いてあって、それにどう答えるかというもの。 ちなみに、ちょっとやってみたら、「くう」は、「みんなもやってるよ」との悪友側のせりふに対して「みんなって言っても、ウチは吸ってないもん」と。エライ。そのせりふ。今度「みんな持ってるから買ってよ」と来られたら、その言葉でお返ししてあげよう。 そのほか、時代を反映しているのか、シンナーなどの薬物、タバコ、酒の害、はたまた生活習慣病予防など盛りだくさん。事故や災害の防止について、どんな工夫が必要かにも触れられている。 ただ、エイズにも触れられているが、「感染している人の血液などが傷口などから入ることでうつります」としている。現在ではほとんど性感染症なのに、果たしてこの書き方でいいのだろうか。もちろん、書きにくいのはわかるが。 自分の小学生時代に、果たして保健の教科書があったかどうか。記憶にすらない。しかし、まあ、よく出来てはいるように感じる。あとは、これをどう教えるかなのだろうが。
2005.04.08
コメント(8)
-
5年生の教科書・家庭科
うりぼうずが教科書を持って帰って来た。 5年から始まる家庭科。もっとも、自分が小学校のころどんな家庭科の教科書だかまったく覚えていないが。 それにしても、家庭科の教科書の守備範囲の広さには驚かされる。調理と裁縫ぐらいかと思っていたが、環境教育の一環としてのゴミの出し方、ボランティアなど。さらには、金銭教育として、買い物の計画(チラシ、ネットでの情報収集のやり方なども含め)、持っている消しゴムと実際に使っている数を比較して「モノの使い方を見直そう」なんてコーナーも設けられている。 「快適な住まい」といったコーナーでは、部屋を明るくするための工夫、エネルギーを浪費しないための配慮など、社会、理科の学習にまで踏み込むような内容。まさに総合学習とでも呼べるような内容になっている。教え方によっては、非常に面白いものになりそう。 基礎学力重視というが、こういった家庭科なら、もっと時間数を増やしてもいいのではないかとも思った。
2005.04.07
コメント(2)
-
GWどうするか
今頃から考えても遅いかもしれないが、さて、GWどうしましょ。塾の日程を考えると(そんなものに、拘泥される必要などないといえば、そうだが)、3,4,5しかない。その日にこちらが休めるかどうか、わからないが。 3日しかないと、フルに使えるのは1日だけ。去年は、姫路から神戸、淡路島、徳島とけっこう充実していたような気もするが・・・。 久々に東北方面とか、これまで縁のなかった北陸方面とか。一生に一度くらい、伊勢参りとか(別に一度でなくてもいいけど)。 こんなとき、つい「お勉強になるところ」などと考えてしまうのが、親のあさましさ。去年のも、野島断層とか、姫路城を見せてみたかったというのが、コース選定の要素になっていたような気がする。いっそのこと、次期世界遺産候補の知床とか(ちょっと遠い)。 でも、あんまり混んでいるのはイヤだし。
2005.04.07
コメント(2)
-
戦艦大和
きょうは、戦艦大和が撃沈されて、60年ということらしい。新聞でも、企画が掲載されていた。 大和、零戦、特攻というのが、どうもあの戦争の象徴として語られることが多い。世界最大、最強の戦艦であり、世界最強の戦闘機であり、もっとも過酷な戦い方であると同時に、その犠牲的精神の象徴として。 しかし、大和については、最大であったことは事実であっても、戦争において、いったいどんな働きをしたか。実際の戦闘としては、マリアナ、レイテ、そして最後の出撃の三回だけであり、そのうち二つは航空機による一方的な攻撃を受けた戦い。レイテにおいても、新聞の企画では米艦隊に打撃を与えたと書いてあったが、実際には一発も当たらなかったという説もあるほど。なんせ、撃ってから着弾するまでに40秒もかかっては、相手がその間にどこに動くかわからず、滅多に当たるものとは思えない。そんな距離の砲撃戦の精度を考えると、やはり大艦巨砲主義の愚かしさが見えてくる。 米軍の物量というが、レーダー技術といい、ダメージを受けた場合の修復力といい、高級指揮官、政治家の能力といい、質的な部分でも勝負にならなかった戦争。そのことを、覆い隠すのに、大和の大きさが語られることに違和感がある。愚劣な仮想戦記ではないのだから。 「華やか」などといっては、語弊があるが、戦争を語る場合に、そんな部分にだけ光があたると、大きなものを見誤る恐れがあるのでは。 一発も弾を撃つこともなく、輸送船で運ばれる途中に、バシー海峡で死んだ兵士たち、フィリピンやニューギニアの山中で、なんの補給もなく餓えて死んだ数十万の兵士たち、あの戦争の本質は、そちらの方にあったのではないだろうか。
2005.04.07
コメント(0)
-
きょうから早くも
塾は金曜日から再開と思っていたら、なんと、もうきょうから始まるとは知らなかった。ヒマだったので、「みい」を駅まで見送りに。 いい加減なようでも、「きょうまたクラスわけがあるけど、落ちるのヤダな」などと言っている。「いやなら、少しはやらんと」といっても、ぬかに釘。 でも、本当に休むヒマなし。それでも、「やめたら」と言っても、絶対にやめるとは言わない。5年のスケジュールが始まるまでは、「こんなにハードなの、絶対ムリ」とかいっていたのに、あまり苦痛は感じていない様子。
2005.04.06
コメント(0)
-
死刑
共同通信のサイトに、昨年1年間の死刑が3800人と出ていた。その9割が中国とか。もちろん、それだけ人口が多いのだろうが。 アメリカなんて、いっぱいやっていそうだが、それでも5、60人とか(もちろん、それでも世界で4番目だったかな)。 日本は、一体何人いたのか。 名張の毒ぶどう酒事件の再審のニュースをみて、考えてしまった。40年間、死刑囚であり続けるというのは、どんなことなのだろう。もしかしたら、帝銀事件よりも長いのだろうか。 そういえば、死刑廃止にむけた活動をしている国会議員の中心メンバーが元警察官僚の亀井静香氏だということを知ったときは、新鮮な驚きを覚えたものだ。
2005.04.06
コメント(0)
-
総合学習見直しのウラ
毎日新聞に、文科相の「ゆとり教育転換」発言の舞台裏の話が出ていた。要するに、あのときは、教育現場から、「ゆとり、総合学習をやめてくれ」という声があったので、ああいう発言をしたように言われていたが、その前後に、視察した現場などからは、そんな話はなかったとのこと。要するに、そのように装って、持論を前面に押し出したというのが、真実らしい。 結局、こういった思いつきのような(それなりに、深謀遠慮の発言なのかも)発言によって、動かされたのでは、教育現場が気の毒になる。
2005.04.05
コメント(2)
-
格差固定化社会
NHKで2日に放送された、番組の再放送が、夜帰ったらやっていた。その中で、格差固定化社会と言う問題が取り上げられていた。 ただ、格差の固定化ということは、今に始まったことではないだろう。昔から、高学歴の親の家庭の子供が、ある程度高学歴になる傾向はあったはず。いや、今よりも強かったのではないか。 確かに、塾に通わせることができる経済力の問題はあるかも知れない。しかし、基本的には、本人のやる気でカバーできるものが大きいように感じる。 ただ、単なる経済力ではなく、文化的な雰囲気を継承する力というのは、非常に大きいのではないだろうか。 もちろん、格差の固定化を是とするわけではないが。しかし、これは今でてきた問題ではないはずだ。
2005.04.04
コメント(0)
-
春期講習おわり
テストでようやく春期講習終わり。間にスキーが入った割には、「みい」は「テストけっこう出来たよ」と、脳天気にいっているが、「くう」はノーコメント。 やっと、春休みらしい春休みに。もっとも、あと何日あるんだ。
2005.04.04
コメント(4)
-
おむつ
父親が倒れたあと、一番ショックだったのは、おむつをしているのを見たときかもしれない。もちろん、頭ではそんなことはわかっていたつもりだが。ショックというより、「歳をとる、倒れるということは、こういうことなのか」という、感慨とでも言った方が正確なのか。 多分、そこで排泄をするということは、人間の尊厳にとって非常に大きなダメージを与えることなのだろうとも。 ただ、それになれることも必要なのかもしれないが、それに慣れてしまうことは、リハビリをはじめ、回復しようと言う意欲をそぐことにつながるのではとも思った。
2005.04.03
コメント(1)
-
わすれもの
スキーから帰り、早速きょうから春期講習の残りが始まった。 スキーと言えば、荷物整理で忘れ物が発覚。「くう」がゴーグル、その他袋ごとバスの中に忘れてきたような。連れて帰ったのが無責任オヤジだったが、それにしても本人が忘れ物をしないためには、どうすればいいか、そういったことには全く気が回らない性格。こういうのも、大げさに言えば「生きる力」なのだろうが。左記が思いやられる。
2005.04.03
コメント(0)
-
草津
草津まで、子供をお迎えに。スキー場なんて行くのは本当に久しぶり(と、いって、すべるわけでもないのだが)。草津の町は行くのは初めて。行くまでは結構不便なところだが、町自体はけっこういい町。町中の商店や旅館などに「ザスパ草津」の宣伝ポスターが張ってあった。 子供たちは、いずれも元気。疲れてはいたけれど。山越えも、大過なく終えることができたとのこと。帰りは、軽井沢の方から新幹線で帰還。
2005.04.02
コメント(0)
-
しまったエイプリルフールだった
しまった、エイプリルフールだった。うりぼうずが模擬試験で満点をとったとか、どうせなら適当なことを書いてやればよかった。 エイプリルフールといえば、十年ぐらい前、某新聞に旧ソ連の人口が実は統計で公表されているもの倍以上いるとの翻訳記事が出ていた。ソ連体制が腐敗し、統計も満足にとれていないなどの理由らしい。もちろん、その記事は4月1日のものではなかった。 しかし後日、その記事は、エイプリルフール用に、書いた外国の雑誌の記事を、ホラ話とは気がつかずに、転載してしまいましたとのお詫びが出ていた。これには笑えました。
2005.04.01
コメント(0)
全51件 (51件中 1-50件目)
-
-

- 共に成長する家族!子供と親の成長日…
- 我が家の「沈黙の戦隊」
- (2025-10-24 09:33:10)
-
-
-
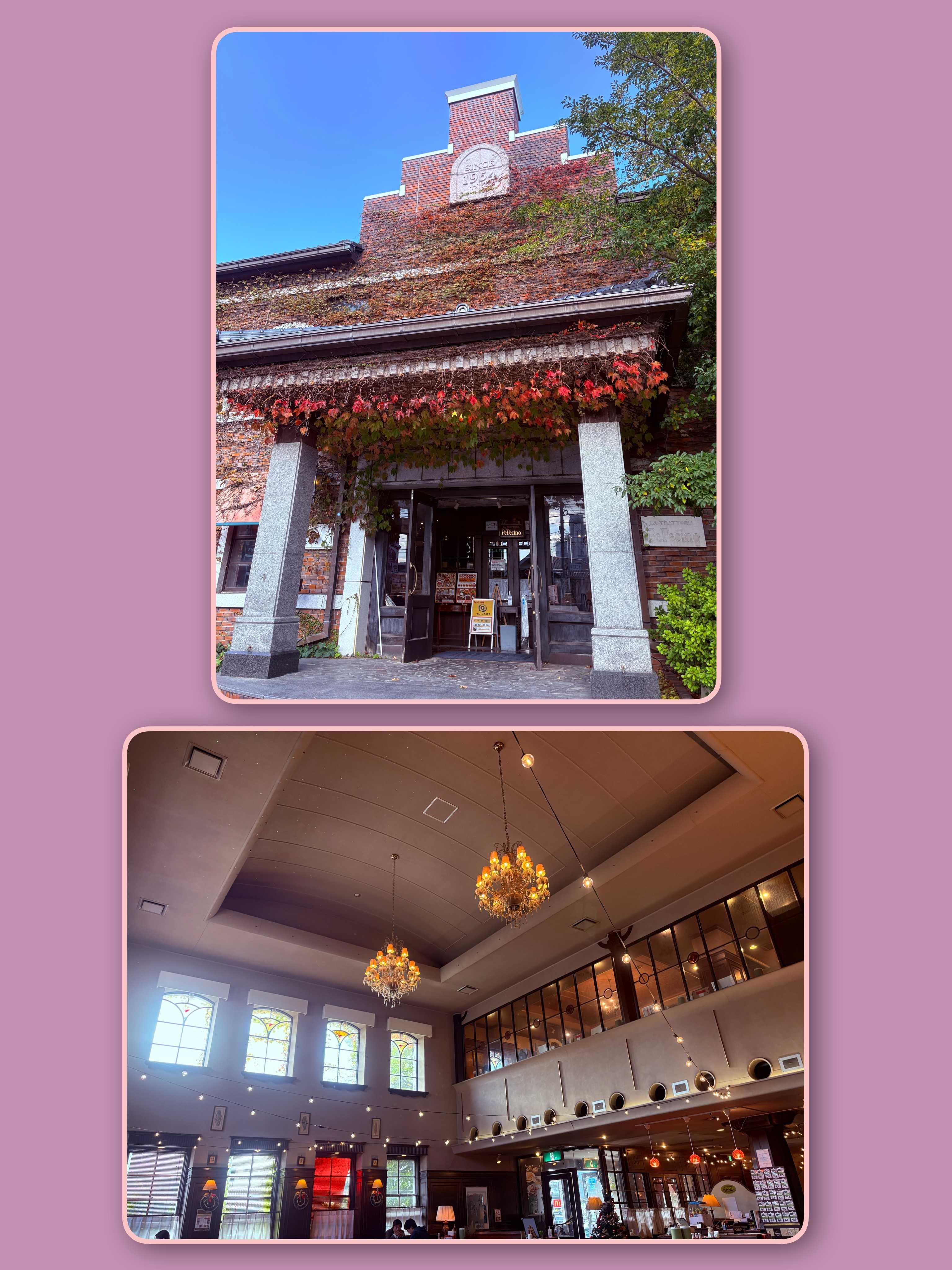
- 高校生ママの日記
- 3連休(ピアノレッスン・夫BD・神社…
- (2025-11-24 23:59:17)
-
-
-

- 塾の先生のページ
- リスクは管理できても、ギャンブルは…
- (2025-11-24 11:50:04)
-








