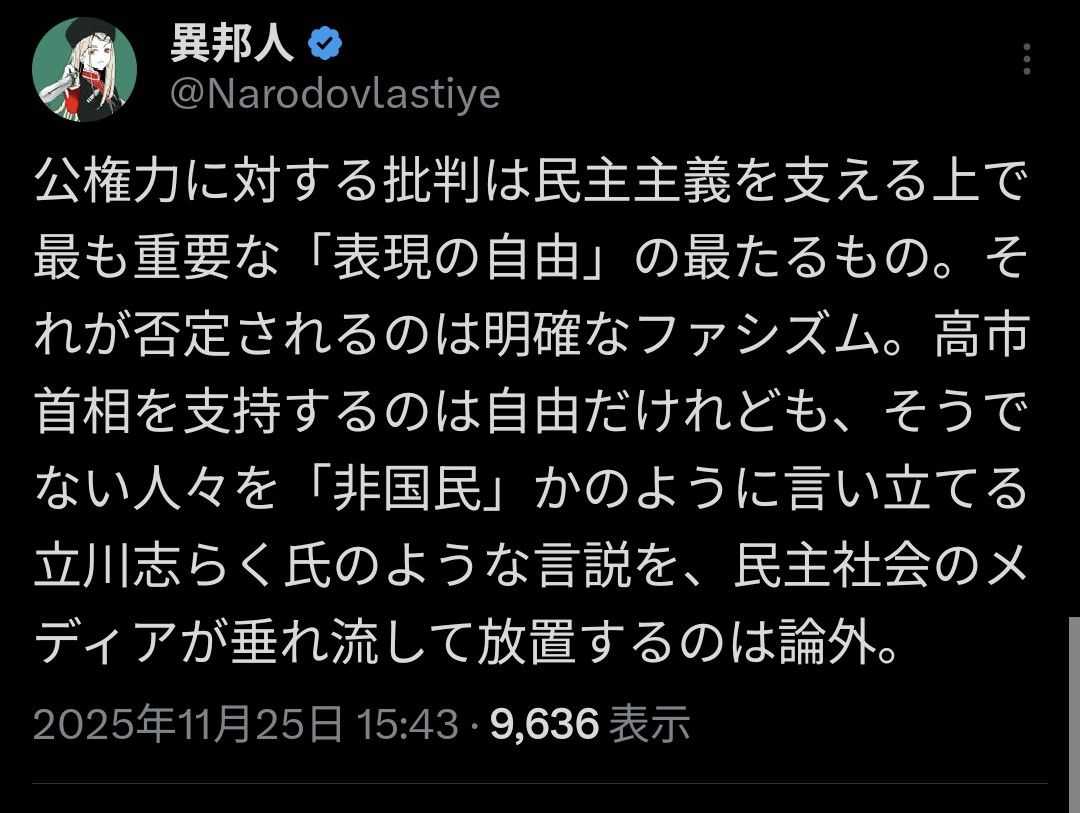2007年01月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
説教要約 196
「罪を赦す権威」 甲斐慎一郎 ルカの福音書、5章21節 「神をけがすことを言うこの人は、いったい何者だ。神のほかに、だれが罪を赦すことができよう」(21節) これは、中風をわずらっている人を床のまま運んで来た人たちの信仰を見たキリストが「友よ。あなたの罪は赦されました」と言われた時、その場に座っていた律法学者とパリサイ人が心の中で言ったことばです。このことばから、人間にとって最大の問題である罪について3つのことを学んでみましょう。 一、人が罪を犯す相手は究極的には神であることについて もし私たちが人々に「人間は、なぜ罪を犯してはならないのか」と聞くならば、恐らく次のような答えが返ってくるでしょう。◇それは、人間として恥ずべきことだから。◇それは、人に迷惑をかけることだから。◇それは、人に悪い影響を及ぼすから。◇それは、家庭や社会の秩序を乱すから。 もしこのようなことが根本的な理由ならば、恥ずべきことと思わず、人に迷惑をかけず、悪い影響も及ぼさず、家庭や社会の秩序を乱さなければ罪ではなく、何をしてもよいことになってしまうでしょう。しかし決してそうではありません。 これらの理由はみな、人間の都合に過ぎません。しかし罪は、人間の都合によってではなく、「律法を定め、さばきを行う」(ヤコブ4章12節)ただひとりの神の前に、どのような姿であるかによって決まるのです。 「神のほかに、だれが罪を赦すことができよう」ということばは、裏を返せば、罪を犯す相手は神のみであることを教えています。あのソロモン王の父であるダビデ王は、「私はあなたに、ただあなたに、罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました」と告白しています(詩篇51篇4節)。 二、人の罪を覚えてさばかれるのは神であることについて 人が制定した法律には、時効というものがあります。これは、あまり長い年月が経過すると、正確な事実関係を調査することが困難になるからであり、もし時効がなければ、事件が解決するまで永久に調査しなければならず、そのようなことは実際には不可能であるために設けられたもので、有限な人間にとっては、やむを得ない措置です。 この時効という考え方があるために、私たちは、「罪などというものは、時間の経過とともに軽くなり、ついには消滅してしまうものである」と思っていないでしょうか。 しかし時間に拘束されない無限の神が定められた律法には、時効などというものはありません。すなわち常に現在しかない永遠の神の前には、過去の罪などというものはなく、どんなに古い罪も、今犯したかのように、はっきりと覚えられているだけでなく、その罪は、私たちが悔い改め、キリストの贖いを信じて赦されない限り、積もり積もって、終わりの日に必ずさばかれるのです。 三、人の罪を赦す権威を持つのは神のみであることについて ひとりの人が、ほかの人を巻き込んで王に反逆し、陰謀を企てたが、それが発覚して捕らえられた場合、この首謀者は、同じ仲間に謝罪し、その人から赦しが得られれば、その反逆罪は赦されるでしょうか。決してそんなことはありません。仲間の人は、巻き添えを食った犠牲者または被害者にすぎず、この首謀者の罪を赦す権威を持つのは王のみです。 このように罪は、王である神への反逆であり、私たちは、その首謀者です。人に対する罪は、私たちの反逆のためにほかの人を巻き添えにした悲劇であるということができます。ですから私たちの罪を赦す権威を持つのは、ただ王である神のみなのです。 そして神は、その計り知れない恵みによって、心から罪を悔い改め、キリストの贖いを信じる者の罪を赦してくださるのです。 東京フリー・メソジスト昭島キリスト教会のホーム・ページの「説教要約 6」より転載(ホーム・ページの説教要約は、コメントを書くことができないので、順次、転載します)。
2007.01.31
コメント(0)
-
説教要約 195
「神との和解」 甲斐慎一郎 コロサイ人への手紙、1章19-23節 私たちは、ひどい目にあったり、大きな迷惑を受けたりして、人を恨んだことがないでしょうか。反対に、人をひどい目にあわせたり、人に大きな迷惑をかけたりして、恨まれたことはないでしょうか。どちらにしても、このような時、私たちにとって必要なことは、その人と和解することです。 この個所には、「和解」という言葉が3回記されていますが(20、22節)、その前後の文は、次のような言葉になっています。 1.神は……御子によって万物を、ご自分と和解させてくださった(20節)。 2.地にあるものも天にあるものも、ただ御子によって和解させてくださった(20節)。 3.神は、御子の肉のからだにおいて、しかもその死によって、あなたがたをご自分と和解させてくださった(22節)。 神は、御子キリストによって万物を、ご自分と和解させてくださいましたが、御子キリストの死によって、私たちをご自分と和解させてくださいました。しかし、どうしてこのようなことが必要なのでしょうか。 一、神と和解した私たち(21、22節) ここには、私たちの「かつての姿」と「今の姿」が対照的に記されています。 1.かつての姿――過去の姿(21節)。 聖書は、私たちの過去の姿について次のような3つのことを教えています。(1)神を離れ――第一段階(2)心において敵となって――第二段階(3)悪い行いの中にあった――第三段階 人間が罪を犯している、すなわち悪い行いの中にあるのは、自分では気がつかないかも知れませんが、心において神の敵となっているからであり、このようになった根本的な原因は、私たちが神を離れたからです。これが聖書の教えであり、この聖書の言葉は、人間の堕落の過程を正しく教えているのです。 2.今の姿――現在の姿(22節)。 このように、神を離れ、心において敵となって、悪い行いの中にあった私たちが、神と和解するためには、本来なら、私たちの方が罪の償いをして、神と和解する道を備えなければならないはずです。しかしこのようなことは、人間には全く不可能なことでした。 そこで神は、キリストを罪のための「なだめの供え物」(ローマ3章25節)としてくださり、「違反行為の責めを人々に負わせないで」(第二コリント5章19節)、和解の道を備え、私たちを「ご自分と和解させてくださ」ったのです(22節)。これは何とすばらしいことでしょうか。 二、神と和解した目的(22節) それでは私たちは、何のために神と和解したのでしょうか。聖書は、「それはあなたがたを、聖く、傷なく、非難されるところのない者として御前に立たせてくださるためでした」と記していますが(22節)、これこそ私たちが神と和解した目的です。 この目的には3つのことが含まれています。(1)聖く(聖い者)――心の状態や性質(2)傷なく(傷のない者)――品性や人格(3)非難されるところのない者――言葉や行動 このようになるのは、これからの姿――将来の姿ですが、同時に、この3つの目的は、私たちの目指すべき目標でもあるのです。 三、神と和解した条件(23節) パウロは、「神の和解を受け入れなさい」と勧めていますが(第二コリント5章20節)、この神の和解を受け入れることこそ信仰であることは言うまでもありません。 そして聖書は、「ただし、あなたがたは、しっかりとした土台の上に堅く立って、すでに聞いた福音の望みからはずれることなく、信仰に踏みとどまらなければなりません」と教えています(23節)。この信仰こそ、私たちが神と和解した条件であるとともに、それを継続していく条件でもあるのです。
2007.01.30
コメント(0)
-
説教要約 194
「忙しさの克服」 甲斐慎一郎 ローマ人への手紙、8章26-30節 「今日のはやりの言葉の一つは、我々が時間の不足を訴えるのに使う、聞きなれた表現であると思う。我々は、それを余りたびたび繰り返すので、繰り返すだけでそうなのだと思い込んでしまう」と述べているのは、英国の名説教者ジョン・H・ジョウェットです。 主は、「ゆっくり食事する時間さえなかった」ほど忙しく奉仕をされましたが(マルコ6章31節)、地上を去る時、「あなたがわたしに行わせるためにお与えになったわざを、わたしは成し遂げて」と報告することがおできになった方でした(ヨハネ17章4節)。 キリスト者のこの地上における使命は、与えられた一生の時間内に、神が私たちになさせようとしておられるわざを成し遂げることです。ですから私たちにとって最も大切なことは、忙しさを克服して私たちの使命を遂行することではないでしょうか。 一、神のご計画に望みを置く まず私たちが忙しさを感じるのは、自分の計画通りに物事が運ばなかったり、自分の計画にはない出来事がはいり込んだりした時ではないでしょうか。しかし私たちの計画は常に最善であるとは限りません。神が私たちのために最善のことを計画してくださるのです。 「神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださる」という言葉は(ローマ8章28節)、物事や出来事に関してだけでなく、時に関しても言えることです。 私たちは、神が命じておられる御心にかなったことのみを行おうとするなら、神はそれをするのに必要な時間をも必ず備えてくださる方ですから、時間の不足を訴える必要はありません。しかし私たちが、神の命じておられない御心以外のことをするなら、時間が足りなくなるのは当然ではないでしょうか。 「もし私たちがもっと祈ったならば、私たちはそんなに忙しく働かなくてもよいであろう」(アンドリュー・A・ボーナー)。なぜなら私たちが祈るなら、神は私たちのために働いてくださいますが、もし私たちが祈らなければ、神のなさることを私たちがしなければならなくなるからです。 二、神と隣人への全き愛を持つ 次に私たちが忙しさを感じるのは、私たちの心が思い煩って分散し、物事に集中することができない時ではないでしょうか。このような時は、焦るだけで能率が悪く、仕事が遅れて時間が足りなくなってしまいます。ですから忙しさを克服する秘訣は、心を集中させて仕事に没頭し、能率を上げることです。 それでは心を集中させるためには、どうすればよいのでしょうか。それは、二心や不純な心がきよめられ、神にのみ心を定めたきよい心を持つことです。これは言い換えれば、神と隣人への全き愛を持つことです。 ヤコブは、ラケルを愛するあまり7年間仕えましたが、「それもほんの数日のように思われた」と聖書は記しています(創世記29章20節)。私たちも神と隣人への全き愛が与えられ、時が経つのも忘れてしまうほど無我夢中になって神に仕えたいものです。 三、永遠の世界を信じて生きる しかし私たちが忙しさを感じるのは、結局のところ、時の流れの中に生きているからです。ですから、もし私たちが時間のない世界に生きることができるなら、忙しさから解放されるはずです。 しかし実際問題として、そのようなことはできるのでしょうか。ここにただ一つだけ可能な道があります。それは私たちが祈りにおいて神と交わり、とこしえからとこしえまで変わらない永遠の神と一つになることです。そうする時、私たちは、モーセのように「主よ。あなたは代々にわたって私たちの住まいです」(詩篇90篇1節)と時間を超越した永遠の神の腕の中に憩うことができるのです。 東京フリー・メソジスト昭島キリスト教会のホーム・ページの「説教要約 20」より転載(ホーム・ページの説教要約は、コメントを書くことができないので、順次、転載します)。
2007.01.29
コメント(0)
-
説教要約 193
「すべての道で主を認めよ」 甲斐慎一郎 箴言、3章1-12節 「あなたの行く所どこにおいても、主を認めよ。そうすれば、主はあなたの道をまっすぐにされる」(6節)。 私たちの人生は、その前途に何が起きるのかだれも知りません。しかしこれまで生きてきた経験から推測すると、これからもあるのではないかと思われることが幾つかあります。それは人間にとって大きな悩みである次のような3つの問題ではないでしょうか。◇これからも、不公平な社会が続くのではないか!◇これからも、苦しみが絶えないのではないか!◇これからも、悪事がなくならないのではないか! 冒頭に記した聖書の言葉は、この3つの問題に対して、どのように考え、どのように対処したらよいかを教えています。「すべての道で主を認めよ」とは、いったいどのようなことなのでしょうか。 一、創造の主権者としての主を認めよ 創世記の1章の「宇宙の創造」の記事において、「神は見て、それをよしとされた」という言葉が5回も記されています(10、12、18、21、25節)。これは、神は、その心によしとされることを行われる主権者であることを教えています(ローマ9章15、16、20、21節)。 神は、多種多様な被造物を、しかもそれぞれがみな違っている千差万別のものを造られました(創世記2章19節、イザヤ書40章26節)。これは、神が主権者として、その心によしとされるところに従ってなされたことです。 さらに神は、あらゆるものに限界や限度、また境界を定められました(ヨブ38章11節、使徒17章26節)。これも、神が主権者として、その心によしとされるところに従ってなされたことです。 「私たちは、与えられた恵みに従って、異なった賜物を持っているので」、「神がおのおのに分け与えてくださった信仰の量りに応じて、慎み深い考え方をし」(ローマ12章6、3節)、神が定められた相違や限界を神の御旨として受け入れ、神のみこころにかなった人になるために「恐れおののいて自分の救いの達成に努め」る(ピリピ2章12節)ことこそ最も大切なことなのです。 二、摂理の支配者としての神を認めよ 使徒パウロは、サタンのことを「この世の神」と呼び(第二コリント4章4節)、ヨハネは、「全世界は悪い者の支配下にある」と述べています(第一ヨハネ5章19節)。 全世界がサタンの支配下にあることは事実ですが、それがすべてではなく、神は、その上にあってサタンさえも支配しておられる方です(ヨブ1章12節、2章6節)。 ヨブ記の1章と2章には、神と神の子ら(天使たち)がサタンと激しく戦う(ここでは白熱化した討議をする)という「天上の出来事(会議)」と、その結果として起きる「地上の出来事」が記されています。この世の神であるサタンも、神の許しがなければ何もできないのです(マタイ10章29節)。 三、究極の審判者としての主を認めよ 神がすべてを支配しておられるにもかかわらず、「悪い行いに対する宣告がすぐ下されないので、人の子らの心は悪を行う思いで満ち」(伝道者8章11節)、悪事が行われているのが、この世です。 そのためアサフのような人は、「悪人が栄え、義人が苦しむのはなぜなのか」と言って悩み、神の前に心をきよめて、正しく歩むことがむなしく思えてくるのです(詩篇73篇13~15節)。しかし彼が聖所に行って、究極的な神の審判を知った時、問題はすべて解決しました(同73篇17-19節)。 私たちが、「不公平」と「苦しみ」と「悪事」という3つの問題に直面した時、主なる神を「創造の主権者」、「摂理の支配者」、「究極の審判者」として認める時、主は私たちの道をまっすぐにしてくださいます。すなわち障害物が取り除かれて、つまずくことも迷うこともなく、平らな道を神の国に向かって歩むことができるのです。
2007.01.28
コメント(0)
-
説教要約 192
「万物の創始者であり完成者である神」 甲斐慎一郎 ピリピ人への手紙、1章6節 「あなたがたのうちに良い働きを始められた方は、キリスト・イエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は堅く信じているのです」(ピリピ1章6節)。 この御言葉から3つのことを学んでみましょう。 一、万物の創始者である神 聖書は「初めに、神が天と地を創造した」(創世記1章1節)と記し、神は「万物の創造者」であると教えていますが、これは、神は「万物の創始者」でもあることを啓示しています。しかも「それは非常によかった」とあるように(同1章31節)、神は非常に「良い働きを始められた方」です(ピリピ1章6節)。 私たちも、この世に誕生したという初めがあるからこそ、それ以後の人生があるのであり、初めがなければ、それこそ何も始まりません。私たちは、誕生という初めだけでなく、学校生活には入学、会社生活には入社、結婚生活には入籍、信仰生活には入信という初めがあります。しかし私たちにとって最も大切なことは、それが神によって始められた良い働きであるかどうかということです。 「もし、その計画や行動が人から出たものならば、自滅してしまうでしょう。しかし、もし神から出たものならば」、だれもそれを「滅ぼすことはできない」のです(使徒5章38、39節)。 二、万物の統治者である神 宇宙や地球には、秩序正しい自然界の法則が定められています。「ヒストリー・イズ・ヒズストーリー(歴史は神の物語)」という言葉のように、世界の歴史を学ぶなら、神は、すべての国の人々に「それぞれ決められた時代と、その住まいの境界とをお定めにな」ったことがわかります(使徒17章26節)。人の心には、善悪の規準に基づいた良心の平安や呵責というものがあり、「人は種を蒔けば、その刈り取りもすることになります」(ガラテヤ6章7節)。 しかしこの世は、「悪人が栄え、義人が苦しむ」という「善悪の法則」だけでは説明できない不可解なことに満ちています。これに関しては「あなたがたは、私に悪を計りましたが、神はそれを、良いことのための計らいとなさいました」(創世記50章20節)という人間の目には災いと悪にしか映らないことをも用いて最終的には私たちを善に導く「神の摂理の法則」というものがあります。 神は、万物の創始者であるだけでなく、宇宙や地球、世界の歴史や人間の社会を自然界の法則や善悪の法則、また神の摂理の法則によって支配しておられる万物の統治者です。 三、万物の完成者である神 初めに神が天と地を創造されたという聖書の教えと宇宙は大爆発によって誕生したというビッグ・バン説とに共通していることは、この宇宙には明らかに初めがあるということです。しかしビッグ・バン説は、完成することについては何も教えていませんが、聖書は、神がその天と地を「完成された」と記しています(創世記2章1節)。 私たちも、この世に生を受けたという初めがあるからこそ、それ以後の人生があるのですが、完成しなければ何にもなりません。神は、「良い働きを始められた方」であるだけでなく、「それを完成させてくださる」方です(ピリピ1章6節)。神は、「わたしは、終わりの事を初めから告げ……わたしの望む事をすべて成し遂げる」(イザヤ46章10節)と仰せられる万物の完成者です。 しかし現実の世界には、神の摂理では、どうしても理解することができない矛盾や不可解な出来事が数多くあります。このようなことに関して神は、すべてのことを世の終わりに公平にさばかれ、明らかにされます(第一コリント4章5節)。これが最後の審判です。 神の目から見るなら、完成したことも、人の目には完成したとは見えないことに関しては、神は、最後の審判によって物事を完結してくださる万物の完成者なのです。 東京フリー・メソジスト昭島キリスト教会のホーム・ページの「説教要約 11」より転載(ホーム・ページの説教要約は、コメントを書くことができないので、順次、転載します)。
2007.01.27
コメント(0)
-
説教要約 191
「聖書の成立について(2)」 甲斐慎一郎 テモテへの手紙、第二、3章14~17節 二、収集について 預言者や使徒たちが生存し、霊感が働いている間は、どの書が霊感されていて、どの書が霊感されていないかを知ることは容易なことでした。しかしこれらの人々が死に、霊感が停止した時、霊感を受けた記録を一書にまとめ、それを保存することが当然のことながら、必要となってきました。 この収集には、人間の側と神の側の二つの面があります。すなわち人々の厳しいテストと神の導きです。 聖書は、66巻の正典から成り立っていますが、他に経外典や偽作書というものがあります。聖書の正典とこれらのものを見分けるためには、次のようなテストが行われていたのです。1.神が著者であるか?2.聖書記者の資格があるか?3.記録が純粋であるか?4.記録が真実であるか?5.ユダヤ教会、キリスト教会、教会会議、聖書の古代訳本などの 証拠があるか? このようにしてすべての書は、厳しくテストされ、正典は教会とその指導者の確信を通して徐々に形成されるに至ったのです。しかしそれは、いかなる教会会議によって宣言されたものでもなく、多くの書の中から選び出されたものでもありません。いかなる教会会議も正典の形成に携わったことはないのです。これらの会議は、人人の見解と収集の存在を承認し、すでに認められていたリストを反復したにすぎません。聖書を霊感によって記者たちに書かせた同じ聖霊は、正典の形成においても教会を一歩一歩導かれたのです。 三、保存について 聖書が記されるために用いられた言語は、旧約聖書においては、エズラ記、エレミヤ書、ダニエル書の一部にアラム語が入っているほかは、すべてヘブル語であり、新約聖書はギリシャ語です。 当時は印刷技術がありませんでしたので、聖書は手で写し、写本として残っています。現在、旧約聖書においてヘブル語で書かれた写本の数は、約1700、ギリシャ語の70人訳は350に及んでいます。また新約聖書においては、4000以上のギリシャ語の写本があり、その他に8000のラテン語ブルガダ訳の写本があります。これらの写本を他の歴史的文書と比べるなら、その数は圧倒的に多く、その純粋性は驚くほど正確です。 ユダヤ人の民事的および宗教的な律法とその注釈を記した「タルムード」には、旧約聖書の写本を作成するための規則が、次のように述べられています。 1.各欄は、48行以上、60行以内でなければならない。 2.インクは、黒でなければならない。 3.いかなる文字も記憶から記されてはならず、一語一語声をあげて読まなければならない。 4.神ということばを書く前に敬虔にペンをぬぐい、エホバということばを記す前に全身を洗わなければならない。 5.文字の形、文字の間隔、ペンの使用法に関しても厳密な規則が適用された。 6.一つの巻物の吟味は、筆写が終わってから30日以内にされなければならない。 7.各文字と各語は数えられ、もし一字でも落ちていたり、余分にあった時には、その写本は無効とされ、破壊された。 新約聖書の写本家たちは、旧約聖書の写本家たちと比べて、これほど厳密な規則はありませんでしたが、彼らは、注意深く、また忠実に、その務めを果たしたのです(インマヌエル聖宣神学院発行、「聖書序論」52、53、58、85、87、93、112頁より抜粋)。 このようにして神は、霊感によって聖書を記者たちに書かせ、聖霊の導きによって収集させ、多くの人たちの血のにじむような努力によって聖書を保存させたのです。 私たちは、このような神に心から感謝をささげるとともに、そのみことばに生きる者とさせて頂こうではありませんか。
2007.01.26
コメント(2)
-
説教要約 190
「聖書の成立について(1)」 甲斐慎一郎 テモテへの手紙、第二、3章14~17節 「聖書(バイブル)」ということばは、ギリシャ語の「本(ビブロス)」という語から派生したものです。聖書は、霊感を受けた永遠の神のことばであり、神が人類に与えてくださった「本の中の本」です。 パウロは、テモテに「聖書はあなたに知恵を与えてキリスト・イエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書はすべて、神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練とのために有益です。それは、神の人が、すべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられた者となるためです」と述べています(15~17節)。 聖書は、旧約聖書と新約聖書との二つに大きく分かれています。旧約と新約の「約」は、「契約」または「約束」という意味です。イスラエル人に与えられた救いの準備としての約束が旧約であり、イエス・キリストによって成就された救いの約束が新約です。 旧約聖書は、5巻の律法、12巻の歴史書、5巻の詩歌、5巻の大預言書、12巻の小預言書の合計39巻から成り立っています。新約聖書は、4巻の福音書、1巻の歴史書、21巻の手紙、1巻の預言書の合計27巻から成り立っています。 聖書が神のことばであるからと言って、現在、私たちが手にしているような完成された聖書が、天から降ってきたわけではありません。聖書は、66巻の書から成り立っている歴史書でもあります。ですから聖書が現在のように出来上がるためには、他の書物と同じような道筋と過程があったことは、言うまでもありません。旧新約聖書が現在あるように完成するまでには、少なくとも次のような3つのことが必要でした。1.第一は、著作です。2.第二は、収集です。3.第三は、保存です。 聖書は、正しく著作され、正しく収集され、正しく保存されたからこそ、現在のように存在するのです。 一、著作について 聖書は、66冊の書から成り立ち、少なくとも約40人の聖書記者たちによって記されています。それらの記者たちは、実に様々な人たちです。ある人たちはダビデやソロモンのように王であり、ある人たちはダニエルのように政治家、ある人たちはパウロのように法律家、ある人たちはエズラのように学者、ある人たちはルカのように医者、ある人たちはマタイのように取税人、ある人たちはアモスのように羊飼い、ある人たちはペテロやヨハネのように漁師でした。 そして彼らは、年代としても、互いに相当な隔たりがありました。律法を記したモーセは紀元前約1400年の人で、詩篇を記したダビデは紀元前約1000年の人で、ダニエル書を記したダニエルは紀元前約550年の人で、黙示録を記したヨハネは紀元後約100年の人でした。 彼らは、最初に記した人から最後に記した人まで、約1500年近くも隔たっています。また彼らが聖書を記した場所も、相当の隔たりがあったことは言うまでもありません。 ところが、彼らがそれぞれの時代に記した書物を一つに集めてみると、驚くほど調和し、統一されています。それは聖書の真の著者が神ご自身だからです。これらの聖書記者たちは、神より受けた啓示のほかに、資料を参照したり、歴史に関する自分の知識を用いたり、自分の経験を記録したりしています。 しかし神は、聖書の記者たちが聖書を書くにあたって、間違いなく神の啓示を記し、それが神の意志の表現となるように聖霊によって働かれました。これが「霊感」です。まず神は、霊感によって、一つ一つの聖書の著作を整えられたのです。 次回は、収集と保存について述べます。
2007.01.25
コメント(2)
-
説教要約 189
「三つの創造」 甲斐慎一郎 コリント人への手紙、第二、5章17節 「だれでもキリストのうちにあるなら、その人は新しく造られた者です」(第二コリント5章17節) 聖書は、開巻第一ページにおいて神は万物の創造者であると記しています。この万物の創造者である神のわざについて、次のような「三つの創造」を教えています。 1.今の天と地の創造――「初めに、神が天と地を創造した」(創世記1章1節)。 2.人間の新しい創造――「だれでもキリストのうちにあるなら、その人は新しく造られた者です」(第二コリント5章17節)。 3.新しい天と新しい地の創造――「私は、新しい天と新しい地とを見た」(黙示録21章1節、第二ペテロ3章13節)。 第一は過去、第二は現在、第三は将来における神の創造のわざです。もし私たちが、第一の創造のわざを信じるならば、第二と第三の創造のわざをも信じることができます。しかしそれを信じなければ、あとの二つも信じることができないでしょう。 一、私たちが新しく造られるという「人間の新しい創造」こそ最も大切なことです 人間が直面している最大の問題は何でしょうか。無知や無力でしょうか。短所や弱さでしょうか。病気や怪我でしょうか。苦しみや悩みでしょうか。老いや死でしょうか。確かにこれらのことも問題ですが、人間の最大の問題は罪であると、聖書は教えています。 それではこの罪を解決するためには、どうすればよいでしょうか。学びや勉強をして高い教育を受けることでしょうか。運動や体操をしてからだと心を鍛えることでしょうか。倫理や道徳を守ることでしょうか。努力して苦行や修行に励むことでしょうか。しかしこのようなことでは決して罪を解決することができないことを聖書は教えています。 聖書は、「だれでもキリストのうちにあるなら、その人は新しく造られた者です」と記し(第二コリント5章17節)、キリストによる「人間の新しい創造」こそ罪を解決する唯一の秘訣であることを教えています。 二、そのためには「今の天と地の創造」者である神の救いを信じることが必要です 聖書は、生まれながらの人間は「罪過と罪との中に死んで……肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行」う罪深い者であると記しています(エペソ2章1、3節)。このような罪人が新しく造られるということなどあり得るでしょうか。そのような人に造り変えられるということなど信じられるでしょうか。 進化論者は、無から有を生じる自然発生という偶然から始まり、無生物から生物へ、そして猿から人間へ進化したことを信じる者です。もし私たちが進化論者のように「この世界とその中にあるすべてのものをお造りになった」(使徒17章24節)全知全能の創造者である神を信じなかったならば、罪深い人間が新しく創造されるということなど決して信じることができないでしょう。 罪深い人間が新しく造り変えられるという「人間の新しい創造」は、ただ「今の天と地の創造」者である神のみがおできになることで、この方以外に不可能なのです。 三、すると「新しい天と地の創造」者である神とともに永遠に生きることができます 現在の地球は、公害や環境破壊によって汚染され、それがもたらす異常気象や天変地異によって狂いが生じ、もし核戦争が起きるなら破滅してしまうでしょう。罪深い人間が新しく創造されなければ、だれも地球の破滅を食い止めることはできないでしょう。 聖書は、「その日が来れば、そのために、天は燃えてくずれ、天の万象は焼け溶けてしまいます。しかし、私たちは、神の約束に従って、正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます」と記し(第二ペテロ3章12、13節)、新しく創造された人間は、今の天と地が破滅しても、新しい天と新しい地に永遠に住むことができると教えています。 私たちが神とともに永遠に住むことができる「新しい天と地の創造」を信じることができるのは、神が「今の天と地の創造」者であることを信じているからなのです。 東京フリー・メソジスト昭島キリスト教会のホーム・ページの「説教要約 5」より転載(ホーム・ページの説教要約は、コメントを書くことができないので、順次、転載します)。
2007.01.24
コメント(2)
-
説教要約 188
「三種類の友」 甲斐慎一郎 ヨハネの福音書、15章13~16節 箴言の著者は、「滅びに至らせる友人たちもあれば、兄弟よりも親密な者もいる」と述べています(18章24節)。 人間というものは、その友によって良くも悪くもなります。友というのは、それほど私たちの生涯に計り知れない影響を及ぼすものです。そこで聖書が教えている友について学んでみましょう。 一、罪人の友について イエス・キリストは、この時代をたとえて次のように嘆かれました。「人の子(キリスト)来たりて飲み食いすれば、『見よ、食を貪り、酒を好む人、また取税人・罪人の友なり』と言うなり」(マタイ11章19節、文語訳)。 世の中の科学や文明がどんなに発達しても、自殺する人は絶えませんが、その理由は、次のようなものではないでしょうか。1.孤独で寂しい。2.自分を本当に愛してくれる人がいない。3.真に悩みを打ち明ける人がいない。4.心から信頼できる人がいない。5.問題を解決してくれる人がいない。 しかしこれは、自殺しないまでも、すべての人が抱えている問題ではないでしょうか。この人間共通の問題をよくみると「真の友」がいるなら、解決することが分かります。 キリストは、人々から忘れられたり、軽蔑されたり、白い目で見られたりしている取税人や罪人に伝道されましたが、そのために当時の人々から「罪人の友」と言われました。 それは、キリストに対する悪口であり、非難の言葉でした。しかし罪人にとっては何と幸いな言葉でしょうか。キリストは、ご自分のいのちを捨てるほど私たちを愛し、また私たちの悩みを知って、それを解決するとともに、私たちの最も信頼できる「罪人の友」となるために、この世に来られたからです。 二、信仰の友について パウロは、ピレモンに次のような手紙を書いています。「もしあなたが私を親しい友と思うなら、私を迎えるように彼を迎えてやってください」(ピレモン17節)。 オネシモは、主人ピレモンの金を盗んで逃げた奴隷です。ですからピレモンにとってオネシモを迎え入れることは容易なことではなかったでしょう。しかしオネシモもピレモンもパウロを通してキリストの救いにあずかって救われ、キリスト者になり、同じ「信仰の友」となりました。ここにどんな人間をも結びつける強いきずなができたのです。 キリストが「罪人の友」となられたのは、互いに憎み合い、いがみ合っている人間同志が主にあって一つとされる「信仰の友」(テトス3章15節)となるためです。主にあって互いに「信仰の友」となることこそ、一致を妨げる人間のエゴや人の相違、また互いに利害の相反することをも乗り越えて、人間を一つにするのです。 三、神の友について ヤコブは、アブラハムについて「彼は神の友と呼ばれた」と記しています(ヤコブ2章23節)。主は「わたしはあなたがたを友と呼びました」と言われました(ヨハネ15章15節)。キリストが「罪人の友」となられたのは、人間同志が「信仰の友」となるだけでなく、キリスト者が「神の友」となるためです。 1.「神の友」とは、神に愛され、神に選ばれている人です(ヨハネ15章13、16節)。 2.「神と友」とは、アブラハムのように、神のみこころを披瀝され(創世記18章17節)、父の啓示を知らされるほど神に信頼されている人です(ヨハネ15章15節)。 3.「神の友」とは、神のみこころを行って、豊かな実を結ぶように神に期待されている人です(同15章14、16節)。 四、キリスト者が罪人の友となることについて このように私たちが「神の友」となるのは、人々を救いに導くために、今度は私たちがキリストのように「罪人の友」となるためです。ただここで大切なことは、私たちが「罪人の友」となる前に、「神の友」となっていなければ、いわゆる「ミイラとりがミイラ」になってしまうということです。 パウロは、自分のことを「罪人のかしら」(第一テモテ1章15節)であると告白しています。そして彼は、「神の友」となり、より多くの人を獲得するために「ユダヤ人にはユダヤ人のようになり」、「律法の下にある人々には……律法の下にある者のようになり」、「律法を持たない人々に対しては……律法を持たない者のようになりました」と述べています(第一コリント9章19~21節)。これこそ「罪人の友」となるということです。 もう一つ例をあげるなら、「良いサマリヤ人」(ルカ10章30~37節)のたとえのサマリヤ人です。彼は、強盗に襲われた人を介抱しましたが、これこそ「罪人の友」となったということです。「罪人の友」となるとは、言い換えれば「あなたの隣人をあなた自身のように愛する」(マタイ22章39節)ことにほかなりませんが、これは、信仰と聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれなければ不可能であり、信仰の最高峰であるということができます。
2007.01.23
コメント(4)
-
説教要約 187
「真の愛について」 甲斐慎一郎 ヨハネの手紙、第一、4章7-21節 聖書は「神は愛です」(16節)と教え、また多くの人々も「キリスト教は、愛の宗教である」と思っています。このこと自体は少しも間違ってはいません。しかしその内容となると、この愛ほど正しく受け取られずに誤解されているものはないでしょう。そこで真の愛について学んでみましょう。 一、新約聖書の原語であるギリシャ語には、愛と訳される言葉が四つあります 1.エロース(恋愛、夫婦愛)――これは初恋から始まり、本格的な恋愛を経て結婚し、夫婦愛となるもので、肉体的には性愛です。 2.ストルゲー(情愛、肉親愛)――これは親子、兄弟姉妹などの血縁の極めて近い者に対する愛です。 3.フィリア(友愛、朋友愛)――これは自分の好みに合い、自分と共通な場を持つ者に対する愛です。 4.アガペー(聖愛、神的愛)――これは人間が神の像に似せて造られた不滅の霊を持つ尊いものであるゆえに愛する愛です。 二、真の愛は、自分にではなく、相手に価値があると判断して愛するものです このエロース(恋愛、夫婦愛)とストルゲー(情愛、肉親愛)とフィリア(友愛、朋友愛)という三つの人間的な愛は、その相手が「自分にとって価値がある」と判断して愛するものです。これは対人関係においては、互いの価値を認め合い、良いものを分かち合うことによって成り立っています。 これに対してアガペー(聖愛、神的愛)は、主がイスラエルの民に「わたしの目には、あなたは高価で尊い。わたしはあなたを愛している」(イザヤ43章4節)と仰せられたように、また「キリストが代わりに死んでくださったほど」(ローマ14章15節)、「相手に価値がある」と判断して愛するものです。 三、真の愛は、三つの人間的な愛を拡大したものではありません 1.エロース(夫婦愛)の対象は、夫または妻という一人の異性であり、この愛を他の人に広げるならば、姦淫の罪を犯すのです(マタイ5章27、28節、箴言5章15~20節)。 2.ストルゲー(肉親愛)の対象は、肉親だけであり、この愛をすべての人に広げることは不可能です。もし私たちが、すべての人を肉親愛で愛するならば、その苦しみのために正常な精神を持つことはできないでしょう。 3.フィリア(朋友愛)の対象は、友人だけであり、この愛を自分の好みに合わず、自分と何の共通点もない他のすべての人に広げることは不可能です。 なぜなら3つの人間的な愛と真の愛(アガペー)とは根本的に異なるからです。真の愛(アガペー)は、すべての人を愛して、人を差別しない愛です。しかし3つの人間的な愛は、ある特定の人しか愛せない(または愛してはならない)愛であり、それは結果的には人を差別する愛なのです。 日本の諺に、「可愛さ余って憎さが百倍」、「愛多ければ憎しみもまた多し」、「愛憎は表裏一体をなす」、「愛憎は紙一重」、「愛は憎悪の始め」とあるように、この3つの人間的な愛は、聖霊による真の愛(アガペー)を持たない限り、自分の思い通りにならないと、愛していながら同時に憎んでいるという心の状態になるのです。 四、真の愛は、本能的また自然的なものではなく、超自然的な神からの賜物です このエロース(恋愛、夫婦愛)とストルゲー(情愛、肉親愛)とフィリア(友愛、朋友愛)という3つの人間的な愛は、教えられなくても生まれつき備わっている本能的なものであり、どのような人の心の中にも自然に芽生えてくるものです。ですから様々な限界があるとともに、真理に基づくものではなく、善悪をわきまえないために、暴走したり、脱線したりする危険性があるのです。 これに対して真の愛(アガペー)は、生まれながらの人間にはなく、聖霊による超自然的な賜物であり、信仰と祈りによって与えられるものなのです。 東京フリー・メソジスト昭島キリスト教会のホーム・ページの「説教要約 15」より転載(ホーム・ページの説教要約は、コメントを書くことができないので、順次、転載します)。 この「真の愛について」を4回にわけて詳細に記したのが、説教要約の「104」から「107」の「真の愛」です。
2007.01.22
コメント(2)
-
説教要約 186
「キリストの汗と涙と血」 甲斐慎一郎 ルカの福音書、22章39~46節 聖書は、イエス・キリストが真の人として、この地上におられた間、私たちのために流されたものを3つ記しています。それは「汗」と「涙」と「血」です。永遠の神の御子キリストは、人としてこの世に生を受けられただけでなく、私たちのためにその尊い「汗」と「涙」と「血」を流されたとは、何と驚くべきことでしょうか。 一、尊い汗を流されたキリスト 汗には次のようなものがあります。 1.汗水――これは一生懸命に働く時、水のように流れる汗のことです。 2.冷や汗――これは非常に恥じたり、恐れたりした時に出る冷たい汗のことです。 3.脂汗――これは悶え、苦しむ時に出る脂の混じった汗のことです。 キリストは、30歳までは大工として「汗水」たらして働かれただけでなく、その後の公生涯においても、スカルの井戸においてサマリヤの女に水を求められたほど、「汗水」を流して巡回伝道と奉仕をされました。また十字架につけられることは、最も恥ずかしく、恐ろしいことですから、「冷や汗」をかかれたのではないでしょうか。そしてゲッセマネの園や十字架上の後半の三時間においては、悶え苦しんで「脂汗」を流されたのです。 二、尊い涙を流されたキリスト 涙には次のようなものがあります。 1.悲しみの涙――これには悔し涙や悔い改めの涙、また罪を憂える涙や切なる涙があります。 2.喜びの涙――これには感激して涙を流す感涙や嬉し涙、またありがた涙があります。 3.愛の涙――これは喜ぶ者とともに喜び、泣く者とともに泣く共感の涙のことです。 「キリストは、人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって、大きな叫び声と涙とをもって祈りと願いをささげ」られ(ヘブル5章7節)、またラザロが葬られた墓において「イエスは涙を流された」(ヨハネ11章35節)と聖書は記しています。キリストは、私たちの罪を憂えて「悲しみの涙」を流されるとともに「愛の涙」を流され、また私たちのために「切なる涙」を流して祈られた方なのです。 三、尊い血を流されたキリスト しかしキリストが私たちのために、どんなに汗水を流して働かれ、脂汗を流して苦しまれたとしても、また私たちのために、どんなに罪を憂えて涙を流されたとしても、もし血を流して私たちのために、「贖いの代価として、自分のいのちを与え」てくださらなければ(マルコ10章45節)、私たちは罪から救われることはできません。なぜなら「血を流すことなしには、罪のゆるしはあり得ない」からです(ヘブル9章22節、聖書協会訳)。 四、キリストの愛に応える道 私たちのために尊い汗と涙と血を流してくださったキリストに対して、私たちは、どうすればよいのでしょうか。聖書は、「神に対る悔い改めと、私たちの主イエスに対する信仰」を教えています(使徒20章21節)。 私たちは、これほどまでに私たちを愛してくださったキリストの愛を知らずに生きて来た罪を心から悔い改め、そのキリストの尊い血は私たちのために流されたものであることを信じることです。そうするなら、私たちは、今まで犯して来たすべての罪が赦されて、新しく生まれ変わり、神の子どもとされます。 その結果、私たちは、キリストのために汗水を流して奉仕をし、恥を受けて冷や汗をかき、十字架を負って脂汗を流すだけでなく、人々のために悲しみの涙と愛の涙を流すことができるようになるのです。 東京フリー・メソジスト昭島キリスト教会のホーム・ページの「説教要約 12」より転載(ホーム・ページの説教要約は、コメントを書くことができないので、順次、転載します)。
2007.01.21
コメント(2)
-
説教要約 185
「最も大いなる愛」 甲斐慎一郎 ヨハネの手紙、第一、3章16節 「キリストは、私たちのために、ご自分のいのちをお捨てになりました。それによって私たちに愛がわかったのです。ですから私たちは、兄弟のために、いのちを捨てるべきです」(16節)。 一、最も大いなる死――キリストは、私たちのために、ご自分のいのちをお捨てになりました この聖書の言葉の主題は、いのちを捨てること、すなわち死です。人間にとって最大の問題や課題は死です。私たちは、あらゆる分野や世界において、死が人間にとって最大の問題や課題であることを知っています。 政治の世界、それは国際、国内を問わず、最大の問題は、多くの人たちのいのちを奪う戦争でしょう。経済の世界においても、飢え死には最大の課題であり、社会の問題は、天災、人災を問わず、やはり死が最大の問題です。医学の世界は、死との戦いであり、倫理や道徳の世界において最大の問題は殺人です。 しかしここに不思議な死があります。それはキリストの死です。このキリストの死は何百年も前から預言され、人に殺されたのではなく自ら進んで死なれたのであり(ヨハネ10章18節)、かと言って自殺ではなく、人類を罪から救うための身代わりの死でした。これは何と驚くべき偉大な死でしょうか。 このように死そのものは、人間にとって最大の問題や課題ですが、キリストの死は人類を罪から救うための最も偉大な死なのです。 二、最も大いなる愛――それによって私たちに愛がわかったのです この聖書の言葉の主題は、愛です。人間にとって最もすばらしいものは、愛ではないでしょうか。私たちは、あらゆる分野や世界において、愛こそ最もすばらしく、あらゆる問題や課題の解決の鍵であることを知っています。 政治の問題、経済の問題、社会の問題のどれ一つをとってみても、その根底に愛があるなら、たとえ完全には解決することができなくても、問題を最小限にとどめることができることを知っています。 しかしここに最もすばらしい愛があります。それは、キリストの十字架によって現された愛です。実に神は私たちのために、そのひとり子キリストをお与えになることによって、その愛を最大限に現されたのです。 このように愛そのものは人間にとって最もすばらしいものですが、その愛の中で神の愛は最も偉大ですばらしいものです。 三、最も大いなる変化――ですから私たちは、兄弟のために、いのちを捨てるべきです この聖書の言葉の主題は、人間が変わること、すなわち変化です。人間にとって最も必要なことは、良い人間に変わることではないでしょうか。人間は、自分が変わらない限り、決して問題は解決しないからです。 しかし人間ほど悪い方には変わっても、良い方には変わらないものはないでしょう。人間は、どんなに良い話を聞いても、またどんなに良いことに一生懸命に励んでも、その心は相変わらず自己中心で罪深く、少しもよくなりません。 しかしここに最も大いなる変化があります。それは、最も偉大な死であるキリストの死によって現された最も大いなる神の愛に触れることによる人間の変化です。 人間は、死に直面した時ほど厳粛で真剣な心になることはありません。まして私たちの罪のために死なれたキリストの最も偉大な死に直面した時、人間は最も厳粛で真剣な心にならないでしょうか。また人間は愛に触れた時ほど心が動かされることはありません。まして私たちの罪のために、そのひとり子キリストをお与えになったほどの最も大いなる愛に触れた時、人間は最も心が動かされて変わらないでしょうか。 私たちは、信仰により「聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれ」る時にのみ(ローマ5章5節)、この神の愛に応えて「栄光から栄光へと、主と同じかたちに姿を変えられて行」くのです(第二コリント3章18節)。
2007.01.20
コメント(2)
-
説教要約 184
「永遠に存在する人間」 甲斐慎一郎 マタイの福音書、10章28節 現代は、いのちを重さを知らず、いのちを軽視する風潮があるように見えますが、一昔前の戦争をしていた時代も同じではないかと思われます。それで人のいのちはどのようなものかについて考えてみましょう。 一、人のいのちの重さについて パウロは、「聖霊は、神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるため」と述べています(使徒20章28節)。この箇所にはキリストのことは記されていませんが、実際に血を流されたのはキリストです。父と子と聖霊なる神は、ご自身のいのちを捨てるほど私たちを愛し、私たちの救いのために贖いのわざを成し遂げてくださいました。言い換えれば、このみことばは、私たちのいのちは、三位一体の神がいのちをかけるほど重く、尊いということを教えているのです。 二、人間の不滅性について なぜ人のいのちは、それほど重くて尊いのでしょうか。それは神によって造られた計り知れないほど価値のあるもので、決して消滅することなく、永遠に存在するからです。 人間がほかの動物とは異なる根本的な特徴を述べるなら、次のような3つです。1.自由意志――人間は選択と決断をする自由を持っています。2.自己批判――人間は自分で自分を批判することができます。3.継続性――人間は永遠に存在し、消滅することはありません。 自由意志を持ち、自己批判ができる人間は、責任をとるべき自己というものが消滅することはありません。墓は、人が来世に行くために通過するトンネルのようなものです。私たちの来世の運命は、私たちがキリストの贖いのわざを信じるかどうかによって決まります。「御子を信じる者は永遠のいのちを持つが、御子に聞き従わない者は……神の怒りがその上にとどまる」のです(ヨハネ3章36節)。 「霊魂不滅の事実に関して、正常な人間が本能的に所有している根本的自覚につけ加えて、いくつかの、それを支持する論拠がある。心理学的論拠は、霊魂の、非物質的存在であり、分割不能、したがって不滅であるという性質に基づいている。目的論的論議は、人間の霊魂というものは、この世においてはその可能性のすべてを成就していないし、できない、したがって、そのさいわいが十分に開花するにいたるために来世と存在の継続とが必要である、と主張している。最後に、道徳的論議はその個人的、社会的面から述べて、人間はこの世においては、常に正義の取扱いを受けているとは限らない。ゆえに、単にその存在が消滅するということでは、その異なった程度の罪科に対して相応な程度の刑罰を受くるを可能にしない、と主張している」(H・オートンワイレー、P・T・カルバートソン共著「キリスト教神学概論」513、514頁、日本ウェスレー出版協会、1977年)。 三、人間の不滅性を教えている聖書のことば 神のことばである聖書は、来世が存在し、人は永遠に消滅しないことを教えています。 ヨブは、「私は裸で母の胎から出て来た。また、裸で私はかしこに帰ろう」と述べ(ヨブ1章21節)、「私は知っている。私を贖う方は生きておられ、後の日に、ちりの上に立たれることを。私の皮が、このようにはぎとられて後、私は私の肉から神を見る」と告白しています(同19九章25、26節)。 イエスは、「からだを殺しても、たましいを殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより、たましいもからだも、ともにゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい」と言われました(マタイ10章28節)。 ヨハネは、「死んだ人々が、大きい者も、小さい者も御座の前に立っているのを見た。そして、数々の書物が開かれた。また別の一つの書物が開かれたが、それは、いのちの書であった。死んだ人々は、これらの書物に書きしるされているところに従って、自分の行いに応じてさばかれた」と神からの啓示を記しているのです(黙示録20章12節)。 東京フリー・メソジスト昭島キリスト教会のホーム・ページの「説教要約 19」より転載、但し、人間の不滅性については、参考文献を記しました(ホーム・ページの説教要約は、コメントを書くことができないので、順次、転載します)。
2007.01.19
コメント(0)
-
説教要約 183
「真のキリスト教について」 甲斐慎一郎 マタイの福音書6章31~34節 「神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのものはすべて与えられます」(33節)。 一、真のキリスト教は、キリストの十字架と復活による救いを人生の土台とする――新生を求め、信じて、体験する キリストは、宣教を開始された時、最初に「時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい」と宣べ伝え(マルコ1章15節)、ニコデモに「人は、新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません」と言われました(ヨハネ3章3節)。 人が新しく生まれるためには、次のような3つのことが必要です。 1.第一は認罪、すなわち人に対して、自分に対して、そして神に対して罪を犯していたことを認めることです。 2.第二は悔い改め、すなわち神に背を向けていた罪を悔い、神に立ち返ることです。 3.第三は信仰、すなわちキリストが私たちの罪のために死なれたことを信じることです。 このようにする時、私たちは、罪が赦され、義と認められ、新しく生まれ変わり、神の子どもとされるのです。 二、真のキリスト教は、「神のご性質にあずかる者」となり、「御霊の実」を結ぶ者となるという品性や人格や人徳を建て上げる――聖化を求め、信じて、体験する パウロは、「神の国は、飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからです」と述べています(ローマ14章17節)。 メソジストの創始者のジョン・ウェスレーは、「神の国」とは、「あなたがたの関心事は、神がご自分をあなたがたの魂の中に現して下さり、そして、そこに住まわれて支配してくださること」であり、「神の義」とは、「神が心の中で統治して下さっていることの結ぶ実である。……それは、イエス・キリストを信じる信仰から流れ出てくる、神への愛と全人類への愛である」と述べています。 私たちは、心の中に罪があることを認め、神に全く明け渡して光の中を歩み、イエスの血はすべての罪から私たちをきよめることができると信じるなら、聖霊によって罪がきよめられ、神の愛が心に注がれるのです。 三、真のキリスト教は、「キリスト・イエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得る」という「人生の目標」に向かう――栄化を求め、信じて、歩む パウロは、「私たちの国籍は天(神の国)にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを、私たちは待ち望んでいます。キリストは、万物をご自身に従わせることのできる御力によって、私たちの卑しいからだを、ご自身の栄光のからだと同じ姿に変えてくださるのです」と述べています(ピリピ3章21節)。 またパウロは、「キリスト・イエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです」とも述べています(ピリピ3章14節)。 神「ご自身の栄光のからだと同じ姿に変え」られ、「キリスト・イエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得る」ことこそ、私たちの「人生の目標」であり、パウロは、この「目標を目指して一心に走ってい」たのです。 四、真のキリスト教は、新生と聖化を求め、信じ、体験し、栄化を求め、信じて歩み、その結果、善行、奉仕、伝道などの神のわざに励む 1.真のキリスト教は、緑の四角の「キリストの十字架と復活による救い」を人生の土台として、その上に桃の四角の「神のご性質(聖、愛、義、憐れみ、真実)にあずかる者とな」り(第二ペテロ1章4節)、「御霊の実(愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制)」(ガラテヤ5章22、23節)を結ぶ者となるという品性や人格や人徳という家を建て上げ、青い三角の「人生の目標」に向かうのです。 2.緑の四角と桃の四角と青い三角の中が「内なる人」(第二コリント4章16節、エペソ3章16節)であり、その結果また現れとして黄色い四角のものがあるのです。 3.私たちが緑の四角と桃の四角と青い三角のものを軽視して、黄色い四角のものを最も重要なものとして優先したり、第一のものとして強調したりするなら、霊的ないのちを失い、聖書の真理からはずれてしまいます。 4.私たちは、まず第一に緑の四角と桃の四角と青い三角の「内なる人」が強められることを祈り求めていくなら(エペソ3章16節)、その結果として黄色い四角のものが備わっていくだけでなく、健全なものとしてとらえていくことができるのです。
2007.01.18
コメント(2)
-
説教要約 182
「キリスト教の神髄」 甲斐慎一郎 マタイの福音書、6章33節 「神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのものはすべて与えられます」(33節) マタイの福音書の5章から7章に書かれているキリストの教えは、「山上の説教」と呼ばれ、聖書の中で最も有名なことばが数多く記されています。 たとえば、「あなたの右の頬を打つような者には、左の頬を向けなさい」とか、「自分の敵を愛し……なさい」というようなことばはあまりにも有名です(マタイ5章39、44節)。 しかし私たちが、このような聖書の教えを真の神を信じる信仰を持たずに、ただ外側の行為だけを模倣しようとするなら、必ず行きづまり、失望落胆して、はては「キリスト教は、実行不可能なきれい事を教えているに過ぎない」と言って、聖書の教えやキリスト教を敬遠したり、非難したりするようになってしまうでしょう。 このようなまちがいは、どこから来るのでしょうか。それは、聖書が教えている最も大切で中心的な事柄を見失っているからです。そこでキリスト教の神髄とも言うべきことをこの箇所から学んでみましょう。 一、それは外側の行為の模倣ではなく、心の生まれ変わりです キリストは、「もしあなたの目が健全なら、あなたの全身が明るいが、もし、目が悪ければ、あなたの全身が暗いでしょう」と言われました(22、23節)。ここで言う「目」とは、意図や動機また心や霊性を指しており、「全身」とは、行為や行動また品性や人格など私たちの全存在を意味しています。 キリスト教は、キリストとその弟子たちの模範的な行いや高潔な人格を学んで、それを自力で模倣する宗教ではありません。心の中に罪を持っている私たちは、このような外側の行いを模倣することは不可能です。 それよりも私たちは、生まれ変わらなければなりません。私たちは、罪を認めて、心から悔い改め、キリストが十字架の上で、私たちの罪をその身に負ってくださったことを信じるなら、生まれ変わることができます。模範的な行いや高潔な人格は、心の生まれ変わりの結果なのです。 二、それは物質的な御利益の追及ではなく、霊的な救いを求めることです キリストは、「神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのものはすべて与えられます」と言われました(33節)。 キリスト教は、この世における物質的な祝福や恩恵を得るために打算的に神を信じる御利益宗教ではありません。どこまでも生まれ変わった私たちが、良い行いと立派な人格によって神を喜ばせることを目的とする霊的な宗教です。 私たちが神とその救いをまず第一に求めるなら、神は、それに加えて、必要なものはすべて与えてくださいます。ですから私たちは、「何を食べるか、何を飲むか、何を着るか、などと言って心配する」必要はないのです(31節)。 三、それは人に依存することではなく、神に拠り頼むことです キリストは、「あなたがたのうちだれが、心配したからといって、自分のいのちを少しでも延ばすことができますか」と言われました(27節)。私たちは、人の生命に関すること、また明日や未来のこと、そして死や罪の問題などは、人間の力ではどうすることもできないことを認めなければなりません。 キリスト教は、人間の力の限界を認めず、それを過信して、人に依存する宗教ではありません。謙虚に人間の力の限界を認め、生殺与奪の権を握っておられる偉大な神の力を信じ、すべてをゆだねて神に拠り頼む宗教です。 このように神に拠り頼む時、いままで罪のために妨げられていた神からの賜物や才能また様々な能力が十分に発揮されて、神の栄光を現す人に変えられていくのです。 東京フリー・メソジスト昭島キリスト教会のホーム・ページの「説教要約 4」より転載(ホーム・ページの説教要約は、コメントを書くことができないので、順次、転載します)。
2007.01.17
コメント(2)
-
説教要約 181
「姦淫の女性」 甲斐慎一郎 ヨハネの福音書、8章1~11節 この「姦淫の女性」の話は、後からこの個所に挿入されたものらしく、時間的には、ルカの福音書の21章38節の後に起きた出来事のようです。しかしこの個所に置かれているのは、深い意味があるのでしょう。 一、思いもよらない出来事に遭遇した律法学者とパリサイ人(1~7節) 律法学者とパリサイ人は、姦淫の場で捕えられた女の人を連れて来て、イエスに質問しました。彼らの質問に対して、イエスが彼女を石打ちにしなくてもよいと答えるなら、モーセの律法に逆らう者として(レビ記20章10節)、反対に、彼女を石打ちにせよと答えるなら、ローマの法に逆らう者として(18章31節)、どちらに答えても彼らに告発されてしまうものでした。 このような狡猾な質問に対して、イエスは何も答えられませんでした。しかし彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは、「あなたがたのうちで罪のない者が、最初に彼女に石を投げなさい」と言われました(7節)。 これは、彼らにとって思いもよらない言葉でした。九分九厘、イエスを告発することができると思っていた彼らは、土壇場においてその立場が逆転し、今度は彼らが告発される羽目になってしまったのです。聖書は、「神は、知者どもを彼らの悪賢さの中で捕える」と教えています(第一コリント3章19節)。 人間は、自分の考えや思いの通りに物事を進めようとするものです。しかし神は、人の考えや思い、また知恵や賢さを越えた思いもよらないことをされるのです。 二、思いもよらない罪を示された律法学者とパリサイ人(5~9節) 律法学者とパリサイ人は、姦淫の女性を捕えてイエスを告発しようとしている間は、自分たちの罪に気がつきませんでした。私たちは、人の罪を責めたり、自分の考えや思いの通りに物事を進めたりしている時は、多くの場合、自分の心の姿が見えなくなっています。 彼らが自分たちの罪に気がついたのは、自分の思いや考えを越えた思いもよらない出来事が起き、人の罪を責める立場から、自分が罪を責められる立場になった時でした。 人の心というものは、底が知れないほど深いものであり、自分でも気がつかない神への不信仰と反逆という罪がひそんでいます。私たちは、思いもよらない出来事に遭遇する時、この思いもよらない罪が示されるのです。 三、思いもよらない救いにあずかった姦淫の女性(7~11節) この女性は、イエスが「罪のない者が、最初に彼女に石を投げなさい」と言われた時、心の中で死を覚悟したことでしょう。しかしだれも石を投げる人がいないので、不思議に思って周囲を見渡すと、イエスのほかにはだれもいませんでした。さらに不思議なことにイエスは、彼女に「わたしもあなたを罪に定めない」と言われたのです(11節)。 イエスは彼女の罪を赦されました。それは、イエスが地上で罪を赦す権威を持っておられるからであり、また彼女も「そのままそこにいた」ことにより(9節)、逃げ隠れはしないで、心から罪を悔い改め、処罰を受けることをイエスにゆだねたからです。神が私たちに思いもよらない罪を示すのは、私たちに思いもよらない救いをお与えになるためです。 世の人々は、「神がいるなら、どうしてこのような不可解なことがあるのか」と神の存在を疑っています。しかし聖書は、神がおられるからこそ、このような思いもよらない不可解なことを通して、私たちに思いもよらない罪を示し、そして思いもよらない救いを与えてくださるのであると教えているのです。拙著「キリストの生涯の学び」100 「姦淫の女性」より転載
2007.01.16
コメント(2)
-
説教要約 180
「神の発想と人の発想(3)」 甲斐慎一郎 イザヤ書、55章8、9節 「わたしの思いは、あなたがたの思いと異なり、わたしの道は、あなたがたの道と異なるからだ。――主の御告げ。――天が地よりも高いように、わたしの道は、あなたがたの道よりも高く、わたしの思いは、あなたがたの思いよりも高い」(8、9節)。 最後に神の発想は人の発想にはないものであるということについて学んでみましょう。 一、三つの言葉について 私たちが何げなく用いている言葉の中に、私たちの発想にはなかったものを表す言葉がいくつかありますが、そのうちのおもなものは、次の3つではないでしょうか。 1.不可思議 「可」という言葉を省いて「不思議」とも言いますが、これは文字通り思いはかることができないということで、到底考えることができないという意味です。 2.まさか 漢字は「真逆」と書きますが、これは、とてもありそうもないとか、起こりそうもない様子を表す言葉です。 3.意想外 「想」という言葉を省いて「意外」とも言いますが、これは文字通り自分の意想、すなわち思いや考えの外ということで、思いのほかとか、思いがけないという意味です。 「事実は小説よりも奇なり」という言葉がありますが、この世に実際に起きる出来事というものは、作り話や小説以上に不思議な巡り合わせや、まさかと思われるような事件、また作家の空想も及ばないような意外なことが多いものです。 二、人の発想について これらのことは、信仰の世界においては、どうでしょうか。 1.思いもよらない出来事 このような思いもよらない出来事というものは、世の中だけでなく、聖書とそこに記されている人物の生涯にも、2000年に亙る教会歴史と代々の神の聖徒たちの生涯にも見ることができます。しかしなぜでしょうか。 2.思いもよらない罪 人間の心というものは、底の知れないほど深いものであり、自分でも気がつかないような神への不信仰と反逆という罪が潜んでいます。私たちは、思いもよらない出来事に遭遇する時にのみ、この思いもよらない罪が示されるのです。 3.思いもよらない救い 私たちは、自分の考えで神の救いのわざを限定してしまうことが多いものです。神が私たちに思いもよらない出来事を通して、思いもよらない罪を示すのは、私たちを苦しめるためではなく、私たちの想像を遥かに越えた思いもよらない救いを与えるためです。 三、神の発想について それでは、なぜ神のなさることは、私たちの想像を遥かに越えた思いもよらないことなのでしょうか。 この宇宙を造られたのは神です。しかし聖書が教えている神は、宇宙とは別個に、その外におられる方、いや宇宙(被造物)がなくても、それを超越して存在される方で、これを「超越神」と言います。しかし同時に「私たちは、神の中に生き、動き、また存在しているのです」(使徒17章28節)とあるように、宇宙(被造物)の中に存在しておられる方で、これを「内在神」と言います。 私たちの思考の範囲は、どんなに広くても、この宇宙の中に限られていて、その外側の世界を考えることは、到底不可能です。しかし神は、この宇宙の外におられると同時に、この宇宙のどこにでもおられるゆえに、神のなさることは、人間の目には、私たちが到底考えることができない不思議なことに見えるのであり、また私たちの思いや考えの外にある実に意外な出来事に映るのです。 次回は、「神の発想は人の発想にはないものである」という例を学んでみたいと思います。
2007.01.15
コメント(2)
-
説教要約 179
「放蕩息子の父」 甲斐慎一郎 ルカの福音書、15章11~32節 この「放蕩息子」のたとえ話は、弟息子や兄息子に焦点を合わせると、失われた人が、信仰によって神に立ち返るという人間の側から見た救いを教えています。しかし、二人の息子の父に焦点を合わせると、神が、失われた人を捜し求めておられるという神の側から見た救いを教えています。 それで第三回目は、放蕩息子、いや二人の息子の父に焦点を合わせてみましょう。 一、なぜ父は、弟息子の求めるままに身代を分けてやったのでしょうか 弟息子が父に財産の分け前を求めた時、父は、「悪銭身に付かず」という諺のように、彼が放蕩して財産を使ってしまうことなど全く考えなかったのでしょうか。決してそうではありません。父には、そのようになることは、初めからわかっていました。 しかし父は、すでに心が離れてしまっている弟息子を無理に引き止めて、強制的に服従させてもむだであることをよく知っていました。それよりも彼が父を離れて放蕩し、様々な苦しみをなめることによって、自分の愚かさと罪深さをいやというほど知るようにさせたのです。これこそ、神が私たち人間をお取扱いになる方法です。 「神は、弟息子に罪を憎ませるため、彼に罪の苦さを味わわせただけでなく、彼を罪から救うために、彼を罪の悲哀の中から招かれました。弟息子は、このような懲らしめを受けなければ、おそらく神の招きの声を聞いても、それに聞き従わなかったでしょう。弟息子の上にふりかかった禍は、彼の罪に対する神の怒りの現れであることは言うまでもありませんが、見方を変えれば、彼に対する神の愛の現れなのです」(R・C・トレンチ)。 二、なぜ父は、少しも叱責しないで弟息子を子として迎えたのでしょうか 父は、弟息子を少しも叱責しないで、子として迎えました。それは、彼が父の家を出て行った時の姿や、遠い国へ行って放蕩していた時の姿とは、全く違った別人として帰って来たからです(R・C・トレンチ)。これが、弟息子の側の理由です。 父は、弟息子を少しも叱責しないで、子として迎えました。それは、父が弟息子の罪による苦しみや悩みを全部自分が負って、彼の罪をすべて赦したからです。これが、父の側の理由です。 この両者があったからこそ、父は弟息子を子として迎えたのです。もし弟息子が、家を出て行った時の姿や、遠い国で放蕩していた時の姿のままで帰って来たならば、また父が弟息子の罪による苦しみや悩みを全部彼に返していたならば、父は、弟息子を子として迎えることはできなかったでしょう。 三、なぜ父は、兄息子が知ったならば怒るような祝宴を催したのでしょうか 近所の人たちは、弟息子の方は親不孝で、とても悪い子だが、兄息子の方は親孝行で、りっぱな子だとうわさをしていたにちがいありません。弟息子のほうのうわさは当たっていました。しかし父は、兄息子のほうに関しては、近所の人たちがうわさをしているようには、決して思っていませんでした。 父は、弟息子を子として迎え入れ、祝宴を催すことによって、兄息子の心の中に隠れていた罪を自覚させ、悔い改めの必要を気づかせたのです。兄息子は、弟息子を迎え入れた父を責めることによって、自分の心の中に隠れていた罪が現れるとは、夢にも思っていなかったことでしょう。それは放蕩した弟息子にとっても同じでした。しかし父は、すべてを見通して、二人の息子を神に立ち返らせるために、このようにしたのです。拙著「キリストの生涯の学び」130「放蕩息子の父」より転載
2007.01.14
コメント(2)
-
説教要約 178
「放蕩息子の兄」 甲斐慎一郎 ルカの福音書、15章25~32節 「放蕩息子」のたとえは、弟息子の話だけで終わらず、兄息子の話が続いています。 それは、弟息子は「取税人や罪人たち」という「堕落した罪人」を、兄息子は「パリサイ人や律法学者たち」という「自称義人の罪人」を表し、どちらも救われなければならないことを教えているからです。 それで第二回目は、放蕩息子の兄に焦点を合わせてみましょう。 一、父の心を知ろうともしなかった兄息子 兄息子は、弟が帰って来た時、父が喜んで迎えたことをしもべから聞きました。「すると、兄はおこって、家にはいろうともし」ませんでした(28節)。このような態度の中に、父の心を知ろうともしなかった兄息子の姿を見るのです。 兄息子は、父が弟息子を迎え入れたことをしもべから聞いた時、怒る前に、父に直接話をして、その理由を聞く必要がありました。しかし、腹が立つだけで、父に聞く余裕などなかったのでしょう。 また兄息子は、父があの弟息子を迎え入れるからには、正当な理由があるにちがいないと考えてもよかったのです。しかし、そんなことは考えもしませんでした。 そして兄息子は、父があの弟息子を迎え入れるからには、たとえ自分には理解できなくても、深い理由があるかもしれないと思ってもよかったのではないでしょうか。しかし、そんなことは夢にも思いませんでした。 二、父の心と一致していなかった兄息子 兄息子は、父に「仕え、戒めを破ったことは一度もありません」と言いました(29節)。聖書は、律法学者やパリサイ人の姿は、「外側は人に正しいと見えても、内側は偽善と不法でいっぱいです」と教えています(マタイ23章28節)。彼は、外側の正しさだけで、内側の正しさがありませんでした。 また兄息子は、戒めを破ったことがないのに、子山羊一匹ももらえなかったので、父に文句を言いました(29節)。聖書は、イスラエル人は「自分自身の義を立てようとして、神の義に従わなかった」と教えています(ローマ10章3節)。彼は、自分の正しさを主張して、神の正しさに従いませんでした。 そして兄息子は、遊女におぼれて、身代を食いつぶして帰って来た弟息子のために、肥えた子牛をほふった父親を非難しました(30節)。パリサイ人のように、「自分を義人だと自任し、他の人々を見下してい」たのです(18章9節)。 このように兄息子が、父の心を知ろうともしなかったのは、彼の心が父(神)の心と一致していなかったからです。 三、父から心が離れてしまっていた兄息子 父は彼に、「おまえは、いつも私といっしょにいる」と言いました(31節)。これは、父が深い愛をもって兄息子を厳しく叱責した言葉です。それは、「私は、おまえにとってだれよりも勝る者ではないか」ということを意味しています(R・C・トレンチ)。 また父は「私のものは、全部おまえのものだ」と言いました(31節)。これは、父が熱心に兄息子に与えた警告の言葉です。それは、「おまえが、このことを認めるなら、私のものは全部おまえのものではないか」ということを意味しています(R・C・トレンチ)。 兄息子は、父をだれよりも勝る者と思わず、からだは父といっしょでも、心はそうではなく、父の心(喜び)を自分の心(喜び)とすることができませんでした。 このように兄息子の心が、父の心と一致していなかったのは、彼の心が父(神)から離れてしまっていたからです。拙著「キリストの生涯の学び」129「放蕩息子の兄」より転載
2007.01.13
コメント(2)
-
説教要約 177
「放蕩息子」 甲斐慎一郎 ルカの福音書、15章11~24節 イエスは、「失われた銀貨」のたとえを話された後、「放蕩息子」のたとえ話をされました。第一回目は、弟息子に焦点を合わせてみましょう。 一、神から離れている人間の姿 「弟は、何もかもまとめて遠い国に旅立」ちました(13節)。これは、その霊が「神を離れ、心において敵となって」、「罪過と罪との中に死ん」だことを表しています(コロサイ1章21節、エペソ2章1節)。 そして弟は、「そこで放蕩して湯水のように財産を使ってしま」いました(13節)。これは、神から与えられた財産である神の像を失ってしまったことを教えています。すなわち、神を知る知識も神を喜ぶ感情も神に従う意志もなくしてしまったのです。 「その国に大ききんが起こり、彼は食べるにも困り始め」ました(14節)。ききんは、穀物の欠乏のことであり、穀物は、この世の哲学や宗教や救いを表しています。神の像を失った罪人は、この世の哲学や宗教や救いという代用品で生きようとします。しかし彼には、その代用品さえなかったのです。 「彼は豚の食べるいなご豆で腹を満たしたいほどで」した(16節)。豚の食べるいなご豆で腹を満たす人とは、「忌みきらうべき汚れた者、不正を水のように飲む人間」を表しています(ヨブ一五章16節)。この世の哲学も宗教も救いもない弟は、何の歯止めもなく、あらゆる罪に陥ってしまったのです。 二、神に立ち返る人間の姿 弟は、「我に返」りました(17節)。彼は、その霊が神から離れ(遠い国)、その心が神の像を失い(放蕩)、この世の哲学や宗教や救いもなく(大ききん)、あらゆる罪に陥っていた(いなご豆)ことがわかったのです。 弟息子は、「おとうさん。私は天に対して罪を犯し……ました」と言いました(18節)。ダビデは、「私はあなたに、ただあなたに、罪を犯し……ました」と祈っています(詩篇51篇4節)。そのように彼は、神の前における罪を自覚して、罪の告白をしたのです。 弟は、「もう私は、あなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人のひとりにしてください」と言いました(19節)。神の前に砕かれて、身をまかせる決心をしたのです。 弟息子は、「立ち上がって、自分の父のもとに行」きました(20節)。「暗やみから光に、サタンの支配から神に立ち返」ったのです(使徒26章18節)。これこそ「いのちに至る悔い改め」です(同11章18節)。 三、神に迎えられる人間の姿 弟息子は、父親のもとに返った時、少しも叱責されることなく、かえって喜んで父親に迎えられました(20節)。これは、彼のすべての罪が赦されたことを教えています。 父親は、しもべたちに命じて、弟息子に一番良い着物を着せ、手に指輪をはめさせ、足にくつをはかせました(22節)。これは、キリストの「正義の外套」を着て(イザヤ61章10節)、義と認められ、また「御国を受け継ぐことの保証」として、「聖霊をもって証印を押され」(エペソ1章14、13節)、そして子としての権利を回復したことを表しています(R・C・トレンチ)。 父親は、弟息子のために盛大な祝宴を催しました(23節)。このように神は、罪人が救われることを何よりも喜ばれるのです。 父は、「この息子は、死んでいたのが生き返……ったのだから」と言いました(24節)。このように「あわれみ豊かな神は……その大きな愛のゆえに、罪過の中に死んでいたこの私たちをキリストとともに生かし」てくださったのです(エペソ2章4、5節)。拙著「キリストの生涯の学び」128「放蕩息子」より転載
2007.01.12
コメント(2)
-
説教要約 176
「神の発想と人の発想(2)」 甲斐慎一郎 イザヤ書、55章8、9節 「わたしの思いは、あなたがたの思いと異なり、わたしの道は、あなたがたの道と異なるからだ。――主の御告げ。――天が地よりも高いように、わたしの道は、あなたがたの道よりも高く、わたしの思いは、あなたがたの思いよりも高い」(8、9節)。 次に神の発想は人の発想よりも遥かに大きいということについて学んでみましょう。 一、三種類の相違について なぜ神の発想は、人の発想よりも遥かに大きいのでしょうか。それは、神ご自身が人よりも比べものにならないほど大きな方だからです。 1.空間的なスケールの大きさ――無限 私たちの知る限りにおいて最も大きなものは、果てしもなく広がる大宇宙です。しかし「天も、天の天も、あなたをお入れすることはできません」(第一列王8章27節)とあるように、神は大宇宙よりもさらに大きな方です。 2.時間的なスケールの大きさ――永遠 科学者が用いる時間の単位は、どんなに長くても何十億年、または何百億年です。しかし「とこしえからとこしえまで、あなたは神です」(詩篇90篇2節)とあるように、神は初めもなく終わりもない永遠の方です。 3.実質的なスケールの大きさ――無限 このように神は、空間的には無限、時間的には永遠であるだけでなく、知識においては全知、能力においては全能であり、聖さ、愛、正しさ、憐れみ、真実さなど、その性質や属性のすべてにおいて無限の方です。 二、人の発想について 文字通り「ちりにすぎない」(詩篇103篇14節)人間が、大宇宙よりも大きな神をとらえようとするなら、次のようなことになるのではないでしょうか。 1.一部分を見て、それを全体であると思い込んでしまう。 これは、最も浅はかな考えであり、多くの人たちが陥っている誤りです。 2.一部分を見て、それをそのまま拡大したものが全体であると想像してしまう。 これは、「針の穴から天上のぞく(狭い見聞で、大きな問題を判断することのたとえ)」という諺のように、往々にして間違いのもとになることが多いものです。 3.全く分からなくなってしまう。 これは、「燕雀(えんじゃく)安んぞ(いずくんぞ)鴻鵠(こうこく)の志(こころざし)を知らんや(つばめやすずめのような小さな鳥には、おおとりやくぐいのような大きな鳥の志すところはわからないように、小人物は大人物の心を知ることができないというたとえ)」という言葉のように、小さな人間の心で、無限に大きな神のみこころを知ることは到底不可能です。 三、神の発想について それでは、人が神を知ることは永久にできないことなのでしょうか。決してそのようなことはありません。まず神が私たちにご自身を示してくださる――すなわち啓示してくださる――なら、私たちは神を知ることができるのであり、その神の啓示が記されている書物こそ聖書です。 その神を知るためには、どうすればよいのかということについて、ヨブ記には次のようなことが記されています。1.神の啓示を信じ、受け入れることです(42章2節)。2.へりくだって罪を悔い改めることです(42章6節)。3.神に祈り、信仰によって歩むことです(42章10節)。 聖書は、「神に近づきなさい。そうすれば、神はあなたがたに近づいてくださいます」と教えています(ヤコブ4章4節)。私たちは、へりくだって神の啓示を信じ、祈りと信仰によって神に近づくなら、神も私たちに近づいてくださり、いよいよ深く神を知ることができるようになるのです。 次回から3回にわたって、「神の発想は人の発想よりも遥かに大きい」という例を学んでみたいと思います。
2007.01.11
コメント(2)
-
説教要約 175
「三つの現実」 甲斐慎一郎 創世記、50章15-21節 「あなたがたは、私に悪を計りましたが、神はそれを、良いことのための計らいとなさいました。それはきょうのようにして、多くの人々を生かしておくためでした」(20節)。 私たちは一日や一週間また一月や一年の終わりになると、過ぎ去った時を振り返って、良かったことやすばらしかったことを感謝するでしょう。キリスト者であるならば、「数えてみよ主の恵み」という賛美のように神の恵みを数えて感謝することを知っています。 しかし私たちが悪かったことや芳しくなかったことには、いっさい目をつむって見ようとせず、ただ良かったことやすばらしかったことだけを見て感謝するなら問題です。なぜなら悪かったことや芳しくなかったことは、反省して悔い改めなければならないにもかかわらず、それをしないことになるからです。それとともに冒頭に記したみことばが教えている大切な真理を見失ってしまうからです。 一、悪い計略の現実 ヨセフは、兄たちに「あなたがたは、私に悪を計りましたが」と言いましたが、これは、どのようなことでしょうか。 1.ヨセフは、父に特別に愛されていたために兄たちに憎まれました(37章4節)。 2.ヨセフは、夢の話をしたので、兄たちにねたまれました(37章11節)。 3.ヨセフは、兄たちのたくらみによって殺されそうになりました(37章18節)。 4.ヨセフは、ルベンやユダのことばによっていのちだけは助かりましたが、エジプトに奴隷として売られました(37章28節)。 5.ヨセフは、ポティファルの妻の中傷によって監獄に入れられました(39章20節)。 6.ヨセフは、献酌官長の忘恩によって2年間も忘れられました(40章23節)。 5番目と6番目は、直接的には兄たちの計略ではありませんが、彼らがヨセフをエジプトに売らなければ、このようなこともなかったはずです。ともかくこれらが悪い計略の現実であり、ヨセフは、このことのためにどんなに苦しんだことでしょうか(42章21節)。 二、良い計画の現実 ヨセフは、「良いことのための計らい」と言いましたが、これは、どのようなことでしょうか。 このようにヨセフの生涯は、兄たちの憎しみとねたみによる悪い計略が現実であることを教えていますが、この中にもう一つの現実があります。それは、ヨセフがエジプト全土の統治者となることによってエジプトとイスラエルの家族のいのちを救うという神による良い計画の現実です。 ヨセフが兄たちに憎まれてエジプトに売られたのも、ポティファルの妻の中傷によって監獄に入れられたのも、献酌官長の忘恩によって2年間も忘れられたのも、彼がエジプトの統治者となって人々のいのちを救うためでした(45章5、8節)。 三、神の摂理の現実 このように「悪い計略の現実」の中に、もう一つ「良い計画の現実」が組み込まれており、この二つの現実を正しく支配しているのが「神の摂理の現実」です。摂理とは、「窮地に陥り、困難に直面している人間に対して、神がその無限の知恵と愛によって、その必要なすべてのものをあらかじめ知って備え、また配慮してくださること」です。 ですから私たちは、悪い計略の現実を直視して神の前に砕かれることが必要であり、それから目をそらしてはなりません。なぜなら悪い計略の現実から目をそらすことは、その中に含まれている良い計画の現実を見失ってしまうからです。 私たちは、神の摂理を信じる時にのみ、悪い計略の現実の中にあっても、それに打ち勝ち、それを乗り越えて、良い計画の現実の中を生き抜いていくことができるのです。 東京フリー・メソジスト昭島キリスト教会のホーム・ページの「説教要約 17」より転載、但し、冒頭の図は、原書にはなく、付加したものです(ホーム・ページの説教要約は、コメントを書くことができないので、順次、転載します)。
2007.01.10
コメント(4)
-
説教要約 174
「摂理を信じる信仰」 甲斐慎一郎 創世記、22章1~19節 「摂理」という言葉の語源は、「アドナイ・イルエ(主が備えてくださる)」(14節)であると言われ、その意味は、「神の予知による人間への配慮」です。アブラハムがイサクをささげた出来事から、摂理とそれを信じる信仰について学んでみましょう。 一、キリスト者の悩みとその解決 アブラハムが神よりイサクをささげよという大きな試練を受けた時、彼とても先に何が起きるのかを全く知らない人間である以上、神のなさることを理解することができず、悩んだことでしょう。しかしこのアブラハムの悩みは、キリスト者の共通の悩みです。 人間は神を信じて罪から救われても、様々な苦難や不幸や災いはなくなりません。この苦難や不幸や災いがあるということは、世の人々が神を信じない最大のつまずきになっているだけでなく、神を信じているキリスト者にとっても最大の悩みであり、また多くの場合、それは信仰の成長を妨げる最大の原因にもなっています。 このような苦難があっても、先に必ず良いことが待っているのがわかっていれば、それにも耐えられますが、実際には神を信じても、先のことは全くわかりません。 しかして、この二つの大きな悩みに十分な答えと解決を与えてくれるのが神の摂理であり、またそれを信じる信仰です。 二、キリスト者の宗教とその本質 アブラハムが試練に会ったのは、最愛の子イサクを神にささげるかどうかによって、彼の神に対する真実な愛があるかないかを試されるためでした。真の宗教の本質は、神が与えてくださる祝福や恵みよりも、神を真実に愛する愛を持つことです。 ですから、この世におてい苦難や不幸や災いから逃れるためだけに神を信じるなら、それは御利益信仰以外の何物でもなく、人は、ただ自分の利益のために神を利用していることになってしまうでしょう。その結果、真の宗教の本質である神への真実な愛などあり得ず、ただ罪深い、貪欲な人間が生まれるだけであり、宗教は、その存在価値を失ってしまうことでしょう。 また先のことに関して、もしアブラハムが天からの声によって止められることを予め知って、イサクをささげたとしたなら、彼の行為は芝居であり、その完全な献身も真実かどうか疑わしいものです。 このように苦難があることや先のことがわからないことは、御利益信仰や打算や偽りなど、真の宗教にとって致命的な不純物を取り除いて、真実な愛を持つために必要なことなのです。 三、キリスト者の勝利とその秘訣 アブラハムは、具体的には先に何が起きるのか全く知りませんでしたが、神は、良いものを必ず備えてくださることを信じていました(8節)。神の摂理を信じる信仰は、具体的な一つ一つのことに関しては、先に何が起きるのか、その時になるまではわからなくても、神は良いことはもちろんのこと、現在、目前にある苦難や不幸や災いなどの悪いことをも用いて、予め私たちのために最善のものを備えてくださると信じるのです。 しかしこの摂理を信じる信仰を持ち、また神の摂理の道を歩むために必要なことは、アブラハムがイサクをささげたように自分を完全に神にささげることです。これは具体的には、絶えず自分のためにではなく神のために、しかも安易な道ではなく、苦しくても最善の道を選ぶことです。 なぜなら、「ノークロス、ノークラウン(No cross,no crown)十字架なくして栄光なし、苦難なくして栄冠なし」という諺のように、神の道は、十字架の道、また自己否定の道だからです(マタイ16章24節)。十字架の道のみ生命に至る道であり、その苦しみは喜びに変わるのです。
2007.01.09
コメント(2)
-
説教要約 173
「聖書が教える逆説の宗教」 甲斐慎一郎 マタイの福音書、16章24-28節 「キリスト教は、パラドックスの宗教である」と言われます。この「パラドックス」ということばは、日本語では「逆説」とか「逆理」また「背理」とか「矛盾論」と訳されています。その意味は、「外観的には矛盾していて、一見不合理に見えながらも、その実は真理であるもの」ということです。 一、聖書が教える逆説の例について 聖書には数多くの逆説が記されています。 聖書は、私たちが神とキリストと福音のために1.悲しむなら、慰められる(マタイ5章4節)。2.義に飢え渇くなら、満たされる(マタイ5章6節)。3.くびきを負うなら、安息する(マタイ11章29節)。4.いのちを失うなら、それを見いだす(マタイ16章25節)。5.仕えるなら、偉くなる(マルコ10章43節)。6.自分を低くする者は、高くされる(ルカ14章11節)。7.見えないことを認めるなら、見えるようになる(ヨハネ9章39 ~41節)。8.苦難をともにしているなら、栄光をともに受ける(ローマ8章 17節)。9.死ぬなら、生かされる(第二コリント4章10節)。10.弱い時にこそ強い(第二コリント12章10節)。 と教えています。 代表的なものを10ほど挙げましたが、イエス・キリスト自身が逆説の道を歩まれました。このように聖書は、私たちに逆説を教えているのです。 二、聖書が教える逆説の理由について それでは神の真理は、なぜ私たちの目に逆に見えるのでしょうか。それは神と人との根本的な相違にあるということができます。 1.実質的な相違 神は聖なる方です。これに対して人間は罪と汚れに満ちた者です。罪人は「悪を善、善を悪」と言うような(イザヤ5章20節)ひねくれた者です。ですから神の真理が逆に見えるのではないでしょうか。 2.時間的な相違 神は永遠の方です。これに対して人間は有限な者です。神は永遠の目をもって目標点から出発点を見ることがおできになりますが、人間は有限な目しか持っていませんから、出発点からしか目標点を見ることができません。ですから神の真理を後ろや裏から見ていることになり、逆に見えるのではないでしょうか。 3.空間的な相違 神は高い霊の世界に住んでおられる方です(イザヤ55章8、9節)。これに対して人間は低い物質の世界に住んでいる者です。言わば次元が異なります。神は高い霊の世界から低い物質の世界を見下ろしておられますが、人間は低い物質の世界から高い霊の世界を見上げている者です。ですから神の真理を底や裏から見上げていることになり、逆に見えるのではないでしょうか。 三、聖書が教える逆説の宗教について このような3つの大きな溝を渡ることはできないのでしょうか。 罪深い人間は、聖なる神に近づくことはできません。しかし聖なる神は罪深い人間のところに来られ――これがキリストの受肉です――神に至る道をつくってくださいました。これがキリストの十字架による救いです。 有限な人間は、永遠の神を知ることはできないのでしょうか。たった一つだけ知る方法があります。それは「望んでいる事がらを保証し、目に見えないものを確信させる」(ヘブル11章1節)信仰を持つことです。 私たちは、低い物質の世界から高い霊の世界に行くことはできないのでしょうか。たった一つだけ方法があります。それは「新しく生まれ」ることです(ヨハネ3章3~6節)。 新しく生まれたキリスト者は、聖書が教えている逆説を信じて実行する以外に神の祝福を受けることができないことを知るのです。
2007.01.08
コメント(2)
-
説教要約 172
「神の発想と人の発想(1)」 甲斐慎一郎 イザヤ書、55章8、9節 「わたしの思いは、あなたがたの思いと異なり……わたしの思いは、あなたがたの思いよりも高い」(8、9節)。 「発想」とは、文字通り思想を表現することです。冒頭のみことばには、神の思いと人の思いが異なっているということが記されています。思いが異なっていれば、その表現である発想も異なっています。 神の発想と人の発想の違いには様々なものがありますが、代表的なものは、次のような3つではないでしょうか。(1)神の発想は人の発想とは反対である。(2)神の発想は人の発想よりも遥かに大きい。(3)神の発想は人の発想にはないものである。 まず神の発想と人の発想とは反対であるということについて学んでみましょう。 一、実質的な相違 神は聖なる方であり(イザヤ6章3節)、人間は罪深い者です(ローマ3章10~18節)。ですから「善にして善を行われ」る(詩篇119篇68節、日本聖書協会訳)神の発想と、「悪を善、善を悪」(イザヤ5章20節)というような罪深い人間の発想が反対になるのは当然ではないでしょうか。 生まれながらの人間の本性というものは、◇自分の思い通りに何でも物事が運ぶ時、◇自分の欲しいものが何でも手に入る時、◇自分がどんなに偉い者であるかを知る時、 最も幸福であると思います(人の発想)。 しかしもしすべてのことが私たちの思い通りになるなら、どうなるでしょうか。私たちは、努力する必要がなくなるために怠慢になるだけでなく、思い上がって高慢になり、ついには堕落してしまうでしょう。それで神は、私たちが勤勉さと謙虚さを失わずに向上し、成長していくために、様々なことが私たちの思い通りになるようにはされないのです(神の発想)。 二、時間的な相違 神は永遠に存在する方で、人間は有限な者です(詩篇90篇1~3節)。ですから永遠の目をもって目標点から出発点を見ることができる神の発想と、有限な目を持っているために出発点からしか目標点を見ることができない人間の発想が反対になるのは当然ではないでしょうか。 もし私たちが将来に起きることを予め知っていたなら、どうなるでしょうか。良いことに関しては安堵し、悪いことに関しては恐怖を抱き、どちらにしても仕事が手に付かなくなるでしょう。かといって将来に何が起きるのかを全く分からないのも不安です(人の発想)。 人生の旅路は、障害物競走のようなものです。神は、私たちが信仰によって歩み、その信仰が試されて、純粋なものとなるだけでなく、その信仰に成長するために、私たちが乗り越えなければならない、あらゆる障害物を予め備えて私たちを訓練されるのです(神の発想)。 三、空間的な相違 神は高い天に住んでおられる方であり(イザヤ57章15節)、人間は低い地上に住んでいる者です。ですから天から地上を見下ろしておられる神(詩篇53篇2節)の発想と、地上から天を見上げている人間の発想とが反対になるのは当然ではないでしょうか。 この世には様々な矛盾があり、不可解な出来事も数多くあります。そしてこのために多くの人々は神の存在を疑っています(人の発想)。 しかし「地上に残された時を……神のみこころのために過ごすように」(第一ペテロ4章2節)変えられたキリスト者は、この地上の生涯というものは、神によって織られている美しい織物を裏から見ているようなものであることを知っているのです(神の発想)。 次回から3回にわたって、「神の発想は人の発想とは反対である」という例を学んでみたいと思います。
2007.01.07
コメント(0)
-
説教要約 171
「神の祝福に満ちあふれた人(2)」 甲斐慎一郎 マタイの福音書、5章1~16節 「神の祝福に満ちあふれた人」の第一回目は旧約聖書の詩篇84篇から「真の祝福」は、「神を求める幸い」(1~4節)と「神にある幸い」(5~8節)と「神の与える幸い」(9~12節)という3つの段階があることを学びましたが、第二回目は、新約聖書の「至福の教え」から学んでみましょう。 一、至福の教えは、詩篇84篇が教えている幸福の三段階を教えています 「山上の説教」の中の5章の前半は、「至福の教え」と言われているところです。この8つの幸いの前半の部分には、「神を求める幸い」と「神にある幸い」が、後半の部分には、「神の与える幸い」が記されています。 二、8つの幸いは、内側の心における幸いで、塩と光です 8つの幸いは、互いに何の関係もないものではなく、「心の貧しい者」を第一段階とし、「義のために迫害されている者」を第8段階とする「真の幸福の八段階」を教えています。 山上の説教が教えている8つの幸いは、外側に表れた幸福というよりも内側の心における幸福です。この内側の心における幸いは、「塩」と「光」であり、それは必ず外側の行為に表れます。 「塩」は、腐敗(社会の堕落)を防ぎ、良い味をつけます(世の人々に良い感化や影響を与えます)。「光」は、やみ(罪深い世)を照らし、世の人々に救いの真理を示します。 英語で幸福と訳されることばには「ハッピネス(happiness)」と「ブレッスィング(blessing)」の二つがあります。前者は、いくつかの偶然がうまく重なった幸運な出来事で、後者は、神が与えてくださる真の祝福で、それは必ず外側の行為に表れる「塩」と「光」です。 三、塩と光という内側の心の幸いは、必ず外側の行為に表れ、真の祝福を受けます 主は、「心に満ちていることを口が話す」(マタイ12章34節)と言われましたが、心は、ことばだけでなく、行為に表れます(ヤコブ2章14、16節、第一ヨハネ3章17、18節)。 心の貧しい者とは、自分の心の姿が「富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って」、うぬぼれているのではなく、かえって罪のために「みじめで、哀れで、貧しくて、盲目で、裸の者であること」(黙示録3章17節)を知ってへりくだり、救い主の必要を自覚して神から離れない人のことです。天の御国はその人のものです。 心の貧しい者は、自己憐憫に陥って世の楽しみや慰めを求めることなく「神のみこころに添って」罪を悲しむ者になります(第二コリント7章9節)。その人は慰められるのです。 罪を悲しむ者は、悪者の栄えるのを見てねたんだり(詩篇73篇3節)、悪人に復讐したりすることなく、悪を耐え忍んで柔和な者になります。その人は地を相続するのです。 柔和な者は、悪と妥協することなく、義を愛し不正を憎む、義に飢え渇いている者になります。その人は満ち足りるのです。 義に飢え渇いている者は、「あわれみのないさばき」をすることなく(ヤコブ2章13節)、あわれみ深い者になります。その人はあわれみを受けるのです。 あわれみ深い者は、「不正を喜ばずに真理を喜び」(第一コリント13章6節)、心のきよい者になります。その人は神を見るのです。 心のきよい者は「争ったり、戦ったりする」ことなく(ヤコブ4章2節)、平和をつくる者になります。その人は神の子どもと呼ばれるのです。 平和をつくる者は、不正を憎んで「敬虔に生きよう」とするので(第二テモテ3章12節)、義のために迫害される者となります。天の御国はその人のものです。 四、神の栄光が現されます 心の幸いという「塩」と「光」は、必ず外側の行為に現れ、それは罪深い世を照らし、世の人々に救いという真理を示し、人々は、その良い行いを見て、神をあがめるようになります(16節)。これこそ神から与えられる真の祝福(blessing)です。
2007.01.06
コメント(2)
-
説教要約 170
「神の祝福に満ちあふれた人(1)」 甲斐慎一郎 詩篇、84篇1~12節 「幸福」は人類共通の切なる願望であり、だれでも幸福を願わない人はいないでしょう。しかし現実には、多くの人々は「幸福」を求めながら、「真の幸福」が何であり、どこにあるかが分からないために、「偽りの幸福」に甘んじたり、「真の幸福などあり得ない」と言って、あきらめてしまったりしているのではないでしょうか。 英語で幸福と訳されることばには「ハッピネス(happiness)」と「ブレッスィング(blessing)」の二つがあります。前者は、いくつかの偶然がうまく重なった幸運な出来事で、後者は、神が与えてくださる真の祝福です。 この詩篇には、「なんと幸いなことでしょう」というみことばが3回も記されています(4、5、12節)。聖書は、私たちに真の幸福があることをはっきりと教えています。この84篇は、休止を表す「セラ」ということばによって次のような3つに区分することができ、幸いの3つの段階を教えています。 一、神を求める幸い(1~4節) ここには、「慕わしい」とか、絶えいるばかり(死ぬほど)「恋い慕って」ということばが記され、詩篇42篇の記者のように「生ける神を求めて渇いてい」る姿が描かれています(2節)。すなわち全身全霊をもって神を慕い求めているのです。 真の宗教の中心は何でしょうか。すばらしい神のことばや教えを学ぶことでしょうか。荘厳な宗教的儀式や礼典に出席して、その雰囲気に酔うことでしょうか。神の戒めを堅く守り、神への奉仕に励むことでしょうか。これらはみな大切なことですが、中心的な事柄ではありません。真の宗教の真髄は、生ける神との親しい人格的な愛の交わりです。そのために神を慕い求める人は幸いです。 人間の幸福の第一の段階は、この神を求める幸いです。神は、まず私たちにこのことを学ばせるために、私たちに様々な体験をさせたり、色々な所を通らせたりするのです。 二、神にある幸い(5~8節) このように神のみを慕い求める人は、「その力が、あなた(神)にあり、その心の中にシオンへの大路(すなわち神に近づく心)」があり(5節)、「シオンにおいて、神の御前に現れます」(7節)とあるように、ついには神にまみえ、神と一つになって、その力も、その心も神にあるようになります。このような人は、目に見えるものや周囲の環境に惑わされず、神のみを喜ぶことができ、神にある幸いを知っているのです。 人間の幸福の第二の段階は、この神にある幸いです。この幸いを知っている人は、「涙の谷を過ぎるときも、そこを泉のわく所とします」(6節)とあるように、苦難と試練の涙の谷を過ぎるようなことがあっても、そこを祝福と恵みの泉がわく所とするのです。 三、神の与える幸い(9~12節) 最後にこの詩篇の記者は、「主は恵みと栄光を授け、正しく歩く者たちに、良いものを拒まれません」(11節)と言っています。これはだれが見てもわかる祝福です。私たちが普通に考えている幸いというのは、このように神から恵みと栄光と良いものが豊かに与えられることです。 人間の幸福の第三の段階は、この神の与える幸いです。しかしこの神の与える幸いは、まず神を求める幸いを体験し、次に神にある幸いを体得した者だけが、ほんとうの意味において得ることができるものであり、先の二つの幸いを飛び越えて、いきなりこれを味わうことはできません。 この真の幸福の三段階を地で行った人が聖書に記されています。それは旧約のヨセフです。彼は、エジプトに売られ、監獄にまで入れられましたが、これは神を求めるのに妨げになるものを取り去られて、神のみを求める幸いを体験したのであり、次に同じ監獄にいる人を慰めることができましたが、これは神にある幸いを体得したのであり、ついにエジプトの支配者になりましたが、これは神の与える幸いを得たのです。
2007.01.05
コメント(2)
-
説教要約 169
「将来と希望を与える神の計画(2)」 甲斐慎一郎 エレミヤ書、29章10、11節 「バビロンに七十年の満ちるころ、わたしはあなたがたを顧み、あなたがたにわたしの幸いな約束を果たして、あなたがたをこの所に帰らせる。わたしはあなたがたのために立てている計画をよく知っているからだ。――主の御告げ。――それはわざわいではなくて、平安を与える計画であり、あなたがたに将来と希望を与えるためのものだ」(10、11節)。 主は、ご自分に反逆した罪のためにバビロンへ捕囚の民として連れて行かれたユダの人たちに対して、祖国イスラエルに帰ることができるという希望と平安に満ちた将来を約束されました。その時期は、バビロンに70年の満ちるころ、すなわち、バビロンにおける70年間を懲らしめの期間として過ごし、いままでの罪をすべて悔い改めた後のことです。 一、二種類のこれからの時(未来と将来) 宗教哲学者の波多野精一は、二種類の「これからの時」をそれぞれ「未来」および「将来」と呼び、実存哲学者ハイデガーは、「未来」および「到来」と呼んで区別しました。 ◇未来――いまだ来たらずという意味で、見通しがきかない絶望と不安の時です。 ◇将来――まさに来たらんとするという意味で、見通しがきく希望と平安の時です。 未来は現在から離れて人の手が届かない時であるのに対して、将来は今につながる人の手が届く時であり、大きな違いがあります。 二、二種類のいままでの時(過去と由来) 前述した実存哲学者のハイデガーは、二種類の「いままでの時」をそれぞれ「過去」および「由来」と呼んで区別しました。 ◇過去――過ぎ去ったという意味で、今さらどうすることもできない時です。 ◇由来――由って来たるという意味で、今にまで伝えられて来た時です。 過去は現在から離れて人の手が届かない時であるのに対して、由来は今につながる人の手が届く時であり、大きな違いがあります。 三、過去――現在――未来という生き方 バビロンへ捕囚の民として連れて行かれたユダの人々は、過去における神への反逆の罪をどんなに悔やんだことでしょうか。また神に従って平和と祝福に満ちていた時をどんなに懐かしがったことでしょうか。しかし今となっては取り返しがつかず、今さらどうすることもできませんでした。そして捕囚の身として一寸先は闇であり、未来は絶望と不安に満ちていました。 もし私たちが、「いままでの時」を「過去」としてしかとらえることができなければ、悪かった過去も良かった過去も、すでに過ぎ去って人の手が届かない、今さらどうすることもできないものとなるので、それを改めて現在という時に生かすことができません。その結果、「これからの時」を「未来」としてしかとらえることができず、絶望と不安に陥るのです。 これは、時というものを三つに区切り、あたかも互いに関係がないかのように考える物理的な時のとらえ方です。 四、由来――今――将来という生き方 主は、このような捕囚の民に対してバビロンにおける70年間の懲らしめの期間が終わるなら、悔い改めにふさわしい実を結ぶので、祖国イスラエルに帰ることができるという希望と平安に満ちた将来を約束されました。 もし私たちがこの神に対する信仰によって、「いままでの時」を「由来」としてとらえるならば、――すなわち主の良くしてくださったことを何一つ忘れず心から神に感謝するとともに、すべての罪を心から悔い改めて神に立ち返るならば――良い由来も悪い由来も、人の手が届く今にまで伝えられたものとなるので、今という時に生かすことができます。その結果、「これからの時」を「将来」としてとらえることができ、希望と平安に満ちるのです。 人間は物質や機械ではないので、時というものを3つに区切るような物理的な時のとらえ方はしません。人間の心や生命・生活・生涯というものは、3つの時に決して区切ることはできず、時というものを一つにつながったものとしてとらえるのです。 東京フリー・メソジスト昭島キリスト教会のホーム・ページの「説教要約 18」より転載(ホーム・ページの説教要約は、コメントを書くことができないので、順次、転載します)。
2007.01.04
コメント(2)
-
説教要約 168
「将来と希望を与える神の計画(1)」 甲斐慎一郎 エレミヤ書、29章1~14節 「わたしはあなたがたのために立てている計画をよく知っているからだ。――主の御告げ。――それはわざわいではなくて、平安を与える計画であり、あなたがたに将来と希望を与えるためのものだ」(11節)。 一、捕虜としてバビロンへ捕らえ移されたユダの人々(28章14節、29章1~4節) ユダの人々は、神に対する不信仰と反逆の罪のためにバビロンに滅ぼされ、生き残った民は捕虜になりました。捕囚の民は、その地に住むことを許されましたが、「バビロンの川のほとり、そこで、私たちはすわり、シオンを思い出して泣」きました(詩篇137篇1節)。祖国を失った民の心中は、察するにあまりあるものがあります。 バビロンへ引いて行かれた捕囚の民は、過去における神への反逆の罪をどんなに悔やんだことでしょうか。また神に従って平和と祝福に満ちていた時のことをどんなに懐かしがったことでしょうか。しかし今となっては取り返しがつかず、今さらどうすることもできませんでした。捕囚の身として一寸先は闇であり、未来は不安と絶望に満ちていました。 二、バビロンに70年の満ちるころ祖国に帰ることを預言したエレミヤ(5~14節) エレミヤは、このような捕囚の民に「家を建てて住みつき、畑を作って、その実を食べよ。妻をめとって、息子、娘を生み……そこでふえよ。……わたしがあなたがたを引いていったその町の繁栄を求め、そのために主に祈れ」と仰せられた主のことばを告げました(5~7節)。民は、このエレミヤのことばに従って生活し、その地でふえました。 ハナヌヤは、ゼデキヤの治世の初めに捕囚の民は年のうちに帰るという偽りの預言をしました(28章1~4節)。それでエレミヤは、にせ預言者の誤りを指摘し、それに惑わされないように警告するとともに、捕囚の期間は70年であり、その後に祖国に帰ることが主のご計画であることを記した手紙をエルサレムから送りました(1、8~10節)。 主は、捕囚の民にバビロンにおける70年間の懲らしめの期間が終わるなら、悔い改めにふさわしい実を結ぶので、祖国イスラエルに帰ることができるという平安と希望に満ちた将来を約束されました(10、11節)。 また主は「あなたがたがわたしを呼び求めて歩き、わたしに祈るなら、わたしはあなたがたに聞こう。もし、あなたがたが心を尽くしてわたしを捜し求めるなら、わたしを見つけるだろう」と仰せられました(12、13節)。 このエレミヤの預言は、バビロンが滅ぼされ、紀元前538年にペルシャ王クロスが勅令を宣布し、ユダの民が捕囚から解放されて帰国した時に成就したのです(エズラ1章)。 三、私たちのために平安と将来と希望を与える計画を立ててくださる神(11節) 私たちも弱さのために何度も同じ過ちを犯して悩んだり、神に対する不信仰と不従順の罪のために苦しんだりするだけでなく、不安と絶望に満ちる時、主は私たちを顧みて、私たちに平安と将来と希望を与える神の計画を示してくださるのです。 それでは平安と将来と希望を与える神の計画が実現するための秘訣は何でしょうか。 ◇過去を振り返って、「主の良くしてくださったことを何一つ忘れ」ず(詩篇103篇2節)、心から神に感謝をささげるとともに、今まで犯してきたすべての罪を悔い改めて、悔い改めにふさわしい実を結ぶことです。 ◇現在を見つめて、にせ預言者に惑わされず(マタイ24章5、11節)、「締まりのない歩み方」をすることなく(第二テサロニケ3章11節)、「勤勉で怠らず、霊に燃え、主に仕え」ることです(ローマ12章11節)。 ◇将来を展望して、神が私たちのために、「平安」と「将来と希望を与える」計画を立ててくださっていることをよく知り(11節)、その神の計画が実現し、その預言が成就するために真剣に主を「呼び求めて歩き」、「祈る」とともに、「心を尽くして」主を「捜し求める」ことです(12、13節)。
2007.01.03
コメント(0)
-
説教要約 167
「二つの生き方」 甲斐慎一郎 ヤコブの手紙、4章13~17節 私たちは、年末や年始を迎えると、過去を振り返り、未来のことを考えます。 「過去のない人は、動物に近い。そうして未来のない人は、まさしく動物である」と言った人がいます。人間にとって未来は大切であり、いわゆる「その日暮らしの生活」は決して良いものではありません。「明日に向かって生きる」ところに人間の尊さがあるのではないでしょうか。 しかしこの場合、聖書は、次のような二つの生き方があることを教えています。 一、自分を中心とした高慢な生き方 ヤコブは、「きょうか、あす、これこれの町に行き、そこに一年いて、商売をして、もうけよう」(13節)と言う人たちに向かって「あなたがたはむなしい誇りをもって高ぶっています。そのような高ぶりは、すべて悪いことです」と述べています(16節)。これはどうしてなのでしょうか。 「高ぶり」という言葉は、原語において、もともと「浮浪者」を指す語で、それが転じて「かたり」や「ぺてん師」また「大言壮語する者」という意味になりました。ですから高ぶりは、実際以上に誇大に吹聴することであり、その根は、ありのままの現実の姿や状態を素直に認めない、かたくなな心にあります。 人間というものは、次の瞬間に何が起きるのか全く分からないほど無知な者であり、またどんなに力んでも一瞬でも生命を延ばすことができないほど無力な者です(14節)。 未来のことに関して、このような厳粛な事実を直視せず、また生殺与奪の権を握っておられる神(申命記32章39節)を認めずに、あたかも自分の思い通りに何でもできるかのように振る舞うことは、不遜な態度でなくて何でしょうか。同様に自らの罪深さも、その罪からの救い主の必要性も認めないことは、神の前において高慢であることを聖書は教えています。 二、神を中心とした謙虚な生き方 これに対して、ありのままの現実の姿を直視し、神を恐れて歩む謙虚な生き方というものがあります。 1.「主のみこころなら……生きていて」 これは、神のみこころと私たちの生命の関係を教えています。人間は自分で生きているのではなく、神によって生かされているものです。ですから私たちは、自分の思い通りに生きることをやめ、その生命を神のみこころにゆだねるなら、神は私たちの生命を保証してくださるのです(マタイ6章25、26節)。 2.「主のみこころなら……このことを、または、あのことをしよう」 これは、神のみこころと私たちの生活の関係を教えています。人間は自分の計画や野心を成し遂げるために生きているのではなく、神のみこころを行うために生かされているものです。ですから私たちは、自分の計画や野心を捨て、神のみこころを求めていくなら、神は「みこころのままに」私たちの「うちに働いて志を立てさせ、事を行わせてくださるのです」(ピリピ2章13節)。 3.「主のみこころなら……生きていて、このことを、または、あのことをしよう」 これは、神のみこころと私たちの生涯の関係を教えています。私たちは、その生命を神にゆだねるとともに、神のみこころを求めて、それにふさわしい生活をしていくなら、その生涯は、神の遠大なご計画によって導かれ、「生きるにも死ぬにも私の身によって、キリストがあがめられる」のです(ピリピ1章20節)。 この「生命」と「生活」と「生涯」は、英語においてはみな同じ言葉(Life ライフ)であることは誠に興味深いものです。「生命」は、「生活」によって維持され、その総計が「生涯」ですから、この3つは決して切り離して考えることはできません。 私たちの「生命」と「生活」と「生涯」は、神に対してどうでしょうか。
2007.01.02
コメント(0)
-
説教要約 166
「新しい年を迎えて」 甲斐慎一郎 ヨシュア記3章1~4節 私たちが新しい年の初めに当たり、その出発点に立って、これから進もうとしている道について考えることは、何よりも大切なことです。私たちの前には、どのような道があるのでしょうか。 一、私たちが通ったことのない道 この個所において、つかさたちは「あなたがたは、今までこの道を通ったことがないからだ」(4節)と言いましたが、「この道」というのは、直接的にはヨルダン川を渡る道のことを指していました。しかしこのことはイスラエルの人々が、これから行くすべての道についても同じように言えることです。 私たちがこれから歩もうとしている人生の道も、同じように私たちが通ったことのない道です。このことはキリスト者も世の人々も同じです。しかしキリスト者は、途中の道は分からなくても、出発点と目標点は、はっきりと分かっているということです。 イスラエルの人々はエジプトの国を出て、カナンの地に向かいましたが、キリスト者は罪の生涯を出て、天の御国に向かっているのです(ピリピ3章20節)。 ですから私たちは、一度も通ったことのない人生の道を進むために、次のような3つのことを心がけていなければなりません。 1.出発点である罪からの救いを明確にする。2.目標点である天の御国に向かう自覚を持つ。3.途中の道については信仰によって歩む。 二、キリストが通られた道 しかし私たちが通ったことのないこの道を、すでに通られた方がおられます。それはイエス・キリストです。キリストは、苦しみも弱さも涙も経験されたのであり(ヘブル4章18節、15節、5章7節)、「すべての点で、私たちと同じ」でした。人としてのキリストと私たちの違いは、ただ一つ「罪は犯され」なかったことだけです(同4章15節)。 しかしキリストは無実の罪を着せられ、私たちの代わりに罪とされました。これは誰も経験したことがない想像を絶する苦しみでした(マタイ27章46節)。このようにしてキリストは、私たちのために「苦しみを受け、その足跡に従うようにと」、私たちに「模範を残され」たのです(第一ペテロ2章21節)。 よく言われるように私たちが行く道のすべてにキリストが立っておられます。キリストは、私たちのために先にそこを通られ、「道を踏み固め、平らにしてくださったのです」(S・D・ゴードン)。 誰も通ったことがなく、踏み固められていないものは道ではありません。キリストは、ご自身のことを「道」であると言われました(ヨハネ14章6節)。これは、キリストが私たちのために神に至る道となってくださったという意味だけでなく、私たちのためにすべてのことを経験して、私たちが通りやすいように踏み固めてくださったという意味においても道なのです。 三、キリスト者が通るべき道 パウロは、晩年に「私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました」と告白しています(第二テモテ4章7節)。 1.勇敢に戦う生涯――私たちは、どんなに小さな良いことでも勇敢に戦って獲得しなければ、真に自分の身につきません。 2.走るべき道のりを走り終える生涯――私たちは、「いっさいの重荷とまつわりつく罪とを捨てて」、身軽になり、「忍耐をもって走り続け」なければなりません(ヘブル12章1節)。しかもコースを間違えずに、また完走するためには、途中で脱落しないように節制と計画性が必要です。 3.信仰を守り通す生涯――主は、私たちのためにいのちを捨ててくださいました。ですから私たちは、どんなことがあっても信仰を守り通さなければならないのです。
2007.01.01
コメント(2)
全31件 (31件中 1-31件目)
1