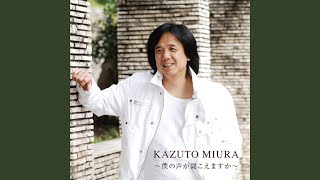2008年01月の記事
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-
説教要約 377
「信仰と固定観念(2)」 甲斐慎一郎 列王記、第二、5章8~14節 「わが父よ。あの預言者が、もしも、大きなこと(欄外の直訳)をあなたに命じたとしたら、あなたはきっとそれをなさったのではありませんか。ただ、彼はあなたに『身を洗って、きよくなりなさい』と言っただけではありませんか」(13節)。 これは、エリシャの使いにヨルダン川へ行って身を洗うように言われたナアマンが、怒って帰途についた時、彼のしもべたちが近づいて彼に言った言葉です。 一、罪と固定観念 ナアマンには財産や地位、また名誉や体面がありました。ですから彼は、正しいことであっても、小さいことのために自らの利益や体面が失われることを極度に恐れたのです。 主は「小さい事に忠実な人は、大きい事にも忠実であり、小さい事に不忠実な人は、大きい事にも不忠実です」と言われました(ルカ16章10節)。この「小さい事」は地上のものを表し、「大きい事」は天上のものを表しています(R・C・トレンチ)。 神とその救い(すなわち天上のもの)は大きなことであり、地上のものは小さなことです(ルカ16章10~12節)。しかし身勝手な固定観念にとらわれている人は、自らの目先の利益や体面に直接関わりのあるものを大きなこととし、それに関わりのないものを小さなこととしてしまいます。 このような人は、事の大小が転倒しているので、神の命じられた救いに関する大きなことが小さなことにしか見えないために、自らの利益や体面を失わせるものとして激しく怒ります。このように身勝手な固定観念にとらわれて、事の大小が転倒し、ただ自らの利益や体面のために怒ることは罪なのです。 二、恵みと固定観念 ナアマンは、自らの狭い固定観念にとらわれている間は、小さなことをすることができず、そのために救いも恵みも受けることができませんでした。しかし彼が自分の固定観念という小さな殻から抜け出して、神の命じられた小さなことをした時、大きな神の恵みを受けたのです。 身勝手な固定観念にとらわれている人は、何か大きなことをしなければ、神の恵みを受けることはできないと考えています。このような人は、何でも当然であるかのように考えてしまうので、神の目には大きなことでも人の目に小さく見えることを行うことができず、ただむやみに大きなことをしようとするのために、感謝も感激もなく、幻滅の悲哀を味わって恵みを受け損なってしまうのです。 しかし身勝手な固定観念にとらわれていない目の開かれた人は、何でもないような小さな出来事の中にも、大きな神の恵みを見いだして喜ぶことができるのです。 三、信仰と固定観念 「ナアマンは……神の人の言ったとおりに……した。すると彼のからだは……きよくなった」(14節)。ナアマンは、大きなことを命じられて、それを行うことが救いであると考えていました。しかし神は彼に大きなことをするように言われたのではなく、誰にでもできる小さなことを命じられました。 ナアマンにとって最も必要なことは、からだのいやしではなく、目先の利益や体面を捨てる罪からの救いでした。もし大きなことを命じられて行うなら、ますますこの罪を助長してしまったことでしょう。ナアマンにとっては、神の命じられた小さなことをすることが救いだったのです。 人間の目には小さなことでも、神の目に大きなことをすることが真の信仰です。神への信仰というものは、神の目には大きなことであっても、人間の目には小さく見えます。私たちは、人の目から事の大小を見る身勝手な固定観念を捨てて、神の目から事の大小を見て物事を行うことが必要なのです。
2008.01.29
コメント(0)
-
説教要約 376
「信仰と固定観念(1)」 甲斐慎一郎 列王記、第二、5章8~14節 ナアマンは怒って……言った。「何ということだ。私は彼がきっと出て来て、立ち、彼の神、主の名を呼んで、この患部の上で彼の手を動かし、このツァラアトに冒された者を直してくれると思っていたのに」(11節)。 これは、ナアマンがツァラアトを直してもらうためにエリシャの家に行ったところ、エリシャが使いをやってナアマンにヨルダン川へ行って身を洗うように命じたので、彼は、それに腹を立てた時に言った言葉です。 一、人間と固定観念 固定観念とは「それが正しいと一度思い込んでしまって、変えることの出来ない考え」であると辞書には記されています。 この「きっと……してくれると思っていたのに」というナアマンの言葉は、身勝手な固定観念の典型的なものです。ナアマンは、神の導きや摂理を信ぜず、ただ自らの狭い考えで、自分や他の人の行動や在り方を勝手に決め込んでしまったのです。 このナアマンの言葉を私たちに当てはめるなら、次のようになります。 ◇人に対して――「私は、このような人間であり、これこれのことをしているのだから、あの人は私に対してこうするに違いない」とか、「あの人は、このような人間になるべきであり、このような道を歩むのが最善だと思う」と決めてかかることです。 ◇神に対して――「私は、このような人間であり、これこれのことをしているのだから、神は私を苦しみに会わせず、もっと祝福してくださるにちがいない」と思い込むことです。 ◇自分に対して――「私は、これこれのことをして、このような道を歩むのが最善なのだ」と勝手に決め込むことです。 人間は、神を信じても、神の導きと摂理を信じない限り、このような身勝手な固定観念にとらわれてしまうのです。 二、罪と固定観念 「こうして、彼は怒って帰途につ」きました(12節)。このナアマンの態度は、このような固定観念にとらわれている人が――自分の思いどおりに人間や物事が動いている間は問題がありませんが、しかし自分の思いどおりにならないのが現実の世界です。――自分の思いどおりにならない時に陥る罪の姿です。 私たちも、このような固定観念にとらわれている限り、自分の思いどおりにならないと、自分の心を悩ませ、苦しめて、失望落胆や自暴自棄に陥るだけでなく、神と人に対して不平や不満やつぶやきを言い始め、それが次第に怒りや憎しみに変わり、遂には非難や中傷そして復讐にまで爆発してしまうのです。 ある人が他人である私の思いどおりに歩むことが、その人にとって最善のことでしょうか。その人の本当に歩むべき道を私が決める権利があるでしょうか。ましてその人が私の思いどおりに歩まないからと言って、怒るのは正しいことでしょうか。私たちは自分の歩みでさえも自分で決めることができないのですから(エレミヤ10章23節)、自分の思いどおりにならないからと言って、悩んだり嘆いたりしてはなりません。このように固定観念にとらわれて自分の思いどおりにしなければ気がすまないという心こそ罪なのです。 三、救いと固定観念 「神の人の言ったとおりに……した。すると……きよくなった」(14節)。 私たちも、自分の狭い固定観念を捨てて、神の言葉を受け入れる時、罪から救われることができます。そして私たちが、この救いを持ち続けていくための秘訣は、自分に対する神の導きと摂理を認めるとともに、他の人には自分と違った神の導きと摂理があることを認めて、自分の思いどおりではなく、神の思いどおり、すなわち神のみこころのとおりになればよいのだということに徹することなのです(ルカ22章42節)。
2008.01.26
コメント(0)
-
説教要約 375
「信仰の効用(3)信仰を建て上げる三要素」 甲斐慎一郎 出エジプト記、3章6節 真の信仰を形造る三要素は、敢行と忍耐と熱望ですが、敢行は獲得力、忍耐は持久力、熱望は推進力ということができます。この三つの力の均衡が取れていくことが自らの信仰の成長と人間関係の問題を解決する鍵です。 一、信仰の成長を妨げるもの 人間関係の問題は、語る資格がなく、神と人に仕えず、行動が伴わない人が勝手な批判をする時に起きます。 敢行に表れるアブラハム型の人は、忍耐の欠如によって厳しく人を批判する問題がありますが、神のことばを信じて敢えて行う行動が伴うので、この点においては問題は少ないということができます。 忍耐に表れるイサク型の人も、忍耐の偽物である怠慢に陥る危険性はありますが、行動が伴わないことは批判しないので、この点においては問題は少ないということができます。 しかし熱望に表れるヤコブ型の人は、忍耐の欠如による失敗のほかに、イスラエル人のように「その熱心は知識に基づくものでは」ない(ローマ10章2節)という問題をはらんでいます。すなわち熱望は、まだ心の段階で、行動に移る敢行の一歩手前ですから、行動が伴わず、口先だけの熱心になりやすいということができます。たとえ行動が伴ったとしても、目的を得るためには手段を選ばない行動に陥り易いところがあります。 ヤコブは、父イサクと兄エサウを欺いたので、伯父ラバンと子どもたちに欺かれています。彼は、「私のたどった年月は百三十年で……ふしあわせで」(創世記47章9節)と述懐しているのも無理からぬことでしょう。 ヤコブは、知識に基づかない熱心さのゆえに、貧乏くじを引くまいと焦りましたが、結果的には、神によって貧乏くじをひかされているかのようです。それにもかかわらず、「ヤコブの神」と言われる祝福を受けたのは、ただ計り知れない神の恵みによるのです。 二、信仰を建て上げる三要素 信仰者の務めは、人をつまずかせず、人を建て上げていくことです(ローマ14章1、19節、15章1、2節)。信仰の弱い者をつまずかせるのは、敢行や熱望の欠如よりも、忍耐の欠如によることが多いということができます。堪忍袋の緒が切れて、怒りが爆発する時、人をつまずかせるからです。その時、加害者は、信仰の強いアブラハム型やヤコブ型の人が多く、被害者は信仰の弱いイサク型の人が多いのではないでしょうか。 被害者は、心の中で加害者を赦せばよいのですが、加害者は、被害者に謝罪するまで罪は赦されません(マタイ5章22~26節)。アブラハム型やヤコブ型の人は、不得手な忍耐を身につけていくことによって信仰が成長し、円熟していきますが、それまでの間、忍耐の欠如によって弱い者をつまずかせる危険性があります。信仰の弱い者をつまずかせる罪は決して小さくありません(マルコ9章42節)。 イサク型の人は、不得手な敢行や熱望を身につけていくことによって信仰が成長し、円熟していくので、信仰の弱い者をつまずかせる危険性は小さいということができます。 現実の世界は、どれほど敢行と熱望の信仰をもって奉仕しても、一朝一夕にできるものではなく、いつも順風満帆で、物事が運ぶとは限らず、必ず苦難があり、忍耐を要することが多いもので、完成するまで、神のお取り扱いを受けて、砕かれ、教えられなければならない多くの信仰の学課があります。 旧約時代のヨセフは、まず孤独と人に仕えることと中傷や非難を耐え忍んだからこそ、立派な指導者になり得たのです。指導者の運命また十字架は、この孤独と人に仕えることと中傷や非難を受けることです。 どのような信仰の型の人であれ、神はヨセフのように、1.まず忍耐、次に希望、最後に愛を学ばせ、2.そこから生じる健全な熱望と敢行を身につけさせることによって、3.他の人をつまずかせず、人の徳を高める器に私たちを造られます。 これこそ信仰を建て上げる三要素です。
2008.01.23
コメント(2)
-
説教要約 374
「信仰の効用(2)信仰を形造る三要素」 甲斐慎一郎 出エジプト記、3章6節 世の中には様々な問題や課題が絶えませんが、その中で人間関係の問題ほど複雑で厄介なものはないでしょう。この根本的な原因は罪ですが、たとえ罪が赦され、きよめられたとしても、性格の相違についての正しい認識が欠けているなら、人間関係の問題は決して解決しないでしょう。信仰と性格の関係について考える時、忘れてはならなのは大切なことは、信仰というのは、どのようなもので形造られているかということです。 そこで信仰を形造る三要素について学んでみましょう。 一、信仰の三つの型について 「アブラハムは、相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従い、どこに行くのかを知らないで、出て行きました」(ヘブル11章8節)とあるように、神の言葉を信じて敢えて行動を起こした(すなわち敢行した)人です。 信仰の積極面は敢行です。しかしアブラハムは忍耐深さに欠けていたので、女奴隷ハガルによって子どもを儲けるなど、多くの失敗をしています。「敢行」に表れる信仰、これがアブラハム型の信仰です。 アブラハムの子イサクは、父とは全く反対で、どんなに大切なものでも、それを得るのに焦ったり、争ったりすることなく、どこまでも柔和にふるまい、謙譲な態度を取り、神が与えてくださるまで困難を耐え忍んで待ち望んだ人です(創世記26章14~22節)。 信仰の消極面は忍耐です。しかしイサクは信仰の積極面である敢行は不得手であったために、優柔不断で、その子ヤコブに欺かれています。「忍耐」に表れる信仰、これがイサク型の信仰です。 イサクの子ヤコブは、これまた異なり、飽くなき探求心によって、どこまでも神の祝福を求め続けた熱心な人です。しかし彼は、その名前(押しのける者)のように、父イサクと兄エサウを欺いてまで熱心に神の祝福を求めたために、自分の息子たちやおじラバンにだまされています。「熱望」に表れる信仰、これがヤコブ型の信仰です。 二、信仰と性格について 真の信仰は、神の言葉を信じて踏み出す敢行と、神の言葉を待ち望む忍耐と、神の祝福を熱心に求める熱望の三つを含んでいます。 しかし人はみな、先天的な性格や性質が異なっており、また育った環境による後天的な性格や性質も違っています。ですから人は、信仰を持つなら、罪から救われますが、持ち前の性格や性質は変わり難い面があるために、その人の性格や性質からにじみ出る信仰になり易いのです。すなわち、その性格によって、ある人は敢行の面の強い信仰、他の人は忍耐の面の強い信仰、別の人は熱望の面の強い信仰になるのです。 三、信仰の成長について 私たちは、信仰に成長するために次のような二つのことが必要です。 1.他の信仰の型の人を受け入れること 人は、それぞれ性格や性質、また信仰の型が異なるので、自分の信仰の型に他の人を合わせようとしたり、異なる信仰の型の人を非難したり、排斥したりしてはなりません。 アブラハム型の人はイサクやヤコブの信仰に、イサク型の人はアブラハムやヤコブの信仰に、ヤコブ型の人はアブラハムやイサクの信仰に、それぞれ必ず学ぶところがあるはずであり、また学ばなければなりません。私たちは、信仰に成長するために他の信仰の型の人を受け入れることが必要です。なぜなら神は、「アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神」だからです(出エジプト3章6節)。 2.自分に不得手なものを求めること 私たちは、信仰に成長するために信仰の三つの面である敢行と忍耐と熱望が片寄ることなく、均衡が取れるように自分に不得手なものを神に祈り求めることが必要です。 そしてこの信仰の三つの面に均衡が取れていた信仰者は、ヤコブの11番目の子である四代目のヨセフではないでしょうか。
2008.01.20
コメント(2)
-
説教要約 373
「信仰の効用(1)信仰を成長させる三要素」 甲斐慎一郎 創世記、50章15節 私たちが神への信仰を持つなら、神は私たちの信仰に応えて私たちの心に働いて良い実を結ばせてくださいます。そこで信仰の効用について三回に分けて考えてみましょう。◇信仰の効用(1)――信仰を成長させる三要素◇信仰の効用(2)――信仰を形造る三要素◇信仰の効用(3)――信仰を建て上げる三要素 一、忍耐を生じさせる信仰 聖書は「信仰がためされると忍耐が生じる」と教えています(ヤコブ1章3節)。 ヨセフは、祖先から良い信仰を受け継ぎ、神を愛し、罪を憎む青年でしたが、彼の温室育ちの信仰は、嵐が吹き荒れる厳しい現実の世界で試されなければなりませんでした。 ヨセフは、兄たちに妬まれて穴に投げ込まれましたが、まず孤独に耐えなければなりませんでした。そしてエジプトに売られて奴隷になりましたが、次にしもべとして人に仕える忍耐を学ばなければなりませんでした。さらにポティファルの妻に訴えられ、無実の罪を着せられ、投獄されましたが、第三に中傷や非難を耐え忍ばなければなりませんでした。 信仰が厳しい現実の世界で生かされていくための第一の要素は忍耐です。信仰は「見えないものを確信させる」もので(ヘブル11章1節)、神の約束と保証に立って、遠くの良いことを見ることです(同11章13節)。決して霊的な近視眼ではありません。 ですから現在の一時的な孤独や苦難の中でも、つぶやかず、疑わずに、忍耐をもって黙々と神と人とに仕えていくことができます。信仰は、人を焦らせず、性急にさせずに、神のよしとされる時まで耐え忍ばせるものなのです。 二、希望を生じさせる信仰 聖書は、「信仰により……望み」を抱くと記しています(ガラテヤ5章5節)。 ヨセフは、兄たちによって穴に投げ入れられる時には理解することができずに苦しみましたが、エジプトに奴隷に売られてからは、嘆いたり、つぶやいたり、くよくよしたりせずに、喜々として働いています。また無実の罪を着せられて牢獄に入れられても、嘆いたり、つぶやいたり、くよくよしたりせずに、かえって人を慰め、励ましています。 信仰が厳しい現実の世界で生かされていくための第二の要素は希望です。「心に憂いがあれば気はふさぐ」のであり(箴言15章13節)、希望を失ったなら、気力がなくなり、自暴自棄に陥ってしまいます。 しかし信仰は私たちに希望を与えます。なぜなら信仰は、自分の周囲の様々な人間や境遇は、第二原因に過ぎず、第一原因は神であることを私たちに教えるからです。信仰者は「雀の一羽でも……父のお許しなしには地に落ちることは」ないことをよく知っています(マタイ10章29節)。信仰は、過去のいかなることにもとらわれず、くよくよせずに第一原因である神を信じて希望的観測をするのです。 三、愛を生じさせる信仰 聖書は「愛によって働く信仰」が大事であると教えています(ガラテヤ5章6節)。 ヨセフは、過去を回顧し、兄たちの嫉妬やポティファルの妻の中傷や献酌官長の忘恩など、人間の罪や失敗をも凌駕して余りある神の支配と導きを現実に見ながら、今さらのように神の愛の広さ、長さ、高さ、深さの計り知れないことを知って感激したにちがいありません。この神の愛を現実に知ったヨセフは、兄たちに対して恨みや復讐心などはみじんもなく、ただあるのは赦しと愛だけでした。 信仰が厳しい現実の世界で生かされていくための第三の要素は愛です。ヨセフは、その人の信仰の有無を問わず、周囲の人は自分の姿を写す「鏡」(箴言27章21節)、自分を磨く「砥石」(同27章17節)、神に仕えるための「相手」(マタイ25章40、45節)であることを知ったのでしょう。 しかしこれは、自尊心が強く、体面を重んじ、誇りの高い人には受け入れがたいものです。ただヨセフのように、様々な逆境や苦を通らせられて、謙遜と自己否定を学んだ人のみ愛と感謝をもって受け入れることができるのです。
2008.01.17
コメント(4)
-
説教要約 372
「御言葉への応答(3)御言葉を実行する」 甲斐慎一郎 ヤコブの手紙、1章19~25節 ヤコブは、信仰と行為とは切っても切れない不可分の関係にあり、真の信仰は、必ず行為が伴うことを私たちに教えています。 ヤコブの周囲には、律法学者やパリサイ人がいましたが、主は、「彼らは言うことは言うが、実行しないからです」(マタイ23章3節)と言われました。ヤコブは、口先だけの、行いの伴わない、浅薄な信仰をいやというほど見ていたことでしょう。 主は、山上の説教において「わたしに向かって『主よ、主よ』という者がみな天の御国に入るのではなく、天におられるわたしの父のみこころを行う者が入るのです」(マタイ7章21節)と説教されました。ヤコブは、小さい頃からそのようなことを教えられたにちがいありません。 この手紙を章毎に五つに分け、行いに表される真の信仰について学んでみましょう。 1.一章、境遇または環境の問題――御言葉を聞き、素直に受け入れることに表される信仰 この章の前半には、試練や誘惑、また貧しい境遇や富んでいる境遇について記され、後半には、御言葉を聞くことと、素直に受け入れること、そしてその結果、罪から救われて新しく生まれることと御言葉を実行することについて記されています(22、25節)。 真の信仰は、まず御言葉を聞いて、素直に受け入れ、罪から救われて新しく生まれることに表れます。その結果、すべての良い贈り物は神から下り、悪の誘惑は、自分の欲に引かれるからであることを知って、私たちは、どのような境遇や環境の中でも、すべてのことを働かせて益としてくださる神によって喜ぶことができるようになるのです。 2.二章、対人関係または隣人愛の問題――神の律法を守ることに表される信仰 この章の前半には、人をえこひいきすることについて記され(1、9節)、後半には、隣人を自分と同じように愛するという最高の律法について記されています(8、16節)。 次に真の信仰は、神の律法を守ることに表れます。対人関係の問題は、人に対して偏見を抱き、人をえこひいきして、隣人への愛がないことが、その原因だからです。 3.三章、言葉または舌禍の問題――神からの知恵を持つことに表される信仰 この章の前半には、舌の禍について記され、後半には、神からの知恵について記されています。主イエスは、「心に満ちていることを口が話すのです」(マタイ12章34節)と言われましたが、言葉は私たちの心の表現です。私たちは、舌がどんな禍を引き起こすかを知りつつも、黙っていることは許されず、神と隣人の前に正しく語ることが求められているのです(9、10節)。 真の信仰は、第三に神からの知恵を持つことに表れます。私たちは、心に神からの知恵を与えられることによってのみ、舌を制御して正しく語ることができるからです。 4.四章、世俗または自己愛の問題――神を恐れて、へりくだることに表される信仰 この章の前半には、神を無視し、神に敵対している世について記され、後半には、神を恐れて、へりくだることが記されています。神を無視し、神に敵対している世を愛することは、とりもなおさず、神を恐れず、自分で何でもできるかのように高ぶっていることです(4、15、16節)。 真の信仰は、第四に神を恐れて、へりくだることに表れます。このようにする時にのみ、私たちは、汚れた世俗を離れて、聖い生活を送ることができるからです。 5.五章、苦難または迫害の問題――忍耐と不屈の祈りに表される信仰 この章の前半には、苦難や迫害について記され、後半には、忍耐と不屈の祈りについて記されています。この世の中は、不可解な出来事や矛盾に満ち、主が来られて、すべてを正しくさばかれるまで、完全な解決はないでしょう(8、16節)。 真の信仰は、最後に忍耐と不屈の祈りに表れます。なぜなら最後まで耐え忍ぶ者のみ、救われるからです(マタイ24章13節)。
2008.01.14
コメント(0)
-
説教要約 371
「御言葉への応答(2)御言葉を信じる」 甲斐慎一郎 ヘブル人への手紙、4章1~13節 ヘブル人への手紙の著者は、荒野を旅したイスラエルの民および新約のキリスト者を問わず、神の言葉を聞く時に大切なことは信仰であることを次のように述べています。 「福音を説き聞かされていることは、私たちも彼らと同じなのです。ところが、その聞いたみことばも、彼らには益になりませんでした。みことばが、それを聞いた人たちに、信仰によって、結びつけられなかったからです」(2節)。 それで「信じる」ということについて、この箇所から三つのことを学んでみましょう。 一、信仰の時――今日 このヘブル人への手紙の3章と4章には、「きょう」という言葉が5回も記されていますが(3章7、13、15、4章7節に二回)、これは、どのような意味でしょうか。聖書を読んだり、説教を聞いたりしたならば、何が何でも、すぐに信じなければならないということでしょうか。そうではありません。これは、信仰というものは常に現在のものでなければならないことを私たちに教えています。 神は時間を超越された方ですから、「神にとっては過去や未来というものはなく、すべての事柄は等しく現在です」(ジョン・ウェスレー)。また人間の場合も、過去のことは、いまさらどうすることもできず、未来のことは不確かですから、確実に自分の時間として用いることができるのは、現在のみです。 神は、聖霊を通して、その古い御言葉を私たちにの心に新しく語りかけられる時が必ずありますが、その時こそ信じる時です。そしてその信仰は、常に新鮮に「きょう」という現在的なものでなければならないのです。 二、信仰の根拠――神の約束 この手紙の6章には、信仰の根拠について詳しく述べられています。6章12節から17節の間に「約束」という言葉が4回も記されています(6章12、13、15、17節)。 私たちが「信仰を持つ」とか「「信じる」という時、その信仰は何を拠り所としているでしょうか。神の存在でしょうか。神の愛とか真実さという神のご性質でしょうか。または神の言葉でしょうか。もちろん私たちは、神の存在を信じ、すばらしい神のご性質を信じ、また聖書を神の言葉であると信じなければならないことは、言うまでもありません。 しかしこれらのことを前提にしながらも、もっと中心的で大切な信仰の根拠があります。それは私たちに対する「神の約束」です。旧約聖書は、神が人と結ばれた「古い契約」であり、新約聖書は、神が人と結ばれた「新しい契約」ですが、それは同時に私たちに対する「神の約束」でもあるのです。 三、信仰の結果――安息 ヘブル人への手紙の3章と4章に、もう一つ多く出て来る言葉があります。それは、11回も記されている「安息」です(3章11、18、19節、4章1、3、5、6、8、10、11節)。 「彼らが安息に入れなかったのは、不信仰のためであった」(3章19節)とか「信じた私たちは安息に入るのです」(4章3節)という言葉は、信じた結果は安息であることを私たちに明白に教えています。私たちは、自分がほんとうに信じたのか、信じなかったのかということは、自分の心に安息があるかどうかですぐに分かります。この安息こそ、いわゆる頭だけで信じている「頭脳的な信仰」を「真の信仰」であると錯覚している誤りから私たちを救うものです。 人々がイエスに「私たちは、神のわざを行うために、何をすべきでしょうか」と聞いた時、イエスは、「あなたがたが、神が遣わした者を信じること、それが神のわざです」と答えられました(ヨハネ6章28、29節)。 私たちは、自分のわざを終えて(10節)、神とその約束を信じるなら、この安息に入ることができます。そしてこの安息に入った者のみ、神の約束を忍耐をもって待つことができるだけでなく、その約束のものを得ることができるのです(ヘブル10章35、36節)。
2008.01.11
コメント(0)
-
説教要約 370
「御言葉への応答(1)御言葉を聞く」 甲斐慎一郎 ヘブル人への手紙、2章1~4節 ヤコブは、神の言葉について、「聞く」こと、「信じる」こと、「実行する」ことについて述べていますが(1章22、21節)、これこそ御言葉に対する三つの応答です。◇御言葉への応答(1)――御言葉を聞く◇御言葉への応答(2)――御言葉を信じる◇御言葉への応答(3)――御言葉を実行する 言葉を覚えるために最も必要なことは、聞くことです。人格を持ち、言葉を語る人間にとって、聞くということほど大切なことはありません。パウロが「信仰は聞くことから始まり」と述べ(ローマ10章17節)、ヤコブが「聞くには早く……しなさい」(ヤコブ1章19節)と勧めているのも、もっともなことではないでしょうか。 このヘブル人への手紙の2章から4章までの間に「聞く」という言葉が8回も記されています(2章1、3節、3章7、15、16節、4章2、7節)。 それで「聞く」ということについて、聖書の中から三つのことを学んでみましょう。 一、私たちは、なぜ聞かなければならないのでしょうか 古今を通じて、また洋の東西を問わず、政治の世界であれ、経済の世界であれ、またどのような世界であれ、人民の声は何か、世論はどうか、世界の動向はどうなっているのか、ということに耳を傾けず、また様々な情報を適確にとらえずして、大成したり、成功したりした人はひとりもいないでしょう。 現代は情報化時代であり、人々は、この世に取り残されず、賢く生き抜くために適確な情報を得ようと汲々となっています。 しかしここに世のどんな情報よりも大切な情報があります。それは、この天地万物を造られ、この世界を支配しておられる神の声であり、神の言葉です。世の情報は私たちの地上における生活を左右します。しかしこの神よりの天の情報は、私たちの永遠の運命を決定するのです。 「神は……語られました」(ヘブル1章1、2節)。「ですから、私たちは聞いたことを、ますますしっかり心に留めて、押し流されないようにしなければなりません」(1節)。 二、聞くことに密接に関係のあることは、何でしょうか 聖書は、聞くということに密接な関係にあることを5つ教えています。 1.「イエスの話を聞こうとして」(ルカ15章1節)。 聞くということに密接に関係のある第一のことは、願うことであり、求めることです。 2.「父から聞いて学んだ者は」(ヨハネ6章45節)。 聞くということに密接に関係のある第二のことは、知ることであり、学ぶことです。 3.「羊はその声を聞き分けます」(ヨハネ10章3節)。 聞くということに密接に関係のある第三のことは、判別し、判断することです。 4.「聞いたことを……しっかり心に留め」(ヘブル2章1節)。 聞くということに密接に関係のある第四のことは、信じて心に留めることです。 5.「羊は、彼の声を知っているので、彼について行きます」(ヨハネ10章4節)。 聞くということに密接に関係のある第五のことは、従うことです。 三、聞くということは、私たちにとって何を意味するのでしょうか 私たちにとって聞くか聞かないかということは、主が「聞く耳のある者は聞きなさい」(マルコ4章9、23節)と言われたように、私たちの心の問題です。 私たちは、何を聞こうとしているか、何を聞いているかによって、私たちの実質が計られ、また私たちが神の御声を聞こうとしているかどうかによって、私たちの心が神の前にどうであるかが計られます。私たちが信仰者として、また一人の人間として成長していくかどうかは、神の御声と人の声を正しく聞くか、聞かないかにかかっているのです。
2008.01.08
コメント(0)
-
説教要約 369
「神をあがめる生涯」 甲斐慎一郎 マタイの福音書、5章13~16節 一、人間の創造と礼拝 東京フリー・メソジスト教会の教理問答集には、次のように記されています。問……人間の創造された目的は何ですか。答……神の栄光を現し、永遠に神を喜び楽しむためです(創世記1 章27節、イザヤ43章7節、エペソ1章5、6節、第一ペテ ロ5章10節)。 神の栄光を現すこと、言い換えれば神があがめられることについて、聖書には、多くのことが記されていますが、おもなものは次のような5つです。 1.「神を神としてあがめ」る(ローマ1章21節、第一ペテロ3章15節)、「霊とまことによって父を礼拝する」(ヨハネ4章23節)。 2.「あなたがたの光を人々の前で輝かせ、人々があなたがたの良い行いを見て、天におられるあなたがたの父をあがめるようにしなさい」(マタイ5章16節、ピリピ1章20節)。 3.「ふさわしく奉仕し……キリストを通して神があがめられる」(第一ペテロ4章11節)。 4.「異邦人も……神をあがめるようになる」(ローマ15章9節)。 5.「すべての人々に惜しみなく与えていることを知って、神をあがめる」(第二コリント9章13節)。 第一は、神を礼拝すること、第二は、私たち自身や良い行いを通して神があがめられ、第三は、ふさわしい奉仕、第四は、福音宣教の前進、第五は、惜しみなく与えることを通して神があがめられることを教えています。 二、聖日礼拝と説教 人間は、神の栄光を現すために創造されました。第一は、聖日に教会に集まって神をあがめることです。第二から第五は、日々の生活と歩みにおいて神をあがめることですが、そのようになるためには、礼拝に出席し、説教を聞き、それに応答することが必要です。 私たちは、説教に応答することによって、人々が私たちの良い行いを見て神をあがめる人に、ふさわしく神に奉仕することによってキリストがあがめられる人になり、また福音を宣べ伝える人、惜しみなく与える人に変えられ、人々が神をあがめるようになるのです。 三、説教と礼拝の生活 ヤコブは、みことばを「聞く」こと、「信じる」こと、「実行する」ことについて述べていますが(1章22、21節)、これこそ説教に対する3つの応答です。 説教者は、説教する準備をしますが、会衆に語る前に祈りのうちに神のことばを聞き、神のことばを信じ、神のことばを実行するように神のお取り扱いを受けて講壇に上り、講壇において説教する時は、会衆とともに神を礼拝しているのです。 1.神のことばを聞くこと 私たちは、説教者が聖霊に満たされて神のことばを正確に語ることができるように、そこで語られる神のことばが聖霊によってわかり、この礼拝において神が語ってくださることを明確にとらえることができるように祈りつつ、説教にに耳を傾けなければなりません。 2.神のことばを信じること しかし私たちは、説教を「ただ聞くだけの者であっては」ならず、「すなおに受け入れ」る、すなわち信じなければなりません(ヤコブ1章22、21節)。確かにキリスト者は、神のことばを信じていますが、この礼拝において説教者を通して今、神が語られたことを新しく信じることが必要です。そうするなら、新しい神体験をし、神のことばを実行することができる人に変えられるのです。 3.神のことばを実行すること これから始まる一週間、礼拝説教で教えられたこと、示されたこと、信じたこと、新しい神体験をしたことを毎日の生活において実行することを祈りのうちに神に約束し、礼拝を終えることです。 このようにする時、新しく始まる一週間、私たちの日々の生活と歩みを通して神があがめられ、このことを毎週、行うなら、私たちの一生の間、神があがめられます。これこそ神が求めておられる真の礼拝です。
2008.01.05
コメント(0)
-
説教要約 368
「目標を目ざして(2)」 甲斐慎一郎 ピリピ人への手紙、3章13、14節 二、前のものに向かって進むこと 「前のもの」とは、未来や将来のことではありません。パウロは、言葉を続けて、「キリスト・イエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために」と述べ、殉教の死を前にして、「今からは、義の栄冠が私のために用意されているだけです」と告白しています(第二テモテ4章8節)。これは、主人である神から「よくやった。良い忠実なしもべだ」(マタイ25章21、23節)とお褒めの言葉を頂くことです。この「神の栄冠」や「義の栄冠」こそ「前のもの」です。 しかしこの栄冠を得るためにはジョン・ウェスレーが「根本を撃つ」という神学論文で述べているような「きよめ」が必要です。 「今神にむかって生きている者以外、後にだれも神とともに生きないであろう。地において神の像(神の聖と愛と義と真実)をもつ者以外、だれも天において神の栄光を楽しまないであろう。現在罪から救われていない者は、だれも将来地獄から救われ得ない。この世で自分の中に神の国をもたなければ、だれも天において神の国を見ることはできない。天においてキリストとともに支配しようとする者は、だれでも地において自分を支配されるキリストをもたなければならない」(ジョン・ウェスレー著、野呂芳男訳「ウェスレーの神学」175頁、新教出版社、1963年)。 この「神の栄冠」や「義の栄冠」こそ私たちをひたむきに前に、進ませるものです。私たちは、神とキリストの贖いによる「救い」と「きよめ」を信じなければ、私たちをひたむきに前に進ませる「神の栄冠」や「義の栄冠」を得ることはできません。それでは前進も成長も期待することはできないでしょう。 三、目標を目ざして一心に走ること キリスト者にとって「神の栄冠」や「義の栄冠」を得ることは、最終的な目標ですが、それは、現在においては目に見えないものですから、その目標を達成するために、目に見える具体的な目標というものが必要です。 パウロの最終的な目標は、「キリスト・イエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得る」ことでした。しかしそのためにパウロは、「キリストの御名がまだ語られていない所に福音を宣べ伝え」(ローマ15章20節)、「神のご計画の全体を、余すところなく……知らせ」(使徒20章27節)、「聖徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストのからだを建て上げ」る(エペソ4章12節)という3つの目標を目ざして、一心に走りました。これは、私たちの目標ではないでしょうか。 1.私たちは、キリストの御名がまだ語られていない所に福音を宣べ伝えているでしょうか。 それはまだ福音を聞いていない遠い外国の人たちだけではありません。日本の、いや私たちのすぐ近くにいる家族や友人や知人の中に福音に耳を傾けようとしない人たちがいないでしょうか。私たちをあざけり、ののしり、私たちに反抗する人たち、私たちとうまが合わず、接することが難しく、私たちの嫌いな人たちの中にまだ福音を聞いていない人たちがいないでしょうか。福音は、貴賎上下の別なく、人種の差別なく、あらゆる階層のすべての人に宣べ伝えなければなりません。 2.私たちは、神のご計画の全体、すなわち聖書全体を隅から隅まで語っているでしょうか。 自分の好きな聖句や得意な聖書の箇所だけを話したり、人の嫌がる罪や神のさばきのことなどを語ることを避けたりしていないでしょうか。「健全な教えに耳を貸そうとせず、自分につごうの良いことを言ってもらう」ことを願う人たち(第二テモテ4章3節)の誘惑に決して負けてはならないのです。 3.私たちは、どれだけ「自分自身と群れの全体とに気を配」っているでしょうか。 パウロは、自分が出発した後、狂暴な狼が群れを荒らし回ったり、いろいろな曲がったことを語ったりする人が起こることを知っていました(使徒20章28~30節)。教会は、改革しなければ、マンネリ化し、形式的になり、沈滞を招くだけでなく、曲がった方向に行く危険性があります。2000年に亙る教会の歴史には数多くの宗教改革がありました。私たちは、自分が属する教会と群れの建て上げのために、私たちに従ったり、賛成したりする人たちだけでなく、私たちに反対したり、改革したりする人たちの意見や考えに耳を傾け、常に軌道修正していかなければなりません。 神は、私たちがこのような目標を目ざして一心に走ることを求めておられるのです。
2008.01.02
コメント(2)
全10件 (10件中 1-10件目)
1