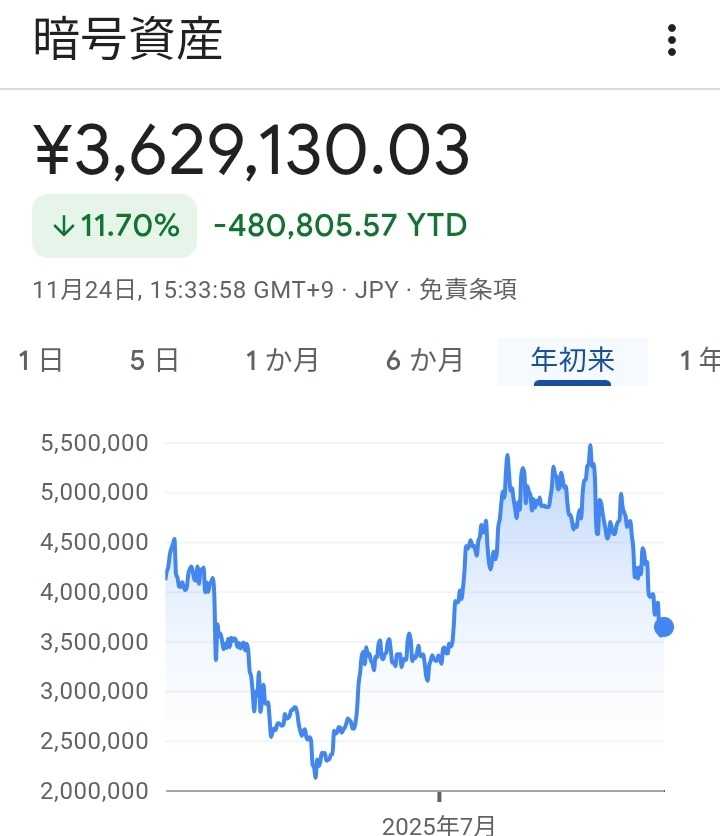2010年01月の記事
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-
説教要約 621
「不正な管理人」 甲斐慎一郎 ルカの福音書、16章1~13節 ルカの福音書の15章の三つのたとえ話は、キリスト者は、自然の世界から信仰によって超自然の世界に移った者であることを教えています。すなわちキリスト者は、その国籍が天にあり(ピリピ3章20節)、この世のものではありません(ヨハネ17章16節)。 しかしキリスト者(光の子ら)も、この世の子らとともに、この世に住んでいます。そこで光の子らは、この世においてどのような生き方をすればよいのか、ということを教えているのが「不正な管理人」の話です。 一、光の子らは、天上のものに賢くなければなりません(8節) 聖書は、「この世の子らは、自分たちの世のことについては、光の子らよりも抜けめがないものなので、主人は、不正な管理人がこうも抜けめなくやったのをほめた」と教えています(8節)。これは、どのような意味なのでしょうか。 この不正な管理人は、文字通り不正な人であり、彼は、まちがったことをしています。ですから私たちは、この不正な管理人を模範としたり、その行動を見習ったりすべきではないことは言うまでもありません。 このたとえ話は、「世の子らが、世のことに抜けめがないように、光の子らは、天のことに賢くなければならないことを教えています」(R・C・トレンチ)。世の子らは、この世をすべてとして、これに全力を注いで抜けめがないようにふるまっています。とすれば、なおのこと、光の子ら(キリスト者)は、天のことをすべてとして、それに全力を傾けて賢く行動しなければなりません。 二、光の子らは、天に宝を積まなければなりません(9節) 聖書は、「不正の富で、自分のために友をつくりなさい。そうしておけば、富がなくなったとき、彼らはあなたがたを、永遠の住まいに迎えるのです」と教えています(9節)。これは、どのような意味なのでしょうか。 不正の富とは、「朽ちず衰えず限りなく保つ天の宝を指すまことの富」に対して不正と言ったまでで、「定めのない朽ちるこの世の富」のことを指しています(R・C・トレンチ)。この不正な管理人は、真の愛もなく、ただ利己的な動機から、世の富を用いて債務者たちを助け、職を失った時に備えて、自分を迎えてくれる友をつくりました。 それならば、なおのこと、信仰によって罪から救われて、真の愛を与えられた光の子らは、どうして、この世の富を神を知らない人たちや信仰者のために用いることによって、天に宝を積み、永遠の住まいに迎えてくれる友をつくれないことがあるでしょうか。 三、光の子らは、地上のものに忠実でなければなりません(10~12節) この「小さい事」(10節)や「不正の富」(11節)や「他人のもの」(12節)は、地上のものを表し、「大きい事」(10節)や「まことの富」(11節)や「あなたがたのもの」(12節)は、天上のものを表しています(R・C・トレンチ)。 イエスは、地上のものに不忠実な人は、天上のものにも不忠実であるので、そのような人に天上のものをまかせたり、持たせたりすることはできないと言われました。 私たちは、この地上のものに忠実であるかどうかによって、天上のものを与えられるかどうかが決まります。すなわち、世の富を忠実に管理し、神と人のために正しく用いていくなら、天の宝が与えられます。しかし、それを浪費したり、乱費したりするなら、不正な管理人として、天の宝を失ってしまうのです。拙著「キリストの生涯の学び」131「不正な管理人」より転載
2010.01.31
コメント(0)
-
説教要約 620
「放蕩息子の父」 甲斐慎一郎 ルカの福音書、15章11~32節 この「放蕩息子」のたとえ話は、弟息子や兄息子に焦点を合わせると、失われた人が、信仰によって神に立ち返るという人間の側から見た救いを教えています。しかし、二人の息子の父に焦点を合わせると、神が、失われた人を捜し求めておられるという神の側から見た救いを教えています。 それで第三回目は、放蕩息子、いや二人の息子の父に焦点を合わせてみましょう。 一、なぜ父は、弟息子の求めるままに身代を分けてやったのでしょうか 弟息子が父に財産の分け前を求めた時、父は、「悪銭身に付かず」という諺のように、彼が放蕩して財産を使ってしまうことなど全く考えなかったのでしょうか。決してそうではありません。父には、そのようになることは、初めからわかっていました。 しかし父は、すでに心が離れてしまっている弟息子を無理に引き止めて、強制的に服従させてもむだであることをよく知っていました。それよりも彼が父を離れて放蕩し、様々な苦しみをなめることによって、自分の愚かさと罪深さをいやというほど知るようにさせたのです。これこそ、神が私たち人間をお取扱いになる方法です。 「神は、弟息子に罪を憎ませるため、彼に罪の苦さを味わわせただけでなく、彼を罪から救うために、彼を罪の悲哀の中から招かれました。弟息子は、このような懲らしめを受けなければ、おそらく神の招きの声を聞いても、それに聞き従わなかったでしょう。弟息子の上にふりかかった禍は、彼の罪に対する神の怒りの現れであることは言うまでもありませんが、見方を変えれば、彼に対する神の愛の現れなのです」(R・C・トレンチ)。 二、なぜ父は、少しも叱責しないで弟息子を子として迎えたのでしょうか 父は、弟息子を少しも叱責しないで、子として迎えました。それは、彼が父の家を出て行った時の姿や、遠い国へ行って放蕩していた時の姿とは、全く違った別人として帰って来たからです(R・C・トレンチ)。これが、弟息子の側の理由です。 父は、弟息子を少しも叱責しないで、子として迎えました。それは、父が弟息子の罪による苦しみや悩みを全部自分が負って、彼の罪をすべて赦したからです。これが、父の側の理由です。 この両者があったからこそ、父は弟息子を子として迎えたのです。もし弟息子が、家を出て行った時の姿や、遠い国で放蕩していた時の姿のままで帰って来たならば、また父が弟息子の罪による苦しみや悩みを全部彼に返していたならば、父は、弟息子を子として迎えることはできなかったでしょう。 三、なぜ父は、兄息子が知ったならば怒るような祝宴を催したのでしょうか 近所の人たちは、弟息子の方は親不孝で、とても悪い子だが、兄息子の方は親孝行で、りっぱな子だとうわさをしていたにちがいありません。弟息子のほうのうわさは当たっていました。しかし父は、兄息子のほうに関しては、近所の人たちがうわさをしているようには、決して思っていませんでした。 父は、弟息子を子として迎え入れ、祝宴を催すことによって、兄息子の心の中に隠れていた罪を自覚させ、悔い改めの必要を気づかせたのです。兄息子は、弟息子を迎え入れた父を責めることによって、自分の心の中に隠れていた罪が現れるとは、夢にも思っていなかったことでしょう。それは放蕩した弟息子にとっても同じでした。しかし父は、すべてを見通して、二人の息子を神に立ち返らせるために、このようにしたのです。拙著「キリストの生涯の学び」130「放蕩息子の父」より転載
2010.01.28
コメント(0)
-
説教要約 619
「放蕩息子の兄」 甲斐慎一郎 ルカの福音書、15章25~32節 「放蕩息子」のたとえは、弟息子の話だけで終わらず、兄息子の話が続いています。 それは、弟息子は「取税人や罪人たち」という「堕落した罪人」を、兄息子は「パリサイ人や律法学者たち」という「自称義人の罪人」を表し、どちらも救われなければならないことを教えているからです。 それで第二回目は、放蕩息子の兄に焦点を合わせてみましょう。 一、父の心を知ろうともしなかった兄息子 兄息子は、弟が帰って来た時、父が喜んで迎えたことをしもべから聞きました。「すると、兄はおこって、家にはいろうともし」ませんでした(28節)。このような態度の中に、父の心を知ろうともしなかった兄息子の姿を見るのです。 兄息子は、父が弟息子を迎え入れたことをしもべから聞いた時、怒る前に、父に直接話をして、その理由を聞く必要がありました。しかし、腹が立つだけで、父に聞く余裕などなかったのでしょう。 また兄息子は、父があの弟息子を迎え入れるからには、正当な理由があるにちがいないと考えてもよかったのです。しかし、そんなことは考えもしませんでした。 そして兄息子は、父があの弟息子を迎え入れるからには、たとえ自分には理解できなくても、深い理由があるかもしれないと思ってもよかったのではないでしょうか。しかし、そんなことは夢にも思いませんでした。 二、父の心と一致していなかった兄息子 兄息子は、父に「仕え、戒めを破ったことは一度もありません」と言いました(29節)。聖書は、律法学者やパリサイ人の姿は、「外側は人に正しいと見えても、内側は偽善と不法でいっぱいです」と教えています(マタイ23章28節)。彼は、外側の正しさだけで、内側の正しさがありませんでした。 また兄息子は、戒めを破ったことがないのに、子山羊一匹ももらえなかったので、父に文句を言いました(29節)。聖書は、イスラエル人は「自分自身の義を立てようとして、神の義に従わなかった」と教えています(ローマ10章3節)。彼は、自分の正しさを主張して、神の正しさに従いませんでした。 そして兄息子は、遊女におぼれて、身代を食いつぶして帰って来た弟息子のために、肥えた子牛をほふった父親を非難しました(30節)。パリサイ人のように、「自分を義人だと自任し、他の人々を見下してい」たのです(18章9節)。 このように兄息子が、父の心を知ろうともしなかったのは、彼の心が父(神)の心と一致していなかったからです。 三、父から心が離れてしまっていた兄息子 父は彼に、「おまえは、いつも私といっしょにいる」と言いました(31節)。これは、父が深い愛をもって兄息子を厳しく叱責した言葉です。それは、「私は、おまえにとってだれよりも勝る者ではないか」ということを意味しています(R・C・トレンチ)。 また父は「私のものは、全部おまえのものだ」と言いました(31節)。これは、父が熱心に兄息子に与えた警告の言葉です。それは、「おまえが、このことを認めるなら、私のものは全部おまえのものではないか」ということを意味しています(R・C・トレンチ)。 兄息子は、父をだれよりも勝る者と思わず、からだは父といっしょでも、心はそうではなく、父の心(喜び)を自分の心(喜び)とすることができませんでした。 このように兄息子の心が、父の心と一致していなかったのは、彼の心が父(神)から離れてしまっていたからです。拙著「キリストの生涯の学び」129「放蕩息子の兄」より転載
2010.01.26
コメント(0)
-
説教要約 618
「放蕩息子」 甲斐慎一郎 ルカの福音書、15章11~24節 イエスは、「失われた銀貨」のたとえを話された後、「放蕩息子」のたとえ話をされました。第一回目は、弟息子に焦点を合わせてみましょう。 一、神から離れている人間の姿 「弟は、何もかもまとめて遠い国に旅立」ちました(13節)。これは、その霊が「神を離れ、心において敵となって」、「罪過と罪との中に死ん」だことを表しています(コロサイ1章21節、エペソ2章1節)。 そして弟は、「そこで放蕩して湯水のように財産を使ってしま」いました(13節)。これは、神から与えられた財産である神の像を失ってしまったことを教えています。すなわち、神を知る知識も神を喜ぶ感情も神に従う意志もなくしてしまったのです。 「その国に大ききんが起こり、彼は食べるにも困り始め」ました(14節)。ききんは、穀物の欠乏のことであり、穀物は、この世の哲学や宗教や救いを表しています。神の像を失った罪人は、この世の哲学や宗教や救いという代用品で生きようとします。しかし彼には、その代用品さえなかったのです。 「彼は豚の食べるいなご豆で腹を満たしたいほどで」した(16節)。豚の食べるいなご豆で腹を満たす人とは、「忌みきらうべき汚れた者、不正を水のように飲む人間」を表しています(ヨブ一五章16節)。この世の哲学も宗教も救いもない弟は、何の歯止めもなく、あらゆる罪に陥ってしまったのです。 二、神に立ち返る人間の姿 弟は、「我に返」りました(17節)。彼は、その霊が神から離れ(遠い国)、その心が神の像を失い(放蕩)、この世の哲学や宗教や救いもなく(大ききん)、あらゆる罪に陥っていた(いなご豆)ことがわかったのです。 弟息子は、「おとうさん。私は天に対して罪を犯し......ました」と言いました(18節)。ダビデは、「私はあなたに、ただあなたに、罪を犯し......ました」と祈っています(詩篇51篇4節)。そのように彼は、神の前における罪を自覚して、罪の告白をしたのです。 弟は、「もう私は、あなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人のひとりにしてください」と言いました(19節)。神の前に砕かれて、身をまかせる決心をしたのです。 弟息子は、「立ち上がって、自分の父のもとに行」きました(20節)。「暗やみから光に、サタンの支配から神に立ち返」ったのです(使徒26章18節)。これこそ「いのちに至る悔い改め」です(同11章18節)。 三、神に迎えられる人間の姿 弟息子は、父親のもとに返った時、少しも叱責されることなく、かえって喜んで父親に迎えられました(20節)。これは、彼のすべての罪が赦されたことを教えています。 父親は、しもべたちに命じて、弟息子に一番良い着物を着せ、手に指輪をはめさせ、足にくつをはかせました(22節)。これは、キリストの「正義の外套」を着て(イザヤ61章10節)、義と認められ、また「御国を受け継ぐことの保証」として、「聖霊をもって証印を押され」(エペソ1章14、13節)、そして子としての権利を回復したことを表しています(R・C・トレンチ)。 父親は、弟息子のために盛大な祝宴を催しました(23節)。このように神は、罪人が救われることを何よりも喜ばれるのです。 父は、「この息子は、死んでいたのが生き返......ったのだから」と言いました(24節)。このように「あわれみ豊かな神は......その大きな愛のゆえに、罪過の中に死んでいたこの私たちをキリストとともに生かし」てくださったのです(エペソ2章4、5節)。拙著「キリストの生涯の学び」128「放蕩息子」より転載
2010.01.22
コメント(0)
-
説教要約 617
「失われた銀貨」 甲斐慎一郎 ルカの福音書、15章8~10節 イエスは、「迷い出た羊」のたとえを話された後、「失われた銀貨」のたとえ話をされました。この二つのたとえ話は、神が失われた人を捜し求めておられるということについては全く同じです。しかし両者には、次のような点について、様々な違いがあります。◇羊と銀貨という失われたものの違い。◇野原と家という失われた場所の違い。◇百分の一と十分の一という比率の違い。◇羊飼いと女の人という捜す人の違い。 天の御国のたとえ話においては、毒麦と地引き網、からし種とパン種、畑に隠された宝と良い真珠を捜している商人という二つが対になっており、それぞれに共通点とともに互いに補い合う対照的な相違点があります。そのように、この二つのたとえ話にも、互いに補い合う対照的な相違点があるのです。 一、失われた銀貨の姿 銀貨は、神のかたち--外面的な形ではなく、内面的な像--に創造された人間を表しています(創世記1章27節)。すなわち、神の像--霊、人格、不死、自由意志、支配する能力を持つとともに、聖、愛、義、真実という道徳的な姿--がきざまれた人間です。 ですから、失われた銀貨は、神の像を失った罪人を表しています。しかも、神の像を失ったのは、迷い出た羊のように無知のためではなく、知っていながら、神を離れた結果なのです(R・C・トレンチ)。 失われた銀貨は、「神について知りうることは......明らかである」にもかかわらず、また、「神を知っていながら、その神を神としてあがめず」、そして「神を知ろうとしたがらない」で、神にそむいて罪を犯し、滅びに向かっている罪人の姿を教えています(ローマ1章19、21、28節)。 二、捜し求める女の人の姿 迷い出た羊を捜し歩く羊飼いは、キリストを、放蕩息子の父は、父なる神を表していますが、女の人は、聖霊を表しています。 それとともに羊飼いがキリストですから、女の人はキリストの花嫁である教会であるということもできます(R・C・トレンチ)。なぜなら女の人が失われた銀貨を捜し求めるとは、聖霊が、神の像を失った罪人に罪を自覚させ、その罪を悔い改めるように働かれることであり、このことは、実際には、教会において行われるからです。 罪人は、「あかりをつけ」るように御言葉の光が照らされ(8節)、「家を掃いて」ちりが舞い上がるように(8節)、心の中に隠れていた罪が現れる教会において、罪を自覚し、その罪を悔い改めるようになります。聖霊は、キリスト者の集まりである教会を通して罪人の心に働かれるのです。 三、見つかった銀貨の姿 銀貨は、神の像がきざまれた人間を表し、失われた銀貨は、神にそむいて罪を犯し、その神の像を失った罪人を表していることは、すでに述べた通りです。ですから、見つかった銀貨は、聖霊によって、再び神の像を取り戻した人間を表しています。 聖霊は、教会を通して神の像を失った罪人に罪を自覚させ、その罪を悔い改めるように働かれます。これが、女の人が失われた銀貨を捜し求めるということです。 その人が、これに応答して、罪を自覚するとともに、その罪を悔い改めて神に立ち返る時、聖霊によって再び神の像を取り戻した人間になります。すなわち、「真理に基づく義と聖をもって神にかたどり造り出された、新しい人」になります(エペソ4章24節)。これが、女の人が失われた銀貨を見つけたということです。拙著「キリストの生涯の学び」127「失われた銀貨」より転載
2010.01.20
コメント(0)
-
説教要約 616
「迷い出た羊」 甲斐慎一郎 ルカの福音書、15章1~7節 「さて、取税人、罪人たちがみな、イエスの話を聞こうとして、みもとに近寄って来」ました(1節)。するとパリサイ人、律法学者たちは、つぶやいて、「この人は、罪人たちを受け入れて、食事までいっしょにする」と言いました(2節)。そこでイエスは、彼らに、「迷い出た羊」と「失われた銀貨」と「放蕩息子」のたとえを話されたのです。 パリサイ人や律法学者たちは、神に近づくために、罪や汚れから分離していましたが、次第に罪人からも遠ざかって行きました。彼らは、「正しい人を招くためではなく、罪人を招いて、悔い改めさせるために」来られたイエスを全く理解することができなかったのです(5章32節)。 一、迷い出た羊の姿 この一匹の「迷い出た」羊は(マタイ18章12節)、「何をしているのか自分でわからない」で(23章34節)、「無知のために」(使徒3章17節)、「知らないで」(第一テモテ1章13節)、神にそむいて罪を犯し、滅びに向かっている罪人の姿を表しています(R・C・トレンチ)。 無知には、学問的(または頭脳的)な無知と、道徳的(または意志的)な無知があります。学問的な無知は、直接的には罪はなく、無罪ですが、道徳的な無知は、罪をまぬかれることはできず、有罪です。 「罪とは律法に逆らうこと」ですが、知らなくても律法を破れば罪になります(第一ヨハネ3章4節)。ペテロは、「無知のために」イエスを十字架につけたイスラエル人たちに、「あなたがたの罪をぬぐい去っていただくために、悔い改めて、神に立ち返りなさい」と勧めています(使徒3章17、19節)。 二、捜し歩く羊飼いの姿 この迷い出た羊を捜し歩く羊飼いの姿を、絵画的または物理的なイメージで描くと、道なき道を、ものともせずに、いばらをかきわけ、深い谷まで降りて行く光景になります。 しかし全知全能の神が、私たちの姿を見失って、捜し歩かれるということは、あり得ません。神は、目に見えない心の世界や霊的な真理を教えるために、目に見えるわかりやすいたとえを用いて話されたのです。 それでは、神が罪人を捜し歩かれるとは、どのようなことでしょうか。迷い出た羊は、無知であっても、神にそむいて罪を犯し、神の前に失われている罪人を表しています。 ですから、神が罪人を捜し歩かれるとは、神が人の心の中に働かれることによって、神の前に失われている罪人が罪を自覚するとともに、その罪を悔い改めて神に立ち返らなければならないことがわかるようになるということです。 三、見つかった羊の姿 羊飼いが迷い出た羊を捜し歩いて、ついに見つけた姿を、絵画的または物理的なイメージで描くと、どこにも見えなかった羊をとうとう発見したという光景になります。 しかし全知全能の神が、どこにもいなかった私たちを、ついに発見されたということは、あり得ません。神は、目に見えない心の世界や霊的な真理を教えるために、目に見えるわかりやすいたとえを用いて話されたのです。 それでは、罪人が神に見いだされるとは、どのようなことでしょうか。迷い出た羊は、無知であっても、神にそむいて罪を犯し、神の前に失われている罪人を表しています。 ですから、罪人が神に見いだされるとは、神の前に失われている罪人が罪を自覚するとともに、その罪を悔い改め、神に立ち返ることによって、神がその人を罪から救われるということです。拙著「キリストの生涯の学び」126「迷い出た羊」より転載
2010.01.17
コメント(0)
-
説教要約 615
「三つのたとえ話」 甲斐慎一郎 ルカの福音書、15章1~32節 一、上の図の説明 上の図は、左から右の横軸は、この世と死と次に来る世という、時間の経過を表しています。上から下の縦軸は、この世においては、超自然の世界と自然の世界、次に来る世においては、天の御国と地獄という次元を異にする二つの世界と、それぞれの世界を隔てている大きな淵を表しています。 聖書は、天の御国と地獄との間を隔てている大きな淵は、「ここからそちらへ渡ろうとしても、渡れないし、そこからこちらへ越えて来ることもできないのです」と教えています(16章26節)。 また聖書は「生まれながらの人間は、神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼には愚かなことだからです」と記し(第一コリント2章14節)、この世においても神の御霊に属する超自然の世界と、生まれながらの人間の属する自然の世界との間には、隔たり(大きな淵)があることを教えています。 二、大きな淵と十字架の橋 私たちは、死後の次に来る世においては、この大きな淵を渡ることはできないので、この世に生きている間に、この大きな淵を渡らなければなりません。しかし、どうすれば、この大きな淵を渡ることができるのでしょうか。 キリストは「罪人を救うためにこの世に来られ」ました(第一テモテ1章15節)。すなわち、人間としてお生まれになることによって、超自然の世界から自然の世界に来られ、また、十字架の上で私たちの罪をその身に負われることによって、この大きな淵を渡ることができる橋をかけてくださいました。あとは、私たちが、この十字架の橋を信仰によって渡ればよいのです。 三、三つのたとえ話の特徴 ルカの福音書の15章の三つのたとえ話は、私たちに次のようなことを教えています。 「迷い出た羊」と「失われた銀貨」のたとえ話は(4~10節)、神(キリスト)が、失われた世界(自然の世界)にはいって来て、失われた人(罪人)を捜し求めておられることを記しています。「放蕩息子」のたとえ話は(11~32節)、失われた人(罪人)が、失われた世界(自然の世界)から神(超自然の世界)に、信仰によって立ち返る(渡る)ことを記しています(R・C・トレンチ)。 前者は、失われた人が信仰によって神に立ち返ることが省略されており、後者は、神が失われた人を捜し求めておられることが省略されています(R・C・トレンチ)。 私たちが信仰によって神に立ち返ることができるのは、神が私たちを捜し求めておられるからです。しかし神が私たちを捜し求めておられても、私たちが信仰によって神に立ち返らなければ、私たちは神に見いだされず、救われることはできないのです。拙著「キリストの生涯の学び」125「三つのたとえ話」より転載
2010.01.14
コメント(0)
-
説教要約 614
「将来と希望を与える神の計画(2)」 甲斐慎一郎 エレミヤ書、29章10、11節 「バビロンに七十年の満ちるころ、わたしはあなたがたを顧み、あなたがたにわたしの幸いな約束を果たして、あなたがたをこの所に帰らせる。わたしはあなたがたのために立てている計画をよく知っているからだ。--主の御告げ。--それはわざわいではなくて、平安を与える計画であり、あなたがたに将来と希望を与えるためのものだ」(10、11節)。 主は、ご自分に反逆した罪のためにバビロンへ捕囚の民として連れて行かれたユダの人たちに対して、祖国イスラエルに帰ることができるという希望と平安に満ちた将来を約束されました。その時期は、バビロンに70年の満ちるころ、すなわち、バビロンにおける70年間を懲らしめの期間として過ごし、いままでの罪をすべて悔い改めた後のことです。 一、二種類のこれからの時(未来と将来) 宗教哲学者の波多野精一は、二種類の「これからの時」をそれぞれ「未来」および「将来」と呼び、実存哲学者ハイデガーは、「未来」および「到来」と呼んで区別しました。 ◇未来--いまだ来たらずという意味で、見通しがきかない絶望と不安の時です。 ◇将来--まさに来たらんとするという意味で、見通しがきく希望と平安の時です。 未来は現在から離れて人の手が届かない時であるのに対して、将来は今につながる人の手が届く時であり、大きな違いがあります。 二、二種類のいままでの時(過去と由来) 前述した実存哲学者のハイデガーは、二種類の「いままでの時」をそれぞれ「過去」および「由来」と呼んで区別しました。 ◇過去--過ぎ去ったという意味で、今さらどうすることもできない時です。 ◇由来--由って来たるという意味で、今にまで伝えられて来た時です。 過去は現在から離れて人の手が届かない時であるのに対して、由来は今につながる人の手が届く時であり、大きな違いがあります。 三、過去--現在--未来という生き方 バビロンへ捕囚の民として連れて行かれたユダの人々は、過去における神への反逆の罪をどんなに悔やんだことでしょうか。また神に従って平和と祝福に満ちていた時をどんなに懐かしがったことでしょうか。しかし今となっては取り返しがつかず、今さらどうすることもできませんでした。そして捕囚の身として一寸先は闇であり、未来は絶望と不安に満ちていました。 もし私たちが、「いままでの時」を「過去」としてしかとらえることができなければ、悪かった過去も良かった過去も、すでに過ぎ去って人の手が届かない、今さらどうすることもできないものとなるので、それを改めて現在という時に生かすことができません。その結果、「これからの時」を「未来」としてしかとらえることができず、絶望と不安に陥るのです。 これは、時というものを三つに区切り、あたかも互いに関係がないかのように考える物理的な時のとらえ方です。 四、由来--今--将来という生き方 主は、このような捕囚の民に対してバビロンにおける70年間の懲らしめの期間が終わるなら、悔い改めにふさわしい実を結ぶので、祖国イスラエルに帰ることができるという希望と平安に満ちた将来を約束されました。 もし私たちがこの神に対する信仰によって、「いままでの時」を「由来」としてとらえるならば、--すなわち主の良くしてくださったことを何一つ忘れず心から神に感謝するとともに、すべての罪を心から悔い改めて神に立ち返るならば--良い由来も悪い由来も、人の手が届く今にまで伝えられたものとなるので、今という時に生かすことができます。その結果、「これからの時」を「将来」としてとらえることができ、希望と平安に満ちるのです。 人間は物質や機械ではないので、時というものを3つに区切るような物理的な時のとらえ方はしません。人間の心や生命・生活・生涯というものは、3つの時に決して区切ることはできず、時というものを一つにつながったものとしてとらえるのです。
2010.01.10
コメント(0)
-
説教要約 613
「将来と希望を与える神の計画(1)」 甲斐慎一郎 エレミヤ書、29章1~14節 「わたしはあなたがたのために立てている計画をよく知っているからだ。――主の御告げ。――それはわざわいではなくて、平安を与える計画であり、あなたがたに将来と希望を与えるためのものだ」(11節)。 一、捕虜としてバビロンへ捕らえ移されたユダの人々(28章14節、29章1~4節) ユダの人々は、神に対する不信仰と反逆の罪のためにバビロンに滅ぼされ、生き残った民は捕虜になりました。捕囚の民は、その地に住むことを許されましたが、「バビロンの川のほとり、そこで、私たちはすわり、シオンを思い出して泣」きました(詩篇137篇1節)。祖国を失った民の心中は、察するにあまりあるものがあります。 バビロンへ引いて行かれた捕囚の民は、過去における神への反逆の罪をどんなに悔やんだことでしょうか。また神に従って平和と祝福に満ちていた時のことをどんなに懐かしがったことでしょうか。しかし今となっては取り返しがつかず、今さらどうすることもできませんでした。捕囚の身として一寸先は闇であり、未来は不安と絶望に満ちていました。 二、バビロンに70年の満ちるころ祖国に帰ることを預言したエレミヤ(5~14節) エレミヤは、このような捕囚の民に「家を建てて住みつき、畑を作って、その実を食べよ。妻をめとって、息子、娘を生み……そこでふえよ。……わたしがあなたがたを引いていったその町の繁栄を求め、そのために主に祈れ」と仰せられた主のことばを告げました(5~7節)。民は、このエレミヤのことばに従って生活し、その地でふえました。 ハナヌヤは、ゼデキヤの治世の初めに捕囚の民は年のうちに帰るという偽りの預言をしました(28章1~4節)。それでエレミヤは、にせ預言者の誤りを指摘し、それに惑わされないように警告するとともに、捕囚の期間は70年であり、その後に祖国に帰ることが主のご計画であることを記した手紙をエルサレムから送りました(1、8~10節)。 主は、捕囚の民にバビロンにおける70年間の懲らしめの期間が終わるなら、悔い改めにふさわしい実を結ぶので、祖国イスラエルに帰ることができるという平安と希望に満ちた将来を約束されました(10、11節)。 また主は「あなたがたがわたしを呼び求めて歩き、わたしに祈るなら、わたしはあなたがたに聞こう。もし、あなたがたが心を尽くしてわたしを捜し求めるなら、わたしを見つけるだろう」と仰せられました(12、13節)。 このエレミヤの預言は、バビロンが滅ぼされ、紀元前538年にペルシャ王クロスが勅令を宣布し、ユダの民が捕囚から解放されて帰国した時に成就したのです(エズラ1章)。 三、私たちのために平安と将来と希望を与える計画を立ててくださる神(11節) 私たちも弱さのために何度も同じ過ちを犯して悩んだり、神に対する不信仰と不従順の罪のために苦しんだりするだけでなく、不安と絶望に満ちる時、主は私たちを顧みて、私たちに平安と将来と希望を与える神の計画を示してくださるのです。 それでは平安と将来と希望を与える神の計画が実現するための秘訣は何でしょうか。 ◇過去を振り返って、「主の良くしてくださったことを何一つ忘れ」ず(詩篇103篇2節)、心から神に感謝をささげるとともに、今まで犯してきたすべての罪を悔い改めて、悔い改めにふさわしい実を結ぶことです。 ◇現在を見つめて、にせ預言者に惑わされず(マタイ24章5、11節)、「締まりのない歩み方」をすることなく(第二テサロニケ3章11節)、「勤勉で怠らず、霊に燃え、主に仕え」ることです(ローマ12章11節)。 ◇将来を展望して、神が私たちのために、「平安」と「将来と希望を与える」計画を立ててくださっていることをよく知り(11節)、その神の計画が実現し、その預言が成就するために真剣に主を「呼び求めて歩き」、「祈る」とともに、「心を尽くして」主を「捜し求める」ことです(12、13節)。
2010.01.08
コメント(0)
-
説教要約 612
「二つの生き方」 甲斐慎一郎 ヤコブの手紙、4章13~17節 私たちは、年末や年始を迎えると、過去を振り返り、未来のことを考えます。 「過去のない人は、動物に近い。そうして未来のない人は、まさしく動物である」と言った人がいます。人間にとって未来は大切であり、いわゆる「その日暮らしの生活」は決して良いものではありません。「明日に向かって生きる」ところに人間の尊さがあるのではないでしょうか。 しかしこの場合、聖書は、次のような二つの生き方があることを教えています。 一、自分を中心とした高慢な生き方 ヤコブは、「きょうか、あす、これこれの町に行き、そこに一年いて、商売をして、もうけよう」(13節)と言う人たちに向かって「あなたがたはむなしい誇りをもって高ぶっています。そのような高ぶりは、すべて悪いことです」と述べています(16節)。これはどうしてなのでしょうか。 「高ぶり」という言葉は、原語において、もともと「浮浪者」を指す語で、それが転じて「かたり」や「ぺてん師」また「大言壮語する者」という意味になりました。ですから高ぶりは、実際以上に誇大に吹聴することであり、その根は、ありのままの現実の姿や状態を素直に認めない、かたくなな心にあります。 人間というものは、次の瞬間に何が起きるのか全く分からないほど無知な者であり、またどんなに力んでも一瞬でも生命を延ばすことができないほど無力な者です(14節)。 未来のことに関して、このような厳粛な事実を直視せず、また生殺与奪の権を握っておられる神(申命記32章39節)を認めずに、あたかも自分の思い通りに何でもできるかのように振る舞うことは、不遜な態度でなくて何でしょうか。同様に自らの罪深さも、その罪からの救い主の必要性も認めないことは、神の前において高慢であることを聖書は教えています。 二、神を中心とした謙虚な生き方 これに対して、ありのままの現実の姿を直視し、神を恐れて歩む謙虚な生き方というものがあります。 1.「主のみこころなら……生きていて」 これは、主のみこころと私たちの生命の関係を教えています。人間は自分で生きているのではなく、神によって生かされているものです。ですから私たちは、自分の思い通りに生きることをやめ、その生命を主のみこころにゆだねるなら、神は私たちの生命を保証してくださるのです(マタイ6章25、26節)。 2.「主のみこころなら……このことを、または、あのことをしよう」 これは、主のみこころと私たちの生活の関係を教えています。人間は自分の計画や野心を成し遂げるために生きているのではなく、主のみこころを行うために生かされているものです。ですから私たちは、自分の計画や野心を捨て、主のみこころを求めていくなら、神は「みこころのままに」私たちの「うちに働いて志を立てさせ、事を行わせてくださるのです」(ピリピ2章13節)。 3.「主のみこころなら……生きていて、このことを、または、あのことをしよう」 これは、主のみこころと私たちの生涯の関係を教えています。私たちは、その生命を神にゆだねるとともに、主のみこころを求めて、それにふさわしい生活をしていくなら、その生涯は、神の遠大なご計画によって導かれ、「生きるにも死ぬにも私の身によって、キリストがあがめられる」のです(ピリピ1章20節)。 この「生命」と「生活」と「生涯」は、英語においてはみな同じ言葉(Life ライフ)であることは誠に興味深いものです。「生命」は、「生活」によって維持され、その総計が「生涯」ですから、この3つは決して切り離して考えることはできません。 私たちの「生命」と「生活」と「生涯」は、神に対してどうでしょうか。
2010.01.05
コメント(0)
-
説教要約 611
「新しい年を迎えて」 甲斐慎一郎 ヨシュア記3章1~4節 私たちが新しい年の初めに当たり、その出発点に立って、これから進もうとしている道について考えることは、何よりも大切なことです。私たちの前には、どのような道があるのでしょうか。 一、私たちが通ったことのない道 この個所において、つかさたちは「あなたがたは、今までこの道を通ったことがないからだ」(4節)と言いましたが、「この道」というのは、直接的にはヨルダン川を渡る道のことを指していました。しかしこのことはイスラエルの人々が、これから行くすべての道についても同じように言えることです。 私たちがこれから歩もうとしている人生の道も、同じように私たちが通ったことのない道です。このことはキリスト者も世の人々も同じです。しかしキリスト者は、途中の道は分からなくても、出発点と目標点は、はっきりと分かっているということです。 イスラエルの人々はエジプトの国を出て、カナンの地に向かいましたが、キリスト者は罪の生涯を出て、天の御国に向かっているのです(ピリピ3章20節)。 ですから私たちは、一度も通ったことのない人生の道を進むために、次のような3つのことを心がけていなければなりません。 1.出発点である罪からの救いを明確にする。2.目標点である天の御国に向かう自覚を持つ。3.途中の道については信仰によって歩む。 二、キリストが通られた道 しかし私たちが通ったことのないこの道を、すでに通られた方がおられます。それはイエス・キリストです。キリストは、苦しみも弱さも涙も経験されたのであり(ヘブル4章18節、15節、5章7節)、「すべての点で、私たちと同じ」でした。人としてのキリストと私たちの違いは、ただ一つ「罪は犯され」なかったことだけです(同4章15節)。 しかしキリストは無実の罪を着せられ、私たちの代わりに罪とされました。これは誰も経験したことがない想像を絶する苦しみでした(マタイ27章46節)。このようにしてキリストは、私たちのために「苦しみを受け、その足跡に従うようにと」、私たちに「模範を残され」たのです(第一ペテロ2章21節)。 よく言われるように私たちが行く道のすべてにキリストが立っておられます。キリストは、私たちのために先にそこを通られ、「道を踏み固め、平らにしてくださったのです」(S・D・ゴードン)。 誰も通ったことがなく、踏み固められていないものは道ではありません。キリストは、ご自身のことを「道」であると言われました(ヨハネ14章6節)。これは、キリストが私たちのために神に至る道となってくださったという意味だけでなく、私たちのためにすべてのことを経験して、私たちが通りやすいように踏み固めてくださったという意味においても道なのです。 三、キリスト者が通るべき道 パウロは、晩年に「私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました」と告白しています(第二テモテ4章7節)。 1.勇敢に戦う生涯 私たちは、どんなに小さな良いことでも勇敢に戦って獲得しなければ、真に自分の身につきません。 2.走るべき道のりを走り終える生涯 私たちは、「いっさいの重荷とまつわりつく罪とを捨てて」、身軽になり、「忍耐をもって走り続け」なければなりません(ヘブル12章1節)。しかもコースを間違えずに、また完走するためには、途中で脱落しないように節制と計画性が必要です。 3.信仰を守り通す生涯 主は、私たちのためにいのちを捨ててくださいました。ですから私たちは、どんなことがあっても信仰を守り通さなければならないのです。 新しい年、私たちは、どのような道を歩もうとしているでしょうか。
2010.01.02
コメント(6)
全11件 (11件中 1-11件目)
1