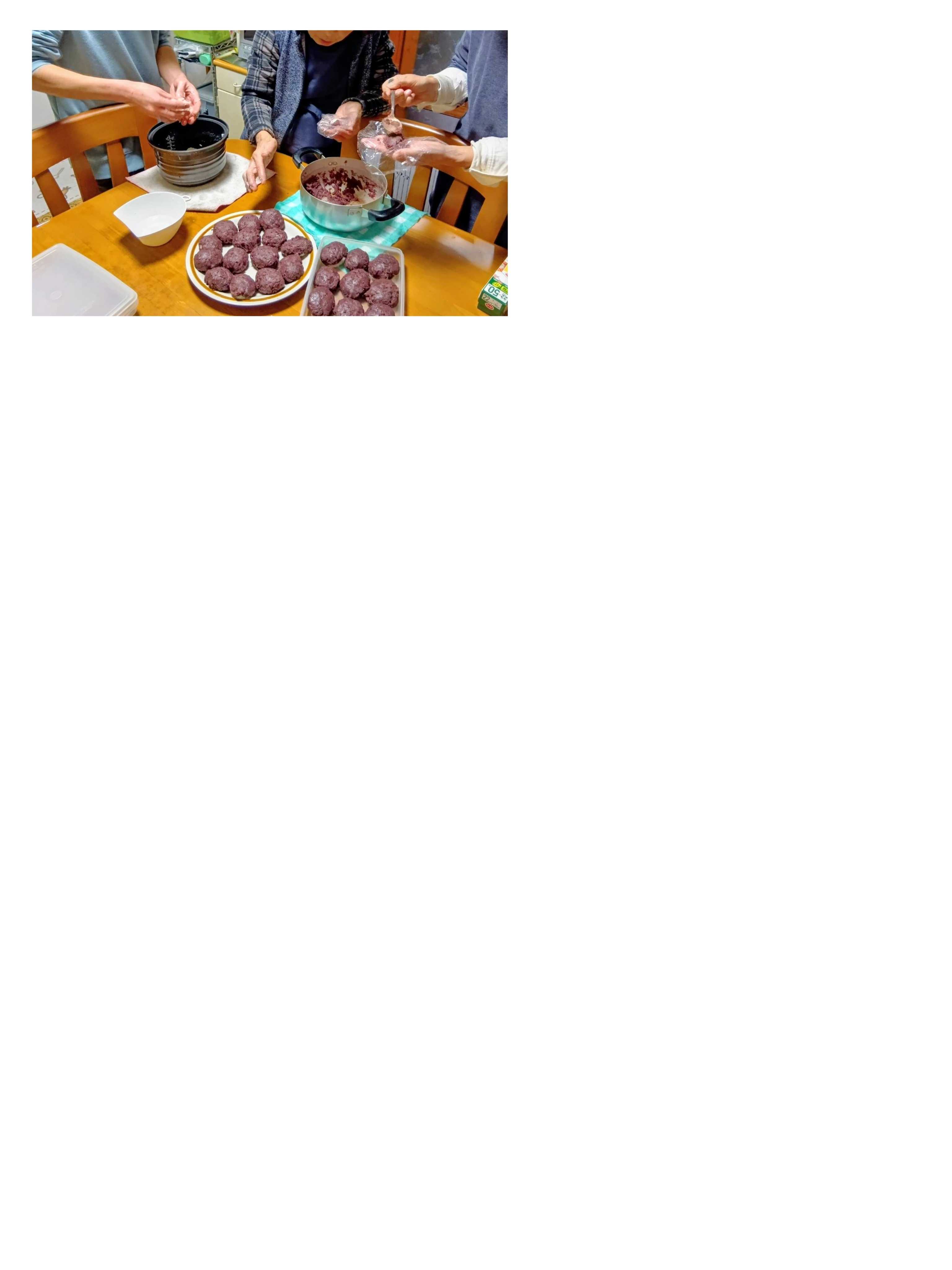2018年01月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
説教要約1084
「心を見守れ(6)福音と律法」 2018年1月28日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しました。2015年11月5日放映「神の思いと人の思い(1)」 「心を見守れ(6)福音と律法」 甲斐慎一郎 テモテへの手紙、第一、一章3~11節 テモテへの手紙の第一の1章3節から11節には、パウロのテモテに対する命令が記されています。その命令を要約するなら、「祝福に満ちた神の、栄光の福音」(11節)を自らが正しく理解し、体験するとともに、人に正しく宣べ伝えるようにということです。 一、福音の正しい理解(3、4節) 福音を正しく理解するためには、真の福音が何であるかを知るとともに、異端や偽福音がどのようなものであるかを知らなければなりません。 異端は、聖書の正しい教えに反するものや非聖書的なものすべての総称です。その代表的なものは、父なる神と子なる神と聖霊なる神は三つにして一つという三位一体の教理や、キリスト、真の神であるとともに真の人であるという神人両性の教理を信じないものです。またそれは、使徒信条を信じないものと言うこともできます。 真の福音は、人はキリストの贖いを信じる信仰によってのみ救われ、その結果、律法を守るようになるというものです(ローマ三章28、31節)。これに対して律法を守ることによって救われるという「律法主義」や、反対に救われた人は律法を守る必要はないという「律法無用主義」、また聖書の啓示ではなく、主観によって神と一つになるという「神秘主義」、そして目的のためには手段を選ばないという「熱狂主義」などは決して真の福音ではありません。 二、福音の正しい体験(5節) 福音の正しい体験とは、どのようなことでしょうか。パウロは、「この命令は、きよい心と正しい良心と偽りのない信仰とから出て来る愛を目標としています」(5節)と述べていますが、これこそ福音の正しい体験です。 きよい心とは、罪という不純物を全く含んでいない交じり気のない純粋な心ということです。また正しい良心とは、不正や不義が全くなく、後ろめたさとかやましさがない良心のことです。さらに偽りのない信仰とは、演技をしない信仰という意味で、表裏がなく、飾らず、繕わず、変装せずに、ありのままの真実な信仰ということです。 真の愛は、このようなきよい心と正しい良心と偽りのない信仰から出て来るもので、真の福音の体験は、この愛が日毎に深くなっていくことです。この真の愛こそ「きよめ」であり、もし私たちがこれ以外のものを求めるなら、福音から全く外れているのです。 三、福音の正しい実践(6~10節) 最後に福音を正しく実践し、宣教するためには、どうすればよいのでしょうか。そのためには、神の律法の目的と意義を知らなければなりません。 1.律法は、神がどのような方であり、その神のみこころがどのようなものであるかを私たちに教えるものです(出エジプト20章2~17節)。 2.律法は、人間の心を照らし、私たちの罪深さと無力さを教えて、私たちに罪の意識を生じさせるものです(ローマ3章20節)。 3.律法は、人間に救い主の必要を示し、私たちを救い主イエス・キリストのもとに導く養育係の役目を果たすものです(ガラテヤ3章24節)。 メソジストの創始者のジョン・ウェスレーは、神の「律法は、人間に向かって、あきらかにされた神の心である。……あなたがキリストに密着していようとするならば、律法に密着していなさい。かたくそれをつかんでいなさい。離してはならない」と述べています(ウェスレー説教集・中「律法の原形・性質・属性・用法」)。 私たちは、神の律法を学べば学ぶほど神のみこころを知るようになるだけでなく、律法は私たちを神のもとに追いやるとともに、私たちが神のもとから離れないように私たちを神のもとに引き留めるものです。私たちは、福音を正しく理解しているでしょうか。私たちの福音の体験は、日毎に深くなっているでしょうか。私たちは、福音を正しく宣べ伝えているでしょうか。 甲斐慎一郎の著書→説教集
2018.01.27
コメント(0)
-
説教要約 1083
「神の祝福に満ちあふれた人(2)」 2018年1月21日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しました。2015年10月1日放映「神を信じる人生と神を信じない人生」 「神の祝福に満ちあふれた人(2)」 甲斐慎一郎 マタイの福音書、5章1~16節 「神の祝福に満ちあふれた人」の第一回目は旧約聖書の詩篇84篇から「真の祝福」は、「神を求める幸い」(1~4節)と「神にある幸い」(5~8節)と「神の与える幸い」(9~12節)という3つの段階があることを学びましたが、第二回目は、新約聖書の「至福の教え」から学んでみましょう。 一、至福の教えは、詩篇84篇が教えている幸福の三段階を教えています 「山上の説教」の中の5章の前半は、「至福の教え」と言われているところです。この8つの幸いの前半の部分には、「神を求める幸い」と「神にある幸い」が、後半の部分には、「神の与える幸い」が記されています。 二、8つの幸いは、内側の心における幸いで、塩と光です 8つの幸いは、互いに何の関係もないものではなく、「心の貧しい者」を第一段階とし、「義のために迫害されている者」を第8段階とする「真の幸福の八段階」を教えています。 山上の説教が教えている8つの幸いは、外側に表れた幸福というよりも内側の心における幸福です。この内側の心における幸いは、「塩」と「光」であり、それは必ず外側の行為に表れます。 「塩」は、腐敗(社会の堕落)を防ぎ、良い味をつけます(世の人々に良い感化や影響を与えます)。「光」は、やみ(罪深い世)を照らし、世の人々に救いの真理を示します。 英語で幸福と訳されることばには「ハッピネス(happiness)」と「ブレッスィング(blessing)」の二つがあります。前者は、いくつかの偶然がうまく重なった幸運な出来事で、後者は、神が与えてくださる真の祝福で、それは必ず外側の行為に表れる「塩」と「光」です。 三、塩と光という内側の心の幸いは、必ず外側の行為に表れ、真の祝福を受けます 主は、「心に満ちていることを口が話す」(マタイ12章34節)と言われましたが、心は、ことばだけでなく、行為に表れます(ヤコブ2章14、16節、第一ヨハネ3章17、18節)。 心の貧しい者とは、自分の心の姿が「富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って」、うぬぼれているのではなく、かえって罪のために「みじめで、哀れで、貧しくて、盲目で、裸の者であること」(黙示録3章17節)を知ってへりくだり、救い主の必要を自覚して神から離れない人のことです。天の御国はその人のものです。 心の貧しい者は、自己憐憫に陥って世の楽しみや慰めを求めることなく「神のみこころに添って」罪を悲しむ者になります(第二コリント7章9節)。その人は慰められるのです。 罪を悲しむ者は、悪者の栄えるのを見てねたんだり(詩篇73篇3節)、悪人に復讐したりすることなく、悪を耐え忍んで柔和な者になります。その人は地を相続するのです。 柔和な者は、悪と妥協することなく、義を愛し不正を憎む、義に飢え渇いている者になります。その人は満ち足りるのです。 義に飢え渇いている者は、「あわれみのないさばき」をすることなく(ヤコブ2章13節)、あわれみ深い者になります。その人はあわれみを受けるのです。 あわれみ深い者は、「不正を喜ばずに真理を喜び」(第一コリント13章6節)、心のきよい者になります。その人は神を見るのです。 心のきよい者は「争ったり、戦ったりする」ことなく(ヤコブ4章2節)、平和をつくる者になります。その人は神の子どもと呼ばれるのです。 平和をつくる者は、不正を憎んで「敬虔に生きよう」とするので(第二テモテ3章12節)、義のために迫害される者となります。天の御国はその人のものです。 四、神の栄光が現されます 心の幸いという「塩」と「光」は、必ず外側の行為に現れ、それは罪深い世を照らし、世の人々に救いという真理を示し、人々は、その良い行いを見て、神をあがめるようになります(16節)。これこそ神から与えられる真の祝福(blessing)です。 甲斐慎一郎の著書→説教集
2018.01.20
コメント(0)
-
説教要約 1082
「神の祝福に満ちあふれた人(1)」 2018年1月14日インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しました。2015年9月21日放映「摂理と運命」 「神の祝福に満ちあふれた人(1)」 甲斐慎一郎 詩篇84篇1~12節 「幸福」は人類共通の切なる願望であり、だれでも幸福を願わない人はいないでしょう。しかし現実には、多くの人々は「幸福」を求めながら、「真の幸福」が何であり、どこにあるかが分からないために、「偽りの幸福」に甘んじたり、「真の幸福などあり得ない」と言って、あきらめてしまったりしているのではないでしょうか。 英語において幸福と訳されることばには、「ハッピネス」と「ブレッスィング」の二つがあります。前者は、いくつかの偶然がうまく重なった幸運な出来事で、後者は、神が与えてくださる真の祝福です。 この詩篇には、「なんと幸いなことでしょう」というみことばが3回も記されています(4、5、12節)。聖書は、私たちに真の幸福があることをはっきりと教えています。この84篇は、休止を表す「セラ」ということばによって次のような三つに区分することができ、幸いの三つの段階を教えています。 一、神を求める幸い(1~4節) ここには、「慕わしい」とか、絶えいるばかり(死ぬほど)「恋い慕って」ということばが記され、詩篇42篇の記者のように「生ける神を求めて渇いてい」る姿が描かれています(2節)。すなわち全身全霊をもって神を慕い求めているのです。 真の宗教の中心は何でしょうか。すばらしい神のことばや教えを学ぶことでしょうか。荘厳な宗教的儀式や礼典に出席して、その雰囲気に酔うことでしょうか。神の戒めを堅く守り、神への奉仕に励むことでしょうか。これらはみな大切なことですが、中心的な事柄ではありません。真の宗教の真髄は、生ける神との親しい人格的な愛の交わりです。そのために神を慕い求める人は幸いです。 人間の幸福の第一の段階は、この神を求める幸いです。神は、まず私たちにこのことを学ばせるために、私たちに様々な体験をさせたり、色々な所を通らせたりするのです。 二、神にある幸い(5~8節) このように神のみを慕い求める人は、「その力が、あなた(神)にあり、その心の中にシオンへの大路(すなわち神に近づく心)」があり(5節)、「シオンにおいて、神の御前に現れます」(7節)とあるように、ついには神にまみえ、神と一つになって、その力も、その心も神にあるようになります。このような人は、目に見えるものや周囲の環境に惑わされず、神のみを喜ぶことができ、神にある幸いを知っているのです。 人間の幸福の第二の段階は、この神にある幸いです。この幸いを知っている人は、「涙の谷を過ぎるときも、そこを泉のわく所とします」(6節)とあるように、苦難と試練の涙の谷を過ぎるようなことがあっても、そこを祝福と恵みの泉がわく所とするのです。 三、神の与える幸い(9~12節) 最後にこの詩篇の記者は、「主は恵みと栄光を授け、正しく歩く者たちに、良いものを拒まれません」(11節)と言っています。これはだれが見てもわかる祝福です。私たちが普通に考えている幸いというのは、このように神から恵みと栄光と良いものが豊かに与えられることです。 人間の幸福の第三の段階は、この神の与える幸いです。しかしこの神の与える幸いは、まず神を求める幸いを体験し、次に神にある幸いを体得した者だけが、ほんとうの意味において得ることができるものであり、先の二つの幸いを飛び越えて、いきなりこれを味わうことはできません。 この真の幸福の三段階を地で行った人が聖書に記されています。それは旧約のヨセフです。彼は、エジプトに売られ、監獄にまで入れられましたが、これは神を求めるのに妨げになるものを取り去られて、神のみを求める幸いを体験したのであり、次に同じ監獄にいる人を慰めることができましたが、これは神にある幸いを体得したのであり、ついにエジプトの支配者になりましたが、これは神の与える幸いを得たのです。 甲斐慎一郎の著書→説教集
2018.01.13
コメント(0)
-
説教要約 1081
「理解を越えた大いなる事を 2018年1月7日 なさる神を呼べ」インターネットのテレビ局CGNTV(⇒みことばに聞く⇒関東⇒東京B)の番組「みことばに聞く」に当教会の牧師が出演しました。2015年9月8日放映「初めに情報ありきか物理法則ありきか」 「理解を越えた大いなる事をなさる神を呼べ」 甲斐慎一郎 エレミヤ書、33章3節 「わたしを呼べ。そうすれば、わたしは、あなたに答え、あなたの知らない、理解を越えた大いなる事を、あなたに告げよう」(エレミヤ33章3節)。 この箇所における「あなたの知らない、理解を越えた大いなる事」というのは、第一義的には、4節以下に記されているユダとエルサレムの復興と繁栄のことを指しています。しかしここでは、すべての人に当てはまる神の啓示としてとらえてみます。 一、私たちの知らない、理解を越えた大いなる事が起きるのが人生です フランスの文学者が「ある赤ん坊が母親のおなかから出てくると、まわりをキョロキョロ見回し、『なんだ、人生とは、こんなものか』とひとこと言って、おなかの中に引っ込んでしまう」という即興劇をつくりました。 しかし実際は「事実は小説よりも奇なり」というエマソンの言葉のように、現実の人生は、作家の空想も及ばないような意外なことが多いもので、人が一生かかっても極め尽くすことができないほど不思議な巡り合わせや複雑な変化に富んでいるものです。 聖書は「順境の日には喜び、逆境の日には反省せよ。これもあれも神のなさること、それは後の事を人にわからせないためである」と教えています(伝道者7章14節)。 二、私たちの知らない、理解を越えた大いなる事をなさるのが神です 私たちは、新年を迎えて新しい計画や目標を立てたり、新年の希望や抱負を語ったりすると、何か新しくなったような気がします。しかし正月も終わり、通常の生活に戻ると、去年と少しも変わっていない自分を発見して、愕然とすることがあります。「日の下には新しいものは一つもな」く(伝道者1章9節)、人は、神による以外に新しくなることはできません(第二コリント5章17節)。 神は「見よ。わたしは新しい事をする。今、もうそれが起ころうとしている」と語っておられます(イザヤ書43章19節)。 イスラエルの民は、何度も神にそむいて罪を犯し、神が遣わされた預言者たちの警告にも耳を傾けず、ついに敵国バビロンに滅ぼされ、生き残った者は捕虜となり、バビロンに連れて行かれてしまいました。彼らは、神に対して犯した罪の報いを受けたのです。 ところが神は、ペルシャの王クロスの霊を奮い立たせられたので、王のおふれによってイスラエル人は捕囚の身から解かれ、祖国に帰ることができました(エズラ1章)。 彼らは、「主がシオンの捕らわれ人を帰されたとき、私たちは夢を見ている者のようであった。そのとき、私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた」と歌っています(詩篇126篇1、2節)。このバビロン捕囚からの帰還こそ、神がなされる「新しい事」です。 パウロが述べているように、神は「私たちの願うところ、思うところのすべてを越えて豊かに施すことのできる方」です(エペソ3章20節)。ダビデは、「私の時は、御手の中にあります」と記しています(詩篇31篇15節)。ブッシュネルは、「どの人の生涯も神の計画による」、「神の心の中には、すべての人のために完成された完全な計画が大切にしまわれている」と述べています。 三、私たちの知らない、理解を越えた大いなる事を告げられる神を呼び求めることこそ私たちの義務であるとともに特権です。 このように神は、「私たちの願うところ、思うところのすべてを越えて」、あふれるばかりの恵みを注いで「新しい事」をなさる方です。神は、私たちの知らない、理解を越えた大いなる事をなさる方ですから、神のなさることはみな「新しい事」です。 私たちの知らない、理解を越えた大いなる事を告げられる神を呼び求めることこそ私たちの義務であるとともに特権です。新しい年、私たちの知らない、理解を越えた大いなる事を告げられる神を呼び求め、その神に新しい事を期待して歩もうではありませんか。 甲斐慎一郎の著書→説教集
2018.01.06
コメント(0)
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…
- 元セクシー女優・高橋しょう子“アン…
- (2025-11-25 02:00:05)
-
-
-

- ★資格取得・お勉強★
- 『仕事上資格が必要な人』ほど、資格…
- (2025-11-24 17:24:13)
-