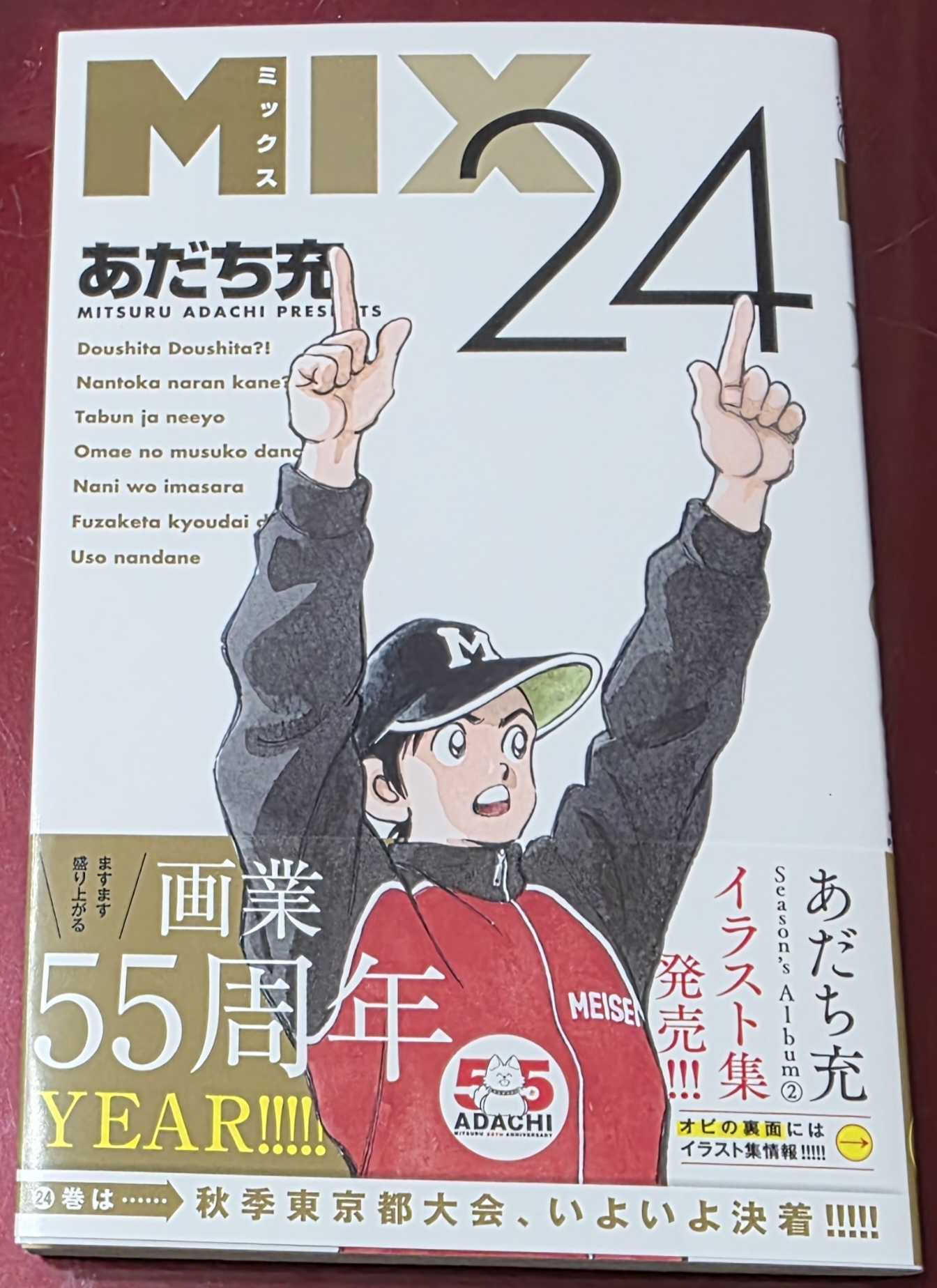2015年07月の記事
全2件 (2件中 1-2件目)
1
-

「純粋小説」とホームドラマ
『家族会議』横光利一(新潮文庫) このタイトルは、一体何を表しているんでしょうね。 タイトルの意味がよーわからんという小説(特に純文学小説)は、結構ありそうに思えます。 よいように理解すれば、象徴性って事でしょうけれど、なんか、「もうちょっとなんとかならんかったんですか」と思わず口に出してしまいそうなタイトルも結構ありますよねぇ。 具体的にどんなタイトルがそうなのか、今ちょっと考えてみたんですが、例えば、徳田秋声の『黴』なんてのも大概じゃないかと、かつて思った記憶があります。 秋声には『爛れ』なんて小説もあったと思いますが、こちらは読んでいないので、内容と比較してタイトルが大概なものかどうか判断できません。 で、今回の本作のタイトルですが、これはひょっとしたら横光利一は、少し照れたのかも知れませんね、そんな気がします。 よーするにこれはホームドラマですよ宣言をした、と。 本書の解説に、横光利一は昭和十年前後、日本の文芸復興を考えたとき、文学に社会性を盛り込むために「純粋小説」という概念を考え出し、その最初の実験作みたいなのが本作であると書いてありました。 そういえば横光の「純粋小説」という概念は、高校時代、私が好きだった国語の先生が教えてくださったのを覚えています。 その先生がおっしゃるには、純文学というのは奥行き・内容の深さはあるが、そのぶん取り上げられた世界が狭い。いわば、間口の狭いウナギの寝床住宅のようなものである。 一方大衆小説は、起伏に富んだストーリーを持つ作品が多く、しかし例えば「人間」について深く描かれているかと言えば、それはどうもそうとは言い切れない。 先ほどの例えで言えば、間口は広く、表正面から見れば大邸宅のように見えながら、中に入ってみるとすぐに勝手口に至るような建物である。 横光の提唱した「純粋小説」とは、大衆小説の持つ間口の広さと、純文学の持つ奥行きの深さを兼ね備えた小説のことである、と。 高校時代の素直な紅顔の美少年だったわたくしは、その説を聞いて、なるほど「純粋小説」とは、きっとスリルたっぷりに面白くも大号泣という、すっごいすっごい小説であるのだなぁ、と思ったんですね。 根が単純ですから。頭の造りがアバウトですから。 今考えたら、そんな小説なら最低トルストイの『戦争と平和』くらいの分量がいるだろう、よーするに大長編小説のことだなと気づくのですが、さて本書『家族会議』は、新潮文庫で317ページであります。 長編小説といって決して悪くはありませんが、『戦争と平和』の長さ(と内容)には比ぶべくもありません。 そこで、まー、そんな予感を持ちつつ書き始めようとした横光利一氏が、いや、これは、ちょっと、いえ、ある意味、ホームドラマみたいなものですがね、……と照れて、……で、『家族会議』と。…… ……いかがでしょうか。 なるほど本作は、株の世界、今で言うビジネス小説の要素も兼ね備えた「大人の男」が読めそうな小説の結構を持ってはいますが、突き詰めて内容をまとめてしまうと、嫁探しのホームドラマともいえます。 その上、どういうんでしょうか、ある意味「ハードボイルド」に描かれようとしたためか、主人公(ならびに数名のヒロイン達)の内面に深く関わっていこうという文体は持たず、そしてさらに少し厳しく言えば、ストーリーはさほど波瀾万丈でもなく、ということで、何とも中途半端な感じの読後感を、わたくし持ってしまいました。 でも、出てくる各場面が少しくすんだ感じで、登場人物をさほど魅力的に書こうとも筆者が思っていないのなら、まぁ、これこそが実験作なのだと言われれば、はぁそんなものですかと思えないわけではありませんが、一言で言えば、殺風景な小説ですわね。 ただ、横光利一は、この後、さらに「純粋小説」を突き詰めて『旅愁』という、これは新潮文庫で上下2巻、千ページを超えようという作品に着手します。(ただし、時代状況の大きな変化があり未完となり、さらにこの作品のせいで、横光は晩年けっこう辛い状況に追いやられたと聞きます。) 同じ「新感覚派」の川端康成にも、かなりエッジの立った実験小説がありますが、かたやノーベル賞で、と考えると、人の一生とは実に薄氷の上を歩むがごときものでありますなぁ。 よろしければ、こちら別館でお休み下さい。↓ 俳句徒然自句自解+目指せ文化的週末にほんブログ村
2015.07.28
コメント(0)
-

小説家にとっての母親の不在
『漱石 母に愛されなかった子』三浦雅士(岩波新書) 本ブログのどこかで、近代日本文学史上の作家の中で、様々な理由であまり母親から愛されることがなかった作家を挙げていったら、その数が多かったことと、挙がった作家が「大物」ばかりだったのに少し驚いたことがありました。(誰を取り上げたときの事だったのでしょーねー。自分が書いたのにいっこうに思い出せません。) 母に愛されないことが一流作家の条件である、と言うのはもちろん冗談ですが、幼児から少年時代にかけて母の愛情を十分に得ることができないというのは、少し考えるだけで、いかに本人の自我形成過程に大きな影響を与えるかは類推できます。 そして、おそらく創作意欲というものは、そんな内面の不如意と大きく関係していると思います。 さて本書ですが、以前よりわたくし、文芸評論のテーマで読んでハズレがないものは源氏と漱石だと思ってきました。 その理由は簡単で、原典の並はずれた懐の深さが、様々な角度からのテーマ設定を可能にし、同理由が様々な論証をも可能にしているということであります。 そして、やはり本書もその例に漏れないと、基本的には考えています。 ただ、ただねぇ、母に愛されなかった故にという「補助線」一本だけでは、いくらなんでもちょっと立論が雑駁になりすぎる気が、実はわたくし、致しました。 本書は九章からの構成になっていまして、第一章が『坊っちゃん』を扱っており、そして最後の第九章が『明暗』を扱うという、ほぼ漱石作品の成立順に書かれています。 特に第一章と、『吾輩は猫である』を扱う第二章において、筆者は「母に愛されなかった」テーマがいかに漱石作品全体を貫いて重要なテーマであるかを再三強調して書いているのですが、……うーん、ここの展開が、失礼ながら、一番雑駁な感じがしました。 そもそもこんな大きな「補助線」だと、どうでも展開できるような所があります。 例えば『坊っちゃん』には、誰が読んでも両親から(母親から)の愛情の不在は読み取れましょうし、筆者の展開による『猫』の中に再三出てくる「自殺」テーマも、成長期における大きな愛情の欠落が自己愛の成熟を阻み、そして自殺に結びつくというという論証は納得できないわけではありません。 しかし、なんというか、……それはまぁ、母親の愛情が子どもにとって最も重要である以上、その欠落がこういった性格を形作ったといわれれば、まぁ確かにそう考えられもするわなぁとは思いつつ、でもそれって、犬が西向きゃ尾は東、……って言ったら少し言いすぎですかね。 わたくし、読みながら、漱石が随筆で書いていた(小説内だったかしら)、探偵の話を思い出してしまいました。 その話とは、探偵嫌いの漱石らしい、探偵とは頼みもしないのに自分の背後から付いてきて、お前は今屁をひった、またひった、これでお前はいくつ屁をひった、と言い続けるような存在だというものでありますがー、……失礼ながら。 もちろん、読んでいて、うーんこれはなかなか鋭い指摘だなぁと思うところもたくさんあります。 例えば後半部、『彼岸過迄』に触れて、いわゆる「修善寺の大患」体験がどのように作品に結実しているかを説明した個所であったり、『道草』『明暗』がいかに優れた作品かを説いた部分などは、わたくし大いにスリリングに感じ、納得いたしました。 それともう一つ、これは実は「あとがき」に書いてあるのですが、「母に愛されなかった子」というのは私的な状況ではないと説き出したところが、(「あとがき」という文章の性格上十分な立証がなされているとはいえないながら)不思議な魅力と可能性を持った説明部でありました。こんな本文であります。 むしろ、母に愛されなかった子という主題は、かつては公共のものとしてあったが、ある段階から私的なものと見なされるようになった、と考えた方がいい。たとえば、家族、親族、部族といった、ある程度、血縁を基盤とした社会においては、母に愛される、愛されないという主題はじつは公共のものとしてあった。それが、社会の基盤が別のものに移ることによって、公私の分け方が地滑り的に変わったのだと考えたほうがいい。 わたくし、ここに至って、「ああ」と思い出したのですが、というのは、筆者三浦雅士の評論はむかーし、たぶん大学時代あたりに一冊だけ読んだ記憶があります。(本書に書かれている筆者略歴を見て分かったのですが、『メランコリーの水脈』という評論だったと思います。) その内容は、もう全くといって覚えていないのですが、かすかな記憶に印象だけが残っていて、それが、どこか不思議な評論だったなぁというものでありました。 なるほど、そういうことだったんだなと、(こういう説明は、今考えると文化人類学的なアプローチのように感じますが、いかんせん無教養な私にはそれ以上の知識がありません)……いえ、だからどうだと言うことではないのですが、本の魅力というものも、当たり前ながら、様々なものがありますねぇ。 よろしければ、こちら別館でお休み下さい。↓ 俳句徒然自句自解+目指せ文化的週末にほんブログ村
2015.07.11
コメント(0)
全2件 (2件中 1-2件目)
1