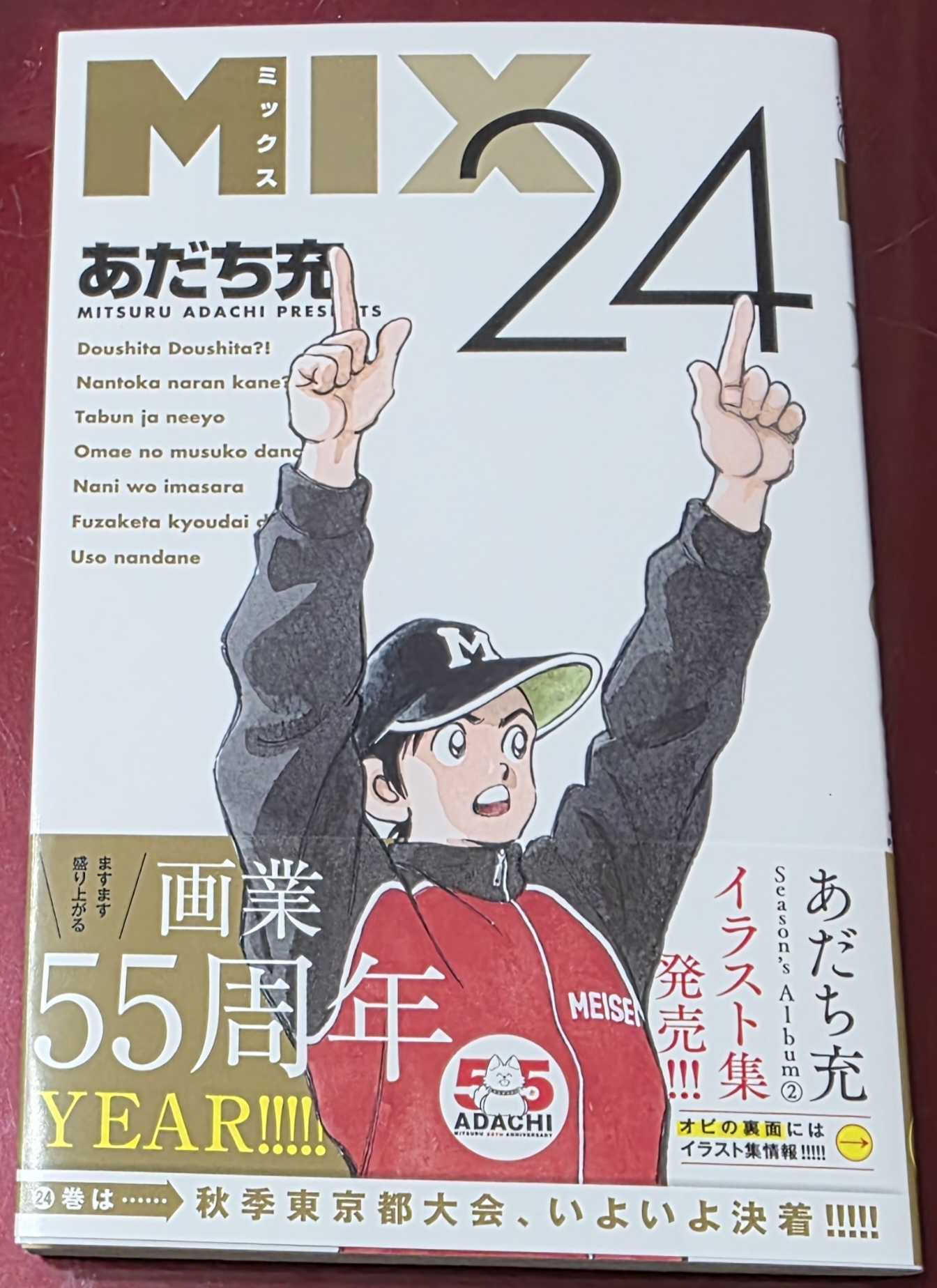2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2006年07月の記事
全28件 (28件中 1-28件目)
1
-
薬草魔女への道
また、新しい子を連れてきてしまいました。「セダム・マキノイ・バリエガータ」という中世ヨーロッパ貴族みたいな名前の、多肉植物です。ちっちゃい葉っぱが、まるでお花みたいで、本当にかわいい!友達と待ち合わせをしていた駅の改札で、ものすごい人ごみにもまれて具合わるくなりそうだったわたしに、お花やさんの店先にそっとたたずんでいたこの子が、小さな葉っぱを揺らして、「だいじょうぶ?」って話しかけてくれたのです。胸がきゅーんとして、夕方、友達と別れた後にもう一度花屋さんへ行き、ストーカーのように店の前を2、3度うろうろしながらちら見した挙句、「このひと…じゃなかった、この鉢をください」と店員さんに声をかけちゃいました。紙袋に入ったセダムちゃんを受け取りながら、ふと、自分の狭い部屋を思い浮かべました。西日が切ない1DK。猫の額より小さいベランダ。山のような本とCDのコレクションで、人間さまは食事をする寝る場所もありません。それなのにそれなのに!既に鉢植え、4つ目…帰宅後、顔を洗うよりも先に、植物たちに声をかけながら土を触って回り、乾いていたらせっせと水をやるわたくし。今は25歳独身☆OLだからまあ何とか格好がつくけど(…と、思ってるのはわたしだけか)、5年後も、10年後もこのままひとりで、夜毎植物たちと話し、近所の子供から「緑のおばさん」と呼ばれるようになったらどうしよう…なんて。一抹の不安もなくはないけれど、それはそれで幸せかもなあ。薬草魔女みたい!魔女が活動しやすい時代に生まれて、本当によかった。それにしても、極度の無精者でせっかちで、植物を育てるなんて思いつきもしなかった、誰かに親指サイズのサボテンを譲ってもらっても、あっという間にミイラにしてしまったこのわたしが、植物の生きるペースに自分をチューニングする時間を持つようになるなんて、3年前は思いもよらなかったことだよ。根のある植物を育てはじめたら、アロマオイルや乾燥ハーブにも、敬意と感謝のきもちを持てるようになりました。それは人間を癒すための薬やサプリメントではなく、植物の生命力そのものなんだと。大切に、ひとつもむだにせずに使わせてもらわなければならないのだと、身体でわかった感じです。植物って、ただ水と肥料をやれば育つっていうんじゃなく、たまには水やりを忘れても風に当てるのを忘れても、とにかく「一緒に生きている」ことを感じつづけるのが大事みたいです。何をしていても、その存在を常に頭のどこかで意識すること。動物や、人間の子供と一緒かもしれないな。ところでわたしは、とにかくとろくて、何につけても人よりスタートが遅いらしいのです。「よーい、どん!」と号令がかかってみんなが飛び出してから、きょろきょろ周りを見回してなぜか空まで見上げて、それからようやく走り出す、というくらい。幼稚園時代からうすうす自覚はあったが、今日、すごい人にそのことをずばりと指摘されました。今までは、自分のそういうところを隠そう、隠そうとして、やたらに人と自分を比較し、人より後ろにいることを認識しては焦り、自信をなくしていたのです。でも、スタートが遅いなら仕方ないや。と何だか肩のちからが抜けました。ゆっくり、焦らず、自分のペースで。何よりも楽しんで!…と、冬になると成長を止めてじっと春を待つセダムの葉っぱが言ってくれてるみたいです。ありがとう。これからよろしくね。
2006.07.30
コメント(0)
-
ローズマリーちゃんが来た日
朝からフル回転で動き回る。だって休みの日に、こんないいお天気はひさしぶり!シーツと布団カバーを洗い、掃除機をかけ食器を洗い、およそ1カ月ぶりのヨーガ教室へ。おおー!きもちいい。疲れて縮こまっていた全身の筋肉がふわーっと広がって、こわばりや滞りがひとつずつほぐれてゆく。きもちよくて笑いだしそうになったり、ため息がもれそうになるのをぐっとこらえる。帰りに日本橋へ。高島屋でローズマリーとラベンダー、ジュニパーのアロマオイル、レモンバームのハーブティーを。夏に欠かせません。三越屋上のガーデニングショップで、観葉植物の土と鉢、ハエよけスプレー、それから探していたローズマリーの小さな木を手に入れる。まだ20センチほどの高さなのに、自転車のかごに積んで走っていると、すっとする野生の香りをぷんぷんさせている。かわいいなあ!これから大事に育てるからね。お肉料理やハーブティーに、ときどき葉っぱを分けてね。葉っぱがしょんぼりと黄色くなってしまったアイビーの葉は、大きめの鉢に植え替えて土を替え、たっぷり水をやる。ときどきベランダに出して日に当てていたら小バエがついてしまった「万両」の木は、ハエよけスプレーをちょっとだけかけて虫を追っ払い、家の中に入れてあげる。さて。人間のごはん。なすとみょうがと大葉とクレソンのサラダ、梅種しょうゆかけ。ナンプラーで味つけした豚そぼろ、しいたけ炒め添え。高山さんのレシピです。ビールをちびちび飲みながら作り、食べ終わってふとアイビーの鉢を見たら、つい2、3時間前まで黄ばんでいた葉が、くっきりした緑と白になり、しおれていた若葉がぴんと元気を取り戻している。うわあ、この子たちほんとに生きてるんだなあ。…ところで、身体と心のために玄米食を始めるつもりです。こないだ、伯父の葬儀で北海道へ帰ったとき、従兄のお嫁さんが「すごーくいいよ!」と勧めてくれたので。やっぱり無農薬。と思い、玄米は通販で買うことにしました。問題は鍋。玄米が炊ける炊飯器を買ってもいいのだけれど、この際だから鍋で炊きたい。となったら大奮発して、フィスラーの圧力鍋を買っちゃおうかと思ってます。どきどき。使ったことのある方、ぜひ使い勝手を教えてください♪
2006.07.29
コメント(0)
-
トトロの森
朝、路地裏で黒猫の親子(母1ぴき、子供2ひき)を見かけた。子猫たち(あの様子はたぶん、オス)がじゃれ合いすぎて、遠くからみたらぐるぐる回る丸い毛玉みたいだった(←ちびくろサンボのホットケーキみたいなイメージ)。写真を撮ろうとしたら毛玉をほどいてぱっと茂みに隠れ、金色の目を6つ並べて、じーっとわたしを見つめている。驚かせてごめんね。また、帰りにね。とあいさつをして通り過ぎる。写真を撮れるころには、子猫たちが成猫になってるかも。猫が子育てをするにも、この街はいい環境みたい。午前中、新聞配達少年たちが会社見学に来た。まさか、わたしが話をすると思っていなかったのだけれど、上司に「やってみる? どっちでもいいよ」と言われ、なりゆきでみんなの前に立つことに。しどろもどろ、上司に助けを求めながら、必要なことはどうやら伝えられたんじゃないかと。きのう、おとといとディズニーランドで遊びまくってきたらしいので、「そりゃあ!今さら、会社見学なんて眠いだけだろう…」と思っていたのですが、思いのほか真剣に聞いてくれてどきどきしました。こんなこと、できるようになるなんて!人前で話すことを、何よりも苦手とするわたしが!すごいなあ。人間の回復力って。元気になったんだなあ、自分。会社の中を案内して回ると、みんながにこにここちらを見て、「がんばってね」などと声をかけてくる。誰にとっても、若さは救いで、無条件に応援すべきものなのだなあ。編集局長席で記念撮影をしていたら本物の編集局長があらわれて激励され、びっくりしたり。トトロのところにも行ってきました。男の子はゲド戦記の展示の方に夢中でしたが、女の子は目をきらきらさせてトトロを見上げていて。よかった、よかった。高校生たちのテンションに合わせて、老体…じゃなかった、疲れた身体にむちうって動き回っていたら、さすがにくたくた、ぼろぼろ。自分のデスクにぐでーっと伸びていたら、「何かこう、がっつり汗が出るものを食おう!」と文化的上司さまに誘われ、3代続く老舗中華料理店で激辛のスーラータンメンを。あまりの辛さとボリュームに、今まで完食できた試しがなかったのですが、本日はスープまでしっかり飲みました。もうひとりの上司いわく、「全身の毛穴から汗が噴き出す」感じで、夕方まで汗がひきませんでした。あまりに疲れたので、帰りにあの、癒しの喫茶店でブレンドコーヒーを一杯。なみなみとつがれたカップにゆっくりと顔を近づけて湯気を吸い込むと、もう、疲れの半分はどこかへ溶けてしまっている。ここのコーヒーのんだら、もう社員食堂の煮詰まったコーヒーなんか飲めないし、まして、スターバックスなんかぜったい行けません!というくらいおいしい。滋味ぶかい、魅惑ののみもの。恋を忘れたアラブの男が、人生の喜びを取り戻しちゃうのもわかる。いつか、この街を離れる前に、コーヒーの味だけでなく、安らぎの雰囲気も自分の部屋に再現し、「喫茶biscuit」をいつでもどこでも開店できるようにコツを盗もう。写真の景色は、トトロの田舎!と思い、新幹線の中から慌ててシャッターを切りました。トトロのアニメを見ていると、何気ない場面、たとえば草壁おやこが3人で自転車に乗っているシーンなんかで、突然涙がばーっと出てきて困る。すごい映画だなあ、これ。
2006.07.28
コメント(2)
-
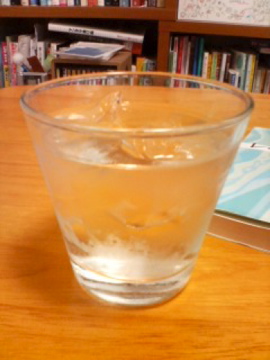
梅酒試飲。
人生初の梅酒を漬けて、もうすぐ2ヶ月。まだまだ漬かりが浅いのはわかっていたけれど、今日はひさしぶりに青空を見たし、どうしても初夏の味を楽しみたくて、グラスに氷を入れ、ちょっとだけ注いで味見してみました。おおー!梅の香りがする!!…って当たり前ですね。でも、お店で買ってきた梅酒とひと味ちがう、やさしい梅の香りとほのかな甘さがたまりません。この夏の、ささやかな贅沢になりそうです。仕事。最近忙しいです。大きな会議を明日に控えているので。きのうなぞは、おふろに入る気力もなくばたんきゅーと寝てしまうくらい、朝から夕方まで一生けんめい働きました。まだ疲れやすいこの身体。まして今月に入ってから、週末の度に日本を縦断し、ほとんど休日らしい休日を過ごしていないこともあり、体はくたくた。けど、ふしぎなくらい、楽しい。働くことそのものが昔から好きなのだけれど、いまは、職場がすごく好き。この人たちと一緒に…というか、この人たちの仲間に入れてもらって仕事をしているこの時間は、まちがいなくこれからのわたしの宝になる。たくさんの人の上に立つような、定年間近のおじさまたちばかりなのに、手が空けば惜しみなく、細かい雑用をどんどん、楽しそうにやるのです。名簿のまちがい探しから、資料の袋づめまで!そして、手を動かしながらどんどん意見を出し合い、「それいいね」ということになったら、会社がつけた順番で言うといちばん位が上の人がさっと席を立って電話をかけ、どんどん話を進めていく。ああでもないこうでもないと言い合ううちに、資料の内容はどんどんブラッシュアップされ、議論がふかまってゆく。ひと息つきたいなあと思っていると、絶妙のタイミングで、誰かが頼んだコーヒーが人数分運ばれてくる。みんながよりよい仕事をしようという共通の目標の下で、周りを思いやりながら楽しんで働いている。「仕事」の本来の姿がここに!という感じ。過酷な3K労働(笑)に長年耐え、その中でも自分が納得できる仕事をしっかり成し遂げてきた人たちの見事なチームプレイに、ほんの隅っこだけれど参加させてもらえる楽しさよ。彼らが何気なくかわしている雑談の中には、きらりきらりとダイヤモンドが光っているし、コピーを頼まれる資料の内容はびっくりするくらい濃くて、こっそり一部余計にコピーして読み込んでしまうほど。ランチ時間の会話までもが宝!今日はパスタを食べながら、ドラクエと唐十郎の深い関係について話す。おもしろくて、パスタそっちのけで「それから?それから?」と続きをねだる成長期の子供のようなわたし。順風満帆に記者をやっていたら、この場所にいることもなかったのだなあと思うと、何だかふしぎなきもち。いや、あのころだって、毎日の中に宝はたくさん転がっていたのだ。ただ、あまりにも拘束時間が長く、仕事の内容がわたしにはつらいものも多く、大切なものを「これは宝だ」と感じる余裕すらなかったんだろうなあ。この先、わたしは子供を育てたり家事をすることも含めて、さまざまな場所で一生仕事をつづけるだろう。そのとき、仕事をつまらなくしてしまいそうになったら、いつでも、この場所のことを思い出そう。仕事を楽しくするのも苦行にするのも、共に働くみんなの心がけ次第だということを、何度でも確かめよう。そのためにも、いまは、目を見開いて注意深く、限られたこの時間を胸に刻み付けるんだ。
2006.07.26
コメント(2)
-

田口ランディ「聖地巡礼」
メルマガ出してたころからファンだったランディさんの「聖地巡礼」。心身を壊していた時期は、文章の光が強すぎて読めなかったのですが、ここにきてようやく、読めるようになりました。ランディさんと愉快な仲間たち(通称?「聖地開発事業団」)が、屋久島や知床、ヒロシマ、出雲大社などを巡る旅のエッセイ。人の営み、「水」のちから、教科書に書かれていない日本の歴史。異形のものたち。見えないものを見ること。軽妙な文体で書かれてはいますが、内容の濃度はすさまじいです。間にたくさん挟まっている旅の写真が、そのぎゅっとつまった文章を、ゆっくり自分の中にしみ込ませるちょうどいい「間」になっています。ランディさんが信頼する占い師さんが、何気ない岩肌を、森の力と人間意識が接触する「森の生殖器」に例えている場面が、すごーく印象的でした。屋久島も出雲大社も、ぜったい行こう。この本には出てこないけれど、伊勢神宮も。さて。週末にお花畑のスカートをおろしたので、会社にもはいていきました。軽くてしわになりにくいし、ふわっと広がる裾がいつものオフィスをとっておきの場所にしてくれる感じ。この夏のヘビーローテーションになりそうだなあ。こういう服って、特別な日に意識してはくより、ふだんの日にさらりと着るのがいいのかも。
2006.07.25
コメント(2)
-

りんこ日記
写真家、川内倫子さんが、「携帯のカメラで撮った」写真つきの日記なのです。高山なおみさんの「日々ごはん」に通じる、周りに流されない、りんこさんだけの速さで、密度ですすむ時間軸がすてき。ある日の日記に、飛行機の中から撮った雲の写真があるのだけれど、それが、画面の中に窓枠も入れて撮っているのが、「はっ」とさせられました。わたしも最近、同じように飛行機の中から雲の写真を撮ったのだけれど、何だかかっこわるい気がして、窓枠やエンジンや翼が入らないように気をつけていたのです。それは、おそらく、わたしが人生で最初に使い捨てじゃないカメラを持ったとき、新聞に載せる写真を撮るために教えてもらった技術で。「人に見せるため」じゃなく、「自分に見えた景色をその通り切り取る」大切さを、思い出させてもらいました。プロってつまり、そういうことだよなあ。で、最近はりんこさんの真似をして、カメラを持ち歩いていないときも、携帯で写真をいっぱい撮っています。パソコンに取り込んでみると、思っていたよりうんといい写真撮れるんですねー、これが!すごいわねえさいきんのケイタイは(←おばちゃんの立ち話ふうに)。カウンセリング。伯父の死から始まって、この2週間に起こったさまざまな出来事を、順を追ってていねいに話す。そしていまはもう、誰の言葉にも行動にも流されず(まあ、流されちゃうんですけども)、自分の、自分だけの地に足の着いた生活を、何よりも大切にしようと決めたことも。小説を書く愉しさと、どうやって物語が展開していくかについて、夢中になって話していたら、「本当に、いちばん楽しそうに話すね」ってカウンセラーさんが。うん。それは、わたしにとって、たとえば宇宙旅行をするより楽しいのだ。それは、わたしがさんざん回り道をしたあげくに見つけた、わたしの「まんなか」。自分のための写真を撮ること。自分のための料理をすること。自分で見つけた音楽を聴くこと。自分の好きな本を読むこと。自分で選んだライブに行くこと。自分でチケットを買って映画を観ること。自分が興味をひかれた美術館に行くこと。部屋を居心地よく整えること。植物を育てること。大好きな服を着ること。自分のために、ハーブティーやアロマオイルのブレンドを考えること。お気に入りの喫茶店で、時間をかけて1杯のコーヒーを飲むこと。これらは全部つながっていて、ひとつの旅で、「書く」ということにまっすぐ収斂されていく。病気になる前のわたしは、たとえば心の中に「さみしい」という感情があったら、それを2倍にも、10倍にも、ときには100倍にも増幅して、自分の感情にすっかり支配されて、自分の人生すべてが不幸であるような気になっていた。でも、ちがう。感情には、人のすべてを支配する力なんてない。それが錯覚であることは、自分の内側にじっくりと目をこらせばすぐにわかる。いま、わたしの胸の中には、「かなしみ」がある。それは、直径15センチくらいの、丸い透明な水でできたボールのように、胸骨の真ん中あたりに、静かに浮かんでいる。しかしそれさえも、奇妙なことだがわたし自身の幸福にはちっとも関係がないのだ。封印する必要も、むりやり力づくで押し出す必要も、ない。常にそこにあり、ときどき冷たく心臓を冷やす悲しみを、ただ見つめているわたしがいる。かなしみがここにあっても、わたしはごはんをおいしいと感じられるし、夕日の美しさに感動できるし、大切な人と話して笑うことだってできる。悲しいけれど、幸せ。という感じ。ふしぎだな。かなしみの内側は、青い、森の奥の湖のような、静寂に満ちた場所だ。いつか、この悲しみがゆっくりと消えてなくなることを、わたしは知っている。ボールが暴れ出したら、深呼吸をして感情を味わいながら、一滴ずつ空へ返してやればいい。傷ついたことも、傷つけたことも、隠さなくていい。それはかわいそうなことでも、執着すべきことでも、自分や誰かを恨む筋合いのことでもない。ただ、傷という事実があるだけ。「まんなか」を忘れなければ、こわいものなんて何も、本当に何ひとつないんだ。
2006.07.24
コメント(0)
-
Slow Live '06 in 池上本門寺
アンサリーさんを聴くために、行ってきました池上本門寺の野外ライブ!いやあ、本当にすばらしかったです!アンサリーさんは小鳥がさえずるように、耳元でささやくように歌うけれど、それでも歌声に強烈な存在感があるのは、本当はすごーく張りのある、とおーくまで響く声を持っているから。とわかりました。自分の持つちからを全部使って声を張り上げるんじゃなく、ちからをコントロールして、静かに、心をこめて歌っているのです。「Over the Rainbow」がとてもとてもすてきで、音楽と一緒に、本当に虹の向こうへ飛んでゆけそうで、どきどき、ぞくぞく。目をつぶって、声を身体にしみ込ませました。「蘇州夜曲」も、緑の中の、夏の夕暮れにぴったり。空も、風も、葉っぱも、土も、みんなアンサリーさんの声に共鳴して音楽を楽しんでいるみたいでした。妖精さんのようなたたずまい。控えめで落ち着いた、飾らない様子。ひとつの焦りもない、ゆったりしたていねいな話しかた。わたしの大切なお友達にもこんな女性がひとり、いますが、同じ女性として本当に憧れる。胸がときめいちゃいます。野外ライブってお仕事以外では初めて来たけれど、すごくいいものですね。せみの声は伴奏に、お寺の林を包む夕日が照明に。緑と土の匂いに混じって、微かにお線香の香りが漂ってくるのは、お寺ならでは。音楽と木の天使さんがステージや客席の周りをうろうろしていて(…なんだかあぶない人みたいな発言ですが、本当にいたのです!)、ライトアップされた境内がとてもきれいで、神聖で。場内は撮影禁止なので、写真をお見せできないのが本当に残念!いろいろなスローフードの出店もあり、食い意地を発揮して、梅酢ジュースと赤ワイン、夏野菜のおそうめんに焼きおにぎり、ソーセージまで食べてしまいました。来年も来られたら、今度は誰か大切なひとを誘って、テーブル席に陣取り、有機トマトときゅうりのまるかじりを試してみよう!いろいろなことがあって絡まっていたきもちが、やさしくほどけていくようなすてきな時間でした。こういう時間がわたしの「まんなか」を形づくる、人生の宝なのだなあ。ここ数日ほとんど寝ていなかったので、まぶたは腫れ身体はだるく、心は千々に乱れていたのですが、多少むりをしても来て本当によかった!
2006.07.23
コメント(6)
-
よく晴れた朝には
夏の陽射し。コンコースには冷房もないというのに、この駅はなぜか涼しいのです。いったいなぜ??とふしぎに思って足を止めて心を静かにしてみたら、ああ、そうか!駅の構内に、たくさんの風鈴がぶら下がって、りんりんとやさしい音を立てているのです。改札を入ってホームに下りてみたら、ホームにも!一列に風鈴が並んで、さえずり合うようにかわいい音を響かせています。ちょっとテレビの音を小さくして、耳を澄ませてこの写真を眺めてみてください。…ね、聴こえるでしょう?
2006.07.22
コメント(2)
-
牛すき焼き弁当♪
駅弁は、列車の旅の大きな楽しみのひとつ。写真は米沢牛のすき焼き弁当(限定品)です。ひもをひくとじゅわーって湯気が出て(隣のおじさんがびっくりしてのけぞっていた)、7、8分でごはんも牛肉もあつあつのほっかほかになります。ふたを開けて、湯気を立てる牛肉に温泉たまごをぽとんと落とし、だしを回しかけ、唐辛子を振り、軽くまぜまぜしてごはんと一緒にいただきます♪うーん、至福。1300円は決して安くないけど、これはまた食べてもいいなあ!
2006.07.21
コメント(2)
-
東京駅にて。
東京駅のホームから見上げた夕景です。夕暮れは、地球上のどんな場所にも等しくやってきて、一瞬のあいだだけ、世界をやさしく包みます。さて、今月に入ってから3回目の旅です。すっかり旅慣れてきて、荷造りは最小限、体調を整えるカモミールのハーブティーと、何種類かのアロマオイル、それにカメラは欠かせません。写真をたくさん撮って、せっかくなのでおいしいものも食べてきます。…しかし、見送りも、出迎えもない新幹線の旅って結構さみしいなあ。
2006.07.20
コメント(2)
-

UA×菊地成孔「cure jazz」
疲れた身体を引きずって帰ってきたら、密林さんからメール便が届いていました。今日発売の「cure jazz」ジャケットかっこいい…着替えをする間ももどかしく、わくわくしながらプレーヤーに載せました。「Born to be blue」あーこれ!やばいよやばいよすっごいよ。とひとりつぶやくあやしいわたし。幸せだあ。こんなに幸せな音楽があっていいのか?そもそもUAって、こんな、包み込むような声でうたえるひとだっけ?ああ、そうか。UAは天才なんだった。七色の声を持ち、母にも恋人にも妹にも教師にも親友にも、愛にも恋にも冒険にも姿を変えられる。菊地さんのサックスが聴こえるころにはもう、心が半分溶けそうになっています。甘くやさしくあたたかく、息苦しいほどたくさんの、欲しかった音。「Over the rainbow」が始まるころには涙まで。去年、アートスフィアで、菊地さんがエンジェルの霧をまきながらこの曲を空に向かって鳴らした夜のことを思い出して、甘い恋の記憶に胸がきゅんとしてしまいました。このふたりの音は、もともとひとつのものだったみたいに、ぴったり寄り添って響くんだなあ。1枚のCDを、こんなに苦しい思いでこれほどていねいに耳を澄ませて聴くのは、生まれて初めて自分のお小遣いでCDというものを買った10歳のとき以来だ。これは、わたしが菊地さんの追っかけ(笑)だから言うのではなく、まちがいなく名盤と呼ばれるようになるだろうと。これからたぶん千回くらいこのCDを聴くんだろうなあ。ああ。ため息が止まらない。しあわせな夜。ライブ行ったら、どうなっちゃうんだろうわたし。
2006.07.19
コメント(4)
-

「ソーネチカ」「海からの贈物」「人生の旅をゆく」
最近読んだ本と、女性の生きかたについて考えたこと。ロシアの女性作家リュドミラ・ウリツカヤの小説「ソーネチカ」。幼いころから本の虫、青春時代を本に埋もれて過ごした主人公ソーネチカはある日、偶然図書館を訪れた芸術家ロベルトに見初められて…というロマンチックな物語。…と、思いきや、それだけで終わらせないのがこの作家のすごいところ。すべての女性がそうであるように、年をとり、容姿が醜くなり、運命の波にどしどし巻き込まれていくソーネチカの一生が、1ミリのごまかしもなく描かれています。もっとすごいのは、どんなすさまじい出来事の中にも、ソーネチカが必ず「しあわせ」を見つけ出すこと。果てしなく広がる本の世界を泳ぎ回ってきたソーネチカは、どこかの時点で、愛と幸福が外から与えられるものではなく、自分の内側にあるものだということを見つけたのでしょう。明け方、生まれたばかりの娘のターニャに母乳を与えながら、同時に、その広い背中で夫をあたため、家族の飢えを癒すことに限りない幸福を感じるシーンがとても印象的です。何もないところから愛を創り出して分け与えるちからはおそらく、神さまが女性だけに授けた特別な能力のひとつだと思うのです。世界で初めて、単独で大西洋を横断したチャールズ・リンドバーグの妻、アン・モロウ・リンドバーグは「海からの贈り物」の中で、「女はいつも自分をこぼしている」とそのことを表現しています。女はいつも、男や子供、社会のために、時間も気力も創造力も、そして愛も、すべてを与えつづけている。そして、文明の進歩と共に爆発的に広がった生活空間と、便利になると同時に創造性を失った家事に追われて、現代の女性は自分の「杯」をいっぱいにする時間も余裕もなくしている。というのです。半世紀近くも前、しかも、利便性と時間の短縮が絶対的な正義と考えられていたアメリカで、既にこんなことを深く考察していた女性がいたことを知るだけでも、この本は読む価値があります。付け加えるならば随筆の名手、吉田健一の訳もちっとも古びていなくて、日本語のうつくしさにぞくぞくします。では、どうすれば現代の女性は自分のコップを満たすことができるか。「一人になること」だとアン・リンドバーグは書いています。たとえば彼女にとっては、年に一度、一週間、海辺の質素な家で過ごす時間がそれに当たります。年に一度、月に一度、週に一度、あるいは日に一度、ひとりで過ごす時間が、自分の本質を見出し、魂に糧を与えてくれるのだ、と。それに加えて、できるだけ外側からの刺激を遮断すること。現代の日本にあふれる情報の量たるや、当時のアメリカの比ではないですね。せっかくひとりの時間をつくっても、気を紛らわすために次から次へと新しい情報を取り込んで過ごすのでは、いつまで経っても全然自分の中心に近づけないというのは、感覚としてわかる気がします。本能の要求に応えるためにモノを増やし、情報を増やし、価値観を増やしてきたはずなのに、ふと立ち止まってみたら「余計なものをいかに削るか」が精神的にも、物質的にもテーマになっているというのは、何だか皮肉だなあ!よしもとばななも、エッセイ集「人生の旅をゆく」の中で書いています。…今の日本では、おじさんと若い女性に重いものがのしかかっている。特に若い女性で、現実の要求にのまれて現実に参加できなくなったり、身体を壊してしまうひとがたくさんいる。(この辺りは、わたしの周りの聡明で美しく、生きることに真摯な女の子たちの多くがそうなので、すごーくわかります)彼女たちは炭坑のカナリアだ。部屋もきれいで、自分もきれいで、男並みに金は稼ぎ、男にかしづき、子も産み、情報に敏感で…などなど、到底不可能な、ありえない数の要求に、まじめな人ほど全部応えようとしてしまう。人生は一度しかない、自分はひとりしかいないということを忘れてしまう。自分の情熱を燃やすため、向いていることをやりつくすための人生なのに。愛情を抱き、すばらしい思い出を抱えて悔いなく死ぬためにここにいるのに。別にすごくなんかならなくてもいいじゃないか。日常の中で創造性を発揮し、小さなことに誇りを感じ、ペースを落として生きよう。…と、いうような主旨の文章です。初出は「ゆっくりAERA」、「単純に、バカみたいに」という題名のエッセイです。勇気づけられ、自分の中心を思い出させてくれる本当にすばらしい文章なので、立ち読みでも何でもいいので若い女性の方、ぜひ読んでみてください。…ちなみにわたしは、コピーして手帳に入れて持ち歩いていて、ほとんど暗記しています。ばななオタクなので(笑これらの本を偶然同じ時期につづけて読み、わたしがおもちゃみたいに小さな台所で料理をしているとき、体調を考えながらハーブティーをブレンドしているとき、感じている豊かさは、根拠のあるものだったのだなあと思いました。ずっとずっと、何千年も、ひょっとしたら何万年も昔から、女性がエネルギー源にしてきた創造的な時間。宇宙の恵み。女性には、男性から与えられるのでも、子供からもらうのでもなく、地球から吸い上げて、分け与える能力が備わっているのですね。すごいなあ女って!削ぎ落とす。立ち戻る。あえて手をかける。時間をかける。わざとゆっくり、歩く。そういうことが、これからの時代の、そしてわたし自身のテーマになっていく気がします。
2006.07.17
コメント(6)
-

「ハチミツとクローバー」最新刊☆
ついに出ました「ハチクロ」9巻!(上の写真はハチクロをイメージして撮りました☆)青豆ちゃんに聞いて多少覚悟はしていたものの、今までとはだいぶ毛色がちがうぞー。ずっしり重いです。人間の暗い面と本当の強さがしっかり描かれていて、もう、涙止まりません。だってはぐちゃんが!はぐちゃんが…読み終えたその足でまっすぐ最新刊のコーラスを買っちゃいました。けど、先月号で修ちゃんがはぐみに何を言ったのか、その肝心なコトバがわからないのです。ああー気になる。気になって夜も眠れません。また1年待たなくちゃならないのかー。ふう。羽海野さんの描く人物は、なぜだかわからないけど、ただの「登場人物」ではなくて、みんな魂を吹き込まれて生きて動いているみたいなのです。彼らの言葉ひとつひとつが、わたしの胸に、友達の言葉みたいにずずーんと響いてきちゃうのです。彼女たちがひとつつらいことを乗り越えるたび、わたしも「がんばらなくちゃ」って勇気をもらってしまうのです。これだけていねいに描いていたら、そりゃあコミック1冊分描くのに軽く1年はかかるよ、母さん!という感じです。…ちなみに「ダ・ヴィンチ」最新号はハチクロ特集です。大好きなばななさんの文章も読めるので、迷いなく買っちゃいました☆「テレプシコーラ」もたいへんなことになってます。千花ちゃんがー(泣さて、今日は妹を見送りに、東京駅へ行ってきました。東京駅って、特に新幹線に乗ろうとしているとき、ひとりでいるとほんとうに淋しい場所なので。いやあ、わたしなんぞは東京から飛行機に乗っただけだからまだましだけど、広島から出てきた妹は実際、心身ともにしんどかったと思います。「どんなに乗り物のスピードが速くなって、移動時間が短くなっても、疲れは移動距離に比例して、時間とは関係なく増える」とはかかりつけのカウンセラーさんの名言ですが、まさにその通りで。片道2日がかりでお葬式に来た妹の気持ちは、伯父さんに必ず伝わっているはず。仕事も人生も、無理するなよー。新幹線も便利だけど、時には各駅停車に乗った方が、よく見える景色もある。
2006.07.16
コメント(2)
-

パウロ・コエーリョ「11分間」
北海道へ連れていくのに手頃な大きさ、厚さ、読みやすさだったので、何気なく手にとって、飛行機の中で3年ぶりくらいに再読。主人公は売春婦、テーマは「愛とセックス」なので、そのとき自分が置かれている状況によって、読み返すたびに別の物語を読んでいるみたいな新鮮さがあって、本当におもしろい。世の中は愛と性をめぐる情報でいっぱいなのに、そのことを素直に、ありのままに、真正面から真剣に取り上げた本はほとんどないから、そういう意味でもすごく貴重な小説だと思う。印象的なのは鳥かごのエピソード。大空を飛び回る鳥に恋をした女が、罠をしかけて鳥をつかまえ、かごに閉じ込め、眺めて暮らす。皆はうらやましがるが、空を飛んで自分を表現する手段を失い、また、その必要もなくなった鳥は、醜くなって死ぬ。女は鳥のことを想って日々を送る。かごに入った鳥の姿ではなく、生き生きと雲の間を抜けていく彼の姿を。やがて、死が女を迎えにやってきたとき、彼女は初めて知る。自分が愛したのは、何よりも鳥の「自由」、姿ではなくそのエネルギーだったのだと。そうです。わたしたちはいつも、かごの扉を閉めることを、愛と勘違いしてしまう。本物の愛は、かごの扉も、外の世界につづく窓も、開け放しておくことなのに。そして人が、誰かを「失う」なんてことは、本当はあり得ないのだ。だってそもそも、人はほかの誰かのものになることなんて、できないんだから。
2006.07.15
コメント(0)
-
当たり前の日々
お葬式の朝。伯父が煙になる日。このころには、親族一同へろへろに疲れ果てて、読経のあいだ、あちこちで舟をこぎながら何とか座っているという感じ。いとこの子供たち(幼稚園のクラスがひとつ、作れるくらいたくさんいる)もだんだん疲れてきて、常に誰かが泣いたり走り回ったりし、目の下にくまをつくったお母さんがそれを抱き上げたり、追いかけて後ろから捕まえたり、年上の子供たちがそれを手伝ったりしている。この間まで若く元気だった人が年をとって亡くなり、一方でつい最近まで一緒に遊んでいた子供たちが、次の世代の子供をどんどん産む。わがままで手がつけられなかったやんちゃ坊主が、しっかりしたお母さんの下で、弱者にやさしい、すてきな少年に育っている。生々しいなあ、人のいのちは。それにしても、親戚の子供って、どうして食べちゃいたいくらいかわいいんだろう?もみじみたいなちっちゃい手とか、にたーっと笑う顔とか、ほわほわした髪の生え際を見ているだけできゅーんとして、嫌がる小さいひとたちを無理やり引き寄せ、ぎゅうっと抱きしめてほおずりしてしまう。ジーパンによだれを垂らされても全然きたないと思わないし。お世辞にも子供好きとは言えないわたしなのに、血のつながりってふしぎだなあ!いとこの子供でさえこうなのに、自分のおなかから出てきたひとだったら、一体どうなっちゃうんだろう。わくわくする。けれどどんなに好きでかわいくても、「他人さまを預かっている」というきもちを忘れてはだめだな。と、子育てをするいとこたちを見ていてつよく思う。町外れの焼き場で、棺を窯に入れるとき、わたしや妹とあまり年の変わらない従姉妹たちが半狂乱になって泣き叫んでいるのを見て、息が止まりそうになった。これがわたしの父だったら、わたしもたぶん、同じことをするだろう。喪失の悲しみで気が狂いそうになるだろう。けれど、いつかはたぶん、そのことを乗り越えて受け入れるだろう。どんなに大切な、かけがえのない、命がけで愛するひとが亡くなっても、わたしたちは自分の寿命が尽きるまで、生きつづけなければならないからだ。今日も北海道はじりじりと暑い。エアコンのお世話になるという習慣がないので、余計に暑いのだ。ぶんぶん回る扇風機が、旧式の窯からたちのぼる、人の体が焼けるにおいをかき回している。その中で、大人も子供も老人も若者も、みんな談笑したり突然涙ぐんだりしながらごはんを食べる。待つのに飽きた子供たちはピンクのバッタを捕まえるのに夢中になったり、おばさんに花冠の編み方を習ったりしている。大人もひそひそ声でうわさ話や今後の推測をするのに飽きると、高鼾をかいて昼寝をはじめる。そうこうするうちに安っぽい電子レンジみたいな音がして、伯父が骨になったことを皆が知る。伯父の骨は驚くほど少なく(塗料に入っているシンナーを吸っていたせいじゃないか、と後で兄が教えてくれた)、窯から噴き出した熱で蒸し風呂のようになった部屋で、皆黙って汗をかきながら骨を拾う。人はいつか死ぬ。だから後悔しないように、この世界の美しさを目に焼き付け、大切なひととかけがえのない思い出を作ってしっかり生きなさい。と死者たちが教えてくれるのだとしても。あと何回、わたしはこのさびしい場所で骨を拾うのだろう。とふと思いついてしまうと、孤独に胸がつまりそうになる。わたしにとって死の恐怖とはまだ、大切なひとを失うことの喪失感を意味している。大切なひとと、当たり前の幸せを共有する日常を犠牲にしてまでやり遂げなければならない「何か」なんて、人生にはたぶん、ない。少なくとも、わたしにとってはそう。それは別に特別なことじゃなくて、おいしいものを一緒に食べるとか、きれいな夕焼けを一緒に見るとか、くだらない冗談を言い合って笑うとか、つらいときはできるだけそばにいるとか、そういうシンプルなこと。この3年くらいで、そのことがようやく、わかるようになった気がする。
2006.07.14
コメント(2)
-
時間の記憶
7時起床。慌ただしく身支度をして家を出る。荷物重いし寝不足だし汗だくだし、ふたりともいらいらしてけんかしながら、それでも何とか羽田へたどり着き、飛行機に滑り込む。お昼すぎ、北海道に到着。空港へ迎えにきてくれた父の痩せたシルエットに、去年、祖母が亡くなったとき、空港までわたしを迎えにきてくれた伯父の姿が重なって、どきっと胸が痛くなる。 北海道はこの夏いちばんの暑さだって、みんな口を揃えて言うけれど、むしむしべたべたの東京からやってきたわたしたちには、まるで天国。風は涼やかで、空は高く青く、そしてとても大きい。空港から車で1時間半。白い木の箱に納まった伯父の身体は急に小さくなり、若々しかった顔はまるでおじいさんみたいに疲れ切ってみえる。もう、悲しみも喜びも痛みも、何の感情も浮かんでいないその顔を見てようやく、ああ、伯父はもうここにいないのだとわたしは知った。でも、どうして?いたずら好きの男の子みたいに、どんなときも、悲しいときほどわざとふざけて皆を笑わせる伯父のあかるい声と表情を、わたしは昨日のことみたいに、いつでも記憶の引き出しから取り出せるのに。もういないなんて、誰が言えるんだろう。誰が決めるの? 北海道では、お葬式ではなくお通夜の晩に、親族以外のひとがたくさん集まる。伯父の通夜には、小さな田舎町の葬儀場には到底入り切らないほどのひとが集まり、ホールには端までずらっと花が並んだ。献花の名前はいつも、この町で行われるどんなお葬式のときも、伯父のすっきりした迫力のある流麗な文字で書かれていた。(親族のお葬式になると、本家のテーブルの上に筆と硯を並べて、背筋を延ばしてその前に座った伯父が、そこにいる親族の名前を「献花」の紙に片っ端から書いていくのだけれど、それはまるで、美しい踊りを見ているようにきもちのいい光景だった)それなのに。なのに伯父のお葬式のときだけ、別の人の文字が式場に並んでいることがとても奇妙で、「あ、いけない」と思ったときにはもう涙が止まらなくなっていた。ホールの外に出て深呼吸したら、見上げた夕焼けがきれいで、息が止まりそうだった。ああ、そうか。誰かが亡くなるというのは、つまり、これ以上その人をめぐる記憶が増えないということだ。大勢の親族が遺影の前に長机を並べ、夜通しにぎやかに酒盛りをするのも毎度のこと。物心ついたときから見慣れた光景だ。ただひとつ、子供のころとちがうのは、人は心のなかに喜びより悲しみの方が多くあっても、むしろ、つらいときの方が多いからこそ、集まると酒をのんで笑うのだと知ったこと。笑い合っているこのひとたちはみんな、それぞれに千差万別の運命と、愛憎うずまく日常を抱え、人に迷惑をかけたり傷つけたり傷ついたり恥をかいたりしながら、必死に生きているんだ(たとえば、わたしの両親でさえ)。大人になるということは、かっこいいことでもなんでもない。まして、幸せを約束されることでもない。それは、毎日の小さな、膨大な数の決断の中にしか存在しない。たとえば伯父は、あまりにも理不尽な苦労をたくさん、たくさんした。けれど伯父が運命や人を憎んで亡くなったとは、わたしは思わない。伯父はたぶん、自分で決めてきた宿題をきちんとやり終えたのだ。しなくてもいい苦労なんかひとつもなかったんだし、いま亡くなったことを若すぎると泣いて過ごすのは、たぶん、伯父の意にそぐわないだろう。わたしたちにできるのは、今いる場所に根を張って、じぶんの人生をきちんと全うすること。ほかには何も、本当に何もないのだ。だって伯父さんとすごした時間の記憶は、わたしのなかに確かに刻まれていて、それはわたしが死んでも伯父さんが亡くなっても、消えることがない。人が人に残すことができるものは、金でもモノでも名誉でもない。未来永劫つづいてゆく記憶だけなんだ。
2006.07.13
コメント(4)
-
三たび鍵をめぐる冒険
すごい勢いで今日の(…ってか今週の分ぜんぶ?)仕事を終わらせ、東京駅で妹を出迎える。いったんわたしの部屋へ荷物を置き、喪服を取りに実家へ戻る…はずが、母が郵便で送ってくれたはずの家の鍵がまだ届かない。つくづく鍵に縁のない俺の人生!(下町で自転車の鍵をなくす事件・マンションの鍵破壊事件参照)仕方ないので、ひと休みしてからふたりでデパートへ行き、黒いスーツとインナー、ストッキングにかばんに数珠まで一式ぜんぶ揃え直すはめに。とほ。あまりにたくさん黒いものを買ったので意識がもうろうとし、ふたりでレベッカ・テイラーに入って、ものすごーくかわいい夏のワンピースを一枚ずつ買う。妹のは青。わたしのはしっとり落ち着いたピンクの花柄。ノースリーブだけど襟元までボタンがついていて、ボタンの脇には肩から腰まで縦に3本フリルがついていて、まるで赤毛のアンみたいなのです!とっておきの日におろそう。菊地さんとUAのライブにも着ていこう。あーもうこのワンピースのことを考えるだけで、たいていのことはがんばれる気がする。荷造りをして、眠りについたのは結局3時。明日は早起きして北海道へ向かいます。
2006.07.12
コメント(0)
-
伯父さんのこと。
今朝早く、伯父さんが亡くなりました。両親の仲を取り結び、わたしと妹が生まれたらものすごくかわいがり、いつも笑わせてくれた明るくてやさしい、大好きな伯父さん。ものすごく手先が器用で達筆で、車で町を走っていて、ちょっと気の利いた看板を見かけたらそれは十中八九伯父さんの作品、というくらいでした。だけど去年の春、おばあちゃんが亡くなったときに空港で会ったおじさんは、前よりうんと険しい顔をして、急に年をとったように見えました。あれは、おばあちゃんが亡くなって悲しくつらい、というだけの険しさではなかったのだと、今になって思います。いつだって「いま、このとき」を楽しんでいるように見えたあの明るさが消え、焦って遠くを見ている感じだったのです。そのことを思うと、わたしは心臓をぎゅっとつかまれるような思いがします。ゆっくり話をしたのは、あのときが最後になってしまったけれど、あれから1年の間に、1度でもいいから伯父さんが心から笑ってくれていたらいいな、と思います。たくさん働いて苦労もひと一倍だったから、どうか向こうでおばあちゃんと、おじいちゃんとゆっくり休んでほしい。残された者の気休めなどではなく、心の底から、腹の底から、吐くようにそう願います。大切なひとが、いて当たり前だと思っていた人たちが、次々にこの世を卒業していく。いなくなるなんて思ってもみなかった。思ってもみなかったよ、伯父さん。わたしにできることは?甘えずに、姿勢を正して、日々を大切に生きること。明日わたしが、あるいはわたしの大切なひとがいなくならないという保証はどこにもないのだから、毎日のなかにひとつでも宝物を見つけ、心から笑って、笑わせて過ごすこと。迷わないで、おそれないで、大切なひとに寄り添って、できるだけたくさんの時間をそばにいて過ごすこと。わたしには書くことしか能がないから、つらくて死にそうでもうれしくて天に昇りそうでも、とにかくこうやって書きつづけること。朝、妹から知らせを受けてショックで頭が真っ白になりました。覚悟はしていたけれど、だって、こんなに早く? どうして?手がふるえて仕事にならず、しかもこんな日に限って仕事がたくさんあるので、いざというときのために各種薬を入れて持ち歩いているポーチを開けました。どの薬をのんだらいいかも考えられなくて、「いま、わたしに必要な、しかも副作用のでない薬を教えてください」と守ってくれるひとにお願いしたら「ドグマチール」と教えてくれました。でも最近はソラナックスしか飲んでないんですが? と聞いても、やっぱり「ドグマチールならだいじょうぶだよ」と言うので、ドグマチールをひとつぶ、飲みました。そうしたらすーっと心が鎮まって、妹とわたしが伯父の住んでいた北海道へ行く段取りや、明日中に最低限の仕事を片づける知恵がどんどん浮かんできて、ひとつずつ順番にこなしていくうち、だいぶ落ち着きました。頼りになるなあ、後ろの方。いつもありがとうございます!あ、そうか。伯父さんもきっと、こんなふうに、こっちにいたときと同じようにわたしたち一家を心配して、これからはずっとそばにいてくれるんだ。…すぐには割り切れないけれど、とにかくひとめ会って(たぶんすごく泣いてしまうなあ)、ちゃんとお別れをしよう。ふう。今月はどうも、日本中を行ったり来たりする星回りのようです。こういうときこそ、慎重に行動せねば。追記:広島写真日記、ついに完結しました(笑
2006.07.11
コメント(6)
-

妹とふたり旅をしてきました☆縮景園編
2日目の朝は8時起床。3方をぐるりと海に囲まれたレストランで、コンチネンタルブレックファースト。海を横切っていくボートの軌跡が波紋をひろげて、とってもきれいです…(レストランにカメラ持っていくの忘れたので、携帯で撮りました。なんだか茫洋とした写真になっちゃいましたが、雰囲気だけでも)しかし昨日はしゃぎすぎたおかげで、ふたりともだいぶ疲れています。かわいい広電に乗って、縮景園へ。レトロな車体は昭和40年、大阪市電から譲り受けたものだそうです。たくさんの人の暮らしを運びながら、大切に使われてきた幸せなのりもの。それにしても、昨夜の嵐がウソのようないいお天気。…というか、蒸し暑くて死にそうです。それでも、水と緑のある縮景園の中はふしぎに涼しく、ほっと息がつける感じ。昔の日本にはエアコンなんてなかったけれど、こんな場所が町のあちこちにあって、いくらでも涼むことができたんだろうなあ。暑いので、つい水辺の景色ばかり撮っています。見えますか?真ん中左寄り、石の上に小さくちょこんと登ったかめの姿。かめも暑そうにぐったりしてます。締めのランチはMIKUNIカフェ。隣の席の女性2人組が、どうやら広島のセレブ☆妻で、ものすごい赤裸裸トークを繰り広げています。「うちの○○ちゃん(夫のことと思われる)なんかね…(こわいので以下略)」「うちのお義母さんがね…(食欲が減退するほどこわいので以下略)」「子供産むとき、痔にならんかった?」「抜糸がね…(もう言葉も出ません。無言で俯くピュアな姉妹)」それにしても、広島の女のひとって、話すときほんとに「じゃけん」って言うんだなあ。(話の内容はともかく)すごくかわいい。ところで今回は、弱ったわたしの心がやめた方がいいというので、あえて原爆資料館には行きませんでした。けれど、たとえばバス停や路面電車の駅名にさえ「原爆ドーム」という言葉が使われており、路線図にも載っているし車内アナウンスでも流れ、これはおそらくわたしがよそ者だからなのだが、「原爆」という言葉を見かけたり耳にするだけで、子供のころから日本人として蓄積してきたさまざまなイメージが喚起され、目の前がくらくらした。身体にしみ込んだイメージが持つ力って、すごい。特にいま、わたしはよくも悪くも感受性がむき出しのゆで卵状態なので、風の匂いや何気ない街の景色のいたるところで、ふとした拍子に、街の「記憶」に触れてしまう。暮らしている人も気づかないほど明らかに、すべての瞬間の中に、当たり前のように悲劇の断片が滑り込んでいる。どんな明るい出来事の中にも、くだらない会話の中にも。世の中がどんなに変化し、平和の尊さなどという建前が風化しても、この街を訪れればそれだけで、理由などないが戦争は悪。核は使ってはいけない。人を殺してはいけない。穏やかに過ぎる日々はかけがえのないもの。ということを肌で感じられる。街の記憶というのは、それほどすさまじいものだ。それはいま、わたしが暮らす下町でも同じ。絨毯爆撃を受けて火の海になった夜のことを、人が変わり建物が変わっても、水が、風が、土が憶えている。自転車で橋を渡りふと夕焼けを見上げた瞬間に、風向きがそのことを教えたりするのは、日常茶飯事。前に仕事をしていた街はもっと顕著で、11年前の地震の傷から、街も人も血を流しつづけていた。人の生活が破壊され、命が奪われるというのはそういうことなんだろう。リセットボタンはない。元に戻すことはできない。悲しみ、絶望、その泥の底から生まれる希望。それら人の営みにはおかまいなく、ただ、黙々と土に刻まれていく。さて。広電で居眠りしながら駅へ着いたら、あっという間に新幹線の時間です。独身のうちに、またふたりで色んなところへ旅行しようね、と約束して別れる。はじめてのひとり暮らしで、慣れない仕事もつらいだろうが、1年もすればきっと楽になるからね。と思いながら手を振る。そして新幹線のホームでふと、もうわたしたち家族が4人で同じ屋根の下、ごちゃごちゃ集まって暮らすことはないのだなあと思いついてしまい、不覚にも涙が。なんて大切な、宝石のような時間だったんだろうあのときは。時間は戻らない。東京で暮らすいまだって、きっと10年後には宝物になっているだろう。わたしはどうも、ずっと東京にいる気がしないので(おそらく日本の田舎にしばらく住み、やがて外国へ行くでしょう。電線のない国へ!)、とにかく今を大切にしよう。こんなとらえどころのない街にも、数えるほどだが地道な時間を積み重ねてきたすばらしい場所がある。そういう場所へできるだけたくさん足を運び、シャッターを切り同時に言葉をつづり、心にしっかりとスクラッップしておこう。それだけがわたしの、死んでも消えない宝になる。
2006.07.09
コメント(0)
-
妹とふたり旅をしてきました。
妹の住む町で、週末を過ごしてきました!じゅうでーん!(←「のだめ」ふう)日記はまたゆっくり書きますが、とりあえずフォトアルバムを公開したのでお知らせです。左のフォトアルバムで「ほかのフォトも見る」をクリックするとアルバムが開きます。機能を使い慣れていなくて、時系列が逆さまになってしまったので、お手数ですが反対側から見ていただいた方が旅のきぶんが味わえます。写真はぜんぶで30枚くらいあります。しばらく皆さんにみていただいたら、このブログからは片づけてしまっておくつもりなので、よろしければお早めに。では、ごゆっくりお楽しみください♪にゃ。
2006.07.09
コメント(8)
-

妹とふたり旅をしてきました☆厳島神社編
宮島あなご編☆の続きです。ビール飲みながら書いてます。つまみはたたききゅうりベトナム風(塩もみきゅうり、しそ、香菜、ミントをすりおろしにんにく、ナンプラー、ごま油で味つけ)と、めかぶ&オクラ(残ったら炊きたてごはんにざばっとかけてがつがつ食べます。じゅる)。とにかく緑のものが食べたかったので、やたらヘルシーです。…そんなわけなので、乱文乱筆ご容赦ください。さて。ぶじ宮島に上陸し、厳島神社に到着したわれわれ姉妹。厳島神社は、まさに聖地。海と溶け合っているせいもありますが、鳥居の内側は、歩いているだけで、気の滞りがすこーんと抜け、つま先から頭のてっぺんまで、きもちよく流れ、心が広がっていくのがわかります。あー書いているだけできもちよくなってきた。とにかくすごいところで、わたしや妹のようなふつうの人でも、自然と背すじが伸び呼吸がふかくなります。たくさん写真を撮り、土とひとつになって、木の中に溶け込む感覚を味わいました。なんだかヨーガの瞑想みたいです。境内では宮大工さんが、干潮の時間を利用して、傷んだ欄干にうるしを塗り込み、修復する作業をしていました。竹本くん…(いえ、ひとりごとです)こうやって、連綿と脈々と、ひとつの場所が守られていく、その流れのうつくしさよ!きりりと海を見据え、神さまを守る狛犬さま。町並みも、昔のまま手を加えず、そのまま残されています。ほうっと息がつける感じ。天然石のお店で、トルコ色のペンダントを買いました。ハウライト、という白い天然石にトルコ色の塗料をしみ込ませた、いわばトルコ石の模造品です。お店にはもちろん、本物のトルコ石のアクセサリーもたくさんあったのですが、なんとなく色がきつい感じがして、どうしてもこれ。ハウライトのペンダントが欲しかったのです。調べてみたら、トルコ石は、人望や仕事運などの意味があるのに対し、ハウライトは肉体と精神を強化し、強迫神経症などにも効果があるそうです。なるほど。いまのわたしに必要なのはトルコ石じゃなくて、ハウライトだったんだなー。夕涼みに入ったかき氷屋さん。懐かしい店構えがなんとも言えずよい。かき氷もすごくおいしかったです。ふらふらになるまで一日遊んで、周囲をぐるりと海に囲まれたプリンスホテルへ。それほど高くない値段で、ひとつ上のお部屋にグレードアップできると言われたので、そうしてもらいました。まさかこんな夜景が見られると思っていなかったので、びっくり。外はあいにくの雨でしたが、最上階のバーでジャズの生演奏を聞きながら軽めのコース料理をいただき(大人になったなあ…)、妹とゆっくり、ゆっくり大切な話をする。妹とは、家族に生まれていなくてもきっと、どこにいても必ずお互いを見つけ出し、かけがえのない親友になった気がする。それにしても、物心ついたころからあんなに感情をぶつけ合い、取っ組み合いのけんかまでした相手と、こうやって1ミリのわだかまりもなく自分をさらけ出してごはんを食べられるんだから、家族ってほんと、すごいしくみだなーと思う。新しく家族をつくる相手は、レンアイカンジョウはさておき、そういう視点で選ばないとだめね。ホテルの部屋でカンパリオレンジをつくり、乾杯。旅の夜はふけてゆくのでした。(明日につづく)
2006.07.08
コメント(2)
-

妹とふたり旅をしてきました☆宮島アナゴ編
朝、6時に起きて新幹線に乗り、広島へ着いたのはお昼過ぎ。こんなに西へ来たのは、ひょっとしたら生まれて初めてだなあ。妹はふんわりしたロングスカートにレースの縁取りのついたキャミソールを合わせ、髪を斜めに結って、涼しげな夏の装い。妹の方が背が高いし大人顔だし(わたしは童顔で背もちっこいので)、わたしはいつものGパンにてんとう虫のTシャツだし、どう見ても完全に姉妹が逆。それにしても、ずいぶん大人っぽい顔をするようになったなあ、この子は。JRで宮島口へ。駅に降り立つと、見渡す限りもみじ饅頭屋。「もみまんソフトっていうのがあってね、ソフトクリームの上にもみじまんじゅうがのってるの」という何がなんだかわからない妹の説明に、もしやランチはもみじまんじゅう…と怯えていましたが、明治34年創業のあなごめし屋さん「うえの」に連れて行ってくれました。店先で働くかわいいロボット。待合室で福を招くロックな招き猫(9日の記事参照)。あなごめし!あんまりおいしそうなので、写真とるまえに左側ひとくち食べちゃいました。あなごがふかふかで、炭の香ばしい香りがして、塩味がしっかりきいていて、ごはんはやわらかめで、とにかくこんなうまいあなごは食べたことがない。今まで食べてたあなごは、別の魚だったにちがいありません。なかなかの量だった上、最近のわたしは食欲にムラがあって、お昼は食べられないことも多いのに、あっという間にぺろりと完食。フェリーに乗って厳島神社へ。見えますか?海の上にヘタウマ文字で「かき」って書いてあります。名産なのはわかるけど、何も海の上にまで書かずとも…宮島は、鹿がいっぱいです。鹿せんべいなんか買わなくても、人間が来ると寄ってきます。そしてエサを持っていないことがわかったとたん、一気に熱がさめて去っていく…駅に降りたときは珍しくて写真を撮りまくりましたが、帰るころにはもはや違和感ゼロ。そのあたりで寝そべっていたただの柴犬を、鹿とまちがえるくらいでした。そしていよいよ厳島神社に…乗り込むのですが、時間切れになってしまったので、続きは後ほど。お楽しみに!
2006.07.08
コメント(2)
-

愛する言葉
ちょっと、ふつうに生きていたらまず関わらないような人から早朝6時、いきなり自宅に電話がかかってきて起こされ、飛び上がるほど驚き、びっくりしすぎてものすごくきびきびとていねいに応対してしまい、混乱のあまり電話を切った瞬間に二度寝して、会社に遅刻しそうになった。人生ってほんとに、明日のことなんかさっぱりわからなくて、だから結構おもしろいのだよなあ。別に無理やり修羅場に突っ込んでいかなくても、日々おもしろがって生きていると、おもしろいことが向こうからどんどん飛び込んでくる。それにしても、お国訛りが素朴であたたかく、すごくやさしくてきちんとした人だった。ああいうひとが近くにいるなら安心だな。よかった。それにしても朝6時って…あまりと言えば、あんまりだ。(いや、ひょっとして、わたしの生活時間が夜側にずれているだけで、ほんとはそんなに非常識でもないのかな?)なんとなく読みたくなって、最近、おふろに入る時間に岡本敏子さんの本を読み返しています。岡本太郎さんと、敏子さんが「愛」について語った言葉を集めた刺繍(詩集、と書こうとしたら誤変換されましたが、こっちのほうがしっくりくるのでそのままに)のような本です。わたしは女なので、太郎さんの言葉は「へえ、純粋だなあ。ロマンチックだなあ。でもちょっときれいごとだなあ」と思っちゃうのですが、敏子さんの言葉はすごいです。「子宮の中にくるみ込んで、あっためてあげたい」とかね。水の滴るような生身の言葉。並大抵の覚悟では言えないですよ。女ってつよい。このふたりの関係について、世間はいやらしい憶測で今もいろいろなことを言いますが、この本を何ページかぱらぱらめくれば、「ははあ。世間がどうとか常識がどうのとか、もうそんなことはどうでもよく、どうでもいいという次元さえ超えて、ただただ強くまっすぐに愛し合っていたのだな」ということがよくわかります。人間ってほんとはすごく単純な生きもので、だけど、そのことを認めて無防備になるのがこわいから、頭の中で理屈をぐるぐるこねくり回して、勝手に複雑にしているような気がする。それからこれ↑は、敬愛するばななさんとの対談集。何度読み返しても新しい発見があります。今回は、「もう肩のちからを抜いて、好きな本を読み好きな音楽を聴き、好きな服を着て、好きな文章を好きなだけ書き、誰かをばかみたいに死ぬほど好きになって、傷つくなら正面からずばっと切られてどばどば血を流し、若いうちにたくさん子供を産み、げらげら笑って死のう」と決意をあらたにしました。だって、人の真似をして生きるなんて、本当にくだらない。人生は、たった一回しかないのに。「生まれてくるには、ものすごくたくさんの手続きや申請が必要で、結局その資格が得られない魂もいて、とにかく身体を持ってこの世に生まれてくるっていうのはすごーく大変なことなんだから!」と、おとといのオーラの泉で美輪さんがまるでアフリカ旅行の話のように力説していたし。せっかく苦労してやってきた旅行なんだから、楽しまなかったらこれはもうぜったいに損だ。青山の、岡本太郎記念館。岡本太郎さんの作品のことは「へえ、色がきれいだなあ」とか「うわあ、かわいい形だなあ」くらいしかわからないけれど、この場所は敏子さんの愛がしっかりと根を張っていて、すごーく気の巡りがいい。庭にある、木でできたへんないきもの(「もののけ姫」の木霊にちょっと似ている)もおそらく魂が入っていて、抱きしめたいほどかわいいんだよなあ。ひさしぶりに会いたい。まだ元気にしているかしら。書いていたら、無性に行きたくなってきた。今度、天気のいい日にふらりと見てこようっと。…明日から、1泊2日で妹に会いに行ってきます。写真をたくさん撮って、言葉でもどんどんシャッターを切って帰ってくるつもりです。おみやげにハーブティー持っていこうかな。
2006.07.07
コメント(2)
-
焼きたてクロワッサン。そして夏の豆カレー。
雨降りで、遠出するのが億劫な日は、あのコーヒーのおいしい喫茶店で遅いランチを食べます。片手の指で足りるほどしか通っていないのに、わたしの顔を覚えて、隅っこ(書きものをするので好都合)の同じ席に案内してくれるやさしい店員さん。ノートを広げて豆の香りをかぐだけで、もう心が穏やかに、しずかになります。コーヒーは「苦すぎるのが得意じゃないんですが、どれがいいですか?」と店員さんに相談して、さっぱりしたエチオピアを注文。自家製クロワッサンにはさんだクリームチーズとたまごのサンドイッチも、ひとつひとつすごくていねいに作られていて、コーヒーも心をこめていれてあるのがわかります。大雨なのに常連さんが次々とやってきて、「いつもの」席に座り、「いつもの」コーヒーを頼んで、雨宿りついでにおしゃべりして、さっぱりした顔で帰っていく感じ。とても居心地がいいのです。クロワッサンもあんまりおいしいので、朝ごはんにしようと思っていくつかテイクアウトしてきました。歩けるようになったばかりの子どもを連れたお母さんもやってきて、やんちゃに駆け回る男の子を、マスターも店員さんもお客さんも、みんなでにこにこしながら見守り、自分のテーブルに近づいてきたら抱き上げたり、遊んだりしている。子どもを産んで育てるなら、こんな喫茶店のある街がいいなあ。ところで最近、街で無邪気な小さいひとを見ると、うれしくなってにこにこしてしまうのです。何年か前まで、子どもはちっとも好きじゃなかったのに(だって、繊細じゃない子どもって、生きている時間が短いということを盾にして、明確に人格を傷つける意図を持って、ものすごく残酷なことを言うんだもの)。自分のおなかから小さいひとが出てきたら、きっと、かわいくてかわいくて、そのひとのためなら死んでもいいし、その子に危害を加える人がいたら平気で罪も犯すだろうなあ、と想像したりもする。だけどまあ、そのためには、まずお父さんを探さないとならないしなあ。めんどくさ…などと言ってはいけません25歳の乙女が。もうちょっとめげずにがんばります。それにきっと、小さいひととどっぷり深く付き合うには、体力や気力も充実してた方がいいし、まだもう少しひとりで充電しようっと。などと思いながら、玉ネギを泣きながら刻んで炒め、赤ワインを飲み、玉ネギの鍋に大量のひき肉を入れ、オリーブをつまみ、にんにく、唐辛子、ガラムマサラ、カレー粉、ナンプラー、豆板醤、塩、完熟トマト、にんじんの絞り汁などをじゃんじゃん鍋に放り込んでさらに煮込み、またワインを飲み、ぐつぐつ音を立てるカレーのそばで過ごす「構造5(笑)」の夜。自分のほかに、誰も料理を待つひとのいないキッチンで何かを煮ている音や匂い、その時間は、心の安定にとても、とても役立ちます。…これはまだしばらく、やめられそうにありませんな。写真は、喫茶店の前で雨を受け止めていたあじさいの葉っぱ。きもちよさそうだなあ。
2006.07.06
コメント(4)
-
虫よけ・虫さされのためのアロマテラピー
梅雨です。夏です。薄着とミニスカート、花火大会に海!キャンプ!の季節です。涼しい夜は、できればエアコンのスイッチを入れずに、窓を開けて網戸から自然の風を入れて、かすかな風鈴の音に耳を澄ませながら眠りたいものですが、そんな夜、必ず乙女の安らかな眠りを妨げる輩がいます。そう。あれです。耳元でぷーんとうなる目障りなやつ。人の柔肌からただで血を吸った上、たまらないかゆみまで残していく「あいつ」です。蚊取り線香も夏らしくていいけれど、虫が目を回して落っこちるのと同じ成分を自分の身体にも吸い込むのは、どうもきもちわるい…という貴女のために。アロマオイルを使った虫よけスプレーと、お肌にやさしい虫さされクリームの作り方をご紹介します!アロマオイルは100%天然のやさしい成分なので、市販のスプレーや薬品のような強力な効果はありませんが、人の身体にプラスの効果をもたらす、すっきりした香りと一緒に虫さされ対策ができたら一石二鳥、ですよね?お肌が敏感な方や、化学物質にアレルギーのある子どもにも安心して使えます。【虫よけスプレー】エッセンシャルオイル(精油) レモングラス…4滴 ティートゥリー…3滴 ゼラニウム…2滴 ラベンダー…1滴アルコール(無水エタノール)…3ミリリットル水(ミネラルウォーターか精製水)…50ミリリットルスプレー容器(1)アルコールに精油を1滴ずつ加えてよく混ぜる。(2)そこに水を加えてさらに混ぜ、スプレー容器に移して完成。あーら。なんて簡単なのでしょう!精油の種類がそろわなければ、10滴以内に収まるように2~3種類でブレンドしてみてください。ここに挙げた精油のほか、ユーカリ、シトロネラ、フランキンセンス、バジル、レモンも効果的です。使うときは必ずよく振ってから、手足やカーテン、網戸に吹きつけて使ってください。スプレーも作るのが面倒なら、これらの精油をアロマランプや熱湯を張ったマグカップ(使った後はよーく洗ってください)に落として焚くだけでもだいぶ違います。虫さんがそうっと遠回りして逃げていきますよ。【虫さされクリーム】エッセンシャルオイル(精油) カモミールジャーマン(なければカモミールローマンでも)…2滴 ラベンダー…1滴 ゼラニウム…1滴ミツロウ(細かく砕いてあるものが使いやすい。ミツバチさんが出す天然ワックスです)…3グラムキャリアオイル(なんでも。ホホバオイルかスイートアーモンドオイルがおすすめです)…15ミリリットルガラス製クリーム容器(1)ミツロウにキャリアオイルを加え、湯せんで溶かす。ガラス製の容器なら、殺菌消毒してからそのまま湯せんにかけてもだいじょうぶ。(2)ミツロウが完全に溶けたらあら熱をとり、固まる前に精油を加えながら清潔な竹ぐしでよく混ぜる。常温で冷まして固まったら完成です。のんびりしていると、あっという間に固まっちゃいますよ。蚊に刺されたところに塗ると、穏やかにかゆみを抑え、お肌もきれいに戻してくれます。材料は、すべて、全国のアロマテラピーショップで手に入ります。スプレーと同様、精油は濃度が変わらなければお好みでブレンドを変えても構いませんが、カモミールはぜひ!ほかに、ゼラニウムやティートゥリー、フランキンセンスが効果的です。※一般的な注意直接肌につけるものなので、精油の濃度は必ず守ってください。たくさんつけたり、精油の量を増やしても、効き目は変わりません。防腐剤を含まないので、スプレーは2週間、クリームは1カ月くらいで使い切ってください。とても、とてもやさしい成分ですが、まれにお肌に合わないことがあるので、敏感肌の方や赤ちゃんに使う場合は、腕の内側などに少量つけて、かぶれが出ないかどうかテストすることをおすすめします。…精油の香りと効果をあれこれ思い浮かべながらレシピを書くのはすごーく楽しかったので、アロマテラピー活用法で知りたいことがあったら、リクエストしていただけるとうれしくてはなぢ出ちゃいます(だりりんさん、ありがとうございました♪)。何しろ「アドバイザー」なので、誰かにアドバイスしたくて日々うずうずしているのです。リアルでお知り合いの方には、うれしさのあまり作って送っちゃうかも!病院に行くほどではないけどつらい心身の不調や、掃除、洗濯、部屋の除菌などなど、大抵のことにはアロマが想像以上に役立つのですよ。次回(…っていつだ?いつから連載が始まったんだ??)は、夏にぴったりのさわやかルームフレグランスか、汗かきさんのためのコロンの作り方を書こうかなあと思います。お楽しみにー。
2006.07.05
コメント(8)
-
DCPRG@渋谷O-EAST
菊地成孔さん率いる「デートコースペンタゴンロイヤルガーデン」のライブに行ってきました!菊地さん追っかけ仲間(わたしが引きずり込んだ)で、親友で人妻の青豆ちゃんと一緒に。…えー、今日の日記は、これまでの平均から言ってかなり過激なので、心臓の弱い方は注意してください(笑)で、われわれは女の子ですから、お互い夫や恋人に言えないことをどっさり腹の底にためてますから(笑)、ましてわたしの恋人は青豆ちゃんのふるいお友達でもあるので、ふたり集まればもう何時間でも一晩中でも何日でも、話すネタには事欠かないのです。結局、ライブが始まる前に相当テンションを上げてしまい、アルコールが入ったこともあり、おそろしく人口密度の高いO-EASTの薄暗いフロアで2列目に陣取るころには、もうへろへろ。…ちなみにデートコースはふたりとも初体験で、勢いだけでチケットを取ったので予習もしてません。これから180分、この状態で耐えられるのか?という不安のうちにフロントアクトが終わり、もこもこの帽子(尻尾ついてました。かわいい)をかぶり、へんなハーフパンツを履きジャージを着た菊地さんが目の前に。ああ、きくちさんきくちさんきくちさん…と思っていたら、さっきからむかむかしていた胃が、突然逆さまにひっくり返るような吐き気。そして案の定、目の前が真っ暗に。「ああ、卒倒するってこういう感じなんだ。へえ、生まれて初めてだな」などと頭の隅で一瞬冷静に思ったりしたのですが、慌てて我に返り、青豆ちゃんにお願いして、いったん後ろに下がることに。トイレで頭を冷やし、前の方で踊り狂う人たちとすさまじい音の洪水に思わず耳を塞ぎながら「…前の方にいなくて本当によかったね…」「…うん」「1曲だけ聴いたら出ようか…」「うん…」と話し合う私たち。しかしどこが曲の切れ目なのかもわからず、何となく出るタイミングを失ってぼんやり階段に座り込んでいるうちに、だんだん、吐き気が妙なきもちよさに変わってきた。「あ、青豆ちゃん。えーと、なんかわたし、変にきもちいいんだけど」とおそるおそる言ってみる。むむ?とふたりで顔を見合わせて立ち上がり、ステージの菊地さんをそうっと見てみる。思えばそのときには、もう絡めとられていたんですねー。「ああ、これ菊地さんの音だ」とうっとりした様子の青豆ちゃん。そうなのでした。初めて聴いたけど、いつもの正装の、ホールの、サックスの、ジャズの、コンサートと全然違うけど、このジャンルさえも定かではない音の洪水のなかに、確かに菊地さんが。次に気づいたら、身体がリズムを刻んでいました。何?何これ?なになになにー?とふたりとも変なスイッチが入って笑いが止まらず。悲しくも、うれしくも、感動したわけでもないのに、涙がずるずる流れて止まらず。どんどんきもちよくなって、もう身体が勝手に動いちゃうので踊らないわけにいかず、最後には汗だくになって踊っていました。夢中になって「ぎゃー」とか「助けて」とか叫んだ気がするけど、よく覚えてません。らせんを描くように少しずつ、少しずつ巧妙に、ていねいに、ぎりぎりまで計算ずくでのぼりつめさせておいて、絶頂の寸前でたたき落とし、ほしくて泣き叫びそうになったところでまたがっとつかんで死ぬほど、浴びるほどくれる。ということが何度も何度も、吐き気がして腰がとろけ立っていられなくなるまで繰り返されるのです。目眩。吐き気。原因不明の手足の痺れ。それらすべてがすさまじい快感でもある。という倒錯した状況。自分を構成するすべてが音楽の支配下にあり、けれどもう、いまはどうなってもいいし、明日なんか来なくてもいいし、今夜この場所はまちがいなく「完全」で、いま菊地さんの音とひとつに溶け合ってこの場所にいることだけがすべてで、だから全部任せてしまっていいのだというもだえるような快感。 頭がおかしくなりそう。きっと、もうおかしくなっているのかもしれない。だって。 もっと欲しい。もっと、もっと。お願い。 気がついたら、ステージに向かってうわごとのようにつぶやいているわたし。なるほどー!これをトランス状態というのかー。25年間、まじめに実直に(笑)生きてきたわたくし、こんなきもちよさがあることを知ってしまって、本当にだいじょうぶなのだろうか?嫌われ松子のように、ここから転落人生が……などと考える間もなく、音がどんどん身体にしみ込んできて、今ではすっかり菊地さんに全神経を弄ばれているのです。 何ひとつ、本当に何ひとつもうわたしの思い通りにはならず、あちこちの神経を竪琴のようにつまびかれたり、ぎゅうっと壊れるほどわしづかみにされたり、乱暴に引っぱられたり、息が止まるほどやさしく愛撫されたり、宝物のように慎重に、指先だけで触れられたり。頭のてっぺんからつま先まで何度も電流が流れ、「お願い、今度こそ本当にもうだめ」と喘ぎながら何度懇願しても菊地さんは例によってにやにやにたにた笑うだけで全然ゆるしてもらえず(本当は欲しいんだろ、と言ってるにちがいない)、音が身体を満たし心臓を裏側からくすぐり、えぐり、わしづかみにし、きもちよすぎてきもちいいという感覚さえも麻痺し、ほとんど卒倒する寸前で、立っているのもやっとなのです。 もう限界なのにそれでもまだ欲しいと思ってしまう自分の貪欲さに戦慄し、その戦慄さえも恍惚に変わり。そして驚くべきことに、絶頂のとき、その混沌と汗と不協和音となんだかわからない奇声と、トランス状態で叫びながら踊り狂う無数の人たちと、いちゃいちゃするカップルたちが発するぬるい欲望の入り交じったフロア全体を包んでいたのは、ものすごく純度の高い愛。でした。うわー、なんだこれ?まさか!こんな場所に。何かの見間違いだろうと思って階段を一段上がり、ステージからわたしのいるフロアの最後尾まで、じーっとなめるように見直してみたけれど、やっぱり、ラブ&ピースが人びとの頭の上からもくもくと。湯気のように立ち上っちゃってます。あーあ。菊地さんは、こんなの全然意図してないだろうし、むしろいやがるだろうなあ。と思ったり。興奮さめやらぬまま、青豆ちゃんとふたり、ふらふらとO-EASTを出て(「MUSICALFROMCHAOS2」のCDだけは、忘れずに買ってしっかり手に握りしめていました)、道玄坂を下りメトロに乗って部屋に帰るまでのあいだに、どんどん吐き気が収まり、頭の芯のもやもやがさーっと晴れてすっきりクリアーになり、そして仕上げにデトックスの知恵熱が!いやあ。それにしてもすごい夜でした。人生変わっちゃいました。どうしよう。どんなにたくさんお酒をのんでも、どんなに耳元で音をたくさんもらっても、今夜を境に、きっと、ほかの人の音では満足できない。菊地さんの音じゃないと、もうわたしだめだ。きもちよくなれない。と気づいて、死ぬほどうれしくて死ぬほど切なくて死ぬほど憂鬱で。また泣きそうになる。次は10月。ふたたびO-EASTだそうです。もう完全に中毒なので、きっと行っちゃうなあ。ふう。
2006.07.04
コメント(4)
-
ラタトュイユみたいに幸福。
お昼すぎに起きる。寝ころんだままカーテンを少し開けてみたら、ぬるい雨が降っていた。少し時間をかけてヨーガをして、実家に電話。母が出た。親戚のもめごと。祝いごと。お父さんの様子。妹の近況。最近の心配事。などをいつものようにわやわやと話す。ついでにわたしの愚痴も。「男のひとなんてみんな同じよー」と母は豪快に笑い、そして言った。「今までしてもらったことを順番に、全部書き出してごらん。そして、してあげたことは全部忘れなさい」なんだかわからないけどちょっと泣いた。お母さん。と呼びたくなって呼んでみた。うちのお父さんは世界一なの。ってあなたが毎日、わたしたち姉妹に言って聞かせるから、わたしたちは今でも、地球が1日に1回転するのと同じくらい当たり前に、そのことを信じている。そう。お父さんは世界一の男だ!だけど、お母さん。お母さんにも、女の子だったときがあって、傷ついたり、悩んだり迷ったりしながら歩いてきたこと、今ならわたし、少しだけわかるよ。ありがとうを言って電話を切ったら、くさくさしていたきもちがだいぶ、穏やかになっていた。してもらったこと。書き出さなくても、いくつも、いくつも数えきれないくらい思い出せた。生まれてから今まで、あなたがわたしにしてくれた無数のこと。わたしはばかだから、手の中にこんなにたくさんの宝物を持っているのに、こんなにたくさんの愛とやさしさに取り巻かれて生きているのに、すぐそのことを忘れて、ひとりぼっちの悲劇のヒロインを気取りたがる。毎日忘れて、毎日思い出して、そのありがたさに泣いている。ばかだなあ。でも、その間抜けさゆえに世界一幸福とも言える。孤独と自由はふたつでひとつ。けれど、寂しさに苦しみながら生きるか、楽しさで胸を満たして暮らすか、選ぶのはわたし。夕方になって雨が上がったので、スーパーで夏の野菜を山ほど買ってきて、アンサリーさんの歌を聴いてさらに泣きながらラタトュイユをつくりました。なんでこのひと、こんなにきれいな声でうたうんだろう。妖精?天使?何者?蘇州夜曲。ピーマン。赤ピーマン。ズッキーニ。なす。タマネギ。セロリ。ニンニク。それにトマトをたっぷり!野菜が足りないとき、おつまみが欲しいとき、パスタのソースに悩んだとき。冷凍庫に入れておくと便利なのです。これからタンドリーチキン(ヨーグルトとレモン汁、カレー粉、とうがらし、すりおろしニンニク、ローリエでじっくり下味をつけました)を焼いて、イタリアのワインを開けて(小さい瓶です。ご安心を)、静かにひとりの夜をたのしみます。食後にはコーヒーをのんで、ぬるめのお風呂にゼラニウムのアロマオイルを落とし、楽しみにとっておいたグレハム・スウィフトの「最後の注文」を読むつもりです。ああ。本当に楽しみ。ちょっとだけ読んじゃおうかな。
2006.07.02
コメント(4)
-

パウロ・コエーリョ「ザーヒル」
ブラジルの作家、パウロ・コエーリョの「ザーヒル」を読む。「星の巡礼」も「11分間」も「ベロニカは死ぬことにした」もみんなハッピーエンドだが、「ザーヒル」には、ハッピーエンドの続き、リアルな現実の世界のことが書いてある。コエーリョ本人を思わせる作家の妻で、従軍ジャーナリストのエステルが、ある日突然、姿を消してしまうところから、物語が始まる。たくさんの奇跡に祝福されて結ばれた夫婦が、日々習慣に従って、小さな違和感には目をつぶりながら生きるあいだに少しずつ、少しずつずれてゆき、後ろを振り返ったらもう、取り返しがつかないほどすべてが違っていた。というのは、この世界ではもう、驚くべきことでもなんでもない、ごくありふれた日常。「ザーヒル」はイスラム的な観念で、「何か、あるいは誰か、ひとたび接触をもってしまうと、徐々に私たちの思考を支配していくことになって、ついには他の何にも意識を集中できなくさせてしまうもの」のこと。聖なる境地。そして狂気。けれどそのふたつが別のものだなんて、一体誰が決めたんだろう?作家にとって、いなくなったエステルの存在はザーヒルそのもの。エステルを探す心の巡礼をつづけながら、作家は最愛の妻を見つけるために、彼女を失うことを受け入れていく…という、深くて難しい小説。コエーリョの今までの作品とは、かなり毛色が異なります。愛と狂気、生と死について、じっくり考えながらでないと読み進められない本。でも、だからこそ、読後の充実感は重量級です。ひさしぶりにずしんとくるいい本を読みました。洗濯。掃除。ヨーガ教室。土曜の日課になりつつあります。夏は洗濯物が多いなあ!特にいま、布ナプキン使い始めて2回目の月経なので、ものすごい量の洗濯物。ところで布ナプはほんとにすごい。各所の痛みも、だるさも、いらいらもなくなって、わたしのからだとこころはたいへんうれしそうです。けれど、もっと喜んでいるのは、洗った水をもらえるうちの植物たち。「万両」というちっちゃい木を育てているのですが、なんだか、小さい実みたいのが葉っぱの根元にたくさんでき始めました。リ、リアル…アイビーの葉も目に見えて色が明るくなり、朝日にきらきらと輝き、明らかにわたしの月のものを楽しみにしている様子。誰にも、本人にさえ楽しみにされたことのなかった生理が、こんなにも歓迎されるのは、やや照れくさいが、生物として正しい感じ。仕事やもろもろで精神的にいちばんつらかったときは、生理も半年とか平気で止まってて、でもそれどころじゃなく、無視して働いてたからなあ。いま考えるとおそろしいことよ。ごめんねわたしのからだ。あのころに比べると、だいぶ自分を大事にできるようになったなあ。うん。ヨーガ教室で、先週なくしたあるものが見つかった。実はわたし、このなくしものが見つかるかどうかに、ささやかな賭けをしていたのです。出てきたか。そうか。ああ、なつかしい。おかえり。しかし、見つかったということはそういうことだ。ふう。ならば仕方がない。自分で決めたことに従おう。やれやれ。また同じことを繰り返すのか。どういう意味があるんだろう。わたしが、いま経験しているこのことには。ここから何を学べば、わたしは卒業できる?ヨーガは回を重ねるごとにどんどん集中が深まり、頭で作り出していた限界を、身体がどんどん裏切って超えていく。すごいなあ。こんなこともできちゃうのかわたしの身体は。憧れの壮美のポーズ。まだ全然途中までしかできないが、だいぶ膝が伸びて足が上がり、長持ちするようになった。いつか必ず完成形を!レッスン後、先生にsuriaのパイル地のTシャツ(この夏の新作。淡いピンク)をほめられ、うれしいきもち。しかし今日は、呼吸と筋肉に集中しながらも、雑念が次から次へ、頭をよぎっていく。いかんいかん。煩悩の多い人生。かくなる上は。と思い、髪を切った。「ヴォーグ」によると、この秋はショートがブームらしいので、背中の真ん中くらいまであった髪をアン王女みたいにばっさり……切ったらおもしろいのですが、どうも、まだいろいろな意味でそういう段階ではないようなので、傷んだ毛先と伸びたレイヤーだけ切り、入念にトリートメントし、前髪をそろえてもらう。もうずいぶん長いこと、色は入れていない。わー。小学生のころの髪型に戻ったよ。こけしちゃんみたいだ。切った髪と一緒に、いくつかの雑念がはらり。はらりと落ちてゆく。うん。いい調子だ。早くほんとうの夏が来ないかな。
2006.07.01
コメント(0)
全28件 (28件中 1-28件目)
1