全2231件 (2231件中 1-50件目)
-
プランクトンの心遣いに感激したっ!
ネットで注文したライブのチケット(12月の公演2枚)が届かなくて、 「事故でもあったんすか?」と問い合わせたら昔登録しといた住所(実家)に間違えて送っちゃったそうで。 実家から転送してもらって事なきを得たんだけど、 それに対してプランクトンさん「お詫びの品を送る」だって・・・! うひゃー。 チケットは無事に私の手に渡ったのに。 そんな丁寧な対応を・・・ いいのかな? 甘えちゃっていいのかな? 誠意が嬉しかったよ。プランクトンさん、ありがとうございました。
2015/11/16
コメント(0)
-
#1297 EMILY SMITH 《A DIFFERENT LIFE》2004年スコットランド
The Bonny Labouring Boy (words trad, music trad/Donal Maguire)Always A Smile (E. Smith)Edward Of Morton (E. Smith)The Tressle Bridge (J. McClennan): Aodhan’s Jig/Mick McAuley/The CicadaStrong Winds For Autumn (Bob McNeill)Go To Town (E. Smith)It Fell About The Martinmas (words trad, music E. Smith)Bonny Baby Kate (E. Smith)The Lochmaben HarperThe Lowlands Of Holland (words trad, music E. Smith)Cancro Cru (Anxo Pintos)/The Salt Necklace (J. McClennan)/Ian’s No. 56 (J. McClennan)Far O’er The Forth Emily Smith(vo, p, accordion/1981-) Steve Byrne(g, cittern, bouzouki) Jamie McClennan(fiddle, vo) Duncan Lyall(double-b) Jonna Inge(viola) Sarah Murray(cello) Paul Jennings(per) Martin O Neill(bodhran, shaker) Brian Finnegan(flute, whitle) Andy Saunders(french horn) Hamish Napier(backing-vo) produced by Joe Rusby & Emily Smith・engineered & mixed by Joe Rusby・photo & design by Craig MacKay 様々な音楽賞を受賞しているエミリー・スミスの2作目にして日本デビュー盤。 2012年6月にスヴェングのライブに行った際、ロビーで呼び屋さんによるCD叩き売りセールをやってましてね。500円ポッキリだったんで「うおおおおおこれ私のだ誰にも渡さんぞ!」と即ゲットしたんですよ。 エミリー作品はずっとほしかったけどなかなか入手できずにいたので思いがけず安く買えてラッキーでした。ちなみにそのセールではハウゴー&ホイロップやレイチェル・アンサンクなんかも同時購入しました。オホホ。 ぶっちゃけ初エミリーだったわけですが、これが実に完成度が高くて。 帯には「スコットランドの伝統を今に伝える期待の新人女性ヴォーカリスト」とあるし、収録曲も民謡っぽいものが多いからトラディショナルを中心に歌っているのかな、と聴く前は思っていたのだけど。 ふたを開けてみれば民謡歌手と言うよりかはシンガー・ソングライターでした。 収録曲のクレジットを見てごらんよ。共作やカバーもいくつかあれど、まったくのピン作品が4曲。歌詞はトラッドだけど曲は自分で作ったものも2曲。 中でもちょっぴり切ないメロディの7は秀逸! これは生涯のお気に入り曲トップ100には確実に入るよ。 その次のインスト8も心が洗われる~。自身のピアノを中心としたアレンジが施されているのだけど、バックで鳴っているストリングスがそれはそれは優美で…。 さらにその次の9は旦那でもあるジェイミー・マクレナンのコーラスが超・超・超効果的! これもトップ100に入れたい! …なんだかお気に入り曲が後半に集中しとるなあ。 エミリーの声は萌えでもなければ姐御でもない、どこにでもいそうな普通の女の子といった感じです。自分で作詞作曲できてもちろん歌えてトラッドも時々歌う…、同郷のカリン・ポラートに通じるものがあるなあ。歌声もどことなく似てるし。 マリンキー(カリンが歌い手を務めているバンド)のスティーヴ・バーン、フルックのブライアン・フィネガン、バック・オブ・ザ・ムーンのヘイミッシュ・ネピア、2002年の全アイルランド・バウロン・チャンピオンに輝いたマーティン・オニール等に協力してもらっての編曲も無駄に凝り固めず自然の風合いです。 http://www.emilysmith.org/ 【期間限定特価】【送料無料】 RUCD-146★CD/エミリー・スミス/ディファレント・ライフ
2015/11/15
コメント(0)
-
#1296 BERT JANSCH 《FROM THE OUTSIDE》93年スコットランド
Sweet Rose In The Garden (Bert Jansch)Blackbird In The Morning (Bert Jansch)Read All About It (Bert Jansch)Change The Song (Bert Jansch)Shout (Bert Jansch)From The Outside (Bert Jansch)If You’re Thinking ‘bout Me (Bert Jansch/Nigel Portman Smith)Silver Raindrops (Bert Jansch)Why Me? (Bert Jansch)Get Out Of My Life (Bert Jansch)Tiem Is An Old Friend (Bert Jansch)River Running (Bert Jansch)High Emotion (Bert Jansch)From The Inside (Bert Jansch)Bert Jansch(vo, g, banjo/1943.11.3- 2011.10.5)cover artwork by Kieran Jansch もうちょっとノルウェーもの出したいなー、と思ったんだけどレビュー対象になるやつがなかったんで同じ93年発売のこれにしてみました。 今は亡きバート・ヤンシュのソロです。 これは85年に15枚目のアルバムとして500枚限定でリリースされたもののCD再発となります。曲順と収録曲に若干の変更があるみたい。 この人は20代の時も40代の時も歌声が大して変化してないんだよね。 いや少しは変わっているけど、むしろ若い頃の歌声が老け…じゃなくて大人っぽすぎたから、年月を重ねるにつれ実年齢と喉年齢が合ってきたというか。 本作聴いてても「実は68年にレコーディングしたものです」と言われれば、それはそれで信じてしまいそうだしなあ。 あ、でもギターは幾分マイルドになっているかな。弦が切れるんじゃないかとハラハラするようなかつての力強いピッキングはなりを潜めていまして、随分と柔らかくなっています。 6と14はインスト。これがまた上品で良いのだ。 何の気なしに聴き始めてもクレッシェンド式に「いいなあ」と思う気持ちが増していくのはいつものヤンシュ節だね。 この内容で500枚限定生産って意味がわかりません。 http://bertjansch.com/
2015/11/15
コメント(0)
-
#1295 BUKKENE BRUSE 《BUKKENE BRUSE》93年ノルウェー
Til Saetersdal (trad/Geirr Lystrup)SeljefloyelHaslebuskaneTabhair Dom Do LahmBon (Knut Buen)Navarsetermarsjen (Ola Molokken)Miriams Voggelat (Steinar Ofsdal/Sondre Bratland)FanitullenNu Rinner Solen Opp (trad/Thomas Kingo)Malfrid Mi FruveBruremarsj Etter FiskestigenHodalsbrura (Jo Gjermunds)Rotnheims-Knut Arve Moen Bergset(vo, hardanger fiddle, fiddle/1972-) Annbjorg Lien(hardanger fiddle, fiddle, nickelharpa/1971.10.15-) Steinar Ofsdal(sea flute, willow pipe, tin whistle, ditze, jew’s harp, cello, key) produced by bukkene bruse & jan erik kongshaug engineered by jan erik kongshaug photograhs by morten krogvold へえ。ブッケネ・ブルーセってリレハンメル五輪の閉会式で演奏したのか。 リレハンメル五輪っていつだったっけ?と記憶の糸をたどりながら88年に結成された彼らが93年に出したファーストを聴いてます。 女1男2という編成はかつてのドリカムのようだけど(今ならいきものがかりに例えたほうがいいかね)、この人らは女性メンバーには歌わせていません。マキャヴェッリみたいなおかっぱ頭がかわいいArve君(読み方わからん)がマイルドな喉を披露しています。 95年発表の2作目をレビューした時に「けだるい」「暗い」と書いた私ですが、本作は「ゆるい」ですね。ミドルテンポの曲が多く、歌入り曲もインスト曲も全体的にまったりしてる。 インストの8はほかのノルウェーフォーキーが演奏しているのを何度か耳にしているけど、こちらのバージョンは結構ゆったりしてます。こういう器楽ものってアレンジ次第で超高速チューンになるものね。 4は本作中唯一の非ノルウェー音楽でアイルランド民謡。プランクシティも72年の1作目で披露していたよね。 “ティンホイッスルの魔術師”マイコー・ラッセル(94年2月に78歳で交通事故死。。。)に習ったというこのインスト、笛を主役に据えたアレンジメントがもう最高です。和みの境地です。 あまり…というか全然エキサイトはしないけど、妙に聴き続けたくなるアルバムですね。 ああそうそう。リレハンメル五輪は94年2月開催でした。
2015/11/14
コメント(0)
-
#1294 STORM WEATHER SHANTY CHOIR 《WAY HEY (AND AWAY WE’LL GO)》2011年ノルウェー
SheanandoahWhip JamboreeJohnny, Come Down To HiloVokt Dig VelDrunken Sailor (featuring Dave Cloud)Hand Over HandBom FaderiThe Maid Of CoolmoreHieland LaddieRio GrandeBully In The AlleyBoneyCape Cod Girls (featuring W. Hut) Hakon Vatle(lead-vo, e-g, a-g) Ronny Saetre(vo) Roald Kaldestad(mandolin, a-g, banjo, laud, mandobanjo, vo) Rune Nesse(bongos, floor tom, bodhran, vo) Gisle Ostrem(concertina, accordion, b-accordion, prepared-p, p, vo) Vidar Veda(tuba, vo) Dave Cloud(pirate-vo;5) William Hut(vo;13) Sigrid Moldestad(fiddle) Nils Okland(fiddle, hardanger fiddle) Helge Haaland(double-b) Bjorn Bunes(noise) mixed by Bjorn Bunes mastering by Bjorn Ivar Tysse & Bjorn Bunes japanese version jacket design by Shigekazu Yamada バーバラ・ディクソンの次は同じスコットランド人つながりでラブ・ノークス出しまーす♪ …なんてことを言う予定はありません。ファンの人ごめんね! しばらく古い音源が続いていたのでここらで新しめのを出そうかと思いまして。 できるだけ新しいやつ…今年(※これ書いた当時は2012年)リリースされたものを出そうと思ったんだけど1枚も持ってなかったんで2011年に発売されたものを選びました。 2011年11月に「よく知らないけど面白そう」と行ったコンサートがたまげるほど良くて、普段は貧乏性ゆえにそんな行動絶対に取らないのに帰りに物販コーナーでCD買っちゃったストーム・ウェザー・シャンティ・クワイアです。 あ、日本盤のリリースが2011年ってだけで本国でのリリースは2009年ね。 2000年に結成しデビュー盤を出したのは2001年でセカンドがその翌年、2005年にサードを出し本作が4作目兼現時点での最新作兼日本デビュー盤となります。 ガチ船乗りのホーコン・ヴァトレを中心とするノルウェー男6人組で、バンド名の通りシー・シャンティ(海の歌、船乗りの歌)を全員で歌っています。 年の頃は30~40代ってとこかな、見た目かなりむっさいからどんな漢臭を漂わせてくれるのやら、とドキワクしていましたら意外や意外、爽やかさも持ち合わせてる。 だけどそこは男盛りの皆さん、中低音を何重にも重ねたハーモニーの厚みは尋常じゃない。 そしてシンガロング度はめっちゃ高いです。 ご覧の通り定番トラッドがずらり並んでいて(お国の歌はあんましない)、最も有名と思われる5なんてどうですか。これ絶対一緒に歌いたくなるってば。 ノリとしては健康的になったポーグスって感じもするし、グレート・ビッグ・シーとかアマダンあたりに近いものも感じるなー。 曲によってアカペラだったり楽器が入ってきたり。 個人的にはマンドリンが入ってくると耳をそばだててしまうなあ。先述の“ドランクン・セイラー”とかね。 楽しい曲だけじゃなくホロリ曲も。 アメリカ民謡の1やアイルランド民謡(たぶん)の8、ラスト13がそれに当たるよ。 http://www.shantychoir.com/ コンサートではホーコンがやたらと筋肉を見せびらかしていたのが印象に残っています。…アニキなのか? ひそかに二丁目まで行ってきたのか? 日本盤を出してくれたハーモニーフィールズさんによる紹介ページ→ http://www.harmony-fields.com/a-swsc/index.html 【メール便送料無料】Storm Weather Shanty Choir / Way Hey (And Away We'll Go) (輸入盤CD)【I2015/2/3発売】
2015/11/14
コメント(0)
-
#1293 BARBARA DICKSON 《DO RIGHT WOMAN》70年スコットランド
Easy To Be Hard (Gerome Ragni/James Rado/Galt Macdermot) from “Hair”Turn A Deaf Ear (Rab Noakes)Something’s Wrong (Allan Taylor)The Garton Mother’s LullabyDainty DavieReturning (Archie Fisher)Do Right Woman (Chips Moman/Dan Penn)The Long And Lonely Winter (Dave Goulder)A Lover’s GhostThe BlacksmithGloomy Sunday (Rezso Seress/Laszlo Javor/Sam M. Lewis/Carter)And I Will Sing (Archie Fisher) Barbara Dickson OBE(vo/1947.9.27-) Archie Fisher MBE(g, dulcimer, concertina, backing-vo/1939.10.13-) Rab Noakes(g, backing-vo/1947.3.13-) Ronnie Rae(b) Bill Kemp(ds) Alex Sutherland(arrangements & string sexted conducted) produced by Ray Horricks engineered by Robert Sibbald, David Grinsted photography by Ian Mccalman バーバラ・ディクソンのソロデビュー作はフツーの歌ものでした。 アーチー・フィッシャーとラブ・ノークスが協力してて、おおっとスコティッシュ・フォークの名人がいっぱい!と色めき立ったんですが思ったほどトラッド/フォーク色は強くなかった…。 1曲目からミュージカル曲をモダンに歌いあげています。レコードで言うところのB面1曲目もこれまたアダルトでお洒落な雰囲気に支配されてる。 どうにもバーバラさんはコンテンポラリー歌手としての側面が強いような…アレンジにもよるのだろうけど、おなじみのトラッド10ですらトラッドに聴こえない。 その前の9も大好きな歌だけど、これも現代風の味付けだなー。ま、元々の旋律が良すぎるから流れてくれば意識を集中させて聴いてしまうのだけどね。 彼女は歌が上手く、歌い方がとても丁寧。一音一音を確実に発音することを意識していそうです。 声域はそれほど高くまでは出していないけど、声はわりと綺麗だよ。 でもまあ本作の一番の聴きどころは2でしょうな。ラブ・ノークスの作で、リンディスファーンのカバーも秀逸だった大人気曲。 作者本人がコーラス参加しているバーバラのバージョンも良いよ~。ピアノ主体の伴奏もすごく好きだし、リンディスファーンのバージョンより気に入ったかもしれない。 全体が好きってわけじゃないけど、あちこちに大好きな曲が散ってるからなんだかんだでよく聴く盤です。 http://www.barbaradickson.net/
2015/11/14
コメント(0)
-
#1292 ARCHIE FISHER 《ARCHIE FISHER》68年スコットランド
Open The Door SoftlyReynardineThe Terror Time (Ewan MacColl)The Three GipsiesThe Kilder HuntThe Trooper And The MaidThe Child On The RoadThe Beggar WenchBogie’s Bonny BelleMatt HighlandFarewell SheThe Snows Archie Fisher MBE(vo, g, dulcimer, concertina, sitar/1939.10.13-) John MacKinnon(violin, mandolin) John Doonan(piccolo, whistle/1921-22-2002.3.8) produced by Bill Leader cover Brian Shuel 前回のポール&リンダ・アダムスでアーチー・フィッシャーの名前が出てきたので、ならば本人を出さないわけにはいかないなと選んだのですが、聴き始めて1分しないうちから瞳にハートが浮かんじゃってます、私。 こんなに美声だったっけこの人? スコットランドの重鎮フォーキーで妹が少なくとも4人もいる、某方面の諸兄にはものすっごく羨ましがられそうな人って認識だったんだけど、この初ソロを聴いていたら、ああいい声だなあ…って。 音域は高くはなくどちらかと言えば低め。曇りが一点もなさそうなダンディ声です。 ミステリアスなメロディでも大衆的なメロディでもたまらん! もうね、絶対フェロモン出てる。聴いてるだけで妊娠しちゃいそうなレベルだよ。あ、色っぽいけどエロは皆無ですので念のため。 トーンを抑えたギターがこれまた素敵。 翌69年にバーバラ・ディクソンと3人で「ザ・フェイト・オ・チャーリー」を録音することになるジョン・マッキノンのヴァイオリンも良いアクセントになっているし、アイルランド人で笛の名手でハイ・レヴェル・ランターズのオリジナルメンバーでもあるジョン・ドゥーナンのホイッスルも実にキュートです。 8のメロディはアン・ブリッグスやマディ・プライア&ジューン・テイバーが歌ったことで知られる“ドフィン(グ)・ミストレス”と同じです。 ほかにも10はマーティン・カーシーの名唱が忘れられないし、3人の魅力が等しく堪能できる5も好き。 7は歌詞の内容からして(英語苦手だからなんとなくだけど)ちびっ子と悪魔の問答の歌“フォルス・ナイト・オン・ザ・ロード”の別バージョンかな。 三十路前でこの貫禄…滋味すぎです渋すぎますアーチーさん。 プロデューサーとジャケット担当の2人も英国フォーク界ではど定番だね。
2015/11/14
コメント(0)
-
#1290 ROSEMARY HARDMAN 《QUEEN OF HEARTS》69年英国
Child Of Merseyside (R. Hardman)HuntingtowerBanks Of ClaudyThe Golden VanityI Left My Baby Lying ThereThis Is My Mountain (R. Hardman)The Weavers ForeverA Long Way To Go (Tony Hardman)Pretty SaroLady Bernard + Little MusgraveOntario Bound (R. Hardman) Rosemary Hardman(vo, g/1945.2.26-) produced by Bob Siddall recorded by Brian Horsfall sleeve design by Ralph de Berry recorded live 29. 12. 68 at the Bate Hall Hotel Macclesfield ローズマリー(ロージー)・ハードマンのデビュー作にしてライブ盤です。 ローズマリーの作品を出すのは今回が初めてなのだけど、彼女が書いた楽曲をミリアム・バックハウスやコントラバンドが取り上げていた縁で存在だけは知っていました。それにこのアルバム名「クイーン・オブ・ハーツ」と同名のトラッドがあって、それが結構好きなのでね。(※ただし本作にそういう名前の歌は入っていない) おそらくは本人が弾いているギターを伴奏楽器にのびのびと歌っています。 歌唱力の点では絶賛できないけど音程は取れているし(←なぜか偉そうなワタシ)、何より心をこめて歌っている雰囲気がにじみ出ていて好感度は大です。 曲によってはお客さん(おとなしそうな男性が多い)も一緒になって歌っていて、それが温かくていいんだよね~。こういうのって目をつぶって聴いて疑似ライブ体験したくなっちゃうよ。 見覚えのあるタイトルのトラッドがいくつか入っていますが、チャイルド・バラッド81番で10分超えの10は“マティ・グローヴス”のタイトルでよく知られているマーダー・バラッド。フェアポート・コンヴェンションやフランキー・アームストロング、マーティン・カーシー&デイヴ・スウォブリックなども取り上げています。 ローズマリーのバージョンはお客さんによる柔らかなコーラスとも相まって人殺しの歌とはとても思えない仕上がりです。 自作曲もクオリティが高く、6などを聴くと自作曲を中心としたほかのアルバムもほしくなっちゃいます。 なお同姓の8は赤の他人のようですよ。 http://www.rosiehardman.com/ 自分で「太め」と言ってます。なんかいいなあ(笑)
2015/11/14
コメント(0)
-
#1289 BONNIE DOBSON 《BONNIE DOBSON》72年カナダ
ThymeLong River (Gordon Lightfoot)Farewell To Nova ScotiaUn Canadien ErrantPoor Little Girl Of OntarioFou Strong Winds (Ian Tyson)Vive La CanadienneLand Of The Silver BirchIse The ByeSixteen Miles To Seven Lakes (Gordon Lightfoot)A La Claire FontaineSomeday Soon (Ian Tyson) Bonnie Dobson(1940.11.13-) produced by Kevin Daly recorded by Iain Churches トロント出身のボニー・ドブソンが72年に出したアルバム。 60年代から活動している人で、本作以前にすでに何枚も出しているようです。 1曲目からペンタングルが歌っていた“レット・ノー・マン・スティール・ユア・タイム”の同曲異タイトルでテンション上がっちまったのですが、男性コーラスを従えて楽しく歌う“アルプス一万尺”と同じメロディを持った5、大昔にケベックで習ったという7、フィドルとバンジョーが軽やかな9の3曲を聴いたらさらにハイテンションに。 もうかわいすぎる。7なんて初めて聴いた時はあまりのかわいさに萌え死にするかと思いましたからね! かわいさで言えば3も負けてないけどね! 1とか8、12のようなゆったりめの曲もじっくり聴けて好きだけど、5、7、9みたいにアップテンポでなおかつ愛くるしい曲はさらに好きだわ。 ボニーは親しみやすい綺麗な声の持ち主です。 ジョーン・バエズに似ていないこともないけれど、ジョーンよりも場馴れしている感じはありますね。でも不必要に玄人臭は出しておらず、知り合いのお姉さんが歌ってるような印象です。 伴奏はギターがメイン。たまに上述のフィドルとバンジョーのほか、ホイッスルやマンドリンらしき音も加わってます。 全体的に軽やかでキュート、毒気がまったくないので小学校低学年(というよりその保護者や教師)が好みそうな気がするなあ。 カバーしているゴードン・ライトフットとイアン・タイソンはボニーと同じカナダ人。 タイソンはイアン&シルヴィア名義のアルバムを何枚かレビュー済みだし、ライトフットは演奏家としての登場はまだだけど様々な人にカバーされてます。個人的にはフォザリンゲイがやった“ザ・ウェイ・アイ・フィール”が印象に残ってるね。 前回紹介したコリン・ウィルキー&シャーリー・ハート・ウィズ・ジョン・ピアースと2曲かぶっていますが、ボニーのバージョンのほうが聴く回数は多いかな。 2006年にリマスターCD化されてるから入手はしやすいかもしれません。 【メール便送料無料】BONNIE DOBSON / BONNIE DOBSON (RMST) (輸入盤CD)
2015/11/14
コメント(0)
-
#1288 COLIN WILKIE & SHIRLEY HART with JOHN PEARSE 《FOLK ‘66》 66年英国
Kilgarry MountainI De Dybe DaleThe White CockadeA La Claire FontaineThe Ash GroveDella La RiviereOld BillErev Shel SoshanimThe Road Tae DundeeChansons D’enfantsThe Golden Willow TreeWill Ye Lassie GoPoor Little Girls Of Ontario Shirley Hart(vo:1932.12.8-) Colin Wilkie(vo, g, 5 string banjo:1934.5.9-) John Pearse(g, bouzouki, appalachian dulcimer:1939.9.12- 2008.10.31) これまた非常にオーガニックなアルバムですなあ。生の歌に生のギター、バンジョー、ブズーキ、ダルシマー。間違いなくノンケミカル処方ですよ。 とりわけコリン・ウィルキーの歌声が素朴すぎる…と言うか素朴通り越して地味です。絶対に背中丸めて足元に視線落としてボソボソ歌ってそうだよー。これで満面の笑みでステージ中央に仁王立ちして歌ってたらイメージ違いすぎる。 シャーリー・ハートもやっぱり派手の対極にある歌声で、だけどコリンとは違って力強さは感じ取れますね。 この2人夫婦のようで、シャーリーのほうが少し年上です(←妙に納得)。結婚の時期は不明だけどヴィンセントという名前の息子が69年に生まれています(音楽畑で活動してるけどフォークではない)。 伴奏で協力しているジョン・ピアースはギターが相当達者なようで、マーティン・カーシーは彼からも影響を受けているのだとか。英国フォーク界では重要な人物らしいけどワタクシ勉強不足ゆえ存じ上げませんでした。戯言レビューに出てきたのも今回が初です。 収められている13曲は英国産に限らずアイルランド(1)、デンマーク(2)、カナダ(4、7、13)、ウェールズ(5)、ベルギー(6)、イスラエル(8)、フランス(10)などなど。 1は“ウィスキー・イン・ザ・ジャー”と同じメロディです。歌詞もほぼ一緒なんじゃないかな。 ラストもきっと多くの人が知っているメロディを持っています。“ヤンキー・ドゥードゥル”もしくは“アルプス一万尺”ね。 2人はヨーロッパのみならず北米にもたびたび足を運んでいて、そこで友達になった人に歌を教えてもらっているみたい。 聴く人によってはテンション低すぎて物足りないかもしれないけど、「覇気がない」と言われることが少なくない私にとってはこのくらいでもちょうどいいや。
2015/11/14
コメント(0)
-

#1287 ALEANNA 《ALEANNA》 78年英国
Star Of Munster/Nora StacksNext Market DayThe OrphanBunch Of Green Rushes/Maid I Ne’er Forget/Eileen Curran’s/Eel In The SinkStep It Out MaryJulia Delaneys/Patsy TouneysJig Song/Mahons 3/Sonny Brogans (Mahons)MazurkasCairnlough BayBroken Pledge/Captain RockWill You Come Away With Me? (Mahons)Maud A Bawn Chapel/Temple House Angela Carthy(vo, g) Pauline Mahon(vo, fiddle, whistle) Mandy Murray(vo, concertina) John Higgins(banjo, mandolin, mandola) Kevin Higgins(bouzouki, mandolin, banjo) sound engineered by Ian Grant produced by Brendan Mulkere photos by Eamon Mcdonagh art work by Michael Feather 娘っ子3人と兄さん2人の5人組アレアナ。たぶん唯一の作品です。 当時は自主制作でプレス枚数も少なかったようですが、近年紙ジャケCD化されました。 彼らはアイルランド系のようで、チョイスしている曲からも演奏の雰囲気からもアイリッシュ臭が漂っている…と思いきやそうでもないなあ。 アイリッシュの連中が放っている疾走感とか漲り感がアレアナからはあまり感じられないんだよね。 コンサーティーナ×バンジョーの合わせを聴いた時はスコットランドのシリー・ウィザードが頭をよぎったし、フィドルが前面に出ているものはスティーライ・スパンのインストメドレーを思い出したことだし。 急いではないけどゆったりもしていない…なんだろうな、血圧は全然上がらない楽しさってか。 9みたいなゆるやかーな調べでもちっとも退屈しないしね。 歌入り曲は2、5、7、9、11。 お嬢さん方が皆垢抜けていないかわいい歌声をしてね、器楽曲もいいけどこれもかなり萌えるんだわ。
2015/11/14
コメント(0)
-
#1286 LAINE & ALAN 《ON AN AUTUMN DAY…》 82年英国
At The Dawning Of The Day/On Raglan Road (poem by Patrick Kavanagh)Bonny Light HorsemanThe Sea MaidenThomas Leixlip The Proud (O’Carolan)Dragons (Laine Nunn)Mrs McGrathOne I Love (Jean Ritchie)Down By The Salley Gardens (poem by William Butler Yeats)Three Danish GalleysTwisting Of The Rope (O’Carolan)Planxty Fanny Power (O’Carolan)Bantry Girls’s LamentLakes Of PontchartraineThe Parting Glass Laine Nunn(vo, g, autoharp) Alan Nunn(g, flute, harmonium, mandolin, vo) John Rose(fiddle) Nick Dow(b, g, backing-vo) enginnered & produced by Robin Brown, Ric Sanders sleeve design by Gordon Griffin レイン・ナンとアラン・ナンによるレイン&アラン。 1982年発表ですが雰囲気はモロに70年代です。 たおやかで瑞々しい女性ヴォーカルとフルートを中心とした器楽の組み合わせがとろけそうなほどに美しい。 レインのビューティホーな歌声を聴いているとなんだか昇って行ってしまいそうです。悪いおくすりとかの影響ではなく。 歌入り曲はそんな彼女の魅力を存分に堪能できる仕様で、アランとゲストのニック・ドウがコーラスを付けるのはアカペラで楽しく歌う6のみです。 アラン(顔は似てないから夫婦なのかな)が弾くギターがとろとろと切なく素朴です。 盲目のハーパー、ターロック・オキャロランの作品が多数を占めるインストではフルート独奏を披露していたりして、これが実に幽玄なのですよ。 そのオキャロランをはじめ、1の詩を書いたパトリック・キャヴァナも8の詩を書いたウィリアム・バトラー・イエーツもアイルランド人。 アイルランド民謡も何曲か取り上げているからアイルランド出身なのかなあ?と思ったけど録音場所がイングランドなんで英国扱いにしちゃいました。(本当のところはどうなんでしょうね。誰か知ってたら教えて) お気に入りはレイン作の5とローナ・キャンベル(イアン・キャンベルの妹)の編曲バージョンだというアメリカ人民謡歌手ジーン・リッチーの作品7。 どっちも私好みのウルトラ美旋律短調でね、聴いているとネガティブ感情は一個も沸いていないのに無性に泣きたくなってくるんだ。 もっと多くの人に聴いてもらいたい逸品です。
2015/11/14
コメント(0)
-
#1285 FRANKIE ARMSTRONG 《SONGS & BALLADS》 75年英国
Little Duke Arthur’s NurseThe Pitman’s UnionLady DiamondLament For The Hull Trawlers (MacColl/Armstrong)The Month Of JanuaryThree Drunken MaidensJack The Lad (John Pole)The Whore’s LamentLittle MusgraveThe Collier LassThe Female Drummer Frankie Armstrong (vo/1941.1.13-) Graham Coffee (g) Andrew Brown (fiddle) Susie Rothfield (appalachian dulcimer, vo) Heather Wood (vo/1945.3.31-) Brian Pearson (vo) produced by Tony Engle sleeve design & photo by Tony Engle 執筆の際の資料が不足してたんでレビューするのは後回しにしようと思っていたのだけど、あまりに素晴らしいので急遽取り上げることにしました。 20代だった頃は前回紹介したクリティックス・グループでも活動していたフランキー・アームストロング。英国を代表するフォーク・シンガーである彼女が75年に発表したたぶん2作目のソロ。 私個人はまず72年のファーストを聴き、次に84年の作品を聴き、こちらを初めて聴いたのはここ数年のことなのだけど、これがもう最高傑作と言っちゃいたいほどの出来で。 シャーリー・コリンズとかアン・ブリッグスなんかの“細めでかわいめの声質であまり感情を込めずに淡々と歌う”タイプを引き合いに出すならば、フランキーさんは間違いなく熱唱型シンガーに分類されるでしょう。 声域はアルトの辺り、決して美声ではないけれど胸打たれます。彼女の歌声が大好きって人は意外と多いんじゃないかな。 短調の歌がたくさん入っているのもポイント。しかもわざとらしいまでのお涙頂戴節ではなくてさりげなく泣かせるものが多いのです。 2なんて生涯の宝物にしたいほどの名演だし、イワン・マッコールと共作した4もすこぶるクオリティが高い。 若い男と不倫をした妻を間男ともども殺害するマーダー・バラッドの9は“マティ・グローヴス”のタイトルでフェアポート・コンヴェンションがやっていたけれど、ここでのメロディはフェアポートのバージョンとは違います。行進曲のようなテンポでさほど深刻さはなかったフェアポートと比べるとこっちははるかに重い。ダルシマーによる伴奏もどことなく不気味です。 ラストも有名なスティーライ・スパンのバージョンとはメロディが違ってる。サビではコーラスも入って何やら楽しげです。でもどことなく切ない…これはアレか? みんなで楽しく歌おう感がドン・マクリーンのウルトラ名曲“アメリカン・パイ”とモロかぶりだからホロリしちゃうのか? 7はリンディスファーンから派生したまったく同じ名前のバンドがどちらかと言うとお笑い路線だったから、この曲もさぞファニーなんだろうと思いきや…。 マイナー炸裂してました。 ジョン・ポールって人の正体が長らく謎だったんだけど、どうやら学校の先生をしながら曲を書いていた人のようです。某掲示板に本人自らが晒していたメールアドレスから推測すると1934年生まれみたいね。 彼の曲は84年のソロでも2曲歌っているよ。 それにしても10代の頃はエルヴィス・プレスリーやリトル・リチャードの曲を歌い、スキッフルのグループに入っていたとは意外だなあ。 http://www.frankiearmstrong.com/ 現在は歌の先生がメインの活動なのかな? 元気そうでなによりです。 2006年12月に来日した際のレポ 圧倒的歌唱力でした。また歌いに来てくれないかな~。
2015/11/14
コメント(0)
-
#1284 CRITICS GROUP 《THE FEMALE FROLIC》 68年英国
The Doffin MistressGirl Of Constant SorrowThe BlacksmithMy Husband’s Got No Courage In HimThe Generous LoverThe Whore’s LamentGeordieCome Me Little Son (Ewan MacColl)The Female FrolicChildren’s Sequences: All The Boys In Our TownI Built My Lady A Fine Brick HouseCollier LadsBroken Hearted I WanderThe Lady From LeighAll Around The Shoe RoundAn Old Man Came Courting MeMiner’s Wife (Ewan Maccoll)The Factory GirlLowell Factory GirlThe Broomfield HillThe Housewife’s Lament Frankie Armstrong vo/1941.1.13- Sandra Kerr vo, tin whistle/1942.2.14- Peggy Seeger vo, g, autoharp, concertina, 5 string banjo/1935.6.17- Jack Warshaw g John Faulkner english concertina クリティックス・グループの68年の作品。フランキー・アームストロング、サンドラ・カー、ペギー・シーガーの3人の女性シンガーをフィーチャーしています。 クレジットが見当たらないけど今回もイワン・マッコールとペギー・シーガーの2人が主宰者だろうね。 各国のトラッドを3人で分け合って歌ったりあるいは全員で歌ったり。 2、6、16等の北米産トラッドはアメリカ人のペギーが歌っています。それ以外のブリテン諸島のトラッドはフランキーとサンドラが担当。 この中では一番知られていそうにないサンドラについて言及すると、彼女は一時期ジョン・フォークナー(20でコンサーティーナ弾いてる。後年はアイルランドの歌手ドロレス・ケーンとの仕事でも有名に)と組んでいたことがあり、またマーティン・カーシーの娘イライザと連名作を出したこともあるナンシー・カーの母上でもあります。 このサンドラの歌声が実に瑞々しくて清楚なんだよね。系統で言えばアン・ブリッグスに近いよ。 フランキーの地に足がつきすぎてる歌唱やペギーの余裕たっぷりの歌唱も聴きごたえがあるけれど、個人的にはサンドラのかわいい声がツボだなー。 伴奏はごくごくシンプル。2、8、9、17、20、21以外はアカペラです。 全員で楽しげに歌う曲、ピンで若干深刻そうに歌う曲、あるいは情景を描写するだけのように淡々と歌う曲…。 10~15の6曲はは本来は“Children’s Sequences”とひとまとめになっていましたが、ここでは1曲1曲分割されています。 ペギー・シーガーの公式サイト→http://www.peggyseeger.com/
2015/11/14
コメント(0)
-
#1283 CRITICS GROUP 《WATERLOO-PETERLOO》 68年英国
With Henry Hunt We’ll GoLancashire LadsThe Labouring ManJohn O’Grinfell’sCast Iron SongVan Diemens LandDeath Of ParkerDrink Old England DryBattle Of WaterlooBoney Was A WarriorThe VictoryThe Dudley Boys (tune: Pam Bishop)Keepers And PoachersI Should Like To Be A Policeman (tune: Brian Pearson)The Way To LiveHandloom Weaver’s Lament Denis Turner vo; 1, 4, 5, 12, 16 Frankie Armstrong vo; 2, 7, 11, 15/1941.1.13- Brian Pearson vo; 3, 10, 13, 15 Terry Yarnell vo; 5, 8, 9, 14John Faulkner vo; 6, 9/mandolin, english concertina Peggy Seeger g/1935.6.17- Sandra Kerr g, dulcimer, tin whistle, spoons/1942.2.14- Jim O’Connor ds, per イングランド民謡と1780年~1830年のブロードサイドに印刷された歌を集めた作品。 クリティックス・グループは60年代後半から70年にかけて7枚ほどレコードを出していたようで、これは68年発表の4作目。 クレジットはないけど今回もイワン・マッコールとペギー・シーガーの2人が主宰者と思われます。 歌い手は5人。普段は歌うことが多いペギーとサンドラ・カーは演奏に専念しているので男性シンガー率が8割となっています。 テリー・ヤーネルは高音域に入るとピーター・ベラミーを思いきり親しみやすくしたような歌声になるし、ブライアン・ピアソンはマッコールの子分ってことに至極納得してしまう声質。ジョン・フォークナーはヘタレ感の薄いA・L・ロイドって感じ。 まあみなさん概して庶民派ですな。紅一点フランキー・アームストロングも親しみやすさが激増してる。 お気に入りは12。デニス・ターナーのリード+男性陣のコーラスなんだけど、わずかにショボン入りのリードと猛々しいコーラスって組み合わせがツボなのだ。しかも無伴奏だしね! 打楽器のみをバックにヤーネルのリード+男声コーラスで歌われる14も好きだなあ。 あとは旋律が“ロウランズ・オブ・ホランド”と一緒な2も聴きごたえがあるし、16曲中最も長尺の6も良い。男女デュエットの15もかわいいんだ~。 ラストのターナーはマッコールにクリソツだなあ。実は御大が歌ってました説が出てもおかしくないほど声似すぎ…本当に12で歌ってる人と同一人物なの?? これ、曲名から来るイメージの通りちょっぴり切なくて素敵なメロディだよ。 バックはシンプルだけど、ことさらに歌い手を強調してるって感じではないんだよね。メンツは激渋だけど聴き疲れは全然ないわ。
2015/11/14
コメント(0)
-
#1282 BARDS 《TIME FOR THE BARDS》 71年英国
Turn A Deaf Ear (Rab Noakes)Coming Of The Roads (Billy Edd Wheeler)Blackleg MinerEarly Morning Rain (Gordon Lightfoot)Elizabethan (Chris Simpson)The Boxer (Paul Simon)Scarborough FairThe Urge For Going (Joni Mitchell)Time (Alan St. John)Innocent HareAcross The Hills (Leon Rosselson)Chicken Song (W. Watson) Sheelagh Holt(vo) Alan St. John(vo, g) Rod Williscroft(b) Folk Heritage Recordings Production 男女デュオです。おそらくは唯一作。 バーズって片仮名表記にしちゃうとメジャーなほうのバーズとごっちゃになるし、声に出して言うにしても“英国フォークの”って付けないと通じません。いやこっちのバーズ自体ごく一部の英フォークファンにしか知られてないな。うん。 静かに淡々と、しかし奥底には強い意志が流れていそうな歌と演奏。 シーラ・ホルトは目鼻立ちが幼いものだから、その落ち着き払ったアルトを初めて聴いた時には「声と顔が合ってなーい!」とびっくりしたのだけど、よく見りゃほうれい線の辺りがそれなりに齢を重ねてそうな質感だしさらにガン見してれば三十路は超えてそうな顔に見えてくるから、最初に抱いた「もっとキャピキャピした歌声を予想していたのに」は早合点だったと気づくわけです。 対してアラン・セント・ジョンは見たまんまです。人の良さそうなおっさんフォーキーそのものって感じですね。彼の歌声は簡素というかブツクサ系というか、とにかく素朴です。どこかのメガネ芸人に似ていなくもない風貌のアラン、ラスト12ではお笑い路線に挑戦したのか歌声がちょっとコミカル。 トラッド3曲にカバーが8曲、自作が1曲。 トラッドは3曲とも人気が高いけど、中でも7は特に有名だよね。これはもうシーラの低音がたまらん! 無伴奏でデュエットする10はアレンジメントがヤング・トラディションっぽいなあ。 カバーも1や6など定番がいくつか。中でもラブ・ノークスが書いた1はリンディスファーンのカバーバージョンが人気だけど、これ聴いた瞬間バーズのバージョンが首位に立ちました。まったく1曲目からこんなクオリティ高くて大丈夫なの!?!? なんて思ってたら6もオリジナルに匹敵する完成度の高さだし、アランが書いた9もホロリ切なくて好み。 なおカバー曲の作者の出身国は2と6がアメリカ、4と8はカナダ。5はおそらくマグナ・カルタの中の人で11は英国。最後12はわからず。 無駄に豪勢にしようとしていないから聴き疲れはまったくありません。 こんなサイトを発見。こんなことしてたのかアラン。 http://www.thephilknightexperience.co.uk/
2015/11/14
コメント(0)
-
#1281 BRENDA WOOTTON & RICHARD GENDALL 《CROWDY CRAWN》 73年コーンウォール
Morvah FairKemer Ow Ro (Take My Gift)Hus Gans Mynfel (Charm With Yarrow)Well Of St. KeyneTekter (Beauty)Pyu A Wor? (Who Knows?)Merrymaidens (Frank Ruhrmund)Bre Cambron (Camborne Hill)Ow Heryades (My Darling)An Hos Los Coth (The Old Grey Duck)An Jow Al (The Jewel)Carol An Mysyow (Stratton Carol Of The Months)Newlyn (Frank Ruhrmund)Mount MiseryAn Scath (The Boat)Tryphena Trenerry (Herbert Thomas)Pyth Whrama? (What Shall I Do?)Lul Ha Lay (Lullaby)Farwel (Farewell) Brenda Wootton(vo/1928-1994) Richard Gendall(vo, g/1924-) Mike Sagar(g; 1, 4, 14) production: Richard Gendall, Irene Morris, Job Morris, Brenda Wootton cover: Peter Ellery コーンウォールの詩人兼民謡歌手のブレンダ・ウートンが、英国生まれながらコーンウォール語の達人として知られるリチャード・ジェンドール(読み方適当)と組んで作ったのがこちら「クラウディ・クラウン」。 ワタクシてっきりこの人達のことをウェールズ出身かと思っていたのですがコーンウォール出身だったのですねえ。ついでに言うと“クラウディ・クラウン”がグループ名で連なった二つの人名がアルバム名とも思い込んでいました。 でも日本語しかできない者にとってはウェールズ語もコーンウォール語も似たような印象なのでしてね、ずっと勘違いしていたからと言っても大したダメージは受けていないのです。 コーンウォール語による語りがふんだんに散りばめられています。独り語りだったり対話していたり…。ひょっとしたら歌パートより語りパートのほうが多いかもしれない。 喋っている内容はいつも通りわかりませーん!(一応英語の対訳が載っているんだけどね) メインで歌っているのはブレンダ。余計な装飾は付けていない朴訥極まりない歌声で、しかし感情はさりげなく込められているので実に親しみやすい。 リチャードもまた庶民的な喉を持っていて、この人が出す低音がまたまろやかでよろし。あ、でも声がダンディすぎてちょっと舞台俳優みたいな雰囲気になってる時があるや。 曲調は基本的にはスキップスキップるんたった♪とは別タイプのピクニックかな。まったりとお弁当広げていそうというか。間違っても脳内花畑ではありません。 どことなくシャンソンっぽいものもあればケルトの哀愁味たっぷりのナンバーもあり。 伴奏はギター1本、時折アカペラ。シンプル・イズ・ベスト!な体の43分間だから何度でも繰り返し聴けるね。 ブレンダの腰の据わった歌声をはじめ、この2人それなりに年食ってそうだなあ…と思ってたらやっぱりです。 録音がスタートした時すでに40代半ばだしブレンダは20年以上前に亡くなっています。リチャードももしかしたら…?(ハラハラ)
2015/11/14
コメント(0)
-
#1280 ELIZA CARTHY & NANCY 《KERR SHAPE OF SCRAPE》 95年英国
Edward Corcoran (Turlough O’Carolan)/Black JokeI Know My LoveLow Down In The BroomThe Downfall Of ParisThe Keek (Or Ride) In The CreelMary Custy AirGrowing (The Trees They Do Grow High)The Poor & Young Single SailorBalter Svens ParapolkettBonny Light Horseman/Michael Turner’S WaltzThe Wanton Wife Of Castlegate/Princess RoyalThe Gypsy Hornpipe/The Hawk (James Hill)/Indian Queen Eliza Carthy(fiddle, vo/1975.8.23-) Nancy Kerr(fiddle, vo/1974.6.24-) Ian Carr(g) Saul Rose(melodeon/1973-) produce: Nancy & Eliza with Ray Williams engineer: Ray Williams & Ollie Knight(1969-) sleeve Design & Photography: Bryan Ledgard イライザ・カーシーはマーティン・カーシーとノーマ・ウォーターソンの娘。ナンシー・カーはサンドラ・カーとロン・エリオット(ノーサンバーランドのパイプ奏者)の娘。 歌い手でありフィドラーでもある2人は2年前の93年にも「イライザ・カーシー&ナンシー・カー」というタイトルで連名作品を出しています。 メロディオンを弾いているソール・ローズはイライザの義兄(イライザの姉妹の旦那なのでひょっとしたら義弟かも)、エンジニアのオリー・ナイトは叔母ラル・ウォーターソンの息子、つまりは従兄弟。 彼女達による曲解説には「母サンドラから習った」「ママが教えてくれた曲」「マイク叔父さんから」といった記述が見受けられます。 アイルランドの盲目パイパーによる1の前半部と12の真ん中以外はすべてトラディショナル。 アイルランド民謡の2だとかイライザのパパも歌っていた7だとか、モリス・チューンである1の後半部だとか同じくモリス・チューンの11の後半部だとか、なじみ深い曲が多いのも嬉しいね。 2人とも20歳そこそこのピチピチギャルなのだけど、フィドルはかなり重いです。 例えばマーティンお父さんの盟友であり英国フォーク界を代表するフィドラーであるデイヴ・スウォブリックと比較すると、スウォブリックが重厚度5だとすればギャル達は10。中低音域を中心に弾いていることが多いし、高めの音でさえもヘヴィ極まりないのです。 んで歌声はというと、イライザはフィドル同様に重め。声域もアルトのあたり。 余談ながらこの後体型もどんどん重量感溢れるものに…お母さんそっくりに…ゴホッゴホッ… あ、ナンシーはキュート声です。古き良き昭和の時代の舞台女優っぽいかわゆいお声ですよ。 無伴奏で歌っている箇所もあって、その堂々としたシンギングはとてもじゃないけどハタチ前後とは思えません。特にイライザ、貫禄ありすぎだろ。 フィドル・パートと歌パートはフィドル・パートの方が若干高めかな。 いやあ最後まで実に重かったわ。 http://www.eliza-carthy.com/ http://www.kerrfagan.com/
2015/11/14
コメント(0)
-
#1279 BATTLEFIELD BAND 《QUIET DAYS》 92年スコットランド
Captain Lachlan MacPhail Of Tiree (P. MacFarquhar)/Peter MacKinnon Of Skeabost (Dr. J. MacAskill)/The Blackberry BushThe River (A. Reid/J. McCusker)Dalnabreac/The Bishop’S Son/Miss Sharon Mccusker (All J. McCsuker)From Here To There (A. Russell)/Jack Broke The Prison Door/Toss The Feathers/The Easy Club Reel (J. Sutherland)The St. Louis Stagger (I. MacDonald)/The Ass In The Graveyard (T. Tully)/Sandy’S New Chanter (T. MacAllister)Captain Campbell/Stranger At The Gate (Benedict Koehler)/John Keith Laing (A. Harper)Hold Back The Tide (J. Tams)Blistered Fingers: The Cumbernauld Perennials (A. Reid/J. McCusker)/The Keep Left Sign (J. McCusker)/Taking The Soup (A. Reid/J. McCusker)/Bonnie George Campbell/Mo Dhachaidh/The Loch Ness Monster (Peter MacLeod Jr.)Curstaidh’S Farewell (A. Reid/J. McCusker)The Hoodie Craw (A. Reid/J. McCusker)Col. Maclean Of Ardgour (J. MacLellan)/Pipe Major Jimmy MacGregor (John Scott)/Rocking The Baby (I. MacDonald)How Will I Ever Be Simple Again? (R. Thompson)/Dawn Song (I. MacDonald) Alistair Russell (vo, g, cittern/1951.2.15-) Alan Reid(vo, key/1950.5.2-) John McCusker(fiddle, whistle, accordion, key, cittern, vo/1973.5.15-) Iain MacDonald(highland bagpipe, flute, whistle, vo) Kate Rusby(backing-vo/1973.12.1-) produced by Robin Morton(1939.12.24-)/engineers Moray Munro, Robin Morton, Gene Carroll/graphic design Graham Ogilvie/cover photo Edinburgh Photographic Library this album is dedicated to the memory of Bruce Kaplan 1969年に結成されたスコットランドのバトルフィールド・バンド、12枚目のスタジオ盤。 結成時から1990年まで在籍していたブライアン・マクニールの後釜に収まったのはジョン・マッカスカー。ゲスト参加しているケイト・ラスビーと2001年に結婚(のちに離婚)することでも知られている若きフィドラーです。 今ではすっかり禿げ上がってますが92年当時は10代のヤング。まだフサフサですよ。 裏ジャケに決め顔で写り込んでいるこの若者が曲作りの面でも演奏の面でも大活躍していまして、アラン・リードとの共作も含めれば手がけた楽曲はかなりの数に上ります。 担当楽器もメインはフィドルだけど笛や蛇腹や鍵盤もやってるし。 泣きメロ満載のゆるやかな曲進行と攻撃性皆無の歌声は今まで通りですが、インストの比重が若干増えているかな。中でもホイッスルがよく鳴っているね。 まあバグパイプもインパクト充分な音色なだけに存在感はあるっちゃあるけれど、独演状態の11以外はパイプがしゃしゃりまくってる場面はそう多くないなあ。 ジョン・タムスやリチャード・トンプソンの曲も取り上げていて、特にタムス作の7は穏やかな美旋律+ケイトのキュートなバッキングにもうメロメロっす。 http://www.battlefieldband.co.uk/
2015/11/14
コメント(0)
-
#1278 BATTLEFIELD BAND 《HOME GROUND》 89年スコットランド
Home Ground: Skinners Compliments To Dr. MacDonald (J. S. Skinner)/The Ivory Reel (B. McNeill)/Miss Susan Fedderson (B. McNeill)/Tuireadh Iain Ruaidh/The Ladies From Hell (J. MacMillan)/The Roe’s Among The Heather/Islay’s Charms (Iain C. Cameron)/The Banks Of The AllanThe Yew Tree (B. McNeill)After Hours (C. McGettigan)/Whiskey In The Jar/The Green Gates/The Ship In Full SailPincock’s Pleasure: Lady Carmichael’s Strathspey/Laird O’Drumblair (J. S. Skinner)/The High Road To Linton/Conway’s Farewell (D. Pincock)/Andy Renwick’s Ferret (G. Duncan)The Dear Green Place (A. Reid)Fare Thee Well WhiskeyThe Hornpipes: John MacKenzies Fancy (J.Barrie)/Dr. John Mcinnes’ Fancy/The Train Journey North (T. Anderson)The Rovin’ Dies Hard (B. McNeill)Bad Moon Rising (J. Fogerty)/Rising Moon Reel (Pincock)The Four Minute Warning: The Tides Out/James MacLellan’s Favourite (Duncan Johnstone)/Dougies Decision (John Gahagan)/The Ferryman (Donald MacLeod)/Lady Doll SinclairFarewell Johnny Miner (Ed Pickford)Band Of A Thousand Chances: Land Of A 1000 Dances (Kenner/Domino)/The Dashing White Sergeant/Donald Where’S Your Trousers (McLeish/Kennedy)/The Fairy Dance/Lets Twist Again (Appell/Kalman)/Mrs. McLeod Of Raasay/With A Little Help From My Friends (Lennon/McCartney)/The Atholl HighlandersPeace And Plenty (B. Mcneill) Alistair Russell (vo, g/1951.2.15-) Brian McNeill (vo, fiddle/1950.4.6-) Alan Reid(vo, key/1950.5.2-) Dougie Pincock(bagpipes, whistle, flute, harmonica, per /1961.7.7-) produced by Robin Morton(1939.12.24-), sleeve design Graham Ogilvie ※メンバー表記がなかったんでネットから適当に拾ってきました。これ以外にも弾いてるかも。パイパーはサイトによってはイアン・マクドナルドになっている場合もありましたがとりあえずピンコック氏にしちゃった☆ 1969年に結成されたベテラン、バトルフィールド・バンドによる初のライブ盤。1989年早春にスコットランドをドサ回った時の模様が収められています。 音色のインパクトが強いパイプが目立っているのは確かなのだけど決してそれを中心に進行していることはなく、むしろリーダー格はフィドルのB・マクニールと鍵盤のA・リードと思われますね。 楽器の編成だとか同じケルト圏だとかでアイルランドのボシィ・バンドが浮かんでくるのだけど、あちらさんほど熱血してないし聴いていてやたら脈拍が上がることもないです。 それはおそらく高速チューンが入っていないこと(せいぜいちょっと速めのジョギング程度)と、歌声が明朗でありつつもなんとなくドンくさいことに原因があるんじゃないかと。 コーラスも多用していてね、これがまた同郷のタナヒル・ウィーヴァーズみたいな心地よさなのですよ。 J・S・スキナーみたいな“その筋”の音楽家、自作曲、トラッドを中心に演奏していますが、注目すべきは9と12。 9ではクリーデンス・クリアウォーター・リヴァイバルの、12の後半ではビートルズのカバーを披露しています。 12も初っ端から「ナ~ナナナナ~♪」(←あちこちで耳にするあのメロディ)とみんなでコーラスしているし、コンテンポラリーとトラッドを交互に演奏してはいるけれど全体的には「ツイストを踊ろうよ」的な。この人達、ガチムチのトラッダーかと思いきや実はまったくそんなことないんじゃ…? ほっといたらモンキーダンスをおっぱじめてしまうんじゃ…? それにしてもビートルズ・ナンバーからスコットランド民謡へのスムーズすぎる移行は見事としか言いようがないね! ラストはフィドルとハープ(誰が弾いてんの? アラン?)とフルート(ロウホイッスルかも)のアンサンブルがとんでもなく美しいインスト。 このバンドにおける美メロ作者はアランが筆頭だとばかり思っていたけどブライアンもなかなかやるじゃないか。(←なぜか上から目線のワタクシ) http://www.battlefieldband.co.uk/
2015/11/14
コメント(0)
-
#1277 ORA 《ORA》 69年英国
SeashoreAbout YouDeborahWhitchVenetia IIYouFlyLadyfriendAre You SeeingEmma’s SagaThe Morning After The Night BeforeThe Seagull & The SailorSeashoreNo More LovePommeDeborahIt Was An Easy LegendFlyThank God all songs written by Jamie Rubinstein except for ‘Pomme’ written by Chloe Walters Jamie Rubinstein(vo, a-g, e-g, ds)John Weiss(e-g) Robin Sylvester(b, key, g, backing-vo/1950-) Julian Diggle(ds, per, backing-vo) Chloe Walters(g on Pomme) Mick Barakan(g on Thank God/1954.10.10-) Gordon & Jennie Hunt(oboe, violin) ロリー・ギャラガーやイースト・オブ・エデンのセッションに参加したり、ケンブリッジ大へ進学したりギャラガー&ライルと一緒に演奏したりコーンウォールで芸術学校を建てたりと解散後のその後の活動が地味にゴージャスなオーラ。 ピーター・バラカン氏の実弟が在籍していたことで有名なバンドの母体としても知られていて、8はそのビザンチウムでもレコーディングしてます。なおビザンチウムに移動するのはジェイミー・ルビンステイン、ロビン・シルヴェスター、そしてミック・バラカンの3人。 オーラはハムステッドの同じ学校に通っていたジェイミー、ロビン、ジュリアンの3人によって結成されたんだけど、どうやらミックも同じ学校の後輩だったらしいです。 69年当時ジェイミーとロビンはともに18歳。頼りなげな歌い方が青っちいティーンエイジャーっぽさを醸し出していて微笑ましい。しかし楽曲のレベルはそれなりに高いので和んでばかりもいられない。 薬局で売っていないおくすりを常用している感じはまったくしないものの(まだ10代ってこともあるかも。ブックレットの写真なんて若い通り越して子供だし)、この覇気というものがほとんど感じ取れない気だるい雰囲気はドリーミー・サイケ・フォークとすればいいのかしら…。 オーボエの切ない響きが絶品の3、エレキのとんがり具合とほのかに汚い歌声に処理したヴォーカルがハードな4といったあたりが好き。 こじゃれた雰囲気の15(数年前にエンゲルベルト・フンパーディンクの下で歌っていたクロエ・ウォルターズ作)も◎(マル)。 音質はお世辞にも良いとは言えない。しかしこういうマニアックな音源が手軽にCDで(しかも安く)入手できるとはいい時代になったものだよね。
2015/11/14
コメント(0)
-
#1276 ACCORDION TRIBE 《SEA OF REEDS》 2002年多国籍
Tangocide (Klucevsek)Unikko (Kalaniemi)Pas Du Valse (Hollmer, First melody in “Fuga” part by M. Berekmans)Swither (Klucevsek)Portaletyde (Hollmer)Gras (Lechner)Goldhorn (Bibic)Silvia’s Tongue (Lechner/Hollmer)Sudaf (Hollmer)Tuttuni (trad/Kalaniemi)Chalk Dust (Klucevsek)Thursday Night’s Fridays (Bibic, Waltz part by Jean Maurice Rossel)Spinning Jennie (Kluecevsek) Bratko Bibic(1957-、スロヴェニア・hohner tang opiano accordion, vo) Lars Hollmer(1948.7.21-2008.12.25、スウェーデン・zerosette piano accordion, suzuki melodica, vo) Maria Kalaniemi(1964-、フィンランド・lasse pihlajamaa timangi standard 5-row botton accordion, lasse pihlajamaa free-bass 5-row button accordion, vo) Guy Klucevsek(1947.2.26-、アメリカ/スロヴェニア・titano piano bayan with 45-key piano keyboard, convertor bass (120 bass converts to 4-row chromatic free bass), vo) Otto Lechner(1964.2.25-、オーストリア・hohner lucia piano accordion, vo) produced by The Accordion Tribe, executive producer Phillip Page, cover art Pelle Engman, design M4 Media アコーディオンを弾く5人の国籍はスロヴェニア、スウェーデン、フィンランド、アメリカ、オーストリアと様々。 最も有名なのはかつてスウェーデンのプログレ・バンド、サムラ・マンマス・マンナでブイブイ言わせていたラーシュ・ホルメルかしら? それとも北欧トラッド好きにとっては基本と言うべきマリア・カラニエミ? いやひょっとしたらこの2人よりはるかに名の知られた人物が残る3人の中にいたりして。 96年に活動を開始し翌年にアルバム・デビュー。本作は2枚目。 基本的にオール・インストで時折歌声が入るものの、マリアが歌う10を除くと明確な歌詞の存在しないスキャットが中心なので「ヴォーカル曲」という感覚はあまりなし。 口琴が時折顔を出しているが、クレジットには載っておらず…どうやら各人の歌声を巧いこと加工しているようだ、と書いたけどやっぱりどう聴いても口琴使ってるよなあ…。真相はどうなってるんだい!? 同じ楽器しか使っていないという点でフィンランドのハーモニカ集団スヴェングを思い出したりも。 場末感漂うオールドタイミーな舞踏曲っぽいものあり、ちょいとアンニュイな表情を見せてくれる曲あり。 アコーディオンという楽器はここ日本でも合唱の伴奏楽器に使われたりしているからわりとなじみ深いのだけど、ここまで徹底してアコーディオンだらけってのは初体験。 …ええ、とても楽しく聴いてますよ。歩きながら聴いていたらいつの間にかステップが軽やかになってたもんね。そう、この楽器は長調だろうが短調だろうがテンポが遅かろうが速かろうが、さりげなく踊り出してしまうのが大きな特徴なのです(←言いきった!)。 スタジオ盤よりライブの方が絶対に楽しそうという点では先述のスヴェングと一緒だけど、ラーシュが亡くなってしまっているため5人が勢揃いすることはもうありえない。享年60歳ということを併せて考えると一層切なくてね。 ラストがそんな気持ちを代弁しているかのようなとびきりの哀メロで…、いかん。泣きそう。 【メール便送料無料】ACCORDION TRIBE / SEA OF REEDS (輸入盤CD)
2015/11/14
コメント(0)
-
#1275 JACKIE DALY AGUS SEAMUS CREAGH 《JACKIE DALY AGUS SEAMUS CREAGH》 77年アイルランド
Seamus O Caoimh/Th Trasna (Jim Keeffe’s/The Newmarket) polkasCailini Mha Chromtha/An Fanai I gCorcaigh (The Macroon Lasses/The Rambler In Cork) reelsAn Gleann Faoi Dhraiocht (The Enchanted Valley) slow airAn tEan Ar An gCrann/An Da Ean Ar An gCrann (The Bird In The Bush/The Two Birds In The Bush) hornpipesCon O Conaill/Cuilinn Ui Chaoimh (Connie O’Connell’s/Cuilinn Ui Chaoimh) jigsLiam O Suilleabhain/Bristi Breaca (Bill Sullivan’s/O The Britches Full Of Stitches) polkasA Oganaigh An Chuil Chraobhaigh slow airBrid Mhin Bhaile Mhuirne/Quille (Sweet Biddy Of Baile Mhuirne/Quilles) reelsCornphiopa Ui Bhroin (Byrne’s) hornpipeBi Liom/Sortanna Suiri (Follow Me Down/The Game Of Love) reelsA Brat Chomh Deas Glas (Her Mantle So Green) slow airSean Mhici/Padraig O Caoimh (Johnny Mickey’s/Padraig O’Keeffe’s) slidesDonncha O Murchu/Glanadh Cro Na gCearc (Denis Murphy’s/Cleaning The Hen House) reelsAn Tailliuir Ban (The Tailor Ban) songNa Ceithre Thiomaint (The Four Shoves) polkas ※すべてトラディショナル Jackie Daly(1945.6.22-・accordion) Seamus Creagh(1946~2009.3.15・fiddle, vo) Colm Murphy(bodhran) デ・ダナンやパトリック・ストリートに在籍していた蛇腹奏者ジャッキー・デイリー(74年にボタン・アコで全アイルランド・チャンピオンに輝いている)と、フィドル奏者のシェイマス・クレイがアラサーだった頃に作ったデュオ作。 ジャッキーの出身地であるSliabh Luachraの音楽をたっぷり紹介している本作には、後にデ・ダナンで活躍することになるコルム・マーフィーがゲストに。 不純物などまったくないアコーディオンとフィドルのアンサンブルを聴いていると、雑念だらけの私の心も浄化されていくみたい。 高速ダンス曲もいくつかやっているんだけど、そこへバウロンが加わったとしても急かされている感がまったくしないし、逆にゆったりした曲調でも間延び感は皆無。 ジャッキーは2006年11月に来日した際には達者すぎるノールック奏法で我々を唸らせ、また少々天然入った性格で和ませてくれた(観に行きました)。 一方、相方のシェイマスは残念ながら2009年に鬼籍に……。そのことを考えながら唯一の歌もの14を聴くと、シェイマスのあまり巧くはないけど純朴で人間味ある無伴奏独唱が実にしみてきます。 曲名になっている(12)と同時にライナーで言及されてもいる「最後のフィドル・マスターのうちの1人」パドレイグ・オキーフの演奏は#437のクランシー一家のアルバム(55年)で聴くことができます。 またシェイマスは当ブログ初出。ジャッキーとコルムはそれぞれ8回&3回登場していますが、2人が共演しているアルバムは今回紹介した本作が初。 かっこよすぎるバウロン・ソロをちらっと入れた15で引き締めて終演するのもまた良し。
2015/11/14
コメント(0)
-
#1291 PAUL & LINDA ADAMS 《FAR OVER THE FELL》 75年英国
The Keswick Driver (Robbie Ellis)Jolly Boys SongJimmy’s EnlistedThe German ClockwinderA Brisk Young SailorKing DunmailThe Lament Of The Border WidowTarry Woo’The Sun Shines Fair On Carlisle WallPaul JonesFarewell To The Miner (Paul Adams)The Witch Of The Westmorlands (Archie Fisher Paul Adams(vo, per) Linda Adams(1954-・vo, g, p) Alan Green(b) produced & engineered by Alan Green、sleeve design Paul Adams 女性フォーキー作品が2つ続き、男性ヴォーカルものが聴きたくなってきたなあとふと思ったんでこちらをチョイスしてみました。 当時20歳そこそこのリンダとメガネ男子ポール(65年にこの世界に入ったということなのでリンダよりは確実に年上のはず)によるアダムス夫妻です。 これは本当に好きなアルバムなのですよ。 メロディが耳になじみやすいものばかりだし、それでいて適度な緊張感も持ち合わせてる。 大好きな無伴奏混声重唱がしっかり入っていて、ポールもリンダもアクの少ない歌声なので実に気持ちよく聴くことができます。 リンダが弾くギターがうるさすぎずサポート。 その他4でピアノとベースが、10で太鼓が登場しています。 “クルエル・マザー”の別バージョン9とか歌詞だけならドロドロ系のトラッドが含まれていますが、メロディは素朴で明るめのものが多め。4はアイルランド民謡の“茶色の小瓶”みたいに弾むような楽しい旋律だしね。 コンテンポラリー曲に目を向けてみると1のロビー・エリスは2人のホームタウン、カンブリアにあるペンリスという町出身のシンガーらしい…と、情報を求めてネットサーフィンしていたら「CUMBRIA FOLK SONGS Robbie Ellis」って動画が出てきました。ギターをやたら上の方で抱えて美声を披露している白髪のおじさんなんだけど、これ本人だよね?(こちらです。17分近くあります→ http://www.youtube.com/watch?v=5Cmt2H0RwDk) ラスト12はいわずもがな、スコットランドの重鎮フォーキーで女王陛下から勲章までもらっちゃってるアーチー・フィッシャーの曲ね。 のちにフェルサイド・レーベルを設立し良質なレコードを量産することになる2人。私個人としては、ポールに関しては歌い手としてよりもプロデューサーとしてのイメージがずっと強いです。これまでにレビューしたものだとドクター・フォースタス(ジョン・カークパトリックの息子が在籍)、ナンシー・カー&ジェームス・フェイガン(ナンシーはサンドラ・カーの娘)、ピーター・ベラミーのソロなんかがあるよ。 http://www.fellside.com/
2015/11/14
コメント(0)
-
#1274 PHIL COULTER 《CLASSIC TRANQUILITY 想い出に抱かれて》 83年アイルランド
1. The Derry Air 2. Mary From Dungloe 3. Love Thee Dearest 4. The Old Man (Phil Coulter) 5. Carrickfergus 6. Buachaill O’n Eirne (Come By The Hills) 7. Steal Away (Phil Coulter) 8. Mise Eire (Sean O’ Riada) 9. My Lagan Love 10. The Spinning Wheel 11. Maggie 12. Scorn Not His Simplicity (Phil Coulter) 13. Boulavogue 14. Lake Of Shadows (Phil Coulter) 15. The Wind In The Willows (Alan Bell) 16. The Town I Loved So Well (Phil Coulter) arranged and produced by Phil Coulter (1942.2.19~) ピアノにオーケストレーションのバッキングが付くスタイルで全曲インスト。 こじゃれたお店で流れていそうなヒーリング系の雰囲気プンプンなんだけど、なじみのアイルランド民謡がたっぷり収録されているので飽きないんだよね。よく知っているメロディが出てくるとつい旋律をなぞっちゃって。 こういうトラッドてんこ盛り盤を入手すると、多くの録音が存在している5や9、10を別の演奏家のバージョンと聴き比べてみたくなるし、15はブラックモアズ・ナイトが99年の「アンダー・ア・ヴァイオレット・ムーン」で取り上げていた歌と同じものと判明してテンションがちょっぴり上がったりもします。 ぶっちゃけ地味です。でも妙に好き。 http://www.philcoulter.com/ 【メール便送料無料】PHIL COULTER / CLASSIC TRANQUILITY (輸入盤CD)
2015/11/14
コメント(0)
-

3年ぶりの復帰です
また戯言レビューを書きたくなってきた。のだけど、かつては駆使しまくってたHTML全部忘れました。。。適当にやっていきます。相変わらずの駄文ですが。輸入盤CD/ブルース・カントリー(インポート・海外版)Transatlantic Story【中古】こちらは今月に入ってからヘビロテ中のトランスアトランティック箱。「ブルース・カントリー」ってなってますが、ペンタングルとかジョンストンズとかを出してたあのレーベルです。いろいろ入ってて楽しいよ。
2015/11/14
コメント(0)
-
【注意!】ブログの引っ越しはとっくに終わってます!【注意!】
こっちに引っ越ししました。ここで書いていたレビューも全部移動させてあります。こちらの旧サイトをブックマークしている方は、お手数ですが新サイトのURLを登録し直してくださいませ。リニューアル後はABC順の索引を画面の右側に常駐、多すぎると省くこともあった録音参加者は全員掲載などなどそれなりに改善されています。レビュー以外の記事(コンサート評とか)もすべて移動させたらこちらは閉鎖するつもりです。
2012/11/17
コメント(0)
-
言い忘れてたけど
新しい記事だけでなく古い記事も引っ越しさせてるのですよ。5年前に書いたレビューも1年前に書いたレビューもすべてね。ゆくゆくは戯言レビューは全部FC2ブログで事足りるようにしたいなあ、、、と。新ブログ「英国民謡好きの戯言・おかわり」ではどのページを開こうが常に右側にABC順の索引を常駐させてます。ツリー状になっていて、バンド名または個人名をクリックするとその下にさらにアルバム名が出てくるのでご覧になりたいアルバムをクリックしてください。またジャケット画像はアマゾンのものを使用しています。「これほしいかも!」と思ったらジャケをクリックしてみてください。ただしクリック先とレビュー本文の内容が若干違うことがありますのでご了承くださいませ。ちなみにアフィリエイトはやってないです。新ブログ「英国民謡好きの戯言・おかわり」はこちら→http://englishtradition.blog.fc2.com/
2012/05/30
コメント(0)
-
ブログの引っ越しをしました
こちらのブログの行間の狭さにブチ切れそうなので言い訳は省きます。心機一転、FC2ブログに引っ越ししました。「英国民謡好きの戯言・おかわり」です。工夫もへったくれもない新ブログ名ですが。しかもどういうわけかメタルなラジオ番組の文字起こしを大量に載せていたりもしますが。右側に索引を常駐させていることやらツイッターによるつぶやきを載せていることなどなど自分なりに「この部分便利よね♪」な箇所もいくつかあります。そしてジャケは基本的にアマゾンのものを載せているのでほしくなったら即クリックして購入可能☆キャハッ新しいURLは以下になります。http://englishtradition.blog.fc2.com/(「englishtradition」は残したかったのだ)まだ半分も引っ越し作業は終わっていませんが、今後ともご愛顧のほどよろしくお願いいたします。
2012/01/14
コメント(0)
-
【お知らせ】
只今、ブログの引越作業を進めています。引越先のURLは後ほどお知らせします。(ブログ名はほとんど一緒なので検索すれば出てくるかも)基本的に作業が終わるまで新作レビューは載せませんが、NHK-FMで不定期放送している「三昧シリーズ」の文字起こしは載せる予定。12/25のメタル三昧は遅くても1週間ぐらいで終わらせてアップしたいですね。尚ほぼ毎日ツイッターでつぶやいていますので、お暇な方はチェックしてみてください。@tanuki_kaidoです。
2011/11/26
コメント(0)
-
2011年11月3日20:00~J-WAVE JAM THE WORLD~和合亮一さんが出た部分の文字起こし~ 3/3
続き。DJ竹田圭吾→青文字アシ小林まどか→赤文字ゲスト和合亮一→黒文字最後に一つ伺いたいのは、もうすぐ8ヶ月になって…東京にいるとどうしても震災の記憶とか報道全体が少し風化してきているというか薄れてきているような部分があって。ま、時間とか距離のこと考えると色々やむを得ない部分もあるんですけど、本来風化しちゃいけない部分がおそらく必ずあって。それをどうやって僕達は自分の中に繋ぎとめておかなきゃいけないのかなって意識することもあるんですけども。福島にいらっしゃって福島の思いをこういう形で発信されてきた和合さんからご覧になって、段々風化していくような記憶というか状況についてどうお感じになるか。それからこの先和合さんは、詩を通じて発信してきた和合さんは何をなさっていくつもりなんでしょうか。一番それが8ヶ月経って自分の頭の中で、心の中で最も大きな問題の1つに…私自身もなってるんですけど。ずっと今は静かな日常が福島にも戻ってきています。だけど出口は相変わらず見えない。そういう時間を過ごしています。静かな難しさと今向き合っている状況で。静かな難しさ?はい。ともすれば時にはふたをされてしまうんじゃないか。このままふたをされてしまうんじゃないかっていう、そういう不安を感じることもあります。だからむしろ今ふたをされてしまうその時間の中で、声を小さくてもいいから上げていく。その上げていく声が上からのしかかってくる静かな時間の重たさを少しずつでも変えていくんじゃないか。私達、この日本人である限り日本を信じて故郷を愛して日本語で正しい気持ちを伝えていくことをしていくためには子供たちに何を残していくか。それはこの、今震災からずっと続いている出口の見えなさを正確に記録して。その記録の厚みと重さをそのままこれからの未来の子供たちに渡していくことこそが、大人の私たちが暮らしていく決意を持った人間達の役目だと思うんですね。それで泣く泣く故郷を離れていく方々もいます。そして残って暮らしている人達もいます。まったく同じ気持ちで過ごしていかなくちゃいけないと思うんですね。それが故郷を離れた方々と故郷に残ってる方々が温度差があってはいけないと思うんですよね。もっといろんなことを受け止めていろんなことをそこで話をしていって、私たちが暮らしてきた生活そのものを…すべてを残していくということが、これから先の子供たちの社会を望ましい方向に向かわせなくちゃいけない。そんなきっかけになればなと思ってるんですね。だから全村避難がありました飯館村。その飯館村のある方は、「私達の代でよかった。そんな風な気持ちで頑張りましょう」って。「これから先の子供達にこういうことが起きないように、私達の代でよかった。そんな風に言えるように頑張りましょう」って聞いたことがあって。僕涙が出そうになったことがあったんですね。「福島を生きる」っていうことを僕はずっと地元で…、「福島に生きる。福島を生きる」ということをいろんなところでお話ししているんですけど、福島“に”生きるというのは僕が今福島で暮らしていることなんですが、福島“を”生きるというのは、例え故郷を離れて暮らしていても、福島で暮らした思想を大切にして自分を愛すると同じような気持ちで福島で暮らした思想を生きていく。そういうことをきちんと受け止めて福島の、遠く離れても福島で暮らした思想を生きていくことでその背中を見て子供たちは次の世の中を作っていくと思うんですね。だから僕のやりたいことというのはきちんとした背中を子供達に見せていって、今震災で苦しんでいる私達全員で背中を見せていって。そして何か光を求めていくような、そういう時間をふたをされていくことに負けずにですね、小さな箱にメッセージを込めてたくさんの方に受け渡していくような。そういうことしか僕はできないんですけど、それをやっていきたいなって思ってますね。そうした意味でも和合さんの思いや気持ちを引き続き私達にメッセージとして伝えていただければと思います。今夜はどうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。今夜は被災地・福島から様々な思いが込められた言葉を発信し続ける詩人・和合亮一さんをお迎えしました。以上ブレイクスルーでした。おしまい。
2011/11/03
コメント(0)
-
2011年11月3日20:00~J-WAVE JAM THE WORLD~和合亮一さんが出た部分の文字起こし~ 2/3
続き。DJ竹田圭吾→青文字アシ小林まどか→赤文字ゲスト和合亮一→黒文字文章だけで読むのとやはり違うのと、あと録画したものでは和合さんの朗読私拝見したことあるんですけど、やっぱりさっきおっしゃってたように1回1回おそらく微妙に違う読み方なのかもしれないなという風に感じました。特に「放射能が降っています。静かな夜です。」という、「放射能が降っています。(まる)静かな夜です。(まる)」で1つのツイートなんですけど、ほかのいろんな詩を読ませていただいても結局ここに戻ってきてしまうんですよ、僕は個人的には。これがすべてを語っているような気がして。詩の力、それがツイッターっていうもので表現された時に、今回何か特別な力というかメッセージみたいなものを持つようなのを実感します。J-WAVEジャム・ザ・ワールド、ニュースの先を読むブレイクスルー。今夜は福島県福島市を拠点にする詩人・和合亮一さんをお迎えしています。和合さん引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして先ほどはその「詩の礫」から朗読していただいたんですけれども、和合さんは避難所となった福島県郡山市にある展示場ビッグパレットふくしまのこれまでの記録をまとめた本である「生きている 生きてゆく:ビッグパレットふくしま避難所記」にも詩を寄せていらっしゃるんですよね。今日も竹田さんも用意されてますけれども。ほかの本よりも大型でビジュアルがたくさん使われています。避難所の色々な様子、避難所に暮らしていらっしゃる方の様子がテレビなどで断片的に報道されているものだけではなくて、ペットだったりとかご高齢の方とか非常に細かく報じられてます。それに和合さんの詩も一緒に掲載されているというんですね。一番は足湯…えっと、この避難所のある場所に足湯の場所を設けたんですね。それで避難者の方がそこの足湯に来てリラックスする。足湯のボランティアの方が足をマッサージする。その時に出た呟きをマッサージしている方がその後書きとめて。ここに載っているのは避難者の方々がふと漏らした心の底から出た言葉なんですよね。だからある意味僕もツイッターをずっと…今もやり続けているわけなんですけど、その呟きというものの力というのをこの本をもう一度できあがって拝見してですね、私自身も改めて見直して感じたところですね。こうして見てみると被災者の方達の笑顔っていうのもたくさん収められているんですよね。そうですね。被災者の方々というのは…このビッグパレットは県内で一番大きな避難所なんですけれども、このビッグパレットが生活圏となって、そこには様々な物語があった様子をうかがって…何度かきましたけども。いろんなものを乗り越えてその笑顔なんですね、この写真に収められているものは。段々と、最初のうちは漠然としていた避難所の中が自治組織のようなものができたりコーヒーを飲むようなところができたり。あとコミュニティーFMのようなところができたりみんなで遊ぶ場所ができたりお風呂入るところができたりして、段々とこの自治空間になっていって、その時に生きるとは何か? 町の暮らしとは何か?っていうことをみんなで考えて。そこの考えた先にたどり着いてる笑顔のような、そういうものがたくさん見受けられるんですね。面白いのはこの避難所の中でコミュニティーFMを作って、それでボランティアでコミュニティーFMが運営されていて。いろんな方が番組をここでやってですね、避難所の方がラジオを聴いているんですけど。このお話うかがっていて、公開録音とかよくされるんですけど。みんな公開録音の場所に集まってラジオ片手にですね、公開録音聴きながらラジオ耳で聴いてるっていう(笑)。そういうことが多かったみたいですね。今までそういう風に人前で自分の思いとか感じたことを言葉で表現したことがなかった方々ですよね。そうですね。そういう方々が今お話あったようなコミュニティーFMみたいなところに出てきて、自分で番組にも出たりとかってのは何か発露するようなものがあったということなんですかね?そのビッグパレットの避難所の1つの建物の中に町のすべてが出来上がっていたっていう。そういう印象が私、取材で伺った時に思ったんですね。だから町っていうのは場所を変えてもそこに人間の暮らしがある限り、1つの何か円環するような真理というのを町は持っているんだなあって改めて思いましたね。だから何かものを作る人もいれば困った人達に手をさしのばす人もいれば、頼る人もいるし何か教える人もいれば何かを作る人もいるっていうそういうものが避難所の暮らしの中で見えました。それではその「生きている 生きてゆく:ビッグパレットふくしま避難所記」の中からここで朗読をお願いします。おやすみなさい。眠れないのなら私がかたわらで聞いてあげる。おやすみなさい。そして眠れないその理由を。悲しいのなら私が一番先に聞いてあげる。ひどい話だ。やっぱり悲しいその理由を。怒りたいのなら私が叫びを受け止めてあげる。どこにもぶつけようがない。そうさ怒りは静かでも激しい。私。私は誰。私は日付変更線の先の明日。です。夜明けです。このおやすみなさいというのは誰に向けたおやすみなさいなんでしょうか。ツイッターで詩を書いている時に必ず終わりに「おやすみなさい」って書くようになったんですけども。一番最初に思い浮かべてたのは避難所でなかなか寝付けずにいる方々に最初は書いていたんですけど。段々と僕自身がこの「おやすみなさい」を書いて、今日の1日を閉じます、読んでくれてありがとうございましたっていう気持ちに変わっていって。だけどその中には明日は何かいいことがあるといいですねっていうそんな気持ちも込めて書いたんですね。だから必ず…ツイッターを発信する時はどうしても夜遅くなっていくんですけど、夜更けにですね、最後に「おやすみなさい」って書くとなんか自分の気持ちも「次へと向かって行こう」って。だけどここにこう書いた本当のおやすみなさいというのは明日の朝に向かっていく、その前向きな気持ち。それを避難所で色々取材をしていくうちにある方がですね、避難所に来てとても塞ぎ込んでしまって少し気持ちがもう絶望の中で這いあがれないような、そんな気持ちでいたと。その時に「なんでも話してください」っていう方が避難所の中にいらっしゃって、それでその人に空っぽになるまで話をしたと。そしたら本当に自分が空っぽになって言葉がもう空っぽになるまで話をしたら、頑張ってみようっていう気持ちになった。そういうことを取材して聞いた時に私でよかったら話を聞きますっていう、そういう気持ちをここに込めたんですね。だからおやすみなさいって言いながらそれは自分に向けた気持ちでもあるし、また明日出会う誰かに向けた、そういう光が見えるような一言にしたいなと思ってます。続く。
2011/11/03
コメント(0)
-
2011年11月3日20:00~J-WAVE JAM THE WORLD~和合亮一さんが出た部分の文字起こし~ 1/3
DJ竹田圭吾→青文字アシ小林まどか→赤文字ゲスト和合亮一→黒文字この後はブレイクスルー。詩人の和合亮一さんをお迎えして“言葉の力”に迫ります。東京六本木ヒルズからお送りしている竹田圭吾のジャム・ザ・ワールド。続いてはブレイクスルー。アシスタントは小林まどかさんです。はい、よろしくお願いします。さて注目の話題や人物にフォーカスしてニュースを読み解くブレイクスルー。今夜は文化の日の「文化」にシンクロして、文化を感じて文化を伝えてそしていろんな文化の違いを理解する上で最も重要なコミュニケーション手段の1つ、言葉の力に迫りたいと思います。東日本大震災の発生から6日目の3月16日の夜、ツイッター上に言葉を投げかけ始めて多くの方からフォローされて共感を呼びまして、そして言葉の向こう側にある具体的な被害や、それから極限に達した人々の気持ちを代弁する詩人・和合亮一さんをお迎えしました。こんばんは。よろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずですね、震災から今日まで間もなく8カ月が経とうとしているんですけども、これまでの活動を振り返ってみて、改めてどういう風に感じていらっしゃいますか?震災のことを考えない日は1日もないという…そういう状況ですかね。そして今ご紹介詳しくいただいたんですけども、代弁者ということではないにしろ、なんかあの大変…紹介していただいて光栄に思うんですが。福島の1人の住人としてこういうことを訴えていきたいとか話していきたいとか伝えていきたいということを考えていると、1日や1週間や1カ月が過ぎていってしまうという。そういう日々の連続です。3月11日の地震があった時、それからその後に津波が来た時というのは和合さんはどちらにいらっしゃったんでしょうか。僕は福島のいわゆる中通り…内陸の方におりました。津波の被害とそれからすぐに起きました原子力発電所の爆発の知らせとを聞いて、内陸の方も放射能の数値高かったもんですから余震と放射能の恐怖に苛まれた毎日を送ってました。「詩の礫」という詩をツイッターで和合さんが呟き始めたのが3月の16日だったと思うんですけども、それまでの5日間というのはどのように過ごされていて、3月の16日に何故突然ツイッターで詩を始められたんでしょうか。3月の11日の震災の夜から3日間避難所の方におりました。でもこれは家の中がとにかくもう滅茶苦茶でして。家ってのはご自宅?はい。ガラスの破片が飛び散っていて子供が一番心配だったんですね。それでガラッと開けたら、あっこれはなかなか中に入れないな。で、それでお父さん先に入るからそこで待ってなさいって言って入った途端に足怪我しまして(笑)。それでこれは少し落ち着いてから、とにかく余震が静まってから家に戻ろうと思って。そういう方が避難所にたくさん…福島の避難所に様々集まりましてですね。とりあえず余震の心配に怯えて夜を明かしたという方々。そういう方々と一緒に見つめておりました。16日に詩を突然呟き始めたのは何かきっかけがあったんでしょうか。3日間過ごした後に自宅に戻ったんですね。その後原子力発電所の爆発がずっと続きまして、それで家内と息子を…家内が山形実家なものですから3月16日に避難していったんですけれども。そこで私が1人になって、それでまだまだ余震と放射能がずっと頭の中にあってですね、それでこのまま暮らしていくこの気持ちをそのままに伝えたいという風にその時思いまして。それはたぶん1人になったというところから始まっているのかもしれないんですけども。1人になって詩人としての…詩を書く人間としての自分を意識したということでしょうか。いわゆる今生の別れみたいな感じだったんですね。今生の別れ…。たぶん妻と子供には会えないだろう。そういう気持ちが凄く強くあって。これ私だけじゃなくて福島の皆さん決意して家族の別れをして妻と子供が避難して父親は職場に残ってっていう、そういうことが大変多くてですね。私もその中の1人で。妻と子は避難していって、これから先会うことも難しいんじゃないかって思った時に本質的に1人になったんですね。その孤独感がもの凄く強くなって。それが僕は詩を書いてきたのでそのまま言葉になっていったという。そういう時間でした。「詩の礫」なんですが、このタイトルはどういう思いがこもっているんですか?目の前ががれきの世界になってすべてが崩壊したような、そういう気持ちになりました。それまでは絶対福島は地震が来ても大丈夫っていう。実は福島は下に岩盤が広がっていて、小林さんも福島にいらしたということで。いました、はい。岩代の国と言われてたんですよ。「岩」に代々の「代」と書いていて、代々岩が守ってくれる。そういう土地だという風に祖母とか祖父に言われて絶対大丈夫だと言われていたんですけど、その絶対とあと原子力発電所は絶対大丈夫だって言われてた。二つの絶対が目の前で崩れた時に僕自身の書いてきた詩ですよね。ポエジーというか詩を書くということの絶対性もまた崩れていって、それで「詩の礫」というタイトルがふっと浮かんできて。これでやってみようかなって思いました。ちょうどツイッターってのが140字という文字の制限があって。これも礫っていう表現が割とぴったりくるのかなとも思ったんですけども。何故ツイッターだったんでしょうか。ネットで普通にもっと長い表現で詩を書くことも可能だったと思うんですけれども。これが不思議なんですけどね、簡単に言うとひらめいたって言いますかね(笑)。ツイッターで…今のこの状況をリアルタイムに伝えるにはツイッターが一番いいのではないかという風にひらめいたんですね。震災前は実は少しだけやってるんですけども、だけど自分にはツイッターは向かないなって思って。10個ぐらい呟いているんですよ。だけどフォロワーも7人ぐらいしかいなくて(笑)。これ向かないなと思って(笑)。ツイッター止めてるんです。1月の9日に始めてそこで止めてるんですけども。ひらめいたんですね。ツイッターで今のこの状況をとにかく思うがままに、そのままに皆さんに伝えることができないだろうか。そういうところから始まっていったんですけども。誰が読んでくれるっていうそういう意識もまったくなかったので、窓を開けて夜空に叫ぶようなそんな感覚でしたね。どちらかというと。結果的にその後2ヶ月3ヶ月という風にツイッターで詩を呟き続けられたということは、ツイッターで自分の思いであるとか、悲しみとか怒りみたいな感情・思いを表現することができる・できたという実感があったんですかね?実感がもの凄くあったんです。竹田さんがおっしゃったように140字の世界というのが、これがいわゆる定型の世界っていうか、140を超えたら届かないんですよね。僕の頭の中にあったのは、小さな箱の中に今のこの福島の現状をメッセージとして盛り込んでは誰かに投げて、そしてまた違う箱に盛り込んでは投げてっていうそういう印象だったんですけども。私に必要だったのは言葉とかメッセージよりも小さな箱だったんですね。その箱があってその箱に盛り込むという、メッセージを盛り込むということができたのも形があってだったんですね。だから日本語って不思議なんですけど、短歌とか俳句のそういう伝統形式がずーっと続いてるんですけど、定型と日本語ってのは基本的に兄弟のように結びついているところがあるんだなって改めて思いましたね。もう1つ、和合さんのご活動で印象にあるのは日本中のいろんなとこ行かれてご自分の詩を朗読されているんですけど、朗読することで何か別な意味とか引用が詩に与えられるっていうことなんでしょうか?朗読するというのが僕は20年間ずっと続けてきて詩を書き始めたのと朗読というのがほとんど一緒なんですけど、五感を使うんですよね朗読って。そう言いながらこれから朗読するのは非常にプレッシャーなんですけど(笑)。皆さんの前で、お客さんの前で呼吸を感じながら朗読するというのが、それが自然と頭の中に言葉が降ってくる瞬間と似てるんですよね。音が最初なんですよ。言葉が浮かんでくる時音が最初でその後言葉が見えてくるような。そんな風に自分が朗読をしていきながら変わっていったんですよね。その和合さんの思いが凝縮されたものが詰まったこの箱ですよね。その「詩の礫」の中からここで朗読を是非お願いしたいと思います。震災に遭いました。避難所にいましたが、落ち着いたので仕事をするために戻りました。皆さんに色々とご心配をおかけしました。励ましをありがとうございました。本日で被災6日目になります。物の見方や考え方が変わりました。行きつくところは涙しかありません。私は作品を修羅のように書きたいと思います。放射能が降っています。静かな夜です。ここまで私達を傷めつける意味はあるのでしょうか。ものみなすべての事象における意味などは。それらの事後に生ずるものなのでしょう。ならば事後そのものの意味とは何か。そこに意味はあるのか。この震災は何を私達に教えたいのか。教えたいものなぞないのなら、尚更何を信じればよいのか。放射能が降っています。静かな、静かな夜です。屋外から戻ったら髪と手と顔を洗いなさいと教えられました。私達にはそれを洗う水などないのです。私が暮らした南相馬市に物資が届いていないそうです。南相馬市に入りたくないという理由だそうです。南相馬市を救ってください。あなたにとって故郷とはどのようなものですか。私は故郷を捨てません。故郷は私のすべてです。今ですね、2011年3月16日の4時23分から4時44分までのツイッター、呟きを続けて朗読していただいたんですけれども。やはりその文字制限の中でいろんなものがそぎ落とされて。だからこそ響いてくるというのもあるんですかね。続く。
2011/11/03
コメント(0)
-
10/28にNHK-FMで放送された「とことんNo.2を考えてみたら?」を文字起こししてみた。2/2
続き。1972年4月22、29日。この2週間ナンバー2だった“ロッキン・ロビン”。この曲はボビー・デイというシンガーが1950年代、1958年にヒットさせた曲のカバーなんですが、このボビー・デイ・バージョンも最高2位だったんです。だからオリジナルもカバーもどっちも2位。ちょっと珍しい。もう1曲は1982年。あのポール・マッカートニーとの世紀のデュエット“ザ・ガール・イズ・マイン”。この曲が収められているアルバム「スリラー」はウルトラマンモスヒットですよね。もう1億超えるわけですから凄いヒットです。マイケル・ジャクソンがキング・オブ・ポップと言われるようになったわけですが。このポール・マッカートニーとは1983年にも“セイ・セイ・セイ”で共演して、こっちはナンバー1を独走しました。ところで“ロッキン・ロビン”のナンバー1を阻止したのはロバータ・フラックの“ザ・ファースト・タイム・エヴァー・アイ・ソー・ユア・フェース”(邦題:愛は面影の中に)。そして世紀のデュエット“ザ・ガール・イズ・マイン”のナンバー1を阻止したのはホール&オーツ“マンイーター”、そしてメン・アット・ワークの“ダウン・アンダー”。それにしてもポール・マッカートニーと共演してナンバー1を取れなかったってのはびっくりしましたよ。あの頃は。ではキング・オブ・ポップ、マイケル・ジャクソンのナンバー2ソング。2曲続きます。 “ロッキン・ロビン”、“ザ・ガール・イズ・マイン”。06 MICHAEL JACKSON // ROCKIN’ ROBIN07 MICHAEL JACKSON & PAUL McCARTNEY // THE GIRL IS MINE「とことんNo.2を考えてみたら?」。2曲続きましたね。マイケル・ジャクソンで“ロッキン・ロビン”、そしてポール・マッカートニーとの共演“ザ・ガール・イズ・マイン”。さてそのポール・マッカートニーなんですが、ビートルズ解散後も数々のヒットを量産するギネスシンガー。意外にもポール・マッカートニーのナンバー2はわずかに“ザ・ガール・イズ・マイン”を除くと1曲のみなんですよ。ポール・マッカートニーはナンバー2少ないですね。やっぱついてる人ってことが言えるかもわかんないですよ。1973年に007シリーズの「死ぬのは奴らだ」の主題歌として発表した“リヴ・アンド・レット・ダイ”(邦題:007/死ぬのは奴らだ)。この曲はビートルズ時代のプロデューサー、ジョージ・マーティンが必死で力を入れたアレンジで。すっごい出来だったでしょ。でもこれがナンバー2なんですよ。そしてポール・マッカートニーと来ればやはりジョン・レノンですが、1980年12月8日マイク・チャップマンの凶弾に倒れて帰らぬ人となった後、生前最後のアルバムとなった「ダブル・ファンタジー」から2枚目のシングルとしてカットされた“ウーマン”。これ残念ながら最高位2位で終わりました。そしてさらにこのジョンの死を追悼するために書かれたジョージ・ハリスンの“オール・ゾーズ・イヤーズ・アゴー”(邦題:過ぎ去りし日々)。この曲も最高位2位でした。ちなみにリンゴ・スターは最高位2位という曲はありません。ビートルズの元メンバーの揃い踏みは第2位に関してはできません。ところでポール・マッカートニーの“リヴ・アンド・レット・ダイ”を阻んだのは3曲あります。モーリン・マクガヴァンの“ザ・モーニング・アフター”。これは映画「ポセイドン・アドヴェンチャー」の主題歌。覚えていますかねぇ?そしてダイアナ・ロスの“タッチ・ミー・イン・ザ・モーニング”。これは名曲。そしてストーリーズの“ブラザー・ルイ”という。「ルイ、ルイ、ルイ、ルイ♪」という。簡単な曲でちょっと暗い内容。人種を超えた物語。これが1位ですから。それに阻まれちゃったんですね。さてジョン・レノンの“ウーマン”を阻んだのはREOスピードワゴンの“キープ・オン・ラヴィング・ユー”。そしてブロンディ“ラプチュア”。この2曲。当時強力でした。そしてジョージ・ハリスンの“オール・ゾーズ・イヤーズ・アゴー”のナンバー1を阻んだのは9週間もナンバー1を続けていたキム・カーンズの“ベティ・デイヴィス・アイズ”(邦題:ベティ・デイビスの瞳)。これもしょうがないですね。ということでポール・マッカートニー&ウィングスの“リヴ・アンド・レット・ダイ”、ジョン・レノンの“ウーマン”、そしてジョージ・ハリスンの“オール・ゾーズ・イヤーズ・アゴー”(邦題:過ぎ去りし日々)。3曲。08 PAUL McCARTNEY & WINGS // LIVE AND LET DIE09 JOHN LENNON // WOMAN10 GEORGE HARRISON // ALL THOSE YEARS AGO小林克也がお送りしています「とことんNo.2を考えてみたら?」。ビートルズ関係が3曲続きました。ポール・マッカートニー&ウィングスの“リヴ・アンド・レット・ダイ”、ジョン・レノンの“ウーマン”、ジョージ・ハリスンの“オール・ゾーズ・イヤーズ・アゴー”。最後にこんな話なんですが、アメリカの映画協会ってのがあって、アメリカ映画が100周年を迎えた1998年から映画のランキングをアカデミーの会員が投票するんですけど、2007年にアメリカ映画ベスト100ってのを投票で選んで発表しているんですが。第2位は…音楽の第2位やってるから映画の第2位は「ゴッドファーザー」です。第1位は「市民ケーン」。これが1位ですよ。「ゴッドファーザー」は主演のマーロン・ブランドがマフィアのドンをやりましたね。彼のセリフで「I’m gonna …」「絶対断れないような申し出をするから」っていう。これがなんと名セリフ100の第2位なんです。これなんか、あんまり面白くないと思うでしょ。だけどマーロン・ブランドが言ったから面白いんですよね。ちなみにセリフの第1位は「風と共に去りぬ」でクラーク・ゲーブルが言った「…」っていう。やっぱクラーク・ゲーブルが男らしく「勝手にしろよそんなのは。俺には関係ないことだ」っていう。そういうセリフが第1位で。第2位がマーロン・ブランドだって。だけどあの人は結構凝っちゃって、ちょっと整形したりセリフを言う時は口の中へティッシュを両方に入れてるんですよ。それであれを言ったから。そういうような総合的なところがあるんだと思います。というわけでゴッドファーザーが公開された頃の第2位ちょっと聴いてみる? ビル・ウィザースです。“ユーズ・ミー”。11 BILL WITHERS // USE ME小林克也がお送りしてきました「とことんNo.2を考えてみたら?」。今日お届けした曲はクリーデンス・クリアウォーター・リヴァイヴァルの“プラウド・メアリー”、同じくクリーデンスの“グリーン・リヴァー”、同じくクリーデンス、あるいはCCR。呼び方いろいろありますが“トラヴェリン・バンド”。そしてティナ・ターナー“ウィー・ドント・ニード・アナザー・ヒーロー”、同じくティナ・ターナー“ティピカル・メイル”。マイケル・ジャクソン“ロッキン・ロビン”、マイケル・ジャクソン&ポール・マッカートニー“ザ・ガール・イズ・マイン”。そしてポール・マッカートニー&ウィングス“リヴ・アンド・レット・ダイ”、“死ぬのは奴らだ”。ジョン・レノン“ウーマン”、そしてジョージ・ハリスン“オール・ゾーズ・イヤーズ・アゴー”、“過ぎ去りし日々”。そしてビル・ウィザースの“ユーズ・ミー”。どうですか。この番組そろそろ定着し始めたかな。僕の中ではもう定着し始めましたよ。皆さん良かったら間奏、意見。リクエスト。リクエストは全米ナンバー2ソングのみ受け付け…(略)「とことんNo.2をかんがえてみたら?」。お相手は小林克也でした。
2011/10/28
コメント(2)
-
10/28にNHK-FMで放送された「とことんNo.2を考えてみたら?」を文字起こししてみた。1/2
こんばんは。小林克也です。今宵いかがお過ごしでしょうか。「とことんNo.2を考えてみたら?」。もう何回か放送しておりますけども、皆さんの間で評判はどうでしょうか。世間的には大ヒットしたんだけど第2位だったんだよっていう話よくあるんですけど、その第2位が意外に凄かったりするわけですよね。ただの曲だった場合もあるわけですが、ドラマがあるわけです。全米で1960年から今までの2位の曲を数えるとおよそ450曲あります。そんな中から選りすぐった世紀のナンバー2ソングを楽曲のエピソードを交えながら、さらに世界のナンバー2情報、これも交えてお送りしていきます。小林克也がお届けする「とことんNo.2を考えてみたら?」。この時間最後までどうぞ。さて「とことんNo.2を考えてみたら?」。クリーデンス・クリアウォーター・リヴァイヴァル。長いんであの頃はみんなCCRと言いましたね。活動期間中全米のシングルチャートで数々のトップ10ヒットを出したアメリカのバンドです。実は彼ら、とても不運なナンバー2の記録保持者なんです。バンドとしてもちょっと運が悪いんですよこの人たちは。最後はレコード会社と揉めたりするんですよね。で、解散しちゃったりするという。まずナンバー2の記録なんですけども、全米ナンバー1を獲得できなかったアーティストの中で最多の5曲の全米ナンバー2を持っている。ナンバー2が5曲あるわけです。その悲劇のスタートは1969年3月8日からの3週間、2位につけながらナンバー1に上りきれなかった“プラウド・メアリー”。いい曲でしょ。この曲のナンバー1を阻止したのはスライ&ザ・ファミリー・ストーン“エブリデイ・ピープル”。それからトミー・ロウ“デイジー”。どちらも4週連続でナンバー1を獲得する大ヒットでした。ちょっとCCR運が悪かった。続いては1969年の6月の終わり、“バッド・ムーン・ライジング”。勢いよく2位まで上ったんですが、この時ナンバー1だったのはヘンリー・マンシーニの“シーム・フロム・ロミオ&ジュリエット”。「ロミオとジュリエット」の映画のあの曲ですから。これはどうでしょう。2度目の挑戦も2位で終わります。続いて1969年の9月の終わり、“グリーン・リヴァー”。これもまたもやナンバー1にリーチをかけます。しかしこの時ナンバー1だったのはアーチーズの“シュガー・シュガー”。バブルガム。やっぱ10代のお子様ミュージックと言われたもんですよね。“シュガー・シュガー”なんて。これに阻まれました。このアーチーズってのは実際にはメンバーがいなくてスタジオのミュージシャンばっかりのグループだったんですが、これに負けちゃった。それから3度連続でナンバー1を取り損ねたジョン・フォガティ率いるCCR。今度こそと1970年、超強力な“トラヴェリン・バンド”。これを持ってきました。ロックンロールです。またまた勢いよくヒットチャートを駆け上がって3月7日ナンバー1にリーチをかけるんですが、しかし相手が悪かった。サイモン&ガーファンクル。まあサイモン&ガーファンクルはわかりますが、“ブリッジ・オーヴァー・トラブルド・ウォーター。”“明日に架ける橋”。これはもう不動のナンバー1ですから、ちょっと本当運が悪かったですね。翌週の14日もナンバー2を堅持するんですが、そこまで。4度目の挑戦も失敗です。そして結果的に最後の挑戦となったのは“ルッキン・アウト・マイ・バック・ドア”。この曲はちょっとカントリーっぽい。彼らはカントリーっぽいものもやるスタイルなんですけど、何しろマール・ハガードというカントリー・シンガーを一番尊敬しているジョン・フォガティですから、本来のスタイルだったかもしれませんけども。10月3日またもやナンバー1にリーチをかけます。この当時ソロになったばっかりで話題満載のダイアナ・ロスの“エイント・ノー・マウンテン・ハイ・イナフ”。これが3週目のナンバー1に居座っていて。ナンバー1になれなかった。結局5度の挑戦も儚く破れ去ってしまったというわけです。ということで悲しきクリーデンス、ナンバー2物語ここまでですけども。それでは“プラウド・メアリー”、“グリーン・リヴァー”、そして“トラヴェリン・バンド”。3曲続きます。01 CREEDENCE CLEAWATER REVIVAL // PROUD MARY02 CREEDENCE CLEAWATER REVIVAL // GREEN RIVER03 CREEDENCE CLEAWATER REVIVAL // TRAVELLIN’ BANDクリーデンス・クリアウォーター・リヴァイヴァル。“プラウド・メアリー”、“グリーン・リヴァー”、そして“トラヴェリン・バンド”。アメリカン・ロックの歴史を作った人たちですね。小林克也がお送りしている「とことんNo.2を考えてみたら?」。さて先ほどのCCR、クリーデンス・クリアウォーター・リヴァイヴァルの“プラウド・メアリー”をカバーしてヒットさせたアイク&ティナ・ターナー。1980年代ティナ・ターナーがソロになって大きな成功を手にします。夫であるアイク。公私ともに迷惑夫だったわけですね。でも有名にしてくれたのは夫で何とも言えない感じが残りますけども。しかしこの夫から離れてティナの風向きがガラッと変わるわけです。彼女も80年代ヒットチャートの常連として大活躍するんですが、そんなティナもナンバー2ソングが2曲あります。1つは1985年の映画「マッドマックス/サンダードーム」の主題歌となった“ウィー・ドント・ニード・アナザー・ヒーロー”(邦題:孤独のヒーロー)。1985年9月14日2位まで上ったんですがこの時ナンバー1だったのはやはり映画の主題歌。ジョン・パーの“セント・エルモス・ファイアー”。こっちの方が強かったわけです。そしてもう1曲1986年の10月18日から3週間連続で2位だった“ティピカル・メイル”。この曲のナンバー1を阻止したのはジャネット・ジャクソンの“ウェン・アイ・シンク・オブ・ユー”(邦題:あなたを想うとき)、そしてもう1曲シンディ・ローパーの“トゥルー・カラーズ”。この2人に阻止されてしまいました。これちょっと仕方なかったかなという感じですが。それではティナ・ターナーで“ウィー・ドント・ニード・アナザー・ヒーロー”、そして“ティピカル・メイル”。04 TINA TURNER // WE DON’T NEED ANOTHER HERO (THUNDERDOME)05 TINA TURNER // TYPICAL MALEお送りしたのはティナ・ターナーが2曲。“ウィー・ドント・ニード・アナザー・ヒーロー”、そして“ティピカル・メイル”。さてティナ・ターナーのナンバー1を阻止した人の1人ジャネット・ジャクソンというとマイケル・ジャクソン。お兄ちゃんです。生前ソロではマイケルは26曲トップ10ヒットを持っておりました。でも以外にもナンバー2ソングというのはマイケル、2曲あります。続く。
2011/10/28
コメント(0)
-
10/27にNHK-FMで放送された「とことんNo.2を考えてみたら?」を文字起こししてみた。
こんばんは。小林克也です。いかがお過ごしですか?「とことんNo.2を考えてみたら?」。世間的には大ヒットしたんだけどナンバー2。惜しくも1位になれなかった。そういった曲をとことんお届けしてしまおうというこの番組。全米で1960年から今まで最高位2位止まりだった曲は数えてみるとおよそ450曲あります。もちろんナンバー1は「えー、そんなのナンバー1だった?」みたいなイメージの曲があるかと思えばナンバー2が本当鮮やかに残っているっていう、ナンバー2ソングがあるわけですが。この番組ではそんな中から選りすぐった世紀のナンバー2ソングを楽曲のエピソードを交えながら、さらにナンバー2的な情報、おなじみのナンバー2情報を交えてお送りします。小林克也がお届けする「とことんNo.2を考えてみたら?」。この時間最後までお付き合いください。さて、「とことんNo.2を考えてみたら?」。1960年代最もナンバー1ソングを輩出したのはもちろんザ・ビートルズ。そんな無敵の彼らに負けず劣らずナンバー1ヒットを量産していたのはシュープリームスです。1964年から69年まで6年間で12曲ものナンバー1を記録しています。となると当然このシュープリームスの影で泣いたアーティストがいるわけですが、ちょっと調べました。1964年10月から4週間シュープリームスの“ベイビー・ラヴ”はナンバー1になりましたが、その中で11月7日、2週目のナンバー1の時にJ・フランク・ウィルソン&キャバリアーズの“ラスト・キッス”。これがナンバー1になれなかった。翌1965年の3月の終わり~4月の初めの2週間ナンバー1だったシュープリームスの“ストップ・イン・ザ・ネーム・オブ・ラヴ”。この曲はですね、ハーマンズ・ハーミッツの“キャント・ユー・ヒア・マイ・ハートビート”(邦題:ハートがドキドキ)、これをナンバー2に抑え込んじゃった。それから同じ年の6月の2週間最高2位だったサム・ザ・シャム&ザ・ファラオスの“ウーリー・ブリー”は1週目をビーチ・ボーイズの“ヘルプ・ミー・ロンダ”、2週目をシュープリームスの“バック・イン・マイ・アームズ・アゲイン”(邦題:涙のお願い)にナンバー1を阻止されています。まだまだあるんですが、同じ年、11月20日、シュープリームスの“ア・ヒア・ア・シンフォニー”(邦題:ひとりぼっちのシンフォニー)にナンバー1を阻まれたのはレン・バリーの“1-2-3”。これもナンバー1になれなかった。66年9月はシュープリームスの“ユー・キャント・ハリー・ラヴ”(邦題:恋はあせらず)。これが強力でしたが、ライバルのビートルズの“イエロー・サブマリン”のナンバー1を阻止しています。そして67年、ダイアナ・ロス&シュープリームスに名義を変更して最初のナンバー1だった“ザ・ハプニング”(邦題:恋にご用心)はアーサー・コンリーの“スウィート・ソウル・ミュージック”(邦題:レッツ・ゴー・ソウル)のナンバー1を阻んでいます。以上シュープリームスがナンバー1を邪魔してしまった曲の数々ですが、ではここでハーマンズ・ハーミッツの“キャント・ユー・ヒア・マイ・ハートビート”、レン・バリーの“1-2-3”、それからアーサー・コンリーの“スウィート・ソウル・ミュージック”。続けてどうぞ。01. Can't You Hear My Heartbeat / HERMAN'S HERMITS02. 1-2-3 / LEN BARRY03. Sweet Soul Music / ARTHUR CONLEYいかがですか?ハーマンズ・ハーミッツの“キャント・ユー・ヒア・マイ・ハートビート”、レン・バリーの“1-2-3”、そしてアーサー・コンリーの“スウィート・ソウル・ミュージック”。若い方も「あ、聴いたことがあるなあ」っていう有名な曲ですが。小林克也がお送りしている「とことんNo.2を考えてみたら?」。話はガラッと変わってカバー曲がオリジナル以上のヒットとなったものの、惜しくもナンバー1にはなれなかった作品からお届けしましょう。まずは1980年。テリー・デサリオ・ウィズ・KCがヒットさせた“イエス・アイム・レディ”。この曲のオリジナルは1965年のバーバラ・メイソン。全米チャート最高位は5位でした。それを上回ったのはテリー・デサリオ・ウィズ・KCのバージョンです。でもクイーンの“クレイジー・リトル・シンク・コールド・ラヴ”(邦題:愛という名の欲望)にはかなわなかった。続いて1980年、スピナーズがヒットさせた“ワーキング・マイ・ウェイ・バック・トゥ・ユー~フォーギヴ・ミー・ガール”(邦題:ワーキング)。これメドレーなんですが、最初のヒットはフォー・シーズンズが1966年全米最高9位まで上昇するヒットとしたんですが、14年後スピナーズのバージョンはナンバー2。ちなみにメドレーになっている“フォーギヴ・ミー・ガール”はこの曲のプロデューサー、マイケル・ゼイガーの曲であります。こちら特にヒットした曲じゃないんです。そしてこのスピナーズのナンバー1を阻んだのは唯一のナンバー1だったピンク・フロイドの“アナザー・ブリック・イン・ザ・ウォール(パート2)”です。さらになぜかこの1980年もう1曲あります。レオ・セイヤーがヒットさせた“モア・ザン・アイ・キャン・セイ”(邦題:星影のバラード)。この曲のオリジナルはバディ・ホリーを失ったクリケッツ。グループとして1960年に発表してその後1961年にボビー・ヴィーがカバーしたんですが、これもヒットします。それから19年後の1980年、レオ・セイヤーがカバーして見事大ヒットになったというわけです。でも大ヒットだけど第2位で終わった。そしてこの曲のナンバー1を邪魔したのはケニー・ロジャースの“レイディー”、ジョン・レノンの“スターティング・オーヴァー”だった。ではここでこの曲たちを紹介しましょう。テリー・デサリオ・ウィズ・KCで“イエス・アイム・レディ”、スピナーズで“ワーキング・マイ・ウェイ・バック・トゥ・ユー~フォーギヴ・ミー・ガール”、そしてレオ・セイヤーで“モア・ザン・アイ・キャン・セイ”。04. Yes, I'm Ready / TERRI DE SARIO WITH K.C05. Working My Way Back To You-Forgive Me Girl / THE SPINNERS06. More Than I Can Say / LEO SAYER「とことんNo.2を考えてみたら?」。お送りしたのはテリー・デサリオ・ウィズ・KCで“イエス・アイム・レディ”、スピナーズで“ワーキング・マイ・ウェイ・バック・トゥ・ユー~フォーギヴ・ミー・ガール”、そしてレオ・セイヤーで“モア・ザン・アイ・キャン・セイ”。さて引き続いてオリジナルを越える大ヒットとなりながら第2位で終わった曲たちを続けてお送りしましょう。1984年、シェレールがクラブチャートでヒットさせた“アイ・ディドント・ミーン・トゥ・ターン・ユー・オン”。この曲はジャム&ルイスが書き下ろしたものなんですが、翌年、1985年ロバート・パーマーが自分のアルバム「リップタイド」で取り上げて、1986年シングル・カットされて2位になりました。これもオリジナルをはるかにしのぐ大ヒットになります。この曲のナンバー1を阻んだのはボストンの“アマンダ”だったわけですね。で、もう1曲。1988年、ガールズ・バンドとしてヒットが多いあのバングルスの“ア・ヘイジー・シェイド・オブ・ウィンター”。“冬の散歩道”。これはあのサイモン&ガーファンクルが1966年に発表して全米チャート最高13位までだったんですね。あんまりヒットしなかったですね。でもカバーしたバングルスの方が上回るヒットになりました。尚このバングルスの方の“ア・ヘイジー・シェイド・オブ・ウィンター”のナンバー1を阻んだのはティファニーの“クッダヴ・ビーン”(邦題:思い出に抱かれて)でした。ではなぜか80年代に集中したオリジナルを上回るカバー・ヒットによる第2位シリーズ。まずはロバート・パーマーで“アイ・ディドント・ミーン・トゥ・ターン・ユー・オン”、そしてバングルスで“ア・ヘイジー・シェイド・オブ・ウィンター”。07. I Didn't Mean To Turn You On / ROBERT PALMER08. A Hazy Shade Of Winter / THE BANGLES「とことんNo.2を考えてみたら?」。ここでお届けした2曲、ロバート・パーマーで“アイ・ディドント・ミーン・トゥ・ターン・ユー・オン”、そしてバングルスで“ア・ヘイジー・シェイド・オブ・ウィンター”。2曲。さ、バングルスというとプリンスが提供した“マニック・マンデー”でヒットして一躍脚光を浴びたわけですが、そのプリンスもヒットチャートの常連でしたね。特に80年代はヒットが多かった。自分の曲、提供作品、カバー作品など80年代、90年代、常に彼の作品がチャートの上位を賑わせたんですが。ここではそんなプリンスの作品からナンバー2をお送りします。まずは1984年、映画でも話題になった“パープル・レイン”。1984年11月の17、24日の2週間ナンバー2だったんですが、この曲のナンバー1を阻んだのはなんとワム!の“ウェイク・ミー・アップ・ビフォー・ユー・ゴー・ゴー”(邦題:ウキウキ・ウェイク・ミー・アップ)。続いて1985年のアルバム「アラウンド・ザ・ワールド・イン・ア・デイ」に入っていた“ラズベリー・ベレー”。1985年、1週間デュラン・デュランの“ア・ビュー・トゥ・ア・キル”(邦題:007/美しき獲物たち)これは「007」の主題歌に使われた曲ですが、これが1位。そして“ラズベリー”は2位まで付けましたがそのまま下がっています。そしてもう1曲あります。「サイン・オブ・ザ・タイムス」に入っていた“ユー・ガット・ザ・ルック”。この曲ではシーナ・イーストンがゲスト・ヴォーカルとして参加しています。この曲のナンバー1を阻止したのはリサリサ&カルト・ジャムの“ロスト・イン・エモーション”。そういえばバングルズのスザンナ・ホフスとシーナ・イーストン、どことなく似ていますよね。プリンスの好みが見えてきますよね。その頃はいろいろ噂されたりしたもんですよ。まあそういう話はほかの番組で…。ではプリンスのナンバー2ソングス。続けます。“パープル・レイン”、そして“ユー・ガット・ザ・ルック”。09. Purple Rain / PRINCE & THE REVOLUTION10. U Got The Look / PRINCE FEAT. SHEENA EASTONNHK-FM「とことんNo.2を考えてみたら?」。さて最後にこんな話題なんですが。発明王というとトーマス・アルヴァ・エジソン。アメリカの有名な、ミドルネーム知っていますか? トーマス・アルヴァ・エジソンですね。彼が発明したものは何かと聞かれたら電球と答える方が少なくないと思いますけど、実は白熱電球を発明して最初の特許を取ったのはエジソンじゃないんですね。ジョゼフ・スワンというイングランドの科学者です。ではエジソンは何をやったのかというと、電球のフィラメントに京都の竹を使って…京都産の竹を使って電気が点灯している時間を圧倒的に伸ばしたんです。つまりエジソンは白熱電球の発明者ではなくて実用化した人物。電球については2番手だった、エジソンは。ということで。まぁそれにしてもエジソンが偉大な発明家であることは変わらないわけですが。彼が生涯で取った特許の数はなんと1300以上だったそうです。発明のために昼も夜も関係なく時間を忘れて研究に没頭したエジソンはやっぱり発明王。ではエジソンに相応しいかどうか。このナンバー2ソング、ボブ・ディラン“ライク・ア・ローリング・ストーン”。11. Like A Rolling Stone / BOB DYLANお送りしたのはボブ・ディランの“ライク・ア・ローリング・ストーン”。ビートルズの“ヘルプ!”に阻まれていますが。ロックの雑誌「ローリング・ストーン」がいつかやった過去の名曲、どれが名曲だと思うかという100曲を選んだナンバー1に輝いてんですよこれは。でもチャートの上では2位に終わった。小林克也がお送りして参りました「とことんNo.2を考えてみたら?」。今日お送りしたのは…(略)さてこの番組は皆さんからの…(略)「とことんNo.2を考えてみたら?」。お相手は小林克也でした。
2011/10/28
コメント(0)
-
10/10にNHK-FMで放送した「今日は一日プログレ三昧・再び」 まとめ 2/2
・・・続きその23 ●ピーター・ハミルからメッセージ40. Pilgrims / VAN DER GRAAF GENERATOR / STILL LIFE (76) 英 http://www.vandergraafgenerator.co.uk/41. Register Magister / FINCH / GLORY OF THE INNER FORCE (75) オランダその24 ●私とプログレ:貴志祐介さんその25 42. Watcher Of The Skies / GENESIS / FOXTROT (72) 英 http://www.genesis-music.com/その26 ●画家の諏訪敦さんからリクエスト http://members.jcom.home.ne.jp/atsushisuwa/43. YYZ [LIVE] / RUSH /LIVE IN RIO (2003) カナダ http://www.rush.com/rush/44. Casablanca Moon / SLAPP HAPPY / ACNALBASAC NOOM (73) 英&独45. Season's Overture / HOSTSONATEN / SUMMEREVE (2011) 伊その27 ●デイヴ・シンクレアさん登場、様々語る46. Wanderlust / DAVE SINCLAIR / MOON OVER MAN (93) 英 http://davesin.net/ (日本語) http://www.dave-sinclair.co.uk/ 47. Island / DAVE SINCLAIR / STREAM (2011) 英その28 ●デイヴ・シンクレア・バンドのライブ演奏山本精一さん公式 http://www.japanimprov.com/syamamoto/syamamotoj/ 上野洋子さん公式 http://www.uenoyoko.com/ クラムボン公式サイト内のミトさんのコーナー http://www.clammbon.com/mito/ 富家大器さん公式(デザイナーとして) http://tomiiedesign.jp/ その29 48. Ce Un Paese Al Mondo(邦題:ある国) / MAXOPHONE / MAXOPHONE (75) 伊 http://www.maxophone.it/その30 ●デイヴ・シンクレア・バンドの日本人4人を加えてスタジオでトークその31 ●UKのエディ・ジョブソンからメッセージ49. In The Dead Of Night / U.K. / U.K . (78) 英50. A Kid Called Panic / MOON SAFARI / LOVER’S END (2010) スウェーデン http://www.moonsafari.se/51. To France / MIKE OLDFIELD / DISCOVERY (84) 英 http://mikeoldfieldofficial.com/その32 ●作曲家の千住明さんからリクエスト http://www.akirasenju.com/ 52. A Pauper In Paradise: 2nd Movement / GINO VANNELLI / A PAUPER IN PRADISE (77) カナダ http://www.ginov.com/ 53. A Pauper In Paradise: 3rd Movement / GINO VANNELLI54. Uffe's Woodshop / TYONDAI BRAXTON / CENTRAL MARKET (2009) 米55. Birdman / McDONALD & GILES / McDONALD & GILES (70) 英その33 ●私とプログレ:スターレス高嶋さん(の暴走) http://www.toho-ent.co.jp/actor/show_profile.php?id=1308(東宝芸能オフィシャル)その34 56. Starless / KING CRIMSON / RED (74) 英 http://www.dgmlive.com/57. And You and I(邦題:同志) / YES / CLOSE TO THE EDGE (72) 英●エンディング【紹介された作品を購入できる可能性の高い通販サイト】アマゾン カケハシ・レコード サード・イアー 新宿レコード ディスクユニオン ワールドディスク CRAZY WORLD RECORDS(アナログのみ) GARDEN SHED Seven Beat Records Waterloo Records
2011/10/24
コメント(0)
-
10/10にNHK-FMで放送した「今日は一日プログレ三昧・再び」 まとめ1/2
【公式サイト】http://www.nhk.or.jp/zanmai/past/20111010progressive/index.html【目次】※曲名/バンド名/収録アルバム(発表年)国※公式サイトはわかる範囲内ですその1 ●オープニング01. Atom Heart Mother(邦題:原子心母) / PINK FLOYD / ATOM HEART MOTHER (70) 英 http://www.pinkfloyd.com/その2 ●岩本晃市郎さん登場02. Jerusalem(邦題:聖地エルサレム) / EMERSON, LAKE & PALMER / BRAIN SALAD SURGERY (73) 英 http://www.emersonlakepalmer.com/その3 ●ラジオ教養講座「プログレッシヴ・ロックの傾向と発展」(講師:岩本晃市郎さん)03. 5% For Nothing(邦題:無益の5%) / YES / FRAGILE (71) 英 http://www.yesworld.com/04. Time / PINK FLOYD / DARK SIDE OF THE MOON (73) 英その4 ●ラジオ教養講座「プログレッシヴ・ロックの傾向と発展」(講師:岩本晃市郎さん)の続き05. Catharine Of Aragon(邦題:アラゴンのキャサリン) / RICK WAKEMAN / The Six Wives of Henry VIII (73) 英 http://www.rwcc.com/06. The Song Remains the Same(邦題:永遠の詩) / LED ZEPPELIN / Houses of the Holy (73) 英 http://www.ledzeppelin.com/07. Love in Song(邦題:歌に愛をこめて) / WINGS / VENUS AND MARS (75) 英 http://www.paulmccartney.com/08. Funeral For A Friend(邦題:葬送) / ELTON JOHN / GOODBYE YELLOW BRICK ROAD (73) 英 http://web.eltonjohn.com/index.jspその5 ●ジョン・ウェットンからメッセージ09. Daylight / ASIA ※83年発表のシングル”DON’T CRY”のB面 英 http://originalasia.com/10. Rhayader(邦題:醜い画家ラヤダー) / CAMEL / THE SNOW GOOSE (75) 英 http://www.camelproductions.com/11. Question(邦題:クエスチョン ) / MOODY BLUES / A QUESTION OF BALANCE (70) 英 http://www.moodybluestoday.com/その6 12. 1°tempo:Allegro / NEW TROLLS / CONCERTO GROSSO PAR 1 (71) 伊 http://www.newtrolls.it/13. Gravita 9,81(邦題:重力) / ARTI & MESTIERI / TILT (74) 伊 http://www.artiemestieri.it/14. Northern Lights(邦題:北の輝き) / RENAISSANCE / A SONG FOR ALL SEASONS (78) 英 http://renaissancetouring.com/その7 ●私とプログレ:小林明子さん http://www.office-seto.com/akikoその8 ●プログレ諸国漫遊・再び15. デブカ / SHESHET / SHESHET (77) イスラエルその9 ●プログレ諸国漫遊・再びの続き16. AEri-Tobbi / HINN ISLENSKI PURSAFLOKKUR / PURSABIT (79) アイスランド17. System Manipulation / DISCUS / TOT LICHT (2003) インドネシアその10 18. Fanfare - All White / SOFT MACHINE / SIX (73) 英 「Calyx」内のソフト・マシーンのコーナー http://calyx.perso.neuf.fr/softmachine/●カンサスのリチャード・ウィリアムス、フィル・イハート、ビリー・グリア、デイヴィッド・ラグスデールからメッセージ19. Paradox(邦題:逆説の真理) / KANSAS / POINT OF NO RETURN (77) 米 http://www.kansasband.com/20. Sylvia(邦題:シルヴィア) / FOCUS / FOCUS III (72) オランダ http://www.focustheband.com/その11 ●ミスターシリウスこと宮武和広さん登場宮武和広さんの傘屋「心斎橋みや竹」 http://www.kasaya.com/ (ミスター)シリウスなどの作品が買えるサイト http://www.kasaya.com/sirius.htm 21. Step Into Easter / MR.SIRIUS / BARREN DREAM (86) 日 ミスターシリウスのギタリスト・釜木茂一さん http://www5b.biglobe.ne.jp/~kamaki/top.htm22. 月の位相 パート1 / KENSO / 夢の丘 (91) 日 http://www1.u-netsurf.ne.jp/~kenso/index.htmlその12 ●俺たちが裁くプログレ裁判23. 【プログレ裁判 1】夜桜お七 / 坂本冬美 / 夜桜お七 (94) 日 http://www.fuyumi-fc.com/24. 【プログレ裁判 2】キグルミ惑星(アニメ「はなまる幼稚園」から) / 高垣彩陽 / はなまるベストアルバムCHILDHOOD MEMORIES (2010) 日 http://ameblo.jp/takagakiayahi-blog/その13 ●俺たちが裁くプログレ裁判の続き25. 【プログレ裁判 3】ポリリズム / PERFUME / GAME (2008) 日 http://www.perfume-web.jp/26. 【プログレ裁判 4】タルカス変奏曲 / KOKOO / SUPER NOVA (2000) 日 http://www.kokoo.com/27. 【プログレ裁判 5】ビッグブリッヂの死闘 / 植松伸夫(ゲーム「ファイナル・ファンタジーV」)(2004) 日その14 28. Om Mani Padme Hum(邦題:曼荼羅組曲) / MANDALABAND / MANDALABAND (75) 英 http://mandalaband.co.uk/home/その15 ●PFMのフランツ・ディ・チョッチョ、フランコ・ムッシーダ、パトリック・ジヴァスからメッセージ29. River Of Life(邦題:人生は川のようなもの) [LIVE] / PFM / COOK [DELUXE EDITION] (2010) ※最初のリリースは74年 伊 http://www.pfmpfm.it/30. Le Voleur d'Extase(邦題:恍惚の盗人) / ATOLL / L’ARAIGNEE-MAL (75) 仏その16 31. Sea Song / ROBERT WYATT / ROCK BOTTOM (74) 英32. Tenemos Roads / NATIONAL HEALTH / NATIONAL HEALTH (78) 英 「Calyx」内のナショナル・ヘルスのコーナー http://calyx.perso.neuf.fr/nathealth/index.htmlその17 ●私とプログレ:宮台真司さん http://miyadai.com/33. The Sad Skinhead(邦題:悲しきスキンヘッド) / FAUST / FAUST IV (73) 独 http://faust-pages.com/index.htmlその18 ●ミスターシリウスこと宮武和広さんが語る「今だから語ろう関西プログレ」34. Crystal Voyage [LIVE] / SIRIUS ※宮武さん持参のレア音源。80年録音 日その19 ●ミスターシリウスこと宮武和広さんが語る「今だから語ろう関西プログレ」の続き35. 少年期~時の崖 / NOVELA / 魅惑劇 (80) 日その20 ●ミスターシリウスこと宮武和広さんが語る「今だから語ろう関西プログレ」のさらに続きその21 ●ミスターシリウスこと宮武和広さんが語る「今だから語ろう関西プログレ」のさらにさらに続き36. Sons of Sand / MR.SIRIUS / THE SECRET TREASURES (2006) 日37. エピローグ / PAGEANT / 螺鈿幻想 (86) 日38. パラノイア / BLACK PAGE / OPEN THE NEXT PAGE (86) 日その22 ●ミスターシリウスこと宮武和広さんが語る「今だから語ろう関西プログレ」ラスト39. ナイルの虹 / MR.SIRIUS / DIRGE (90) 日続く・・・
2011/10/24
コメント(2)
-

10/21にNHK-FMで放送された「とことんスーパーギタリスト列伝・番外編」を文字起こししてみた 2/2
続き。「とことんスーパーギタリスト列伝」。今日はですね、私、野村義男が好き勝手に選んだ隠れたスーパーギタリスト。これ特集しておりますけれども。続いてご紹介するのはチープ・トリックでございます。チープ・トリックのリック・ニールセン。もうね、リック・ニールセンといえば凄いギターマニアでございまして、コレクターでもあるんですけど。そこでもうすでに好きね。そこでもう大好き。ギターいっぱい持ってる人大好きなんだ。それでリック・ニールセンのギター…なんて言うの? 「ライブ・アット・武道館」だったっけかな、それでやっぱ日本でもバーン!てね、世界でも火がついたんですけども。ちょうどその後に出した「ドリーム・ポリス」って名盤がございまして。そこでやっぱこう、ギター聴いてノックアウト。大ノックアウトでございましたね。そん中でも最も好きな曲をお届けしたいと。このソロはもうほんとに…なんかね、長いソロじゃないんですけど涙なくしては聴けないぐらいのすっごい素敵なソロです。聴いていただきましょう。チープ・トリックが1979年に発表したアルバム「ドリーム・ポリス」から彼らのバラードでございます、“ヴォイシス”。Cheap Trick/Voices (Dream Police / 79 / 米) ※リック・ニールセン:1946.12.22~1979年に発表したアルバム「ドリーム・ポリス」からチープ・トリックで“ヴォイシス”聴いていただきました。ちなみにですね、この「ドリーム・ポリス」というアルバムでございますがこの頃メンバーがツアー中で忙しかったためですね、プロデューサーのトム・ワーマンという方がですね、スティーヴ・ルカサーを呼んで「ちょっとレコーディング手伝ってくんない?」みたいな話で。もしかして今聴いたのルカサーのソロだった?いやいやいやいやいや。どうでしょう。もちろんリック・ニールセンも弾いてるしスティーヴ・ルカサーも参加しているというアルバムで。本当に名盤中の名盤でございます。さあ。まあそんな…いいなーリック・ニールセン。だってネック5本あったりするギター弾くんだよ!? 1人で弾けるのは1本までだって、だから。もうそういうのとか、変形ギター。とんがったギターとかね、いろんなギターとか。もちろんヴィンテージの凄いのも持ってたりなんかしますけど。元々ご実家が楽器屋さんだったりするんでそういうの手に入りやすかったりするのかな。ちょっと悔しい限りでございますけども。さ、どんどん参りたいと思います。続いてのスーパーギタリストはですね、僕もギター教えてもらったことがあるんでございますけれども、この方をご紹介したいと。ドゥービー・ブラザーズというバンドでございまして。そこの最後までいたオリジナル・メンバー。唯一のオリジナル・メンバーですね。最終的に周りのメンバーみんな変わっちゃったんですけど、最後までドゥービーに残っていたパット・シモンズというギタリストをご紹介しようかなと思ってます。これはですね、パットもそうなんだけどほかのメンバーもそうなんですけども、すーごくね、コーラスとかが凄い素敵な。歌巧いしギター巧いしっていう。そういう曲をおかけしたいと思います。1974年に発表したアルバム「ドゥービー天国」。そのタイトルないだろみたいな。そっから“ブラック・ウォーター”。Doobie Brothers/Black Water (What Were Once Voices Are Now Habits / 74 / 米) ※パット・シモンズ:1948.10.19~ドゥービー・ブラザーズで1974年のアルバム「ドゥービー天国」から“ブラック・ウォーター”でございました。さ、次のスーパーギタリストはですね、もうすっごい大好き。リック・デリンジャーでございます。リュック・便利ジャーじゃないですからね。リュックは便利ですよー。なんでも物入りますから。リック・デリンジャーの方でございますけれども。もうね、ほんとギター巧いこの人。で、なんて言うの? ロックの作るリフの大天才でございますね。どの曲選ぼうってこれこそ僕ほんとに迷っちゃうぐらいだったんですけども、やっぱりリック・デリンジャーの一番入りやすいところですかね。リックがソロになって、まあ最初マッコイズという兄弟バンドでアイドルっぽいバンドやってたんですけども、その後ソロで出して大ヒットですよ。大ヒットした曲を今からおかけしようと思います。1973年発表のソロ・デビュー・アルバムですね。「オール・アメリカン・ボーイ」。これに出てる…ジャケットで持ってる赤いギターがね、実は凄い珍しいギターで。世界で2本しかないギターっていう。まあ本人はもう持ってないんですけども。「ニューヨークで売ってるよ」なんてことを言っておりましたが。あれね、ジャケット剥がすと見えるんだよね。あの見えないパーツが。ということで聴いてみましょう。これ後にね、ジャズでもやってるんだよね。今はロックンロールでもちろんお届けしますけども。大人になってもジャズなんだ。“ロックン・ロール・フーチー・クー”。Rick Derringer/Rock and Roll, Hoochie Koo (All American Boy / 73 / 米) ※リック・デリンジャー:1947.8.5~リック・デリンジャーで1973年発表の「オール・アメリカン・ボーイ」というアルバムの中から“ロックン・ロール・フーチー・クー”をお届けしました。この後ですね、リック・デリンジャーは80年代に入りましてシンディ・ローパーのツアー・ギタリストとかやってたりとかね。のちにはソロ・アルバムとかいっぱい出してるんですけども、今度はブルースの方に行っちゃって。凄いどブルースやったなあと思ったら急にジャズやって。またブルース戻ってみたいな。自分の可能性をどんどんやっていこうっていう人なんだろうなって思って。もちろん今でもギター弾いてる。凄いかっこいいなと。僕はもうほんと。でもあのね。若い時はルックスが可愛すぎて結構みんなにかわいこちゃんギタリスト~?とかって言われてた時期もあったんですけど、やっぱこの“ロックン・ロール・フーチー・クー”で「お前かっこいいよ」に変わってきて。今は渋々ですからね。まあそんなギタリストになれることを夢見てみたいな感じでございます。そのリック・デリンジャーのギターうちにあったりする。ただこれ自慢コーナーですけどね、さっき言ったリック・ニールセンのギターもうちにある。エース・フレーリーのギターもうちにあるっていう。どんなコレクター?みたいな。ただ自慢してみました。ということでございまして(笑)。さ! もうあっという間ですね。続いて最後にお届けするスーパーギタリスト。やっぱこの人がいなかったら世界のロックは違ったんじゃないかな。もしかしたら本当違う方向に行ったんじゃないかなと思います。驚異の速弾きだったり驚異の発明家だったり。レス・ポールさん。レス・ポールおじさんいなかったらきっとみんなが持っているギターも違ってただろうし、いろんな形が違ってたんだろうなあなんてこと思うと、もうやっぱりレス・ポールおじさんいないとダメだよねと思います。ここでお届けしましょう。レス・ポール&メアリー・フォードで1951年全米ナンバーワン・ヒット・ソングでございます。“ハウ・ハイ・ザ・ムーン”。Les Paul & Mary Ford/How High The Moon (51 / 米) ※レス・ポール:1915.6.9~2009.8.12とりあえずベスト盤のジャケを載せてみました野村義男がお送りしてきました「とことんスーパーギタリスト列伝」。今日は僕が選んだ隠れたスーパーギタリストを特集してきましたがいかがだったでしょうか。もう長きにわたり毎日のようにいろんなギタリストをご紹介して参りましたけどもですね、あの…なんていうのかな、たぶん紹介したギタリスト達に同じギターを、1本しかないこのギターをみんなに弾かせると全員違う音が違うんですよ。それがエレキギターの面白さ。もちろんアコースティックギターもそうかもしれませんけど、エレキギターの“ため”だったり“哀愁”だったり“速弾き”だったり。いろんな形ありますけど、それが表現するのに凄く…技術だけじゃなくて感情とかも移入。ね、こうやって入れて。一発のチョーキングだけでみんなが違うっていう風にいくのがエレキギターの醍醐味じゃないかなって思います。もちろんいろんな色だったりいろんな形だったりっていうギターの魅力はたくさんあるんですけども。結局はやっぱり弾いて出てきた音に色気があるかとか哀愁があるかとか。そういうところをね、今度。やっぱこういうギタリストを取り上げてる番組だからこそなのかもしれませんけど、普通にラジオで流れてくるほかの音楽とかでもいろんなギターが入ってたりします。もちろん日本の音楽でもね。その辺もそういう風な気持ちで聴くと、みーんなの世界観が変わってくるんじゃないかななんて思います。僕今回やってて本当いっぱい勉強になったし凄い楽しかったんでございます。またぜひやりたいななんて思ってます。「とことんスーパーギタリスト列伝」。この時間のお相手は私、野村義男でございました。それではまたお会いしましょう。さようなり~。おしまい。
2011/10/22
コメント(0)
-

10/21にNHK-FMで放送された「とことんスーパーギタリスト列伝・番外編」を文字起こししてみた 1/2
ギタリストの野村義男です。「とことんスーパーギタリスト列伝」と題してお送りしてきましたこの番組ですが、残念ながら今日が最終日となってしまいました。今日はですね、私、野村義男が好き勝手に選んだ隠れたスーパーギタリスト特集ということでございまして。これまでにご紹介してきた様々なスーパーギタリストのほかに、もっと聴いてよみたいな、ぜひお届けしたいギタリストたくさんいるんで、そん中からさらにかいつまんで今日はご紹介しようかななんて思っております。ただ今日紹介するのは基本的には、ま、ジャケ買いですか。今どきないですね。僕らの若い時はジャケ買いって言ってCD屋さんもしくはレコードショップでジャケット見て「これかっちょいいだろうなー」と思って聴いたら「あれ?」みたいのがあったりなんかしたんですけども。そん中でもまず最初にお届けするのはジャケ買いで大当たりだったこのアーティストのこの曲からお届けしたいと思います。1人目はですね、レス・デューディックで“シティ・マジック”。Les Dudek/City Magic (Les Dudek / 76 / 米) ※レス・デューディック:1952.8.2~すいません・・・単独アルバムなかった・・・1976年発表のアルバム「レス・デューディック」から“シティ・マジック”。1曲目に入ってる曲でございました。ジャケ買いって先ほども言いましたけれどもジャケットがですね、レス・デューディックが黒いコートっていうのかな、なんかこういうの羽織ってて、それでギターを持ってるんですけど、ギターのネックにオウムがくっついてるっていう。なんでこの人はこうなんだろ?みたいな。そういうジャケットでちょっと不思議な感じで買ってしまったんですけども。中は爽やかでほんとにカリフォルニアを疾走するかのような。これのって車乗ってるともはや都内でもロサンゼルスみたいな気持ちになっちゃって。凄く爽やかな感じになったんで、もうその時からずーっとこれ、車の時は聴いてましたね。ほんとに。手に入れた頃はね。今でももちろんレス・デューディックはアルバム出しておりまして、最近はもうロック・ブルースみたいな感じになっちゃってて。格好も黒いコートは着てない…マントは着てないんですけども、凄くね、テキサスオヤジな格好してて。横にはなんかこんなでっかいオートバイかなんかね。派手派手しい。FIRE書いてあるみたいな。そういうのと一緒にジャケット撮ってたりなんかして。またかっこいいブルースをすごい聴かしてくれてますが。もちろん今でも凄いいいギタリストなんでぜひぜひ探して皆さんも聴いていただきたいなと思います。さ! 続きましてはですね…お届けするのはデラニー&ボニー。これギタリスト?っていう風にするとどうなのかなって思うと、ギタリスト達のためのギタリストかなあ、デラニーは。デラニーの下にいろんなギタリストが集まるんですよ。エリック・クラプトンだったりジョージ・ハリスンだったり。とにかくみんなデラニーのところに集まってアメリカン・ミュージック…その、スライドギターだったりとかそういうのをデラニー&ボニー&フレンズ、フレンズの中に入ってしまうという。で、「演奏させてよ!」みたいな…。不思議な魅力のある方の曲を聴いてみたいと思います。69年に発表されたライブ・アルバム「オン・ツアー・ウィズ・エリック・クラプトン」から“カミング・ホーム”。Delaney & Bonnie & Friends/Coming Home (On Tour With Eric Clapton / 69 / 米) ※デラニー・ブラムレット:1939.7.1~2008.12.27デラニー&ボニー&フランズで1969年に発表されたライブ・アルバム「オン・ツアー・ウィズ・エリック・クラプトン」から“カミング・ホーム”聴いていただきました。デラニーのところにみんなレコーディング来たりバンドメンバーだったりすると、最終的に楽器とか置いてくんですよ。エリック・クラプトンがアンプ置いてったり、ジョージ・ハリスンがオールローズのギターを置いてっちゃったりとか。まあデイヴ・メイスンが参加してたこともあるんですけど。デュアン・オールマンが…名手ですねスライドの。デュアン・オールマンがボトルネック置いてって、そのボトルネックが今うちにあるっていう。それがほんとにデュアンのボトルなのかっていうまあ、真偽はどうなのよ?みたいな。そういう風に言われて僕のところまでやってきたんですけどもね。そんな虎の穴とでもいいますか、デラニーところはね。そういう素晴らしいところでございますけども。さ! どんどん今日は! もうどんどん行きたいと思います。続いてのスーパーギタリストはですね、ドアーズのロビー・クリーガー。ここは凄いとこ突いてると僕は思うんですけども、やっぱドアーズというとどうしてもジム・モリスンのカラーが凄く強くてね、間奏が長かったりするんですけども。ロビーは指弾きで…ロック・バンドでは結構早めだったんじゃないかな指弾き。で、すっごい個性的なフレーズ。そんなスケール聴いたことないみたいな。ずっとギター弾かせるとね。ところがメロディは構成が凄い素晴らしいんですよ。たぶんそのメロディ構成に相当ノックアウトされたのが続いて紹介するギタリストはキッスのエース・フレーリー。これ2曲続けて聴いていただかないといけないんですけども、なぜかと言うとドアーズの曲で68年発表のアルバム「太陽を待ちながら」っていうアルバムがあるんですけど、そっからですね、“ファイブ・トゥ・ワン”って曲がありまして。そののちにキッスが1975年に…7年後ですね、発表した「地獄の接吻」。なんで全部地獄がつくんでしょうかねこの人たちは。「地獄の接吻」からですね、“シー”という曲を聴いていただきたいんですけども。これは確実にエース・フレーリーがジム・モリソン(註:ロビー・クリーガーの言い間違いと思われる)に敬意を表して、「このソロ、キッスで弾きたい」と思ったんでしょうね。間奏が…ギターソロ同じになっております。ぜひその辺も続けて楽しんでいただけたらと思いまして。2曲続けて聴いてください。Doors/Five To One (Waiting For The Sun / 68 / 米) ※ロビー・クリーガー:1946.1.8~Kiss/She (Dressed To Kill / 75 / 米) ※エース・フレーリー:1951.4.27~ドアーズで1968年のアルバム「太陽を待ちながら」から“ファイブ・トゥ・ワン”。そしてキッスの1975年のアルバム「地獄の接吻」から“シー”でございました。ちなみに今聴いた“シー”は僕がエレキで初めてコピーできた曲です。こっからスタート!野村義男って感じですけども。続く。
2011/10/22
コメント(0)
-

10/10にNHK-FMで放送した「今日は一日プログレ三昧・再び」 文字に起こしてみた。(その34)
続き。山田五郎→山森田美由紀→森岩本晃市郎→岩ミト→ミ上野洋子→上森 それから埼玉県の50歳の男性、イシワタリヒロオさん。「俳優の高島お兄さんが熱唱しているものを聴いてオリジナルを聴きたくなりました」。全員 (笑)ミ なにそれ? なにそれ?山 高嶋さんが“スターレス”の…出してんですよ。ミ 歌ってるんすか!?山 歌ってますよ。だから「スターレス高嶋」と。ミ うわーマジか…。森 ずっとBGMでかかってた、ね。山 最初かかってたやつがそうです。高嶋バージョン。森 もうひと方。17歳女性、マンハッタンさん。「プログレ三昧、今回も楽しく聴かせていただいています。父親の影響でプログレ・ファンになって早3年。有名どころは一通り聴いたつもりでしたが、番組ではまったく知らないアーティストの曲も多く、まだまだプログレ界は奥が深いんだなあと改めて実感しました。いろいろなバンドを聴きましたがやっぱり私の一番はキング・クリムゾンです。特にこの曲は絶対に自分の葬式でかけることに決めてます」。山 あ。さっきね。マクドナルド&ジャイルズを聴きながら僕と岩本さんで「葬式に何かけます?」って。そろそろそういうこと考える年ですよって話してたんですけど。ミ 墓標をロジャー・ディーンに描いてもらおうっていうって言ってるのがウケましたけどね(笑)。森 ちなみに岩本さんは「“エピタフ”かな~」なんて。岩 “エピタフ”ですね。ロジャー・ディーンに掘ってもらうというね(笑)。山 墓石はロジャー・ディーン(笑)。ミ 完全に聖地化しますね(笑)。森 ではもう1つ。これリクエスト曲は違う曲、“フラクチャー”なんですけれども、クリムゾンへのメッセージ。「この曲を聴くと大学生の頃アルバイトをしていたお店を思い出します。私はこの曲を聴くと徐々にテンションが高くなり、曲が終わった時にとても気合が入るところが大好きで、毎朝開店準備中にかけていました」。なんのお店なんでしょうね?山 “フラクチャー”かかるお店って(笑)。岩 行きたくないなああんまり。森 「同じくキング・クリムゾン好きの社員さんから『朝から“フラクチャー”はテンション下がるからやめてくれ』と言われて、逆の人もいるんだなあと感じたという思い出です」。全員 (笑)山 逆の人の方が多いかもしれない(笑)。森 千葉県34歳のフツカゾウさんからですね。ではお聴きいただきましょう。キング・クリムゾン74年のアルバム「レッド」から“スターレス”。56. Starless / KING CRIMSON森 キング・クリムゾン“スターレス”でした。さあいよいよ本日…岩 終わっちゃった(笑)。ミ (笑)森 …最後のリクエストにまいります。今日まだかかっていないあのバンドへのリクエスト、神奈川県のトゥーステップスさんから。「高校の時によく聴いたアルバムがイエスの「危機」でした。当時陸上部に入っていて、炎天下のきつい練習から家に帰ってきて疲れて横になってこのアルバムを何度も聴いているうちにうとうととまどろみ、夕方の涼しい風にふっと目が覚めた時この“同志”が鳴っていて疲れも心なしか軽くなったような。音楽に助けてもらったなという感謝の気持ちとともにある曲です」。ということで、イエス72年のアルバム「危機」から“同志”。57. And You and I(邦題:同志) / YES森 イエスの“同志”でした。午後12時15分よりお送りしてまいりました「今日は一日プログレ三昧・再び」。10時間の生放送でしたけれどもいよいよお別れの時間が近づいてきましたね。山 早かったでしょ森田さん。やっぱ10時間じゃ足りないんですよ。岩 全然足んないですよね。森 最後にもう1枚ご紹介いたしますね。「ミスターシリウス、ページェントのヴォーカルの大木理紗です。去年も今年も自分が歌っているものをこの番組で聴くことができて大変光栄なことでした」。ということで。ありがとうございます。山 ありがとうございます。森 岩本さんも長い時間ありがとうございました。岩 全然短くて。これから後半かなって今思ってたんです。山 物足りないって岩本さん。岩 物足りない。森 ここまで来るとそういう感じしますよね。岩 年に2回ぐらいやらないとダメかなという。そういう感じですね。森 上野洋子さん、素敵なライブとそのあとのお付き合いも…。上 ありがとうございます。山&森 ありがとうございました。山 もうすぐお誕生日ですからね。上 (笑)森 本当にカウントダウンですね。そしてミトさんもいかがでしたか?ミ 僕も2年連続です。楽しかったです!森 演奏もね。素晴らしい演奏を。山 スタジオにライブにと大活躍してくれてありがとうございました本当に。森 さあこの三昧シリーズまだまだ続いていくと思いますので、今後三昧シリーズで取り上げてほしいテーマなどございましたら番組ウェブサイトのメールフォームからお送りください。もちろんプログレまたやって!っていうのもね。山 もう細かくやんないと。辺境三昧とかね、カンタベリー三昧とかね(笑)。岩 読めないんじゃないかと。何て読んだらいいかわかんないバンドばっかりになっちゃう(笑)。森 今日もタイトルと、それからバンド名もね、ええ。山 大使館のご協力を得ましたから。ぜひまた来年やりたいですね。森田さんまだやり残したこといっぱいありますよ。森 本当にそうですね。私NHKで仕事をして28年、初めてのFMのディスクジョッキーがプログレで大変幸せでございました。山 もうね、いっぱいメール来てんの。2015も来てる中のね、30ぐらいが「森田さんがプログレ・ファンで嬉しいです」って。もう決定ですからこれでプログレ・ファン。森 またやらせていただければ。本当に2015通ものメール、32通ものファックス、リスナーの皆さんも本当にどうもありがとうございました。山&岩 ありがとうございました。森 「今日は一日プログレ三昧」。森田美由紀と、岩 岩本晃市郎と、上 上野洋子と、ミ ミトと、山 山田五郎でお送りいたしました。それでは皆さんおやすみなさい。良い夢を。おしまい。
2011/10/20
コメント(6)
-
10/10にNHK-FMで放送した「今日は一日プログレ三昧・再び」 文字に起こしてみた。(その33)
続き。山田五郎→山森田美由紀→森岩本晃市郎→岩ミト→ミ※発言していないが上野洋子氏も同席「今日は一日プログレ三昧・再び」をお聴きの皆さん、スターレス高嶋こと高嶋政宏です。いやー僕ね山田五郎さんとはね、いろんな番組でプログレの話させていただいたりとか、全然プログレじゃない普通の民放の番組でもですね、僕のことスターレスと読んでくれるんでね。本当ありがとうございます。もう今日はね、スタジオに行けなくてこんな悲しいことはないですよ。そしてまたこの間、UKのクラブチッタの時に声をかけてくださった岩本さん。岩本さんとね、ぜひお知り合いになりたかった。メールアドレス交換したかったんですけど今日は残念ながら無理です。僕が小学5年だったかな、6年だったかな…石田っていう同級生のお兄さんから弟である僕がいつもつるんでる奴にいろんなレコードが来るわけですね。「高嶋、うちの兄貴がこれも聴いた方がいいよって持ってきたんだ」って言ったアルバムがキング・クリムゾンの「クリムゾン・キングの宮殿」と「レッド」と、それとピンク・フロイドの「アニマルズ」だったんですよ。僕はまず「なんだこの顔!? 3人の顔がある黒っぽいジャケットは」っていうことで、まず「レッド」を聴いてしまったんですよ。この“レッド”を聴いた時のガーガガガガー(と“レッド”冒頭のリフを口ずさむ)とこれを聴いた瞬間にね自分の中で何かがね音を立てて崩れ落ちた後に何かが音を立ててね、こう隆起してきた。ドーーーー!! これが僕のね、プログレとの出会いで。その後「クリムゾン・キングの宮殿」、まあキング・クリムゾンっていうとね皆さん「クリムゾン・キングの宮殿」なんですけども、これよりも先に「レッド」を聴いてしまったためにロバート・フリップ、ジョン・ウェットン、ビル・ブラッフォード。これにデイヴィッド・クロスを加えたこれが僕の中でのキング・クリムゾンっていう。まず最初にできてしまったんですよ。結局本当に物心ついた、もう小学校6年なんていうといろんなね、いろんなことこれから覚えていく時期ですよ。その時期に最初にのめり込んでしまったのがプログレだったと。ということで僕にとってプログレっていうのは皆さんがどう言おうとこの世のメインストリームの音楽なんです。これがね、やっぱりプログレ・ファン…特にキング・クリムゾン・ファンはみんな思ってると思うんですけど、とにかくずるいわけですよ。1枚出てた元々あったやつを紙ジャケで出す。で、バージョン違いで出す。リマスターとかって出るわけじゃないですか。でも買わざるを得ないわけじゃないですか。外盤ではもう出てんのかなー。「暗黒の世界」と「ディシプリン」のリマスターのなんか、あれですか? スティーヴン・ウィルソンがまたやってるんですか? これがもうすぐ出るわけじゃないですか。もう外盤だとね、特典とかが少ないからあえてそれは買わずに今もう予約しました。やっぱりその…バンド…レコードメーカーさん達の戦略ってものにずーっとこう、その都度都度はまってきたわけなんですけども。でも凄い幸せですよね。僕なんかが学生だった頃って情報が極端に少ない。ロックというものの意義っていうんだよね。当時その、ない中でさらにプログレってのはないわけでなんですよ。だから本当に飢えてた状態だったんですよね。そこに来て観た5大プログレの1つであるジェネシスの曲が「アバカブ」とは!?ですよ? あれを観た時に「なんでこれがプログレなんだ?」と。「ラム・ライズ・ダウン・ブロードウェイ」、ここまでが僕の中でのジェネシスなんですけど、でも「トリック・オブ・ザ・テール」も意外といいんですよね。ただね、どうもねフィル・コリンズのあの歌い回し。あとライブ・アルバムありますよね、フィル・コリンズがやってる…「セカンズ・アウト」でしたっけ。“サパーズ・レディ”とかがね、あの歌い回しが嫌。フィルコリンズの。あの「ヘ~イベイベ~♪」ってこうね、歌うんですよ。フィル・コリンズ。あの「ヘ~イベイベ~ェッ♪」ってこうならないといけないわけですよ。「今日は一日プログレ三昧・再び」をお聴きの皆さん。僕もずーっとプログレッシヴ・ロックこそこの世の音楽のメインストリームだと言い続けます! 真顔で!言い続けます! ぜひ皆さんも言い続けてください。別に笑われたり何言われたっていいじゃないですか。自分がそれを好きだと思って聴いているわけですから。そういう意味で言えばこの「今日は一日プログレ三昧・再び」を聴いているリスナーの皆さんは素敵ですね。素晴らしいです。ビューティフルです。森 今日タイトルコールをお願いしたのは俳優の高嶋政宏さんでした。山 大丈夫ですかこの人?全員 (爆笑)山 本当に心配です。いっつも心配です。お会いするたびに心配です。全員 (笑)山 おっしゃってたようにね、いろんな街の情報を紹介する番組にいらして。地元の二子玉川の回ですよ? お洒落な街の階にいらして開口一番した話がプログレ(笑)。僕はここでクリムゾンの何を買ったって、いやそんな話聞いてないですから(笑)。森 小学校5年生で「レッド」を聴いてガラガラガラと。山 何かが崩れたと言ってましたね(笑)。何かが芽生えたわけじゃなく何かが崩れちゃったんですから(笑)。森 崩れ落ちてしまったわけですから(笑)。岩 なんかプログレってそういうイメージありますよね。「実は」とか、別に隠さなくてもいいと思いますけど。「実は好きだった」とか。メインストリームでいいじゃないかと、堂々と。なんかねプログレって。山 ほかの音楽はそんなこと言わないですよね。岩 なんかこう小さい声で「岩本さん。僕実は…」みたいな。何言われるのかと。隠すことないよって言いたくなっちゃいますよね。ミ こんなに度胸がある喋り方のプログレ好きの人、僕は初めて知りましたけど(笑)。山 度胸あるけど脈絡はないよ(笑)。全員 (笑)山 いつからジェネシスの話になったんだっけ?みたいな(笑)。ミ 筋トレしながら喋られてるみたい。森 本当力強かったですね。山 力強さはありますよ。間違いないですね。全員 (笑)森 スターレス高嶋さんのコメントの後ですから、お聴きいただくのはもうこの曲しかないかなと思います。キング・クリムゾン“スターレス”で。リクエスト、まずこちらご紹介…山 あ、リクエストね、こちら変わった方がいらっしゃるんですけども、山口県の男性の方ラジオネーム、サイモンアタローザさんなんですけども。これ10月1日にいただいてるんですけども、勝手にね、今日のプログレ三昧・再びのエンディングを予想しているんですよ。で、「今日はプログレまみれの最高の一日でした。特に中盤のあのコーナーのあのあたり、とても面白かったです。さて僕のリクエストはキング・クリムゾンの“スターレス”です。これを番組の最後に流していただきたいです。プログレ三昧を締めくくるにふさわしい名曲だと思います。それでは視聴者の皆さん、最後までお疲れさまでした。また来年のプログレ三昧を…」。ミ 仕切った! はははは(笑)。森 ま、ちょっと残念。ラストにはならなかったですけどもね。山 もう意地でもラストにしません。こういうのは…。続く。
2011/10/20
コメント(0)
-

10/10にNHK-FMで放送した「今日は一日プログレ三昧・再び」 文字に起こしてみた。(その32)
続き。山田五郎→山森田美由紀→森岩本晃市郎→岩ミト→ミ※発言はしていないが上野洋子氏と富家大器氏(途中まで)も同席森 続いてちょっと変わった曲のリクエスト。2通来ています。内容からご紹介しますと、「キング・クリムゾンもイエスもELPもプログレの花形ですが、僕はAORと呼ばれる前のジノ・ヴァネリの“ア・ポーパー・イン・パラダイス”。これをリクエストします」。山 ジノ・ヴァネリ!? ジノ・ヴァネリにプログレ時代ってあんの? AORなんじゃないすか? アダルト・オリエンテッド・ロックな。お洒落なもんなんじゃないの?森 「プログレから次のムーブメントへと移り変わる時代、プログレ時代のセンスの総集編として、ロンドンのロイヤル・フィルハーモニックとのセッションは圧巻です。プログレの醍醐味が独自のアプローチでしか決定的に表されている究極? これを聴いた時この人は何者なんだと思いました」。山 今ジノ・ヴァネリの話してるんですよね?森 そうです。続きです。「オーケストレーション、実はドン・セベスキー。巨匠アレンジャーだったんですけれども、生のオケの魅力を教えてくれた間違いなく僕の人生を決めた1枚です」。ということで、リクエスト、作曲家、S・千住明さん。山 あっ千住さん! へー! 千住さんがジノ・ヴァネリ押し!森 ジノ・ヴァネリを、ええ。先日同じ日曜美術館という番組を担当していて、その打ち上げの席で。山 いいなー日曜美術館毎回打ち上げあって。森 いえ、時々です時々(笑)。山 プログレ三昧なんか打ち上げないもん。デイヴさん電車で帰っちゃったもん。森 またなんとかやりましょうね(笑)。で、その時に「このジノ・ヴァネリはAORだけじゃないんだ」と。「曲を聴けばわかります」ということでリクエストいただいています。そしてもうひと方。岐阜県28歳男性、ユルヌルさん。「最近では一番プログレッシヴだと思ったバンドがバトルスでしたが、その一員のタイヨンダイ・ブラクストンのソロで彼が見せた才能に戦慄を感じました。バンドもオーケストラもサンプラーも同じように自由自在に操る迷宮のようなサウンド。カズーみたいな音がずっと鳴っててかなり変。なのにポップ。はまると抜け出せなくなりました」。とうことで。山 タイヨンダイ・ブラクストンの皆様の評価は高いですねえ。精 タイヨンダイって抜けてたんだ。ミ 抜けてました。精 今年はもう、フジはバトルス良かったですね。山 アンソニー・ブラクストンの息子ですね。森 まず聴いていただきましょうか。2曲続けてお聴きください。ジノ・ヴァネリ77年のアルバム「ア・ポーパー・イン・パラダイス」から“ア・ポーパー・イン・パラダイス組曲第2楽章”、“第3楽章”。タイヨンダイ・ブラクストン2009年のアルバム「セントラル・マーケット」から“ウッフェズ・ウッドショップ”。52. A Pauper In Paradise: 2nd Movement / GINO VANNELLI53. A Pauper In Paradise: 3rd Movement / GINO VANNELLI54. Uffe's Woodshop / TYONDAI BRAXTON森 ジノ・ヴァネリ“ア・ポーパー・イン・パラダイス組曲第2楽章”と“第3楽章”。タイヨンダイ・ブラクストン“ウッフェズ・ウッドショップ”。続けてお聴きいただきました。山 …ということでね。山本さんと富家さんが帰っちゃいました。森 お帰りになりました(笑)。京都にお住まいということで。ミ コメントもなく風のように。風のように去って行きました(笑)。山 ジノ・ヴァネリがかかったかなと思ったら。プログレと言えばプログレなんですかこれも?岩 ロックというよりもちょっとこう…ロック・サイドというよりもなんて言うんでしょうね、違うところから力が働いている。だからマハヴィシュヌ・オーケストラとか、そういうプログレなんだけどもジャズで。でもオーケストラの付け方なんかがちょっとこう、ロックよりはジャズとかクラシックに近いというね。そういう感じがしますね。ミ スフィアン・スティーヴンスとか、そういうあの流れとかも今ちょっとやっぱり、近いところがありますよね。岩 ありますね。ミ それで言うとエニドの流れじゃないですけどそういうところにもかかるっちゃかかるし。山 タイヨンダイのほうはまあアート系のいわゆる、プログレと言えばプログレですよね。ある意味正しい意味でのプログレかもしれない。岩 そうかもしれませんね。70年代の遺伝子から発展していったものと90年代から出てくる…例えばレディオヘッドのようなところから出てくるプログレというか。ディセンバリストとか、さっき言ったスフィアン・スティーヴンスとかボン・イヴェールとかね。そういう感じのアートフォームな匂いがしますね。森 続いてのリクエスト。まずリクエストからご紹介します。富山県30歳女性、ミツマメさん。「マクドナルド&ジャイルズ大好きです」。山 おおー出た。30歳の女性が。岩 出ました!森 「『宮殿』」よりも好きなくらい。複雑なことをやっているのに緊迫感があまり感じられないのが凄いです。テンションが低いわけではないのに聴いている側に緊張感を強いないと申しましょうか。クリムゾンの対極の音楽をクリムゾンとほとんど同じ手法で作るなんて。この当時のイアン・マクドナルド素晴らしいです。ジャケットの彼がまたかっこいいんですけど、彼女と写ってるなんて…」。山 それぞれ彼女と(笑)。ミ 僕ジョージ・ハリスンのジャケと勘違いしました。見て「ジョージ・ハリスンかなあ」って。山 ちょっと似てますよね。森 もうひと方。茨城県41歳男性、プログレ・イズ・ノット・デッドさん。「十数年前、妻に反対されながらも結婚披露宴の再入場曲に選んだ思い出深い曲です」。全員 (笑)山 結婚披露宴の!全員 (笑)山 凄いなー! これは筋金入りだ!森 それからファックスですね。いただいています。「プログレ最高。父と息子で聴いています。父のリクエスト“バードマン”、マクドナルド&ジャイルズ」。ちなみに息子さんのリクエストは“エコーズ”、ピンク・フロイドでして。群馬県太田市、21世紀の精神正常者さんからいただいていますが、マクドナルド&ジャイルズ。岩 これはもうキング・クリムゾンのね、プログレの始まり。作って辞めてしまったイアン・マクドナルドがマイケル・ジャイルズとともに作った。結局このマクドナルド&ジャイルズも1枚で終わってしまったんですけどね。クリムゾンのファンタジックな部分とマクドナルドの理想みたいなものが…たぶんそのキング・クリムゾンのファーストがあってセカンドの「ポセイドン」っていうのがあって、中間に位置するようなね。非常にいいアルバムですよね。山 「ポセイドンの目覚め」を凄く意識して、結構あてつけっぽい。岩 そういうとこもありますよね(笑)。山 そのわりにジャケットがね。ミ なんかやっぱサイケ感のほうが漂う。山 お互いの彼女とラブラブなだけの写真が。結構びっくりしましたけどね、あの落差。プログレじゃないですよねあのジャケは。岩 実はこれスティーヴィー・ウィンウッドが入ってるんですよね。山 入ってます。入ってますね。森 それではお送りします。マクドナルド&ジャイルズ、70年の同名アルバムから“バードマン”。55. Birdman / McDONALD & GILES森 マクドナルド&ジャイルズ、 “バードマン”。21分40秒の曲をお聴きいただきました。ミトさんお好き…?ミ いや僕…なんともなくいきなり振られましたね(笑)。凄い好きです。なんかその、プログレっていう風に聴く前はどっちかというとサイケデリックなイメージのとこで僕は結構聴いてて。僕はサイケデリックなバンドで凄く好きな、ちょっとマニアックなんですけどサンフランシスコのバンドでマッシュルームってバンドがありますけど、その2枚目の「水素でぶっ飛ばせ」っていうアルバムの2曲目かなんかが“マクドナルド&ジャイルズ”って書いてある曲で(笑)。それで20何分ですっごいいい曲なんですよ。でもなんかね、サイケからプログレっていうのが綺麗に枝葉が分かれてるみたいのがちょっとわかるような。山 プログレの中の因子としてちょっと忘れられがちな部分ですよね、サイケって。初期はもう濃厚にありましたよね。岩 そうですね。ありましたね。山 ピンク・フロイドなんかでもシド・バレット期は完全にサイケですから。岩 うん、うん。ミ クリムゾンだってファーストは。山 クリムゾンはファーストはサイケ入ってますよね。岩 そうですね。入ってますね。森 さて、「私とプログレ」。最後の方にご登場いただきましょう。山 このコーナーがありましたね、「私とプログレ」。森 今回のタイトルコールやジングルを担当していたのもこの方なんです。山 そうなんです。それではご登場願いましょう。続く。
2011/10/20
コメント(0)
-

10/10にNHK-FMで放送した「今日は一日プログレ三昧・再び」 文字に起こしてみた。(その31)
続き。山田五郎→山森田美由紀→森岩本晃市郎→岩富家大器→富ミト→ミ上野洋子→上※発言こそしていないが山本精一氏も同席している<UKのエディ・ジョブソンからメッセージ>森 エディ・ジョブソンさん本当ですかという声がスタジオに溢れましたけども。山 ホンマもんのエディ・ジョブソンですから山本さん。森 今年UKで来日を果たしたエディ・ジョブソンさんでした。リクエストもいただいています。ご紹介しましょう。大阪府28歳の女性、シューレティンガーオデコさん。「大人のプログレって感じがするUKの1作目。渋みにはまってCDだけじゃなくアナログ盤まで探しちゃいました。邦題を見てびっくり。アルバムが『憂国の四士』」。これ4人の侍ってことなんですかね?それから「“イン・ザ・デッド・オブ・ナイト”は“闇の住人”。なんて仰々しい。こういう権威主義っぽい打ち出しがパンクの時代には必要だったのかなあと思いました」。ということですね。山 いやあパンクが始まる前からプログレはそうでしたよ。森 タイトルがね(笑)。山 邦題はね、基本的に漢字。岩 漢字好きなんですよプログレは。山 ヤンキーとプログレは漢字が好きっていう共通点があるんですけども。森 そして48歳の男性、サザナミさんから。「ずーっと聴いてます。最高だー!」。ということでUKのリクエストをいただいています。ではお聴きください。UK、78年のデビュー・アルバムから“イン・ザ・デッド・オブ・ナイト”。49. In The Dead Of Night / UK森 UK、78年のデビュー・アルバムから“イン・ザ・デッド・オブ・ナイト”をお聴きいただきました。富家さん、この曲コピーしたことが?富 コピーしてましたね、昔ね。その当時のバンド少年とか、ある程度楽器に興味があって難しいことしたくなったらやるんじゃないかなあ結構…昔はねえ。そういう標的の曲です。やっぱり。山 必ず通ってくる。富 通ってくる道の1つ。僕は同世代の人は多いです、そういう話するとね。懐かしい。山 特に太鼓の人は今で言うブルフォード? 昔で言うブラフォード?は必ずやっぱり…通る道でしたよね。富 必ず通ってくる道ですね。プログレとかね、うん。森 リクエストにお答えしていきます。これ最近のバンドなんでしょうか? ムーン・サファリ。岩 そうですね、スウェーデンのバンドですね。最近プログレッシヴ・ロックというのは流行っていまして。流行っているんです実は。山 なんかスウェーデンで流行ってるらしいじゃないですか。岩 イタリアとスウェーデンからいろんな新しいバンドが出て、昔のバンドも再結成してる。その中でかなり人気があるバンドですね。森 ふーん…ムーン・サファリですね。リクエストいただいています。千葉県30歳の女性、ムシャシャビさん。「ムーン・サファリの『ラヴァーズ・エンド』はこの数年の最高のアルバムでした。噂を聞いて期待したものの、通販サイトは軒並み売りきればかり。数ヶ月間輸入盤屋さんを梯子し続けてやっと見つけた時の喜び。とても思い入れも深まりました。途方もないいいメロディばかりで、これほどの曲を揃えるのにどれだけのメロディを書いたのかなあと気が遠くなります。作品に釣り合わないあまりにひどいジャケットが残念です」。という(笑)。山 これですよね? 僕も今これ、「ラヴァーズ・エンド」っていうからこれだよなあと思って。大概なジャケットなんですけども。森 これはワインカラーの地に女性のシンプルな…髪の長い女性が。富 開けると…尻尾ですか?山 尻尾なのか…森 動物になっているんですかね?山 動物のようにも見える。岩 でもなんか、モノクロの頃のマレーネ・ディートリッヒの真っ白い、なんか描いちゃいましたっていうか(笑)。山 滅茶滅茶よく言えばマレーネ・ディートリッヒですけども、素人が描いたような絵ですよこれ。全員 (笑)山 このジャケットを見てさっき「俺は好きやなあ」って言ったの山本さんだけですよ!?全員 (笑)森 いいですか?(笑)富 ファンタジックな音楽が出てきそうな感じじゃないですかねえ。山 一体このジャケットからどんな音が飛び出るか。森 この曲にもうひと方リクエストいただいてます。東京都35歳男性のブタバニさんからもリクエストをいただいてます。では本当にこのジャケットからどんな曲が出てくるんでしょうか。ムーン・サファリ2010年のアルバム「ラヴァーズ・エンド」から“ア・キッド・コールド・パニック”。50. A Kid Called Panic / MOON SAFARI森 スウェーデンのバンド、ムーン・サファリの“ア・キッド・コールド・パニック”でしたが。山 うわあびっくりした!森 このスタジオ中の皆さん、反応は爽やか。山 ま、爽やかでしたね。ミ ずっと裏切らないっていう(笑)。山 だけど長い。そして単音のシンセのソロがある。ミ 大団円で終わる。山 リフが若干イエスの“危機”の最後のリフに似ていなくもないみたいな。…これですか。これが今流行っていますか。岩 流行ってますね。爽やかな。山 そしてあの、ジャケはこれですよ。全員 (笑)岩 そうですね、ジャケがちょっとね。山 これさあ、メジャーなバンドのジャケじゃないですよ。岩 ジャケットで言うとバンド名がメドゥーサみたいものになりそうな。山 インディーズの手売りしてる人のジャケですよこれ。森 これが今手に入らないくらいの人気だっていうんですからね。富 ジム・オルークとかああいう世界ですかね、どっちかというと。ミ ああ、近いですね。岩 ジム・オルークの世界に近い。ジャケットは。山 確かに確かに。森 曲、続けていきましょう。続いてはマイク・オールドフィールドの美しい歌ものということなんですが、どうですかマイク・オールドフィールド?岩 最初デビューした頃は多重録音というか、独りで長い曲。でも段々短くなってきて“ムーンライト・シャドウ”という大ヒット曲が出た後にマギー・ライリーと組んで。その路線しばらく行くんですね。その辺で好きになった方も実は多いんですよね。山 あれ? ヴォーカルってアニー・ハズラム?岩 えーと、マギー・ライリーという人で。アニー・ハズラムはソロでそれをカバーしてますね。山 ああ、なるほどね。森 リクエストご紹介しましょう。京都府27歳女性、ミネコさん。「ポップな歌ものマイク・オールドフィールドがプログレかという疑問はありますが、この美しさの前ではその疑問も問答無用で消え失せてしまします。民俗音楽っぽい空気と神経質なギターはやっぱりプログレなのさ」。山 「なのさ」って(笑)。ミ 凄い、言い切られちゃった。森 「マギー・ライリーの歌はこんな風に歌えたら幸せだろうなあと思ってしまします。ライブのゲストの上野さんがいたザバダックを思い出しもする曲です」。山 出ましたザバダック。あれかな、「ディスカヴァリー」のかな。岩 はい、「ディスカヴァリー」ですね。森 上野さん絡みでもう一通いただいています。三重県31歳男性、これ…ボインシモダさん?ですか? 「先ほどのセッション素晴らしかったです。上野洋子さん、明日お誕生日なんですね」。おめでとうございまーす!(拍手が起こる)山 おめでとうございます! マニアックな情報を!上 ありがとうございます。森 お誕生日なんですね。上 はい。森 というお便りもいただいています。ではお聴きいただきましょう。マイク・オールドフィールド84年のアルバム「ディスカヴァリー」から“トゥ・フランス”。51. To France / MIKE OLDFIELD森 マイク・オールドフィールド“トゥ・フランス”お聴きいただきました。ザバダックを思い出しもするという曲ということですが。上 好きでしたね、結構。喫茶店でかかると「あっこれマイクだ!「とか言いながら騒いでました。山 喫茶店でかかってたんだねってことがね、この曲が当時は。森 これ結構、日本のいろんなアーティストにも影響あったんでしょうか。岩 マイク・オールドフィールドっていうのはギタリストで、その手法とか録音方法とかいろんなことでは与えているんですよね、影響をね。ただ後半になってヴォーカリストが変わってシングルのポップ・ソングを出していく頃になると、マイク・オールドフィールドっていうよりも曲だけが独り歩きしていくんですよね。上 「エクソシスト」とかね。あった。山 「チューブラー・ベルズ」ね。富 結構分かれますよね。山 この辺からちょっとその、ケルト的な感じも入ってきて。いろんな影響受けてるミュージシャン多いですよね。日本もね。岩 多いです。本当多いですね。続く。
2011/10/20
コメント(0)
-
10/10にNHK-FMで放送した「今日は一日プログレ三昧・再び」 文字に起こしてみた。(その30)
続き。山田五郎→山森田美由紀→森岩本晃市郎→岩ミト→ミ山本精一→精上野洋子→上富家大器→富山 その曲の間にですね、先ほどのデイヴ・シンクレア・スペシャル・バンドのメンバー4人にスタジオにお越しいただきました。森 ありがとうございました!山 お疲れ様でしたー! お疲れさまというしかない、ミトね。ミ なんで僕なんですか(笑)。森 ご紹介しましょうか、まずね。いらしていただいた皆さん。山本精一さん。精 あ、どうも。山本です。山 山本さんの見たことのないギター・プレイを拝見いたしました。カッティング。精 コードカッティングしかしてないですからね。山 しかもめちゃコードが展開激しかったですね。精 すいません1曲目のケツ出まして申し訳ないです。マニアの方すいません。ほんと。本当に申し訳ないです。修業足らないですね。森 そして上野洋子さん。上 どうもー。ありがとうございました。山 アニー・ハズラムになって。上 いやいや! アニー・ハズラムのファンの方ごめんなさい(笑)。森 そして富家大器さん。富 はいお疲れさまでした。森&山&岩 お疲れさまでした。富 リチャード・コフランになりきりましたね。山 コフランと言うらしいということが今日判明しましたよね。富 コーフランじゃないのかね?山 コーフランてかコクランとか、いろんな表記がありましたけど、どうも今日のデイヴさんの発音を聴くにコーフランでしたね。森 そしてミトさん。山 お疲れさまでした!ミ リチャード・シンクレアというよりは無茶なシンクレアでしたけども。全員 (笑)山 無茶なシンクレアでしたね~。またこう、今日も早い時間からリハをやっていたのがずっとモニターに映ってたんですけども、結構な緊張感が音もないのに感じられるリハでしたよ。ミ まずさ、全員が集まってドンと音鳴らしたのが今日が初めてだ。富 彼が来て本当にようやくバンドになったなって。山 ミトが来て。精 本当ベースがない状態だった。岩 大変ですねえ。富 ベースってやっぱ大事だね。精 思ったね。本当にね。ミ もうね、本当無茶シンクレアしちゃって。山 もうね、さっきから皆さんね、プロと思えないご発言なんですよ。ミ だって難しいっすよ。山 高校生の文化祭終わった後のね、話し合いしてるんじゃない(笑)。精 軽音みたい。山 軽音!(笑)森 でもなんか素人で申し訳ないんですけど、あれやっぱり相当難しいんですか?精 うーん…僕にはね。森 山本さん(笑)。ミ 鍵盤ギターとか、なんかそういう次元の話じゃないですよね。どっちが難しいとかあるじゃないですか。鍵盤で作ってる人はギターだと難しいとか。両方ですよね。山 ミトのベース・ラインだって相当大変な。ミ 面白かったのが、結構ほぼ完コピ状態で実は行ったんですよ、当日…僕今日。そしたら結構変えるっていうか、その…上 そう。変わったことがあったんです。ミ でも内訳で言うとデイヴさんは作った時はコード弾いてもらいたかったんだよねリチャードに的なところが。富家さんの話で言うと、リチャードは非常にイタリア的な気質で。富 そうそうおおらか。まあ良く言えばおおらかなんだけど。まあノリで弾いちゃうところがあるからね。それをもしかすると本来の姿に近いバージョンでできたかも?山 そんなリチャードシンクレアへの不満を。ミ 違う違う。そういうことじゃない(笑)。山 ミトにぶつけられても。ミ まあまあまあ。で、だから僕は間違えたところのその、ブーンて間違えたところとかも完コピで来たんですよ。そしたらデイヴが「面白いからそれはやっていい」って言われて(笑)。山 ある意味、じゃあデイヴ・シンクレアさんとしてはですよ、キャラヴァンよりも理想的な演奏ができたかもしれない。精 でもなんか微妙な反応でしたけどね、終わったあと。(えーそうですか? そんなんじゃないよ、という声が周りから上がる)ミ 山本さんもなんかもう「はー…」みたいな。いろんなもう、エネルギーすべて使い果たしたみたいな。山 山本さんね、いつ弾き出すんかと思って。いつソロ弾き出すんだ。精 一番ケツだけです。最後の“ナイン・フィート”の。だからもう知恵熱が出ますよ。全員 (笑)精 マジしんどかったですねー。今ちょっと2度くらい上がってますよ体温。山 平熱じゃないっすね。精 絶対コード間違えないってか、そういえば2回ぐらい間違えましたけども。そんなプレッシャーがあるねんやなと思いましたね。山 今回山本精一さんやっていうので一部マニアの間でえらい騒ぎになってて。精 リードをやると思ったんじゃないかなと思う。山 でもま、よくよく考えてみたら、“ナイ・フィート・アンダーグラウンド”ってどこ弾くんかな?みたいな。精 そうなんです。実はあの曲ってリード・ギター入ってないんですよ。山 そうなんですよね。精 あれね、全部キーボードの音なんですね。どこがギターパートやってずっと。富 ギター入ってないじゃんって山本さん言ってた。ミ 全然。どこでチェンジしたのか、サックス・パートが変わったぐらいしかわかんない。富 サックス入ってる時はサックス。山 ミト君、やっぱり実際に演奏してみると、聴いてる時と違う部分とかってありましたか?ミ いやでも演奏してる時はもうやっぱデイヴさんと一緒にやれてるってのがあるから、なんかもう別物っちゅう発想だったと思います。ま、僕上野さんとかは本当に。全然プログレとかは関係なく、アニソンとしての上野さんも大好きですから。上 (照れ笑い)山 声の魔術師としての上野さん。(※奥でアニソンの話をしているようだがマイクが遠くて聴き取れず)山 そんなもう部室みたいな話するっつー。ここへ来てね(笑)。精 放課後ティータイム。山 三昧ですけど(笑)。ちょっとプログレ今微妙に影薄くなってる(笑)。ミ 何故か僕が“キグルミ惑星”を選曲したということになってますけども。精 どうどう? どうどう?富 そういうのもちゃんとね、受け継いでいくってのも大事なミッションかな?山 それ大事なミッション! また良いことを言ってくださいますねえ。まとめてくださいましたね。本当皆さんね、お疲れ様でした。ありがとうございました。これもう伝説に残るライブになれたと思いますよ。ミト 忘れられないですね。山 今日エアチェックした人はもう。精 すいません申し訳ないです。僕折れそうですわ。山 いやあ、まあまあ(笑)。森 山本さんそんな(笑)。富 もうなんか演奏しながら泣くと思ったね。精 泣いてました。山 最後の“オー・キャロライン”なんか泣くでしょ。ミ そう、すっごいハッピーなことがあって。リハーサルまで実はコーラスのパート振り分けるっていう、そのところを山本さんはいつもなんか、もう盛り上がってずーっと必ず全部歌ってたんですよ。富 本番行けましたよ。ミ そう、それが凄い、それでちょっと僕涙目。わー、すげー奇跡だーみたいな。山 ちゃんとできました?ミ もう超スペシャル。山 奇跡が起きましたねやっぱりね。森 皆さん本当にありがとうございました。全員 ありがとうございます。ありがとうございました。森 山本さんと富家さんは京都にお帰りになるということで、ここでお別れ。山 あ、もう帰らはるんですか。上 残るって言ってますよ。山 まだ電車ありますよ。精 早く東京行かないといけないんで。森 そうですか? じゃあ皆さんもう少しお付き合い…山 僕も明日朝イチで東京行きますんで。精 あ、そうですか。みんなそうだね。ミ そうか山本さんてプログレ好きなんですか…。全員 (笑)山 そっからすか!? そっから(笑)。ミ そんな全然…。へー…。森この後も次々にプログレの曲一緒にお聴きいただきたいと思います。山 よろしくお願いいたします。続く。
2011/10/20
コメント(0)
-

10/10にNHK-FMで放送した「今日は一日プログレ三昧・再び」 文字に起こしてみた。(その29)
続き。山田五郎→山森田美由紀→森岩本晃市郎→岩<ジングルとタイトルコール>山 この暑苦しいジングルの声の主は番組の後半で明らかになりますのでお楽しみにお待ちください。森 続いてのリクエストまいりましょう。イタリアのマクソフォーネというバンドですね。山 出ましたね(笑)。岩 イタリア多いですね。そういえば今年イタリアの建国というか一緒になってから150周年なんですよね。山 あ、そうなんですか。ドイツもなんかの150周年ですけどねえ。岩 ヨーロッパはいろいろありますよね。山 これはどういうバンドですか? マクソフォーネは岩本さん。岩 マクソフォーネ。これは典型的なイタリアのバンドなんですけども、ホルンというかですね、そういう楽器が入っていてちょっとジャズっぽくて。ただ、あるパートはシンフォニックでPFMのような感じですね。当時PFMに対抗する最有力候補のバンドだったんですけども、残念ながら1枚だけアルバムを残してですね、解散してしまったんですね。凄くいいバンドですねこれも。イタリアン・ロックが好きな人は、僕の友達の…知り合いのお医者さんがいるんですけども、彼はたぶんこれ聴いてると思うんですよ。これかかったらもう狂喜乱舞という感じですよね。森 ほかにもリクエストもいただいています。宮城県35歳男性、大丈夫ダイジョブさん。「正式メンバーにホルンがいる。しかも普通なら一番盛り上がるギター・ソロが入るような、ここぞというところでホルン」。山 ホルンが出てくるんだ(笑)。岩 これが素晴らしいんですね。森 「曲も目まぐるしく展開して、1分前に何が起こっていたのか忘れてしまうほど。考えすぎなのか何も考えていないのか、イタリアってすげー!と思いました」。山 なーるほど。巧いこと説明してくれてますねこの方。イタリアにありがちな(笑)。展開しすぎの(笑)。森 それではお聴きください。マクソフォーネ75年のアルバム「生命の故郷」から“ある国”。48. Ce Un Paese Al Mondo(邦題:ある国) / MAXOPHONE森 イタリアのバンド、マクソフォーネの“ある国”をお聴きいただきました。続く。
2011/10/20
コメント(0)
-

10/19にNHK-FMで放送された「とことんスーパーギタリスト列伝・デイヴ・ギルモア特集」を文字起こししてみた 2/2
続き。さ! 野村義男がお送りしているとことんスーパーギタリスト列伝。今日はデイヴィッド・ギルモアを特集しております。さてここでギルモアのピンク・フロイド以外の活動にも目を向けてみたいと思います。ギルモアはですね、様々なアーティストの作品でギターだったりとかね、プロデュースだったり、作曲なんかでもしているんですけども。中でも有名なのはやっぱりケイト・ブッシュですかね。僕も大好きですけども。そのケイト・ブッシュの作品から、今からギルモアがギタリストとして参加している曲を聴いてもらおうと思うんですけど。ケイト・ブッシュもこれ素晴らしいのはあの、僕大好きなのはね、“バブーシュカ”って曲が大好きでね。この人の歌声こそ本当に不思議な歌声。天使の歌声とはまたちょっと一味違うかなあ。よくこんな人を見つけたなと思ったら、ケイト・ブッシュのお兄さんがデモテープをギルモアのとこに持ってきて「うちの妹すげぇんだよ」とか言って、「おお。デビューさせようよ」みたいな話でトントントンといったらしいんですけどもね。そんなケイト・ブッシュ、1989年のアルバム「センシュアル・ワールド」からですね。ケイト・ブッシュで“ロケッツ・テイル”。04. Rockets Tail / KATE BUSH1989年のアルバム「センシュアル・ワールド」からケイト・ブッシュで“ロケッツ・テイル”でございました。とても綺麗な人なので一度皆さん見ていただくというのも素敵かもしれませんよ。今日ご紹介しているギタリスト、デイヴィッド・ギルモアでございますけども、ピンク・フロイドと活動を並行してですね、ソロ活動も行っておりまして。これまでスタジオ・アルバムを3枚、ライブ・アルバムを1枚出しております。今日最後の曲はですね、そのライブ・アルバムからお送りしましょう。ポーランドでライブをしたっていう。ギルモアはなんか初めてポーランドで演奏したらしいんですけども、そのライブをですね、40人編成のオーケストラ。ポーランドのね。ポーランド・バルトフィル・ハーモニック交響楽団なんかも参加してですね、とても…きっと大所帯なバンドでやったんでございますけども。この時のは「狂気の祭典」。ライブ・イン・グダニクス。グダニクス? クダニクス? グダニクス? 土地の名前ですかこれ? 難しい名前でございますけども。2006年8月のポーランドでの演奏でございます。“オン・アン・アイランド”。05. On An Island [Live] / DAVID GILMOUR2006年8月のポーランドでの演奏“オン・アン・アイランド”でございました。グダニスクに僕住めないなあやっぱり。いやいやいやいやいや。野村義男がお送りしてきました「とことんスーパーギタリスト列伝」。今日はデイヴィッド・ギルモアを特集しました。50分では聴きつくせない、語りつくせないギルモアの魅力。いかがだったでしょうか。番組では皆さんからのご感想を…(略)今日はデイヴィッド・ギルモアでございましたけど…、あのねぇ、いい男なんですよ。見た目がかっくいいの。で、なんか元々モデルさんとかもやったことあるっていうね。だからまあ容姿は素敵。ギター上手。歌も巧いっていう。もう言うことなしでございますけどもね。ピンク・フロイドもなんての、ライブ、音も素晴らしいんですけど照明も凄い。びっくりするぐらい照明踊りまくりみたいなぐらい。すっごい別世界に連れて行ってくれるぐらい照明綺麗だったり。あと豚の風船飛んでたりね、ライブによってはね。そういうこともあるんで、ぜひそういうのも体験しにね。もう日本にも来てくんないかな―なんて思いますけれどもね。まああとはもうデイヴィッドは凄いギター好きで。あのねぇ…僕に言わせると凄い悔しいですね。ビンテージの凄い貴重なギターがあるんですけど、エレキギター。それのねぇ、シリアルナンバー0001のギター持ってる。おいおいおいおいおいおい~!みたいな感じですけども。力関係こういうところに出るってことですかね~。あとはもうだいたいライブで使っているギターとラップスティール、ペダルスティールとか使うんですけど、同じ色で特注で注文しちゃったりとか。ギター三昧なんだなこの人やっぱり。ギター好きに悪い人はいないということでございますよ。ということでございまして、デイヴィッド・ギルモア。本当にかっこいい男でございます。「とことんスーパーギタリスト列伝」。この時間のお相手は私、野村義男でございました。それではまたお会いしましょう。さようなり~。
2011/10/19
コメント(0)
-

10/19にNHK-FMで放送された「とことんスーパーギタリスト列伝・デイヴ・ギルモア特集」を文字起こししてみた 1/2
ギタリストの野村義男です。「とことんスーパーギタリスト列伝」。ここからの時間はロック史に燦然と輝くスーパーギタリスト、彼らが残してきた名演をとことん聴いていただきます。さて今回特集するのは、まだまだいますよ~素敵なギタリスト。デイヴィッド・ギルモアでございます。デイヴィッド・ギルモア。1946年イギリスに生まれまして、現在65歳ということで。10代後半からですね、バンド活動を始めます。で、1968年、既にもうプロとして人気が出ていた友達のバンド、ピンク・フロイドからバンドへの参加を要求されまして、「入りま~す」みたいな感じですかね。で、これはもう、なぜかというとギタリストのシド・バレットがですね、精神的な病気でまともに活動を続けられない状況になったためでございまして。で、ギルモアの参加後、すぐにシド・バレットは脱退します。以降ギルモアは全世界でシングル、アルバム、合わせてなんと!2億万枚以上も売り上げるモンスター・バンド、ピンク・フロイドのギタリストとして大活躍しているということでございましてですね。デイヴィッド・ギルモアのスーパーなところはずばり!湿りっけたっぷりなブルージーなプレイと幻想的なサウンド! これですかね。こういうロングトーンもさながら本当素晴らしいプレイでございますけども、どういうふうに言うのかな…あともうリヴァーブだったりディレイだったりこう、いろいろ音が飛んでいく感じ? うん、そういうかんじでございますけど。じゃあそんなギタリスト、デイヴィッド・ギルモアが在籍するバンド、ピンク・フロイドの代表曲をここで聴いていきたいと思います。そうそう、今からお届けする曲ね、最初に時計の、目覚ましみたいのがチャーみたいなのが鳴るんで驚かないでくださいね。運転中の人も気を付けてください。今から眠りに入ろうとしている方も気を付けてくださいね。目が覚めちゃう感じでございます。お届けしましょう。1973年にリリースされた名盤「狂気」から“タイム”。01. Time / PINK FLOYD1973年発売の大ヒット・アルバム「ザ・ダーク・サイド・オブ・ザ・ムーン」、邦題は「狂気」ですね。これからピンク・フロイドで“タイム”でございました。そういえば今日の放送は絶対に皆さん、イヤホンとかヘッドフォンで聴いた方が音が右に左にあららららみたいになるんで楽しめると思いますよ。ということでそんなピンク・フロイドということでございますけども、1967年のデビュー当時から人気のありましたピンク・フロイド。メイン・ソングライターのですね、シド・バレットが脱退した後もですね、ちゃんとこう1年にほぼ1枚ずつアルバムを出し続けて人気を得ます。そしてですね、何と通算5枚目のアルバムになりますね、「原子心母」というのでですね、全英初の1位を獲得するとですね、以降も「おせっかい」とか「雲の影」とかコンスタントにアルバムを出し続けて、73年先ほど聴いてもらいました“タイム”を収録したアルバム「ザ・ダーク・サイド・オブ・ザ・ムーン」を発表して大ヒットするということでございまして。このアルバム本当ロック史に残る現在も売れ続けている。こう、みんなが聴いているじゃなくて売れ続けていると。ここがポイントなんでございますね、本当にもう。で、さらにそのあとですね、これまた名盤でございます、「炎」というアルバムがありまして。「炎~あなたがここにいてほしい」。握手しているんですよね、火の中。火がついた人たちがね、ジャケットがね。これ発表しましてまた全英・全米ともに1位を記録ということでございまして。これなんかしかも、炎のやつは映画の「チャーリーズ・エンジェル」とかを担当してきた炎専門のスタントマン。あれ合成とかじゃないんだよねジャケットがね。本当に火のついた人がジャケットに使われてる。熱かったろうになー…。ということで。さ!ここではですね、ギルモアのクリーンなギターが、音色(おといろ)が印象的な名曲を聴いていただきましょう。02. Shine On You Crazy Diamond / PINK FLOYD1975年のアルバム「炎~あなたがここにいてほしい」からピンク・フロイドで“シャイン・オン・ユー・クレイジー・ダイヤモンド”でございました。かっけ~…! マジかっくいー! ということでございまして。もう100点満点だね。100点満点。曲の長さも100点満点。最高かっこいいです。もう大ヒット作をですね、連発し続けるピンク・フロイドでございますけども、1979年にコンセプト・アルバム「ザ・ウォール」でまたまた大ヒットということでして。これもう全米1位を記録しまして、何とこの頃ベースのロジャー・ウォーターズがバンド内の主導権を握ろうとしたためにメンバー間の仲が悪くなっちゃった、みたいな。まあのちにそのウォーターズはバンド脱退しまして、メンバーとは訴訟問題にまで発展すると。そこまで喧嘩するか!?みたいな感じでございますけども。さあ、そのコンセプト・アルバム「ザ・ウォール」から聴いていただきましょう。ギルモアのエモーショナルなギターが大変素晴らしい曲でございます。“コンフォタブリー・ナム”。03. Comfortably Numb / PINK FLOYD1979年のアルバム「ザ・ウォール」からピンク・フロイドで“コンフォタブリー・ナム”でございました。これジャケットが凄いんですよ。壁一面が白で、裏側だったかな、顔がニョッ!みたいな。夜見ない方がいいですよ、怖いから。びっくりしちゃいますからね。続く。
2011/10/19
コメント(0)
-

10/10にNHK-FMで放送した「今日は一日プログレ三昧・再び」 文字に起こしてみた。(その28)
続き。山田五郎→山森田美由紀→森岩本晃市郎→岩山 さて、「今日は一日プログレ三昧・再び」。いよいよですね。森 はい。山 ライブ・コーナーでございます。先ほどこのスタジオお越しくださいましたデイヴ・シンクレアさんがこの日限りのスペシャル・バンドを率いて名曲の数々を生で披露してくださいます。森 メンバーの皆さんをご紹介します。ギターに羅針盤や想い出波止場、ROVO、またご自身のソロでも活躍する関西のロック・シーンの重鎮山本精一さん。ヴォーカルにザバダックで活動の後はヴォーカリストとしてはもちろん映画やゲームやCMの音楽なども手掛ける上野洋子さん。ベースに人気ロックバンド・クラムボンからミトさん。ドラムスに伝説のパンク・バンド、ウルトラビデのオリジナル・メンバーにしてアイン・ソフで活動する富家大器さん。そしてもちろんキーボードはデイヴ・シンクレアさんです。山 岩本さん、凄いメンバー揃いましたね。たぶん二度とないですね、このメンバーが揃うことはね。岩 エイジアよりも凄いんじゃないですか?山 この凄いメンバーで昨日からみっちりリハをやって。今日も昼の1時過ぎぐらいからずーっと厳しいリハをやってましたからね。岩 凄いですね。期待しちゃいますよね本当に。山 デイヴ・シンクレアさんの名曲にどんな新しい命が吹き込まれるのか楽しみですよね。それでは演奏を開始していただきましょう。デイヴィッド・シンクレア・スペシャル・バンド!<約42分のライブ演奏>山 いやー素晴らしいですね。これちょっと伝説作っちゃったんじゃないですか。岩 凄いですね。ちょっと目頭が熱くなっちゃってこう、目が赤くなっちゃっいました。本当にもう素晴らしかったです。山 いい演奏でしたね。岩 “オー・キャロライン”どうしようか…手が震えてきましたよ僕。森 本当に岩本さん目が潤んでますね。岩 本当ですよ。もうびっくりしました。森 この緊張感。山 いいですね。素晴らしい。森 リスナーの方からも感想いただいてます。岩手県54歳男性、カンタベリー・スチューデントさんから。「キャラヴァンで一番好きな曲、“ダブソング・コンチェルト”の“マッド・ダブソング”。生放送で、しかも日本で聴けるとは思ってもみませんでした」。山 「ロッキン・コンチェルト」と邦題は言われてますけどね。この“マッド・ダブソング”というタイトルをアニー・ハズラムが変えてくれっていうことで、今日演奏したこの“マン・イズ・ザ・チャイルド”という曲に変わったんですよね。森 「カンタベリー・ミュージックの生きる歴史、ミスター・デイヴ・シンクレアに感謝。カンタベリー音楽は私の生きる力の源です」。ということですね。山 カンタベリー好き多いなあ。森 それから新潟県の男性、ヒグチマサトシさん。「三昧スタッフの皆様お疲れ様です。シンクレア・スペシャル・バンドの作り出す温かみのある小宇宙空間。素晴らしい」。いただきました。岩 なんかもう、オルガンの音というか、キーボードの音が手癖から何から何まで人格がそこに出てるというかね、プログレッシヴ・ロックの歴史が詰まってるような音でしたね。森 演奏された曲目改めてご紹介しましょう。キャラヴァンの曲“手遅れの愛”(“If I Could Do It All Over Again, I’d Do It All Over You”)。キャラヴァンの“ダブソング・コンチェルト”の一部を改作した“マン・イズ・ザ・チャイルド”。最新アルバム「ストリーム」に収められていた“ディスタント・スター”。キャラヴァンの最高傑作の1つ“ナイン・フィート・アンダーグラウンド”。そして最後がマッチング・モールの“オー・キャロライン”。以上5曲お送りいたしました。“手遅れの愛”(“If I Could Do It All Over Again, I’d Do It All Over You”)収録作品“ダブソング・コンチェルト”収録作品“ナイン・フィート・アンダーグラウンド”収録作品“オー・キャロライン”収録作品山 大作“ナイン・フィート・アンダーグラウンド”ありましたけども、これ頭のパートが“ナイジェル・ブロウズ・ア・チューン”っていう曲なんですね。このナイジェル・ブロウっていう人はデイヴ・シンクレアさんの従兄弟にあたる人で、バロック期のイギリスの有名な作曲家のジョン・ブロウの子孫にあたるんですって。ジェームス2世の頃のヘンリー・パーセルやなんかと同じ頃の作曲家。つまりデイヴ・シンクレアさんもそのジョン・ブロウの子孫なんです。岩 血を引くということですね。山 その従兄弟のナイジェル・ブロウさんが今年亡くなったんですって。だからそういう思いも込めての今回の演奏なんですよ。岩 なるほどね…。そうですか。山 一際ね、これは歴史に残る演奏になったと思いますね。岩 伝説ですねこれはね。森 NHK大阪放送局R1スタジオも、もうみんな浸ってましたね。山 席を立ちませんもんまだ。森 番組ではリスナーの皆さんから出演者へのメッセージ、そしてプログレへの思い入れなどを募集しております。今いただいているメッセージもう2通ご紹介いたしましょうか。神奈川県48歳男性、ロビさん。「プログレッシヴ・ミュージックの世界は底なし沼のように深く、高校生の時よりこの世界にどっぷりつかっている自分でも実は聴いたことのないメジャーな曲もたくさんあるのですが、それをまとめて聴けるこの企画はもうNHK-FMの年中行事にしていただきたいです」。山 よろしくお願いいたします森田さん。森 できればいいですよね。岩 よろしくお願いしまーす。森 そして…これは今の演奏についての感想ですね。東京都23歳女性、フライパンキノコさん。「デイヴさんとミトさんの声がそっくりでびっくりしました。ミトさん、マッチング・モールの曲をカバーしてくださーい」。という。山 しましたよ。岩&森 (笑)山 カバーしました。それも“オー・キャロライン”をしました!森 メッセージはファックスとインターネットで受け付けています。ファックスは…(略)続く。
2011/10/18
コメント(4)
-
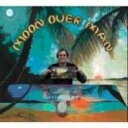
10/10にNHK-FMで放送した「今日は一日プログレ三昧・再び」 文字に起こしてみた。(その27)
続き。山田五郎→山森田美由紀→森岩本晃市郎→岩デイヴ・シンクレア→デ山 はい、後半戦に突入いたしました「今日は一日プログレ三昧・再び」。ナビゲーターの山田五郎です。森 NHKアナウンサーの森田美由紀です。そして音楽評論家の岩本晃市郎さんです。岩 こんばんは。森&山 よろしくお願いいたします。森 この番組12時15分から始まったんですよね。山 先ほど30分お知らせをいただいて、その間トイレが大混雑でございました。森 今日は10時45分まで続けます。リクエストは先ほど7時で締め切らせていただいてますけれども、出演者へのメッセージ、プログレへの思い入れなどは大募集しております。ファックスは…(略)(※デイヴ・シンクレア発言(通訳さん)の書き取りは少し手を加えています)山 さて、スタジオには素晴らしいゲストをお迎えしております。デイヴ・シンクレアさんでございます。デ (英語で挨拶)山 通訳は山上久美子さんにお願いいたします。よろしくお願いいたします。森 よろしくお願いいたします。山 これからはデイヴさんの個人的なカンタベリー・ロック史とでもいうべきテーマでお送りいたしていきます。デイヴさんは本格的なバンド活動というのはいつ頃から?デ 実は1966年にベースのプレーヤーとしてワイルド・フラワーズに入りました。それからプログレスしていってキーボード奏者になりました。山 ワイルド・フラワーズと言いますとね、まさにカンタベリー・ツリーズの原点と言われるバンドですけども。デ (※英語でYes, that’s rightみたいなこと言っている)山 そこからソフト・マシーンとかキャラヴァンが。デ ワイルド・フラワーズを母体として様々なグループに分かれていきましたが、中でも一番有名なのはソフト・マシーンとキャラヴァンだと思います。山 デイヴさんが加入した時のワイルド・フラワーズのメンバーというと?デ ブライアン・ホッパー、ヒュー・ホッパー、ロバート・ワイアット、パイ・ヘイスティングス、リチャード・コーフラン…でしたかね、それぐらいだと思います。ロバート・ワイアットは1964年に発足した時からの一番最初のメンバーです。作った時からのメンバーだということですね。山 もうほぼそれはキャラヴァンのメンバー?デ 最終的には1967年には5人が残っていました。それから分裂して私の従兄弟であるリチャード・シンクレアが入ってきました。山 キャラヴァンっていうバンド名はどこから?デ そもそもはパイのアイデアなんです。パイ・ヘイスティングスは非常に面白いことを考えつくのが上手な人で、とても変わった名前というのも出してくる人で。砂漠のキャラヴァン、あと音楽のキャラヴァン。曲のキャラヴァンからもイメージしているんですが、その砂漠のキャラヴァン隊なんかでも人が出入り自由って言いますか、様々な人が入ってきてはまた去っていく。音楽界にもそういう同じようなものがあってもいいんじゃないかなっていうアイデアからキャラヴァンという風に名付けました。山 カンタベリー・ロックのバンドは人が出たり入ったりが。デ 私自身も4、5回キャラヴァンを脱退しているんじゃないかと思います。岩 元々バンドを作る、元々のきっかけはなんだったんですか?デ ワイルド・フラワーズ時代にはやはりカバーが多かったんです。それで、カバー曲ばっかりやっているのではどうしても面白くないというか。自分の本当の音楽を作りたい。たくさんの創造性も生まれてきた。それならば自分たちの曲を作ろうということでキャラヴァンが生まれました。山 キャラヴァン当時の思い出としては?デ 本が書けるぐらいです。一番の思い出は1974年に最初のアメリカ・ツアーをした時です。なんと51回もフライトして3ヶ月間いろいろな場所を飛び回ってました。山 そのうち1回はヘリコプターだったっておっしゃってましたけど。アメリカでどうでしたキャラヴァンは? その当時…74年当時。デ 大盛況でした。本当に幸運なことに快く受け入れられまして、評判もとても良かったんです。非常に嬉しかったですね。初めてのツアーだったにも関わらずアメリカ人はとても優しく、実に寛大に受け入れてくださって。ウェザー・リポートなど有名なミュージシャンとも共演しました。岩 その頃ってみんなで共同生活? キャラヴァンでは共同生活をしていた?デ 結成当時は4人だったんですけど、みんなで共同生活をしていました。その後は一緒に暮らすということはなく、みんなバラバラにそれぞれの家で暮らしていました。岩 ちょっと戻りますけど74年の前に、71年にマッチング・モールを結成してますよね。デ キャラヴァンは1971年の8月に脱退したのですが、その当時ジョン・マーフィーというギターが非常に巧い男がいましてね。その彼とどうしても曲作りがしたいという大きな野望があったんです。ですが彼がある時消えてしまったんですよ。と言うのもジョンは結婚してポルトガルに新婚旅行に行ってしまったんです。でも私はどうしても諦めきれなくて、ジョンを追いかけてヒッチハイクで8日間かけてポルトガルに行きまして。トントンってドアを開けたら本当にびっくりされました。ポルトガルまで追いかけていって数日間はそこに滞在していたのですが、どうやって私の居場所を知ったのかロバート・ワイアットから直にメッセージが届きまして。「今すぐ帰って来い。イギリスでは君が必要なんだから早く帰って来てくれ」と…。そんな感じの流れでマッチング・モールを結成しました。山 そのマッチング・モールっていう名前なんですけれどもね、ソフト・マシーンがフランス語でマシン・モルと呼ばれてる。それをもじってマッチング・モールという名前を付けたという説がありますけれども、それは本当ですかね?デ そうです。山 マッチング・モール時代の思い出は何か?デ (本人が)マシーン・モル。私はその時海辺の大きな家に住んでいたんですが、ある日遊びに来たロバートに「君の曲を全部弾いてくれ」と言われましてね。で、弾いているうちに「その曲は何だ?」って凄く気になるらしい曲があって。それがまさに“オー・キャロライン”だったんです。で、ロバートが「これに新しく詩を付けてもいいか」と言ってきました。山 ロバート・ワイアットはその…自分が好きだった女性ですか? そのキャロラインさんっていうのは。デ キャロラインは実在する女性なんです。「インターナショナル・タイムス」っていうちょっとアンダーグラウンド系の新聞社で働いていた女性です。その彼女に向けてのラブソングですね。ミュージシャンというのははみんなラブソングを書くものですが、ロバートもそうでした。山 ところでデイヴさん、今京都に、日本の京都にお住まいと伺いました。だから今日来ていただくことができたんですけど、どうしてまたその、どんなきっかけで京都に?デ 実はかなり若い頃から日本にとても興味を持っていました。日本の文化や歴史、日本人というものに非常に興味を持っていたんです。19歳の頃には日本食を作っていたんですよ!それから1979年にキャメルのワールド・ツアーで初めて来日したわけなんですが、実はその1979年のワールド・ツアーで来た時に一日オフがあったんですね。その時に大阪から京都に行きまして、竜安寺に行きました。そこでじーっと静かに座っていたら、何だかこう、故郷に帰ってきたような落ち着いた気分になって凄く癒されたんですね。その後25年経ちまして、また竜安寺に行って同じ所に座ったんです。そしたらここが故郷なんじゃないかなっていう気持ちになりまして。その時に京都に住みたいな、と心から思いました。山 それでそのまま住んじゃった?デ 京都に住み始めた最初の頃はもちろん友達は少なかったですけど、日本式にゆっくりゆっくり…ゆっくり友達が増えていきました。そのあとにドーンと私の世界が広がっていくような感覚を受けまして。音楽を作る際にも非常に多くの新鮮なインスピレーションをもたらしてくれたので、京都という町には本当に感謝いますよ。今ではあまりにも友達が多すぎて離れられないような感じになっています。山 京都ではどんな…日本家屋みたいなところにお住まいなんですかね?デ 和室が一部屋だけあります。山 これからその京都でどんな作品というものを作っていきたいという風にお考えですか?デ 新しい音楽は常に作っていますし音作りというのはいつもやっていますが…、今新曲を作っている最中なんです。だから京都で暮らせてラッキーだと思っていますし、毎日の生活は素晴らしくて満ち足りた気分です。日本の皆さんが本当に暖かくサポートしてくださっているので、まるで夢のような日々です。森 デイヴさんにメッセージをいただいています。東京都46歳男性、東村山さん。「今日はシンクレアさんのライブが聴けるのはとても嬉しいです。今年の夏に夜行列車に乗って京都のパン屋で行われたライブに行きましたが、こじんまりとしたスペースで行われたライブはとても印象に残りました」。ということです。デ ヴィンセントという私の友達がとてもおいしいパン屋さんを経営していましてそこにレストランが併設してあるのですが、そこで非常にアットホームな小さなコンサートをしました。穏やかな音楽をやりまして。非常にスピリチュアルと言いますかクラシカルと言いますか、非常に穏やかな空間の中で演奏しました。実は私の家のすぐ近くに小学校があるのですが、その子供たちのために歌を作ったんです。そのコンサートに子供たちが実際に来て歌ってくれました。本当に最高の思い出です。森 そしてもう一通いただいております。女性53歳、アイスメロンさん。「今回京都にお住まいのデイヴ・シンクレア氏が番組にゲスト出演すると小耳に挟みましたが本当でしょうか」。本物でいらっしゃいますよね?デ はい本物です(笑)。森 間違いなく本物でいらっしゃいます。せっかくなので彼名義のソロ、「ムーン・オーヴァー・マン」の1曲“ワンダーラスト”をリクエストしたいと思います。この曲のキーボード・ソロのメロディはいかにもデイヴ節で、涙を誘うような響きである思います」。というリクエストをいただいています。そしてもう1曲、デイヴさんの一番新しいアルバム「ストリーム」から“アイランド”も聴いていただきます。この後デイヴさんにはライブの方にも向かっていきますのでそちらのほうのご準備もよろしくお願いいたします。デ (英語ではい、わかりました的なことを言っている)山 もの凄いリハーサルをされてましたよね、僕さっきモニターで拝見していましたけど。昼から何度も。デ 実を言うとまだまだできるんですよ(笑)。森 本当にありがとうございました。演奏の方も楽しみにしております。山 じゃあご準備の方を。森 そして通訳は山上久美子さん。全員 どうもありがとうございました。森 それではデイヴ・シンクレアさんの曲、2曲続けてお聴きください。46. Wanderlust / DAVE SINCLAIR47. Island / DAVE SINCLAIR森 デイヴ・シンクレアさんの“ワンダーラスト”、そして“アイランド”。2曲続けてお聴きただきました。続く。
2011/10/18
コメント(0)
全2231件 (2231件中 1-50件目)
-
-

- LIVEに行って来ました♪
- サーカスパフォーマーまおのライブ
- (2025-11-23 13:17:54)
-
-
-

- プログレッシヴ・ロック
- Yes【イエス】ロンリーハート~ビッ…
- (2025-11-25 21:23:42)
-
-
-

- 吹奏楽
- ちくたくミュージッククラブ7thコ…
- (2025-11-22 23:43:42)
-








