2022年10月の記事
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-
マエストロ・マノロ・サンルーカルとコルドバの記憶 その2
フラメンコギターを始めたばかりの頃だまだ、何をどのように聞いてよいのか判らなかった僕は、当時習っていた先生に「聴いておいた方が良いアルバム」を尋ねてみた「そうだね、パコ・デルシアとマノロ・サンルーカル、そしてセラニートはどうかな?彼らは現代フラメンコギターの三羽烏(いささか古典的な表現ですが 笑)と以前は呼ばれていたんだ」その名前だけを頼りに店で購入したマノロのアルバムは、偶然にもデビュー作であったようだ。古典も現代も何も判らない状態で初めて耳したマノロの響きは、スペインの空気のように乾きながら重厚で、思わず聞き入った記憶がある時が過ぎて、当時、急速に名前が上がりだしたビセンテ・アミーゴというギタリストはマノロの弟子であることを知るようになった。当時の僕からすると、そんな雲の上のような話に強い関心を抱いたわけでもなく「ふーん そうなんだ・・」という感じだったと記憶しているやがて、スペインで修行中のギタリストの友人からスペインのコルドバという土地で「マノロのクルソを受講してきた」と聞いた、彼が語ってくれた、その灼熱のコルドバでの体験談は講座の内容にとどまらず、マノロの音や人柄はもちろん、マエストロと正面から向き合うことの在り方、そして世界中から学びを求めて集まるギタリストの交流から生まれる「その地でしか起こらない何か」等多岐に渡るその話は、僕を魅了するには十分なもので、今、思えばこの時だったのかもしれません「自分が求めている学びとは何か?」そして「僕もそこに参加することは可能なのか?」と具体的に思うようになったのは続く
2022.10.28
コメント(0)
-

マエストロ・マノロ・サンルーカルとコルドバの記憶
先日、フラメンコギターの巨匠マノロ・サンルーカルが亡くなったパコ・デ・ルシアとは違う手法、道筋を辿りながらマノロがフラメンコギター界に残した足跡の大きさや、その敬意の払われ方を知ることになったのは、やはりスペインでの生活経験によるものが大きい、それらは決して「アルバムの作成部数」や「世界でのコンサート回数」等数字として、あるいはデータとして容易に提示されるものとは異なる価値観であり、表層的に眺めていてはうっかり通り過ぎてしまう、また、当地で信頼できる人々からのレクチャーや案内を要するものも多分に含まれていたまた、一年に一度だけ行われる「コルドバ・ギターフェスティバル」のクルソでマエストロの直接指導を受ける機会に巡り合えたことはあらゆる意味で、今の僕を大きく支えることにもなったいつか「コルドバ」で過ごしたこの記憶を記しておきたいと思いつつ「機が熟したら・・」という言葉を理由にそのまま今日まで引き延ばしてしまったもはや、「機を逸してしまったのではないか?」仮にそう問われたなら、その通りなのかもしれない・・でも、その時のマノロのギターの音がまだ頭の中に鳴っているうちに、コルドバのメスキータの木陰で練習していた僕に毎朝「おはよう」と声をかけてくれたその温かさが、また思い出せるうちに少しづつ記していこうかと思っていますいつも通り ノンビリ書いていくことになると思いますがそれはご容赦ください!
2022.10.12
コメント(0)
-
ルーツと巡礼の旅 その15(旅の終わりは始まりでなかろうか?)
讃岐への旅から戻ってこの数か月、頭の片隅に引っかかる何かを常に感じていました。それは、自分が気が付いていないだけで多くの取りこぼしが存在するのではないか?というシンプルな問いみたいものです。今回、様々な図書館でレファレンスを受けながら、其の時点で考えうるほとんどの資料、文献に目を通したものの、当時の時代背景や制度、習慣、宗教観、生活の在り様等の「基本的素養」みたいものが圧倒的に欠如した自分の眼では見抜けなかったこと、気が付かなかったことが無数にあるのでは?そんな自身に対する問いが生まれてくるのは当然のことなのでしょう例えば「菩提寺」という言葉は知っていても当時を生きていた人が、どのようにお寺と関わりまた仏教がどの位生活に密着していたのか、その信仰のあり様などを考え始めてしまうとより深く、そして時間を費やして学んでいくしかないのかもしれません。まずは自分の家と関係性があった「真言宗」「弘法大師 空海」の文献資料などを読み進めながら、それだけでは腑に落ちずより総合的な視点から俯瞰しなければと考えていくとどうしても「天台宗」「最澄」はもちろん、より現代に近い「法然」「親鸞」「道元」等の鎌倉仏教を知る必要があるのではないか?という感じになってしまい、その膨大な内容に圧倒されながらもコツコツ進めております・・・「具合的にどうなるのか?」「どんな役に立つのか?」そういう意味性みたいものを求めずに進んだ時に、その先にどんな風景が見えてくるのか?あるいは何も見えないのか?物理的な移動のみではないそんな旅も悪くないのかもしれません!
2022.10.05
コメント(0)
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-
-
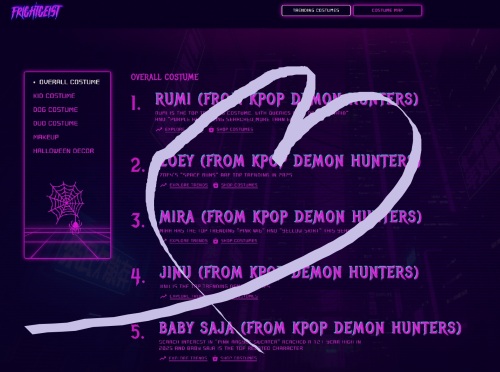
- ♪♪K-POP K-POP K-POP♪♪
- 영원히 깨질 수 없는
- (2025-11-11 06:13:39)
-
-
-

- ギターマニアの皆さん・・・このギタ…
- 【ギター×イス軸法®︎】体軸でギター…
- (2024-08-17 21:14:58)
-
-
-

- 今日聴いた音楽
- ☆乃木坂46♪久保史緒里(MC)『乃木坂46…
- (2025-11-20 05:18:39)
-







