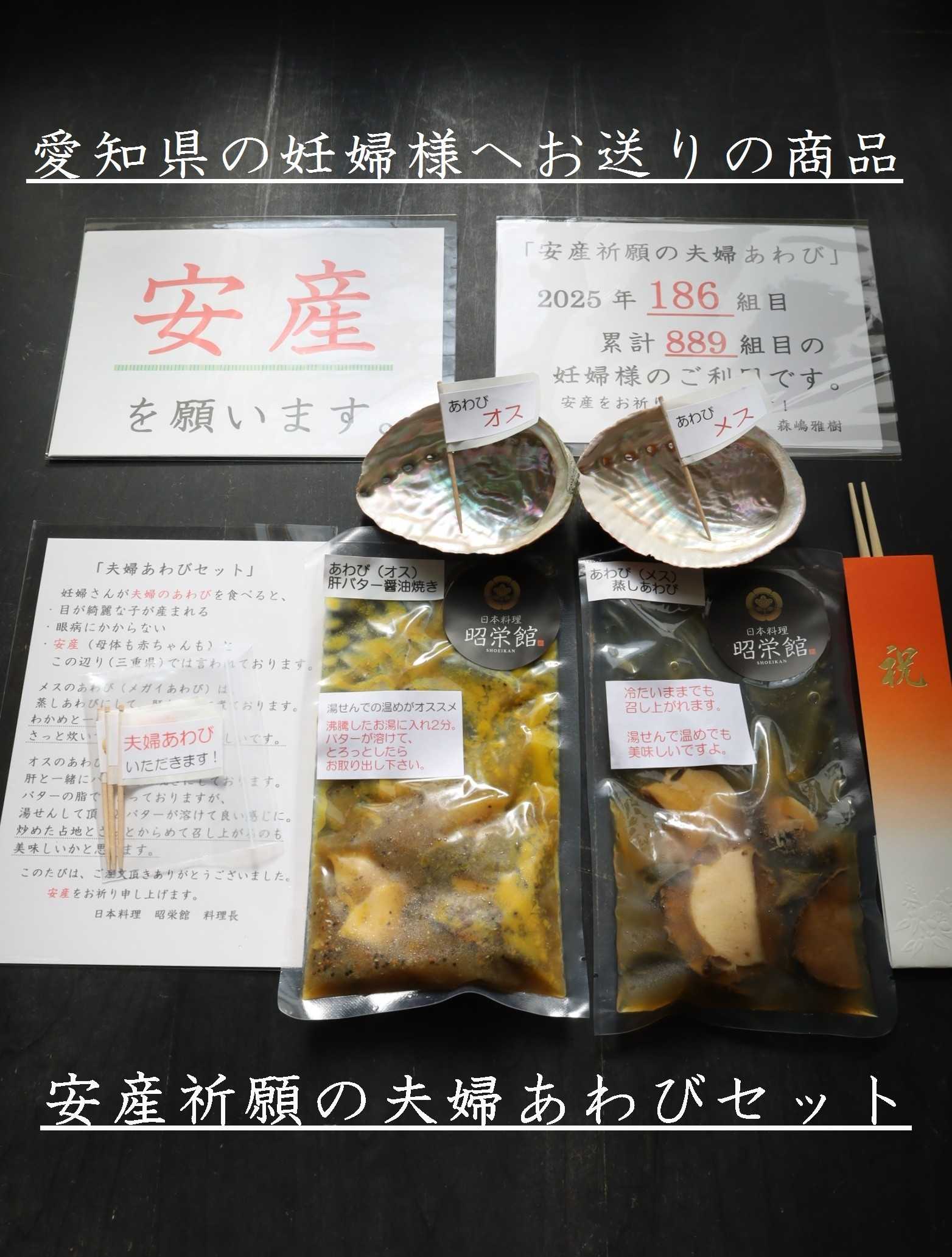全43件 (43件中 1-43件目)
1
-
第4回岐阜ADHD親子の会相談会より《相談-2-》
【相談内容】リタリンの副作用が心配です。【答】リタリンの副作用で、一番多いのは(1)食欲不振、(2)夜、眠らない、 でしょう。(1)に関しては、体重減少の程度により、服薬を継続するかどうかが問題となりますが、一般に服薬を中止しなければならないほど、体重減少を来たした例は、経験していません。 というのは、1か月に2キロ以上あるいは、現在の体重の10%以上の体重減少を来たすことはないからです。 もうひとつの理由は、この食欲不振は、朝服用して、お昼の給食を食べる量が極端に減った、というのがもっとも多く、そのあと、一日のうちで反動で沢山食べている例を多く経験します。 とはいっても、お母さん方にはとても気掛かりな副作用です。そこで私は、2つの基準を提示することにしています。ひとつは、1か月に体重減少が2Kg以内、あるいは体重の10%以内なら、様子をみます。 いまひとつは、その子の身長から、平均体重曲線のグラフを用いて、その身長に対応する平均体重の正常範囲を割り出すことが出来ます。この範囲内に入っておれば、心配ないということになります。この平均体重曲線のグラフは、小児科のお医者さんに見せてもらえます。(2)の睡眠障害は、午後4時以降はリタリンの服用を避けることで、防ぐことが出来ます。その他の副作用としては、滅多にありませんが、(3)異常興奮(4)痙攣の誘発があります。リタリンは元来、中枢神経刺激剤ですので、こういった副作用が起こり得るわけです。痙攣誘発を出来るだけ避けるために、投与前に脳波検査と、頭部断層撮影MRI検査を施行しています。 てんかんの患児にみられるような脳波異常が、痙攣を経験したことのないADHD児に見付かることがあります。てんかんは200人~250人に1人という高い有病率だから、100人に2~3人のADHD児に見付かっても、不思議ではないのです。 そのような場合でも、1)てんかんが発症するとは限らないこと、また、2)リタリン服用後にてんかんが発症しても、自然に発症したのか、リタリンで発症したのか、区別が付かないこと、3)たとえてんかんが発症しても、起こり得ることだという、心理的な準備が出来ていて、早期にてんかんの診断、治療が出来て、しかも小児のてんかんは、成人に比べ、治癒する率が高いこと、4)てんかんで、ADHDの診断基準を満たす子にも抗てんかん薬服用で、てんかんの発作が抑止されても、ADHDの症状がなお存続すれば、リタリンを服用して、けいれんをしょうじた例が無いこと、を親に充分説明して、リタリンを投与して、効果を挙げています。 その他、副作用としての報告は沢山記載されていますが、服用中は年に少なくとも2~3回は、副作用のチェックのために、血液検査、肝機能検査、腎機能検査、血液生化学検査(以上は一回の血液採取で済みます)それに尿検査を受けてもらっています。 このようにして、医師と患児と保護者、それに学校の先生と、治療の輪を作って、それぞれがよくADHDを理解し、根気良く長期間の治療を継続していくことが、大切です。
2003年10月04日
コメント(3)
-
第4回岐阜ADHD親子の会相談会より《相談-1-》
【相談内容】9歳男子、ADHD 1)担任の先生が、突然席変えをして、うちの子をいちばんうしろから、いちばん前の席に変えられてしまいました。ごく自然に、いつも通りの席変えに乗じて変えてほしかったです。 2)先生が他の児童に「○○さんは病気だから。」というふうに説明されました。そのあとクラスの女の子から「特殊学級に入らないといけないよ。」といわれました。 3)家でいくら注意しても、「分った」といって、またすぐ同じよくないことをしてしまい、くどくどと叱る繰り返しです。 4)宿題をぜんぜんやってくれません。【答】 1)まず担任の先生に、ADHDのことをよく理解してもらうことが大切です。それには主治医の先生から、また私のような立場(学校カウンセラー)の者から、担任の先生だけでなく、担任以外の先生にもADHDのことをよく理解してもらい、学校全体として、ADHDの子に適切な配慮と対応が出来る体制を作るようにしていきます。 2)これも先生の理解が適切でないことから生じた問題のひとつです。先生から他の児童への説明として、適切な例は「○○さんはいろいろなものごとに、気をとられがちで、なかなかじっとしていられない性質があって、本人はお医者さんにも相談して、一生懸命直そうとしているところだから、みんなも○○さんを応援してあげて下さいね。」というふうに説明してあげることです。私達は、決して他児の前で「病気だから。」という言葉は使ってはならない、と説明しています。 ADHDは知的には問題がなく、行動面の問題が主です。従って基本的には特殊学級入級対象ではありません。各務原市教育委員会はADHDの取り組みが非常に熱心で、通級学級として鵜沼第ニ小学校に関エリコ先生がおられます。そこに通級することもご相談下さい。 3)ADHDの子が何か良くない行動をした時は、間髪入れず「よくないことだよ。」と注意してやめさせ、本人の興味をそらせたり、場所を変えたりします。そして、またすぐに同じことを繰り返した時は、もういちど叱ります。叱ったり注意したりするのは、2回までとし、3回以上は叱らないことです。3回以上叱っても、効果がなく、叱るほうの心理状態が不安定となり、おかしくなってくるからです。 親がADHDの子をしつけたり、叱ったりする時、一度叱って「分った。」と言って5秒後にはまた同じよくない事をやってしまい、また叱って「分ったと言ってまたやってしまうのです。このようにADHDの子は親を逆なでするように、悪く思われてしまい、母親も辛抱強く、子どもと付き合うことが大切だと、頭の中では分っていても、感情が尾さえきれなく、理性と感情と母親の言動がかみ合わないのが、普通です。とにかく時間をかけて、お母さん自身、かみ合いをみつけていくことです。 4)宿題はひと目見て。「これは多い」と思ったら、最初から取り組む姿勢を見せないのが、ADHDの子の普通の反応です。そこで、担任の先生と連絡を取りながら、ADHDの子用に、その子がやりとげることが出来る程度に、特別少なくしてもらい、減らした量をやり遂げたら、「よくできたね。」と褒めてあげ、自信をもたせ、またやる気を起こさせ、出来たらまた褒める、という繰り返しをして、少しずつたくさんこなせることが出来るようにしていってあげるのです。
2003年10月02日
コメント(0)
-
第4回 岐阜ADHD親子の会-相談会-を開催して
9月28日(日)に、『第4回 岐阜ADHD親子の会-相談会-』を昨年に引き続いて、岐阜大学教育学部附属障害児教育実践センターで、開催しました。運動会シーズンで、前日の土曜日が運動会、という小学校が多く、もし土曜日が雨なら、翌28日(日)になる、というので、その場合はADHD相談会に参加出来ません、とおっしゃるお母さん方が沢山おられました。となると、この相談会がうまくゆくかどうかは、土曜日の天気にかかっていることになります。お蔭様で、心配していた天気も、土、日ともに晴れて、当日は11家族のお母さんと子ども達、それにお父さんも2人、参加して下さいました。11家族と言いますと、10時から2時間という相談時間を考えますと、ちょうどうまく行く人数なので、多すぎでも少なすぎでもなく、ひとりほっとした気持ちで居りました。発達心理学専門で、臨床心理士でもある別府先生と,医療を担当する私とで、来訪された順に相談会を進めていって、予定よりも約30分延びて、12時半ごろに、相談会を終了することが出来ました。進行役の私が、時間のことを考えるあまり、参加者の中には、もっと充分相談を受けたかった、とお想いの方がいらっしゃるかもしれませんが、ついてこられたADHDの子ども達が待っていることを考えますと、相談会は2時間が限界と思われます。これから順次、今回の相談会の内容をご紹介してゆくことに致します。、
2003年10月01日
コメント(0)
-
その後の経緯
こんにちは。さっそくのご返事ありがとうございます。来週の火曜日にひまわり学園の相談の予約がとれましたので、分かり次第ご連絡いたします。何も知らなかったので、保育園も普通の近所の所へ入園させてしまい、約1週間が過ぎようとしています。園の先生のお話では、「テレビを見せている時はじっとしているんですが・・・。」ということでした。(それ以外は動き回っているという事だと思います・・・。)お昼寝は何とか出来ているということと、ケンカなどのトラブルは今の所ないということそれから、本人が喜んで通園しているということが、多少救いになっています。ただ、暴れ回りすぎていて、興奮しすぎているのか、ここ3.4日夜間に必ずぐずります。 又、ご連絡します。【お返事】 ひまわり学園の予約がとれて、よかったですね。学園では、丁寧に相談に乗って下さいますので、ご安心下さい。
2003年05月14日
コメント(0)
-
ADHDでしょうか?
【質問】はじめまして。3歳の男子を持つ母親です。3歳時検診をうけた所、言葉が遅いので、言語の先生に相談した際、発達の方に問題ありと言われ来週ひまわり学園(大垣市)に相談に行く事になりました。はじめはとてもショックでしたが、ADHDである(かもしれない)ということが少し分かり、少し安心?(今まで、どうしてこの子はこうなんだろう、私の育て方が間違っているからなのか・・・?という自問自答ばかり繰り返していました。)しました。(安心というよりも納得)ただ、これから先、具体的にどの様に接していったら良いのか、就学、就業(就業できるのか?)するにあたってどうしていけば良いのか、支援機関などは近くにあるのか等々、分からない事ばかりです。何かアドバイスを頂けたらと、思いメールしました。宜しくお願いいたします。【答】お子さんのことで、さぞご心配のこととお察し致します。発達に問題があるということですが、少なくとも3歳ではADHDもしくはその疑いとは言えません。ADHDの場合は4歳、5歳と年齢とともに、多動、不注意、衝動性が年々ひどくなっていって。年長組で、診断可能です。 心理面に問題のない発達障害、もしくは広汎性発達障害が疑われると思います。ひまわり学園の判定を、よろしければお知らせ下さい.。
2003年05月12日
コメント(0)
-
アメリカ在住のお母さんからのご質問-2-
【質問】 私共はここ10年間ずっと米国A州在住で、昨年引っ越しまして来ましたのも車で2時間程の所からです(2年前、長男が2歳の時に日本から移住しました)。 子供達は英語が母国語ですが、日本語でも会話出来ます。特に相談致しております長男は、流暢な日本語です(私の日本の家族と交流が一番多かった為だと思います)。 息子は幼少から興味が次々と移行し、目まぐるしく動き回りました。でも最初の子でしたので当初は随分活発な子だな、位に思っておりました。未だにテレビ等を見ていても、何処かしら爪や洋服噛んでいたりします。 突飛な行動(テレビにわざと水をかける、体温計を電子レンジで暖める、公園等の噴水に入ってしまう、注意してもマッチ等で火遊びする)を取って物を壊したりで、周囲を困惑させて来ました。 忘れ物、無くし物もしょっちゅうで殆ど人のせいしたり、忍耐が無いので何でもすぐに放棄してしまう性格です。大声で雄叫び声をあげる事も多々あります。 幼稚園の年長時、担任の先生から息子がなかなか左右やアルファベットをなかなか覚えられない事等で耳に障害があるのでは?と聞かれた事もありました。現在も何度も読み書きが4年生レベルと補修塾からも言われております。(ADHD教育で学位を取られた補修塾の先生も息子は軽度のADHDと学習障害があるのではないか?と仰られました) 小学生の時も、社交性が低く友達を作るのが苦手で時間がかかりました。小さい頃からの経験で自分を全面に出すと皆に叱責される、嫌がられると分かっている為か、学校では自分の短気やすぐに席から立ってしまう、乱暴してしまう等衝動のを一生懸命に抑制して来た様子です。そして帰宅すると、爆発、と言う感じが何年も続きました。そして本人からも何故か授業中すぐに違う事を考えてしまうと聞かされました。 それでも学校をずる休みしたり、学校へ行くのを拒絶する事はありませんでした。彼が小学校3年生の頃、注意欠陥多動症、と言う障害の記事を読み特徴や症状が酷似しているので驚きました。 考えて見ると、母親の私が多動の少ないADDの症状が子供の頃から多くあったのに気が付きました。息子と不器用さや性格も良く似ています。 中学校に通う様になり、今迄に無く学校で緊張して登校前に嘔吐する様になり小児科に連れて行き、医師に今迄の経緯をお話し、学校の先生方にも息子に関する書類を作 成して頂いた結果、医師から刺激剤の薬物治療を勧められました。が、副作用等の理 由から、すぐには服薬しませんでした。 そして昨日のメールでもお話しました通り、現在不登校に至っております。 5歳の頃から叱責され続け私を憎んで来た事、学校で授業内容が理解出来ない、課題が時間内にこなせない不安を抱え、数人からイジメられていたのに強制登校させた親、学校カウンセラー、医師達に対する不信感を泣きながら吐露しました。 私は傷付いた息子を休ませてあげたい気持ちと、何でも困難になるとすぐに放棄し逃避する性格を矯正しなくてはいけない、という責任感が葛藤し、不登校させる迄随分と悩みました。 しかし、家で何する事も無く一日中テレビを見て、私の言う事に反抗し私が憎いと罵る息子を見ながら、とても不安です。 カウンセラーは登校する様にかなり息子にプレッシャーをかけるので、今週は休みました。登校せず家に居るなら罰を与える様に、とも言われました。そのカウンセラーとは馬が合わないと感じたので、新しいカウンセラーを捜そうとも思っています。【返答】 私は小児神経専門医ですので、決して不登校児専門ではありません。その点は充分ご 理解下さい。ただ、小児科医は専門のいかんを問わず、不登校児の問題を、専門外だ からと言って、避けられないのも、日本の現実です。ご存知のように、日本では不登 校児が増える一方で、中学生では12万人を越えています! 私なりに出来る範囲内で、助言を試みることに致します。1)お母さんのメールからは、1)集中力の欠如、2)注意の持続欠如、3)多動、4)衝動性 が当てはまります。 忘れ物、無くし物もしょっちゅうで殆ど人のせいしたり、忍耐が無いので何でもすぐに放棄してしまう、大声で雄叫び声をあげる事も、ADHDの徴候ととらえてよいでしょう。2)幼稚園の年長時、なかなか左右やアルファベットをなかなか覚えられない事、現在も読み書きが4年生レベルというのも、ADHDがあ り、未治療で、学習困難なため、学習を獲得されていない状態と考えられます。これは「学習障害」とは呼びません。ほとんどのADHDは、未治療の場合、学習困難で、習得不十分なまま、進級させてしまうから、お子さんのようになっ てしまうのです。3)ADHDの子は成長とともに、周囲への配慮は出来ていくので すが、基本的には治療しないかぎり、問題行動は引き起こす事になります。 お子さんは多分ADHDであって、副次的に上述の問題が生じて、不 登校になったと考えるのが、自然な考え方と思います。 4)お子さんのカウンセリングには、順序が大切です。今お子さんは傷付いているのです。その傷を癒さない限り、何を させようとしても、傷が治らないか、さらに傷を深くすることになるのではないでし ょうか?5)何でも困難になるとすぐに放棄し逃避する性格;は、もとはADHDから生じてい るように思います。解決法のひとつに、ADHDの薬物治療があるわけです。6)「家で何する事も無く一日中テレビを見て、私の言う事に反抗し私が憎いと罵る息子 」さんは、どこにでも見られる不登校の中学生の徴候で、それ自体、理由付けをして もしなくても、どちらでもよいことです。 登校する様にかなり息子にプレッシャーをかける、登校せず家に居るなら罰を与え る;ことは絶対に避けなければならないことです。大切な事は、不登校児に精通したカウンセラーに依頼することです。アメリカでそ のようなカウンセラーが見つかるのかどうか、私には分りませんが、どなたかにお聴きになってみて下さい。7)お子さんは今は、医療(服薬)の助け無しで は、解決しないと思います。教育やしつけでよくなる、というレベルははるかに超え てしまっているからです。 服薬をお勧めします。理解のある医師の指導のもとで。お子さん自身が、これでは 大変だ、なんとかしないと、という気持ちにさせるのが、親や教師、周囲の大人の役 目です。そして本人が自分で、服薬しよう、と決心したように、もっていくのです。 8)メチルフェニデートに、「刺激剤の為に対人関係や勉強に対する不安が強まってしまっては、学校へ復帰したり、社会へ出る事が更に困難になる」ような副作用はありません。 以上が私にお答えできる精一杯の助言です。付記:1)ADHDの診断はおそらくあっている、と思います。メチルフェニデート(日本 ではリタりン)は抗うつ剤ですが、ADHDの60%以上に有効です。ただし、服薬 開始が小学3年以上と2年以下とで、効果がはっきり低下します。今では小学入学1 年前に治療開始して、入学後すべてが順調にゆくように、私自身が3年前から始めた のですが、今ではアメリカの小児神経医が私の実践と同じことを勧めておられること を、学会で知りました。2)服薬は、決して、多動を抑えたり、学校でうまくやってゆくために、ではありま せん。服薬によって、本人が落ち着いて必要なことを、必要な時期に、必要な場所で 身に付け、その結果、将来社会人として自立できる大人になってもらうために、服薬 する、のです。3)薬に副作用のないものは、ありません。その中でも、リタりンは、ADHDにと って、それほど副作用を恐れて、服薬を拒否するようなものではないと考えていま す。もちろん、副作用のために、服薬中止例があるのは、当然で、致し方ないこと で、だからといって服薬は駄目だということにはならない、と申し上げているのです。4)家庭内暴力が出てくると、セレネースのごく少量が有効なことがあり、試みてい る治療法です。薬万能では決してありません。服薬と並行して、カウンセリングを行 います。服薬しないと、カウンセリングも空振りになるのがほとんどだからです。5)ADHDも不登校も、日本では本当に大変な状況です。文部科学省もやっと重い 腰をあげ、全国的な取り組みが始まりますが、遅きに失した感が致します。教育界と 医療との連携のまずさ、および日本人独特の教育観、医療への不信感が、問題解決を 遅らせ、悪化させたものと、私自身は考えていますが、私自身は個人の力でできることをやるのみ、です。ご参考になれば幸いです。お子さんがよい方向に向かわれますように。 三 牧 孝至
2003年03月22日
コメント(0)
-
アメリカ在住のお母さんからのご質問-1-
【質問】はじめまして。私は米国に夫(米国人)と4人の子供達(12、10、8、6歳)と暮らしております30代前半の主婦です。 突然で恐縮ですが、お時間があれば息子12歳(6年生)の事で相談に乗って頂けるでしょうか? 昨年秋、小児科医から注意欠陥多動症の可能性が高いと診断されましたが、薬物治療は開始していません。 状況をお話しますと、私達は昨年夏、現住居に引っ越して来ました。この地域は6年生から中学生になり、新しい環境で友達も出来ない中、授業は毎時間生徒も先生も教室も変わるという緊張感や勉強に対する不安、またイジメにも遭い、嘔吐や腹痛を訴えました。 最初の内は私も登校を強制していましたが、今年に入ってから死にたいと言う様になり2月からは完全に不登校になっています(夫は将来を心配して早く学校に戻したい、と非常に焦っておりますが)。 しかし、こちらのカウンセラーや小児科医から登校する様に言われますと、息子は興奮状態になり私に暴言を(私が憎い、死んで欲しい等)吐き続けます。泣きながら自傷行為(ベルトやネクタイを首に巻いて締め付ける)も2度いたしました。朝、布団の中で泣いている時もある様です。 息子は鬱病気味だと思い、なるだけ楽しく一緒に時間を過ごそうと私も怒らない様に気を付けて暮らしています。私の方が息子が可哀想だ、また爆発されると恐い、と思っているのも確かです。 それでも家で好きなテレビをずっと見ている時や自分の好きな事をしている時は以前の普通の息子で楽しそうにしています。 昔から弟達や妹の邪魔は日常茶飯事でしたが、不登校になってからはそれが執拗になり、暴力的にもなってきました。私の言う事も聞き入れず、俺に指図するな、と暴力を振るったりして反抗するだけです。父親の言う事もあまり聞きません。 不登校になってから反抗的、暴力的になった、と言う話は聞いた事がありますが、息子の場合はかなり以前からあまのじゃくで嘘もよくつきました。私は思春期になって反抗挑戦性障害が併発したのでは無いかと危惧しています。 夫は忙しく家に殆ど居ませんし、このままでは私の方が参ってしまいそうです。体重も減ってきました。 息子も苦しいでしょうし、とうとう薬物投与が必要では無いか、と言う時期に来ていると思います。 こちらの小児科の先生には、ADHDの為の刺激薬(アデレール)は神経症状を増加させるので、もし不安が強いならば抗鬱薬の方が良いと説明されました。 しかしここ最近は時々、自分が緊張する様な場面に出会うと静かになり腹痛を訴える程度で、鬱傾向は良くなって来ている様に見えます。 そんな中、本人が別の学校なら行ってみても良いました。早速夫が珍しいスタイル(自分のペースで学習を進めて行く)でいつでも入学可能の小規模の私立の学校を見付け、今日息子と見学に行って来たのです(しかし、予想通りその後数時間は気分が悪くなっていました)。もしその学校へ行く事に決めても、彼はまたとても緊張すると思うのです。 先生、リラックスするにはADHDの刺激剤は逆効果なんでしょうか?また反抗挑戦性障害に関しては効果はどうなのでしょう?また息子が薬を拒否する可能性も大です。その時、私はどう対処したら良いのでしょうか?御多忙とは思いますが、先生のお考えを教えて頂けたら幸いです。【返答】 異文化の社会で生活するだけでもいろいろと大変なのに、お子様のことでお悩みのご様子、お察しするにあまりあるようです。 問題点と解決への手がかりを整理してみたいと思います。1)まず、お子様は、最近アメリカに移り住まわれたのでしょうか?それとも、ずっと長年お住まいなのでしょうか?最近移り住まわれたのでしたら、異文化社会への不適応だけで、すべての症状が説明できるからです。その場合は、お子さんのような症状が、ここまで強く出て来ますと、日本に帰国するのが、一番よい解決策と思われます。2)ずっと長年お住まいでしたら、ADHDの診断が正しいとすれば、いろいろな問題行動は、ADHDそのものから生じる症状と、ADHDに合併した症状として、説明が付きます。 この場合、ここまで症状が進みますと、服薬が不可欠ですが、効果の期待度は低くなります。服薬も初期で、低年齢のほうが、高い効果が期待できるのです。通常、5歳から7歳に開始しますと、高い効果が期待できます。3)不登校に対して、登校を強制するのは、適切でない方策で、逆効果と考えられています。まず悩みをかかえた本人の心に寄り添ってあげて、本人のよき理解者になること、そうしてその子のかかえている心の悩み、不登校の原因は何かを、見つけだす努力をすることが、大切です。4)暴力的、反抗挑戦的な態度は、ADHDから不登校、ADHDから反抗挑戦性障害、の構図と思われます。薬物治療では、中枢神経刺激剤で、抗うつ剤でもあるメチルフェニデートが第一選択薬です。この薬で、随分穏やかになり、落ち着きを取り戻されて、集中力が出て来て、本人にとって必要な学習、知識の獲得が促されていくのです。 家庭内暴力を含め、暴力行為には、少量のセレネースが有効な場合があります。
2003年03月19日
コメント(0)
-
あるお母さんの悩み
【問】長男(4歳)がADHD です。2歳のころから 検診にいくたび 『この子おかしいよ』といわれ、A病院のBDRのところにも いきました。でもその時は「ふつう」という診断でした。まだ3歳になってなかったころです。いまは保育所にかよっています。時折普通の子供とはべつのことを、しているようです。生後半年ぐらいからはじまった指すい(おやゆび)もいまだになおりません。これもなやみのたねです。ことばはすこしずつふえてきましたが、いまひとつです。まねっこができず、いらいらすることもただあります。 こんなんじゃ、ママ失格ですよね・・・つらいです。ほんと、どうしていいのかわからず、はずかしながら気がつくと、怒りんぼママになっています。 こんなどうどうめぐりの毎日です。どうかたすけてください【答え】 メールを拝見致しました。お母さんとしての子育ての難しさ、悩み、葛藤、そしてそのあとに残る「母親失格」という自己嫌悪.......子育てってどうしてこんなに大変なのでしょうね。なんでもない子はなんでもないのに、と思われることでしょうね。 4歳の長男がADHDということですが、専門の医師の断なのでしょうか?私自身、4歳ではADHDの診断は非常に難しいと思われます。年長組(5歳)まで待ってから診断するようにしています。と言いますのは、正常の発達の3才児や発達の送れのある児は、立ち居振る舞いが、ADHDに非常によく似ているからです。 ADHDは基本的には知能発達、言語発達は正常です。お子さんの場合、まず言語発達の送れがないか、知的発達の送れがないか、さらに言語性知能指数と動作性知能指数に歪みがみられないか、を確認することが大切と考えられます。 ADHDの診断は5歳でも6歳でも、遅くはありません。治療による効果も差がありません。ただ、小学入学前に治療を開始するほうが、小学入学後、学校生活、本人の知的発達、学習面で、より効果があり、より成果が上がります。 ADHD以外の発達の上での障害の場合は、今の4歳の時点で診断可能な場合があります。その中にはむしろもっと早く診断して、療育を開始するほうが、本人にとって、よりよい結果が得られる障害もあります。 以上、まとめますと、小児神経専門医(小児科または小児神経科)、もしくは児童精神医学専門医(精神神経科もしくは小児専門病院)による正しい診断が先決です。その診断に基づいて、療育を進めてゆきます。【お母さんからのお返事】きのうは ありがとうございました。いきなりの メールにもかかわらず ごていねいな返信を早速いただき お礼申し上げます。まだ 専門の先生に診ていただいたことはないのですが住まいが小さな村なもので、検診のたび、この子があまりにもおちつきがなく、よその子とはあきらかにちがうので、まわりの人たちにいろいろいわれたあげく、「自閉症の多動症やで」といわれ・・・たくさんきずつきました・・・あたるところもなく、実は姑が20年前に入院歴のある、いまもくすり療養をしている精神病をわずらっているひとなんです。で、ある日『隔世遺伝』と言う人がいて、こころのなかで、姑をうらんでみたり、あたしのほうが精神病ですよね・・・でも先生の言葉で、救われました。この子は 1999年3月10日生まれで、クラスのなかでは、一番最後の誕生日・・・もうすぐ 5歳になるお友達とおんなじこと、できるほうがすごいんですかねぇ?この子の下に、1歳の妹がいますが、この子の1歳のころとは全然ちがいます。男女の差があるのでしょうか?また、相談させてもらってもいいですか?よろしくおねがいします。【お返事】 メールを拝見致しました。前のメールでおよそ大切なことは述べたように思います。今回のメールで気付いたこと、問題点を整理してみますと、母親として、1)この子は本当に障害があるのだろうか?と言う疑問と障害はないのだ、と思いたい気持ち、のあいだで、揺れておられる、ということ、 2)専門の医師に相談するのが最も良いことだ、ということは充分理解できたが、もし障害があるといわれたら、どうしよう、という恐怖・不安を抱いておられること、3)現実には、医療機関が無いか、遠いか。周りの他人はいろいろ忠告はしてくれるが、かえって悩みが増えて、心の傷は癒されるどころか、深くなる一方、医療機関を受診するには、現実にいろいろ障壁があり、これは私自身のせいではない(遠い、下にもう一人手のかかる子がいる、身内にいろいろ助けてくれる者がいない、この子がこんな状態なのは、姑の隔世遺伝かもしれない、など)という責任転嫁によって、自己の正当性を見出そうとしている自分。といったところでしょうか?1)は早くはっきりさせることが、解決の糸口になります。2)は、すぐれた医師なら、母親の心理を充分理解して、お子さんの障害の有無、内容、程度について説明し、その後の対応、療育の必要性の有無、経済的負担まで、説明してくれるはずです。 3)は結婚して配偶者と同居しておられる場合は、配偶者の協力が第一に重要です。医療機関については、この交通網が発達している日本で、私達は、「遠方だから受診出来ない」場所は、日本には無い、と考えています。と申しますのは、私の知り合いのクリニックには、世界各国から受診してこられるからです。交通費が出せない場合は、各自アイデアを出していただくしか方法がありません(募金を募る、身内で工面する、など、-サラ金は手を出さないこと-)。医療費に関してなら、ご相談に応じます。【付記】 メールによるご相談はいつでもお受け致します。ただ、そこにはおのずと限界があり、今回のお母さんからのご質問のように、メールによるやりとりでは、解決しない場合が多く、そのような場合は、私自身は面談による相談とお子さんを診せて頂くことを、お勧めしています。 面談による相談とお子さんを診せて頂くことから、問題点をより正確に見つけ、解決法を養育義務者(通常はご両親)とご相談して、その子にとって最も適切な療育は何かを、決めていくことになります。
2003年03月15日
コメント(1)
-
ADHDと適正就学相談
【問い】私の長男(小学校3年生)が、今年の5月にADHD傾向。7月にADHDと診断されました。 学校から勧められて、近くの国立小児病院の精神科を訪れ、田中ビネーとWISCを受けての診断でした。 年長さんの夏までA市に住んでいました。そこで通っていた保育園では「落ち着きはない時もあるけれど、みんなのリーダー格で頼りになります」と、先生に言われていました。 主人と私の転勤でB市へ引っ越してきてから通った保育園からは頻繁に呼び出され、落ち着きがない、人と同じ事が同じ時に出来ないと言われました。 小学校へ上がってからは官舎の子供達となじめずにいじめられていました。その頃から、学校へも頻繁に呼び出されるようになりました。 最初はクラスの中でうろうろしている。そのうち、お友達のものを隠した。盗った。壊した。と言う内容でした。子供も悪かったのですが、注意してもどこか「聞いていない」感じを受けました。 ある冬の日学校で物がなくなったとき、息子が疑われ(結果息子が盗ったんじゃなくて、定位置にあったのを担任が見落としていたのですが)担任に、鞄の中を引っ張り出され、まだ隠してるかも知れないと裸にされているところに出くわしました。子供は「僕じゃない、僕じゃない」と言ったけど、信じてもらえなかったことにショックを受けて、学校へは行くけれど教室には入れず学校の中を徘徊するようになりました。 そのうち、障害児学級の担任の先生(今は教頭先生になりました。)が障害児学級で保護してくれるようになりました。そのころ、診断を受けるよう勧められましたが、私が受け入れられず、診断は受けませんでした。2年生になったときも、籍は移さず障害児学級と、普通学級を往復する生活を続けていましたが、障害児学級の先生の指導と、学校側が担任を変えるなど配慮してくださったので、快方へ向かったとして、障害児学級への出入りをなくして、純粋に普通学級の子として3年生は行こうと言うことになりました。でも、やはり、落ち着きが無く、教室の中をうろうろしたり、みんなと同じ事が同じ時間に出来ないと言うことで、再び診断を受けるよう勧められ、小児病院へ出向きADHDと判断された・・・と、言うのが今までの大まかな経緯です。 ご相談したいのは、今後のことについてです。学校側から「来年度はADHD児として障害者学級へ・・・」というお話が来ています。最初は、それがいいんだろうと思い、こちらもそのつもりにしていました。でも、ADHD児であることだけで、障害児学級へ入れるのか。邪魔にされてるだけでは無いだろうか?今は薬療もうけて、ある程度の行動はコントロールされていて、時折保健室で過ごすだけなのですが、4年生になると、保健室に行くことも制限されてしまうのか?いろいろ思いが錯綜して、学校側に返事を保留にしてもらっています。 小児病院のDrからは、「知能も高くて、授業の内容がつまらない物に感じてうろうろしてるだけだろう。以前の結果からすると、最近の検査結果も向上しているし普通学級で充分やっていけると思う。ADHD児という特性を学校も認識しているし、これから4年生・5年生と成長していく中で改善されていくだろうから、普通学級に居た方がいい。友達との関わりもこれから益々大きくなっていくし、一番重要な頃だから。学校側が、手のかかる子をひとくくりにしたくて特殊学級へ勧めているように感じる」と言われました。5月に受けた田中ビネーでは生活年齢 8歳7ヶ月精神年齢 10歳0ヶ月知能指数 117所見 8歳級不合格 文の構成(A) 共通点(B) 9歳級合格 話の不合理(B) 10歳級すべて合格 等とありました。先日受けた田中ビネーでは、生活年齢 9歳3ヶ月精神年齢 11歳6ヶ月知能指数 124所見 9歳級不合格 図形の記憶(A) 10歳級全部合格 11歳級合格 話の記憶(B) 話の不合理(C) 積み木の数(A) 12歳級合格 絵の不合理(B)とありました。7月に受けたWISC-?の結果は言語性 94動作性 121全検査 107言語理解 99知覚統合 126注意記憶 82処理速度 86 言語理解 知識 11言語理解 類似 11注意記憶 算数 6言語理解 単語 8言語理解 理解 9注意記憶 数唱 8知覚統合 絵画完成 11処理速度 符号 9知覚統合 絵画配列 13知覚統合 積み木模様 18知覚統合 組み合わせ 14処理速度 記号 6というものでした。Drはこれを説明してくれましたが、詳しいことはよく分からないままですが・・・これを見る限り充分普通学級に適応できるはずだ(少しの配慮をもらえば)と、Drは言うのです。 学校側からは、親やDrが見ているよりも長い時間学校で過ごしている。その中で学校生活に支障を生じているから・・・とも言われました。 本心では出来ることなら普通学級へ居て欲しいと思います。どうしても、私の中では「邪魔な息子を排除したいんじゃないか?」と言う気持ちと、障害者学級という名前への偏見が捨て切れません。 でも、障害児学級でいることが息子にとって良いことならば、見栄を捨てて障害児学級へ行かせることも考えています。 Drと学校の言うことが正反対で、私の考えもまとまらないまま2学期が終わりましたが、障害児学級へ入る、入らないの返事は3学期のはじめにはしないといけないので悩んでいます。 出来れば、よいアドバイスをいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。 【答】メールをいただき、ありがとうございます。こういう相談を、適正就学相談と呼んでいます。答は、非常に明快です。ADHDの診断が正しい、という前提で、1)普通学級が適切です。2)現時点では服薬が必要です。いずれ不要になる可能性は充分あります。今迄に服 用していないとすれば、3年生からの服用でも、うまくいっている例があります。3)主治医と担任(学校側)との話し合いが必要です。(親が仲介します)この3条件がそろってはじめて、普通学級での就学が可能になります。どれかが欠け れば、普通学級は無理です。かえってお子さんの状態を悪化させるからです。主治医と担任とよく話し合って、感情的なしこりを残さないことも大切です。 三牧 孝至 【その後の経過】ご無沙汰しております。B市の高木です。以前障害児学級へ入れるか否かで相談のメールをお送りした者です。お忙しいところ、相談に乗って頂きました結果を報告します。 結論を出したのは1月下旬になりますが、学校の申し出のとおり情緒障害児学級に入ることになりました。 主治医とも何度も話をしていきました。学校側とも何度も話をしていきました。三者懇談は主治医が申し出てくれましたが、結局実現せずに結論を出すことになったので、自分の気持ちの整理がつかず、報告が遅れてしまったことをお詫び致します。 ただし、服薬の効果はとても顕著に現れていて、増量したとたん、まだ教室内でうろつくことはあるにしても教室から外へでていくとか、校外へ出ていくと言った行動はなくなりましたし、友達との関わりの中で口論になったとしても自分で自制したり、友達の取りなしに応じることができるようになってきました。 スポーツ少年団でバスケットをしていますが、監督からもすこしずつ信頼を受けているようです。このあいだも、監督に「お母さんちょっと・・・」と呼ばれ、話をしたのですが(ADHDであることは監督にはまだ言っていません)以前は指導するとふてくされて隅っこで泣きじゃくっていたのがいまは自分から何処が悪いからうまくいかないのか聞いてくるようになってきたけれど、なにかあったんですか?と聞かれました。 3学期に入ってから学校からの呼び出しもなく、とてもうまく回っているように感じます。息子が無理をしすぎないように気を付けてはいるつもりですが、息子本人も服薬の効果を実感しているようで、「イライラが止められないとおもったら、薬飲み忘れてた」と、以前ほど薬を飲むことに抵抗もないようです。 結局学校の言い分を全面的に聞くことになったので障害児学級に入るにあたって学校へは条件を付けました。本人や他の生徒に障害児学級に籍があることを気付かせないような配慮をお願いしますと。息子には、どうしても自分の中にあるイライラを収めきれない時に自分を見直す場所として障害児学級の教室を利用してもいいことになったと伝えました。いずれ本当のことを伝えなければいけないのでしょうが・・・ ほんとうにありがとうございました。そしていつも不躾なメールで申し訳ありません。
2003年03月11日
コメント(0)
-
K市のNさんへ
メールでお返事してもうまく届かないようです。メールアドレスは正しいのでしょうか?仕方がありませんので、これをご覧下さい。ご覧になったら、ご連絡下さいね。===========================================メールで最近の様子をお知らせいただき、ありがとうございます。私自身、この年齢になりますと、いろんな人物に巡り会ってきていますので、いろん なお医者さんがおられることも、充分理解しているつもりです。どうもお子さんには ふさわしくない先生に、巡り会ってしまったようですね。H先生とよくお話なさって下さい。<最後に、ひとつ質問があります。薬は毎日飲み続けるようですが、息子は「今日は 飲まない。」と、飲まない日が多くあります。今は無理に飲ませていませんが、そん な時でも飲ませたほうがいいのでしょうか?>この場合、「今日は飲まない。」と言って、飲まなかった日は、振り返って、うまく いった一日でしたか?飲んでおられるお薬がリタりンでしたら、ドラッグ・ホリデイ と言って、飲まない日があっても、効果や身体にはまったく差し支えありません。ただ、ADHDで、服薬開始して、数ヵ月でうまくゆくことは、普通ありません。つま り、飲まない日は、本人がそれでよいと思っていても、まったくうまくいっていない ことが、ほとんどです。2年生でADHDは治ることは通常はありませんので、服薬は本人ま かせではだめだと、考えて下さい。その前に、本当にADHDですか?私の助言はそこから出発します。本当にADHD なら、リタりンは学校がある日は、毎日服用をお勧めします。本人にも2年生なりに自 覚させて、親が、服薬を決めるのですが、お子さんが決めるように、仕向けていくのです。そうしないと、ADHDの治療はうまくゆきません。もっとも、服薬により、 お子さんがなにか不快なこととか、食欲が低下したとか、いやなことがあるために、 お子さんが服用したがらない場合は、主治医の先生とよく相談して解決することが必 要です。お宅のお子さんの場合は、その主治医の先生との信頼関係が出来上がっていないようですので、スタートからやり直しをおすすめします。英語では reassessmentといいます。多分H先生も同じような考え方で、お話されると思います。終わりに、私の好きなことばを述べさせていただきたいと思います。「過去は反省はしても、後悔はしないで。未来はこれから創っていくことが出来るのです。」 三牧 孝至
2003年03月06日
コメント(0)
-
「8歳男児。ADHDではないか心配です。」
【ご質問】始めまして・・8歳の男の子ですが最近ADHDが一般に知られてテレビなどで特集がくまれたりしたのを見て「もしかして・・・」って気持ちです。今、気になることは何度も同じことを教えてもできていないってことです。例えば「ご飯を食べるときはお茶碗を持ちなさい」と一度の食事に何度言うことでしょう。「ご飯のときも足がコソコソ動いたり食べながらボーっとしたり」 「宿題をするとき特に漢字なんかはボーっとして時間だけがすぎていきます」 「学校へもって行く鉛筆はかじってボロボロになったり消しゴムも細かく切ったりしているようです」 「トイレも流さずに出てくることもしばしばあります」 「一人で歩いているときでも何かしゃべっています」 「買い物に行くと必ず迷子になります」 「ダメと禁止していても必ずしてしまう」歯科矯正をしているのですが2度も壊してきました 「興味があるとそちらに気がいってしまう」 二年生なので「こんなものかも・・っと思えば思えることなのですが・・・・ 授業中も席を立つこともなく話をすることもないようです。学校では友達と仲良く遊びルールも守れているようでトラブルはありません。学校のテストなどは平均80ぐらいはとってきます。弟の面倒も良く見ることができます。 おかたずけはこちらが言えば嫌がらずにできます。電車などに一人で乗って出かけることができます。時間割などは言わなくても自分でやります。いいところはたくさんある子なのですがADHDの本などを読んだとき「当てはまることがあるな」っと思ったのでメールいたしました。先生はどう思われますか?【お答え】まずADHDの診断基準に当てはまるか、考えてみましょう。お母さんの記述(上記の)だけで考えますと、ADHDの診断基準のうち、「不注意」の項目の(c)直接話しかけられた時にしばしば聞いていないように見える。(d)しばしば指示に従えず、学業、用事、または職場での義務をやり遂げることができない(反抗的な行動または指示を理解できないためではなく)。の2項目、および「多動性」の項目のうちの(a)しばしば手足をそわそわと動かし、またはいすの上でもじもじする。が当てはまると推察されます。しかし、「6項目以上が6か月以上続く」という診断基準に適合しません。発達の送れが最も考えられるのですが、平均80点が取れるお子さんですので、いわゆる「知的障害」ではなさそうです。他児ともうまくやっており、コミュニケーション障害はありませんね。とすると、あと考えられることは、心理的に不安定な状況にある場合、親子のコミュニケーションに問題がある場合、小児神経症、などが考えられます。今後の進め方としては、学校での様子を知ること、担任もしくは第3者による観察に基づく児の判定が重要です。それで小児神経専門医あるいは児童精神科専門医の受診が必要かどうかを決めることになります。
2003年02月20日
コメント(0)
-
学校訪問の大切さ
昨年暮れに、A小学校を訪問し、通常学級に在籍している、行動面に問題のある児童、特殊学級に在籍中の児童について、実際の学校での様子を観察させていただき、ひとりひとりについて、担当の先生方と協議しました。 こうして現実の学校生活を観察して、毎回思いますのは、診察の場だけでは、小児の行動面に問題を持ったお子さんの把握、判定、薬剤治療とその評価にあたって、大きな限界がある、ということです。 さらに、実際の行動、学校での様子観察することによって、その解決策が比較的容易に見出せることが少なくありません。 これからも出来るだけ学校訪問を進めていこうと考えています。
2003年01月09日
コメント(0)
-
学校での様子-(2)-
S小学校を訪問しました。この小学校には、ADHDが軽快して、お薬を止めることが出来たA君がいます。そのA君、はたして本当に学校でお薬無しで、うまくやっているかを、確認するのが、今日の学校訪問の目的です。先日、クリニックを受診してくれたA君。本当に『よくなってね。』という印象を受けました。服薬前とはまったく違って、服薬を中止した状態で、大人しい、良い子なのです!ところが、診察室での様子と、学校でのその子の態度に、大きなギャップがある場合をよく経験しますので、今回のように、学校訪問して、確認する必要があるわけです。今日、訪問してA君の学校での様子を見せていただきますと、本当に『よくなった!』ということが、確認できました!A君、心から『おめでとう!』お母さん、本当にお疲れ様でした。
2002年12月19日
コメント(0)
-
15歳のM君
M君は15歳のADHDです。リタリンを服用して学校ではずいぶん落ち着いて、勉強も出来るようになりました。このM君、1か月前に、いとこの小学校4年生のSちゃんと遊んでいて、突然Sちゃんの下着を脱がせて、身体を触ったので、Sちゃんはびっくりしてしまい、それ以来、Sちゃんは心理的に不安定な状態で、男性を見ると、おびえるようになってしまいました。Sちゃんのお母さんも精神的ショックで、落ち着きを無くしてしまい、M君とSちゃんが遊んでいるのを見ていたおばあちゃんまで、『わたしがよくみていなかったから、大変なことになってしまった。』とふさぎ込んでしまいました。よく話を聞いてみると、今回が初めてではなく、2回目であることが分かり、Sちゃんの両親は、怒りをあらわにしています。問題点として、1)ADHDと性的いたずらとの関係について、2)ADHDは責任能力があるのか?3)指導法と防止策 が挙げられます。1)ADHDだからといって、性的いたずらを起こしやすい、ということはありません。2)ADHDで衝動的な行動を起こしてしまうことはありますが、責任能力はあると考えています。3)思春期になる迄に、きっちり治療を受けておれば、思春期頃には、7割くらいのADHDは寛解が期待できます。つまり、小学校1年生くらいから治療開始することが、大切なわけです。思春期のコントロール不良のADHDの場合、小学生の女の子と遊ばせるのを避けるほうがよいでしょう。コントロール良好であれば、問題ありません。
2002年11月10日
コメント(0)
-
ADHDと広汎性発達障害
私へのよき助言者のひとりの、児童精神医学専門医の友人と、いろいろなことをお話しました。なかでもいちばん重要なことで、つい見落としがちなことを、教えて下さいました。それは、私達はつい、ADHDにしても広汎性発達障害にしても、いろいろな問題行動にばかり目を奪われ、それらの問題行動を起こす背景や、その子の訴えたいこと(私はそれを、『その子が発信しているメッセージ』と表現していますが)に、気付かずにいて、問題行動に振り回されていることが多い、ということです。大切なことは、問題行動の背後にある、その子の心理状態を理解し、できるだけしっかりと『その子が発信しているメッセージ』を受け止め、把握することが、解決策の第1段階である、ということです。そこから、それらの問題行動を起こさないようにしていく手がかりが、得られる、というわけです。これから、また具体例を中心に、問題行動について、対処法を考えてみたいと思います。
2002年11月04日
コメント(2)
-
学校での様子
A小学校を訪問して、親御さんを通じて、診察に来るADHDの子ども達の学校での様子を聞いていたつもりだったのですが、先生の見方と少しへだたりがある場合があることを、再認識しました。比較的頻回に、学校の先生と連絡を取り合って、学校でのその子の様子を把握する大切さを痛感していましたが、本当にそうだと思います。できれば毎月連絡を取り合っていくのがよいと思っています。
2002年10月29日
コメント(0)
-
H小学校の3人のADHDの子ども達
今日、H小学校の3人のADHDの子ども達の様子を見に出かけました。1人あたり10分間くらい費やしたのですが、診察場で診るのとは違って、3人の学校での様子が本当によく分かりました。医療の効果とまだ足りない点、学校生活や授業での問題点など、やはりこうして学校現場を見せていただくと、本当によくひとりひとりが理解出来、大変勉強になりました。早速これを、療育に生かせたいと思って、帰ってきました。ADHDが治ったT君も、念のため、学校訪問してみようと考えています。その後の様子を確認するためです。
2002年10月18日
コメント(0)
-
ADHDのA君、治ってよかったね!
おうちでも学校でも大変だったADHDのA君。8歳の春からリタリンを2年半服用しました。最近は、おうちでも学校でも見違えるようにしっかりしてきました。お母さんも学校の担任の先生も、もうお薬は服用しないでもやってゆけるのでは、と思うようになりました。そこで、担任の先生には告げずに、1週間休薬してみたところ、まったく変化がみられず、調子良く過ごせましたので、そのままリタリンを止めることにしました。A君、治ってよかったね!
2002年10月14日
コメント(0)
-
岐阜ADHD親子の会より《相談-22-》
【問】小学4年ADHD男子。親や教師をイライラさせたり、逆なでするようなことを言う。【答】ADHDは、適切な治療を受けますと、約7割以上が軽快します。他方、適切な治療を受ない場合は、学童期後半から青年期にかけて、約50%が、周囲の大人と口論したり、反抗したり、いらいらさせたりするようになると考えられています。これを『反抗挑戦性障害』と呼んでいます。これらの症状が出現した場合は、専門医の受診と治療が必要です。 『反抗挑戦性障害』の診断基準は、トップページを御覧下さい。
2002年09月29日
コメント(0)
-
岐阜ADHD親子の会より《相談-21-》
【問】8才ADHD男子。おじいちゃん、おばあちゃんに言いたいことを言って、甘えている。おじいちゃん、おばあちゃんから、子どもを切り離したいのだが、どうすればよいか?本人はおじいちゃん、おばあちゃんと、居たがる。【答】無理に切り離すことは出来ません。相手がおじいちゃん、おばあちゃんであろうが、誰であろうが、『これはしてよいけれど、これはだめだよ。』というルールを、両親と本人とのあいだで、取り交わすことが大切です。『よいこと』と『よくないこと』のけじめをきっちりと付けることです。また、おじいちゃん、おばあちゃんとも、ルールを作って、約束を取り交わしておきます。
2002年09月22日
コメント(0)
-
岐阜ADHD親子の会より《相談-20-》
【問】小学6年ADHD男子。すぐ適当にごまかして、その場逃がれのことを言う。良くないと言って叱っても。本人はADHDだから仕方がないよ、といってADHDを理由にして言い逃れを言う。【答】ADHDの子はよくその場限りの分かり切ったうそや言い逃れを言いますが、この子の場合はADHDをよいことにして、何でも放免にしてもらえる、と思っているふしが感じられます。ここが許し難いところです。ADHDのせいとは必ずしも言えないことを、はっきり本人に認識させることが重要です。つまり、本人がADHDであると認めているのですから、ADHDから来る、よくない現象、症状を無くするように、親子で取り組む体制を作り上げてみることです。具体的なやり方は、今迄に述べてきたとおりです。基本的には、親子のあいだで、メッセージのキャッチボールをするのです。親がまず子のメッセージをキャッチし、そのメッセージに合った、親からのメッセージを送り返すことから、始まります。
2002年09月16日
コメント(0)
-
岐阜ADHD親子の会より《相談-19-》
【問】小学6年ADHD男子。中学校は特殊学級に行かなければならないか?【答】現在、6年生のクラスの集団の中で、うまくやってゆけているかどうか、授業面と集団生活面の両方で、判断することが重要です。どちらかでもうまくゆかなければ、中学校になると、通常学級ではなかなか大変で、本人も学校が楽しくなくなってくると大変です。 ここで大切なことは、『特殊学級』は『ダメな子学級』といったような評価をしてはならないことです。「『特殊学級』に行くと、こういう良いことがあるんだよ。こんな勉強が、こんなに分かりやすく教えてもらえるんだよ。」というふうに、周囲の大人がポジテイブな考え方で、本人に接することで、本人を伸ばし、明るく楽しい学校生活を送ることができるようになるのです。
2002年09月08日
コメント(0)
-
岐阜ADHD親子の会より《相談-18-》
【問】小学5年生(10歳)ADHD男子。4年生の時の担任に充分理解してもらっていなかった。友達関係もうまくいっていない。5年生になって、学校の先生方と、これからどうしていこうか、検討会を持ちたい。【答】基本的にはそのADHDのお子さんのペースで、マンツーマンで個別に指導していくことでしょう。ただ、学校というところは、集団の中で学んでいく場ですので、集団の中でもうまくゆくように、指導していくことが、教師や親にとって必要です。
2002年09月02日
コメント(0)
-
岐阜ADHD親子の会より《相談-17-》
【問】7歳のADHD男子。自動車を恐がらないため危険。興味のあるものしか視界に入らない。どう対処すればよいか?【答】危険を避ける方法を、その子に応じたやり方で見つけることが必要です。たとえば、まず特定の大人との信頼関係を築いておき、その大人の言うことには従う、というように仕向けておきます。そうして、その大人と行動して、危険なところで、『ちょっと待て!』というと、立ち止まって、危険を避けることを教えていくのです。このような方法で、長い目でみて、車が来れば『飛び出さない』ようになっていきます。他の危険な物事や場面を教えるのも同じです。
2002年08月24日
コメント(0)
-
岐阜ADHD親子の会より《相談-16-》
【問】中学2年生ADHD男子。本人がどのような道に進みたいか、についての指導の仕方、本人の考えさせ方について。【答】本やメデイアによる紹介や説明はあまり効果がありません。実際に作業所や、職場、働いている大人の現場に連れていって、雰囲気を肌で感じさせると、進路について具体的な興味や「やる気」が出てくることがあります。
2002年08月17日
コメント(0)
-
岐阜ADHD親子の会より《相談-15-》
【問】中学1年男子。1)身体が小さい方なので、言い返したらいじめられないか心配。教師に大人が見ていない状況を作らないようにとは言ってある。2)「こだわり」があって、それについて怒ったりした時にどのように対処すればよいか?【答】1)その子の支えとなる友達、信頼できる大人がそばにいるようにすると、少なくともいじめの対象になることは避けられると思います。2)困った時、いらいらした時に言いに行ける相手(たとえば教師)を見つけておく、などして「こだわり」を、長く心中に持ち続けないで、すぐにかわせるようにしておくのも、ひとつの解決法です。対処法としては、「こだわり」があって、それについて怒ったりした時に、『それもそうね。じゃ、あの〇〇先生に相談してみたら?』という具合にかわすのも一法です。
2002年08月02日
コメント(0)
-
岐阜ADHD親子の会より《相談-14-》
【問】小学5年ADHD男子。リタリン服用中。朝、服薬前にカ―っとなりやすい。弟や妹に手をあげることもある。家に帰ってからの兄弟関係は、お互いに接する場面が少ないので、うまくいっている。【答】これには、いくつかの対応策があり、それらを組み合わせてみることを、お薦めします。(1)生活のリズムを整える。早寝早起きをさせる。(2)弟や妹と朝起きる時刻をずらす。(3)ADHDの兄の朝食を先に済ませてリタリンを早めに服用させ、弟や妹が起きてきた頃には、リタリンの効果が出てきているようにする。この場合、学校で早く効果がなくなります。(3)弟や妹の成長を待ってから、ADHDのお兄ちゃんとうまくやってゆけるように指導する。(4)うまくゆかない時は、弟、妹は、『いつもうるさいお兄ちゃん』、ADHDの兄は『いつも怒る弟(妹)』と、お互いに思っているから、余計いらいらするので、できるだけ生活場面を切り離すようにする。
2002年07月28日
コメント(0)
-
岐阜ADHD親子の会より《相談-13-》
【問】小学4年生ADHD男子。ハサミの使い方が下手。勉強もよく間違える。LDではないか、と言われる。うまくできないことに、どこまで要求してよいものか?【答】手先の細かい作業が苦手なADHDの子が多く、以前は微細脳損傷症候群と呼ばれた時代があり、その特徴として、多動と手先の細かい作業がうまく出来ないことが、挙げられていました。現在は微細脳損傷症候群と呼ばずに、ADHDと呼び、1)注意集中困難、2)多動、3)衝動性、が中核症状ですが、手先の細かい作業がうまく出来ないことも、診断基準には入れられていませんが、よくみられる特徴のひとつと考えられています。 勉強については、量や質を評価するのではなく、行為、取り組む姿勢を評価してあげることが大切です。例えば、算数で1問☆秒で解く、と(出来る秒数で)決めて、1問に集中出来るようにし、答が正しいか間違っているかは別にして、集中して『出来た』ことをすぐに評価し、親子で『集中して出来た』ことを喜び、それを積み重ねていくのです。答は間違っていてもいいのです。そうして自信をつけさせ、良く評価してもらっている、という喜び、快感を味わわせることが大切なのです。
2002年07月21日
コメント(0)
-
岐阜ADHD親子の会より《相談-12-》
【問】来年中学生になるADHD男子。小学生の時のように担任の先生にこまめに指導してもらえないのではないか、と不安。他の生徒の親にも相談しづらい。【答】中学生になると、生徒も親も、なかなか小学生のころのようにはゆかないのが、現実です。みんな自分のことで精一杯になってくるのと、ある程度、よい意味の個人主義が生徒各人に出てくるからです。したがって、クラスメートの親にも、小学生の時のようには話しにくくなるのも事実です。中学の先生方も教科毎に変わり、なかなか生徒ひとりひとりに特別に指導してもらうことが、出来なくなります。このような状況では、担任(中学でも一応決まっています)あるいは学年主任、あるいは養護教諭(保健室の先生です)、あるいは、特殊学級の先生に相談してみるのもよいでしょう。
2002年07月13日
コメント(0)
-
岐阜ADHD親子の会より《相談-11-》
【問】小学6年ADHD男子。遊びの中で、近所の子どもとのトラブルから、子ども同志の中で、よくない評価が出来上がってきている。ADHDの子を持つ親から、友達の親にどのように話を進めてゆけばよいか?【答】子どもの友達の親に積極的に話していく姿勢が大切と考えています。そこで、分ってくれる親と全然分ってくれない親とが、はっきり区別できます。親の中で、1人でも2人でも分ってもらえる仲間を得ることが重要なのです。その分ってもらえる親の子ども1人、2人が、クラスの中でそのADHDの子を支えてくれるようになれば、うまくゆく場合が多いようです。
2002年07月08日
コメント(0)
-
岐阜ADHD親子の会より《相談-10-》
【問】小学5年生ADHD男子。クラスの強い子の言いなりになって、万引きをしたり、よくないことをする。【答】まず、この場合ADHDの本人を責めないで下さい。本人自身が悪いわけではないのであって、そういうことをやらせる子が一番悪いのだ、ということを、まず、クラスのみんなに認識させることが大切です。つまり、クラス全体の問題として取り扱うことです。解決の仕方は、このような問題を、教師、クラスの児童、親同士、の三者で取り組むことです。その相談役として、主治医や臨床心理士が関与すると、更にうまく解決できるのではないかと、考えています。
2002年07月04日
コメント(0)
-
岐阜ADHD親子の会より《相談-9-》
【問】小学5年ADHD男子。思い通りにならないと周囲の者に当り散らす。【答】その時は、その場の気分、雰囲気をとっさに変えることが先決です。どんなに言葉で諭しても本人は聞く耳を持ちません。当り散らす相手が弟や妹の場合は、弟や妹を避難させます。友達もその場に居合わせていたら、本人を除く全員を一時避難させて、本人と大人の2人だけにします。そうすると大抵の場合は落ち着いてきます。ここで、母子家庭でなければ、父親の存在が重要になってきます。ADHDの我が子と一緒に遊び、出来れば共通の趣味を持って、行動を共にして、子どもが自分でコントロールする力を身に付けさせる機会を多く持つようにするのです。父親と2人でなら、目的達成のためにじっと我慢したり、自分で行動の準備をしたり出来るものなのです。
2002年06月30日
コメント(0)
-
岐阜ADHD親子の会より《相談-8-》
【問】小学5年生ADHDの男子。約束が守れない。【答】『小学5年生だから、こんな約束は守れないとだめ!』とか、『あなた、お兄ちゃんでしょ!弟との約束を守らないとだめですよ!』と言って叱ってはいませんか?大切なことは、何年生であろうが、ADHDの子にはその子なりに、約束が守れる範囲があるのですが、一般的に通用する範囲ではなく、年齢よりも2~3歳下の子に通用するような範囲のことがほとんどです。そういう意味では、社会面での発達が歪んでいるともいえます。だけれども、それがADHDの子の実態なのですから、その子が守れる約束をして、守れたら、充分評価してあげて、少しずつ社会面の発達の歪みを根気良く直していくことが大事なのです。
2002年06月25日
コメント(0)
-
岐阜ADHD親子の会より《相談-7-》
【問】小学5年のADHD男子。みえすいたうそを言う。【答】人間、誰しもいつも『良くないよ』と言われてばかりいると、いいかげん、もうこれ以上『良くないよ』と言われたくないのが本音です。その気持ちが、言いのがれたい、という気持ちにつながって、とっさに言い逃れようとするために、みえすいたうそ、になってしまうのです。したがって、ADHDの子がみえすいたうそを言うようになった、ということは、かなり自尊心が傷つけられており、その子を知らず知らずのうちに追い詰めている段階にきてしまっていることを、親は認識しなければ、問題は解決しません。つまり、みえすいたうそを言わなくてよいような状況に戻していくことです。具体的には、『またやってしまって!』『もう同じことを何回言ったらわかるの?』『本当にダメな子ね!』などと言って、親がわが子を本当にダメな子にしていってしまっているのです。解決法はこれらの逆をすることです。『またやってしまうのは、あなたの意志とは無関係にやってしまうことも多いのだよ。』と、まずADHDを認めることからスタートして下さい。そうして、『お母さんは、あなたがADHDでも、どんな場合でもあなたの味方なのよ。』『失敗して、やってしまったら、お母さんには正直にごめんなさい、って言ってね。』と、一緒によくしていく姿勢作りが、解決への糸口になるのです。
2002年06月23日
コメント(0)
-
岐阜ADHD親子の会より《相談-6-》
【問】小学4年のADHD男子。テレビゲームが好きで、何時間も一人でいる方が好き。【答】このご質問は、ADHDに限らず、最近は特にゲームなど自分の世界で楽しむタイプの子どもが多いようです。この場合、同じ仲間同志、ひとつの部屋で、数人集まっても、それぞれ別の遊びやゲームをしていて、けっこう楽しんでいる光景がみられます。各自が自分のペースを乱さない相手、同じ仲間、が出来てくるとそれなりのひとつの友達社会が出来て、仲間同志のルールのようなもので結びついてゆけば、それでよいと考えて下さい。それが逃避で、いつもひとり、にならないように、配慮が必要です。その場合は、お兄さん代わりのつもりで相手になってもらえる家庭教師のような方を見つけるのも一法です。
2002年06月21日
コメント(0)
-
岐阜ADHD親子の会より《相談-5-》
【問】小学4年のADHD男子。何かひとつの事を我慢させると、他の事に欲求が向けられ、我慢できない。【答】我慢させた結果、うまくゆかなかっても、まず、『よく我慢できたね。』と褒めることが第一です。褒める前に本人が、『うまく行かなかったのは、先生(友達)(親)のせいだ』と暴言をはいたり、罵ったりしても、です。とにかく『よく我慢できた』ことを褒めてあげて、親子で喜び合うことが大切なのです。
2002年06月20日
コメント(0)
-
岐阜ADHD親子の会より《相談-4-》
【問】4年生男子。病院で小さい子どもの声に、『うるさい!』といって騒ぎ立てる。そのあとで『どうしても自分が悪い子になってしまうんだ』と言う。【答】子どもの声や状況の変化に過敏で、感覚的に自分でコントロール出来ない子がおられます。この場合は、結果として良くないことをしてしまわないように、そのような状況や場面を変えるようにするしか方法はないでしょう。病院なら、受け付けに告げて、外で待つのもひとつの解決策です。 良くないことをしてしまってから、『また、やってしまった』と、傷付きやすい、その結果、イライラして、また良くないことをやってしまう、という悪循環の体系が出来てしまっている場合もあります。このような時は、少しでも、自分をコントロール出来た部分を、大きく拡大して『よくコントロールできたね!』と褒めて、親子で喜び合うことが大切な事です。こうして親子で、プラス思考で、よい精神状態を保つようにすることにより、悪循環の体系を断ち切ることが出来るのです。
2002年06月19日
コメント(0)
-
岐阜ADHD親子の会より《相談-3-》
【問】9歳男子。誰とでも友達になってしまう。場の雰囲気がつかめず、くどい。言いたい事を話すため、友達から『変わった子だな』という周囲の評価が出来つつある。【答】学校の先生の対応、周囲の大人の態度を見て、子ども達はADHDの子の評価を作り上げていくようです。学校の先生や周囲の大人が、その子との対応の仕方、ルールを、周囲の子ども達に伝えることで、うまくいくことがあります。たとえば、言いたいことを我慢できない子には、我慢させないで、『関係ないことですけれど、』と一言言って、発言させるようにすると、本人はすっきりし、周囲の子ども達もそれ以上追求しなくなります。ひとつの妥協点を見い出すルール作りが、悪い評価を作り上げるのを防ぐことにつながります。
2002年06月18日
コメント(0)
-
岐阜ADHD親子の会より《相談-2-》
【問】同じ学級の女の子に触ったり抱きついたりしていやがられています。性教育について。【答】行為そのものは自然な成長の結果であることをまず認めてあげることです。次に大切なことは、ルールをどのように教えていくか、です。自分がいやなことをされると、不愉快なように、他人がいやがることは、してはいけない、という指導方針で。ひょっとしたら、触った感触、抱きついた感覚を楽しんでいるのかもしれません。その場合は、他にも落ち着ける、安心できる、楽しいことがあることを味わわせる、という解決の仕方があります。例えば、ほめられることをするように仕向け、褒めてあげて、その楽しみを味わわせる体験を作っていくことです。
2002年06月16日
コメント(0)
-
岐阜ADHD親子の会より《相談-1-》
【問】小学4年生普通学級男子:将来の進路と親としてできる準備は?【答】思春期になると周囲から『自分はどう見られているか』が気になり始め、ADHDでも、自分で自分の行動をコントロールできるようになってきます。そこで、『悪い点もあるけれど、良いところもあるんだ。自分は頑張っている。』というふうに、プラスの自分を本人に見えるように、変わってきていること、がんばっていることを、より高く、より強く、親として評価してあげる時間を、毎日5分間ずつでも持つことが大切です。その積み重ねが、本人の将来うまく生きていく力になるのです。
2002年06月15日
コメント(0)
-
第3回岐阜ADHD親子の会、盛会のうちに修了
第3回岐阜ADHD親子の会は参加者14家族、大人16名、子ども18名のも と、盛会のうちに修了致しました。親御さん達の多彩な質問のひとつひとつに、学校教育心理学がご専門の別府哲先生が明解にお答え下さって、医者で教育者でもある私自身、目からうろこが落ちる想いで、聴かせていただきました。参加者は皆さん、本当に満足されたご様子で、企画させていただいた者にとって、本当に充実した半日でした。 岐阜ADHD親子の会はまだ3回を終えたばかりですが、何かもうこれ以上よい企画が、しばらくは頭に浮かんで来そうにないように想われるくらいです。別府先生、本当にありがとうございました。
2002年05月27日
コメント(0)
-
さらに忙しくなりました。
本職に関係した仕事と、本職以外に頼まれてしまった仕事と趣味の世界とで、ぐったりの毎日です。趣味だけならどんなに幸せなことでしょうか。
2002年05月04日
コメント(0)
-
プロフィール
私の職種:『小児科医師』で『小児神経専門医』;私の現在の所属:岐阜大学教 育学部障害児教育講座で障害児医学を教えています。必要に応じて小児神経クリニックも行っています。特に障害を持ったお子さんのクリニックが専門です。
2002年04月26日
コメント(3)
全43件 (43件中 1-43件目)
1