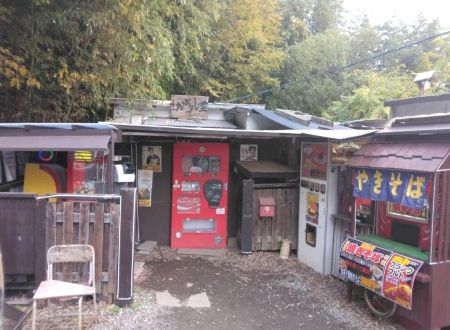2023年02月の記事
全2件 (2件中 1-2件目)
1
-

インド洋 日本の気候を支配する謎の大海(感想)
夏になってインド洋東部熱帯域で南東貿易風が強まると、東風によって高温の海水が西側へ移動し、深海からの冷たい湧昇や海面からの蒸発によって海水温が低下します。 一方、インド洋西部では、東から運ばれた高温の海水で海面水温がさらに上昇します。 これは太平洋のエルニーニョ現象と類似の現象で、エルニーニョ現象とは関係なく独立して発生する場合と、エルニーニョ現象と関連して発生する場合とがあります。 ”インド洋 日本の気候を支配する謎の大海”(2021年8月 講談社刊 蒲生 俊敬著)を読みました。 海面水温などさまざまな海洋気象観測のデータや構造に、インド洋の東西で双極的対照的な現象が現れるダイポールモード現象と、日本の気候との関りなどを解説しています。 海面水温などさまざまな海洋気象観測のデータや構造に、インド洋の東西で双極的、対照的な現象が現れ、海面水温が高くなると、そこでは対流活動が活発化し降水量が増加します。 そのため、東側では乾燥して少雨、西側では多雨となるなど異常気象がもたらされます。 これがインド洋独自の大気海洋現象でありダイポールモード現象と言われ、インドから日本にかけてのモンスーンアジア地帯の気象に大きく影響します。 日本の夏は猛暑となり、干魃や猛暑といった異常気象を引き起こすことになると考えられるというこです。 蒲生俊敬さんは1952年長野県上田市生まれ、東京大学理学部化学科を卒業し、同大学大学院理学系研究科化学専攻博を課程を修了しました。 理学博士で、専門は化学海洋学です。 1986年から1992年まで東京大学海洋研究所助手、1993年に海洋研究所 無機化学 助手を経て、1994年に同大学海洋研究所助教授となりました。 1996年に同大学海洋研究所教授となり、以後、2000年に北海道大学教授、2010年から2016年まで同大学大気海洋研究所教授を歴任しました。 2017年に東京大学大気海洋研究所特任研究員、2018年から2020年まで同大学大気海洋研究所名誉教授となりました。 海洋のフィールド研究に情熱を傾け、これまでの乗船日数は1740日に及び、深海潜水船でも15回潜航しました。 海洋の深層循環や海底温泉に関する研究により、日本海洋学会賞・地球化学研究協会学術賞(三宅賞)・海洋立国推進功労者表彰(内閣総理大臣賞)などを受賞しています。 人類の誕生以降、インド洋は、人類の英知が試される、いわば試練の海でした。 数え切れない多数の人々がインド洋と接触し、航海技術や漁業の発展のために苦闘を重ね、その結果として、インド洋からさまざまな恩恵を受けてきました。 ことに、インド洋が過去2000年以上の長きにわたって、東洋と西洋との交易・交流の場を育み、発展させ、国際社会の構築に限りない役割を果たしてきました。 さらに未来へと目を向けてみれば、今世紀末頃には、アフリカとアジアとを合わせた人口は世界人口の8割を超え、90億人にも達するといわれます。 急膨張するこのアフリカとアジアに接し、かつこの地域と他の世界とを強く結びつける海こそ、インド洋なのです。 ここ数年、インド洋に生じる特異な海洋変動であるダイポールモード現象という言葉を、新聞や雑誌等でひんぱんに見かけるようになりました。 ダイポールモード現象とは、インド洋の熱帯海域において、正反対の気候状態が同時に、東西に横並びになることです。 東側は低温で晴天続きである一方、西側では高温で豪雨に見舞われる、といった具合です。 この現象は1999年に、気候学者・山形俊男博士の研究グループによって発見されました。 ダイポールモードという名称の名付け親も山形博士で、ダイポールとは、二つの極という意味です。 日本から遠く離れたインド洋で生じる現象ですが、日本の気候と強い関わりをもっています。 たとえば2019年に出現した強烈なインド洋ダイボールモード現象は、日本列島に夏の猛暑と、それに続く異常な暖冬をもたらした主因であると指摘されています。 ダイポールモード現象の影響をまず最初に強く受けるのは、アフリカ諸国やインド、オーストラリア等々の、インド洋に接する国々です。 しかし、影響が及ぶ範囲はそれだけにとどまらず、遠くヨーロッパの国々や、日本列島にまで達しており、広く世界的なスケールで気候を支配しています。 インド洋と日本のように、はるか遠く離れた地域をつないで気候現象が伝わることをテレコネクションと言うそうです。 インド洋はこのテレコネクションを通じて、日本列島の気候をコントロールする陰の大物だったのです。 インド洋では、強い季節風(モンスーン)のために夏と冬とで流れる向きが完全に逆転する海流で、南極海からやってくる深海水の複雑怪奇な動きがみられます。 また、大陸移動のせめぎ合いと海底から湧き出る高温の熱水や、インド洋にのみ生息するふしぎな生物たちがみられます。 さらに、プレートの沈み込みにともなう超弩級の火山噴火や巨大地震や、ダイポールモード現象がみられます。 これらダイナミックな地球の姿や営みが、インド洋にはところ狭しと詰め込まれていて、インド洋を抜きにして地球は語れないそうです。 インド洋熱帯域の海面水温は、エルニーニョ現象の発生から2~3か月遅れて平常よりも高くなり始め、エルニーニョ現象の終息後もしばらく高い状態が維持される傾向があります。 そのため、エルニーニョ現象が発生した翌年など、インド洋熱帯域の海面水温が平常より高い夏の場合、大気下層の東風の影響でフィリピン付近の対流活動が抑制される傾向があります。 インド洋の海面水温が平常よりも高い場合の大気下層の高低気圧の平年からの偏りで、夏の日本付近の気圧が低くなります。 このような夏には、北日本を中心に、多雨、寡照、沖縄と奄美で高温となることがあります。 インド洋熱帯域の海面水温が南東部で平常より低く、西部で平常より高くなる場合を、正のインド洋ダイポールモード現象といいます。 逆の場合を、負のインド洋ダイポールモード現象と呼んでいます。 両現象ともに概ね夏から秋の間に発生しますが、発生頻度は年代によって大きく変わり、2000年以降は正のインド洋ダイポールモード現象の発生頻度が高まっています。 正のインド洋ダイポールモード現象では、夏から秋ごろにインド洋熱帯域南東部の海面水温が平常時より低く、その上空の積乱雲の活動が平常時より不活発となります。 この時、ベンガル湾からフィリピンの東海上では、モンスーンの西風が強化されます。 そして、フィリピン東方に達するモンスーンの西風と太平洋高気圧の南縁を吹く貿易風の暖かく湿った空気により、北太平洋西部で積乱雲の活動が活発となります。 このため、上空のチベット高気圧が北東に張り出し、日本に高温をもたらします。 また、インド付近でも積乱雲の活動が活発になり、地中海に下降流を発生して高温化させる方向に働きます。 地中海は日本上空を通過する偏西風の上流に位置するため、偏西風の蛇行を通じて日本に高温をもたらすとも考えられます。 なお、負のインド洋ダイポールモード現象については日本の天候への影響は明瞭ではないそうです。 インド洋を抜きにして、地球を語ることはできません。 本書は、そのようなグローバルな観点から、一冊まるごと、インド洋という大海の魅力に迫り、この海ならではの自然現象の数々を、できるだけ平易に紹介しています。 また、インド洋と人間社会との関わりについても、少しであるが視野を広げたといいます。第1章 インド洋とはどのような海かー二つの巨眼と一本槍をもつ特異なその「かたち」/第2章 「ロドリゲス三重点」を狙え!-インド洋初の熱水噴出口の発見/第3章 「ヒッパロスの風」を読むー大気と海洋のダイナミズム/第4章 インド洋に存在する「日本のふたご」-巨大地震と火山噴火/第5章 インド洋を彩るふしぎな生きものたちー磁石に吸いつく巻き貝からシーラカンスまで/第6章 「海のシルクロード」を科学するーその直下にひそむ謎の海底火山とは?[http://lifestyle.blogmura.com/comfortlife/ranking.html" target="_blank にほんブログ村 心地よい暮らし]インド洋 日本の気候を支配する謎の大海 (ブルーバックス) [ 蒲生 俊敬 ]インド洋海域世界の歴史 人の移動と交流のクロス・ロード (ちくま学芸文庫 ヤー31-1) [ 家島 彦一 ]
2023.02.18
コメント(0)
-

幕末の漂流者・庄蔵 二つの故郷(感想)
鎖国と身分制度によって閉ざされていた江戸時代に、その殻を突き破って、日本史を近代の方向へと動かしていく上で大きな役割を果たした人々がいました。 本来はいずれも名もなき一庶民でしたが、漂流が人生を変え、歴史に名を刻むことになりました。 ”幕末の漂流者・庄蔵 二つの故郷”(2022年1月 弦書房刊 岩岡 中正著)を読みました。 自らが船頭を務める船で天草を出航し長崎へ向かったものの、途中で嵐に遭って船員3名とともにルソン島へ漂流した、肥後国出身の庄蔵の生涯を紹介しています。 大坂の質屋の息子だった伝兵衛は、1696年に江戸に向かう途中で嵐にあってロシア領カムチャッカに漂着し、モスクワでロシア皇帝に謁見しました。 伊勢の船頭だった大黒屋光太夫は1782年に、江戸へ向かう途中で漂流し、ロシア帝都サンクトペテルブルグで女帝エカテリーナニ世に謁見しました。 土佐の漁師だった万次郎は、1841年に14歳で漂流してアメリカの捕鯨船に救助されて東海岸に行き、幕末に帰国して幕府に登用され咸臨丸に乗り込み、使節団の通訳として条約締結に尽力しました。 1837年にモリソン号で帰国しようとして果たせなかった日本人漂流者7人のうちの1人の音吉は、上海でイギリス商会につとめ、幕末期の日英交渉でイギリス側の通訳として活躍しました。 そして、原田庄蔵は音吉とともにモリソン号に乗りましたが、終生帰国を果たせず、日本人漂流民の帰国のために尽力しました。 庄蔵は1807年に、当時、海外も開かれた海上交通の要所だった肥後川尻の、12の町の中でも小さい正中島町の廻船業の屋号・茶屋に生まれました。 1835年に両親と妻子を残し、八十石船でほかの寿三郎、力松、熊太郎の三人と共に天草へ行き、ここから帰る途中、大風で東シナ海からフィリピンのルソン島北岸へ漂流しました。 そこでスペイン官憲に救われ、マニラを経て船で中国マカオヘ送られました。 1837年に尾張の音吉ら3人を含め、漂流者7人は、開国や通商をめざす米船モリソン号に乗せられて日本へ向かいました。 しかし、無二念打払令で浦賀沖と薩摩で砲撃されて断念し、命からがらマカオヘ戻りました。 このマカオで庄蔵は、のちにペリー提督の日本語公式通訳の米国人宣教師S・W・ウィリアムズに日本語を教え、ともに、その下で聖書「マタイ伝」の初めての邦訳に協力しました。 1841年9月にマカオから、故郷・肥後国川尻、正中島町の父の茶屋・嘉次郎あての書簡を出し、書簡は2年半後の1844年2月に家族のもとに届きました。 帰国することはできず、その後香港へ移住し、アメリカから来た女性と結婚しました。 そして、洗濯屋仕立屋として成功し、ゴールドラッシュに湧くアメリカのカリフォルニアヘ、人夫10人をつれて金採掘に渡ったこともあるといいます。 また、周防の漂流民・船頭宗助ら12人のような、日本人漂流民の世話もしました。 ただ、その没年、墓、子孫については不明です。 著者は、小さな正中島町から世界へ漂流した、庄蔵という「地域」的で「地球」的な横軸と、前近代社会から近代人へと再生・自立していった歴史の縦軸から庄蔵に接近したいといいます。 またこれは、肥後川尻、正中島町と中国のマカオ・香港という、庄蔵の「二つの故郷」の物語でもあります。 岩岡中正さんは1948年熊本市生まれ、九州大学法学部を経て同大学院を修了しました。 1991年に学位論文で法学博士(九州大学)の学位を取得し、熊本大学法学部で教鞭を取りました。 政治学者で俳人で、現在、熊本大学名誉教授を務めています。 研究テーマは、政治思想史・共同性の思想研究です。 大学時代から俳句を嗜み、俳誌「阿蘇」を主宰しています。 日本伝統俳句協会副会長で、朝日俳壇賞受賞、熊本県文化懇話会賞、熊日文学賞、山本健吉文学賞評論部門を受賞しています。 香港最初の定住日本人となった原田庄蔵一行は、漂流から8年を経た1845年から、香港での定住生活が始まりました。 当時の香港は人口7450人で、1841年から英国軍が香港島を占拠していて、アヘン戦争の真っ最中でした。 アヘン戦争が終結した1842年に南京条約が締結され、香港島は正式にイギリスに永久割譲され、ビクトリア市と命名されました。 西地区が中国人街、中央がイギリス街、何もなかった湾仔の関所を超えた東側の銅鑼湾がジャーディンマセソン王国と、大きくは3地区に分かれていました。 夫々の地区が物すごい勢いで開拓されていた時代に、庄蔵一行がやってきたのでした。 1845年に香港に移住した庄蔵一行は、中環と上環の境目当たりに住居を構えたと思われます。 後年、ペリー率いる第二次日本遠征隊は香港から出発しましたが、庄蔵一行で一番若かった力松が、自分たちは湊の上の方にある関帝廟のそばに住んでいると言ったそうです。 関帝廟とは文武廟のことで、香港最古の道教寺院として有名でした。 この寺院は、庄蔵達が香港に定住してから2年後の1847年に創建されています。 当時の香港の中国人の人口は、家族が25世帯、娼婦の館が26軒で、あとは、独身、単身で大陸から流れ込んだ無数の中国人でした。 庄蔵は4人の中では一番成功し、洗濯業と裁縫業を手広く展開して、3階建の家にアメリカ人の夫人と息子と住んでいました。 夫人が白人だったか中国系だったか不明ですが、マカオでギュツラフの影響を受けてキリスト教に改宗しました。 ギュツラフは中国を訪れた最初の西洋人で、外交官としても活躍しましたが、実際は敬虔で影響力のあるキリスト教伝道師でした。 語学の天才で、日本語についても庄蔵達から日本語を学び、聖書の日本語訳なども行いました。 庄蔵はクリスチャンとしてギュツラフの聖書翻訳作業を助け、その後の香港でも引き続き5年を掛けてマタイ伝の日本語訳に成功しました。 共同作業者のギュツラフは1850年にマカオから香港に移り住み、1851年に香港で48歳で病死しました。 その功績を称えて、中環にある通りにギュツラフの名が冠せられているといいます。 庄蔵は、そのほかにもいろいろと活発な人生を送ったようです。 1852年ころ一獲千金を夢見て、中国人の苦力10数人を引き連れて、ゴールドラッシュに沸くカルフォルニアまで金採掘に行きました。 1853年には、やはり漂流民として香港に立ち寄った永久丸乗員2名の世話をしました。 乗員によると、当時44歳であった庄蔵は、20歳ほども若く見える円満でほのぼのとした男だったそうです。 そして、この証言を最後に庄蔵の足取りはしばらく途絶えています。 そして、幕末に帰国して幕府に登用され、1860年に出航した咸臨丸に乗り込み、使節団の通訳として条約締結に尽力したのでした。 その後、日本領事館開設の1873年のの香港在住日本人は8名(12名とも)でしたが、その中に庄蔵の名前もその家族の名前も見当たらないといいます。 庄蔵も家族も、香港籍として名前も変えていた可能性があり、名乗り出る事もなく明治政府の知るところなく、巷中に没したのではないでしょうか、墓石も見つかっていないそうです。 寿三郎、力松、熊太郎の3人のうち、寿三郎と熊太郎の香港滞在に関する記録はほとんど残されていません。 寿三郎は1853年に病死、熊太郎は1845年に病死したといいます。 力松は13歳のときに漂流し、日本人としての教育も充分に受けられないまま、マカオ、香港と渡り歩き、キリスト教を信じ、アメリカ女性と結婚し、3人の子供を持ちました。 出版社に勤め、日本語、英語、広東語に通じていたようです。 1855年には、エリオット提督率いるイギリス遊撃艦隊に通訳として乗り込み、函館に寄港した時の通訳として活躍しました。 同年の日英和親条約の批准書交換の際にも通訳として長崎にきています。 その後、力松の記録は途絶えますが、しっかりとした仕事もあり、通訳としても活躍し、家族に囲まれて平穏な人生を香港で全うしたと思われます。 漂流が人生を変え、それぞれが歴史に名を刻みました。 本書は、日本人を超えて国際人として生きた肥後出身の漂流者の実像に迫っています。はじめにー原田庄蔵とその故郷/1 漂流物語ーマカオから父への手紙「日本より出し日を命日に」(庄蔵の手紙/寿三郎の手紙/庄蔵と寿三郎)/2 聖書物語ーウィリアムズと庄蔵 本邦初訳「聖書・マタイ伝」(「マタイ伝」写本の運命/庄蔵の聖書とその特徴)/3 故郷物語ー庄蔵と故郷の人々(父と子の盆踊り/庄蔵の教養/正中島町「家屋鋪賣買帳」と庄蔵旧居/庄蔵の長女ニヲとその末裔)/おわりにー運命と時代を切り開く力[http://lifestyle.blogmura.com/comfortlife/ranking.html" target="_blank にほんブログ村 心地よい暮らし] 幕末の漂流者・庄蔵 二つの故郷 [ 岩岡中正 ]日本初、新聞が発行された 幕末の漂流者ジョセフ・ヒコがまいた種 理論社 小西聖一 / 新・ものがたり日本歴史の事件簿【中古】afb
2023.02.04
コメント(0)
全2件 (2件中 1-2件目)
1