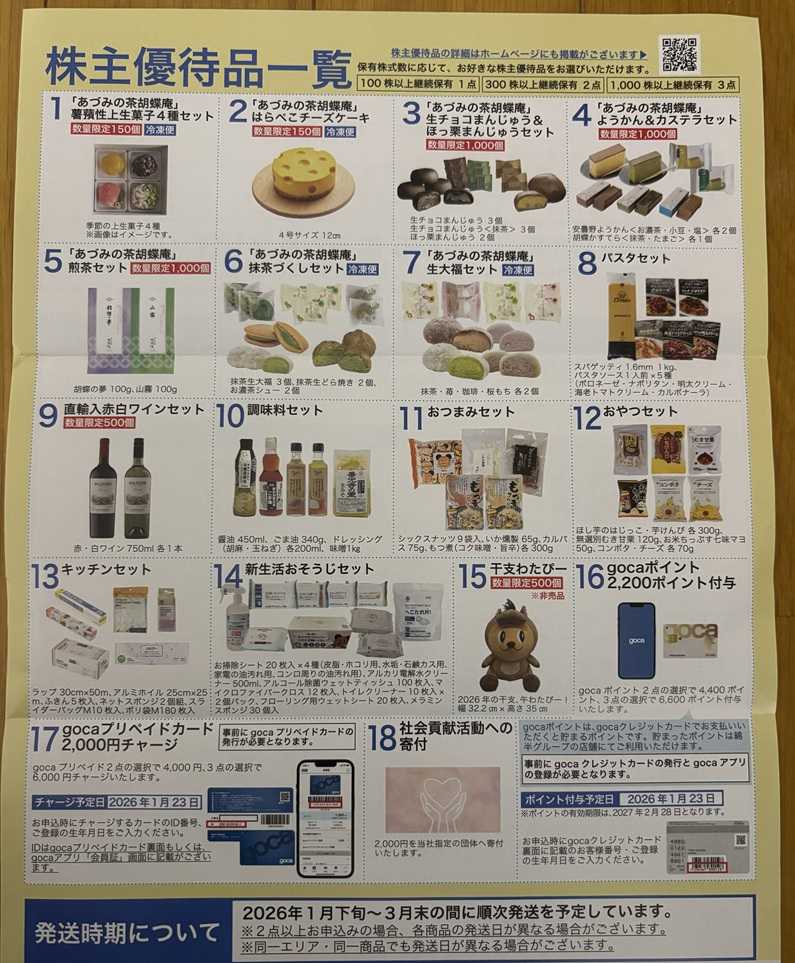2023年05月の記事
全2件 (2件中 1-2件目)
1
-

家康の正妻 築山殿 悲劇の生涯をたどる(感想)
築山殿=つきやまどのは徳川家康の正室だが、生年は不詳で実名は不明です。 1579年9月19日に亡くなった、戦国時代から安土桃山時代にかけての女性です。 ”家康の正妻 築山殿 悲劇の生涯をたどる”(2022年10月 平凡社刊 黒田 基樹著)を読みました。 築山殿は今川家の血脈を受け継ぎ、徳川家康の人質時代にその正室となりましたが、のちに武田家との内通疑惑があがり織田信長から死罪を命じられました。 そして、嫡男の信康とともに生涯の幕を閉じたその生涯を、本書が紹介しています。 瀬名の名があてられことがありますが、当時の史料にも江戸時代前期の史料にも瀬名の名はみられません。 築山の由来は岡崎市の地名で、具体的な場所は”岡崎東泉記”によると、岡崎城の北東約1キロほどに位置する、岡崎市久右衛門町であったとされます。 父親は関口親永(氏純とも言われる)、母親は今川義元の伯母とも妹ともいわれ、もし妹ならば築山殿は義元の姪に当たります。 夫の徳川家康よりも2歳くらい年上、低くみても同年齢くらいと推測されています。 母親は井伊直平の娘で先に今川義元の側室となり、後にその養妹として親永に嫁したといいます。 その場合、井伊直盛とはいとこ、井伊直虎は従姪に当たります。 関口氏自体は、御一家衆と呼ばれる今川氏一門と位置づけられる家柄でした。 家康(当時は松平元信、その後松平元康)が今川氏一門である関口氏の娘婿になったのは、今川氏一門に准じる地位が与えられたことを意味していました。 築山殿に関する当時の史料はわずか一つだけで、その動向を伝えるものは江戸時代に成立した史料かほとんどです。 江戸時代がすすむにつれて、その動向は様々に伝えられるようになり、また解釈されていくようになったようです。 本書では、江戸時代の成立ではあるものの、できるだけ内容の信頼性が高い史料をもとに、その実像を明らかにしていきます。 黒田基樹さんは1965年生まれ、1989年に早稲田大学教育学部を卒業し、1995年に駒澤大学大学院博士課程(日本史学)を単位取得満期退学しました。 1999年に駒澤大学より博士 (日本史学)の学位を取得し、2008年に駿河台大学法学部准教授となり、2012年に教授となって、今日に至っています。 築山殿の生涯における最大の謎は、築山殿が家康に殺害された、とされていることでしょう。 嫡男松平信康もまた同時に家康に殺害されたものでした。 そのため、それは「築山殿事件」「築山殿・信康事件」あるいは「信康事件」などとも呼ばれています。 1579年7月16日に信長から家康に、築山殿と信康に謀反の疑いがあると通告があり死罪を命じられました。 それを訴え出たのは、信長の娘で信康の正室となっていた徳姫でした。 信康は家康の独立時には駿府にいて母の築山殿と取り残されましたが、まもなく救出されて岡崎城に入りました。 1563年に5歳で信長の娘・徳姫と婚約し、やがて元服して岡崎城を任ぜられました。 徳姫との間には2女を儲け、夫婦仲はよかったといいますが、やがて築山殿と徳姫が不和となると、最期は築山殿とともに謀反の嫌疑をかけられ、信長から死罪を命じられて自害しました。 徳姫がいつまでたっても息子を産まないため、心配した築山殿は、元武田家家臣で後に徳川家家臣となった浅原昌時の娘など、部屋子をしていた女性を、信康の側室に迎えさせました。 1579年に徳姫は、築山殿が徳姫に関する讒言を信康にした、築山殿と唐人医師・減敬との密通があった、武田家との内通があったなど、12か条からなる訴状を信長に送ったといいます。 築山殿は8月29日に自害を拒んだことから首をはねられ、信康は9月15日に二俣城で自害しました。 もう一人の子の亀姫は、1576年に家康が長篠の戦いで功をあげた旧武田家臣の奥平信昌に娶らせました。 亀姫は信昌との間に4人の男児と1女を設け、信昌の死後は剃髪して盛徳院と号しました。 おそらく、築山殿事件は家康にとっては寝耳に水の事態だったと思われます。 経緯についてはある程度は把握することかできていますが、真相を伝える史料は存在していません。 そのため事件の真相をめぐって、先行研究において様々な解釈か出されています。 その解釈は、詰まるところ、家康と築山殿・信康をめぐる政治環境をどのように理解するかによっています。 本書でも事件の真相に迫りますが、信頼性の高い史料にもとづいて事件の輪郭を描き出し、築山殿の立場を、家康の正妻、徳川家の「家」妻という観点からしっかりと評価したい、といいます。 戦国大名家は、当主たる家長と、正妻たる「家」妻との共同運営体とみなされます。 そこでは正妻あるいは「家」妻が管轄する領域があり、その部分に関しては、当主あるいは家長であっても独断で処理できず、正妻あるいは「家」妻の了解のもとにすすめられたと考えられます。 戦国大名家の妻妾については、「正室」「側室」の用語か使用されることか多いですが、「側室」は江戸時代に展開された一夫一妻制のもと、妾のうち事実妻にあたるものについての呼称です。 しかし、戦国時代はまだそのような状況にはなく、当時は一夫多妻多妾制でした。 家康には正室・継室のほかに、16~20人を超える側室をかかえたとされています。 側室の多くは実は身分の低い者たちで、特に寵愛したのは名もない家柄の娘たちでした。 名家の出身者ばかりを側室にしていた豊臣秀吉とは対照的で、家康は出自には全くこだわらなかったようです。 たとえば、小督局=こごうのつぼねは家康の最初の側室とされ、家康二男・結城秀康の生母として知られます。 はじめは築山殿の侍女でしたが、風呂場で家康の手付となって秀康が産まれたといいます。 築山殿が彼女の妊娠を知ったとき、寒い夜に裸にされて城内の庭の木にしばり付けられ、これをたまたま見つけた家康の家臣の本多重次に保護され秀康を出産した、といいます。 また、秀康双子説もあり、当時双子は忌み嫌われていたことから母子ともに家康に疎まれたといいます。 西郷局=さいごうのつぼねは遠州の名もない家柄の娘で、通称はお愛の方といいます。 はじめは下級武士に嫁いで一男一女を設けましたが、夫が戦死し、のちに家康に見初められて側室となりました。 家康最愛の側室といわれ、江戸幕府2代将軍・秀忠と松平忠吉の母でもあります。 美人で温和な人柄といい、家康のほか、周囲の家臣や侍女らにも信頼されて好かれていたといいます。 築山殿の動向、そして殺害事件は、家康の正妻、徳川家の「家」妻という観点からみていくと、どのように理解することかできるかが、本書の眼目になります。 何事も、視点か転換すると違う様相がみえてきます。 これから、新たな視点をもとに、築山殿の生涯をたどっていくことにしたい、といいます。 これまでに築山殿の生涯をまとめた書籍かなかったわけではありません。 しかしそれらは、正妻や「家」妻についての研究が進捗していない段階のもので、依拠する史料も、江戸時代成立のものについて、内容の信頼性の高さ低さを区別なく用いられていました。 本書では、現在の研究水準をもとに、信頼性の高い史料によりながら、築山殿の生涯を描き出すことをこころがけた、といいます。第1章 築山殿の系譜と結婚(「築山殿」の呼び名/築山殿の父は誰か ほか)/第2章 駿府から岡崎へ(松平竹千代(徳川家康)の登場/竹千代「人質」説の疑問 ほか)/第3章 家康との別居(嫡男竹千代の岡崎帰還/諸史料が伝える人質交換 ほか)/第4章 岡崎城主・信康(岡崎城主としての信康の立場/信康の初陣はいつか ほか)/第5章 信康事件と築山殿の死去(家康による武田家への反撃/信康の悪行のはじまり ほか) [http://lifestyle.blogmura.com/comfortlife/ranking.html" target="_blank にほんブログ村 心地よい暮らし]家康の正妻 築山殿(1014;1014) 悲劇の生涯をたどる (平凡社新書) [ 黒田 基樹 ]【中古】 築山殿無残/講談社/阿井景子 / 阿井 景子 / 講談社 [文庫]【メール便送料無料】【あす楽対応】
2023.05.27
コメント(0)
-

中世武士 畠山重忠 秩父平氏の嫡流(感想)
畠山重忠は1164年生まれ、平安時代の終わり頃から鎌倉時代のはじめにかけて活躍した武蔵国を代表する武将で、大族秩父氏の一族で、畠山荘を領して畠山氏の祖となった重能の子です。 ”中世武士 畠山重忠 秩父平氏の嫡流”(2018年11月 吉川弘文館刊 清水 亮著)を読みました。 平安時代末に武蔵国男衾郡畠山、現在の深谷市を本拠として、武勇に優れ清廉潔白な人柄から「坂東武士の鑑」と称された、有力御家人の畠山重忠の生涯を紹介しています。 源頼朝の挙兵にあたり、はじめ平家方について三浦氏を攻めましたが、のち帰順して平家追撃軍に加わり各地に転戦しました。 治承・寿永の乱で活躍し、知勇兼備の武将として常に先陣を務め、幕府創業の功臣として重きをなしました。 1187年の梶原景時の讒言によって、謀反の罪を着せられそうになりましたが、謀反を企てているとの風聞が立つのは武士の眉目と語って、嫌疑を一蹴したといいます。 1205年に平賀朝雅を将軍にたてようと企図する北条時政とその後妻牧の方の陰謀にまきこまれ、子の重保が鎌倉由比ヶ浜に誘殺され、ついで重忠にも大軍がさし向けられました。 このとき重忠は本領に帰って、決戦を勧める郎党の言を制し寡勢でこの大軍を迎え撃ち、一族郎党とともに討死したと言われます。 清水亮さんは1974年神奈川県生まれ、1996年に慶應義塾大学文学部を卒業し、2002年早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程を単位取得退学しました。 2005年に学位論文により早稲田大学より博士号(文学)を授与され、2007年より埼玉大学教育学部准教授を務めています。 畠山氏は坂東八平氏の一つの秩父氏の一族で、武蔵国男衾郡畠山郷、現在の埼玉県深谷市畠山を領し、同族には江戸氏、河越氏、豊島氏などがあります。 多くの東国武士と同様に畠山氏も源氏の家人となっていましたが、父の重能は平治の乱で源義朝が敗死すると、平家に従って20年に亘り忠実な家人として仕えました。 1180年8月17日に義朝の三男・源頼朝が以仁王の令旨を奉じて挙兵しました。 この時、父・重能が大番役で京に上っていたため、領地にあった17歳の重忠が一族を率いることになり、平家方として頼朝討伐に向かいました。 23日に頼朝は石橋山の戦いで大庭景親に大敗を喫して潰走し、相模国まで来ていた畠山勢は頼朝方の三浦勢と遭遇し合戦となり、双方に死者を出して兵を引きました。 26日、河越重頼、江戸重長の軍勢と合流した重忠は三浦氏の本拠の衣笠城を攻め、三浦一族は城を捨てて逃亡しました。 重忠は一人城に残った老齢の当主で、母方の祖父である三浦義明を討ち取りました。 その後9月に頼朝が安房国で再挙し、千葉常胤、上総広常らを加えた大軍で房総半島に進軍し武蔵国に入りました。 すると10月に重忠は、河越重頼、江戸重長とともに長井渡しで頼朝に帰伏しました。 重忠は先陣を命じられて相模国へ進軍し、頼朝の大軍は抵抗を受けることなく鎌倉に入りました。 1183年に平家を追い払って京を支配していた源義仲と頼朝が対立し、頼朝は弟の源範頼と義経に6万騎を与えて近江国へ進出させました。 翌年正月に、鎌倉軍と義仲軍が宇治川と勢多で衝突し、義経の搦手に属していた重忠が丹党500騎を率い、馬筏を組んで真っ先に宇治川を押し渡りました。 宇治川の戦いで範頼、義経の鎌倉軍は勝利し、義仲は滅びました。 1184年2月に、範頼と義経は摂津国福原まで復帰していた平家を討つべく京を発向し、重忠は範頼の大手に属していました。 一ノ谷の戦いで鎌倉軍は大勝して、平家は讃岐国屋島へと逃れました。 その後、頼朝は範頼に大軍を預けて中国・九州へ遠征させましたが、 『吾妻鏡』ではこの軍の中に重忠の名は見当ないそうです。 1185年3月に、義経は壇ノ浦の戦いで平家を滅ぼしました。 その後、頼朝と義経は対立し、義経は京で挙兵しましたが失敗して逃亡しました。 義経の舅の河越重頼は連座して誅殺され、重頼の持っていた武蔵留守所惣検校職を重忠が継承しました。 1186年に義経の愛妾の静御前が頼朝の命で鶴岡八幡宮で白拍子の舞を披露したとき、重忠は銅拍子を打って伴奏を務めました。 1187年に、重忠が地頭に任ぜられた伊勢国沼田御厨で彼の代官が狼藉をはたらいたため、重忠の身柄は千葉胤正に囚人として預けられました。 頼朝は重忠の武勇を惜しみ赦免しましたが、重忠が一族とともに武蔵国の菅谷館へ戻ると侍所所司の梶原景時がこれを怪しみ謀反の疑いありと讒言しました。 頼朝は重臣を集めて重忠を討つべきか審議しましたが、小山朝政が重忠を弁護し、とりあえず、下河辺行平が使者として派遣されることになりました。 行平から事情を聞いた重忠は悲憤して自害しようとしましたが、行平がこれを押しとどめて鎌倉で申し開きするよう説得しました。 景時が取り調べにあたり、起請文を差し出すように求めましたが、重忠は「自分には二心がなく、言葉と心が違わないから起請文を出す必要はない」と言い張ったそうです。 これを景時が頼朝に取り次ぐと、頼朝は何も言わずに重忠と行平を召して褒美を与えて帰しました。 1189年夏の奥州合戦で先陣を務め勝利し、藤原泰衡は平泉を焼いて逃亡し、奥州藤原氏は滅びました。 奥州合戦の功により、陸奥国葛岡郡地頭職に任ぜられました。 1190年に頼朝が上洛した際は先陣を務め、右近衛大将拝賀の随兵7人の内に選ばれて参院の供奉をしました。 1193年に武蔵国の丹党と児玉党の両武士団の間に確執が生じ、合戦になる直前にまでおちいった際に仲裁に入り、和平をさせ国内の開戦を防ぎました。 1199年正月の頼朝の死去に際し、重忠は子孫を守護するように遺言を受けたといいます。 1203年の比企能員の変では、重忠は北条氏に味方して比企氏一族を滅ぼしました。 畠山氏が成立した12世紀前半~中葉は、日本中世の成立期にあたります。 この時期、日本列島各地に荘園が形成される一方、各国の国府の行政組織が管轄する公領も、中世なりの郡・郷として確定されていきました。 荘園と公領が一国内に併存し支配の単位として機能した荘園公領制を基盤として、中世前期の支配システムである荘園制が成立しました。 そして、中世前期の在地領主は都鄙間に立脚して所領を支配し、その所領を超えた地域の住民に影響力を行使する存在でした。 ですが、全ての武士が在地領主であったわけでも、在地領主の全てが武士であったわけでもありません。 武士とは武芸を家業とする職業身分であり、地方の所領に本拠を形成し、収益を取得する在地領主とは、そもそも異なります。 本書では、近年の武士研究・在地領主研究の達成をふまえ、武士(団)・在地領主としての畠山重忠・畠山氏のあり方をできる限り具体的に示すことを目指すといいます。 畠山重忠の振る舞い・言説に関する史料は多く残されていますが、そのほとんどは鎌倉末期に成立した 『吾妻鏡』や、 『平家物語 『諸本の記事です。 在世中においても一流の武士としての評価を得ながら、北条時政らのフレームアップによって非業の死を遂げた重忠の振る舞いの言説については、 『吾妻鏡』編者などによる賛美(曲筆)の可能性が古くから指摘されてきました。 本書でも、 『吾妻鏡』 『平家物語』諸本に記された重忠の振る舞い・言説の一つ一つを、無前提に事実としない自制を心がけたいとのことです。 本書ではこのようなスタンスのもと、 『吾妻鏡』 『平家物語』諸本の記事に加え、諸系図や考古学の成果・現地調査の成果などを援用することによって、武士団・在地領主としての畠山氏のあり方に迫っていきたいといいます。畠山重忠のスタンスープロローグ/秩父平氏の展開と中世の開幕(秩父平氏の形成/秩父重綱の時代)/畠山重能・重忠父子のサバイバル(畠山氏の成立と大蔵合戦/畠山重忠の登場)/豪族的武士としての畠山重忠(源頼朝と畠山重忠/在地領主としての畠山氏)/重忠の滅亡と畠山氏の再生(鎌倉幕府の政争と重忠/重忠の継承者たち )/畠山重忠・畠山氏の面貌ーエピローグ/あとがき[http://lifestyle.blogmura.com/comfortlife/ranking.html" target="_blank にほんブログ村 心地よい暮らし]中世武士 畠山重忠(477) 秩父平氏の嫡流 [ 清水 亮 ]畠山重忠
2023.05.13
コメント(0)
全2件 (2件中 1-2件目)
1