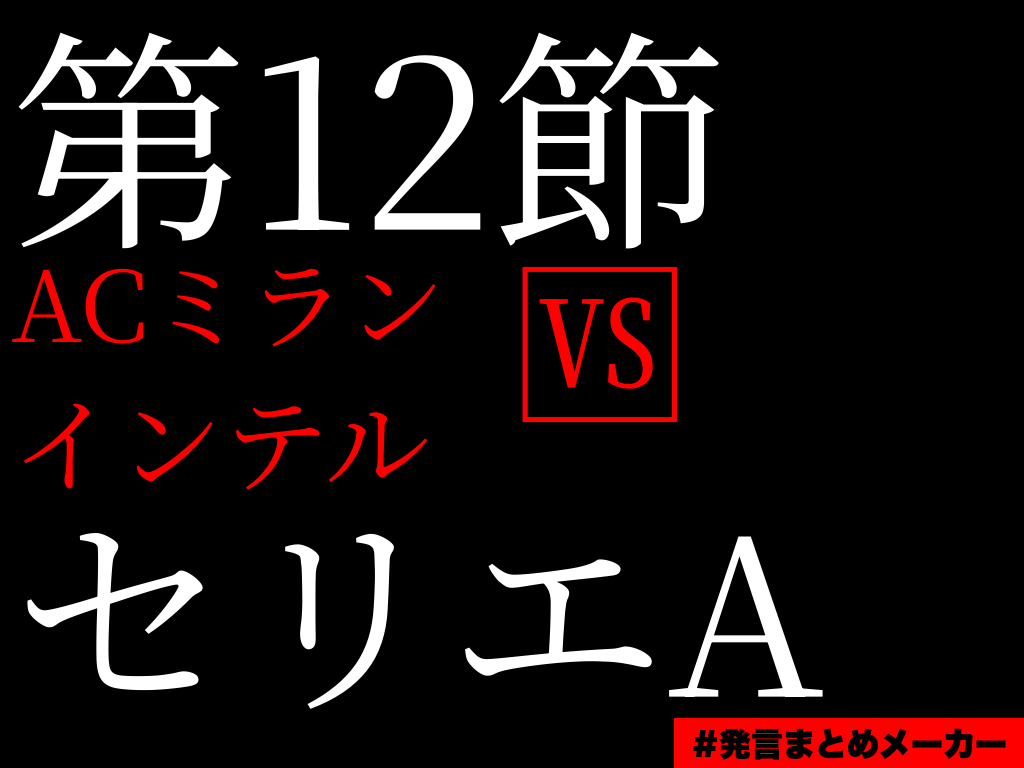2007年01月の記事
全19件 (19件中 1-19件目)
1
-
ADSL 20日には波照間と黒島、西表上原周辺でもサービスが始まる
やっとブロードバンド環境実現竹富町内で高速なインターネット接続環境を提供するADSL(非対称デジタル加入者線)サービスの開始記念式典が9日午前、竹富島まちなみ館で開かれた。県の離島地区ブロードバンド環境整備促進事業で2005-06年度に整備したもので、NTTによると、これまでに約380件の申し込みがあった。今回の辞表では整備されなかった船浮や鳩間などでは07年度に整備する予定になっており、町内全域の高速インターネットが可能になる。 今回サービスの提供が可能となるのは、竹富島と黒島、小浜島、波照間、西表東部の豊原、大原、大富、古見、同西部の船浦、上原、中野、住吉、浦内。8日にはすでに竹富と小浜、西表東部の大原周辺でサービスが始まっており、20日には波照間と黒島、西表上原周辺でもサービスが始まる。06年度までの2年間の総事業費は1億5600万円で、国が80%、県と町が10%ずつを負担した。 07年度事業ではアンテナを設置して無線で高速通信ができるように整備し、ADSLサービスの未提供地域を解消する計画。事業費は1億1000万円程度を見込む。 式典では、テープカットを行ったあと、大盛武町長が「町内でも最新の情報を瞬時に入手し、情報発信できるようになるなど、幅広い活動は可能となる」と式辞。 このあと、同館と町内の4校をADSL回線で結んでテレビ会談を行った。
2007年01月30日
-
新城島のジュゴン奉納頭骨について
八重山近海にジュゴン200頭20世紀初め・奉納頭骨解析で推測 【八重山】「八重山にジュゴンをとりもどそう」と題した研究報告会が十一月二十七日、石垣市の大浜信泉記念館で開かれた。竹富町新城島にある世界でも珍しい、ジュゴンの頭骨を奉納した「七門御嶽」の調査結果から、八重山近海には二十世紀初頭、約二百頭のジュゴンが生息していた、と推測されることが報告された。 文部科学省の助成金を受けて本年度までの五年間、八重山とジュゴンのかかわりを調査してきた研究者らでつくる「沖縄のジュゴン個体群の保全生物学的研究グループ」が報告した。 研究員の島袋綾野さん=石垣市=は「新城島のジュゴン奉納頭骨について」と題し報告。千片以上からなる頭骨の歯はすべて抜き取られており、「印材として利用されたと考えられる」と説明した。 これら頭骨を一個体ずつに復元し、年齢群に分けて解析した結果、「八重山には二百頭以上のジュゴンが生息していたと推定される。その後、明治中期から大正初めにかけて百五十頭前後のジュゴンが八重山海域で捕獲され、極端に減少した」という。 当山昌直さん=浦添市=は、八重山諸島におけるかつてのジュゴン猟について、住民らから聞き取り調査を行った結果を報告。ジュゴンは主に小浜島や石垣島の登野城、大川、石垣、新川、宮良、白保地区の前の浅瀬で捕れたことが分かった。「猟の時期は決まっていないが、時間帯はおおよそ夜。捕獲場所が決まっていた理由の一つに、ジュゴンの食草が関係していたようだ」と説明した。
2007年01月29日
-
石垣市新川から見た黒島
「島浮き」現象がこのほど撮影された。場所は石垣市新川から見た黒島で、島の根元が切れて浮き上がっているよう。 「島浮き」現象は蜃気楼(しんきろう)の1種で、海水の温度が気温より著しく高く、海面付近の層が上冷下暖の状態になったときに見られる光学的現象で、日本国内では冬の三陸や瀬戸内海、長崎県の端島(はしま)、通称・軍艦島などで確認されており、県内では珍しい。 この日の石垣島地方は最低気温12.5度と冷え込み、最高気温は20.5度と大きな気温差が生じ、上冷下暖の状態ができたとみられている。 「島浮き」現象を撮影した市内新川の中西康治さん(39)は「昔、大阪にいたころに1度見たことはあったが、青い海に浮かぶ島の風景はとても神秘的だった」と話した。
2007年01月27日
-
「黒島にアンテナを三基ほど導入すれば、島全体をカバーできるのではないか。事業を検討している」
肉用牛増頭でシンポジウム 肉用牛増頭シンポジウム(主催・沖縄総合事務局、全国肉用牛振興基金協会)が二十九日、八重山支庁で開かれた。牛の分べんの間隔を短くして繁殖性を改善し、肉用牛の増頭につなげる取り組みについて、事例発表や質疑応答が行なわれた。沖縄県は牛の初産月齢、分べん間隔とも全国より長くなっており、繁殖性を改善して「一年一産」を実現することで、現在七頭を産む期間内に八頭の分べんが可能とされる。経営改善に向けた「わが家のアイデアコンテスト」(主催・石垣島和牛改良組合女性部)も行なわれた。 県内の牛の平均初産月齢は二十六・四ヵ月(全国平均二十四)、平均分べん間隔は十四・四ヵ月(同十三・二ヵ月)となっている。 シンポジウムで比屋根牧場の比屋根和史さんは、牛の発情発見システム「牛歩」の導入事例を報告。牛に設置した万歩計から、パソコンに歩数が送信されるシステムで、牛の行動量がリアルタイムで把握できるため、発情の開始が明確になる。 導入後五カ月の結果では、導入前、繁殖障害などが原因でなかなか受胎しなかった六頭のうち五頭が、一~二回の人工授精で受胎したという。 琉球大生物生産学科の玉城政信助教授、鹿児島大農学部獣医学科の窪田力助教授ら専門家との質疑応答では、参加した農家から「牛歩」について「(従来は)発情を見過ごしていたことが結構多いのでは。これがないと仕事ができないほどだ」と普及を促す声が出た。 JAおきなわ八重山地区営農センターの又吉健夫畜産部長は「黒島にアンテナを三基ほど導入すれば、島全体をカバーできるのではないか。事業を検討している」と応じた。
2007年01月23日
-
オーストラリア・ブリスベーン→同ケアンズ→名古屋→米グアム。中部国際空港の滞在時間は、わずか60分
井端、大移動 自主トレ2人旅立浪の誘いに海外はしご決断 中日・井端弘和内野手(31)が13日、オーストラリアから航空機で中部国際空港に到着した。井端はそのままグアム自主トレに出発するため同空港にいた立浪和義内野手(37)と合流、約1時間後、グアムに向けて2人で出発した。5日から小田、鎌田を伴ってオーストラリアで自主トレしていたが、1日早く切り上げ、前代未聞の強行スケジュールでのグアム自主トレ合流。その狙いは立浪からのリーダーとしての心構えの伝授だった。 パイロットや外交官、エリートビジネスマンでもありえない!? オーストラリア・ブリスベーン→同ケアンズ→名古屋→米グアム。中部国際空港の滞在時間は、わずか60分。北へ南へ、井端が前代未聞の海外自主トレを敢行だ。 「2次キャンプに行ってきます。ハード? 自主トレはハードでいいんですよ」。約10時間ものフライトを終えて日本にたどり着いた井端の声は明らかにへばっていた。 今月5日に小田、鎌田とゴールドコーストに出発。予定では14日の帰国だった。その計画を急きょ変更。この日午後7時2分に到着すると、税関内で乗り継ぎ手続きを終えてグアム自主トレの相手・立浪と合流。午後8時2分に出発したグアム便に乗り込んだ。 グアム自主トレへの合流を、オーストラリア自主トレ中に呼びかけたのは先輩の立浪だった。実は昨年末から計画していたが、ケアンズ発グアム行きが週2便しかないなどの理由で、一度は立ち消えになりかけていた。それでもあえて日本経由の強行軍を選択したのは、中日を支えてきた先輩と行動をともにしたいという意欲の表れだった。 「これからは井端が引っ張っていかないといけない。昔、オレも星野(仙一元監督)さんから『調子が悪くても関係ない。言うことは言え』と言われたけど、井端も同じ。2人で一緒にいれば食事する時とか、そういう話にもなると思う」 出発前の立浪が力説した。今月初旬、井端が「いままで立浪さんに引っ張ってもらっていた。これからは自分が引っ張りたい」と発言。目覚めたリーダーへの意欲、それを先輩も感じ取っていた。現地ではランニング中心で調整するが“リーダーとしての心得”も授かることになる。 「立浪さんから勝負強さも学びたい」。総フライト時間は約13時間、精神的にも体力的にも強靭(きょうじん)なリーダーになって帰ってくるはずだ。
2007年01月21日
-
八重山周辺海域においてカツオノエボシやその仲間が多く見掛けられています
○カツオノエボシ(クラゲ) また、近年は八重山周辺海域においてカツオノエボシやその仲間が多く見掛けられています。 刺された時はそれほど痛みを感じませんが、数時間後から痛みや痒みが出てきますので注意が必要。 ハブクラゲ同様、手足以外の部位や広範囲に刺された時、体調に異常が見られた場合は早急に医師の診察を 受けて下さい。ハブクラゲ同様に毒が強いので要注意。(沖縄県立病院には血清があるそうです) ミミズ腫れになること,治療法を誤ると傷跡が残ることやショック死の危険性があります。 食酢をかけるのはハブクラゲだけ。それ以外のクラゲなどの場合、逆に刺激し刺胞を刺激する結果になる 可能性があります。 ※クラゲの仲間は、ハチやある種の食品などと同じように、アナフィラキシーショックを起こす可能性があります。
2007年01月17日
-
〔若雌一類〕▽最優秀・下地太(竹富町黒島)
入賞牛18頭決まる畜産共進会 八重山の優秀な肉用牛を一堂に集めて審査する第九回八重山郡畜産共進会(主催・同共進会協議会)が九日、石垣市の八重山家畜セリ市場で開かれた。審査結果は次の通り。〔成雌一類〕▽最優秀・新垣公得(石垣市大川)▽優秀・玉代勢元(竹富町黒島)▽優良・大底克(石垣市平得)〔成雌二類〕▽最優秀・仲嵩善幸(竹富町黒島)▽優秀・牛種子牧場(石垣市崎枝)▽優良・石川貴淳(同新川)〔若雌一類〕▽最優秀・下地太(竹富町黒島)▽優秀・牛種子牧場▽優良・石垣英樹(石垣市大浜)〔若雌二類〕▽最優秀・石垣英樹▽優秀・白玉克弘(石垣市大浜)▽優良・宮良実英(石垣市宮良)〔去勢子牛〕▽最優秀・前津盛祥(石垣市大浜)▽優秀・長嶺畜産(同大浜)▽優良・前津恵子(同大浜)〔雌子牛〕▽最優秀・南風本武一(竹富町南風見)▽優秀・大底克▽優良・多宇正栄(石垣市白保)〔肥育牛〕▽最優秀・金嶺克次(石垣市白保)▽優秀・仲大盛吉幸(同真栄里)▽優良・大和牧場(同
2007年01月16日
-
潮位が低いときは観光客がサンゴに接触しやすい場所でのシュノーケリングを避けることなどのサンゴ礁環境保全策を盛り込んでいる
サンゴ礁保護などルール化白保の観光事業者 石垣市白保の貴重なサンゴ礁を将来にわたって保全しようと、地域住民で組織する白保魚湧く海保全協議会(山城常和会長)はこのほど「サンゴ礁観光事業者のルール」を策定した。地元の観光事業者と合意した自主的なルール。潮位が低いときは観光客がサンゴに接触しやすい場所でのシュノーケリングを避けることなどのサンゴ礁環境保全策を盛り込んでいる。観光事業者が守るべきルールが明文化されるのは初めて。同協議会は「白保のシュノーケリング観光の質が高まるのでは」と期待している。同協議会は昨年九月から、白保海域を観光資源として利用する民宿やシュノーケル業者など十六業者と自主ルールづくりに向けた話し合いを続けてきた。ルールは、六月の同協議会総会、今月八日の白保公民館運営審議委員会で承認を得た。
2007年01月15日
-
竹富島からは黒島、西表島からは鳩間と内離、舟浮、新城島に送電されている。
小浜島に「電力直行便」海底ケーブル敷設で竣工式 沖縄電力が石垣島~小浜島間で初めて敷設した海底ケーブルの竣工式が二十二日、同社八重山支店で開かれた。従来、竹富町の島々への電力供給は石垣島~竹富島間の海底ケーブルで竹富島を経由して行われていたが、石垣島から直接小浜島に送電する海底ケーブルの敷設で、電力安定供給の信頼性が向上するものと期待されている。石垣~小浜海底ケーブルは七日から運用開始している。竹富町への電力供給は、石垣~竹富島~小浜島~西表島のルートで行われている。石垣~竹富島、竹富島~小浜島で各二本、計四本の海底ケーブルを使用。電力供給はすべて竹富島を経由する方法を取っている。竹富島からは黒島、西表島からは鳩間と内離、舟浮、新城島に送電されている。石垣~竹富島、竹富島~小浜島の海底ケーブル1号は一九七四年に運用開始し、三十年経過して老朽化。同社はケーブルの取り替えを検討したが、過去に石垣~竹富島間では、クリアランス船の投錨による海底ケーブル切断事故が発生していることから、石垣島から小浜島へ直接送電する海底ケーブルを敷設することになった。
2007年01月14日
-
新石垣空港起工式が二十日午後、白保の建設予定地で開かれ、各界の関係者多数が八重山の歴史的な節目を祝った
新石垣空港、待望の起工式自然環境への配慮が課題 新石垣空港起工式が二十日午後、白保の建設予定地で開かれ、各界の関係者多数が八重山の歴史的な節目を祝った。一九七六年に県が新空港基本計画を策定してから三十年。環境保護と開発のはざまで揺れ続けた住民の「悲願」は、達成に向けた確かな一歩を踏み出した。起工式で稲嶺恵一県知事は「産業基盤の整備や観光資源の活用、交流・物流の拡大など、八重山圏域の振興発展に大きく貢献する」と式辞。自然環境に配慮しながら整備事業を進めていく方針を改めて示した。整備事業が順調に進めば、新空港は二〇一二年度末に供用開始する。総事業費は約四百二十億円。この日は、さわやかな秋晴れ。起工式に先立ち、白保の神司四人が天、地、水の神に工事の安全を願う地鎮祭(シチマチリ)をとり行った。地固め(ジービシ)では、稲嶺知事や大浜長照市長(八重山市町会会長)、施工業者代表や九人がクワ入れした。
2007年01月11日
-
ハブの20倍以上の強力な毒をもっている
○ウミヘビは人を襲いません! よほどのことがない限り(通常ウミヘビ自身が身の危険を感じない限り)、ウミヘビが人間を襲うことはありません。 つかんで放さなかったり、踏みつけたり、イタズラをして咬まれることは考えられますが、なにもしていないのに 咬んでくるようなことはありません。 しかし、ハブの20倍以上の強力な毒をもっていると言われていますから、その毒が体に入ってしまった場合は 確実に死亡しますので注意が必要です。 他の生物も同様。むやみに触ったり、刺激しないようにしましょう。 (一部の縄張りを持つ魚などは、そのテリトリーに入ると攻撃をしてくることがあります。 そんな場合は、引き返すなどその場から離れると大丈夫)
2007年01月09日
-
2006/5/3現在、今年はすでに7件の咬傷被害が出ている
ハブ(ヘビ)について○2006/5/3現在、今年はすでに7件の咬傷被害が出ている(例年平均4件)。○ハブは、毒の強い蛇で、かまれると激痛を伴い肉体組織の壊死がおきる。 かまれた場合は速やかに病院に。大きな病院では血清も準備されている。 もしも咬まれた場合は、119番に連絡するか、八重山病院へ(このページ最下部に連絡先あり) 傷口から毒を口や毒吸いだし器で吸い出したり、(口内に傷がないこと・飲みこまないこと) 心臓に近い側を強めに縛るのも有効(20分に1回はゆるめること)。○八重山諸島に生息するハブはサキシマハブで、ハブの中では毒性はあまり強くないほう。 八重山諸島では、石垣島、西表島、外離島、内離島、小浜島、竹富島、黒島、カヤマ島に生息している。○春暖かくなると活動をはじめ、冬期気温が下がる頃まで活動に活動。湿った場所を好み、夜行性。 日中は岩穴や木陰、木の上などの日のあたらない場所で休んでいます。 主にネズミなどを食べているので、畑に多くみられます。 農作業や草刈り作業時に被害に遭うことが多い。また、琉球列島のハブは冬眠しない。 普段、日中に野山に入ってもめったに出会うことはありませんが、危険な場所に入っていくときは、急に驚 かさないよう、熊に対してと同じように歌を歌ったり、音を立てながら歩くといいでしょう。 また、咬傷を防ぐには、ハブの眼は光を感じる程度で、体の熱を感じて襲ってきます。熱を通しにくいゴムで できた長靴・ゴム長が有効です。○ハブの頭は毒蛇特有のエラが張ったような三角形。体色は赤茶色で体にクサビ状の模様が入っています。 また、もちろん沖縄でもハブ以外にたくさんのヘビが住んでいます。
2007年01月08日
-
竹富町は二日、約三年四ヵ月ぶりに黒島診療所の常駐医を確保した
黒島の常駐医確保三年四ヵ月ぶりに 竹富町は二日、約三年四ヵ月ぶりに黒島診療所の常駐医を確保した。大盛武町長が、福岡県の久留米大から来島した田中勝一郎医師(33)に、町役場で委嘱状を交付した。田中医師は五日から現地での診療を開始する。黒島では二〇〇三年五月末、診療所を運営していた医介輔(いかいほ)が引退して以来、常駐医の不在が長引いていた。地元からは「常駐医がいてくれることは心強い」と歓迎する声が上がっている。田中医師は月曜日から金曜日まで勤務する。診療時間は午前九時から午後四時。町は来月までに、看護師一人、受付医療事務一人を配置し、三人体制で診療所を運営する方針。委嘱状交付式で田中医師は「地域の人たちの健康を守るために、精一杯努力したい」と抱負を語った。
2007年01月07日
-
石垣―伊丹線の運休
日本トランスオーシャン航空(JTA、市ノ澤武士社長)はこのほど、石垣―伊丹線の運休と、石垣―神戸線の開設を決定した。JTAは現在、石垣から関西圏の直行便として石垣―関西、伊丹線を二路線それぞれ毎日一往復運航している。このうち、伊丹線が四月一日で運休とし、七月一日から石垣―神戸線を(毎日一往復)の開設を計画しており、関西圏の直行路線全体を次年度も二路線(一日合計二往復)の運航を維持していく。
2007年01月06日
-
世界に誇る白保の海、アオサンゴの海が今後も変わらぬ姿で、観光客を迎えられるようにしてほしい
児童生徒がメッセージ朗読新空港の早期開港に期待 二十日の新空港起工式では、白保小、白保中の児童生徒二人がメッセージを朗読し、次代の担い手として、島の未来を開く新空港の早期開港に期待した。白保中三年の菊池円さんは「新空港への願いを込めて」と題して発表。現空港の滑走路が短く、オーバーラン事故の危険性が指摘されていることに「事故の起きる心配がなく、気軽に利用できる安心・安全な新空港が一日も早く開港してほしい」と訴えた。その上で「世界に誇る白保の海、アオサンゴの海が今後も変わらぬ姿で、観光客を迎えられるようにしてほしい。さらに多くの観光客が石垣島を訪れるようになると、白保はだんだん活気に満ちていくと思う」と期待。「できたら、新空港供用開始一番機に乗りたい」と述べると、会場から拍手が起こった。「未来へ広がる新石垣空港」と題し発表した白保小六年の仲宗根莉也君は「(新空港は)ぼくたちの大切な自然のことを考えて作ってください。そうすれば、便利ですばらしい空港になり、観光客も増え、きれいな石垣島をたくさんの人に見てもらえると思う」と呼び掛けた。
2007年01月05日
-
石垣島においては東シナ海側のフサキ,名蔵湾,底地,石崎,裏底湾等に多い
○ハブクラゲ ハブクラゲは自力遊泳力が強く、比較的波が穏やかで、遠浅の砂地の海岸の波打ち際に多くみられます。 ハブクラゲは小魚が多く集まる場所に捕食に来ているのであって、人間を狙ってきているのではありません。 特に、子供たちが波打ち際でバシャバシャ水しぶきをあげると、小魚が跳ねているものと勘違いしてハブクラゲ が寄ってきますので注意して下さい。 (石垣島においては東シナ海側のフサキ,名蔵湾,底地,石崎,裏底湾等に多い) 夏の時期、波打ち際で激痛が走れば、ほぼこのクラゲに間違いないでしょう。即座に海からあがり、誰かに 救助を求めてください。透明の糸状の触手が付着している場合は、指、割り箸などで触手をはがして下さい。 くれぐれも擦らないで、指などで剥がすこと。(指先などの厚い皮膚の部分には毒針が刺さりません) (もし、食酢があれば触手をはがす前にしばらくかけ続ける) (四肢以外の場所を刺された場合や)子供、異常が感じられた場合などは早急に医師に相談すること。 ミミズ腫れになること,治療法を誤ると傷跡が残ることやショック死の危険性があります。
2007年01月04日
-
石垣市の株式会社石垣の塩(東郷清龍代表取締役)の製品を使った「かっぱえびせん のり塩」
カルビー株式会社(本社東京)は、石垣市の株式会社石垣の塩(東郷清龍代表取締役)の製品を使った「かっぱえびせん のり塩」をこのほど期間限定で再発売した。カルビーがかっぱえびせんのホームページ上で実施した人気投票で第一位に選ばれたことを受けたもので、石垣の塩社は「石垣島のイメージアップにも寄与できる」と喜んでいる。
2007年01月03日
-
八重山にジュゴンを取り戻そう
八重山ジュゴンを取り戻そう研究グループが報告会 「八重山にジュゴンを取り戻そう!」をテーマにした公開報告会(主催・竹富町教育委員会、共催・石垣市教育委員会)が二十七日夜、市内の大浜信泉記念館で開かれた。研究グループが、ジュゴンを祀った新城島下地の七門御嶽の調査結果から「八重山には少なくとも二百頭余りのジュゴンが生息していた」と報告。竹富町が世界自然遺産登録を目指していることについて「絶滅に向かっているジュゴンを取り戻す目標を持つことは(登録を進める上で)評価されると思う」と指摘した。報告したのは、科学研究費沖縄のジュゴン個体群の保全生物学的研究グループ。文部科学省の助成金を受け、今年度まで五年間、八重山とジュゴンの係わりについて研究を進めてきた。
2007年01月02日
-
打率、本塁打、打点ではなくヒーローインタビューの回数増が公約だ。
谷繁、恐怖の8番復活だ横浜での自主トレ公開 中日の谷繁元信捕手(36)が11日、横浜市内の国学院大グラウンドで自主トレを公開した。すでに肩は7割できており、捕手・谷繁は調整順調。だが、今季こだわるのは打者・谷繁。鬼の8番打者復活へ、自らに課したノルマとは…。 年末から年始にかけて、ハワイで肉体の土台を作り、国学院大で仕上げる。沖縄に乗り込むのは月末ぎりぎりというスケジュール。19年目の今季も谷繁の足取りは変わらない。 「調整? さすがに去年よりは少し遅いですよ。でも順調です」。ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)への出場が決まっていた昨年よりも、若干遅い程度。谷繁が笑顔をこぼす理由もここにある。小田の挑戦をはねつけ、希望枠ルーキー・田中にプロのレベルを見せつけたいシーズン。捕手としてはもちろんだが、今季の谷繁がこだわるのは打者として。それも「打ちっぷり」だ。 「守るだけじゃなく、やっぱり打たなきゃいけないっていうことです。それもここぞっていう場面でね。(昨季は)得点圏打率(2割5分)そのものは前の年と変わりなかったんですが、そういうヒットが少なかった。今年はヒーローになって、インタビューを受ける機会が増えるようにがんばります」 打率、本塁打、打点ではなくヒーローインタビューの回数増が谷繁の公約だ。本拠地ならばお立ち台、敵地でもベンチ前のインタビューがヒーローの特権だ。設定したノルマ回数は「5回だと少ない。8回。末広がりってことで」。勝利を決定づける一打を8番打者が8回打つようなら、そのチームはかなり強い。もちろん、ヒーローになったあかつきには…。 「舌もなめらかに回るようにしなきゃね」。バットを3年前までの太めタイプに戻した。右肩が突っ込み気味だった悪癖も修正した。勝利を呼び寄せ、マイクを握り、ファンに訴える。目標8回。鬼の8番が復活する。
2007年01月01日
全19件 (19件中 1-19件目)
1