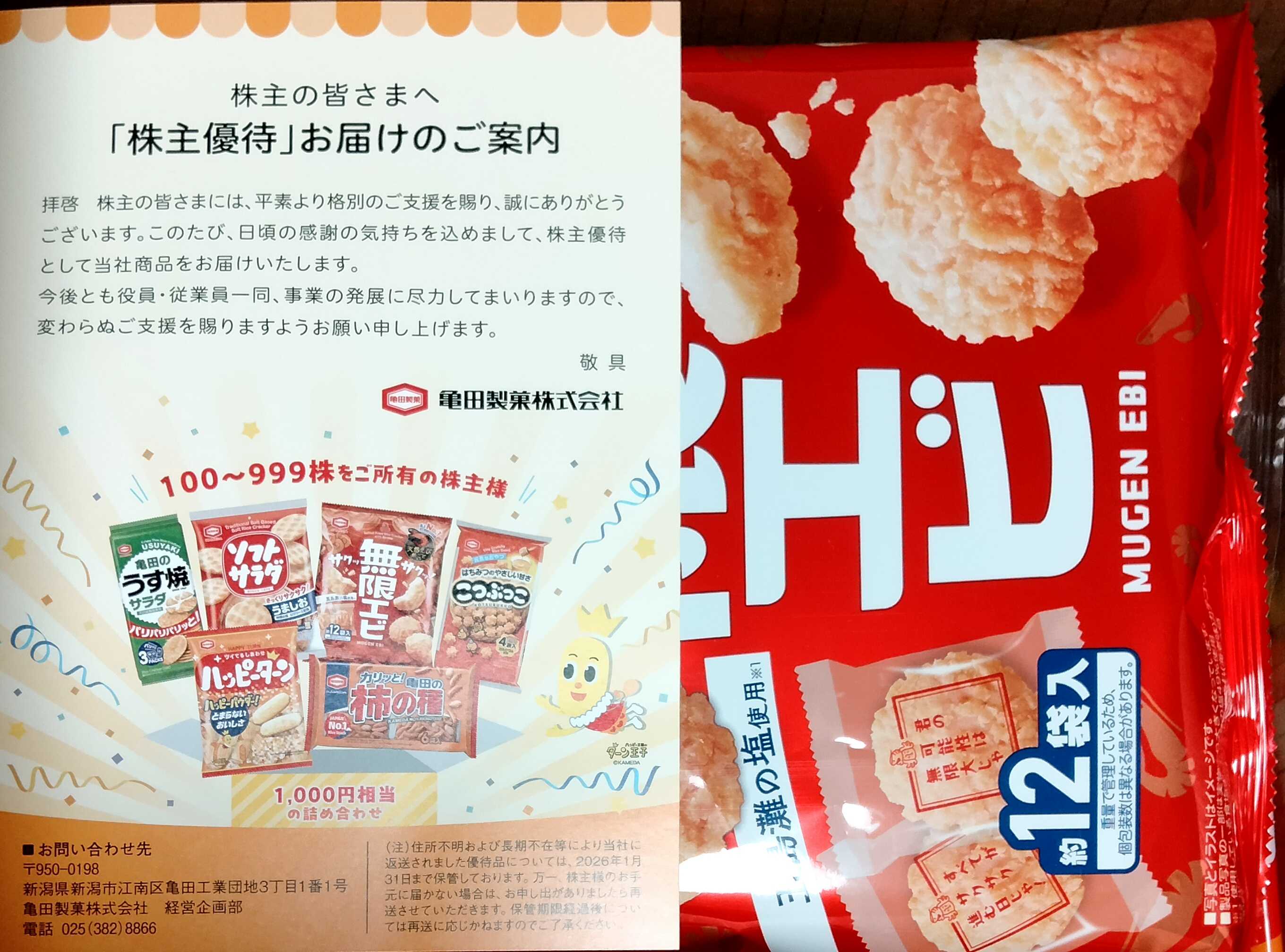2016年02月の記事
全67件 (67件中 1-50件目)
-
2月29日(月) 仕事の棚卸し
2月29日(月) 仕事の棚卸し 春は、職場においても人の出入りが多くなる時期です。勤める部署は替わらなくても、仕事の範囲や担当が替わる人もいるでしょう。 私たちの仕事はすべて、最後は、会社に返す仕事です。今引き受けている仕事も、いずれ新任者に引き継いだり、後進に譲る時がやってきます。 担当者が替わるたびに「前はできたが、今はできない」「担当が替わったので、よくわからない」ということでは、周囲も困ってしまうでしょう。 職場は、様々な人の個性があってこそ成り立つものですが、チームの仕事であるからには、一定の平準化は必要です。 今の仕事を「次の担当者がやりやすいか、否か」という視点で振り返って、蓄積していくデータの見直しや、備品の整理をしていきましょう。 会社の仕事は、今だけではなく、これから先も継続していきます。「前任者がよく整理しておいてくれたお陰で、スムーズに引き継ぐことができた」と言われるよう、日頃から心がけておきたいものです。 今日の心がけ◆先を見据えて整理をしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。
2016年02月29日
コメント(0)
-
2月28日(日) 一日一回
2月28日(日) 一日一回 大小の違いはあっても、誰もが「こうなりたい」という将来への夢や希望を持っているでしょう。 その夢が実現するかどうか、あるいは夢に近づけるか、成就へと導くキーワードの一つに、「一日一回」があります。 これは、地球のリズムに乗るということです。地球は一日に一回転します。そこで、自分の夢を一日一回、声に出してみましょう。または、文字に表わしてみましょう。この一日一回を毎日繰り返してみるのです。 未来は、急にはやってきません。今日の続きが明日であり、未来です。未来を輝かせるには、今日一日を輝かせることです。 一日一回と心に決め、今日一日を大切にしていると、次第に「いつまでに」という期限が設定されます。この時、夢ははっきりとした目標へと転ずるのです。 目標となった時、漠然としていた夢が、具体的なイメージとなって、頭の中に鮮明に浮かび上がるでしょう。一日一回が成功の秘訣です。 今日の心がけ◆自分の夢を一日一回言葉にしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。朝礼に利用すると、とても効果が高いと思います。書店では売っていません。倫理法人会に入会すると毎月30冊もらえます。職場の教養は、毎日当日分を掲載しています。朝礼の準備などであらかじめ読みたい方のため、楽天ブログの当月の1日に、1か月分をまとめて掲載させていただきます。左のカレンダーから1日をクリックしてください。翌月分の職場の教養は20日に、それまでに出来たぶんだけを掲載します。
2016年02月28日
コメント(0)
-
2月27日(土) 偕楽園
2月27日(土) 偕楽園 日本三名園の一つ、茨城県水戸市の偕楽園では、二月下旬から「梅まつり」が始まります。 偕楽園は天保十三年(一八四二年)に、水戸藩第九代藩主の徳川斉昭によって開園され、約百品種、三千本といわれる見事な梅林で有名です。 偕楽園の「偕」とは「ともに」という意味で、武士だけでなく、一般の領民とともに楽しむ園にしたい、という斉昭公の願いが込められています。 そのため、偕楽園は、水戸藩の一般領民にも広く開放されました。「ともに楽しむ」という精神は、その後も受け継がれており、偕楽園は現在でも入園無料となっています。 また、領民の憩いの場とされただけではなく、梅は梅干として備蓄食料となり、園内には弓の材料にする孟宗竹の林もあり、さらに園内随一の見晴らし台は、有事には砲台としての利用も考慮されていたといわれます。 梅を楽しむだけではなく、水戸城を守る防衛上の配慮もされていたのです。 今日の心がけ◆地域の名所について学びましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。
2016年02月27日
コメント(0)
-
2月26日(金) 名前に込められた想い
2月26日(金) 名前に込められた想い ベネッセコーポレーションが、二〇一五年に産まれた赤ちゃんの名前人気ランキングを発表しました。男の子の一位は「悠真」、女の子の一位は「葵」でした。 男女それぞれ十位以内に、「大和」や「さくら」といった名前がランクインしています。ラグビー日本代表などの活躍が、日本の良さを再認識させるきっかけになったからではないかと、同社では分析しています。 Mさんが、小学四年生の息子の授業参観に参加した時のことです。親には事前に、「お子さんへ手紙を書いてください」という宿題が出ていました。 Mさんが手紙に書いたのは、長男の名前の由来でした。どのような想いを込めて名前を付けたか、手紙で初めて息子に伝えたのです。 授業参観の後、長男から返事をもらったMさん。感謝の言葉と共に記された文面を読み、自分の想いが伝わったことを嬉しく思いました。 名前は、親が最初にわが子へ贈るプレゼントです。自分の名前の由来を知ることは、親の願いを受け止めることになるでしょう。 今日の心がけ◆名前の由来を知りましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。
2016年02月26日
コメント(0)
-
2月25日(木) 「ハイ」の力
2月25日(木) 「ハイ」の力 N社長は、休日に、自宅で庭木の手入れをしていました。 居間でテレビを見ていた小学生の孫に、「縁側にある剪定ばさみを持ってきて!」と声をかけました。しかし、返事がありません。 思わず「おーい、○○君、聞こえないのか!」と大きな声を出すと、孫はしぶしぶ立ち上がって、はさみを持ってきました。 呼ばれたら返事をするようにと、孫に言って聞かせたN社長。「返事がないと聞こえているのかわからないし、無視されたと思うと、いい気持ちはしないよ」と孫に話しながら、さて、自分自身はどうだろうと振り返ったのです。 会社で社員に呼ばれても、返事をしないことはよくあります。自分では「身内だから」「社長だから」という思いがあったのですが、社員にとっては、決していい気持ちはしなかっただろうと反省しました。 たった一言の「ハイ」という言葉ですが、その力は絶大です。相手の存在を認め、受け入れる意思表示であり、好意を示すバロメーターでもあるのです。 今日の心がけ◆爽やかな返事をしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在まで一日も欠くことなくずっと続いています。著作権に問題があることは承知していますが、倫理の普及に役立ち、かつO君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。以上の点をご理解いただき、文章の取り扱いには配慮をお願いします。
2016年02月25日
コメント(0)
-
2月24日(水) 聞いていないのは誰?
2月24日(水) 聞いていないのは誰? 出張の多いAさんは、日頃から、早めの準備を心がけています。先の予定を見越して、妻にもあれこれ頼みごとをしています。 ある時、妻に「この前クリーニングを頼んだスーツを着て出張に行く」と告げると、妻は「忘れていた」と言います。Aさんは「二週間も前にお願いしたことだよ。しっかり聞いてないから忘れるんだ」と、妻に厳しく言ったのです。 そんなAさんですが、今度は、息子との会話でハッとさせられることがありました。小学生の息子から「歴史の勉強いつ教えてくれるの?どうせ教えてくれないんでしょ」と言われたのです。 実は、歴史好きな息子から、以前からせがまれていたのでした。「いいよ」と返事をしながら、そのことをすっかり忘れていたのです。 「そうだったね、ごめんね」と息子に謝りながら、自分も家族の話を聞いていなかったことを反省したAさんです。その後、忘れそうなことはカレンダーにメモをすることが、家族みんなの習慣になりました。 今日の心がけ◆相手の話をしっかり聞きましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。
2016年02月24日
コメント(0)
-
2月23日(火) 「机の上」を整える
2月23日(火) 「机の上」を整える 今やパソコンは、様々な業種で欠くことのできないツールとなりました。 文書やグラフなどの資料作成や、社内外における情報の伝達や共有においても、重要な役割を果たしています。容量や処理速度などの性能は、日進月歩をもじって「秒進分歩」とまでいわれるほど、進化を続けています。 パソコンを起動すると、画面にはデスクトップが表示されます。デスクトップには、様々な絵柄のアイコンやボタンが配置されています。 デスクトップとは、日本語では「机の上」です。仕事をする机の上が散らかっていたり、不要な書類が山積みになっていては、必要な資料が取り出せません。 パソコンのデスクトップも同様です。アイコンだらけで整理されていないと、効果的な仕事はできないでしょう。 デスクトップにたくさんのアイコンがあると、それを読み込むためのメモリを消費し、動作が遅くなる原因にもなります。余計なファイルやフォルダ、使っていないアイコンがないか、定期的に見直して、すっきりさせたいものです。 今日の心がけ◆パソコンを整理しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在までずっと続いています。O君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。
2016年02月23日
コメント(0)
-
2月22日(月) 問いを発する
2月22日(月) 問いを発する 何事にもよく気がついて、積極的に動ける人に、共通していることがあります。それは、問題意識を持って、仕事に取り組んでいることです。 問題意識は、どのようなことにも関心を持ち、よく見て、考えるところから芽生えてきます。問題意識とは、答えを求める心であり、問いを発する意識のことでもあります。 例えば、「お客様に喜んでもらうためにできることはないか」「職場を明るくするために何ができるか」「いきいきと生活するにはどうすればよいか」「家族が仲良くするには何をすればよいか」など、身のまわりをよく見ていると、問題がたくさんあることに気がつきます。 ここで、気をつけたいことは、他人の問題ではないということです。本当の問題意識とは、「自分には何ができるか」を問うことであって、周囲の人たちを責めるために問うのではありません。 正しい問題意識のある人は、人間としても成長していく人だといえるでしょう。 今日の心がけ◆健全な問題意識を持ちましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。日本各地にある倫理法人会では、毎週「モーニングセミナー」が開催されます。また毎月1回「経営者の集い」があります。モーニングセミナーも経営者の集いも、一般の方や社員に参加いただけます。いずれも経営のためだけでなく人生を豊かに過ごすための講演会です。(私自身が誤解していましたので、あえて申し添えます。宗教ではありません)
2016年02月22日
コメント(0)
-
2月21日(日) 応急手当てのガイドライン
2月21日(日) 応急手当てのガイドライン 応急手当ての方法は、五年に一度、より良い方法へ改正されています。 目の前で倒れている人のために、救急車が到着するまでの間。一般市民ができることをより有効に行なうことで、救命率や社会復帰率を高めるためです。 二〇一五年の改正では、胸骨圧迫の回数について、これまでの「一分間に百回以上」から「百~百二十回の間」に見直されました。その深さも「五センチ以上」から「五~六センチ」と改正されています。最も大きな特徴は、心停止状態かどうかの判断に迷っても、まず心臓マッサージを開始するよう明示されたことです。 「AED」の普及率も向上してきましたが、救命の他にも、事業所では通報、消火、避難誘導などの訓練を毎年実施することが義務づけられています。 緊急事態は、いつ、どのような形で、誰に訪れるか予測できないだけに、日頃から、防災に対する意識づけや情報の共有を大切にしていきたいものです。 また、個人としても、不規則な生活による睡眠不足やストレスの蓄積は万病の元だと捉えて、病気を予防する生活を心がけましょう。 今日の心がけ◆不測の事態に備えましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。
2016年02月21日
コメント(0)
-
3月10日(木) いつも心にナマズを
3月10日(木) いつも心にナマズを 「一年の計は元旦にあり」という諺があります。一年の初めである元旦に、その年の決意や抱負を声に出したり、紙に書いたりして披瀝します。 しかし、どんなに強い思いであっても、二月、三月と時が経つにつれ、その熱意は薄れ、緊張感も欠けてしまいがちです。 緊張感を持ち続けることの効用として、御誕生寺の住職・板橋興宗氏は、自著の中で、次のような話を紹介しています。 外国から日本にウナギの稚魚を運ぶ際、途中で八割から九割が死んでしまうそうです。 ところが、天敵であるナマズを一匹入れておくと、二割はナマズに食べられてしまいますが、残りの八割は生きていて、しかも飛びっきりイキがいいそうです。 「生き物というのはちょっと緊張感があったほうが生命力、活力が高まる」と述べる氏。慣れやマンネリ、熱意が薄れていることを感じたら、心にナマズを置いて、自分を奮い立たせる気持ちを常に持ちたいものです。 今日の心がけ◆緊張感を持って業務に臨みましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在まで一日も欠くことなくずっと続いています。著作権に問題があることは承知していますが、倫理の普及に役立ち、かつO君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。以上の点をご理解いただき、文章の取り扱いには配慮をお願いします。
2016年02月20日
コメント(0)
-
3月 9日(水) きょうだいの言い分
3月 9日(水) きょうだいの言い分 Kさんには、七歳と五歳の二人の息子がいます。 いつも兄が、弟をからかっては、泣かせています。いつか兄に、「自分より弱いもの、下のものをかばってやらなければいけない」と、言い聞かせようと思っていました。 その日も、きょうだいの言い合いが始まりました。Kさんは、兄の手が出る前によく言い聞かせようと、二人を呼び寄せました。 すると、弟に言い分があったのはもちろんですが、兄にもしっかりとした言い分のあることがわかったのです。弟を思う気持ちも伝わってきました。 このことから一歩進んで、両者の間に対立がある時は、どちらにも「自分が正しい」という言い分があるからこそ対立するのだと学びました。そして、今後は二人の話をよく聞こうと思ったのです。 現象だけを見て決めつけていた自分を反省したKさんは、何事も状況をしっかりと見極めてから判断しようと心に決めたのです。 今日の心がけ◆相手の言い分にも心を傾けましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。職場の教養を利用すると、活力ある朝礼をするのに役立ちます。倫理法人会に入会すると毎月30冊送ってもらえます。ご希望があれば、活力朝礼のやりかたを指導してもらえます。(もちろん無料で)お問いあわせはお近くの倫理法人会まで
2016年02月20日
コメント(0)
-
3月 8日(火) 一字の微差大差
3月 8日(火) 一字の微差大差 Yさんは日頃、部下に、積極的に言葉をかけるようにしています。「頑張っているか」と問いかけては、様子をうかがいます。 部下は「はい」と答えながらも、覇気のない様子です。〈これだけ話しかけているのに、なぜ無愛想な返事しかできないのだ〉と、苛立ちがつのりました。 家庭内でも同様に、「風呂は沸いているか」「勉強しているか」と問いかけていると、ある時妻に、「信頼されていないように感じる」と告げられました。 人は、高圧的な物の言い方には、反発を覚えるものです。〈自分は上司だ〉 〈一家の主だ〉という思いが強ければ、仮に相手を動かすことはできても、心を動かすことはできないでしょう。 妻の言葉に、日頃の物言いを振り返ったYさん。翌朝から「おはよう、今日も元気に頑張っているね」と肯定する言葉をかけるようにしました。職場の雰囲気に活気が出ると共に、部下の頑張りにも気がつくようになったのです。 語尾の「か」と「ね」、わずか一字の違いですが、職場は大きく変化しました。 今日の心がけ◆肯定的な言葉を使いましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在までずっと続いています。O君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。
2016年02月20日
コメント(0)
-
3月 7日(月) 結果にこだわる
3月 7日(月) 結果にこだわる 女子サッカー選手の澤穂希さんが、現役を引退しました。 昨年末の皇后杯決勝で、決勝ゴールを決めて有終の美を飾った澤さん。二十年以上にわたり日本女子サッカーを牽引し、六大会連続で、W杯に出場しました。 日本代表として国際Aマッチ二百五試合出場、八十三得点は、男女を通じて国内最多です。現役引退の記者会見では、「結果が全て」と振り返りました。 なぜなら、結果の善し悪しが、選手の待遇面や練習環境に直結していたからです。結果にこだわる背景には、「少しでもいい環境でプレーしてほしい」と、後輩たちの行く末を案ずる思いもあったのでしょう。 私たち職場人にとって、こだわるべき結果とは、仕事を通じて、何らかの形でお客様に喜ばれることです。 お客様に関わる人はお客様を、また、直接関わらない場合でも、同僚や上司、取引先の向こうにいるお客様を常にイメージして、喜ばれる働きにこだわりたいものです。 今日の心がけ◆喜ばれる働きを目指しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。
2016年02月20日
コメント(0)
-
3月 6日(日) 曲水の宴
3月 6日(日) 曲水の宴 漢人も 筏浮かべて 遊ぶてふ 今日そ我が背子 花綴せな これは、万葉歌人・大伴家持が、曲水の宴を催した時に詠んだ歌です。「中国の風流な人たちも筏を浮かべて遊ぶという今日の日です。さあ皆さん、花で編んだ髪飾りをおつけなさい」という意味です。 曲水の宴は、平安時代に朝廷や公家の間で、年中行事の一つとして、三月三日に行なわれていました。その起源は、中国古代だとも伝えられ、書聖・王義之が催した曲水の宴は有名です。 曲水の宴は、現在でも各地で催されています。色とりどりの平安装束を身につけた出席者が、庭園の水の流れのふちに座ります。 流れてくる盃が自分の前を通り過ぎるまでに、即興で詩歌を詠みます。その詩歌を筆で認めて、盃の酒を飲んで次へ流すという雅なものです。 平安時代の美しい着物を身にまとまった人々が、ゆったりとした時間が流れる庭園に集う情景は、まるで王朝絵巻のようです。 今日の心がけ◆伝統行事に関心を持ちましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。朝礼に利用すると、とても効果が高いと思います。書店では売っていません。倫理法人会に入会すると毎月30冊もらえます。職場の教養は、毎日当日分を掲載しています。朝礼の準備などであらかじめ読みたい方のため、楽天ブログの当月の1日に、1か月分をまとめて掲載させていただきます。左のカレンダーから1日をクリックしてください。翌月分の職場の教養は20日に、それまでに出来たぶんだけを掲載します。
2016年02月20日
コメント(0)
-
3月 5日(土) 挨拶の形と心
3月 5日(土) 挨拶の形と心 Bさんが一礼して部屋を出る際、先輩から思いがけない言葉が飛んで来ました。 「君のお辞儀はコメツキバッタのようだね」。さらに「今どんな気持ちで礼をしたんだい?」と聞かれ、言葉に詰まってしまいました。 Bさんの会社では、挨拶の型を重視しています。顎をひくこと、腰骨を立てること、指先をそろえること、そして、頭を下げた時も背筋が伸びていると、きれいなお辞儀ができることなどを、社員研修で教わっていました。 Bさんも、いつもその型を意識していました。ただ、形を意識するだけで、気持ちはまったく伴っていなかったのです。心ここにあらずで、ペコペコ頭を下げる姿を捉えて、先輩はコメツキバッタと揶揄したのでしょう。 挨拶に限らず、礼儀作法は、相手や場所への敬意を形で示すものです。形と心が一致した挨拶は、受け手だけでなく、周囲をも清々しくさせます。 指摘してくれた先輩に、〈ありがとうございます〉と心に思いながら、深く頭を下げたBさんでした。 今日の心がけ◆形と心を一致させましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。職場の教養は、毎日当日分を掲載しています。職場の教養を使うと、活力あふれる朝礼が出来ます。朝礼の準備などであらかじめ読みたい方のため、楽天ブログの当月の1日に、1か月分をまとめて掲載させていただきます。左のカレンダーから1日をクリックしてください。翌月分の職場の教養は入力が出来た分だけ、20日の日記にまとめて掲載します。
2016年02月20日
コメント(0)
-
3月 4日(金) 三つの初心
3月 4日(金) 三つの初心 「当流に万能一徳の一句あり。初心忘るべからず。この句、三箇条の口伝あり。是非の初心忘るべからず。時々の初心忘るべからず。老後の初心忘るべからず」 室町時代の能役者、世阿祢の格言である「初心忘るべからず」は、芸道を極めるために、三つの初心を忘れてはいけないと説いています。一、 是非の初心。若い時は上手くいっても驕らず、上手くいかなくても一所懸命の心を忘れずに、ただひたすら稽古を積んでいくと必ず飛躍につながる。二、 時々の初心。いつ、いかなる時も、馴れに慢心せず、その時々の初心を大切にすれば、芸はより磨かれていくもの。三、 老後の初心。芸を学び極め、人生の先達になるが、老いても老いにふさわしい新たな芸を磨くことは新鮮であり、充実した人生を送ることができる。 私たちは、「物事を始めた時の志を忘れてはいけない」という意味で「初心忘るべからず」を使います。世阿弥の言葉は、最初の志に限らず、人生のあらゆる時期に、全力を尽くすことの尊さを教えてくれています。 今日の心がけ◆今この時を大切にしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。各地の倫理法人会では、毎週モーニングセミナーが開催されます。特定の宗教や政治にとらわれることなく、多面的な学びができるのが特徴です。
2016年02月20日
コメント(0)
-
3月 3日(木) 卒業式
3月 3日(木) 卒業式 春は、冬の寒さに耐えた植物が一斉に芽吹く時期です。卒業式、人事異動、入社前の研修など、人も動き出す季節です。 毎年三月になると、K氏は、同級生と別れ、学び舎を後にした卒業式のことを思い出します。懐かしい母校や恩師に思いを馳せています。 当時は、通勤のための定期券を購入するなど、様々な手続きを通して、「いよいよ社会人の仲間入りをするのだ」という希望と不安が入り混じっていました。 その頃の初々しかった自分と比べて、今の自分の仕事はマンネリ化していないか、希望や決意を持ち続けているだろうかと、確認をするのです。 「鹿を追う者は山を見ず」という格言のように、目先の獲物ばかりに目を奪われていると、山全体、いわゆる大局が見えなくなりがちです。日々の業務に追われる生活も、こうした状況に近いでしょう。 人生には節目があります。時には過去の節目を思い起こし、人生を大局的な視点で眺めて、今の自分を再点検してみましょう。 今日の心がけ◆自らを再点検する工夫をしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在まで一日も欠くことなくずっと続いています。著作権に問題があることは承知していますが、倫理の普及に役立ち、かつO君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。以上の点をご理解いただき、文章の取り扱いには配慮をお願いします。
2016年02月20日
コメント(0)
-
3月 2日(水) やがて花咲く
3月 2日(水) やがて花咲く 春の訪れを感じられる季節になりました。とはいえ、三月上旬のこの時期は、真冬のように寒い日もあるでしょう。 特に北日本の各地では、まだあちこちに雪が残って、春には程遠いと感じるかもしれません。 「何も咲かない寒い日は、下へ下へと根を伸ばせ。やがて大きな花が咲く」 この言葉は、シドニーオリンピックの女子マラソンで金メダルを獲得した高橋尚子さんの座右の銘です。高校時代の恩師に教えられた言葉だそうです。 人は時に、自らの状況を不遇だと感じる時があるかもしれません。それは、人生における、厳しい冬のようなものでしょう。 凍えるような寒い日は、自分を大きくするチャンスです。いずれ来る春に向けて、大きな花を咲かせるために、今できることが必ずあるはずです。 地中にしっかりと根を張った植物は、少しのことでは倒れない強さと、しなやかさを兼ね備えて、天に向かって力強く伸びていくでしょう。 今日の心がけ◆地道な努力で力を蓄えましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。
2016年02月20日
コメント(0)
-
3月 1日(火) 成功の反省
3月 1日(火) 成功の反省 反省とは、何か失敗をした時にするもの、と捉えがちですが、成功した時にも必要なことです。 仕事上で失敗をすれば落ち込みますが、それだけに「次は失敗しないぞ」という思いで真剣に原因を探り、気が引き締まります。 一方、成功した時は、嬉しさで気が弛んでしまいがちです。成功の要因をしっかり理解していないと、次の仕事をより良くすることも難しくなるでしょう。 Mさんは、大きな社内イベントを成功に導いた責任者でした。終了後、ホッと一安心している時に、上司から、関係者に礼状を書くよう指示されました。 〈今やらなくても・・・・・・〉と思いましたが、礼状を書くことで感謝の気持ちが湧き、チームワークこそ成功の要因であったと気づくことができたのです。 成功時の反省の意義は、驕りや心の弛みを防ぎ、成功の要因をしっかりと把握することで、さらに良い仕事をすることにあります。 うまくいっても反省し、工夫を重ねながら、仕事の質を向上させましょう。 今日の心がけ◆成功した時ほど気を引き締めましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在までずっと続いています。O君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。
2016年02月20日
コメント(0)
-
2月20日(土) やればできる
2月20日(土) やればできる Yさんは、ある人から、次のような言葉を教わりました。「実行すれば進歩、実行しなければ退歩である。やるか、やらないかである」 この言葉が心に響き、「いいな」と思ったことは、実際にやってみることをモットーにしています。清潔感のある身なりを心がけ、始業時間に余裕を持って出社し、「おはようございます」と明るい挨拶を交わして一日をスタートします。 仕事においては、身のまわりを整理整頓し、と優先順位を明確にしています。仕事のできあがりを迅速にチェックして、時間厳守で取り組んでいます。 さらに、「できる。やってみる。何とかなる」と、肯定的な言葉を積極的に使うようにして、喜んで仕事に当たっています。 私たちも、与えられた今の境遇を「これがよし」と受け入れて、まっしぐらに仕事に励む時、幸運が切り拓かれていきます。まずやってみようという前向きな姿勢で、仕事を、人生を、より良いものにしていきたいものです。 今日の心がけ◆前向きに取り組みましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。職場の教養は、毎日当日分を掲載しています。職場の教養を使うと、活力あふれる朝礼が出来ます。朝礼の準備などであらかじめ読みたい方のため、楽天ブログの当月の1日に、1か月分をまとめて掲載させていただきます。左のカレンダーから1日をクリックしてください。翌月分の職場の教養は入力が出来た分だけ、20日の日記にまとめて掲載します。
2016年02月20日
コメント(0)
-
2月19日(金) 父とラッキー
2月19日(金) 父とラッキー 毎年二月になると、Mさんは二つのことを思い出します。二月に亡くなった父と、飼い犬ラッキーのことです。 銀行員だった父親は、五十代の後半に癌を思いました。手術を受け、一命はとりとめましたが、長期入院で痩せ細った体を回復させるためには、リハビリをしなければなりませんでした。そのリハビリは、退院後も続きました。 将来への不安に悩む父の支えになったのが、飼い犬のラッキーです。家族の勧めもあって、リハビリを兼ねて、散歩をするようになったのです。 毎日一緒に散歩をするうちに、体を動かす心地良さを知り、太陽の光や風を感じることが喜びとなりました。「リハビリのため」という思いがいつしか消え、ラッキーとの触れ合いが、何より楽しくなりました。 この散歩は、父が亡くなるまでの六年間続きました。「良い人生だった」と笑顔で亡くなった父。ラッキーが死んだのは、ちょうど一年後の同じ日でした。 人生の最期に、幸せな時間を共にしたことを思うと、胸が熱くなるMさんです。 今日の心がけ◆動物と触れ合う時間を持ちましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。
2016年02月19日
コメント(0)
-
2月18日(木) 職場のユーモア
2月18日(木) 職場のユーモア 営業マンのGさんは、営業成績がいつもトップです。誠実で一見生真面目に見えますが、会話の内容はウイットに富み、ユーモアたっぷりです。 職場におけるユーモアとは、どういうことでしょう。「ユーモア学」を専門とする大学教員の大島希巳江氏は、ビジネスにおけるユーモアについて、「おもしろいことを言って相手を爆笑させることではない」と言います。 「ユーモアがある人は、語彙が多いだけでなく、場を読み、適切なところで適切なことを言うコミュニケーション能力も高い」と、氏は説いています。 たしかにGさんは、難しい専門用語でも、比喩表現を使ってわかりやすく説明します。意外な視点が笑いを誘って、和やかな雰囲気を作り出す達人です。 ユーモアは、人や場を和ませ、人間関係を良好に保つための調味料的な役割を果たします。これは、「おもてなし」精神の一面ではないでしょうか。 職場でギャグが受けなくてもめげることなく、会話の中にユーモアをタイミングよく盛り込む工夫をして、人間関係向上の一助にしたいものです。 今日の心がけ◆ユーモア力を高めましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在まで一日も欠くことなくずっと続いています。著作権に問題があることは承知していますが、倫理の普及に役立ち、かつO君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。以上の点をご理解いただき、文章の取り扱いには配慮をお願いします。
2016年02月18日
コメント(0)
-
2月17日(水) 人は鏡
2月17日(水) 人は鏡 自分自身ではなかなか気づかないことでも、人の姿を通して気づくことは多くあります。 会社で書類を提出したAさんは、上司に呼び出されました。文章の表現が粗雑だというのです。指摘を受けながら、内心では腹を立てていました。 次の日、部内でのミーティングでのことです。ある部下が、自分に対して、ぞんざいな受け答えをします。言葉遣いに気をつけるよう注意し、ミーティングを続けました。 Aさんは、会社から帰る道すがら、部下の態度が、自分が上司に取った態度に似ていることに気がつきました。まるで、鏡のように自分の姿を見せてくれたことに驚き、一人静かに反省したのです。 部下の姿は、自分を客観的に見つめる、いい機会になりました。 「殷鑑遠からず」という故事にあるように、自分を省みるための事柄はすぐ近くにあります。職場での人間関係も、それに当てはまるでしょう。 今日の心がけ◆人の姿から学びましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。
2016年02月17日
コメント(0)
-

2月16日(火) 家康の「しかみ像」
2月16日(火) 家康の「しかみ像」 誰にでも、忘れてしまいたいような失敗はあるものです。 失敗をきれいさっぱり忘れられれば、たしかに気持ちは楽になるでしょう。その一方で、失敗から学び、大事な教訓として活かすこともできるのです。 江戸幕府を開いた徳川家康には、堂々とした、威厳のある肖像画が残されています。それとはまったく異なり、憔悴しきった家康の姿を描いた「しかみ像」と呼ばれている画があります。 家康は、三十一歳の時、三方ヶ原の合戦で武田信玄に散々打ちのめされ、恐怖のあまり、脱糞しながら敗走したといいます。 この敗戦を肝に銘ずるため、家康は己の惨めな姿を従軍絵師に描かせ、いつも身近に置いて、慢心を自戒したと伝えられています。 失敗は苦い経験です。しかし、眼をそむけずに真正面から受け止め、と謙虚に教えを乞い、自己成長の糧とする時、失敗は一変して輝く宝物となるのです。 今日の心がけ◆失敗を糧にしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在までずっと続いています。O君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。
2016年02月16日
コメント(0)
-
2月15日(月) 字に表われる心
2月15日(月) 字に表われる心 人の書く字には、心の状態が表われます。丁寧に書けば整った字となり、急いでいると、殴り書きになってしまいます。 昨今はパソコンが普及し、文字を書く機会が少なくなりました。それでも、手書きの手紙や葉書がなくならないのは、手間ひまを惜しまない心が、文字を通して相手に伝わり、温かい印象を与えるからでしょう。 ある日、離席していたYさんがデスクに戻ると、一筆のメモが置かれていました。不在中に電話があった、という知らせでした。 メモの文字の丁寧さと美しさに、Yさんは驚きました。さらに、そのメモには一言、「お互い午後も頑張りましょう」と添えられていたのです。 Yさんは、嬉しさを感じると共に、自分のメモ書きを省みました。忙しい時には、乱暴な字で、用件を書き殴っていたのです。 人が目を通すものは、たとえメモであっても「相手が快く読めるように」と気を配りたいものです。ほんの些細な心遣いが、相手に元気を与えます。 今日の心がけ◆些細なことにも心を配りましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。
2016年02月15日
コメント(0)
-
2月14日(日) 熱い風呂
2月14日(日) 熱い風呂 関東地方のある海沿いの町では、今も銭湯が健在です。番台があって、富士山のペンキ絵が描かれている、昔ながらの銭湯です。 その町はかつて漁師町だったので、銭湯が社交場の役割を果たしていました。その日の漁や海の状態について、銭湯で情報交換をしていたのです。 海で冷えた体を温めるため、お湯の温度はかなり高めでした。今もそれは変わりません。熱い湯を求めて、常連の年配者たちが毎日通い続けています。 その一方で、銭湯のオーナーには悩みがあります。古い銭湯に、若い人がなかなか来ないのです。何しろお湯が熱いため、子供には敬遠されます。 長年支えてくれたお客様は大事にしたい。とはいえ、新しいお客様にも来てほしい。お湯の温度を下げ、今風に改装すれば、客層は広がるかもしれません。しかし、馴染み客の足は遠のくでしょう。経営を維持できるかも不安です。 町の銭湯文化を絶やさないために、一番いい方法は何か。老舗の銭湯オーナーは、まだ答えが出せないままです。 今日の心がけ◆何を守り何を変えるか考えましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。朝礼に利用すると、とても効果が高いと思います。
2016年02月14日
コメント(0)
-
2月13日(土) 成功者
2月13日(土) 成功者 川の中の魚は、どうすればとれるでしょう。「一日中、川の底をのぞいていたとて、魚は決してとれるものではない」と、岩崎弥太郎は言いました。 貧しい家庭環境の中で育った弥太郎は、勉学に励み、才能を発揮して、三菱財閥を築き上げました。人生の成功者である弥太郎は、チャンスを捉える方法について、こう述べています。 「たまたま魚がたくさんやってきても、その用意がなければ、素手ではつかめない。魚は招いて来るものでなく、来るときに向こうから勝手にやってくるものである。だから魚をとろうと思えば、常平生からちゃんと網の用意をしておかねばならない。人生全ての機会を捕捉するにも同じ事がいえる」 人生におけるチャンスは、待っていれば必ず与えられるものではありません。また、チャンスが訪れても、それをつかめなければ、手にすることはできません。 大切なのは、チャンスが訪れた時にそれを活かせるよう、準備を怠らないことでしょう。 今日の心がけ◆チャンスを活かしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。職場の教養は、毎日当日分を掲載しています。職場の教養を使うと、活力あふれる朝礼が出来ます。朝礼の準備などであらかじめ読みたい方のため、楽天ブログの当月の1日に、1か月分をまとめて掲載させていただきます。左のカレンダーから1日をクリックしてください。翌月分の職場の教養は入力が出来た分だけ、20日の日記にまとめて掲載します。
2016年02月13日
コメント(0)
-
2月12日(金) デッドライン
2月12日(金) デッドライン Nさんは製造業に携わっています。毎月、自分が受け持っている複数の部品を仕上げるのが仕事です。 しかし、頑張って取り組んでいるにもかかわらず、納期に間に合わないことがあります。どうすればいいか、職場の先輩に相談してみました。 「そうだなあ、僕は一ヵ月の仕事全体を見て、自分の中でデッドラインを決めているよ」「デッドラインとは何ですか?」 「締め切りのことだよ。納期とは別に、自分の中で締め切りを決めると、集中して仕事ができるんだ。もし違う仕事が入ってきても、ある程度仕事が進んでいるから、どれを優先するか判断しやすいんだよ」 振り返ると、別の仕事が入ってくると、どちらを優先するべきか迷ってしまい、時間をロスしていたことに思い至りました。 早速、自分の仕事のデッドラインを設定したNさん。突発的な仕事へもしっかり対応し、今では、納期前に仕事を終わらせることが当たり前になりました。 今日の心がけ◆自分の締め切りを設定しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。各地の倫理法人会では、毎週モーニングセミナーが開催されます。特定の宗教や政治にとらわれることなく、多面的な学びができるのが特徴です。
2016年02月12日
コメント(0)
-
2月11日(木) 地球益
2月11日(木) 地球益 「地球益」という言葉をご存知ですか。平成二十一年十二月、COP15に関連して、当時の鳩山由紀夫首相が「国益も大事だが、地球益も大変大事だ」と、記者団にコメントしたことに起因する言葉です。 世界的に地球環境に対する意識が高まり、経営者や技術者の間で「地球益」を意識した技術や商品が生まれています。また、自社の利益の一部を環境保全へ充当するという方針を立てる人の輪が広がっています。 本誌の発行元・倫理研究所では、今から二十年前、「地球倫理の推進」という方針を発信しました。地球倫理とは「地球人の、地球人による、地球人のための倫理」で、三つ目の地球人には、地球そのものも含まれます。 私たちは日頃、地球環境や人類全体の利益を意識しているでしょうか。頭で理解しても、地球や人類という言葉の壮大さに、意識が散漫になりがちです。 だからこそ「目標(意識)は高く、実践は足元から」の精神で、身のまわりのものを無駄にせず、整理・整頓・清潔を心がけたいものです。 今日の心がけ◆地球のために身近な実践をしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在まで一日も欠くことなくずっと続いています。著作権に問題があることは承知していますが、倫理の普及に役立ち、かつO君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。以上の点をご理解いただき、文章の取り扱いには配慮をお願いします。
2016年02月11日
コメント(0)
-
2月10日(水) 雑用はない
2月10日(水) 雑用はない 新入社員のKさんは、自動車販売店に就職して、もうすぐ一年が経過します。職場に慣れてきたものの、担当する仕事に不満を抱き始めていました。 通常業務とは別に、FAXの送信を頼まれることが多いKさん。(FAXを送るために会社に入ったんじゃない)と、嫌々ながら仕事をしていたのです。 Kさんの態度を見て、先輩のSさんは「FAXを送ることも大切な仕事だよ。自分の心が仕事を『雑用』にしてしまうんだ。もっと改善できることはないか、工夫してごらん」と助言しました。 その後Kさんは、FAX送付状の挨拶文や、文面のレイアウトを工夫するようになりました。すると、送付先のお客様から「いつも心のこもった挨拶文を送っていただき、ありがとうございます」と電話でお礼を言われたのです。 「雑草」という名の草がないのと同様に、「雑用」という名の仕事はありません。どのような仕事であっても、会社にとっては必要な仕事であると受け止めて、心を込めて働きましょう。 今日の心がけ◆小さな仕事を丁寧に行ないましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。
2016年02月10日
コメント(0)
-
2月 9日(火) 急な雨降りに
2月 9日(火) 急な雨降りに Aさんが、職場の仲間と、昼食に出かけた時のことです。食事を終え、店を出ると、雨が降っていました。傘がなかったので、会社まで走って戻りました。 ふと気がつくと、一緒にいたBさんがいません。Bさんに電話をすると、途中で雨宿りをしているようでした。 くらいに思っていると、一緒にいたCさんが、傘を持って外に出かけていきました。 しばらくして、BさんとCさんが一緒に、傘をさして会社に戻ってきました。Bさんがお礼を言う様子を見て、と、考えさせられたのです。 何気ない日常の中でも、人の役に立つチャンスはたくさんあります。いつも気がつけばよいのですが、Aさんのような人もたくさんいるでしょう。 よく気がつく人が身近にいれば、と、折にふれて考えてみるのも、自分を磨く方法です。 今日の心がけ◆気づきの感性を高めましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在までずっと続いています。O君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。
2016年02月09日
コメント(0)
-
2月 8日(月) 何のために?
2月 8日(月) 何のために? 中堅社員として働くAさんは、職場で行なわれている朝礼に戸惑っていました。 挨拶や返事を練習することが堅苦しく、『職場の教養』の感想を述べることも気恥ずかしくて、朝礼に前向きになれなかったのです。 その悩みを、同じような朝礼を行なっている取引先の担当者に打ち明けました。その担当者も、最初は同じような戸惑いを感じていたそうです。 その後、「何のために朝礼をするのか」という意義をはっきりさせることで、取り組み方が変わったといいます。その意義は次のようなものでした。 1朝礼という共同作業を通じて、チームワークの向上を図る。2『職場の教養』を読み、感想を述べることで、考える力や自分を省みる意識を養う。 3元気な声を出すことで、活力をもって一日をスタートする。4その日の業務を確認し、一日のイメージを共有して業務に取りかかる。 朝礼への意識が変わり、少しずつ前向きに参加できるようになったAさんは、業務においても「何のために?」と考えるようになったのです。 今日の心がけ◆朝礼の意義を再確認しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。
2016年02月08日
コメント(0)
-
2月 7日(日) おもねらない
2月 7日(日) おもねらない 既製の商品に改造を施すことをカスタムといいます。カスタムバイクの世界的アーティストとして知られる木村信也氏は、アメリカに渡って十年間、一人でこつこつとオートバイを作り続けています。 その木村氏が、グリーンカードと呼ばれるアメリカの永住権を取得しました。しかも、ノーベル賞受賞者に与えられるのと同等の、最高ランクのカードです。 その理由は、氏の手がける唯一無二のオートバイが芸術作品とみなされたことによります。氏は、自身のオートバイについて、次のように語っています。 「芸術作品として認められようと思って製作してきたら、他人におもねるようなものになってしまう。そうではなくて、自分の思いを込めて作ってきたものが、結果として芸術作品とみなされた。これからも、自分が良いと信じるオートバイを作り上げ、それを認めてくれる人に提供していきたい」 日頃私たちは、「どうしたら売れるのか」を考えながら仕事をしています。しかし時には、自分の理想とするものに心を向ける時間も大切です。 今日の心がけ◆理想を追い求めましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。朝礼に利用すると、とても効果が高いと思います。
2016年02月07日
コメント(0)
-
2月 6日(土) お客様からの苦情
2月 6日(土) お客様からの苦情 飲食業に携わるKさんは、接客に関する研修を受けました。苦情を受けた際の対応について、次のように学びました。 1何よりも先に、こちらの不手際で起こったことは、誠意を持って謝罪する。 2お客様の言葉に最後まで耳を傾け、こちらの言い分や都合で遮らない。 3その後に、必要があれば説明や補足を伝えて対応する。 4不快な思いをさせたことは動かぬ事実。誠心誠意、真心を込めて、最後に改めてお詫びをする。 過去にもクレームを受けた経験を持つKさんは、その時の対応を振り返ってみました。まず口から出たのは言い訳でした。また、お客様の話が長過ぎて、途中で遮ったのです。その後、そのお客様は来店することはありませんでした。 クレームが発生しないよう、万全の体制を整えることは大切です。その体制には、クレームを想定した心の準備や研修も含まれます。 真のプロとは、あらゆる状況を想定して、その準備を怠らない人なのでしょう。 今日の心がけ◆クレームへの対応を準備しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。職場の教養は、毎日当日分を掲載しています。職場の教養を使うと、活力あふれる朝礼が出来ます。朝礼の準備などであらかじめ読みたい方のため、楽天ブログの当月の1日に、1か月分をまとめて掲載させていただきます。
2016年02月06日
コメント(0)
-
2月 5日(金) 二つ褒める
2月 5日(金) 二つ褒める 一つ注意したら、二つ褒めることを心がけましょう。 注意される側にとっては、怒られてばかりいると、と落ち込んでしまいます。褒められることで、やる気が出て、前向きに取り組む気持ちが芽生えてきます。 また、「一つ注意したら二つ褒めよう」と心がけることで、相手を「褒める」という視点で見るようになります。 褒めるためには、相手の良い点を見つけようとします。今まで気づかなかった新たな発見があり、視野が広がるだけでなく、相手に対する親愛の情が湧いて、コミュニケーションが深まります。 これは、人だけではなく、仕事でも同じでしょう。仕事を褒めるようなつもりで、その仕事の良い点を見るようにすると、やりがいが生まれてきます。 人も仕事も、良い点、褒めるべき点は必ずあります。注意点が気になったら、その倍の良いところを見つけましょう。 今日の心がけ◆美点を多く見つけましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。各地の倫理法人会では、毎週モーニングセミナーが開催されます。特定の宗教や政治にとらわれることなく、多面的な学びができるのが特徴です。
2016年02月05日
コメント(0)
-
2月 4日(木) 良い姿勢は良い結果を招く
2月 4日(木) 良い姿勢は良い結果を招く 近年ゴルフ場では、カートを利用してプレーする人が増えています。それに伴ない、歩いてラウンドできるコースが減少しています。 歩いてプレーする機会が減ると、ゴルファーの歩く姿勢が悪くなります。あるプロゴルファーは「歩くこともゴルフというゲームの一部なので、歩く姿勢が成績を大きく左右する」と言います。 また、「プレーの調子が良さそうなお客様は背筋が伸び、颯爽と歩いている方が多いです」と話すキャディーもいます。 ゴルフに限らず、スポーツの上達と姿勢は密接に関係しています。また、ビジネスの世界においても、一流といわれる人は、背筋を伸ばして、颯爽と歩く人が多いようです。 車や乗り物での移動が多くなり、現代では歩く時間が少なくなりました。また、長時間のデスクワークやパソコン作業も、悪い姿勢を招く一因でしょう。 できるだけ歩く時間をつくって、良い姿勢で歩くことを心がけましょう。 今日の心がけ◆良い姿勢で歩きましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在まで一日も欠くことなくずっと続いています。著作権に問題があることは承知していますが、倫理の普及に役立ち、かつO君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。以上の点をご理解いただき、文章の取り扱いには配慮をお願いします。
2016年02月04日
コメント(0)
-
2月 3日(水) 心の鬼に克つ
2月 3日(水) 心の鬼に克つ 節分といえば、「豆まき」を思い浮かべる人も多いでしょう。隣近所から、「鬼は外、福は内」と、子供たちの大きな声が聞こえてきます。 節分とは文字通り、季節の分かれ目のことです。もともとは春夏秋冬、年に四回ありました。 その中でも、冬から春の変わり目は、草木が芽吹く時期であり、旧暦では新年が始まることから、立春の前日を指すようになりました。 東京都西多摩の小学校では、創立以来、四十年以上にわたって、節分の豆まきを行なっています。伝統となっているのが、児童一人ひとりが、自分の心に棲む「鬼」をカードにして、その鬼を退治していくことです。 「友達を思う心がたりない鬼」「すぐ人のせいにしてしまう心の鬼」「お父さんお母さんの言うことを聞かない心の鬼」など、鬼の種類は様々です。自分の「鬼」カードに向かって豆をまき、クラス皆で、心を新たにしていくのです。 私たち大人も、節分の豆まきを機に、心の中の鬼を退治したいものです。 今日の心がけ◆自己の弱さと向き合いましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。職場の教養を利用すると、活力ある朝礼をするのに役立ちます。倫理法人会に入会すると毎月30冊送ってもらえます。ご希望があれば、活力朝礼のやりかたを指導してもらえます。(もちろん無料で)お問いあわせはお近くの倫理法人会まで
2016年02月03日
コメント(0)
-
2月 2日(火) トラックの名前は
2月 2日(火) トラックの名前は 運送会社を起業し、十五年になるB社長。毎年、事故が減らないことに頭を悩ませていました。大事故にはならないものの、「大きな事故の前には、小さな事故が重なって起きるもの」という話を聞き、気が気ではありません。 ある時、同業者の集まりで、ある会社がちょっと変わった取り組みをしたことで、事故がなくなったという情報を聞きました。 さっそく話を聞きにいくと、事故が減った経緯を惜しげもなく教えてくれました。それは、社長も社員も、自分が運転するトラックに、子供や伴侶など最愛の人の名前を付けて、挨拶をしているというのです。 話を聞いたB社長はと思いました。それでも、ものは試しと、まずは自家用車に「よしこさん」と、妻の名前を付けてみました。 運転前に「よしこさん、今日もよろしく!」と声をかけると、いつもの車に対して、今までとは違った感情が芽生えるのを感じました。そして、無事に目的地に着いた時、「ありがとう」という言葉が自然に口をついたのです。 今日の心がけ◆感謝を持って物を扱いましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在までずっと続いています。O君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。
2016年02月02日
コメント(0)
-
2月29日(月) 仕事の棚卸し
2月29日(月) 仕事の棚卸し 春は、職場においても人の出入りが多くなる時期です。勤める部署は替わらなくても、仕事の範囲や担当が替わる人もいるでしょう。 私たちの仕事はすべて、最後は、会社に返す仕事です。今引き受けている仕事も、いずれ新任者に引き継いだり、後進に譲る時がやってきます。 担当者が替わるたびに「前はできたが、今はできない」「担当が替わったので、よくわからない」ということでは、周囲も困ってしまうでしょう。 職場は、様々な人の個性があってこそ成り立つものですが、チームの仕事であるからには、一定の平準化は必要です。 今の仕事を「次の担当者がやりやすいか、否か」という視点で振り返って、蓄積していくデータの見直しや、備品の整理をしていきましょう。 会社の仕事は、今だけではなく、これから先も継続していきます。「前任者がよく整理しておいてくれたお陰で、スムーズに引き継ぐことができた」と言われるよう、日頃から心がけておきたいものです。 今日の心がけ◆先を見据えて整理をしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。日本各地にある倫理法人会では、毎週「モーニングセミナー」が開催されます。また毎月1回「経営者の集い」があります。モーニングセミナーも経営者の集いも、一般の方や社員に参加いただけます。いずれも経営のためだけでなく人生を豊かに過ごすための講演会です。(私自身が誤解していましたので、あえて申し添えます。宗教ではありません)
2016年02月01日
コメント(0)
-
2月28日(日) 一日一回
2月28日(日) 一日一回 大小の違いはあっても、誰もが「こうなりたい」という将来への夢や希望を持っているでしょう。 その夢が実現するかどうか、あるいは夢に近づけるか、成就へと導くキーワードの一つに、「一日一回」があります。 これは、地球のリズムに乗るということです。地球は一日に一回転します。そこで、自分の夢を一日一回、声に出してみましょう。または、文字に表わしてみましょう。この一日一回を毎日繰り返してみるのです。 未来は、急にはやってきません。今日の続きが明日であり、未来です。未来を輝かせるには、今日一日を輝かせることです。 一日一回と心に決め、今日一日を大切にしていると、次第に「いつまでに」という期限が設定されます。この時、夢ははっきりとした目標へと転ずるのです。 目標となった時、漠然としていた夢が、具体的なイメージとなって、頭の中に鮮明に浮かび上がるでしょう。一日一回が成功の秘訣です。 今日の心がけ◆自分の夢を一日一回言葉にしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。朝礼に利用すると、とても効果が高いと思います。書店では売っていません。倫理法人会に入会すると毎月30冊もらえます。職場の教養は、毎日当日分を掲載しています。朝礼の準備などであらかじめ読みたい方のため、楽天ブログの当月の1日に、1か月分をまとめて掲載させていただきます。左のカレンダーから1日をクリックしてください。翌月分の職場の教養は20日に、それまでに出来たぶんだけを掲載します。
2016年02月01日
コメント(0)
-
2月27日(土) 偕楽園
2月27日(土) 偕楽園 日本三名園の一つ、茨城県水戸市の偕楽園では、二月下旬から「梅まつり」が始まります。 偕楽園は天保十三年(一八四二年)に、水戸藩第九代藩主の徳川斉昭によって開園され、約百品種、三千本といわれる見事な梅林で有名です。 偕楽園の「偕」とは「ともに」という意味で、武士だけでなく、一般の領民とともに楽しむ園にしたい、という斉昭公の願いが込められています。 そのため、偕楽園は、水戸藩の一般領民にも広く開放されました。「ともに楽しむ」という精神は、その後も受け継がれており、偕楽園は現在でも入園無料となっています。 また、領民の憩いの場とされただけではなく、梅は梅干として備蓄食料となり、園内には弓の材料にする孟宗竹の林もあり、さらに園内随一の見晴らし台は、有事には砲台としての利用も考慮されていたといわれます。 梅を楽しむだけではなく、水戸城を守る防衛上の配慮もされていたのです。 今日の心がけ◆地域の名所について学びましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。職場の教養は、毎日当日分を掲載しています。職場の教養を使うと、活力あふれる朝礼が出来ます。朝礼の準備などであらかじめ読みたい方のため、楽天ブログの当月の1日に、1か月分をまとめて掲載させていただきます。左のカレンダーから1日をクリックしてください。翌月分の職場の教養は入力が出来た分だけ、20日の日記にまとめて掲載します。
2016年02月01日
コメント(0)
-
2月26日(金) 名前に込められた想い
2月26日(金) 名前に込められた想い ベネッセコーポレーションが、二〇一五年に産まれた赤ちゃんの名前人気ランキングを発表しました。男の子の一位は「悠真」、女の子の一位は「葵」でした。 男女それぞれ十位以内に、「大和」や「さくら」といった名前がランクインしています。ラグビー日本代表などの活躍が、日本の良さを再認識させるきっかけになったからではないかと、同社では分析しています。 Mさんが、小学四年生の息子の授業参観に参加した時のことです。親には事前に、「お子さんへ手紙を書いてください」という宿題が出ていました。 Mさんが手紙に書いたのは、長男の名前の由来でした。どのような想いを込めて名前を付けたか、手紙で初めて息子に伝えたのです。 授業参観の後、長男から返事をもらったMさん。感謝の言葉と共に記された文面を読み、自分の想いが伝わったことを嬉しく思いました。 名前は、親が最初にわが子へ贈るプレゼントです。自分の名前の由来を知ることは、親の願いを受け止めることになるでしょう。 今日の心がけ◆名前の由来を知りましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。各地の倫理法人会では、毎週モーニングセミナーが開催されます。特定の宗教や政治にとらわれることなく、多面的な学びができるのが特徴です。
2016年02月01日
コメント(0)
-
2月25日(木) 「ハイ」の力
2月25日(木) 「ハイ」の力 N社長は、休日に、自宅で庭木の手入れをしていました。 居間でテレビを見ていた小学生の孫に、「縁側にある剪定ばさみを持ってきて!」と声をかけました。しかし、返事がありません。 思わず「おーい、○○君、聞こえないのか!」と大きな声を出すと、孫はしぶしぶ立ち上がって、はさみを持ってきました。 呼ばれたら返事をするようにと、孫に言って聞かせたN社長。「返事がないと聞こえているのかわからないし、無視されたと思うと、いい気持ちはしないよ」と孫に話しながら、さて、自分自身はどうだろうと振り返ったのです。 会社で社員に呼ばれても、返事をしないことはよくあります。自分では「身内だから」「社長だから」という思いがあったのですが、社員にとっては、決していい気持ちはしなかっただろうと反省しました。 たった一言の「ハイ」という言葉ですが、その力は絶大です。相手の存在を認め、受け入れる意思表示であり、好意を示すバロメーターでもあるのです。 今日の心がけ◆爽やかな返事をしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在まで一日も欠くことなくずっと続いています。著作権に問題があることは承知していますが、倫理の普及に役立ち、かつO君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。以上の点をご理解いただき、文章の取り扱いには配慮をお願いします。
2016年02月01日
コメント(0)
-
2月24日(水) 聞いていないのは誰?
2月24日(水) 聞いていないのは誰? 出張の多いAさんは、日頃から、早めの準備を心がけています。先の予定を見越して、妻にもあれこれ頼みごとをしています。 ある時、妻に「この前クリーニングを頼んだスーツを着て出張に行く」と告げると、妻は「忘れていた」と言います。Aさんは「二週間も前にお願いしたことだよ。しっかり聞いてないから忘れるんだ」と、妻に厳しく言ったのです。 そんなAさんですが、今度は、息子との会話でハッとさせられることがありました。小学生の息子から「歴史の勉強いつ教えてくれるの?どうせ教えてくれないんでしょ」と言われたのです。 実は、歴史好きな息子から、以前からせがまれていたのでした。「いいよ」と返事をしながら、そのことをすっかり忘れていたのです。 「そうだったね、ごめんね」と息子に謝りながら、自分も家族の話を聞いていなかったことを反省したAさんです。その後、忘れそうなことはカレンダーにメモをすることが、家族みんなの習慣になりました。 今日の心がけ◆相手の話をしっかり聞きましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。
2016年02月01日
コメント(0)
-
2月23日(火) 「机の上」を整える
2月23日(火) 「机の上」を整える 今やパソコンは、様々な業種で欠くことのできないツールとなりました。 文書やグラフなどの資料作成や、社内外における情報の伝達や共有においても、重要な役割を果たしています。容量や処理速度などの性能は、日進月歩をもじって「秒進分歩」とまでいわれるほど、進化を続けています。 パソコンを起動すると、画面にはデスクトップが表示されます。デスクトップには、様々な絵柄のアイコンやボタンが配置されています。 デスクトップとは、日本語では「机の上」です。仕事をする机の上が散らかっていたり、不要な書類が山積みになっていては、必要な資料が取り出せません。 パソコンのデスクトップも同様です。アイコンだらけで整理されていないと、効果的な仕事はできないでしょう。 デスクトップにたくさんのアイコンがあると、それを読み込むためのメモリを消費し、動作が遅くなる原因にもなります。余計なファイルやフォルダ、使っていないアイコンがないか、定期的に見直して、すっきりさせたいものです。 今日の心がけ◆パソコンを整理しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在までずっと続いています。O君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。
2016年02月01日
コメント(0)
-
2月22日(月) 問いを発する
2月22日(月) 問いを発する 何事にもよく気がついて、積極的に動ける人に、共通していることがあります。それは、問題意識を持って、仕事に取り組んでいることです。 問題意識は、どのようなことにも関心を持ち、よく見て、考えるところから芽生えてきます。問題意識とは、答えを求める心であり、問いを発する意識のことでもあります。 例えば、「お客様に喜んでもらうためにできることはないか」「職場を明るくするために何ができるか」「いきいきと生活するにはどうすればよいか」「家族が仲良くするには何をすればよいか」など、身のまわりをよく見ていると、問題がたくさんあることに気がつきます。 ここで、気をつけたいことは、他人の問題ではないということです。本当の問題意識とは、「自分には何ができるか」を問うことであって、周囲の人たちを責めるために問うのではありません。 正しい問題意識のある人は、人間としても成長していく人だといえるでしょう。 今日の心がけ◆健全な問題意識を持ちましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。日本各地にある倫理法人会では、毎週「モーニングセミナー」が開催されます。
2016年02月01日
コメント(0)
-
2月21日(日) 応急手当てのガイドライン
2月21日(日) 応急手当てのガイドライン 応急手当ての方法は、五年に一度、より良い方法へ改正されています。 目の前で倒れている人のために、救急車が到着するまでの間。一般市民ができることをより有効に行なうことで、救命率や社会復帰率を高めるためです。 二〇一五年の改正では、胸骨圧迫の回数について、これまでの「一分間に百回以上」から「百~百二十回の間」に見直されました。その深さも「五センチ以上」から「五~六センチ」と改正されています。最も大きな特徴は、心停止状態かどうかの判断に迷っても、まず心臓マッサージを開始するよう明示されたことです。 「AED」の普及率も向上してきましたが、救命の他にも、事業所では通報、消火、避難誘導などの訓練を毎年実施することが義務づけられています。 緊急事態は、いつ、どのような形で、誰に訪れるか予測できないだけに、日頃から、防災に対する意識づけや情報の共有を大切にしていきたいものです。 また、個人としても、不規則な生活による睡眠不足やストレスの蓄積は万病の元だと捉えて、病気を予防する生活を心がけましょう。 今日の心がけ◆不測の事態に備えましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。朝礼に利用すると、とても効果が高いと思います。書店では売っていません。倫理法人会に入会すると毎月30冊もらえます。職場の教養は、毎日当日分を掲載しています。朝礼の準備などであらかじめ読みたい方のため、楽天ブログの当月の1日に、1か月分をまとめて掲載させていただきます。左のカレンダーから1日をクリックしてください。翌月分の職場の教養は20日に、それまでに出来たぶんだけを掲載します。
2016年02月01日
コメント(0)
-
2月20日(土) やればできる
2月20日(土) やればできる Yさんは、ある人から、次のような言葉を教わりました。「実行すれば進歩、実行しなければ退歩である。やるか、やらないかである」 この言葉が心に響き、「いいな」と思ったことは、実際にやってみることをモットーにしています。清潔感のある身なりを心がけ、始業時間に余裕を持って出社し、「おはようございます」と明るい挨拶を交わして一日をスタートします。 仕事においては、身のまわりを整理整頓し、と優先順位を明確にしています。仕事のできあがりを迅速にチェックして、時間厳守で取り組んでいます。 さらに、「できる。やってみる。何とかなる」と、肯定的な言葉を積極的に使うようにして、喜んで仕事に当たっています。 私たちも、与えられた今の境遇を「これがよし」と受け入れて、まっしぐらに仕事に励む時、幸運が切り拓かれていきます。まずやってみようという前向きな姿勢で、仕事を、人生を、より良いものにしていきたいものです。 今日の心がけ◆前向きに取り組みましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。
2016年02月01日
コメント(0)
-
2月19日(金) 父とラッキー
2月19日(金) 父とラッキー 毎年二月になると、Mさんは二つのことを思い出します。二月に亡くなった父と、飼い犬ラッキーのことです。 銀行員だった父親は、五十代の後半に癌を思いました。手術を受け、一命はとりとめましたが、長期入院で痩せ細った体を回復させるためには、リハビリをしなければなりませんでした。そのリハビリは、退院後も続きました。 将来への不安に悩む父の支えになったのが、飼い犬のラッキーです。家族の勧めもあって、リハビリを兼ねて、散歩をするようになったのです。 毎日一緒に散歩をするうちに、体を動かす心地良さを知り、太陽の光や風を感じることが喜びとなりました。「リハビリのため」という思いがいつしか消え、ラッキーとの触れ合いが、何より楽しくなりました。 この散歩は、父が亡くなるまでの六年間続きました。「良い人生だった」と笑顔で亡くなった父。ラッキーが死んだのは、ちょうど一年後の同じ日でした。 人生の最期に、幸せな時間を共にしたことを思うと、胸が熱くなるMさんです。 今日の心がけ◆動物と触れ合う時間を持ちましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。各地の倫理法人会では、毎週モーニングセミナーが開催されます。
2016年02月01日
コメント(0)
-
2月18日(木) 職場のユーモア
2月18日(木) 職場のユーモア 営業マンのGさんは、営業成績がいつもトップです。誠実で一見生真面目に見えますが、会話の内容はウイットに富み、ユーモアたっぷりです。 職場におけるユーモアとは、どういうことでしょう。「ユーモア学」を専門とする大学教員の大島希巳江氏は、ビジネスにおけるユーモアについて、「おもしろいことを言って相手を爆笑させることではない」と言います。 「ユーモアがある人は、語彙が多いだけでなく、場を読み、適切なところで適切なことを言うコミュニケーション能力も高い」と、氏は説いています。 たしかにGさんは、難しい専門用語でも、比喩表現を使ってわかりやすく説明します。意外な視点が笑いを誘って、和やかな雰囲気を作り出す達人です。 ユーモアは、人や場を和ませ、人間関係を良好に保つための調味料的な役割を果たします。これは、「おもてなし」精神の一面ではないでしょうか。 職場でギャグが受けなくてもめげることなく、会話の中にユーモアをタイミングよく盛り込む工夫をして、人間関係向上の一助にしたいものです。 今日の心がけ◆ユーモア力を高めましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在まで一日も欠くことなくずっと続いています。著作権に問題があることは承知していますが、倫理の普及に役立ち、かつO君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。以上の点をご理解いただき、文章の取り扱いには配慮をお願いします。
2016年02月01日
コメント(0)
全67件 (67件中 1-50件目)