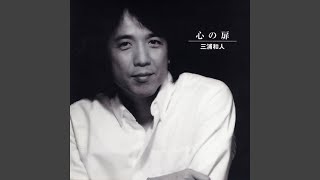2016年01月の記事
全67件 (67件中 1-50件目)
-
1月31日(日) 箸の作法
1月31日(日) 箸の作法 Aさんが同僚と食事をしていた時のことです。箸をのばすAさんの手元を見ていた同僚から、「箸の持ち方が変わっている」と指摘されました。 「仕事上の会食の場で、恥ずかしい思いをするかもしれない。今からでも意識して直してみてはどうか」と、同僚は真剣にアドバイスをしてくれたのです。 Aさん自身、食事の際、他人の咀嚼音が気になることがありました。その一方で、箸の持ち方をはじめ、自分自身の食事マナーについては振り返ることはありませんでした。 言いにくいことをきちんと言ってくれた同僚に礼を言い、Aさんはその後、正しい箸の持ち方を練習するようになりました。 箸には、持ち方と共に、使い方のマナーも多く存在します。「迷い箸」や「探り箸」「ねぶり箸」など、タブーとされることが様々あります。 社会人としての常識は、仕事をしている時以外にも必要です。自分が当たり前だと思っている作法や礼儀を見直してみたいものです。 今日の心がけ◆日常の行儀作法に気をつけましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。
2016年01月31日
コメント(0)
-
1月30日(土) 職場に調和を生むために
1月30日(土) 職場に調和を生むために 看護師のAさんは、主任になってほしいと上司から内示をもらいました。 主任になれば、全体を管理する立場にまわらなければなりません。Aさんは、現場で患者の顔を見て働くことが大好きなため、主任の内示を丁重に断りました。 周囲からは「せっかくのチャンスなのに」「もったいない」と言われました。「変わり者」と揶揄されることもありました。 Aさんにも周囲の声が耳に入り、と自問自答することもありました。 しかし、その後は気を取り直し、以前にも増して明るく、来院者のために働いています。そんなAさんを周囲も受け入れ、人望を集めています。 価値観の違う人間が集まり、職場は作られています。その違いを埋めるには、お互いに感情的にならず、自分から歩み寄ることが大切です。 価値観の違いを大切にした上で、互いの調和を生み出し、連携のとれた職場作りを目指していきましょう。 今日の心がけ◆違いを大切にしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。
2016年01月30日
コメント(0)
-
1月29日(金) 明るい挨拶
1月29日(金) 明るい挨拶 ホテルに勤務するNさんは、ある年配のお客様を客室まで案内しました。その夫婦は、二泊滞在して帰っていきました。 二ヵ月ほど過ぎた日、Nさん宛に礼状が届きました。その夫婦の夫からでした。手紙には、ホテルに宿泊した時、妻がすでに余命わずかであったことが書かれていました。夫婦の、最後の思い出としての旅行だったとのことでした。 その婦人は、ホテルに泊まった際、Nさんの挨拶が何ともすがすがしく心に響いたと、しきりに話していたそうです。夫婦の心の重石が取れたようだと手紙に綴られていました。 帰宅後もNさんのことが話題に上がり、入院中も、周囲に笑顔をふりまいて、明るさのお裾分けをしていたそうです。「落ち込んでいた妻が旅行を満喫できたのは、あなたのお陰です」という文字を見て、Nさんも胸が熱くなりました。 Nさんはと心に刻み、仕事に邁進しています。 今日の心がけ◆心を込めて挨拶をしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。各地の倫理法人会では、毎週モーニングセミナーが開催されます。特定の宗教や政治にとらわれることなく、多面的な学びができるのが特徴です。
2016年01月29日
コメント(2)
-
1月28日(木) 小さなミスから
1月28日(木) 小さなミスから 入社五年目のK君は、仕事にすっかり慣れてきました。その反面、このところ今一つ仕事に力が入りません。小さなミスで肝を冷やす場面が続いています。 その都度、と自分に言い聞かせるのですが、時間が経つと気が緩んできます。確認作業も、おざなりになりがちでした。 そのような中で、会社にとって大事な得意先の支払い伝票に、取り返しのつかないミスをしてしまいました。先方より厳しい叱責を受け、上司と共にお詫びに行きました。帰りの道すがら、K君は上司に次のような指摘を受けました。 「今の君には集中力が欠けている。仕事は慣れなければならないが、慣れ過ぎはダメだ。君なりに目標を掲げ、気合を入れて仕事をしてほしい」 「それに、仕事は君一人でやっているのではない。常に、皆様のお陰でやらせていただいているという謙虚な姿勢で取り組むように」 大きな失敗への反省から、上司の言葉を噛みしめたK君。その後、折りに触れて「皆様のお陰」という言葉を口にすることで、気を引き締めています。 今日の心がけ◆お陰様の心を持ちましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在まで一日も欠くことなくずっと続いています。著作権に問題があることは承知していますが、倫理の普及に役立ち、かつO君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。以上の点をご理解いただき、文章の取り扱いには配慮をお願いします。
2016年01月28日
コメント(0)
-
1月27日(水) 九州のユニーク列車
1月27日(水) 九州のユニーク列車 九州の最南端に「指宿のたまて箱」という特急列車が走っています。 わずか二両編成のその列車は、特急なのに速くありません。車両の内装には、上質な木が使われています。座席は窓を向いて座れる設計になっていて、乗車時には、玉手箱さながらに霧が噴出するなど、仕掛け満載の特別列車です。 車両をデザインしたのは、水戸岡鋭治氏です。JR九州では、他にも「ななつ星」「或る列車」など、水戸岡氏が手がけた個性的な列車が走っています。 という思いから、氏は、列車の内装や外装に、木材を使うことを提案しました。腐食しやすく、コストがかかるといった不安を抑えて「やってみよう」と決断したのは、石原進社長(現相談役)でした。 「どこの企業も『お客様第一』とお題目を掲げますが、最後は事業者の論理が働いてしまうものです。目先の利益を考えず、長い目で地域のことを考えられるか。それがやり切れるかどうかは、トップ次第です」 地域おこしの背景には、独創的な案を採用した度量と決断があったのです。 今日の心がけ◆お客様のためになることを追求しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。
2016年01月27日
コメント(0)
-
1月26日(火) 突然の代役
1月26日(火) 突然の代役 物事には二通りの受け止め方があります。明るく肯定的に受け止めるか、不足不満の心で受け止めるかの二つです。 ある会合で、突然上司が出席できなくなり、挨拶の役割が回ってきたとします。 Aさんは、「たまたま上司が欠席で、自分に役割が回ってきた。いい勉強の場が与えられた。ありがたい」と肯定的に受け止めました。 Bさんは、「なぜ約束通り出席しないのか。上司として失格だ。突然言われても困る。恥をかきたくない」と不平不満でいっぱいでした。 あなたなら、どちらの受け止め方をするでしょうか。冷静に判断をすれば、Aさんのように肯定的に受け止めたいと思うでしょうが、いざという時にそれができるかどうかが最大のポイントです。 いついかなる時も、目の前に起こってきたことは「自分にとって必要なことだ」と肯定的に受け止めるところに、自分を成長させる糧があります。 日頃から、些細なことでも喜んで引き受ける生活を心がけましょう。 今日の心がけ◆物事を肯定的に受け止めましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在までずっと続いています。O君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。
2016年01月26日
コメント(0)
-
1月25日(月) 社内で一番になる
1月25日(月) 社内で一番になる 広告会社で働き、入社五年目となるFさん。人事異動で、営業部から経理部勤務となりました。これまでの仕事内容とは異なりますが、と心に決めました。 しかし、異動から一ヵ月経っても、任される仕事はコピー取りや資料整理ばかりです。仕事にやりがいを見いだせず、不満を抱くようになっていきました。 その悩みを、先輩に相談すると、「阪急グループの創業者・小林一三氏を知っているかい?彼は『下足番を命じられたら、日本一の下足番になってみろ。そうしたら、誰も君を下足番にしておかぬ』という言葉を残している。今の君の状況にぴったりだね」といわれたのです。 Fさんは、自分が与えられた仕事に集中することなく、仕事に優劣をつけ、不満を抱いていたことに気づきました。そして、と決めたのです。 仕事に取り組む姿勢が変わり、少しずつやりがいを取り戻したFさんです。 今日の心がけ◆目前の仕事に全力を向けましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。日本各地にある倫理法人会では、毎週「モーニングセミナー」が開催されます。また毎月1回「経営者の集い」があります。モーニングセミナーも経営者の集いも、一般の方や社員に参加いただけます。いずれも経営のためだけでなく人生を豊かに過ごすための講演会です。(私自身が誤解していましたので、あえて申し添えます。宗教ではありません)
2016年01月25日
コメント(0)
-
1月24日(日) 面倒だから面白い
1月24日(日) 面倒だから面白い Nさんの趣味は映画鑑賞です。観たい映画は必ず映画館で観ます。古い映画も、再上映する機会を待って、劇場で観るようにしています。 「映画館の暗闇で観てこそ映画。日常から離れて、作品の世界に没頭したい」というのが、Nさんなりの理由です。 とはいえ、映画のチケット代も安くありません。映画を観に行って帰るだけでも、時間がかかります。その上、わざわざ観に行ったのに、ものすごくつまらなくて、ガッカリして帰ることもたびたびです。 お金もかかるし、時間もかかる。ハズレもある。それでも映画館で映画を観るのは、「失敗も含めて映画体験だから」とNさんは語ります。 いい映画に出合った時の喜びはより大きく、期待外れだった時はより失望する。感情の振り幅が大きい分、その体験は、より記憶に残るのでしょう。 物事への価値観は人それぞれですが、手軽な方法と、手間のかかる方法があった時、あえて手間のかかる方を選択するのも一つの道です。 今日の心がけ◆あえて手間をかけてみましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。朝礼に利用すると、とても効果が高いと思います。書店では売っていません。倫理法人会に入会すると毎月30冊もらえます。職場の教養は、毎日当日分を掲載しています。朝礼の準備などであらかじめ読みたい方のため、楽天ブログの当月の1日に、1か月分をまとめて掲載させていただきます。左のカレンダーから1日をクリックしてください。翌月分の職場の教養は20日に、それまでに出来たぶんだけを掲載します。
2016年01月24日
コメント(0)
-
1月23日(土) 缶自動分別ゴミ箱
1月23日(土) 缶自動分別ゴミ箱 愛知県に住む小学生の女子が、スチール缶とアルミ缶を自動的に分別する装置を考案して、特許を取りました。 その装置には、内部に仕切りがあり、「スチール缶入れ」と「アルミ缶入れ」に分かれています。上部の投入口からアルミ缶を入れると、そのまま真下に落ち、スチール缶を入れると、磁石の力で反対側に落ちるという仕組みです。 この発明をした動機は、スーパーを営む祖父が、自動販売機のゴミ箱の缶を分別する大変さを見ていたからでした。夏休みの自由研究の課題として、取り組んだ成果でした。 発想の原点には、「おじいちゃんが大変そうだった。何とかできないかと思って」という心があったといいます。「誰かのために」という強い思いが、実を結んだといえるでしょう。 人に対して優しいまなざしを向けることは、新しい発見や発明をするチャンスにつながるのかもしれません。 今日の心がけ◆思いやりの心で環境を変えましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。職場の教養は、毎日当日分を掲載しています。職場の教養を使うと、活力あふれる朝礼が出来ます。朝礼の準備などであらかじめ読みたい方のため、楽天ブログの当月の1日に、1か月分をまとめて掲載させていただきます。左のカレンダーから1日をクリックしてください。翌月分の職場の教養は入力が出来た分だけ、20日の日記にまとめて掲載します。
2016年01月23日
コメント(0)
-
1月22日(金) 住み慣れたはずの町
1月22日(金) 住み慣れたはずの町 「人生の中で、一度も引っ越しをしたことがない」という人は、恐らく少ないでしょう。不思議なことに、その土地を離れてみて初めて、その良さに気づくことが多いものです。 Aさんは数年前に、転勤で九州から関東へ引っ越してきました。ある時、休暇を利用して、以前住んでいた場所に家族で訪れてみました。 環境整備などで、ところどころ景観は変わっているものの、豊かな自然や町並みはそのままです。リーフレットを見ると、町の名物や歴史について紹介されています。知らなったことがたくさんありました。 住み慣れた町を数年ぶりに訪れたAさんは、いかに周囲を見ていなかったかを痛感し、新たな発見をいくつもすることができました。 目には見えていても、関心を持っていなければ記憶に残らないのが、人の心の不思議です。今住んでいる場所の歴史や景観に関心を持って、地元の良いところを発見してみましょう。後で気づくのは、もったいないことです。 今日の心がけ◆地域に関心を持ちましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。各地の倫理法人会では、毎週モーニングセミナーが開催されます。特定の宗教や政治にとらわれることなく、多面的な学びができるのが特徴です。
2016年01月22日
コメント(0)
-
1月21日(木) 勝手な思い込み
1月21日(木) 勝手な思い込み 人は仕事に慣れてくると、自分勝手な「思い込み」によって、思わぬミスを起こしてしまうことがあります。 さらに、一度そうだと思い込んでしまうと、なかなか間違いだと気づけなかったり、間違いを認められないから厄介です。 ある日、Sさんは、取引先の相手と打ち合わせをするため、いつも待ち合わせに使っている会場へ向かいました。 余裕を持って行動した分、早めに会場に到着しました。相手が到着するまでの間、資料を眺めつつ、打ち合わせの段取りを確認していました。 確認が終わり、そろそろ来る頃かなと資料を片づけようとした時、パッと目についたメモには、別の待ち合わせ場所が書かれていたのです。 幸い、約束には間に合ったSさんですが、慣れによる思い込みの恐さを知りました。それ以降、朝一番にスケジュールを確認してから、一日のスタートを切るようになったのです。 今日の心がけ◆確認を怠らないようにしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在まで一日も欠くことなくずっと続いています。著作権に問題があることは承知していますが、倫理の普及に役立ち、かつO君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。以上の点をご理解いただき、文章の取り扱いには配慮をお願いします。
2016年01月21日
コメント(0)
-
2月 2日(火) トラックの名前は
2月 2日(火) トラックの名前は 運送会社を起業し、十五年になるB社長。毎年、事故が減らないことに頭を悩ませていました。大事故にはならないものの、「大きな事故の前には、小さな事故が重なって起きるもの」という話を聞き、気が気ではありません。 ある時、同業者の集まりで、ある会社がちょっと変わった取り組みをしたことで、事故がなくなったという情報を聞きました。 さっそく話を聞きにいくと、事故が減った経緯を惜しげもなく教えてくれました。それは、社長も社員も、自分が運転するトラックに、子供や伴侶など最愛の人の名前を付けて、挨拶をしているというのです。 話を聞いたB社長はと思いました。それでも、ものは試しと、まずは自家用車に「よしこさん」と、妻の名前を付けてみました。 運転前に「よしこさん、今日もよろしく!」と声をかけると、いつもの車に対して、今までとは違った感情が芽生えるのを感じました。そして、無事に目的地に着いた時、「ありがとう」という言葉が自然に口をついたのです。 今日の心がけ◆感謝を持って物を扱いましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在までずっと続いています。O君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。
2016年01月20日
コメント(0)
-
2月 1日(月) 自社を知る
2月 1日(月) 自社を知る A社長が、新しい取引先に電話をした時のことです。 電話に出た社員に、会社の住所と電話番号、社長のフルネームを確認したところ、すぐに答えが返ってきませんでした。怪訝に思ったものの、と考えて、電話を切りました。 ふと「うちの社員はどうだろうか」と気になったA社長は、思い切って、会社の基本情報についての社内テストを実施しました。 すると、会社の電話番号を知らなかったり、社長のフルネームを書けない社員が、少なからずいたのです。 著名講師を招くなど、時間とお金をかけて社員教育に力を入れてきたA社長ですが、最も基本的な情報を社員が知らなかったことに愕然としました。 これを機に、A社長は、まずは社員に自分の会社のことをよく知ってもらうという方針を立てました。そして自らも、日常の基本的な事柄を疎かにしないよう、足元の実践に取り組むようになりました。 今日の心がけ◆基本を見直しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。日本各地にある倫理法人会では、毎週「モーニングセミナー」が開催されます。また毎月1回「経営者の集い」があります。モーニングセミナーも経営者の集いも、一般の方や社員に参加いただけます。いずれも経営のためだけでなく人生を豊かに過ごすための講演会です。
2016年01月20日
コメント(0)
-
1月20日(水) 声に出す
1月20日(水) 声に出す 朝礼において、本誌を活用する方法の一つに「輪読」があります。本文を声に出して読み、かつ、一段落ごとに読み手を変えるという方法です。 「輪読」とは「数人が順番に一つの本を読み、解釈研究などをすること」をいいます。これを朝礼で行なうことの意義は、1積極性を培う、2気づいたらすぐする即行力を養う、3内容への理解が深まることにあります。 人前で声に出して読むのは、勇気の要ることです。自ら進んで朗読することで、躊躇逡巡する心を取り去り、一歩を踏み出す積極性が養われます。 また、という思いと、朗読という行動を一致させることで、即行力が養われます。 そして、音読の言葉を最もよく聞いているのは、自分自身に他なりません。目で見る理解と共に、耳から入る音声情報が加わることで、内容の理解もさらに深まるでしょう。 毎日の朝礼を活かし、仕事の底力を磨いていきたいものです。 今日の心がけ◆朝礼を活かしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。
2016年01月20日
コメント(0)
-
1月19日(火) 心構え
1月19日(火) 心構え 西郷隆盛に「その才器、識見、到底自分が及ぶものではない」と言わしめた人物に、橋本佐内という幕末の志士がいます。 幼少の頃から才覚を発揮し、周囲からも将来を嘱望された左内は、著書『啓発録』の中で、己の心身を磨き高めるための五つの心構えを説いています。 1「稚心を去れ」・・・甘えた心を捨てる。 2「気を振え」・・・怠け心を捨てる。 3「志を立てよ」・・・志を立て行動を起こす。 4「学を勉めよ」・・・学問に励む。 5「交友を択ぶ」・・・磨き合う友を選ぶ。 高い志と実行力を兼ね備えた左内は、その後、多くの知己を得ながら、新しい時代の幕開けに一石を投じる存在となりました。その生き様は、現代を生きる社会人にも、大切な心の構え方を教えてくれています。 自分を律する強い心を持ち、日々の業務に精励していきたいものです。 今日の心がけ◆目標を叶える努力をしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在までずっと続いています。O君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。
2016年01月19日
コメント(0)
-
1月18日(月) ルーティン
1月18日(月) ルーティン 昨年秋に行なわれたラグビーワールドカップで、一躍、時の人となった日本代表の五郎丸歩選手。特に話題を集めたのは、得点を狙うキックの際に見せる「ルーティン」と呼ばれる独特のポーズです。 「ルーティン」とは、決められた一連の動作のことを指します。五郎丸選手は、ボールをセッティングしてから、蹴るまでの一連の動作を固定し、その動作に集中することで、状況や雰囲気に左右されず、常に百パーセントの力を発揮できるようにトレーニングを積んできました。 私たちも、その日の体調や天候、仕事の状況によって起こる気持ちの浮き沈みで、業務に集中できなかったり、ミスを起こすこともあるでしょう。 窓を開けて空気を入れ替えたり、清掃を行なったり、朝礼で笑顔をつくるなど、毎朝必ず行なう自分だけの「ルーティン」を決めることで、仕事へのスイッチが自然と入るものです。 些細なことでも、一日一回、同じことを繰り返し行なってみましょう。 今日の心がけ◆良い習慣を毎日繰り返しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。
2016年01月18日
コメント(0)
-
1月17日(日) 他人事ではない
1月17日(日) 他人事ではない 「特殊詐欺」とは、不特定の人に対して、対面することなく、電話やメールなどを使って行なわれる詐欺のことです。オレオレ詐欺や架空請求詐欺などがこれにあたります。 特殊詐欺の被害については、ニュースでもしばしば取り上げられ、注意勧告がなされています。しかし、他人事だという認識で聞き流してしまいがちです。 「何で騙されるの?」「かわいそうに」と安易に片づけず、改めて「自分ならどうするか」「親が巻き込まれないためにはどうすればよいか」などと、対策をとる必要があるでしょう。 警察庁によれば、二〇一四年の特殊詐欺の被害総額は、およそ五六〇億円でした。詐欺の手口は年々巧妙になっており、被害額も前年より約七〇億円増えたそうです。被害に遭った人の八割弱が高齢者でした。 この問題を他人事として捉えるのではなく、定期的に連絡するなど、家族の絆を深めるきっかけとして、より良い関係を築いて:いきたいものです。 今日の心がけ◆家族で連絡を取り合いましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。
2016年01月17日
コメント(0)
-
1月16日(土) 十年の節目に
1月16日(土) 十年の節目に 建築会社に勤めるBさんは、勤続十年を迎えました。この節目に、公私共に面倒をみてもらっている先輩から、夕食に誘われました。 先輩の手を離れ、事務処理から現場まで一人でこなすようになって、三年が経っていました。食事をしながら先輩は、Bさんの話を穏やかに聞いてくれます。 話を受け入れてくれる心地よさを感じながら、Bさんは、普段は言えない心の内を話し始めました。帰宅時間が遅いことや、仕事量に比べて給料が低いことを「割に合わない」と言った時、穏やかだった先輩の表情が一変したのです。 「おまえは何のために仕事をしているんだ!」と一喝する先輩を前に、Bさんは、言葉を返すことができませんでした。そして先輩は、いきいきと仕事に向かうBさんの姿に喜びを感じていたことを、ゆっくり話し始めたのです。 先輩の話を聞きながら、お客様からの感謝の言葉が何よりの生き甲斐だった、入社当時を思い出したBさんです。 十年の節目を機に、気持ちを引き締め直して帰路につきました。 今日の心がけ◆原点に返る時間を持ちましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。
2016年01月16日
コメント(0)
-
1月15日(金) 父の思い出
1月15日(金) 父の思い出 Kさんは、物心がついた頃から父親が嫌いでした。休日は昼まで寝ていて、一緒に遊んでくれることもなく、夕食の時間はたいてい母と二人きりでした。じっくり話すこともないので、どんな仕事をしているのかも知りませんでした。 Kさんが小学生の高学年になった時のことです。よそ行きの服を着た母と二人で、父が勤める会社に行きました。 そこで初めて、働く父の姿を見たのです。ヘルメットをかぶって、大きなショベルカーを操る父は、とても逞しく見えました。チラッとこちらを見た父が、わずかに片手を挙げたので、Kさんも思わず大きく手を振りました。 その後、父の職場の社長から、「日本の国をつくり上げる素晴らしい仕事をしているのですよ」と教わりました。この日を境に、Kさんは父を誇らしく思えるようになったのでした。 これは、親の働く姿を見るという社会科の授業の一環でした。今は子供を持つ年齢になったKさんですが、当時のことがありありと思い出されるのです。 今日の心がけ◆自分の仕事を家族に語りましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。
2016年01月15日
コメント(0)
-
1月14日(木) 心の癖を取り去るには
1月14日(木) 心の癖を取り去るには 街中で知人を見かけた時、挨拶をしようか、どうしようかと躊躇して、結局、声をかけずに通り過ぎてしまうことがあります。 というタイプの人は、他の面でも、言いたいことを言えずに、不満を溜めてしまったり、やらなければいけないことを後回しにするような傾向があるかもしれません。 その背景には、どうやら「心の癖」がありそうです。人は誰にも癖があります。この場合は、何かにこだわり過ぎたり、考え過ぎたり、先のことを覚えてしまうような心の癖を持っているのでしょう。 その癖を取り去る鍵は、日々の生活にあります。「気づいた時、気軽に朗らかにサッと処理をする」。これを常に心に留めておくことです。 中でも一番のお勧めは、朝、目が覚めたらサッと起きることです。朝一番のスタートから「気づいたらすぐする」ことを実行できれば、その日一日の行動も、きっと変わってくるでしょう。 今日の心がけ◆気づいたらすぐに行ないましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在まで一日も欠くことなくずっと続いています。著作権に問題があることは承知していますが、倫理の普及に役立ち、かつO君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。以上の点をご理解いただき、文章の取り扱いには配慮をお願いします。
2016年01月14日
コメント(0)
-
1月13日(水) 商品を知る
1月13日(水) 商品を知る お客様に商品を売るために、官伝や広告、販売方法を考えることは大切です。商品に愛情を持つことも、重要な要素でしょう。 販売部門のAさんは、売り上げが伸びない時期に、先輩から「この商品のことを知っている?」と問われました。名前と値段は、もちろん知っています。どのような効果があるということも、一応は知っているつもりです。 しかし、「それ以外は?」と先輩に問われ、言葉に窮してしまいました。 「愛情が足りないね。商品が誕生した由来やできあがるまでの過程に関心を持つことは愛情であり、その愛情は、お客様にも伝わるはずだよ」 Aさんは日頃、お客様と接しながら、と、その場で判断をしながら販売をしていました。先輩の言葉を聞き、Aさんは、販売手法だけにとらわれていたことに、気づかされたのです。 商品をよく知ることは、その商品への愛情につながります。愛情のある商品の説明には熱が入り、相手の心にも響くものです。 今日の心がけ◆扱う商品の由来を知りましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。
2016年01月13日
コメント(0)
-
1月12日(火) 挨拶
1月12日(火) 挨拶 挨拶は人間関係の入り口です。Yさんは、その挨拶に、こだわりを持っています。それは、誰に対しても、自分の挨拶によって元気になってもらえるよう、気持ちを込めて挨拶するということです。 ところが、こうした挨拶をしようと決めた当初、戸惑うことがありました。この挨拶のポイントは、「誰にでも」ということですが、気持ちを込めて挨拶をできない相手が少なからずいたのです。 Yさんは、多くの顧客や取引先とやり取りをする中で、「人の好き嫌いはない」と自負していました。しかし、心のどこかで避けていたり、些細な欠点を気にしてしまう人がいることに気づいたのです。 挨拶を通じて、自分の心の意外な一面を知ったYさん。朝礼での挨拶練習に真剣に取り組んで、基本を確認しつつ、苦手な人ほど心を込めた挨拶をしようと心がけました。 三ヵ月が経った今、その人の美点を発見できるようになっています。 今日の心がけ◆挨拶に心を込めましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在までずっと続いています。O君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。
2016年01月12日
コメント(0)
-
1月11日(月) 仕事模様
1月11日(月) 仕事模様 若手社員のAさんは、入社から半年、早く仕事を覚えて貢献できる自分になろうと努めてきました。 経験を積むことと合わせて、先輩の仕事ぶりからも多くのことを学んできました。ある時、「職場にはいろいろな人がいるな」と思ったそうです。 「指示されたことしかしない人」がいれば、「指示されたこともしない人」もいました。Aさんが「自分はどうなりたいか」と思った時に浮かんだのは、指示がなくても仕事の流れを考えて動いているBさんの姿でした。 Bさんは、社歴は短いものの、部署全体の方針と年間計画を踏まえて、段取りを進めています。目の前の仕事と並行して、次の仕事の準備を進め、いつ指示されてもよいように備えていました。 そうしたBさんの、慌てる様子はほとんど見たことはありません。 「自分も視野を広げて、仕事の流れが見られるようになろう」と、決意を新たにしたAさんでした。 今日の心がけ◆仕事全体の流れを把握しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。
2016年01月11日
コメント(0)
-
1月10日(日) 知の地平線
1月10日(日) 知の地平線 昨年、ノーベル物理学賞を受賞した東京大学教授・梶田隆章氏は、研究に取り組む自身の姿勢を「人類の知の地平線を拡大するような好奇心でやっている」と述べています。 梶田教授の研究成果は、「あらゆる物質をすり抜けていくニュートリノという素粒子が、実は質量を持っている」という、それまでの定説を覆す発見でした。宇宙や物質が誕生した謎の解明に迫る、大変な業績だといわれています。 「知の地平線を拡大する」という壮大な表現を用いるほどの好奇心こそ、ノーベル賞受賞という高いハードルに到達する、エネルギーの源だったのでしょう。 「好きこそものの上手なれ」といわれるように、興味や好奇心を強く持てることには、人は熱心に打ち込めます。その結果、自ずとそのことに習熟し、さらなる実力を養うことにもつながります。 日常の中で、興味が湧いたこと、関心を持ったことを大事にしましょう。その好奇心のつぼみは、いずれ仕事の場で花が開くかもしれません。 今日の心がけ◆好奇心を成長のエネルギーにしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。
2016年01月10日
コメント(0)
-
1月 9日(土) 奇跡はない
1月 9日(土) 奇跡はない 学生や社会人のラグビー全国大会が、各地で行なわれています。その熱戦に、昨年のラグビーワールドカップを思い出す人も多いでしょう。 大会後、世界のラグビーファンの投票による「ワールドカップ最高の瞬間」に、日本代表対南アフリカ代表の一戦が選ばれました。 優勝候補の南アフリカ代表に、逆転トライをあげて勝利した日本代表は、「ブレイブ・ブロッサムズ(勇敢な桜の戦士たち)」と称賛されました。 世界中がこの勝利に驚く一方で、選手たちは三年半に及ぶトレーニングを通して、「南アフリカに勝てる」と確信していたと言います。強豪国と伍するため、世界一厳しい練習を毎日してきた、という自負があったからです。 勝利の立役者である五郎丸歩選手の「ラグビーに奇跡なんてないんです。必然です」というコメントからも、努力に裏づけされた、誇りと自信が窺えます。 自信は、大きな仕事を成し遂げる上で欠かせない心です。その源となるのは日々の努力でしょう。「努力は人を裏切らない」からです。 今日の心がけ◆努力を重ねて大業を成し遂げましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。
2016年01月09日
コメント(0)
-
1月 8日(金) 適切な言葉
1月 8日(金) 適切な言葉 他部署に渡す報告書の作成を任されたAさん。報告書を作成し、上司に提出すると、言葉の使い方についての指摘を受けました。 Aさんは、自分の部署内でのみ使われる言葉で、報告書を作成していたのです。そして、その言葉が一般的な名称とは異なるものだとは、まったく気がついていませんでした。 「相手にわかりにくい文書は不親切だ」と上司に指摘され、早速、適切な言葉に置き換えて修正しました。日頃慣れ親しんだ言葉でも、正確に伝えたい時には、相手に応じた配慮が必要なのだ、とAさんは痛感しました。 私たちは、日々、たくさんの人とコミュニケーションをとりながら仕事を進めています。相手に正しく伝わるように、適切な言葉を使うことは必要不可欠です。 「伝えたいこと」と「伝わること」が、必ずしも一致しないこともあります。文章の要点は、何よりもまず、相手に自分の言いたいことや思いが伝わることです。そして、その言葉が気持ちの良いものであればさらに良いでしょう。 今日の心がけ◆わかりやすい言葉を使いましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。各地の倫理法人会では、毎週モーニングセミナーが開催されます。特定の宗教や政治にとらわれることなく、多面的な学びができるのが特徴です。
2016年01月08日
コメント(0)
-
1月 7日(木) 仕事に尊卑はない
1月 7日(木) 仕事に尊卑はない リサイクル業を営むDさんは、地域の異業種交流会に参加しました。 はじめに、簡単な自己紹介の時間があります。Dさんは業種について「恥ずかしながら、3K(汚い、きつい、危険)そのものの業種です」と話しました。 その後、交流会の中で、参加者の一人が声をかけてきました。「私も同じ業界ですが、この仕事を恥ずかしいと思ったことはありません」と言われたのです。「どういうことですか?」とDさんは尋ねてみました。 「仕事そのものは、Dさんのおっしゃる通りです。でも、この仕事があるから、リサイクルが活発になり、皆さんの生活に役立っているのでしょう。家庭にも職場にも再生品は多くあるし、限られた資源を再生することは大切ですよ」 Dさんは、その話を聞いて、人には誇れない仕事だと思っていた自分が恥ずかしくなりました。 同じ仕事に情熱を持っている人との会話を機に、と自分に言い聞かせて、喜んで取り組んでいる毎日です。 今日の心がけ◆自分の仕事に誇りを持ちましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在まで一日も欠くことなくずっと続いています。著作権に問題があることは承知していますが、倫理の普及に役立ち、かつO君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。以上の点をご理解いただき、文章の取り扱いには配慮をお願いします。
2016年01月07日
コメント(0)
-
1月 6日(水) 良い年にする
1月 6日(水) 良い年にする 新春には、各地で消防出初式が行なわれます。その起源は江戸時代に遡ります。 一六五七年、江戸は明暦の大火により、焦土と化しました。その二年後に、時の老中・稲葉伊予守正則が、当時の消防隊(火消し)四隊を率いて、上野東照宮の前で「出初」(出勤初め)と称して気勢をあげました。 これは、復興作業などで気落ちしていた江戸の人々に、大きな希望と信頼を与えたそうです。その後、「出初」は儀式化され、今日に受け継がれています。 大火に見舞われた江戸の町のように、人生の中でも、大きな困難に遭遇することはあります。打ちひしがれ、苦しみを抱える中にも、何か具体的に行動に移すことは、一つの転機になるでしょう。 また、行動と共に、心の底から「こうしよう」と腹を決めることも必要です。真の決心には、状況を変える力が潜んでいます。 一歩踏み出す行動と、「今年を良い年にする」という決心の両輪で、新しい年のスタートを切りたいものです。 今日の心がけ◆本気の決心をしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。職場の教養を利用すると、活力ある朝礼をするのに役立ちます。
2016年01月06日
コメント(0)
-
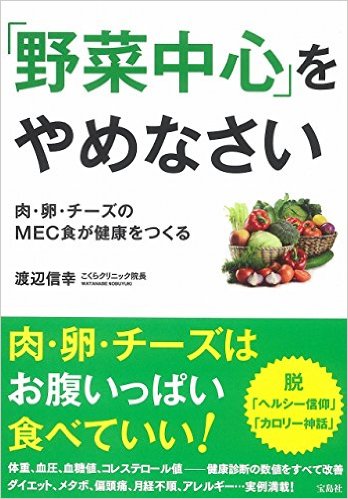
MEC食の本が届きました。
MEC食の本が届きました。挫折だらけのアル中お気楽ダイエット日記 この日記は1月6日の朝 昨日の日記を書いています。 今朝の体 重:71.5kg 前日比マイナス0.2kg昨日の飲酒量:缶ビール1個、赤ワイン3杯昨年末、お肉と卵とチーズをしっかり食べて痩せましょうという情報を得ました。で、手配したのがこの本です。なんとなんとアマゾンでは2,000円を超える金額で売られていました。定価1,000+税の本ですよ。なんとか定価で買いたいと、探したら・・・ありました。楽天ブックス!注文したのが12月21日、届いたのは1月5日その間、何度も「入手できません」のメールが届きました。まぁ、届いたのだから好しとします。この本を読んで、MEC(肉・卵・チーズ)をたっぷり食べて、痩せますよ。ほぼ、100%近い人が、「なんと馬鹿な!!」という目でこの記事を読んでいるのでしょうけれど、もうすでに、12月22日からMEC中心にしてきて74.2kg⇒⇒⇒71.5kgと2.7kgの減量に成功しているんですからね。しかも、年末年始の過渡期を乗り越えているのだから。2007年4月30日 ダイエットスタート時82.5kgでした。 2016年2月18日目標68.0kg BMI=21を達成します。 ♪♪♪ 私のダイエット方針 ♪♪♪ MEC(肉・卵・チーズ)をたっぷりよく噛んで食べる。節酒につとめ、お酒は3つ(個、本、杯)までとする。 失敗してもめげない。いつも笑顔でいる。
2016年01月06日
コメント(0)
-
ダイエット方針を変えました。
ダイエット方針を変えました。挫折だらけのアル中お気楽ダイエット日記 この日記は1月5日の朝 昨日の日記を書いています。 今朝の体 重:71.7kg 前日比マイナス0.7kg昨日の飲酒量:缶ビール1個、赤ワイン5杯、生ビール1杯 芋のお湯割り3杯、日本酒2杯昨年末から、いろいろ考え、このたびダイエット方針を変えることにしました。新しいダイエット方針は・・・ ♪♪♪ 私のダイエット方針 ♪♪♪ MEC(肉・卵・チーズ)をたっぷりよく噛んで食べる。節酒につとめ、お酒は3つ(個、本、杯)までとする。 失敗してもめげない。いつも笑顔でいる。 これまでとの違いは、2つです。玄米と運動をダイエットの手法とすることを止めます。これまでどおり基本、白米は食べません。これまでどおり、食べるなら玄米にします。ダイエットの為の玄米ではなく、おいしいから少量だけ味わって食べることにします。これまでどおり、なるべく歩くよう心がけますが、ダイエットの為にではなく、健康の為とします。昨年末出会った、MEC食を中心にしてみようと思うのです。2007年4月30日 ダイエットスタート時82.5kgでした。 2016年2月18日目標68.0kg BMI=21を達成します。 ♪♪♪ 私のダイエット方針 ♪♪♪ MEC(肉・卵・チーズ)をたっぷりよく噛んで食べる。節酒につとめ、お酒は3つ(個、本、杯)までとする。 失敗してもめげない。いつも笑顔でいる。
2016年01月05日
コメント(0)
-
1月 5日(火) 前もって
1月 5日(火) 前もって 作家の池波正太郎氏は、毎年の年賀状を五月から準備したそうです。 宛名を書くのも人任せにせず、一枚ずつ自身で書き、千枚近い年賀状を書き終わるのが十二月近くになるという寸法でした。 それが池波氏の仕事の流儀でした。カレンダーに記入するのも、三ヵ月を単位として、三ヵ月先を見越した上で、時間を使っていくようにしていました。 「すべて前もって、事を進めていくことが時間の使い方の根本だよ」と池波氏は言います。とかく目先のことに追われている現代人は、改めて時間の使い方を見直してみる必要があるかもしれません。 今やるべきことを後回しにしたために、臍を噛むというのは、よくありがちなことです。時間に余裕があれば、行動や思考にも幅が生まれ、より深い人生の喜びが得られるでしょう。 まずは、一年の予定を三ヵ月ごとに大掴みにし、すべてを「前もって」取り組む習慣をつけることから始めてみませんか。 今日の心がけ◆早めに行動しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在までずっと続いています。O君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。
2016年01月05日
コメント(0)
-
今年こそ!!
今年こそ、68kg見事達成いたします。
2016年01月04日
コメント(2)
-
1月 4日(月) 和服で仕事始め
1月 4日(月) 和服で仕事始め 北陸に本社を構えるA社では、仕事始めに、社員が皆、和服を着用します。 きっかけは社長の発案でした。といった社長の思いから、毎年の恒例となったそうです。 社員は皆、色鮮やかな振袖や羽織袴を着用します。その際、地元の美容室や呉服店が協力し、着付けをしてくれます。 和服を持っていない社員には、無料でレンタルするなど、和服を愛する地元の人の協力があって、仕事始めの式典が執り行なわれます。 新入社員のK子さんは、「着慣れていないので少し苦しかったですが、地元の代表的な柄の着物を着られて、楽しく参加できました」と述べています。 どの会社も、恒例行事や会社独自の習慣を持っているものです。若い社員たちが、日本の伝統に触れることにもなるA社の仕事始めは、地域の特色を活かした企業文化となって、これからも受け継がれていくでしょう。 今日の心がけ◆会社独自の文化を育みましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。
2016年01月04日
コメント(0)
-
1月 3日(日) 念ずれば花ひらく
1月 3日(日) 念ずれば花ひらく 新年を迎え、初詣に出かけた人も多いでしょう。どのようなことを願い、どのようなことを誓ったでしょうか。 明治四十二年に生まれ、「癒しの詩人」と呼ばれた坂村真民は、「念ずれば花ひらく」という言葉を遺しました。 真民は「午前零時に起床して、夜明けに重信川のほとりで地球に祈りを捧げる生活」を長年続けていたといいます。一つの願いを心に思うだけでなく、行動として習慣にしていたのです。 人の心は、そのままに保つことが難しいものです。しかし、行動を伴わせることで、願いが薄まっていくことに抗し、さらに思いを高めていくことができます。 日記をつける、太陽に挨拶をするなど、毎日決まった型を身に付けることで、生活にくさびが打たれ、けじめがつきます。一日一度、同じことを続けられていることに自信が湧いてきます。 心の中にある思いを実現するため、日に一つ、何か始めてみませんか。 今日の心がけ◆一日一度行ないましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。
2016年01月03日
コメント(0)
-
1月 2日(土) 寒さ対策
1月 2日(土) 寒さ対策 新年に開かれた同窓会に出席したK氏。かつて数々の人生相談をした恩師に、「先生、風邪をひかないコツを教えていただけませんか」と尋ねました。 恩師は、ニコニコしながらこう答えました。「それは君、寒さを嫌わないことだよ。寒かったら服を着る。暑かったら脱げばよい。それだけだよ」 K氏は、博学な恩師の健康法を期待していましたが、当たり前過ぎる答えに、やや拍子抜けしました。それでも、恩師の短い言葉の中に、長い人生経験がにじみ出ているようで、心が温かくなるのを感じたのです。 「寒いね」と 話しかければ 「寒いね」と 答える人のいる あたたかさ これは俵万智さんの歌集『サラダ記念日』の中の短歌です。平凡な日常の中で、互いに共感する、心のぬくもりが感じられます。 私たちは、何気ない会話や、相手の表情や態度にも、温かさや冷たさを感じます。「寒の入り」で寒さが増す季節ですが、互いに温かい言葉をかけ合って、ぬくもりのある職場にしていきたいものです。 今日の心がけ◆温かい言葉をかけましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。
2016年01月02日
コメント(0)
-
1月31日(日) 箸の作法
1月31日(日) 箸の作法 Aさんが同僚と食事をしていた時のことです。箸をのばすAさんの手元を見ていた同僚から、「箸の持ち方が変わっている」と指摘されました。 「仕事上の会食の場で、恥ずかしい思いをするかもしれない。今からでも意識して直してみてはどうか」と、同僚は真剣にアドバイスをしてくれたのです。 Aさん自身、食事の際、他人の咀嚼音が気になることがありました。その一方で、箸の持ち方をはじめ、自分自身の食事マナーについては振り返ることはありませんでした。 言いにくいことをきちんと言ってくれた同僚に礼を言い、Aさんはその後、正しい箸の持ち方を練習するようになりました。 箸には、持ち方と共に、使い方のマナーも多く存在します。「迷い箸」や「探り箸」「ねぶり箸」など、タブーとされることが様々あります。 社会人としての常識は、仕事をしている時以外にも必要です。自分が当たり前だと思っている作法や礼儀を見直してみたいものです。 今日の心がけ◆日常の行儀作法に気をつけましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。
2016年01月01日
コメント(0)
-
1月30日(土) 職場に調和を生むために
1月30日(土) 職場に調和を生むために 看護師のAさんは、主任になってほしいと上司から内示をもらいました。 主任になれば、全体を管理する立場にまわらなければなりません。Aさんは、現場で患者の顔を見て働くことが大好きなため、主任の内示を丁重に断りました。 周囲からは「せっかくのチャンスなのに」「もったいない」と言われました。「変わり者」と揶揄されることもありました。 Aさんにも周囲の声が耳に入り、と自問自答することもありました。 しかし、その後は気を取り直し、以前にも増して明るく、来院者のために働いています。そんなAさんを周囲も受け入れ、人望を集めています。 価値観の違う人間が集まり、職場は作られています。その違いを埋めるには、お互いに感情的にならず、自分から歩み寄ることが大切です。 価値観の違いを大切にした上で、互いの調和を生み出し、連携のとれた職場作りを目指していきましょう。 今日の心がけ◆違いを大切にしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。
2016年01月01日
コメント(0)
-
1月29日(金) 明るい挨拶
1月29日(金) 明るい挨拶 ホテルに勤務するNさんは、ある年配のお客様を客室まで案内しました。その夫婦は、二泊滞在して帰っていきました。 二ヵ月ほど過ぎた日、Nさん宛に礼状が届きました。その夫婦の夫からでした。手紙には、ホテルに宿泊した時、妻がすでに余命わずかであったことが書かれていました。夫婦の、最後の思い出としての旅行だったとのことでした。 その婦人は、ホテルに泊まった際、Nさんの挨拶が何ともすがすがしく心に響いたと、しきりに話していたそうです。夫婦の心の重石が取れたようだと手紙に綴られていました。 帰宅後もNさんのことが話題に上がり、入院中も、周囲に笑顔をふりまいて、明るさのお裾分けをしていたそうです。「落ち込んでいた妻が旅行を満喫できたのは、あなたのお陰です」という文字を見て、Nさんも胸が熱くなりました。 Nさんはと心に刻み、仕事に邁進しています。 今日の心がけ◆心を込めて挨拶をしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。各地の倫理法人会では、毎週モーニングセミナーが開催されます。特定の宗教や政治にとらわれることなく、多面的な学びができるのが特徴です。
2016年01月01日
コメント(0)
-
1月28日(木) 小さなミスから
1月28日(木) 小さなミスから 入社五年目のK君は、仕事にすっかり慣れてきました。その反面、このところ今一つ仕事に力が入りません。小さなミスで肝を冷やす場面が続いています。 その都度、と自分に言い聞かせるのですが、時間が経つと気が緩んできます。確認作業も、おざなりになりがちでした。 そのような中で、会社にとって大事な得意先の支払い伝票に、取り返しのつかないミスをしてしまいました。先方より厳しい叱責を受け、上司と共にお詫びに行きました。帰りの道すがら、K君は上司に次のような指摘を受けました。 「今の君には集中力が欠けている。仕事は慣れなければならないが、慣れ過ぎはダメだ。君なりに目標を掲げ、気合を入れて仕事をしてほしい」 「それに、仕事は君一人でやっているのではない。常に、皆様のお陰でやらせていただいているという謙虚な姿勢で取り組むように」 大きな失敗への反省から、上司の言葉を噛みしめたK君。その後、折りに触れて「皆様のお陰」という言葉を口にすることで、気を引き締めています。 今日の心がけ◆お陰様の心を持ちましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在まで一日も欠くことなくずっと続いています。著作権に問題があることは承知していますが、倫理の普及に役立ち、かつO君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。以上の点をご理解いただき、文章の取り扱いには配慮をお願いします。
2016年01月01日
コメント(0)
-
1月27日(水) 九州のユニーク列車
1月27日(水) 九州のユニーク列車 九州の最南端に「指宿のたまて箱」という特急列車が走っています。 わずか二両編成のその列車は、特急なのに速くありません。車両の内装には、上質な木が使われています。座席は窓を向いて座れる設計になっていて、乗車時には、玉手箱さながらに霧が噴出するなど、仕掛け満載の特別列車です。 車両をデザインしたのは、水戸岡鋭治氏です。JR九州では、他にも「ななつ星」「或る列車」など、水戸岡氏が手がけた個性的な列車が走っています。 という思いから、氏は、列車の内装や外装に、木材を使うことを提案しました。腐食しやすく、コストがかかるといった不安を抑えて「やってみよう」と決断したのは、石原進社長(現相談役)でした。 「どこの企業も『お客様第一』とお題目を掲げますが、最後は事業者の論理が働いてしまうものです。目先の利益を考えず、長い目で地域のことを考えられるか。それがやり切れるかどうかは、トップ次第です」 地域おこしの背景には、独創的な案を採用した度量と決断があったのです。 今日の心がけ◆お客様のためになることを追求しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。職場の教養を利用すると、活力ある朝礼をするのに役立ちます。倫理法人会に入会すると毎月30冊送ってもらえます。ご希望があれば、活力朝礼のやりかたを指導してもらえます。(もちろん無料で)お問いあわせはお近くの倫理法人会まで
2016年01月01日
コメント(0)
-
1月26日(火) 突然の代役
1月26日(火) 突然の代役 物事には二通りの受け止め方があります。明るく肯定的に受け止めるか、不足不満の心で受け止めるかの二つです。 ある会合で、突然上司が出席できなくなり、挨拶の役割が回ってきたとします。 Aさんは、「たまたま上司が欠席で、自分に役割が回ってきた。いい勉強の場が与えられた。ありがたい」と肯定的に受け止めました。 Bさんは、「なぜ約束通り出席しないのか。上司として失格だ。突然言われても困る。恥をかきたくない」と不平不満でいっぱいでした。 あなたなら、どちらの受け止め方をするでしょうか。冷静に判断をすれば、Aさんのように肯定的に受け止めたいと思うでしょうが、いざという時にそれができるかどうかが最大のポイントです。 いついかなる時も、目の前に起こってきたことは「自分にとって必要なことだ」と肯定的に受け止めるところに、自分を成長させる糧があります。 日頃から、些細なことでも喜んで引き受ける生活を心がけましょう。 今日の心がけ◆物事を肯定的に受け止めましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在までずっと続いています。O君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。
2016年01月01日
コメント(0)
-
1月26日(火) 突然の代役
1月26日(火) 突然の代役 物事には二通りの受け止め方があります。明るく肯定的に受け止めるか、不足不満の心で受け止めるかの二つです。 ある会合で、突然上司が出席できなくなり、挨拶の役割が回ってきたとします。 Aさんは、「たまたま上司が欠席で、自分に役割が回ってきた。いい勉強の場が与えられた。ありがたい」と肯定的に受け止めました。 Bさんは、「なぜ約束通り出席しないのか。上司として失格だ。突然言われても困る。恥をかきたくない」と不平不満でいっぱいでした。 あなたなら、どちらの受け止め方をするでしょうか。冷静に判断をすれば、Aさんのように肯定的に受け止めたいと思うでしょうが、いざという時にそれができるかどうかが最大のポイントです。 いついかなる時も、目の前に起こってきたことは「自分にとって必要なことだ」と肯定的に受け止めるところに、自分を成長させる糧があります。 日頃から、些細なことでも喜んで引き受ける生活を心がけましょう。 今日の心がけ◆物事を肯定的に受け止めましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在までずっと続いています。O君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。
2016年01月01日
コメント(0)
-
1月25日(月) 社内で一番になる
1月25日(月) 社内で一番になる 広告会社で働き、入社五年目となるFさん。人事異動で、営業部から経理部勤務となりました。これまでの仕事内容とは異なりますが、と心に決めました。 しかし、異動から一ヵ月経っても、任される仕事はコピー取りや資料整理ばかりです。仕事にやりがいを見いだせず、不満を抱くようになっていきました。 その悩みを、先輩に相談すると、「阪急グループの創業者・小林一三氏を知っているかい?彼は『下足番を命じられたら、日本一の下足番になってみろ。そうしたら、誰も君を下足番にしておかぬ』という言葉を残している。今の君の状況にぴったりだね」といわれたのです。 Fさんは、自分が与えられた仕事に集中することなく、仕事に優劣をつけ、不満を抱いていたことに気づきました。そして、と決めたのです。 仕事に取り組む姿勢が変わり、少しずつやりがいを取り戻したFさんです。 今日の心がけ◆目前の仕事に全力を向けましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。
2016年01月01日
コメント(0)
-
1月24日(日) 面倒だから面白い
1月24日(日) 面倒だから面白い Nさんの趣味は映画鑑賞です。観たい映画は必ず映画館で観ます。古い映画も、再上映する機会を待って、劇場で観るようにしています。 「映画館の暗闇で観てこそ映画。日常から離れて、作品の世界に没頭したい」というのが、Nさんなりの理由です。 とはいえ、映画のチケット代も安くありません。映画を観に行って帰るだけでも、時間がかかります。その上、わざわざ観に行ったのに、ものすごくつまらなくて、ガッカリして帰ることもたびたびです。 お金もかかるし、時間もかかる。ハズレもある。それでも映画館で映画を観るのは、「失敗も含めて映画体験だから」とNさんは語ります。 いい映画に出合った時の喜びはより大きく、期待外れだった時はより失望する。感情の振り幅が大きい分、その体験は、より記憶に残るのでしょう。 物事への価値観は人それぞれですが、手軽な方法と、手間のかかる方法があった時、あえて手間のかかる方を選択するのも一つの道です。 今日の心がけ◆あえて手間をかけてみましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。
2016年01月01日
コメント(0)
-
1月23日(土) 缶自動分別ゴミ箱
1月23日(土) 缶自動分別ゴミ箱 愛知県に住む小学生の女子が、スチール缶とアルミ缶を自動的に分別する装置を考案して、特許を取りました。 その装置には、内部に仕切りがあり、「スチール缶入れ」と「アルミ缶入れ」に分かれています。上部の投入口からアルミ缶を入れると、そのまま真下に落ち、スチール缶を入れると、磁石の力で反対側に落ちるという仕組みです。 この発明をした動機は、スーパーを営む祖父が、自動販売機のゴミ箱の缶を分別する大変さを見ていたからでした。夏休みの自由研究の課題として、取り組んだ成果でした。 発想の原点には、「おじいちゃんが大変そうだった。何とかできないかと思って」という心があったといいます。「誰かのために」という強い思いが、実を結んだといえるでしょう。 人に対して優しいまなざしを向けることは、新しい発見や発明をするチャンスにつながるのかもしれません。 今日の心がけ◆思いやりの心で環境を変えましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。
2016年01月01日
コメント(0)
-
1月22日(金) 住み慣れたはずの町
1月22日(金) 住み慣れたはずの町 「人生の中で、一度も引っ越しをしたことがない」という人は、恐らく少ないでしょう。不思議なことに、その土地を離れてみて初めて、その良さに気づくことが多いものです。 Aさんは数年前に、転勤で九州から関東へ引っ越してきました。ある時、休暇を利用して、以前住んでいた場所に家族で訪れてみました。 環境整備などで、ところどころ景観は変わっているものの、豊かな自然や町並みはそのままです。リーフレットを見ると、町の名物や歴史について紹介されています。知らなったことがたくさんありました。 住み慣れた町を数年ぶりに訪れたAさんは、いかに周囲を見ていなかったかを痛感し、新たな発見をいくつもすることができました。 目には見えていても、関心を持っていなければ記憶に残らないのが、人の心の不思議です。今住んでいる場所の歴史や景観に関心を持って、地元の良いところを発見してみましょう。後で気づくのは、もったいないことです。 今日の心がけ◆地域に関心を持ちましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。各地の倫理法人会では、毎週モーニングセミナーが開催されます。特定の宗教や政治にとらわれることなく、多面的な学びができるのが特徴です。
2016年01月01日
コメント(0)
-
1月21日(木) 勝手な思い込み
1月21日(木) 勝手な思い込み 人は仕事に慣れてくると、自分勝手な「思い込み」によって、思わぬミスを起こしてしまうことがあります。 さらに、一度そうだと思い込んでしまうと、なかなか間違いだと気づけなかったり、間違いを認められないから厄介です。 ある日、Sさんは、取引先の相手と打ち合わせをするため、いつも待ち合わせに使っている会場へ向かいました。 余裕を持って行動した分、早めに会場に到着しました。相手が到着するまでの間、資料を眺めつつ、打ち合わせの段取りを確認していました。 確認が終わり、そろそろ来る頃かなと資料を片づけようとした時、パッと目についたメモには、別の待ち合わせ場所が書かれていたのです。 幸い、約束には間に合ったSさんですが、慣れによる思い込みの恐さを知りました。それ以降、朝一番にスケジュールを確認してから、一日のスタートを切るようになったのです。 今日の心がけ◆確認を怠らないようにしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在まで一日も欠くことなくずっと続いています。著作権に問題があることは承知していますが、倫理の普及に役立ち、かつO君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。以上の点をご理解いただき、文章の取り扱いには配慮をお願いします。
2016年01月01日
コメント(0)
-
1月20日(水) 声に出す
1月20日(水) 声に出す 朝礼において、本誌を活用する方法の一つに「輪読」があります。本文を声に出して読み、かつ、一段落ごとに読み手を変えるという方法です。 「輪読」とは「数人が順番に一つの本を読み、解釈研究などをすること」をいいます。これを朝礼で行なうことの意義は、1積極性を培う、2気づいたらすぐする即行力を養う、3内容への理解が深まることにあります。 人前で声に出して読むのは、勇気の要ることです。自ら進んで朗読することで、躊躇逡巡する心を取り去り、一歩を踏み出す積極性が養われます。 また、という思いと、朗読という行動を一致させることで、即行力が養われます。 そして、音読の言葉を最もよく聞いているのは、自分自身に他なりません。目で見る理解と共に、耳から入る音声情報が加わることで、内容の理解もさらに深まるでしょう。 毎日の朝礼を活かし、仕事の底力を磨いていきたいものです。 今日の心がけ◆朝礼を活かしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。
2016年01月01日
コメント(0)
-
1月19日(火) 心構え
1月19日(火) 心構え 西郷隆盛に「その才器、識見、到底自分が及ぶものではない」と言わしめた人物に、橋本佐内という幕末の志士がいます。 幼少の頃から才覚を発揮し、周囲からも将来を嘱望された左内は、著書『啓発録』の中で、己の心身を磨き高めるための五つの心構えを説いています。 1「稚心を去れ」・・・甘えた心を捨てる。 2「気を振え」・・・怠け心を捨てる。 3「志を立てよ」・・・志を立て行動を起こす。 4「学を勉めよ」・・・学問に励む。 5「交友を択ぶ」・・・磨き合う友を選ぶ。 高い志と実行力を兼ね備えた左内は、その後、多くの知己を得ながら、新しい時代の幕開けに一石を投じる存在となりました。その生き様は、現代を生きる社会人にも、大切な心の構え方を教えてくれています。 自分を律する強い心を持ち、日々の業務に精励していきたいものです。 今日の心がけ◆目標を叶える努力をしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在までずっと続いています。O君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。
2016年01月01日
コメント(0)
-
1月18日(月) ルーティン
1月18日(月) ルーティン 昨年秋に行なわれたラグビーワールドカップで、一躍、時の人となった日本代表の五郎丸歩選手。特に話題を集めたのは、得点を狙うキックの際に見せる「ルーティン」と呼ばれる独特のポーズです。 「ルーティン」とは、決められた一連の動作のことを指します。五郎丸選手は、ボールをセッティングしてから、蹴るまでの一連の動作を固定し、その動作に集中することで、状況や雰囲気に左右されず、常に百パーセントの力を発揮できるようにトレーニングを積んできました。 私たちも、その日の体調や天候、仕事の状況によって起こる気持ちの浮き沈みで、業務に集中できなかったり、ミスを起こすこともあるでしょう。 窓を開けて空気を入れ替えたり、清掃を行なったり、朝礼で笑顔をつくるなど、毎朝必ず行なう自分だけの「ルーティン」を決めることで、仕事へのスイッチが自然と入るものです。 些細なことでも、一日一回、同じことを繰り返し行なってみましょう。 今日の心がけ◆良い習慣を毎日繰り返しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。日本各地にある倫理法人会では、毎週「モーニングセミナー」が開催されます。また毎月1回「経営者の集い」があります。モーニングセミナーも経営者の集いも、一般の方や社員に参加いただけます。いずれも経営のためだけでなく人生を豊かに過ごすための講演会です。(私自身が誤解していましたので、あえて申し添えます。宗教ではありません)
2016年01月01日
コメント(0)
全67件 (67件中 1-50件目)