2025年01月の記事
全12件 (12件中 1-12件目)
1
-

裁判より簡単な解決方法?
皆さん、様々なトラブルの解決に裁判によらない方法があるのをご存知でしょうか?今回は、「裁判外紛争解決手続(ADR=Alternative Dispute Resolution)」について簡単にお話したいと思います。 裁判外紛争解決手続(ADR)とは、様々な民事上のトラブルに対し、裁判によらず話合いで解決する手続きです。一般的に裁判となると、多額の費用と多くの時間が必要となります。また、あまり知られたくない情報まで法廷で公開されるのがイヤって場合もあると思います。そんなケースにADRが使えるかもしれません。ADRは、当事者と利害関係のない公正中立な第三者が間に入り、当事者同士の話合いを支援して、合意によるトラブル解決を図ります。通常の裁判の様に「勝ち負け」ではなく、「これならお互い納得できる」というゴールを目指します。ADRには、調停や裁判上の和解などの「司法型ADR」、行政関連機関が行う「行政型ADR」、そして、民間のADR事業者が行う「民間型ADR」があります。この民間型ADRには、各種業界団体や我々士業団体も含まれています。行政書士会でもADRセンターを設置し、情報発信・相談・申し込み&調停手続きを行っています。 さて、今回は「裁判外紛争解決手続き(ADR)」についてお話しました。裁判と比べて、時間と費用をかけずに紛争を解決できる可能性があるADRですが、まだまだ一般的に知られていません。ADRを利用する場合は、紛争内容に精通する専門家が在籍するADR事業者を選定する事も重要です。ちなみに行政書士ADRセンター福岡では、「愛護動物(ペット等)」「自転車事故」「外国人の労働環境・職場環境」「外国人の教育環境」に関する調停を行っております。
2025.01.26
コメント(0)
-

生命保険金の受取人の変更、どうやると?
皆さん、生命保険入っていますでしょうか?多くの方が入られている生命保険、色んな事情で受取人の変更をする事があるやもしれません。今回は、生命保険の受取人変更について簡単にお話したいと思います。 生命保険の受取人の変更は、保険期間中であれば、契約者によって変更可能です。ただ、支払い事由が発生した後ではできません。そして、契約者と被保険者が違う場合、被保険者の同意が必要となります。 ※保険法第45条この被保険者の同意は、契約時にも必須となっています。だって、勝手に保険に加入させられてたり、受取人を変更されてたりって、むちゃくちゃヤバいじゃないですか。そんな犯罪に使われそうな状況にならない様に決まりがあるんですね。また、保険金受取人は2名以上を指定する事も可能です。その際、受取割合も決めておく必要があります。 さて、今回は生命保険金の受取人変更についてお話しました。変更の時期が決まっていたり、契約形態により被保険者の同意が必要なんですね。ちなみに、受取人変更は、遺言書でも可能です。その際、証券番号・契約締結日・保険者(保険会社名)、保険契約者・被保険者、死亡保険金受取人を記載が必要となります。遺言書で生命保険の受取人変更の際は、確実に有効な遺言書にする為、公正証書遺言をお勧めします。
2025.01.25
コメント(0)
-

名義預金って何?相続で困る?
皆さん、名義預金って聞いた事ありませんでしょうか?相続の際、問題になったりする場合もあります。今回は、この名義預金について簡単にお話したいと思います。 まず言葉の整理から、「名義預金」とは、銀行口座などの名義と実際のお金の所有者が違う預金の事を言います。例えば、親が子の名義で銀行口座を開いて、親のお金を子の名義として預金したり、専業主婦(夫)が配偶者の稼いだお金を自分の名義の口座に預金したりって場合が該当します。では、なぜこれが相続の際問題になったりするのでしょうか?それは、実際のお金の所有者が亡くなった場合、名義は他の人でも、その財産は亡くなった人のものとして、相続税の課税対象となるからです。ですので、相続税の計算の際、名義預金分も含めて計算しないといけません。それを含めて相続額が、3000万円+(法定相続人×600万円)の基礎控除を超えなければ、相続税は発生しません。控除額ギリギリ相続の際は、特に注意が必要です。 さて、今回は「名義預金」についてお話しました。実際のお金の所有者と名義が異なると名義預金として相続税の課税対象となります。名義預金は申告漏れが多い為、しばしば税務調査の対象となったりします。気を付けたいですね。ちなみに、銀行口座のみならず、証券会社の証券口座=株や投資信託も、名義の本人が出資&管理をしていないと、「名義預金」となり、相続税の課税対象となります。お子さんや配偶者の預金や株式などを管理されている場合、名義預金とならない様に、実際に自分で管理させたり、暦年贈与(年110万円まで非課税)の制度を使うなりで、相続対策を早めに行う事をお勧めします。
2025.01.19
コメント(0)
-

みなし相続財産って何?
皆さん、「みなし相続財産」って聞いた事ありますでしょうか?相続は日常的に起こるものではないので、分からない事もたくさんありますよね。今回は、みなし相続財産について簡単にお話したいと思います。 「みなし相続財産」とは、本来の相続財産じゃないけど、相続によって財産が移るものを指します。①死亡保険金・生命保険金②死亡退職金③被相続人死亡前3年以内に受けた贈与などがあります。まず、①死亡保険金や生命保険金の保険料を被相続人(亡くなった方)が負担していた場合、みなし相続財産として相続税が課税されます。次に、②死亡退職金ですが、これは本来被相続人が受取るはずだった退職金が、遺族に対して支払われる場合に相続税が課税されます。ただし、①死亡保険金・生命保険、②死亡退職金ともに、その金額が、500万円×法定相続人数以内であれば非課税となります。最後に③被相続人死亡前3年以内に受けた贈与は、原則として贈与された金額を相続財産金額に加算して相続税の計算をします。なので、年間110万円以下の非課税枠で贈与をしていても、3年前~死亡時までに贈与を受けた分は相続税の計算に含まれます。 さて、今回はみなし相続財産についてお話しました。死亡保険金や退職金、そして3年以内に受けた贈与は、みなし相続財産として相続税の対象になるんですね。ちなみに、法改正により令和6年1月1日以降にされた贈与は、7年間相続税の課税対象となります。つまり、相続税課税対象が、3年→7年に延長されたんですね~。実質増税です。こういうステルス増税、多いですねぇ~。
2025.01.18
コメント(0)
-

戸籍法改正?フリガナが付くと?
皆さん、戸籍ってじっくり見られた事ございますでしょうか?日常生活では、そんなにガッツリ見る事はありませんよね?今回は、今年5月から施行される改正戸籍法について簡単にお話したいと思います。 令和7年5月26日に施行される改正戸籍法では、全国民の戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになります。「え、今までは振り仮名なかったと?」って思われる方もおられるかもしれません。そうなんです。見て頂けると分かりますが、現在の戸籍には振り仮名はありません。例えば、「山崎」は「やまざき」なのか「やまさき」なのか漢字だけだと分かんないですよね。また、「熊谷」も「くまたに」、「くまや」、「くまがや」など複数読み方があり、分かりません。そうすると、行政サービスの際、この氏名の読み方で本人確認を行う事は困難です。そこで、法改正を行い、全戸籍の氏名に振り仮名を記載する様になったのです。 さて、今回は今年施行される改正戸籍法についてお話しました。これからのデジタル社会に対応すべく、各種システムの検索や管理等の正確性・効率化の為、氏名に振り仮名を記載する様になるんですね。ちなみに今年令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、皆さんの現住所へ「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名」を郵便にて通知されます。この通知書にご自身の正しい振り仮名が記載されているかご確認ください。もし間違っていた場合、必ず令和8年5月25日までに、市区町村に正しい振り仮名の届け出をしてください。翌日の令和8年5月26日より、戸籍に振り仮名が記載されます。
2025.01.13
コメント(0)
-

被相続人の確定申告、いると?
相続の際、亡くなった方の確定申告が必要って聞いた事ありませんでしょうか?年金等含めて所得があった場合、どうなんだろうって思っちゃいますよね。今回は、亡くなった方(被相続人)の確定申告について簡単にお話したいと思います。 被相続人の確定申告は、準確定申告と言い、必要なケースと不要なケースがあります。公的年金の収入が400万以下で、それ以外の収入が20万円未満ならば準確定申告は不要です。また、年収2000万円以下の給与所得者や相続放棄を選択した場合も不要となります。なので、それ以外の方は準確定申告をしなければなりません。しかもこの準確定申告、申告期限は4ヶ月と短いです。相続でバタバタしている中、亡くなった方の所得状況を把握して申告しなければならないので、結構大変です。期限を過ぎたり、思わぬ収入(生命保険解約金等)を見逃して、後に延滞税や過少申告加算税などを課される事もあります。気を付けましょう。 さて、今回は、準確定申告についてお話しました。相続で忙しい中、4ヶ月以内に準確定申告をしなければならないって大変ですよね。被相続人の状況を確認して、必要であれば専門家(税理士)に頼る事もありですね。ちなみに、準確定申告不要な方も医療費控除等の各種控除の適用で払い過ぎた所得税の還付を受ける場合には準確定申告をするって選択もあります。
2025.01.12
コメント(0)
-
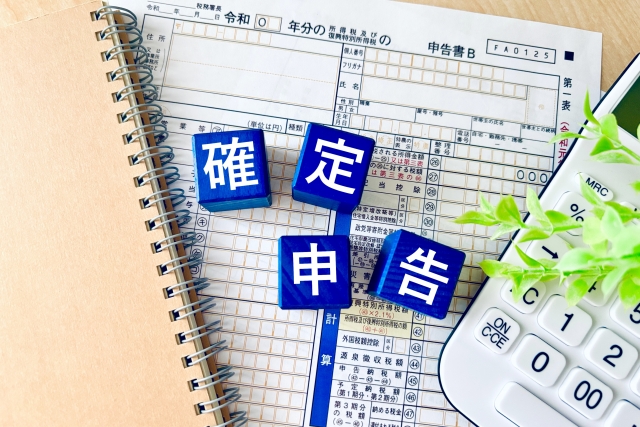
遺産相続したら確定申告必要?
皆さん、遺産を相続した場合に自身の確定申告ってどうなるのかご存知でしょうか?今回は、遺産相続したら確定申告が必要か?ってお話を簡単にしたいと思います。 原則として、遺産を相続しても確定申告は不要です。なぜなら、課税対象が違うからです。そもそも遺産相続は、相続税として、被相続人の財産を取得した時に課されますよね。確定申告は、所得税として、給料や事業所得等に課される税金です。相続財産取得は、相続税の対象となる為、所得税として二重に課税はされません。ただ、遺産相続でも確定申告が必要となってくる場合があります。それは、相続した遺産が、賃貸物件の不動産で賃料を得たり、相続した物を売却したりしたケースでは、所得税の申告が必要です。その場合、通常の確定申告同様、翌年の2月16日~3月15日の間に申告手続きを行います。 さて、今回は遺産相続の際の確定申告についてお話しました。基本、遺産を相続しただけでは確定申告不要(所得ではない為)ですが、賃貸物件などの利益や物を売った場合には確定申告が必要な事もあるんですね。ちなみに、受け取った死亡保険金も、その保険料を受取人本人が払っていた場合は所得税(一時所得)となり、確定申告が必要となります。保険料を払っていたのが被相続人本人の場合は相続税。保険料を払っていた人、受取人、被相続人が全て別人であれば、贈与税が課されます。
2025.01.11
コメント(0)
-
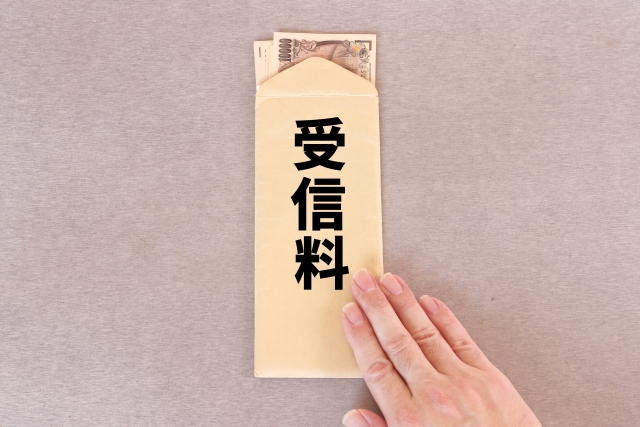
NHK受信料、払わないといかん?
皆さん、NHK見られていますでしょうか?前回、放送法改正によりスマホやPCでも受信契約を結べるって記事を書きました。今回は、そもそもNHKに受信料払わないといけない?ってお話をしたいと思います。 放送法第64条に、NHK番組を受信できる機器を持ってる場合、NHKと受信契約を結ばなければならないと書いています。つまり、義務です。ただし、罰則はありません。よって、警察に捕まるとかって事はありません。そして、受信契約を結んだ場合、受信料を払わなければなりません。これは、放送法を根拠にした施行規則(総務省令)に定められています。つまり、義務です。ただし、こちらも罰則はありません。「な~んだ、罰則ないなら払わんでよかね~」とはなりません。確かに刑事罰はないので警察は動きませんが、民亊でNHKから裁判を起こされた場合、「支払督促」が裁判所から届く事があります。まぁ裁判を起こされるのは超稀(約0.006%)ですが。その場合、最終的にNHKから強制執行を申立てられ、財産が差押えられる事もあります。 さて、今回は、NHKの受信料についてお話しました。刑事罰はないけど、法律に規定があるので、民亊で裁判を起こされるリスクは(超低いですが)あります。ちなみに、NHK受信契約は1世帯につき1契約でOKです。が、単身赴任や別荘などでは個別に契約が必要です。その際は、家族割引や学生での免除規定もあります。
2025.01.05
コメント(0)
-
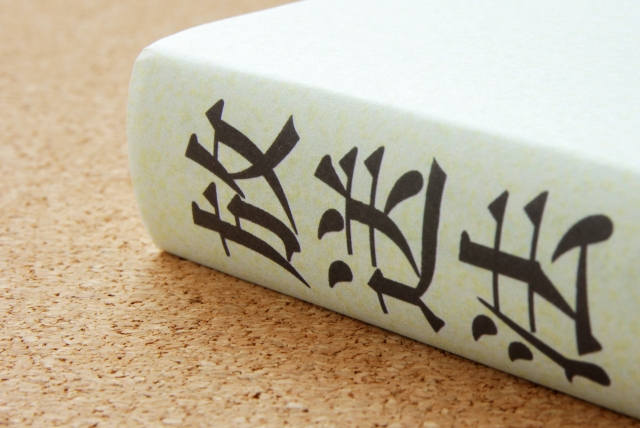
放送法改正?スマホ持ってるだけでNHK受信契約?
皆さん、2024年5月に改正放送法が成立したのをご存知でしょうか?「スマホを持っているだけでNHK受信契約必要?」など疑問を持たれる方もおられると思います。今回は、この改正放送法について簡単にお話したいと思います。 この法改正の要点は、NHKがネット配信業務を必須化する事です。これに伴い、ネットでNHK配信番組を受信する場合、通常の地上波同様額の受信契約を締結しなければなりません。具体的には、2025年10月より、テレビを持たない人でもスマホやPCのみで受信契約が結べる様になります。最近テレビ(地上波)って見る人少なくなってきてますよね。私も全くではないですが、かなり地上波は見なくなりました。(TVついててもYou Tubeが流れてますw)ただ、今回の法改正、スマホを持っているだけって事で受信契約する必要はありません。スマホやPCで、NHKの番組を受信できるアプリやサイトから、「同意して利用する」ってボタンを押さないと受信契約の対象とはなりません。この同意後、アカウント登録や受信契約を結びます。 さて、今回は、今年10月から施行される改正放送法についてお話しました。NHKのネット配信が必須業務となり、テレビを持たない人でもスマホやPCがあれば、受信契約を結べる様になるって事ですね。ちなみに、この受信契約、一度結ぶと解約は困難です。解約するには、スマホを持たない等、NHK視聴できる端末を持っていない証明をする必要があります。契約をする際は、慎重に検討した方が良いと思います。なお、現在テレビの受信契約を結んでいる人は、新たにネット配信で追加費用等は発生しない事になっています。
2025.01.04
コメント(0)
-
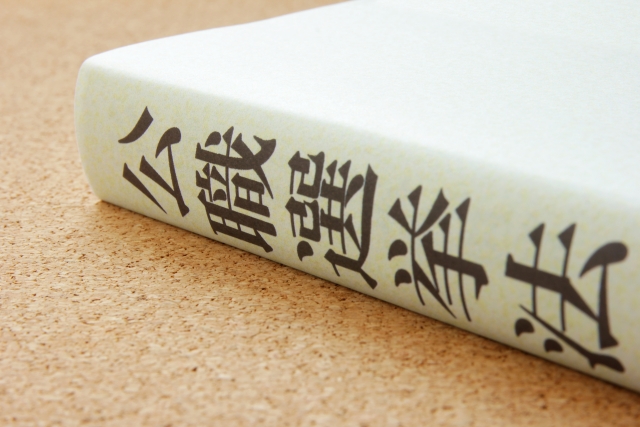
選挙違反、どんな罰則があると?
前回は、どんな選挙違反があるのかって記事を書きました。今回は、じゃあ選挙違反をしたらどんな罰則があるのか?について簡単にお話したいと思います。 候補者、その関係者、はたまた投票を行う有権者であれ、選挙違反をすると罰則があります。もちろんその違反によって罰則は異なります。具体的には、最も多い「買収及び利害誘導罪」(公職選挙法台221条)だと、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金ですが、候補者本人の場合、4年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が科されます。また、「詐偽投票罪」(公職選挙法第237条)では、選挙人ではない人が投票した場合、1年以下の禁錮または30万円以下の罰金ですし、他人になりすまして投票したり、投票しようとした場合、2年以下の禁錮または30万円以下の罰金となります。例えば、病気で選挙に行けないからと他人が投票した場合、1年もしくは2年以内の禁錮刑に処される可能性があります。 さて今回は、選挙違反をしたらどんな罰則があるのかについてお話しました。選挙違反の罰則は結構厳しいですよね。ちなみにそれに加え、一定期間、選挙権の停止などの措置も取られます。捜査機関は公職選挙法違反に対してかなり厳しい姿勢で臨んでいます。万が一選挙違反を指摘され、立件された場合、早急に弁護士に相談する事をお勧めします。まぁ、そうならない様にルールを知っておく事が重要ですね。
2025.01.03
コメント(0)
-
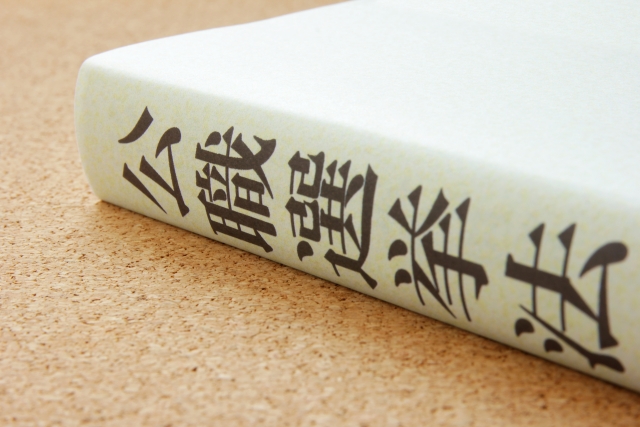
どんな事が選挙違反?
よくニュースで公職選挙法違反って言って、候補者や選挙事務所の関係者なんかが話題になったりしていますよね?今回は、どんな事をしたら選挙違反になるのか?について簡単にお話したいと思います。 まずは、買収罪。これは言わずと知れた「買収」ですね。金銭・物品、それに接待等による票の獲得や誘導があたります。買収に応じたり、促した場合も処罰の対象です。次に利益誘導罪。これは、一定の有権者等に対し、その有権者等またはその関係ある団体に対する寄付などを通じて投票を誘導した際に成立します。この利害誘導に応じたり、促した場合も処罰の対象です。次に選挙妨害罪。これは、候補者や有権者などに対する暴行・脅迫や、演説の妨害・ポスター等の破棄・候補者の情報の虚偽公表などがあたります。最近はSNSなどで簡単に個人が情報発信できますので、虚偽公表(知らずして拡散)には注意が必要ですね。 さて、今回は、どんな事をしたら選挙違反になるのかについて簡単にお話しました。候補者と関係者はもちろん、一般の有権者もSNSなどの使い方によっては選挙違反となる危険性はありますよね。ちなみに、投票所で本人確認の際、虚偽の宣言をしたり、本人になりすまして投票したりすると、当然処罰されます。投票は我々と子供・孫の未来を決める行為です。ちゃんと考えて、正しく行動しましょう。
2025.01.02
コメント(0)
-

2025元日です
新しい年が始まりました。本年もよろしくお願い致します。 無茶苦茶良い天気だったので、早速走り初めです。いつものジョグコースを気持ち良く走れました。香椎宮の末社・御島(みしま)神社の鳥居もキレイに映えてました。そして、今年も毎年恒例の洋風おせちを頂きます。美味いんですよね~♪今年1年が、皆様にとって良き年となりますように!
2025.01.01
コメント(0)
全12件 (12件中 1-12件目)
1









