2025年02月の記事
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-

確定申告、必要な物とは?
皆さん、絶賛確定申告期間中ですね。医療費控除やふるさと納税などで還付金が発生する方はやっとかないと損ですよね。今回は、確定申告時に必要な物について簡単にお話したいと思います。 現在の確定申告は、スマホで全て出来ます。税務署に出向く事もなく、郵送する事もなく、電子申請で完結します。私も一昨日、電子申請で確定申告完了しました。国税庁の確定申告書等作成コーナーで、質問に答える形で入力すればOKなので思ったより簡単にできます。では必要な物はなんでしょうか? ・スマホもしくはPC(PCの場合、カードリーダーか事前にID申請が必要) ・マイナンバーカード ・給与所得の源泉徴収票 ・医療費領収書(医療費控除の場合) ・寄付金受納証明書(ふるさと納税の場合) ・その他控除に対する証明書(該当者)こんな感じの物が必要ですね。 さて、今回は確定申告必要な物は?ってなお話をしました。ちなみに現在は、マイナポータルと連携させる事で、控除証明書当のデータを一括で取得し、確定申告書の該当項目へ自動入力する機能が使えるので、無茶苦茶楽です。それにより、収入関係では、給与や年金の源泉徴収票、株式の特定口座年間取引報告書。控除関係では、医療費・ふるさと納税・社会保険料・生命保険・iDeCo・住宅ローンなどが自動入力されます。便利な世になりましたねぇ。
2025.02.24
コメント(0)
-

天皇誕生日、天皇って何?
皆さん、本日は天皇誕生日で祝日ですね。天皇って何?って考えた事ありませんでしょうか?今回は、天皇について簡単にお話したいと思います。 天皇に関して、日本国憲法第一章(第一条~第八条)に記載があります。天皇は国民主権に基づき、日本国の象徴であり国民統合の象徴って事。皇位は世襲で、天皇の国事行為は内閣の助言と承認を必要とし、内閣が責任を負うって事。天皇は憲法で定められた国事行為のみを行い、国政に関する権能は持たないって事。天皇は内閣総理大臣と最高裁判所長官を任命するって事。皇室の財産の出入り(譲渡・譲受・賜与)は、国会の議決が必要ってな事が書かれています。なので、天皇は勝手に何かをしたり、国政にも関与できません。また、公職選挙法では、戸籍法の適用を受けない人の選挙権・被選挙権が停止されている為、戸籍を持たない天皇及び皇族は選挙権・被選挙権がありません。あとご存知の通り、日本は史上最も長い歴史を持つ国家で、皇室も同じく長い歴史を誇ります。現在の天皇は、第126代目の天皇です。 さて、本日は天皇誕生日という事で天皇についてお話しました。生まれた時から自由が制限され、思う通りにできないって何かかわいそうな気もしますが、長い歴史を継ぐ者として自覚されておられるやもしれませんね。ちなみに、現在世界には27の君主国があり、王(King)はたくさんいますが、皇帝(Emperor)は天皇陛下ただ一人です。国際社会において、皇帝である天皇は王よりも慣習的・儀礼的に格上とみなされます。だから天皇が訪問されると海外でも敬意を持って接するんですね。
2025.02.23
コメント(0)
-

贈与契約書の注意点
皆さん贈与契約書作っていますでしょうか?贈与した場合は贈与契約書作った方が良いよーって何度か言ってきました。今回は、贈与契約書の注意点について簡単にお話したいと思います。 贈与契約書を作成する際、①誰が、②誰に、③いつ、④何を、⑤どうやって、を記載しないとダメです。この5つの記載が無いと贈与契約書として認められません。なので、作成時には必ず記載しましょう。また、何年分かとまとめて契約書に記載すると、「定期贈与」とみなされ、全額その年に贈与された事となり、110万円を超える金額に贈与税が課されます。面倒でも贈与都度作成しましょう。あと、「昨年や一昨年の分も今年作成しよう」なんて思わないでください。それは、back date(バックデート)と言い、文書偽装行為にあたります。その行為自体に罰則はありませんが、税務署がback dateと判断すれば、重加算税の対象になる可能性もあるので、絶対にやめましょう。契約書を作ってなかった場合は、「過去の送金は、生前贈与であったことを確認する」覚書を交わしておくのも一つの手です。 さて今回は、贈与契約書の注意点についてお話しました。作成する際には、記載する事項、やっちゃダメな事があるんですねぇ。ちなみに、金銭の贈与であれば贈与契約書に収入印紙を貼る必要はありませんが、不動産の贈与にはその価値に関わらず一律200円の収入印紙が必要になります。収入印紙の柄は不定期で微妙に変えられている為、文書作成時には存在しない収入印紙が貼られていると、back dateを強く疑われます。デザインそのものだけでなく、透かしの糸の色だけが変えられる場合もあるみたいです。まじめに生きましょう。
2025.02.22
コメント(0)
-

確定申告どんな人がすると?
皆さん大好き確定申告(ぉぃ。令和6年度分が、明日2月17日(月)から始まりますね。3月17日(月)までの1ヶ月間に申告&納税をしなければなりません。今回は、「確定申告しなければならない人」について簡単にお話したいと思います。 確定申告とは、毎年1月1日~12月31日の所得額・所得の状況に応じてかかる「所得税」を計算して確定させ、税務署に申告する手続きです。この所得額とは、収入額から必要経費を差引いた額の事です。では確定申告が必要な人はどんな人でしょうか?通常、サラリーマン(会社員)は確定申告不要です。ただ、以下の人は確定申告が必要となります。 ・年収が2,000万円を超えている ・副業の所得が20万円を超えている ・不動産所得があったり、不動産の売却益がある ・株式投資などを「特定口座」ではなく「一般口座」で行っていて、源泉徴収されていない人の中で、年間利益が20万円を超えている ・一時所得がある(利益が50万円を超える場合) ・退職所得があり「退職所得の受給に関する申告書」未提出(通常出してます)それと当然、個人事業主の方は確定申告が必要ですね。 さて今回は、確定申告が必要な人についてお話しました。ちなみに、確定申告が義務づけられていない人でも以下の人は確定申告した方が良いです。 ・年の途中で退職した(年末調整していない) ・医療費が10万円を超えている ・ふるさと納税した(ワンストップ特例制度以外の方) ・今年住宅ローンを組んだこれに当てはまる人は、還付を受けられます。お得なので確定申告しましょう。
2025.02.16
コメント(0)
-
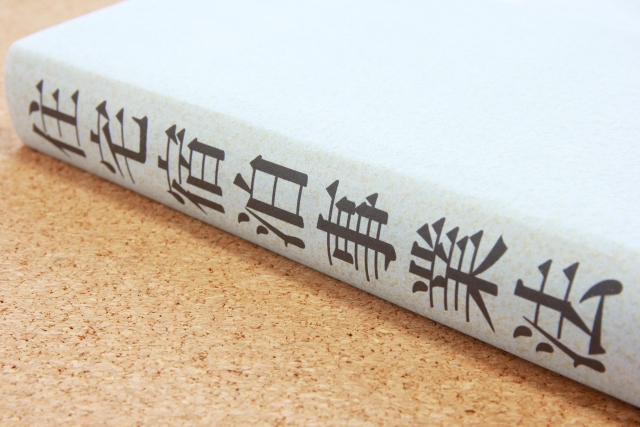
民泊⁈許認可必要?
皆さん民泊ってご存知ですか?昨今インバウンドの影響で住宅を宿泊営業として利用する方も増えています。今回は、この「民泊」について簡単にお話したいと思います。 当然ですが、民泊として住宅を使用する際、勝手にやっちゃダメです。住宅を民泊として営業する人を「住宅宿泊事業者」と言い、都道府県知事に届出を行います。でも住宅ならどんな家でもいいって訳ではありません。設備要件として、「台所・浴室・トイレ・洗面設備」が無いとダメです。また、居住要件として、「人が生活している家屋」「入居者の募集が行われている家屋」「随時誰かが居住している家屋」のいずれかに該当しないとダメです。そして、この民泊、人を宿泊させる日数が年間180日を超えてはダメです。なので、「180日じゃ採算合わないよ!」って人は、「旅館業法の簡易宿所営業の許可」が必要となります。この場合、「届出」ではなく「許可」ですので、ハードルが少し上がります。 さて、今回は民泊についてお話しました。住宅宿泊事業法(民泊新法)の制定により、簡単に住宅を使用したビジネスができる様になったんですね。ちなみに民泊の仲介業を行う人を「住宅宿泊仲介業者」と言い、観光庁長官に登録を行います。また、民泊の管理を委託する場合、その委託業者を「住宅宿泊管理業者」と言い、国土交通大臣に登録しなければなりません。変な業者が暗躍してはヤバいですからねぇ~。
2025.02.15
コメント(0)
-

建国記念の日?どんな日?
皆さん、本日2月11日は「建国記念の日」で多くの人がお休みですよね。今回は、この「建国記念の日」について簡単にお話したいと思います。 実は2月11日、「建国記念日」ではありません。「建国記念の日」です。「建国記念」と「日」の間に「の」が入るんですね。カレンダーなど見ても「建国記念の日」と書かれています。そもそも「建国記念の日」が2月11日なのは、初代天皇とされる「神武天皇」の即位日の旧暦紀元前660年1月1日を現在の新暦に換算した日付だからです。通常、諸外国では、「建国記念日」や「独立記念日」などとしてお祝いする事が多いです。これは、建国(独立)した日が明確だからですね。日本はご存知の通り、現存する世界最古の国家です。あまりに古いので明確にこの日に国が建国されたって証明できないんですね~。なので、「記念日」ではなく「記念の日」なんです。 さて、今回は、本日2月11日「建国記念の日」についてお話しました。もともと明治時代より神武天皇即位日を「紀元節」として祝っていましたが、戦後「天皇中心に日本人の団結力が高まる」というGHQの懸念から「紀元節」は廃止されました。その後ようやく昭和41年「建国記念の日」として祝日に追加されたんですね。ちなみに、2月11日「建国記念の日」には「建国をしのび、国を愛する心を養う」として定められた国民の祝日です。今日は日本について考えてみるってのも良いかもしれません。しかし日本の過去の偉人が現状を観たらどう思いますかね・・・。皆さん、選挙には行きましょう!
2025.02.11
コメント(0)
-
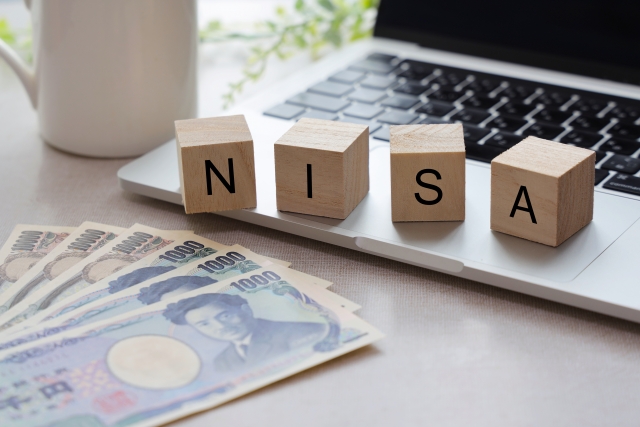
NISA口座なのに課税?
皆さん、NISAやってますでしょうか?1,800万円までの非課税枠がある新NISA、公的年金だけでは不安でしょうがないので、資産運用は今や必須ですね。けど、非課税が売りのNISAですが、配当金については課税される可能性があります。今回は、NISAで課税されるかもしれない点について簡単にお話したいと思います。 ご存知の通り、NISAは売り買いで出た利益や配当金に税金はかかりません。通常は20.315%も税金を納めなきゃいけないですよね。ただ、配当金については注意が必要です。受け取り方によっては税金がかかっちゃうんです。配当金の受取方式は次の4つがあります。 ①株式数比例配分方式:証券口座で配当金受取 ②登録配当金受領口座方式:銀行口座で全銘柄の配当金一括受取 ③個別銘柄方式:銘柄ごとに指定した金融機関で配当金受取 ④配当金領収証方式:配当金領収証郵送し、指定した金融機関で配当金受取このうち、NISAで配当金が非課税になるのは①の株式数比例配分方式のみです。他の方式では課税されちゃいます。 さて、今回はNISAの配当金についてお話しました。せっかく非課税の制度があるのに、知らずに課税されてたらもったいないですよね。ちなみに、当該株式の権利確定時までに「株式数比例配分方式」になっている必要があります。ちゃんと確認しましょう。
2025.02.09
コメント(0)
-
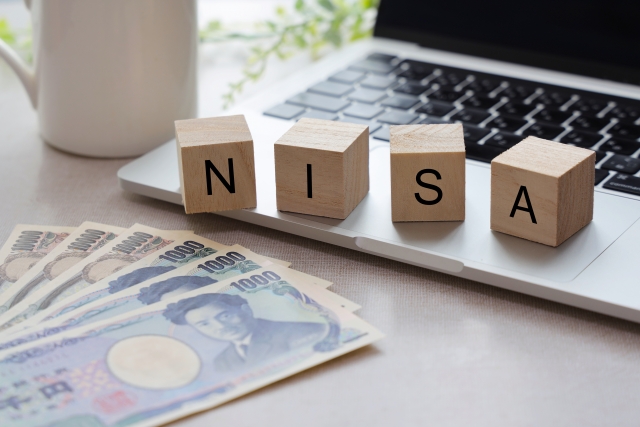
今持ってる株をNISA口座に移管できる?
前回、特定口座について記事を書きました。「その特定口座で株買ったけど、やっぱ非課税のNISAがよかばい」って場合、どうなるのでしょう?今回は、特定口座の金融商品をNISA口座に移管できるのか?について簡単にお話したいと思います。 結論から言うと、「できません」。ですので、特定口座にある資産をNISA口座に移したい場合、一旦売却してNISA口座で購入しなおす必要があります。売却と購入を同時に行う事で、同じ金額で取引出来、実質移管した事になります。ただ、その行為が本当にお得かどうかは状況により異なります。なぜなら、現在特定口座で保有している資産に含み益がある(買った時より価値が上昇している)場合、売却すると20.315%の所得税が発生するからです。例えば、リーマンショックの時に100万円で買った株が、現在500万円になってるってケースだと、400万円の利益に対して20.315%の所得税なので、81万2600円納税義務が生じます。その株が今後あまり上昇しなかった場合、特定口座で持ってた方が良かった、なんて事もあります。逆に、移管しようとする資産の運用損益が少ない(買った時と価値があまり変わらない)場合、損益確定の影響は少ないですし、将来の株価上昇による利益&配当金も非課税になる為、速攻NISAにした方が良いかもしれません。 さて、今回は、特定口座からNISA口座に移管できるか?についてお話しました。移管はできんけど、特定口座で売却&NISA口座で購入する事で実質移管した事になります。でも、状況によって移した方が良い場合・そのままの方が良い場合があるって事ですね。ちなみに個人的意見としては、運用期間が長いなら少々含み損益があろうとも(大きくなければ)、NISAへと変更しますかね~。世の中物価は上昇していきますし、それに応じて株価も上昇します(株はインフレに強い資産です)。なので将来的にみて、非課税って大きいです。
2025.02.08
コメント(0)
-

証券会社の特定口座?一般口座と何が違うと?
皆さん、株や投資信託されていますでしょうか?通常預金だと微々たる金利だから、物価上昇で資産が目減りしちゃいますよね。最近はNISAで投資を始める方も増えてきています。今回は、証券会社で開設する口座について簡単にお話したいと思います。 通常、証券会社に口座開設する際、「一般口座」と「特定口座」を選択します。一般口座は、名義人本人が、ご自身で確定申告の書類を作成しなければなりません。これに対し「特定口座」は、証券会社等が年間取引報告書を作成してくれます。そして、この「特定口座」は「源泉徴収口座」と「簡易申告口座」の2つに分かれます。「源泉徴収口座」は、その名の通り、特定口座の中で管理している投資商品の配当金や分配金等・そして売買した際の譲渡損益を都度、証券会社が計算して、所得税・住民税が源泉徴収または還付されます。よって、基本的に確定申告が不要です。楽ですねぇ。対して「簡易申告口座」は源泉徴収無しの特定口座です。ですので、損益が発生した場合、利用者自身で確定申告する必要があります。ただ、証券会社が1年間の損益を計算して「特定口座年間取引報告書」を発行してくれるので、確定申告の手続きが簡易になります。 さて、今回は証券会社の特定口座についてお話しました。特定口座には、確定申告不要の「源泉徴収口座」と自身で確定申告する「簡易申告口座」があるんですね。ちなみに、会社員等で給与以外の所得(配当や譲渡利益)が20万円以下の場合、確定申告不要です。なので、「源泉徴収口座」にすると、納税しなくて良い税金を源泉徴収されちゃいます。ご自身の状況に合わせて選択ください。NISAなら非課税ですけどね~。
2025.02.02
コメント(0)
-
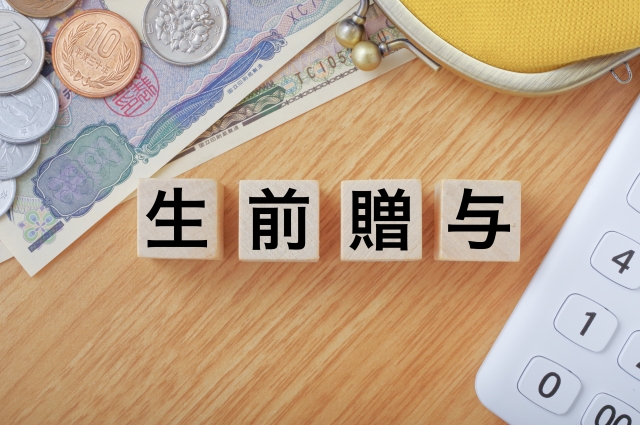
定期贈与って何?危険?
皆さん、定期贈与ってご存知でしょうか?親から子、祖父母から孫など贈与を行う際、気を付けておきたいのが定期贈与になっていないか?です。今回は、この定期贈与について簡単にお話したいと思います。 ご存知の通り、年間110万円までならば贈与税がかかりません。じゃあ「1000万円を10年に分けて贈与するね」って1年に100万円ずつ贈与すれば非課税で贈与できるね。これが定期贈与です。定期贈与とみなされれば、贈与税の課税対象となります。これは、先の例では、「1000万円取得の権利」を贈与されたものとする為です。だから、基礎控除110万円を除く890万円に対して贈与税が課されるって訳です。なので、そうならない為に以下の対策が必要となります。①毎年、贈与契約書を作成する②毎年決まった時期・金額を贈与しない③銀行振込で贈与するいずれも定期贈与ではない事を客観的に示す為に行うものです。贈与契約書に関しては要件があるので、心配ならば専門家に相談しましょう。そして、贈与する人・される人が自筆で署名し、2通作成&お互い保管します。 さて今回は、定期贈与についてお話しました。110万円まで非課税の制度を使い贈与する場合、定期贈与とみなされない様に気を付けたいですね。ちなみに、計画的ではないにしろ、例えば誕生日などに毎年一定額を贈与すると定期贈与と税務署に判断される危険性はあります。なので、上記②の様に時期・金額をズラしたり、あとは111万円贈与して、相続税1,000円を申告・納付する事で贈与税を確定させるって手もあります。
2025.02.01
コメント(0)
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-
-

- みんなのレビュー
- 内勤です。☁️(19度)秋模様🍁
- (2025-10-13 16:37:45)
-
-
-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…
- 【楽天お買い物マラソン】「欲しいも…
- (2025-10-13 22:00:05)
-
-
-

- あなたのアバター自慢して!♪
- バーチャル渋谷おでかけハロウィン
- (2022-11-01 19:50:06)
-






