2025年07月の記事
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-

自分で作る遺言書、何に注意する?
遺言書、作成するのにルールがあるってご存知でしょうか?法的要件を満たさなければ、遺言書は無効となってしまいます。今回は、自分で作る遺言書(自筆証書遺言)の注意点について簡単にお話したいと思います。 自筆証書遺言は、全文を自身の手で書く事が法的な有効性の大前提です。その為、パソコンやワープロで作成されたものは、正式な遺言書とは法的に認められず、無効となります。その他、以下の注意点があります。 ・作成日は、何年、何月、何日と正確に記載 ・署名は必ず実名、フルネームで記載 ・必ず押印(認印でも可、母印は有効の判例があるが避けた方が無難) ・相続人の名前だけでなく、続柄や住所などを併記した方が確実この様に記述の仕方などに色々な決まりがあります。書き方が分からない場合や、無効になるか不安な場合は専門家に相談しましょう。 さて、今回は自分で作る遺言書(自筆証書遺言)についてお話しました。「自筆」証書と言われる通り、全て自分で文字を書かないと無効になるんですね~。※2025年現在ちなみに、自筆証書遺言書で、唯一パソコンやワープロでの作成が認められているものに「財産目録」があります。財産が多岐に渡る場合など、自筆すると大変ですからね。ただし、その「財産目録」の用紙には、署名・押印が必要となります。
2025.07.27
コメント(0)
-

遺言書作成前の準備?どんなんすると?
遺言書作成って大事ですよね。でも何から取り掛かれば良いか分かんないですよね。そこで今回は、遺言書作成前に準備する事について簡単にお話したいと思います。 遺言書で『誰に何を遺すか』を明確にするためには、まずご自身がどのような財産を持っているのか、その全体像を明らかにする必要があります。具体的には、土地や建物といった不動産、預貯金、株式や投資信託などの有価証券という様なプラスの財産はもちろんのこと、ローンや借入金といったマイナスの財産も全てリストアップする必要があります。こうすることで、財産の全体像が明確になり、遺産の分配を具体的に検討できるようになりますし、相続人が後々困らないように、財産の把握漏れや予期せぬ負債の存在を防ぐことにも繋がります。また、財産のリストアップと並行して、法律で定められている相続人(法定相続人)が誰になるのかも正確に把握しておく事も重要です。状況により、配偶者、子、両親、兄弟姉妹などが該当します。法定相続人を特定することで、遺言がない場合に誰にどの程度の財産が渡るのかが分かります。その上で自身の意思を遺言にどう反映させるかを考えます。例えば、「特定の人に多く渡したい」とか、「法定相続人以外の人にも遺したい」などの希望がある場合、具体的に検討する基礎となります。(遺言書が無ければ、法定相続人全員での遺産分割協議となります)また、法定相続人には『遺留分』という最低限保障される権利がある場合があり、それを考慮した遺言内容にするためにも、まずは誰が法定相続人なのかを知ることが不可欠です。 さて、今回は遺言書作成前に準備しておくことについてお話しました。自身の財産について、何が、どのくらいあるのか?自身が亡くなった時、法定相続人は誰になるのか?分かっていないと的確な遺言書が作成できないって事になります。ちなみに今は書店などで「エンディングノート」が数百円くらいから売られています。その財産一覧などの項目でまとめると抜けもれなく自身の財産が把握できます。遺言書作成の前に「エンディングノート」を書いてみるのも良いかもですね。
2025.07.26
コメント(0)
-

次の国政選挙って、いつ?
昨日、参院選の投開票日でした。皆さん投票には行かれましたでしょうか?予想通り与党は過半数を維持できませんでした。これで衆議院に続き、参議院でも与党単独で法案を通す事ができなくなりました。ただ、そうは言っても、最大議席を有しているのは与党・自民党です。なぜなら、今回改選されたのは、参議院の半分124議席だけ(衆議院465議席、参議院248議席、計713議席)だからです。では、次の選挙っていつ?ってお話になると思います。今回は、次の大きな国政選挙がいつになるか?について簡単にお話したいと思います。 今回2025年7月20日に行われたのは参議院選挙です。参議院は任期6年ですが、半数が3年毎に改選されます。となると、次の参院選は、2028年7月となります。参議院は解散がない為、このスケジュールは動きません。しかし、衆議院は違います。衆議院は、昨年2024年10月27日に選挙が行われました。任期4年なので、任期満了による次の選挙は2028年10月26日までに行われます。その前に、首相が衆議院解散を決めれば、すぐにでも選挙が行われます。 さて、今回は、次の国政選挙はいつ?ってお話をしました。参議院は間違いなく、2028年7月まで選挙はありません。が、衆議院は解散による選挙が任期の2028年10月を待たずして行われる可能性があるんですね。ちなみに、参議院は半分ずつ3年毎に通常スケジュールで選挙を行う為、「通常選挙」と言い、衆議院は全員をいっぺんに選挙する為、「総選挙」と言います。
2025.07.21
コメント(0)
-

投票日当日、やっちゃダメな事あると?
本日2025年7月20日は、参議院議員通常選挙の投票日です。私も投票してきました。ところで、この投票日当日のNG行為があるってご存知でしょうか?今回は、選挙投票日当日のやっちゃいけない事について簡単にお話したいと思います。 選挙の公正を期すため、投票日当日には公職選挙法で禁止されている行為があります。選挙運動は投票日の前日までと定められており、投票日当日の選挙運動は全面的に禁止されています。違反した場合、1年以下の拘禁または30万円以下の罰金が科される可能性があり、選挙権や被選挙権が停止されることもあります。超厳しいですね。でも、「別に選挙運動とかしてないし」って方もおられると思います。が、ビラやポスターを配布したり、街頭演説を行う事だけが選挙運動ではありません。特定の候補者や政党への投票を呼び掛ける事(口頭もしくはSNS投稿)も該当します。なので、SNSに「〇〇候補に投票しよう」とか「比例は〇〇党へ」といった投稿したり、過去の選挙運動に関する投稿を再投稿(リツイートやシェア)する事も違反となる可能性があります。また、自身が投票した候補者名や政党名を書いた投票用紙の写真をSNSにUPする行為も、特定の候補者や政党への投票呼びかけとみなされる可能性があるため注意が必要です。 さて、今回は投票日当日にやっちゃいけない事についてお話しました。投票日当日は、選挙運動がガチで禁止されています。そして選挙運動とは、SNS投稿なんかも含まれますので、知らずに法律違反をする事が無い様、知っておく事が重要ですね。ちなみに、「選挙に行こう」とか「投票に行って来たばい」といった、特定の候補者や政党への投票を依頼しない、投票参加を呼びかける投稿は問題ありません。
2025.07.20
コメント(0)
-

投票率低いとどうなる?
皆さん、明日は、いよいよ、参議院議員選挙の投票日です。三連休の真ん中に設定された投票日、思惑に抗い投票しましょう。そういう策略で投票率が低いとどうなるのでしょう?今回は、投票率が低いとどうなるか?について簡単にお話したいと思います。 投票率が低いということは、国民の一部の意見しか政治に反映されないことを意味します。これは、投票に行く人が多い特定の世代や集団の意見が重視され、その結果、その層に有利な政策ばかりが実現しやすくなります。例えば、高齢者の投票率が高く、若者の投票率が低い場合、年金など高齢者向けの政策が手厚くなる一方で、子育て支援や教育といった若者向けの政策が後回しにされる可能性があります。→現在、これ。また、投票率が低いと、政治家は「どうせ投票に行かないだろう」と考え、国民全体の利益よりも特定の支持団体の利益を優先するようになります。→現在、これ。 さて、今回は、明日の参院選を前に「投票率が低いとどうなる?」についてお話しました。投票率の低下は、単に「政治への関心が薄い人が多い」という問題にとどまりません。それは、民意が適切に政治に反映されなくなり、特定の世代や集団に不利益が生じ、ひいては社会全体の活力が失われることにもつながりかねない重大な問題です。「投票したい政党がないっちゃね~」って場合も、投票する事が重要です。少しでも自身の考えに近い政党へ投票しましょう。一人ひとりが投票に行くことで、健全な民主主義社会を維持し、より良い未来を築く事につながるとです。
2025.07.19
コメント(0)
-
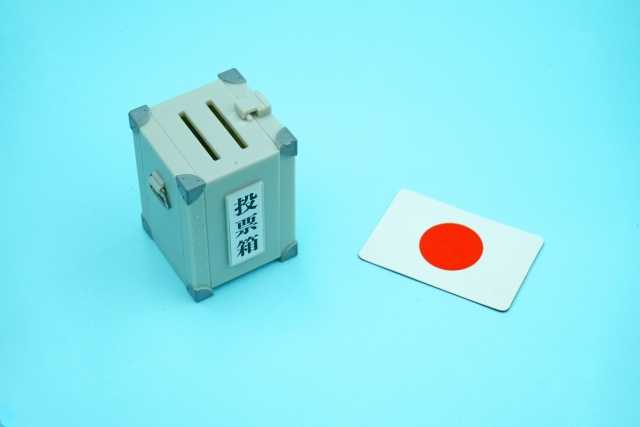
投票率?!低い原因は?
7月20日(日)いよいよ我々の将来を決める選挙が行われます。自身と子どもや孫など大切な人の生活に大きな影響を与える大事な選挙です。組織票を持つ与党が投票率を下げる為にわざわざ三連休の中日に設定した参院選。必ず投票に行きたいですよね。そんな投票率ですが、なぜ低いのでしょうか?今回は、選挙の投票率の低い原因について簡単にお話したいと思います。 日本の投票率が低い原因は、単一のものではなく、複数の要因が複雑に絡み合っていると思われます。まず個人の意識=政治への無関心(教育にも原因)や政治不信(生まれた時から不景気な若者など)があります。これは、戦後教育やマスコミの影響が大きいと言えます。次に、選択肢の不在・魅力の欠如=選挙戦では各党良い事しか言わない(差が分からない等)や、有権者を引きつける魅力的なリーダーの不在(マスコミの報道のしかたも問題)があったりもします。結局、若年層が選挙に行かない事で政治が「高齢者向け」となり子育て世代の施策も「やってます感」を出して終わりみたいな事になっちゃいます。これらの要因は独立している訳ではなく、相互に関連し合っています。政治不信→政治への無関心→「1票では何も変わらない」→投票に行かなくなる→投票率の高い高齢者向けに手厚い政治→更なる若者の投票離れ→政治不信みたいな負の連鎖がこれまでの流れかなと推察します。 さて、今回は投票率の低さについてお話しました。投票率の低迷は民主主義の基盤を揺るがす問題です。本来ならば、政治側から投票しやすい環境を整える必要があるはずです。・・・なのに三連休の中日って・・・ちなみに、今回の参院選、与党が過半数を割り込むと、衆議院に続き参議院でも与党が主導権を失い、現在の増税路線・国民所得軽視の政策が変わる可能性が高くなります。みなさん、選挙に行きましょう。
2025.07.13
コメント(0)
-

不在者投票?期日前投票?違いは?
来週末はいよいよ参議院議員選挙の投票日ですね。ところで、「不在者投票」とか「期日前投票」とかって聞いた事ありませんでしょうか?今回は、「不在者投票」と「期日前投票」の違いについて簡単にお話したいと思います。 選挙で投票日当日に投票所へ行けない場合に利用できる「期日前投票」と「不在者投票」。この二つの制度は似ていますが、対象となる人や投票方法などに違いがあります。まず「不在者投票」ですが、これは、選挙人名簿のある市区町村から離れた場所にいるなど、特別な事情がある人のための制度です。例えば、出張や旅行で他の市区町村に滞在している方は、事前に投票用紙を請求することで、滞在先の選挙管理委員会で投票できます。また、指定された病院や老人ホームに入院・入所中の方は、その施設内で投票することが可能です。次に「期日前投票」ですが、これは、投票日に用事があるほとんどの有権者が利用できる便利な制度です。投票日に仕事、旅行、レジャー、冠婚葬祭、地域の行事、病気、出産などで投票所へ行けないと見込まれる人が利用できます。手続きは、投票所入場券が届いていれば持参し、期日前投票所に備え付けの宣誓書に必要事項を記入して提出するだけです。投票期間は、選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までです。今回の参院選は、7月19日(土)までという事になります。 さて今回は、「不在者投票」と「期日前投票」についてお話しました。多くの人が簡単に利用できる「期日前投票」と、特別な事情がある人が手続きをして行う「不在者投票」、全く別の制度なんですね。ちなみに、選挙日には18歳になるものの、期日前投票の時点では17歳の方は、選挙権がまだないため期日前投票ができません。この場合、不在者投票として投票することになります。
2025.07.12
コメント(0)
-

なりすまし投票?どういう罰があると?
7月20日(日)いよいよ日本の将来を決める選挙が行われます。自身と子どもや孫など大事な人の生活に大きな影響を与える選挙です。組織票を持つ与党が投票率を下げる為にわざわざ三連休の中日に設定した参院選。必ず投票に行きたいですよね。そんな選挙ですが、もし他人になりすまして投票した場合、どの様な罪に問われるのでしょうか?今回は、「なりすまし投票」について簡単にお話したいと思います。 他人になりすまして投票する事は、日本の選挙制度の根幹をゆるがす重大な犯罪です。公職選挙法第237条の「詐偽投票罪」に該当し、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科されます。例えば、他人の「投票所入場券」を不正に入手して投票する事はもちろん、家族や知人などの名前をかたって投票する事などがあたります。また、「本人は足が悪くて投票所に行けないから・・・」と本人の同意があったとしても、代理で投票する事は認められず、罰則の対象となります。 さて、今回は、「なりすまし投票」についてお話しました。選挙は民主主義の根幹となる最も重要な制度です。将来の我々の命・生活・自由の為に正しく、自身の信念のもと投票しましょう。ちなみに、投票を偽造したり、投票数を増減させた場合、また買収・利益誘導により投票を依頼した場合、更に重い「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」が科されます。 ※公職選挙法第236条、第221条
2025.07.06
コメント(0)
-
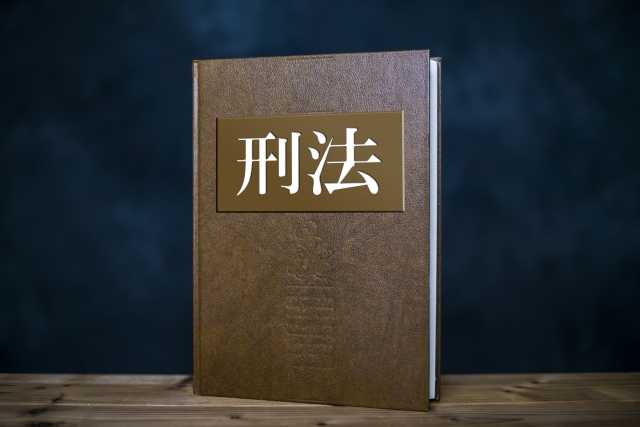
拘禁刑?懲役刑とどう違うと?
最近ニュースなんかで「拘禁刑」と言う言葉が増えてるのご存知でしょうか?今回は、拘禁刑について懲役刑などとどう違うのかについて簡単にお話したいと思います。 「拘禁刑」とは、従来の「懲役刑」と「禁錮刑」を一つにまとめた新しい刑罰です。これは、今年2025年6月1日より施行された改正刑法によるものです。従来の「懲役刑」では、刑務作業が義務となっていました。そして、従来の「禁錮刑」は、刑務作業の義務はありませんでした。その二つがガッチャンコしたので、「拘禁刑」は刑務作業が義務ではなくなったんですね。そもそも「懲役刑」での刑務作業は、犯した罪に対して罰として労働させる「懲罰」が目的の中心でした。今回の法改正により誕生した「拘禁刑」は、受刑者の「改善更生」と「社会復帰」が目的の中心となっています。そこで、刑務作業を義務とせず、個人の更生に必要な指導や教育を優先できるようになったんですね~。 さて、今回は、今年2025年6月1日より施行された改正刑法により「懲役刑+禁錮刑」が「拘禁刑」になったというお話をしました。「拘禁刑」は罰を与えることより、再犯を防ぐ為の教育や指導に重点を置いた、より柔軟な刑罰と言えます。ちなみに、なぜこの様な改正となったか?ですが、「画一的に刑務作業を科すだけでは、必ずしも再犯防止に繋がらないという課題があった」からなんですね~。「罰」を与えるのはいいけど、再犯を減らした方が社会にとってはプラスですからね。
2025.07.05
コメント(0)
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-
-

- 自分らしい生き方・お仕事
- 金星がいて座に移動
- (2025-11-30 09:00:06)
-
-
-

- 株式投資日記
- 金関連商品の口座残高は、1,324万円に…
- (2025-11-29 16:12:06)
-
-
-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- 「SONIC Tシャツ」 音速ロック==…
- (2025-11-30 00:42:20)
-






