2008年07月の記事
全18件 (18件中 1-18件目)
1
-
担当業務は誰が決めるべきか
また先日の水球観戦で思ったことの続きで申し訳ないのだが,「組織での担当者の役割」をどう決めるべきか,改めて考えさせられた.母校の水球部は僕の後輩が監督をしている.彼の真面目な性格を反映してか,一人一人の選手にきちっと役割を与えている.泳力に劣る選手には後ろのディフェンスの役割を,まだ経験の浅い二年生には中継の役割を,そしてチームの中心でシュート力のある選手には最前線のフォワードというポジションをあらかじめ割り振り,チームとしての戦術・試合運びもそれらの役割を前提として組み立てられている.実は僕は,そういう役割分担を特定の指導者が決めるやり方はどうかなと思う.良い悪いではなく,好き嫌いの問題かも知れないけど,とにかく「それぞれの役割を予め決めておく」ということが性に合わないのだ.ではどうするかというと,かなり緩やかな役割を適性を見ながら決めてはおくのだけど,これはいわば「仮決め」で,事態が進行していくにつれ,その役割は自然と収まるべきところに収まっていくというのが好きだ.シュートが好きな選手は自然とボールを貰えるポジションに行くし,そういう選手が「成り行き上」,最後尾のディフェンスに回ったりする.普段はシュートを打たない選手が,また成り行き上チャンスでシュートを決めるというのが面白いのじゃないかと思っている.だって子供のころ,監督もコーチもいないのに遊びの中では(それはそれで適正な)「役割」が自然と決まっていったじゃないかと思うし.会社組織でもそうで,上司が社員の職務範囲を決めてしまうこと自体,現実的でないものはないと思っている.能力も興味も人それぞれだから,そう言うのは自分で決めるものだと思うからだ.営業担当者でも,商品開発に興味があれば自分の顧客に協力してもらってフィールド試験をして貰えば良いし,興味のある専門分野を学んで「技術営業」と呼ばれるようになってもいい.虫の研究を社内でやってる社員が,ある日突然ネットショップの店長に指名されて実績をあげていったり,営業統括をやってる担当者が,前職の特技を生かしてソフトウェア開発を行ったり,まあ何でもありで「自分のポジション」を自分で決めていけばいいと思っている.そう言えば前職印刷会社の担当者は今では海外業務を担当していて台湾の工場やラオスのマラリア地帯に出掛けているし.別に命令した訳でもなんでもないんだけど,それはそれで自然と収まるべきところに収まるものだと思う.経営者の役割は,そのように「自分の意思で変化する役割」をベストに組み合わせて,顧客や社会に最大の価値を提供することだ. 好きこそものの上手なれだけど,一人一人の能力を信じて,役割を変化させていって,臨機応変に「試合展開」に対応していけたらと思っています.
Jul 28, 2008
コメント(0)
-
イギリスの余裕
BBCのニュースサイトを見ていたら,チャールズ皇太子が観戦していたポロ競技(馬に乗ってするスポーツ)で,ストリーキング事件があったらしい.日本で皇室が見ている場でそんなことが起こったら関係各所のクビが飛びそうなものだけど,同試合の主催者側のコメントは以下のようであった.A spokeswoman for the club said: "I think it is the hot weather and the Pimms to blame. These things happen."広報担当官(女性)によると,「それはこの暑さとピムス(イギリスでよく飲まれているアルコール飲料)のせいですね.こんなこと,起こる時には起こるものですよ」.まあイギリス的と言うか,余裕の対応である.お客様相手の企業活動にこんなことを言えるかは別の話だけど,いつも心に余裕を持って何事も対応したいと思います.
Jul 28, 2008
コメント(0)
-
先週のランニング
先週は4.2キロ,8キロ,6.5キロ,11.5キロでした.やはり外で走ると5キロでしんどく,ジムで走った11.5キロ(90分)は丁度良い疲労感でした.今日から那覇マラソン(12月7日)のエントリーなので,さっそく朝ネット経由で参加手続きを済ませました.まだ時間はあるけれど,10月11月はイベント続きなので思うように練習できるかなあ.
Jul 28, 2008
コメント(0)
-
自分の人生は自分で決める
今日は母校の水球部のインターハイ予選で,近畿で3位までに入ると本戦出場が決まる.一日目は昨日で無事勝ち進み,今日の朝からやってた準決勝には間に合わなかったが,電話で聞いてみると惜しくも5対6での敗戦であった.午後から行われた3位決定戦,相手は実力的にも互角の尼崎北高校である.前半一点リードしていたのだが,凡ミスが重なり最終クォーターを迎えた時には逆に一点差で負けていた.問題はここからである.相手のフォワードを恐れるあまりに,6人しかいないフィールドプレーヤーの内,3人が全く攻めにいかない.自チームのオフェンスの時に半分の選手が攻めに参加していないわけで,相手のディフェンスは5人,こちらが3人でこれでは点は入れられない.逆に守りは相手一人に対して三人もマークについている状況である.試合はそのまま(当然のことながら),一点差で負けてしまった.観戦しながら悔いが残る試合だったので,試合終了後,先輩として(ありがた迷惑だろうけど),泣きじゃくる生徒を前に説教を垂れた.「戦術うんぬんの話ではない.インターハイに出れるか出れないかと言う人生を賭けた試合で,どうして攻めに出ないのか.自分がフリーでボールを持っているのに,どうして自分でシュートを打たずに,数的不利にいるフォワードにパスするのか.どうして,自分の人生を左右する場面で,何も考えずパスを出すのか.攻めないと勝てない時に,どうして後ろに下がっているのか.自分の人生は自分で判断し行動しないといけない.監督が言ったから,自分に自信がないからと言って,シュートを打ちに行かずに他人にパスする精神が間違っている.修羅場になればなるほど,自分の人生が懸っている試合では,他人の言うことなんか聞くな.他人に自分の人生を決めてもらってはいけない.自信がなくても,自分でシュートを決めようとする根性がないと駄目だ.」これは本当にそう思う.水球の試合なんて単なる青春の一コマに過ぎない.でもそれは人生の縮図であって,一事が万事であって今後の人生がかかっている(そしてそのことを後から気付く).自分の人生が懸っている場面で,他人にボールを渡してしまう人生は一番良くない.自分がフリーでボールを持っているんだったら,自分でシュートを打つ気合いと覚悟がないといけない.これはまさしく会社でもそう.真剣勝負の場面では,予定通り,計画どおりに展開する訳がない.思わぬ事態が起こって,思わぬところでピンチやチャンスが巡ってくる.それを自分が解決すると思わずに,事務的に他人に任せてしまう根性が会社を駄目にしていき,また知らず知らずに自分の人生も左右されてしまうのだ.またまた高校生の試合を観て,考えさせられた一日でした.
Jul 26, 2008
コメント(0)
-
フィロソフィー
稲盛さんの教えの根幹をなすものに,「フィロソフィーを共有する」というものがある.京セラでは京セラフィロソフィーと言うものが小冊子になって,定期的に勉強会もしている.飲み会(コンパと呼ばれる)の際も,雑談をするのではなくて,ほとんど仕事の延長でフィロソフィーを共有(要するに分かっていない人に分からせる場)となっているようである.当社ではフィロソフィー研修はおろか,社員研修すらあまりやってない.でもフィロソフィーと言うか,「判断の基礎になる原理原則」,「モノの考え方」,「社風」,「価値観」みたいなものは,必ず社員全員が共有していないといけないと思う.ではどうすれば,「判断の基礎になる原理原則」を共有することが出来るのだろう?やはりこれは経営者,すなわち僕が率先垂範で示していかないといけない.打ち合わせの場面,他社との交渉,顧客へ訪問時に話す内容の端々に,決して原理原則を外さない「当社の考え方」を反映するということだ.そして経営者自らが,小企業なら尚更,すべての場面に目を配ってベストの判断がなされているかを確かめる必要もある.結局,フィロソフィーは経営者の価値観だから,これを共有するには経営者がしっかりと自らを律し徹底し,それを飽きずに社員に説いていくという地道な作業を通じてしか共有されないのだろう.社内で起こることはすべて経営者の心の反映だ.これからも努力を続けていきたいと思っています.
Jul 25, 2008
コメント(2)
-
練習と実践
今日はスポーツジムのランニングマシンで走ってみた.いつも家の周りを走っていて,5キロも走ると結構疲れてもう帰りたくなる.でもマシンの上で走ると全然しんどくない.結局1時間20分ほど走って(11.5キロ),終了とした.感覚的にはまだまだ走れる感じである.もちろんジョギング程度でゆっくり走っているから全然大したことはないんだけど,外で走るのとこんなにも違うかと思う.ジムだと適度に冷房の効いた部屋で,しかも傾斜をつけず,一定スピードで心拍数を定期的に測りながら走っている.周りの環境も変わらないし,着地面ももちろんスムーズで何の障害になるものもない.外で走ると,僕の家の周りは丘の上で,下の方にある川沿いまで降りていって,その周りを走ったりすると,結構起伏がある.それにやはり石ころも転がっているし,ペースもいまいち分からないから,早くなったり遅くなったりしているのだと思う.そうこうしているうちに,今の暑さと相まって,30分も走れば結構疲れてしまう.そうすると,ジムと外では,同じ走るにしても倍以上の難易度の差があるということだろう.会社経営も,ジムで走る様な「管理された環境」と,何が起こるか分からない外界で走るのと同じくらいの差はあるのだろう.学校で習う「経営学」はもちろん,会議で皆で討議したようなことでも,よほど余裕を持って実行計画を立てないと不可能になる.出来るはずのことが出来ないのが実際の世界だろうし,机上の空論は全然通用しないのだろう.さて,ランニングだが,いつもは環境の厳しい外で走り,たまにジムで走って進歩を振り返りながら自信をつけるのがいいように思う.営業の実戦で苦労し,会議で確認を行う様に.さて,今週も経営にエクササイズ,両方頑張りましょう.
Jul 21, 2008
コメント(2)
-
今週のエクササイズ
今週は,4.0キロ,5.3キロ,7.7キロ,3.6キロのランニングと1500メートルの水泳だった.まあだんだんと慣れてきた.また来週もがんばろう.
Jul 20, 2008
コメント(0)
-
学びと実践
盛和塾で塾長の稲盛さんからよく言われていることは,「学ぶだけでは,幾ら良いことを学んだとしても意味がない.学びを自分の経営に実践し,業績を良くしないといけない」ということだ.今回も様々なことを学んでいる.どれもこれも自分ではまだ出来ていないことだから,まずは何かを実践してみようと思う.「学びを実践し,業績を伸ばす」,きわめて単純なんだけど,なかなか奥が深いですね.
Jul 19, 2008
コメント(2)
-
盛和塾全国大会参加
今年も恒例の盛和塾全国大会に参加してきた.今回で25回周年となる節目の年で,全国から塾生経営者が2500人余り横浜の国際会議場に集まっての大会だ.例年のように,8人の発表者がかなり熱い経営体験を語り,それに対して塾長である稲盛さんがコメントをする.二日間の会議だったのだけど,本当にいつも勉強になる.稲盛さんへの参加者の心酔振りは尋常でない.今回一番驚いたのは,一日目に行われた日本を代表する松山バレエ団の特別公演である.代表の森下洋子・清水哲太郎両氏も塾生なのだが,稲盛さんへの感謝の意を表すために,なんと稲盛さんのこれまで歩みを表現する1時間の創作バレエを上演したのだ.松山バレエ団は総勢200人で,その人たちが何か月もゼロからバレエを創り上げていく.それもたった1回の全国大会での上演のために.30ページくらいの冊子も作られ,そこには稲盛さんへの感謝や賞賛の言葉にあふれている.ここまで来ると本当にいろんな意味ですごいなと思わされる.ここまで感謝を表す松山バレエ団の思いの深さは尋常でない.そしてそこまで人を心酔させる稲盛さんという人間の力も凄い.あまりのことに,ちょっとびっくりして開いた口がふさがらないという感じだった.結局,「思いの深さ」ってこういうことなんだろうなあと思う.良い悪いは別として,思いが深くそれを表現することで人に伝わり,そして人を感動させていく.深い思い,それと行動,本当にいいものを観せてもらいました.
Jul 18, 2008
コメント(0)
-
今週のランニング
今週(月曜日~日曜日)は,5.7キロ,4.5キロ,5.0キロ,7.7キロの計4回22.9キロ(それに日曜日の30分間水泳)であった.だんだん慣れてきました.
Jul 13, 2008
コメント(2)
-
外すか外さないか
今日も昨日に引き続き,母校の練習を見に行った.静岡県からチームが来校して,一日練習試合である.我が高の選手層は薄くて,二・三年生合わせてやっとレギュラーの7人を占めるに過ぎない.一年生は初めてばかりで使い物にならず,基本的には上級生だけでチーム作りをせざるを得ないのが実情である.しばらく試合を見ていて,特定の二人にミスが多いことに気がついた.しかもミスが多いのに,やたらにボールが回ってくる(そしてミスで相手にボールを取られる).一人はいわゆるフルバックで,一番後ろで相手のフォワードのマークにつく割と重要なポジションである.もう一人は中継役で,キーパーから出されたボールを中継して前線にボールを運ぶことに専念している.この二人がミスを連発するものだから,まあまあの実力の残りの4人のフィールドプレーヤーにボールが渡る前に,途中で相手ボールになってしまうことが多数みられた.水球は基本的にはロースコアスポーツだから,攻撃が完了する前に相手にボールを取られてしまうと非常に展開が苦しくなる.誰も途中で相手ボールに変わっているとは思わないから,カウンター攻撃を食らって逆に点を決められてしまう.プラスマイナスで2点のダメージである. 僕はどうして実力の劣る二人がボールに触る機会の多いポジションについているかを聞いてみた.そうすると「彼らを何らかの形で活用するには,それしかないから」というのが答えであった.攻め上がることが出来ないから一番後ろでディフェンスをさせる,攻めも守りもダメだから中継くらいをさせる,というのがその真意のようだ.僕だったらそういう考え方はしないと思う.その役割を果たすことでチームにマイナスならば,その選手は単純に外す,もしくは何の重要な役割も果たさせるべきではないと思う.ちょっとキツイ考え方かも知れないけど,チームは出来ない二人の「居場所」を与えるためにある訳ではない.「中継」しかできない(それも実は出来ていない)人がたまたまいるから,「中継」という業務を作るというのは本末転倒だ.実は中継なんて要らない役割かも知れない.でもその人がいるからその役割を廃止できないのは,本末転倒だと言うのだ.果たしてその「中継専門」の上級生を外し,実力にかなり劣る一年生を入れたらたちまちチームのリズムが良くなった.一年生は実力に劣るから,最初からゲーム展開には入っていない(中継も出来ないからそれもしない).そしてその方がずっとましなゲームを作ることが出来るのだ. 特定の人がいるから多少はプラスだろうからと考えてその役割を残すのは,実は「いない方がまし」ということが多いと思う. だからそう言う人は思い切ってはずして,新しい自分の存在価値を考えてもらうことが,チームにとってもその人にとっても実は幸福なことだと思う.高校生の水球を見ながら,今日はこんなことを考えていました.
Jul 13, 2008
コメント(2)
-
どちらが先か
今日は母校の水球部の現役激励会があって,監督をしている後輩と話す機会があった.来校していた他の高校チームとの試合を見ていたのでその感想を聞かれたので,「一人一人が今自分はどういう役に立っているかを考えている様に見えない.試合中に自分がいま貢献していないと考えたら,次の展開を考えて行動すべきじゃないか」と答えておいた.例えば相手ボールでディフェンスをしている時でも,相手チームには必ず一人や二人攻める意志もそのポジションにもいない選手がいる.そうした選手をマークしている人は,その瞬間自分もチームに貢献していないことになってしまう.その場合は(正しくは),ゲームの中では現在ディフェンス中であっても,次のオフェンスのことを考えた行動をとっておくべきだということだ.分かりにくいかもしれないけど,例えば学校の掃除でも,床を掃いた後に机の上を雑巾で拭く作業が次に待っているなら,十分な数の他の生徒が床を掃いていると判断して,自分は次の雑巾がけの用意に走るような「要領の良さ」のことを言っている.掃除を始めた瞬間にほうきを取り出しに行く人を見ながら,自分は次の工程に向けてまっさきに準備を始める様な生徒が,水球だってなんだってよくできる子供と言うものだ. 後輩の監督はそんな話を聞いて僕にこう言った.「最近の生徒は,上から言われたことは馬鹿正直な位に取り組むけれど,それ以外のことは気がつかない.これはスポーツ以前の問題で,普段の生活でもそうなんです.だから生活の中でも考え方をまず改善するべきなのか,それともスポーツで培われた考え方が生活にも好影響を与えるのか,どちらなんでしょうね?」「そんなこと,卵か鶏みたいな話だけれど,僕の場合は水球で得た考え方でその後の人生すべて乗り切っている.だからまあスポーツと言う特殊な世界で教育すればいいんじゃないの」と僕は彼に答えた. 会社経営でも似たところがある.本当に要領が悪くて,ものごとの順序が違ってしまう社員もいないではない.良かれと思ってやったことが逆に顧客の機嫌を損ねてしまったり.こういう社員でも,会社と言う特殊環境で育てていくのが僕らの役割なんだよなと思う.会社で得た考え方は私生活でも役に立つだろうし,逆にそういう普遍性のある(応用の効く)考え方でないと,会社と言えども通用しないのだろうなとも思う.
Jul 12, 2008
コメント(0)
-
一番みじめなこと
プロ囲碁棋士の依田氏の本を読んで,一番印象に残ったこと.依田棋士が歌舞伎町でギャンブルや酒に溺れかけていた頃,同じく酒飲みであたら才能を潰してしまった典型である先輩棋士に,以下のように言われたらしい. 「『依田くん.何がみじめかって,碁が弱い碁打ちの人生ほど,みじめなものはないよ.』 酒を口に運ぶ手が一瞬止まった.プロの碁打ちで,碁が弱い.たしかに,これほどわびしく,情けないことはないだろう.胸に鋭く突き刺さった.」経営者なら,「なにがみじめかって,経営内容の悪い経営者の人生ほど,みじめなものはない」 ということになるのだろう.ほんとに,そう思う.好調なときでもいつでも,こういう健全な恐怖心を持って経営に当たりたいと思っている.
Jul 9, 2008
コメント(2)
-
中小企業戦略
ネット上のニュースで,北海道十勝管内にある「花畑牧場」の経営者として成功を収めている田中義剛の記事を読んだ.35歳のときにスタートした花畑牧場は年商40億円らしい.インタビューで語られた成功の秘訣が参考になる. 「第一に、『少なく作って高く売れ』です。今、消費者は大企業には出せない手作りの安心感を求めている。薄利多売の時代ではないんです。次 に大切なのは、『足し算をして売値を決めろ』です。最初に確保したい利益を決めて、それにマージンやコストを足していく。スーパーのように初めに売値あり きだと、どうしても品質を落とさざるを得ないのです。この方法だと売値は割高になりますが、それでも売れるプレミア感を出すのです。3つ目は、『売る場所 を考えろ』です。スーパーなどの量販店では、プレミア感は出せません。お客さんがありがたがって、お金を落としてくれる場所を選んで売るのです。」特に第一の点は中小企業にとって大事なことだ.中小企業がマスマーケットを狙って単一の商品・サービスで大成功しようと言うのは確率が大変低い.大企業が入ってこないニッチ市場をいくつも開拓して,ニッチの中の更にニッチ商品を少しだけ市場に出して,価格競争をせずに勝つことを数多く重ねていくべきだということだ.大きいヒットは狙わず,少なく利益率高く商品展開をするという発想はとても有益だと思う.第二の点も第一の点の帰結となる.少なく作っているから高く売ることが可能になる.第三の点も,第一の点のための販売手法である.そうするとやはり,「少なく作って高く売れ」がキーワードか. 「少なく作って高く売る」ためには, 資金の勝負ではない.知恵の勝負だ.知恵を毎日絞って,ニッチの中のニッチ商品を如何に数多く重ねていけるのかが,中小企業戦略といえるのだろう.
Jul 6, 2008
コメント(2)
-
トレーニング経過
先週は4.5キロ(月),3.9キロ(木),5.3キロ(金),6.8キロ(土)のランニングに,本日1.5キロ(日)の水泳だった.少しずつ慣れているような気がするが,それにしてもランニングは最初の1キロから結構しんどい.30分近く経過すると,足の筋肉までだるくなってくるから,相当鈍っている感じである.水泳の方は30分位の連続だったら全然問題なし.まあここ10年以上,運動らしい運動もしてなかったものなあ.まだ始めて二週間だから,これは根気強く頑張るしかないですね.
Jul 6, 2008
コメント(0)
-
理念と現場
友人のブログで読んだんだけど,海外に現地法人を作る時の,欧米企業と日本企業との典型的な違いについての一文が興味深かった.いわく,「欧米企業は企業理念を明確にし現地企業にもその理念を浸透させることを目指すが,現場のオペレーションは現地化していく」.これに対し,「日本企業は逆に,企業理念はあまり明確にしないが,現場のオペレーションは日本と同じように画一性を求めていく」とのことだ.まあこういうことって白黒ではないし,京セラのようにあくまでフィロソフィーを貫いていく(そっして成功する)会社もあるから,日本企業が欧米企業がということはあまりないと思う.でも面白いのは,「理念を統一し,現場の個性を尊重する」経営スタイルが成功している事例が多いと言うことだ.企業経営に一番大事なことは,企業理念,もっと簡単にいうと「自社の存在意義」とか「自社の考え方」 が一人一人の社員に浸透していることだ.そしてその統一化された価値観の下で一人一人が個性を発揮することが企業競争力につながる.「一つの考え方と,一人一人の個性」,当社ではこのアプローチで企業経営をしていきたいと思っています.
Jul 5, 2008
コメント(0)
-
競争のルール
日経ビジネスの最新号で,スピード社の水着に負けたミズノの責任者のインタビュー記事が載っていた.経営者にとってはドキっとするような内容だった.「昨年11月,国際水泳連盟が水着に関するルールを改定しました.オリンピックの開催が1年以内に迫った段階では,通常ありえないことです.ルールの変更により,(開発)アプローチの仕方を完全に変えなければならなくなりました.」 「本当の課題はメーカーの技術開発力にあるのではなく,幹部にロビイングするなど,国際水連とのコミュニケーションが足りなかったことにあります.」要するに,水着に関するルールという市場環境が急に変わってしまって,それに対応する時間的余裕がなかったと言うことだ.そして環境が変わることを事前に察知できなかった情報力を敗因に挙げている.企業経営でも全く同じで,それまで好調に推移していても,「突然」事業環境が変わってしまうことがある.なぜ知っておくことが出来なかったのかという情報収拾不足や,もっと悪いのは「わかっていても対応しなかった」ということがある.少しの未来でも市場環境は不透明だ.どんな事態になっても大丈夫なように慎重に経営し,またどんな小さな変化でも見落とさないように注意しておきたいと思う.
Jul 4, 2008
コメント(0)
-
ランニングのデータ化
12月の那覇マラソンに向けて,ちょこちょことほぼ毎日走っているのだけど,ようやく続けて30分走れるようになってきた.30分だとよちよち走って5キロ弱で,10キロ続けて走るにはまだまだである.走るときに,携帯電話アプリで「ラン&ウォーク」という優れモノがあって,GPS機能で走ったコースや距離・消費カロリー,平均速度などを記録してくれる.それがインターネットにも連動していて,パソコン上で今月走ったデータとか,コースまでもリプレイすることが出来る.単に近所をでたらめに走るのではなく,こうやって数字として記録が残ると大変やる気が出る.データがない日があると(つまり走っていない日)があるとなんだか気持ち悪いし,がんばった日は後からデータを見直してニヤニヤとうれしくなってしまうことさえある.やっぱり何でもデータ化,「見える化」することがモチベーションにつながるのだなと改めて思う.もちろん仕事でも,一か月に何件訪問したか,何件見積もりを出して何件決まったか,何の話をしたか,進行中のプロジェクトの状況はどうなっているか,誰がどこにいて何をしているのか,なんかがリアルタイムでデータ化されていると,経営資料うんぬんよりも先に,動きが「見える化」されることによって,各人のモチベーションが上がるんじゃないかと思う.そう言えば,良く泊まっているホテルのポイントでも飛行機のマイレッジも,溜める(=データ化)することで,改めて見直すと楽しいものなあ. 当社では日報システムにかなり力を入れているが,これを更に進めてこういう細かい「動き」ももっとよく見えるようにならないかなあと思います.
Jul 3, 2008
コメント(2)
全18件 (18件中 1-18件目)
1
-
-
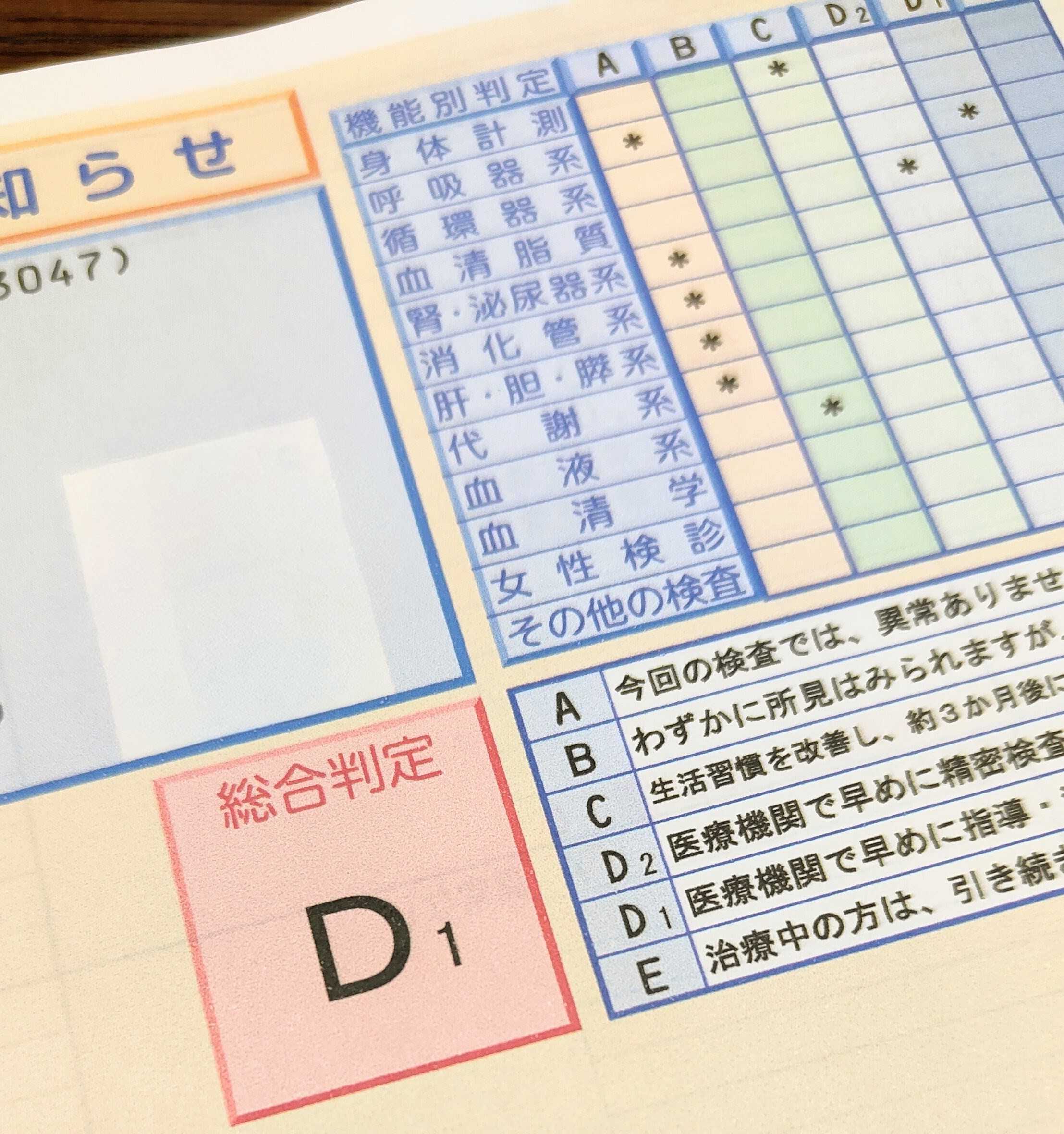
- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- 🍅 My Healthy Life! [Recommended I…
- (2025-11-24 11:12:06)
-
-
-

- 自分らしい生き方・お仕事
- 古い知人を大切に
- (2025-11-24 08:20:34)
-
-
-

- 楽天市場
- ドライマンゴー4袋で1000円ポッキリ❤️
- (2025-11-24 11:10:03)
-







