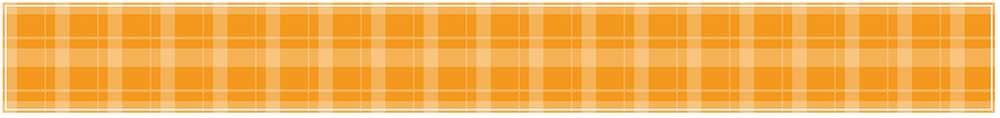2012年01月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-

茶筌の里を歩く☆3
奈良と大阪・京都の境目にある「茶筌の里・高山」2月の本番を前に今回はその下見で歩きました。さて竹の資料館には竹園もあります。4 posted by (C)snowrun29一口に「竹」と言ってもこんなに千差万別色んな種類があるんですね~竹園では沢山の竹に出会ったのですが9 posted by (C)snowrun29こんな竿に斑の入るものから葉に10 posted by (C)snowrun29斑の入るものまた14 posted by (C)snowrun29こちら「カンチク」…先日の初瀬の里で見た竹やっあれはカンチクだったのか、と解って嬉しい他に色んな珍しい竹たちが沢山ありましたが本番当日には竹に詳しい方に説明してもらおうそんなでこの高山資料館を見たあと今度は里山を歩いて高山八幡宮へ、、つづくのであった
2012.01.31
コメント(2)
-

茶筌の里を歩く☆2
奈良と京都・大阪との境目にある「茶筌」の里・高山2 posted by (C)snowrun29今回は2月の本番を前にの下見。高山は室町時代中期に茶筌が考案されて以来ずっと「茶筌の里」として推移しています。詳しくはこちらでどうぞ。そんな高山には竹の資料館がありそこで本番には茶筌作りの実演が見られるのですが今回は下見なのでそれはなく3-1 posted by (C)snowrun29資料館に貼られたものを。淡竹、黒竹、煤竹、竹も色々な種類が使われていますね。更に3-2 posted by (C)snowrun29各千家毎に使う竹が違う。またこちらも3-3 posted by (C)snowrun29展示している茶筌を見ると形も様々ありこんなに違うものなのか、と実は私は一応裏千家のお免状も頂いていますがそれははるか遠い日の話で…なので2月の本番は目の前での実演、楽しみですさてここは色んな竹園でにもなっており4 posted by (C)snowrun29一口に「竹」と言ってもこんなに種類がそんな竹園で見たのが…つづく
2012.01.30
コメント(4)
-

茶筌の里を歩く☆
奈良の長谷寺の後ですがまたまた同じく奈良の「茶筌の里」を歩きました。ここは奈良・京都・大阪の3府県の境目にある「高山」茶道で使う茶道具「茶筌」作りは室町時代にこちらで考案されて以来、一子相伝で伝わり(現在は流石にその技術は皆のものとなっています)今でも日本産の茶筌の殆どをこの里で作っているのですが今回は2月の「高山を歩く」企画のその下見。ってのは竹の「寒干し」が2 posted by (C)snowrun29道路沿いに見えるこの光景アップでどうぞ。2-2 posted by (C)snowrun29こちらの里ではこうした風景が2月頃、あちこちに見られるそうです。現在、竹は各地で猛威をふるい厄介者扱いの困った存在となっていますが茶杓、茶筌、柄杓などの茶道具だけでなく扇子の骨から曲垣や枝折戸の材料まで「竹」の利用は多い。日本人は昔から上手に竹を利用して生活道具から文化・芸術にまで高めてきていますね。500年程前から茶道の「茶筌」作りで栄えた里。そんな高山を歩いてみます。
2012.01.29
コメント(0)
-

初瀬の里で☆7
奈良県桜井市初瀬の里を歩き長谷寺にお参りした今回色んな「」に出会いましたが最後に見かけたこちら山上の本殿を出て、広い山際をぐるり歩くと42 posted by (C)snowrun29無縁仏などを集めた一角が。よく見ると信州辺りで見かける道祖神も多く山の上で苔むした仏様たちや、墓石を見るとやはり集団の持つ力というか、、凄いですね。5時で閉まるのでありがたいかも。さてそんな長谷寺を後にして近鉄電車まで歩く20分ほどの初瀬の街で45 posted by (C)snowrun29こんな大根の寒干しを見ました。アップで見たら45 take de posted by (C)snowrun29細い竹をかませていました。なるほど~こういう利用の仕方ってあるんやなぁ言うても有名寺院の長谷寺。詳しくはこちらでどうぞ。牡丹の頃の参道は賑やかでしょうがやはり冬は静かな状況。私もかつて5月頃に来た事がありますが回廊の横などそれはそれは見事な大輪の牡丹ラッシュで沢山の人が行き交ってましたね。でもまたこんな静かな冬の初瀬もいいなぁと
2012.01.28
コメント(4)
-

初瀬の里で☆6
奈良県桜井市初瀬の里歩きその総本山の長谷寺などで見た「」それはこちら40 posted by (C)snowrun29石灯籠の「窓」半月の灯り取りが開いてますがあちらとこちらで開いてる形が揃っていません。何のことと思われる方こちらをどうぞ。16 posted by (C)snowrun29あちら側とこちら側の開いてる空間の形が違いますね。これは初瀬の里の興喜山天満宮のもの。またこちらは20 susano posted by (C)snowrun29初瀬の里の別の神社のもの。今までそういう眼で見てなかったので気づかなかったのですがこうした灯り取り窓(この言い方でいい)って左右で揃った開き方ではないもの例えば先日の湖西のなどは4 posted by (C)snowrun29こんな風に四角で揃っています。こんなものかと思っていたのですが。以来、灯籠を見かける度に確認していますが確かに「揃ってない」ものが結構多い。片方が「半月」で片方が「満月」とか半月でも上弦・下限で変えるとか。…これは職人さんの遊び心なのかな
2012.01.27
コメント(0)
-

初瀬の里で☆5
奈良県桜井市初瀬の里を歩き最後に長谷寺に参拝ですが昨日の「寒牡丹」を再度アップ30 posted by (C)snowrun29牡丹は普通5月前後に咲くものですがこうしてこの寒い時期に咲くものも。二期咲きの牡丹を特別な地温管理などしてこうして冬に咲かせているようで牡丹としては同じものらしいです。関西で寒牡丹と言えば同じ奈良・当麻の里の石光寺が有名です。そこに2年前に出かけた際の写真はこちらでどうぞ。背後の「寒さ除けの藁」にも色々あるようです。さて話は長谷寺に戻りますが37 posted by (C)snowrun29何折れにもなり、延々と続く長い石段を登り山上の本殿に到着。ここの標高はどの位なのだろう。一応、平たくなっている山上広場で38 posted by (C)snowrun29こんな看板を見ました。へぇ~近江高島からの楠で「琵琶湖周行235」で歩いてるあの辺りの、と思うとちと嬉しい。流石にそのご本尊の写真はNGなので詳しくは長谷寺のページでどうぞ。さてここ初瀬の里でも「」だったものがまた1つそれは…つづくのであります
2012.01.26
コメント(2)
-

初瀬の里で☆4
奈良県初瀬の里歩きいよいよ長谷寺に42 posted by (C)snowrun29こちらは5月頃の牡丹などが有名な花の寺。真言宗豊山(ぶざん)派の総本山です。下から本殿まで長い階段を1歩ずつ上るのですが26 posted by (C)snowrun29これが何とも情緒あります桜も牡丹もシャクナゲもないこの時期は32 posted by (C)snowrun29「寒牡丹」です。寒牡丹は同じ奈良でも当麻の石光寺が有名ですが28 posted by (C)snowrun29ここ長谷寺でも藁の傘を被せてのこの姿やはりこれを見ると「わ~」です。30 posted by (C)snowrun29白も清楚ですねぇ。ただ幾つかは温室かどこかで咲く寸前まで育ててとも思えまぁ雪の多いここ初瀬では仕方ないかもって事で35 posted by (C)snowrun29ロウバイは今の時期の花中心が赤い普通のロウバイですがやはり香りがいいですね~
2012.01.25
コメント(8)
-

初瀬の里で☆3
奈良県初瀬の里山を歩くと出会う色んな「」ここ興喜山天満宮では27 mitizane kou posted by (C)snowrun29怖いお顔の道真公をお祀りしていますがその本殿の賽銭箱に13 posted by (C)snowrun29お正月だからお供え餅はいいとして何で「油揚げ」14 osonae posted by (C)snowrun29油揚げは「お狐さま」の好むものでしょうでも賽銭箱だけでなく15 posted by (C)snowrun29狛犬さんの足元にほらほら15 osonae posted by (C)snowrun29ここにも油揚げ…不思議です。昨日の日記でもこちらの里の「信心の篤さ」をアップしましたがこの謎に関して何かご存知の方、どうぞ宜しくです
2012.01.24
コメント(5)
-

初瀬の里で☆2
奈良県初瀬の里山を長谷寺まで歩くここ初瀬の里はとても信仰心が篤い方が多いのか昨日の山口座(やまぐちにいます)神社の狛犬さんも1no posted by (C)snowrun29赤い涎掛けを着用していますが勿論、これは手作りでしょう。そして山の中で見た祠では8 osonae posted by (C)snowrun29お餅とか正にお正月のお供えものもあるし何でか「生卵」も下見の際に見ました。またこちらの興喜山天満宮は26 posted by (C)snowrun29こんな石段の上におや、あれは27 posted by (C)snowrun29もしや菅原道真公なるほど27 mitizane kou posted by (C)snowrun29…怖いお顔。怒っておられるな。こちらの本殿では13 posted by (C)snowrun29「あれこれは」…つづくのであった
2012.01.23
コメント(6)
-

初瀬の里で
奈良県初瀬の里でのハイク初瀬と書いて「はせ」と読みます。町を通る初瀬街道もですが、そこから「長谷寺」にも。その初瀬の里は牡丹で有名な長谷寺のお膝元。花の寺として有名なこちらも1月も半ばでは寒牡丹位なのですがそこへのお参りの前に初瀬の里山を。まずは長谷山口座(やまぐちにいます)神社へ2 posted by (C)snowrun29これは12月の下見の時のもの。こんな寒い土地でもまだ紅葉が、、こちらの由来です2no posted by (C)snowrun29小ぢんまりした神社は3 posted by (C)snowrun29清々しい空気の中こうして建っていますが屋根の上に「てんこ盛り」の賑やかさ4 posted by (C)snowrun29…逆光なので暗くて申し訳ないですがこちらの狛犬さんは1no posted by (C)snowrun29「角」をつけている。そのまま山道を歩くと9 posted by (C)snowrun29長谷寺を見下ろす形となります。これは下見の時のもの。ここ初瀬の里は住んでる方々がとても信仰心が厚いのか「え」と思う光景があちこちに。それは…つづくのであった
2012.01.22
コメント(2)
-

ロウバイと言えば
昨日の近江高島のロウバイを再度22 sosin posted by (C)snowrun29これは花の真ん中が黄色いままなのでソシンロウバイ同じロウバイでも花を覗き込むと真ん中が赤いロウバイとこの黄色いままのソシンロウバイと2タイプあります。それで別場所で見たのを24 posted by (C)snowrun29まだこの程度の、ですがこれは中央の赤いロウバイでした。ここではまた39 roubai posted by (C)snowrun29これが面白いこれとは40 roubai posted by (C)snowrun29ロウバイの実この透かし俵のような廻りを開けると出て来る実。ロウバイの実は今年の花と一緒に同じ枝に。そんなロウバイを見たのはこちら42 posted by (C)snowrun29奈良・初瀬の長谷寺。1月半ば、出かけた長谷寺で見たもの。ではそのシリーズでまた
2012.01.21
コメント(2)
-

琵琶湖岸を歩く☆北小松から近江高島・本番編5
歩いて琵琶湖一周の企画「琵琶湖周行235」その9回目本番日今回は湖西・北小松から近江高島へさて「町村合併」により「北小松」は大津市に編入。しかし天気予報を見ても湖西は全く違うし何だかなぁ…ですが今回で隣の高島市へ入りました。20 posted by (C)snowrun29何故か、この「ガリバー」がここ高島の名物。もう1つのマンホールは21 posted by (C)snowrun29こちらもガリバーの絵。ここ近江高島に「ガリバー旅行村」があるからですが高島とガリバーのつながりは「」です。まぁ子ども達に夢を持ってほしいという事でしょうね。さてJR近江高島駅に程近いここは池ですが71 posted by (C)snowrun29ここも内湖でしょうね。木の橋が見えてきます。ここは72 posted by (C)snowrun29「乙女が池」なかなか感じのいい空気の流れる場所です。一応74 kogamo posted by (C)snowrun29コガモも見かけましたし。高島港の近くでは雪の中22 sosin posted by (C)snowrun29ソシンロウバイも香ってました。これで9回目本番は無事に終了。ところでロウバイと言えば、、つづく。
2012.01.20
コメント(6)
-

琵琶湖岸を歩く☆北小松から近江高島・本番編4
歩いて琵琶湖一周の企画「琵琶湖周行235」その9回目本番、今回は湖西・北小松から近江高島へ。さて近江高島市内に入ってすぐの最勝寺(この名前はかなりの)14 Saisyouji posted by (C)snowrun29こちらの庭には昨日の雪がどっさりその雪の上に17 Saisyouji posted by (C)snowrun29何でか落ちてるビナンカズラの実…誰かが途中で採取したものかビナンカズラは正式名はサネカズラマツブサ科サネカズラ属のつる性常緑低木百人一首で有名な 名にし負わば 逢坂山のさねかずら 人に知られで来るよしもがなあのサネカズラはこの木本ですね。お庭の片隅には19 Saisyoji posted by (C)snowrun29こんな仏塔も。苔蒸して風情ありますね。またこちらは16 tamaryu posted by (C)snowrun29タマリュウの青い実。まるでラピスラズリみたいとの声も。タマリュウはジャノヒゲの矮小化された園芸種でユリ科ジャノヒゲ属の常緑多年草。普段、山で見ているジャノヒゲに比べて葉が短く実が大きいですね。またこちらは10 sennin posted by (C)snowrun29センニンソウの実何で「仙人」草かは解りますよね。この白い髭のような毛が仙人の謂れでしょう。キンポウゲ科センニンソウ属の多年草。所謂クレマチスの仲間です。そうこうする内にようやく到着したのが…つづく
2012.01.19
コメント(6)
-

琵琶湖岸を歩く☆北小松から近江高島・本番編3
歩いて琵琶湖一周企画「琵琶湖周行235」の9回目本番今回は湖西・北小松から近江高島へ。本番当日のこの日は5 yama posted by (C)snowrun29白髭神社辺りでは「高島時雨」で地面が、のでしたが少しだけ山側の9 ukawa48 posted by (C)snowrun29鵜川四十八体石仏群もこんな気の毒な状況。湖西線でもこの辺りから「白い世界」になる分岐点そこで近江高島に入ると14 Saisyouji posted by (C)snowrun29道路は大丈夫でも「最勝寺」の境内はこんなの。昨日の雪が大盛りですね~こちらの裏側は13 Saisyouji posted by (C)snowrun29雪も「中盛り」ですが溝はこんなの。18 Saisyoji posted by (C)snowrun29何か面白い形状。さてこちらで見たのは、、つづく
2012.01.18
コメント(4)
-

琵琶湖岸を歩く☆北小松から近江高島・本番編2
私の参加しているNPO企画歩いて琵琶湖岸を一周の「琵琶湖就行235」その9回目本番がありました。今回は湖西線・北小松駅から近江高島まで。12月の下見の時は「高島時雨」のお陰で所々「雪」が、でしたが、今回は昨日の「クモの卵」のあったメタセコイア並木もこんな1 posted by (C)snowrun29地面は時折の「時雨」で濡れている程度。背後の比良の山々は白いですが5 yama posted by (C)snowrun29「弁当忘れても傘忘れるな」の日本海気候からしたらまぁこの程度で済んで「」かも。ってのは例の「鵜川四十八体石仏群」も詳しくはこちらをどうぞ。6 posted by (C)snowrun29こんな雪が残る状態本当は安土の方を向いて鎮座され六角義賢の「母の菩提」を弔って頂く仏達も8 ukawa48 posted by (C)snowrun29前に「ごっつん」とぶつかりそうな仏さまも。言うても460年の時の流れの前には9 ukawa48 posted by (C)snowrun29あっち向いたり、下向きにつんのめったりその上にこの積雪、、お疲れさまです。この近くの対岸(それこそ安土方面)に見える32 posted by (C)snowrun29これはやはり「蜃気楼」でしたがこの日も遠目にそれと解るもの。条件が色々あるのでしょうが、冬の風物詩なのかな
2012.01.17
コメント(2)
-

蓑虫かと思ったら!
メタセコイアの並木道を歩いていたら1 posted by (C)snowrun29あれれと思ったこちら。2 posted by (C)snowrun29何とも「貧相な蓑虫やわ~」メタセコイアの細い小葉だけ、それもこんなに少しの量で。更に横にあったもう1つ3 kumo2 posted by (C)snowrun29何とも粗雑な感じの作り。こんな「雑い作りの蓑虫」もいるんやなぁと思ったらOさんが「これは蓑虫と違います」と。4 kumo posted by (C)snowrun29えでは何と思うと「クモの卵やね」と。4 kumo2 posted by (C)snowrun29うわ~確かに蓑虫ではない何クモかはですがこんな蓑虫にも似たような作りをするクモもいるんですね~ちょっとびっくりした1コマ。って事でここは琵琶湖岸。はい、歩いて琵琶湖一周の9回目「本番」の日でした。なのでまた少々、続けますね
2012.01.16
コメント(8)
-

ヒメイチゴノキ?
昨日の「イチゴノキ」を再度アップ1月12日3 itigonoki kana posted by (C)snowrun29これがツツジ科アルブツス属の「イチゴノキ」そう書いたのですが私が最初に「イチゴノキ」を見た3年前の京都府立植物園のは61 itigonoki posted by (C)snowrun29これがその花。実はまだ、の11月でした。この12日に見た花芽がその時に見たのにそっくりで1月12日4 itigonoki kana posted by (C)snowrun29それで「あ、イチゴノキかな」と思った次第。ところでその「府立植物園」でのイチゴノキの実の画像はないかな、と探しているとこちらの画像が。この「H23年11月25日」ページの真中辺りまで探して下さいね。この実が微妙に違うような感じに見えます。そこで更に画像を探すとこちらみたいのも。これが「ヒメイチゴノキ」となってます学名がArbutus unedoでツツジ科アルブツス属は同じですが。なので「」なのですが学名が同じなのに頭に「ヒメ」の有る無しは流通名という事それとも園芸種の若干の違いというだけ…ここのところがよく解りません。どなたかお解りの方があれば宜しくです。さてその同じ12日にご近所で見たもう1つは1月12日1 posted by (C)snowrun29お馴染み「ツルニチニチソウ」えこれって今頃咲く花1月12日2 posted by (C)snowrun29何しろこんな状況幾つかがちらほら咲いている。こんな広い面積だと狂い咲きがあってもおかしくないツルニチニチソウはキョウチクトウ科ツルニチニチソウ属の常緑つる性多年草花期はやはり春から初夏。結構、あちこちで見かけるのでつい見るのがおろそかにまぁ花のないこの時期、咲いてくれてありがとう、かな
2012.01.15
コメント(2)
-

イチゴノキって!
ご近所で見つけたもの1月12日3 itigonoki kana posted by (C)snowrun29おぉ~これはよく見ると1月12日4 itigonoki kana posted by (C)snowrun29この花芽に見覚えがありました3年前だかの京都府立植物園あちらの北門?前で見た「イチゴノキ」の花芽に似ている。何せこの赤い実、直径1cm強の小ぶりサイズで確かに苺といえば苺、、でもヤマモモの方に似ているけどそれで帰宅後、探したらやはりイチゴノキはツツジ科アルブツス属の常緑高木学名:Arbutus unedoだから、なるほどですね。原産は地中海辺りのヨーロッパ南部らしく西洋ヤマモモとも。あの花芽はピンクの筒型の可愛い花で開花は10月~6月頃(不定期開花)、結実は10月~2月頃苺みたいな実は甘酸っぱくてジャムに良いようです。耐寒性もあり、放っておいても大丈夫らしく庭木としてはの木のようですがそう見かけないのは何でかな
2012.01.14
コメント(8)
-

ウスタビガの繭で!
NPOの事務所で見たこちら1月10日1 posted by (C)snowrun29ふっふっふ…たっくさん採ってきはったなぁこれは冬の雑木林などで目立つウスタビガの繭。漢字では「薄手火蛾」で「蛾」の1種ですが、この繭の形での別名「ヤマカマス」はその昔の「カマス」という袋に似ているので。色もですが、目立つ形ですよね~繭から雌が羽化する時早めに出てた雄が、近くで待機。雌が羽化した途端に交尾となり、雌はこの繭に産卵1月10日2 posted by (C)snowrun29なのでこうして卵のついてる繭も時々あります。さてこの繭は見事なARTなのでクラフトに使うというので「はがした卵」を貰って来ました。ウスタビガはコナラなどのブナ科の植物が食樹と思ってたらツツジやサクラだのカエデだのもらしい。…うちに義父の植えた赤い楓がある。園芸種だけどあれにつけてみたらってのはこのウスタビガの幼虫は10 usutabiga2 posted by (C)snowrun29こんなヤツですがこれは昨年6月に見たもの(こちらをどうぞ)その時は知らなかったのですが()何と「触れるとキーキー鳴く」のですその泣き声は小さな鼠の赤ちゃんのよう。聞きたい方はこちらでどうぞ。この幼虫のどこに発音器官がって事でうまく羽化してもらえたらうちでもこの鳴き声がと1月12日4 posted by (C)snowrun29赤い楓の木につけました。左側のは1月12日5の posted by (C)snowrun29クラフトに使えないボロボロのを1つ貰って改めて「両面テープ」でつけた7粒右のは1月12日3 posted by (C)snowrun29プラスチックにテープで貼り付けた3粒…この時点で1粒、こぼれ落ちた後()お隣との塀も丁度、風除けのなくなった場所なので風がきついと春まで持たないな、と背後に板も貼って…こんなでは孵化自体さてですけどね。とにかくこれで春を待とう、、
2012.01.13
コメント(10)
-

ギンバイカの実が!
2010年11月に近所で見たこちら11月29日1 posted by (C)snowrun29何の実と友達が聞いて来たものです。私も初めて見るもので「」でしたが、探した結果ギンバイカではないかと。地中海原産のフトモモ科ギンバイカ属の常緑樹。11月29日1ginbaika kana posted by (C)snowrun29この割合薄い感じの葉が決めてでした。実の感じなどはこちらとそっくりだし。ドイツ語では「ミルテ」と言うらしくだとあのシューマンの歌曲集「ミルテの花」とはこの花さてその後、花も見たかったのに時期を逸しふと先日、立ち寄ってみたら2012年1月6日の posted by (C)snowrun29おぉ~こんな実に熟している。道路に落ちてた2粒を頂き2012年1月7日1 posted by (C)snowrun29家で撮影。これはまた不思議な形状ですね。2012年1月7日2 posted by (C)snowrun29完熟と言う事は、と齧ってみたら「甘い」ハーブのような不思議な味わいでしたが。それで齧ったもので2012年1月11日2 posted by (C)snowrun29こんな「種」が4粒出てきましたって事で本日、鉢に蒔きました。…うちでもあの可愛い白い花が見れたら嬉しいな。まずは発芽しないと、なんですが花のない新年早々、また見果てぬ夢が
2012.01.12
コメント(0)
-

青春18切符で冬を見に行く♪♪♪
母と青春18切符で冬を見に出かけた1日結局は石川県・加賀温泉郷までの往復となりましたが兵庫大阪京都滋賀福井石川と通過したものの最初は福井の永平寺に行くつもりでした。そんなで福井での時間待ちの時に14 posted by (C)snowrun29どちらも福井の名物の越前おろし蕎麦とソースカツ丼遅いお昼ご飯となりましたが。辛い大根おろしは蕎麦の味を引き立てますね。またこのソースは不思議な味でウスターソースに甘酢と醤油にお出汁をプラスしたような薄い豚肉のカツによくマッチしてましたこの後、駅に隣接するスーパーで22 posted by (C)snowrun29こちらの「お揚げさん」をGET薄揚げと厚揚げの中間っぽいこちらは以前ここ福井に来た際、薦められたもの。今回思い出して買ってみました。これを1/4カットしレンジで1分「チン」してからトースターで焼くこと3分25 posted by (C)snowrun29それに「大根おろし」と「ショウガの千切り」を乗せ醤油をたらす。…外はカリカリ、中はしっとり以前、読んだ内田百間(本当は門構えに月)の「ご馳走帖」にあったお揚げさんを七輪だかで焼いてから醤油をじゅっとかけて食べる話これは美味そうとやってみて「」でもこうした厚みのある揚げでもでした。なお隣の小皿のは越前大野の名物里芋を煮たもの。やはりのもっちりねっとり、の美味しい里芋でした
2012.01.11
コメント(4)
-

青春18切符で冬を見に行く♪♪
母と青春18切符で冬を見に行く1日何と今回は「石川県」加賀温泉郷まで行くことに。兵庫大阪京都滋賀福井石川同じ1月でも太平洋側は寒いけど乾燥ばかり。それが滋賀(湖西)でもう「白い世界」になる。新快速で1時間も走れば「雪」に出会う。何か不思議な気すらします。さて初めての加賀温泉郷で私達を迎えてくれたのが9 posted by (C)snowrun29この駅貼りポスター昨日のもう1枚はこちらでどうぞ。「Lady Kaga」勿論、あの「レディーガガ」をもじったもの。…素晴らしいっっLady Kagaは加賀温泉郷の「女将さん達」のこと。確かにそんなニュースで見たと思うけどこうして駅壁で大きいのを見たら「」さてその加賀温泉郷駅で30分程あったので外に出てみたら各温泉の送迎車が何台も雪の中「特急の時間待ち」をしている。…そりゃ普通お客さんは特急サンダーバードで来るよなぁ寒いし、時間まで駅前の立派なスーパーのお土産ものを見ようと母と歩き始めたら11 kaga posted by (C)snowrun29むむっあれはああ、あの…加賀大仏やわ12 kaga posted by (C)snowrun29かつて通過する車窓から見て知っていた大仏さま…って事で永平寺の代わりにこちらを参拝。南無。そしてまた普通で福井に戻るようやくお昼ご飯となったけど(もう2時廻っている)14 posted by (C)snowrun29ここは福井となればそりゃあ「越前おろし蕎麦」でしょうそしてもう1つの名物「ソースカツ丼」の小鉢つき。…うう、美味しかったさて福井からまた敦賀に戻る普通の車窓17no posted by (C)snowrun29もう少ししたら「駅名」が判別不可になる石川より福井の方が雪が多い20 posted by (C)snowrun29同じ「日本海側」でも地形でこうも違うものか。滋賀に入って21 siotu sugi posted by (C)snowrun29近江塩津を越えてもまだこの景色。この後、徐々に雪は減ってゆき遂に高島辺りではもう普通の「土」の色となりました。母は最初「暖かい方がいい」と言ってたけど冬なら「白い世界」を見なくてはと私が押し切ったもの。でも冬ならではのものを、暖かい車窓から見たと喜んでおりました。そんな大忙しの電車ツアーでしたが、お土産は…つづく
2012.01.10
コメント(6)
-

青春18切符で冬を見に行く♪
お正月の1日、青春18切符で母と冬を見に出かけました。今回は福井県まで行こうと1 oumi posted by (C)snowrun29湖西廻りの新快速「敦賀」行きに乗ると近江高島辺りでもう「白い世界」に。これで背景は比良辺りかな。今回は福井駅から永平寺に行く予定で敦賀に着いて、福井までの普通に乗るまで28分も待つ。(北陸線の連絡の悪さはいかがなものか)勿論、敦賀の駅前も雪がかなり。やっと乗った普通「福井」行き7 posted by (C)snowrun292両編成ですよその車窓からがこんなの。3 posted by (C)snowrun29これは南今庄駅この辺りが1番積雪量が多いかも。窓枠にも6 posted by (C)snowrun29こんな霰のような雪がばしばし。福井に到着後、駅前の積雪と細かい吹雪を見てこれは母には無理かも、と行ける所まで行こうと次の「金沢」行きに乗ろうという事に。時刻表を繰ると加賀温泉郷辺りなら時間的に加賀温泉郷駅に到着したら待っていたのが8 posted by (C)snowrun29…つづくのであった
2012.01.09
コメント(6)
-

琵琶湖岸で美味しいもの♪
「琵琶湖周行235」企画のオマケ本日は湖西で食べた美味しいものそれはこちら20 hitumabusi posted by (C)snowrun29「ひつまぶし」ですここは湖西では有名な「西友」さんってスーパーの読みでなく「にしとも」さんウナギを始め、川魚の佃煮などを作っているお店。勿論、このひつまぶしはウナギのお茶漬け21 hitumabusi posted by (C)snowrun29最初は普通に食べて、その後、海苔・ワサビ・ネギなどの薬味と一緒に食べてその後、それを「お出汁」でお茶漬け風に食べて、、というあれ。それって名古屋ではと思いますが(そうです、名古屋の熱田蓬莱軒などが有名ですよね)ここ湖西でも食べられましたここは22 posted by (C)snowrun29近江今津の駅傍お店はとてもいい感じで23 posted by (C)snowrun29こんなショーウインドウ展開も楽しい勿論、ひつまぶしも美味ですしって事でもし湖西に来られる事がありましたらこちらでお食事など如何でしょうか、とお勧め。湖西の番外編でした
2012.01.08
コメント(6)
-

琵琶湖岸を歩く☆北小松から近江高島9
歩いて琵琶湖一周企画その名も「琵琶湖周行235」の9回目下見シリーズ今回は湖西・北小松から1駅向こうの近江高島まで。 白髭神社 鵜川四十八体石仏群 日吉神社と歩いていよいよ近江高島に到着。湖西線のトンネルをくぐると車窓にすぐ見える72 posted by (C)snowrun29乙女が池こちらも琵琶湖の内湖ですね。大きな池には一部70 posted by (C)snowrun29ヒシや外来生物のオオフサモも繁殖してるとこもありますがこちらがびっしりオオフサモ69-2 posted by (C)snowrun29これは越冬の姿でしょうね。12月半ばのこの時期は冬鳥も何羽か。その写真はあまりにも…なので割愛ですがここは気持ちのよい、開けた公園風の所ですがすぐ傍にあるのが77 omizojou posted by (C)snowrun29大溝城址あの「江」の姉、「初」が嫁入りした京極高次の城です。今はもう石垣と天守の跡しかないのですが76 posted by (C)snowrun29そんなで「江」の幟もはためいておりましたね。このお城は明智光秀の作ったものだとかで一旦は明智に味方して立場の無くなった京極高次が復興なって入ったお城がこちらって、と。そんな歴史ももう、この石垣からは遠いものとなっておりますが。ここ大溝城址はJR湖西線・近江高島駅から徒歩5分ほど。と言う事で今回の下見はここで終わりで帰途につきました。最後まで読んで下さってありがとうございました
2012.01.07
コメント(2)
-

琵琶湖岸を歩く☆北小松から近江高島8
歩いて琵琶湖一周の企画「琵琶湖周行235」の9回目下見の続編です。さてさて昨日の日吉神社66 hiyosijinja2 posted by (C)snowrun29狛犬さんはこんなの。「灯籠」も再度アップ。65 posted by (C)snowrun29この古めかしい灯篭の窓をご覧下さい。実はこの数日前に同じ湖西ですが、別のT神社で見たのが4 posted by (C)snowrun29この石灯籠。この灯り窓を止めるもの。金属製の「へら」のような。へぇ~こんなのあったっけってその時思ったのです。なので今回のは「」だったのですが、、如何でしょうか、これって普通のもの因みにこのT神社の狛犬さん17 posted by (C)snowrun29ちと痩せていますね。アップで見たら17-2 posted by (C)snowrun29こんなのですが。ただこちらのT神社には更にもう2対の狛犬さんもいて16 posted by (C)snowrun29こちらは新しい感じですね。またこちらは古い感じで尻尾もですが、背中の筋模様が面白い12 posted by (C)snowrun29こういうのって結構あるのかな因みにこちらのT神社では6 sakakaki posted by (C)snowrun29サカキの実が物凄い。アップでどうぞ。8 sakakaki posted by (C)snowrun29サカキは神社ならではの奉納植栽木。でもここまで実がってのはあまり。生り年なのか石灯籠も、また狛犬さんも同じ湖西の神社でも色んなバリエーションがと思った次第。ちと回り道しましたがではまた高島辺りへつづくのであった
2012.01.06
コメント(4)
-

琵琶湖岸を歩く☆北小松から近江高島7
歩いて琵琶湖一周の企画「琵琶湖周行235」の9回目の下見は12月半ば。今回は湖西線・北小松から1駅向こうの近江高島まで。さて昨日の「鵜川四十八体仏群」を越えて暫く歩くと今度は63 posted by (C)snowrun29日吉神社に到着。ここは比叡山の麓・近江坂本の日吉大社の末社滋賀には日吉神社が多いのかですが坂本の本社に比べれば規模が小ぶりですがなかなか風格のあるこちらの石段には67 posted by (C)snowrun29紅葉に前日の雪がもう12月半ばだし、結構寒いのにまだ紅葉があるんやねぇと66 hiyosijinja posted by (C)snowrun29石段を登りきるとこんな狛犬さんがお出迎え。うっ背中にも雪が66 hiyosijinja2 posted by (C)snowrun29そんなで驚く狛犬さんではないところでこの境内で見たのが65 posted by (C)snowrun29この石灯籠。実は少し前に別の神社で見た石灯籠で「」だったのがあります。同じく湖西の、なのですが…つづく
2012.01.05
コメント(2)
-

琵琶湖岸を歩く☆北小松から近江高島6
歩いて琵琶湖一周企画の「琵琶湖周行235」その9回目下見。今回は湖西線・北小松から近江高島まで。白髭神社から湖岸を離れて少し山の中を歩く。すると坂の上に現れたのが55 posted by (C)snowrun29鵜川四十八体石仏何なの、これは57 posted by (C)snowrun29物凄いインパクトやわ。定印を結んだ阿弥陀如来像が同じ形でこんなに。横から見たら58 posted by (C)snowrun29何でかやや斜めに傾いている。遠ざかりつつ見ると59 posted by (C)snowrun29イチョウの大木の陰に整然と。背後は共同墓地で普通の墓石が並んでいます。鵜川四十八体石仏は滋賀県指定史跡で近江半国の守護職で安土・観音寺城主だった六角義賢が天文22年(1553)対岸のここ高島町鵜川の地に母の菩提の為に作らせたもの。花崗岩で出来た高さ1・6mの同サイズの阿弥陀様達は安土の方を向いて座しており6体ずつ8列並んで48体あった仏さまも今は33体だかで近江坂本のお寺に移動されたり、盗まれたり(何と罰当たりな)らしい。そのつもりで歩いてても「」なのに知らずに山中で出会うと「わわわっ」かと。しかし460年も経過しててこのインパクト。近江の歴史も深いですし、まだまだ知らない事って多いなぁと嬉しいです
2012.01.04
コメント(4)
-

琵琶湖岸を歩く☆北小松から近江高島5
歩いて琵琶湖一周の「琵琶湖周行235」その9回目下見は12月半ばにJR湖西線・北小松から近江高島へ。さて蜃気楼などを見ながら到着の白髭神社この日は前日の雪も残り44 posted by (C)snowrun29駐車場では、わわっでしたが。白髭神社の53 Sirahigejinaja posted by (C)snowrun291つ目の鳥居は琵琶湖の水中にあり3 posted by (C)snowrun29これが為に「近江の厳島神社」と言われます。この鳥居から5 posted by (C)snowrun29道路を挟んでまた鳥居。この赤い鳥居がの2枚目の手前のもの。逆光だと別物に見えますね。神社の本殿は45 Sirahigejinaja posted by (C)snowrun29こんな感じで7 Sirahige posted by (C)snowrun29本殿横はこんな風です。12月半ばのこの日、47 Sirahigejinaja posted by (C)snowrun29背後の山にもまだ雪が残っておりシイの古木林内の神社群50 Sirahigejinaja posted by (C)snowrun29流石に近江最古と言われるだけの荘厳さ。そこにはこんな祠と石も。14 posted by (C)snowrun29祠の囲いの中も石なのですが流石に撮れません巨石は神の降臨したものを表わしているのか、何とも良い雰囲気を味わった後でまた湖岸沿いを歩くと、次に現れた「石」は、、つづくのであった
2012.01.03
コメント(10)
-

琵琶湖岸を歩く☆北小松から近江高島4(おけら火の話)
さて私の参加するNPO企画「琵琶湖周行235」9回目下見の続きに戻りますが今回はJR湖西線・北小松から近江高島までの1駅分。「高島時雨」の湖西では前回は虹を5回見てまた今回は「蜃気楼」も見れました。40-3 posted by (C)snowrun292日前のを再度アップ。さてその蜃気楼を見た湖岸沿いを歩き到達したのが53 Sirahigejinaja posted by (C)snowrun29こちら「白髭神社」近江最古の神社だそうで、ここの湖岸に浮かぶ鳥居3 posted by (C)snowrun29この為にこちらは「近江の厳島神社」とも呼ばれています。個人的な話で申し訳ないですが私の父がここの神社で名前をつけてもらったとかで後でその話を聞いてかなり「」でした。ついでの事に「お正月」なのでおおむらさき57さんとこの記事を見て思い出したのが子どもの頃の父とのお正月の記憶。父は京都生まれの京都育ちなので大晦日に八坂神社に「おけら火」なるものを貰って来るのが毎年の事。それで付けた火で元旦のお雑煮を作るのだそうでこれを「おけら参り」と言います(こちら)八坂さんで求めた「火縄」の「縄の先に付いた火」を消えないようにくるくる廻しながら各家庭に持ち帰るのです。とは言え、当時私達は甲子園に住んでいたのでそんなの無理でしょうところがその昔、大晦日は京阪電車が2時頃まで深夜運転しており乗客が「おけら火」を持ったまま乗ってだったのです。…何とも凄い事ではないでしょうか。当時の電車の床は「木製」の時もあったので流石にそれから程なく「持ち込み禁止」となった「おけら火」…当然ですよね、ほんまに信じられない記憶ですが父にとってはそれは「夢の火」だとかで何度か大晦日の夜は父に連れられて八坂さんへ。京都市内の祖母宅からならともかくも、ですがまだ小さかった私達も眠いよ~と京阪電車の中で居眠りしながらまた甲子園まで。よく元旦は普通に起きられたものですが今は昔の良き時代の思い出ですねでは白髭神社の話はまた明日に
2012.01.02
コメント(6)
-

明けましたねv
明けましておめでとうございます今年こそは明るい穏やかな年となりますように。2012年 posted by (C)snowrun29今年もどうぞ宜しくお願いいたします。「Dファン」としても今年は「」で今年の曲は勿論「燃えよドラゴンズ」です。宜しければこちらでお聞き下さい。マスコットのドアラはともかく、横の2人はですがさて「琵琶湖岸歩き」のさなかですが新年早々のネタとしては1 posted by (C)snowrun29こちらでしょうか。12月下旬のお墓参りの際のハクモクレン7 posted by (C)snowrun29もう「蕾」が衣を脱ぎかけていました。確かにここは和歌山市内なのですが。何か早いなと思い、かつてのを確認2月20日2 posted by (C)snowrun29これで一昨年の2月20日。花が咲いたのを探すと3月11日の! posted by (C)snowrun29これも一昨年の3月の。クリスマス寒波はあっても今年の冬はやや暖かめなのかまた、この日掃除をしてたら、墓所に生えていたのがこちら11 posted by (C)snowrun29松の赤ちゃんやわ~何か可愛いですね。今日は初詣に出ても暖かくまだまだ難問山積の寒~い日本ではありますがどうぞこの1年はほっこり暖かい1年となりますように、と
2012.01.01
コメント(14)
全31件 (31件中 1-31件目)
1