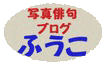2011年05月の記事
全20件 (20件中 1-20件目)
1
-

花の世界は面白い~2
先日、出かけました箱根湿生花園では数多くの未知の花々に遭遇致しました。今回は紹介しきれなかったものの中からどうしてもお見せしたいお花をご覧頂けたらと思います(気になったものは画像クリックしてフォト蔵の特大サイズで見てね♪) シコタンソウ(色丹草)和名の由来は、南千島の色丹島で発見、採取されたことから。まだ咲き始めの為か?色が薄めだけれど黄と赤の斑点模様がおわかりになります?カワイイ~模様でしょ♪カワイイと言えばこちらも・・・ イワヒゲ(岩髭)ツツジ科の高さ10cm程の常緑小低木の高山植物ヒノキやイブキの葉に似ている。岩の間から生える姿が髭を伸ばした様に見えることからイワヒゲ。木には見えないトコがまた驚き。 バラ(安曇野)一重のミニのつるバラ日本のバラの育種家・小野寺透氏が1983年、安曇野の素晴らしい風景をイメージして、アルプスを望む田園風景や白壁に映える可憐なバラをつくりあげました。それがこの《安曇野》話はズレますが今、NHKの朝ドラ『おひさま』は安曇野が舞台です♪珍しく、十何年ぶりかでほぼ毎日見ていますがこのバラを見て想像したのは主人公を含めた仲良し三人組の姿でした。本当に清純で明るい、誰にでも好かれる可愛らしさもあって独特のキツイ香りも殆どない純真さが溢れるバラです上の3種の花は箱根湿生花園の売店で販売されている高山植物や珍しい植物等の一部です。ついつい目に入ったものを撮影しちゃいました。私に育てる愛情と力量と環境があったら欲しいお花がいっぱいでした♪こちらは、入園してすぐの小さな池にありました。 オニブキ(鬼蕗)植物の世界では名前に、小さいものには姫(ヒメ)大きなものには鬼(オニ)とかつけちゃう様で。(つい最近知りました・・・)このオニブキもその類ですね~、フキと名乗ってもフキの仲間でない何の類縁関係も持たない一科一属の植物だとか。花の名前はけっこう見た目でつけられちゃうって事、多いのね。(これもつい最近気づいた・・・)「何コレ~おっきぃぃぃ!!」でしたからね、第一声は。とにかくまだまだ巨大になるそうで・・・これはまだまだ序の口サイズです。1990年大阪で「国際花と緑の博覧会」が開かれた時話題になった植物のひとつだとか。《別名》グンネラブラジル南部の海岸山脈の極めて限られた地帯にしか自生していないらしい。葉柄で2m以上、葉径で3m以上花序(赤い部分)で1mになる。茎なんて、トゲトゲして鬼のこん棒みたいでしょ 花は緑色、花序に無数に付く様です・・・見てみたい♪ 正体不明・・・ 名前も良く見ないで撮影し、今もって不明。昨夜も一晩かけて検索したけど手がかり無しです 珍しいモン好きが祟ったかしら。どこ見てもこんな植物撮影している見学者いないみたいだし醤油漬けのタラコ粒にも、粟やキビにも見える・・・花なのか、実なのか?!いつかわかるかしら~???追伸・・・先日わからなかった《一重咲きのタンポポ》の正体が判明しました。追加しておきましたのでお暇がありましたらど~ぞ♪
2011年05月28日
-

同僚Mさんとaikoの限定版CD
勤め先で仲良しの同僚Mさんの話先々週だったかしら・・・Mさん「神奈川から関西で一番近い県て何処かなぁ?」仕事中に、日本地図は関東圏辺りしか把握していない私に聞いてきた。何故か聞き返すと、Mさん「ホラYさん(Mさんの交際相手の年下社員)さ、 歌手のaikoの大ファンじゃない♪ 今度aikoが関西限定版のCD発売するんだけど、 通販もしてくれないし、買いに行くしかないかなって」取り扱いは大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山の一部CDショップのみ交際相手のYさんは、同じaikoファンの友人とどうしたものかと思案している最中だと言う。Mさん「家に帰って調べてみるわ」と言いつつ・・・翌日にはMさん「滋賀のCDショップに電話して予約入れちゃった♪ Yさんにはまだ言ってないんだけど、 もし行けなかったら、くろすけサン一緒に車で行こうね~」なんて冗談とも本気とも取れる発言にビビッた私数日後・・・Mさんから携帯に写メールが入ったのは、私が箱根湿生花園に入園して1時間もしない頃。 「清水寺に着いたよ」 (あら、やだ!MサンてばホントにCD買いに 関西まで行っちゃったよ!!京都に寄ったんだぁ~)で、帰りの車の中で返信するとまた返信が・・・Mさん「今、琵琶湖を出発する所、 清水寺でおみくじ引いたら凶だった~ しかも二人とも」(CDはアトだったんだ~、でも京都行くなら 京都のCDショップでも良かったんちゃうん?) それにしてもふたり合わせたら大凶だねぇ~) Mさん「Yさんの奥歯詰め物が取れた(*≧m≦*)プププ これはおみくじのせい?!」(じゃ、Mさんの歯もお揃いにならない様に気をつけてね~)Mさんの急な思いつきで滋賀まで予約CDを買いに車で行く事になったYさんもさすがに、その行動力に驚きを隠せなかった様で。でもウカウカしてたら買えなかったかもしれないんだから、ね~ お土産の八ツ橋 で、22日の今日Mさんは遊びに来ていたお姉さんを嫁ぎ先の千葉まで夜勤明けに車で送って、日帰りして帰って来ました。かりんとう饅頭をお土産に買って来たからとわざわざ自宅に帰ったのに夜、持って来てくれました・・・15個も「お姉さんが買ってよこしたから、無料でいいよ~」って・・・タフなMさん、太っ腹なお姉さまいつもお世話になります~
2011年05月22日
-

次男、売れ残りのアントルメを持ち帰る
洋菓子店に職人として勤める次男もこの春で2年目を迎えまして、基本を真似てのアントルメの飾り付けをさせて貰えるようになりました。アントルメというのは洋菓子店では小さめのホールケーキの事をさしますで、昨日の夜の事・・・次男「チーズのアントルメなんだけどさ、 作った日から2日目で売れないと捨てちゃうんだ。 勿体ないから貰って来たよ」私 「わぁ~♪どんな?!どんな?! 店員価格で買うんじゃなくて、貰えるんだ~」(タダほど嬉しいものはないと思ういじましい母)次男「自分で飾ったヤツだから捨てるに忍びないし」と、ケーキボックスから取り出したのがコレ ドゥーブル・フロマージュ 私 「まさかいつもあなたの作ったの 売れ残ってルンじゃないでしょうね~」(シークレットな部分にツッコミ入れる意地悪な母)次男「そんなことないよ、明日だって5個も飾りつけ しなくちゃなんないの任されてるのにさぁ~」私 「へぇ~、でもデザイン的に素人っぽいなぁ~ バランスとかデザインを人の作品とか見て 研究した方がいいんじゃない?!」(素人のクセに上目線でモノを言う母)次男「う~ん、元のデザインより 良くなったと思うんだけどなぁ~」 ちょいと切れ味の悪い包丁で潰れ気味ですがスポンジの台の上に上が先輩職人が担当のスフレチーズケーキ下が次男が担当したカマンベールチーズケーキ 生クリームで全体をナッペして、ふわふわクラム(スポンジケーキをそぼろ状にしたもの)をまぶしてあります上のチーズの方が甘酸っぱくて下のチーズはこってりで美味しゅうございましたそれでも2日目の夜だと味が落ちると作った本人は言ってます・・・当然だわね その前の日も・・・この日は駅前店にお手伝いに行く日で本店と駅前店では若干、ケーキにも違いがあります。私が思うに・・・本店は町外れにある分、ファミリー、子供向けのケーキ。町なかの店は若者向きで、見た目重視って感があるわ。で、本店にはないプティガトー(カットケーキ)を味見用に店員価格で3個ばかり購入してきた次男。 フロマージュ・マムフロマージュブランのムースと(フランスの牛乳からつくられたフレッシュチーズ)カシスのソース上にちょこっと生クリームが絞ってあるかな。上にあるのはソフトクッキーの砂糖がけ(バナナかと思ったわ~) イチゴチーズケーキ濃厚なチーズケーキにイチゴの甘酸っぱさはよく合う♪ちょっと甘めだったけれど、長男はお気に召し~ クレープ・シュゼットクレープで包んだケーキ・・・なんだかカワイイシュゼットとは、クレープをバターとオレンジのリキュールの中で温めたデザートのことだとかもちろん、このクレープの皮もオレンジのシロップに浸けて、中にはスポンジの上にオレンジムース、カスタード、生クリームスライスオレンジものって、中央にカシスのジュレが入ってる オレンジ好きにはたまらないかも~私はちょいと苦手なんだけどね、オレンジ系+クリーム系でも、これだけ手が込んでいれば素敵なケーキだわ♪
2011年05月21日
-

高層湿原区~仙石原湿原区~湿性林区【箱根湿生花園】
尾瀬やサロベツ原野など高山や寒冷地に発達するミズゴケがモデルという高層湿原区が6番目となります ヒメシャクナゲ高さ10~30cm、ツツジ科の常緑小低木同じツツジの仲間のシャクヤクとはサイズもだいぶダウンしたので・・・ヒメシャクナゲ(姫石楠花)北海道、本州(中部以北)の寒冷地の湿原に生息 カサスゲ かつて簑(みの)や笠(かさ)を作る為栽培までされていたというこのカサスゲ湿原のソコココに見られます。なんだか可愛い~白と茶の2色分けの穂上の茶色が雄花の穂、黄色のボサボサしているのは花粉を出してる真っ最中なんだそうで、下の白いのが雌花の穂。ちょっと離れた場所の背の高い黄色い花が~ サワオグルマ で、遊歩道まで背伸びしている黄色い花が エンコウソウエンコウソウとリュウキンカは同じ物として扱うほど、見分けが難しい植物名前の語源は花茎が長く伸びるのでこれをテナガザルにたとえたものサル=(えんこう・猿猴)とかコチラの水辺にはドクゼリ丈は80~100cmになるそうです。花のツボミがあり、夏には白い花を咲かせます。名前の如く、食べると中毒になります流れる水は澄んでて、子供の頃良く遊んだ故郷の川を思い出します7番目の仙石原湿原区こちらには地元仙石原に見られるの湿原植物が紹介されています。仙石原湿原は低い山地に残されている貴重な湿原として一部が国の天然記念物にもなっています 神代杉(水面が光って見難いとは思いますが)水中にあるのは樹齢340年程の大木が850年前に土砂に埋まって枯れた杉の根株(古いものは3000年前のもあります)地下0・5m程に埋没していたものを展示の為に土砂を掃い水の中で保存しています。いにしえの巨大地震で埋没した木々が普通の土地なら微生物や土壌動物により土に変わるけれど酸素不足で貧養な湿地では有機物を分解する生物が少ない為埋没しても腐らないそうです仙石原一帯では昔からこの埋もれた木を掘り返し箱根細工等に使っていたそうで杉の他にも、ヒノキ・モミ・ケヤキ等もあるとか(園内案内板文章抜粋) 各所に生物もいます。この池には大きな鯉が口パクしていました。手前の小川では小魚やイモリ等も見ましたし今時あまり見かけないナマズもいるそうです 遥か遠くまで続く水路の先は湖底からの湧き水が水源と言われる芦ノ湖かなぁ湿生花園南側には、昔の仙石原湿原植生を蘇らせる為設けられた復元区があります。復元区の中にも遊歩道がつくられ、湿原の植生が観察できますハンノキでできた林の最後の8区どうしてハンノキなのかなぁって思うわけでして・・・なんでも低地を好み、荒地を肥沃な土地に変える肥料木なんですって 3区の低層湿原にもつながる水芭蕉の群落カキツバタの咲く水辺ハイハイ、わかっておりますくろすけからのお土産のおまけわからない方にはお助けね♪もちろん、私も ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆これにて箱根湿生花園で見てきたお話おしまい。ふつうの観覧時間は40分程とか言われてマスが一緒に出かけた長男は20分で見て周り、2周するハメに。私は約1時間40分見てましたまだココで有名なヒマラヤの青いケシも、展示室も、これからの夏、秋の園内も見ていないのであと何回か来てみたいなぁ~と思うのでありました
2011年05月20日
-

高山のお花畑区で萌える【箱根湿生花園】
5区画目は高山のお花畑区です。富士山、大雪山等に咲く日本の代表的な高山植物を見ることができます。写生したり、撮影したりお花好きにはたまらない魅力的なお花が集結してました。 ミヤマオダマキ高山の礫地に生える多年草。市販されているオダマキはこのミヤマオダマキを改良したものだそうです クロユリ 黒い花って見たときちょっぴりドキッとしますね。でもユリと言うには丸みがあるのでうなだれたチューリップの様にも見えてなんだか可愛く思えてしまいました有名な生息地は白山で、大量に群生しているそうです。 オオバキスミレ今年はスミレには驚かされます。白、フレックルスに続いて黄色のスミレ一輪だけ咲いていました。このスミレの特徴は、他のスミレの葉よりも目立って大きな葉。 エゾルリソウ 北海道の高山(十勝・日高)の礫地に生息。自然界にある青って神秘的ですよね~なんだかね、ブルーのワンピースに見えてしまうんです。この花を横から見た姿が・・・ リシリヒナゲシ 北海道の利尻島利尻岳の山頂付近の岩礫地に特産透明感のあるレモンイエローはヒナゲシの色にありそうでなかったんじゃないかな。日本に自生するケシ属はリシリヒナゲシのみ貴重なお花ですこれも一輪だけ咲いてました。 チシマキンバイ北海道の海岸の岩地に生息キンバイは梅に似た金色の花の様子からの命名確かにまぶしいくらいなヤマブキ色。 キクバクワガタ名前だけ聞いたらクワガタムシの名前かと思うけどお花の名前なんですわ~葉の形が菊の葉に似ているためにキクバ(菊葉)、クワガタは兜(かぶと)についている角(つの)状の飾りを意味する鍬形に実の時期の萼(がく)の様子が似ているのでついた名前とか白いのもありました ハヤチネウスユキソウ 本州(早池峰山)のみ生息山頂の蛇紋岩の礫地に生えるウスユキソウは、白い毛が密生し、薄く雪を被ったような様子からの命名で、エーデルワイスの仲間です。エーデルワイスは絵でしか見たことがありませんし歌でしか想像できなかったモノですが~同じ仲間のウスユキソウ2種類に逢えました エゾウスユキソウ 北海道(礼文・釧路)の風衝草地に生える私はコチラのウスユキソウの方が雪の積もり具合?!と形が好きですねぇ エゾノツガザクラ北海道、東北北部の雪田周辺に生える常緑小低木もう花が落ちてしまってました。でも残った赤い茎の部分が可愛いからついつい撮影してしまいました ごめんなさい~まだまだ続きます
2011年05月19日
-

ヌマガヤ草原区を歩く【箱根湿生花園】
4番目の区画は、低層湿原から高層湿原へと変化していく途中の湿原でヌマガヤが多いのでヌマガヤ草原と呼ばるそうです 池には黄色の花をつけた水草のコウホネ(河骨)が生息しています。肥大した根っこが白骨の様に見えるからそう呼ばれるそうです・・・根っこが見てみたくなりました ミツガシワ池の中に見つけた白い花ミツガシワ北半球の寒帯に広く分布し、北海道から東北地方の湖沼などに見られます。カシに似た葉を3枚つけるのでついた名前。花もアップで見ると面白い~箱根にはあるハズが無くても、その場所にしかないっていう生息地へ出向かなくても、箱根湿生花園には見ることができる植物がたくさんあります。上のミツガシワもそうですね。日本では、北海道、茨城県より北の太平洋側や鳥取より北の日本海側の海岸に自生するというハマナス関東に住んでいる私なんて旅行でもしない限り見れないかもしれないでしょ・・・ ハマナスハマナスの名前は、浜(海岸の砂地)に生え、果実がナシに似た形をしていることから《ハマナシ》と呼ばれそれが訛ってハマナスになったそうです♪でもね~、この時はハマナスは咲いてなかったの!コレは売店で販売されていたハマナスでした~花はコレからみたいですね。 レンゲツツジ レンゲツツジが咲き始めていました。艶やかなオレンジ色のツツジは我が故郷、群馬県の県花でもあります♪猛毒をもっているので、普通のツツジの様に蜜を吸ったらいけません。中毒を起こす場合も有るそうですよ~ 北国の海岸に生える多年草、センダイハギ仙台を舞台にした歌舞伎「伽羅先代萩」にかけてついたとも、船を修理する台(船台)の周りに咲く萩だからついたものだとも言われているようで・・・これも地域限定の花なんですねぇ~ センダイハギ こちらも本州中北部の日本海側の山地でしか見られないというガクアジサイに似たケナシヤブデマリケナシ(毛無し)があれば毛の有るのもあります。太平洋側に分布するヤブデマリがソレ。 ケナシヤブデマリ(花と茎の間にカエルのタマゴ?!と思ったらどうやらアワフキムシの家らしい)
2011年05月19日
-

低層湿原区を歩く【箱根湿生花園】
園内は8つの区画に分けられています。こちらは3つ目の区画、低層湿原区。川や沼地、湖の周辺に見られる湿原で川や湖の色々な養分が含まれる水に潤されている湿原の事を低層湿原と言うそうです 午後から雨の予報が出ていたこの日、いたるところからカエルの鳴き声がしました。シュレーゲルアオガエルって蛙が生息してるんですね。声はすれども姿は見えず・・・(コチラで鳴き声が聞けますよ~)木製の遊歩道は歩いていても心地良い。車椅子の貸し出しもあるので身体の不自由な方でも楽しめるのが素晴らしい~♪いたるところで職員の方が作業管理されてました。これだけの膨大な敷地の植物管理・・・大変そうデス約3万平方メートルあるそうですから~気が遠くなります。アサザの池は黄色のツボミがいっぱいです。もうちょっと気温が上がらないと咲かないのかなぁ~左側は水芭蕉の群落です。開花の時期は春だった様で、今は大きな葉がワッサワッサです。水芭蕉で有名な尾瀬には、群馬県民だったワリには行った事がありませんで、故に水芭蕉も見たことがない・・・こんな近くで見れるなら、そんな時期に来てみたいなぁ♪ちなみに水芭蕉の名前の由来は大きな葉がバナナの葉の仲間のバショウに似ているからとか~アサザの池の反対側に小川が流れています。川辺に沿って緑に映える朱赤のクリンソウが咲いています。一枚の絵を見るかの様で、カメラを持つ中高年のお花好きは必ずここで立ち止まりシャッターを切りますクリンソウは日本に自生するサクラソウ科の植物のなかでは最も大型で高さは30~50cmにもなるとか花が段々に重なり咲く姿がお寺の多重塔の天辺にある【九輪】に似ていることが名前の由来だそうで。 まだまだ続く~もんね
2011年05月18日
-

落葉広葉樹林区の花【箱根湿生花園】
順路としては落葉広葉樹林区からススキ草原区と進みます。 この案内図の横に休憩所がありますがその近くに咲いていたのが クサタチバナ橘の花に似ているので名付けられたとか・・・ バイカイカリソウ イカリソウという船の錨(イカリ)に似た形をした花があります。(アトでご紹介しますね)このイカリソウの特徴が無く、小さな梅の様な咲き方をするのがバイカイカリソウ・・・清楚ぉ ヤマツツジ私の田舎の群馬ではドコに行っても見かけた気がするのがこの赤みのあるオレンジ色のヤマツツジ。すんごく懐かしかったぁ~ ヤマブキソウ花がヤマブキに似ているので命名。しかし、ヤマブキは花びらが5枚、ヤマブキソウは4枚。ヤマブキの生えている近く咲いていたりもするらしいです。 ヤマシャクヤク平地に咲くシャクヤクと比べると手の中に優しく包んでしまいたくなるような本当に慎ましい咲き方をしています まだまだ続く~
2011年05月18日
-

箱根湿生花園へ花観賞に行く
私の花の観賞撮影も度を増してきたようで、とうとう足を伸ばしてまでも花を見たいと思うようになってきて、今日は箱根にあるこちらに出かけて来ました 箱根湿生花園こちら駐車場からの入り口です。駐車料金は無料♪開園時期は3月20日~11月30日(冬季休業)入場料700円(ネットで100円割引有)本当はひとりで来ようと思っていたのだけど、暇そうな主人と、運動不足で血流の悪い長男も誘ったらま~さか!全く花なんて興味がないくせに二人とも「気分転換に行く」というので驚きでした。で、この日出発時間朝の6時半246号線を通って御殿場経由。到着は8時半で・・・開園9時前に着いてしまいました。(画像クリックしてフォト蔵特大画像で案内板がよく見れます~)箱根町仙石原にある箱根湿生花園は1976年仙石原湿原を知って貰う為、湿原環境保護の見地から設けられたものだそうで湿原をはじめとして川や湖沼などの水湿地に生息している植物を中心にした植物園です。園内には、低地から高山まで日本の各地に点在している湿地帯の植物200種のほか、草原・林・高山植物1100種が集められ、その他、珍しい外国の山草も含め、約1700種の植物が四季折々に花を咲かせています。(箱根湿生花園HPより抜粋)入出園口兼、売店や喫茶室等館内施設の集まったこの場所を通り抜けると・・・外国の山野草と園芸種のある一角紫の西洋キランソウや咲き終わって葉っぱだけになった植物が混在する中から今咲いている花と名札を照合させます。名札にはちゃんと挿し絵と説明もあって親切なつくりにはなっているんですけど~ココのはちょっとわからないのもあったなぁ イリス・クリスタータ一番先に目に入った小さなこのお花花径5~7cm、高さ7~12cmのアヤメの仲間。 コマクサ子供の頃図鑑や絵葉書で見た覚えがある高山植物ピンク色のコマクサはよく見かけるけれど赤は初めて見た気がする~ ロドヒポクシス(アッツザクラ) ナンだか普通にお花好きの庭で見かけるお花も・・・園芸品種だからね他にもありますけど、名前が判らないので次行きます~ 続く・・・
2011年05月17日
-
長男、初めての新司法試験予備試験に挑む
15日の昨日は、長男が初めて挑戦する司法試験予備試験の日この試験に合格しなければ新司法試験の受験資格を得る事さえできないのだ。新司法試験を受けるためには原則として法科大学院を2~3年修了することが条件。しかし、法科大学院入学には経済的な余裕がある者でなければ入学なんてできないそんな不公平さを無くす為に予備試験がある。予備試験をクリアすれば来年以降に新司法試験受験ができる。読売新聞の情報によれば、昨日は全国7都市の8会場で初めて実施され、6477人が臨んだという。その中のひとりに長男が含まれた。予備試験は3段階で実施され、この日はマークシートによる短答式試験合格者は7月の論文式試験に進み、同試験の合格者の中から、10月の口述試験を経て最終決定長男は、今年は合格は頭に無く力試しの為に受験した。自分独自の今までの勉強方法が正しいかどうか確認する為、今後の試験対策をどうして行くべきか。 ★★★★★★★★★★★★★★★・・・で14日の土曜日は都心に近い長男の彼女のお宅に宿泊させて貰う。15日朝、現地に8時半には着いていないとならない。試験は9時半から一般教養、民法・商法・民事訴訟法、憲法・行政法、で、5時半に終了する刑法・刑事訴訟法までの1日仕事になる。・・・てな塩梅で15日の夜も彼女のお宅にお世話になった長男16日の朝帰って来た。長男「いやぁ、驚いたよ。受験している顔ぶれ見たらさ、 オジサン、オバサンばっかりなんだ。 オレみたいな若造なんて数えるくらいだよ」私 「それって旧司法試験の残党が多いって事?」長男「そうそう、若い奴等は皆親の金アテにして 法科大学院に入るからさ」私 「オジサン、オバサンの中には家庭だってある人もいるし 仕事やりながらの人もいるだろうしね。 学校なんて行ってられないだろうしね~」長男「でね、試験監督員が試験前に言うんだ。 『カンニング等の不正行為を働いた者は 直ちに試験を中止させ、取り調べを行います』 ってさ、『取り調べ』ってもう犯罪者扱いになるの?! て笑っちゃッたよ」私「」 ★★★★★★★★★★★★★★★「今回の試験は自信のあるモノは点数は取れた でも母ちゃんの言う『ボッと合格』も無いから。 今年はもう母ちゃんに迷惑かけられないから バイトもして、教材費とデート代くらいは稼ぐからね。 試験が終わった後、どれくらい勉強したかで 来年の試験に差が付くんだから、勉強時間は無駄にできない。」長男はそう言うと帰宅したこの日もまた机に向かった。来年の新司法試験予備試験合格を目指す!
2011年05月16日
-

何コレ~?!なお花を前に・・・花知らず也
世間知らずだとは思っていましたが、花のことも何も知らない花知らずの私です。生まれてこのかた半世紀になろうとする今日この頃まで、1度も目にした事がない花が多い多い!ご覧の皆様は私より花知らず? フキカケスミレ何気に通り過ぎようとした門扉の前の小さな花壇でみつけました。先日、真っ白なスミレを見つけてビックリしたばかりなのに今度は紫のインクを吹きつけた様なこのスミレ。最近、こういう発見があると得した気分になる安上がりな毎日を送っている気がします学名をビオラ・ソロリア・フレックルスと言います。フレックルスっていうのはそばかすって意味名は体を表すカワイイネーミングですね♪ ★★★★★★★★★★★★★★★ 西洋オダマキフランス人形が着ているドレスに見えました日本のあの古風な紫色のオダマキしか頭の中にない私は、園芸品種として改良され続けているオダマキの存在はありません。優雅で綺麗ですが、花が重いのか?皆うつむいてて困りもの。カメラ目線になって欲しい~ ★★★★★★★★★★★★★★★同じうつむいていて困ったのはコチラも同じ・・・ ヒメウズ オダマキと同じ属仲間(暴走族みたい~)キンポウゲ科のオダマキ属とか。森林公園に咲いていたのだけどこれが小さくて、小さくてとてもじゃないけれど、私の安いカメラではこの辺までが限度みたいです。おまけにうつむいてるから、しゃがんで、しゃがんで、ローアングル・・・疲れる割に苦労の甲斐ない出来。草丈10~20cm、花径約5mm程の白い小さな花。小さい(ヒメ=姫)根がトリカブトに似た植物(ウズ=鳥頭)という意味の名前。 ★★★★★★★★★★★★★★★ 小判草 カワイイでしょ♪小判草(コバンソウ)っていうの。コレを最初に発見したのは13年前位の引越しした先の駐車場でみつけたのだったわ乾いてカサカサ音のする穂をフリフリすると釣り糸の様に細い枝が絡んだり、けっこう楽しい小判草~花に見えない小判の様な集まりを小花【小穂】と言います。画像をよくみると、一番左の小穂から黄色のおしべがチョコッと見えてます~(判り難かったら画像クリックしてフォト蔵で特大で見てね)小判草は花粉を風に運ばせて受粉を促す風媒花イネの仲間なんですって。だから我が家の猫娘達もコレは大好物(葉っぱがね)時期がくれば黄金に色付いた小判になるのよ~で、今回、発見したのはコレじゃなくて・・・ 姫小判草 小判草の小穂は卵形で平たく、長さ1~2cm、幅約1cmに対して姫小判草は長さ4mmほどの三角状卵形の小穂まだ穂が開き始めです。カワイイおむすび型がたくさん♪小判に姫小判、あとは大判があれば、ザックザクだね~とか思ったら・・・コチラ ★★★★★★★★★★★★★★★ さて、花の名前は検索をかければたいがいはヒットするものと、思っていたのは素人のアサハカサ、ハマヤラワ・・・この花の正体がわかりません。たんぽぽの一重っていうお方もいたり。背丈は10cm前後かな~確かに葉にはタンポポ特有の切れ込み歯の広がりは同じくロゼッタ状でもナンだかちょこっと毛深い。ツボミはつやつやしてるし、ツボミの時の花茎が赤い。花は黄色のデージーみたいだしインターネットの世界ならわからないことはないんじゃない♪と思っていたけれど・・・世界植物図鑑を兼ねているとも思えない。本当に一重のタンポポなのか?!いつかわかる日まで、一重のタンポポということに 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 5月30日より追伸一重のタンポポの正体がわかりました♪アークトセカ・カレンデュラキク科ハゴロモギク属の多年草で、別名ワタゲハナグルマ南アフリカケープ地方原産観賞用のほかグランドカバーに用いられるそ~です。タンポポはキク科タンポポ属似てるけどやっぱちょいと違ったのね~
2011年05月14日
-

雌雄異花で実が生る植物の花
単純に「花は好き♪」と言ってはいてもその生態についてはまるで知らない事が多いので驚かされることが新鮮で、楽し~い♪花っていうのは1本の花の中に雄しべと雌しべがあって、受粉して種が出来てって簡単な思考しか持ちあわせていなかった様で同じ1本でも木に咲く花にはこういうのもあるんだなぁって私にとっては新しい発見に感動だったのが下の花ですね~ オニグルミ(雄花) 山の合間の集落に住まいがあると今そこいらじゅうでこんなぶら下がった奇妙なモノを目にします。高い木の上の方にあるので間近にはなかなか見れないのですけど、勤めの行き帰りの橋の下から伸びているので橋からだとちょうど目線の高さで見ることができます。鬼胡桃(オニグルミ)の木です。「花?!なん??」(栗の木もそういえば こんなひも状のモノがぶら下がってたなぁ~)とか思いながら何気に上を見ると・・・ オニグルミ(雌花) このオニグルミは1本の木に雌雄別々の花が咲きます。キウイや銀杏の木は雌雄が別々にあるというのは知っていました。オスメスの2本ないと実が生らないんですよねオニグルミの雌花には初めて気がつきました。胡桃の木は高く伸びるのでなかなか雌花までは目が届く事はありません。今年初めて雌花を見た、というか雌花の存在があることに気がつきました。先端の赤い花が受粉すると真下の部分がぷっくり膨らんで私の大好きなクルミが生るワケですね♪子供の頃、拾った石ころで硬い殻をカチ割っておやつ代わりに食べた覚えがあります。下手な割り方をすると木っ端微塵になりましたっけ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 4月に撮影したムベです。 初めて目にしたこの花は小さなシンビジュームの様に見えるけれど目にした事のないちょっと不思議な形。ムベという存在すら知らなかったのに、「むべなるかな」って言葉は聞いた事があったり。昔々、天智天皇が(現在の)滋賀県に狩に出かけた際、子だくさんの健康な老夫婦に出会いました。「どうしたらそんなに元気なのか?」と尋ねると「無病長寿の霊果とされたこの実を食べているから」と、出されたムベの実を食べた天智天皇が「むべなるかな」(まさしくその通り)と言ったことから<ムベ>と呼ばれ以降毎年献上するようになったという伝説があるそ~です。砂糖が輸入される前は、この実を甘味の材料として使われていたとか。いにしえのお人には貴重な《甘さ》身体にも心にも良しとされた時代だったのですね ム ベ(雄花) ムベもオニグルミと同じで1本の木に雌雄別々の花をつけますアケビの実はよく目にする人は多いと思うけれどムベもアケビの仲間です。田舎に帰った時、見た覚えがあるのは実の方だった私。「あ~、アレがムベだったんだ」と、今になって思ったワケでして。出来る実もアケビと同じ形なんですが違いがございます、さてその違いとは何でしょう~正解はコチラをご覧になって。 ム ベ(雌花) 雄花が先に咲き始めるそうです。うかうかしてたら受粉し損ねるんじゃないですか~雄花と雌花の違いは・・・雌花には3つの雌ずい(めしべ)、雄花には1本の雄ずい(おしべ)があります。
2011年05月12日
-

違いの分からない女?!難しい判別
とにかく花って判別するのが大変~それが間違い探しのクイズみたいで面白いのだけど、やっぱり、ど素人だから決定!と思ってもブログみたいな公の場所で自分の考えを発表するのも気が引けるそれでも自分の検索結果を残さずにはいられない只今、花に凝り始めたくろすけでございます ★★★★★★★★★★★★★★★★★★今、満開ですね~でもこれってサツキ?あれっツツジだったっけ?!皆さんはサツキとツツジの区別ってご存知ですか?フォト蔵に花の画像をアップするのに花の名前くらいはどうしても必要だし、この数日悩みました・・・下の2枚の花の画像はサツキ?ツツジ?どっちなのぉぉぉ~!!(4月19日近所で撮影)双方とも葉っぱの大きさも形も違えば花の大きさも倍以上違う、おしべの本数も違えば花の色から咲き方、木の高さまで違う・・・不可解な花・・・ (森林公園で5月9日撮影)そもそもサツキはサツキツツジが正式名称で、ツツジの一種で同属なのだ。それはわかったけれど、ふたつに分かれるにはソレ相応の違いがあるからなのじゃないかと、思って検索し始めるとどうも画像だけだと具体的な判別には首を傾げるモノがある。・花びらの中にある斑点模様=ツツジの方が濃い・花の数 =ツツジは一つの枝に複数の花 サツキは枝先に1個(まれに2個)・ツボミにある毛=ツツジは緑色で、サツキは茶色 ・一つの枝に違った色の花をつける=ツツジ有・サツキ無・ツツジの葉の裏側は服などに付着し易い中にはツツジとサツキを確実に断定できる相違はないとか判別するるための目安はあり、 おおよその判別は可能であるが、慣習によるものが大きいとかナンだか曖昧なご意見一番肝心なのは、比べるサツキとツツジが目の前に無い。比べようがないじゃない~と、気づく。今、手っ取り早く分かりやすいのは開花時期に違いがあるということ。ツツジは4月~5月半ばに花が咲く。サツキはツツジが咲き終わる5月半ば頃咲く。春に咲く類をツツジといい、初夏より咲く類がサツキとなるそもそもサツキの名前は「皐月」旧暦の5月に咲くことからそう呼ばれる5月1日を旧暦で言うと、今年は6月2日とか。ならば6月頃咲いているのがサツキということになるまぁ、咲く場所によって違いが出るのだろうけれど、関東圏だけでで言えばそうなるのかなぁ~じゃ、今ならツツジが見れる時期なワケだわねで、ちゃんと見てみようと近所にあるつつじで満開の公園 に初めて行ってみた。 あつぎつつじの丘公園公園のツツジは、平成17年の市制施行50周年を記念し、市民の手で2年掛けて植え付けたもの。約1万7千平方メートルの敷地に7品種、約5万2千本のツツジが鮮やかな花を咲かせている。 (厚木市HPより抜粋)つつじの丘公園 posted by (C)くろすけcat★花の大きさとおしべ★でいうとツツジは大きくサツキはやや小ぶりとかでも大きさを比べるサツキがこの場にはないし~おしべの数でいうとツツジ5本~10本 サツキは殆ど5本 とかあっても例外もあるっていうこの園の中では一番小ぶりなキリシマツツジサツキなんて盆栽で見た記憶しかないし・・・この小ぶりよりは大きいのかなぁ★花葉のつき方★ツツジは先に花が咲き、その後、新芽が伸びるサツキは反対に新芽が伸びたあとに花が咲くサツキは小枝が多く出て花葉が小さいまた、葉に蝋細工のような光沢をもつ。常緑樹が多いツツジは、葉の表と裏には毛があるものが多く見られる(琉球ツツジ等例外有り)落葉性・常緑性共に有りサツキにはキメラいう赤や白などの色が混じっているもの(混色)があり、同じ植物体に遺伝子の異なる細胞が混じっているのだとか。こういうのはキメラとは呼ばないの?ヒラドツツジ posted by (C)くろすけcatということで・・・私が撮影した上の2枚の花は咲く時期を見て、ツツジということに。あんまり頭をツッコンでも専門家でも大変なツツジとサツキの広大な世界。ド素人の私が長居するトコじゃないわ~これから見られるかもしれないサツキに期待しつつココでおしまい
2011年05月10日
-

次男、初の免許更新に行く
次男が自動車免許を取得したのは2008年。わざわざ福島の郡山まで合宿に出かけてマニュアル車で取得したのにも関わらず、実際、自動車を運転したのは家族で回転寿司を食べに出かけた帰りの20分と、私に付き合って買い物に出かけた田舎道の3分の2度程しかなかったりする。私の前の車がマニュアル車で初心者が運転するのは免許を取れたとはいえ実際本道に乗り出すのは大変だろうし、そういう点では過保護な私は「じゃ、今度車を買い替える時、オートマにするから乗ればいいんじゃないの」とか、言ってたわりにオートマ車になったのに乗る時間もないのはもちろん、本人が自動車への興味が全くないこともあって結局の所、ペーパードライバーになってしまってる。それでも原付のバイクに乗って約1年。とうとう自動車免許の更新をむかえたのだった次男の洋菓子店ではこの春3人程のスタッフが辞める事になり定休日がなくなり、シフト制に変わったそうで。とりあえず、月曜日が次男の休日になった。買い物に出かけて帰宅途中、原付に乗って出かける次男に団地内で遭遇~私 「あれ?!・・・そっか、免許の更新に行くのかぁ! ちょっと~そんなカッコでいいの?!」見れば次男はヨレヨレのオレンジ色のTシャツにちょいと厚めのチェックのYシャツをひっかけた姿。私 「あなたさ~、免許の写真を撮るんだから もうちょっとマシなカッコウで行けばいいじゃない」普通、免許の写真は次の更新まで何年間かお世話になるから少しでも良く撮って貰う様に気にするモンじゃないのかと、思うんだけれど・・・そうでしょ?次男「いいよ、コレで何か変?」全くシャレッ気のない次男はそんなこと気にもならない様で・・・ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★ で、昼近くに帰ってきた次男、私の目の前に差し出したのが、シャレッ気はなくても存在する食い気でなのか?勉強熱心なのか?・・・味見をする為のケーキ厚木市内にございます洋菓子店シェ・ヒロコ(Chez Hiroko)のケーキ4点。次男「前から気になっててさ、警察署の近くだから 寄ってみたんだ~」下の他にティラミスとベイクドチーズケーキ見た目が普通過ぎるのであえて写真なしで。 レアチーズケーキ モノ的にそんなに着飾るケーキではないのですので見た目は地味~なレアチーズケーキ。こちらのお店のケーキはチーズを使ったケーキがウリなのだけあって、さすがと言う感じです。酸味と甘さが大人向け、おまけに中に洋酒漬けのチェリーがしのばせてありました。次男のお店には無いタイプです。これは美味い♪ モンブランタルト こちらはバタークリーム系のモンブランクリームまったぁ~りな舌触り、中に生クリームタルトは、基本私は甘すぎて苦手なのだわ。ベイクドチーズもティラミスもやはりチーズを使用したケーキは大人好みの味かもしれません。やっぱりイチオシされるだけの美味しさは存在しました次男よ、味見ふた口ずつでもご馳走様でした~
2011年05月09日
-

菜の花はどの花色々あれど
田舎者の私でも見たことのない野菜の花はたくさんありますが、先日、買い物に出かけた先で見つけた菜の花をご紹介致します。菜の花といえばこんな姿ですよね~でも、 《菜の花》という植物はこの世には存在しないって知ってました?《菜の花》はアブラナ科の植物の総称だって知ってました?あぶら菜・ミブ菜(京菜)・蕪・カリフラワー・クレソン小松菜・白菜・チンゲン菜・かき菜・ターツァイ・菜花野沢菜・キャベツ・西洋からし菜・ブロッコリー・葉牡丹等などどれも菜の花が咲くって知ってました?白い菜の花はご覧になった事ありますか? ダイコンの花前から何の花なのかなぁ~と思っていたけれど、まさか、大根の花だったなんて驚きでした。ちなみに・・・ ノダイコン白地に淡い紫が美しい~大根が野生化したものと言われるのが、ノダイコン、別名ハマダイコン野山に咲くのがノダイコン、海辺の浜に咲くのがハマダイコン?!ダイコンの花もわずかだけれど紫が少~し入るし真っ白って~ワケじゃない ムラサキハナナ かと思いきや、別名ハナダイコンとも呼ばれる真紫の菜の花も野原に咲き乱れていたりする。でも野菜ではないとか菜の花からダイコンの花に乗り変わってしまいました
2011年05月07日
-

次男、母の日ケーキを作る
次男「母の日は忙しいから今日ね。ちょっと早いけどハイ、食べて♪」と、勤め先の洋菓子店から帰宅した次男が差し出したのが プレゼントケーキ 悲しい事に、店から家までの移動中に絞った生クリームのツノが全部潰れたのと、ホワイトチョコのプラカードに次男の手書きで 「〇〇〇さん、いつもおつかれさま」(〇は私の名前、うちの息子二人は母親を名前で呼ぶことが多い)と、書いたのがあるのだがさすがに名前入りなのでお見せできない。薄いスポンジの台に甘酸っぱい苺とミルキーなバニラの2層のムース。上の飾りつけは店の規定のアントルメのデザインに次男が手を加えてちょいと豪華にしたらしい。店のお勧めのケーキになっているので味は抜群でございますよ♪ 先日、駅前店での仕事の帰りに自動車と衝突事故を起こした次男。乗っていた原付バイクは、修理する方が新品を買うより高くつくことになり、早く言えば、購入して1年1ヶ月程でオシャカになってしまいました。本人は運が良かった様でピンピンしています。とりあえず自腹で同じ型の色違いを購入した次男です。やっぱり自転車で7キロ半の山坂通勤は、行きは良くても、仕事に疲れての帰り道は辛いらしい。くれぐれも安全運転で頼みますよ~何はともあれ、身体に気をつけて、日々精進。頑張っている姿を見せてくれているだけで十分幸せ気分の母なのでございます
2011年05月06日
-

お久しぶりです、小梅です♪
おしゃれ?!おしゃれ1 posted by (C)くろすけcatおしゃれ2 posted by (C)くろすけcat 変な顔小梅の変な顔 posted by (C)くろすけcat ホコリ取りホコリ取り posted by (C)くろすけcat 鏡鏡 posted by (C)くろすけcat 風車風車 posted by (C)くろすけcat カーテン大好きカーテン大好き posted by (C)くろすけcatたくしあげてたるみのできたカーテンの中は小梅の秘密基地かハンモックの様になっている。カーテンのハンモック? posted by (C)くろすけcat 肩乗り猫、小梅 主人「小梅が、俺がトイレに入ると 中に一緒に入ってきて、肩に乗るんだよ。 で、最終的に・・・耳たぶ舐めるんだ」私と息子二人にはそんなことはしたことないので「ウソだ~」と言ったら携帯写真でコレが送られてきた (クサいシーンですみません)
2011年05月05日
-

同じ花?!でも何かが違う花の話
花の名前を調べようと、画像だけで判断するのはめちゃくちゃ難しかったりします例えばこのての白い花びらがたくさんある花ね。よく、恋占いとかやりませんでした?「すき~、きら~い、すき~・・・」なんて花びら1枚ずつ抜きながら エリゲロン アスファルトの間からホフク前進しながら草丈20~30cm位1.5cm程のかわいい小花を開いてました。園芸用のがコボレたんですね~この花の生まれが北・中央アメリカ本名はエリゲロン・カルビンスキアヌス(エリゲロンにも多種あってその1種です)でもいくつかある日本名の別名の方が、花の特徴がよくわかって面白いと思うのですゲンペイコギク(源平小菊)=咲き始めは白色、徐々に赤く変化する (源氏・平家の旗の色からとったのね♪) ムキュウギク (無休菊)=咲いてる期間が長い (無休で咲いてるなんて、エライ!)ペラペラヨメナ(ペラペラ嫁菜)=葉が薄くペラペラしてヨメナ(嫁菜)に似ている (ぺらぺらって~) ノースポール公園の花壇・ガーデニングされてる家歩道にに置かれたプランターとか使い勝手がいいのか、持て囃されているのがこのノースポール(北極)できた種をほったらかしても翌年また咲きその繁殖力の強さ、花つきの良さで株全体を覆うほどに咲く姿は白い北極大陸を思わせたのでしょうか?草丈は15cm~25cm、花径は3cm前後マーガレットからするとだいぶ小ぶりです。 ★★★★★★★★★★★★★★★ と、まぁここまでは名前を知らなかっただけの話なんです。でも、小学校からず~っとそうだと思って一番自信のあった花の名前が違っていたのがめちゃくちゃショック!!っていうのが道端や空き地に普通に咲いてた下の花。自信満々でマーガレットで調べると出てくるのが殆どこの花の部類一般にマーガレットとして扱われているのは、本来のマーガレットである木春菊(モクシュンギク)の園芸品種等で茎が木質化し、葉が春菊に似ている ものと、ある。一方、私がマーガレットだと思っていた花はシャスタ・デイジーと言うそうで~一昔前のマーガレット、フランス菊の子孫だったのだ。葉にギザギザの鋸歯があるのが特徴です。 シャスタ・デイジー フランス菊★ヨ-ロッパ原産で江戸末期渡来★日本の冬を越せる程の耐寒性と強い繁殖力で野生化★フランス語で《マーガレット》と呼ばれていたので 昔も、今もってそう呼ぶ人がいる(私の事じゃん)マーガレット★カナリア半島原産で明治時代渡来★越冬ができず、野生化できない★フランス地域で様々な改良がなされ種類も豊富になる★フランスで《木のマーガレット》とも呼ばれ、 日本でも《木春菊》よりマーガレットの名が定着するってことは、手っ取り早く言えばフランス菊の方が早いモンがちでマーガレットって呼ばれていたのに後から来た木春菊の方が持て囃されて名前を横取りされたってことになるの~?!う~ん・・・業界の中ではそうであってもなんだか私はまだマーガレットと呼びたい気がする・・・
2011年05月03日
-

藪から蛇なイチゴの話
花の写真を撮るのは簡単だけれど、(出来の良し悪しはともかくね)いざブログやらフォト蔵に載せようと思っても名前が判らないままは無理なので、パソコンの前で検索し続けます。そんな姿を見て長男に「花の研究家にでもなったら~?」とか、笑われているこの頃です。「だって、判らない事を放って置くのが嫌なんだもの~」(嫌な性分だとつくづく思う)見たこともない花は勿論、名前の知らない花が多い事!!調べ始めると思い違いや、種類が多い中のひとつとか画像から判断して名前にたどり着くまで貴重な休みの時間が消えていくこの頃・・・(たぶん、B型のツボにハマッた趣味を始めてしまった様だ) ★★★★★★★★★★★★★★★★★★ハイ、で、今日はヘビイチゴの花です♪子供の頃は「蛇が食べるイチゴ」「蛇が出てくる場所にあるイチゴ」「食べると毒だから食べれないイチゴ」とか、大人や友達に教わったあのヘビイチゴです。殆ど、ウソのお話ですけど田舎の田んぼじゃ、ヘビイチゴの側に蛇は出てきたからその話は多少は有りかもしれないけどさて、ヘビイチゴ(バラ科ヘビイチゴ属)には2種類あるのをご存知でした?ヘビイチゴヤブヘビイチゴがあるのです。(あ~やぶ蛇な事をしてしまってる私)私は、ヘビイチゴはヘビイチゴだけだと思ってました。なので困惑・・・私が勤めの帰宅中、撮ったのはいったいどっち?!今日、たまたま出かけた近所の観音様の敷地にたまたま偶然隣り合わせに2種類のヘビイチゴが並んで生えておりましたのよ!!あ~なんて偶然!観音様の御引き合わせ♪と、喜んでしまった私 ヘビイチゴ ヤブヘビイチゴ 画像を見て間違いさがしじゃないけれど、違いがわかりますか? ★★★★★★★★★★★★★★★★★★ヘビイチゴとヤブヘビイチゴの違いは実が生ってから見ると判りやすいそうですが、私は花から判断しなければならないのでございますね。(今は実が生ってませんもの~) ガクで見分けるイチゴのガク(萼)はお分かりになるでしょう?実の下にくっついた葉っぱの事で萼片(ガクヘン)と呼びます。ヘビイチゴ属の萼片は三角状の内萼片が5枚葉状の外萼片(副萼片)が5枚重なる2種類のガク片があるんです。花を上から見て、花弁(花びら)の下に副萼片が見えるのがヤブヘビイチゴで、花弁に隠れて副萼片が見えにくいのがヘビイチゴとなります。 葉っぱの色がヘビイチゴが黄緑、ヤブヘビイチゴが濃緑で大きめとか、ありますけど2種類のヘビイチゴ属が並んでいないと分かり難いモノです。素人目からすると花弁の形がヘビイチゴがハート型で丸みがあるヤブヘビイチゴは楕円ぽいとか見えますけどね~そこまで説明してるHPを見つけるのが大変なのでこの辺で~ ちなみに、ヘビイチゴとヤブヘビイチゴは食べても平気、そこそこ甘さはあるけど海綿質でおいしくないって試しに食べてみます?
2011年05月02日
-

世にも奇妙な花物語
花を探しながら山の中の道を歩いていると眉をしかめてしまう様な出逢いがあるのです。以前、主人と一緒の登山が趣味だった頃も山に咲く花を愛でながら登るのが楽しかったものですが、その時初めて遇ったマムシ草らしき黒く異様な花に驚愕したのを覚えています。4月に八重桜を見に行ったついでに登山道の入り口まで花探しをしてみました。その時発見したのが・・・ ミミガタテンナンショウ久しぶりに出遭ってしまったの水芭蕉は白、カラーなんて白・黄・ピンクと様々でマムシ草もこのミミガタテンナンショウも同じサトイモ科のお仲間なのに色が黒っぽいというだけで異様さを感じさせるのは何故でしょう?筒の口のふちに幅広い耳たぶ状の部分があるのわかりますか?これが耳型天南星(ミミガタテンナンショウ)の特徴のひとつ。<天南星>とは中国で夜空に広がる星の意味をあらわすそうで。花言葉が【壮大な美】というのはココからきているのかなぁ(沢の土手にあったのでこの向きでしか撮影できなかったの~) ★★★★★★★★★★★★★★★★★★先日出かけた森林公園で見かけたのがやはりサトイモ科の仲間でした。 ウラシマソウ浦島草 posted by (C)くろすけcat私が前回、森林公園に3度も行ったといううちの2回分はこのウラシマソウと呼ばれる植物のせいで・・・最初は上の画像を撮って帰ってきてしまいました。よく見ると花の開口部から太いモノが伸びてるでしょ、「何コレ?!」で、調べて「え~?!そんなのあったのぉ!!」で、もう一度お出かけしたって訳です。植物の事を知らないとこういう手間もかかると、いう教訓を得ました、ハイ。 回想 posted by (C)くろすけcat私が森林公園に2度見に来たのは、口から伸びるモノがこんなに長いとは、確認しなかったからなのです。1度目はついでにちょっと寄っただけでさっさと帰っちゃったし、ちょうど雑草の間にあったから目に入らなかったのかなぁ~2度目に行ったらそこいらじゅうに咲いてました、ウラシマソウ。素人の私から見て1枚の花びらで包まれた様に見えるのは仏炎苞(ぶつえんほう)と呼ばれる穂や花などを包む大きな包葉で本当の花は仏炎苞の中に隠されているそうで(水芭蕉は見えているんですけどね)それは肉穂花序(にくすいかじょ)と呼ばれ、多肉な花軸の周囲に柄のない花が多数密生するものを言います。その花序の先の付属体が長く外へ伸びて垂れるのですっ。(まるで学校の教科書の様だわぁ~)それも長いのは50~60cmと超ロングにもなるっていうから凄いでしょ~(長い付属体の全体が見えないと言う方は画像クリックしてフォト蔵で 特大画像にして見てみましょう~)浦島草 posted by (C)くろすけcat私が愉快だなと思ったのは、名前の由来ですねウラシマソウが、かの有名な浦島太郎が釣り糸を垂れている姿に見えたから~と、いうお話。確かに・・・葉の高さは花よりも高く伸びるので私には海辺の松の木陰に座り、釣り糸を垂れる浦島太郎の姿が想像できますよ~しかし・・・何故ここまで付属体が長くなる必要があるのか???ドコにも説明がありません。誰か私の疑問にお応えできる方がいらっしゃらないかなぁ~花言葉も 【不在の友を思う】【注意を怠るな】【過ぎ去った日々】【懐古】【回想】と、何やら名前からついたであろう浦島草(ウラシマソウ)らしき言葉ばかりです。ウラシマソウの成長がよくわかるので良かったら見てね~♪コチラ
2011年05月01日
全20件 (20件中 1-20件目)
1