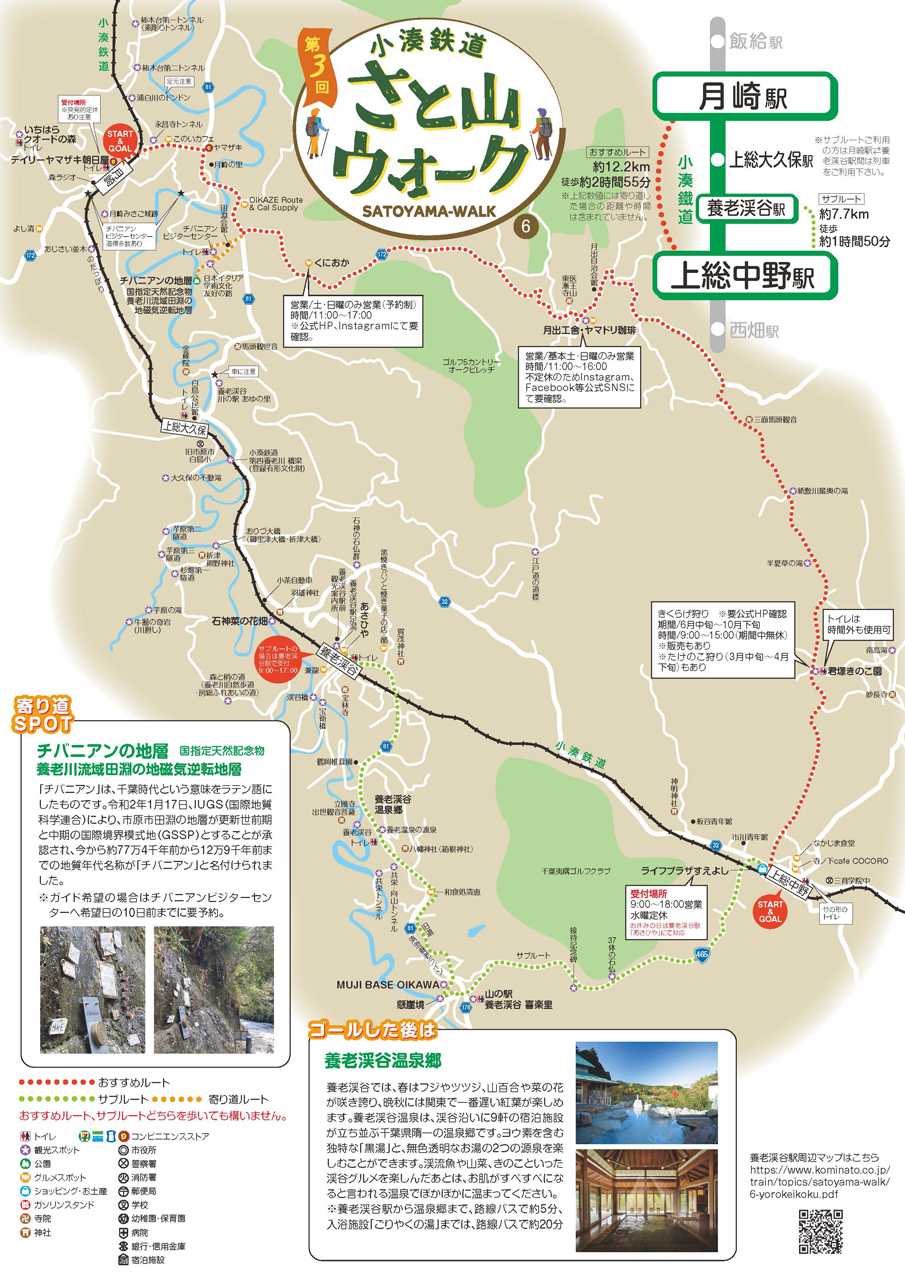2012年05月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
破産会社の敷金放棄が無償行為にあたるとされた事例
1 破産会社が賃貸人に対し,保証金(敷金)を放棄して賃貸借契約を解除することが,破産法160条3項の無償行為に該当するとされた事例 2 保証金(敷金)の返還請求を放棄することにより賃貸借契約を即時解約することができる旨の合意がされていた場合において,破産管財人による破産法53条1項に基づく賃貸借契約の解除により保証金返還請求権が消滅するものとは解されないとされた事例(東京地判平成23年7月27日)「事案の概要」破産会社Aの破産管財人Xが,建物の賃貸人であるYに対し,破産法53条に基づいて賃貸借契約を解除したとして,建物賃貸借に係る保証金(敷金)預託契約の終了に基づき,保証金の返還を求めた。A・Y間の賃貸借契約(本件賃貸借契約)には,保証金を放棄することにより即時契約を解除する旨の条項(本件放棄条項)があるところ,AはYに対し,本件賃貸借契約を解除する旨の意思表示をし,その5日後,破産手続き開始申立をして同日破産手続開始決定を受けたという事情があった。 Xは,Aによる本件賃貸借契約の解除が「破産者が支払停止があった後又はその前6月以内にした無償行為」(破産法160条3項)に該当するとして否認する旨主張した。これに対しYは,本件賃貸借契約には破産手続開始の申立てにより解除された場合には,AはYに対して保証金残金を請求することができない旨の条項(本件制限条項)が存在したとして無償行為該当性を争った。 また,Xは,前記の否認により無償行為前の状態に服した本件賃貸借契約に基づく法律関係につき,破産法53条1項に基づく解除を主張した。Yは,同項に基づく解除にも本件放棄条項が適用されるから,Xが即時解除するには保証金返還請求権を放棄する必要があると主張した。「判旨」1 AがYに対して保証金残金の返還請求権を放棄して本件賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした行為は,Aが支払停止等の前6か月以内にした無償行為に当たる。2 本件放棄条項は合意に基づく解約権(約定解約権)の行使を定めたものと解され,Xによる破産法53条1項に基づく解除権の行使についての要件とは解されない上,同項は,契約の相手方に解除による不利益を受任させても破産財団の維持増殖を図るために破産管財人に法定解除権を付与し,もって破産会社の従前の契約上の地位よりも有利な法的地位を与えたものと解されることをも併せ考えると,Xによる上記の解除により,保証金残金の返還請求権が消滅するものとは解されない。 1について,本件では,破産手続開始申立てをしたAのYに対する保証金返還請求権は,実質的に価値がないから,同請求権を放棄する行為は無償行為に当たらないのではないかが問題となった。本判決は,本件制限条項につき,借地借家法28条の規定の趣旨に反して建物の賃借人に不利なものであるから,同法30条により無効であるとし,この判断を前提とすれば,保証金返還請求権は経済的価値があるから,これを放棄する行為は無償行為にあたると判示したものである。 判例時報2144号 99頁
2012.05.28
-
労働契約上の安全配慮義務違反による損害と弁護士費用
労働契約上の安全配慮義務違反による損害と弁護士費用(最判平成24年2月24日) 「事案の概要」Xは,Yに雇用され,工場においてプレス機の操作に従事していたところ,同プレス機に両手を挟まれて両手の親指を除く各四指を失う事故にあった。同事故は,Yが労働契約上の安全配慮義務に違反したことにより発生したものである。Yは訴訟追行を弁護士に委任した上で,Yに対し,債務不履行に基づく損害賠償請求等を求める本件訴えを提起した。一審は弁護士費用も損害と認めたが,原審は弁護士費用を損害と認めなかった。「判旨」労働者が,使用者の安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償を請求するため訴えを提起することを余儀なくされ,訴訟追行を弁護士に委任した場合には,その弁護士費用は,事案の難易,請求額,認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り,上記安全配慮義務違反と相当因果関係に立つ損害というべきである。 不法行為の被害者が損害賠償を請求するため訴訟追行を弁護士に委任した場合には,相当額の弁護士費用を請求することができるとするのが確立した判例である(最判昭和44年2月27日)。 本判決は,労働者が使用者に対し,安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償を請求する場合,その主張立証すべき事実が不法行為に基づく損害賠償請求の場合とほとんど変わらず,弁護士に委任しなければ十分な訴訟活動をすることが困難な類型に属する請求権であることを根拠に,弁護士費用の請求を肯定した。 本判決はあくまで労働契約上の安全配慮義務違反について判示したものであるが,その説示に照らすと,労働契約以外の法律関係において安全配慮義務違反の債務不履行があった場合にもその射程は及ぶと思われる。他方,安全配慮義務違反以外の債務不履行が問題となっている場面については,その射程は及ばないと思われる。 判例時報2144号89頁
2012.05.23
-
破産者による不法原因給付について、破産管財人の不当利得返還請求の可否
破産者による不法原因給付について、破産管財人の不当利得返還請求の可否 (東京地判平成24年1月27日)「事案の概要」本件は、訴外会社が無限連鎖講防止法及び出資法に違反する事業を行い、その後破産手続開始決定が行われたところ、同事業は公序良俗に違反し無効であるとして、訴外会社の破産管財人であるXが、本件事業に参加することで金員を得た元会員Yに対して、不当利得に基づき、Yが本件事業により受領した金員と本件事業で出捐した金員の差額の返還を求めた事案である。Xは、破産管財人が、破産債権者全体の利益を代表して総債権者に公平な配当を行うことを目的として破産者に帰属する財産について、破産者に代わって管理処分権を行使する者であり、破産者とは独立の法主体であるから、民法708条(不法原因給付)は適用されないと主張した。 「判旨」本件事業が無限連鎖講防止法で規定される無限連鎖講に当たり、同法が無限連鎖講の開設等を禁止している趣旨や、違反者に刑罰が科されること等を考慮した上で、本件事業に係る契約は無効であり、本件事業に係る契約に基づく破産会社のYに対する金銭の交付には法律上の原因がないと認定した。しかし、総債権者のために破産財団に属する財産を管理する破産管財人が破産財団に属する債権を行使する場合であっても、破産者が破産開始決定前に当該債権を取得した時から不法原因給付により返還請求権が否定される場合には、破産管財人よる不当利得返還請求権は、民法708条により許されないと判示してXの請求を棄却した。判例時報2143号101頁
2012.05.18
-
法律上の親子関係はあるが自然的血縁関係がない子に対する養育費の支出につき不当利得返還請求できるか
夫が,妻の不貞相手の子であることを知らずに実子として養育した子につき支出した養育費相当額について,妻に対する不当利得返還請求権が認められなかった事例(東京高裁平成21年12月21日判決) 「事案の概要」XとYとは元夫婦である。Yは婚姻後,不貞相手の子Zを出産したが,Xはこれを知らされないままZを自己の実子として養育し,20年近くたってからZが実子でないことを知った。XはYに対し離婚訴訟及びこれに伴う損害賠償請求訴訟を提起し(前訴),前訴ではXのYに対する慰謝料600万円が認められた。前訴確定後,XがYに対し,<1>嫡出子として養育してきたZが不貞相手の子であったこと自体について,不法行為に基づく慰謝料1500万円の賠償及び<2>20年にわたってXがYに交付したZの養育費1800万円の不当利得返還を求めた。「判旨」<1>については,前訴と実質的に紛争の実体が同一で紛争を蒸し返すものであり,信義則に反して許されないとして,訴えを却下した。<2>については,以下の理由で請求を棄却した。1.Xは,婚姻費用の一部として,婚姻期間継続中に嫡出推定を受けるZについての養育費を支払っていたのであるから,養育費は,法律上の原因に基づいて支払われていたものである。2.養育費はZの養育に投じられたものだからY自身は利得していない。3.不当利得の法理は,一方が利得し他方がその結果損失を被っている状態を放置しておくことを正当としない違法状態を是正しようとするものであるところ,Xは約20年間Zと良好な親子関係を形成し,Zを1人の人間として育て上げたのであり,その過程では自らの経済的負担のいわば対価として,Zから金銭には代えられない無上の喜びや感動を与えられたものであるから,養育費を投じた結果に,不当利得の法理により是正しなければならない違法な不均衡状態があると解することはできない。判例タイムズ1365号 223頁
2012.05.01
全4件 (4件中 1-4件目)
1