2019年07月の記事
全15件 (15件中 1-15件目)
1
-

ザ・フー 「アイ・ソー・ハー・スタンディング・ゼア(I Saw Her Standing There)」ほか
偉大なるザ・フーの名曲・名演集(その4) ザ・フー(The Who)の名曲・名演を不定期更新でお届けしていますが、今回は同じイギリスから出たバンドであるザ・ビートルズのナンバーのカバーを取り上げてみたいと思います。巷ではイギリスの“3大バンド”とか“4大バンド”とかいう形で、ビートルズとザ・フーは一緒に語られたりしますが、そのザ・フーによる、ビートルズで有名な曲のカバーという趣旨です。 まずは、1982年のライヴのアンコールでビートルズのカバーを披露しているところをご覧ください。「アイ・ソー・ハー・スタンディング・ゼア(I Saw Her Standing There)」と「ツイスト・アンド・シャウト(Twist and Shout)」を連続して演奏しています。 続いては、よく見えないレベルの画質ですが、いわゆるレア映像というやつです。1979年のロッキュメンタリー(ロック+ドキュメンタリーの造語)映画『キッズ・アー・オールライト』のアウトテイク映像とのことです。「アイ・ソー・ハー~」を演奏しているところで、映像が撮られたのは1977年だそうです。 最後にもう一つ。もともとビートルズのものもカバーだったわけですが、再び「ツイスト・アンド・シャウト」です。1989年のライヴの模様です。 ↓ザ・フーのベスト盤(今回取り上げた曲が含まれているわけではありません)↓ 【メール便送料無料】ザ・フー / マイ・ジェネレイション〜ザ・ヴェリー・ベスト・オブ・ザ・フー[CD]↓元のビートルズの演奏が収められたアルバムです↓ プリーズ・プリーズ・ミー/ザ・ビートルズ[CD]【返品種別A】 下記のブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、バナーをクリックお願いします! ↓ ↓
2019年07月30日
コメント(0)
-

380万アクセス御礼
本ブログの累計アクセス数が3800000件を超えました。日々、多くの方々にアクセスいただいた結果です。この場をお借りして、あらためてご覧のみなさまに感謝いたします。400万アクセスに向けて、引き続きよろしくお願いします。 以下のブログランキングに参加しています。お時間の許す方は、 クリックで応援よろしくお願いします。 ↓ ↓ ↓
2019年07月29日
コメント(0)
-

ラムゼイ・ルイス 『テキーラ・モッキンバード(Tequila Mockingbird)』
ファンクさを感じるクロスオーバー盤 フュージョンやクロスオーバーといった流れは、1960年代後半から1970年代にかけて展開していった。少なくともジャズの側から見れば、電気楽器が導入され、他ジャンルの音楽が取り入れられていくことで、新たな音楽が生み出された一方、“耳障りがよい”あるいは“大衆迎合的な”音楽として批判も受ける。 確かに、猫も杓子もクロスオーバーみたいな時代があった。けれども、その中には、それに飛びついたアーティストもいればそうではないアーティストもいた。1960年代から80年代にかけてとりわけ数多くの吹込みを残しているラムゼイ・ルイス(Ramsey Lewis)は、後者の部類で、彼がやろうとしていたことに時代が追い付いていったタイプだったのではないかと思う。 分類するならば“ジャズ・ピアニスト”ということになるのだろうけれど、当初からR&B色あるいはファンク色の強いピアノ奏者だった。1960年代後半、モーリス・ホワイト(後のアース・ウィンド・アンド・ファイアーのリーダー)をドラマーとして活動しており、1970年代に入ると今度はモーリス・ホワイトがラムゼイ・ルイスのアルバムをプロデュースしたりということがあった。こうしたことからも、ジャンルで切り分けがたい行き来があったことがよくわかる。 本盤のプロデュースは、EW&Fのメンバーだったラリー・ダンが担当している。耳障りがよく、お洒落なBGMにも最適な1枚といった仕上がりになっているが、随所でなるほどファンクにきまっている。そのファンクな部分というのは、上述の通り、“付け焼刃”ではなくて、ラムゼイ・ルイス自身がずっと維持してきたノリでありグルーヴなのだろう。言い換えると、彼が時代に適合していったというよりは、時代が彼に追いついてこういう作品が生まれることになったのだろうという気がする。筆者はこういう傾向の音楽はあまり得意ではなく、たまにしか聴かないし、ラムゼイ・ルイスの多作な作品群もその一部しか知らない。でも、この人の作品を聴くにつけ、うわべだけではないプロフェッショナルぶりと、それがプロデュースも含めうまく作品に昇華されたことの絶妙さを感じる。筆者の中では、本盤はそうした感覚を与えてくれる1枚だったりする。[収録曲]1. Tequila Mockingbird2. Wandering Rose3. Skippin'4. My Angel's Smile5. Camino El Bueno6. Caring For You7. Intimacy8. That Ole Bach Magic1977年リリース。[パーソネル]Ramsey Lewis (p, elp, harpsichord, syn)Ron Harris (b, 2, 4, 5, 6, 7)Verdin White (b, 1, 3, 8)Keith Howard (ds, 2, 4, 5, 6, 7)Leon Ndugu Chancler (ds, timbales, 1; ds, perc, 8)Fred White (ds, 3)Byron Gregory (g, 2, 4, 5, 6, 7)Al McKay (g, 1, 3, 8)Johnny Graham (g, 8)Derf Reklaw Raheem (perc, 2, 4, 5, 6, 7)Philip Bailey (perc, 1; conga, 3, 8)Victor Feldman (elp, perc, 3)Eddie Del Barrio (elp, 8)Larry Dunn (syn prog, key, 1, 8)Ronnie Laws (ss, 1)Ernie Watts, George Bohannon, Oscar Brashear (horns, 1, 3, 8) Eddie Del Barrio, Larry Dunn (horn arr,1, 3, 8)Bert DeCoteaux, Ramsey Lewis (rhythm arr, 2, 4, 5, 6, 7)Bert DeCoteaux (strings & horn arr, 2, 4, 5, 6, 7)George Del Barrio (strings arr, conductor, 1, 3, 8) [期間限定][限定盤]テキーラ・モッキンバード/ラムゼイ・ルイス[CD]【返品種別A】 下記ランキングに参加しています。 お時間のある方は、“ぽちっと”応援お願いいたします! ↓ ↓
2019年07月26日
コメント(0)
-

スティーヴ・キューン 『スリー・ウェイブズ(Three Waves)』
若きキューンの二重丸推奨盤 スティーヴ・キューン(Steve Kuhn)はニューヨーク市出身のピアニストで、1938年生まれだから御年81歳である。ジョン・コルトレーンのカルテットなどで活躍したほか、ストックホルムへの移住、1990年代以降はヴィーナスへの吹込みなど日本でもなじみのピアノ奏者であろう。そんな彼の初リーダー作(ただしサイドマンとしての吹き込みはそれ以前にもある)とされるのが、1966年録音の『スリー・ウェイブズ(Three Waves)』である。 キューンについては、“エヴァンス派”などといった表現で、ビル・エヴァンスの影響や彼に似たスタイルがしばしば引き合いに出される。でも、キューンの愛好者からすると、おそらくこれは不本意で、違うところがもっと耳についていいという意見が出てくるのではないか。そんなことを考えた場合、初期のキューンは“無骨”という言い方がよくなされたりもする。確かに、硬質な感じのピアノのタッチと響きは本盤では特に印象的である。この点は、エヴァンスとも、彼自身の後の録音(ヴィーナスへの吹込みなど)からイメージされがちなキューン像とも違っていて、個人的には、これがよかったりする。 そんなわけで、本盤は私的名盤に数えたくなる一つなのだが、強いて物足りない点を挙げるならば、各曲の演奏があまり長くない点(最も長尺なのは3.の6分弱と6.の7分弱の2曲で、他の曲の中には2分台の演奏曲も多い)であろうか。個人的に聴きどころとして挙げたいのは、反復的なフレーズがやたらと耳に残る1.「アイダ・ルピノ」、とにかくピアノに注目の6.「スリー・ウエィブス」、アグレッシヴな勢いが感じられる8.「ビッツ・アンド・ピーセズ」。目立つものを挙げるとなると、文字通り目立った演奏を挙げてしまうことになるのだけれど、緩急のめりはりがついているのも本盤の優れた点だと思う。[収録曲]1. Ida Lupino2. Ah, Moore3. Today I Am A Man4. Memory5. Why Did I Choose You?6. Three Waves7. Never Let Me Go8. Bits and Pieces9. Kodpiece[パーソネル、録音]Steve Kuhn (p), Steve Swallow (b), Pete La Roca (ds)1966年録音。 【輸入盤】Three Waves [ Steve Kuhn ] ブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、ぜひ“ぽちっと”お願いします。 ↓ ↓ ↓
2019年07月23日
コメント(0)
-

ザ・フー 「アイム・ア・ボーイ(I’m A Boy)」
偉大なるザ・フーの名曲・名演集(その3) ザ・フー(The Who)のナンバーを動画とともに取り上げるシリーズですが、前回更新に続けてこの第3回です。前回と同様、最初期のお気に入りナンバーをもう一つ取り上げてみたいと思います。 「アイム・ア・ボーイ(I’m A Boy)」という曲ですが、オリジナル・アルバムには収録されず、デビュー間もない1966年にシングルとして発表されました。後には、コンピ盤(『フーズ・ミッシング』)、ライヴ盤(『ライヴ・アット・リーズ』の25周年拡充版)、ベスト盤(『ザ・シングルス』や『フーズ・ベター・フーズ・ベスト』)などいろんなところで公表されています。まずは、当時のプロも映像をご覧ください。 もう一つ、この曲の別ヴァージョンなるものをお聴きください。1971年のベスト盤に収録されたものですが、録音は当初のものの少し後になされたとのことで、テンポを少し落としてフレンチホルン入りのステレオ・ミックスというものです。 ちなみに、ザ・フーは後に『トミー』や『四重人格』のようなコンセプト盤(ロック・オペラ)を発表していますが、この曲は、P・タウンゼントが発案した『クアッズ』なるミュージカルの一部になる予定の曲だったとか。未来の西暦2000年(とっくに過ぎてしまった!)を舞台として、男女が産み分けられる世になったものの、4人の女の子のはずが1人は男の子が生まれてくる、という設定だったとのことです。これを聞くとこの曲のテーマもなるほどといったところではないしょうか。[収録アルバム]The Who / Meaty, Beaty, Big & Bouncy(1971年)The Who / Who’s Missing(1985年)ほか [枚数限定][限定盤]アイム・ア・ボーイ/イン・ザ・シティ/ザ・フー[SHM-CD][紙ジャケット]【返品種別A】 【メール便送料無料】ザ・フー / アルティメイト・コレクション[CD][2枚組][期間限定盤(3ヵ月限定特別価格)]【K2018/12/5発売】 ライヴ・アット・リーズ +8/ザ・フー[SHM-CD]【返品種別A】 ブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、ぜひクリックをお願いします。 ↓ ↓ ↓
2019年07月21日
コメント(0)
-

ザ・フー 「キッズ・アー・オールライト(The Kids Are Alright)」
偉大なるザ・フーの名曲・名演集(その2) ザ・フー(The Who)のナンバーを不定期更新の記事として取り上げています。今回はその第2回ですが、ザ・フーと言えばファースト作の『マイ・ジェネレーション』(1965年リリース)のイメージが強いという方も多いかと思います。同盤の表題となった有名曲は以前に取り上げていますので(参考過去記事)、今回は同盤所収の同じく代表曲である「キッズ・アー・オールライト(The Kids Are Alright)」です(余談ながら、その当時の表記は「キッヅ・アー・オールライト」だったそうで、時代を感じさせます)。 まずは、往時の演奏を往時の写真と共にご覧ください。1968年の演奏です。 ザ・フーは、ローリング・ストーンズやビートルズと並べて“3大バンド”とか、キンクスを加えて“4大バンド”とかに数えられたりします。当時のザ・フーを振り返ると、確かにこの曲なんかは、ビートルズと並べてもっと語られてもいいのかなという気がしたりします。 とはいえ、ビートルズと違う(そしてストーンズと共通する)のは、ザ・フーは今も現役というところです。確かに活動が止まった時期もあったし、最近ではロジャー・ダルトリーが“数年のうちに声が出なくなるだろう”みたいなことを発言したりしていますが、キース・ムーン(ドラム)の死(1978年)を乗り越え、ここまで活動しているのは並大抵ではありません。 そのようなわけで、直近ではありませんが、21世紀なってからの映像ということで、ロイヤル・アルバート・ホールでのライヴをご覧ください。 [収録アルバム]The Who / My Generation[英盤],The Who Sings My Generation[米盤] (1965年リリース) 下記のブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、バナーをクリックお願いします! ↓ ↓
2019年07月19日
コメント(0)
-

スタン・ゲッツ/ジョアン・ジルベルト 「イパネマの娘(The Girl from Ipanema)」ほか
ジョアン・ジルベルト追悼 もう1週間以上前(2019年7月6日)のことですが、ジョアン・ジルベルト(João Gilberto)が亡くなりました。享年88歳で、何年か前から体調を崩していて自宅で亡くなったとのことです。ミト(神話、伝説を意味するポルトガル語)と呼ばれ、アントニオ・カルロス・ジョビン(1994年に67歳で逝去)と並んでボサノバ(ボッサ・ノヴァ)のパイオニアとして知られた人物です。 1950年代後半からボサノバは人気が高まっていきましたが、1960年代に入ってジョアン・ジルベルトとスタン・ゲッツのコラボ作『ゲッツ/ジルベルト』が吹き込まれ、米国や世界でヒットします。これと前後して特にジャズ界ではボサノバが大きなブームを引き起こしました。本ブログでは、この盤を過去に取り上げているということもあり、以下、ジョアン・ジルベルト追悼ということで、同盤から3曲ばかりピックアップします。 まずは大ヒット曲となった「イパネマの娘(The Girl from Ipanema)」です。女性ヴォーカルは当時、彼の妻(後に離婚)だったアストラッド・ジルベルト。決して歌がうまいタイプではないかもしれませんが(とはいえこれが初レコーディングだったとか)、心に染み入る歌声です。 ちなみにこの曲は有名でも、イパネマがいったい何なのだかはあまり知られていないような気がします。イパネマというのは地名なのですが、リオデジャネイロ南部のビーチで、ついでながら、コパカバーナ(こちらは有名なビーチですね)との境辺りは地元では“コパネマ”と呼ばれたりもするのだそう。 さて、次の曲は「デサフィナード(Desafinado)」です。アフィナード(afinado)が“調律された”という意味ですので、その反対を指すデサフィナードというのは、“音程の外れた”という意味だったりします。こちらも有名な曲(本録音の前にスタン・ゲッツはチャーリー・バードと共にこの曲を取り上げています)ですが、単にヒット曲とか有名曲というのではなく、ジャズのスタンダード・ナンバーとして親しまれることになりました。 最後は、『ゲッツ/ジルベルト』の中で密かな一押しと思っている曲です。アルバム最後に収められた「ヴィヴォ・ソニャンド」です。同盤の中では、ゲッツとジルベルトがもっとも美しく融合している演奏と歌ではないかという気がしていたりします。 ボサノバのレジェンド、ジョアン・ジルベルトのご冥福をお祈りします。[収録アルバム]Stan Getz and João Gilberto (featuring Antônio Carlos Jobim) / Getz/Gilberto(1963年録音)↓『ゲッツ/ジルベルト』です。↓ ゲッツ/ジルベルト/スタン・ゲッツ[SHM-CD]【返品種別A】↓こちらは続編となるライヴ盤。↓ ゲッツ/ジルベルト#2 +5 [ スタン・ゲッツ&ジョアン・ジルベルト ] 次のブログのランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、クリックで応援をよろしくお願いします! ↓ ↓
2019年07月16日
コメント(0)
-

INDEXページの更新
INDEXページ(ジャンル別、アーティストのアルファベット順)を更新しました。ここ最近の記事を追加しています。INDEXページへは、下のリンク、もしくは本ブログのトップページ右欄(フリーページ欄)からお入りください。アーティスト別INDEX~ジャズ編(A-G)へ → つづき(H-M)・つづき(N-Z)アーティスト別INDEX~ロック・ポップス編(A-B)へ → つづき(C-D)・つづき(E-I)・つづき(J-K)・つづき(L-N)・つづき(O-S)・つづき(T-Z)アーティスト別INDEX~ラテン系ロック・ポップス編(A-L)へ → つづき(M-Z)アーティスト別INDEX~邦ロック・ポップス編へ 下記ランキングに参加しています。応援くださる方は、各バナー をクリックお願いします! ↓ ↓ にほんブログ村 : 人気ブログランキング:
2019年07月15日
コメント(0)
-

渡辺美里 「10 years」
“10年ひと昔”と言いますが… いきなりですが、これをお読みの方にとって“10年”とはどんな時間でしょうか。10代や20代の若者にとって、10年というのは想像しにくく、相応に長い時間だろうと思います。でも、もっと長く生きてきた人にとっては、ある種イメージしやすいまとまった時間単位と言えるかもしれません。要は、10歳の時に20歳の自分、20歳の時に30歳の自分は容易に想像しがたいですが、40歳や50歳にとって10年後の自分ははるかに想像しやすいものでしょう。 最初にこの曲を聴いたときは、筆者も10年なんて単位でまだ物事が考えられなかったのですが、気がつくと10年前が“ついこの間”とすら思えることも増えてきました。先日ふと耳にしてこの曲の存在を思い出し、落ち着いて聴いてみたので、本ブログでも取り上げようと思った次第です。 渡辺美里と言えば、小室哲哉作曲のイメージが強いかもしれませんが、この「10 years」は大江千里の作曲です。メロディも素晴らしいですが、注目したいのは作詞です。渡辺美里は早い段階から作詞を結構手掛けており、この曲の頃はほぼすべての発表曲を作詞していたようです。冒頭に書いた筆者の凡人的感性とは違い、発表当時21歳だった渡辺美里は、この頃から10年単位でものが見えていたということになるでしょうか。そう思うと、物事を広く見通し、そしてそれを詞にすることができる感受性の高い21歳だったということになります。 以下、映像です。まずは往時のライヴの様子から。1989年、東京ドームでのライヴでの歌唱です。 正直、歌のうまさで聴かせるタイプというよりは、勢いで迫るタイプという印象を持っています(17歳でコンテスト受賞時にセックス・ピストルズが好きと言っていたそうですが、何となくわかる気がします)。ともあれ、渡辺美里と言えば西武球場(後に西武ドーム)で20年連続ライヴをやったことでも知られています。 最後は、比較的最近の映像も見ておきたいと思います。2年前(2017年)のものをご覧ください。“10年”を5回重ねた年齢に達した渡辺美里ということになりますが、スターダスト・レビュー(さすがにベテランという貫禄の演奏です)との共演による「10 years」です。 [収録アルバム]渡辺美里 /『ribbon』(1988年リリース) ribbon [ 渡辺美里 ]↓昨年(2018年)、30周年記念エディション(リマスター、ボーナストラック入り)が出ているようです。↓ ribbon -30th Anniversary Edition-/渡辺美里[Blu-specCD]通常盤【返品種別A】 下記ランキングに参加しています。 お時間のある方、応援くださる方は、“ぽちっと”よろしくお願いします! ↓ ↓
2019年07月14日
コメント(0)
-

RCサクセション(忌野清志郎) 「アイ・シャル・ビー・リリースト(I Shall Be Released)」
本音が言える社会… 世の中、政治が話題になっている時期だからという訳ではないのですが、少し前から思い出したように聴いているナンバーを、突発的ですが取り上げてみたいと思います。 「アイ・シャル・ビー・リリースト(I Shall Be Released)」は、ザ・バンドによる演奏(参考過去記事)がよく知られていますが、ボブ・ディランが作ったナンバーです。元の詞は、刑務所の中の人物が1人称になっていて(表題は“われは解放されるべし”といった意味)、その内容は様々な解釈がなされてきているようです。 1980年代後半、これに日本語詞を付けてカバーしたのが、RCサクセションの忌野清志郎(2009年没)でした。その詞の内容は、多義性や多様な解釈の余地のない、実にストレートなものでした。少しだけ引用すると、“頭の悪い奴らが 圧力をかけてくる”、“はめられて消されたくはない”、“頭のいかれた奴らが世の中を動かして、このオレの見る夢を力で押さえつける”といった具合。詞の中ではいちおう未来の希望も示されていて、“日はまた昇るだろう、このさびれた国にも”、“いつの日にか自由にうたえるさ”というもの(ちなみにいちばん最後だけは“自由に”ではなく、“自由を…”と歌っています)。 このカバーが発表されたのは、今からもう30年も前の話ですが、社会は何にも変わっていない気がします。否、言論の自由という意味では後退すらしているかもしれないと懸念したくもなります。“本音と建前”は昔からあったのでしょうが、何かと説明責任が求められるご時世となり、近頃では、いっそう本音が包み隠される傾向すらあるように思えてしまいます。表面的には美辞麗句で飾りつつ、裏でこそこそと行動し、上に忖度して変なことを押し通す大人が闊歩できる社会になってしまうならば、本音を言いたい人は結果的に押さえつけられてしまう。波風を立てたくない大人は、あえて本音を言わなくなり、結果的に多様な見方や違った見解に不寛容な世の中へと向かっていってしまう…。未来を予言したわけではないでしょうが、キヨシローという人は、あの当時の体験を通してそんなことを見据えていたんでしょうかね。 ともあれ、歌のシーンを2つご覧ください。1つめは、ライヴ盤となった1988年のライヴ(日比谷野外音楽堂)の映像、2つめはチャボ(仲井戸麗市)とのデュオでのテレビ共演の映像です。 [収録アルバム]RCサクセション / 『コブラの悩み』(1988年リリース) コブラの悩み/RCサクセション[CD]【返品種別A】 下記のランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、バナーをクリックして応援いただけると嬉しいです! ↓ ↓
2019年07月13日
コメント(0)
-

ブルース・スプリングスティーン 『ウィ・シャル・オーヴァーカム:ザ・シーガー・セッションズ(We Shall Overcome: The Seeger Sessions)』
アメリカン・ロック界のボスによる初のカバー盤 ブルース・スプリングスティーン(Bruce Springsteen)と言えば、1970年代の『明日なき暴走(ボーン・トゥ・ラン)』、1980年代の『ボーン・イン・ザ・USA』のようなロック・アルバム然とした作品が代表作と言えるのは確かである。とはいえ、米国ロック界の“ボス”と呼ばれる彼は、突如作風を変えたりする。自宅録音で弾き語り調の『ネブラスカ』(1982年)なんかはその例だったし、今回取り上げる『ウィ・シャル・オーヴァーカム:ザ・シーガー・セッションズ(We Shall Overcome: The Seeger Sessions)』は、彼がロックの王道から外れた盤としては突出した例と言える。 通りいっぺんの言い方をするならば、スプリングスティーンにとって初のカバー・アルバムである。取り上げているのは、フォーク・シンガーのピート・シーガー(1919~2014年)の楽曲である。公民権運動に関わったピート・シーガーのスタンスとか政治的・信条的な側面をスプリングスティーンと関連付けることもできるだろうが、実際にアルバムを聴いてみると、“音楽(音を楽しむ)”を地で行くような演奏や歌が何より印象的なアルバムに仕上がっている。 とはいっても、アメリカン・ロック界のボスの歌声がスティール・ギターやバンジョーなどの中で軽快に踊っている姿は想像しにくいかもしれない。しかし、スプリングスティーンの根は結局のところ、フォークやカントリー、ブルーグラスといった米国トラディショナル音楽にあることを再認識させられる(今さらながら、ウッディ・ガスリーなんかの曲だってそういえば以前からスプリングスティーンは取り上げていた)。 上述の“音を楽しむ”という観点を中心に考えながら、お勧め曲を挙げておきたい。1.「オールド・ダン・タッカー」、4.「オー、メアリー・ドント・ユー・ウィープ」、5.「ジョン・ヘンリー」、8.「マイ・オクラホマ・ホーム」、11.「ペイ・ミー・マイ・マネー・ダウン」といった楽曲は、こうした観点では本盤を代表するナンバーと言える。他方、おとなしくシンプルな曲調の哀愁漂うナンバーも見られる。あと、個人的な好みでは、10.「シェナンドー」と表題曲の12.「ウィ・シャル・オーヴァーカム」がいい。 あと、筆者所有の盤(アメリカン・ランド・エディション)のボーナストラックにも魅力的な曲が並んでいる。14.「バッファロー・ギャルズ」は本編に収録して欲しかったと思うほどの出来。16.「ハウ・キャン・ア・プア・マン・スタンド・サッチ・タイムズ・アンド・リヴ」は、スプリングティーン節の歌や演奏と本盤の楽曲たちの接点が垣間見られるという意味で興味深い。18.「アメリカン・ランド」はニューヨークでのライヴ・テイクだが、本盤の雰囲気がそのままにライヴで演奏されている。 本盤はブルース・スプリングスティーンの代表盤と言われることは決してないだろう。けれども、彼の音楽にある程度親しみ、その先(否、そのルーツなので“さかのぼる”と言った方が正確か)にあるものを垣間見たいと思った人には真っ先に勧めたくなる盤ということになる。その一方で、いわゆる“アメリカン・ロック”と“アメリカン・ルーツ・ミュージック”の関係を考えるとき、こういうところで実はつながっているのというのは、ヒット・チャートやメジャーどころのロック/ポップスだけを聴いていては決してわからない、そんな奥深い世界を垣間見させてくれるアルバムでもあると思う。[収録曲]1. Old Dan Tucker2. Jesse James3. Mrs. McGrath4. O Mary Don't You Weep5. John Henry6. Erie Canal7. Jacob's Ladder8. My Oklahoma Home9. Eyes on the Prize10. Shenandoah11. Pay Me My Money Down12. We Shall Overcome13. Froggie Went A-Courtin'~以下、手持ちの盤(アメリカン・ランド・エディション)のボーナストラック~14. Buffalo Gals15. How Can I Keep from Singing?16. How Can a Poor Man Stand Such Times and Live?17. Bring 'Em Home18. American Land2006年リリース。 ウィ・シャル・オーヴァーカム:ザ・シーガー・セッションズ [ ブルース・スプリングスティーン ] 以下のブログランキングに参加しています。お時間の許す方は、クリックで応援よろしくお願いします。 ↓ ↓ ↓
2019年07月11日
コメント(0)
-

ザ・フー 「バーゲン(Bargain)」
偉大なるザ・フーの名曲・名演集(その1) 本ブログでは、INDEXページなるものを作っていて、時々更新していますが、先日ふと気がつくと、その偉大さに比してザ・フー(The Who)の曲を意外と取り上げてこなかったことに気づきました。そんなわけで、ザ・フー名曲・名演選をやってみようかと思いついた次第です。何回続くかわかりませんが、不定期更新という形で、できれば長く続けてみたいと思っていたりします。よろしければぜひお付き合いください。 でもって第1回目ですが、まずは筆者にとって特別な愛聴盤である『フーズ・ネクスト』からの1曲です。「バーゲン」というナンバーですが、まずはアルバム所収のものをお聴きください。 続いては、往時のライヴの音源から。残念ながら映像は動かないのですが、1971年、カリフォルニアはロング・ビーチでのライヴの演奏です。その当時のザ・フーというと、爆発力や破壊力という連想をする人も多いでのはないかと思います。この演奏もまさしくそれを地で行くといったところでしょうか。 [収録アルバム]The Who / Who’s Next(1971年リリース) フーズ・ネクスト+7/ザ・フー[SHM-CD]【返品種別A】 ブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、ぜひクリックをお願いします。 ↓ ↓ ↓
2019年07月09日
コメント(0)
-

コンテ・カンドリ(コンティ・カンドリ) 『シンシアリー・コンテ(Sincerely, Conti)』
勢いのある初リーダー作 コンテ・カンドリ(Conte Candoli,1927-2001年)は、いわゆる西海岸(ウェスト・コースト)ジャズを象徴するトランペット奏者で、ウディ・ハーマン楽団やスタン・ケントン楽団などでも活躍した。彼にとって初のリーダー名義の作品となったのは、1954年録音の本盤『シンシアリー・コンテ(Sincerely, Conti)』だった。ちなみに、本名はセコンド・カンドリ(Secondo Candoli)で、“コンテ”というのは愛称なわけだけれど、本盤の時点では、“コンティ(Conti)”となっていて、まだ芸名が定まっていなかった。 初リーダー作ということが大きいのか、全編にわたって、とにかく勢いよく、“パワーハウス”(発電所)という形容そのままのトランペット演奏を繰り広げている。収録曲は主にスタンダード曲で、全曲を合わせた収録時間も25分に満たない。けれども、テンポの速い曲を勢いよく吹き鳴らし、テンポを抑えた曲では、余裕を見せながら悠々とトランペットを奏でる。このある種の“爽やかさ”こそ、本盤のいちばんの特徴であり、聴き手が楽しむべきポイントだと思う。 そんな観点を念頭に入れつつ、筆者的に勧めたい曲を少し挙げてみたい。まずは、冒頭の1.「ファイン・アンド・ダンディ」。流れるような、かつ勢いに満ちたトランペットに圧倒されてみるのも悪くない。2.「ナイト・フライト」も同じ流れで聴けて、一聴すれば頭から離れなくなりそうなリフ、さらには一気に畳みかけるフレーズが病みつきになる。その一方、4.「オン・ジ・アラモ」や6.「ゼイ・キャント・テイク・ザット・アウェイ・フロム・ミー」に代表されるような、楽しげな余裕に満ちた、かつ流れるような演奏も印象に残る。最後に収められている有名曲の8.「四月の思い出」は、これら2つの特徴が集約された演奏といえるだろう。勢いがとにかく凄いのだけれど、よくよく聴くと、やっぱり“流れるような演奏”という特徴がちゃんと踏まえられている。初リーダー作だから気合が入り、勢いよくという気持ちはあったのだろうけれど、実のところ、余裕いっぱいに流れるような演奏もできたのだろう。だからこそ、ただ勢いで押すだけではない、ここで聴かれるような演奏内容に仕上がったのだろうと思ってみたりする。[収録曲]1. Fine & Dandy2. Night Flight3. I Can't Get Started With You4. On The Alamo5. Tune For Tex6. They Can't Take That Away From Me7. Everything Happens To Me 8. I'll Remember April[パーソネル・録音]Conte Candoli (tp), Claude Williamson (p), Max Bennett (b), Stan Levey (ds)1954年11月20日録音。 シンシアリー・コンテ [ コンテ・カンドリ ] 下記のブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、バナーをクリックお願いします! ↓ ↓
2019年07月06日
コメント(1)
-

レイ・ブライアント 『ライヴ・アット・ベイズン・ストリート・イースト(Live at Basin Street East)』
ジャズ奏者にとっての“ブルース感覚”とは レイ・ブライアント(Ray Bryant)は、1931年フィラデルフィア出身のジャズ・ピアニストで、2011年に79歳で亡くなっている。この人の作品としては、『レイ・ブライアント・トリオ』のような有名盤(かつ名盤)や『レイ・ブライアント・プレイズ』といった秀逸な盤がある。けれども、今回取り上げる『ライヴ・アット・ベイズン・ストリート・イースト』はもう少し気軽な盤で、必ずしも世間での評価はそれほど高くはないかもしれない。 よく言われるように、レイ・ブライアントには、ブルースやゴスペルに根差した独特のフィーリングがある。ジャズの世界では“やっぱりブルース感覚なんだよな”なんて声が聞こえてくる一方で、本盤のようなどこか肩の力が抜けていて、かつ大衆迎合的な要素を含む盤には否定的評価が下される傾向にある。本盤『ライヴ・アット・ベイズン・ストリート・イースト(Live at Basin Street East)』は、R&B系のスー(Sue)・レーベルの録音ということもあるせいか、いっそうそういう判断を下されがちな盤だと思う。 1.「恋とは何でしょう」や2.「C・ジャム・ブルース」、5.「ラヴ・フォー・セール」のようにジャズの王道のスタンダードもあるかと思えば、ボブ・ディランの6.「風に吹かれて」のように、いかにも流行りなナンバーも含まれている。同時に3.「シスター・スージー」、10.「オール・ザ・ヤング・レディーズ」といった自作曲も配されている。この点では、コアなジャズ愛好家から“何でもありなのか”という疑問が呈されかねない内容なのは事実である。 けれども、ブルース、ゴスペルといったルーツ音楽に根差した感覚が支配しているのは、本盤を一度聴けばすぐにわかる。つまるところ、それをどういう風に表現する(とはいっても、無理に表現するということではなく、自然と滲み出させる)かの問題であるように思う。本盤は、1963年のその時にベイズン・ストリート・イーストに集まった聴衆を楽しませることに主眼があり、その演奏者(つまりはレイ・ブライアント)の背後には、そうした音楽的ルーツが避けようもなく存在していた。結果、高尚な音楽に仕上がったと言えるかどうかはわからないものの、演奏者のバックグラウンドに根差した聴衆を楽しませる音楽が演奏された。新たな試みや実験がなされるのもジャズであれば、こういう演奏もまたジャズなのだということを再確認させられる、本盤はそういうアルバムなのなのだろうと思う。[収録曲]1. What Is This Thing Called Love?2. C Jam Blues3. Sister Suzie4. This Is All I Ask5. Love for Sale6. Blowin' in the Wind7. Satin Doll8. Days of Wine and Roses9. Blue Azurte10. All the Young Ladies[パーソネル、録音]Ray Bryant (p), Jimmy Rowser (b), Ben Riley (ds)1963年録音。 【メール便送料無料】RAY BRYANT / LIVE AT BASIN STREET EAST (輸入盤CD) 以下のブログランキングに参加しています。お時間の許す方は、 クリックで応援よろしくお願いします。 ↓ ↓ ↓
2019年07月03日
コメント(0)
-

ハーマン・フォスター 『ハヴ・ユー・ハード(Have You Heard Herman Foster)』
名脇役によるリーダー盤 ハーマン・フォスター(Herman Foster)は、1928年フィラデルフィア生まれで、1999年に亡くなった盲目のジャズ・ピアニスト。彼の初期のキャリアは、ルー・ドナルドソンと切っても切り離せない。1950年代後半、ドナルドソンの複数の吹込みに参加し、その名を世に知らしめることになった。 本盤『ハヴ・ユー・ハード(Have You Heard Herman Foster)』は、1960年に吹き込まれた彼のリーダー作となるトリオ演奏盤である。ルー・ドナルドソンの作品には複数登場するのだが、よく知られた盤で言うと、『ブルース・ウォーク』が1958年、もう少し後だと『グレイヴィー・トレイン』が1961年だから、1960年録音の本盤はこれらに挟まれた時期に録音されていたということになる。つまりは、ルー・ドナルドソン名義の作品制作が続く中、自身のトリオ作も吹き込んでいったわけである。 ハーマン・フォスターが単なる脇役でないというイメージがある人は、ドナルドソン作品のファンにも多いことだろう。その特徴は枠に収まらない点といってもいいかもしれない。フォスターは好きなピアニストにエロール・ガーナーなんかを挙げていたそうだけれど、型にはまらないという点ではなるほどと思える。粘っこく、個性的というのが彼の形容としてしっくりくる。よく言えば、玄人好みで不当にその名が知られていない人物、あるいは別な言い方をすると、正統的な感じではない隠れたB級的な掘り出し盤といったところだろうか。 最後に、個人的に気に入っている演奏をいくつか挙げておきたい。1.「ハーマンのブルース」は本盤収録曲中で唯一の自作曲。彼のピアノの特徴を表す曲はどれかと言われれば、たぶん筆者はこの曲を推すことだと思う。2.「ボラーレ(ヴォラーレ)」は、イタリア人シンガーのドメニコ・モドゥーニョ(1958年)やジプシー・キングス(1989年)などで知られる有名曲。あと、4.「恋に落ちるとき(ホエン・アイ・フォール・イン・ラヴ)」は、ナット・キング・コール(1957年)やセリーヌ・ディオン(クライヴ・グリフィンとのデュエット、1993年)で知られるナンバー。これら2曲の演奏を聴いていると、ハーマン・フォスターという人の“料理の仕方”がよく伝わってくる。ジャズの世界でいう“クッキング”である。原曲そのままではもちろんどうしようもない。だからと言って何でもかんでもその人の世界に引き込まれてしまっては、きっと退屈になる。原曲を意識しつつも、その奏者にしかできない伝え方(しかもその人の色に染まっている)という意味では、これら2曲の演奏はなかなか気に入っていたりする。[収録曲]1. Herman's Blues2. Volare3. Lover Man4. When I Fall In Love5. Strange6. Angel Eyes[パーソネル・録音]Herman Foster (p), Frank Dunlop (ds), Earl May (ds)1960年9月19日録音。 [期間限定][限定盤]ハヴ・ユー・ハード/ハーマン・フォスター[CD]【返品種別A】 次のブログのランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、クリックで応援をよろしくお願いします! ↓ ↓
2019年07月01日
コメント(0)
全15件 (15件中 1-15件目)
1
-
-

- 70年代サブカルチャー URC, ELEC, …
- まんだらけの優待のまんだらけZEM…
- (2023-06-24 23:18:46)
-
-
-

- ギターマニアの皆さん・・・このギタ…
- 【ギター×イス軸法®︎】体軸でギター…
- (2024-08-17 21:14:58)
-
-
-
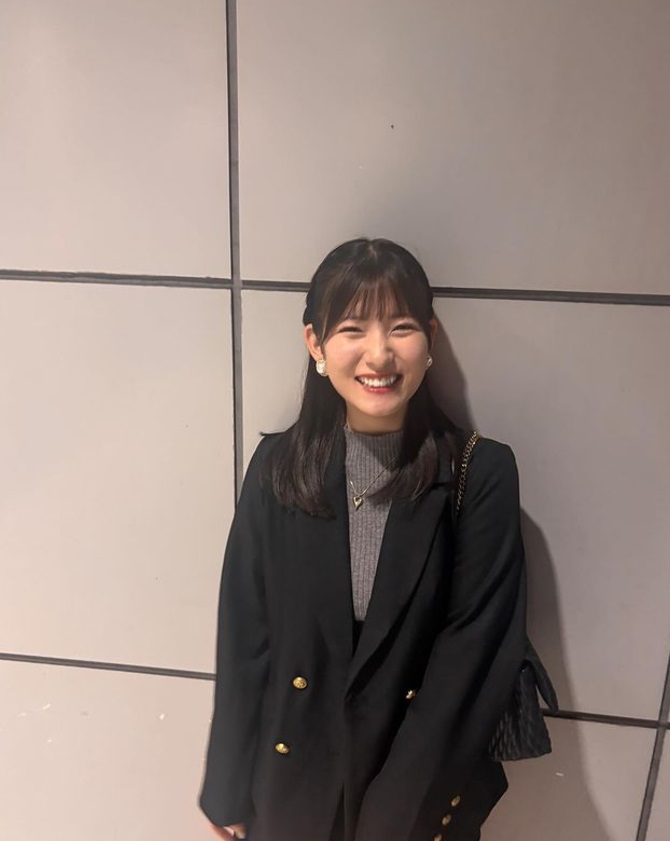
- ☆モー娘。あれこれ☆
- 【北川莉央(モーニング娘。'24)】S…
- (2024-12-04 23:13:00)
-







