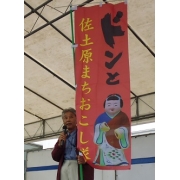テーマ: 四季を楽しむ暮らし(49)
カテゴリ: 庭の手入れ
前回、ヨドガワツツジで紹介したツツジは「ヒラドツツジ」のオオムラサキの間違いだった。
植えた当時から「ヨドガワツツジ」だと思い込んでいた。呉れた人がそう言ったのかもしれない。
そのオオムラサキというより赤いヒラドツツジ、昨日の雨にも散らずに本日5分咲きほど。

ヨドガワツツジは落葉種で八重咲が殆どらしいのでまるで違う品種だった。

自然実生5年生ほどの多分「タブノキ」。
葉を押しつぶすと楠に近い独特の香りがする。クスノキ科の植物で実を野鳥が食べる。
タブの語源は丸木舟(朝鮮語でトンバイ?)からついたとあった。大木になる。

自然実生3年生の「ハマヒサカキ」やはり鳥が運んできた。
日南海岸の崖にたくさん自生している。ツバキ科らしく照葉樹である。黒い実がなる。

自然実生の「ヒサカキ」前記ハマヒサカキと同属種。やはり黒い実がなる。
実はこちらが美味しいらしく、冬にはシロハラ、ヒヨドリが盛んに食べるので芽生えも多い。

子どもの頃種まま食べた「エノキ」これは10年くらいたっている。
エノキやムクノキの枯葉は硬い粗目で紙ヤスリのように板磨きに使うと聞いたことがある。
オオムラサキの食樹であるが飛んでいるのを見たことはない。柄の木説は嘘だとあった。

ブルーベリーは貰ったもの。花は済んで赤味のある新緑が美しい。
ツツジ科だとは知らなかった。そういえばドウダンツツジに似ているかな?

クマザサ、これは近くの里山で採取したもの。なかなか縁が白くならない。
名前の由来は白く隈取りがが出ることから。新芽のジュースは健康にいいとか?

イワヒバ、樹齢40年以上の古強者。山の小学校から貰ってきた野生種。
シダ類であるが、葉を小さくむしり、鹿沼土の微粒に伏せておけば簡単に繁殖する。
水は全くやらなくても枯れることは先ずない。通称を岩松と呼ぶ。

ミズフキ、増えすぎて困るが簡単に食べられるので家内は重宝している。

これは何だろう?クヌギかキンモクセイの幼木。実生の3年生。
植えた当時から「ヨドガワツツジ」だと思い込んでいた。呉れた人がそう言ったのかもしれない。
そのオオムラサキというより赤いヒラドツツジ、昨日の雨にも散らずに本日5分咲きほど。

ヨドガワツツジは落葉種で八重咲が殆どらしいのでまるで違う品種だった。

自然実生5年生ほどの多分「タブノキ」。
葉を押しつぶすと楠に近い独特の香りがする。クスノキ科の植物で実を野鳥が食べる。
タブの語源は丸木舟(朝鮮語でトンバイ?)からついたとあった。大木になる。

自然実生3年生の「ハマヒサカキ」やはり鳥が運んできた。
日南海岸の崖にたくさん自生している。ツバキ科らしく照葉樹である。黒い実がなる。

自然実生の「ヒサカキ」前記ハマヒサカキと同属種。やはり黒い実がなる。
実はこちらが美味しいらしく、冬にはシロハラ、ヒヨドリが盛んに食べるので芽生えも多い。

子どもの頃種まま食べた「エノキ」これは10年くらいたっている。
エノキやムクノキの枯葉は硬い粗目で紙ヤスリのように板磨きに使うと聞いたことがある。
オオムラサキの食樹であるが飛んでいるのを見たことはない。柄の木説は嘘だとあった。

ブルーベリーは貰ったもの。花は済んで赤味のある新緑が美しい。
ツツジ科だとは知らなかった。そういえばドウダンツツジに似ているかな?

クマザサ、これは近くの里山で採取したもの。なかなか縁が白くならない。
名前の由来は白く隈取りがが出ることから。新芽のジュースは健康にいいとか?

イワヒバ、樹齢40年以上の古強者。山の小学校から貰ってきた野生種。
シダ類であるが、葉を小さくむしり、鹿沼土の微粒に伏せておけば簡単に繁殖する。
水は全くやらなくても枯れることは先ずない。通称を岩松と呼ぶ。

ミズフキ、増えすぎて困るが簡単に食べられるので家内は重宝している。

これは何だろう?クヌギかキンモクセイの幼木。実生の3年生。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[庭の手入れ] カテゴリの最新記事
-
今日は9時から17時半まで8.5h、飲まず… Oct 15, 2016
-
庭師2h、ケール間引きなど2h、高速バス… Nov 7, 2015
-
珍しい植物2種「コモチラン、シロダモの花… Dec 7, 2013
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
Keyword Search
▼キーワード検索
Category
カテゴリ未分類
(1009)菜園と株と釣りを楽しむ日々
(739)釣り、つり、ツリ
(52)愚利公の動物記
(90)ドンと佐土原まちおこし隊
(4)地域づくり協議会
(118)美味いものが喰いたい
(178)庭の手入れ
(117)伝統行事
(34)佐土原城下の自然と文化
(276)いただきもの
(61)ニュース
(495)スポーツ
(574)読書
(502)徒然草
(209)ミッドナイト・コメント
(119)トラブルいろいろ
(61)今日のトピック
(292)自然の移ろい
(97)菜園雑草
(20)愚利公の岡目一目
(22)今日の出来事
(3526)午前中の出来事
(230)午後の出来事
(259)夜間の出来事
(121)早朝の出来事
(162)新聞を読んで
(63)パソコンのこと
(17)愚利公の今日の心だぁ~!
(39)今朝の菜園作業
(371)自治会長の仕事
(235)今日の菜園作業
(154)今日の菜園収穫
(99)夕方の菜園作業
(113)午後の菜園作業
(46)加地訓で読む4度目の論語
(141)大学章句
(11)フォト575
(49)余命3か月
(1)Calendar
06月25日 なすび …
New!
hatabo1237さん
我家で咲く花たち!… New!
だいちゃん0204さん
New!
だいちゃん0204さん
もうひと花咲かそう… New! かみ と えんぴつさん
オキザリス・パルマ… New! wildchabyさん
ピノガールが・・・(… New!
choromeiさん
New!
choromeiさん
我家で咲く花たち!…
 New!
だいちゃん0204さん
New!
だいちゃん0204さんもうひと花咲かそう… New! かみ と えんぴつさん
オキザリス・パルマ… New! wildchabyさん
ピノガールが・・・(…
 New!
choromeiさん
New!
choromeiさんFreepage List
© Rakuten Group, Inc.