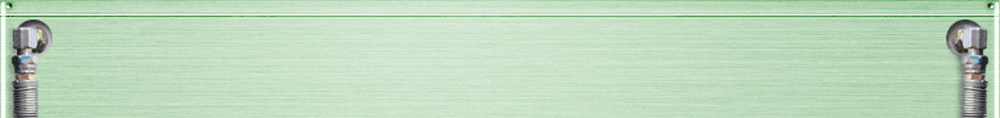全て
| カテゴリ未分類
| プレスリリース
| ドライアイ
| 文献発表
| 厚生労働省通知
| 妄想
| 新聞報道
| お勉強
| 前立腺がん
| 医療費
| 原発
| 制がん剤
| 政治
| 自閉症
| 子宮頸がんワクチン
| 哲学
| 宣伝
| 憲法
| 医療用医薬品
テーマ: ニュース(99741)
カテゴリ: 制がん剤
日刊現代の「海外の医者は処方しないのに、日本の医者がなぜかよく出す「薬」一覧 日本人は世界一の「薬依存」!?」という記事は表面的な理解で記載されているので、反論します。
しかし、胃潰瘍の原因になるリスクはどれぐらいあるのでしょうか。300人に5人ぐらいでプロトンポンプ阻害剤併用するとそれが300人に1人(記憶で書いているので間違いがあるかもしれません©稲田朋美防衛省大臣)とリスクを80%減少しますが、少なくとも295人の人には不要の薬です。医療経済学的な観点から欧州で使われていません。
胃潰瘍の治療の第一選択肢はプロトンポンプ阻害剤なので、本当に併用する価値があるかどうかは私は疑問を持っています。
TS-1の前の世代であるUFTという薬剤の評価はFDAで意見が割れて承認されませんでした。しかし、アメリカ以外の欧州では承認されています。
最近はテーラーメードをめざして腫瘍の成長因子をターゲットにした薬剤が脚光を浴びていますが、その成長因子を持たない腫瘍を有している患者さんには殺細胞効果がある薬剤が使われています。
免疫は攻撃と免疫チェックポイントによる攻撃中止により調節されていることが近年、日本発で発見されました。
腫瘍細胞は免疫の攻撃を避けるために免疫チェックポイントと同様の仕組みで免疫を避けている可能性があり、オプジーボ点滴静注100mg 10mLという、高薬価で問題になった薬剤が発売されています。
肺がんにたいして有効といわれていますが、臨床データをみれば、免疫療法(この免疫療法とは攻撃因子を患者に与えることです)。
まず、オプジーボは肺がんに対して生存期間を2ヶ月ほど長くしましたが、2年生存した患者はいませんでした。これは既存の治療を受けた患者なので、オプジーボの臨床試験をした会社はファーストラインの肺がんに対する臨床試験を行いましたが、殺細胞役との殺細胞薬との比較試験で差を見いだすことができませんでした。
オプジーボと同じような効果を示す薬剤を持っている会社はPD-1が発現している腫瘍のみの臨床試験を行った結果、殺細胞薬に対して有意な効果を示し、長期生存例も見られました。
直接の比較ではないので、厚生労働省は優位性を認めず、PD-1の発現している患者のみにい縛ることになりました。
オプジーボも同様な縛りが必要と考えますが、今のところ添付文書は変更されていません。(審査報告書では高発現は10%もなく、測定方法が確立していないということで逃げていました。)
上記のデータから推測されることは、免疫療法が効果があるのは免疫チェックポイントを活性化させることができる腫瘍だけだだということです。(あくまで仮説ですが)
腫瘍は最初に発現したときから、免疫にさらされ、ほとんどがアポトーシス(細胞死)しているという考えもあります。その中で、免疫に対する耐性を持った腫瘍のみが大きくなって疾病としてのがんとなるという説が免疫チェックポイントをターゲットとした薬剤の臨床効果から推測されます。
年齢を重ねることにより、免疫の力が落ちてきたので、腫瘍細胞が生き延びる可能性が高まり、がんという疾病が成立している説も、ある年齢からがんが急激に増えることから否定はできません。そのため、免疫を強化することによりがんの治療ができる可能性は否定しませんが、いままで、エビデンスレベルが低いので、おすすめできない状態です。
年齢に関しては、腫瘍細胞は遺伝子のミスコピーから発生する説に乗れば、免疫は関係なく、腫瘍細胞の発生量が増えて、免疫をくぐり抜ける方法を身につけた細胞ががんという疾病になるという仮説も成り立ちます。
精神病薬に関してはよく知らないので、反論しないでおきます。
これはかぜ薬に抗生物質が処方されることに対して文句を言っている部分の根拠です。確かに問題にはなっていましたが、伊勢志摩サミットで耐性菌の問題がトピックとして挙げられ、今後は動物用抗生物質まで規制していく方針で厚生労働省は動いています。(動物の抗生物質使用に対して国の規制を考えているのは日本だけです。「日本人は風邪で医者にかかっても、とにかく薬をもらいたがる傾向があります。これが実は大きな問題なのです」
こう語るのは、日米の医療システムに詳しい医師でミシガン大学教授(家庭医学)のマイケル・フェターズ氏だ。
「熱冷ましでロキソニンやボルタレンが処方されていますが、胃潰瘍の原因になるほか、腎機能の低下で排尿困難になる可能性もあります。しかも、長く使い続けると心臓のリスクにもなるといわれているので、使い方には注意が必要です」胃潰瘍に対するリスクに対しては、プロトンポンプ阻害剤を併用することがアメリカの学会で標準治療としてあげられたことから、アスピリンで(他の用途で長期利用する場合が多い)さえ、プロトンポンプ阻害剤の併用が保険適用されています。
しかし、胃潰瘍の原因になるリスクはどれぐらいあるのでしょうか。300人に5人ぐらいでプロトンポンプ阻害剤併用するとそれが300人に1人(記憶で書いているので間違いがあるかもしれません©稲田朋美防衛省大臣)とリスクを80%減少しますが、少なくとも295人の人には不要の薬です。医療経済学的な観点から欧州で使われていません。
胃潰瘍の治療の第一選択肢はプロトンポンプ阻害剤なので、本当に併用する価値があるかどうかは私は疑問を持っています。
経口の5FUからUFTそしてTS-1に関しては日本発の制癌剤です。日本の腫瘍専門医は免疫の大切さを理解していないとおっしゃっていますが、本当にそう思うなら、日本癌学会や日本臨床腫瘍学会できちんと発言していただきたいものです。また、アメリカでもロシュの5FU系経口薬が販売されており、ファーストラインあるいは術後補助療法(再発防止)に関してエビデンスが存在します。「抗がん剤にTS1という飲み薬があります。これが今でも飲まれているのは日本とロシアだけです。これは5FUという'50年代に開発された最も古いタイプの抗ガン剤を、注射薬から経口薬に変えただけのもの。
TS1は殺細胞剤とも言われていて、がん細胞だけでなく、それを攻撃するべき免疫細胞まで弱らせてしまいます。TS1でがんの再発予防ができる可能性は)ほとんどありません。日本ではがん治療における免疫の大切さがまだまだ理解されていないのです」(新日本橋石井クリニックの石井光院長)
TS-1の前の世代であるUFTという薬剤の評価はFDAで意見が割れて承認されませんでした。しかし、アメリカ以外の欧州では承認されています。
最近はテーラーメードをめざして腫瘍の成長因子をターゲットにした薬剤が脚光を浴びていますが、その成長因子を持たない腫瘍を有している患者さんには殺細胞効果がある薬剤が使われています。
免疫は攻撃と免疫チェックポイントによる攻撃中止により調節されていることが近年、日本発で発見されました。
腫瘍細胞は免疫の攻撃を避けるために免疫チェックポイントと同様の仕組みで免疫を避けている可能性があり、オプジーボ点滴静注100mg 10mLという、高薬価で問題になった薬剤が発売されています。
肺がんにたいして有効といわれていますが、臨床データをみれば、免疫療法(この免疫療法とは攻撃因子を患者に与えることです)。
まず、オプジーボは肺がんに対して生存期間を2ヶ月ほど長くしましたが、2年生存した患者はいませんでした。これは既存の治療を受けた患者なので、オプジーボの臨床試験をした会社はファーストラインの肺がんに対する臨床試験を行いましたが、殺細胞役との殺細胞薬との比較試験で差を見いだすことができませんでした。
オプジーボと同じような効果を示す薬剤を持っている会社はPD-1が発現している腫瘍のみの臨床試験を行った結果、殺細胞薬に対して有意な効果を示し、長期生存例も見られました。
直接の比較ではないので、厚生労働省は優位性を認めず、PD-1の発現している患者のみにい縛ることになりました。
オプジーボも同様な縛りが必要と考えますが、今のところ添付文書は変更されていません。(審査報告書では高発現は10%もなく、測定方法が確立していないということで逃げていました。)
上記のデータから推測されることは、免疫療法が効果があるのは免疫チェックポイントを活性化させることができる腫瘍だけだだということです。(あくまで仮説ですが)
腫瘍は最初に発現したときから、免疫にさらされ、ほとんどがアポトーシス(細胞死)しているという考えもあります。その中で、免疫に対する耐性を持った腫瘍のみが大きくなって疾病としてのがんとなるという説が免疫チェックポイントをターゲットとした薬剤の臨床効果から推測されます。
年齢を重ねることにより、免疫の力が落ちてきたので、腫瘍細胞が生き延びる可能性が高まり、がんという疾病が成立している説も、ある年齢からがんが急激に増えることから否定はできません。そのため、免疫を強化することによりがんの治療ができる可能性は否定しませんが、いままで、エビデンスレベルが低いので、おすすめできない状態です。
年齢に関しては、腫瘍細胞は遺伝子のミスコピーから発生する説に乗れば、免疫は関係なく、腫瘍細胞の発生量が増えて、免疫をくぐり抜ける方法を身につけた細胞ががんという疾病になるという仮説も成り立ちます。
精神病薬に関してはよく知らないので、反論しないでおきます。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[制がん剤] カテゴリの最新記事
-
TAS-118について 2020年09月14日
-
オブジーボとキイトルーダ オプジーボは… 2016年11月13日
-
オブジーボの予算委員会でのやりとり 2016年10月13日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.