2011年04月の記事
全32件 (32件中 1-32件目)
1
-
更新休止のお知らせ。
といっても大袈裟なものではありません。家族と旅行の為、明日の更新を休ませていただきます。
2011年04月29日
コメント(2)
-

白銀之華 第151話
修道院での生活にも慣れ、璃音はアベルとともに農作業やハーブの石鹸作りなどに勤しんでいた。「璃音、上手に出来たね。」「ありがとう、お父様。」アベルに完成した石鹸を褒められ、璃音は笑顔を見せた。「アベル、お客様ですよ。」「はい、今行きます。」アベルはそう言って璃音を残して作業場から出た。「お父様・・」作業場から出て行くアベルの背中を、璃音は寂しそうに見つめていた。 アベルが作業場から出て修道院の玄関ロビーへと出ると、そこには1台の馬車が停まっていた。「アベル様、ですね?」「はい。あなたは・・」「申し遅れました。わたしはカルロ、ルクレツィア伯爵家の者です。」「ルクレツィア伯爵家は・・レディー=ソフィー様はお亡くなりになられた筈では?」ルクレツィア伯爵家の者だと言うカルロに、アベルは思わず彼を見た。「ソフィー様は確かにお亡くなりになられましたが、わたし達の父・・あの子にとっては祖父にあたるルクレツィア伯爵家当主・ダヴィド様は生きておられます。」「その当主様が、璃音を引き取りたいと?」アベルの問いに、カルロは無言で頷いた。「璃音を・・呼んで参ります・・」璃音を呼びに、アベルは作業場へと戻った。生まれてからずっと、璃音とともに実の親子同様に過ごしてきたアベルだったが、こんなにも早く彼女と別れなければいけないとは。「璃音。」「お父様。その方は?」「璃音、話がある。お前のお祖父様が、お前を引き取りたいと言っているんだ。」「え・・それじゃぁ、お父様ともう一緒には暮らせないの?」気まずい沈黙が、璃音とアベルとの間に流れた。「璃音、これをお父様だと思って大事にしなさい。」アベルは自分の首に提げているロザリオを外すと、璃音の首にそれを掛けた。「お父様、いつかまた会える?」「ああ、会えるよ。」璃音は涙を流しながら、アベルに抱きついた。「どんなにお前と離れていても、心はお前の傍にいるからね。」「璃音、行きますよ。」カロルの手を不安げに握った璃音は、彼と共に馬車に乗り込んだ。「お父様、さようなら!」馬車の窓から身を乗り出し、璃音は修道院が見えなくなるまでアベルに手を振った。「璃音、元気で・・」アベルは馬車が見えなくなるまで、必死に涙を堪えた。 一方エスティール皇国では、皇帝の在位40周年を祝う式典の準備が進められていた。「ユーリ様、助かったわ。」「いいえ・・式典はいよいよ明日ですね。」「ええ。わたくしはもう休みます。」ユーフィリアはそう言うと、自室へと向かった。「ユーフィリア様、お手紙が届きました。」「そう。」自室に入ったユーフィリアは、女官の手からルディガーの手紙を受け取ると、それをソファに座って読み始めた。(ルディガー様、いよいよ明日が勝負ですわね・・)ユーフィリアはソファから立ち上がり寝室に入ると、鍵が掛けられたサイドテーブルの二段目の引き出しを開けた。そこには、正方形の箱が入っていた。「勝負は明日・・絶対に失敗できませんわね・・」 箱から拳銃を取り出すと、ユーフィリアはそれを撫でながらそう呟くと、口端を歪めて笑った。にほんブログ村
2011年04月28日
コメント(2)
-

白銀之華 第150話
「お休みなさい、お母様。」夕食後、羅姫はそう冬香に挨拶をしてダイニングから出て行った。「ちょっと待ちなさいよ。」部屋へと向かおうと羅姫が階段を上っている時、遥が息を切らして彼女の後を追い、羅姫の手首を掴んだ。「何かしら?」「どうしてあなたって無愛想なの? お母様もお父様もあなたのことを気にしているのに、あなたったらいつも不機嫌そうな顔ばかりして・・」「不機嫌そうな顔? それをさせているのはあなたではなくて?」遥にそう言い放った羅姫は、彼女の手を振り払うと部屋に入った。「やっぱり気に入らないわ、あの子・・」ドアの向こうへと消えてゆく羅姫の金髪を睨みつけながら、遥はそう呟いて自分の部屋へと入った。 遥とともに学校に通い始めた羅姫だったが、級友たちとおしゃべりする事も、共に遊ぶ事もなく、休憩時間は図書室で借りた本を読んでいた。「ではこの問題を羅姫さんに解いて貰いましょうか?」算術の時間、羅姫はさっと椅子から立ち上がり、黒板に書かれている計算問題をすらすらと解いた。「良く出来ましたね、羅姫さん。」「ありがとうございます。」教師に向かって頭を下げた羅姫が自分の席に戻ろうとした時、数人の級友達が聞えよがしに嫌味を言った。「すました方ねぇ。」「全く愛想がないわ。いくら学が出来てもあれじゃぁねぇ・・」女に学問など不要、必要なのは愛嬌と良い嫁ぎ先だと言われていた時代で、成績優秀で無愛想な羅姫はこの頃から教室で孤立した存在となっていた。(ただヘラヘラと笑って生きるなんて、わたしは嫌。)放課後、迎えの馬車を待っていた羅姫は、教室で図書室から新たに借りた本を読んでいた。「何を読んでいるの、羅姫さん?」突然頭上から声がして羅姫が本から顔を上げると、そこには担任の教師が優しい笑みを湛えて彼女を見ていた。「地理の本です。前に父上が夜眠る前に読み聞かせてくれたので。」「そう。羅姫さんは勉強が好きなのね。」「はい。わたしは知りたいんです、世の中の事を。学が良くて愛想がないと言われても、気にしません。」羅姫の言葉に、教師は溜息を吐いた。「羅姫さんは他の皆さんとは違うものを持っているのよ。その事を恥じずに生きることが、あなたには出来るのではないかしら?」教師の言葉を聞いた羅姫は、彼女に笑顔を浮かべた。「これからも勉強に励みます。」羅姫が本をランドセルに詰めていると、瀧丘家の執事、河野が教室に入ってきた。「お嬢様、お迎えにあがりました。」「ありがとう。では行きましょうか。」羅姫が河野とともに馬車に乗り込むと、そこには遥の姿がなかった。「遥さんはどちらに?」「遥お嬢様なら、お先にお帰りになりました。」河野とともに帰宅した羅姫がリビングに入ろうとすると、賑やかな笑い声が聞こえた。「お客様がいらしているの?」「ええ。奥様のお知り合いの方が。」養母の知り合いに挨拶をしておこうと、羅姫はリビングのドアを開けて中に入ると、そこには洋装姿の数人の女性達がソファに座っていた。「お母様、只今帰りました。」「あら羅姫さん、お帰りなさい。皆さんご紹介いたしますわ、養女の羅姫です。」「初めまして、羅姫と申します。」女性達に頭を下げると、彼女達はまるで珍獣を見るような目つきで羅姫の頭から爪先まで品定めするかのように見た。「まぁ、可愛らしい事。」「まるで西洋のお人形さんのようね。」「遥ちゃんとはまた違った可愛さねぇ。」羅姫が視線を感じて少し顔を上げると、冬香の隣で遥が恨めしそうな顔をして羅姫を睨んだかと思うと、彼女はリビングから飛び出して行った。(何よ、いつもあいつばかり!)突然現れた“新しい妹”に母の愛情を奪われてしまうと、遥は幼いながらも危惧していた。にほんブログ村
2011年04月28日
コメント(0)
-

白銀之華 第149話
―ユーリさん・・何処かで、蓮華の声がしてユーリが辺りを見渡すと、彼岸花の中に彼女は静かに佇んでいた。(レンゲさん・・生きていたんですね。)ユーリが安堵の表情を浮かべながら蓮華の方へと駆け寄ると、彼女はユーリを手で制した。―わたし達は行かなくてはなりません。どうか、あの悪魔を倒してくださいね。白い着物の袖を振りながら、蓮華は漆黒の髪をなびかせるとユーリに背を向けて歩き出した。(待ってください、レンゲさん!)不思議な夢から目を醒ましたユーリは、鉛のように重い身体を引き摺りながら寝台から降りた。「おはようございます、ユーリ様。」寝室にユーリ付の女官が入ってきたので、ユーリは彼女に微笑んだ。「ユーフィリア様がお呼びです。」「わかった。」女官に着替えを手伝って貰いながら、身支度を終えたユーリは寝室から出てユーフィリアの部屋へと向かった。「ユーリ様は、もうすぐ来られるかしら?」「ええ。」「そう・・」ユーフィリアはそう言うと、今朝届いたばかりのルディガーからの手紙を読み直していた。「ユーフィリア様、ユーリ様がお見えです。」「失礼致します、ユーフィリア様。」部屋に入ってきたユーリを、ユーフィリアは笑顔で迎えた。「ごめんなさいね、ユーリ様。朝早くから呼びだしてしまって。色々と相談したい事があって・・」「そうですか。相談したい事とは?」「実は、数週間後にエスティア皇国皇帝在位40周年記念式典があるの。その式典にも、ユーリ様達もご出席願えないかと思いまして・・」「ええ、是非出席させていただきます。」「そう・・ありがとう。」そう言ったユーフィリアの瞳は、妖しい光を湛えていた。「ではお母様、行って参ります。」一方、瀧丘子爵家の養女として新しい生活を送っている羅姫(らひ)は、遥(はるか)とともに小学校へ向かう為、馬車へと乗り込んだ。「羅姫さん、先に言っておくけれど、わたくしに恥をかかせないでね。」遥はそう言うなり、羅姫にそっぽを向き、その後学校に着くまで2人は何も話さなかった。 羅姫が遥とともに馬車から降りて小学校の校門へと潜ると、彼女は周りから好奇の視線を浴びた。―見て、あの髪・・―異人さんみたい・・遠巻きに羅姫を見ながらひそひそと話す女子児童達は、新参者を歓迎しようとする気が全くない事を態度に示していた。今まで鴾和家の、鬼族の里の中で暮らしてきた羅姫にとって、自分に向けられた好奇の視線には少し驚きもしたが、それに臆することは鬼族としての誇りが廃れると思ったので、胸を張って堂々と教室へと入った。「皆さん、新しいお友達を紹介しますね。瀧丘羅姫さんです。」「瀧丘羅姫です、宜しくお願いします。」羅姫は教壇に立ち級友達に向かって自己紹介したが、返ってきたのはやる気のない拍手だった。「あなた、どちらのご出身なの?」休み時間となり、羅姫の元に1人の女子児童がやって来た。「鬼族の里からです。」「そう。道理で髪や瞳の色が違うと思ったわ。」初めての学校生活は余り芳しくない結果に終わったが、羅姫はそんな事を気にもせずに、遥とともに帰宅した。「お帰りなさい、羅姫さん。学校はどうでしたか?」「余り楽しくありませんでしたけど、いずれ慣れると思います。」 淡々とした口調で学校生活初日の事を報告する羅姫を、冬香はどこか不安げな表情を浮かべていた。にほんブログ村
2011年04月27日
コメント(0)
-

白銀之華 第148話
翌朝、アベルと璃音は修道院で暮らし始めた。 物心ついた頃から修道院附属の孤児院で育ったので、農作業などはすぐに慣れたが、初めて土に触る璃音にとっては、些細な事でも大きな発見となった。「ねぇお父様、いつまでここに暮らすの? 伯母様のお邸は燃えてしまったのでしょう?」真紅の双眸を輝かせながら、璃音はそう言ってアベルを見た。「いつまでここで暮らせるかわからないけど、お父様はずっと璃音の傍にいるからね。」「そう・・じゃぁ、何も心配しないわ。」璃音はそう言ってアベルの手を握った。彼女と別れの時が来るなどと、アベルはまだその時は思いもしなかった。 アベルが璃音ともに修道院で新しい生活を送り始めている頃、ユーリ達も異国の王宮で新しい生活を始めていた。祖国に戻る術もないユーリ達は、ダブリスとは違うしきたりがあるエスティール宮廷での生活は気苦労が絶えず、一日が終わると同時にユーリは溜息を吐いていた。「ユーフィリア皇女様は、一体何をお考えなのでしょう? 突然ユーリ様を呼び出すなど・・」「解らない・・ユーフィリア様とは滅多に会わないし、会話も交わされないから、彼女が何を考えてわたし達をここに呼んだ理由が全く解らない。それさえ解ればいいんだけど・・」ベッドの上で欠伸をしながら、ユーリはそう言って寝返りを打った。「麗欖(れいらん)だけが宮廷に馴染んでいるようですね。ユーフィリア様もあの子を大層可愛がっておられますし。」匡惟はそう言って妻を見ると、彼女は複雑そうな表情を浮かべていた。赤の他人が我が子と親しくしていることを夫から聞かされたら、母親は心中穏やかではいられないだろう。「・・すいません、こんな話をするつもりでは・・」「いや、いいんだ。」ユーリはそう言って匡惟に背を向けた。「ユーフィリア様、ユーリ様達をここへ呼び寄せたのは何故です?」ユーフィリアはそんな女官の質問に対し、口元に笑みを浮かべた。「ユーリ様にわたくし、密かに憧れておりましたの。滅多にお会いする事が出来ない方だけれど、今は違う。わたくしはこれから、ユーリ様に色々な事を学べるわ。そう思わない事?」皇女の澄んだ紫紺の瞳を見つめながら女官は静かに頷いたが、主の本心は解らぬままだった。「もう休みます。お前達は下がって。」「お休みなさいませ、ユーフィリア様。」女官達が部屋から出て行くと、ユーフィリアは先程届いたルディガーからの手紙を読み始めた。「計画は、順調そうですわね・・」ユーフィリアはそう呟くと、手紙を蝋燭で燃やした。炎に仄かに照らされた彼女の顔は、少し歪んでいた。「ユーフィリア様からお手紙が届きましたわ。」「そうか。」ルディガーは妻・羅姫の手からユーフィリアの手紙を受け取ると、それに目を通した。「ユーフィリア様はなんと?」「君が気にする内容ではないよ。それよりも羅姫、そろそろ結婚式の準備をしなければね。お腹が目立たない内に。」「ええ、そうですわね。」羅姫はそう言ってそっとまだ膨らんでいない下腹を擦った。「ねぇルディガー様、蓮華達は今どうしているのかしら?」「さぁ・・元気にしているだろうね。」ルディガーは羅姫にはまだ、蓮華達に罪を被せた事を話していなかった。(羅姫、君は何も心配は要らないよ。わたしが居る限り、わたし達の敵は完全に排除する。)隣で眠る妻の髪を梳きながら、ルディガーは次の計画の為に動こうとしていた。(ユーフィリア、君は使えそうだ。このまま何とか上手くユーリを騙してくれよ・・)異国の協力者に向かってルディガーは密かに呟くと、眠りに就いた。にほんブログ村
2011年04月27日
コメント(2)
-

白銀之華 第147話
「待っていたよ、“龍の炎”よ。」老人はそう言ってアベルの方へと一歩近づくと、彼の前髪を掻き上げた。その額には、あの奇妙な文様が現れていた。「やはり、あなたが“龍の炎”でしたか。」アベルの額を見つめながら、アンドリューは驚愕の表情を浮かべた。「あなた方は何者なのですか?」「わしらはマリナラル・・かつて異端とされ、処刑された神の子孫じゃ。」老人はアベルの額にそっと触れると、彼から離れていった。「人魚の末裔も、そこにおるのか。」「璃音とあなた方には、何か関係があるのですか? それにアンドリューさん、どうしてレディー=ソフィーを・・」「君の質問に丁寧に答えるとしましょう、アベル。その前に夕食にしませんか? ルクレツィア伯爵邸を出てから何も食べていないでしょう?」(何か妖しい・・)アンドリューと謎の老人の解せない態度に疑惑を抱きながらも、アベルは璃音の手をひいて彼らと共に食堂へと向かった。 修道院の食事なのだからさぞや粗末なものかと思いきや、食卓に出てきたのは熟成されたハムやチーズ、バター、葡萄酒などの豪勢な食事だった。「アベル、あなたは確か修道院附属の孤児院で育ちましたね?」「ええ。それが何か?」「あなたは知りたくないですか? 何故突然あなたが、“龍の炎”を使えるようになったのか。そして、何故“彼女”があなたに人魚の末裔を託したのか。」思わず魂を吸い取られそうなアンドリューの勿忘草色の瞳を、アベルはじっと見つめていた。彼は深呼吸すると、ゆっくりと口を開いた。「あなたが何かを知っているというのなら、わたしは真実を聞かなければなりません。」「そうですか・・長い話になりますが・・」アベルの言葉を聞いたアンドリューは、老人に目配せした。「わしがそなたに一度だけ、真実を話そう。」微かに食堂内を照らす燭台の炎が揺らめいた。 夜の帳が下りると、提灯の仄かな光が活気で賑わう花街を照らす。置屋や揚屋がひしめく通りで、香欖(からん)はある置屋の下働きとして独楽鼠のように働いていた。「香欖、ちょっときぃ。」置屋の女将がそう言って白魚のような手をひらひらと振りながら香欖に手招きした。「あの、何かご用でしょうか?」「このままお前を下働きとして置屋に置いてゆく訳にもいかへんし、明日からうちの仕込みとして芸事の稽古を受けよし。」「え・・」「あんたは光る子やと、置屋の暖簾をくぐったあんたを見た時から解ったんや。あんたは下働きには勿体ない子や。」両親を亡くし、訳も分からぬまま姉と逸れ、途方に暮れていたところを人買いに攫われ、この置屋へと連れて来られた香欖は、未だ状況が掴めないでいた。「あんたが芸事に励んで、有名になったら、別れた姉さんも見つかるんと違う?」女将の言葉に、幼い香欖の心が決まった。「解りました。明日から芸事に励みます。」(姉上、いつかきっと会えるよね?)部屋の格子窓から見える月を眺めながら、香欖は離ればなれとなった姉を想った。「お父様、これからわたしたち、どうなるの?」夕食の後、アンドリュー達から用意された部屋に入った璃音は、そう言って不安そうにアベルを見た。「大丈夫、お父様がついているから、璃音は何も心配しなくてもいいよ。」「うん・・」眠りに就いた璃音の髪をそっと撫でながら、アベルは溜息を吐いた。これから先の生活がどうなるのか、アベルにも解らない。だが璃音の前では、不安がっている顔をしてはいけない。彼女を守れるのは、自分だけなのだから。(しっかりしなければ・・)にほんブログ村
2011年04月26日
コメント(0)
-

白銀之華 第146話
「大丈夫ですか、ユーリ様?」「ん・・」匡惟の声で、ユーリは目を覚ました。(確かわたしは、急に倒れて・・)「匡惟、ユーフィリア様は?」「皇女様ならお部屋にいらっしゃいます。それよりもこれからどうなさいますか?」匡惟はそう言って、ユーリを見た。「どうって・・ダブリスに戻るに決まっている。そして兄様にお会いする。」「ダブリスに戻ることは無理です。先ほどダブリス側の国境が封鎖されたとの知らせを使者から聞きました。」国境が封鎖されたということは、それほど疫病が国中で猛威をふるっているということか。今すぐルディガーと会って、彼に問い質したいことが沢山あったが、彼に会う前に二度と故郷の土を踏めぬ事を知ったユーリは、溜息を吐いた。「ユーリ様、ユーフィリア様がお呼びです。」「解りました、すぐに参ります。」今後の事を考え始めながら、ユーリはユーフィリアの元へと向かった。「ユーリ様、先程は倒れられましたけれど大丈夫ですか?」「はい。それよりもユーフィリア様、ダブリス側の国境が封鎖されたというのは本当の事でしょうか?」「ええ。疫病はもうダブリス中に猛威を振るい、リヒトの街は一面焼け野原になったとか。恐らくそれも悪魔の仕業でしょうね。」ユーフィリアは紫紺の瞳を曇らせながら、庭園の中を歩き始めた。「ユーフィリア様、ルディガー皇太子様は・・わたしの兄です。」「知っております。ルディガー皇太子様は一体何をお考えなのでしょうね?」「それは・・わたしにも解りません。」ユーリにとってただ一つ解るのは、ルディガーが完全に常軌を逸しているということだけだった。「足元に気をつけて歩きなさい。」一方アベルと璃音は、アンドリューとその部下から背後に剣を突き付けられながら、リヒトの地下通路を歩いていた。「一体わたし達を何処へ連れて行くつもりです?」「行けば解ります。後少しで出口です。」暗闇の中をアベル達は歩き続けると、やがて地下通路の出口へと出た。そこには、蔦に覆われた修道院が建っていた。「ここは・・?」「ちょっと失礼。」アンドリューはそう言ってアベルの前に出ると、首に提げていた鍵を取り出し、十字を切った。すると古びた扉が軋んだ音を立てながら開いた。「お父様、怖いよ・・」不気味な風音に怯えながら、璃音はアベルの腰にしがみ付いた。「大丈夫、お父様がついているからね。」「こちらです。」アンドリューとその仲間が靴音を響かせながら修道院内へと入っていき、アベルは璃音の手を繋ぎながら慌てて彼らの後を追った。荒れ果てた外観とは違い、修道院内の大理石の床は鏡のように磨きあげられ、中庭の芝生も綺麗に刈り込まれている。「ここは、一体何処なのですか?」「ここはわたし達の家です。“お父様”があなたにお会いしたいとおっしゃるので、少々手荒な事をいたしましたが、こちらに連れて参りました。」アンドリューはそう言って笑みを浮かべたが、夜会の時に浮かべたものとは違うものだと、アベルは感じた。暗い感情を押し隠したかのような笑みを浮かべながら、アンドリューは修道院の最奥部にある部屋の前で止まった。「“龍の炎”と人魚の末裔の娘を連れて参りました。」「よろしい、入りなさい。」重厚な扉の向こうから、しわがれた老人の声が聞こえた。「失礼致します。」アンドリューとアベル達が部屋の中へと入ると、窓際に立つ老人がゆっくりと彼らの方を振り向いた。 老人の瞳は、アンドリュー達と同じ勿忘草色だった。にほんブログ村
2011年04月26日
コメント(0)
-

白銀之華 第145話
「ん・・」羅姫(らひ)が目をゆっくりと開けると、そこにはレースの天蓋がかかった寝台の上だった。「気が付かれましたか?」ドアが静かに開くとともに、女中が部屋に入ってきた。「ここは、何処?」「旦那様を呼んで参ります。」女中は羅姫の質問には答えずにそう言うと、部屋から出て行った。「ねぇあなた、あの子はもしかして、鴾和家の・・」「そうかもしれないな。あの子は追手から逃げる途中に崖から落ちたのだろうな。」「これからどうなさるおつもりですの? あの子は親兄弟を亡くしているのでしょう? うちの養女にするしかありませんわ。」「そうだな。これも主がわたし達とあの子をひき会わせたのかもしれないな。」晃之介がそう言って溜息を吐くと、女中が部屋に入って来た。「旦那様、あの子がお目覚めになりました。」「解った。冬香、君も来てくれ。」「ええ、あなた。」夫の部屋を出た冬香は、鴾和家の姫・羅姫が眠る部屋へと向かった。(一体此処は何処なの?)その頃羅姫は、自分が寝かされている寝台から部屋の内装を見渡しながら、鴾和家の寝殿造りとは違う趣の部屋でありながら、ここが上流階級に属する者の邸である事に理解した。「失礼致します。」部屋には先程の女中が入って来た。「旦那様と奥様がお見えです。」彼女はそれを言うと、部屋から出て行った。その後、背広姿の男性と、洋装姿の女性が入って来た。「あなたが、羅姫さんね?」「はい。わたくしは鴾和家の姫、羅姫です。助けて頂いてありがとうございます。」羅姫は女性に礼を言うと、彼女に頭を下げた。「わたくしは瀧丘冬香と申します。こちらは主人の晃之介よ。羅姫さん、これからあなたは瀧丘家の養女としてわたくし達と暮らしましょう。」「奥様の養女ということは、わたしはあなた方の家族になっても良いのでしょうか?」羅姫の問いに、洋装の女性―冬香はにっこりと笑った。「ええ、そうよ。これから宜しくね、羅姫さん。」この瞬間、羅姫の新しい人生が始まった。 その夜、彼女は瀧丘子爵家のダイニングルームで晃之介夫妻とその子ども達とともに夕食を取った。「お母様、その子だぁれ?」遥は突然現れた金髪の少女をじろりと睨みながら、そう言って両親を見た。「この子は羅姫さん。あなたの新しい妹よ。」「ふぅん、そうなの・・」羅姫は遥の敵意に満ちた視線を感じながらも、振り袖を着ながらもピンと背筋を伸ばしてワイングラスの水を優雅に飲んだ。 純和風の邸宅に住みながらも、香や鴾和家の者達は時間さえあれば羅姫と香欖に西洋のテーブルマナーをはじめ、礼儀作法や舞踏、刺繍やピアノなどの教養や、武術などを厳しく叩き込んでいた。それは、鴾和家の跡をいずれ継ぐ娘達が社交場に出ても恥を掻かぬようにとの親の想いからだったのだろう。それらが今確実に自分の中に生きていると、羅姫は感じた。「この子が、僕の新しいお姉様になるの?」冬香の隣に座っていた涼太が、円らな瞳を輝かせながら羅姫を見た。「ええ、そうよ。仲良くしてあげてね、涼太。」「よろしくね、お姉様。」「こちらこそ。」夕食の後、羅姫は用意された部屋の寝台に入り、ただじっと天井を見つめていた。その時初めて、両親が永遠にいなくなってしまった事を、彼女は解ったのだった。にほんブログ村
2011年04月25日
コメント(0)
-

白銀之華 第144話
夜明け前の山道を、一台の馬車が走っていた。 そこには瀧丘家(たつおかけ)の主、晃之介とその妻・冬香、そして彼らの子ども達である娘の遥と、息子の涼太が乗っていた。彼らは親戚の法事が終わり、この山道を抜けて帰路へとついている途中だった。「お母様、川に何か浮かんでるよ。」涼太がそう言って窓の外に流れる川を指した。「馬車を停めろ。」御者にそう命じるなり、晃之介は馬車から降りて川へと向かった。滔々(とうとう)と流れる川に、小さな少女の身体が浮き沈みを繰り返していた。晃之介は服が濡れるのも構わず川へと入り、少女を川から救い出した。「おい、しっかりしろ、おい!」彼が少女の頬を叩くと、彼女は薄らと蒼い瞳を開いた。「袋・・袋は・・?」晃之介は少女が首に提げている袋を見た。あの中には何か大切な物が入っているのであろう。「大丈夫、あるよ。」「あなたは・・」「こんなに濡れているね、可哀想に。」晃之介は寒さで震える少女の身体に自分が纏っていた羅紗織のコートで包むと、馬車の中へと戻って行った。「あらあなた、その子は?」「川で溺れていたんだ。」「まぁ、こんなに冷えて。それに全身傷だらけ・・きっとあそこの崖から落ちたのだわ。」冬香はそっと少女の頬を撫でた。「お母様、この子どうなさるの?」「それはお父様がお決めになることですよ。」馬車は再び動き出し、やがて山道を抜けた。 一方、ユーリと匡惟はエスティール皇国第二皇女・ユーフィリアと向き合うようにソファに座っていた。「その・・本当なんですか? ルディガー兄様が悪魔と契約し、ダブリスを滅ぼそうとしていると?」「ええ。今回の疫病は悪魔の仕業です。そしてあの方は・・ルディガー様は疫病を広めた罪をあなたの大切な友人に着せようとなさっているのです。」ユーリの脳裡に、香と蓮華の顔が浮かんだ。(まさか・・そんな・・)「ユーフィリア様、失礼致します。」「お入りなさい。」部屋に入って来た女官の顔が少し蒼褪めていて、ユーリは何か悪い知らせがあると感じた。「実は・・鬼族の里の者が、疫病を蔓延させたという罪で一族郎党処刑されたと。」「そんな・・」鬼族の里に滞在していた頃、香と蓮華は何かと妊娠中のユーリの体調を気遣ってくれ、良くしてくれていた。友人達が無実の罪を着せられ、処刑されたことを知った彼女はソファから立ち上がろうとしたが、その途端に気を失ってしまった。 隣で妻が顔を蒼褪めて鬼族の一族が処刑されたという知らせを受けているのを見た匡惟も、俄かに信じられなかった。ただ一つ解っているのは、ルディガーがダブリスを崩壊させようとしていることだ。「行かなければ・・鬼族の里に・・」ユーリはそう呟くなり、ソファから立ち上がると覚束ない足取りで扉へと向かったが、その身体は床に崩れ落ちた。「ユーリ様、お気を確かに!」「誰か、お医者様を!」女官達が慌てふためく中、ユーフィリアだけ平然とした様子で紅茶を飲んでいた。「どうなさったのかしら、ユーリ様?」目の前でユーリが倒れたというのに、平然としている皇女を、匡惟は思わず睨みつけた。にほんブログ村
2011年04月25日
コメント(0)
-

白銀之華 第143話
「敵の手にかかることなく自害して果てたか・・」馬から降りた敵兵は、互いに抱き合うような形をして果てている香と蓮華を見つめた。 金色の睫毛に縁取られた蒼い瞳は、もう開くことはないと知りつつも、鬼族の次期頭領である香がまだ死んでいないように思えた。彼はちらりと喉元を蓮華に切り裂かれ、息絶えた大将の遺体に転がっている懐剣を拾い上げ、白銀の刃を濡らしている血を懐紙で拭うと、刀身を鞘に納めた。「浅野殿!」「敵は自害して果てた。撤収せよ。」「はい・・それは・・」小姓の視線が、男が握っている懐剣へと移った。「この懐剣は我らのものではない。いずれ元の持ち主に返す日が来るまで、わしが預かっておく。」「は・・」「ゆくぞ、もうここには用はない。」再び馬に乗った男とその小姓は、鴾和邸から立ち去った。 同じ頃、高台へと女房達や里の者達とともに避難した羅姫達は、そこから鴾和邸が炎上し崩れ落ちるさまを見た。「父上、母上・・」羅姫は涙を堪えながら、血が出る程に唇を強く噛み締めた。その時、上空から羽音が聞こえたかと思うと、一羽の鷹が彼女の前に舞い降りた。(この鷹は、父上の・・)鷹の首に何かがぶら下がっていることに気づいた羅姫は、それを鷹の首から外して袋の口を開けた。そこには母・蓮華が愛用していた簪と、両親の結婚指輪が入っていた。「姉上、どうして泣いているの?」弟の言葉で、羅姫は初めて自分が泣いていることに気づいた。「何でもない・・」彼女はギュッと、両親の形見が入った袋を握り締めた。「羅姫様、香欖様、参りましょう。」「解ったわ。」(父上、母上、もう泣きません。鬼族としての誇りを持って生きてゆきます。)女房達と里の者達とともに、羅姫と香欖が山を下っていると、遠くから地鳴りのような蹄の音が聞こえた。(何?)「姉上!」馬の嘶きとともに、老人や子ども達の泣き叫ぶ声と、刀で肉を切り裂く音が風に乗って聞こえた。「香欖様、羅姫様、早うお逃げくだされ!」状況が解らずに呆然と立ち尽くしている羅姫達の手を、鴾和家の女房が引っ張った。「退け、女。わしらはお主が隠しておる子らに用がある。」「お願いです、どうか羅姫様は・・羅姫様達はお助けを!」女房は羅姫達を敵の手に渡すまいと彼女達を守るように立ち塞がったが、敵は躊躇いなく刃を女房の首に突き刺した。「お逃げ・・くだされ・・」女房は口端から血を流しながらも、羅姫達に微笑んだ。「香欖、行こう。」羅姫は恐怖に震えている香欖の手を握り、恐怖で委えている足を何とか奮い立たせると、袋を握り締めてその場から逃げた。「逃がすな、追え!」「矢だ、矢を射て!」キリリと、敵兵が矢をつがえる音が背後から聞こえ、羅姫と香欖は我武者羅に暗闇の中を走った。「香欖、大丈夫だから・・」羅姫がそう言って隣に居る弟を見ると、彼は敵兵の矢に射たれ、地面にゆっくりと倒れていった。「香欖、しっかりして!」「殺すな、生け捕りにしろ!」敵兵の声がすぐ近くで聞こえ、羅姫は弟をその場に残して再び走り出した。(ここまで来れば、もう・・)敵兵の声と彼らが持っている松明の炎が見えなくなるのを確認した羅姫がほっと安堵の溜息を吐いた瞬間、彼女の足元の地面が崩れ、彼女は崖から川へと真っ逆様に落ちていった。にほんブログ村
2011年04月24日
コメント(2)
-

白銀之華 第142話
「父様、母様!」 香と蓮華が次々と斬りかかっている敵を迎え撃っていると、遠くから子ども達の声がしたかと思うと、彼らは自分達のすぐ傍に立っていた。「羅姫(らひ)、香欖(からん)、来てはなりません!」蓮華は自分達に駆け寄ってきた双子にそう叫ぶと、彼らを睨んだ。「だって、わたし達だけ逃げるなんて出来ません!」「そうです父上、わたし達も戦って・・」「駄目です、お前達は逃げなさい。逃げて、生き延びなさい。」蓮華は腰を屈め、息子と娘にそう優しく諭すと、彼らの小さな背中を押した。「父様・・母様・・」炎に照らされた両親の黒髪と金髪は、禍々しい光を放っていた。「お前達は生きなければならない。鴾和の血を途絶えさせては・・鬼族としての誇りを途絶えさせてはいけないんだ。だから・・」香はゆっくりと振り向き、羅姫と香欖の頭を交互に撫でた。「俺達の生き様を、鬼族としての誇りをしっかりと目に焼き付けて逃げろ。」「父様、母様・・ここでお別れです。」羅姫は涙を袖口で拭い、両親に別れを告げ、弟の手を引いて邸から出た。「羅姫様、香欖様、ここにおられましたか! さぁ早う、高台へ!」邸から出てきた女房達は羅姫と香欖の手をそれぞれ引きながら、高台へと向かおうとしたが、香欖は足が地面に貼り付けられたように全く動こうとしなかった。「嫌だ・・父様と母様が・・」香欖は、燃え盛る邸の中へと入ろうとしていたが、羅姫が彼の頬を叩いた。「今は耐えるのです! 耐えて生き抜くのです!」真紅の瞳を涙で潤ませながら、香欖は邸から背を向けて姉達の方へと向かった。 邸の中では敵の断末魔と血煙が上がり、蓮華と香が握る刀は血と脂に塗れて重くなっていた。「蓮華、大丈夫か?」「ええ・・何とか・・」全身に返り血を浴びた彼らは、肩で息をしながら互いの背中を預けた。互いの息を合わせ今まで敵を斬って来た2人だったが、最早体力も限界が来ていた。彼らはここが己の死に場所だと、悟っていた。「香様、覚えておられますか? 昔、あの池で夏になると姉とわたくしと香様と3人で泳いでおりましたね。」「ああ、女房達や父上達にこっぴどく叱られたものだったな・・あの頃が一番、楽しかったな・・」「ええ・・あの子達は、これからどうなるんでしょうか? 楽しい思い出も作れずに、申し訳ないです・・」「何を言う。あの子達なら大丈夫だ。俺達の子だからな。」香はそう言うと、口笛を鳴らした。すると上空に旋回していた鷹がひらりと彼の腕に舞い降りた。「これを子ども達に。頼んだぞ。」香は鷹の首に袋を提げさせると、鷹は甲高く鳴いて再び上空へと飛んでいった。彼が鷹の姿が徐々に見えなくなっていくのを見届けていた時、背後の茂みから敵の残党が飛びかかって来た。「香様!」蓮華は敵の首に刃をめり込ませ、その返り血が白い顔を緋に染めた。「済まない、蓮華。」「何をおっしゃいます、わたくしはあなたの妻。今わの際までお供致します。」蓮華がそう言って香に微笑んだ時、香の脇腹を銃弾が貫いた。「香様!」「疫病を広めた忌まわしき鬼め、ここで成敗してくれる!」陣羽織の裾を翻しながら夫に向かって白刃を振り下ろす敵大将の喉元を、蓮華は懐剣で切り裂いた。「魔物め!」2発の銃弾が蓮華の首を襲い、彼女は吐血して香の腕の中で絶命した。「蓮華、お前を独りには死なせぬ・・」香はそっと絶命した妻の目を優しく閉じると、刃を頸動脈に突き立てた。朦朧とする意識の中で、香はかつてここで過ごした懐かしい日々を思い出していた。(羅姫・・香欖、済まない・・)宝石のような美しい蒼い瞳をゆっくりと閉じ、香は妻とともに27の短い生涯を終えた。にほんブログ村
2011年04月23日
コメント(0)
-

白銀之華 第141話
「やっと見つけた、人魚の末裔を。」 勿忘草色の瞳を狂気で輝かせながら、アンドリューはアベルの背後に隠れ、恐怖に震えている璃音を見つめた。「いや・・来ないで・・」「怖がることはありませんよ。」アンドリューはそう言うと、何かの印を結んだ。その途端、璃音の小さな身体は誰かに突き飛ばされたかのように床へと吹っ飛んだ。「璃音!」「彼女を助けたければわたしと来るのです。」アンドリューは壁にぶつかり痛みで呻く璃音を見ながら、アベルの方へと向き直った。「一体あの子に何をした!?」「煩い口ですね。暫く黙って頂きましょうか。」そう言うなりアンドリューはアベルの鳩尾を拳で殴った。(ユーリ様・・)意識を失う前、アベルは愛しい人の名を呼んだ。(今、誰かに名を呼ばれたような気が・・)一方、ユーリは夫と息子と共にエスティール皇国第二皇女・ユーフィリアに謁見する為に兵士に引率され、彼女の部屋へと向かっていた。「どうされましたか、ユーリ様?」眠っている息子を肩に担ぎながら、匡惟は妻が突然歩みを止めたことに気づいた。「いや・・さっき誰かに呼ばれたような気がして・・」「気のせいでしょう。」「いや、確かに・・」その時、部屋の扉の両脇を固めていた警備兵達がゆっくりと扉を開いたので、ユーリ達は慌てて部屋の中へと入った。「ユーフィリア様、ダブリスのユーリ様がお見えになられました。」「そうですか、お前達はもう下がりなさい。」久しぶりに聞いたユーフィリア皇女の声は、何処か嬉しそうな様子だった。ユーリ達がゆっくりと顔を上げると、そこには薄紅色の長い髪を結いあげたユーフィリア皇女が、宝石のような紫紺の瞳を輝かせながら彼らを見つめていた。「お久しぶりです、ユーフィリア様。こちらはわたくしの夫の匡惟と、息子の麗欖(れいらん)です。」「まぁ、可愛いこと。」「ユーフィリア様、わたくしに何故お会いしたいのですか?」「実は、この世界が滅びるかもしれないのです。」ユーフィリアはそう言って、窓の外を見た。「この世界が、滅びる?」ユーリの美しい眦が上がり、隣に立っていた匡惟も険しい表情を浮かべた。「ええ。あなたのお兄様・・ルディガーは悪魔と契約し、ダブリスの国民を殺そうとしているのです。」2人は、皇女の言葉を聞き絶句した。(ルディガー兄様・・)ユーリの脳裡に、幽閉される前に王宮でルディガーと過ごした楽しい幼少期の光景が浮かんだ。(どうして、わたし達は何処かで間違ってしまったのでしょうか・・) ダブリス王国の首都・リヒトの街は紅蓮の炎に包まれ、人々は逃げ惑いながらも炎の渦に巻き込まれて命を落とした。王宮から少し離れた大聖堂の尖塔の上に腰掛けながら、漆黒の羽根を畳んだリュミエルは、口端を歪めて笑った。「愚かな人間どもよ、燃えてしまえ。」「まぁ、綺麗です事。」「そうだろう、羅姫。この炎はわたし達の未来を照らす祝福の炎だ。」ルディガーは狂気に彩られた蒼い瞳を煌めかせながら、眼下に広がる炎を嬉しそうに見下ろしていた。 悪魔が放った業火は一晩でリヒトの街を焼き尽くし、その炎は鬼族の里にまで伸びようとしていた。「皆の者、高台に逃げよ!」「早うお逃げなさい!」里の者達を安全な場所へと避難させながら、蓮華と香は共に背中を預けて向かい来る敵へと刃を振るっていた。「父様、母様!」女房達に連れられて邸を出ようとしていた2人の子、羅姫と香欖(こうらん)は両親の元へと駆け寄ろうとしたが、女房達に止められた。にほんブログ村
2011年04月23日
コメント(0)
-

白銀之華 第140話
ダブリス王国を離れたユーリ達を乗せた馬車は、東へと向かっていた。「あの・・ここは何処ですか?」「ここはダブリスの隣国・エスティール皇国です。此処まで行けば疫病に罹ることはないでしょう。」兵士はそう言うと、ユーリに微笑んだ。「わざわざ送っていただき、ありがとうございます。」「いいえ、わたしは仕事をしたまでですから。ユーリ様方に会いたいとおっしゃるお方がおられまして・・」「わたしに会いたい方というのは?」「エスティール皇国第二皇女・ユーフィリア様です。」「ユーフィリア様が、わたしに?」ユーリの脳裡に、数年前の出来事が浮かんだ。 エスティール皇国第二皇女・ユーフィリアとは宮殿で開かれた舞踏会で数回会った事があるが、会話を一言二言交わしただけで、余り彼女とは親しくなかった。「はい。なのでこのままユーリ様方には皇宮に入っていただきます。」ユーフィリアは何故今になって、自分に会いたいと言い出したのだろうか?その理由は何なのかユーリが考え始めている間、馬車は皇宮の美しく装飾された白亜の門の下を潜った。「そうか、疫病がとうとう国中に広がったか・・」一方ダブリスでは、王宮のバルコニーからリヒトの街を見下ろしていたルディーガがそう言って背後に控えている悪魔の言葉を聞き、口元を歪めて笑った。「はい。どうされるおつもりですか?」ルディガーはゆっくりと悪魔に振り向くと、そっと彼の頬を撫でた。「街を焼き尽くせ。全員殺せ、1人たりとも逃がすな。」「御意。」悪魔は漆黒の羽根を広げると、外へと飛び立っていった。「行くぞ、我が妻よ。」「はい、あなた。」ルディガーが差し出した手を、羅姫はそっと握ると彼と共に部屋を出た。(何だか嫌な空だな・・)アベルがルクレツィア伯爵邸に用意された部屋の窓から空を見上げながらそう思っていると、部屋に璃音が入って来た。「お父様、嫌な空ね。」「ああ。どうしたの、璃音?」「あのね・・」璃音が口を開こうとした時、階下から突然悲鳴が聞こえた。「璃音、ここにいなさい。」「わかったわ。」アベルが階下に降りて悲鳴が聞こえた居間に入ると、そこには男の生首が転がり、レースのカーテンには赤黒い血が飛び散っていた。「一体何が・・」蒼褪めているレディー=ソフィーの方へと駆け寄ろうとしたアベルは、彼女の傍に首のない男の死体を見つけた。耳元で、冷たい音がした。「神よ、どうか我らをお救いくださ・・」レディー=ソフィーが祈りの言葉を捧げようとした時、彼女の喉元を白銀の刃が貫いた。「アンドリューさん・・どうして・・?」サーベルを握り締めている男の名をアベルが呼ぶと、彼―アンドリューはゆっくりとアベルの方へと振り向き、レディー=ソフィーの喉元から白銀の刃を抜いた。レディー=ソフィーは糸が切れた操り人形のように床に崩れ落ちた。「見られてしまいましたね。あなたにだけはこんな姿を見られたくはなかったのに。」アンドリューはそう言うと、刃を濡らす緋の血をペロリと舐めた。その瞳は、禍々しい光を湛えていた。「どうして・・こんな事を・・」「さぁ、自分でもよく解りません。」口端を上げて笑ったアンドリューは、ゆっくりとアベルの方へと近づいてきた。「お父様?」ドアが軋む音がして、璃音が居間に入って来た。彼女は目の前に広がる惨状を見て悲鳴を上げた。「彼女が、人魚の末裔ですね?」アンドリューの狂気じみた視線が、アベルから璃音へと移った。にほんブログ村
2011年04月22日
コメント(0)
-

白銀之華 第139話
激しい剣戟の音が、死の宮殿内に響いた。「随分と弱いのね。」そう言ってドレスの裾を翻しながら、羅姫は香を見た。彼の結い上げられた髪は崩れ、漆黒のドレスは血で赤黒く滲んでいた。「羅姫・・お前は・・あの男を・・親殺しの男を愛しているのか?」「ええ、とっても。わたくしを甦らせてくださったんですもの。」羅姫は優雅に微笑むと、香を見つめた。「わたくし、まだ死にたくはなかったの。美しく若い時にどうしてわたくしが死ななければならなかったのか、何故死んでしまったのかが解らなくて、暫く彼岸に呆然と立ち尽くしていたわ。そんな時、あの方が手を差し伸べてくださったの。」うっとりとした表情を浮かべながらルディガーとの出逢いを語る羅姫の顔を見ながら、香は胸が張り裂けそうだった。既に死んだ彼女が甦って目の前に居るというのに、当の彼女は他の男を想っている。(もう羅姫とは終わったんだ。しっかりしろ!)自分を叱咤した香は、剣の切っ先を羅姫に向け、突進した。彼女の胸に、香の刃が深々と突き刺さった。「どうして・・香様・・」紅の瞳を驚きで大きく見開かせながら、羅姫は生前愛した男を見つめ、彼の手を握ろうとした。だが香は廊下に倒れた羅姫を放置し、そのまま宮殿から出て行った。「羅姫、しっかりしろ、羅姫!」胸に剣が突き刺さったままの妻を抱き上げ、ルディガーは慌てて彼女を医者の元へと連れていった。「お帰りなさいませ、香様。まぁ、一体どうなさったんですの!?」「あちこち血だらけではありませんか!?」鴾和邸へと香が戻ると、彼の姿を見た女房達が悲鳴を上げ、慌ただしく衣擦れの音を立てながら廊下を走って行った。「香様・・」「蓮華、宮殿で羅姫に会った。」香がそう妻に告げると、彼女は蒼褪めた。「姉様が、宮殿に? それは本当ですの?」「ああ。ルディガーが羅姫を甦らせたらしい。悪魔と契約してな。」「では最近の疫病も、国王の死も全て、悪魔が関わっているんですね?」「恐らくそうだろう。俺はユーリが心配だ。あいつも疫病に罹らなければいいが・・」香の嫌な予感は的中し、ユーリは疫病に罹り、床に臥せっていた。全身に広がる謎の発疹と、高熱が彼女に襲い掛かり、ユーリは呼吸をすることがやっとの状態だった。「どうすれば妻の病は治りますか?」「まだ疫病の原因が掴めていないので、なんとも言えません。」医師はそう言って申し訳なさそうに匡惟に向かって頭を下げると、家から出て行った。「母様、死んじゃ嫌だ~!」麗欖はユーリの枕元でそう叫ぶと、彼女の手を掴んだ。「大丈夫、母様は死なないから。」ユーリが息子の頭を撫でていると、外から蹄の音が聞こえたかと思うと、軍服に身を包んだ数人の男が家の中に入って来た。「何だ、貴様ら!」匡惟がユーリと麗欖を庇うように男達と彼らの間に立つと、男の1人がじっと匡惟を見た。「あなたは、土御門匡惟様ですね?」「ああ、そうだが、貴殿らは?」「わたくし達は摩於様の命により参った者です。今すぐ妻子を連れてここから離れてください。」「だが妻は病気で動けぬ。」「この街に居る限り、奥方様の病は治りませぬ。」男の言葉に首を傾げた匡惟だったが、彼の言葉に従い匡惟達は荷物を纏め家を出ると、家の前には馬車が停まっていた。「父様、これから何処行くの?」「さぁ、わからない。でも大丈夫、母様の病気は治るから。」匡惟達を乗せた馬車はやがてダブリス王国を離れた。するとユーリの肌から謎の発疹が突然消えた。「ユーリ様、もう大丈夫ですか?」「ああ。」にほんブログ村
2011年04月20日
コメント(2)
-

麗しき薔薇 最終話
2011年9月。 ローゼンシュルツ王国皇太子・セーラは、夫・リヒャルトの立ち会いの下で男児を無事出産した。皇位継承者の誕生に、国民達は喜びに沸いた。「可愛らしいですね。」「ああ。」難産の末に男児を産んだセーラは、疲労困憊しながらも夫に微笑んだ。生まれた男児はガブリエルと名づけられ、両親の愛情に包まれてすくすくと育っていった。幸せの只中に居た2人は、この時黒い影が自分達に忍び寄っていることにまだ気づいていなかった。 2018年9月28日。 ローゼンシュルツ王国の首都・リヒトにある白鳥宮にて、ガブリエル皇子の7歳の誕生パーティーが賑やかに行われていた。「ガブリエル、何処に居るんだ?」「ガブリエル様、どちらにおられますか~!」「ガブリエル様~!」父や世話係達がパーティーの主役を探している頃、当の本人は母・セーラの部屋へと向かっていた。セーラの部屋は、白鳥宮から少し離れた翡翠宮にあった。「母上!」「ガブリエル、来たのか。」ガブリエルが母の翡翠宮に入ると、母は中庭で剣術の稽古中だった。「母上、お身体のお加減はもういいの?」「ああ。それよりもガブリエル、パーティーの主役がこんな所に居てどうする? 早く行きなさい。」「でも・・」「大丈夫、わたしは後で行くから。」そう言ってセーラは、渋る息子の頭を優しく撫でた。「じゃぁ、後でね!」笑顔で自分に向かって手を振る息子に、セーラは笑顔で手を振り返した。「セーラ様、そろそろお時間です。」「解っている。」剣術の稽古を終えたセーラはシャワーを浴び、身支度を終えると愛息子の誕生パーティーへと向かった。「ガブリエル様、誕生日おめでとうございます。」「ガブリエル様、おめでとうございます。」「ありがとう・・」次々と祝辞を述べてくる貴族達に向かって、ガブリエルは子どもながらに必死に愛想笑いを浮かべた。「誕生日おめでとう、ガブリエル。」セーラはそう言って息子に微笑むと、彼を抱き締めた。「ありがとう、母上!」「ガブリエルは相変わらず甘えん坊だな。将来が思いやられる・・」息子が母親にベッタリなのを傍目で見ながら、リヒャルトは溜息を吐いた。「なんだ、嫉妬しているのか?」「わたしはそんな訳では・・」リヒャルトがそう言った時、突然パーティー会場が爆音と炎に包まれた。「う・・」リヒャルトは低く呻きながら、ゆっくりと菫色の瞳を開いた。「なんだ、これは・・?」彼の目の前に広がっていたのは、優美な白亜の王宮が崩れ去り、瓦礫の山と化した無残な姿と、血の海だった。 その中に、全身蜂の巣となったセーラとガブリエルの姿があった。セーラは、しっかりとガブリエルを抱き締めていた。リヒャルトは突然の妻子の死と目の前に広がる惨状に、ただ呆然とするばかりだった。「セーラ様・・?」彼がゆっくりと妻子の元へと向かおうとした時、眩い閃光が彼の視界を遮った。 この日、テロリストが白鳥宮を襲撃し、死者は186人にも上った。その中には、セーラ皇太子とガブリエル皇子も居た。唯一の生存者であるセーラ皇太子の夫・リヒャルト=マクダミアは全身火傷を負い、4日後に敗血症にて死亡。この襲撃事件は“白鳥宮の悲劇”と呼ばれ、ローゼンシュルツ王国は再びテロの嵐に襲われ、中世以来600年以上続いた立憲君主制は廃止され、輝かしい王朝の歴史に幕を閉じた。 血で血を洗う内戦の末、共和国としてローゼンシュルツが生まれ変わったのは“白鳥宮の悲劇”から12年後の2030年の事だった。悲劇の舞台とされた白鳥宮は、忘れてはならぬ悲劇の歴史として保存され、そこには事件で犠牲となった者たちへの慰霊碑が建立され、かつて白鳥宮の庭園に咲き誇った白薔薇が毎日国民達によって供えられていた。「わたしは麗しき薔薇をこの手で摘み取ってしまった。この罪は一生消えないことだろう。」事件の首謀者であるテロリストは、処刑前夜に看守にそんな言葉を残していた。幾度もテロと戦争の嵐が吹き荒れ、侵略された王国は、共和国へと生まれ変わり、国民達は平和な日常を取り戻しつつあった。 しかし平和が訪れても、亡くなった者達は永遠に戻って来ない。麗しき薔薇達は散り、その花は永遠に咲く事は叶わない。白鳥宮の前に建つ慰霊碑には、今日も誰かによって供えられた白薔薇の花束が美しく咲き誇っていた。慰霊碑には、王国を心から愛し、変革しようとしていたセーラ皇太子とリヒャルト、そして2人の息子、ガブリエル皇子が描かれた肖像画が嵌めこまれてあった。かつて王家の花とされていた白薔薇は、今や悲劇の花として世界中で知られる花となった。 ローゼンシュルツ王家の皇妃達に代々受け継がれていたダイヤモンドとエメラルドのブローチは、スイスのレマン湖畔にある修道院内に展示されており、祝福と歓喜に満ちたセーラの胸元を飾っていたブローチは、悲劇の象徴として哀しくも美しい輝きを放っていた。―FIN―ほのぼのラストかと思いきや、何とも後味の悪いラストになってしまいました。読者の皆様、すいません。戦争の愚かさ、亡くなった命と引き換えに生まれ変わった国。悲劇の歴史の象徴として最後にあのブローチを登場させました。にほんブログ村
2011年04月18日
コメント(4)
-

麗しき薔薇 第22話
2011年5月、ブタペスト。新緑薫る季節に、2組のカップルがマチャーシュー教会で結婚式を挙げようとしていた。 Aラインの純白のウェディングドレスを纏い、白いレースのヴェールで顔を覆った瑞姫オーストリア=ハプスブルク帝国皇太子妃と、白い軍服を纏ったルドルフ皇太子がゆっくりと祭壇へと向かう。 彼らの背後には、純白のマーメイドラインのドレスを纏ったローゼンシュルツ王国皇太子・セーラと、白いタキシードを長身に包んだリヒャルトは、幸せそうな笑顔を浮かべていた。 2組の幸せそうなカップルの結婚式が、粛々と行われた。「まぁ、見てくださいな、あなた。セーラの幸せそうな顔・・」アンジェリカはそう言って隣に座っている夫を見たが、彼は終始仏頂面だった。「皇太子妃様、万歳!」「オーストリア、万歳!」「セーラ様、万歳!」「ローゼンシュルツ、万歳!」マチャーシュー教会から出た2組のカップルを乗せた白亜の馬車が教会を離れゲデレー城へと向かう凱旋パレードでは、オーストリア=ハプスブルク帝国民とブタペスト在住のローゼンシュルツ国民達が、それぞれの国旗を振りまわしながら歓声を上げた。「皆さん、わたし達の結婚を祝福してくださっているようですね。」「ああ。」セーラはそう言うと、胸元を飾るダイヤとエメラルドのブローチにそっと触れた。「ルドルフ様とミズキ様も、お幸せそうで何よりだ。」自分達の前方を走る馬車に乗っているもう1組のカップルの笑顔を思い出しながら、セーラは愛しい夫の顔を見た。「セーラ、リヒャルト、結婚おめでとう。」2組のカップルの結婚披露宴にて、アンジェリカが嬉しそうに花嫁衣装に身を包んだセーラの元へと駆け寄った。「そのティアラ、良く似合ってるわ。」「ありがとう、母上。」 セーラの頭を飾るティアラは、ローゼンシュルツ王国の皇妃や皇女、皇太子妃から中世の頃まで代々受け継がれてきた名品だった。 繊細なカメオ細工が施され、周囲を真珠とエメラルドを鏤めたそれは、シャンデリアの下で美しい輝きを放っていた。「セーラ様、リヒャルト様、ご結婚おめでとうございます。」「ありがとうございます、ミズキ様。」「リヒャルト様と、末永くお幸せに。」「ありがとうございます、ミズキ様。」セーラの元に、挨拶を終えた瑞姫とルドルフがやって来た。「これから色々と大変でしょうけど、お二人ならどんな困難も乗り越えられると思うわ。」「ありがとうございます。ただひとつ心残りなのは、今この場で養父に自分の花嫁姿を見せられないことです。」5歳の頃からセーラを実子のように育てていた養父は、数年前に鬼籍に入ってしまっていた。「きっと天国から、あなた方の幸せな姿を見守ってくださっていることでしょう。」「ええ・・」結婚式が行われた翌週末、ローゼンシュルツ王国皇帝夫妻と、セーラ皇太子とリヒャルトは、王室専用の豪華客船でナポリ港から出航し、母国へと帰っていった。「あのお二人、幸せそうでしたわね。」「ああ。」ナポリ港から出航した豪華客船をオペラグラス越しに見た瑞姫とルドルフは、溜息を吐いた。「ねぇあなた、またあのお二人といつか遠乗りや狩猟を楽しみたいわね。」「そうだな。もう風が冷たくなったから、部屋に入ろうか。」燦々と輝く太陽に背を向けた瑞姫達は、部屋の中へと消えていった。セーラとリヒャルト、瑞姫とルドルフ様の結婚式を書いてみました。次回が最終回です。にほんブログ村
2011年04月16日
コメント(0)
-

麗しき薔薇 第21話
(こいつ・・あの時の・・)「お久しぶりです、セーラ様。いつぞやは失礼な事を・・」ハンナはそう言って、セーラの視線に気づき彼に向かって頭を下げた。「着替えを持って参りました。」ハンナが用意したのは、胸に白薔薇のコサージュが付いたワインレッドのドレスだった。「ありがとう。」「母のドレスなんです。きっとセーラ様に似合うかと思いまして・・」ハンナからドレスを受け取ったセーラが着替えを終えて衝立の陰から出て来ると、ヒメルは歓声を上げた。「良くお似合いですよ。」「そうですか。ではわたしはこれで。」「ドレスはクリーニングを終えた後、お届けいたします。」ハンナはそう言って頭を下げた。「セーラ様、そのドレスは?」セーラをパーティー会場で待っていたリヒャルトは、彼が纏っているワインレッドのドレスを見た。「着替えを借りてきた。汚れたドレスは後でクリーニングして返すとあのメイドが言っていたが、本当に返すかどうか・・」「ヒメルとかいう少年はどうでしたか?」「余り良く解らない奴だったな。もう帰るか。」「ええ。」リヒャルトとセーラは、何ひとつ収穫を得られないままハイゼルフ子爵邸を後にした。「ねぇハンナ、そのドレスどうするつもりなの?」リヒャルトとセーラを乗せた馬車が子爵邸を出て行くのを窓から見ていたヒメルは、そう言ってメイドを見た。「クリーニングしてお返しいたします。」「それじゃぁつまんないよ。僕がこれを着てセーラ様に会いに行こうかな。驚くだろうね、きっと。」ヒメルは口端を歪めて笑ったが、その目は笑っていなかった。 翌日から、セーラとリヒャルトは結婚式の準備に追われ、セーラはウェディングドレス選びの為にプラハ市内のブライダルサロンに来ていた。「セーラ様はAラインよりもマーメイドラインのドレスがお似合いですね。」「そうか? マーメイドラインだとウェストが目立つんだが・・」「一生に一度の結婚式ですから、あなたの美しさを引き立てるドレスをお決めになってください。」そう言ったリヒャルトは、嬉しそうに恋人を見ていた。「じゃぁマーメイドラインのドレスにしようかな。」セーラはカタログを閉じると、そう言って店員を呼んだ。「かしこまりました。仮縫いなどで少々お時間がかかりますが、宜しいでしょうか?」「構わない。」「お色直しの回数はいかがいたしましょう?」「まだ決めてないが、それは両親と相談する。」サロンを出たセーラは、馬車に乗り込むと同時に溜息を吐いた。「ただ神の下で永遠の誓いを交わして終わり、という訳にはいかないのだな・・」「結婚は2人だけのものですが、ひっそりと内輪で挙げる式にはどうやらいないようですね。」「ああ。それに結婚式を間近に控えているというのに、婚約者からは婚約指輪ひとつも貰っていないしな。」セーラがわざとらしく溜息を吐いてリヒャルトを見ると、彼はスーツのポケットから何かを取り出した。「わたくしと、結婚してくださいませんか?」リヒャルトは長方形の箱を開けると、そこにはダイヤモンドのエンゲージリングが入っていた。彼はそれを箱から出すと、セーラの左手薬指に嵌めた。「イエスだ。但し、浮気したら殺されると思え。」「解りました。」リヒャルトは苦笑しながら、セーラを見た。「セーラ、久しぶりね。リヒャルトも。」「母上。」プラハ城へと帰ると、そこにはアンジェリカが立っていた。「お久しぶりです、皇妃様。」「あなた達はいずれこうなるかと思っていたわ。」やっとセーラの母親が登場。次回はセーラとリヒャルト、瑞姫とルドルフ様の結婚式です。にほんブログ村
2011年04月16日
コメント(2)
-

麗しき薔薇 第20話
カレル大学で開かれたチャリティファッションショーから数日後、セーラの元にハイゼルフ子爵から園遊会の招待状が届いた。「ハイゼルフ子爵といえば、かつて栄華を誇った名門貴族だというが、今や没落寸前の貧乏貴族になり下がったと聞く。」「ええ。ですが園遊会を開く余裕がおありのようで。」セーラは入院していた時に病室を訪れたハンナというメイドの存在が気になり、ハイゼルフ子爵の園遊会に出席する事にした。「結婚式の準備で、色々と忙しくなるな。」「ええ。アンジェリカ様がアルフリート陛下を説得してくださって良かったです。あれ程反対されていた陛下があっさりとわたくし達の結婚を許してくださったのは、何か裏があると思うのですが・・」リヒャルトがそう言って眉間を揉むと、セーラは溜息を吐いた。「別にそんな事を考えなくてもいいだろう。これから結婚式の準備に追われるんだからな。その後は出産準備に取りかからなければならないし。考えただけで頭が痛くなりそうだ。」「そうですね。安定期に入ってから結婚式を挙げるか、それとも出産後に挙げるかは、後で考えるとしましょうか。」「安定期に入ってからだ。出産後は育児に追われて結婚式の準備どころではなくなるからな。」「そうですね。」恋人達は互いの顔を見合せながら、笑い合った。 ハイゼルフ子爵の園遊会は、没落寸前まで落ちぶれてしまったものの、かつての名門貴族としての栄華を感じさせる豪華なパーティーで、ボヘミアやオーストリアの貴族達を楽しませた。「ハイゼルフ子爵は何処に?」袖口と襟元にレースがふんだんに使われた蒼のモスリンのドレスを着たセーラは、帽子のつば越しに招待客の中からハイゼルフ子爵の姿を探そうとした。その時、彼は誰かにドレスを掴まれた。振り向くと、そこには金髪の少年が立っていた。歳の頃は13,4位か、アイスブルーの瞳を輝かせながらセーラを見つめていた。「あなたが、セーラ皇太子様ですね?」「ああ、そうだが。」「初めまして、わたしはヒメル=ハイゼルフと申します。以後お見知りおきを。」「あなたが、ハイゼルフ子爵ですか。随分とお若いですね。」「ええ。先代である父が数年前に亡くなって、爵位を急遽継がねばなりませんでしたから。」そう言って子どもらしい笑みを口元に浮かべているヒメルだったが、彼が視線をセーラからリヒャルトへと移した時、急に彼の顔が険しくなった。「あの方は?」「これは、わたしの婚約者であるリヒャルト=マクダミアです。」「婚約者ですか・・?」「ええ。どうかなさいましたか、子爵?」「いえ、何でもありません。それよりもセーラ様、後で2人で色々とお話しを・・」ヒメルが一歩下がってそう言った時、ウェイターがバランスを崩し、シャンパングラスをセーラのドレスに掛けてしまった。「申し訳ございません!」「いえ、お気になさらず。リヒャルト、行くぞ。」「はい。」セーラがリヒャルト共に子爵邸の中へと入ろうとすると、ヒメルがセーラの手を掴んだ。「わたしが案内致します。セーラ様、参りましょうか。」「ではお言葉に甘えて。」(この餓鬼、一体何を考えている?)ちらりとリヒャルトの方を見たセーラは、彼が静かに頷いていたのを確かめると、ヒメルとともに子爵邸の中へと入った。「汚れを落としますので、ドレスを脱いでください。」「はい。」化粧室に置かれた、金箔を使った豪奢な衝立の陰に隠れたセーラは、ドレスを脱いだ。「失礼致します、旦那様。」ドアが開き、誰かが入って来る気配がした。「お客様のドレスの染みを取ってくれ。それと着替えのドレスを。」「かしこまりました。」セーラがそっと衝立の陰からヒメルの方を見ると、そこにはあのメイドの姿があった。ひょんなことで、実の両親からリヒャルトとの結婚の許しを得たセーラ。これから式の準備に忙しくなりそうですね。そして、あのメイドと、クソ生意気な貴族の少年が登場。そういえば、瑞姫とルドルフ様が出ていない(。゚ω゚) ハッ にほんブログ村
2011年04月15日
コメント(0)
-

麗しき薔薇 第19話
「とにかく、わたしはリヒャルトとお前との結婚には反対だからな!」「そうですか。どうぞあなた方はぎゃぁぎゃぁ騒いで居て下さい。わたしとリヒャルトの居ない所でね。」「お前は親に向かって何て言葉を吐くんだ!」「顔を合わせば一方的に自分が言いたい事を捲し立てる父上が、何をおっしゃいますか!」セーラとアルフリートの口論が、一般病棟の廊下にまで連日響き、その度に患者達は何事かとVIP病室の方をちらちらと見ながらひそひそと囁き合っていた。「セーラ様、陛下、もうその辺になさいませ。毎日顔を合わせれば喧嘩ばかりなさっては、セーラ様のストレスが溜まります。陛下、どうぞお引き取りを。」「わかった・・」アルフリートは不快そうに鼻を鳴らしながら病室から出て行くと、セーラは溜息を吐いた。「全く、頭が痛い・・」「お水をお飲みになってくださいませ。アルフリート陛下は一方的過ぎますわね。セーラ様の意見も聞かず、リヒャルトとの結婚を反対されるなど・・弟はセーラ様の結婚相手として相応しいですわ。一体何が気に入らないのでしょう?」「さぁ・・長い間生き別れていて、実の両親と暮らし始めたのはほんの数年間だから、余り父上達が何を思っているのかが解らない。だが、親は常にこの幸せを優先しようと思うのは正しいかもしれないな。」セーラは水を飲むと、ベッドに横たわった。「セーラ様、退院後の予定ですが、カレル大学でチャリティファッションショーへのご出席はどうなさいますか?」「勿論出席するに決まっているだろう。ヒールのある靴も履き慣れてきたし。」「そうですか。英国時代には、貴婦人姿がさまになっておられたと未だに噂されておりますよ。」「まぁ、あれも良い経験になったな。色々と苦労したが。」「セーラ様を支持される国民は多いですわ。貴族階級のみならず、労働階級からもセーラ様を次期皇帝にと望む声がありますし。」「ふぅん、そうなのか。それよりも、ミズキ皇太子妃様とルドルフ皇太子様は仲睦まじいご夫婦だな。わたしとリヒャエルも、ああなりたいが・・」「ミズキ皇太子妃様はウィーン宮廷に入られてまだ日が浅く、色々と苦労されているそうですが、ルドルフ皇太子様がバッグアップなさっておられますからね。セーラ様と弟も、近い内にお二人のような仲睦まじい夫婦になれますわ。」セーラは、レイチェルの言葉に笑顔を浮かべた。 数週間後、カレル大学で開催されたチャリティファッションショーで、モデルとして出席したセーラは、素肌に緋のドレスを纏いランウェイを颯爽と歩いた。豊かなブロンドの髪を波打たせ、真珠色の肌に緋のドレスがよく映え、照明によって彼の全身は宝石のように美しく輝いた。ファッションショーには、ファッション界の名士達や高級ブランドデザイナー達が出席しており、セーラの艶姿に彼らは酔いしれ、何も飾らず自分らしさを身に纏ったプリンスの姿に感銘を受けていた。「セーラ様、素晴らしかったですよ。」「ありがとう。」ファッションショーが大盛況に終わった後、セーラは舞台裏で労いの言葉を掛けてくれた恋人に微笑んだ。「最近体調の方はいかがですか? 怪我の事もありますし・・」「大丈夫だ。久しぶりにハイヒールを履いて疲れてしまったがな。」セーラはそう言ってハイヒールを脱ぐと、足首をマッサージしながら溜息を吐いた。「余り無理をなさらないでくださいね。あなた1人のお身体ではないのですから。」「ああ、解っている。全く、お前はいつも小言ばかり言うな。」セーラはリヒャルトの小言にうんざりしながらも、彼と共に過ごせる時間が嬉しくて仕方がなかった。両親への説得はまだ時間がかかるかもしれないが、セーラはリヒャルトと結婚して幸福な家庭を築きたかった。かつて、横浜の孤児院で養父に愛情深く育てられ、幸福であった幼少時代のような、愛に満ちた生活をセーラはいつしか夢見ていた。レイチェルの正体が明らかに。ちょっとブラコン気味なレイチェル。にほんブログ村
2011年04月13日
コメント(2)
-

麗しき薔薇 第18話
「皇帝陛下には困ったものですわね。」アルフリートを病室から追い出したレイチェルは、そう言ってセーラを見た。「コーヒー、お淹れいたしますわね。」「あ、ありがとう・・」突然事務的な態度を崩したレイチェルに、セーラは戸惑いを隠せなかった。「陛下はいつまで経っても子離れなさいませんわね。弟と結婚したら婿いびりをなさるかもしれませんわね・・」「弟って、じゃぁ君は・・」セーラはそう言ってレイチェルを見ると、彼女は照れ臭そうに笑った。「自己紹介が遅れましたわ、セーラ様。わたくしはリヒャルトの異母姉・レイチェルと申します。」「リヒャルトに腹違いの姉が居るなんて、聞いていなかったが・・」「わたくしも、長年異母弟の存在を知らずにおりました。リヒャルトの母親が悋気の強い性格で、わたくしの母を屋敷から追い出したものですから、彼の父親もわたくしの存在を知りませんでした。」「そ、そうだったのか・・」突然レイチェルがリヒャルトの異母姉と知り、セーラは暫し頭がぼうっとした。「い、今お母さんはどうしているの?」「母は、数年前に亡くなりました。丁度リヒャルトの母親もお亡くなりになったので、旦那様とわたくしは実の親子として漸く名乗りを上げることが出来たのです。」「へぇ、そう・・」リヒャルトとレイチェルは昨夜、普通に接していたが、その裏では色々と複雑な感情を互いに抱いていたに違いないと、セーラは彼女が淹れたコーヒーを飲みながら思っていた。「失礼致します。」セーラがコーヒーを飲んでいると、病室に1人のメイドが入って来た。「あの、どちら様ですか?」「申し遅れました、ハイゼルフ子爵家から参りましたハンナと申します。以後お見知りおきを。」「は、はぁ・・」「あら、ハイゼルフ子爵家といえば、数年前に宮廷から追い出された挙句、領地を没収された貴族と同じ家名ですわね? まだメイドを雇う経済的余裕がお有りになられるだなんて・・」「あらあら、そちらこそマクダミア公爵が外に産んだ女が、何故皇太子様のお傍にお仕えしているのかしら?」2人のメイドの間に、バチバチと見えない火花が散り始めていた。(一体俺はどうすれば・・)「セーラ様、お加減はどうですか?」リヒャルトが病室に入ってくると、ハンナと名乗ったメイドがそそくさと病室から出て行った。「ハンナ、どうだった?」「思っていたより守りが堅いです。あの姉弟は一筋縄ではいきませんから。」「そうだな・・」ハンナと話していた相手は、肩越しにセーラの病室を見た。「あの2人が居る以上、セーラ様と2人きりで話せる事はできません。」「急ぐ事はない、ハンナ。徐々に策を練り上げて行く方が良い。」「はい、旦那様。わたくしは旦那様のおっしゃる通りに致します。」「お前は良く働いてくれるな、ハンナ。」ハンナはにっこりと自分に仕えている相手を見下ろした。 そこには、金髪に灰青色の瞳をした少年が立っていた。「必ずセーラ皇太子と会わせてよね、ハンナ。頼りにしているよ。」「はい・・旦那様・・」少年はコートの裾を翻すと、病院の廊下を颯爽と歩いていった。「全く、手のかかる坊やだこと・・」そう言ってハンナは、溜息を吐いた。「没落寸前の嫡子として、家も財産も売り払い、残ったのは気位の高さだけとは・・皮肉なものね・・」彼女は口端を歪め、病院から出て行った。「ハンナ、遅かったね。」「申し訳ありません、旦那様。」「早く帰ろう。」「ええ・・」(愚かな子ども・・この子を地の底に叩きこむのは、このわたくし・・)また謎のメイド登場。にほんブログ村
2011年04月12日
コメント(4)
-

麗しき薔薇 第17話
翌朝、セーラは何かと自分に対して事務的な態度を取るメイド・レイチェルに少しストレスを感じていた。「セーラ様、お口をお開けください。」朝食が病室に運ばれて来た時、レイチェルはそう言ってスプーンでスープを掬い、それをセーラに食べさせようとした。「赤ん坊じゃあるまいし、これ位は出来る。」セーラがそう突っぱねると、レイチェルは不服そうに溜息を吐くと、病室から出て行った。(食事なんて1人で出来るのに。一体彼女は何を思ってやってるんだろう?)何故リヒャルトはあんな変わり者のメイドを雇ったのだろうと、セーラは首を傾げながらスープを飲み始めた。 幸い傷は大したことはなかったし、数週間で退院できるだろうと医師から言われていたので、出来る事ならセーラは大部屋に移りたかったが、一国の皇太子である彼が個人の我が儘を通せるほど甘くないということを嫌でも知っていた。「セーラ様、皇帝陛下がお見えになられました。」「皇帝陛下が? お通ししてくれ。」「かしこまりました。」フランツ=カール=ヨーゼフ帝の耳にも、今回の事件が届いたのだろうか。多忙な彼が自分に見舞いに来るなど珍しいなとセーラは思いながらパンを食べていると、病室に入って来たのは実父でローゼンシュルツ王国皇帝・アルフリートだった。「セーラ、身体は大丈夫なのか?」アルフリートはそう言うなり、ベッドで上半身を起こしている息子に勢いよく抱きついた。「お前が撃たれたと聞いて、議会を中止させてプラハまで来たんだ。無事で良かった!」「陛下、セーラ様はまだ本調子ではございませぬゆえ。」息子の無事を知り、涙を流して熱い抱擁をするアルフリートに向かって、レイチェルはピシャリとそう言うと、セーラを見た。「おお、済まぬ! それよりもセーラよ、お前の縁談相手には会ったか?」「会っていませんが。それよりも父上、このような忙しい時期に、わざわざプラハまでおいでとは・・母上は何も言わなかったのですか?」あの日以来、“影の支配者”とまで呼ばれるようになった母皇妃・アンジェリカの事をセーラが聞くと、アルフリートは苦笑いを浮かべながらこう答えた。「アンジェリカは数日後お前に会いに来る。国に戻ったら結婚式の準備やお前の快気祝いのパーティーの準備で忙しいから、プラハに居る間は親子水入らずで過ごしたいと思ってな。」「結婚式とは、一体何の事ですか? わたしはリヒャルト以外誰とも結婚する気はないと申した筈でしょう?」セーラがそう言って冷たい目で父親を見ると、彼は口ごもった。「お前ももう30だ、セーラ。結婚適齢期をとうに過ぎているし、お前と同年代の相手を見つけるのも簡単な事ではない。早くお前には身を固めて欲しいと思っているんだよ。」アルフリートの言い分も解るし、子を心配する親心も解るが、一方的に自分の結婚を決めてしまう両親に嫌気が差した。「父上、わたしはリヒャルトの子を妊娠しております。」「それは・・冗談ではないのか?」鳩が豆鉄砲を喰らったかのような顔を浮かべながら、アルフリートはセーラを見た。「ええ。リヒャルトはわたしと結婚すると申しておりますし、わたしも彼との結婚を望んでいますので・・」「ならん、ならんぞ! 婚前交渉などもっての外だというのに、妊娠した上にお前がリヒャルトに結婚を迫るなど、あってはならん事だ、恥ずべき事だ!」暫くして状況を呑みこめたアルフリートはセーラの言葉を聞いた途端、烈火の如く怒った。「今は21世紀、婚前交渉など交際しているカップルの間では当たり前ですし、順序は違えども妊娠して結婚するなんて事はもう珍しくも何ともありません。新しい時代に生きているというのに古い時代の価値観を持ち出さないでいただきたい!」「何と言う事を・・」アルフリートがセーラに手を挙げようとすると、レイチェルが咄嗟に彼を押さえた。「陛下、ホテルにお戻りください。セーラ様を暫くお独りにして差し上げてください。」セーラと目が合ったレイチェルは、そう言った後口元に笑みを浮かべた。謎のメイド・レイチェル。セーラの実父、アルフリートさんが登場しました。にほんブログ村
2011年04月12日
コメント(0)
-

麗しき薔薇 第16話
「何を余所見しているのです!」 瑞姫の鋭い突きを、令嬢は辛うじて受けることしかできず、あっという間に彼女は壁際まで追い詰められた。 鬼神の如く剣を振るう瑞姫の漆黒の瞳は、禍々しい黄金色へと変化していた。「ひぃ・・」令嬢は泣きベソを掻きながらも、必死に反撃しようとしたが、瑞姫はそんな彼女の小さな勇気をも挫いた。瑞姫の一撃で令嬢の手から剣が弧を描き大理石の床に突き刺さった。彼女はドレスの裾をたくし上げ、令嬢を蹴飛ばし彼女の上に馬乗りになって鋭い剣の切っ先を向けた。「良く回るお前の舌は剣の前では役に立たなかったようね?」口端を歪めて瑞姫は令嬢に向かって笑うと、彼女は涙を流した。「お、お許しを・・」「お黙り、この脆弱者が!」瑞姫は泣き叫ぶ令嬢を無視すると、鋭い刃を彼女に向かって振り下ろそうとした。「やめないか、ミズキ。彼女を許してやれ。」ルドルフはそう言って、剣を振り下ろそうとする瑞姫の手を握った。「命拾いしたわね?」興を削がれ、瑞姫はつまらなそうに舌打ちした。「妻が乱暴な真似をしてすまないね?」ルドルフはちらりと令嬢を見ながら彼女に微笑むと、彼女は頬を赤く染めた。「ウィーン宮廷で生き残りたければ、噂をばら撒くその舌を引っ込めておくんだね。さもなくばわたしの妻が君の舌を引っこ抜く時が来るだろう。」耳元で彼女に甘い声でそう脅すと、ルドルフは瑞姫の元へと戻った。「これで暫く、余計な噂を広げようとする者は居なくなるでしょう。」「ああ。でもかなり派手にやり過ぎたんじゃないか?」「いいじゃありませんか、あんな者達を黙らせるくらいなら。」瑞姫はそう言って扇子の陰で笑い始めたが、その目は全く笑っていなかった。彼女を怒らせると怖いと、ルドルフが実感したプラハの夜は静かに更けていった。 一方、プラハ市内の病院にあるVIP専用病室で、セーラは呆れた顔でリヒャルトを見ていた。「お前、プラハ城に戻らなくていいのか?」「そうですね・・ずっとあなた様のお傍についているのも限界がありますし。」「失礼致します。」ドアがノックされ、病室の中に入ってきたのは、白いエプロンに青いワンピースを着たメイドが入って来た。「セーラ様、こちらがあなた様が入院なさっている間の世話係の、レイチェルです。レイチェル、くれぐれもセーラ様の世話を怠らないように。」「かしこまりました、リヒャルト様。」そう言ってメイドはリヒャルトに頭を下げると、ちらりとセーラを新緑の瞳で見つめた。「初めてお目にかかります、セーラ様。心からあなた様にお仕え致します。」「よ・・宜しく・・」セーラは何処か事務的な態度のメイドを見ながら少し戸惑っていたが、わざわざ忙しい時間を割いてプラハに来てくれたのだから、文句は言えまい。「ではわたくしはこれで。レイチェル、後は頼んだぞ。」「はい。」リヒャルトが病室から出て行くと、セーラは溜息を吐いてベッドに寝転がった。「セーラ様、早くお休みになられてください。夜更かしなさるとお身体に差し支えますので。」「わかった・・」(何だか慇懃無礼なメイドだな・・)レイチェルと退院するまで彼女と一緒に過ごすのかと思うと、セーラは気が沈みそうになった。 病院を出てプラハ城へと向かっているリヒャルトは、病院で預かったセーラのバッグの中で、彼の携帯が振動していることに気づいた。『もしもし?』「貴様は誰だ?」相手はリヒャルトの質問に答えずに通話を切り上げた。リヒャルトは携帯の電源を落とし、バッグの中へとしまった。漆黒の闇に包まれてゆくプラハの街を、フロックコートの裾を翻しながらリヒャルトはカレル橋を渡り始めた。その先には、荘厳なプラハ城が聳え立っていた。にほんブログ村
2011年04月11日
コメント(2)
-

麗しき薔薇 第15話
数分後、“オディール”はセーラ皇太子暗殺未遂の容疑でチェコ警察に逮捕された。そのセーラ皇太子は、プラハ市内の病院で一命を取り留め、彼が宿していた小さな命も無事だった。「う・・」「セーラ様、お気づきになられましたか?」「リヒャルト・・済まないな・・」「何をおっしゃいます、セーラ様。あなたがご無事で良かった!」リヒャルトはそう言うと、セーラに覆い被さって泣いた。「殿方って、あんなにお泣きになるものなのね。」病院から出た瑞姫がそうぽつりと呟くと、ルドルフは苦笑しながら馬車へと先に乗り込んだ。「リヒャルト殿は、セーラ様を本当に心の底から愛しておいでだ。」「そうですわね・・セーラ様は幸せ者ですわ、愛して下さる方が傍に居て。」「わたしでは不満か、ミズキ?」「いいえ。」瑞姫とルドルフは互いの顔を見合せると、唇を重ねた。「舞踏会は中止になるかしら? あんな事があったのだから当然だと思うけれど・・」「さぁな。父上にはこの事を報告したし、まだ安心できないから警備を怠るなと城内の者には伝えている。」ルドルフはそう言って溜息を吐いた。今夜プラハ城で開かれる予定だった舞踏会を急遽中止にすることを、ルドルフの一存では決められなかった。現に、ルドルフの父・フランツ=ヨーゼフは、セーラ暗殺未遂事件の報告をルドルフから聞いても、“予定通りに舞踏会を開け”とウィーンからの電報で言ってきたのだから。 セーラが不在のまま舞踏会が開かれる事で、何か嫌な予感がしたルドルフだったが、瑞姫にはそんな事は言えなかった。「あら、今夜はセーラ様はいらっしゃらないのね?」「何処へ行かれたのかしら?」「あなた、ご存知ないの? セーラ様はリヒャルト様に横恋慕した女に撃たれたそうよ。」「なんでもその女の方がセーラ様よりも先にリヒャルト様の方をお慕いしていらしたとか・・」「それを横からセーラ様が掠め盗ったということなの?」プラハ城の大広間で開かれた舞踏会では、噂好きの貴婦人や令嬢達が根も葉もない噂話をひそひそと囁き始めているのを聞いた瑞姫は、怒りが沸点に達しそうだった。彼らは何も知らないで、無責任な噂話をこの場で広め始めようとしている。そんな事はさせるものか―瑞姫は彼女達の元へと近寄ると、その中の1人の肩を叩いた。「ちょっと、そこのあなた。」「まぁ皇太子妃様、何か?」振り向いた彼女に、瑞姫は右手に嵌めていた長手袋を投げつけた。「あなたはこの場で、わたくしの友人の名誉を汚しました。よって決闘を申し込みます。」瑞姫の凛とした言葉に、先ほどまでざわついていた大広間がしんと水を打ったように静かになった。「そんな・・決闘など・・」「手加減はしていただかなくても結構よ。誰か、剣を!」突然の事に戸惑う周囲を余所に、ルドルフは苦笑しながら友人達とその光景を遠巻きに見ていた。「止めなくてもよろしいのですか?」「ミズキはやると言ったら聞かない性格だ。彼女達を黙らせるには絶好の機会だとは思わないか?」やがて彼女達の元に二振りの剣が渡され、互いに背を向け十歩歩き始めた。―まさか本気で皇太子妃様は決闘をなさるおつもりで?―なんという方なのかしら・・瑞姫が十歩目で振り向くと、そこには恐怖で蒼褪め、剣を握り締めて震える令嬢の姿があった。彼女は周囲に助けを求めるように目を泳がせたが、その時瑞姫の剣の切っ先が令嬢が持っていた剣に触れ、彼女は悲鳴を上げた。「何を余所見しているのです!」瑞姫さん、キレる。まぁ、決闘相手にされたお嬢様も気の毒だと思いますけれど、瑞姫さんにコテンパンにされるといいと思います(←オイ)にほんブログ村
2011年04月11日
コメント(0)
-

麗しき薔薇 第14話
聖ヴィトー大聖堂から出たリヒャルトは“オディール”をすぐさま追ったが、コルセットでウェストを締めあげられた上に裾の長いドレスを纏い、踵の高い靴を履いている彼女は、どんどんリヒャルトとの間に差が開き始めていた。(くそ、逃げ足が早い!)リヒャルトは舌打ちしながら、護身用の拳銃を取り出し撃鉄を起こした。余り人を傷つけたくはなかったが、止む終えぬ状況というものがある。リヒャルトが“オディール”の右肩に狙いを定めて引き金を引こうとしていると、不意に彼女が振り向いて不敵な笑みを口元に湛えた。 その瞬間、リヒャルトの視界が怒りで赤く染まった。「銃声が聞こえたわ!」「一体何事かしら!?」「随分と近かったような・・」女官達の話を聞いた瑞姫とルドルフが聖ヴィトー大聖堂の方へと向かうと、そこには胸を撃たれ担架に乗せられたセーラの姿と、慌てふためくフィリップの姿があった。「フィリップ、何があった?」「あの女性が突然、セーラ様を撃ってきて・・リヒャルト様が・・」ルドルフは嫌な予感がして、妻と共にリヒャルトの姿を探した。 彼は、“オディール”に向かって銃を向けたまま、菫色の瞳を怒りで滾らせながら彼女を見ていた。「よくも・・よくもセーラ様を!」「殺したいのなら、殺しなさい。」「貴様!」リヒャルトは床に銃を投げ捨てると、“オディール”の首を右手で締めあげてその身体を宙に浮かせた。「お前は一体何を企んでいる、吐け!」「光は闇に呑まれるだけ・・ただそれだけの事。」リヒャルトは空いている手で“オディール”の右肩を握り潰すかのように掴むと、彼女は手負いの獣のような叫び声を上げた。「吐け、吐かぬか!」“オディール”は一瞬口元に笑みを浮かべると、リヒャルトに向かって唾を吐いた。リヒャルトは彼女の身体を地面に叩きつけ、彼女の上に馬乗りとなって万力のように彼女の首を締めあげた。「リヒャルト殿、止めないか!」「こいつが・・この女が、セーラ様を!」怒りで正気を失ったリヒャルトは、止めに入ろうとしたルドルフ達を睨み付けると、間髪いれずに“オディール”の頬を拳で殴った。彼女の端正な美貌がリヒャルトに殴られる度にいびつに歪み始め、口端や鼻から出血し、その血が大理石の床を赤く染め始めた。「この女を殺しても、セーラ様は喜ばないぞ!」「止めないでください、わたしはこの女を殺す!」ルドルフの背後で静観していた瑞姫がつかつかとリヒャルトの方に近づくと、彼の頬を平手で打った。「いい加減になさい! あなたが今彼女を殺したら犯罪者になりますよ! そうなって苦しむのはセーラ様と生まれてくるお子様なのですよ! この者にはしかるべき場で裁かれて貰いますから、安心なさい!」「皇太子妃様・・」瑞姫の言葉を聞いたリヒャルトが漸く“オディール”から離れると、瑞姫は夫の方を振り返り、こう言った。「サーベルをわたくしに渡して下さい。」「ミズキ、何をするつもりだ?」「早く、渡して下さい。」ルドルフは腰に帯びているサーベルを瑞姫に渡すと、彼女はその二本の長剣を地面に交差するように突き刺し、“オディール”の首を固定した。「フィリップ、警察に連絡を。セーラ皇太子様を殺害しようとした犯人が居ると。」「はい・・皇太子妃様。」フィリップが慌てて身を翻して廊下の角へと消えてゆくのを見送った瑞姫は、腰を屈めて“オディール”の耳元でこう囁いた。「逃げられると思ったら大間違いですよ。」“オディール”の勝利に酔っていた蒼い瞳は、瑞姫の言葉で瞬時に恐怖へと彩られた。怒りにまかせ、“オディール”に拳を振るうリヒャルト。恋人が目の前で撃たれたのだから、当然と言えば当然ですが、殺人犯にはならなかった。どんな時でも冷静に事態を見極めようとしている瑞姫は、静かに“オディール”に向かって怒りをぶつける。感情をむき出しにした“怒り”よりも、感情をむき出しにせず静かに“怒る”方が怖いと思うのですが。“絶対零度の笑み”とか、一見微笑んでいるようにいるけれども、笑ってはいないとか・・。瑞姫の怒り方は、間違いなく後者の方に当てはまりますね。ルドルフ様も、時折熱くなりがちですが、冷静沈着な性格なので、同じ怒り方ですかね。にほんブログ村
2011年04月10日
コメント(0)
-

麗しき薔薇 第13話
ルドルフ達を乗せた蒸気機関車がプラハ駅へと着くと、乗客たちは一斉に降り始め、出口へと向かって行った。「セーラ様、お足元にお気をつけてください。」「ありがとう。」一等車両から先に降りたリヒャルトは、そう言ってさっと主に手を差し出した。セーラが辺りを見渡すと、乗客達も駅員たちもみなヴィクトリア朝時代の服装をしている。まるで、ヴィクトリア朝時代にタイムスリップしたかのような感覚にセーラは陥った。セーラは汽車が吐き出す煙の向こうに、人影が見えたような気がした。「セーラ様、どうされましたか?」「いや・・何でもない。」目を擦り再度人影を見ようとしたが、それはすぐに掻き消えた。「セーラ様、外へと参りましょう。」「ああ、解った。」駅からセーラ達が出ると、そこには瑞姫とルドルフの姿があった。「さぁ、参りましょうか?」「ええ。」四頭立てのハプスブルク家紋章付の馬車と、ローゼンシュルツ王家の紋章付の馬車が蹄の音を響かせながら、一路プラハ城へと向かった。「馬車に乗ったのは初めてだが、少し揺れるな。」「ええ。それよりもプラハ城に行かれる前に、何処か寄りたい所でもありますか?」「いや・・プラハ城に着いたら聖ヴィトー大聖堂に行きたいんだが、いいか?」「わかりました。」2台の馬車はやがて、カレル橋を渡り始め、プラハ城へと入っていった。「ルドルフ皇太子、わたくしとセーラ様は聖ヴィトー大聖堂へと参ります。昼食会の時間には間に合うようにいたしますので。」「解りました。フィリップ、セーラ様達を聖ヴィトー大聖堂へとご案内しろ。」「はっ!」フィリップとセーラ達の姿が廊下の角へと消えると、ルドルフは溜息を吐いた。「ミズキ、“オディール”は昼食会に現れるか?」「さぁ、わかりませんけれど・・ご挨拶に来たのだから、現れるでしょうね。」ルドルフと瑞姫が汽車の中で話した“オディール”の行動を思い出していると、瑞姫は視線の隅に喪服姿の女性がこちらに向かって歩いてくるのが見えた。「あら、オディールさんではなくて?」「皇太子妃様、御機嫌よう。」“オディール”はそう言うと、瑞姫に向かって優雅に礼をした。「セーラ様を探していらっしゃるの?」「ええ。少しセーラ様とお話ししたい事がありまして・・」「彼ならお部屋で休まれていると思うわ。」瑞姫の言葉に、“オディール”の顔が少し曇った。「ミズキ、どうしてあんな嘘を吐いたんだ?」「セーラ様とあの方を会わせてはいけないかと思いまして。」 フィリップの案内で聖ヴィトー大聖堂へと向かったセーラは、首に提げていたロザリオを握り締めると、祭壇の前に跪き、天におわす父なる神に向かって静かに祈りを捧げた。フィリップとリヒャエルは、聖堂の入口に立っていた。「セーラ皇太子様は、一体何を祈っていらっしゃるのでしょう?」「さぁ・・それはセーラ様にしか解りません。」リヒャルトがそう言った時、聖堂へと向かってくる靴音が聞こえた。「矢張りここに居たのね、オデット。」リヒャルトとフィリップが振り向くと、そこには黒いベールを被った女性―“オディール”が立っていた。「セーラ様、お逃げ下さい!」リヒャルトがセーラに向かって叫ぶのと同時に、“オディール”がドレスの胸元を破り、そこから拳銃を取り出した。「漸く復讐の機会が訪れた。神から遣わされた光の皇子よ、闇に呑まれるがいい!」銃声とともに、セーラが胸に紅い華を散らせて祭壇の前に倒れた。「誰か救急車を!」「衛兵、あの女を捕えよ!」「セーラ様!」 怒号が聖堂内に響く中、司祭がセーラに人工呼吸を施しているのを見たリヒャルトは、“オディール”を追った。外伝第13話です。“オディール”がとんでもないことを。セーラは助かるんだろうか?にほんブログ村
2011年04月09日
コメント(2)
-

麗しき薔薇 第12話
自分の前に突然現れた、セーラ皇太子と同じ顔をしたオディールと名乗る女性を、瑞姫は品定めするように見た。(この方、何か企んでいるわ・・)「初めまして。ごめんなさい、わたくし少し驚いてしまって・・」「まぁ、何かわたくしの顔についていますか?」「いいえ。ただセーラ皇太子様と瓜二つの顔をなさっているから、てっきり・・」「良く言われますのよ。皇太子妃様、プラハ城での舞踏会は是非出席致しますわ。」「あら、そんな事をわたくしたちに伝えに、この汽車に?」「まぁ、それもそうですけれど・・わたくしには、まだ用事がありますの。」そう言って笑ったオディールの瞳にまた、あの妖しい光が揺らめいていることに瑞姫は気づいた。「そうなの。色々とお忙しいのね。」「ええ。ではわたくしはこれで。」オディールは笑顔を崩さずに、瑞姫達の前から下がった。「勘の鋭い女・・一筋縄ではいかないね。」自分の客室へと戻る最中、オディールはそう呟き舌打ちした。「あなた、あの方ですけれど・・さきほどわたくし達に挨拶に来られたオディールという方・・」「セーラ皇太子に似ていたな。」ルドルフは妻の言葉に相槌を打ち、彼女を見た。「ええ、まるで実のご兄弟のようだわ。セーラ様には確か、双子の弟君がおられたとか・・」「確かに居たが、その弟君は数年前に死んだ事になっている。」ルドルフは瑞姫にそう言うと、ウィーンを発つ前に側近の者から渡された書類を彼女に見せた。それは、セーラ皇太子の双子の弟・ミカエルに関する報告書だった。「数年前にローゼンシュルツで起きた白薔薇革命によりセーラ皇太子の弟・ミカエルは離宮で起きた自爆テロにて死亡とここには書いてあるが、その事実が確かなものではない。遺体が未だに発見されていないからな。」「もしかしたら、あのオディールという女性は、死んだ筈のミカエルという可能性も?」「有り得るかもしれないな。現在ローゼンシュルツ王国の情勢は数年前の革命前後より安定しているとはいえ、常に国民はテロリストの陰に怯え、我が帝国と同様に長年続いた階級制度による歪みが生じ、貧困層による暴動や凶悪犯罪が増えつつある。そんな中でミカエル生存が国民に伝えられたら、セーラ皇太子は廃嫡されるだろう。」「そんなに、深刻な状態なんですの?」「ああ。ミカエルは貧困層を長年支援してきたから、革命でその死を報じられてもなお彼を慕う者が多く居ると聞く。それとは対照的にセーラ皇太子の評判は余り良くないらしい。その原因は皇太子が外国籍であるからだとか・・」「ローゼンシュルツの国民は、排他的な方が多いと聞きましたけれど・・セーラ皇太子様は先の内戦時で暗殺を逃れる為に日本人神父の養子となったことを彼らは知っているのでしょうか?」「そんな深い事情を知っていたとしても、次期皇帝が母国を捨て海外に逃亡したというのは、自分達を見捨てたのと同じ事。セーラ皇太子はその汚名を返上する為に今回の欧州視察に命を懸けているのだそうだ。」「複雑ですわね・・」瑞姫は夫の話を聞き、いかにセーラ皇太子の前に数々の困難が立ちはだかっているのかを初めて知った。「わたくしは、皆様に認められるかしら?」「認めるさ。わたしがお前を、ハプスブルクの皇太子妃であることを認めさせてやる。」ルドルフはそう言うと、瑞姫をそっと抱き締めた。「何も心配する事はない、ミズキ。わたしがついている。」「ええ、あなた。」もう瑞姫は、独りで戦う事はない。夫という強力な味方がついた今、何としてでも自分をハプスブルクの皇太子妃として世間が認めるまで、頑張らなければならないと彼女は奮起した。(わたくしはこの人と、戦い続ける。独りでは決して勝てない戦いに、彼と共に手を取り合い、逃げずに立ち向かってみせる。)その心はセーラ皇太子も同じだろうと、瑞姫は思っていた。彼もまた、人生の伴侶となるべき男が居るのだから。 それぞれの想いを乗せた汽車は、やがてプラハへと着こうとしていた。次回からプラハ編スタートです。外伝なのに長く続きそうな予感・・にほんブログ村
2011年04月08日
コメント(0)
-

麗しき薔薇 第11話
セーラとリヒャルトが乗っている一等車両には、もう1組乗客が居た。「ねぇ、ここに“オデット”が乗っているって、本当なの?」 宝石のように美しく煌めく蒼い瞳で、喪服を着た女性がそう言って向かいに座る長身の男性を見た。「ああ、それにこの車両にはオーストリアのルドルフ皇太子夫妻もご乗車している。」「ふぅん。確かルドルフ皇太子の妃はミズキとかいう日本人女性だったね? ホーフブルクで開かれた舞踏会では、“オデット”と親しい様子が見られたって、ハンナが言ってたよ。」女性は黒繻子の扇子を開くと、口端を上げた。「“オデット”に会いに行こう。それと、ミズキ妃にもご挨拶しないとね。」彼女が立ち上がると、耳朶を飾る真珠の耳飾りがシャラリと揺れた。「わたしも行きます・・」「お前はここに居なよ。どうせ足手纏いになるだけなんだからさ。」客室の扉を開けた女性は振り向きざまに男にそう言って笑うと、“オデット”の元へと向かった。「そうですか・・あのサリームに息子が居たとは・・」「俺も初めてその事を知って、驚いたさ。貴賓室で先程会ったが、まだまだ青臭い餓鬼だった。周りに依存し、頼る事でしか生きられない、礼儀知らずな奴だった。あんなのがもしあの王宮内で暮らしていたのなら、あいつの性根は腐りきることだろうよ。」滅多な事で他人の悪口を言わぬセーラにしては珍しくサリームの息子に対して毒を吐いているので、リヒャルトは驚愕の表情を浮かべながらも彼の話に耳を傾けた。「セーラ様がそんな風に毒づいておられるお姿は初めて見ました。まぁ、自分で何も考えようとしない者にはそれ相応の罰が下ることでしょう。」「あの餓鬼を冷たく突き放して正解だったな。母親が謂れのない中傷を受けて精神を病んだ事には同情するが、初対面の相手に礼を尽くさぬ相手に情けをかける余裕などない。」セーラがそう言って溜息を吐いた時、不意に客室の扉が開いた。「ふぅん・・数年前はお人よしだったのに、今ではすっかり傲慢で冷酷になったものだね、“オデット”?」衣擦れの音を立てながら、喪服姿の女性が滑るようにして客室に入って来た。「お前は・・」リヒャルトとセーラは、彼女の顔を見て険しい表情を浮かべた。「そんなにわたしに会いたくなかったの? それはそうだよね、誰が好きこのんで悪魔の娘に会いたい人なんて居る訳ないよねぇ、王女様?」黒繻子の扇子を持った女性は、自分と同じ顔をしているセーラに向かって微笑んだ。「どうしてお前が此処に居る、“オディール”?」「生きているからさ。それよりも妊娠したんだってね、おめでとう。」女性―“オディール”はゆっくりとセーラに近づくと、彼の頬に優しいキスを落とした。震える彼の耳元に、“オディール”はそっと囁いた。「わたしが居る限り、お前は絶対に幸せにはなれない。」彼女はさっとセーラとリヒャルトに背を向けると、優雅な足取りで客室から出て行った。「どうしてあいつが・・何故今更になって・・」「セーラ様、落ち着いてください。あいつはもう死んだのです。」リヒャルトはそう言うと、恋人の手を優しく握った。「確かに、あいつは死んだ。だが、あいつはまだ生きている。俺が鏡を見ればあいつと同じ顔がある・・」「あなた様はあいつとは顔は同じですが全く違います。わたしがあなた様の事を一生お守り致します。」「ありがとう、リヒャルト。」 一方セーラ達の客室から出た“オディール”は、ルドルフ達の客室の扉をノックした。「どなた?」瑞姫が扉を開けると、そこにはセーラと同じ顔をした喪服姿の女性が立っていた。「初めまして、皇太子妃様。わたくしはオディールと申します。以後お見知りおきを。」そう言って優雅に微笑んだ女性の瞳が、妖しく煌めいたのを瑞姫は見逃さなかった。少し間が空いてしまいましたが、外伝11話です。セーラ達の前に現れた、“オディール”。セーラと同じ顔をした“オディール”は、『白鳥の湖』に登場する悪魔の娘からとりました。にほんブログ村
2011年04月07日
コメント(0)
-

麗しき薔薇 第10話
「お前達の目的は何だ? 金か?」「今にも自分を殺そうとしている奴にそんな事を聞くなんて、大したタマだなぁ、皇太子様よ。」リーダー格の男はセーラの首筋にナイフを押し当てたまま、そう言って笑った。「修羅場を幾つも潜って来たんでね。それで、お前達の目的は?」「リシェーム王国のサリームを知っているな?」「サリームか・・懐かしい名だな。」セーラはゆっくりと目を閉じ、数年前に起きた、忘れたくても忘れられない事を思い出した。砂漠の王国・リシェームに拉致されたセーラは、白亜の王宮の奥深くの後宮で囚われ、国王アルハンに凌辱された。セーラを拉致したのは、アルハンの息子で第1皇子であったサリームだった。彼は、セーラを父親の貢物として密かに武装組織を雇い、英国に滞在していたセーラを拉致した上に、滞在先であったヘルネスト伯爵家令息ロバートと、令嬢エリザベスの命を奪ったのだ。サリームはあの日から反国王派によって公開処刑されたと聞く。何故ここで彼の名が出てくるのか。「サリームは確か数年前に死んだ筈。死者が俺に何の用だ?」セーラがそう言って口端を上げて笑うと、男は彼の言葉で鼻を笑った。「お前に用があるのは、サリームの息子だ。」「息子?」サリームに息子が居るという話は、初耳だった。「ああ。その息子がお前に会って話したいとな。」「たったそれだけで、大勢の乗客を危険に晒したのか? サリームは自己中心的で傲慢な男だったが、不幸にも息子にもその性格が受け継いでしまっているらしいな。」「おしゃべりはもう終わりだ。サリームの息子は貴賓室で待っている。」数分後、セーラは男達とともに貴賓室に入ると、真紅のチンツ張りのソファに座っている1人の少年がセーラの姿を見るなり立ち上がった。「お前が、セーラ皇太子だな?」「初対面の相手に対して失礼な物言いだな。父親そっくりだ。傲慢で強欲で、最期は非業の死を遂げた哀れな父親に良く似ているな。」セーラがそう言って笑うと、少年はきっと彼を睨んだ。「父は国の為に尽くした。それなのにあんな死に方をするだなんて、俺は納得していない!」関節が白くなるほど拳を固めた少年の顔は、怒りと悲しみに満ちていた。「俺と何を話したいんだ?」「俺と母をローゼンシュルツ王国へ連れて行け。数年前のあの日から、母は謂れのない誹謗中傷を受けた末に精神(こころ)を病んだ。もうわたしはあそこでは暮らせない。」「そうか。だがお前の頼みは聞けないな。自分の名を名乗らず、一方的に自分の要望だけを伝える餓鬼を相手にしている程、こちらも暇ではないのでね。」「じゃぁどうしろっていうんだ!」「それは自分で考えろ。本当に母親を守りたいのなら、他人に頼らず己でその方法を考えてみることだな。話は以上だ。」美しいレースの扇子をパチンと閉じたセーラは、さっとソファから立ち上がり少年に背を向けた。「あんな風に冷たく突き放していいのか? あいつ、真剣だったぜ?」「言っただろう、餓鬼の面倒をみる暇はないと。それにあいつは周りが自分達を助けてくれると思っている。傲慢な考え方を捨てねば、あいつは何も変わらない。もう話は終わったのだから、俺と乗客たちは解放してくれるんだろうな?」「ああ。」男がナイフをセーラの首筋から離すと、セーラはリヒャエルが待つ客室へと戻った。「セーラ様、ご無事でしたか!」「心配を掛けてすまないな、リヒャルト。餓鬼の我が儘に少し振りまわされただけだ。」「そうですか。お怪我がなくて良かったです。」リヒャルトの頬を撫でたセーラは、宝石のように煌めく菫色の瞳を見つめた。この瞳に恋焦がれ始めた時は、いつだったのだろう。ほんの少し前の事なのに、まるで遠い昔のようにセーラは思えてならなかった。第10話です。セーラの前に現れた謎の少年。初対面の相手に対して尊大な態度を取っている彼の名は、次回で判ります。にほんブログ村
2011年04月05日
コメント(0)
-

麗しき薔薇 第9話
一部性描写が含まれますので、苦手な方は閲覧なさらないでください。「セーラ皇太子の客室は何処だ?」「21―Dだ。」「チッ、少し遠いが、獲物は仕留められるな。」密かに一等車両に乗り込んできた数人の男達は、セーラとリヒャルトの客室へと向かい始めた。彼らの目的地である客室の中では、セーラがリヒャルトの股間に顔を埋めていた。「いけません、セーラ様・・このような場で・・誰かに見られでもしたら・・」リヒャルトは羞恥で顔を赤く染めながらセーラを退かそうとしたが、セーラは彼のものを口に含んだまま離そうとしない。セーラは舌でリヒャルトのものを愛撫すると、それがやがて容量を増してゆく感覚がしてますますそれを奥までくわえこんだ。「セーラ様・・」自分を時折上目遣いで見つめる恋人の顔がとても艶やかで、リヒャルトは低く呻いて彼の口に己の欲望を吐きだした。「も、申し訳ございません!」ポケットチーフを取り出したリヒャルトは、慌ててセーラの口端を汚す白濁液を拭った。「そんなに俺に舐められて感じたの、リヒャルト?」セーラはそう言って妖艶な笑みを恋人に浮かべた。「あなたも大胆なことをなさる。こんな人目のつくような場所でなさるとは。」リヒャルトが溜息を吐くと、セーラは彼の隣に座った。「昨夜の火照りが鎮まらなくて、ついな。リヒャルト、本当にわたしと結婚してくれるのか?」「わたしはあなたには絶対嘘を吐きませんよ。たとえどんな困難がわたし達の前に立ちはだかろうとも、あなたを愛し守ります。」「ふん、どうだか。」リヒャルトの言葉を聞いても、セーラはそれに不服そうな顔をしていた。数年前、彼と初めて会った時はまだ皇族としての自覚も何もなく、自分に対してはいつも敬語で話していたが、今では高飛車な物言いだけでなく、皇族として相応しい立ち居振る舞いを身につけている。セーラが皇太子として認められるまでの数年間は、短いようで長く感じた。その間セーラは様々な困難に襲われ、砂漠の王宮で囚われたこともある。幾度も身が引き裂かれるような思いをした末にセーラと結ばれた。「セーラ様は、わたしの事をどう思っていらっしゃるのですか?」「どうって・・そんな事、言わなくても解るだろう?」セーラは突然リヒャルトからそんな事を尋ねられ、少し戸惑った。リヒャルトの事は心から愛しているし、その事を彼に直接伝えなくても彼は解ってくれるだろう。「気持ちを言葉にしなければ解らない場合もあります。」「リヒャルト、俺はお前の事を愛している。絶対にお前の手を離すつもりはないからな。そ、それに、責任を取って貰わないとな!」「はいはい、解っておりますよ。」リヒャルトはそっとセーラの顎を持ちあげると、己の唇とセーラの唇を重ねた。セーラの唇は昨夜も味わったが、一度味わったら病みつきになってしまうほどの感触だった。舌でセーラの口腔内を犯しながら、昨夜の情交を思い出したリヒャルトはセーラの華奢な腰を弄り始めた。「こんな所で、駄目・・」「今更何をおっしゃる。わたくしをその気にさせたのは、あなた様でしょう?」そう言った彼は、セーラを座席に横たえるとドレスの裾を捲り、その中に潜り込もうとした。その時、一等車両の廊下から突然銃声がした。「一体何が・・」セーラがさっと座席から立ち上がった時、勢いよく客室の扉が開いた。「やっと見つけたぜ、セーラ皇太子。」薄汚い服を着た数人の男が客室に入って来たかと思うと、その中のリーダー格と思しき男がセーラの手首を掴むと、彼の頸動脈にナイフを突き付けた。「ちょっと俺らに付き合って貰うぜ、皇太子様。」「お前達、一体何者だ?」「別に名乗るほどの者じゃねぇよ。」「そうか、丁度退屈していたところだ。」ナイフを突き付けられているというのに、セーラは泣き喚きも命乞いもせず、淡々とした口調でそう言うと笑った。(セーラ様・・)(リヒャルト、今は動くな。)やがて賊達はセーラと共に客室から出て行った。第9話です。突然客室に乱入した男達の目的とは?にほんブログ村
2011年04月05日
コメント(0)
-

麗しき薔薇 第8話
翌朝、ダイニングへと現れたセーラとリヒャルトの顔は、何処か嬉しそうだった。「おはようございます、皇太子様、皇太子妃様。」「おはよう、セーラ様、リヒャルトさん。今日はいい旅行日和になりそうね。」「ええ。」この日、ルドルフ達は蒸気機関車でプラハへと向かう事になっていた。「プラハまで汽車に乗って旅行なんて、まるでヴィクトリア朝の頃に戻ったようですわね。」「ああ。今回の旅はヴィクトリア朝貴族の旅行気分を楽しむというテーマだからね。」ルドルフはそう言って紅茶を飲んだ。「セーラ様、お加減はいかがですか?」「大丈夫だ。つわりは軽いからな。まぁ、昨夜は余り眠れなかったが・・」「申し訳ございません、セーラ様。」「別に謝る事はないだろう? 俺としては余計なストレスが減ったから良かった。」セーラはそう言ってにっこりと笑うと、リヒャルトは頬を赤らめた。「全く、あんな事で顔を赤くするだなんて、お前が以外と繊細だったとはな。」部屋へと戻ったセーラは、クスクスと笑いながらリヒャルトを見た。「そんなに笑わないでください、セーラ様。旅行のお支度はもう出来ましたか?」「ああ。行こうか。」ドレスの裾を摘み、セーラはスーツケースを持って部屋から出ようとしたが、それをリヒャエルが制した。「妊婦は重い物を持ってはなりません。わたくしが持ちます。」「過保護だな、お前は。これ位どうってことないのに。」セーラは溜息を吐きながら、部屋から出て行った。 ウィーン西駅のプラットホームには、ヴィクトリア朝に活躍した蒸気機関車が煙を吐きながら停まっていた。その中に次々と、フロックコートやバッスルドレスなどのヴィクトリア朝のファッションを纏った老若男女達が乗り込んだ。この日、ヴィクトリア朝時代のファッションを身に纏い、ヴィクトリア朝の蒸気機関車に乗ってプラハへと向かうという企画が1日限りで行われた。この面白い企画に集まった市民達は、初めて見る蒸気機関車に興奮し、乗車する前まで携帯電話のカメラやデジタルカメラで記念撮影を行っていた。その中で一番華やかなのは、上流階級のみが乗車することを許されたラピスラズリブルーに塗装された一等車両だった。「女装はもうされないのかと思いましたが、違ったようですね?」「別に、辞めるとは言っていないからな!」顔を赤くしてリヒャルトの言葉に反論するセーラは、薔薇色のドレスを纏い、同系色の帽子には羽根飾りが付いていた。「良くお似合いですよ。寒色系のドレスもお似合いですが、暖色系もお似合いです。けれどもブルー系のドレスの方が、あなたの怜悧な美貌を引き立てるかもしれませんね。」「褒めているのか貶しているのか、どっちなんだ?」「それはあなた次第ですよ、セーラ様。」「ふん・・」リヒャルトとともに一等車両へと乗り込んだセーラの姿を、数人の男達が見つめていた。「あれが、セーラ皇太子か・・」「俺達も乗り込むぞ。」「ああ。」「こちらです。」リヒャルトが客室のドアを開けると、セーラはさっと椅子に座って溜息を吐いた。「やっと2人きりになれましたね、セーラ様。」リヒャルトはそう言うと、セーラと向かい合わせの席に腰を下ろした。「リヒャルト、これからどうする? 国に戻ったら色々と・・」「わたくしと結婚して下さい、セーラ様。」セーラは驚きで目を見開きながら、恋人を見た。「本気で、言っているのか?」「わたしは一度も、あなたに嘘を吐いたことがありません。」リヒャルトはそっと、セーラの頬を伝う涙を拭った。やがて汽車は甲高い汽笛を鳴らしながら、ウィーン西駅から離れ一路プラハへと向かった。外伝第8話です。ウィーンからプラハへと向かう汽車の中で、何かが起こるかもしれません。にほんブログ村
2011年04月04日
コメント(2)
-

麗しき薔薇 第7話
「ん・・」 自分の腕の中で眠っているセーラが身じろぎし、リヒャルトはくすりと笑いながら彼の寝室へと向かった。「これはこれは、誰かと思ったら。」リヒャルトの前に突然、軍服を纏った1人の男が現れた。「どなたですか? 初めて見るお顔ですね。」リヒャルトがそう言うと、男は突然笑い始めた。「俺の事を知らないとは、おめでたい奴だ。あんた、リヒャルトっていったよな?」男の視線がリヒャルトからセーラへと移った。「ふぅん、これが俺の縁談相手か。別嬪だなぁ。」「今何と、おっしゃいました?」リヒャルトの眦が上がるのを見て、男は嬉しそうな表情を浮かべながら次の言葉を継いだ。「ああ、言ってなかったっけ? セーラ皇太子に縁談があること。その相手が俺。」「貴様が、セーラ様の縁談相手だと?」セーラの縁談は、リヒャルトにとっては寝耳に水の話だった。セーラは現在30歳で、結婚適齢期をとうに過ぎていたが、一体本人も知らぬ内に何時からそんな話が持ち上がったのだろうか。「アンジェリカ皇妃様からウィーンに居る息子と会って欲しいと頼まれてね。まぁ一度も会わずに結婚するよりは、相手と会って居た方がいいかなぁと思って来たんだけど、まさかあんたと一緒とはね。」そう言った男は敵意を隠そうとせずにリヒャルトを見た。「リヒャルト、どうした?」「セーラ様・・」セーラは低く唸ると、ゆっくりと蒼い瞳を開けて恋人を見た。「降ろしてくれ。」「かしこまりました。」リヒャルトはそっとセーラを降ろすと、彼はドレスの裾を捌くと男の前に立った。「お前は何者だ? どうやってここに入って来た?」「あなたが、セーラ皇太子様ですね?」リヒャルトと接している時の態度とは全く違い、男はそう言ってセーラの前に恭しく跪いた。「お初にお目にかかります、皇太子様。わたしはアリョーシャ=バラノフと申します。以後お見知りおきを。」「バラノフ・・大方母上達から頼まれたのか、わたしとリヒャルトとの仲を引き裂くようにと?」「まさか、とんでもない。わたしはあなたとお会いする為だけにウィーンに来ました。」「そうか。ではアリョーシャ、母上達に伝えておけ。わたしはリヒャルトと別れるつもりはないと。行くぞ、リヒャルト。」セーラはそう言うと、男の横を通り抜けて客室へと入った。「そういう事ですので、お引き取り下さい。」リヒャルトが口端を上げて男を見ると、彼は怒りで顔を赤く染めて何か言おうと口を開こうとしていたが、その前にリヒャルトが彼の鼻先でドアを閉めた。「母上達も俺の知らない内に縁談を決めるとは、良くやるな。お前、一体母上達に何か恨まれるような事をしたのか?」セーラは客室に入るなり、結い上げていた髪に挿していた髪飾りを乱暴に抜き取り、頭を振った。「わたくしは何もしておりませんよ。それにしてもあの男、あの様子だとセーラ様の事を諦めていないようですね。」「諦めさせるさ。それにしても21世紀になってコルセットを締める必要が何処にあるんだ? 苦しいったらありゃしない。」「それもそうですね。ではドレスを着るのはもう止めにいたしましょうか?」「どうしようか今考え中だ。」リヒャルトによってコルセットの紐を緩められ、セーラはほっと溜息を吐きながらソファに横たわった。「そんなお姿だとお風邪を召しますよ。」「はいはい、わかったよ。シャワーを浴びて来る。」セーラは溜息を吐くと、浴室の中へと入って行ったので、リヒャルトも慌てて彼の後を追った。「別に入って来なくてもいいのに・・」「たまにはよろしいでしょう?」なかなか上手く話が繋げられなかった・・。リヒャルトの前に恋敵登場。にほんブログ村
2011年04月02日
コメント(0)
-

麗しき薔薇 第6話
「少し夜風に当たっておりました。」セーラはそう言ってルドルフに微笑んだ。「セーラ様、何か我々に隠していることはありませんか? たとえば、リヒャルト殿との関係について。」ルドルフの言葉を聞いたセーラの顔が、僅かに強張った。「・・鋭い方ですね、あなたは。」セーラは溜息を吐くと、バルコニーから遠くに見えるウィーンの街並みを眺めた。「リヒャルトとわたしが恋人同士として付き合うようになったのは、数年前からです。わたしがローゼンシュルツ王国の皇太子として認められるまで、様々な困難を乗り越えなければなりませんでした。」「存じておりますよ。」セーラの波乱万丈ともいえる半生は、ルドルフのみならず世界中の人々が知っていた。「リヒャルトと紆余曲折を経てわたしは結ばれましたが、その際実の両親は彼に『セーラが皇位を継承する日まで手を出さない』という誓約書を彼にサインさせたのです。彼らにとってわたしは死んだと思っていた息子が生きていた喜びとともに、息子を奪ったリヒャルトへの憎しみが湧きあがったのでしょう。」そう言ったセーラは一旦言葉を切ると、そっと下腹を撫でた。「正直、医師から妊娠を告げられたわたしはリヒャルトへの怒りと、今後の生活への不安で頭が混乱して、腹の子をどうすべきなのかをまだ決めていません。わたしの妊娠を両親が知れば、リヒャルトは最悪死刑台に上がることになるでしょうし。」「死刑台とは大袈裟な。21世紀の現在に於いて、婚前交渉などは当たり前になりつつあるのに、子の恋愛にいちいち目くじらを立てる親が居るなど・・」「馬鹿馬鹿しい、とお思いでしょう? 両親はわたしへの想いが強過ぎて、それがわたしの足かせになっている事に気づかないのです。リヒャルトとわたしが交際している事を知った時、彼らは烈火の如く怒りましたから。」セーラの話を聞いたルドルフは、ローゼンシュルツ皇帝夫妻が何故彼に過保護になっているのかが解らなかった。 長年生き別れていた息子と漸く共に暮らせる喜びは解るが、成人した子どもをおのれの支配下に置くなど、正気ではない。「リヒャルト殿は、何と言っているのですか?」「まだ何も言って来ませんが、彼は産んで欲しいと思っているようです。舞踏会の後、2人で今後の事を話し合うつもりです。」「そうですか・・」ルドルフがちらりと大広間の様子を見ると、リヒャルトが数人の女性に囲まれていた。「失礼。」セーラはバルコニーを後にすると、リヒャルトの方へと向かった。一方リヒャルトは、突然数人の女性に囲まれ、戸惑っていた。「ねぇリヒャルト様、少しお時間ありましたら、わたくしと・・」「ずるいわ、抜け駆けなんて。わたくしが先よ!」「いいえ、わたくしよ!」耳元でぎゃぁぎゃぁ煩く喚く彼女達を鬱陶しく思いながらも、リヒャルトはどう彼女達に声を掛けたらいいのか判らずにいた。「リヒャルト、何をしている!」鋭い声がしてリヒャルト達が振り向くと、そこには眦を上げ険しい表情を浮かべているセーラが立っていた。「セーラ様。」「全く、油断も隙もないな。来い、話がある。」有無を言わさずグイッとセーラに腕を掴まれ、リヒャルトは半ば引き摺られるようにしながら大広間から出て行った。「リヒャルト、お前は俺の事をどう思っているんだ?」「どうって・・わたしはあなた様の事を心から愛しております。たとえ順序が違っても、いずれあなた様と生涯を共にするつもりでおりました。」「そうか。では俺が妊娠せず、俺に縁談が持ち上がれば、お前はさっさと尻尾を巻いて逃げる訳か?」「そんな事は・・」「すまない、リヒャルト。どうしてこんな事しか言えないんだろう。優しい言葉を掛けようとしたのに・・」セーラは壁際に凭れかかりながら、溜息を吐いた。「疲れた・・俺を部屋まで運べ。」「かしこまりました。」リヒャルトはそう言うと、軽々とセーラを横抱きにしながら廊下を歩き始めた。外伝第6話です。リヒャルトとセーラ、些細なことで喧嘩を。妊娠中はストレスが溜まるから、ついリヒャルトにあたってしまったんでしょうね。でもリヒャルトはセーラには甘いです。にほんブログ村
2011年04月01日
コメント(0)
全32件 (32件中 1-32件目)
1
-
-

- これまでに読んだ漫画コミック
- 陽だまりの月 2巻 読了
- (2024-11-25 21:41:16)
-
-
-

- 読書
- Wedge 2024年10月号 読了
- (2024-11-27 22:33:15)
-
-
-
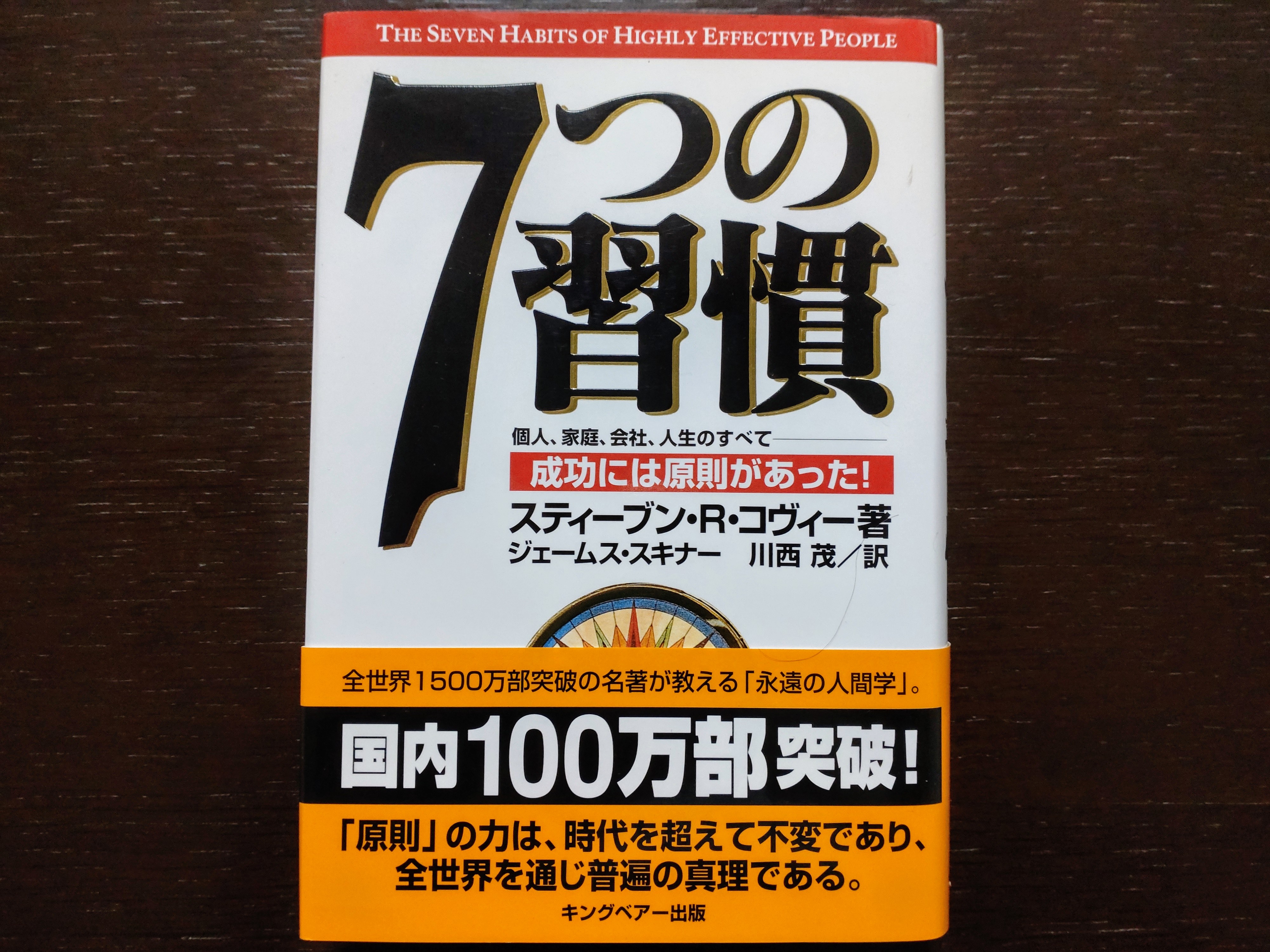
- 今日どんな本をよみましたか?
- 第二の習慣「目的を持って始める」(…
- (2024-11-28 00:00:27)
-







