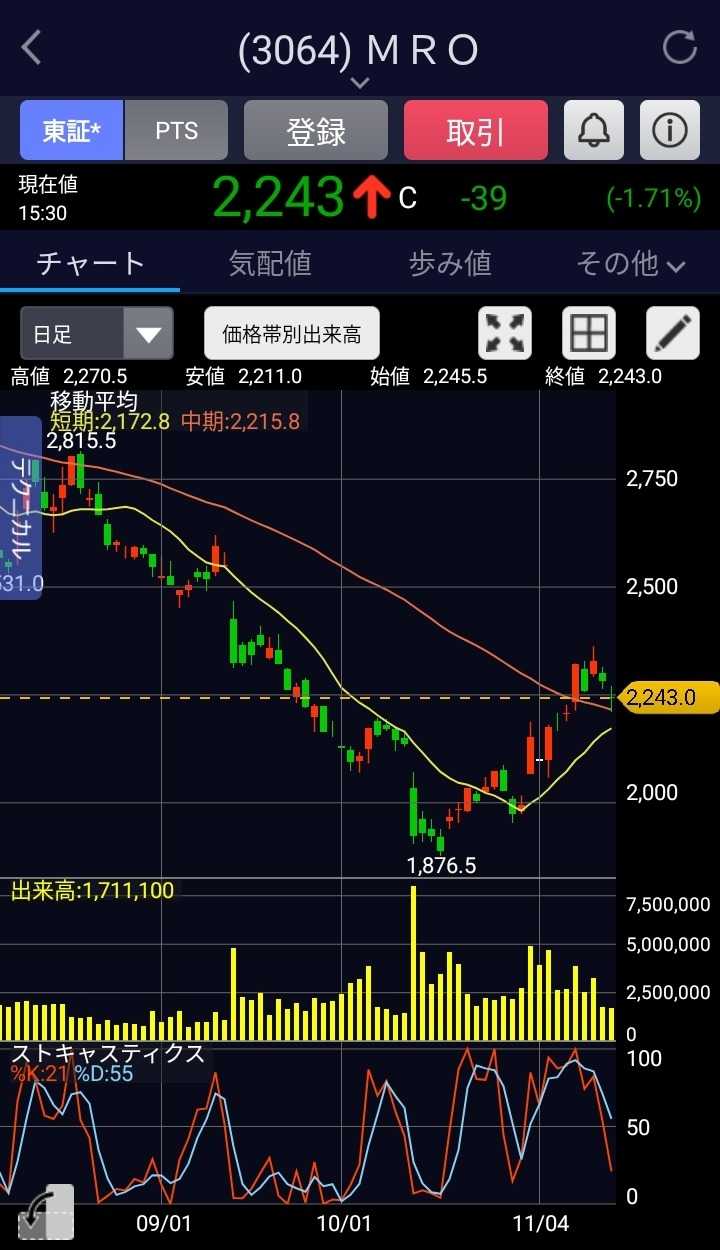2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2006年01月の記事
全2件 (2件中 1-2件目)
1
-
優勝・野洲が起こした反論・アンチテーゼ
結果的にそうなったのか、確信的に意図したのかは両方だろう。高校選手権優勝という最高の成果をあげた野洲サッカー。野洲サッカーを振り返る。 今回の84回選手権の野洲高校を観て、「もし野洲が活躍すればもう一度日本サッカーの流れが変わる・戻ってくる」と、興奮して大きく期待して観ていた。早々と一回戦敗退でがっくりきた常葉橘(静岡)の後、野洲(滋賀)を応援することで楽しく大会を観ることができた。優勝した その意義はとてつもなく大きい。 とりあえず、長いけどここWiki田嶋幸三でも読んでみてください。 1998年、2002年W杯の統計的分析の結果を頼りに、現在JFA技術委員長田嶋氏、2003、2005年ワールドユース代表監督大熊氏、アテネ五輪代表監督山本昌邦氏・・・(岡田氏、柳下氏も含め)指導者の方々は、 元来の日本人の低身長細身の体型・特性に合ってないロングパス→流れてポストプレーのフィジカルサッカーを少なからず信奉し、国際舞台などで実践し、失敗を重ねてきた。 確かにそれは世界の潮流かもしれないが、モダンとよばれるスタイルを追いかけても、サッカースタイルの流行は長いサイクルで一周している三つ巴の関係に過ぎない。その事を認めない流行に飛びつく指導的立場の人たちが日本に多い。日本人は(モダンサッカーと言われると)流行に弱いのだ。 流行り廃りに流されていては信念のぶれる強化となる。 なぜ日本人の特徴を外から眺めて、パスサッカーしかないと気付かないのか。日本人の平均身長がオランダやフランスのようになったり、筋肉がナイジェリアのようになったりする事は今後50年経っても無いのだ。遺伝子はもっと長いスパンでしか変化しない。 日本人が優れているのは組織力、スピード(30、50m)、反応力、判断力などで、体型的に近い強豪国はメキシコやペルー、ついでにポルトガルなど。そしてそれらの国より優れているチームワークを使って、素早いショートパスやドリブルを使って組織的に戦う。日本が世界の強豪となるには長所を前面に打ち出し短所を補う、野洲高校がやったような組織力コンビネーションと個人技術を前面に打ち出したサッカースタイルだ。 早々とちまたでは、20世紀に静岡学園が出てパワー重視から技術へと流れを変え、21世紀に野洲が出てまた流れを技術へと正しく修正したと言われている。 ここ数年のユースはおかしいと思っていた。フランスやドイツの猿マネをしても勝てるものか。答えを出してくれたのはまたも地方の底辺の指導者だ。 日本人は大きいと言われてもせいぜい185cm程度、190cmの選手がごろごろ出るわけが無い。線だって日本人はきゃしゃなんだ。きゃしゃで良いんだ。そう生まれて来たのだから。まず自信を持って自らを肯定してくれ。 野洲のようにすれば小さく細くても勝てるんだ。(強引ですみません) 追記 ユース世代・高校界でも、高い理想と高い技術を持つチームは、静学などに代表されるように少しばかり存在する。 しかし、なかなかトーナメントでは勝てないというリアリズムの壁がある。大阪朝鮮が野洲に対して徹底したボディコンタクトで中盤のメンツを押さえていったように。相手チームはこういうテクニックに秀でるチームを削って押し込めてゆく。試合も後半に入ると足も背中もジ~ンとパンパンに張るぐらいにぶち当たられ、感覚が狂うほどに削られて、チームは精度を欠いて潰されてゆく。そこを選手・監督がやり方を見出し乗り越えたのが野洲サッカー。 野洲高校は半年前、総体滋賀県予選でPK戦負けの時、選手同士が喧嘩して1週間の間、自主練習する選手がいなくなったという。「負け続けたけど、技術で負けてなかった。(金本)」それがプライドを支えたし、その技術を活かして勝てるように攻撃イメージを実戦で反復し、展開力で相手タックルの標的を絞らせなくなった。更にゴール前でのファールは多くをチャンスに繋げた。負け続けたことから研究し、後半にもミスパスなど精度が落ちないように集中力・スタミナも併せ持つチームになった。走力、スタミナ、精神力も充分に併せ持つチームである。もちろん中心は全国一の技術力と攻撃の創造力というプライドだ。
2006年01月10日
コメント(4)
-
観てますか?高校サッカー
とにかく野洲が素晴らしい。楽しくて上手くて感動させる野洲サッカー。野洲(滋賀)ってあまり聞かなかった。ああいう魅せるサッカーが、厳しいトーナメントで決勝にまでくるとはまさか思わなかった。 ピッチの野洲の選手たちが、相手高の応援観衆までも、「お~」「あ~」と、感嘆させ、魅了していった。 何故、名だたる名門が野洲に対し、シビアに守ってカウンターや、しつこいパワープレイを繰り返してリアリズムに徹して倒さなかったか? 守備スタイルの大阪朝鮮はともかく、野洲にああいうドリームのある芸術性のあるサッカーをされては、それを邪魔するのではなく自らのスタイルで堂々と正面から挑んで行きたかった。それが相手監督選手たちのサッカー観に感じられた。特にVS多々良学園などは素晴らしい試合となった。多々良は野洲サッカーにあわせず、自らのスタイルを貫いたところが良かった。 私にはどうしても野洲サッカーって黄金期のジュビロスタイルに感じられた。パス展開で中盤を崩して、個人の技術とイメージで相手をかわしゴールを鮮やかに決めてゆく・・・。トリッキーさだけで言ったらそれ以上だ。マスコミも注目して持ち上げるそのテクニックの数々、ヒールキック、足の裏ボールタッチ、ノールックパス、股抜き、クライフターン、跨ぎフェイント、トリッキーなフェイントの数々。技巧派集団、セクシーサッカー、クリエーティブサッカー賞賛の言葉が踊る。 彼ら監督選手たちの有言実行。まさに高校サッカー界、日本サッカー界を変える、変えつつある野洲サッカー。ぜひ、1月9日14:05キックオフの国立で、鹿児島実に勝って優勝して欲しい。 野洲の山本佳司監督と、ジュビロの山本昌那監督を交換して欲しいくらいだと少し思った。
2006年01月07日
コメント(6)
全2件 (2件中 1-2件目)
1