2025年05月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-

浅草を歩く(その20):浅草寺-16・新奥山の石碑を追う(2/2)~淡嶋堂~三峯社
隣りにあったのが「曽我廼家五九郎顕彰碑」。 浅草に喜劇王と言われた曾我廼家 五九郎(そがのや ごくろう)の顕彰碑。明治~昭和前期に東京浅草などで活躍した喜劇俳優で、この石碑には彼が主演を演じた映画「ノンキナトウサン(通称ノントウ)」が描かれていて、その上には彼が好きだった「群盲撫象」の文字も一緒に刻まれていた。近づいて。円形の上部には五九郎の好きだった「群盲撫象」の文字と「ノンキな父さん」の像を描く。《群盲(ぐんもう)象(ぞう)を評(ひょう)・すの意味《多くの盲人が象をなでて、自分の手に触れた部分だけで象について意見を言う意から》凡人は大人物・大事業の一部しか理解できないというたとえ。》であると。昭和38年建立。題字は大野伴睦筆。下部には金子洋文(プロレタリア文学の小説家、劇作家)からの碑文があった。「あなたは小さな身体に大きな夢をいだいた。・・・・・を叫んで迫害をうけ・・・・」 中央に「五九郎石碑 ノンキナトウサン」 左右の俳句は右:観音の慈悲尊し春の雨 万木左:浅草の茶乃木畑の(能)雪解(ゆきけ)かな 万(久保田万太郎)「私は貝になりたい フランキー堺」の文字が。 『私は貝になりたい』(わたしはかいになりたい)は、ラジオ東京テレビ(KRT→TBS)の「サンヨーテレビ劇場」で1958年10月31日22:00 - 23:40に放送された日本のテレビドラマ。元陸軍中尉・加藤哲太郎の獄中手記「狂える戦犯死刑囚」の遺書部分をもとに創作された橋本忍脚本によるフィクションで、第二次世界大戦中に上官の命令で捕虜を刺殺した理髪店主が戦後B級戦犯として逮捕され処刑されるまでを描く。岡本愛彦演出、フランキー堺主演。第13回文部省芸術祭芸術祭賞(放送部門)受賞作。1959年・2008年に映画として、1994年にテレビドラマとしてリメイクされた。この作品は2008(平成20)年に中居正広、仲間由紀恵主演でリメイクされているが「曽我廼家五九郎顕彰碑」との関連は?フランキー堺は五九郎の甥にあたると。『曾我廼家五九郎顕彰碑』を取り巻くのは「永生之碧」。1964(昭和39)年日本の芸能団が招かれて訪中し日中友好の端緒を作りました。このことを祈念して1965(昭和40)年にこの『永生の壁』が建立され題字の『永生之碧(壁ではなく)』は当時の中国の指導者のひとり郭沫若の揮毫であると。壁にはさらなる日中友好と世界平和を願って約300人の文人・芸能人が思い思いのことを書き連ねています。「相模彫 鏡碩吉」 と。様々な絵や文字が。次に訪ねたのが「新奥山」の前にあった「淡島堂」。「寫経供養塔」を見る。 「浅草観音裏」案内図。 「淡島堂」入口。「淡島堂(あわしまどう)」と。 「寫経供養塔」に近づいて。平成6年(1994)10月26日落慶。木製銅板葺、花崗石造。総高8.8m・屋根軒長3.7m・相輪高3.2m。「寫経供養塔」「写経供養塔浅草寺では、昭和三十三年の本堂落慶を記念して、「観音経写経運動」を発願しご信徒各位にお写経をお勧めしており、ご奉納いただいたお写経は、毎年十月の写経供養会にてご本尊観音さまの御宝前に奉安され、供養されている。平成六年に造立されたこの宝塔型の写経供養塔には、その年にご奉納されたお写経の経題と巻数とを記した「目録」をご奉安し、ご信徒各位のお写経の功を後世に伝え讃嘆している。 金龍山 浅草寺」 境内右側にあった「戦災供養地蔵尊」。 浅草三業地の戦死者慰霊のため造立 と。「浅草大平和堂」。 昭和38年(1963)建立。浅草地区の3万人余の戦災殉難者の霊をまつる。「建設趣意書思い出づる調べも哀し昭和ニ十年三月九日の夜、B29三百機以上の大空襲により浅草一帯は火の海となる。地をなめるようにして這う火啗と秒速三十米をこす烈風にあふられ、親は子を呼び、子は親を求むれど、なすすべもなし。おののき叫び逃げまどい、悪夢の如き夜が去れば・・眼にうつるものは一面の焦土にて、一木一草の生づるもなく、あわれ身を焼かれ路傍に臥す無辜の犠牲者は一万余柱を数う。当時その凄惨な状況は一片の新聞だに報道されることなく、敗戦後に生れた子供達は戦争の惨禍を知るよしもない。いたましく悲しい夜もいつしか歴史の一駒として消えて行くであろう。よって我々はここに当時を偲び、不幸散華された御霊の安らけく鎮まりまさんことを祈り、ニ度とあやまちを繰り返すことなく永遠に世界の平和を守らんことを誓い、浅草観音の浄域にこの碑を建立する 以て瞑せられよ。昭和三十八年八月十五日 浅草大平和塔維持会」 「東京大空襲後の浅草」 近づいて。塔上部の「和」は浅草寺中興第24世貫首、清水谷恭順大僧正の筆。台座の銘にはノーベル物理学賞の湯川秀樹博士の直筆で「みたまよ とこしえに 安らかに われら守らん 世界の和 湯川秀樹」と。 「魂針(こんしん)供養之塔」。 近づいて。「建立の記この針供養之塔は、大東京和服裁縫教師会が五十周年の記念事業として発願し、全国和裁団体連合会の御協賛と裁縫をたしなまれる多くの方々の御助勢とにより、昭和五十七年十月十七日に建立されました省みますれば昭和十年ニ月八日「折れ針」への感謝と裁縫関係者にお呼びかけし、古来の伝承に伴い浅草寺淡島様の御宝前で、供養の法会を営ませて頂いてより、次第に同じ志の方々が増え都内をはじめ近県からも「折れ針」を持って参詣され、懇ろにご供養なさる方々が、年々多くなりつつありますことは報恩の美風を普く世に伝へるためにも誠に有難く喜びに堪へません。大東京和服裁縫教師会針供養之塔保存会会長 鈴木曻造針供養之塔担当責任者 山崎章司」 2月8日は「針供養」として終日参詣信徒で賑わう(午前11時法要)。本堂前には大きな豆腐に針を刺して供養 と。写真はネットから。「写経供養塔」と「五重塔」とのコラボをカメラで追う。 ズームして。黄金に輝く相輪を。移動して。「相輪」をズームして。「五重塔」の九輪の上、先端には水煙・龍車(りゅうしゃ)・宝珠が。「胎内くぐりの灯籠」。 「胎内くぐりの灯籠この石灯籠は「胎内くぐりの灯籠」として江戸時代から有名であったもので、この灯籠の下をくぐることで、子供の虫封じや疱瘡のおまじないとなるとされている。お子様をお連れでご参拝の折には、お子様にくぐらせてみてはいかがでしようか。造立年代は不明 金龍山 浅草寺」 この灯籠の下をくぐることで、子供の虫封じや疱瘡のおまじないとなるとされている と。「天水桶」。明和7年(1770)造立。「天水桶太平洋戦争が激しくなってきた、昭和十八年(一九四三)十一月十八日、浅草寺僧侶らによって夜儀が執り行われ、この天水桶内にご本尊の観音さまをお厨子ごと奉安し、本堂の地中深くに納めたため、ご本尊さまは戦火を逃れたという。戦後の昭和二十二年(一九四七)三月七日、ご本尊さまは再び地中より掘り上げられ、その無事が確認された。 明和七年(一七七〇)造立。 金龍山 浅草寺」 「淡島堂」を正面から。 前方に「常香炉」。 元禄年間(1688~1704)、紀伊国(現在の和歌山県と三重県南部)加太の淡島明神を勧請して建てられた。現在の建物は、ひと時ご本尊様をお守りしたことがある。東京大空襲で本堂が焼失した後、仮本堂となったのである。やがて影向堂として現二天門の南に移り、平成6年に今の地に移築される。加太淡島神社の祭神は少彦名命で、淡島という小島に鎮座しているため、淡島明神の俗称がある。このことから浅草寺では淡島堂と呼んでいる。淡島堂には、本尊の阿弥陀如来像、淡島明神像と本地仏の虚空蔵菩薩像、取子地蔵尊などが安置されている。本地仏とは、日本の神は、仏教の仏が姿をかえて現れたものとする本地垂迹説によるもので、神の本当の姿である仏を指す。淡島明神は女性の守り神として信仰を集め、江戸時代は「淡島の願人」と呼ばれる人びとがおり、江戸市中で婦女子に淡島明神の信仰を説いてまわっていた。現在、淡島堂を中心とした行事に、2月8日の針供養会がある。「和歌山加太之淡島明神勧請淡島大明神本地佛 虚空蔵菩薩毎月十三日 御縁日ニ月八日 針供養 御昇堂 十一時正徳ニ年(一七一ニ) 御出現平成十一年(一九九九) 御遷座白木聖観世音菩薩毎歳 七月九日 大供養御昇堂 十一時」 扁額「淡嶋堂」。 「本尊阿弥陀如来像」。ズームして。他にも虚空蔵菩薩、淡島明神、取子(とりこ)地蔵を安置 と。再び「写経供養塔」と「五重塔」とのコラボを「五重塔」をズームして。 訪ねていなかった「三峰神社」を訪ねた。 「三峯社三峯神社とは、秩父の森厳な聖地に社殿を構える古社である。天台修験の関東総本山とされ、殊に江戸時代には「三峯講」が各地に設けられ、盛んに参詣された。文化一〇年(一八一三)に編纂された『浅草寺志』をひもとくと、境内各所に様々な神社が勧請され、三峯社も弁天山に建立されていたことがわかる(戦災により焼失も再建)。本社は三峯に寄せる敬虔な信心とともに、明治初年の神仏分離令以前の信仰の様子を現在に伝えているのである。 金龍山 浅草寺」 浅草寺境内にある秩父三峯神社の末社。浅草寺内に勧請された事情は詳らかではありません。江戸時代には火事が多かったため、江戸市中には火防祈願のための三峯講が多くありました。こうした三峯信仰の信者が、秩父まで赴かなくても御参りができるようにするため、浅草寺境内に末社を勧請したのかもしれません。こうした三峯神社の末社は、江戸市中あちこちにあった と。秩父の三峯神社と同じく伊弉諾尊・伊弉冉尊を祀っています。「本堂」越しに「東京スカイツリー」を再び。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.05.31
コメント(0)
-

浅草を歩く(その19):浅草寺-15・新奥山の石碑を追う(1/2)
そして「浅草寺」の境内にある「新奥山」を訪ねた。 江戸時代、浅草寺本堂の北西一帯は「奥山」と呼ばれた。地名というよりも本堂の裏手をおおまかに指した俗称で、その範囲も明確ではなかった。その名の由来も定かではないが、浅草寺の山号である「金龍山」の「奥」にちなむと推定される。奥山は江戸きっての庶民娯楽の場であった。参拝者が休息する水茶屋が並び、芝居、見世物、独楽回し、猿芝居、居合、軽業、手妻(奇術)などの大道芸人が人びとを楽しませた。また、水茶屋や楊枝屋の看板娘はいわば当時のアイドルで、鈴木春信や喜多川歌麿などの美人画の題材となって評判となった。明治になり、寺地が浅草公園に入れられ、浅草の盛り場が「六区」に移るにともない、奥山の名は消えていった。現在、本堂西側の一画が新たに「新奥山」として整備され、さまざまな碑、像が立つ。浅草寺近くに住んでいた元禄時代の歌人・戸田茂睡の墓、明治時代、社会事業に尽くした瓜生岩子女史の銅像のほか、「喜劇王」として活躍した曽我廼家五九郎の顕彰碑、喜劇人の碑、映画弁士塚など、浅草の娯楽を支えた人びとを記念する諸碑が並んでいた。案内板にも上記と同様な内容が。「奥山(新奧山)江戸の昔、今の浅草寺本堂の西北一帯は、俗に「奥山」と呼ばれ、江戸の盛り場として大道芸人や見世物小屋で大いに賑わう、著名な場所であった。輿山の名の由来は記録にないが、おそらくその位置が本堂の奥にあることから名付けられたと思われる。明治以後、その賑わいは浅草寺西側の浅草公園六区へと移り、ハ区は日本一の興行街・映画のメッカとして栄えたが、その前身が奥山だったといわれる現在は、この地を「新奥山」として整備し、諸碑が建立されている。この中には、往時の浅草の賑わいを伝える記念碑も建てられている。 金龍山 浅草寺」 そして「瓜生岩子(うりゅういわこ)之像」。 幕末から明治にかけての社会実業家として知られると同時に、福島と東京をまたにかけて社会福祉にも貢献していた。瓜生岩子は、文政12年2月15日に現在の福島県喜多方市で生まれた。雑貨屋を営んでいた父が病気で死亡し、さらに火災で家を失くした岩子は、叔父の山内春瓏の元で社会事業を学ぶ。そして、17歳で呉服屋を営んでいた佐藤助茂と結婚し、一男三女をもうける。しかし、岩子が34歳の時に、夫が肺結核で死亡。その後、救護所、縫製所などを各地に作り、本格的に社会・慈善事業に取り組み、「仏の岩子」と多くの人から慕われていた。「瓜生岩子女史の銅像 台東区浅草二丁目七番岩子は通称。正しくは”岩”という。文政十二年(一八二九)二月十五日、岩代耶麻郡(現在の福島県耶麻郡)熱塩村渡辺家に生まれたが、九歳の時、父を失い、母は岩を連れて生家へ帰った。そのため、岩は母方の姓瓜生氏を称した。十四歳の時、若松(現福島県会津若松市)の叔母に預けられ、その夫で会津藩侍医を勤める山内春瓏の薫陶を受け、堕胎間引きの防止に関心を持つに至る。十七歳で佐瀬茂助を婿に迎え、若松で呉服屋を営み、一男三女を生んだが、早くに夫を亡くした。明治元年会津戦争で孤児となった幼童の教育に尽力したほか、堕胎等、当時のさまざまな悪習を正し、明治二十二年貧民孤児救済のため福島救済所を設立するなど、社会事業の推進に努めた。明治三十年四月十九日、福島で没す。享年六十九。生涯を慈善事業に捧げた岩の善行を賞揚し、同三十四年四月、篤志家によって、浅草寺境内にこの銅像が造立された。台石正面には、下田歌子女史の撰文を刻む。 平成八年七月 台東区教育委員会」「三匠(さんしょう)句碑」。ネットから。「三匠句碑 台東区浅草二丁目三番 浅草寺 ながむとて花にもいたし頸農骨 宗因花の雲鐘は上野か浅草か 芭蕉ゆく水やなににとどまるのりの味 其角江戸時代前期を代表する俳人三匠の句が刻まれている。西山宗因 慶長十年(一六○五)肥後(熊本県)の生まれ。後、大阪に住み談林の俳風を開く。 この句は「新古今集」にある西行法師の和歌「ながむとて花にもいたく・・・」から とった句。天和二年(一六八二)没。松尾芭蕉 正保元年(一六四四)伊賀(三重県)の生まれ。数次の漂泊の旅に出て作品集や紀行文を 残し、『おくのほそ道』は世に知られている。蕉風俳諧を樹立。元禄七年(一六九四) 大坂で没。榎本其角 寛文元年(一六六一)江戸に生まれる。蕉門十哲の一人。のち蕉風を脱し、その一派の 傾向は、洒脱風などともいわれた。宝永四年(一七○七)の没。 碑は文化六年(一八○九)の建立。台石には明治二十七年(一八九四)春の移築の由来が記されている。 平成八年三月 台東区教育委員会」「正岡子規(まさおかしき)」句碑。「観音で雨に逢いけり花盛」の句が彫られている。平成13年9月19日、正岡子規没後百年事業の一環として台東区俳句人連盟により建立 と。「五瀬・植松氏明数の碑算学者関孝和に師事し、算数家として高名。上総国出身。はじめ五瀬氏、のち植松氏を継ぐ。安政5年(1858)の建立。」 「三十六歌人の碑桜の花を詠んだ三十六首を刻む。」 大亀の背に据えられた碑。文化14年(1817)の建立 と。「算子塚(さんしづか)の碑」。算学者会田算左衛門の碑。文化14年(1817)71歳没。日常使用していた「そろばん」が門下生によって埋められた。江戸時代の和算学者、会田安明の功績をたたえた「算子塚」の碑は、文政2年に儒学者の亀田鵬斎や門人によって立てられた。会田安明は、少年時代から和算に興味を持つようになり、土地の学者である岡崎安之について学んでいた。日本古来の和算は、江戸時代になると研究が盛んになり、23歳で江戸に渡った安明も、幕府の役人をしながら算学の研究に励んでいた。多くの学者達が、独自の円周率の計算方法などをあみだしていくなか、安明は算法に手を加えるなどして、難解だった算出法の簡易化をはかった。「天元演段」などの名著も残している。 「力石」熊遊の碑中央に「熊遊」と。 「力石カ石、または「さし石」ともいう。江戸後期、酒屋・米屋の人足たちの間で、酒樽や米俵を曲芸のように持ち上げて、その力を竸うことが流行した。このカ石は、境内で行われた「カくらべ大会」で竸い持ち上げられたものである。正面の「カ石・熊遊の碑」は、明治七年(一八七四)、熊次郎という男が持ち上げた百貫(約三七五キロ )ほどのカ石であり、新門辰五郎らがその記念として建てたもの。 金龍山 浅草寺」 石碑が並ぶ。「一葉観音像碑」。 一葉観音が線刻されている碑。文政9(1826)年の建碑。「高橋石斎之碑」。高橋石斎は、尾張藩の剣道指南役で書家としても有名であった と。明治12(1879)年1月建碑。「石齋高橋先生碑」と。近づいて。「石齋高橋先生碑先生尾陽人姓高橋氏諱豊珪字子玉石齋其號也父諱曽平家世以撃剣著先生状矮皙而志剛毅年未弱冠承業益盛前藩主徳川公擢用為教授既而慨然歎武技之不足以傳於後遂辞職游東京自是専意文物詠國風作繒畫最喜書札而學之自顔柳懐素□蘇米諸家悉鍾其秀以供咀嚼昔者張長史観舞剣自得書法先生固已善剣其法自與書融會不復待悟入故崟崎拓落矜荘婉轉莫不究姿態也家素乏資産又無親戚朋友之援因以傭書養数口黽勉依燈火毎待夜深人定然後輟輟即更展大紙数幅淋漓揮灑自取快曰解放心手一日之束縛其幼時嘗在襁負出游見里中祠扁額書大字因以指畫負者眷不謬一畫人嘆其慧至是遂成一家則其性情之發於書非偶然也明治五年七月廿四日卒於東京年五十六戸田公某舊與先生善戊辰撥亂之初薦先生徴拝史官未幾先生辤而歸徳川公聞而益奇之復欲聘先生亦不就夫與為官而榮於生孰若隠居而不朽於死蓋先生度之熟矣故以二公之貴舊知援而止之而不止二公亦知其止之而不止之非可責乃特假寘間之歳月以成先生之志可謂相尚以道者矣疾革自因其号撰謚大書数字神機愈活動遺命刻之石又賦絶命詞吟誦数次言不乃他既卒弟子数千人皆往賻之以助其葬余受先生知有年二子昌長健三倶来請銘其碑不可辤也乃銘曰一管之頴耶百錬之鐡耶吁嗟先生衆技之傑耶 従五位熊谷武五郎撰并篆額明治十二年一月建 木村凝之書 吉川黄雲鐫」 石齋高橋先生碑 口語訳(現代語・口語体)をchatGPTから。「先生は尾張(今の愛知県)のご出身で、名前は高橋豊珪(とよたま)、字(あざな)は子玉、石齋(せきさい)という号を名乗っていました。お父さんの名前は曽平(そうへい)と言って、代々剣術で知られた家柄でした。先生は体は小柄で色白でしたが、気持ちは強くてまっすぐな人。二十歳にもならないうちから家業を受け継いで、剣術の腕はますます上達しました。やがて藩主の徳川公に見出されて、教授として仕えることになります。けれども、あるとき「剣術だけでは後の時代に何も残せない」と深く感じ、職を辞して東京へ出ていきました。それからは文芸や書、絵などに打ち込み、とくに書(手紙や文字)をこよなく愛しました。学んだのは顔真卿や柳公権、懐素、さらに蘇軾や米芾(べいふつ)といった書の大家たち。その美点を自分の中に取り込んで味わい尽くし、己の書風として磨き上げていきました。かつて唐代の張旭という人が、舞うような剣の動きを見て筆法を会得したという話がありますが、先生もまた剣術の達人でした。その経験がそのまま筆の勢いにつながっていて、あれこれ学ばずとも自然と書の極意を体得していたのです。ときには堂々と威厳があり、ときには優美で繊細。書に現れる表情のすべてを見事に描き出していました。もともと裕福な家ではなかったし、親戚や頼れる知人もいなかったので、先生は筆一本で何人もの家族を養いました。>毎晩遅くまで灯火の下で黙々と仕事をし、ようやく人々が寝静まった頃にようやく自分の楽しみの書に向かいました。そのときは大きな紙を何枚も広げ、思いきり筆を走らせて気持ちを解放し、「今日一日、心と手を縛っていたものを、これでようやく放つことができた」と喜んでいました。子どものころ、まだ背中に背負われていた頃の話です。村の祠に掛かっていた大きな額の文字を見て、指でなぞるように真似したら、付き添っていた人がその上手さに驚いたという逸話があります。そんな才能はまさに天性のもので、先生の書がただの技術ではなく、心そのものの表れだったことがよくわかります明治5年7月24日、先生は東京で亡くなりました。享年56。戸田公という旧知の人が、戊辰戦争ののちに先生を推挙して史官にしようとしましたが、先生はまもなく辞退しました。それを聞いた徳川公もさらに感心し、あらためて招こうとしたものの、やはりお断りされました。世間的な名誉を得るよりも、静かに志を守って生きるほうが本当の価値がある――先生はそのことをよくわかっていたのです。お二方のような大名の厚意にも、先生はきっぱりと応じませんでした。でも、そのお二人もまた先生の意思を尊重して、無理に引き止めることはしませんでした。道を重んじる者どうしだからこそ、互いを尊び合ったのです。病が重くなると、自らの号にちなんだ謚(おくりな)を選び、数字のような文字を大きく書き残しました。そのときも、筆の冴えは変わらず、まるで神がかっていたといいます。石に刻むよう遺言を残し、最後には辞世の歌まで詠んで、何度も口ずさんでから静かに旅立ちました。子たちは何千人と集まり、葬儀の費用を出し合って弔いました。私(熊谷武五郎)も、長年先生に学んだ者のひとりですご遺族のご子息(昌長さん、健三さん)から頼まれて、この碑の文章と銘を書かせていただくことになりました。断る理由はありません。」 「東京都指定旧跡戸田茂睡墓(とだもすいはか)」 手前左に「青蛙神像(せいあじんぞう)」。手前右に「半七塚碑」。 「戸田茂睡墓」に近づいて。 「五輪塔」。五輪塔(ごりんとう)は、古くからお墓や供養塔として使われてきた石造りの仏塔で、下から地、水、火、風、空を表す五つの輪(地輪、水輪、火輪、風輪、空輪)を積み重ねて構成されている。平安時代後期に日本で独自に作られたと考えられ、インドの五大思想を基にしている。「東京都指定旧跡戸田茂睡墓(とだもすいはか)戸田茂睡(一六ニ九~一七〇六)は元禄期の歌人です。渡辺忠の六男として駿府城内で生まれ、父の死後伯父戸田政次の養子になります。名は馮(たのむ)、後に恭光(ゆきみつ)、通称は茂右衛門、茂睡のほか露寒軒などと号しました。一時岡崎藩本多家に仕えましたが出家し、浅草寺近くに居を構えました。「梨本集」「紫の一本(ひともと)」「若葉」などを著し、形骸化した伝統歌学の積極的批判者としての文学的意義が認められています。自然石の土台、宝篋印塔の基壇、五輪塔の順に配されており、茂睡自身が生前に自らの後世を供養した逆修塔です。 平成二十四年三月 建設 東京都教育委員会」 「半七塚」碑。 「半七塚」は岡本綺堂『半七捕物帳』をたたえた記念碑で、昭和二十四年(一九四九年)十一月に建立された。推進役は野村胡堂や江戸川乱歩、海音寺潮五郎、川口松太郎、子母澤寛ほか捕物作家クラブ(現在、日本作家クラブ)同人たちで、碑の「半七塚」の文字は岡本綺堂、裏側には判読が困難であるが「半七は生きてゐる 江戸風物詩の中に 我ら後輩の心のうちに」と胡堂の撰文が刻まれてい、碑の隣には「青蛙神像」がある。綺堂には『青蛙堂鬼談』という著書があるのはよく知られている。「青蛙神像(せいあじんぞう)」 明治の小説家「岡本綺堂(きどう)」の「半七捕物帖」碑のすぐ傍にあった。彼の作品である「「青蛙堂鬼談」で連載されたひとつ、「青蛙堂鬼談1」青蛙神(せいあじん)に因んだモチーフかと思われる。「半七塚碑「半七」とは、捕物小説家の岡本綺堂(一八七二~一九三九)の代表作の一つ、『半七捕物帳』の主人公の名である。この碑は、昭和二十四年(一九四九)に半七を慕う「捕物作家クラブ」(現在の日本作家クラブ)の同人らにより、綺堂の業績を称えて建立された。碑の裏には、「半七は生きてゐる 江戸風物詩の中に われ等後輩の心のうちに」と、『銭形平次捕物控』を著した野村胡堂(一八八二~一九六三)の撰文が刻まれる。青蛙神像半七塚碑に対而するように、一匹の丸々としたカエルがいるよく見ると変わった姿をしており、前足は二本、後足の代わりに尻尾の足が一本伸びている。これは中国の霊獣「青蛙神」であり、福をもたらす存在として特に道教で信仰された『青蛙堂鬼談』シリーズがあるように、綺堂は青蛙神に大きな関心を寄せていた。この像は半七塚を静かに見守っているようである 金龍山 浅草寺」 「瀧澤世古碑」。伊予国出身。書家として名高く、天保5年(1834)没。弘化2年(1845)門人これを建つ。 「櫻癡居士福地君紀功碑」。入口にあるおおきな福地源一郎(福地桜痴)(『東京日日新聞』を主宰)の顕彰碑。山縣有朋の揮毫です。大正2(1913)年に碑の彫工を終えましたが、故あって天女池に建てることができず、大正8(1919)年に浅草公園に建てられました(碑文より)。渋沢栄一が除幕式に出席しています。「大正8年11月28日(1919年) 是日、浅草公園ニ於テ、福地桜痴居士紀功碑ノ除幕式挙行セラル。栄一出席シテ追悼演説ヲナス。」と。 「櫻癡居士福地君紀功碑 正二位大勲位功一級公爵山縣有朋篆額孔子曰君子疾没世而名不稱焉言名之難也夫人之處世或為士為農或為工商雖其選人人殊莫不皆欲以一技一能聞於世是以富駕猗朱貴比許史聲名嘖嘖喧傳遐邇者何限而其名與骨共不歸凘盡泯滅者幾希若夫輿頌赫奕没世而益熾則非偉功耀乎世惠澤施乎後者不能孔子之言豈不信乎元和偃武文教大興學問文章有大可観者而天保以降學者多流浮誇餘弊所及徒聲律之競不者大抵鄙俚雑駁倶不足以黼黻明治之宏謨潤色維新之大業可深慨焉而已矣逮於櫻癡居士崛起樹幟文壇天下翕然嚮之亡論新聞與雑誌苟欲著書立言以木鐸一世者類皆無不效居士歩趨於是乎明治之文章始定矣文摩韓蘇之壘學鍾東西之精縦論横説事理兼該以發世人之蒙而鳴昭代之盛此豈非所謂経國之大業不朽之盛事哉或曰居士之文固豪矣雄矣獨惜陸沈於官場放浪乎湖海而轗軻終其身也吾曰庸何傷乎假令居士志伸於仕進乎紫綬拖旭章輝高車駟馬往來絶塵使婦兒歆羡咨嗟者其或有焉然使後之人稱功懐徳而永不忘者此未可必也則其陸沈而放浪適所以大成其業歟嗚呼如居士真可謂功成名遂互百世稱焉而不止者矣松下君軍治平昔與居士親善将建碑於其故棲天女池畔不朽之請予文因係以銘曰 繄昔明治 星斗呈祥 庶政維熈 奎運未昌 學衰文弊 人飽粃糠 鳳來有期 豈不翺翔 子也崛起 木鐸文場 眼曠千古 識博両洋 日日珥筆 聨珠成章 侃諤警世 犀利露鋩 如日初出 光被遐荒 爝火息矣 魑魅潜蔵 名喧寰宇 材推棟梁 生兮坎壈 死兮煇煌大正二年歳次癸丑一月 正二位勲一等伯爵芳川顯正撰 従六位勲六等 高島張輔書 田鶴年鐫此碑大正二年彫工竣成而有故不能建於天女池畔荏苒閲歳至今年建之於此公園 大正八年十一月」 【碑文本文の口語訳】をchatGPTより孔子は言いました。「立派な人は、世を去ったあとに名が残らないことを恥じる」と。それほど、「名を残す」ということは難しいものです。人は生まれ、ある者は学者になり、ある者は農民や商人になりますが、どんな職業であれ、皆それぞれの道で何かを成し、世に知られたいと思うものです。ですから、財産がある人や、立派な家柄の人が世間に名を知られることはよくあります。しかしその多くは、名声がその人の死とともに消えてしまい、いずれ誰の記憶にも残らなくなるのがほとんどです。逆に、死後もその功績がたたえられ、ますます名が高まる人がいます。そういう人は、世の中に大きな貢献をした人にほかなりません。──孔子の言葉は、まさに真実なのです。さて、明治の初め(元和=明治初期)は戦乱が収まり、学問や文化が盛んになり始めました。しかしその後(天保以降)は、学問は形式に流れ、内容のない美辞麗句ばかりとなり、明治という新時代の大きな改革や理想にふさわしい文章が、なかなか現れませんでした。そうした中で、桜癡居士が現れ、旗を掲げて文壇に立ち上がりました。全国の人々は彼に注目しました。新聞でも雑誌でも、著作を通して世に訴えようとする人は、みな彼の影響を受けました。このとき、明治の文学の方向性が決まったといってよいでしょう。彼の文章は、韓愈や蘇軾(中国の古典の大家)にも並び、東西の学問を取り入れ、自由に論じて筋道を立て、世の中の人々の考えを啓発し、この時代の繁栄を輝かせました。まさに「国を治める大事業」「後世に残る偉業」と言えるものです。ある人がこう言いました。「たしかに彼の文は立派だが、役人としては出世せず、 世の中をさすらい、最後まで苦労したではないか」と。私はこう答えます。「それがどうしたというのか?もし彼が出世し、高い位や勲章を得て、立派な車に乗って人々にうらやましがられたとしても、その名が後世にまで伝わるかどうかはわからない。むしろ、彼が官職に就かず自由に生きたからこそ、大きな仕事ができたのではないか」と。ああ、桜癡居士のような人物こそ、功績を残し、名声を確立し、百年後もたたえられるような人なのです。松下軍治さんは、生前親しかった福地さんをしのび、彼の旧居・天女池のほとりに碑を建てて、後世に残そうとしました。私はその依頼を受け、この文を書いたのです。」 繄昔明治 星斗呈祥 庶政維熈 奎運未昌 學衰文弊 人飽粃糠 鳳來有期 豈不翺翔 子也崛起 木鐸文場 眼曠千古 識博両洋 日日珥筆 聨珠成章 侃諤警世 犀利露鋩 如日初出 光被遐荒 爝火息矣 魑魅潜蔵 名喧寰宇 材推棟梁 生兮坎壈 死兮煇煌【銘文部分】(詩のような上記部分、意訳)かつて明治の始まりに、星の運行に吉兆が現れ政治は整ったが、文化の運命はまだ定まらず学問は衰え、文章も乱れ、人々は粗末な知識に満足していたそんな中、福地桜癡が現れ、世の中に警鐘を鳴らす文章で世を動かし、その見識は古今に通じ、東西にまたがり、日々文章を練り、明快で鋭く、人々を目覚めさせたその名は世界中に知られ、国の柱とも言える人物とされた生きている間は苦労があったが、死して後は、その名がいっそう輝きを放ったさらに「奥山」にある石碑群を追う。 「淺草観光纉緒の碑」。「淺草観光纉緒の碑浅草は伝統と歴史の町である 庶民信仰の大本山 金龍山 浅草寺と共にこの町は幾百千年の世を逞しく生きてきた あるときは源平争乱の戦火に耐え あるときは江戸文化濫觴の地として栄えるなど幾多の興廃消長を繰り返して現在に及んでいる今日浅草は 都内屈指の観光地として隆盛を極めているが その蔭に浅草を守ろうとする多くの人々の血の滲む努力があることを忘れてはならない浅草観光連盟は 発足二十周年の佳日をトして浅草の繁栄に多大な貢献をした人々の業績を讃え過去 現在 未来を通じここに芳名を列記して後世に永く伝えんとするものである庶民の町浅草は この町を愛し慈しみその興隆に一身を捧げる地元の人々によって、滔々たる大河の流れのように淀みなく発展を重ねていくことであろう 昭和43年(1968)10月吉日 東京都台東区長 上條貢浅草観光事業功労者 大谷米太郎 岡田四郎 上條貢 清水谷恭順 山田兵三 小林総介 高坂公一 賴母木眞六 穂刈恒一 橋本秋利 村田藤治郎 澤田要蔵 和田長敬 松村繁一郎 森田新太郎 荒井哲郎 豊田正利 藤谷吉之輔 川喜多忠之助 原戸賴吉 葛谷輝明 市村一雄 堀安孝 阿部高之丞 内山榮一 飯村茂 永野章一郎 守山良順 壬生台舜 清水谷孝尚 穂刈幸雄 野口日出男 中塚泰蔵 小林晴男 矢野隆夫 飯村恵一 吉住弘 西村太刀夫 春木實 松村吉紘 鈴木秋雄 田中久五郎 松澤欣一 荒井修 岩瀬桂助 橋本秋彦」 「浅草観光事業 功労者碑」 「石井漠「山を登る」記念碑」 「石井漠「山を登る」記念碑日本の創作舞踊の創始者石井漠明治19年(1886)秋田に生まれ昭和37年(1962)1月7日に昇天するまで、近代バレエの創造、浅草オペラの旗揚げ、300数曲の創作舞踊など、芸術活動は誠に偉大でありました。舞踊生活50年の山坂道を失明にあえぎながら登りつめた不滅の魂を記念するために、実妹栄子と共に踊った「山を登る」の姿を碑に刻み石井漠を愛した多くの人々や八重子未亡人の哀悼の念を永久に伝えようとするものです。題字 谷崎潤一郎設計 谷口吉郎彫刻 舟越保武施工 清水建設 昭和38年(1963)4月8日」 「映画弁士塚」。 無声映画時代の往年の名弁士たちを記念して昭和33年建立。碑名は鳩山一郎書。「明治の中葉わが国に初めて映画が渡来するやこれを説明する弁士誕生 幾多の名人天才相次いで現れその人気は映画スターを凌ぎわが国文化の発展に光彩を添えたが 昭和初頭トーキー出現のため姿を消すに至った 茲に往年の名弁士の名を連ねこれを記念する 建設省 大蔵貢」 「喜劇人の碑」。 近づいて。浅草はかつて、日本のブロードウェイと呼ばれ華やかな街でした。「喜劇人の碑」は人々に笑いと喜びを与えてくれた喜劇人たちに感謝の意を表し昭和57年(1982)建立された。碑裏面には喜劇人の名前が刻まれていた。川田晴久 昭和三十二年六月二十一日(五十一才)古川ロッパ 同 三十六年一月十六日(五十七才)八波むと志 同 三十九年一月九日(三十八才)清水金一 同 四十一年十月十日(五十四才)堺 駿二 同 四十三年八月十日(五十四才)榎本健一 同 四十五年一月七日(六十五才)山茶花究 同 四十六年三月四日(五十六才)森川 信 同 四十七年三月二十六日(六十才)柳家金語楼 同 四十七年十月二十二日(七十一才)木戸新太郎 同 四十九年八月十九日(五十九才)大宮デン助 同 五十一年十二月二十三日(六十三才)伴淳三郎 同 五十六年十月二十六日(七十三才)三波伸介 昭和五十七年十二月八日(五十二才)佐山俊二 昭和五十九年一月三十日(六十三才)武智豊子 昭和六十年七月十八日(七十六才)トニー谷 昭和六十二年七月十六日(六十九才)有島一郎 昭和六十二年七月二十日(七十一才)東 八郎 昭和六十三年七月六日(五十二才)南 利明 平成七年一月十三日(七十才)益田喜頓 平成五年十二月一日(八十四才)渥美 清 平成八年八月四日(六十八才)三木のり平 平成十一年一月二十五才(七十四才)曾我廼家明蝶 平成十一年四月十三日(九十才)由利 徹 平成十一年五月二十日(七十八才)ミヤコ蝶々 平成十二年十月十二日(八十才)清川虹子 平成十四年五月二十四日(八十九才)関 敬六 平成十八年八月二十三にち(七十八才)谷 幹一 平成十九年六月二十五日(七十四才)森繁久彌 平成二十一年十一月十日(九十六才)橋 達也 平成二十四年一月十六日(七十四才)「喜劇に始まり 喜劇に終る 森繁久弥」と。 「建立記念碑 協力芸能人(順不同)曾我廼家明蝶 コロンビア・トップ 菅原文太 黒沢年男 玉置宏 川津清三郎 志摩夕起夫 小桜京子 木田三千雄 原一平 由利徹 宮城千賀子 北上弥太朗 柳澤真一 コロンビア・ライト 赤木春恵 三崎千恵子 清川虹子 南利明 たこはちろう ハナ太郎 大屋満 大泉滉 宮島一茶 宮田章司 南道郎 徳武忠吉 小野田貝 玉川昭二 岡崎二朗ふじやま竜 関敬六 十勝花子 サトウサブロウ 冠般流川田琉球舞踊団 二代目引田天功朝風まり 松旭斉八重子 松旭斉美江子 小宮スポーツ 長沢純 日高一也 川中美幸 加山麗子 東映剣会 敏いとうとハッピー&ブルー 大塚文雄 平林健二と東京パンチョス 東京ニュースカイオーケストラ 花笠音頭協議会 小野満 干草かほる 榎本ちえ子」 「芸能人碑建立基金寄附御芳名(順不同)」と。 振り返って。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.05.30
コメント(0)
-

浅草を歩く(その18):浅草寺-14・銭塚弁財天~慈雲の泉~正観世音菩薩碑~浅草花やしきタワー~伝法院五重塔塔院
次に訪ねたのが「銭塚弁財天」。 正面から。扁額「錢塚辯才天」。 「銭塚弁財天弁財天さまは、七福神のお一人で仏教をお守りする善神である。芸能や学問の上達、財宝や福徳の神とされる。この銭塚弁財天さまは、福徳財運の弁財天さまとして、特に信仰が篤い。 金龍山 浅草寺」 この日な日曜日、参道には多くの出店が並んでいた。「浅草観音裏」案内図。ここ浅草寺(せんそうじ)は、東京都台東区浅草二丁目にある都内最古の寺で、正式には金龍山浅草寺(きんりゅうざんせんそうじ)と号する。聖観世音菩薩を本尊とすることから、浅草観音(あさくさかんのん)として知られているのだ。山号は金龍山。 「現在地」はここ。 東京スカイツリーと五重塔とのコラボ。多くのインバウンド観光客の姿が。バナナチョコ、広島風お好み焼き・・・・。ゴミ箱にはインバウンド観光客用の説明案内の文字が。列を作る店はなかったが。「浅草寺」の「本堂」を見る。「慈雲の泉」と。 浅倉文雄作「雲」。「荵雲の泉」の彫刻(彫刻名は「雲」というようですが)をアップで撮ったものが下の写真。猿のような顔つきですが、多くの人々が雲に乗って、先を見つめている様子を描いた と。「「讃慈の泉」の碑文東都随一の名刹として廣く世に知られる金龍山浅草寺は幾多の興廃消長の中に法灯連綿として今日に及ぶ とくに往古に優る當山の隆昌は大谷米太郎氏を会長とする浅草観光連盟の献身的努力に負うところ誠に多大である。かねて上野浅草の繁栄に意を注ぐ台東区長上條貢氏は昨秋上野信用金庫理事長長野高一氏寄贈にかかる生誕噴水塔を上野公園入口に建設したがさらに此の度同氏より多額の浄財の寄託を受くるに及び浅草寺 浅草観光連盟と相計り庶民信仰の霊域たる此の地に噴水塔建設を発意す上條区長の委嘱により地元関係者を以って建設委員会が結成され熟議検討の結果聖地に相応しき噴水塔の実現を期す 幸い彫塑家朝倉響子氏の好意により父君朝倉文夫先生の遺作「雲」の像の寄贈を受け ここに近代的噴水を配して「慈雲の泉」と名づく朝倉文夫先生は 日本芸術界の巨匠たると共に我が台東区の名誉区民にして「雲」の像は明治41年壮年に至らんとする先生が未来への欣求を籠めた一代の傑作である「慈雲の泉」は蓋し 長野高一 朝倉響子両氏を始め多くの人々の美しき善意の結晶と云えよう 幸い此の聖地に融和し とこしえに庶民の街浅草の象徴として愛護されんことを祈念してここに讃を記す。 昭和40年9月吉日 慈雲の泉建設委員会」 「五重塔」近くの「大銀杏」の樹の下にあったのが「正観世音菩薩碑」。 近づいて。「正観世音菩薩碑「「正観世音菩薩」と碑の正面に刻まれている。当寺には観音さまを表した金石が多く拳安されているが、その中でもひときわ大きい碑であるこの石碑の銘文は長年の風雪により摩滅が進んでいるが、「文」や「窪世」とわかる所が残されていることから、江戸時代の有名な石工の大窪世祥が、文化・文政年間(一八〇四~二九)頃に文字を彫ったと思われる。他にも世祥の金石は三基、境内に残されており、当寺にも関わりの深い人であった。江戸町人の信仰を載せた金石が運ばれ、活気付く境内の様が目に浮かぶようである。南無観世音菩薩 金龍山 浅草寺」 「新奥山」に向かって西に進む。再び日本最古の遊園地・「浅草花やしき」の「浅草花やしきタワー」を見る。 「花やしき」。 左手の「伝法院」の「五重塔塔院」の建物に沿って進む。裏口門の前には巨大な大狛犬が鎮座。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.05.29
コメント(0)
-

浅草を歩く(その17):浅草寺-13・六地蔵石燈籠~銅造観音菩薩坐像~一言不動尊~佛頂尊勝陀羅尼碑~金翠翁の句碑~金龍権現~九頭竜権現~橋本薬師堂~出世地蔵尊~商得地蔵尊~子育地蔵尊~めぐみ地蔵尊~恵比寿・大黒天堂
「六地蔵石燈籠」。 「東京都指定旧跡六地蔵石燈籠所在地 台東区浅草ニの三の一 浅草寺内仮指定 大正一三年ニ月五日指定 昭和三〇年三月ニ八日」 この石灯籠はかつて元花川戸町にあったものが、明治ニ三年(一八九〇)にあったものが現在地に移転されたものです。高さ約二三五センチメートル余り、龕部(がんぶ)六面に地蔵を彫りつけてあります。石燈籠と呼ばれていますが、「火袋(灯明部)」はありません。詳細は不明ですが、伝承では久安二年(一一四六)、久安六年(一一七〇)あるいは応安元年(一三六八)建立ともいわれます。現在では風化や火災の影響により、竿石に刻まれた文字などの判読は困難です。多くの文献に取り上げられている燈籠ですが、「江戸名所図会」などでもすでに印刻の判読が困難であったようです。そのため、都内でも古い時代の制作のものと考えられます。 平成二四年三月 建設 東京都教育委員会※久安六年は1150年である。「銅造観音菩薩坐像」 「銅造観音菩薩坐像台東区浅草二丁目三番一号 浅草寺本像は銅製、鋳造、鍍金で、大きさは総高が一六九・五センチメートル、像高は九九・五センチメートルである。本像は享保五年(一七二〇)に尾張国知多郡北方村(愛知県美浜町)出身で諸国を遊行した廻国聖、孝山義道が発願し、神田の鋳物師、小沼播磨守藤原長政が制作した。なお造立に際しては、近在の人々はもちろん、遠隔地からも多くの寄進を受け、その寄進者名が刻まれた。また本像の蓮華座は、元禄十五年(一七〇二)造立の阿弥陀三尊像の脇侍(勢至菩薩)のものとして、小伝馬町三丁目の鋳物師、宇田川善兵衛が制作したものであるが、後に本像の蓮華座へ転用された(勢至菩薩像は失われている)。本観音菩薩坐像を制作した小沼播磨守藤原長政は、江戸時代前期に活躍した鋳物師であるが作例は少なく、本像は長政の作例として新たに確認されたものである。江戸時代の鋳物師を考える上で基準となる作例のひとつであり、江戸鋳物師の作風を伝えるものとして貴重な遺品である。また、像や台座に刻まれた銘文は、江戸時代前期の信仰、宗教活動を知る上で貴重な資料である。平成二十五年三月に台東区有形文化財(彫刻)として台東区区民文化財台帳に登載された。平成二十八年三月 台東区教育委員会」 「一言(ひとこと)不動尊」。 「一言不動尊怒りのお姿をした不動明王さまは、そのお姿をして教化し難い者を導き、その力でわれわれの迷いの心を打ち切ってくださる仏さま。この一言不動尊は、何か願い事を一つに限って祈願すると、その願いがかなうとされ、古来より霊験が著しいといわれている。 享保十年(一七二五)造立。 金龍山 浅草寺」 扁額「不動堂」 「一言不動尊」を格子から覗いて。 「影向堂」を振り返って。 「佛頂尊勝陀羅尼碑」。 「仏頂尊勝陀羅尼「仏頂尊勝陀羅尼」とは、唱える人に息災延命などのご利益を授けるとされる、占くから信奉されてきた尊いお経である。碑の正面上部には「仏頂尊勝陀羅尼碑」と題字が、その下に梵字で陀羅尼が刻まれている。背面には漢字で陀羅尼の功徳について、末尾には造立年代である元治元年(一八六四)と製作者の名を見ることができる。この碑を奉納した海如(一八三七~七三)は、奈良の長谷寺などで修業した真言宗の僧侶である。碑の背面に「浅草大悲閣の下に建てた」旨が記され、当時天台宗であった浅草寺に碑を建立した経緯は不明であるが、当寺が宗派を超えて信仰されていたことを物語る。 金龍山 浅草寺」 「金龍権現」手前の石碑は「金翠翁の句碑」と。以下 ネットから 「寸法:総高165.0、幅45.2、奥行44.0形態:角柱型【正面】花の世へ 知らず生れて 又知らず 金翠翁【右面】露や霜 身こそあられぬ 雪の果【左面】かきり有る 人限りなき 月見かな【背面】家父吉村氏名達榮其先勢州大口邑人因稱大口始祖榮廣出勢來于東都而創産業千束村即今御蔵前也後與 官俸事至今五世百三十餘年祖父空翠自少小好俳歌方其時紫野祇空獨卓然斯道世人不堪景慕于今拝祇敬靈神盖尊稱之也遊其門者最多矣空翠亦師事之其伎益進家父幼而頴悟毎從祖父所好未嘗教之而口能成俳句八歳見祇空祇空愛其才名之以金翠俳道乃從祖父傳焉産業之餘嗜千宗易古流之茶事常會風雅友又興閑祠相得彈琴一曲獨樂恬靜云家父齡已六十二令余繼家事自稱翠翁既隱于金龍山下花川戸其居曰花川齋又號萬春庵便欲多年所好俳歌傳于不朽而自撰雪月花之三詠焉今茲刻石建于大悲閣西淡島神祠池上松樹之下蓋家父歳月尊信觀音大士故也使余記其事謹述其始末爾于時天明六年丙午冬十一月吉辰芳村達庵撰并毫《備考》金翠は、浅草天王町の札差大口屋八兵衛。父空翠の影響を受けて俳諧を好み、金翠と号した。また、歌舞伎・茶道にも通じたが、とくに同業札差とともに華美を究めた吉原通いを続けた。かれらは「十八代通」と呼ばれ、その大尽ぶりは『十八大通 一名御蔵前馬鹿物語』等の諸書に記されている。金翠は、本碑造立当時(天明6年、1786)62歳。家業を子息に譲り、浅草寺東方、花川戸の隠宅に住んでいた。本碑は花・雪・月を詠んだ自撰の句を刻んだもので、日頃から当寺を信仰していたことから造立。碑文の撰・書は子息達庵である。」と。 左:「金龍権現」 右:「九頭竜権現」。 「金龍権現」。 「金龍権現寺伝の縁起によれば、浅草寺ご本尊観音さまのご示現にあたり、天より百尺ばかりの金龍が舞い降りて、その功徳を讃え観音さまをお守りしたとされることから、浅草寺の山号を「金龍山」という。これにより奉安されたのが、この「金龍権現」である。このことに因み、現在、3月18日と10月18日の年2回、浅草寺境内にて寺舞「金龍の舞」が奉演されている。 金龍山 浅草寺」 「九頭竜権現」。 「九頭龍権現龍神さまは、仏教をお守りし、雨を操り、われわれに五穀豊穣や福憾を授けてくださる。この九頭龍権現は長野県戸隠山の地主神で、昭和三十三年の本堂再建にあたって、その成就を祈るべく勧請された。現在も浅草寺の伽藍安穏の守護神である。 金龍山浅草寺」 その先の石橋の下の流れには多くのコインが。ズームして。「橋本薬師堂」。 扁額「薬師堂」。 「橋本薬師堂 台東区浅草一一丁日三番 浅草寺当初は観音堂の北方にあって、北薬師と呼ばれた。慶安二年(一六四九) 三代将軍徳川家光が観音堂の北西に再建し、堀にかかる橋のかたわらにあったので、家光自身が橋本薬師堂と名付けた。平成六年、現在の場所に移転した。現在の建物は、権行三間(約五・三五メートル)、梁間三間(約五・一〇メートル)、屋根は人母屋造、瓦葺。外部はかなり改変され、前面にあった三間に一間の向拝は取り除かれているが、浅草寺境内に遺存する堂字のうち、浅草神社の社殿と同時代で、二天門や影向堂脇の六角堂に次ぐ古建築である。薬師如来坐像を本尊とし、他に前立の薬師如来と十二神将像が安置されている。 平成八年三月 台東区教育委員会」 「西境内案内図」。 近づいて。「本堂」を西側から見る。右奥には「東京スカイツリー」。 「出世地蔵尊」。 出世、商徳、子育の3つの地蔵尊が並ぶ右側にある小さな地蔵。古いお堂の中にあり出世が叶うという御利益がある事から多くの人が手を合わせていた。とても穏やかな表情をして赤い前かけが似合っている。「商得地蔵尊」。 出世、商売繁盛、子育といった様々な願いを叶えると言われている地蔵菩薩の尊称。特に商売繁盛にご利益があると信じられており、全国各地に祀られています。「子育地蔵尊」。 近づいて。「めぐみ地蔵尊」。 「お地蔵さま」は、六道を輪廻する衆生をあまねくお救いくださる仏さま。浅草寺境内には、その数何と20体を超える「お地蔵さま」が祀られている と。この「お地蔵さま」は、我々に幸せをお恵みくださることから「めぐみ地蔵」の名で親しまれている。「六道」とは「地獄」、「餓鬼」、「畜生」、「修羅」、「人間」、「天上」の6つ。「六道」すなわち6つの世界を輪廻、つまり、生きかわり、死にかわりしている衆生(生き物)を救ってくださる仏さまがお地蔵さま。私も説明板に書いてある「南無地蔵菩薩」と唱えて参拝した。「めぐみ地蔵お地蔵さまは、六道を輪廻する衆生をあまねくお救いくださる仏さまである。観音さまやお不動さまとともに広く信仰され、当寺境内にも二十体を超えるお地蔵さまがお祀りされているこちらもその一体であり、我々に幸せをお恵みくだされることから、「めぐみ地蔵」の名を以て親しまれているお参りの際には「南無地蔵菩薩」とお唱えください。 金龍山 浅草寺」 「恵比須・大黒天堂」 中に入っている恵比須・大黒天像。扁額「恵比須 大黒天 弘法大師作」 「恵日須・大黒天堂堂内向かって右側の恵日須(恵比寿)、左側の大黒天はともに七福神の神として信仰を集めている。江戸時代前期の延宝三年(一六七五)に浅草寺に奉納されたこれらの石像も、参詣の方々に穏やかな顔を見せてくれる(お堂は第二次大戦後の建立)。天保十五年(一八四四)にお堂脇に建立された石碑などによると、これらの像は真言宗を開いた弘法大師空海(七七四、八三五)が造ったと伝えられている。当時天台宗であった浅草寺においても、宗派を超えた弘法大師への信仰がみられることは、非常に興味深い 金龍山 浅草寺」 「恵比須 大黒天 弘法大師作」と刻まれた石碑。 この石碑は天保15年(1844年)に建てられたものらしい。そして「五重塔」。 手前には出店が並んでいた。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.05.28
コメント(0)
-

浅草を歩く(その16):浅草寺-12・六角堂~三峰神社~影向堂~石橋~句碑~西仏板碑~三尊名号供養塔
「銭塚地蔵堂」を後にして、南に進むと右側にあったのが「花やしき通り」入口。 「花やしき通り」を見る。直進して進むとその先左手にあったのが「浅草寺六角堂」。「浅草寺」境内に残る一番古い建物であると。本堂の北西、影向堂(ようごうどう)のエリアにひっそりとある「六角堂」。手前に「都重宝 淺草寺六角堂」碑。 「都重宝 淺草寺六角堂」に近づいて。扁額「日限地蔵尊」。 「東京都指定有形文化財(建造物)浅草寺六角堂所在地 台東区浅草ニ丁目三番一号指定 昭和二十七年十一月三日六角堂は「浅草寺誌」(文化十年編)に元和4年(1618)の建立とあり、江戸時代初期の建立と考えられ、浅草寺内で最古の遺構である。木造で単層の六角造り瓦(かわら)ぶき形式で、建物中央の直径は1.82mあり、一面の柱真々は0.91mである。建物の基礎は、六角形状に廻(まわ)した土台を布石の基礎で支え、その下部に11段の石積みをした1.5m余りの井戸上の穴が掘られている。六角堂という特異な形式であり、都内においては遺例の少ない建造物で、貴重な文化財である。もとは東方21.8mの場所{現・影向堂(ようごうどう)の南基壇上に元位置の表示あり}に建っていたが、平成6年(1994)10月境内整備のためにここに移された。※東京都文化財保護条例(昭和51年(1976)3月31日改正)により文化財の指定種別を都重宝から東京都指定有形文化財に変更したので、石造標識については、このように読み替えてください。 平成8年(1996)3月25日 東京都教育委員会」 「日限(ひぎり)地蔵尊六角堂のご本尊。地蔵菩薩さまは、慈悲のお心で、この娑婆世界だけでなく地獄や餓鬼道にもおもむき、衆生を救われる仏さま。特にこの日限地蔵尊は、何かのお願い事に対し、日数を定めて祈願すれば、古来より霊験があるとされる。造立年代は不明。木造。 金龍山浅草寺」 浅草寺六角堂は、『浅草寺誌』(文化10年編)に、元和4年(1618)に掘った井戸の上に建っていることを示す記述があり、さらには古い建築様式も採用されていることから浅草寺内に現存する最古の建造物と考えられます。実際、建物の底部は六角形状に廻した木製土台と基礎石で支えられ、更に、その下部に11 段の石積みをした深さ1.5m余りの井戸状の穴が堀られています。建物は、木造、桟瓦葺、朱塗りの六角円堂で、建物中央の直径は1.82m、一面の柱間は0.91m、都内ではあまり見かけない特異な形式の建造物です。屋根を支える垂木は、建物の中心から傘の骨のように放射状に広がる「扇垂木おうぎたるき」という形式で、桁の木組みも六角形に組むため、細工も難しく、大工の腕の 見せ所の一つです。反対側にあったのが「三峰神社」。 「三峯社三峯神社とは、秩父の森厳な聖地に社殿を構える古社である。天台修験の関東総本山とされ、殊に江戸時代には「三峯講」が各地に設けられ、盛んに参詣された。文化一〇年(一八一三)に編纂された『浅草寺志』をひもとくと、境内各所に様々な神社が勧請され三峯社も弁天山に建されていたことがわかる(戦災により焼失も再建)。本社は三峯に寄せる敬虔な信心とともに、明治初年の神仏分離令以前の信仰の様子を現在に伝えているのである。 金龍山 浅草寺」 その先、東・右側にあったのが「浅草寺 影向堂(ようごうどう)」。 本堂の北西に建つ、寄棟造りの堂宇が影向堂である。現在の影向堂は、平成6年(1994)に浅草寺中興開山慈覚大師円仁さまのご生誕1200年を記念して建立された。影向とは、神仏が姿かたちとなって現れることである。浅草寺では、観世音菩薩のお説法やご活躍に不断に協力されている仏さまを「影向衆」と呼び、影向堂に生れ年(干支)ごとの守り本尊八体(影向衆)を祀る。堂内は内陣と外陣に分かれ、内陣の須弥壇中央には聖観世音菩薩を祀り、その左右に千手観音、虚空蔵菩薩、文殊菩薩、普賢菩薩、勢至菩薩、大日如来、不動明王、阿弥陀如来を祀る。また、外陣には浅草名所七福神の大黒天を祀っている。影向堂は当山の朱印所であり、参拝証としてご本尊の聖観世音菩薩と大黒天のご朱印をお授けしている。境域には、元和4年(1618)に架設された石橋、青銅製の阿弥陀如来(元禄6年=1693)、宝篋印塔(宝暦11年=1761)など古い文物が多く存在する。「生れ年十二支本尊 影向堂」碑。 「影向堂影向堂はもと本堂南東にあったものを、平成六年に浅草寺中興開山慈覚大師円仁さまのご生誕千ニ百年を記念して、現在地に再建されたもので、観音さまのお説法やご活躍に不断に讃嘆協力されている仏さま方「影向衆(ようごうしゅう)」をおまつりしているお堂である。堂内には、中央に聖観世音菩薩さま、その左右に十ニ支に応じた生まれ年の守り本尊さま八体がおまつりされている。お堂の上、棟飾りには、火伏せの咒い(まじない)とされる金箔押しの鴟尾を置く。鴟尾を取り付ける際は不思議と雨を呼ぶといわれており、平成六年夏の建立時も記録的な日照りであったが、鴟尾を取り付けると突如として雨が降り、人々を感動させた。 金龍山浅草寺」 本堂東南にあったお堂(現淡島堂)に替わって平成6年(1994)10月20日現在地に落慶。鉄筋コンクリート寄棟造、錣屋根本瓦葺 間口13.3m・奥行13.3m・棟高12.9m・軒長19.7m。金箔押の「鴟尾(しび)」。長さ0.7m・高さ0.8m・幅0.3m 「阿吽(あうん)」の龍がそれぞれ浮彫りされている。鴟尾を取り付ける時には、不思議と雨を呼ぶといわれている。平成6年(1994)の夏は記録的な日照りの年であったが、この鴟尾を取り付けるとその後、恵みの雨がもたらされた と。「影向堂」は「朱印所」になっていた。坂東札所 第十三番江戸札所 第一番浅草名所七福神 大黒天「坂東三十三観音札所 第十三番江戸三十三観音札所 第一番浅草寺坂東三十三観音札所について昔、京の都から見て箱根の坂より東の諸国を「坂東」と呼んでいました。その坂東の武者たちが、源平の合戦にて西国へと歩を進めた際、西国の人々の観音札所巡礼への篤い信仰の姿に感動し、また源頼朝公の観音信仰がもととなり、鎌倉時代初期に坂東三三観音札所が開設されました。やがて、その西国三十三観音・坂東三十三観音に秩父三十四観音を加えて日本百観札所へと発展し、多くの巡礼者をお迎えし、今日に至っています。自身の心の修行や、いろいろな方への供養、さまざまな祈願をかねて、坂東三十三観音札所にお参り下さるようおすすめたします。坂東第十三番札所 浅草寺 御詠歌~ふかきとが 今よりのちはよもあらじ つみ浅草に まいる身なれば~江戸三十三観音札所について浅草から巡り始め、目黒で打ち納めとなる「江戸三十三観音札所」は、享保二十年(一七三五)刊の「江戸砂子拾遺」や、天保九年(一八三八)刊の 「東都歳事記」にも記録されており、江戸期にはかなりの巡礼で賑わいました。現在は江戸期の札所をもとに「昭和新撰江戸札所」として、衆生縁ゆたかな観音札所として賑わっております。どうぞ皆様のお参りをお待ち申しげます。 金龍山 淺草寺」 堂内には、中央に「聖観世音菩薩様」、その左右に「十ニ支に応じた生まれ年の守り本尊様八体」 がお祀りされていた。「大黒天」をズームして。「浅草名所(などころ)七福神」の内、浅草寺では「大黒天」をお祀りしている。大黒天は元々インドや中国で寺院の守護や豊穣を司っていたが、日本では袋を背負い俵に乗る柔和な姿となる。「影向堂のご本尊さま(生れ年守り本尊)」。 内陣の須弥壇中央には聖観世音菩薩を祀り、右:千手観音菩薩、虚空蔵菩薩、文殊菩薩、普賢菩薩、左:勢至菩薩、大日如来、不動明王、阿弥陀如来 を祀る。「影向堂聖観世音菩葮を中心に生れ年十ニ支守り本尊の八躰のほとけさまをおまつりしているお堂です。子 千手觀世音菩薩 縁日 十七日 無数の御手により私たちの苦を除いてくださる丑・寅 虚空蔵菩薩 縁日 十三日 福徳と知恵を無量に蔵し私達に与えてくださる卯 文殊菩薩 縁日 二十五日 ものごとの真相を正しく知る知恵をお持ちでそれを授けてくださる辰・巳 普賢菩薩 縁日 十四日 慈悲の心をもって私たちに延命福寿の幸せをお約束くださる中尊 聖観世音菩薩 縁日 十八日 大慈大悲のお心を持って私たちの苦を除き安楽を与えてくださる午 勢至菩薩 縁日 二十三日 阿弥陀さまの脇侍として知恵ををもって私たちをお救いくださる 未・酉 大日如来 縁日 二十八日 密教の仏の世界を綜合する根本仏としてのはたらきをなさる酉 不動明王 縁日 二十八日 怒りのお姿で教化しにくい者を導きその力でまよいの心を断ち切ってくださる戌・亥 阿弥陀如来 縁日 十五日 極楽浄土にあって法を説き無量の光明と寿命をもって永遠の生命を与えてくださる」 「中尊の聖観世音菩薩と生まれ年十ニ支守本尊の八躰仏」 須弥壇に鎮座する「聖観世音菩薩様」、その左右の「十ニ支に応じた生まれ年の守り本尊様八体」を再び。「恵比寿・大黒天」の「御影」は販売されていた。 「浅草名所七福神大国天このお像は、「浅草名所七福神」の一尊として信仰される大黒天である。別名「米櫃大黒」とも言われる。大黒天とは「大黒天神」とも呼ばれ、元々はインドの神であった。やがて仏教に取り入れられ、日本では袋を背負い俵に乗る柔和な姿に表わされ、商売繁昌や福徳の神としてお祀りされる。大黒天の縁日は「子」の日であり、この日にお参りされるご信徒も多い大黒天のご朱印も堂内にてお求めになれます。ご真言~おん まかきゃらや そわか~ 金龍山 浅草寺」 「御朱印」の列に並ぶインバウンドの方々。「影向堂」の本堂側には清らかな水の流れがあった。湧水なのであろうか?1~1.5m程の幅の流れ。「石橋(しゃっきょう)」の手前には、大きな鯉がのんびりと。この石橋は日光東照宮の神橋になぞられて造ったものだと言われている、全長3.3m幅2.2mの小松石造り。建造年代は元和4年(1618)だとされ、東京では最古の石橋。日光東照宮が出来たのは元和4年4月17日、同時に浅草寺境内にも東照宮を造り、家康を祀る東照宮を江戸浅草にも造り、一般町民にも参拝させようとしたもの。その時同時に本殿・随身門・唐門、石橋などを造りましたが、寛永19年(1642)2月19日浅草寺本堂が焼失した時、江戸東照宮に類焼し焼け残ったのが、現在の二天門として残り、後に重要文化財の指定を受け、この石橋も往事の姿をとどめている と。全身純白の鯉。石造りの太鼓橋。「石橋(しゃっきょう)現存する都内最古とされるこの石橋は、元和四年(1618)浅草寺に東照宮(現存せず)が造営された際、参詣のための神橋として造られたものである。寄進者は、徳川家康の娘振姫【ふりひめ】の婿【むこ】、紀伊国和歌山藩主浅野長晟【あさのながあきら】(広島県浅野家藩祖)である。この石橋は昭和23年、文部省より重要美術品に認定されている。 金龍山 浅草寺」 句碑「此華の 古那木の中の 桜の木 藤吉古老挙定治鐫」。「西仏板碑」。 「東京都指定有形文化財(歴史資料)西仏板碑所在地 台東区浅草ニ丁目三番一号浅草寺指定 昭和十七年九月旧跡 昭和五十六年三月十ニ日種別変更建立者の西仏については明らかではないが、この板碑(いたび)は彼が妻子の後世安楽を祈って建立したものと推測される。建立の年代も不詳であるが、鎌倉末から室町初期かと思われる。上部が破損しているが、製作時には三メートル近くあったものと思われる。寛保ニ年(一七四ニ)暴風雨によって倒れ破損、文化十一年(一八一四)に有志が側柱を立てて支えたという。材質は秩父粘板岩(青石)。現存の板碑の大きさは高さニ一七・九センチメートル、幅四八・〇センチメートル、厚さ四・七センチメートル。中世の信仰を知るうえで貴重な遺品であり、かつ巨大板碑の典型例である。 平成八年三月ニ十五日建設 東京都教育委員会」 「三尊名号供養塔」「三尊名号供養塔三尊名号とは、塔正面に刻まれた「南無阿弥陀仏」、向かって右の、「観世音菩薩」、向かって左の「大勢至菩薩」の阿弥陀三尊の名に山来する。阿弥陀さまは西方極楽浄土にて、往生者を迎えに来て(来迎)くださることから多くの信仰を集め、浅草寺にも影向堂内、本堂西側、境内各所にお祀りされ我々を見守ってくださっている。この塔は、文政十年(一八二七)に江戸屏風坂下(現在の上野)、の鹿島屋弥兵衛が発願した。ご先祖やさまざまな方々の 善提を弔うために本納した旨の銘文が刻まれており、江戸町人の阿弥陀さまを慕う敬虔な心が感じられる。 金龍山 浅草寺」 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.05.27
コメント(0)
-

浅草を歩く(その15):浅草寺-11・耕元先生碑~浅草寺子院群~銭塚地蔵堂~カンカン地蔵尊
「浅草寺」の「本堂」の裏の「大銀杏」。 その下にあった石碑・「耕元先生碑」。「耕元先生碑」は鎌倉時代の仏教者である耕元(こうげん)の墓碑です。耕元は、日蓮宗の僧侶として知られ、鎌倉時代に活躍した仏教者の一人 と。その他の詳細は不明。「大銀杏」を見上げて。 「浅草寺」の「本堂」の裏側入口。 次に「浅草神社」の北側にあった子院群を訪ねた。子院とは、本寺の境内にある小規模な寺院または、本寺に属する寺院を指します。禅寺では「塔頭」と呼ばれることもある と。子院それぞれの建物は民家・一般住宅の如し。子院群の入口には「立入禁止」と。 入口から奥をズームして。「浅草寺」の「本堂」を子院群前から振り返る。 「法善院」。聖観音宗(しょうかんのんしゅう)の寺院とのこと。聖観音宗とは、浅草寺を本山とした仏教の1宗派のこと。浅草寺は1950年より前は聖観音宗ではなく天台宗に属していたが、1950年以降は支院25ヵ寺、末社18舎を率いる聖観音宗の総本山となった と。「観智院」。 「金蔵院」。 都道319号線沿いにあった「浅草寺福祉会館」。 「浅草寺 公式SNSのお知らせ」。 「QRコード」。 都道319号線側から子院群の中にある路地を見る。そして再び「浅草寺」の「本堂」の裏側に戻り再び「一葉観音」を。「本堂」裏広場の像、石碑群を右奥に再び見ながら進む。「本堂落慶 記念植樹」碑。 先ほどカメラで追った石碑・石像群。石碑・石像群の裏には「浅草寺病院」。浅草寺病院は、明治43年(1910年)に浅草地区を襲った水害の被災者を救護するため、浅草寺が境内にあるお堂を開放し、被災者を収容したことからその歴史が始まり と。「浅草寺」の「本堂」の裏側から「浅草花やしき」の塔を見上げる。 ズームして。「浅草寺と浅草「浅草寺縁起」によると、推古天皇3 6年( 6 2 8 )に檜前浜成・竹成(ひのくまのはまなり・たけなり)兄弟が隅田川で漁撈中、一体の仏像を投網の中に発見した。それを上師中知(はじのなかとも)が拝し、聖観世音菩薩の尊像であることを知り、自ら出家し、屋敷を寺に改めて深く帰依(きえ)したという。これが浅草寺の草創である。」 「「浅草寺縁起」寛文ニ年改写本狩野氏信筆 寛文2年(1662 )浅草寺所蔵」。 「浅草寺周辺案内図」 「浅草歳時記」👈️リンク。 そして次に訪ねたのが「銭塚地蔵堂」。 正面から。令和元年11月に再建された鉄筋コンクリート造りのきれいな堂宇。「銭塚地蔵堂昭和三十九年に再建されたこのお堂には、石造の「六地蔵尊」が安置されており、その下に「寛永通宝」が埋められているといわれることから「銭塚」の名がある。江戸時代、摂州有馬郡に山口なる者がおり、その妻がある日、庭先で寛永通宝が沢山入った壺を掘り当てた。だがこれに頼って働かずにいては、家は減びてしまうと考え、誰にもいわず再び土中に埋め戻した。この心掛けによって一家は繁栄したので、その壺の上に地蔵尊を祀ったという。お堂のご本尊は、そのご分身を勧請したもので、商売繁昌のご利益があるといわれる。毎月「四の日」と正・五・九の各月ニ十四日に法要が営まれ、参拝者は塩と線香と口ーソクをお供えする。特に塩をお供えするので「塩なめ地蔵」の名もある。 金龍山 浅草寺」 赤地に白抜きで「銭塚地蔵尊」と書かれた幟旗。廻り込んで。「奉納 融通 銭塚地蔵尊」と。ズームして。「手水場」。 「銭塚地蔵尊」碑。 「内陣」。扁額「銭塚地蔵尊」。 「内陣」をズームして。商売繁盛祈願であり、堂内に「六地蔵」が安置されていた。 この写真はネットから。この像の下には江戸時代の貨幣「寛永通宝」が埋められていると。さらに「六地蔵」尊にズームして。 右側奥に「かんかん地蔵尊」。 もとは大日如来像と伝わっている と。「カンカン地蔵尊このお地蔵さまは、お姿の原型をほとんど残していない。古来よりお参りの方が、付随の「小石」で御身をごく軽く「たたき」お願いごとをする。石で軽く打ち祈ると「カンカン」という音が鳴るので俗にこのように称されている。(刃物や他の石などで御身を「削る」ことは、固くお断りしている) 金龍山 浅草寺」 「カンカン地蔵尊」👈️リンク。 「カンカン地蔵尊は古来より付随の「小石」で御身をごく軽く「たたき」御願いごとをする御地蔵様であります。刃物や石で御身を「削る」事はおやめ下さい」とここにも。 「獅子獅子舞や唐獅子として広く日本に親しめる獅子は百獣の王ライオンをモチーフにした、大陸から伝わった想像上の生き物です。その姿は勇猛果敢で、またその発する声は獅子吼と呼ばれ、お釈迦様の言葉、仏様の言葉とされます。」 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.05.26
コメント(0)
-

浅草を歩く(その14):浅草寺-10・「本堂」裏広場の像、石碑群
「浅草寺」の「本堂」の裏の広場の北側の緑地帯には多くの石碑、石像等が並んでいた。東側から「大谷米太郎夫妻像」。 「大谷米太郎夫妻像」。宝蔵門の寄進建立をはじめ、浅草寺の復興に尽くした大谷夫妻壽像で、昭和42(1967)年10月造立。夫妻の胸像は、昭和37(1962)年に朝倉文夫により製作された。ズームして。「大谷米太郎翁・さと子夫妻」 の胸像。 大谷米太郎翁は明治14年(1881)~昭和43年(1968) 86歳で逝去。昭和15年(1940)、一代で大谷重工業を設立。 東京オリンピックを機にホテル・ニューオータニを建設した実業家。「大谷米太郎翁寿像記翁ハ明治14年富山縣ニ生ル壮ニシテ上京大谷製鋼所ヲ創立シ社運隆々今日ノ大ヲナス夙ニ大慈ニ帰依シ浅草寺信徒総代トナリさと子夫人ト共ニ宝蔵門ノ寄進ノ外伽藍ノ復興に尽力シ衆庶ノ信仰ヲ荘厳ス其ノ功徳永ク金龍ト俱ニ輝カン 昭和四十二年十月一日」 宝蔵門、現在の門は浅草寺の山門として、内部三層のうち上部二層に近代的な防災設備を施した収蔵室を設け、浅草寺の什宝物収蔵の宝蔵門として大谷重工業・ホテルニューオータニ創始者の大谷米太郎氏のご寄進により復興再建された と。「天下泰平 奉納大乗妙典六十六部供養佛」碑。 六十六部とは、六部ともいわれ法華経を書写し、それ を日本全国六十六州の神社仏閣の霊場に奉納して廻る行 脚僧のことであるとされ、その廻国巡礼の証とされる 石塔「廻国供養塔」が、全国津々浦々に残されているのだ と。「消防殉難者表彰碑」 石碑にズームして。「消防殉難者表彰碑」は、宮内省から200円の下賜金を受け、警視庁消防職員が大正元(1916)年に建立したもの。表彰碑の手前の2本の石柱は、昭和36(1961)年に建立された江戸消防記念会の碑です。毎年5月25日の「弥生祭」に、江戸消防記念会により慰霊が行われています。表彰碑の手前の2本の石柱は、昭和36(1961)年に建立された江戸消防記念会の碑。「市部消防組」、「社團法人 江戸消防記念會」「消防殉職者表彰碑明治四十四年(一九一一年)当時の警視総監安楽兼通氏唱道によって享保四年(一七一九年)江戸町火消(いろは四十八組)が創建以来、猛火の中に身を挺して職に殉じた方々の功績が年々忘れ去られ消滅して行くことを憂慮し、これを後世に伝え永久に・・・・・・・」「浅草寺」の「本堂」を裏側から見る。 諸石仏右 :「地蔵菩薩像」 堺町の山城屋萬之助が先祖供養のために建立中央:「地蔵菩薩像」 延宝5(1677)年、木食阿闍梨安信和尚が建立左 :「如意輪観音像」 享保20(1735)年、僧常念が建立右:「地蔵菩薩像」堺町の山城屋萬之助が先祖供養のために建立。法華経供養塔。中央:「地蔵菩薩像」 延宝5(1677)年、木食阿闍梨安信和尚が建立。 木の陰に隠れて。(左:「如意輪観音像」 享保20(1735)年、僧常念が建立。)「竹本津賀太夫碑」。 「大江戸のつよきひいきの力にぞ、かかる千曳のいしぶみはたつ」と刻まれ、台石には百数十名の門下の名が列記されている。文政10年(1827)建立。移動して。手前に「初代並木五瓶句碑月花のたわみこころや雪の竹」現在の場所にどこからか移動したのであろう。後方に「菅沼定敬の歌碑(すがぬまさだちか)」「敷島のみちにはせきもあらなくに、なとてこころのとほらざる覧」と刻まれている。嘉永3年(1850)建立。「初代並木五瓶句碑碑面には、正面に「月花のたわみこころや雪の竹」、右手側面に「なにはづの五瓶、東武に狂言を出して、あまねく貴賤の眼目を驚かし、金竜の山中に雪月花の碑を築て、永く繁栄を仰ぐ、つづくらん百三十里雪の人晋子堂大虎」、左手側面に「寛政八年丙辰十二月十日建之 庭柏子書印」、裏面に「篠田金二迂造」と刻んである。「なにはづの五瓶」は初代並木五瓶のこと。五瓶は大坂に生まれ、歌舞伎狂言作者として活躍した。生存年代は延享4年(1747)から文化5年(1808)まで。はじめ五八、のち吾八・呉八・五兵衛と改め、ついで五瓶という。寛政6年(1794)江戸へ出て、非凡な才能をみせ、初代桜田治助とともに、江戸の二大作者と謳われた。時代物・世話物に優れた作品を遺し、4代市川団蔵、4代松本幸四郎らによって演じられた。作品には、「金門五山桐」「隅田春奴七容性」「富岡恋山開」「幡随院長兵衛」などがある。 平成6年(1994)3月 台東区教育委員会」 左手前の石碑「山東京伝 机塚の碑」。 「山東京伝机塚の碑 台東区浅草二丁目三番一号 浅草寺内山東京伝(一七六一~一八一六)は、浅草や吉原を題材とする戯作を多く著し、北尾政演の画号で浮世絵もよくした人物。この碑は、京伝の弟原山が文化一四年(一八一七)に亡兄を偲んで建立。表面には晩年の京伝撰「書案之紀」を刻む。書案とは机のことで「九歳時に寺子屋に入った際、親の買ってくれた机を生涯愛用し、この机で百部を越える戯作を書いた。しかし五〇年近くも使ったので、ゆがみ、老い込んださまは哀れである」という意味の文と、「耳もそこね あし(足)もくしけてもろともに 世にふる机なれも老いたり」の歌が記されている、また、裏面には、京伝と親交のあった戯作者太田南畝の撰による京伝の略歴を刻む。京伝の生涯や人間性を伝える貴重な資料で、平成二年に台東区有形文化財として登載。平成六年三月 台東区教育委員会」 手前左が「山東京伝机塚の碑」。 その左に「十万人講供養塔」。十万人講は、享保6(1721)年の観音堂修繕に際し、別当公然僧正が組織した講中。その時の施主名簿が収納されています。 「宮古路豊後掾(みやこじ‐ぶんごのじょう)の墓」👈️リンク宮古路豊後掾(みやこじぶんごのじょう・1660年- 1740年)は、江戸時代中期の浄瑠璃の太夫。京都の生まれ。都国太夫半中、都路国太夫、宮古路豊後、宮古路豊後掾橘盛村とも。「天文庚申 還國院本譽自性居士」と。享3(1746)年の建立 と。「釘供養塔」。正面から見た「釘供養塔」、由来などが何も分からない。もしかしたら裏面に書いてあるのかな?見たいが芝生で柵が。「釘供養塔」は今や電動工具で釘を打つ時代だから、釘を使う大工さんは減っている。今はどういう人たちが「釘供養」をしているのだろうか?! 「阿弥陀如来像」。この「阿弥陀如来像」は「針供養塔」に関わるものであっただろうか? 「釘供養会「釘供養会」とは、仏教の儀式の一環で、特に亡くなった人のために、釘を打つことによって、その霊魂を慰め、冥福を祈る行為です。これは、特に釘念仏と関係があり、地獄での苦しみから解放されることを願う信仰に基づいています写真はネットから。ここにも一番手前に「宝篋印塔」。 寛延2(1749)年に建立の宝篋印塔。台座上に十六羅漢像が陽刻されていた。そして「九代目市川団十郎「暫(しばらく)」の像」。 浅草寺境内、浅草寺本堂裏広場にあるのが、九代目市川團十郎像(暫像)。9代目・市川團十郞は、明治時代に活躍した歌舞伎役者で、『歌舞伎十八番之内 暫』(元禄10年に初代市川團十郎が初演)は、9代目上演してから一幕物として独立したという十八番(おはこ)。「銘大正八年 江戸歌舞伎ゆかりの地 浅草の浅草寺境内に 劇聖と謳われた明治の名優九代目市川團十郎の歌舞伎十八番「暫」の銅像が作られました この銅像は 近代彫刻の先駆者新海竹太郎氏の傑作であり 歌舞伎の象徴として全國の人々から親しまれておりました ところが第二次世界大戦中の昭和十九年十一月三十日金属回収のため この「暫」の銅像も供出の命を受け 四十余年を経てまいりましたこの度 十二代市川團十郎襲名を機に 復元の機運が高まり 浅草寺の御理解のもと 多くの方々に御尽力を賜り ここに「暫」の銅像が再現されました 十一代目並びに十二代市川團十郎父子 地元浅草及び松竹株式会社三者の永年の願いが叶えられたことになりますこののちも 歌舞伎の隆盛とともに この「暫」の銅像が歌舞伎の象徴として 日本國民はもとより世界の人々からも 幾久しく愛されますことを願ってやみません 昭和六十一年十一月三日 宇野信夫 撰書 九代目市川團十郎「暫」銅像復元建設委員会 十二代市川團十郎 浅草観光連盟 松竹株式会社」」清原武衡(きよはらのたけひら)が、自分の意に従わない人々を家来に命じて斬ろうとするところに、「しばらく」という声とともに鎌倉権五郎(かまくらごんごろう)が登場し、人々の命を助けるというストーリーです。江戸歌舞伎では、俳優は芝居小屋と1年ごとに契約を結びました。その契約のスタートする11月の興行は「顔見世(かおみせ)」とよばれ、一座する俳優の顔ぶれを披露する最も重要な年中行事でした。この「顔見世」で上演される作品には、おもな俳優が一堂に会し、「しばらく」という声とともに登場する正義感あふれる人物が、悪人に殺されかけている人々を救う場面を組込む慣習がありました。「顔見世」で上演されたさまざまな作品で、何度も演じられたこの場面は、次第に洗練されていき、一定の演出が完成しました。明治以降は、この場面を『暫』として独立させて上演するようになり、現在に至っています。このような経緯で誕生したため、ストーリーを楽しむというよりも様式化された演出を楽しむ演目といえます。主人公は代々の市川團十郎(いちかわだんじゅうろう)が得意とした「荒事(あらごと)」で演じられるため、『暫』は團十郎家の「家の芸」である「歌舞伎十八番」の1つに数えられています。ズームして。現市川團十郎の「暫」。 「堀越秀像銘並序👈️リンク大正戊午九月。銅鑄堀越秀演技像成。堀越氏者倡優名閥。世稱市川團十郎。秀其七世第五子。天保戊戌十月十三日。生於江戸木挽街。弱冠以技名天下。明治甲戌七月。襲稱曰九世團十郎。癸卯九月十三日。病歿茅碕別業。饗年六十有六。事具伊原敏郎撰傳中。秀壯遭中興之運。目睹庶事維新。心有所期。誓欲脱倡優之陋習。於是縄己謹廉。遂能爲士林所齒。豈可不謂卓於往。而赫於來者邪。像之成在秀即世十五年後。其嗣福三郎。請陶庵西園寺侯書跌前。又嘱余銘。余嘗與秀相識。喜其為人。且謂倡優之技雖卑乎。有關於教化也。乃為之銘。曰。」 優孟九世傳衣冠。名噪天下十郎團。睅目隆準顔塗丹。矮軀亦作長身看。其止端重邱山安。其動遄迅鵰鶚搏。音吐訇訇扣金盤。一呼堪息百夫讙。奄忽云亡妙技殫。海澨秋陰葢柏棺。惟見遺像立江干。千載兒女增永歎。 鷗外森林太郎撰 不折中村鈼太郎書建設者 追善會委員 門下一同」 「大正戊午(7年)九月、銅鋳堀越秀演技の像成る。堀越氏は倡優の名閥なり。世に市川團十郎と称す。秀は其の七世の第五子にして天保戊戌(9年)10月13日、江戸木挽街に生る。弱冠にして技を以て天下に名あり。明治甲戌(7年)7月、襲ぎて九世團十郎を称曰(とな)う。癸卯(36年)9月13日、茅ヶ碕の別業にて病歿す。饗年(享年)六十有六。事(事績)は伊原敏郎撰の傳(伝)中に具(つまびらか)なり。秀は壮にして中興の運に遭う。維新の庶事を目睹(目の当たりに)して、心に期する所有り。誓ひて倡優の陋習(ろうしゅう)を脱せんと欲す。是に於いて己を縄(いまし)め謹廉(謹慎廉正)たり。遂に能く士林(立派な人)に歯(なら:同列)ぶ所と為る。豈に往くに於いて卓(すぐ)れ而して来者に於いて赫たりと謂はざる可けん邪(や)。像の成るは、秀の即世十五年後に在り。其の嗣福三郎、陶庵西園寺侯に跌前に書するを請ふ。又余に銘を嘱す。余嘗て秀と相識り、其の人と為りを喜(この)む。且つ倡優の技は雖(もと)卑なりと謂はん乎(や)。教化(まわりの環境の影響)に關わり有る也。乃ち之が為に銘して曰く。」 とネットから。後ろに廻り込んで。1周して。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.05.25
コメント(0)
-

浅草を歩く(その13)・浅草神社(3/3)~浅草寺-9・宝篋印塔~一葉観音
・「浅草神社」の「社殿」を正面から。 「賽銭箱」。 「拝殿内」を見る。薄暗い拝殿内で金色の御幣が鈍く輝き、右大臣、左大臣の随身が守護していた。 金色の御幣をズームして。漆塗りと鮮やか色を用いた浅草神社の社殿の右側。極彩色豊かな浅草神社の社殿をよく見ると、さまざまな生き物が描かれているのが分かるのであった。「鳳凰(ほうおう)」。 漆塗りと鮮やか色を用いた浅草神社の社殿の左側。社殿には三つの霊獣(架空の生き物)が描かれていた。●麒麟(きりん):体は鹿、頭は狼、尾は牛、足は馬、そして角を持つ。虫も踏まず草を折る こともない霊獣。●飛龍(ひりゅう):体が魚で翼をもつ動物。胴が短く尾びれがあり水を司る霊獣。●鳳凰(ほうおう):アオギリという木に宿り、竹の実を食べ、醴泉レイセン(甘い水の泉)の 水を飲み、聖天子出生の瑞兆として出現すると伝わる霊獣。鳳凰と麒麟は中国の古代思想における「四神」の霊獣であり、仏教の影響が強いことが分かる。平成六~八年の大修営によって修繕され、もとの荘厳さが再現されたのだ と。「麒麟(きりん)」。 「飛龍(ひりゅう)」。 「天井画(てんじょうえ)」をネットから。社務所横にあたのが、末社「被官(ひかん)稲荷神社」石鳥居。「正一位 被官稲荷神社」。 石鳥居の柱には「新門辰五郎」と。被官稲荷神社の始まりは 19 世紀にまでさかのぼります。当時、浅草の町火消の親分に 新門辰五郎(しんもん たつごろう)という人物がいた。1854 年(安政元年)、新門辰五郎の妻が病気になりました。新門辰五郎は、京都の 伏見稲荷大社(ふしみ いなり たいしゃ)で彼の妻のために祈った。伏見稲荷大社は、稲荷神社の総本宮(おおもとの神社)。その甲斐あって、新門辰五郎の妻は回復。彼は伏見稲荷大社にとても感謝した。1855 年(安政 2 年)、新門辰五郎は、伏見稲荷大社の稲荷神を浅草に勧請(かんじょう)した。勧請とは、神さまや仏さまの分霊(分身)を他の場所で祀ること。これが被官稲荷神社の始まりである と。 「上野 加藤氏」とも。 「安政二夘(卯)年(1855)九月立之」 と。参道を進むと、三連石鳥居が姿を現した。近づいて。石燈籠にも「新門」と刻まれていた。三連鳥居の3つ目の鳥居の扁額の上下には狐があしらわれていた。そして「被官稲荷神社 社殿」。 社殿の鞘堂?の柱、梁を見ると歴史を感じるのであった。「被官稲荷神社 台東区浅草二丁目三番一号安政元年(一八五四)、新門辰五郎(しんもんたつごろう)の妻女が重病で床に伏したとき、山城(現、京都府南部)の伏見稲荷神社に祈願した。その効果あって病気全快、同二年、お礼の意味を込め、伏見から祭神を当地に勧請し、小社を創建して被官稲荷社と名付けた。名称の由来は不詳だが、被官は「出世」と解せば良いという。 辰五郎は上野寛永寺住職輪王寺宮の家来、町田仁右衛門の養子。本姓は町田であった。輪王寺宮舜仁法新王が浅草寺伝法院に隠居し、上野へ行くのに便のいい新門を造った。その門の番を命じられたので、新門辰五郎と呼ばれた。辰五郎は町火消十番組の組頭としても、多彩な活躍をした。社殿は一間社流造(いっけんしゃながれづくり)、杉皮葺。創建以来のもの。間口約一・五メートル、奥行約一・四メートルと小さいが、覆屋(おおいや)を構えて保護している。覆屋は大正期の建築物であろう。社前には、「安政二年九月立之 新門辰五郎」と刻む鳥居ほかがある。平成四年十一月 台東区教育委員会」 狛狐(右)。社の一番手前のお狐さん。右が食いしばった形の阿形で子抱き。狛狐(左)。吽形で鍵を抱えて。ここにも。右が阿形で宝珠を抱える。左が吽形で鍵を抱えるのであったが・・・。目つきは左右全く異なるが、全体的な造作は同じか。社殿右脇には奉納された数え切れない数の鳥居が。小さな石の祠もあった。社殿に近づいて。「神拝詞 三唱祓え給い 清め給え神ながら 守り給い幸(さきわ)え給えニ拝ニ拍手一拝」 「御供所」。「被官稲荷神社の名物」と言えばコレ。「お姿」と呼ばれる、白狐の姿をした陶器製の置物。今戸焼(らしい)。ズームして。曼陀羅の如く数百並ぶその様子は、どこか異世界の不思議な住人に出くわしたかのよう。狐の顔の形の絵馬。「浅草神社」の社殿前まで引き返して。 「被官稲荷神社島居を御奉納いただいた皆様へ お知らせ平素より当社へ格別なるご厚情を陽り、心より感謝申し上げます。諸般の事情により、泰納島居につきまして今後下記の通り規定変更及び仕様・規格改定をさせていただきます。何卒ご理解の程、お願い申し上げます。①お申し込み ご希望の奉納日の5日前までの受付とさせていただきます,②お焚きをげ 奉納場所が埋まった場合のみ、6月末にお焚き上げする場合がございます。 (※通常は毎年12月末にお焚き上げします。)③浄書内容 ご芳名・願意・宝納日のみ記載と致します。 個人情報保護の観点から住所の浄書は致しませんが、御神前にてご芳名・願意と共に 奉唱させていただきます、④大きさ・形状島居〔大〕 島居〔小〕旧:高さ 約1m30cm 幅1m30cm 旧:高さ約55cm 幅55cm ⬇️ ⬇️ 新:高さ 約1m10cm 幅1m 新:高さ約72cm 幅60cm笠木・貫は平板、柱は丸棒です。なお、初穂料の変更はごぎいません。 被官稲荷神社社務所」 「社殿」を左側から。正面に三柱の御祭神の名が刻まれた「三柱の碑」。浅草神社の宮司が、ご祭神の御名である「土師」姓の名跡を改めて継がれる慶事を記念して、平成30年3月に建立された。社紋と海を表す意匠に三柱のご祭神の御名が刻まれ、観音様との御縁や浅草草創の経緯と信仰を伝え記すと共に、地域社会の更なる隆盛への願いが込められている と。 浅草神社の三体の御祭神が中央:土師真中知命(はじのまなかちのみこと)右:檜前浜成命(ひのくまのはまなりのみこと)左:檜前武成命(ひのくまのたけなりのみこと)「推古天皇三十六年(西暦六二八)三月十八日早朝、檜前浜成・武成の兄弟が江戸浦で漁労中、投網の中に一体の仏像を感得し、これを土師中知が拝された聖観世音菩薩の尊像であることを知り、自ら出家し屋敷を寺に改めて深く帰依した」これは『浅草寺縁起』に記された浅草寺の起こりであり浅草草創のお話です。後に土師中知は「土師真中知命 ( はじのまなかちのみこと )」として、「檜前浜成命 ( ひのくまはまなりのみこと )」「檜前武成命 ( ひのくまたけなりのみこと )」と共に、浅草寺本堂の傍 ( かたわ ) らに「三社大権現 ( さんじゃだいごんげん )」として祀 ( まつ ) られ、また、その子孫は「専堂坊 ( せんどうぼう )」「斎藤坊 ( さいとうぼう )」「常音坊( じょうおんぼう )」の名で「三譜代 ( さんふだい )」と称され、僧侶として代々浅草寺に仕えられました。「専堂坊」を称した土師家「三社権現社」の社僧としても仕えてきましたが、明治元年に政府より発令された神仏分離令において社名が「三社明神 ( みょうじん ) 社」に改められ、専堂坊職であった。「土師忠英 ( ちゅうえい ) ( 土師五十九世専堂坊 )」は同社に移って祀官 ( しかん ) となり、名を「土師長夷 ( ながきよ )」に改め神職として奉仕されました。激しく変動する時代情勢の中に、奇 ( く ) しくもその後は「土師」の名称を継ぐ事が慮( おもんばか ) られ、それを機に改姓せざるを得ませんでしたが、この平成の御代 ( みよ ) において、氏子崇敬者の総意を以て、浅草神社宮司職として「土師」姓を改めて継がれる運びと相成りました。「三社権現社」の社僧から始まり「三社明神社」の祀官を経た「浅草神社」の宮司の姓は「土師」が本来であり、我が国の歴史と文化を背負っていることは、我々浅草の氏子や崇敬者にとっても誇りです。本年は観音様と称される聖観世音菩薩の御示現 ( ごじげん ) より一千三百九十年の節目となり、十年後には一千四百年の慶事の都市を迎えます。玆に、今もなお三社様と親しまれる浅草神社三柱 ( みはしら ) の御祭神の御名 ( みな ) を記した「三柱の石碑」を建立し、連綿と続く「土師」の系統を基に、観音様と三社様の御縁や御由緒、そして浅草草創の歴史的経緯とその信仰を、浅草内外に向けて広く発信すると共に後世へ伝え記し、浅草神社の弥栄 ( いやさか ) と地域社会の更なる隆盛を切に願うものであります。 平成三十年三月十八日」 「観世音菩薩 夢告汝等の親は我を海中より薫護せり。故に慈悲を万民に施し今日に及びしが、その感得供養の功は賞すべきなり。即ち観音堂の傍らに神として親達を鎮守すべし、名付けて三社権現と称し齋祀らば、その子孫・土地共に永く繁栄せしむべし。」 「お近くの神社を紹介浅草富士浅間神社(あさくさhuじせんgeんじんじゃ)御祭神 木花咲耶比売命(このはなさくやひめのみこと)御神徳 安産、病気平癒、疱瘡(疫病除け)御由緒 富士山の神様をお祀りする神社。富士信仰が最も盛んだった江戸時代に静岡県富士宮市の 浅間大社より勧請・分祀されました。例大祭 七月一日植木市 五月・六月最終土日」 「浅草寺周辺案内図」 近づいて。「宝篋印塔」。 「宝篋印塔(ほうきよういんとう)「宝篋印塔」とは、『宝筺印陀羅尼(ほうきょういんだらに)という経典を収めたことに由来する仏塔で、日本では主に石塔婆の一つの形式として盛んに造立された。ごの塔は江戸時代中頃の安永四年(一七七五)に、境内にかってあった荒澤不動堂の實圓を導師として造立され、銘文は江戸深川に住む書家の三井親和によって揮毫された。塔の四方には、「宝篋印陀羅尼」の経文の一部が刻まれており、「お経を書写して奉安し、礼拝供養する者は、過去の罪障が消減する」など、計り知れない功徳を得ることが説かれている。功徳を得ることを願う人々の祈りの声が聞こえる。 金龍山浅草寺」「宝篋印陀羅尼」の経文の一部が刻まれていると。そして「一葉観音」。 近づいて。寛政9年(1797)造立。秩父三十二番札所の本尊の模刻。頭上に笠をかぶって手にかいを持ち、蓮の花びらを舟に模して乗っている唐銅製の観音像。その一葉観音菩薩像は1797年、新吉原江戸町の質両替業万字屋の佐野ひで女によって寄進された。ひで女の子である久次郎は当時14歳。ある日、品川沖に遊山へと出かけた際に、不幸にものり船と衝突、水難死してしまう。そこで子の霊を弔おうと思ったひで女は、浅草寺と本所回向院と菩提寺の三ヵ所に数年を費やして一葉観音菩薩像を建立したという、寄進に関する言い伝えがある。今でもこの菩薩像は観音本堂裏に、金網で囲まれて安置されている。移動して。ネットから。「一葉観音埼玉県の秩父三十四観音札所の第三十二番法性寺の観音像を模して造られた。蓮の一枚の花びらの上に乗り、楫を持ち、笠をかぶったお姿。新吉原の「ひで」という女の十二歳の息子久次郎が、水難事故によって亡くなったことを偲び、息子の菩提のため、また今後このようなことのないようにとの、「ひで」の願いによって造立された。寛政九年(一七九七)に造立。唐銅製。 金龍山 浅草寺」 浅草大百科にはもう少し詳細が記されていて、一部抜粋すると、「新吉原江戸町の質両替業万字屋の佐野ひで女によって寄進された。ひで女の子である久次郎は当時14歳。ある日、品川沖に遊山へと出かけた際に、不幸にものり船と衝突、水難死してしまう。そこで子の霊を弔おうと思ったひで女は、浅草寺と本所回向院と菩提寺の三ヵ所に数年を費やして一葉観音菩薩像を建立したという、寄進に関する言い伝えがある。」と。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.05.24
コメント(0)
-

浅草を歩く(その12)・浅草神社(2/3)
境内の右手に「神楽殿」。 神楽殿に松が使われる理由は、松が神聖な樹木とされ、神社の境内に飾られることで、神楽の場を清浄化する役割があるためです。また、松は長寿や縁起の良い象徴としても知られており、神楽殿に松を飾ることで、神楽の儀式をより一層神聖なものにする意味合いもあるのだ と。ポスター「浅草神社例大祭「三社祭」 フォトコンテスト」。 「令和6年度 三社祭大賞 「三社祭の賑い」」、槌谷義郎氏の作品。令和7年度「三社祭」👈️リンク ポスター。 令和7年5月15日(木)~18日(日)開催「河竹黙阿弥顕彰碑河竹黙阿弥(かわたけもくあみ)は江戸末期から明治中期まで活躍した歌舞伎の狂言作者である。文化13年(1816)3月江戸日本橋通2丁目4代越前屋勘兵衛の長男として生まれ幼名を吉村芳三郎といった若い頃は遊楽生活を送ったが 20歳で狂言作者五世鶴屋南北に師事 はじめ二世河竹新七の名を継いだ 天保14年(1843)江戸三座が浅草猿若町に移転し終ると間もなく黙阿弥も芝からこの浅草の正智院の地内に居を移し 四世市川小団次に多くの新作世話物を書いた 明治維新後は九世市川団十郎 五世尾上菊五郎 初代市川左団次のために世話物 時代物のほか舞踏劇などを執筆した 明治14年(1881)古河黙阿弥と改名し その後も劇作を続けた 作者生活50年 著作は350余編 江戸歌舞伎後半期の第一人者の地位にあり 特に 世話物を得意とした その音楽的効果や味わいは黙阿弥調として知られる代表作には「青砥稿花紅彩絵(あおとぞうしはなのにしきえ)(白浪五人男)」のほか「三人吉三廓初買(さんにんきちくるわのはつかい)(三人吉三)」 「天衣紛上野初花(くもにまごううえののはつはな)(河内山)」などがある 明治26年(1893)1月歿 78歳 昭和43年(1968)10月 東京百年を記念し建立する 東京都台東区長 上條貢」 「花塚碑」。 「花塚碑「濁流」の花道の師、笠翁斉乱鳥の死を悲しんだ弟子たちによって建てられた。笠翁斉乱鳥は、享和3年(1803)7月晦日死去。享年88歳。浅草本然寺(曹洞宗、現西浅草3-25-3)に埋葬。悲しんだ弟子たちが、瓶に花を挿したが、衰える花を惜んで地中に埋め塚とした。戦後、昭和31年(1956)観音堂裏手東北より移転。 建碑 文化元年(1804)3月17日「かめに花を挿こと古しへより聞え来れるを近き代には其花をさすにのろ有事と成り其流くさくさに分れぬ。笠翁斉乱鳥其わざを好てこの大城のもとに濁流としなへて弟子あまた有き。こその文月つごもり、齢八十餘八にてみまかり給。浅草本然禅寺に葬ぬ。ことし3月17日、かの翁の親しき友垣に弟子の集りて、かめに花をさして手向つ。其花のなごりを空しくなさむ事を惜み、はた翁の名の朽さらん事をおもひて、浅草寺の大ひさのみ堂のうしろ清らなる所を撰て其花を埋めて花塚と名付て後の世に残しなんとす。彼弟子の中、平石氏乱雨翁え残されしほほに笠翁斉の名を残したれば人々共に計りて其事成ぬ其わきかいつけよとこはるるにいなひあへずして記つ。 「文化元年七月千蔭」 浅草観光連盟」 「江戸・東京の農業 檜前(ひのくま)の馬牧(うままき)大宝元年(701)、大宝律令で厩牧令が出され、全国に国営の牛馬を育てる牧場(官牧)が39ヶ所と、皇室に馬を供給するため、天皇の命により32ヶ所の牧場(勅旨牧)が設置されました。東京には「檜前の馬牧」「浮嶋の牛牧」「神崎の牛牧」が置かれたと記録にあって「檜前の馬牧」は、ここ浅草に置かれたのではないかと考えられています。浅草神社の祭神で、浅草寺本尊の発見者である、檜前浜成、竹成兄弟の説話から、檜前牧は浅草付近であったと「東京市史稿」では推定していて、「浮嶋の牛牧」は本所に、「神崎の牛牧」は牛込に置かれたとされています。時代は変わり江戸時代、徳川綱吉の逝去で「生類憐みの令」が解かれたり、ペーリー来航で「鎖国令」が解けた事などから、江戸に欧米の文化が流れ込み、牛乳の需要が増え、明治19年の東京府牛乳搾取販売業組合の資料によると、浅草区の永住町、小島町、森下町、馬道と、浅草でもたくさんの乳牛が飼われるようになりました。 平成9年度JA東京グループ 農業協同組合法執行五十周年記念事業」」 「初代 中村吉右衛門 句碑「女房も 同じ氏子や 除夜詣」 吉右衛門」。 「初代 中村吉右衛門 句碑「女房も 同じ氏子や 除夜詣」 吉右衛門建碑 昭和ニ十八年四月ニ十一日初代 中村吉右衛門 歌舞伎俳優 日本芸術院会員 文化勲章受賞明治十九年三月ニ十四日 浅草象潟町に生まれ 幼少から舞台に立って名声を得 長じて大成し大正・昭和期を代表する歌舞伎俳優となった。高浜虚子に師事して「ホトトギス」の同人となり 句集も三冊に及ぶ 初め秀山と号したが 後に吉右衛門の名前を用いた妻千代もまた浅草の生まれ この句の由縁である 昭和十四年冬の作 この碑は自詠自筆である 実名 波野辰次郎昭和ニ十九年九月五日没 享年六十八 浅草観光連盟」 「扇塚」碑。 「古扇 納め箱」 扇塚は使い終わった扇を供養する塚である。 「古扇 納め箱わたくし達日本舞踊を志すものにとりまして扇は欠くことの出来ない品でございます。使い古された扇はどうぞこの箱にお納め下さい。毎年四月八日にご祈祷の上、扇に感謝のご供養を致します。 花柳流花柳会」「初代 花柳壽輔句碑」。「雷は 田町をよけて 鳴りわたる」 「初代 花柳壽輔 略傳出生 文化4年2月19日、芝・新明にて出生6才 文政9年、四世西川扇藏の許に入門し舞踊修業の道に入る。8才 文政11年、七世市川団十郎の鑑識に叶い市川鯉吉の芸名にて舞台を踏む。19才 天保10年(1839)、旧師西川扇藏の許に復帰し、西川芳次郎として振袖師の第一歩を 踏み出す。25才 吉原の玉屋小三郎より俳号の「花柳」なるの二字を与えられ、以後花柳芳次郎と稱す。 爾後、七世市川団十郎が嘉永2年(1849)、当時市川海老藏を名乗り、その俳名「寿海」に 因みて「壽」の字を贈られ、29才にして初めて花柳壽助を名乗り、後に「助」を「輔」に改め、 と共に、諸流に冠絶して振付の第一人者として謳はれる事、実に半世紀。その作品は 一千五百種を超え、就中「土蜘」 「茨木」「戻橋」「舟辯慶」の如きは不滅の傑作と 讃られる。83才 明治36年(1903)1月28日、花柳流の祖としての偉業を樹て、門弟、縁者に見守られ 其の生涯を終わる。 浅草観光連盟」 「手水舎」。「手水舎」には水を吐く龍が3匹。裏側に廻り込んで。水を吐く龍に近づいて。「文化財愛護 重要文化財 浅草神社(三社様)」。 狛犬越しに社殿を。「浅草神社台東区浅草二丁目三番明治初年の文書によると、祭神は土師真中知命・桧前浜成命・桧前竹成命・東照宮である。浜成と竹成は隅田川で漁猟中、浅草寺本尊の観音像を網で拾い上げた人物、真中知はその像の奉安者といわれている。三神を祀る神社なので、「三社様」と呼ばれた。しかし鎮座年代は不詳。東照宮は権現様すなわち徳川家康のことで、慶安二年(一六四九)に合祀された。以来、三社大権現といい、明治元年(一八六八)三社明神、同六年浅草神社と改称した。現在の社殿は、慶安二年十二月、徳川家光が再建したもの。建築様式は、本殿と拝殿との間に「石の間」(幣殿・相の間ともいう)を設け、屋根の棟数が多いことを特徴とする権現造。この社殿は江戸時代初期の代表的権現造として評価が高く、国の重要文化財に指定されている。毎年五月に行われる例祭は「三社祭」の名で知られ、都指定無形民俗文化財「びんざさら」の奉演、百体近い町神輿の渡御があって、人々が群集し、賑やかである。 平成六年三月 台東区教育委員会」」 社殿(拝殿・本殿)前の狛犬(右)。社殿(拝殿・本殿)前の狛犬(左)。「おみくじ処」、その奥に「絵馬掛け所」。 様々な絵馬が。「浅草神社社務所」。 「浅草神社神輿庫」。 三基の神輿が置かれていた。「浅草神社」(通称三社さま)には、このため、三基のお神輿があります。三社祭では、この三基に其々「土師中知」「檜隈浜成」「檜隈武成」がお乗りになるとし、町内神輿とは別格にして「宮神輿」と呼びます。一番大きな鳳凰の飾りがついているのが「土師中知」の「一之宮」疑宝珠(ぎぼし)が「檜隈兄弟」のそれぞれ「二之宮」「三之宮」です。一之宮神輿(中央)高さ:1,770mm幅:1,850mm鳳凰の高さ 660mm台輪 :1,080mm(三尺六寸)総高さ:2,430mm本体重:622.2Kg担ぎ棒総重量 404.0Kg二之宮神輿(右)高さ:1,780mm幅:1,850mm疑宝珠の高さ:540mm台輪 :1,080mm(三尺六寸)総高さ:2,320mm本体重:585.2Kg担ぎ棒総重量:424.0Kg三之宮神輿(左)高さ:1,780mm幅:1,850mm疑宝珠の高さ:540mm台輪 :1,080mm(三尺六寸)総高さ:2,320mm本体重:585.2Kg担ぎ棒総重量:424.0Kg「浅草神社【宮神輿】一之宮・ニ之宮が昭和ニ十五年に、三之宮が昭和ニ十八年に氏子により奉納されたもので、胴が細く屋根四隅の大きい造りとなっており、一之宮の頭には鳳凰が、ニ之嘗・三之宮には擬宝珠が飾られています。一之宮に上師真中知命(はじのまなからのみこと)ニ之宮に檜前浜成命(ひのくまのはまなりのみこと)三之宮に檜前武成命(ひのくまのたけなりのみこと)三柱の御祭神がそれぞれに遷座いたします。」 浅草寺本尊御示現【宮神輿「堂上げ・堂下げ」】三月十七日(堂上げ)・十八日(堂下げ)昔の祭礼である古儀の一部を現代に復元させようと、三基の宮神興にお移りになった三柱の御祭神(三社様)が浅草寺本堂に籠られ、聖観世音菩強(観音様)と一晩をお過ごしになる「堂上げ・堂下げ」の神事が、平成十ニ年三月の御縁日に浅草寺の仏事「浅草寺本尊示現会」を慶賀し、氏子の手により再現・斎行されています。その後も、本堂の修復等で唐櫃による移御の年もありましたが、浅草誕生の歴史を内外に広めるべく、また浅草の町の更なる隆盛を願い、神仏習合の名残りを吉例として毎年恙なく斎行されています。浅神社例大祭【三社祭】五月第三週の金・土・日曜日「三社祭」は毎年五月に行われる浅草神社の祭礼で、氏子四十四ヶ町と浅草組合で構成される浅草神社奉賛会により運営されています。江戸下町の風情を残した勇壮で華やかなお祭りで、町会毎に揃いの半纏をまとった勇ましい担ぎ手達が、戚勢良く御神輿を担ぎ、浅草の町全体を練り歩きます。初日の金曜日は、お囃子屋台・金棒・鳶頭木遣り・総代・各町役員・びんざさら舞・芸妓連の手古舞・組おどり・白鷺の舞・屋台で編成された「大行列」が浅草の町を歩きます。また、浅草神社の社殿と神楽殿で、東京都無形文化財に指定されている「びんざさら舞」の奉納が行われます。中日の土曜日には、「例大祭式典」のあと、正午より「町内神與連合渡御」が行われます。浅草氏子四十四ケ町の町内神輿壱百基が浅草寺裏広場に参集、一基ずつ発進し、浅草神社でお祓いを受けた上で各町会に渡御します。始まります。その後、宮神輿が各町会を渡御し、夕刻に浅草神社へ戻る「宮入り」となります。三日間で約ニ百万人の人出が見込まれる三社祭は、東京の初夏を代表する風物詩の一つになっています。※「三社」とは、浅草神社の旧称「三社権現社」からの呼び名。令和七年浅草神社例大祭「三社祭」五月十六日(金)・十七日(土)・十八日(日)」 「神輿庫」横には多くの提灯が並んでいた。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.05.23
コメント(0)
-

浅草を歩く(その11):浅草寺-8・二天門~浅草神社(1/3)
そして「浅草神社」の前を通過し、まずは浅草寺・「二天門」へと進む。今日のブログに前回訪ねた時と重複する場所が多数あります。浅草寺本堂の東に建つ朱塗りの鮮やかな「二天門」。当初は、境内にあった東照宮の随身門として建てられたと伝えられている。随身門とは、神社を守護する神さまを配置した門のこと。当時は、神道の神さまである豊岩間戸命(とよいわまどのみこと)と櫛岩間戸命(くしいわまどのみこと)の守護神像が左右に祀られていた。しかし、1868年(明治元年)に明治政府が発令した神仏分離令により、仏教寺院である浅草寺には、この2柱の神さまの像を祀ることができなくなった。そこで、浅草寺はこの2柱の像を浅草神社に遷座し、代わりに鎌倉の鶴岡八幡宮にあった仏教の守護神である広目天(こうもくてん)と持国天(じこくてん)の像を二天門に安置。これに伴い、正式名称が随身門から二天門に変更された と。その後、第二次世界大戦により2柱の像は焼失。現在は、上野の寛永寺(かんえいじ)の四代将軍徳川家綱霊廟にあった持国天と増長天(ぞうちょうてん)の像が祀られている。持国天と増長天は、四天王と呼ばれる仏さまとして知られているが、四天王は仏教の守護神であることから武装した姿。どちらも、鎌倉時代以降に流行した複数の木材を組み合わせる技法「寄木造」により造られているとのこと。「現在地」 はここ。「二天門」を潜り、「二天門前」交差点、その先の「隅田川」方向を見る。 そして再び「二天門」を境外から。 本瓦葺 切妻造り木造朱塗り八脚門。「二天門」前の右側にあったのが歴史のある「手水鉢」。 近づいて。正面から。「手水鉢 江戸時代 安永六年(一七七七)「手水鉢」とは、社寺の参拝前に手を清めるために置かれる鉢のことである。鉢の側面には「安永六年(一七七七)に観世音千百五十年法会供養の日に臨時連中によって寄附された」あり、推古三十六年(六二八)のご本尊さまご示現から数えて一一五〇年を祝う記念法会のために明和六年(一七六九)に設置れた浅草寺の消防組織である「臨時連中」によて献じられたと推定できる。また銘文に「随身門前」とあり、文化一〇年(一八一三)に編纂された「浅草寺志」にも「裏門の外」と記されていることから、場所を変えずに今に至ると判明する。現在は使われていないが、江戸時代の多くの人々がここで手を清め、観音さまや三社さまにお参りをされたことであろう。」 扁額「二天門」。 「増長天」。増長天は、右手に法具を掲げ、左手は腰にあてる。「持国天」。持国天は、増長天と対称的な姿勢を取り、左手を上げて密教法具を持ち、右手を腰にあてる姿勢を取る。いずれも江戸時代前期・吉田兵部藤房作・都重宝。元来は全身に華やかな彩色が施されており、今でも顔や鎧(よろい)に古来の鮮やかさが残されている。どちらも「寄木造(よせぎづくり)」という、鎌倉時代以降に流行した複数の木材を組み合わせる技術で造られている。「二天門〔にてんもん〕(重要文化財) 台東区浅草二丁目三番この二天門は、慶安二年(一六四九)頃に浅草の東門して建されたようであるか、江戸時代を通じて浅草寺観音堂の西側に建てられた東照宮の随身門と伝えられ、随身像が安置されていた。なお、浅草寺の東照宮は元和四年(一六・八)に建立されたが、寛永八年(一六三一)と同十九年の火災によって、浅草寺の他の諸堂とともに焼失し、その後東照宮は江戸城内の紅葉山に移された。明治初年の神仏分離令によって門に安置された随身像は、仏教を守護する四天王のうち持国天・増長天の二天像に変わり、名称も、二天門と改称した。現在安置されている二天像は、京都七条の仏師、吉田兵部が江戸時代初期(十七世紀後半)に制作したもので(東京都指定有形文化財)、昭和三十二年に寛永寺の厳有院殿(四代将軍徳川家綱)霊廟の勅使門から移されたものである。二天門は昭和二十五年、国指定重要文化財に指定された。 平成二十三年三月 台東区教育委員会」 そして「浅草神社」入口まで戻る。「石鳥居神社において神域と人間が住む俗界の境界を表し、境内への入口を示すもの。この鳥居は「神明鳥居」と呼ばれる形で、明治18年9月に建立されたもの。その傍らの「社号標石」は、神宮大宮佐佐木行忠候に揮毫された。」 「祭事歴」👈️リンク 「御祈祷」👈️リンク 「教化活動」👈️リンク 「浅草神社」の石鳥居を潜り境内へ。正面に拝殿。「配置案内図」。 鳥居をくぐり、本殿へ向かう参道から右手をみると、庭のようになっている一角に様々な石碑群があった。その中にいらっしゃるのが「夫婦狛犬」。お参りに来られる方の喧噪から少し離れた場所にあるので、狛犬好きの先輩たちからは「隠居狛犬」さんと呼ばれていると。参道から隠居しても、こちらの狛犬は、赤い唐傘の下で大活躍中!にっこりと笑って寄り添っている姿から「良縁」「夫婦和合」「恋愛成就」のご利益があるといわれている と。近づいて。「川口松太郎句碑」。「生きると いうこと 難しき夜寒かな」。 「川口松太郎 句碑川口松太郎ハ明治三十二年十月一日浅草今戸ニ生レル 昭和十年第一回直木賞受賞ノ「鶴八鶴次郎」ヲ初メトシテ小説脚本ニ名作多ク文壇劇壇ニ多大ナ足跡ヲシルス 特ニ新派俳優花柳章太郎水谷八重子等ニョッテ演ジラレタ情緒豊カナ諸作品ハ観客ヲ魅了ス這般ノ功績ニヨリ三十八年菊池寛受賞 四十年芸術院会員更ニ四十四年「しぐれ茶屋おりく」ノ一篇ニヨリ吉川英治文学賞受賞 四十八年文化功労者ニ叙セラレル 最晩年渾身ノ筆デ連載小説「一休さんの門」ヲ脱稿後昭和六十年六月九日永眠ス 行年八十五才 三回忌ニ因ミ故人ノ終世ノ師久保田万太郎ノ傍ラニ同ジク句碑ヲ建テテ逝者ヲ偲ブ 生きると いうこと むずかしき 夜寒かな昭和六十二年六月九日松竹株式会社 文芸春秋社劇団新派 講談社明治座 読売新聞社 浅草観光連盟」 こちらは「久保田万太郎句碑竹馬や いろはにほへと ちりぢりに」 特徴ある四角いデザインの句碑。久保田万太郎句碑は昭和四十年(1965)建立。 久保田万太郎は明治22年(1887)11月7日此地に生まれ、市立浅草尋常小学校へ入学、府立三中に学び大正3年(1914)慶應技術大学文科を卒業し、10月移転する迄の26年間浅草に在住した。 昭和38年(1963)5月6日永眠するまでの明治・大正・昭和の三代に亘り、常に下町の義理と人情を描写した小説、戯曲の作品多く、其他文学、演劇界に多大の功績を残した作家であった。裏に履歴が。「記 久保田万太郎ハ東京ノ人 明治二十二年十一月七日生レ 昭和四十八年五月六日二ワカニ逝ク 慶應義塾在學中年二十二ノトキ小説朝顔ノ一篇ニヨッテ文壇ニ知ラレテ以来五十年 小説戯曲及ビ俳句ニ名作多ク前ニ日本藝術院會員二選バレ 後ニ文化勲章ヲ授ケラレ 更ニ逝去ニ際シ従三位勲一等ニ叙セラレタノハソノ榮トスルトコロト察セラル 久保田ハ淺草ニ生レ淺草ニ人ト成ル 観世音周邊一帯ノ地ノ四時風物トソノ民俗人情ヲ描イタ大小ノ緒篇ハ日本文學ニ永ク淺草ヲ傳エルモノトイフベキデアロウ ココニ有志ノ者等相圖リ コノ地ヲトシ 句碑ヲ建テテ其人ヲ偲ブ時ニ昭和四十年十一月七日 小泉信三」 「粧(よそおい)太夫碑{蕋雲(ずいうん)女史書の柿本人麻呂(かきのもとのひとまろ)}歌碑 』 ほのぼのと 明石の浦の 朝霧に 島かくれゆく 船をしぞ思う「粧(よそおい)太夫碑{蕋雲(ずいうん)女史書の柿本人麻呂(かきのもとのひとまろ)}歌碑 』ほのぼのと 明石の浦の 朝霧に 島かくれゆく 船をしぞ思う有名な万葉歌人柿本人麻呂の和歌を万葉仮名で刻んだもので、骨太な文字を認めたのは、碑文にあるように蕋雲女史である。蕋雲は文化年間(一八○四~一七)、遊里新吉原の半松楼に抱えられていた遊女で、源氏名を粧太夫といい、蕋雲はその号である。粧太夫として当時の錦絵にも描かれており、書を中井敬義に学び、和歌もたしなむ教養ある女性で、江戸時代の代表的な文人、亀田鵬斎から蕋雲の号を贈られたほどの人物であった。この歌碑は、人麻呂を慕う太夫が、文化十三年(一八一六)八月、人丸社に献納したものである。人丸社は幕末の絵図によると、三社権現(現在の浅草神社)の裏手にあったが、明治維新後に廃され、碑のみが被官稲荷社のかたわらに移され、昭和二十九年十一月、現在地に移された。 平成八年三月 台東区教育委員会」 意味・・ほんのりと明るんでいく明石の浦、その明石の浦に立ち込める朝霧の中を、島隠れに 行く舟をしみじみと感慨深く眺めることだ。 ほのぼのと明け行く明石の浦の朝霧の中をぼっとかすみ、やがて点景となって消えてゆく 舟に、危険の多い航路、旅に伴う不安を想いやり無事を祈る作者の心を詠んでいます。石碑の裏には「松竹株式会社 文藝春秋社劇団新派 講談社明治座 読売新聞社浅草観光連盟昭和六十二年六月九日 建之設計 中嶋八郎」と。振り返って。「タマリュウ庭園第20回浅草神社体験学習祈念植栽令和5年8月24・25・26日」 そして「初代 市川猿翁句碑」。 おにぎり型の大きな石碑があって、中に正方形の黒い石がうめてあり、家紋と文字が刻まれていた。初代市川猿翁は1888年(明治21年)の生まれだそうなので、そこまで昔の人ではないようです。1963年に二代目市川猿之助を襲名し、初代猿翁になりました。俳優・香川照之の祖父にあたる人物。浅草神社境内の句碑の類の年代の幅広さに感銘。 碑には「翁の文字 まだ身にそはず 衣がへ」と。屋号は澤瀉屋(おもだかや)。初代市川猿之助の生家が副業として薬草の澤瀉(おもだか:アジアの沼などに生息する多年草。根茎を乾燥させて漢方薬などにする)を扱う薬屋であったことが、この屋号の由来。定紋は澤瀉、替紋は三つ猿。「市川猿之助」の名跡を譲った者が名乗る隠居名となっている と。澤瀉紋は、「勝軍草」(かちいくさぐさ)の異名を持つため、平安時代から武人を中心に用いられました。毛利元就(もうりもとなり)や水野忠邦(みずのただくに)らが用いたことでも知られている と。「翁の文字 まだ身にそはず 衣がへ」。家紋に近づいて。定紋は澤瀉(左)、替紋は三つ猿(右)。「翁の文字 まだ身にそはず 衣がえ 猿翁建碑 昭和42年(1967)5月17日撰文 市川猿翁孫団子に三代目猿之助を譲り、自らは猿翁を襲名。昭和38年(1963)5月、歌舞伎座に於て襲名興行。(浅草寺の襲名お練りは4月16日)『猿翁』(昭和39年(1964)6月東京書房刊)には、「翁の文字まだ身にそはず 衣がへ 猿翁 昭和37年(1962)5月 猿翁襲名のとき」とある。明治21年(1888)5月10日、浅草千束町2丁目に生れる。父、喜熨斗亀次郎(初代市川猿之助ー段四郎)、母古登の長男。(弟妹は十人)兵役を終えたのち明治43年(1930)10月(22才)で二代目市川猿之助を襲名。昭和38年(1963)6月聖路加病院(心不全)にて死去。享年75才。昭和36年(1961)3月28日浅草3丁目39番地に生家に因みて「猿之助横丁碑」を建てる。 浅草観光連盟」 「百度石」。百度石(ひゃくどいし)とは、神社仏閣の境内で、一定の距離を100回往復して参拝する際、距離の目安となる石柱のこと。100回参拝することで神仏の加護を願う習俗で、願いが叶った時には千度参りをするのが基本である と。 「友情は いつも宝物」碑。昭和51年(1976)に「週刊少年ジャンプ」で連載を開始して以来、多くの人々に愛されてきた「こちら葛飾区亀有公園前派出所」。物語の舞台となるここ浅草は主人公である両津勘吉を育み、また多くの感動を生み出してきました。この碑は、両津勘吉の少年時代の友情を描いた「浅草物語」にちなみ、人を思いやる気持ちの大切さ、そして子供たちが夢や遊び心を忘れず健全に成長してくれるよう願いを込めて建てられました。 平成17年(2005)8月6日 建立< 「浅草物語」概略 >ある日、浅草で一緒に遊んだ同級生が偶然再会。かつての悪ガキ両津勘吉は警察官に、かつての優等は、逃亡犯になっていました。両津は、子供の頃にここ浅草神社(三社様)の神木、槐(えんじゅ)の木の下に一緒に埋めたベーゴマの話を持ち出して二人の友情を確かめ合いました。そして、逃亡犯は自首することになったのです。ジャンプ・コミックス「こちら葛飾区亀有公園前派出所」57巻「浅草物語の巻」より < 「こちら葛飾区亀有公園前派出所」 >作者 秋本治連載開始 1976年週刊少年ジャンプ(集英社) < 両津勘吉 >職業 警察官(巡査長)誕生日 3月3日出身地 東京都台東区千束身長 約162cm体重 約71kg特技 自転車乗り 「槐(えんじゅ)の木の下に一緒に埋めたベーゴマ」の絵。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.05.22
コメント(0)
-

浅草を歩く(その10):浅草寺-7・鳩ポッポの歌碑~旧仁王門礎石~お水舎~常香炉~天水桶~本堂内陣
次に訪ねたのが「鳩ポッポの歌碑」。昭和37年(1962)に作詞の舞台となった浅草寺本堂の西側に建立された。童謡「鳩ポッポ」は、作詞家である東くめ女史が、浅草寺の境内にて鳩と戯れている子供たちをみてこの歌詞を書き、滝蓮太郎により作曲されたのだと。「鳩ポッポ👈️リンク の歌碑作曲 瀧 廉太郎 作詞 東 くめ鳩ポッポ 東くめ 八十六才はとポッポ はとポッポ ポッポッポと とんでこい御寺のやねから下りてこい えさをやるから皆たべよ食へてもすにかえらずに ポッポッポと鳴いて遊べ この詩は日本中の多くの人々に親しまれている日本の代表的な童謡の一つです東くめ女史が明治34年(1901)に観音さまの境内に於て鳩とたわむれている子供らの愛らしい姿をそのまま歌によまれたものであります 歌碑を建つるにあたりまして朝倉文夫先生から鳩並に題字を寄せられましたくめは作曲者滝廉太郎先生と同郷旧知の源いゆかりに依る洵にうるわしい御協賛でありました 鳩は平和の象徴です そのためにもこの碑は永久に保存いたしたいものであります 昭和37年(1962)11月3日 浅草古恭順識」 「♪ぽっぽっぽ、鳩ぽっぽ……」という歌い出しの童謡『鳩』とは異なる曲である。なお、そちらは作者不詳とされている と。鳩の姿も。「旧仁王門礎石」。 「旧仁王門礎石この大きな石(本小松石)は、慶安二年(一六四九)に第三代将軍・徳川家光公の寄進により建された、仁王門仁王門の礎石の一つである。惜しくも仁王門は、昭和二十年(一九四五)の東京大空襲で焼失してしまったが、同三十九年(一九六四)に宝蔵門として再建された。 金龍山 浅草寺」 そして「お水舎(おみずや)」を参道側から。 廻り込んで。龍神像(沙竭羅龍王像)を横から。明治36年(1903)8月奉安、高村 光雲 作以前、本堂裏にあった噴水に安置されていた像である。仏法を守護する龍王の1人。龍や龍神は、水をつかさどる神。天井には「墨絵の龍」(東 韶光 画)。昭和39年(1964)4月奉安。ズームして。廻り込んで。龍の吐水口(とすいこう)をズームして。先端には、ビニールホースが取り付けられていた。出口からは浄めの清水が。そして常香炉。常香炉とは、一般的に銅製や石製で、大きく装飾された器具。香炉自体には香を焚くための容器があり、その下には煙や灰がたまるための底部があります。香炉のデザインや装飾は寺院の伝統や信仰に基づいており、美しい彫刻や細部の装飾が施されているのだ。廻り込んで。香炉は、戦国時代末期(約400年前)に中国から伝わり、当初は祭祀や宗教儀式における香りを神に捧げるために使われていた。後に、仏教の伝来とともに寺院や仏教の修行者によって使用されるようになったと。長い時を経て「香炉の煙を体の悪いところにかけると治りが良くなる」という言い伝えが広まりそのような経緯から、今では参拝者が香炉の周りに集まるようになった。香炉の周りで人々をしばらく観察していると、頭に煙を当てる人が沢山いることに気がつく。頭に煙をかけると「頭をよくする、賢くなる」という言い伝えがあるそうで、頭に煙をたくさんかける参拝客が大勢いるんだとか。浅草寺は日本の伝統的な寺院文化を体験するのに最適な場所であり、インバウンドにとって必見のスポットなのである。この日は、早朝のため、人も煙も少なかった。「本堂」正面を見る。 巨大な「天水桶」が右側に。昭和33年10月に「魚がし」の講で奉納されたもので、何回か修理を重ねて、今日に至っている。もう半世紀以上前のものと。正面から見ると、いたるところに「丸魚がし」と「魚市場」の印型が表現されていた。装飾的な意味合いが強く、実用品では無くなっているようだ。正面の「魚がし」は、築地の「浜のや」、小林繁三氏の書で、提燈屋さんらしい江戸文字が書かれているのであった。波柄の青海波(せいがいは)の模様が描かれ、金の装飾もあしらわれた豪華な「天水桶」。 左隣にも。製作は鋳物産地として有名な東京近郊の埼玉県川口市の鋳物師 と。横から五重塔を背景に。「志ん橋」と書かれた大提灯の先に本堂の扁額「観音堂」。 階段を上がり、隅から「お水舎」方向を振り返る。 大提灯を横から。「卍」の文字が。 「本堂」内の「お札申込所」。 「本堂(観音堂)昭和三十三年、全国ご信徒のお力添えにより再建。お堂は南に面し、正面に懸かる「志ん橋」と書かれた大提灯は、東京新橋組合から奉納されたもの。外陣には、天上中央に川端龍子画の「龍の図」が、左右には堂本印象画の「天人の図」が掲げられ、正面には深見玄岱筆「施無畏」額が懸かる。内陣には、中央の御宮殿内に、ご本尊聖観音菩薩さま、慈覚大師円仁作のご秘仏お前立ちご本尊聖観世音菩薩様が奉安されている。また、御宮殿の正面左に梵天・右に帝釈天の二天が、内陣左奥に愛染明王、右奥に不動明王が祀られる。御本尊 聖観世音菩薩 観音さまは、人々の苦しみを見てはその苦しみを除き、願いを聞いては楽を与えてくださいます。特に浅草寺ご本尊のご利益・ご霊験は古今無双であり、ご示現より今日まで千四百年近くにわたり計り知れぬほどの人々を救われご加護なさってきました。観音さまのご信仰とは、観音さまに「慈悲(あたたかい心)」を頂き、その「あたたかい心」で日々を過ごすことと申せましょう。※)ご参拝の際には合掌して「南無観世音菩薩」とお唱えしましよう。」 そして、この日も美しい天井画をカメラで追う。浅草寺本堂外陣の天井画も見どころのひとつ。龍に寄り添うように、左右には堂本印象(どうもといんしょう)作の『天人之図』(右)。川端龍子(かわばたりゅうし)作の『龍之図』。共に6.4m×4.9mの大作。」と。堂本印象(どうもといんしょう)作の『天人之図』(左)。「聖観音宗総本山金龍山 浅草寺(せんそうじ・あさくさかんのん)推古天皇三十六年(六二八)三月十八日、檜前浜成・竹成の兄弟が隅田川に漁撈中、観音さまのご尊像を感得した。土師中知はこれを拝し、聖観世音菩薩さまであることを知り深く帰依し、礼拝供養に生涯を捧げた。大化元年(六四五)、勝海上人がこの地においでになり、夢告によりご本尊をご秘仏と定められた。平安初期には、慈覚大師円仁さまが来山され、お前立のご本尊を謹刻された。鎌倉時代に将軍の篤い帰依を受けた浅草寺は、江戸時にに徳川家康公によって幕府の祈願所とされ、堂塔の威容さらに整い、いわゆる江戸文化の中心として大きく繁栄した。かくして都内最古の寺院である浅草寺は、浅草観音の名称で全国的にあらゆる階層の人たちに親しまれ、年間約三千万人もの参詣者がおとずれる民衆信仰の中心地となっている。」再び天井画の全体を。「本堂」の「正面額」には「施無畏(せむい)」と。高さ 約1.35m・幅 約4m、重さ 約700kg、欅製豊道春海原書 南部白雲工房作〔令和2年(2020)6月奉納〕観音さまは経典において、「施無畏者」とも呼ばれ、人々の不安や恐怖を取り除き、「畏れ無きを施して」下さる。「施無畏」とは、観音さまのおはたらきそのものを意味する と。そして本堂奥には「御宮殿」。「施無畏(せむい)」と。仏さまが人々に「恐れなくていいよ」と安心を与えてくださることを「施無畏」と言う と。物をあげる「布施(ふせ)」の中でも、一番深い心の助けとされているのだと。扁額「施無畏(せむい)」の右側の彫刻。扁額「施無畏(せむい)」の左側の彫刻。外陣の聯(れん)。「仏身円満無背相 十方来人皆対面」誰でも、どこから来た人でも分け隔てなく救いの手を差し伸べてくださる、という意味(浅草寺のご本尊観音さまのことを表す)。「御宮殿」。ご本尊である聖観世音菩薩を安置している場所。御本尊の聖観音菩薩が安置されている金箔のお宮。開基の勝海上人が秘仏と定めて以降、誰も見たことが無い絶対秘仏。つまり観音像を網で掬い揚げた、檜前浜成(ひのくまはまなり)・檜前竹成(ひのくまたけなり)兄弟と、その像を本尊として寺を草庵した土師真中土(はじのあたいなかとも/はじのまつち)と、勝海上人の四名のみが御本尊の実像を知っているということになる。そもそもこの四名の実像を知っている人もまた、歴史上いないので、創建自体がミステリー。毎年12月13日に、御宮殿の幕が開かれ、御前立を拝見することができる。また内陣には御宮殿以外に愛染明王と不動明王が安置され、御宮殿の間裏には御本尊と同じ姿をしたと伝わる観音像(裏観音)が安置されているとのこと。本堂内奥の脇侍。右:不動明王。お姿は見えなかったが。左:愛染明王。お姿は見えなかったが。カーン・不動明王の梵字。サ・観音菩薩の梵字。ウーン・馬頭観音の梵字。燭台。「御札 御守」が並ぶ。 そして本堂横の出口から「浅草神社」の横に並ぶ提灯を見る。「浅草神社」方向に向かいながら「五重塔」方向を振り返る。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.05.21
コメント(0)
-

浅草を歩く(その9):浅草寺-6・平和地蔵尊~久米平内堂~大行院・浅草不動尊~宝蔵門~神木~迷子のしるべ石
「宝蔵門」への参道の右側にあったのが「戦災者供養 平和地蔵尊」。東京大空襲で亡くなりなった御霊がお祀りされている と。 「平和地蔵尊由来記第二次世界大戰はその規模においても その被害についてもまことに甚大であった ことに昭和二十年三月十日の大空襲には この附近一帯は横死者の屍が累として山をなし その血潮は川となって流れた その惨状はこの世の姿ではない これ等の戦争犠牲者の霊を慰めることこそ 世界平和建設の基となるものである ここに平和地蔵尊を祭り その悲願を祈るため 昭和二十四年四月こゝに安置された次第である」 建立者の龍郷定雄翁像。建立年 昭和24年4月 と。平和地蔵を、私財を投じて奉納した龍郷定雄の胸像。築地市場の関係者だったようだ。この龍郷像を作った立川金禄は埼玉県白岡市出身の仏師。白岡市を中心に、埼玉県各地に仏像やブロンズが残っている。日展では「シャモ」を題材に入選を果たしている と。そしてその隣、本堂側・左側にあったのが「久米平内堂(くめのへいないどう)」。 久米平内(くめのへいない)をまつる平内堂は、浅草の縁結びの神様として知られています。仲見世通りの突き当たり、宝蔵門手前、右側にある平内堂には、今日でも縁結びを願う若い人が参拝する姿が見られます。この平内堂は江戸時代に建立され、昭和20年の空襲で焼失したものを、昭和54年に再建したもので、中には小さな石像がまつられています。この石像が平内様です。久米平内は講談で語られるなどフィクションも重なって、実際の人物については謎が多く残されています。例えば、座禅を組んでいる自分の像を平内自身が彫らせたという説。これは、平内が首切り役人とか、刀の試し切りや辻斬りをした浪人だったとかで、死んでから少しでも罪が軽くなるように「大勢の人に踏みつけてほしい」と願ったと言うもの。また、平内が教えていた「仁王座禅の法」の看板がわりのものだったという説もあり、今でいう体操教室かフィットネスクラブの先生であった平内が、生徒募集のためのユニークな看板と作ったと言ったところでしょうか。平内の石像がお堂の中に収まって「平内堂」となったのは、実在の平内が亡くなった後のことと ネットから。「久米平内堂」に近づいて。「久米平内堂 台東区浅草二丁目三番一号 浅草寺久米平内は江戸時代前期の武士。『武江年表』によると、天和三年(一六八三)に没したとされるが、その生涯については諸説あり、実像は明らかではない。平内堂には次のような伝承がある。平内は剣術に秀でており、多くの人をあやめてきた。後年、その供養のために、仁王坐神の法を修行し、浅草寺内の金剛院に住んで禅に打ちこんだという。臨終にのぞみ自らの姿を石に刻ませ、多くの人々に踏んでもらうことによって、犯した罪を償うために、この像を人通りの多い仁王門付近に理めたと伝える。その後、「石像」はお堂に納められたという。「踏付け」が「文付け」に転じ、願文をお堂に納めると願い事が叶うとされ、江戸時代中期以降、とくに縁結びの神として庶民の信仰を集めた。平内道は昭和二十年三月の戦災で消失した。現在のお堂は、同五十三年十月に浅草寺開創千三百五十年記念として再建されたものである。平成十八年三月 台東区教育委員会」「久米平内堂 縁結び絵馬奉納箱」。 「久米平内堂」の正面扉の見事な彫刻。廻り込んで。「久米平内像」👈️リンク をネットから。 「久米平内堂」前から、「宝蔵門」、「五重塔」を見る。 この木も、何か由来があるのだろうか?そして参道の左側にあったのが「大行院・浅草不動尊」。浅草寺の宝蔵門手前に鎮座。浅草寺の境内ですが別のお寺になるのだと。右後ろに見えるのは浅草寺の五重塔。関東三十六不動霊場の二十二番目のお寺だそうだ。「三宝荒神堂」。 正面に「なでぼとけ」。 近づいて。「三宝荒神堂浅草不動尊大行院が戦前にお祀りしていた三宝荒神堂は、明治六年五月に谷中の金嶺寺様のより勧請した御像であり、多くのご参拝者の皆様から「金山三宝荒神」として親しまれていた。 当時の金山三宝荒神は病苦厄難を退け開運繁栄をもたらすとして、金物に関する信仰のみならず諸願成就の信仰をも集めるようになった。惜しくも当院はこの御像と堂宇を昭和二十年の東京大空襲によって焼失したが、それまでの信仰と歴史を大切に受け継ぎ、終戦の直後に再造された御像(秘仏)は仮堂に安置され、昭和五十年には金山堂を三宝荒神堂と改称し堂宇も再建された。当院の三宝荒神信仰においては鍛冶職の方からの信仰にとどまらず「かまどの仏様」という側面に強いことから、その御利益は「台所守護」と称され、長きにわたり日本全国のご家庭の台所や飲食店の調理場等に当院の三宝荒神御礼(御姿と御幣)が祀られ、親から子へ子から孫へと代々その信仰が受け継がれている。 浅草不動尊 大行院」 「浅草大行院」と。 「浅草不動尊 大行院宗派 天台宗(総本山 比叡山延暦寺)御本尊 不動明王当院は、江戸時代には浅草神社様の東側に位置し、「荒澤不動堂」の別当寺院として「専修院」と称していた。荒澤不動堂の御本尊であった不動明王像は、貞観元年(八五九年)に慈覚大師円仁様が日光の荒澤の滝に出現した尊容を刻した御像である。荒澤不動堂は安政の大地震(一八五五)により倒壊したため、御像は仮堂に安置された。その後、神仏分離れいなどにより明治三年正月にこの地(以前は西の宮稲荷があった地)に建立された不動堂に遷された。明治四年6月には、三御門室より大行院の稱號を賜り、専修院から大行院に改称した。改称後の初代住職は荒澤嚴息(日光山台林寺の嚴息の弟子)であった。当院は惜しくも昭和二十年の東京大空襲によりはぼ全てを消失したが、東叡山寛永寺様より不動明王像(秘仏)を勧請し御本尊として仮堂に遷座した後、昭和四九年八月に多くの方々のご尽力と復興への強い願いをもって再建された大行院本堂にお祀りした。現代では「浅草不動」として、開運・厄除・災難消除・当病平癒・身体健全・六算除👈️リンク・虫封じ・商売繁盛・家内安全・学業成就・心願成就・交通安全などの現世利益を願う皆様に親しまれている。」 「浅草不動尊」正面。そして再び「宝蔵門」まで戻り 「宝蔵門」前から大提灯を見る。仁王像(阿形)。仁王像(吽形)。「小舟町」と書かれた「大提灯」。高さ 3.75m・幅 2.7m、重さ 450kg。日本橋小舟町奉賛会より平成26年(2014)10月奉納掛け換え(4回目)。提灯下の彫刻。そして「浅草寺の神木・いちょう」。 「浅草寺の神木・いちょう浅草寺本堂東南に位置するこのいちょうは、源頼朝公が浅草寺参拝の折、挿した枝から発芽したと伝えられる。昭和五年に当時の文部省より天然記念物に指定されたが、昭和ニ十年三月十日の戦災で大半を焼失した。今は天然記念物の指定は取り消されたが、あの戦災をくくり抜けた神木として、今も多くの人々に慕われている。 金龍山 浅草寺」 神木に近づいて。大きな乳根(ちちね)が確認できた。記念撮影用パネルも前日の5月10日のままに。「五重塔」を見る。 そして「本堂」に向かう。人の数も多くなって来た。 浅草寺本堂の階段の西南手前に「迷子のしるべ石」。正面に「南無大慈悲 観世音菩薩」と刻む。「迷子しるべ石昔、迷子が出た時には、この石碑でその旨を知らせた。石碑の正面に「南無大慈悲観世音菩薩」と刻み、一方に「志らする方」、一方に「たづぬる方」とし、それぞれに用件を記した貼紙で情報を交換した。情報未発達の時代には重宝され、「江戸」市内の繁華な地に建てられたものの一つ。安政七年(一八六〇)三月、新吉原の松田屋嘉兵衛が、仁王門(現宝蔵門)前に造立したが、昭和二〇年の空襲で倒壊したため、昭和三十二年に再建された。 金龍山 浅草寺」 「志らする方」と。 「私のところに、このような迷子がいます。」という内容の紙を上部の四角い枠に貼り付けた。四角い枠の上には雨除けの庇の様な突起が在る。「まよひこのしるべ」と。 「たづぬる方」。 反対側の「たづぬる方」には、迷子になった子供の人相や特徴を書いた紙を貼りつけておきます。この紙をみて、迷子を探したわけです。裏面には「安政七年(一八六〇)庚申歳三月建、施主 新吉原 松田屋嘉兵衛」 と。これらが「迷子しらべ石」に刻まれているのは、安政の大地震で亡くなった新吉原の遊女の霊を慰める意味もあったからなのだと。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.05.20
コメント(0)
-

浅草を歩く(その8):仲見世通りシャッター壁画~伝法院通白浪五人男人形
「富士屋 江戸に花咲いた文化 浮世絵」。 同上「犬猫用品 足立屋 三社祭!?」 「小澤清次郎商店 (豆菓子・甘納豆) 三社祭???」。 「松ヶ枝屋 金龍の舞」。 「トヨタ靴店 三社祭」。 「雷おこし・寿々免堂 桜?」。 「??? 朧月」。 「人形焼 三鳩堂」は既に開店準備中であった。 「伝法院通り」。「東京スカイツリー」が姿を現した。 「白浪五人男」👈️リンク の等身大人形が屋根の上に。「浅草名代らーめん 与ろゐ屋」の屋根の上には「赤星十三郎」。「またその次に連なるは、以前は武家の中小姓、故主のために切取も、鈍き刃の腰越も、砥上ケ原に身の錆を、磨ぎ直しても、抜きかねる、盗み心の深緑、柳の都谷七郷、花水橋の切取から、今牛若と名も高く、忍ぶ姿も人の目に、月影ケ谷・神輿ケ嶽、今日ぞ命の明け方に、消ゆる間近き星月夜、其名も赤星十三郎~」と。移動して。「白浪五人男 赤星十三郎元々は武家のお小姓。その佇まいは両性的で年若く美しい顔立ち」。 「白浪五人男の内 赤星十三 中村翫雀」。この絵の上部にも「お馴染みの名台詞」が。そして道路の反対側・「大正ロマン館」の屋根の上には「弁天小僧菊之助」が。 「さて其の次は、江の島の岩本院の稚児あがり、ふだん着馴れし振袖から、髷(まげ)も島田に由比ケ浜、打ち込む浪にしっぽりと、女に化けた美人局(つつもたせ)、油断のならぬ小娘も、小袋坂に身の破れ、悪い浮名もたつの口、土の牢へも二度三度、だんだん越える鳥居数、八幡様の氏子にて鎌倉無宿と肩書も、島に育って其名さえ、弁天小僧菊之助~~」と。移動して。「白浪五人男 弁天小僧菊之助」。 「白浪五人男の内 弁天小僧菊之助 尾上菊五郎」。この絵の上部にも「お馴染みの名台詞」が。「伝法院通」と。伝法院とは、東京都台東区浅草寺の本坊であり、江戸時代初期に作られた池泉回遊式庭園や、客殿、大書院などの建築物で構成される場所です。客殿や玄関、大書院などは国の重要文化財に指定されており、庭園は国の名勝に指定されています。通常は一般公開されていませんが、不定期で特別公開が行われることがあります と。「白浪五人男の内 弁天小僧菊之助 尾上菊五郎」。この絵の上部にも「お馴染みの名台詞」が。 「河竹黙阿弥(かわたけもくあみ)一八一六年三月一日(文化一三年ニ月三日)~一月ニニ日(明治ニ六年)江戸時代幕末から明治にかけて大活躍した歌舞伎作家。黙阿弥は当時、この通りの一角に住んで作家活動を行っていました主に白浪物(盗賊が主役の歌舞伎)を中心に生世話物(江戸の町人社会を描いた歌舞伎)を得意とした人気作家です。生涯に約三百六十偏もの作品を残し、現在でも多くの作品が演じられており、「青砥稿花社彩画(あおとぞうしはなのにしきえ)」👈️リンクは代表作の一つで、白浪五人男の愛称で有名な作品です。」 「四世清元延寿太夫、四世市川小團次、河竹黙阿弥」。 「日本駄右衛門」。「とはれて名のるもおこがましいが 産れは遠州浜松在 十四の年から親に放れ 身のなりはひも白浪の 沖をこえたる夜働き ぬすみはするが非道はせず 人になさけを掛川から金谷をかけて宿々で 義賊とうはさの高札に 廻るはいふの盥(たらい)越し あふないその身のきやうがひも 最早四十に人間の定めはわづか五十年 六十余州にかくれのねえ 賊徒の帳本日本駄右衛門」と。 「青砥稿花社彩画河竹黙阿弥の代表作で通称「白浪五人男」は鼠小僧と呼ぶほど有名な盗賊達を描いた歌舞伎の演目として親しまれてきました。主役は五人の大盗賊。用心棒となってこの通りを守っています。注意深く探して下さい。日本駄右衛門(にっぽんだえもん)弁天小僧菊之助(べんてんこぞうきくのすけ)南郷力丸(なんごうりきまる)赤星十三郎(あかぼしじゅうざぶろう)忠信利平(ただのぶりへい)河竹黙阿弥江戸時代幕末から明治にかけて大活躍した歌舞伎作家。黙阿弥は当時、この通りの一角に住んで作家活動を行っていました。生涯に約360編もの作品を残し、現在でも多くの作品が演じられています。主な名代表作は「三人吉三廓初買」「極付番隨長兵衛」一心太助でお馴染みの「芽出柳緑翠松前」など。 「東京スカイツリー」をズームして。さらに進むと「もつ焼き 千代の家」の壁にあったのが「忠信利平(ただのぶりへい)」、日本駄衛門も認める、元浪人で剣の達人。腕節も強く、いぶし銀の魅力を持った男。「お馴染みの名台詞続いて次に控えしは月の武蔵の江戸育ち、幼児の折から手癖が悪く、抜参りからぐれだして旅を稼ぎに西国をまわって首尾も吉野山、まぶな仕事も大峰に足をとめたる奈良の京、碁打と言って寺々や豪家へ入込み盗んだる金が御嶽の罪科は蹴抜の塔の二重三重、重なる悪事に高飛びなし、後を隠せし、判官の、御名前騙りの忠信利平」「白波五人男の内 忠信利平 中村芝翫」。この絵の上部にも「お馴染みの名台詞」が。中村屋本店のバルコニーにいた「南郷力丸」。「さてどん尻に控えしは磯風荒れえ小ゆるぎの磯馴の松の曲がりなり、人となったる浜育ち仁義の道も白川の夜舟に乗り込む舟盗人 波にきらめく稲妻の白刃で脅す人殺し背負って立たれぬ罪科はその身に重き虎ガ石 悪事千里というからはどうで終めえは木の空と覚悟はかねて鴫立ち沢、然し哀りゃあ身に知らぬ 念仏嫌れえな南郷力丸」。 「白波五人男の内 南郷力丸 市川左團次」。 「大河ドラマ べらぼう 蔦重栄華の夢噺蔦屋重三郎ゆかりの地 台東区 蔦重の夢が息づく粋なまち」と。 江戸時代における掲示板・「高札」と呼ばれる木製の板の如くに、「駐車料金」案内を表示していた。 「仲見世通り」・「伝法院」方向を振り返って。 「伝法院通」。 ズームして。「雷おこし、人形焼・前田商店 花火」。 「浅草寺幼稚園」の「4月24日(木)【全学年】~こいのぼり~全学年、仲見世を通って五重塔前集合!こいのぼり紹介・お加持・贈呈式を行いました。」 「コマチヘア 能狂言」。 「元祖本村家人形焼本舗 薪能」。 「わらびや 観音示現菊供養」。 「ミノリヤ ???」。 そして正面に「宝蔵門」。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.05.19
コメント(0)
-

浅草を歩く(その7):浅草駅~雷門~浅草仲見世シャッター壁画
この日は5月11日(日)、「浅草を歩く」 のブログアップを継続中ですが、前回4月25日(金)の浅草へ行った目的は、学友4人の宴会であり、浅草散策が目的ではなかったため、ブログを書きながら、訪ねなかった、そして訪ね忘れた多くの場所があることが解ったために、この日の再訪を決断したのであった、早朝、6:30近くの小田急線に乗り、「浅草駅」を目指す。 代々木上原から東京メトロ「千代田線」そして表参道駅で銀座線に乗り換え、8時前に「浅草駅」に到着。日曜日・早朝の為、全ての電車に座ってここ「浅草駅」まで来ることが出来たのであった。これも早朝出発の理由の一つ。しかしもっと大きな理由が!!。日本最初の地下鉄駅である、東京メトロ銀座線の浅草駅構内案内。「雷門」に向かって地下道を進む。「東京メトロ銀座線浅草駅床象嵌絵陶板」。 2017年秋、東京メトロ銀座線浅草駅改札前に駅周辺の観光スポットを絵陶板にした「(床象嵌)観光案内方位盤」を岩尾磁器工業株式会社が納入したものとのこと。その先にあったのが、浅草神社の例大祭「三社祭」の浅草東町会の神輿。中央に「浅草東町会 大人神典」。 「浅草東町会 大人神典三社型 台輪寸法二尺五寸五部浅草神社の例大祭「三社祭」は毎年五月の中旬に行われ、宮神輿と共に約百基の町神輿が浅草中を盛大に練り歩きます。当浅草東町会 の神輿は、その中でも有数の大きさ豪華さを誇り、三社型と呼ばれる屋根の下からカ強く伸びる蕨手が特徴です屋根には三社巴紋 と三網紋 が五個ずつ取付けられ黒漆塗りのすっきりとした屋根を引き立てております、屋根裏の林組には金箔 押が流され鋳金具も「地彫り」と呼ばれる彫金細エ が施されております、彫刻類は浅草神社の社殿を模した家華な極彩色が施され艶やかなたたずまいとなっております、また飾り紐は宮神輿に倣い紫の三本然りを用いている点が特徴的です 東京・浅草 宮本卯之助商店 御神輿師 宮本重義 謹製」。 左側にあったのが「子供神輿」。 右側にあったのが、神輿の上部(屋根部分)にある「鳳輦(ほうれん)の飾り」。「鳳輦の飾り」があるのは、鳳輦(ほうれん)と呼ばれる天皇が乗る輿に鳳凰が飾られていたことに由来。鳳凰は不老不死の幻の鳥とされ、平和の象徴としても親しまれていた。神輿の屋根に鳳凰を飾ることで、神輿を神様の乗り物として、また祭りという特別な場にふさわしい豪華さや威厳を与える役割を担っているのだ と。そして地上に出て、この日も「雷門通り」を歩き「雷門」に向かう。 近づいて。前方、道路の反対側にあったのが「浅草文化観光センター」。 「浅草文化観光センター」は東京都台東区雷門二丁目にある、観光案内所などからなる複合施設である。浅草雷門前に位置する。台東区という名前は、「台」が上野の高台、「東」が上野の東に位置する浅草を表し、区の地勢を表しているのだと。この地には2階建の銀行の建物があり、銀行が撤退した後の1985年に台東区が買い取って浅草文化観光センターを開設。その後建物が築50年を過ぎ老朽化が進んだことから、2008年に建替えに向けたコンペが行われ、隈研吾の案が採用された。2012年4月にリニューアルオープン。正面から。正式名称は「東京都台東区立浅草文化観光センター」。平屋の家屋を縦に積み重ねたようなデザインで高さ38.9 m。各層の高さや屋根の角度、内装はそれぞれ変化がつけられている。それぞれの層には杉の不燃材製の縦のルーバーが取り付けられている。隈は、デザインの意図について「敷地が広くないためペンシルビルにならないよう、また浅草の街並みに合うように平屋を積み重ねたデザインにした」とウィキペディアより。そして「雷門」に到着。 ネットから。前回と異なり、インバウンドの方々がまだいない「雷門」を正面から。 浅草のシンポルの「雷門」は正式名称「風雷神門(ふうらいじんもん)」という総門で、門に向かって左手が雷を司る神の「雷神像」。右手が風を司る神の「風神像」が安置され、風水害を除けて、五穀豊穣の祈りも込められているのだ。風雷神像の背後には浅草寺の護法善神である「金龍像(女神)」と「天龍像(男神)」が安置され、どちらも水を司る龍神様と深いがりがあるとされる『パワースポット』として、鎌倉時代から多くの人々や江戸・東京全体を見守って来たのだ。「金龍像(女神)」。「天龍像(男神)」。そしてこの日は早朝に訪ねた理由は、インバウンドの方々が少ない時に!と併せて、「浅草仲見世シャッター壁画 浅草絵巻」を写真に収めたい為に、土産物屋の開店前にと。時間は8:00。 「「地元」、「企業」、「芸術」が三位一体で創り上げた環境芸術。昼の賑やかな仲見世と共に、夜を美しく彩るもうひとつの顔、それが「浅草仲見世シャッター壁画」です。平成元年、地元・浅草仲見世商店街、浅草を発祥の地とする文化シャッター、そして、東京芸術大学が三位一体となって完成させました。総延長400メートルのー大バノラマをお楽しみください。平成18年12月、さらに色鮮やかにリ二ューアルオープンいたしました。」 「平山郁夫教授研究室グループ制作シャッター壁画の元絵は、東京芸術大学・平山郁夫教授研究室グループ(平成元年当時)の制作によるものです。三社祭、ほおずき市、隅田川花火、そして金龍の舞、白鷺の舞など、浅草の伝統行事や季節の風物詩が描かれています。全四巻からなる絵巻を、シャッターにはグラフィックメディアというフィルムで表現しています。」 と。全四巻からなる絵巻。「平成元年 三月吉日 監修 平山郁夫 福井爽人」と。 「三社祭」をネットから。「浅草仲見世通り」の両側に「浅草仲見世シャッター壁画」が拡がっているのだ。そしてこの日の朝の「浅草仲見世シャッター壁画」👈️リンク をカメラで追ったのであった。ここ仲見世通り、東西約400m余にわたり、浅草草創からの歴史を語り、四季折々の伝統行事を繰り広げる「浅草絵巻」-まさに仲見世の財産であり、末長く保存されるべきもの。完成17年をすぎて、各店舗のシャッター本体が傷みはじめ、平成18年6月より7月にかけて、89店全店舗の「シャッター取り替え工事」を先行して行い、平成18年12月に第一期と全く同じ壁画が完成したのだ と。ネットから。「仲見世商店街 店舗MAP」。 「福光屋 出初式」 「浅草きびだんご あづま 松並木?」。「酒井好古堂??? 浅草寺の雪景色」。「たかしまや モリタ 喜久家 源頼朝?の流鏑馬」。 「むさしや人形店 ほうずき市」。 「バッグショップトヨシマ、フジャ、タカイシ、、(有)アオキカメラ??? 桜吹雪?」。「舟和 仲見世1&3号店 浅草寺」。 「新仲見世通り 左」。「新仲見世通り 右」。「かづさや小間物店 ???」。 「松崎屋 朝顔市」。 「モリタ分店 ???」。 「仲見世桝屋 荒井分扇堂 三社祭」。 ・・・もどる・・ ・・・つづく・・・
2025.05.18
コメント(0)
-

浅草を歩く(その6):浅草神社~新仲見世通り
「浅草寺境内案内図」。「現在地」は浅草神社前。 「浅草神社」前から「石鳥居」、「社殿」を見る。 「浅草神社」碑。 ◯浅草神社石碑 案内図。「浅草総鎮守 浅草神社(三社様(さんじゃさま))御祭神 ◆土師真中知命(はじのまなかのみこと) ◆檜前浜成命(ひのくまのはまなりのみこと) ◆檜前武成命(ひのくまのたけなりのみこと) (これら三人を神様として祭っていることから浅草神社の旧名は「三社権現社」といわれ、 現在では「三社様」として親しまれています。)御神徳 家内安全・商売繁盛・心願成就」 御由緒 推古天皇三十六年(六二八)三月十八日の朝、漁師の檜前浜成・武成兄弟が、浅草浦(現在の隅田川)で漁労に精を出していたところ、その日に限り一匹の魚も獲れず、投網に掛かるのはただ人形の尊像だけで、幾度か海中に投げ入れる場所を変えても同じ事の繰り返しです。流石に兄弟は不思議に思い、その尊像を捧持して今の駒形より上陸し槐の木の切株に安置しました。当時、郷土の文化人であった土師真中知に一見を請うたところ、現世御利益の尊い聖観世音菩薩の仏像であると告げられました。土師氏は間もなく剃髪して僧侶となり、自宅を新たに寺と構え、先の観音像を奉安し供養護持の傍ら郷民の教化に生涯を捧げました。いわゆるこれが浅草寺の起源となります。後世となり土師氏の子孫が聖観世音菩薩の夢告を蒙り、郷土発展の功労者である租先等を浅草寺の傍らに鎖守するようにと告げられ、前述三氏を郷土神として祀る三社権現社が茲に創建されました。奇しくも、明治元年の神仏分離により社名を三社明神社と改め、同五年には社格が郷社に列せられ、翌六年に浅草郷の総鎖守として現在の浅草神社に定められました。そして今でも、氏子の方々にはその名残から「三社様」と親しまれています。御社殿現在の御社殿は慶安二年(一六四九)に徳川三代将軍家光公より寄進・建立されたもので、本殿に幣殿を付属させ、渡りの間で繋いだ拝殿からなる権現造り風の様相を呈し、柱や壁等各部の漆塗りと随所には極彩色を用いた彫刻・刳形が施され、その細部に至る手法は時代の象徴を示しています。江戸の大火をはじめ関東大震災や東京大空襲の被災を奇跡的に免れ、昭和ニ十一年に国宝建造物に、更に昭和ニ十六年には国の重要文化財に指定され、江戸初期を代表して現存する責夐な木造築物です。これまでも各時代に修復作業が度々行われており、現代においては昭和三十六~ 三十八年の昭和の修営、平成六~八年の平成の大修営に依って、その壮厳さが見事に復刻・再現されました。三社祭浅草神社の氏子四十四ケ町を中心に五月の第三金・土・日曜日に行われ、江戸風情を残しつつ勇壮且つ華やかな神輿渡御を主として、三日問に亘り約百八十万人の人出を数える日本を代表する祭礼の一つです。祭礼最終日は、「一之宮」「ニ之宮」「三之宮」の各町渡御として、早朝より神社境内から担ぎ出される「宮出し」が行われ、日中は氏子各町を三方面に分かれ渡御し、日没後に境内に戻る「宮入り」を迎えて祭礼行事が終わります。祭礼期間中は浅草の街がお祭り一色に彩られ、神社では各神事が斎行されると共に、境内や神楽殿においても様々な舞踏が披露されます。」鳥居のすぐ横にあったのは大きな「天水桶」。1963年に再建されたもの と。鳥居の右手の方にひっそりいるのが「夫婦狛犬」。鳥居から社殿まで、まっすぐの参道が続きいた。浅草神社の狛犬は、大きな岩の上に乗っていた。狛犬(右)。近づいて。狛犬(左)。近づいて。立派な「手水舎」。「手水舎」のは水を吐く龍が3匹。水を吐く龍に近づいて。浅草神社の社殿(拝殿・本殿)。浅草神社の社殿は権現造り。1649年に徳川家光によって建立された と。社殿(拝殿・本殿)前の狛犬(右)。社殿(拝殿・本殿)前の狛犬(左)。境内左手前にあった「初代 市川猿翁句碑」。2代目市川猿之助は浅草生まれだ と。孫にその名を譲り、自分は猿翁を名乗った時の句が刻まれているとのこと。 「翁の文字 まだ身にそはず 衣がえ」。近づいて。大きな石に御影石を組み込んだ個性的な石碑。「初代 市川猿翁句碑「翁の文字 まだ身にそはず 衣がえ」猿翁。建碑 昭和四十五月十七日撰文 市川猿翁孫団子に三代目猿之助を譲り、自らは猿翁を襲名。昭和三十八年五月、歌舞伎座に於て襲名興行。(浅草寺の襲名お練り行列は四月十六日)『猿翁』(昭和三十九年六月東京書房刊)には、「翁の文字 まだ身にそはず 衣がへ 猿翁 昭和三十七年五月 猿翁襲名のとき」とある。明治二十一年五月十日、浅草千束町二丁目に生まる。父、喜熨斗亀次郎(初代市川猿之助ー段四郎)、母古登の長男。(弟妹は十人)兵役を終えたのち明治四十三年十月(二十二才)で二代目市川猿之助を襲名。昭和三十八年六月聖路加病院(心不全)にて死去。享年七十五才。昭和三十六年三月二十八日浅草三丁目三十九番地に生家に因みて「猿之助横丁碑」を建てる。 浅草観光連盟」 「初代 花柳寿輔句碑(初代花柳壽輔句碑) 雷は 田町をよけて 鳴りわたる」 「初代 花柳壽輔 略傅出生 文化四年二月十九日、芝・新明にて出生六才 文政九年、四世西川扇藏の許に入門し舞踊修業の道に入る。八才 文政十一年、七世市川団十郎の鑑識に叶い市川鯉吉の芸名にて舞台を踏む。十九才 天保十年、旧師西川扇藏の許に復帰し、西川芳次郎として振袖師の第一歩を踏み出す。二十五才 吉原の玉屋小三郎より俳号の「花柳」なるの二字を与えられ、以後花柳芳次郎と稱す。 爾後、七世市川団十郎が嘉永二年、当時市川海老藏を名乗り、その俳名「寿海」に 因みて「壽」の字を贈られ、二十九才にして初めて花柳壽助を名乗り、後に「助」を 「輔」に改め、と共に諸流に冠絶して振付の第一人者として謳はれる事、実に半世紀。 その作品は一千五百種を超え、就中「土蜘」 「茨木」「戻橋」「舟辯慶」の如きは不滅の 傑作と讃られる。八十三才 明治三十六年一月二十八日、花柳流の祖としての偉業を樹て、門弟、縁者に見守られ 其の生涯を終わる。 浅草観光連盟」 「江戸・東京の農業 檜前の馬牧大宝元年(701)、大宝律令で厩牧令が出され、大宝元年(701)、大宝律令で厩牧令(きゅうもくれい)が出され、全国に国営の牛馬を育てる牧場(官牧・かんまき)が39ヵ所と、皇室に馬を供給するため、天皇の命により32ヵ所の牧場(勅旨牧・ちょくしまき)が設置されました。東京には「檜前(ひのくま)の馬牧(うままき)」「浮嶋の牛牧」「神崎の牛牧」が置かれたと記録にあって「檜前の馬牧」は、ここ浅草に置かれたのではないかと考えられています。浅草神社の祭神で、浅草寺本尊の発見者ではある、檜前浜成、竹成兄弟の説話から、檜前牧は浅草付近であったと『東京市史稿』では推定していて、「浮嶋の牛牧」は本所に、「神崎の牛牧」は牛込に置かれたとされています。時代は変わり江戸時代、徳川綱吉の逝去で「生類憐みの令」が解かれたり、ペリー来航で「鎖国令」が解けた事などから、江戸に欧米の文化が流れ込み、牛乳の需要が増え、明治19年(1886)東京府牛乳搾取販売業組合の資料によると、浅草区の永住町、小島町、森下町、馬道と、浅草でもたくさんの乳牛が飼われるようになりました。 平成9年度JA東京グループ 農業協同組合法施行五十周年記念事業」 「初代 中村吉右衛門 句碑女房も 同じ氏子や 除夜詣」 「初代 中村吉右衛門 句碑女房も 同じ氏子や 除夜詣」吉右衛門建碑 昭和ニ十八年四月ニ十一日初代 中村吉右衛門 歌舞伎俳優 日本芸術院会員 文化勲章受賞明治十九年三月ニ十四日 浅象潟町に生まれ 幼少から舞台に立って名声を得 長じて大成し大正・昭和期を代表する歌舞伎俳優となった。高浜虚子に師事して「ホトトギス」の同人となり、句集も三冊に及ぶ 初め秀山と号したが 後に吉右衛門の名前を用いた。妻千代もまた浅草の生まれ: この句の由縁である 昭和十四年冬の作 この碑は自詠自筆である。 実名 波野辰次郎昭和二十九年九月五日没 享年六十八 浅草観光連盟」「河竹黙阿弥顕彰碑河竹黙阿弥は江戸末期から明治中期まで活躍した歌舞伎の狂言作者である。文化十三年二月江戸日本橋通二丁目四代越前屋勘兵衛の長男として生まれ幼名を吉村芳三郎といった。若い頃は遊楽生活を送ったが 二十歳で狂言作者五世鶴屋南北に師事 はじめ二世河竹新七の名を継いだ 天保十四年江戸三座が浅草猿若町に移転し終ると間もなく黙阿弥も芝からこの浅草の正智院の地内に居を移し 四世市川小団次に多くの新作世話物を書いた 明治維新後は九世市川団十郎 五世尾上菊五郎 初代市川左団次のために世話物 時代物のほか舞踏劇などを執筆した 明治十四年古河黙阿弥と改名し その後も劇作を続けた 作者生活五十年 著作は三百五十余編 江戸歌舞伎後半期の第一人者の地位にあり 特に 世話物を得意とした その音楽的効果や味わいは黙阿弥調として知られる代表作には「青砥稿花紅彩絵(あおとぞうしはなのにしきえ)(白浪五人男)」のほか「三人吉三廓初買(さんにんきちさくるわのはつかい)(三人吉三)」 「天衣紛上野初花(くもにまごううえののはつはな)(河内山)」などがある 明治二十六年一月歿 七十八歳 昭和四十三年十月 東京百年記念に台東区が建立する 東京都台東区長 上條 貢」 「花塚」。 「花塚「濁流」の花道の師、笠翁斉乱鳥の死を悲しんだ弟子たちによって建てられた。笠翁乱鳥は、享和三年(一八〇三l)七月晦日死去。享年八十八才。浅草本然寺(曹洞宗、現西浅草三ノ二五ノ三)に埋葬。悲しんだ弟子たちが、瓶に花を挿したが、衰える花を惜んで地中に埋め塚とした。戦後、昭和三十一年観音堂裏手東北より移転。建碑 文化元年(一八〇四)三月十七日「かめに花を挿こと古しへより聞え来れるを近き代には其花をさすにのり有事と成り其流くさくさに分れぬ。笠翁斉乱鳥其わざを好てこの大城のもとに濁流としなへて弟子あまた有き。こその文月つごもり、齢八十餘八にてみまかり給。浅草本然禅寺に葬ぬ。ことし三月十七日、かの翁の親しき友垣に弟子の集りて、かめに花をさして手向つ。其花のなごりを空しくなさむ事を惜み、はた翁の名の朽さらん事をおもひて、浅草寺の大ひさのみ堂のうしろ清らなる所を撰て其花を埋めて花塚と名付て後の世に残しなんとす。彼弟子の中、平石氏乱雨翁え残されしほゝに、笠翁斉の名を残したれば人々共に計りて其事成ぬ其わきかいつけよとこはるゝにいなひあへずして記つ。 「文化元年七月千蔭」 浅草観光連盟」 「友情はいつも宝物」碑。「友情は いつも宝物1976年に「週刊少年ジャンプ」で連載を開始して以来、多くの人々に愛されてきた「こちら葛飾区亀有公園前派出所」。物語の舞台となるここ浅草は主人公である両津勘吉を育み、また多くの感動を生み出してきました。この碑は、両津勘吉の少年時代の友情を描いた「浅草物語」にちなみ、人を思いやる気持ちの大切さ、そして子供たちが夢や遊び心を忘れず、健全に成長してくれるよう願いを込めて建てられました。 平成十七年八月六日 建立「浅草物語」概略ある日、浅草で一緒に遊んだ同級生が偶然再会。かつての悪ガキ両津勘吉は警察官に、かつての優等生は、逃亡犯になっていました。両津は、子供の頃にここ浅草神社(三社様)の神木、槐(えんじゅ)の木の下に一緒に埋めたベーゴマの話を持ち出して二人の友情を確かめ合いました。そして、逃亡犯は自首することになったのです。ジャンプ・コミックス「こちら葛飾区亀有公園前派出所」五七巻「浅草物語の巻」より「こちら葛飾区亀有公園前派出所」作者 秋本治連載開始 1976年週刊少年ジャンプ(集英社)両津勘吉職業 警察官(巡査長)誕生日 3月3日出身地 東京都台東区千束身長 約162cm体重 約71kg特技 自転車乗り」。近づいて。子供の頃にここ浅草神社(三社様)の神木、槐(えんじゅ)の木の下に一緒に埋めたベーゴマ。こちらは「社務所」。 そして、浅草寺周辺のこの日の散策はここまでとし、集合場所に向かったのであった。そして高校時代の学友5人で3時間近く昼飲みし帰路に。「新仲見世通り」を浅草駅に向かって進む。 レストラン「じゅらく」。 「高久人形点」。 「浅草の豆柴カフェ」 「浅草名物 もんじゃ ぜんや」 食べたかったが・・・。 「東京スカイツリー」。 ポスター「淺草 春の観光祭 3月15日~5月6日」 ポスター「淺草芸者のお座敷おどり」 そして再び「雷門」前まで戻る。そして再び「雷門通り」から「東京スカイツリー」、そして「アサヒビール本社ビル」を見る。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.05.17
コメント(0)
-

浅草を歩く(その5):浅草寺-5・弁天山 扇塚~松尾芭蕉の句碑~時の鐘~弁天堂~普閑の歌碑~添田啞蝉坊碑・添田知道筆塚~都々逸塚碑~地蔵菩薩像 阿弥陀如来像~旧五十重塔跡~旧仁王門礎石~神木~二天門
「浅草寺」の散策を続ける。 次に訪ねたのが、石段の上にあった「弁天堂」。本堂南東にある小高い丘は、弁財天を祀る弁天堂が建つことから弁天山と呼ばれる。弁財天は池中の小島に祀られることが多いが、弁天山もかつては池の中にあった。現在、池は埋め立てられて公園となっている。弁財天は七福神のなかの唯一の女神である。弁天堂のご本尊は白髪であるため、「老女弁天」と通称されている。この弁財天は神奈川県藤沢市の江ノ島弁天、千葉県柏市の布施弁天と並んで「関東の三弁天」として名高い。弁財天は、十二支の「巳の日」が縁日で、この日は弁天堂の扉が開かれて法要が営まれる と。 「扇塚」碑。浅草寺境内の弁天山に、二代花柳徳太郎師が建立した「扇塚」があった。日本舞踊では扇子をよく使うが、「扇塚」は古くなり、使えなくなった扇子に感謝し、供養するところ。 一年に一度、初代から四代(現在)花柳徳太郎ゆかりの人たちが集まって、扇の供養をしている と。「君諱徳太郎田代氏 明治十一年七月十一日浅草に生る 六歳叔父初代寿輔の養子となり 其薫陶を受く 同二十四年十三歳西郷邸に於て英照皇太后御前舞踊鶴亀を演ず 同三十六年初代寿輔歿後大正十二年迄花柳家元を継承 同三十八年柳櫻会創立公演九十八回に及ぶ 大正七年初代寿輔嗣子芳三郎に家元を譲り大正十二年自ら分家家元となり 昭和三十四年十一月三日多年舞踊界に盡瘁せる功に依り紫綬褒賞を授与せらる 同三十八年一月十二日歿す 享年八十六歳安隆院達道寿徳居士と諡して深川増林寺に葬る 二代徳太郎故人の遺志に依り茲に此碑を建つ 昭和三十九年四月 二代花柳徳太郎 蘭垌 野田朗書」と刻まれているとネットから。「扇入 泉徳右衛門」と刻まれた石箱。職業 日本舞踊家肩書 泉流家元(初代)本名 田代 民平生年月日 大正13年 4月13日経歴 幼少時より父母に師事。昭和15年泉流を創設、初代家元となる。古典の他、 創作舞踊に取り組み、軽妙、酒脱な芸風で高度な芸境を示した。代表作に 「あたま山」「芸阿呆」がある。所属団体 日本舞踊協会受賞 紫綬褒章〔平成1年〕 芸術祭賞優秀賞〔昭和45年 47年 48年 50年 51年 52年 53年 55年〕、舞踊批評家協会賞〔昭和55年〕、花柳寿応賞(第12回)〔昭和57年〕、 舞踊芸術賞〔昭和61年〕没年月日 平成3年 10月29日 (1991年)家族 父=花柳 徳太郎(初代)、母=花柳 徳太郎(2代目)、妻=泉 摩津枝(舞踊家)、 長女=泉 徳右衛門(2代目)「松尾芭蕉の句碑」。 「くわんをん(観音)の いらか見やりつ 花の雲 はせを」と。 「松尾芭蕉の句碑くわんをんの いらか見やりつ 花の雲 はせを俳諧紀行文『奥の継道』などを著した松尾色蕉は、寬永二十一年(一六四四)伊賀上野(現、三重県上野市)に生れました。芭蕉という俳号は、深川の小名木川ほとりの俳諧の道場「泊船堂」に、門人が芭蕉一枚をえたことに由来します。独自の蕉風を開き「俳諧芭蕉」の異名をとった松尾芭蕉は、元禄七年(一六九四)十月十二日、大坂の旅舎で五十一年の生涯を閉じました。この句碑は寛政八年(一七九六)十月十二日、芭蕉の.一〇三回忌に建立され、元は浅草本堂の北西、銭塚不動の近くにありましたが'戦後この地に移建されました。八十三歳泰松堂の書に加えて、芭蕉のスケッチを得意とした、佐脇嵩雪が描いた芭蕉の座像が線刻してありますが、二百年の風雪を経て、碑石も欠損し、碑面の判読も困難となっております。奥山庭園にある、『三匠句碑」(花の雲 鐘は上野か 浅草か)と共に、奇しくも「花の雲」という季語が詠みこまれております。平成二年四月吉日 浅草観光連盟」 石段を上りきると右側にあったのが「時の鐘」。 「時の鐘」をズームして。「時の鐘(浅草寺) 台東区浅草二丁日三番江戸時代、人々に時刻を知らせる役割を果たしていたのが時の鐘である。当初、江戸城内にあったが、江戸市街地の拡大にともない日本橋本石町にも設置され、さらには浅草寺や寛永寺(上野山内)など、九個所でも時を知らせた。鐘の大きさは、高さ二・一二メートル、直径一・五二メートル。鐘銘によれば、撰文は浅草寺別当権僧正宣存で、元禄五年(一六九二)八月、五代将軍徳川綱吉の命により、深川住の太田近江大掾藤原正次が改鋳し、その費用として下総(現、千葉県)関宿藩主牧野備後守成貞か黄金二百両を寄進した。この鐘は、時の鐘として、あるいは浅草寺の梵鐘として、さまざまな文学作品にも登場しているが、中でも松尾芭蕉の句花の雲 鐘は上野か 浅草かは、あまりにも有名である。昭和二十年三月の東京大空襲で火を浴びたが無事に残り、今なお昔のままの姿を見せている。なお、鐘楼は同空襲で焼け落ち、昭和二十五年五月再建されたものである。 平成十一年三月 台東区教育委員会」 そして正面に「弁天堂」。 「弁天堂弁天山と呼ばれる小丘の上に立つこのお堂は、昭和五十八年に再建されたもの。ご本尊は白髪のため「老女弁財天」といわれる。関東三弁天(神奈川県江ノ島・千葉県柏市布施と合わせ)の一つとされ、小田原北条氏の信仰が篤かった。境内の鐘椄の鐘は、元禄五年(一六九二)五代将軍徳川綱吉公改鋳の江戸時代の「時の鐘」として、芭蕉の句『花の雲 鐘は上野か 浅草か』で有名。現在は、毎朝六時に役僧が撞き鳴らし、大晦日には「除夜の鐘」が点打される。弁財天さまのご縁日は、「巳の日」で、堂内にてお参りができる。 金龍山浅草寺」 「弁天堂」の手前左にあった石碑は「普閑の歌碑」。「かかるとはおもひさだめし・・・」の歌を刻んでいる と。(浅草大百科より)。嘉永5(1852)年の建立。 「聖観音真言梵字の碑」 新吉原の山口巴屋が天保8(1837)年に奉納した碑。「上部に聖観音の種字「サの字」。中部にオン・アロリ・キヤ・ソワカ・ボロン。下部に弥陀の種字キリーク」(浅草大百科より引用)再び「弁天堂」。手を合わせる和服姿の女性は日本人!? 「添田啞蝉坊碑・添田知道筆塚」。「添田啞蝉坊碑・添田知道筆塚建碑 唖蝉坊碑 昭和三十年十一月二十八日 筆 塚 昭和五十七年三月七日添田唖蝉坊 本名・平吉 筆名は唖蝉坊のほか不知山人、のむき山人、凡人など。神奈川県大磯に生まれる。 昭和19年(1944)2月8日歿。享年73歳。明治20年代の壮士節の世界に入り、のち演歌の作詞、 作曲、演奏に従事。作品は「四季の歌」「ストライキ節」「ラッパ節」「ああ金の世」 「金色夜叉の歌」「むらさき節」「奈良丸くづし」「マックロ節」「青島節」「ノンキ節」 「生活戦線異状あり」など。著書に「浅草底流記」「唖蝉坊流生記」「流行歌明治大正正史」 ほか。添田知道 唖蝉坊の長男。東京出身。昭和55年(1980)3月18日歿。享年77歳。父唖蝉坊とともに演歌の 作詞、作曲に従事したあと作家活動に入る。筆名は知道のほか、さっき、吐蒙。演歌作品に 「東京節」「復興節」「ストトン節」など。著書に新潮文芸賞受賞の長編小説「教育者」 「利根川随歩」「演歌の明治大正史」などがある。 浅草の会」 「情歌二六号 都々逸塚 亀屋忠兵衛」碑。明治百年を記念して1967年(昭和42)に建立された。亀屋忠兵衛と刻まれている。亀屋忠兵衛は都々逸作家で、1962年(昭和37)に『都々逸下町 亀屋忠兵衛情歌集』を出版している。都々逸(どどいつ)とは、江戸末期に初代の都々逸坊扇歌(1804年-1852年)によって大成された口語による定型詩。七・七・七・五の音数律に従う。・立てば芍薬 坐れば牡丹 歩く姿は 百合の花(作者不詳)・人の恋路を 邪魔する奴は 馬に蹴られて 死んじまえ(作者不詳) が有名だが。弁天山を下りて浅草神社方向に進む。「浅草寺」の「宝蔵門」、「五重塔」は左手奥に。 次に訪ねたのが「二尊仏」の裏側にあった「地蔵菩薩像 阿弥陀如来像」。 中央 地蔵菩薩像。右 阿弥陀如来像。左 阿弥陀如来像。「地蔵菩薩像 阿弥陀如来像中央にお地蔵さま、左右には阿弥陀さまが奉安されている。中央のお地蔵さまは、我々衆生を苦しみから救ってくださる仏さま。左右に奉安される阿弥陀さまは、西方極楽浄土にあって無量の智慧と慈悲の光で我々衆生を救済してくださる仏さま。この三体の仏さまは、江戸時代より穏やかに我々を見守られている。右 阿弥陀如来像 寛文十一年(一六七一)造立中央 地蔵菩薩像 享保十一年(一七二六)造立左 阿弥陀如来像 延宝五年(一六七七)造立 金龍山浅草寺」 北に進むと、左手に再び藤棚が。その先、右手にあったのが「旧五十重塔跡」碑。旧国宝浅草寺五重塔は、本堂東南に位置し、塔内には、宝勝(ほうしょう)、妙色(みょうしょく)、広博(こうはく)、甘露(かんろ)、離怖畏(りふい)の、五智如来尊像が安置されていました。この塔は、上野寛永寺、芝増上寺、谷中天王寺の五重塔と並んで「江戸四塔」のひとつに数えられ、長きに渡って人々に親しまれましたが、昭和20年(1945)3月14日の東京大空襲によって焼失しました と。「旧五十重塔跡五重塔とは、仏舎利(釈迦の遺骨)を奉安する仏塔の一つで、古くから寺院に建立されてきた。この場所は、江戸時代の慶安元年(一六四八)、徳川家光 によって再建された旧国宝の五重塔(木造・高さ三十三メートル)が建立されていた場所で、現在の五重塔とは反対側に位置していた。浅草寺の五重塔は、天慶五年(九四二)平公雅 により創建され、その後いく度か炎上するもその都度再建されている。江戸時代、家光再建の五重塔は、上野寛永寺・谷中の天王寺・芝の増上寺の塔とともに「江戸四塔」として親しまれていた。また、歌川広重 ・歌川国芳 などの浮世絵 の格好の画題としても全国に知られ、朱塗り・碧瓦(未申にあたる裏鬼門の方角の第三層には、羊角猿面の鬼瓦が葺かれる)の美しい姿を見せていたが、昭和二十年(一九四五)の戦災で惜しくも焼失した。 金龍山 浅草寺」 この場所◯にあったと、ネットから。「東京百景 浅草公園」。 旧五重塔の写真。明治時代・一九〇七年前後の写真。「旧仁王門礎石」 三個の巨大石が並んでいた。近づいて。「旧仁王門礎石慶安二年(一六四九)十二月二十三日、旧本堂と共に三代将軍徳川家光公により、再建落慶した旧仁王門(国宝指定現宝蔵門と同規模)は、三百年間浅草寺山門として江戸・明治・大正・昭和と時代の変遷を見つめ、文学、絵画、芸能など往時の文化にたびたび登場してまいりましたが、残念ながら昭和二十年(一九四五)三月十日の東京大空襲により本堂・五重塔(家光公建立・国宝)と共に炎上焼失いたしました。その後、現本堂に続き昭和三十九年(一九六四)四月一日、仁王門を宝蔵門と改めて同跡地に再建されました。この三つの大石は宝蔵門再建に際して旧仁王門の跡地より昭和三十七年二月六日に掘出された礎石です。旧仁王門には十八本の大木柱があり、それそれに基礎石がありましたが、戦火に遭い、ひび割れ破損し、原型をとどめる大礎石三個を選び保存しました。石材は「本小松石」で上端の仕上げ面は約一・二m角、柱受けのホゾ穴があり、最大幅は約一・四m角、高さ約一m。この礎石の下部と周囲は十~十五cm径の玉石と粘土で突き固められていました。江戸の人々の息吹を感じると共に、平和を祈る記念碑として受継ぎたいと存じます。 浅草寺」 「宝蔵門」と「五重塔」。 「浅草寺の神木・いちょう」。 「浅草寺の神木・いちょう浅草寺本堂東南に位置するこのいちょうは、源頼朝公が浅草寺参拝の折、挿した枝から発芽したと伝えられる。昭和五年に当時の文部省より天然記念物に指定されたが、昭和ニ十年三月十日の戦災で大半を焼失した。今は天然記念物の指定は取り消されたが、あの戦災をくくり抜けた神木として、今も多くの人々に暮われている。 金龍山 浅草寺」 「五重塔 展望 地点」と。 近づいて。ここからの写真を。右奥にあったのが「浅草 二天門」。本堂の東に建つ朱塗りの門で、今の門は慶安2年(1649)に浅草寺の東門として創建された。当初は随身門といわれ、豊岩間戸命、櫛岩間戸命を守護神像(随身像)として左右に祀っていた。明治17年(1884)、神仏分離によって随身門に安置されていた随身像は、浅草神社に遷座されて、鎌倉の鶴岡八幡宮から広目天と持国天の像が奉納された。このとき名称を随身門から二天門と改めた。この二天の像は、昭和20年(1945)に修理先で戦災にあって惜しくも焼失し、現在の持国・増長の二天像は、昭和32年(1957)に上野・寛永寺の厳有院(四代将軍徳川家綱霊廟)から拝領した像。門に向かって右が持国天、左が増長天である。二天門は境内に残る江戸時代初期の古建築として貴重であり、国の重要文化財に指定されている。平成22年(2010)に改修を終え、創建当初の鮮やかな姿によみがえった。表側から。この二天門は、慶安2年(1649)頃に浅草寺の東門として建立されたようであるが、江戸時代を通じて浅草寺観音堂の西側に建てられた東照宮の随身門と伝えられ、随身像が安置されていた。なお浅草寺の東照宮は元和4年(1618)に建立されたが、寛永8年(1631)と同19年の火災によって浅草寺の他の諸堂とともに焼失し、その後東照宮は江戸城内の紅葉山に移された。明治初年の神仏分離令によって門に安置された随身像は、仏教を守護する四天王のうち持国天増長天の二天像に変わり、名称も二天門と改称した。現在安置されている二天像は、京都七条の仏師、吉田兵部が江戸時代初期(17世紀後半)に制作したもので(東京都指定有形文化財)、昭和32年に寛永寺巌有院殿(四代将軍徳川家綱)霊廟の勅使門から移されたものである。二天門は昭和25年、国指定重要文化財に指定された。 平成23年3月 台東区教育委員会」 「増長天(左)・持国天(右)(江戸時代前期・吉田兵部藤房作・都重宝)」 (ネットから)。増長天(左)。持国天(右)。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.05.16
コメント(0)
-

浅草を歩く(その4):浅草寺-4・正観音菩薩碑~藤棚~母子地蔵尊~阿弥陀如来像~二尊仏
「浅草寺」の五重塔と鯉のぼりとのコラボ。 「浅草寺」の「本堂」と「東京スカイツリー」のコラボ。 「浅草寺境内案内図」。 「宝蔵門」を再び斜めから。「正観世音菩薩碑」。 「正観音菩薩碑「正観世音菩薩」と碑の正面に刻まれている。当寺には観音さまを表した金石が多く奉安されているが、その中でもひときわ大きい碑であるこの石碑の銘文は長年の風雪により摩がか進んでいるが、「文」や「窪世」とわかる所が残されていることから、江戸時代の有名な石工の大窪世祥が、文化・文政年間(一八〇四~二九)頃に文字を彫ったと思われる。他にも世祥の金石は三基、境内に残されており、当寺にも関わりの深い人であった。江戸町人の信仰を載せた金石が運ばれ、活気付く境内の様子が目に浮かぶようである。南無観世音菩薩 金龍山浅草寺」 基壇状の建物(塔院)の上に建っている「五重塔」。「五重塔そもそも仏塔とは、遠くインドで釈尊の遺骨(仏舎利)を起塔供養したのがはじまり。アジア東漸を経て、さまざまな形となった。五重塔もその一形態。浅草寺五重塔は、天慶五年(九四ニ)、平公雅によって創建されたのをはじめとする。その後、数度倒壊に遭うも、その都度再建された。徳川家光によって再建された国宝五重塔も、昭和ニ十年三月の戦災によって惜しくも焼失した。(戦前までの五重塔は、今と反対側の本堂向かって右側にあった)以来、浅草寺は十方各位のご信助を得て、また新たにスリランカ国の王立寺院より「聖仏舎利」を勧請(五重塔最上層に奉安)し、昭和四十八年に現在の五重塔を再建するに至った。地上からの高さは約五十三メートルある。 (塔内非公開) 金龍山浅草寺」 「宝蔵門」と「東京スカイツリー」のコラボ。 「宝蔵門」の東側にある藤棚には藤の花が開花中。藤棚の下には、多くの観光客が休憩中。 見事な藤の花をカメラで追う。淡い紫の花が風に揺れる姿は本当に優雅で、春の浅草ならではの風景なのであった。その先にあったのが「母子地蔵尊」。正面から。近づいて。石像のデザインは漫画家のちばてつや氏が担当され、母子3人が寄り添った姿となっている。「母子地蔵建立の由来第二次世界大戦末期ソ連参戦で混乱状態となった中国東北部(旧満州)で避難行の末命を落とした日本人の数は二十万人を超えると云われています。酷寒の曠野を逃げ惑うの母子が生別れとなったり飢えや疫病に苦しみながら亡くなるなどその悲劇は数知れません。犠牲となられた母子の霊を慰め、また、いまだ再会かなわない親と子の心のよりどころとして二度と戦争という過ちを繰り返さない事を祈念しつつここに、母子地蔵を建立いたしました。 1997年4月12日 願主 千野誠治 デザイン ちばてつや 文字 森田拳次 まんしゅう地蔵建立委員会 まんしゅう地蔵建立応援団 中国残留孤児援護基金」 「まんしゅう母子地蔵尊 母子地蔵 第二次世界大戦が終わった1945年。そのとき中国東北部(旧満州)で生活していた多くの日本人は日本へ帰国しようとしました。しかし終戦の大混乱の中での飢えや寒さ、暴動になどによって、約24万人もの一般庶民らが犠牲となってしまいました。そのような中でも、なんとか帰国を果たした引揚者の有志が、、大陸に残された犠牲者や残留者を思い、あの戦争の悲劇を二度と繰り返さないと誓って建立したのが、この「母子地蔵」なのです。」 「阿弥陀如来像」。 「阿弥陀如来像阿弥陀如来とは、無量の智慧と慈悲の光で世界を照らし、西方極楽浄土にあって我々を救済してくださる仏さま。江戸時代前期の承応三年(一六五四)に、都市江戸の人々の願いで造立された。なお、この年には浅草寺が江戸で初めての開帳を行い、観音さまへの信仰を新たにする多くの人々で賑わった。本像は、後の文化一〇年(一八一三)に編纂された『浅草寺志』にも載せられており、江戸時代より我々を見守り続けてくださっている。南無阿弥陀仏 金龍山 浅草寺」近づいて。そして「二尊仏」。近づいて。 左:勢至像。右:観音像「二尊仏(浅草寺) 台東区浅草二丁目三番 浅草寺「濡れ仏」の名で世に知られるこの二尊仏は、観音(右)、勢至(左)、二菩薩の金銅坐像で、像の高さは共に二・三六メートル、蓮台を含めれば四・五四メートルにおよぶ。基壇の組石は、長さ約十二メートル、幅六・二メートル、高さ一・五メートルとなっている。蓮弁台座銘によれば、願主は上野国(群馬県)館林在大久保村の高瀬善兵衛。かって奉公した日本橋伊勢町の米問屋成井家より受けた恩を謝し、観音像は、旧主善三郎の菩提を弔うため、勢至像はその子に次郎助の繁栄を祈るため、貞享四年(一六八七)八月に造立した。江戸時代初期の優秀な鋳造仏の一つで神田鍋町の太田久衛門正儀の作。安永六年(一七七七)二月高瀬仙右衛門が施主、千住の高瀬奥右衛門か願主となり、修理したことが観音像銘に追刻されている。平成十年三月 台東区教育委員会」。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.05.15
コメント(0)
-

浅草を歩く(その3):浅草寺-3・常香炉~お水舎~本堂~銅造宝篋印塔~銅造阿弥陀如来像
「浅草寺」の「本堂👈️リンク」に向かって進む。間口34.5m、奥行32.7m、棟高29.4mで、旧本堂よりそれぞれ3mほど大きい。「浅草寺」の本堂はご本尊の聖観世音菩薩を奉安することにちなみ、観音堂とも呼ばれる堂宇である。国宝に指定されていた旧本堂は昭和20年(1945)3月10日の東京大空襲により焼失したが、その後全国のご信徒からのご浄財により、昭和33年(1958)に今日の本堂が再建された。本堂の創建は、ご本尊が示現された推古天皇36年(628)にさかのぼる。檜前浜成・竹成の兄弟が隅田川(宮戸川)で観世音菩薩のご尊像を感得したのち、10人の草刈り童子によって藜で屋根を葺いた堂に一時安置された。その後、土師中知が私邸を寺として、この聖観世音菩薩のお像を奉安したのが、本堂の起源である。ここに写っている人物はほぼ全てがインバウンド。正面に大きな「常香炉」。「常香炉」からは煙が濛濛と。「常香炉」の煙を浴びるインバイウンド。「常香炉」の煙には魔や邪気、穢れを払う効果があるといわれて折、転じて「体の悪いところが治る」「頭にかければ頭がよくなる」とも言われているのだ。そして「お水舎(おみずや)」。直径 2.3m・高さ 1.0m、八角形錆御影石造り。本堂前右側に位置するお水舎でお参りの前に身を清める。お水舎での作法について👈️リンク天井には「墨絵の龍」(東 韶光 画)、八角形錆御影石造りの手水鉢の上に、かつて本堂裏にあった噴水に安置されていた高村光雲作の龍神像(沙竭羅龍王像)をまつる。 高村光雲作の龍神像(沙竭羅龍王像)。明治36年(1903)8月奉安。仏法を守護する龍王の1人。龍や龍神は、水をつかさどる神である。頭に龍を乗せた銅像で、「龍神像・沙竭羅(さから)龍王像」と言うと。沙竭羅龍王は、法華経を守っているという龍族・八代龍王の1人 と。墨絵の龍の「天井画」。作者:東韻光作画年: 1964年(昭和39年)振り返って。左に「宝蔵門」、中央に「札所」、右に「伝法院」境内に立つ「五重塔」。 ズームして。朱も鮮やかな五重塔は、昭和48年(1973)に再建された、鉄骨・鉄筋コンクリート造りの塔である。外から見ると、五重塔は地上面から建っているように見えるが、実際は基壇状の建物(塔院)の屋上に建っているのだ と。よく解る写真をネットから。「本堂」手前右側にあった「天水桶」。浅草寺魚河岸講が昭和33年に浅草寺へ寄贈した劣化により平成22年(2010年)にリニューアル と。直径4.5mの「志ん橋」と書かれた大提灯が掛かる。江戸時代の浮世絵師・歌川広重「名所江戸百景 浅草金竜山」には、新橋から奉納された、「志ん橋」大提灯が描かれています。現在、本堂に掛かっている「志ん橋」大提灯は広重の浮世絵に描いていたデザインに立ち返っています と。歌川広重「名所江戸百景 浅草金竜山」をネットから。この図は雪の浅草寺雷門から、山門と五重塔を望んだもの。「大はしあたけの夕立」と共に広重の代表作。堂塔の赤と緑が雪に映えて美しく、雷門をくぐり浅草寺境内まで続く参道には雪がこんもりと積もっている。この雪の部分は空摺(からずり)という絵の具を付けずに摺る技法が用いられていて、積雪の量感が巧みに表現されている。大提灯「志ん橋」は、東京新橋組合が奉納(新橋の料亭、茶屋、芸者たちが、芸の一流や街の繁栄、事態の終息などを祈願して奉納)したもので、高さ4.5m、幅3.5m、重さ約600kgと、浅草寺の大提灯の中で最も大きいもの。文字「志」は「し」と読み、1900年以前の変体仮名と呼ばれる字体で書かれている と。この大提灯の下部にも「龍の彫刻」が。 右の柱・向拝の聯(ごはいのれん)には、『実相非荘厳金碧装成安楽刹』・【実相は荘厳に非ざれども金碧装いなす安楽刹】左には、『真身絶表象雲霞画出補陀山』・【真身は表象を絶すれども雲霞画き出す補陀山】と「豊道春海 書」が書かれ、「真如の世界はとても形などに表すことはできないが、見事に整えられた伽藍や自然の景観の妙は、それこそ仏の浄土であり、観音さまの世界である(浅草寺の堂塔伽藍・境内浄域のことを表す)。」という意味 であると。大提灯越しに「宝蔵門」・「仲見世通り」方向を振り返る。移動して。「本堂」の「正面額」には「施無畏(せむい)」と。高さ 約1.35m・幅 約4m、重さ 約700kg、欅製豊道春海原書 南部白雲工房作〔令和2年(2020)6月奉納〕観音さまは経典において、「施無畏者」とも呼ばれ、人々の不安や恐怖を取り除き、「畏れ無きを施して」下さる。「施無畏」とは、観音さまのおはたらきそのものを意味する と。そして本堂奥には「御宮殿」。 ズームして。「御宮殿」。ご本尊である聖観世音菩薩を安置している場所。ズームして。御本尊の聖観音菩薩が安置されている金箔のお宮。開基の勝海上人が秘仏と定めて以降、誰も見たことが無い絶対秘仏。つまり観音像を網で掬い揚げた、檜前浜成(ひのくまはまなり)・檜前竹成(ひのくまたけなり)兄弟と、その像を本尊として寺を草庵した土師真中土(はじのあたいなかとも/はじのまつち)と、勝海上人の四名のみが御本尊の実像を知っているということになる。そもそもこの四名の実像を知っている人もまた、歴史上いないので、創建自体がミステリー。毎年12月13日に、御宮殿の幕が開かれ、御前立を拝見することができる。また内陣には御宮殿以外に愛染明王と不動明王が安置され、御宮殿の間裏には御本尊と同じ姿をしたと伝わる観音像(裏観音)が安置されているとのこと。さらに。「御札御守所」。 「天井画」。 移動して正面に向かって。浅草寺本堂外陣の天井画も見どころのひとつ。川端龍子(かわばたりゅうし)作の『龍之図』、その龍に寄り添うように、左右には堂本印象(どうもといんしょう)作の『天人之図』。共に6.4m×4.9mの大作。」と。 左右には堂本印象(どうもといんしょう)作の左・『天人之図』。移動して。ズームして。右・『天人之図』川端龍子(かわばたりゅうし)作の『龍之図』。移動・ズームして。本堂内右奥の脇侍。不動明王。お姿は見えなかったが。本堂内左奥の脇侍。愛染明王。燭台。「聖観音宗総本山金龍山 浅草寺(せんそうじ・あさくさかんのん)推古天皇三十六年(六二八)三月十八日、檜前浜成・竹成の兄弟が隅田川に漁撈中、観音さまのご尊像を感得した。土師中知はこれを拝し、聖観世音菩薩さまであることを知り深く帰依し、礼扞供養に生涯を捧げた。大化元年(六四五)、勝海上人がこの地においでになり、夢告によりご本尊をご秘仏と定められた。平安初期には、慈覚大師円仁さまが来山され、お前立のご本尊を謹刻された。鎌倉時代に将軍の篤い帰依を受けた浅草寺は、江戸時にに徳川家康公によって幕府の祈願所とされ、堂塔の威容さらに整い、いわゆる江戸文化の中心として大きく繁栄した。かくして都内最古の寺院である浅草寺は、浅草観音の名称で全国的にあらゆる階層の人たちに親しまれ、年間約三千万人もの参詣者がおとずれる民衆信仰の中心地となっている。」 「本堂(観音堂)昭和三十三年、全国ご信徒のお力添えにより再建。お堂は南に面し、正面に懸かる「志ん橋」と書かれた大提灯は、東京新橋組合から奉納されたもの。外陣には、天上中央に川端龍子画の「龍の図」が、左右には堂本印象画の「天人の図」が掲げられ、正面には深見玄岱筆「施無畏」額が懸かる。内陣には、中央の御宮殿内に、ご本尊聖観音菩薩さま、慈覚大師円仁作のご秘仏お前立ちご本尊聖観世音菩薩様が奉安されている。また、御宮殿の正面左に梵天・右に帝釈天の二天が、内陣左奥に愛染明王、右奥に不動明王が祀られる。御本尊 聖観世音菩薩 観音さまは、人々の苦しみを見てはその苦しみを除き、願いを聞いては楽を与えてくださいます。特に浅草寺ご本尊のご利益・ご霊験は古今無双であり、ご示現より今日まで千四百年近くにわたり計り知れぬほどの人々を救われご加護なさってきました。観音さまのご信仰とは、観音さまに「慈悲(あたたかい心)」を頂き、その「あたたかい心」で日々を過ごすことと申せましょう。ご加なさってきました。※)ご参拝の際には合掌して「南無観世音菩薩」とお唱えしましよう。」 「浅草寺」の「本堂」を西側出口から出る。 再び五重塔を見る。ズームして。「本堂」を西側出口の正面にあったのが「銅造宝篋印塔」。 近づいて。総高は730センチメートル、塔高は520センチメートルあります。銅製、鋳造の宝篋印塔(ほうきょういんとう)で、その形状は江戸時代中期以降に流行した、笠部を屋蓋形とした宝篋印塔です。本塔は宝暦11年(1761)9月に日参講、塔婆講などを中心とする多くの信徒の助力によって建立されました。寄進者は700名を超え、石造框かまちの四周に刻まれています。寄進者は現在の台東区・千代田区・中央区・文京区・墨田区の範囲に広がり、中には札差の伊勢屋四郎左衛門等「十八大通」と呼ばれた人々や、俳優の中村鯉長、中村秀鶴等の名も見えます。このことから、本塔の造立は浅草寺を挙げた一大事業であったことが推測されます「銅造宝篋印塔台東区浅草二丁目三番一号宝篋印塔は「宝篋印陀羅尼経」という経典に基づいて造立された塔である。本宝印塔は、高さ約八メートル。西村和泉守藤原政時が宝暦十一年(一七六一)に鋳造した。西村和泉守は、代々和泉守を名乗る江戸を代表する鋳物師で、多くの作例を残している。なかでも本塔は区内に現存する銅鋳造宝篋印塔の中でも最大のもので、近世中期の鋳物師の活動や鋳造技術を知る上でも貴重な遺品のひとつである。また本塔の造立に際しては、台座に刻まれた銘文から、様々な職種や地域からの寄進が確認でき、浅草寺に対する信仰の広がりが示される。安政二年(一八五五)の地震で本塔は被災したが、明治四十年(一九〇七)に日露戦争凱旋記念として修復されたもので、区の歴史を知る上でも貴重である。平成二十三年に台東区有形文化財(工芸品)として台東区区民文化財台帳に登載された。平成二十四年三月 台東区教育委員会」 「銅造宝篋印塔」の南側にあったのが「銅造阿弥陀如来像」。「銅造阿弥陀如来像(台東区有形文化財) 台東区浅草二丁目三番一号 浅草寺阿弥陀如来は西方極楽浄土にあって、住生した人々に仏法を説く仏である。本像は銅製、鋳造で、総高二九四・五センチメートル、像高は一八六・〇センチメートルである。螺髪、肉髻珠、白毫をあらわす。衲衣は左肩を覆って右肩に少しかけ、裙を着ける。腹前で定印を結び、右足を上に結跏趺坐する。本像は台座に刻まれた銘文から、制作年代、奉納者、制作者が知れる。それによると、元禄六年(一六九三)四月に理性院宗海が本像の造立を発願し、鋳物師今井藤治郎藤原吉次が制作した。のち、同十五年(一七〇二)六月に両脇侍像(観音、勢至)が完成し、阿弥陀三尊像として造立された(両脇侍像は勢至薩像の台座を除いて、現存しない)。願主の宗海は、浅草三間町(現・駒形一丁目、雷門一・二丁目、寿四丁目付近)の僧侶で、本像の造立に際して近隣地で勧募活動を行い、結縁者を募った。結縁した人々は、町人が多く、職人や商人など職種はさまざまである。さらに念仏行者や、念仏講中(念仏を修する信徒集団)が関係していることから、宗海の勧進活動には念仏講が協力し、人々は地縁的な繋がりの中で結縁したと考えられる。江戸時代前期の人々の信仰、宗教活動を知ることができる貴重な資料である。制作者の今井藤治郎藤原吉次は、神田鍛冶町二丁目(現・千代田区)の鋳物師であるが、本像以外の作例は知られていない。そのため、本像は今井藤治郎の制作活動を考える上で基準となる作例であり、江戸鋳物師の作風を伝えている点においても貴重である平成二十四年(二〇一二)三月に台東区有形文化財(彫刻)として台東区区民文化財台帳に登載された。 令和三年三月 台東区教育委員会」 お顔をズームして。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.05.14
コメント(0)
-

浅草を歩く(その2):浅草寺-2・浅草寺歴史案内板~宝蔵門~五重塔
さらに「宝蔵門」に向かって進む。左側には、提灯が並ぶ。「浅草寺のご本尊は聖観世音菩薩さまです。お参りの時は、合掌して『南無観世音菩薩』とお唱えしましょう 金龍山浅草寺」 浅草、浅草寺の歴史についての案内板が並んでいた。「一、浅草のあけぼの浅草は利根川・荒川・人間川が運ぶ上砂の堆積によって作られた。古墳時代末期に人々が住んでいたことは、浅草の本坊・伝法院(でんぽういん)に残る「石棺」が示している。この東京湾に面した浅草は、はじめ漁民と農民の暮らす小さな村であったろうが、やがて隅田川舟運による交通の要衝として、また、観音様の示現による霊地として歴史的あけぼのを迎えるのである。二、ご本尊の示現「浅草寺縁起」によれば、推古天皇三十六年(六ニ八)三月十八日の早朝、隅田川(当時の宮戸川)で魚を捕る檜前浜成・竹成(ひのくまのはまなり・たけなり)兄弟が一躰の仏像を感得した。三、浅草寺の草創ニ人の漁師が感得した仏を郷司の土師中知(はじのなかとも。名前には諸説ある)に示した処、聖観世音菩薩像とわかった。そこて、この兄弟は深く帰依し、中知は自ら出家し、自宅を寺に改めて尊像を祀ったのが淺草寺の始まりである。この三人を祀ったのが「浅草神社(三社さま)」である。一方、そうした縁起とは別に、十人の童子がアカザという草で堂を建てたという伝承もあった。四、慈覚大師中興の開山となるご本尊が示現して十七年後、大化元年に勝海上人(しようかいしようにん)が浅草寺に来られ、観音堂を建立し、ご本尊を秘仏と定めた(秘仏の由来)。その後、天安元年(八五七)慈覚大師円仁(えんにん)が比叡山(天台宗の総本山)より来寺し、ご秘仏に代わる本尊ならびに「御影版木(みえいのはんぎ)」を謹刻された。板木が作られたことは、参拝者が増えてきたことを物語るものだろう。五、平公雅堂塔伽藍を建立平安時代中期、天慶五年(九四ニ)安房の国守であった平公雅は京に帰る途次、浅草寺に参拝した。その折、次は武蔵の国守に任ぜられるように祈願した処、その願いがかなったことから、そのお礼に堂塔、伽藍を再建し、田地数百町を寄進したと伝える。その伽藍に法華堂と常行堂の二堂があったことから浅草寺が天台宗の法の流れに属していたことが知られる。」 六、源頼朝の参詣治承四年(一一八○)、源頼朝は平家追討に向かうため浅草の石浜に軍勢を揃えた際、浅草寺に参詣して戦勝を祈った。やがて鎌倉に幕府を開いた後も 信仰を寄せた。鎌倉鶴岡八幡宮造営に際しては浅草から宮大工を召している。このように武将や文人らの信仰を集めた浅草寺の霊名は次第に全国に広まっていった。七、徳川将軍の篤い保護天正十八年(一五九〇)江戸に入った徳川家康は天海僧正の勧めで浅草寺を祈願所と定め、寺領五百石を寄進した。元和四年(一六一ハ)には家康を祀る「東照宮」の造営を認め、随身門(現、ニ天門)も建立されるなど浅草寺への信任は篤かった。寛永年間に観音堂が炎上した際も徳川家光により慶安ニ年(一六四九)再建された。以後、関東大震災にも倒壊せす、国宝観音堂として参詣者を迎えた。だが、昭和ニ〇年の東京大空襲により焼失、現在の本堂は昭和三十三年に再建された。八、江戸時代 境内と奥山の賑わい江戸の繁栄とともに浅草寺の参詣者も増え、やがて江戸随一の盛り場となった。江戸文化の最盛期、境内には百数十の神仏の祠堂(しどう)が建ち並ぶ庶民信仰の聖地となる一方、奥山では松井源水のコマ廻し、長井兵助の居合抜き、のぞきからくり、辻講釈などの大同芸や見世物が参詣者を喜ばせ、水茶屋・揚枝店・矢場(やば)なども立ち並んだのである。さらに春の節分をはじめ季節の行事は大変な賑わいを呈した。明治に人って、浅草寺の境内地は「浅草公園」となり、その第六区が興行街となって日本の映画史、演劇史の上に大きな足跡を残した。同十五年鉄道馬車が開通、同ニ十三年には浅草一帯を眠下に望む「十ニ階」が開業されるなど、浅草は文明開化のさきがけを誇った。九、浅草寺の寺舞(じまい)戦後、東京の復興は浅草の復興でもあり、地元の祈りでもあった。昭和三十三年に本堂が再建されたことを記念して「金龍の舞(きんりゅうのまい)」、昭和三十九年には宝蔵門(旧仁王門)の落慶記念に「福聚宝の舞(ふくじゅたからのまい)、昭和四十三年には東京百年祭を記念して「白鷺の舞(しらさぎのまい)が、それぞれ浅草寺縁起や浅草芝居の由来を受けて創作され、縁日に奉演されている。「浅草名所七福神日本の福神信夘は室町時代に恵比寿・大黒天をはじめとして、商業の盛んな京都方面で発達しました。その数は次第に増えて七福神となりましたが、当初、その顔ぶれは一定ではありませんでした。七という数の根拠には諸説ありますが、一種の聖数と考えられます。京都を中心に盛んとなった七福神信仰ですが、七福神すべてを巡拝する風習は十八世紀末~十九世紀初めに江戸で成立しました。江戸名所七福神も江戸では有名でしたが戦後に中断し、一九七七年(昭和五十ニ年)に再興されて今日に至るものです。なお、福神の働き(ご利益)は次の通りです。恵比寿 漁労・商売の守護。大黒天 五穀豊穰(食物) 出世を司る神。弁財天 知恵・音楽・財福を司る神。毘沙門天 四天王の一つ。 財宝・勇気・決断を司る神。福禄寿 幸運・生活の安定 長寿を司る神。寿老人 延命長寿を司る神。福禄寿 と同一とする場合もある。布袋尊 弥勒菩謹の化身とされる人神。 福徳・家庭円満を司る神。浅草名所七福神 浅草寺 大黒天 浅草神社 恵比須神 待乳山聖天 毘沙門天 今戸神社 福禄寿 不動院 布袋尊 石浜神社 寿老神 鷲神社 寿老人 吉原神社 弁財天 矢先神社 福禄寿」 そして正面に「宝蔵門」が大きく見えて来た。「浅草観光案内図」と「浅草の観光行事」 。「宝蔵門」。「宝蔵門 台東区浅草二丁目三番一号 浅草寺宝蔵門は、大谷米太郎 の寄進で、昭和三十九年に浅草寺宝物の収蔵庫を兼ねた山門として建てられた。鉄筋コンクリート造で重層の楼門である。外観は旧山門と同様に、江戸時代初期の様式を基準に設計されている。高さ二十一・七メートルある。下層の正面左右には、錦戸新観、村岡久作の制作による、木造仁王像を安置している。浅草寺山門の創建は、「浅草寺縁起」によると、天慶五年(九四二)、平公雅によると伝える。仁王像を安置していることから仁王門とも呼ばれる。その後、焼失と再建をくり返し、慶安二年(一六四九)に再建された山門は、入母屋造、本瓦葺の楼門で、昭和二十年の空襲 で焼失するまでその威容を誇っていた。 平成十八年三月 台東区教育委員会」 雷門をくぐり、人通り賑やかな仲見世を歩いてゆくと、前方に堂々たる朱塗りの楼門が参拝者を迎える。浅草寺山門の宝蔵門である。門は初層が五間で、両端の二間には仁王像を奉安し、中央の三間が通行のために開口している。仁王像が安置されていることからもわかるように、この門はもともと仁王門と呼ばれていた。『浅草寺縁起』によれば、平公雅が天慶5年(942)に武蔵守に補任され、その祈願成就の御礼として仁王門を建立したのが創建という。以来、数度の焼失と再建ののち、徳川家光の寄進により慶安2年(1649)に落慶した仁王門が、昭和20年まで諸人を迎えていた。今に伝わる錦絵の数々に描かれた仁王門は慶安の門である。昭和20年(1945)、仁王門は東京大空襲により観音堂・五重塔・経蔵などとともに焼失する。昭和39年(1964)に大谷重工業社長・大谷米太郎ご夫妻の寄進により、鉄筋コンクリート造り、本瓦葺きで再建された。経蔵を兼ねて伝来の経典や寺宝を収蔵することから、仁王門から宝蔵門と改称された。宝蔵門に収蔵されている経典とは、「元版一切経(国の重要文化財)」である。もとは鎌倉の鶴岡八幡宮に収蔵されていたものであるが、明治の神仏分離の際にあわや焼却処分されるところを、浅草寺に深く帰依していた尼僧の貞運尼が買い取り、浅草寺に奉納したという由緒をもつ。この「元版一切経」を鎌倉から浅草まで運ぶ際に助力したのが、町火消し十番組の組頭・新門辰五郎である。境内にあった新門の門番を務めたことから新門と名乗り、安政年間(1854~60)に浅草寺の経蔵を寄進している。戦災で経蔵は焼失したが「元版一切経」は疎開しており無事だった。宝蔵門は篤信の人びとに守られた宝物とともに、多くの参拝者の安寧を見守っている。「浅草寺」額京都・曼殊院門跡の良尚法親王筆の模写 と。「小舟町」と書かれた「大提灯」。高さ 3.75m・幅 2.7m、重さ 450kg。 日本橋小舟町奉賛会より平成26年(2014)10月奉納掛け換え(4回目)。「吊灯籠」 高さ 2.75m、重さ 1.000kg 銅製。 魚がし講より昭和63年(1988)10月奉納掛け換え(2回目)仁王尊像(木曾檜造り 重さ 各約1,000kg)「阿形像」 ネットから。「仁王様(阿行)昭和39年(1964)に、現在の宝蔵門の再建に際し、仏師の錦戸新親氏によって制作された。総高5. 4 5メートル、重さ約10 0 0キログラム、木會檜造りである。仁王さまのご縁日は8日。身体健全、災厄除けの守護神であり、所持している金剛杵は、すべての煩悩を破る菩提心の象徴である。この仁工さまは、宝蔵門にあって、日々参詣諸人をお迎えし、人々をお守りしている。」 「仁王様(吽行)ネットから。「仁王様(吽行)昭和39年(1964)に、現在の宝蔵門の再建に際し、仏師の村岡久作氏によって制作された。総高5. 4 5メートル、重さ約1000キログラム、木會檜造りである。仁王さまのご縁日は8日。身体健全、災厄除けの守護神であり、所持している金剛杵は、すべての煩悩を破る菩提心の象徴である。この仁工さまは、宝蔵門にあって、日々参詣諸人をお迎えし、人々をお守りしている。」 「五重塔」 日本で最も有名な五重塔のひとつが、浅草寺の境内にある五重塔。その高さは約53.32mで、ビルでいうと15~20階だてに相当します。浅草の五重塔は西暦942年に建てられたと言われています。江戸時代には寛永寺、池上本門寺、芝増上寺にある五重塔と合わせて「江戸四塔」と呼ばれ親しまれてきましたが、太平洋戦争の時の空襲で一度焼失してしまいました。いまの五重塔は焼失した後に場所を改めて建て直したものです。現在元の場所には石碑が建っています。五重塔の先端にあるのは「相輪」と呼ばれる金属製の装飾。これは、露盤、伏鉢、請花、九輪、水煙、竜舎、宝珠などが組み合わさったもので、上部に位置する「宝珠」が最先端にある。「相輪」案内図。 上から順に宝珠:仏舎利(釈迦の骨)が納められる。竜舎:奈良時代から平安時代の高貴な者の乗り物水煙:火炎の透し彫り。火は、木造の建築物が火災に繋がるため嫌われ、水煙と呼ばれる。 お釈迦様が火葬されたことをあらわす。九輪(宝輪):五智如来と四菩薩を表す。9つの輪からなる[注釈 1]。受花(請花):飾り台。蓮華の花。伏鉢(覆鉢):鉢を伏せた形をした盛り土形の墓、ストゥーパ形。お墓を表している。露盤:伏鉢の土台。宝珠は仏舎利が納められるため、最も重要とされる。 なお、中心を貫く棒は「擦」(または「刹管」)と呼ばれる。 また、仏舎利は塔の中に安置されていることもある。そしてこちらは「東京スカイツリー」の最上部をズームして。 正面に「浅草寺 本堂」。 「宝蔵門」を「本堂」側から見る。 「大わらじ高さ 4.5m・幅 1.5m、重さ 500kg、藁 2,500kg使用。山形県村山市有志より平成30年(2018)10月奉納〔昭和16年(1941)の初回以来、8回目〕わらじは仁王さまのお力を表し、「この様な大きなわらじを履くものがこの寺を守っているのか」と驚いて魔が去っていくといわれている。」 右側。左側。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.05.13
コメント(0)
-

浅草を歩く(その1):浅草寺-1・雷門~仲見世通り~浅草寺幼稚園
この日は4月25日(金)、高校時代の友人4人で会うことになり、小田急線、地下鉄を乗り継いで浅草駅に向かう。地下鉄を降り、地上に出て「雷門一之宮通り」を「雷門通り」そして「雷門」に向かって進む。 「雷門通り」に出て「アサヒビール㈱本社ビル」そして「墨田区役所」の間に「東京スカイツリー」を見る。そして「雷門」交差点入口より「雷門」を見る。 浅草寺 案内図。「雷門(風雷神門)」を正面から。浅草寺の伽藍守護のために、風水害または火災からの除難を目的としてこの二神(風神、雷神)がまつられたもの。現在の門は、江戸末期に炎上した門に替わり、昭和35年に95年ぶりに松下電器創始者、松下幸之助氏の寄進により、復興再建され、浅草寺の総門として威容を誇っているのだ。人、いや外国人の多さにびっくり!!時間は12:55。以前に訪ねた早朝の写真。「浅草寺」の山号「金龍山(きんりゅうざん)」そして「雷門👈️リンク」と書かれた赤い巨大な提灯。浅草のシンボル・雷門の前は、記念写真におさまる国内外の人びとでいつも賑わっている。雷門は浅草寺の総門であり、正式名称は「風雷神門」という。総門が現在地に移ったのは鎌倉時代以降のことで、移築の際に風神、雷神を安置したとも考えられている。風雷神門がなぜ「雷門」と呼ばれるようになったかは不明であるが、文化年間(1804~18)の川柳に、「風の神雷門に 居候」という句が見え、この頃には雷門という名称が一般化していたようである と。様式:本瓦葺 切妻造り八脚門 鉄筋コンクリート 合成樹脂塗装建坪:69.3m2(21坪)・間口 11.4m・高さ 11.7m炎上史:[1]寛永19年(1642)2月19日焼失、慶安2年(1649)12月落慶 [2]明和4年 (1767)4月9日焼失、寛政7年(1795)3月落慶 [3]慶応元年 (1865)12月12日、田原町大火により焼失現在: 昭和35年(1960)5月1日 95年ぶりに再建 昭和57年(1982)4月17日 塗り替え工事完成 平成25年(2013)11月18日 塗り替え工事完成「雷門(風雷神門)「天慶五年(九四二)、平公雅(たいらのきんまさ)によって創建されたのが始まり。門の正面向かって右に「風神」、左に「雷神」を祀る。このことから「雷門(風雷神門)」と呼ばれる。ともに鬼面蓬髪、風袋を担いで天空を駆ける風神と、虎の皮の褌を締め連鼓を打つ雷神は、お馴染みのものである。また、門の裏側には、向かって右に「金龍」、左に「天龍」の龍神像が祀られ、これら四神は、浅草寺の護法善神として、伽藍守護・天下泰平・五穀豊穣の守り神とされる。現在の門は、慶応元年(一八六五)の浅草田原町の大火で炎上した門に替わり、昭和三十五年に松下幸之助氏のご寄進により復興された。浅草寺参詣の入口にあたる「総門」として、また、東京・浅草の顔として全国的に有名。 金龍山 浅草寺」 提灯の底に施されている龍の彫刻。真下から。風神・雷神は、風や雷をつかさどる神さまであり、浅草寺の護法善神である。元々雷門はこの二神の名前から「風雷神門」と呼ばれていたが、いつの頃からか雷門とだけ呼ばれるようになった と。正面右:「風神像」。高さ2.18m。ネットから。斜めから。正面左:「雷神像」。高さ2.09m。ネットから。斜めから。「金龍山浅草寺」碑。 「聖観音宗総本山金龍山浅草寺(あさくさかんのん)御本尊 聖観世音菩薩(御秘仏)慈悲の仏さま 浅草寺ご本尊の観世音菩薩さま観音さまは、多くの仏さまの中でも最も慈悲深い仏さまであり、人々の苦しみを見てはその苦しみを除き、願いを聞いては楽しみを与えてくださいます。特に浅草寺ご本尊の観音さまのご利益・ご霊験は古今無双であり、ご示現より今日まで千四百年近くにわたり計り知れぬほどの人々を救われご加護なさってきました。観音さまのご信仰とは観音さまに「慈悲」のお心を頂いて生きること、すなわちすべてに「あたたかい心」で接して日々を過すことと申せましよう。※ご参拝の際には合掌して「南無観世音菩薩」とお唱えしましまう。縁起(由来)時は飛鳥時代、推古天皇三十六年(六二八)三月十八日の早朝、檜前浜成・竹成(ひのくまのはまなり・たけなり)の兄弟が江戸浦(隅田川)に漁撈(ぎょろう)中、はからずも一躰の観音さまのご尊像を感得(かんとく)した。郷司(ごうじ)土師中知(はじのなかとも:名前には諸説あり)はこれを拝し、聖観世音菩薩さまであることを知り深く帰依(きえ)し、その後出家し、自宅を改めて寺となし、礼拝(らいはい)供養に生涯を捧げた。大化元年(六四五)、勝海上人(しょうかいしょうにん)がこの地においでになり、観音堂を建立し、夢告によりご本尊をご秘仏と定められ、以来今日までこの伝法(でんぼう)の掟は厳守されている。広漠とした武蔵野の一画、東京湾の入江の一漁村にすぎなかった浅草は、参拝の信徒が増すにつれ発展し、平安初期には、慈覚大師円仁さま(794~864、浅草寺中興開山・比叡山天台座主3世)が来山され、お前立のご本尊を謹刻された。鎌倉時代に将軍の篤い帰依を受けた浅草寺は、次第に外護者として歴史上有名な武将らの信仰をも集め、伽藍の荘厳はいよいよ増した。江戸時代の初め、徳川家康公によって幕府の祈願所とされてからは、堂塔の威容さらに整い、江戸文化の中心として、大きく繁栄したのである。かくして都内最古の寺院である浅草寺は、浅草観音の名称で全国的にあらゆる階層の人たちに親しまれ、年間約三千万人もの参詣者がおとずれる、民衆信仰の中心地となっている。」 「本尊感得の図(浅草寺寛文縁起絵巻より)」をネットから。 「九代目市川團十郎「暫」銅像復元記念奉納 泣き相撲日時 四月ニ十六日(土) 銅像法要 午前十時四十五分 泣き相撲 午前十一時十分 場所 浅草観音本堂裏」 雷門の背面 (本堂側) には水をつかさどる龍神さま(浅草寺の護法善神)の金龍像(女性の姿)、天龍像(男性の姿)が奉安されていた。「天龍像(男神像)」。「天龍像天龍・金龍の二像は雷門の守護神として奉納された。謹刻者は平櫛田中(ひらぐし でんちゅう 1872~1979)及び菅原安男(1905~2001)の両氏である。両像は「金龍山」という当山の寺号に因み、龍神を天龍・金龍の男女二体に擬人化したものである。この天龍像は皮の腰鎧をつけ、右手に独鈷杵(どっこしょ)、左手に金珠を持った男神像である。青色を中心に彩色を施し材は木曽檜を用いる。高さは293cm、重さは250kgである。両像は御本尊示現1350年記念の年である昭和53年(1978)3月19日に奉安され、供養法要が厳修された。 金龍山 浅草寺」 「金龍像(女神像)」。 「金龍像天龍・金龍の二像は雷門の守護神として奉納された。謹刻者は平櫛田中(ひらぐし でんちゅう 1872~1979)及び菅原安男(1905~2001)の両氏である。両像は「金龍山」という当山の寺号に因み、龍神を天龍・金龍の男女二体に擬人化したものである。この金龍像は裙(くん)をはき、胸飾りをつけ左手に銀珠を持つ女神像である。白色を中心に彩色を施し材は木曽檜を用いる。高さは274cm、重さは200kgである。両像は昭和53年(1978)3月19日に松下グループの有志の方々によって奉安され、供養法要が厳修された。 金龍山 浅草寺」「雷門(風雷神門)」を仲見世通り側から見る。巨大な提灯には「風雷神門」と。左右に、「天龍像」、「金龍像」。 巨大提灯には「松下電器産業株式会社 創業者 松下幸之助」と。 ごった返した「仲見世通り」を進む。7~8割はインバウンド・外国人!! まるでこの場所は海外旅行に行っているかの如し。 「本家 梅林堂」。人形焼の店。客寄せの関係上、左右の通行分離が出来ていないので!!和服姿の女性は全てインバウンド!!「喜久屋」。 焼き団子を楽しむ女性インバウンド。「むさし屋人形店」。福幸運を招き寄せてくれる縁起物の招き猫がずらり。「Tシャツ TOKYOU 金龍山雷門」。 様々な文字、色がデザインされたTシャツ。「新仲見世通り」の右側。 「新仲見世通り」の左側。。「浮世絵 タペストリー」。「神奈川沖浪裏」(かながわおきなみうら)は、葛飾北斎の名所浮世絵揃物『富嶽三十六景』全46図中の1図。「仲見世通り」の先にあった「宝蔵門」が見えて来た。「赤富士」がデザインされたタペストリー。「三美堂 仲見世店」 様々なお面が。伝法院通りの左側。伝法院通りの右側には東京スカイツリーの姿が。高さ634mのタワーをズームして。左側にあったのが「浅草寺幼稚園」。 「浅草寺幼稚園」は、下町浅草の仏教寺院である浅草寺が運営する私立幼稚園です。活気あふれる賑やかな仲見世の中で地域に見守られながら約九十年間の歴史を歩んでまいりました。本園の発足は、大正12年に発生した関東大震災(1923年)の直後、復興に奔走して忙しい方々の幼児を預かる施設、託児所を開いたことが発端となっています。その後、保育園を経て、昭和6年に文部省により幼稚園として認可され、今に続く浅草寺幼稚園は誕生しました。創立して14年後の昭和20年(1945年)には、戦災により園舎は全焼してしまいますが、戦後間もなく地元有志の方々のご尽力を頂いて復興し、昭和49年(1974年)には、鉄筋コンクリートの新園舎が完成し、現在に至っております。観音様の「慈悲の心」を実践の場として、長年にわたって地元有志の方々から絶えず後援して頂きながら、充実した園舎の中で理想的な仏教保育に取り組んできた幼稚園です とネットから。「浅草寺幼稚園」の園内の観音様。ズームして。 ・・・つづく・・・
2025.05.12
コメント(0)
-

クリムソンクローバ
この日は4月24日(木)、我が家の裏の農家の畑には一面に「クリムソンクローバ」の赤い花が開花中。花の姿から「ストロベリーキャンドル」とも呼ばれています。クリムソンクローバは観賞用として楽しむほかに、土壌を豊かにするための緑肥としても利用されています。緑肥とは、育てた植物をシーズンが過ぎた後に取り除かずに、そのまま土にすき込んでその後に植える野菜の肥料にするというものです。クリムソンクローバはマメ科植物に属するため、根に根粒菌が共生しています。根粒菌は、空気中の窒素を土壌中に固定して植物が吸収しやすい形に変える働きをもっています。つまり、クリムソンクローバを植えると根粒菌によって土が豊かになり、さらに緑肥として利用することで次に育てる野菜に肥料分が提供されることになります。畑のクリムソンクローバを抜いて根っこを見てみると、根っこに数ミリメートルの瘤(こぶ)のようなものがいっぱいくっついています。これは根粒と呼ばれる器官で、この中に根粒菌(バクテリアの一種)という土壌微生物が住んでいます。根粒菌は大気中の窒素をアンモニアに変換し(窒素固定といいます)、植物の生育に欠かせない窒素を大豆に供給する働きをしています。化学肥料のアンモニアは1000気圧という超高圧、500℃という高温のもとで窒素と水素の化学反応で工業的に作られますが、莫大なエネルギーを費やします。根粒菌はこの反応を常温常圧でいとも簡単にやってしまう、まさに自然が創造した「超すぐれもの」なのです。クローバーに限らずマメ科植物(大豆、エンドウ、なども仲間なのです!)は、根粒菌と共生して窒素固定しています。自然界は不思議なのです。本来は多年草ですが、暑さには弱いため日本では一年草として扱われているようです。真っ赤なイチゴの果実に似た花穂を数多く枝先につけています。別の方向にカメラを向けて。ストロベリーキャンドルの他にもストロベリートーチ、ベニバナツメグサ、オランダレンゲなどの別名を持つとのこと。クリムソンクローバの赤い花は実は集合花です。クリムソンクローバを直訳すると「炎のツメクサ」とのことですが、この名前は花がまるで燃える松明(トーチ)のように見えることに由来していると言われています。菜の花とのコラボを。そして、白のクリムソンクローバを発見。突然変異!?あまり知られていませんが、クリムゾンクローバは栄養価が高く、飼料として優秀ですが、実は食べられるらしい。花は蜜があるので、エディブルフラワーとしてサラダにしたり、お茶できるようです。葉は炒め物、スープにできるようです。私はTRYしたことはありませんが。また、牧草として家畜のえさにされたり、犬や猫、小動物用のおやつに乾燥させたものが販売されたりしているとのこと。以下、2枚の写真はネットから。そして我がミツバチ!?も発見。花に蜜を多く持っているので、我がミツバチ!?やハナアブといった受粉する虫を呼ぶことができます。開花すると多くの我がミツバチが訪花しているのです。近くに置いていたイチゴ、はすべて受粉して実を付けることができるのです。そして、たくさんの蜜を集めて欲しいのです。 ・・・おわり・・・
2025.05.11
コメント(0)
-

地元の藤の花を愛でに(その2)
そしてこの日は2025年5月2日(金)、雨の合間に、我が家から車で10分ほどの場所にある「白旗神社」の藤(フジ)の花を愛でに行って来ました。境内には、多くの「鯉のぼり」が。境内に車を駐め、まずは境内の奥にある紫の「弁慶藤」に向かう。。ここ「相州・藤沢 白旗神社」は、奥州平泉で最期を遂げた源義経を祀る神社。伝承によれば、義経と弁慶の首は鎌倉の腰越の浜で首実検が行われた後、2つの首がここ白旗神社に飛んで来たのだといいます。1m余りの花房を幾重にもつけた、見事な「弁慶藤」。「藤」の原産は日本で、本州または四国から九州の比較的温暖な気候である林に見られる。平安時代からは、観賞用として庭園でも育てられて来た。そして現代では、つる性の特性を活かして藤棚となり、公園や遊歩道でも楽しまれているのだ。これぞ「藤紫(ふじむらさき)」の色。藤紫とは、藤の花のような明るい青紫色のこと。平安の頃より女性に人気の高い『藤色』と、高貴な色の象徴である『紫』を組み合わせた色名で、藤色よりも紫みが強い色。藤紫が染め色として登場するのは江戸時代後期とのことだが、明治期の文学作品や美人画などに数多く見られることから、明治文化を代表する色名の一つといわれている と。また、「藤紫」は大正浪漫の女性を虜にしたことから「大正藤(たいしょうふじ)」とも呼ばれたのだと。「弁慶藤」と。左側に廻り込んで。『万葉集』にはフジを詠んだ歌が題詞を含めて28首あるのだと。次はそのうちのひとつだ。「須磨の海人(あま)の塩焼衣(しおやきぎぬ)の藤衣(ふじころも)間遠(まどお)にしあればいまだ着なれず」フジの繊維は織り上げると白い衣となったが、ゴワゴワして肌触りが良くなかった。庶民の仕事着とされたり喪服として着用された。取り上げたこの歌では須磨(すま)の浜(現・神戸市須磨区須磨海岸)で塩をつくり出すために働く漁師の作業衣とされているが、和歌を詠みながらも、まだ着心地が悪いと愚痴をこぼしているのだと。そして大伴家持(おおとものやかもち)が詠んだ歌「わが屋戸(やど)の時じき藤のめずらしく 今も見てしか妹(いも)が笑(え)まひを」奈良時代には山野の藤を観賞用として家の庭などに移植する技術が普及していたことがうかがえると。藤の木から垂れ下がる花房が芳しい香りをあたりにただよわせ、花房のまわりに蝶やクマバチが羽音をひびかせながら乱舞している。平城の京の街中にある家の庭にはそんなフジの花が咲いていたことであろう。ややピークは過ぎていたが、花びら全体の紫色が今年は薄いようなきがしたのであったが。我が市の「市の花」の「藤(フジ)」。そして「藤」の字を持つ名字は種類も数も多い。桜や梅ほど花の美しさが評価されない藤が、なぜこれほどまでに名字や地名に用いられているのか。それは日本人の生活文化のなかに藤が深くくいこんでいるということだ と。藤原・藤田・佐藤・武藤・近藤・尾藤・首藤・安藤・伊藤・後藤、進藤・斎藤・加藤・・と。風に僅かに揺れて。藤棚には2本の老木が。藤棚前から境内を振り返る。そして「弁慶藤」の右横にあったのが「芭蕉の句碑」。「草臥て 宿かる比や 藤の花」。貞亨5年(1688年)4月11日、『笈の小文』の道中大和八木で詠まれた句。文化2年(1805年)3月、以足建立。以足は江戸の人。別号牛文庵。「芭蕉句碑「草臥て(くたびれて) 宿かる比や(ころや) 藤の花 文化ニ年建」文化ニ年は1805年。碑の裏にも句が刻まれていた。撮り忘れたので、下の写真はネットから。「東路や華にくるまる鈴の音」ここ藤沢で詠まれた句ではないが、ここ藤沢の「藤」にちなんで建てられたものであろう。文化2年(1805年)、以足(いそく)という人が建立したと裏に刻まれていた。文化というのは文化・文政時代、いわゆる「化政文化」が栄えた時代。化政文化は庶民が文化の主体となり広がった。裕福な人だけでなく庶民も文学・美術を楽しむようになっていった。今年のNHK大河ドラマ、蔦屋重三郎が生きた時代(1750-1797)からも続いている。以足については何も情報がなく、白旗神社との関係もわからないのですが、この地に芭蕉のこの句碑を建てた人がいた事実、それだけでも十分に文化・文政時代の藤沢宿の活気を伝える史跡として価値がある。またこのことが江戸時代から藤が美しかった証拠にもなるのだ。ぜひ藤の花と共に句碑もご覧になってください。裏側に「文化二年乙丑三月」としっかり刻まれていたのであった。実はこの藤棚の藤は、昭和の終わりころに当時の総代の小室一郎氏が浦和の天然記念物の藤を接ぎ木して育てたのだと。小室さんは接ぎ木の名人だった。ここにもこの地に尽力した人物がいる。たくさんの人が繋いできた歴史に連なる今この瞬間に自分たちは存在するのだと感じるのであった。右側の藤棚を振り返って。そして次に「社務所」前にある純白の藤の花「義経藤」を訪ねた。「弁慶藤」に比べて一週間ほど遅れて見頃になるのです。こちらは満開。白房花が1m近くに。雨も止み、しばし純白の「可憐」な花をカメラで追ったのであった。「義経藤」。「義経藤」のピークの花を見るのは久しぶり。源平の合戦において、平家は赤旗、源氏は白旗が旗印であった。平家一門が滅んだ後、源頼朝は白旗を源氏嫡流の旗と定め、余人の使用を許さなくなったのだ。もちろん、義経は鎌倉幕府初代将軍源頼朝の異母弟。よって白のこの藤は「義経藤」と。巨大な白い瀑布の如くに。白の花房を垂らす藤棚の姿は、実に幻想的なのであった。鯉のぼり越しに「弁慶藤」を。 巨大な令和7年の絵馬。「おみくじ掛け」も「義経藤」の如し 。「白旗神社」の「一の鳥居」。日本初のグラスファイバー製の「大鳥居」であると。高さ8m、幅6mの明神鳥居で、昭和59年12月に建立された。地震対策のために軽量で耐久性のあるグラスファイバーを取り入れ、建設時には新聞、テレビ、週刊誌等で報道されたのだ と。向かい合うようにあったのが「源義経公武蔵丸弁慶公之像」。この「源義経公武蔵丸弁慶公之像」は2019年(令和元年)10月竣工。源義経公没後830年の「記念事業」👈リンク の一つとして建てられたのだ。「義経公・弁慶公の御首は、文治5年(1189)6月13日に腰越の浜で首実検の後、金色の亀に乗り当地に辿り着いたと伝えられています。義経公の首塚は当社から、南に150メートルの場所に埋葬され、その御霊は白旗大明神として当社に祀られました。一方、弁慶公の弁慶塚は藤沢宿 常光寺境内にあり、その御霊は常光寺内の八王子社に祀られていましたが、現在は塚のみを残しています。一般的に神社は南向きか東向きに建てられますが、この八王子社に限っては、主君 義経公が祀られている白旗神社の方を向いていたため北向きに建てられていたと謂います。此度、令和御大典の嘉年と主従役儀830年の佳節を吉年とし、ここに源義経公・武蔵丸弁慶公の銅像を建立し、御霊の平安と隆昌を永年に亘り祈り奉ります。 令和元年(2019)10月28日 白幡神社 宮司 鈴木大次」。「源義経公武蔵丸弁慶公之像」。馬に乗る「源義経公」。平安武将の大鎧を再現した見事な源義経騎馬像。鎧だけでなく、馬具・轡(くつわ)なども忠実に再現したのだと。ズームして。そして「武蔵丸弁慶公」。武蔵坊弁慶が主君の義経を仰ぎ見る忠義の士の姿。大鳥居脇には小さな日本庭園があり、奥に「白旗弁財天」が祀られていた。そして「御祓川」。 中央に黄金の鯉の姿が。ズームして。巨大な絵馬を背景に。神輿殿を背景に。 ・・・もどる・・・ ・・・おわり・・・
2025.05.10
コメント(0)
-

地元の藤の花を愛でに(その1)
この日は5月1日(木)11時前、友人宅を尋ねるために小田急線の地元の駅に徒歩で向かう。駅前の民家の庭には紫色の藤の花が見事に開花中。玄関近くに、この家にお住まいの方がいらっしゃったので、カメラ撮影、ブログアップの許可をいただきました。藤(フジ)の花は私が住む市の「市の花」(昭和45年10月1日制定)になっているのだ。市内の公園には多くの藤棚があり、4〜5月には長い房に紫色の花を咲かせ、夏には日陰を作り私たちに憩いの場を提供してくれるのだ。単管パイプで出来た藤棚には見事な薄紫のフジの花が。フジの花の名前の由来は諸説ありますが、一般的には「吹き散る」がなまって名づけられたと言われています。また、古くから日本ではフジの姿が振袖の女性に例えられ、優しさや穏やかさを象徴する花として親しまれてきました。フジの英名は「Japanese Wisteria(ジャパニーズ・ウィステリア)」です。フジが日本の固有種であることから「Japanese」が英名に含まれています。「Wisteria」は、フジの研究科家としても活動していたアメリカの解剖学者「Caspar Wistar(カスパール・ウィスター)」の名前にちなんでつけられた とのこと。この家のご主人が手入れをされているのであろうか?巨大なクマバチも訪花中。そして白の藤(フジ)の花も。chatGPTに藤(フジ)の花の美しさを詠んでもらいました。一、薄紫の藤に寄せて風そよぐ 春の夕暮 藤の花 夢のほつれを 空にたらして──そよ風に揺れる薄紫の花は、まるで忘れかけた夢の糸。夕暮れの空に、 ひそやかにほどけていきます。二、白藤の静けさしろたへの 藤はしづけく 咲きにけり 水面に映る 月のごとくも ──白き藤は静かに咲き、その姿はまるで水面に浮かぶ月。 言葉を持たぬ美が、そこに息づいています。 ・・・つづく・・・
2025.05.09
コメント(0)
-
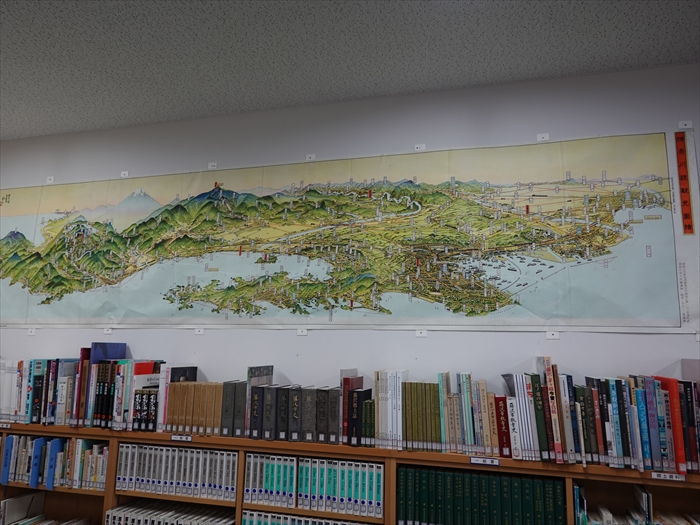
藤澤浮世絵館・『江戸の祭神 弁財天と不動明王』展へ(その6)
『江戸の祭神 弁財天と不動明王』展の見学を終え、常設展示の部屋に。「吉田初三郎 昭和5年(1930) 湘南電鉄沿線名所図絵」が展示されていた。鳥瞰図サイズ:770×177mm。全体の拡大図絵をネットから。大正広重と呼ばれた鳥瞰図絵師・吉田初三郎作。現京浜急行。昭和5年4月に黄金町~浦賀間、金沢八景~湘南逗子間が開通し震災からの復興がようやく地元に実感できた時期に描かれた。昭和8年には品川~浦賀間が直通運転となる。図絵は初三郎独特の一直線に線路を描き距離感を縮める得意技で描かれ、全盛期の素晴らしい構図である。「江の島」周辺、三浦半島をズームして。 「吉田初三郎 昭和5年(1930) 湘南電鉄沿線名所図絵発行:湘南電気鉄道株式会社湘南電気鉄道は京浜急行電鉄の前身の一つで、大正14年(1925)に会社設立。昭和5年( 1930 ) 4月1日に黄金町駅-浦賀駅間、および金沢八景駅-湘南逗子駅の路線を標準軌で開業横浜~浦賀間で営業を開始した際の発行絵図です。」いろいろな角度でズームして。窓から、大山方向を見る。左側の白い建物が「テラスモール湘南」。 「大庭城跡市指定記念ミニパネル展」。「大庭城跡大庭城跡は藤沢市大庭字城山に所在する戦国時代の山城です。お城と言うと、石垣と天守閣を持つものをイメージしがちですが、それらは江戸時代以降のお城で、関東のお城は堀と土塁を多用した、いわゆる「土の城」でした。なぜならば、関東地方に堆積している関東ロームは滑りやすく一度落ちたら容易に登れないからです。大庭城跡も例にもれず「土の城」でしたので、石垣や天守閣はありません。なのでよく「大庭城跡に行っても何も残っていない」との話を聞きますが、そんなことはありません。大庭城址公園内には沢山の堀や土塁の痕跡が残っています。ところで大庭城は誰が築城したお城でどのような人物が守っていたのでしようか。築城時期は不明な点が多いですが、築城したのは当時相模国(神奈川県の大部分)の守護であった扇谷上杉氏と考えられています。またある時期には扇谷上杉朝昌という人物が大庭城を守備していたことが古文書から判明しています。この朝昌という人物は扇谷上杉氏の中ではかなりの重要人物であり、大庭城はそのような人物が守備するほど重要な拠点であったことが指摘されています。」 「大庭景親と大庭城跡大庭城跡は元々、平安時代後期に活躍した大庭景親の居館跡を戦国時代に築城の名手である太田道灌がお城として改修したという話がありますが本当でしようか。残念ながらこの話は江戸時代頃にできた地元の伝承で、室町時代の古文書には大庭景親の居館跡と大庭城は別々の場所にあったことが記されています。」 扇谷上杉氏略系図。大庭城跡(1990年撮影)。「発掘で確認された大庭城の遺構大庭城跡は昭和42年(1967年)から令和3年(2021年)までに25回の発掘調査が行われています。その中でも第2次調査から第6次調査では城を守るために掘られた20本以上の堀が確認されています。また現在「館址広場」と名前がついている大庭城南側の平場からは大型の掘立柱建物が確認されており、ここが城主のいた主郭であると考えられています。なお、この掘立柱建物の1棟の柱穴から炭化したお米が出土していますが、平成28年(2016年)に郷土歴史課でこのお米を化学分析したところ、籾殻の付いた状態で炭化したことが分かりました。また年代測定の結果、大庭城が機能していた頃のものであることも分かりました。近年の調査で注目されるのが、主郭の西斜面で行われた第23次調査と第25次調査です。第23次調査では主郭の西斜面を鋭角に削り、さらに横堀を掘っていることが分かりました。また昨年度から今年度にかけて第23調査より下で新たに2本の横堀と、斜面を平坦に造成して守備兵を配置した「帯曲輪」という防御施設の存在も確認するとができました。横堀と竪堀横堀とは斜面に対して平行して掘られた堀で、攻め手が斜面を登ることを防ぐために築かれたものです。それに対し竪堀は攻め手が横向に自由に移動することを防ぐために築かれた堀となります。」 大庭城発掘調査案内図。横堀(南から)。「帯曲輪(西から)」 3号堀立柱建物の柱穴から出土した炭化米(左上)とその電子顕微鏡写真(右上・右下)。「藤沢宿」ポスター歴史新発見! 藤沢の海じゃないほう。」「旧東海道・藤沢宿」に観光客を呼び込もうと市内のクリエーター3人の方が制作したポスター。街道筋の神社、お寺の見どころ、逸話を写真とイラスト入りのポスター。小田急各駅、JR藤沢駅と近隣駅、公共施設に掲示されている、と。 さー ”「海じゃないほう 藤沢宿」” に行って見ましょう と。 「八犬傅出世雙六 一鶯斎国周 (いちおうさいくにちか )画」。慶応1/1865。八犬伝の11の名場面に、27人の人物を配して双六にしている。振り出しは里見義実、上がりは芳流閣。人気役者の見立絵。「初代 歌川広重 六十余州名所図会 下総 銚子の浜 外浦」「下総 銚子の浜 外浦」は、下総の代表的な名所であった銚子での磯遊びの様子を描いたものです。「外浦」は、現在の銚子市南東部の外川(とかわ)地区の一画で、当時の地元での呼び方と思われます。手前の砂浜が外川の浜で、中央左手の巨大な岩は千騎ヶ岩(せんきがいわ)と呼ばれる奇岩です。また、右手中ほどの断崖絶壁が屏風ヶ浦で、全長約10キロに及ぶ断崖ですが、ここではその西端の刑部岬(ぎょうぶみさき)が描かれています。水平線上には房総半島がかすかに浮かび、その向こうには富士山も見えます。このように見える風景は本来はありませんが、外川の浜で見ることのできる名勝が、一図の中に凝縮されています。「国貞二代 / 里見八犬伝 狗草紙之内 芳流閣上図」 曲亭馬琴の『南総里見八犬伝』の有名な場面。歌舞伎でも、屈指の名場面であり、ここに題材をとった錦絵が多く描かれた。犬塚信乃と犬飼現八が、下総滸我(こが、古河)の灼熱の芳流閣屋上において血戦する。二人は、組み合ったまま屋根の上から利根川に繋がれた舟の上に転落し、利根川の下流・下総行徳へと流される。「豊原国周 里見八犬伝 役者絵」。 「寛朝僧正護摩を修める圖」 「諸人成田山参詣之圖」。 「販売中」と。 「絵はがき 1枚100円」。入口ホール壁のパネル手前:『一寿齋国貞 作 江の島』。 四代豊国(二代国貞)と二代広重との合筆による作品であると。 将軍が江の島の岩屋の前で、海女の親子が海中から鮑を取って来る様子を上覧している場面。手前:『歌川広重 作 東海道五十三次 藤沢(隷書東海道) (とうかいどうごじゅうさんつぎ ふじさわ(れいしょとうかいどう)』 藤沢宿の夜の風景で、右側にある鳥居が江の島一ノ鳥居(江の島道入口)、 左手にあるのが大鋸橋(現遊行寺橋)。宿場に着いた人々と客引きをする宿の人々の 様子が描かれ、にぎわいが感じられる。 ポスター 200円。「歌川広重「相州江の嶋弁才天開帳詣本宮岩屋の図」 2025年 カレンダー 400円。手前:『三代 歌川豊国(国貞) 作 『東海道名所之内 鎌倉七里が浜乃風景』。正面から。ポスター『川崎浮世絵ギャラリー 歌舞伎展 2024.11.23Sat---12.22Sun』。『秦野市立図書館 はだの浮世絵ギャラリー』2017年(平成29年)11月3日から常設展示。静岡市東海道広重美術館 『東海道五十三次 同時開催:だけじゃない東海道』2024/10/8(火)〜2025/1/26(日)。今や誰もが知る歌川広重の代名詞「東海道五十三次」シリーズ。本展では、『東海道五拾三次之内』(保永堂版東海道)をはじめ、東海道シリーズ3作品を各会期ごとに展示し、それぞれ日本橋から京までの全点を楽しめる。同時開催の「だけじゃない東海道」展では、三代豊国や国芳など、初代広重“だけじゃない”「東海道」の浮世絵作品を紹介。ズームして。國學院大學『特別展「文永の役750年 Part2 絵詞に探るモンゴル襲来 ―『蒙古襲来絵詞』の世界―」 /令和6年11月30日(土)~令和7年2月16日(日)2024年はモンゴル帝国が鎌倉時代の日本への侵攻を図った文永の役からちょうど750年目である。これを踏まえ、2024年はモンゴル帝国が鎌倉時代の日本への侵攻を図った文永の役からちょうど750年目である。これを踏まえ、当館ではモンゴル襲来に関する最新の研究状況の紹介を目的とした特別展を2つ計画した。1つ目は「海底に眠るモンゴル襲来−水中考古学の世界−」(会期9月21日~11月24日)であり、モンゴル襲来の終焉の地である長崎県鷹島海底遺跡の実態解明を進めつつある水中考古学調査研究について紹介した。二つ目となる本展では熊本県菊池神社と埼玉県根岸家のご協力をいただき、所蔵する『蒙古襲来絵詞』模写本の展示公開を図ることとした。現在、『蒙古襲来絵詞』の原本は独立行政法人国立文化財機構皇居三の丸尚蔵館所蔵が収蔵し、国宝に指定されているが、『蒙古襲来絵詞』は多くの模写本が作成されており、約40例が知られている。しかし、模写本には原本とは異なる内容を持つものが多く、その違いはそれぞれの模写本が作成された経緯や時期など、さまざまな要因があると考えられる。そこで、本展では、菊池神社と根岸家所蔵の模写本を展示し、原本との違いとともに模写本間の違いを比較検討し、『蒙古襲来絵詞』の模写本が作成される経緯とそれぞれの模写本の位置付けの検討を試みることとする。『豊橋市二川宿本陣資料館 再始動記念展 --東海道の描き方--』2024年11月3日(日)→12月15日(日)『大阪浮世絵美術館 浮世絵が語る日本の名山』。2024.7.23Tue ~2025.2.16Sun『日本浮世絵博物館 浮世絵でめぐる信州』前期: 1月4日(土) ~ 2月9日(日)後期: 2月11日(火・祝) ~ 3月23日(日)『太田記念美術館 江戸メシ』2025年月1月5日(日) ~26日(日)。江戸時代は日本において食文化が大きく発展した時代です。寿司や蕎麦、天ぷらなどのファストフードが人気を博し、味噌や酢、醤油といった調味料も広く流通するようになりました。人々は自宅で気ままに食事を楽しむだけでなく、料亭や屋台で外食して舌鼓を打っていたのです。庶民たちの暮らしを題材とする浮世絵では、さまざまな料理や食材、あるいは食事の様子などが数多く描かれています。本展覧会では、北斎や広重、国芳といった人気絵師たちをはじめとする約90点の浮世絵を通して、現代の食文化にもつながっている「江戸メシ」の魅力を紹介いたします。以前訪ねたことがある「本立寺👈️リンク」 そして7Fにあった「藤澤浮世絵館」を後にする。1階ホールに展示されていた、パリオリンピック体操競技 報告「岡慎之助選手 三冠」、「杉野正尭選手」。体操ニッポンの大活躍に日本中が沸いたパリ五輪――。徳洲会体操クラブの杉野正尭主将と岡慎之助は、燦然と輝く金メダルを首にかけ、表彰台でスポットライトを浴びた。両選手は体操男子の日本代表として出場し、団体総合で金メダルを獲得。さらに岡は個人総合と種目別鉄棒でも金メダルの3冠という快挙を成し遂げ、種目別平行棒でも銅メダルを獲得した。杉野は種目別で、あん馬と鉄棒に出場し、それぞれ6位、7位の入賞。同クラブ創設以来、所属選手が五輪の個人総合で優勝したのは初。五輪の体操男子で日本が団体・個人・種目別を同一大会で制するのは52年ぶり、4個のメダル獲得は1984年のロサンゼルス大会以来となる40年ぶりの偉業だ。 「徳洲会 体操クラブ」 。そして「ココテラス湘南」のビルを出て駐車場へと向かう。左側のビルが「ココテラス湘南」。右側のビルは湘南パスポートセンターのある「AI CROSS SHONAN」。「藤澤浮世絵館」のあった「ココテラス湘南」ビルをズームして。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.05.08
コメント(0)
-

藤澤浮世絵館・『江戸の祭神 弁財天と不動明王』展へ(その5)
展示コーナーの中央にあった「藤沢宿」案内。 「藤沢宿」 「藤沢宿は東海道の江戸日本橋から数えて6番目の宿場です。江戸幕府の道中奉行所の記録では、藤沢宿の名物を「大山詣で、江の島弁財天詣で」と記しています。江戸時代の藤沢宿の特色の一つは多くの道が集まる場所であったことです。メインの東海道を西へ、四ッ谷から北東に分かれる大山道(大山阿夫利神社・大山不動尊へ)、南へ下る江の島道(江島神社・江の島弁財天へ)、遊行寺前で東へ向かう鎌倉道、北へ向かう八王子道(滝山街道)、北西に向かう厚木道などがあリ、観光、流通の中心地となリました。主な名所に、時宗総本山清浄光寺(通称は遊行寺)、江の島(江島神社)一ノ鳥居(江の島は、宿場から一里ほど南)、四ッ谷の立場(宿と宿の間の休憩地)、南湖(茅ヶ崎市)の左富士などがあリました。」そして後期展示の案内。「歌川貞秀 利根川東岸弌覧 慶応4年(1868)👈️リンク」。※後期展示 と。「この画は、利根川(現江戸川)下流の市川・浦安方面と江戸川上空から眺めた形式の鳥瞰図です。左の3枚は、国府台、真間入江、市川の町並。右の3枚は、手前が現江戸川区で、対岸が行徳から浦安です。遠景として、船橋から富津にかけての江戸湾を描いています。国府台の崖や真間の入江はかなり誇張されており、必ずしも実景どおりではありませんが、全体としては当時の様子をよく伝えています。」 そして次に「江戸の祭神 弁財天と不動明王② ~不動明王信仰~」 不動明王は密教とともに弘法大師空海が日本に伝えたとされます。弁財天と同様に国家鎮護のご利益をもつ不動明王は元々「山の守護者」という意味て日本古来の山岳信仰や修験道とも結びつき、信仰が広まっていきました。炎を背景に怒りを浮かべ、にらみつける相貌から厄除け、立身出世、健康祈願など現世利益がある仏として民衆の間にも信仰を集めました。企画コーナーでは船橋市西図書館所蔵の浮世絵や資料を中心に、江の島の弁財天とともに人気の参詣地であった成田山新勝寺の不動明王信仰を紹介します。」 「歌川国郷 成田山開帳参詣群集之夕景 安政3年(1856)」。ネットから。右から。中央。左。「安政3年(1856)3月20日より60日間、深川永代寺で出開帳が行われました。成田山新勝寺の本尊である不動明王は元禄16年(1703)から幕末までに江戸での出開帳を計11回おこないました。開帳とは、厨子や戸張を開いて普段は見ることの出来ない秘仏を拝観させ、民衆と結縁する宗教的行事のことです。この作品は、江の島コーナーに展示されているN0.28「江の島弁才天開帳参詣群衆之図」と同じ構図で描かれています。作者も同じ歌川国郷です。」 「不動明王像の御影」。 「現在の千葉県鴨川市にある安国大山寺不動堂の不動明王像の御影です。御影(おみえ、みえい)とは神仏、貴人、聖者などの姿を紙などで現したもので、神仏の肖像として寺社に参詣した際、授けられるものです。安房国大山寺の開基は良弁上人といわれ、お告げによって安房国に不動明王を鎮座したとされています。」 「不動明王像」。 「歌川国利 千葉県下下総国埴生郡 成田山新勝寺境内一覧 明治14年(1881)」。 「明治十八年の成田山新勝寺の境内を描いた浮世絵です。鮮やかな色彩もあって、成田山の賑わいが伝わってきます。画面右下には成田講でしょうか、多くの人々がこれからお参りする様です。作者の歌川国利は、明治時代に活動した浮世絵師で名所絵のほか、明治以降の人々の様子や建造物などを描いた開化絵や風俗画、銅板の地図の作成もおこないました。」 「中路定俊 成田参詣記(成田名所図会) 五👈️リンク」 「表紙には「成田名所図会」と記載していますが、江戸から成田山参詣までの各地の名所や旧跡の説明がされています。今回展示しているのは5巷で、成田山について詳しい説明がされています。また、成田山のほか宗吾霊堂など付近の寺社のことも書かれています。」 「豊原国周 成田不動尊御着御道筋諸人群集図 明治6年(1873)」。「画面左側には、多くの講中の旗がはためいています。手前の人々が持っているうらわには、「龍王講」と書かれています。龍王講は、龍神を信仰する目的で江戸時代に成立された講のひとつです。成田山新勝寺の本尊は不動明王ですが、様々な神仏が祀られており、その中に龍神がいることから、参拝にきた講と考えられます。」 「成田不動と市川団十郎成田山新勝寺の不動明王といえば、歌舞伎役者の市川団十郎の名前は欠かせません。子どもがいなかった初代団十郎が、成田山新勝寺の不動明王に子授けを祈願したところ九蔵(後の二代目団十郎)が誕生しました。九蔵は「不動の申し子」として元禄十年(1697)十歳の初舞台で不動明王を演じます。九蔵が演じた不動明王は江戸の観客たちの評判となり、成田山には連日信者が参拝したといわれます。このように神仏の霊像に扮して舞台に現れる演技を「神霊事」といいます。元禄時代の江戸で成立し、初代、二代目団十郎の得意芸となります。また演技がピークに達したとき、顔の表情やポーズをそのままにしてしばらくの間動かないでいる「見得」という歌舞伎の芸があります。九蔵を改め三代目団十郎は自作「不動の見得」を披露しました。「不動の申し子」である二代目団十郎に睨まれるとあらゆる病が治るという噂が流れ、団十郎の名とともに不動明王信仰を広めることにもなりました。その後も代々の団十郎が不動明王を演じ、成田山新勝寺へ一門で参詣をしました。その中でも。名優といわれた七代目団十郎は毎年弟子たちを連れて成田山新勝寺へ参詣し、多くの供物や金品を奉納しています。しかし、天保の改革によって七代目団十郎の派手な生活が禁令に触れてしまい、江戸を追放されるという事件が起こります。その息子である八代目団十郎は、成田山不動明王に参詣し、父の放免を祈願しました。嘉永2年12月、七代目の追放処分がとかれることになり、八代目の親孝行に加えてさらに不動明王の霊験が人々に伝わることになりました。成田山新勝寺には、代々の団十郎が奉納した鏡などの品々が残され、不動明王信仰と市川団十郎の関係を今に伝えています。」 「歌川国貞(三代豊国) 成田山不動の霊像 弘化4年一嘉永5年(1847-522)」 「歌舞伎の演目「源氏模様娘雛形」の話の中で、身を投げた平野屋徳兵衛が成田不動の索によって川の中から引き揚げられる場面を描いています。徳兵衛を演じた八代目団十郎は、大病を患ったとき、成田不動に祈願したところ全快し命を救われたというエピソードがあります。不動明王の索によって川から引き揚げられる徳兵衛と重なるようです。」 「豊原国周 奈智瀧祈誓文覚 明治22年」。 右から。中央。左。「「奈智瀧祈誓文覚」は九代目市川団十郎によって明治22年(1889) 6月に中村座で上演されました。誤って同僚の妻を殺してしまた遠藤盛遠が出家し文覚となり、厳寒の那智の滝で荒行を行っていると、矜羯羅童子と制多伽童子を従えた不動明王が現れます。演目では、団十郎演じる文覚が那智の滝壺に飛び込み、早替りで不動明王になるという演出を行いました。九代目団十郎も成田山の不動明王信仰を受け継ぎ、不動明王を演じる際は成田山新勝寺へ参詣し、自筆の不動明王像を寄進していました。」 「濱田吉五郎出版 成田山奉納附 明治18年(1885)」 。「奉納とは寺社に参する際のお賽践とは別に、食物や酒、金銭などを神仏に供物として捧げることです。神仏を敬い、御魂を鎮め愉しませることを目的としてはじまりました。成田山へ奉納した供物や金銭の内容から、成田山の不動明王とともに信仰されていた芝山仁王尊と宗吾霊堂へ奉納した供物も描かれています。神仏に対する当時の信仰が読み取れます。」 「歌川国貞(三代豊国) 七代目市川団十郎成田参詣の図 文化12年-天保13年(1815-42)」 「8枚続の一図です。文化・文政期に一世を風靡した人気歌舞伎役者「成田屋」七代目市川団十郎が赤子を連れて成田山新勝寺に宮参りをする図とされています。描かれている赤子は、文政6年10月5日に、生れた新之助です。新之助は後に八代目団十郎になりました。 」 「歌川国貞(三代豊国) 成田山繁栄乃図 弘化4年-嘉永5年(1847-52)」。「成田山新勝寺に詣でる市川家の歌舞伎役者を描いています。左から2番目に描かれる七代目団十郎(この時は、海老蔵と名乗る)をはじめ、市川家一門の役者たちが後に続きます。成田山神勝寺との関係は、初代市川団十郎の信仰から始まり、以降代々の団十郎が参詣し厄災消除のほか芸事上達などを願って不動明王への信仰を深めました。」 「歌川国貞(三代豊国) 成田山開帳参詣群集図 安政3年(1856)」。「歌舞伎役者たちが成田山新勝寺の開帳にあわせて参詣にきている様子を描いています。成田山新勝寺は、初代市川団十郎の信仰から江戸時代に多くの人々に知るられるようになりました。歴代の団十郎の中でも七代目は門弟を連れて毎年参詣し、多くの奉納品を納めて新勝寺と市川家の関係を深めたとされます。」 「歌川国資(三代豊国) 御礼参り贔屓船之図 弘化4年-嘉永5年(1847-52)」 「江戸から船で成田詣に行きうときには、江戸川を上り、関宿から利根川を下り、木下・安食河岸に出て そこから陸路を成田に向う道中となります。背景には筑波山が見えており、前景に描かれた2艘の船に乗るのは、大絵馬の奉納に向かう歌舞伎役者の一行です。」 「三代歌川広重 下総国成田山新勝寺各講中坊入饗応之図 明治22年(1889)」。 「江戸時代から各地で「成田講」と呼ばれる団体がつくられ、成田山へ参詣していました。成田山に入った講の人々が朝護摩という儀式に参加し、本坊にて精進料理とお神酒が振舞われることを「坊入り」といい、その様子を描いたものとされます。講と寺社の関係も垣間見える作品です。」 「三代歌川国貞(四代国政) 成田山 芝山 宗吾神霊 開帳けん 明治18年(1885)」 「市川団十郎の成田山不動明王、中村芝翫の芝山仁王、尾上菊五郎の宗吾神霊がそろって描かれています。今の成田市竹近において信仰され、深川でそろって出開帳がおこなわれました。」 「三代歌川広重東京深川公園ニ於テ下総成田不動尊 幷芝山仁王像宗吾霊像 開帳参詣群集之図明治18年(1885)」 「明治18年(1885)に深川公園にて成田山の不動明王と、同じく信仰されていた芝山仁王尊、そして佐倉藩(現千葉県佐倉市)の名主として実在し、幕府に藩の圧政を直訴したとされる佐倉惣五郎の霊像の開帳です。深川公園は、富岡八幡宮の別当(神社を管理するために置かれた寺のこと。神仏習合時にみられる。)であった永代寺があった場听です。明治政府の神仏分離によって寺院が廃寺などに追い込まれましたが、多くの人々が参詣している様子からも不勳明王信仰が続いていたことがわかります。」 「三代歌川広重 成田土産名所尽 明治23年(1890)👈️リンク」「三代歌川広重による作品で、東京から成田への道中を描いています。東京から途中で船を使った道順で、東京深川新大橋蒸気船発着場を出発し、市川の渡し、行徳新河岸、船橋大神宮、習志野松原、大和田駅、臼井、佐倉、中川(現酒々井付近)、そして成田山本山が描かれています。」 「歌川国梅 東京深川成田山繁栄群集之図 明治18年(1885)」。正面から。ネットから。「東京の深川で行われた成田山不動明王の開帳の様子を描いています。江戸時代には成田山の出開帳は深川の永代寺で行われていましたが、明治時代になると、神仏分離によって永代寺は廃寺となります。その後は永代寺の跡地である不動堂(現深川不動尊)で開帳が行われました。開帳と書かれた大うちわが所々に描かれ、講中や一般の参詣客も混じって大勢の人々で賑わっています。明治になっても、成田山不動明王の信仰は続いていたことがうかがえます。」 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.05.07
コメント(1)
-

藤澤浮世絵館・『江戸の祭神 弁財天と不動明王』展へ(その4)
「江の島富士山を別格とすれば、浮世絵に描かれた風景の中で、その数では江の島は、かなりの上位に入ると言えましょう。それほどに、江戸時代の江の島詣では一大ブームでした。江の島は、湘南海岸と砂州でつながった島です。波の侵食でできた「岩屋」の存在は、古くから宗教的な修行の場として多くの修行者の来訪を伝えていますが、鎌倉時代に源頼朝の祈願により文覚が弁財天を勧請したという由来から、弁財天の島として信仰を集め、また風光明媚な行楽の地としても人気を得るようになりました。浮世絵では、初期には富土山や朝日などとセットで中国の神仙思想にある蓬莱山に擬して描かれたものが多く、江の島詣でが盛んになるにつれ、参集する人々を描いたものか多くなっています。」 「江の島三社各々の弁財天の由来と来歴を記した記録です。本宮(奥津宮)弘法大師空海が弘仁5年(814)に岩屋に参籠した際、弁財天が現れ、神託をあたえます。弘法大師はこれに敬服し、岩屋に自刻した弁財天像を納め、本宮を創建しました。上之宮(中津宮)仁寿三年(853)に天台座主の慈覚大師円仁が岩屋に参籠します。その際に弁財天が現れ、お告げをします。円仁はその後、自刻した弁財天像や仏舎利を岩屋に納め、江の島に上之宮を建立しました。下之宮(辺津宮)正治元年(1199)に鶴岡八幡宮の良真が江の島に参籠し、千日の修行したのちの建仁2年(1202)に弁財天が現れ、社殿の荒廃を嘆きました。良真は中国に渡って地鎮の石(宋国伝来の石。神社に現存)を持ち帰り将軍源実朝に社殿の建立を進言し、建永元年(1206)に下之宮が創建されました。」 「江島三社辯財天来歴 寛延2年(1749) 文化3年(1806)再刻」。 「作者不詳 江之島金亀山三宮細見之図」。 「本図は江の島の島内全体を詳細に描いた絵図です。江の島の北側から描いていますが、本来なら画中に見えない位置にある南側の岩屋なども描かれ、江の島全体が画中に全ておさまっています。金亀山(きんきざん)とは江の島の別名です。本宮の別当てあった岩本院は、慶安2年(1649)に京都の真言宗御室派仁和寺の直末寺となり「金亀山與願寺(よがんじ)」の寺号を称しました。江の島は初期の浮世絵では霊亀の背中に存在するともいわれる蓬莱山のイメージを仮託されていることがおおく、また実際の島の形が亀に似ているともいわれているため、江の島は亀のイメージが定着していたようです。」 「江戸の祭神 弁財天と不動明王① ~弁財天信仰~弁財天は河川の女神サラスヴァティーとして古代インドで信仰されてきました。日本に伝わった頃は学芸、福徳を授ける他に国家鎮護のご利益があるとして朝廷や貴族といった身分の高い人々を中心に信仰を集めていました。次第に日本古来の神とされる宇賀神(また稲荷神)と習合し、財運や五穀豊穣を授けるとして信仰の広がりをみせます。江の島コーナーては江の島弁財天に関連する資料と、御開帳などを描いた浮世絵を展示し、時代を経て信仰され続ける弁財天の世界を紹介します。」 「歌川国貞(三代豊国)) 題名不詳(弁才天と北條時政) 文政10年-嘉水年間(1827-53 )」。 「江の島にはさまざまな由緒や伝説がありますが、北条氏の家紋である「三つ鱗」のいわれも、その一つです。鎌倉幕府の初代執権であった北条時政(源頼朝の妻の父)は、子孫繁栄を願って江の島の岩屋に籠り祈願していたところ、満願の夜に弁財天が現れ、願いを聞き入れることを約束し、大蛇(龍蛇神)の姿となって海に消えて行き、あとには3枚の鱗が残されていたというものです。時政はその鱗を、北条家を繁栄に導くしるしとして家紋としたといわれています。」 「歌川国安 相州江ノ嶋弁財天 巌屋祭礼之図 文政年間(1818-30)前期」 「弁オ天開帳の際に江の島の岩屋に集まる人々が描かれています。画面左から中央にかけて華やかな着物姿の女性たちが描かれ、画面右には海女や神事を行う人々、後ろからは祝い装束の子どもたちまでやってくる様子も見られます。開帳時の賑やかな江の島の雰囲気をよく伝える作品です。」 「歌川国安 相州江ノ嶋 弁財天巖屋 祭禮之圖👈️リンク」。 以下、ズームして。「歌川広重 江の嶋弁オ天開帳詣 嘉永4年(1852)」。 ネットから。「嘉永4年(1851)の開帳の際に発行されたものです。江の島の砂洲を背景に、3人の美人が揃い立ちます。面中央の女性は、長着の着物の上から浴衣を着ています。このように、着物の上から浴衣を羽織るのは、旅の際に合羽の代用として用いられたもので、海辺の旅となる江の島詣では潮風を防ぐ必需品であたのでしよう。」 右からズームして。中央。左。「歌川広重 相川江之嶋弁才天開帳参詣群集之図 弘化4年-嘉水5年(1844-53)頃」 「江戸後期になると、人々の間で講中を組んで江の島へ参詣することが盛んになり、特に六年に一度の開帳の時は多数の参詣者で賑わいました。本作では江の島詣に向かう芸能の女性たちによる講中を、揃いの日傘で描き分けています。まず中央の列の先頭は「三本の竿」の江戸長唄杵屋、それに続く「菱に三つ柏」は清元節、その左は「角木瓜」の常磐津節、画面右の「桜草」の一群は富本節の人々です。」 近づいて。富士山と帆掛け船の姿。「作者不詳 相州江ノ場弁オ天上下ノ宮己巳年御開帳繁栄之全図 文化6年(1809)」 「落款、版元印ともになく作者不詳となっています。極印が半分に切れているので、元の大きさは現在のものより少し大きかったと考えられます。弁財天の開帳を描いた作品は多くありますが、表題に開帳の場所や年を明記している点が珍しい作品です。また、江の島では海士と呼ばれる男性が鮑取りをしていました。多くの作品で鮑取りをしているのは女性として描かれていますが、この作品では男性の姿で描かれている点も注目されます。」 「歌川国郷 江の島弁弁才天開帳参詣群衆之図 安政3年(1856)」 「安政3年(1856)に江戸の深川八幡宮で行われた江の島弁弁財天の山開帳の賑わいを描ています。実際の安政3年の山開帳は、荒天により人出が少なかったとの記録がありますが、この作品では大勢の人で賑わいを見せています。これは、山開帳の事前に山版されたもので、想像上の群衆を描いています。この作品は、企画コーナーに展示されているN0.30「成田山開帳参詣群集之タ景」と同じ構図で描かれています。作者も同じ歌川国郷です。」 「作者不詳 題名不詳(弁財天十五童子像) 江戸時代中期」 近づいて。「本図の弁財天は、八臂の姿で、頭上には鳥居と蛇の姿の宇賀神(日本古来の穀物神)を戴いています。これは宇賀神と習合し、福神としての側面を強めた日本弁財天です。持物が琵琶ではなく、武具であることから、戦闘神としての性質が強く表されています。図面下部には眷属である十五童子が描かれています。『江嶋縁起』によると弁財天は欽明天皇13年(552)に大地振動して江の島が海底より出現した際に、眷属である十五童子とともに降り立ったとされています。」 「弁財天と十五童子十五童子とは、弁財天の身の回りの世話をしたり、弁財天の福徳を授けるのを手伝う従者です。十五の童子ですが、善財童子を加えて十六童子と称することもあります。印鑰童子・・悟りや解説へ導く童子(右手に宝珠、左手に鑰(かぎ)を持つ)飯櫃童子・・食物授与の童子(満たされた飯櫃を持つ)衣裳童子・・衣服に不自由しない童子(手に衣裳を掲げる)蚕養童子・・蚕、繭の童子(衣類の神てあり、両手に蚕を人れた箱を持つ)酒泉童子・・酒の童子(酒瓶の側に立ち、杓て酒を汲んている)稲籾童子・・五穀豊穣の童子(肩に稲の束、手に宝珠を持っ)船車童子・・交通安全の童子(船と牛車を傍に置く)生命童子・・長寿の童子(右手に宝剣、左手に宝珠)牛馬童子・・動物愛護の童子(牛馬と共にいる)愛敬童子・・愛情、恋愛成就の童子(右手に矢、左手に弓)官帯童子・・法を守る童子(手に官位を司る帯を持つ)従者童子・・経営の童子(手に宝袋)計升童子・・経理、経営の童子(両手に升)金財童子・・金銀財宝、商売繁盛の童子(手に秤の糸と秤量)筆硯童子・・学問成就の童子(筆と硯を持つ)善財童子・・金と福を授ける童子(金や宝が入った袋を持つ)※展示されている「弁財天と十五童子像」は十五童子てあり、手に持つ物も作品によって異なる場合がございます。」 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.05.06
コメント(0)
-

藤澤浮世絵館・『江戸の祭神 弁財天と不動明王』展へ(その3)
「翔んで!浮世絵 空から藤沢」 の約10分のビデオを見る。上空からの江の島。ズームして。渓斎英泉画「東海道五拾三駅名所古跡略記道中双六」より「鎌倉江之島廻路図」。「東海道五拾三駅名所古跡略記道中双六」「鎌倉江之島廻路図」「歌川国貞「東海道名所之内 鎌倉七里が浜の風景」」 ネットから。「江之島名勝江の島そして手前に小動岬」 。現在の上空からの写真。ズームして。江の島そして手前右側に小動岬そして腰越漁港。昭和初期の絵葉書「龍口遊園地よりの展望」。 現在の「湘南モノレール・湘南江の島駅」手前上空から 境川・相模湾を見る。「昭和初期の絵葉書「藤沢宿通り」」 。現在の「藤沢宿」と「富士山」。 「昭和初期の絵葉書「藤沢名所 市街の一部」」 。「歌川国綱「東海道名所之内四ツ谷」」。 「勝典作画「藤沢トラフィック図」南半分」。「四ツ谷不動尊」と「大山道入口」右手に田村通り大山道入口の石鳥居が。「四ツ谷不動尊」の「不動明王像」。 「広重「東海道 七 五拾三次之内の内 藤沢(四谷の立場)」 絵からは旅人相手の茶屋が建ち並んでいたにぎわいが感じられる。この地は大山道と東海道の分岐点で旅人はここで休息後、再び大山に向けて出発して行った。絵の手前左端に“四谷不動堂の道標”が見える。「歌川広重 東海道五十三次細見圖會 藤澤 平塚江三里半」。縦位置の図の上半分に各宿から次の宿までの道程を俯瞰的に眺めたものを描く。歌川広重「東海道五十三次細見図会 藤沢平塚江三里半」。正面には道中風俗「草原野休の図」が描かれていますが、背景の風景画は藤沢宿の「名所案内図」になっています。範囲は、東(左手)は「かまくら」「七面山(龍ロ寺)」「片瀬」「遊行寺(小栗の旧跡)」「江の島」から、西(右手)は「南湖立場」「四ツ谷追分」「大山道」までが描かれています。下半分には街道で見られる旅人の風俗画を描いている。 「歌川広重 東海道五十三次細見圖會 七 藤澤 南湖の松原 左り不二」。本図は、藤沢の宿を過ぎ、馬入川に至る途中の松並木が続く風光明美な所で、畝々と曲がる東海道を描く。「吉原左富士」とともに街道の左に富士の見える「南湖の松原左富士」として有名であった。広重晩年の竪版風景画揃物の一つで、他に「富士三十六景」「名所江戸百景」「六十余州名所図会」がある。藤沢(四谷の立場)の上空からの写真。「南湖の左富士碑」上空からの富士山の姿。「歌川広重「五十三次名所図会 八 平塚馬入の渡し大山遠望」(竪絵東海道)」。茅ヶ崎側から相模川を挟んで平塚側を望んでいる。対岸には馬入村が描かれており、富士山・大山・丹沢山を遠望することができる。現在の航空写真。「馬入の渡し跡」上空からの写真。 「遊行寺坂」上空から「遊行寺」「江の島」方向を見る。 「遊行寺坂」。 「遊行寺」周辺。 ズームして。「貞秀 「東海道名所風景 東海道名所之内 ふちさは遊行寺」(御上洛東海道)」。 「歌川広重「東海道五拾三次之内 藤沢」保永堂版東海道」。製作時期1832~1833年。江の島一ノ鳥居付近。背景の小山は遊行寺。この画は藤沢宿にあった江の島一ノ鳥居を遊行寺を背景にして描いたもので、副題も「遊行寺」となっている。鳥居の後ろに架かる橋は大鋸橋(現遊行寺橋)です大鋸橋の上で鉢巻をして大きな木太刀を担いでいる人は、これから大山詣りに行く人。大山(標高1253㍍。大山阿夫利神社があります)の大山石尊大権現は商売繁盛の神として多くの参詣者を集めていた。大山詣りでは、神社に木太刀を納めるということが行われていた。他ではない独特の様式だった と。 「歌川広重「東海道五十三次之内一藤沢」(行書東海道)」。 「遊行寺橋 (旧 大鋸橋)」。昭和35年に造られたPC桁橋である。この先が、「遊行寺」の「惣門」、「いろは坂」。 「江の島弁財天 道標」 「浮世絵の鳥居近くにあった道標は現在も健在です。」 この道標は、管を用いて鍼をさす管鍼術の考案者で、江の島弁財天を厚く信仰していたといわれる杉山検校が、江島神社に参詣する人々が道に迷うことのないようにと寄進したものと伝えられ、この他に市内にほぼ同形の道標が12基指定されている。「歌川広重「東海道之内江の嶋路片瀬七面山見浜辺(かたせしちめんざんより はまべをみる)」。片瀬から見た江の島を描いた風景です。構図としては、江の島を高い視点から見おろすように捉え、前景に七面山、中景に龍口寺の門前にある家々を配置し、正面には潮の引いた道を江の島へ向う人々が点のように描かれています。片瀬は江の島に直面する陸地の部分ですが、このように画題として取り上げられるものはあまりなく、珍しい図柄の作品と言えるでしょう。画題にある七面山は旅人が休息している左手の山で、日蓮宗龍口寺の裏山にあたります。 「昭和初期の絵はがき「片瀬より江の島全景」」。 現在の江の島を藤沢市片瀬3丁目の上空から。「歌川広重「相州江之嶋弁才天開帳参詣群集之図」」。 江の島の弁財天は、技芸の神として信仰を集めた。特に音曲の世界では講中を組んで江戸から参詣することが多く、六年に一度の開帳の時は、多数の参詣人で賑わったといわれる。ここでも江の島参詣に向かう四組の女講中を揃いの日傘で描き分けている。画面では、江戸長唄の杵屋、清元節、常磐津節などの人々である。「葛飾北斎「富岳三十六景 相州江の島」」。片瀬海岸から江の島を見たところです。江戸時代は、江の島弁財天は江戸から格好の小さな旅先でした。砂洲の参道が現れれているところから、今は干潮時のようです。人々や馬、駕籠など参詣に行くようです。参道の両側に旅館や土産物が軒を連ねています。三角形の屋根は、定規を使って引いたような直線で描いています。その屋根の上の三重塔は、江島神社上之宮の塔です。右端に船を描き、その先の富士に視線を求めています。波打ち際の波の泡の描写など静かな春を思わせます。多少誇張や演出で描く北斎には、珍しく自然な景観を描いています。「歌川広重「相州江之嶋之図」」。 現在の江の島、トンボロ現象時の写真。「昭和初期の絵葉書「江之島桟橋」👈️リンク」。「歌川広重「相州江の嶋弁財天開帳本宮岩屋の図」」。弘化4年~嘉永5年(1847~52)「国貞の弟子であるニ代国貞(四代豊国)と、広重の弟子の二代広重による共筆作品です。江の島の岩屋の前で、海女の親子が海中から鮑を採ってくるようすを、将軍が上覧している場面でしよう。ただし、実際に家茂が上洛の途中て江の島へ寄った事実はなく、源頼朝に仮託したものと考えられます。画面中央の波を境に、陸上のようすをニ代広重が、海中のようすをニ代国貞が描いており、師匠同様に、風景描写に長けたニ代広重、人物が得意なニ代国貞が、それぞれの手腕を発揮しています。 全体図をネットから。江戸時代は、芸能にご利益のある弁財天を詣でに、様々な芸能関係の人が江ノ島に詣でていました。『相州江ノ嶋弁才天開帳詣本宮岩屋の図そうしゅうえのしまべんざいてんかいちょうもうでほんぐういわやのず』では杵屋きねや、清元きよもと節、常磐津ときわづ節の女性たちが列をなして島に向かっています。「昭和初期の絵葉書「岩屋入口」」。「昭和初期の絵葉書「岩屋拝殿」」。江の島の岩場の航空写真。江の島シーキャンドルの姿が。江の島サムエル・コッキング苑の中にある展望灯台で、苑と同じく平成15年(2003)にリニューアルされた。避雷針まで入れた高さは59.8m(海抜119.6m)あり、その斬新なスタイルは江の島の新しいシンボルとして親しまれている。高さ41.75m(海抜101.56m)のところにガラス張りの展望フロア、さらにその上には屋外展望台があり、富士山や丹沢などのワイドな眺望が楽しめる。1階にはエントランスのほか、カフェや郷土資料室などもある。相模湾上空からの江の島の全景。近づいて。「渓斎英泉画「東海道五拾三駅名所古跡略記道中双六」より「鎌倉江之島廻路図」」。「東海道五拾三駅名所古跡略記道中双六」。「菅笠を被った旅装束の女性が、若い娘が引く牛に乗り、七里ガ浜の浜辺を悠々と行く様子が描かれています。海はやや波立ち、海上には船の白い帆が漂っています。波打ち際を見ると、若干の雲母が施される等、摺りの工夫が見られます。「昭和初期の絵葉書「七里ヶ浜の絶景」」。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.05.05
コメント(0)
-
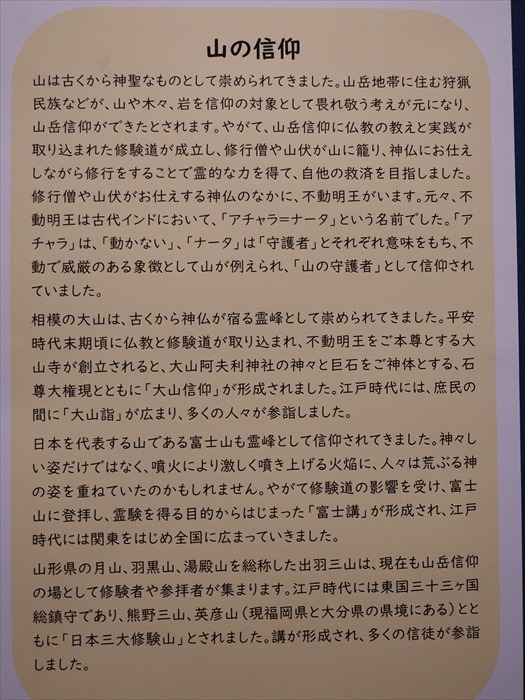
藤澤浮世絵館・『江戸の祭神 弁財天と不動明王』展へ(その2)
「山の信仰山は古くから神聖なものとして崇められてきました。山岳地帯に住む狩猟民族などが、山や木々、岩を信仰の対象として畏れ敬う考えが元になり、山岳信仰ができたとされます。やがて、山岳信仰に仏教の教えと実践が取り込まれた修験道が成立し、修行僧や山伏が山に籠り、神仏にお仕えしながら修行をすることで霊的な力を得て、自他の救済を目指しました。修行僧や山伏がお仕えする神仏のなかに、不動明王がいます。元々、不動明王は古代インドにおいて、「アチャラ=ナータ」という名前でした。「アチャラ」は、「動かない」、「ナータ」は「守護者」とそれぞれ意味をもち、不動で威厳のある象徴として山が例えられ、「山の守護者」として信仰されていました。相模の大山は、古くから神仏が宿る霊峰として崇められてきました。平安時代末期頃に仏教と修験道が取り込まれ、不動明王をご本尊とする大山寺が創立されると、大山阿夫利神社の神々と巨石をご神体とする、石尊大権現とともに「大山信仰」が形成されました。江戸時代には、庶民の間に「大山詣」が広まり、多くの人々が参詣しました。 日本を代表する山てある富士山も霊峰として信仰されてきました。神々しい姿だけてはなく、噴火により激しく噴き上げる火焔に、人々は荒ぶる神の姿を重ねていたのかもしれません。やがて修験道の影響を受け、富士山に登拝し、霊験を得る目的からはじまった「富士講」が形成され、江戸時代には関東をはじめ全国に広まっていきました。山形県の月山、羽黒山、湯殿山を総称した出羽三山は、現在も山岳信仰の場として修験者や参拝者が集まります。江戸時代には東国三十三ヶ国総鎮守であり、熊野三山、英彦山(現福岡県と大分県の県境にある)とともに「日本三大修験山」とされました。講が形成され多くの信徒が参詣しました。「萬古庵 相模国大山全図 明治期」。 大山の全体図を描いています。入口の鳥居から山頂まで細かく描かれており、右下には阿夫利神社や大山寺の不動尊の例祭が記載されています。「歌川国芳 大山良弁滝 弘化4年--嘉永5年(1847-52)」。「良弁の滝で身を清める勇ましい男性たちの姿が描かれています。大山の山頂までの登拝が許される夏の例祭は、短期間に限られていたので、その間に大勢の参拝客が押し寄せたであろうことが想像される一枚です。また、前不動から山頂までは女性の参拝は禁止されていたので、女性の姿が描かれていない点も大山を描いた浮世絵の特徴の一つです。」 「ニ代歌川広重 冨士山東ロ須走り之図 文久元年(1861)」 「富士山の真東にある須走ロの浅間神社の鳥居の前に集まる人々の様子を描いています。菅笠に白装束をまとい、首から数珠をかけた先達(登山の案内人)が描かれています。何人かが肩に背負っているのは、御三幅の入った札箱です。御三幅とは登拝の際に祭壇に掲げる3本の掛軸のことで、御身抜(富士信仰の世界観を表した掛軸)、浅間神社の祭神である木花咲耶姫命の御影(神仏の姿を絵に描いたもの)、小御嶽神の掛軸、をいいます。この画は、もともと団扇に仕立てるために摺られたものが、使用されずに残ったものです。」 「霞峰画 歌川広重模写 湯殿山道中畧圖(りゃくず) 」。 「湯般山を背景に、羽州街道の町並みを描いています。湯殿山は画中に見える月山や羽黒山とあわせて山羽三山と総称され、古来より霊場として信仰を集めていました。本作は山羽国(現在の山形県)の絵師・霞峰の作品を初代広重が模写したものと考えられており、画面左下には「霞峰先生図 東都ー立斎広重 応需 模写」と記されています。」 「縁起絵巻(写本)にみる信仰縁起とは、仏教用語て様々な原因や条件によって物事は起きるという意味の他に、寺社仏閣、仏像や経典などの由来や沿革も意味します。本来は漢文で寺社の由来などが表記されていましたが、平安末期頃から絵を伴った霊験を説く縁起絵巻の制作が盛んになりました。その霊験をあまねく広めるために数々の写本が制作されました。藤沢宿コーナーては、「粉河寺縁起絵巻(写本)」と「住吉物語絵巻断簡(写本)」を展示し、縁起絵巻の世界を通して人々の神仏に対する信仰を紹介します。」 「猪飼嘯谷 住吉物語絵巻断簡(写本) 制作年不詳」 「住吉物語絵巻断簡の写本です。断簡とは、劣化により糊がはがれたり、意図的に切り取られてしまった絵巻物などを、鑑賞用として掛け軸に仕立て直したことをいいます。住吉物語は鎌倉時代に成立された継子いじめ譚(後妻が先妻の子を冷遇、または虐待する昔話の一種。)に分類される物語です。中納言の姫君が、少将との仲を妬む継母の悪だくみを避けて住吉に住む尼のもとへ隠れます。やがて長谷の観音菩薩の導きで尋ねてきた少将と再会し、都へ戻って幸せに暮らすという内容です。展示展示されているのは、物語の後半部分とされ、京都生まれの日本画作家、猪飼嘯谷( 1881 -1939 )によって写されたものと伝えられています。」 「住吉物語の主人公、中納言の姫君は早くに母を亡くし継母に育てられます。姫君は美しく成長し、少将少将は想いを寄せます。しかし、いじわるな継母の悪だくみから逃れるため、姫君は住吉へと隠れることになります。姫君のことを忘れられない少将は、夢に現れた長谷観音のお告げによって住吉という場所にたどり着きます。」「描かれているのは、少将という青年です。長谷観音のお告げによって住吉の地にたどり着いたところです。聞こえてくる琴の音をたよりに、少将は住吉の尼が住む家にたどり着きます。」 尼の屋敷でかっての侍従(主人の側に仕える人)と出会います。姫君が尼の屋敷にいることがわかった少将は尼と対面します。」 「画面左下には少将と侍従と思われる人物が描かれています。侍従に導かれて、少将は姫君がいる部屋へと案内されるところでしようか。さらに画面左上には、姫君、部屋を隔てて少将と侍従が描かれます。」 「少将が住吉にいることが人々に知れ渡り、京の都から少将にゆかりのある人々も訪れてきました。少将と姫君が結ばれたことを祝い、友人たちが管弦の遊びを開いている場面です。」 「姫君と少将は無事に再会することができ、ニ人は結ばれます。描かれる人々は、尼と姫君に仕える人々で、姫君と少将の結婚の祝宴を浜辺で催しているところとされています。」 「姫君と少将は京へ戻ることになりました。尼は住吉に残ることになり、姫君と別れを惜しみました。少将と姫君を乗せたと思われる鴛韲は、住吉の浜へと向いいその前と長ろにはお供の人々が付き添っています。」 「住吉の地て再会したニ人は、船に乗って京の都へ戻りました。画面にはお供の人々と、ニ人が乗った船が描かれています。都に戻たニ人は子を授かり、幸せに暮らしたというところて物語は終盤を迎えます。」 「さても京にのほりつきて、殿にまゐり給、あやしきありきし給とてむつかりなから、北の對をしつらひてすませきえ給けり。」が正しいようだ。 「訳さて、京都に到着して中将が父の邸へ参上なさると、妙な行動については不機嫌であったものの、北の方を設けて姫君をお住ませになった。※少将は姫君に会う前に出世して、中将となっていました。住吉で姫君と再会した少将(中将)が、父である関白に報告をするところてす。父の関白は勝手に住吉に行った少将(中将)に対して不機嫌でしたが、無事に息子である少将(中将)が戻ったことで、姫君のことも受け入れてくれました。」 「猪飼嘯谷 粉河寺縁起絵巻(写本)」 「粉河寺縁起絵巻の前半は、粉河寺の由来を描いています。紀伊国那賀郡に大伴孔子古という猟師がいました。いつものように、猪などを追いかけて狩りをしていたところ、山中で不思議な光を見つけます。その光は、次の日もそのまた次の日もありました。孔子古は、自分が信仰する仏が見せた光であると思い、この地に庵を建てました。ある日、一人の童が孔子古の元を訪れ、一晩泊めてほしいと頼みます。泊めてくれたお礼に、童は孔子古が建てた庵に仏像を造ることを約東します。庵に入った童は、「自分が仏像を彫っている7日間は決して庵に入らないようにと告げました。」 「約束の日が過ぎ、孔子古が庵にやってくると、童の姿はなく、庵の中には、千手観音菩薩が安置されていました。孔子古は、妻や近隣の者たちに伝え、人々は参詣し千手観音菩薩に帰依(仏を信じ、その教えに従うこと)したといわれます。この庵が後の粉河寺となりました。」 「粉河寺縁起絵巻後半の部分です。屋敷の中で床に臥せている女性がいます。よく見ると、顔や体に赤い発疹のようなものができています。この女性は河内(現大阪府)に住む長者の娘です。長く病気を患っていましたが、そこへ童行者が訪ねてきます。童行者は、子どもでありながら修行僧のような存在で登場します。画中では、左側に描かれている人物が童行者です。長く髪を伸ばし、白い浄衣に袈裟をまとった出で立ちです。病気を患ている長者の娘に千手陀羅尼というお経をあげています。」 「童行者がお経をあげたところ、やがて長者の娘は病気から快復しました。長者はお礼にと多くの宝物を差し出しますが、童行者は断ります。童行者は、娘から捧げられた赤い袴とさげざや(僧侶などが持つ小刀)のみ受け取ると、「紀伊国那賀郡粉河の者だ」と告げて去りました。画中では、左側に童行者が描かれ、長者夫妻と娘が感謝している様子がみえます。右側に描かれる人々は長者に仕える人たちでしようか、宝物を運んだり、童行者を見ようと部屋を覗いている人もいます。」 「翌年の春、長者一家は粉河を訪ねました。娘の病を救った童行者を探していましたが、見つかりません。とある川で休んでいると、流れる水が自いことに気づきます。その川を辿っていくと、庵がありました。庵の扉を開くとそこには千手観音菩薩が安置されていました。千手観音菩薩の手には童行者に捧げた赤い袴と、さげさやがありました。長者一家は、娘の病を治した童行者は、千手観音の化身であったことに気づきます。長者一家は深謝したのち、出家し仏門に入りました。画面中央には、赤い袴とさげさやを持っている千手観音菩薩が描かれ、その前では長者の娘でしようか、長い黒髪を僧侶に剃り落としてもらうところのようです。」 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.05.04
コメント(0)
-

藤澤浮世絵館・『江戸の祭神 弁財天と不動明王』展へ(その1)
かなりブログアップまで時間がたってしまったが、昨年末・2024年12月13日(金)、藤沢市内にある「藤澤浮世絵館」を訪ねた。「タイムズ湘南シークロスパーキング」に車を駐め、「藤澤浮世絵館」に向かう。 この日の目的は『江戸の祭神 弁財天と不動明王』展の鑑賞。「藤澤浮世絵館」は藤沢市辻堂神台2-2-2 ココテラス湘南の7Fにある。「Cocco Terrace ココテラス湘南」 案内板。「Cocco(ココ)」は、イタリア語で「かわいい子、秘蔵っ子」などを意味する と。「Terrace(テラス)」は、屋外フロア、バルコニー」のことです。「ココテラス」は、日本語で「此処を照らす」明るい子どもたちの未来の言葉にかけられているのだ と。1Fロビーにあったクリスマスツリー。そして7Fの「藤沢市 藤澤浮世絵館」入口へ。「浮世絵とは」浮世絵とは、江戸時代に発達した版画絵のことです。現実の世相や風俗といった「浮世」を描いた絵画です、その名は17世紀中頃には見られるようになります。「藤沢市は、市民の郷土への愛着を育み、市民の文化の向上に寄与することを目的として、東海道藤沢宿や江の島の浮世絵をはじめとした郷土資料の鑑賞ができる施設「藤沢市藤澤浮世絵館」を開館いたしました。藤沢市の浮世絵等資料コレクションは、1980年(昭和55年)に、市制40周年を記念して、日本大学元総長の呉文炳氏から譲り受けた江の島浮世絵等が中心となり、以来、郷土資料の一環として、藤沢宿、江の島を題材とした浮世絵や、関連資料を収集してきたものです。浮世絵は、人々の暮らしや世相を描く絵画作品であり、江戸時代の庶民文化として発展しました。さらに、19世紀末には、ゴッホなどに代表されるヨーロッパの画家たちに大きな影響を与え、世界中から注目される美術品でもあります。藤沢の地は、江戸時代には東海道藤沢宿がおかれ、また時宗総本山清浄光等(遊行寺)が立地し、信仰・行楽の地であった江の島や大山(雨降山)への参語道の入口として、名所や伝説に根ざした多くの浮世絵が描かれたところです。藤潭浮世絵館は、今後も皆さまに地域の文化を伝え親しんでいただき、楽しくご利用いただける施設となりますよう取り組んでまいります。皆さまのご来訪を心からお待ち申し上げます。 2016年(平成28年) 7月吉日 藤沢市」 「浮世絵の中のこれは何かな?」 浮世絵の画中に見られる、様々な印や、彫り・摺りの技術について、少しくわしく見てみましよう。「東海道五十三次之内 藤沢 小栗判官 歌川国貞(三代豊国)」 一文字ぼかし画面の上部や水平線などに用いられる、真一文字のぼかしのことを言います。主に風景画で空や水の深みを表現するのに用いられ、摺師の熟練を要する技法です。改印(あらためいん)刊行に際して検閲を受けた証に、捺される印のことです。この図では、検閲を行った二つの名主による印と、嘉永五年三月を示す年月印が押されています。落款絵を描いた絵師の名を示します。この図では「豊国」とあり、三代豊国(初代国貞)による作品であることがわかります。毛割人物の頭髪の部分を彫ることを、毛割と呼びます。浮世絵の彫の工程では、最も技術を要する部分とされました。近づいて見ると、その技術の高さを実感できます。彫師・摺師幕末になると、彫り・摺りの技術も飛躍的に進歩し、彫師や摺師も画面に名前を刻むようになります。この図では、彫りは頭髪の名手といわれた「横川彫竹」、摺りは大海屋久五郎の「摺大久」の落款が見られます。板元印(はんもといん)出版元である版元の名や商標を摺り込んだもので、この図では、伊勢屋兼吉という板元を示しています。色々な版元印があるので、ぜひ画中からさがしてみてください。「東海道五十三次東海道五十三次とは江戸時代に整備された五街道の一つ、東海道に置かれた53の宿場のことです。日本橋を起点に三条大橋(京都)まで、約500kmの道のりです。」 慶長6年(1601)正月、江戸幕府は東海道の駅制を定め、戦国期の宿駅を母体としつつ、改めて諸駅を設定しました。諸駅には伝馬の常備を命じ、公的な交通機構を整備しました。古来、道中には風光明媚な場所や名所旧跡が多く、浮世絵や和歌・俳句の題材にもしばしば取り上げられました。江戸後期の旅行(参詣)ブームを背景に五十三次をセットにした名所絵シリーズも多種多様に版行されました。また、各宿の画題を一枚にまとめ浮世絵師か作製した「道中双六」の の版行も流行りました。「参宮上京道中一覧雙(双)六」。江戸時代、道中双六は数多く作られましたが、その中でも特に多かったのが東海道双六でした。ここには、江戸の庶民が、遠く離れた上方に強い憧れを抱いていたことが垣間見えます。東海道双六には、江戸・日本橋を出発点として西へ向かい、京都で上がりとなるところは共通でも、さまざまな特色を持つものがありました。この「参宮上京道中一覧双六」は、京都に向かう途中、伊勢神宮に立ち寄る形式になっています。右下が振り出しの日本橋、右上が上がりの京都で、真中には富士山。実際の地理とは異なりますが、ダイナミックな構図です。当時の一般的な双六と異なり、マスを並べたつくりになっておらず、また全体が鳥瞰図の形で描かれていることも特徴的で、美術的にも価値の高い作品と言われています。藤澤浮世絵館では11月13日(水曜日)から「江戸の祭神 弁財天と不動明王」を開催していた。江戸時代に起こった参詣ブームでは、「江の島詣」や「成田詣」が代表的なものとして知られている。本展では、千葉県船橋市西図書館に協力いただき、江の島の弁財天信仰と成田山の不動明王信仰を題材にした浮世絵と郷土資料を展示していた。双方の祭神の特徴や信仰がどのように人々の間で広まったのかを前期と後期と展示を入れ替えながら紹介されていた。「江戸の祭神 弁財天と不動明王江戸時代は、大きな戦乱もなく街道や宿場町などの整備が進んだこともあり、庶民が中心となって様々な文化や風習などが生まれました。なかでも寺社仏閣への参詣は、信仰とともに物見遊山を目的とした娯楽的要素も含めて、人々の間で広まっていきました。「お伊勢参り」、「富士講」といった遠方への参詣のほか、江戸から近い参詣の場として、古くから弁財天信仰の場てあった江の島、不動明王信仰の中心てあった成田山新勝寺が人気でした。本展では、千葉県や船橋市に伝わる郷土資料を数多く所蔵する船橋市西図書館から成田詣や不動明王に関する貴重な浮世絵と資料をお借りし、藤沢市が所蔵する弁才天信仰のものとあわせて行います。弁財天と不動明王が人々の暮らしの中でどのように親しまれてきたのか、それぞれの特徴と信仰を江戸から明治にかけて描かれた浮世絵とともに紹介します。前期・後期に分け展示を一部人れ替えますので、ぜひどちらもお楽しみください。また、開催にあたり特別ご協力をいただきました船橋市西図書館をはじめ、多くのご協力を賜りましたこと、この場をお借りして深く感謝申し上げます。」「ご利益を求めて 江戸時代の信仰江戸時代の人々にとって神仏は身近な存在でした。初詣といった大きな節目に関わらず、特定の日にお参りすると神仏と縁が深まるといわれる縁日に足を運ぶなど、信仰は日常生活の中に溶け込んでいました。人々は近隣のみならず、「講」というグループをつくって各地の寺社へ参詣に行きました。東海道コーナーては、ニ代広重が描いた「江戸名所四十八景」の中から江戸市中の寺社を紹介するとともに、大山詣をはじめとした山岳信仰を描いた浮世絵も展示します。」 「仏の種類 如来ー菩薩ー明王ー天」 仏の種類は、主に「如来」、「菩薩」、「明王」、「天」の4つに大別されます。如来は悟りを開いた仏の最高位、菩薩は悟りを開くために修行中の存在、明王は悪を懲らしめ、人々を守る仏、天は仏法を守り、人々を助ける神々です。詳細:如来 (にょらい):仏教における最高の存在であり、悟りを開いた者です。代表的な如来には釈迦如来、阿弥陀如来、薬師如来などがいます。菩薩 (ぼさつ):如来を目指して修行中の存在です。代表的な菩薩には観世音菩薩、弥勒菩薩、地蔵菩薩などがいます。明王 (みょうおう):仏の教えに従わない者や悪を懲らしめる仏です。不動明王、降三世明王などが有名です。天 (てん):天界に住む神々であり、仏法や如来を守り、人々を助ける存在です。四天王、弁財天などがいます。これらの仏の分類は、仏教の教えや信仰を理解する上で重要な役割を担っています。「「六十余州名所図」は日本各地の名所を、大胆な配置をもって縦画面に描いた広重晩年の揃物(そろいもの)です。「相模」の名所としては江の島の岩屋が選ばれており、荒々しい岩肌や聳え立っ岩壁などが迫力をもって描かれ、信仰の対象であった場の存在感をよく伝えています。」 歌川広重六十余州名所図会 相模江之嶋岩屋ノロニ代歌川広重諸国名所百景 下総成田山境内「房総随ーの参詣寺院である成田山新勝寺を描いた作品ですが、画題である「成田山境内」は、遠景で詳しくは描かれておらず、山門のほかは本堂と三重塔が樹木の隙間からわずかに見えているただけです。手前の近景の部分は、旅籠が並ぶ坂道の参道で石段のように描かれています。「ニ代歌川広重 諸国名所百景 下総成田山境内 安政6年(1859) 船橋市西船橋図書館所蔵」左:相州江の嶌弁天右:下総国成田山新勝寺「大日本神社仏閣は、三代広重によって日本各地の著名な神社仏閣を描いた画帖です。伊勢神宮や信州の善光寺とともに、相州江の島と下総国成田山新勝寺の風景が描かれています。明治時代の人々にとっても有名な参詣地てあったことが伺えます。」三代歌川広重 大日本神社仏閣」 「江戸名所四十八景 湯島天神 ニ代歌川広重」 「ニ代歌川広重の「江戸名所四十八景」は、全48図の揃物です。江戸の名所が描かれた本シリーズは、江戸だけでなく全国で土産物や観光ガイドとして楽しまれた人気の揃物でした。本展では本シリーズの中から、江戸の人々の人気と信仰を集めた寺社を紹介します。」 「江戸名所四十八景 根津権現 ニ代歌川広重」。 「根津権現」。「江戸名所四十八景 王子稲荷 ニ代歌川広重」 「王子稲荷」。 「江戸名所四十八景 亀戸天神 ニ代歌川広重」。 「亀戸天神」。 「江島本宮岩屋」。「江島上之宮」。 「相州江島下宮」。 「御影(みえい・おみえ)とは神仏が描かれた紙のことで、参詣した証として参拝者に渡されます。西国三十三所といった霊場巡りの巡礼者は、自身で写した経文(お経)などを寺に納め、寺から御朱印とともに御影が授けられます。描かれる神仏は各寺院の本尊などで、特に秘仏として通常に拝観ができない場合、分身として授けられることもあります。作者不詳 お札と御影 制作年不詳」。「江戸名所四十八景 五百羅漢 ニ代歌川広重」。 「五百羅漢 ニ代歌川広重 江戸名所四十八景 万延元年(1860)」。 「江戸名所四十八景 すさき弁天 ニ代歌川広重」。 「すさき弁天」。 「江戸名所四十八景 深川八まん ニ代歌川広重」。 「深川八まん」。 「江戸名所四十八景 目黒不動 ニ代歌川広重」。 「目黒不動」。 ・・・つづく・・・
2025.05.03
コメント(0)
-
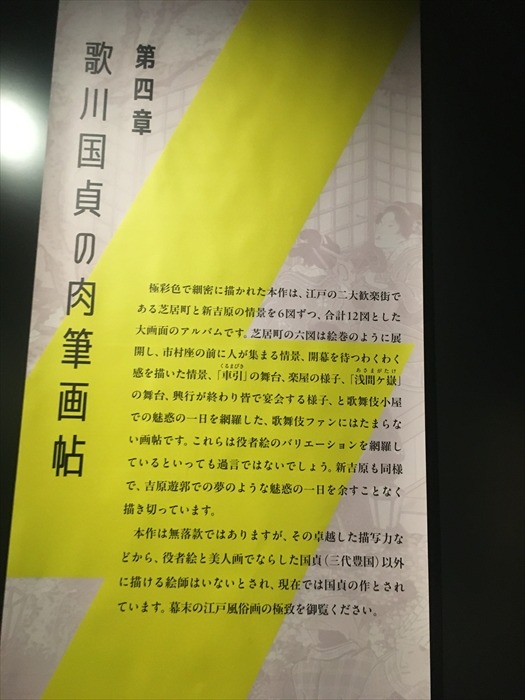
静嘉堂文庫美術館「歌舞伎を描く」へ(その5)
「第四章 歌川国貞の肉筆画帖極彩色で細密に描かれた本作は、江戸の二大歓楽街である芝居町と新吉原の情景を6図ずつ、合計12図とした大画面のアルバムです。芝居町の六図は絵巻のように展開し、市村座の前に人が集まる情景、開を待つわくわく感を描いた情景、「車引」の舞台、楽屋の様子、「浅間ケ嶽」の舞台、興行が終わり皆で宴会する様子、と歌舞伎小屋での魅惑の一日を網羅した、歌舞伎ファンにはたまらない画です。これらは役者絵のバリエーションを網羅しているといっても過言ではないでしよう。新吉原も同様で、吉原遊郭での夢のような魅惑の一日を余すことなく本作は無落款ではありますが、その卓越した描写力などから、役者絵と美人画でならした国貞(三代豊国)以外に描ける絵師はいないとされ、現在では国貞の作とされています。幕未の江戸風俗画の極致を御覧ください。」第4章の展示状況。「隅から隅まで超極彩色密画「芝居町 新吉原 風俗絵鑑」三代歌川豊国(国貞)」「隅から隅まで超極彩色密画「芝居町 新吉原 風俗絵鑑」三代歌川豊国(国貞)江戸時代後期 19世紀」「市村座 表掛(おもてがけ)」。「市村座 表掛(おもてがけ)幟が立ち看板の下では木戸芸者が読立てをして客を招く。赤ん坊をおんぶして口を開けて聞く女や、看板を仰ぐ丁稚や武士、商人などで賑わう。幕などに市村座の橘の紋がみえ、木戸の格子も市村座特有の斜格子。看板に「三幅対書初曾我」とあり、天保5年( 1834 )正月の上演の記録と一致する。三幅対は毛剃と箱根権現と姫小松、浄瑠璃は清元の「初霞浅間嶽」。絵看板の細部までも丁寧に描いている。」「幕間」。「幕間開幕を待つ客席では派手な喧嘩が始まっている。舞台には「木場」の文字と三筋が染められた幕が引かれ、これは「新三升連」とあり団十郎の後援団体から贈られたもの、また下辺に市村座の橘の紋がある。客席は舞台正面の平土間、一段高い高土間、その後ろの桟敷に分かれる。桟敷は後ろに廊下があり、そこから出入りする。現在より舞台が張り出しており、客席の一部は幕の内側になっている。」「車引」。梅王、松王、桜丸の三つ子の兄弟のうち松王は深慮があって藤原時平の舎人となり、菅相丞方の梅王・桜丸が、吉田社頭でその牛車を押し止めようとする有名な場面。「車引「菅原伝授手習鑑」の三段目。梅王、松王、桜丸の三つ子の兄弟のうち松王は深慮があって藤原時平の舎人となり、菅相丞方の梅王・桜丸が、吉田社頭でその牛車を押し止めようとする有名な場面。似顔から時平=五世松本幸四郎、松王=五世市川海老蔵、梅王=四世坂東三津五郎、桜丸=沢村訥升と判るが、この役割での上演は見当たらない。」「舞台裏」。「舞台裏楽屋の一階と舞台裏とを吹抜屋台風に描く。黒御簾の向こうに客席が見え、舞台では女六部に扮した中村歌六かと思われる女方が藪畳の向こうの人物と錦の旗を引き合い、附がバタバタと討たれてその藪畳から武将が現れるところ。小道具方も名鏡を出すタイミングをはかっているだんまりの場面。陰でせりふを付けるのか作者も居り、下座では三味線と大鼓小鼓が奏されている。一方、楽屋の稲荷町連中は四天の扮装準備に忙しく、傍では狂言に因んた趣向か、仕丁姿の面々が幹部俳優たちが差し入れる振舞酒を頂戴する酒番の場面。手前の廊下右方で話をしているのは三世尾上菊五郎と六世岩井半四郎らしい。」「浅間ケ嶽」。「浅間ケ嶽舞台で上演されるのは天保5年(1834)正月市村座での「三幅対書初曾我」一番目四立目浄瑠璃「初霞浅間嶽」で「市村座表掛」の看板のとおり。五世市川海老蔵の京の次郎が焚く起請の煙の中に三世尾上菊五郎の傾城奥州の亡魂が現れる。ニ人の顔は後見の差し出す面明かりの中に浮き上がる。舞台奥には清元の出語りが見え、舞台下手の隅では舞台番(監視役)が後ろを振り返って注意する。」さらに展示品をIphoneカメラで追う。「芝居茶屋」。「芝居茶屋観劇の後、御殿女中ニ人が芝居茶屋ニ階に役者衆や芸者、幇間(ほうかん)を招き、豪勢な宴をはる。描かれた役者は中央奥で三筋の扇に揮毫する五世市川海老蔵、黒羽織で青い扇を持つニ世中村芝翫、相対して盃を後ろに引く四世坂東三津五郎。左の階段を上った黒い羽織の三世尾上菊五郎、その後ろ振り返る沢村訥升。右の衝立の近くに座る岩井紫若。紫冒子をつけお中臈(ちゅうろう)と挙をする縞の着物の六世岩井半四郎、手前で挙に興じ両手を膝につくニ世中山文五郎。」「仲之町の桜」。「仲之町の桜大門を入ると繁華街、仲之町で、両側に茶屋が並ぶ。有名な引手茶屋の山口巴の暖簾が見える。仲之町の桜は寛延2年(1749)、茶屋の店先に桃・桜の鉢植を出したのが初めで、桜を植えたのは1、2年後のこと。毎年2月下旬(旧暦)に植え付け、3月3日、4日の紋日を中心に仲之町の花見は廓のー大行事。花の下を歩く遊女や禿(かむろ)、客引きをする男、茶屋の座敷では芸者が音曲を奏で花見の宴たけなわ。」「格子先」。「格子先江戸町一丁目には一流の妓楼が並ふ。妓楼の入ロの籬(まがき)には店の若い者が提灯を持ち座る。べんがら格子の内側が見世で、暮六ツ(午後六時頃)になると見世張リの遊女がここに並び、振袖新造が三味線の清掻(すががき)をにぎやかに弾き続ける。通りには格子窓を覗き込む遊客やひやかし、地廻りや座敷へ向かう芸者など、人通りも繁くなる。見世は引け四ツ(九ツ・零時)まで開いていた。」「表座敷」。「表座敷妓品の高い遊女は、ニ階に複数の広い座敷を持ち、調度にも贅を凝らした。床の間に法橋某の山水画、立花、琴、違い棚には守り本尊、巻物、本箱、文机等が見え、長持と赤地の夜具、衣桁には打掛が飾られる。床の間を背にした三人が客人で、若旦那とお供の半可通と宗匠といった雰囲気である。総花も出て、返礼の水台も据えられ、幇間、男女の芸者、朋輩女郎などが賑やかに宴を盛り上げている。」そして全ての展示品の鑑賞を完了。再び「歌舞伎を描く 豊原国周生誕190年 秘蔵の浮世絵初公開!」ポスター。静嘉堂文庫美術館と時期を同じくして、太田記念美術館でも「生誕190年記念 豊原国周」が開催されているとのことであった。「KABUKI PRINTS・歌舞伎絵」と。「歌川国貞(三代豊国)江戸生まれ。幼くして初代歌川豊国に入門。画号は一雄斎、五渡亭、番蝶楼など、豊国襲名後は一陽斎など。父庄兵衛は、江戸本所五ツ目の渡船場を経営。初筆は文化5年(1808)の合巻「鏡山誉仇討」、錦絵の上限作は文化6年3月とされる。国貞時代より晩年まで役者絵、美人画で活躍、特に五渡亭時代に三枚続や大首絵風の美人画に優品が多い。香蝶楼国貞の名では柳亭種彦の合巻「偐紫田舎源氏」(1829 ~ 42)の挿絵が知られ、これを錦絵化した「源氏絵」は、国貞錦絵の売り物となる。弘化1年(1844)、二代豊国を称すが、今日では三代目に数える。錦昇堂から刊行された役者大首絵シリーズは画業の集大成。生涯に描いた作品数は全浮世絵師中、最大数量で、広重、国芳らと共に幕未浮世絵界を牽引した。」「豊原国周江戸生まれ。俗称八十八、本性は荒川.はじめ長谷川派の豊原周信に師事し、役者似顔絵を学び羽子板押絵の原図を制作。嘉永1年(1848)、三代豊国に入門。画号は一鶯斎、鶯斎など、美人画・役者絵を得意とし、特に明治2年(1869)の人形町具足屋嘉平兵衛を版元にした役者似顔大首絵シリーズにより「役者絵の国周」として知られ、後世、小島鳥水によって「明治の写楽」と称せられた。また、明治中期の三枚続の大画面に一人の役者の半身像を描く斬新な構図を開拓したほか、写真の流行する時代の影響を受け、陰影法を用いるなど、明治浮世絵に新境地を開いた。83回引っ越し、妻も40回以上かえたという奇行の持ち主。」「顔出しパネル」。上記「顔出しパネル」の絵は「豊原国周「間ロ廾五間奥行卅間余 新富座本普請出来之図」大判錦絵三枚続 明治11年(1878) 1月」「静嘉堂@丸の内ミュージアム ショップで好評発売中!」と。河鍋暁斎「地獄極楽めぐり図」静嘉堂文庫美術館蔵とは・・・日本橋の小間物問屋、勝田五兵術の娘・田鶴は、明治ニ年(一八六九)三月十日に、十四歳で早世してしまう。本作は、田鶴の追善供養のために五兵衛が暁斎に依頼したもの。内容は何弥陀三尊の案内で、観光旅行するかのように冥界見物し、先に亡くなった親族と再会したり、芝居見物をしたり、問魔大王と宴会したりして、やがて極楽に到着するというもの。愛娘が現世同様あの世を楽しむ様子を絵で見せることで、遺族を慰めるべく、暁斎が心血を注いで描いた名品です。」「河鍋暁斎「地獄極楽めぐり図」。大きなTVモニターでは「ビデオ上映プログラム静嘉堂@丸の内 歴史と名宝 10分仕掛け絵の世界 5分」と。「歴史と名宝」では「国宝《曜変天目(稲葉天目)》 南宋時代 12~13世紀」の紹介ビデオが。「中国南宋時代作られ完品が現存するのは3碗、中でもひときわ華やかだとされる」と。「徳川家光が乳母の春日局に下賜したとされ長らく稲葉家に伝わった」。「1934年 岩崎小彌太の所有に」岩崎小彌太は明治12(1879)年、彌太郎の弟・彌之助の長男として東京で生まれた。「窯の中で生じた釉薬の奇跡的な変化が生み出した神秘の世界」。「小彌太は「天下の名器を私に用うべからず」として使用することは一度もなっかったという」。「黒の奇跡・曜変天目の秘密 2025年4月5日(土)~6月22日(日)」に開催されると。開催中!「藤沢と江戸の出版事情 蔦屋重三郎と絵師たち会期 2024年12月24日(火)~2025年2月24日(月/休)」と。そして隣りにあった「ミュージアムショップ」を訪ねた。国宝・曜変天目「稲葉天目」をモチーフにしたオリジナルグッズは絵はがき、ハンカチ、ぬいぐるみ、アロハシャツ・・・と充実の品揃えであった。「アロハシャツ」。「曜変天目ぬいぐるみ」。「ほぼ実寸の曜変天目ぬいぐるみ」。これが本物の「曜変天目」の写真か? 本物をネットから。 ・・・もどる・・・ ・・・おわり・・・
2025.05.02
コメント(0)
-

静嘉堂文庫美術館「歌舞伎を描く」へ(その4)
「松竹梅湯島御額」。 「水墨画の如き静謐な画面に漲る緊迫感!「松竹梅湯島御額」坂東秀調の下女お杉、中村福助の八百屋於七、五世尾上菊五郎の土左衛門伝吉、尾上菊之助の小性吉三豊原国周版元:福田熊次郎 明治28年(1895) 3月「松竹梅湯島御額」に取材。実在した少女放火犯「八百屋お七」と寺の小姓吉三郎の恋を描く。本図は「火の見櫓の段」。雪の夜、吉三郎の命を救うべくお七とお杉は木戸を開けて欲しいと門番の土左衛門伝吉に頼むが断られる。お七の半身像を中央に、その視線は愛しい吉三郎や門番の土左衛門伝吉を見やる。案じるお杉を手で阻止し、その表情に決意がにじみ出ている。」「豊原国周「加賀見山再岩藤」五世尾上菊五郎の岩藤の靈大判錦絵三枚続 版元:福田熊次郎 明治28年(1895)」「水墨画の如き静謐な画面に漲る緊迫感!「松竹梅湯島御額」坂東秀調の下女お杉、中村福助の八百屋於七、五世尾上菊五郎の土左衛門伝吉、尾上菊之助の小性吉三豊原国周版元:福田第熊次郎 明治28年(1895)3月「松竹梅湯島御額」に取材。実在した少女放火犯「八百屋お七」と寺の小姓吉三郎の恋を描く。本図は「火の見櫓の段」。雪の夜、吉三郎の命を救うべくお七とお杉は木戸を開けて欲しいと門番の土左衛門伝吉に頼むが断られる。お七の半身像を中央に、その視線は愛しい吉三郎や門番の土左衛門伝吉を見やる。案しるお杉を手で阻止し、その表情に決意がにじみ出ている。」「北斎の弟子・北雲、希少な錦絵は二代蔦重版五世岩井半四郎東南西北震版元:蔦屋重三郎 文化(1804-18)前期」桜の下、伊達兵庫髷の遊女は千両眼の魅力的な眼の五世岩井半四郎。狂文亭ー通の狂歌は「打かけのしたにかくせる男とは たかいはかきの此かほよ花」。ー通は石川雅望『職人尽狂歌合』(文化5年3月、版元・蔦屋重三郎)に序跋寄せた人。本作は北斎門人で肉筆画や読本挿絵、摺物を手掛けた北雲の錦絵。落款印でなく筆の絵、東南西北雲の落款も洒落ている。」「難波屋店先に蔦重の奉納燈籠!難波屋店先栄松斎長喜」「難波屋店先に蔦重の奉納燈籠!難波屋店先栄松斎長喜版元:蔦屋重三第 寛政4-5年(1792-93 )頃浅草寺随身門の水茶屋「難波屋」の店先を描く。右からニ人目、右手に茶托をさげ左手を上にして振り返るのがこの店の看板娘で歌麿画で有名な寛政の三美人の一人「おきた」。難波屋おきたと、長椅子に座る客の間には木製の燈籠がたつ。そこには「奉納浅草観世音願主蔦屋重三郎」とある。絵師・栄松斎長喜(生没年未詳)は歌麿と同門で、蔦屋重三郎に見出された浮世絵師の一人。」「版元・蔦屋重三郎の足跡静矗堂文庫の所品から蔦屋重三郎(1750-97 )は江戸新吉原で生まれた。はじめ、貸本、小売リを主体とする店を営む。やがて吉原のガイドブック『吉原細見』などの刊行が大当たりし、天明3年に地本問屋となり通油町に進出。自身でも狂歌や戯作も手掛け、蔦唐丸の名で作品を残したほか、蜀山人(大田南畝)や、山東京伝ら狂歌師や戯作者とも親交し、洒落本・黄表紙などを次々と出版した。また謎の浮世絵師・東洲斎写楽を世に出したほか、寬政年間に独自の様式を打ち出した喜多川歌麿の美人大首絵シリーズや狂歌摺物など多くの名作を世に出した。このコーナーでは静嘉堂文庫所蔵の浮世絵版画より、蔦重版と、石川雅望(宿屋飯盛)による墓碑の拓本(右側独立ケース内)を展示する。」石川雅望(宿屋飯盛)による「蔦屋重三郎墓碑の拓本」。近づいて。東京都台東区東浅草の正法寺にあった墓の貴重な拓本。撰文は狂歌師の石川雅望が書いている。蔦重の才能を称え、死を惜しむ内容 と。「蔦重の墓碑のよすがを写した貴重な拓本蔦屋重三郎墓碑拓本版元・蔦屋重三郎(喜多川柯呷)の墓碑の拓本。撰文は石川雅望(1753-1830)。正法寺(現・東京都台東区浅草)に建てられた墓碑が既に失われた現在、本炻本は貴重な資料。石川雅望は狂歌師で戯作者、国学者。狂名は宿屋飯盛。号六樹園、五老。父は浮世絵師・石川豊信。家は代々宿屋。狂歌を頭光、四方赤良に学んで一家をなし、狂歌四天王の一人と呼ばれた。」蔦屋家の墓碑は正法寺にかつてあったが、度重なる震災戦災にて失ってしまった 典拠 → 「台東区史沿革編」安政二年(1855年)の大地震の記述中、「正法寺潰れ」の 記載あり。「浮世絵志(16)」(芸艸堂 1930年)に「関東大震災に倒れはしたが 幸ひに破損は免れた」との記載あり。 東京大空襲が墓碑が失われた一番の要因なのかもしれません。蔦屋家の墓碑はかつて本堂の裏手に2つ(蔦屋家歴代と蔦重)並んで建っていた。現在の墓碑は昔の形を史料を元に復刻したものであるとのこと。 典拠 → 「高潮」、吉川弘文館には 1906年 に「浅草吉野町六番地の正法寺という毘沙門堂のある寺の本堂の右側から 堂裏に廻ると、其處に喜多川氏歴代の墓碑と、重三郎の墓碑と並んで建っていた。 歴代の墓碑の方は䑓石が三段になって居って其上に蓮座、夫れから碑石と見上げる 様な立派な墓で、歴代十四名の法號が記してあるが、其上列五番目に幽玄院義山 日盛信士とあるのが則ち柯理である。此碑は則ち柯理重三郎の全盛時代に建立して 置いたもので、水盤には右に「通油町」中央には例の山形に蔦の紋所左に「蔦重」と 刻んであって〜」・・・・と。下記の左の写真は「蔦重の墓」(高潮より)、右の写真は「蔦屋家歴代の墓」(鈴木俊幸著 蔦屋重三郎より と。【翻刻】喜多川柯理墓碣銘喜多川柯理本姓丸山称蔦屋重三郎 父重助母広瀬氏 寬延三年庚午正月初七日 生柯理於江戸吉原里 幼為喜多川氏所養 為人志気英邁 不修細節 接人以信 書於倡門外開一書舗非他人所能及也 遂為一大買 丙辰秋得重痼彌月危篤 寛政丁巳夏五月初六日謂人日吾亡期在午時 因処置家事訣別妻女 而至午時笑又日 場上末撃柝何其晩也 言擧不再言 至タ而死 歳四十八 葬山谷正法精舎 予居相隔十里 聞此訃音心怵神驚 豈不悲痛哉 吁予霽壌間一罪人 餘命惟怗知己之思遇而巳 今既如此 鳴呼命哉銘日 人間常行 載在稗史 通邑大都 孰不知子五老 石川雑望 撰栄澤 吉田 融 書【大意】喜多川柯理、本姓は丸山、蔦屋重三郎と称す。父の名は重助、母の姓は広瀬氏である。柯理は寛延三年一月七日に江戸・吉原の里に生まれた。幼い頃、喜多川氏に養育された。(柯理は)志が高く度量が大きく細かいことにこだわらず、人に対する際には「信」を重視した。かって吉原大門の外に一軒の書肆を開き、後に住まいを日本橋通油町に移してここに父母を迎えて養った。父母が相継いで亡くなると、柯理は商売の幅を広げ、中国・春秋時代の范蠡のように富を蓄えてゆき、その優れた手腕は常人の及ぶところではなく、ついに大きな書肆となった。寛政八年の秋に重い病気となり、数か月後、危篤となった。寛政九年五月六日、私が亡くなるのは午の時(正午)だといい、家事の始末をして、妻や家族に別れの言葉を告げ、正午になるとまた笑って言うには、浮世の舞台は未だ終わらないが今晩あたりだろう、と言い終えると何も言わなくなり、夕方に亡くなった。享年四十八。山谷の正法寺に葬られた。私は十里ほど離れた場所に住んでいるのだが、この訃報を聞き心から驚いている。悲痛でないことがあろうか。ああ、私はこの世の罪人だ、ただ何もせず余命を安らかに親友・蔦屋重三郎から受けた思遇と共に過ごすだけだなんて。今、既にこのとおりだ ああ、さだめかな。銘に日く 人生は小説のようなもの。この江戸で蔦屋重三郎を知らなi人はいない。石川雅望撰、吉田融書」正法寺の現在の墓石をネットから。「喜多川柯理墓碣銘蔦重の本名は 柯理 ( からまる )と言い、雅望と南畝によって作られた漢文には、蔦重の生い立ちから最期までの他に、蔦重の人柄もこう書かれてあります。為人志気英邁 不修細節 接人以信(その人となりは、志、人格、才知が殊に優れ、小さな事を気にもかけず、人には信頼を もって接した)また、蔦重の訃報を受けた石川雅望の気持ちもこう記されてあります。予居相隔十里 聞此訃音心怵神驚 豈不悲痛哉(自分は十里を離れたところに居て、この訃報を聞き畏れの心と共に心底驚いた。まさに 悲痛の極みである)ズームもネットから。「俳優・俳句・画、三拍子揃った名画集!「梅香百種」豊原国周版元:福田熊次郎 明治26~27年(1893-94)その名の通ri五世菊五郎(俳名:梅幸)の半身の舞台姿とコマ絵に俳句などを描いた百枚からなる豪華で大部な揃物。明治の名優・五世菊五郎が、十三世羽左衛門から家橘をへて五世菊五郎に至るまでの当たり役か選はれた、菊五郎を語る上で欠かせない名品。浮世絵師・豊原国周の集大成でもあり、菊五郎、国周、具足屋のトリオによる渾身の揃物。」「梅幸百種之内 市川團十郎舞台姿とコマ絵に俳句などを描いた百枚からなる豪華で大部な揃物。明治の名優・五世菊五郎が、十三世羽左衛門から家橘をへて五世菊五郎に至るまでの当たり役が選はれた、菊五郎を語る上で欠かせない名品。浮世絵師・豊原国周の集大成でもあリ、菊五郎、国周、具足屋のトリオによる渾身の揃物。」晩年の集大成《梅幸百種(ばいこうひゃくしゅ)》にも表れている。梅幸は菊五郎の俳名で、同作は菊五郎の当たり役を描いた百枚揃(ぞろい)。「鈴森対港杭(すずがもりついのみおぐい)」の1枚では、美少年・白井権八(しらいごんぱち)が悪漢を撃退する様子を、幡随長兵衛(ばんずいちょうべえ)が物陰からうかがっている。この場面を大小のコマで表現しており、なんだか漫画のコマ割りみたいだ。「舞台を切り取る構図力や役者の似顔を捉える画力に優れており、舞台に詳しいからこその臨場感を錦絵で表現している。「五世菊五郎の白井権八と九世団十郎の幅随長兵衛明治22年(1889) 12月棡座「鈴森対港杭」に取材する。五世菊五郎の美少年・白井権八は夜、鈴ヶ森の処刑場の雲助たちに襲われるも、見事に撃退する場面。コマ絵にはこの様子を物陰から見て感心する九世団十郎の幡随長兵衛。見せ場を画面枠を巧みに使って表現。菊五郎の俳句の師・永機の句は「飛鳥や繁花な江戸の這入口」鳥(権八:鳥取出身)が江戸の人口・鈴ヶ森に入って来た様を詠む。」「五世菊五郎の仁木弾上と九世団十郎の荒獅子男之助」「五世菊五郎の仁木弾上と九世団十郎の荒獅子男之助慶應4年8月市村座「梅照葉錦伊達織」に取材。九世団十郎扮する忠臣・荒獅子男之助が「ああら怪しゃなア」と鉄扇で大鼠を打つ。逃げた鼠の正体は五世菊五郎扮する仁木弾上。煙の中から巻物をくわえて印を結現れた男の額には傷が。永機の句は「ぬけ出して鶉になるや溝鼠」。」「真正面の迫力!三世中村歌右衛門の五斗兵衛盛次三代歌川豊国(国貞)」三代歌川豊国(国貞)「五斗兵衛盛次 中村歌右衛門 三世梅玉」大判錦絵 文久3年(1863)「真正面の迫力!三世中村歌右衛門の五斗兵衛盛次三代歌川豊国(国貞)版元:恵比寿屋庄七 文久3年(1863)7月」「大首絵ならぬ大顔絵は三代豊国渾身の作四世中村歌右衛門の熊谷直実三代歌川豊国(国貞)」「大首絵ならぬ大顔絵は三代豊国渾身の作四世中村歌右衛門の熊谷直実三代歌川豊国(国貞)版元:恵比寿屋庄七 万延1年(1860)9月錦昇堂(恵比寿屋庄七)版の役者大首絵として知られる本揃物は三代豊国最晩年の豪華な作品集で60図が刊行された。厚奉書を用いて技巧の限りを尽くした贊沢なこの大企画が実現したのは、神田塗師町の鋼鉄商三谷家の注文による。画中上部に枠をつくり、大きく役者名、描かれた役名、俳号や改名前の名前なとを記す。」豊原周義、右:豊原周義「浄るり 積恋雪関扉」関守関兵衛実ハ大伴黒主、小町姫、 明治 12 年 (1879) 1 月左:塩冶判官と大星由良之助、 明治 11 年 (1878) 11 月「周義は国周の女弟子、実は一時の女房「浄るり 積恋雪関扉」関守関兵衛実ハ大伴黒主、小町姫豊原周義」「周義は国周の女弟子、実は一時の女房「浄るり 積恋雪関扉」関守関兵衛実ハ大伴黒主、小町姫豊原周義版元:福田熊次郎 明治12年(1879) 1月雪が降る逢坂山の関、薄墨色の桜の大樹は満開で、これを背にして怪しい関守と三井寺参詣で通りがかった小町姫が問答する場面。幻想的な舞踏劇の情景をよく表現している。No. 80の忠臣蔵上演の翌年の正月4日より新富座で上演した「積恋雪関扉」でも、団菊左をはじめとした名優が主要な役をすべて日替わりで演じた。本作も贔屓の役者を組合せて楽しめる子持ち絵。」「日替わり役者の思臣蔵、さらに大当たり!塩冶判官と大星由良之助豊原周義」「日替わり役者の思臣蔵、さらに大当たり!塩冶判官と大星由良之助豊原周義版元:福田熊次郎 明治11年(1878)11月通常とは違う趣向の忠臣蔵を上演しようと、明治11年(1878) 11-12月に新富座の「仮名手本忠臣蔵」では名優が主要な役を日替わりで演じた。本図はこれを版画で表現した子持ち絵。子持ち絵とは、顔の部分をめくれば好きな役者の組合せが可能な仕掛絵のこと。本図は忠臣蔵の四段目で、切腹する判官とその場に駆けつけた由良之助を描く。」「白綸子地松竹梅鶴模様打掛明治40年(1907)頃」。「鮮やかな吉祥模様に満たされて白綸子地松竹梅鶴模様打掛明治40年(1907)頃令和6年度・岩崎家寄贈本作は、蜀江文の白編子地に色とりどりの松竹梅や鶴を刺繍で表し、一部、撚金糸が使われる。霞には金泥が施された、とても華やかなー領。岩﨑小彌太の夫人・孝子の旧蔵品として岩﨑家に伝来し、岩家より寄贈された。」「白縮緬地菊立涌紋長襦袢明治40年(1907)頃令和6年度・岩家寄贈」「白縮緬地菊立涌紋長襦袢明治40年(1907)頃令和6年度・岩家寄贈立涌の中に菊花を配した有職(ゆうそく)風の模様と桜・藤・菖蒲(しょうぶ)の花束を交互に配した模様は、武家女性の礼装用のデザインです。刺繡(ししゅう)・描絵(かきえ)・型染(かたぞめ)で模様を表わします。豪華ですが様式化が進んだ江戸時代後期における大奥女性たちの衣装の様子がうかがえます。」「白綸子地松竹梅鶴模様打掛」をズームして。岩﨑彌之助の息子で三菱四代社長、小彌太の夫人、孝子の旧蔵品として岩﨑家に伝来した「白綸子地松竹梅鶴模様打掛」。近づいて。綸子地の余白を取りつつ、金銀色とりどりの吉祥文様と霞を大胆に配置した豪華な打掛。松竹梅に色彩豊かな鶴をイメージしたという吉祥模様。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.05.01
コメント(0)
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
-

- やっぱりハワイが大好き!
- JALのブラックフライデーセール
- (2025-11-20 10:02:25)
-
-
-

- ラスベガス ロサンゼルス ニューヨ…
- エグゼクティブラウンジ 朝食 ヒル…
- (2025-11-26 00:10:04)
-
-
-

- 日本全国のホテル
- 【大阪】ホテルクライトン新大阪/ホ…
- (2025-11-28 13:10:20)
-







